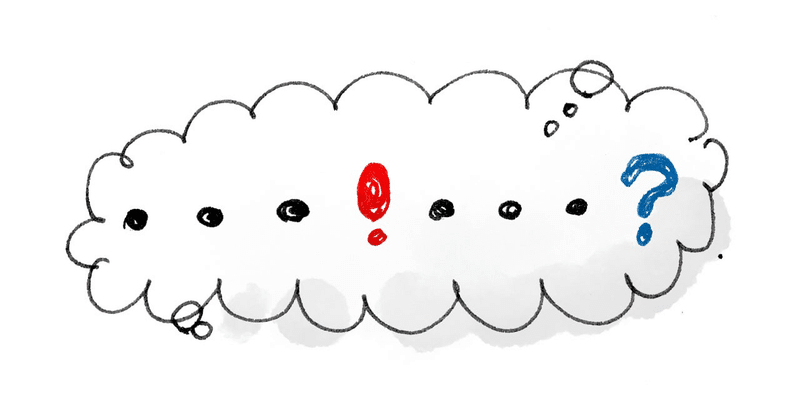
【おはなし】雲をかたづける
たとえば誰かが頭の中で空想をする。
多くの場合、それは白くてもこもこしたキャンバスの中に形成され、まとめて頭の斜め上辺りに出力される。ホワンホワン〜というSEが付いてくることもある。
授業中の妄想も、コンクールで優勝する夢も、書きかけの台本も作り途中の舞台の構想も、この白いもこもこの中に展開される。
空想が途切れたあと、このもこもこは頭から離れ、イメージを抱えたまま空に昇っていく。空想は熱を帯びているため、気流に乗って上昇していくのだ。
各地で発生した空想のもこもこたちは空の上のほうに溜まり混ざりあう。そのあと空気中の小さなホコリやちりなどを核として集まり、やがて濃度の高い雲を形成する。
こうして生まれた雲が厄介である。
雲はその場にとどまり続け、なかなか風に乗って流れていかない。上空の見通しが悪くなり、空に浮かぶ星座、月、衛星それぞれの場ミリや、気圧配置のポジションが乱れたり、梅雨前線が前に出すぎちゃったりと、一帯の空の秩序がめちゃくちゃになる。
さらにこの雲が現れると、地上では長い雨が降る。雲が空にとどまる限りこの雨は何日も何ヶ月も降る。
雨が何十年も降り続き、沈んでしまった町があるという記録も残っている。
雲のできる原因は、誰かの空想の数々である。空想のもこもこがある量を超えて上空に溜まると、この雲が出来上がる。
そのため委託業者による定期的な空の清掃が必要になる。
こうした雲を『錯想性乱層雲』という。
***
清掃のバイトを始めて2年が経った。
ツナギを着て高い鉄骨の足場の上に登り、ナントカ乱層雲が発生しないように、特殊な掃除機で雲になる前の散らかった空想を片付けていく。仕事内容はそれだけ。
海岸のごみ拾いだとか川の掃除だとかと感覚は同じだ。
空想の種類はたとえば映像であったり、絵だったり画像だったり文章であったりする。
クレヨンの絵やイラストの下書き、書きかけの手紙など、それらが半透明のもやのような白い物質に守られて上空に溜まっている。
掃除機のスイッチを押して、ノズルを向けて溜まった空想を吸い込んでいく。
カチ
ブワーン
ズズズズズ
それらは吸い込まれるたびに掃除機のノズルの直径に合わせてくしゃっと縮められ、それほど手応えもなく掃除機に吸い込まれる。そうして吸い込んだものは背中のタンクの中に集まっていく。
誰にでもできる、簡単な仕事だ。高所作業なだけあって、時給は意外と良くて1100円。
はじめのころはそういうのも珍しいなと思っていたけれど、毎日見ているとだんだん何も感じなくなった。足場に登って、空の清掃をする。それだけ。
私たちは2人1組で作業をする。その日の担当地域が決まっていて、ふたりで期限内に担当箇所の清掃を行う。
タジくんは後輩だけど、すっごい無口で目が合ったことがない。仕事中は仕事の話以外なにも喋らないし、メガネかけててもっさりしてるから、そういうのが苦手なのかなと勝手に思っている。
カチ
ブワーン
ズズズズズ
空想のもこもこを吸い込むと、辺りの空気が澄んでいく。
「これでここの箇所の清掃は終わりだね。片付けたら休憩にしようか」
向こうにいるタジくんに声をかける。
「掃除機のタンク、いっぱいだったら出しておいてね」
タジくんから返事がないのはもう慣れた。いつも伝わってはいるみたいだから、あんまり気にはならなくなった。
掃除した後の冴えた雲ひとつない空を、足場ひとつを頼りにして私たちは後にする。
午後の仕事に向けて休憩室でぼうっとしていると、タジくんがやってきて私の近くに腰かける。
「おつかれさま」
「あ、おつかれっす」
タジくんがケータイを取り出し眺め、なんだか気まずい時間が流れはじめる。
「午後は通常の雲が多いみたいだから、ちょっと視界が悪いかも。安全具とゴーグル、忘れないでね」
「分かりました」
会話が終わりまた沈黙が始まる。気まずいけれど、休憩中に積極的に話しかけるのも気がひけた。
「先輩ってここで働く前は、何してたんですか」
ケータイを見ながらタジくんが言った。
「ええと、会社員だよ。普通の」
向こうから話しかけてくるとは思わなかったので、私はあわてて答えた。
前に勤めていた普通の仕事は3ヶ月で辞めてしまった。理由なんて覚えてない。辞めてみたくなったのだ。
「そうすか」
あまり興味がなさそうにタジくんはあっさり答えた。
私が何をしてたのかなんて、私が知りたい。
夢も叶えられず、いやそもそもそれがなんだったのかも覚えてない。
私はいったい何がしたかったのだろう。何になりたかったのだろう。
「タジくんはなんでこのバイトしてるの」
はやくも会話の糸が切れそうだったので私は続ける。
「え、俺すか」
返球を予想していなかったのか、タジくんが慌てたように口にする。
「えと、あの、お、俺、昔から人の考えてる事とか想像するの苦手で、よく人を怒らせちゃったりしてたんですよ」
しばらく長めに考えた後、タジくんが小声でつぶやいた。
「他人が本当に何かを考えてるんだって想像するの、ほんとに分かんなくて、俺」
思い出すように、彼の目が泳いだ。軽い気持ちだった私は少し身構えるが、タジくんは話し続ける。
「あの、空想のもこもこって、あれ質量も実体も無いじゃないですか」
「そうだね」
「でも見てると迫力があったり、すごい繊細だったりして、胸のあたりがなんかじわっとなってくるんです」
空想なのだから当然なのだけど、あのもこもこは空気中のほこりやチリと結びつき、錯想性ナントカ雲になってはじめて実体を持つのだ。
今日のタジくんはどうしたことかよく喋る。
「それでこのバイト選んだの?」
タジくんはもうケータイを見ていなかった。彼の目は私をまっすぐにとらえて、真剣さで突き刺してくるようだった。
「誰かの空想を見るの、好きなんです。俺にはそういうの、できないから」
彼だって彼なりにたくさんの苦労をしてきて、今ここにいる。
そう思うと途端に自分が恥ずかしくなってきた。何もできず、ただただ流されるままに転がるように生きてきた自分のことが。
「まぁ時給もいいしね」
そんなくだらない一言しか出てこなかった。
***
午後の仕事も滞りなく進んでいく。
カチ
ブワーン
ズズズズズ
空に散らかっている空想を掃除機で、吸う。掃除機で、吸う。その繰り返し。
この地域は予報の通り、通常の雲がやや多くて視界が悪いようだ。
単調な作業をしながら、タジくんの言っていたことを思い出していた。
『誰かの空想見るの、好きなんです』
仕事をしてるとき、そんな風に考えた事って、一度もなかった。
散らかっているもこもこの中を見てみると、面白そうなシナリオとか、見たことのない風景とか、たしかにそんなのが包まれてたりする。
私からだって、絶対こんなのは生まれてこない。こんなきらきらした空想が、私の頭の中で作られるわけがないのだ。それは私が悲しいほどよく知っている。
昔からそうだった。
ただ、親に気に入られる自分、先生に気に入られる自分、友だちに気に入られる自分をしていただけで、自分で選択して何かを考えたことって一度も無い。
その場その場で求められる自分をやっているうちに、自分の心でなにかを考えることが、できなくなってしまったのだ。
気づくのが、遅すぎた。だから大した理由もないのに焦って会社をやめて、バイトで時間をつぶしているのだろう。
鉄骨の足場が揺れている。私は掃除機の持ち手を握りしめた。
カチ
ブワーン
ズズズズズズズズズズズ
掃除機の吸い込み音がいつもと違うのに気づいたのは、未来の世界がこんな風だったらいいな、という誰かの想像が包まれたもこもこを吸い込んだ後だった。
ズズズ
ブウゥゥン
いつもとは違う音を立てたあと、掃除機はゆっくり眠るように動かなくなった。
「あれ?」
カチ
カチカチ
カチカチカチカチ
スイッチを入れても起動しない。こんなことは今までなかった。
向こうの足場で作業しているタジくんを呼ぼうとしたとき、背中でピピピと音がした。背負った掃除機のタンクからだった。
「タジくん」
私が言い終わらないうちに、背後で固いものが破裂するような大きな音がした。
そこからはいろいろなことがたくさん起きた。
まず足がもつれ、体がふわりと落ちていく。
風が一瞬、完全に吹くのをやめて、時間が止まる。
どこからか現れた大量の空想のもこもこが勢いよく空に漂っていき、渦を巻いていた。
空想たちは近くのものと混ざり合い、絵や言葉や画像や記憶や写真や文章や映像がひとつになっていった。
色も言葉も大きさもばらばらなそれらは、皆で手をつなぎ、合わさっていく。
小さな子が画用紙に一生懸命描いた絵が脈絡なく切り替わっていく映画フィルムを、一冊の絵本にまとめたような、そんな光景だった。
空一面が空想の世界で染め上げられていく。
空想はひとつひとつが光を放っていた。そのため混ざり合うたびに一瞬、雷のように白く瞬く。
空想は巨大なひとつになり、さらに上空へ吸い込まれていく。不思議なほど音がしなかった。
逆さまのタジくんがこちらに駆け寄ってくる。私が見たのはそこまでだった。
背中のタンクが破裂したのだと教えてもらったのは、休憩室で目を覚ました後だった。
***
私のミスのせいで降り続いた雨は、4ヶ月と少しでやんだ。
運良くこのくらいの雨量で済んだので、お咎めは免れたが、かなり厳しめに怒られた。
タジくんがなぜかけっこう責任を感じているみたいで、いつにも増して口数が少なくなった。
私がタンクの交換を忘れていたせいなので、本当に彼は悪くないのだけど、たまにジュースを奢ってくれるようになったから、まぁしばらくはこのままでいいかと思っている。
「先輩、辞めないでくださいね」
バイトに復帰した日、タジくんが言った。顛末書を提出したすぐ後だった。私が何も答えられないでいると、彼は続ける。
「先輩は仕事教えるのとかも上手かったし、えと、お、俺は結構信用してますよ」
そんなことを言われたのははじめてだった。
「あとあの、先輩だけなんす。俺の話、ちゃんと聞いてくれたの」
タジくんがこちらを見ずに言った。頭の真ん中あたりがあつくなった。嬉しかったのかもしれない。タジくんにとって私はちゃんと『先輩』だったのだ。
「もっと時給のいいバイト見つかるまでは辞めないかな」
あつくなった頭の中から私はあわてて返事を取り出す。
「よかった」
いつもみたいに目線を合わせず、タジくんはそのまま逃げるように去っていく。ちょっと笑ってたかもしれない。
「あ」
よく見るとタジくんの頭の後ろに小さな白いもこもこがくっついている。
彼は自分からもこもこは出ないと言っていたけど、思えばそんなはずはないのだ。
自分の未来、なりたい自分、なんでもいいけどみんな、いろいろ想像しながら生きていく。
ここからじゃ見えないけれど、中にはタジくんが今頭の中で思い浮かべたであろう言葉が入っていた。
それを見てるとなんだか私の頭からももこもこが出そうな気がしたけど、全然そんな気配は無い。頭のあつさはもこもこの出る前兆というわけではないらしい。
私は一体何になるのだろうか。それは私の想像にかかっている。
空想のもこもこは、自分自身で生み出していける。何者でもない私はこれから、何になれるのだろう。
最新型の掃除機を背負い、私はタジくんを追いかけた。
「ちゃんとタンクの中身確認した?」
タジくんがこちらを振り向いたけど、もこもこに顔がかぶってよく見えない。
おしまい
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
