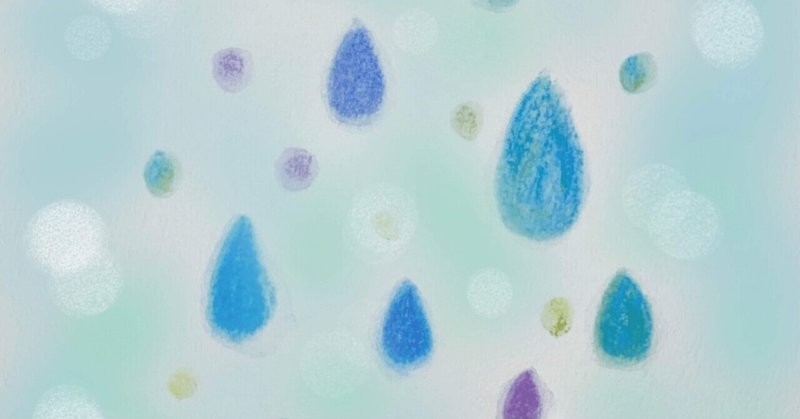
恋愛短編小説 「オタクとヒヨの予言」
ようやく高校の授業が終わった。下駄箱で靴に履き替えていた僕は、ふと隅で外を見つめているヒヨを見かけた。彼女はいつも静かで、クラスではあまり目立たない存在だった。僕もだが。ヒヨには何か秘密を抱えているような、不思議な雰囲気があった。
「雨、降るよ」とヒヨが静かに言った。その言葉が耳に入るか入らないかのうちに、突然、空が暗くなり、土砂降りの雨が降り始めた。まるで彼女が呼び寄せたかのようだった。
「え、どうしてわかったの?」僕は驚きを隠せずに尋ねた。ヒヨは淡々と「雲を見ればわかることよ」と答えたが、そのタイミングの良さにはどこか超自然的なものを感じざるを得なかった。
僕の頭の中でX-メンの天候を操るミュータント、ストームが浮かんだ。本物のミュータントがこの世にいるなんて信じられない。
「君はミュータントなのか?」僕は興奮を隠せずに言った。僕の頭の中では、マーベルコミックのヒーローたちが彼女を取り囲んでいた。彼女はその質問に小さく笑い、「そんなわけないでしょ」と答えた。
その日以降、僕の中でヒヨに対する興味が増す一方だった。僕は彼女が読書をしている図書室に足を運び、彼女の隣に座るようになった。彼女はいつも静かに本を読んでいて、僕がマーベルコミックについて熱く語ると、静かに聞いてくれた。
「君は、本当に普通の人間なの?」僕はある日、再び彼女に問いかけた。ヒヨはまたしても微笑みながら、「普通かどうかはわからないけど、超人やミュータントではないよ」と答えた。
「でも、その特殊能力みたいなのはどう説明するの?」僕は彼女の能力に強く引かれていた。ヒヨは少し考えた後、「私には特別な能力なんてない。ただ、勘がいいだけだよ」と静かに言った。
それからの毎日、僕たちは放課後、図書室で過ごす時間が長くなり、お互いの好きな本について語り合うようになった。ヒヨは僕のマーベルコミックへの情熱を受け入れてくれ、僕も彼女が推薦する小説に手を出すようになった。
ある雨の日、僕たちは一緒に帰ることになった。僕は思い切ってヒヨに聞いてみた。
「ねえ、もし超人だったら、どんな力が欲しい?」
ヒヨはしばらく黙って考えてから、「多分、人の心が少しでも楽になるような力かな。人を癒やすことができる力が欲しい」と言った。その答えに、僕は心から感動した。彼女がどれだけ優しく、思いやりのある人なのかがよくわかった瞬間だった。
僕はその日、ヒヨの手を強く握った。彼女がそれを拒まなかったとき、僕の中で何かが確信に変わった。もしかしたら彼女は超人ではないかもしれないけれど、僕にとっては確かに特別な存在だった。
「ヒヨ、僕と一緒にいてくれてありがとう。君は僕のヒーローだよ」と僕は言った。
ヒヨはそれに答えて、「私も同じよ。ありがとう」と言って、僕の手をしっかりと握り返してくれた。
それが僕たちの新しい章の始まりだった。僕はこれからも彼女と一緒に、お互いの好きな話をしながら、一緒に成長していくことを楽しみにしていた。
時間を割いてくれてありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
