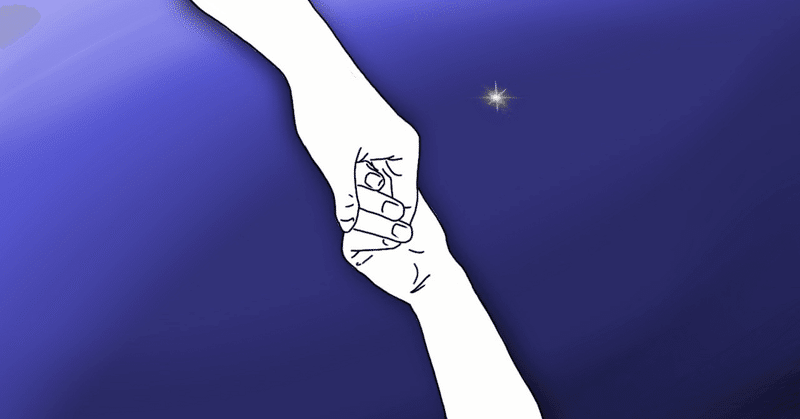
恋愛短編小説 「過敏しょうは手を握りたい」
高校の同じクラスのミヤコと夏祭りに来ていた。僕にとって彼女は初めての彼女だった。噂によるとミヤコはこれまでに十一人の彼氏がいたとのこと。十二番目の彼氏になることに、特に不安を感じるわけでもなかった。
本当の問題は、彼女と手を握ることができないことだった。
手を握ることができないのは、ただ緊張しているからではない。人の温もりや肌の感触が苦手で、接触すること自体が僕にとっての苦痛だった。
夏祭りの賑わう会場に向かう駅からの道のりで、ミヤコは何度も僕の手を取ろうとした。彼女の指が僕の手に触れる度に、僕は反射的に手を引っこめた。最初は彼女もそれを不思議に思ったらしく、首を傾げるばかりだった。だが、三回目のとき、彼女の表情が変わった。
「私のこと嫌い?」彼女は不機嫌そうに聞いてきた。
「違うよ」と僕は素早く答えた。それは本当のことだった。僕はミヤコのことが好きだった。でも、彼女に自分のこの「感覚」を説明する勇気がなかった。
祭りの夜は更けていく。屋台の明かりが賑やかに点滅し、遠くで花火が打ち上げられる音が聞こえた。僕たちは神社の境内に座り、周りの賑わいを眺めた。ミヤコは何かを考え込んでいるようだった。僕は、このままではいけないと感じ、勇気を振り絞って話し始めた。
「実は、触れ合うのが苦手なんだ。それが苦痛で、手を握ることができないんだよ」
「それなら、無理しなくていいよ。わたしと一緒にいてくれるだけで嬉しいから」ミヤコは少し驚いたように僕を見た後、優しい声で言った。「それに嘘じゃないってことはわかる、普通、男なら断らないから」と、ミヤコは笑っていた。
その言葉に、僕はほっとした。同時に、彼女への感謝と愛おしさでいっぱいになった。ミヤコは僕の手を取る代わりに、服の裾を握った。その気持ちは、僕にとって新鮮で、心地よいものだった。
「ありがとう」
その夜、僕たちはたくさん話した。
「彼氏に触れられないなんて、焦らされるのは嫌いじゃないよ」と、ミヤコは笑って冗談を言っていた。その言葉に少しの不安と期待を感じた。
「大丈夫な時もあるんだ、凍えるような寒い日は平気だったりするから」と、僕は返した。ミヤコは腹をかかえて大笑いした。太鼓の音や話し声や祭りのかけ声で、僕たちの話し声や笑いは周りには聞こえていなかった。周りには大勢の人がいるのに、今いる場所は僕たちだけの空間になっていた。
「それじゃあ、冬まで付き合うのは確定ね。冬になったら雪山に行こう」と、彼女は腹をかかえたまま言った。「これから冬が楽しみになるね」
「そうだね」と、僕は手を握れないことがよかったと思えた。
僕はミヤコに自分の過去や、感じていることをすべて打ち明けた。ミヤコは笑う時には腹をかかえて笑った。笑えない時は黙って話を聞いてくれた。
そして、あの夏の夜空の下で、僕たちは互いに寄り添いながら新しい約束を交わした。
凍えるような寒い夜に手を握ろう。
時間を割いてくれてありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
