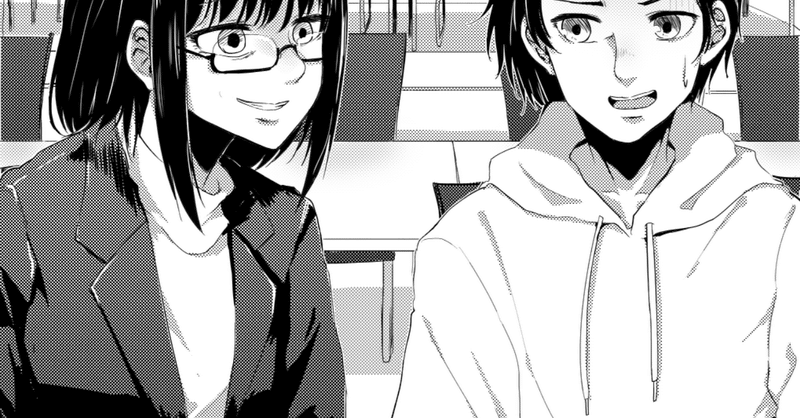
自然言語処理6
[鴨井] は?いまなんて言いました?
[友近] ルールなんて作ってるから駄目なんだよ。
[鴨井] いやいや、僕らが喋っている言葉にはルールがあります!国語とか英語の授業で文法を必ずならうじゃないですか。
[友近] ふむ、そうだね。だからこそルールベースといった考えが始まったんだ。
[鴨井] だったら…。
[友近] しかし、きみ自分が初めてしゃべった言葉はなにか覚えているかい?
[鴨井] なんの話です。
[友近] 私は”ママ”だったらしい。父はずいぶん悔しい思いをしたそうだよ。
[鴨井] 先生、それっていまの話と関係ありますか?
[友近] おおありさ。人間が母語を学習する課程には”ルールを習ったりなんてことはしない”ということは一般的な事実だろう。
[鴨井] え?
[友近] 赤ん坊に対して主語がどうの動詞がどうの、活用がどうのなんて言わないだろう?
[鴨井] それはまあ、そうですけど。
[友近] ここで考えられるのは言語の習得は圧倒的情報の入力が大切になる、という洞察だよ。
[鴨井] 情報の入力ですか?
[友近] まあ、そのアイデア自体が新しかった、というよりは計算機の性能がアイデアを実現できるスペックに追いついた、ということだろうね。
[鴨井] そんなにしょぼかったんですか?昔の計算機は。
[友近] 昔がしょぼいというよりは進化のスピードが恐ろしいというか。ムーアの法則、って聞いたことあるかい?
[鴨井] あー、あの一年半で倍になるとかいう。
[友近] そうそう。その言葉が正しいかはともかく累乗という恐ろしい速度で発展していくんだから恐ろしい話だよ。…そういえば計算量の話はしたことなかったかな?
[鴨井] あんまり。
[友近] まあ、今はおいておこう。とにかく、計算機の性能がアイデアを実現するに足るだけの能力を満たすにつれて新しい手法が流行りだした。
[鴨井] 新しい?
[友近] 統計的手法、というやつだね。それまではRAMやHDといったものの容量の少なさから敬遠されていた方法だが、統計によってより大きな規模のデータを扱うモデルが実用化された。
[鴨井] あれ、でもそれって…。
[友近] うん?どうした?
[鴨井] その統計的手法が実用化したのって結構前ですよね。じゃあその間にまた計算機の性能が上がってるじゃないですか。もしかしてまた新しい方法が実用化されたりするんですか?
[友近] お、鋭い!鋭いねぇ。そういう考え方は大切にしなさい。帰納法というやつだね。
[鴨井] 数学の証明で習った気がしますね、帰納法。
[友近] 考え方は応用が効くということさ。
[鴨井] 数学って役に立つんだなぁ。
私にカフェオレを飲ませるためにサポートしてみませんか?
