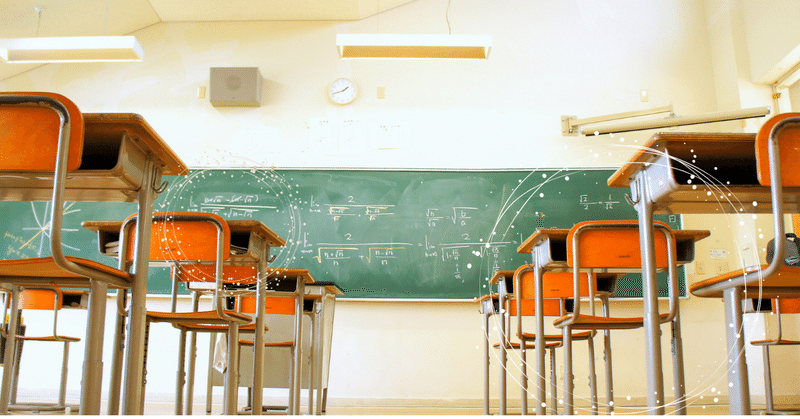
(思考メモ)教育の場でクイズ・パズルを使う際の、構成を分析してみる。
いきなり分類
教育の場でクイズ・パズルを使う際の、構成を分析してみる。
なお、ITを考慮すると人の代わりができることがあるので、ここではアナログ(例えば紙に印字されたパズルや問題を解く)という条件とする。
1.一人で行う(誰かが作った問題を解く)
2.一人が解き、もう一人が出題やヒントを行う
(個別指導の家庭教師のイメージ)
3.一人が講師役(出題やヒント)。残り多数が解く
(ひとまずは学校の授業のイメージ)
この3の「授業パターン」は、もう少し分類ができて、
3-1.実は前述2の個別指導が複数になってるだけ
3-2.講演タイプ(出題をするだけで、解答者個別の進捗などは基本気にしない)
3-3.対戦タイプ(解答者同士が、正解数や速さを競う)
3-4.協力タイプ(解答者は一致団結して、講師役が出すミッションのクリアを目指す)
などがあるかもしれない。
脱線:解答者の快感について
と、唐突に話の発端となっているツイート
(クロスワードや数独などの)パズルをする途中の快感を考える。
— 優さん(マサルさん)・Masaru TAKAYANAGI/高柳優 (@1day1quiz) October 17, 2023
やはりコツコツ解いていき、最後に完成するというのが醍醐味かなと思うので「じわりじわりと進捗が進んでいく」という点にあるのかなぁ?#へまさるメモ
(続く)
せっかくだから、全文書き写す。
(クロスワードや数独などの)パズルをする途中の快感を考える。 やはりコツコツ解いていき、最後に完成するというのが醍醐味かなと思うので「じわりじわりと進捗が進んでいく」という点にあるのかなぁ?
で、これが「50問クイズ」(複数人で遊ぶ早押しクイズではなく、試験の一問一答問題集のイメージ)の場合、(各クイズの面白さは置いといて)システム上、どうやってその快感を得られるのか? ITならば、正解に応じて得点や進捗がわかる(QMAの検定などがそれかな)けど、紙ならどうなる?
「正解の番号を塗りつぶし、最後に絵が出る」とかはできるけど、前述の数独などのパズルと違って「どうやって間違いに気づくか?」「途中からの修正が可能か?」などが課題になりそうな気がする。
分類から、解答者の快感を考える
前提として、出題者や講師役は、解答者に快感を与えたいことを第一目的とする。
(純粋な学習目的の場合、ツラさを感じさせてでも覚えさせたいなど生じるので、そーゆーのは除く)
前述の中で、
2.一人が解き、もう一人が出題やヒントを行う
(個別指導の家庭教師のイメージ)
はそれがとてもしやすい。
なので、複数解答者の授業であっても
3-1.実は前述2の個別指導が複数になってるだけ
も同様(って現実問題、個別指導の同時進行での複数化は相当大変だけどね)
3-3.対戦タイプ(解答者同士が、正解数や速さを競う)
3-4.協力タイプ(解答者は一致団結して、講師役が出すミッションのクリアを目指す)
は、戦う相手が同じ解答者か・講師かという違いはあるが、いわゆる「相手より勝つ」を目的としている点では近いのかも?
いや、ミッションというのは「相手」なのか? うーん、少し悩んできたぞ。
と、こちらも話が長くなりそうなので、一旦ここまでにしよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
