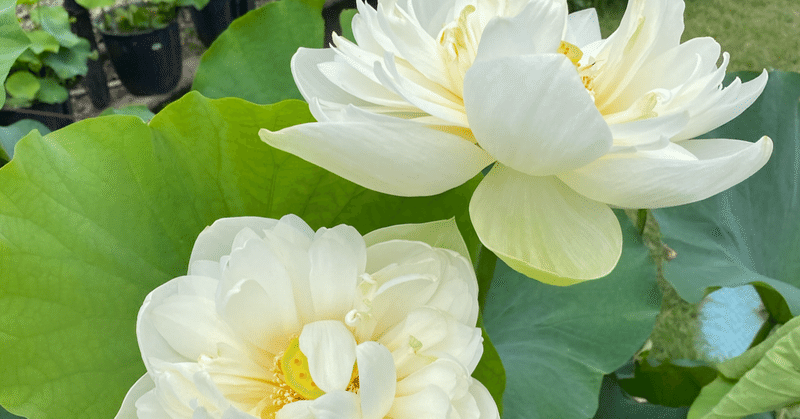
【二人のアルバム~逢瀬㉑~唯一無二~】(フィクション>短編)
§ 1. ミューズ
彼女と夫婦になって、彼が気付いたのは、2人で築いていく事業はひどく彼にとって、簡単に成長した事だった。
何故か不思議になる程、彼は、彼女とプライベートで一緒にドライブしたり散歩している時に、彼女が、彼女の声が何故かが引き金になって、彼の頭に仕事の内容が浮かぶのだ。
然も、この会話の後に時間を置いてから、よくよく考えてみると、不思議と事業展開で考えた事もない様な方法論や、自分でも大胆な営業方法などがいとも簡単に想像出来てしまう。
オフィスで共に時間を過ごしていると、彼女が如何に不要な事務処理作業をしていて喋っていなくても、彼女が真っ直ぐと彼の眼を見て話を聴いてさえいれば、彼の頭は、ひどく難しい客先へのコンサル回答が容易く浮かんだりする。
何かにつけて、彼女が彼の話を聴いていて、後に二人でその事について彼が話をして、彼女が頷いているだけで、彼は自分の中で、仕事について沢山のアイデアが浮かび、前に動かす事が出来なかった考えの展開が、妙に現実味を帯びて容易く動かせる気がしたり、そのアイデアで考え付いた事がさらに花開く気がする。とにかく、ポジティブになれるのだ。
「何?」
はっとして、彼女を見ると、彼女が頭を傾げていた。
「どうなさったの?」
「いや…」
彼はニッコリした。
「何でもない」
「大丈夫?」
「うん。大丈夫だよ」
「良かったわ」
彼女が微笑んで、彼は心がやわらんだ。
彼女の口にする言葉一つで自分が上下左右にいつでも飛んで行ける様だった。
「なんて幸せなのだろう、俺は」、
彼は思った。
「彼女は俺のミューズだ、俺の女神様だ。俺だけの。
—親父にとって美倭子さんがそうであった様に」
§ 2. 唯一無二
彼の父が久しぶりに電話をしてきた。
「どうしている?仲良くやってるか」
「お蔭様で。とても仲睦ましくやってるよ」
「そりゃ好いね」
と父が笑った。
「会いに行っていいかい、話がある」
「今夜?まだそっちへ行って跡を継ぐのは—」
「瑠衣が危篤だ」
「...そりゃ知らなかった」
「あぁ。今病院でね。主治医の市川医師と話して来たよ。幸子は泣いてる」
「そりゃ、そうだろう。…ん。…で、先生は何て言ってるの?」
「もたないだろうと。今まで持ったのが奇跡だったしなぁ」
「瑠衣は?まだ意識はあるの?」
「いや。俺等が着いた時には、意識はなかった。酸素吸入してるし、今、俺等の着替えを取りに戻っているところでな」
「あぁ、そうなんだ。—俺達も行こうか?」
「いや、忙しいところ悪いが、俺等が帰宅するまで、鎌倉の方に週末に番を頼みたい」
「分かった。任せてくれ」
「悪いな」
「大丈夫。こっちへ寄りなよ。彼女、昼と夜の弁当作ってくれると思うよ」
「有難いな」
直ぐに電話の内容を纏め、彼女に連携して
「悪いが親父達の弁当をお願いできるか」
と依頼すると、彼女は快諾した。
「勿論よ。お父様に、こちらが金曜の夜から行きますからってね。お父様がこちらに寄られるなら、出るお時間をお教えくださいって、おっしゃってね」
「うん。訊いたよ。結構早めに出るようだ。車の中で呑む水筒やボトル、お弁当は簡単に食べれる奴にして…。あ、そうだ。今日は物件見せる奴、あるのかな」
「管理会社の間波磔さんから週末に見に来たいカップルがいるんで午後にいらっしゃる予定です、ってお話だったから、家族の急病で来週まで待たせて悪いけれど、って頼んだので、一緒に近隣みて貰って、話しして、中を見せて、あとは来週って事にしようかなと」
「好い案だね。兎にも角にも間波磔さんにはあとでお礼しないとな」
「はい。お持たせのメモして置きます」
「助かるよ」
彼女はクスッと笑って恥ずかしそうにどういたしまして、と言った。
二人は事前にこうして連携して置くと、各々、当日のスケジュールを頭に、相談した通り、オフィスの方へ行かずに自宅でリモートワークする、とした。
管理会社の彼の会社の担当者、間波磔さんに今日は家庭の事情で、親類が病院に入院し、急遽スケジュールを変更しないとダメなので、明日以降は数日不在になるので、頼む、と依頼して、彼と前の晩に相談した通りに動いた。自分達の昼食を用意し、トランクに彼と彼女の着替えを用意し、彼の車に着替えやトランクを先に詰め込み、猫のブルーのケージバッグを用意して、いつでも行ける用意を万端行い、昼過ぎには、彼の両親の車内で食べられる弁当を昼食と夕食分両方を用意した。
彼は午前中にすべての午後の予定を月曜以降に廻して、スケジュールを再設定した。スケジュールが再設定された後、ソレを彼女と電話で確認して、話している内に、彼女が用意しているアパートハウスに戻ってきた。
電話を切りながら、彼女が彼に
「お帰りなさい」
「あぁ、有難うな、今日は忙しくてさ」
「分かるわ。お疲れ様。お父様、大変ね」
今度はテーブルに出したランチを彼に用意してやった彼女は彼を癒した。
彼は有難く頷いた。
「あ~、腹減った」
帰宅すると、彼女はテーブル上には、一つ一つがサランラップに包まれたおにぎりが沢山の野菜と鶏肉がごった煮されたスープの横に、並んでいた。
「うわ~っ❣旨そっ❣」
旨そうな匂いと、腹ペコの自分の右手が掴んだ、木のスプーンでスープを飲み始め、左手でおにぎりを一つ選んで、慌ててがっついて食べ始めた。
彼の横に席を取った彼女は、
「慌てないで、あなた。ゆっくり戴いてくださいな」
と彼の背中を撫でて、頷く彼に水のグラスを手渡した。彼はグラスを貰って、水を呑み干した。
「オヤジの弁当は?」
「作ってあってよ。昼が薄いトーストサンドイッチで、チキンと野菜のスープ。夜が五目混ぜご飯。おつゆ付。お野菜満載だし、多分、お好きになっていただけるメニューだと思うわ」
彼は、手でサンブアップして、頷き、食べ続けた。
午後2時を過ぎたあたりに彼の父から彼に電話が入った。3時にはこちらに着くだろうとの事だった。彼はいつも通り、サポート役に廻り、病院名を訊いたり、瑠衣の介護施設の担当の名前を訊いたりして、状況進捗を行った。
電話を終えて、彼がメモ帳を見直しながら、彼女にその他の情報をくれた。
「あとさ、大塚が電話くれて、俺達が着くまで出るのを待っててくれるらしい。明日朝に妹さんを迎えに行って、別の病院へ移転らしい」
「まぁ」、
と彼女が声を上げた。
「転院なのかしら、何か、手術なのかしら。…どちらにせよ、お家で休むワケじゃないのね。お気の毒に。大変だわね」
「そうなんだよね。寒くなったり、温かくなったりで、病身には響くよ」
「本当に」
食後のコーヒーを呑んでいると、彼の父がアパートメントハウスに一人で到着した。窓から猫と一緒に眺めていた彼女は、パーキングで車を降りたのが父一人で助手席に父のほかに誰も載っていない事が理解できた。
「お、お父様、お一人?」
彼は、ソレを聴いて、彼女の後ろから下階のパーキングスポットに駐車された父の車を見た。
「お義母さん、嘆いてるって、親父言っていたな」
「私、何て言ったら…」
「思ったままに、お見舞いして上げればいいよ」
彼は彼女の肩をむっちりした掌で揉んだ。
「ありがと、色々やってくれて、奥様」
「あなたったら…こんな時に」
「二人には、幸せな我々を見るのは恵みなんだ」
「うん」
彼が彼女を後ろから手を廻して包み込んで、彼女が猫を撫でながら、暫し、2人と一匹はずっと下階を見ていた。
と、ドアベルが鳴った。
「お父様、大変ですわね。何でもおっしゃってくださいませ」
「あぁ、有難うね」
テーブルに一人で座った父は、弱い微笑を見せてくれた。挨拶する猫の頭を撫でてやり、彼女の作ったランチに少し手を付け、有難う、と弱々しく言ってくれた。これから、長時間の運転が父の年齢には辛そうに見えた。
父の話では、義母の幸子は病院近くのホテルに宿泊して、病院に通い詰め、瑠衣の傍に張り付いてたらしく、この週末は疲れてしまい、ホテルで
「少し休ませて」、
と言ってベッドに倒れ込んでしまったらしい。
「あなた」
彼女が彼を呼んだ。
彼が彼女の近くに来た。
「お二人を一緒に連れて行って差し上げましょ」
「そう言ったんだがね…」
「好いんだ、俺の言う事しかあいつは聴かない」
彼の父は彼女に詫びて、自分が幸子を連れて病院へ帰るから、と説明した。
お弁当を包みながら、彼女はどうしたらいいか、考えていた。
あんまり彼女が踏み込むのも、彼の両親には失礼だし、邪魔なだけだろう。
彼も、お父様の下向きな目線を見詰めて、
「おやじ、ホントに大丈夫か、俺等でホテルまで連れて行けるし…」
「いや」
父は手を挙げて、礼を言った。
「有難う。大丈夫だ。すまないが、一時間ほど、仮眠する。寝させてくれ」
「あぁ、好いよ。俺のベッドを使ってください。ほとんど使わないんで」
彼女も彼の父に手を貸しながらベッドを用意し、彼の寝間着を貸してやり、60分後に起こしてくれと父から希望があり、はい、と答えた。
ワンルームだが、彼のベッドの横に大きなパティッションがあり、だいぶ楽に眠れるだろうと彼女は思った。
彼は、仕事でメールを一本出してから、駐車場へ降りて、車にいろんなものを積む、として、5時には出よう、と提案した。父の後をついて運転し、時間を取って、お茶をさせたりしよう、と彼は考えている様子だった。
瑠衣は幸子と父が再婚した当時に生まれた娘で、身体は両足を小さい頃に小児まひで痛め、なかなか介護や支援施設の外へ出してやる事が出来なかった。
長い間、病室で暮らし、そのせいで明るい瑠衣も、段々生命力に翳りが出ていた。幸子は40にもなる娘の瑠衣を幼い娘の様に甘やかし、溺愛していた。学校にもやらず、自分一人ですべてを背負っていた。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
