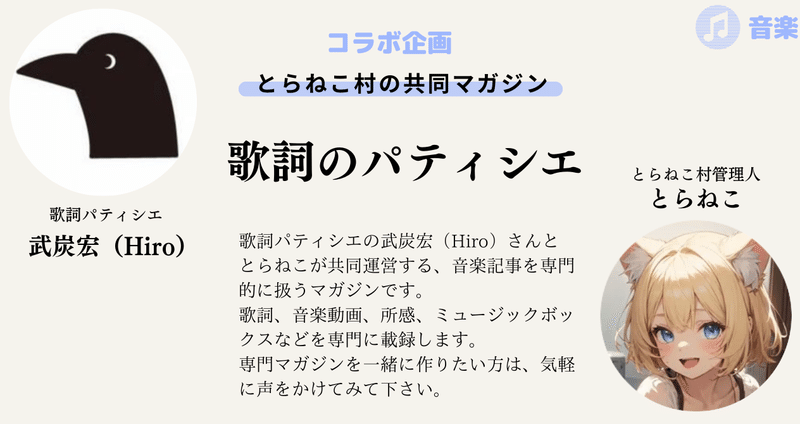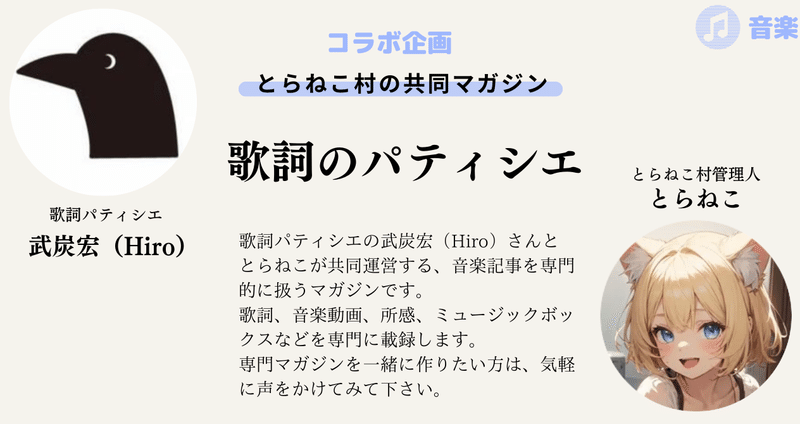夜風と流れ星が奏でる歌 -プッチーニの魅力【エッセイ#58】
『蝶々夫人』や、『トスカ』といったオペラで有名なプッチーニは、最もロマンチックな夜を描写できる音楽家の一人だと思っています。お涙頂戴のオペラ作家と思われがちですが、とてもそれだけには収まり切れない、濃密なロマンと高度な音楽性を持っている、非常に面白い作曲家です。
プッチーニ作品の夜は、二種類あります。一つは、人々が夜の街路に出て思い思い歩いている雑踏の夜。何といっても、『ボエーム』の第2幕、クリスマス・イブのカフェ前の街路。物売りや子供連れの母親や、恋人たち、子供たちがそれ