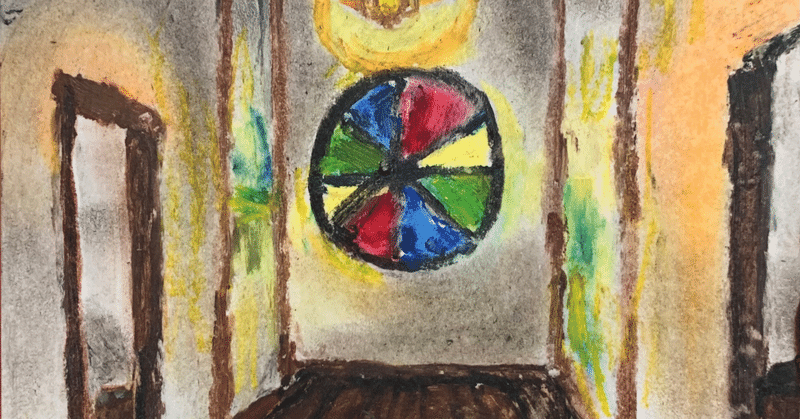
しろ長くつ下のピッピ (1)
「りょう太、ちょっと、ちょっと来てぇー!」
リビングで、姉のいちかが素っ頓狂な声を上げた。
僕はびっくりして、踊り場まで昇りかけた階段をとって返した。
「犬だよ。犬!」
いちかが、リビングテーブルに覆いかぶさってわめいている。
「食パンじゃないよ、この箱! 開けてびっくりよぉ〜」
その声につられ慌てて箱を覗き込んだ。てっきりデニッシュの食パンだと思っていた細長い箱。その中で、大きな深紅のリボンを首に巻いた仔犬が、居心地悪そうにゴソゴソうごめいていた。
「うわっ、ビーグルだ。どうしたの?この犬」
「知らない!父さんに聞いてみてよ」
僕は困惑気味に父さんを振り返る。二人の会話が聞こえない筈は無いのに、サンルームの揺り椅子に腰掛けて、知らん顔でタバコを燻らしている。
父さんは、時折会社帰りの手土産に、子供達の好きなスイートデニッシュの食パンを買ってくる事がある。
今日はデニッシュの食パンでなく、子犬を詰めたこの箱と鞄を持って、帰宅ラッシュの電車に一時間半も揺られて来たという訳だ。
僕が顔を近付けると仔犬のパニックが激しくなった。「ムギュウ」と切なそうに鳴きながら、箱のふちをカリカリと引っ掻いている。出してくれ、と言う要求なのかと思って、僕は仔犬の両脇を持って抱き上げた。すると今度は降ろせと言わんばかりに、首をグリングリンと回して上体をくねらせる。
いちかが、歌舞伎の連獅子の首振りみたいだと言って笑い転げた。
床に降ろしてやるとアンテナの様な尻尾をピンと立て、深紅のリボンを引きずりながら忙しなく匂いを嗅ぎ始めた。
「あー、もしかしておしっこかも。ペットシート、ペットシート」
いちかが大慌てで、箱の中に敷かれてあったシートを床の上に広げると、仔犬は一目散に走りより、後ろ足をぺたりと広げて放尿した。ピンと立ったままの尻尾がプルプル震えている。その差し迫った様子がおかしくて、思わず笑ってしまった。
「女の子ちゃんなんだ。びっくりして確認する間もなかったもんね。」と、いちかが言う。
「この小さな頭で、結構お利口さんなんだ」僕はおとなしくなった仔犬の頭を撫でてやる。 ( 小さな女の子ちゃん)は眩しそうに二人を見上げ、まだ未熟なキンキンした声で吠えた。
歌舞伎役者の様な太くて濃いアイラインが、張りのあるアーモンドの形をした目を縁取っている。
奈良美智の描く、ちっと不敵な女の子の目にそっくりだ。小さいのに一端の、なんと不屈な顔をしているのだろう。
つま先から膝まである純白の毛並みは、まるで四肢に白いハイソックスを履いたようだ。 同じ長さで一毛の乱れも無く、くっきりと上体の毛色から独立している。
仔犬は、( 何が起きたのか解らない。この状況説明してよ。)と言いたげに足を踏ん張って、臆することのない眼差しでグイと見上げている。
——僕たちだって解らないんだよ。なぜってこの家には——
心の中で呟きながら子犬を抱き上げようとした時、バタバタと足音がして、風呂上がりの母さんがリビングに飛び込んで来た。
「さっきから何の騒ぎ?犬、犬って………」言いかけた母さんの足下に仔犬がチョロチョロと歩み寄った。
「何、このリボンの犬は!」
信じられないと言う表情で、母さんは僕に詰問の目を向ける。
いちかが、母さんに目配せしてサンルームのほうヘ視線を誘導した。
「な、可愛いだろ?」
それまで、子供達の様子を面白がって傍観していた父さんは、慌てて椅子から体を起こして取り繕った。
全てを察した母さんは、憤然と抗議の口火をきった。
「もうぉー、冗談でしょ。うちには今、二匹もいるのよ。二匹も!」
そう。母さんの言うとうり、この家にはすでに、ミニチュアダックスのリーナと、いちかが拾ってきた外飼いの大きな雑種、ダンが先住しているのだ。
「一体誰が面倒見るのよ!」
父さんに抗議する母さんの声が、怒ると言うより嘆く様に聞こえた。朝夕の散歩は母さんの仕事だ。餌をやるのも、糞尿の後始末も、すべて。
いちかも、僕も、仔犬をかまう手を止めた。父さんと母さんの攻防が、激しさを増して来たのだ。
「だったら、ダンを捨てろ!どうせ拾った犬だろ」
「ダンを捨てろですって!よくそんなこといえる!」
「じゃあどうしろと言うんだ!」
僕といちかは顔を見合わせた。誰かさんの、状況を考えない無責任な行動が、全て混乱の原因なのに。これは父さんお得意の常套手段だ。身勝手に振る舞っては周囲を巻き込み、結果犠牲を強いて、自分は責任の圏外へ逃れてしまう。
「だったら返すか!」
「引き取る訳ないでしょ!」
「今買って来たばかりだぞ!」
父さんは、まるで未使用の商品の様に言う。
「じゃあ電話して聞いてみろ!」
「それはそっちの仕事だよ」冷ややかに、ぞんざいに母さんは言い放ったけれど、何を思ったのか私が電話するからと言って受話器を取った。
二、三分のやり取りの後、母さんは大きなため息をついて受話器を置いた。それからおもむろに、父さんに向き直り、
「よく聞いてくださいね。一度、人間の生活圏に触れた犬は、病気の問題もあって返却は固くお断りしますって。引渡しの際に、お伝えした筈だって」と、一層冷ややかさを増した声で父さんを直撃した。
「そんな事当たり前だろ」と、自分の非には触れず話をすり替えてしまう父さんを横にらみしながら、いちかが「思考回路の乱れ。理解不能」と小さく囁く。
喧騒をよそに、仔犬は僕の懐で穏やかな寝息を立てていた。
三匹は無理。絶対無理と母さんは言う。勿論、いちかも僕もそう思う。
「じゃ、どうする?」
「家で飼えないのなら、せめてこの仔の幸せを見届ける責任は負わなくちゃ。近所をあたって、貰ってくれる人探してみようか。」
幸せを見届ける責任か……。母さんの言葉を反芻しながら、ほっとした様な、がっかりした様な複雑な思いが交錯した。
僕の腕の中の小さな温もりは、もうすっかり馴染んでいるのに。
いちかは、自分が拾った犬ですら母さん任せなのだから、あれこれ言う立場では無いと言った。
「俺が買って来た犬だぞ、俺の金で!12万もしたんだぞ!」
突然、にがり切った表情で父さんが言う。仔犬の処遇に、ようやく解決の糸口がついた瞬間のひと声だった。
「それなら貴方が面倒みますか?」怯まず母さんは抗弁する。
「うるさい!お前たちの勝手にしろ!」いきり立った父さんは、どすどすと大きな音を立てて、2階の自室に上がってしまった。
「そうかあ、お前12万もしたのか。父さんの気持ち解らない訳でもないけど」
「自分が悪いんだよ。でも12万でしょ。その半分でいいから欲しかったな」
いちかは調子がいい。
仔犬の価格はサラリーマンの我が家にとって、捨て金にはできない金額だ。もっとも父さんの小遣いなのだが、そんなことには容赦なく母さんの決意は変わらなかった。
夕食の席に、父さんはついに姿を現さなかった。ひと騒動あるたびに繰り返される光景だけれど、今日はいつに無く気まずい思いが残った。父さんは、父権を振りかざしてでも理不尽を正当化することがある。いつだってその矢面に立つのは母さんだが、決して翻弄されることは無かった。今回の事も事後承諾で何とかなると思っていた父さんに、撃沈の一発を喰らわせた「貴方が面倒みますか?」の一言。
悪がまいするだけで、世話らしい事は一切しないのだから、父さんにとっては究極の忌み言葉なのだ。
テーブルには手付かずの一人前が、団欒を拒否する様に残されていた。
仔犬は、お湯でふやかしたドッグフードをぺろりと平げ、リーナのキャリーバックの中ですやすやと眠っている。
リーナは、ドームハウスから一歩も出ようとせず、入り口からすっかり白くなったあごを突き出していた。気になる新しい匂いを嗅ぎ分けて、ピクピクと鼻腔をうごかしている。いちかや僕が声をかけても、目だけをうごかしてプイと横をむき、そのうち背中を向けてしまった。
風呂から上がって、僕はキャリーバックの中を覗いた。仔犬はピンク色のお腹を見せて安心し切った様子で寝ていた。自室に引き上げ、窓のカーテンを閉めようとした時、犬小屋の前でちょこんと座っているダンの姿が目に入った。ぽつりと降り始めた雨の中で、まるで聞き耳を立てる様に首を傾げたダンのシルエットは、黒い銅像の様に、いつまでもじっとしたまま動かなかった。
その夜、仔犬はキャリーバックに入ったまま、母さんの枕元で眠ることになった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
