虹色に塗りつぶされていくファッション
この記事での主張はあくまでダイバーシティの推進や差別の撲滅といった価値観の政治利用/利益利用がファッションというフィールドにまで入り込み、そのカルチャーの自由を蝕んでいることに対して危険だと主張しているもので、マイノリティに対する差別に対して賛同するものや、ダイバーシティが世にとって不必要な価値観である、というものではありません。よく読めばわかると思いますが、分量が多いので先に記載しておきます。

ヴァージル・アブローがヴィトンのディレクターとして抜擢されてから早一年が経った。
デビューランウェイとなった2019ssコレクションで、ヴァージルは"オズの魔法使い"の物語に、自身のこれまでの人生をオマージュして捧げた。
ファーストルックから17ルック目まで、全身白のスタイリングに身を包んだ黒人の男性モデルが、レインボーに彩られたパレ・ロワイヤルを闊歩した。
その後のルックは序盤白を始めとし、茶色、グレーといった色合いから、後半に向かうにつれ彩り豊かなルックを織り交ぜながら、ラストは虹色に光を反射するポンチョでショーを締めくくった。

ルイ・ヴィトン史上初の黒人デザイナーとなったヴァージルはショーのフィナーレで人目も憚らず涙を流した。
オズの魔法使いの物語の中では、ドロシーがライオンやブリキの木こり、かかし達と手を取り合いエメラルドの都を目指す姿が描かれている。ドロシーは自分が本来在るべき場所であるカンザスへ戻るために、姿形が全く異なる仲間達と迫り来る困難を乗り越えようとする。
ヴァージルはこの物語に自らとモデル達を投影した。自身がこれまでに抱えた葛藤や直面した困難、差別、苦悩をこのランウェイに昇華するとともに、自らがフランスの老舗メゾンのディレクターとなることで、新たな時代の到来を自身の仲間達に告げた。自らが表現者となり、マイノリティ・差別の檻から全ての弱者を解放し、全ての者が手を取り合う事をランウェイを通じて表明した。
このランウェイは革命だった。ショーのパンフレットにはモデル達の出身国と世界地図が描かれていた。

ダイバーシティ/多様性という言葉が市民権を得て久しい。世の中から実際に差別がなくなったかという議論は別にして、現代では多様性は最も尊重される社会的価値観の一つとされ、また差別についても早急に解決が目指されている社会問題として扱われている。最早、そういった価値感を持ち合わせない人間・団体は過去のものとされ社会から見放されつつある。
https://www.fashionsnap.com/article/2018-02-14/burberry-rainbow/
ファッションについても同じことが言える。
ヴァージルのヴィトン19ssとはかなりコンテクストは異なるが、クリストファーベイリーが手がける最後のコレクションとなったバーバリー19ssも虹色をテーマカラーに多様性を謳っている。ロエベも虹色の広告を打ち出したキャンペーンを行っていた。
ファッションの中にも、多様性を受け入れ、全ての人たちが認められる、誰もが差別の被害者になることがない世の中を目指す動きは間違いなく現れている。
多様性を受け入れる世の中は確かに美しい。全ての人が自分から見た全ての他人を受け入れ、全ての価値観がフラットに、評価されることもなく、受け入れられることもなければ拒絶されることもない。「みんな違ってみんな良い」を地でいく世界観である。
趣味も、性的趣向も、ひいては主義主張も、全ての価値観が個人の尺度に任され、消化されていく。たとえその主義主張が誰かを傷つけようとも、その傷つく側のプールに身を浸かる人達が、その主義主張が別なプールにあることを理解し、自分の主義主張が傷つくことすら別次元の事象として解釈する。
これは本質的な「多様性に対する理解」だと自分は信じている。実質的には人間には感情があり、自分の主義主張が傷つくことを許せない感情を持ち合わせている人がほとんどで、この本質的な多様性の理解を世の中の通例として実現することは極めて難しい。が、目指すことには意味があると自分は考えている。そして、アート/カルチャーはその多様性の理解を最も高次元で実現する唯一無二のユートピアであり、拠り所であるとも思う。(当ブログではファッションはアート/カルチャーのサブディビジョン=1区分という理解で議論を展開していく。)
この世の人全員が本質的な「多様性に対する理解」を持つことが不可能な現実である以上、誰も傷つけることのない表現はこの世には存在しない。しかし、アート/カルチャーはアカデミック、ポリティカル、またはソシオロジカルなコミュニティと違い、それぞれの表現者の主義主張が全ての人に対して自由に投げ込まれ、それを受け取るか受け取らないかもまた投げかけた人間以外の全ての人の自由に委ねられている、極めて多様な世界観だと言える。
ある表現が誰も傷つけないということがありえないことだったとしても、アート/カルチャーというコミュニティについて言えば、上記で定義するような本質的な多様性にかなり近い環境がそこにはある。むしろ、本質的な多様性が担保されている状態こそ、アート/カルチャーというコミュニティの本来あるべき姿かもしれない。
自分はそう言った極めて自由で多様なアート/カルチャーが好きでたまらない。自分が如何なる考えを持とうと、如何なる表現を行おうと、許され、批判され、共感され、拒絶される。そしてどのリアクションが「良い」とされることもない。乱暴で無秩序である一方、なんて自由で多様な世界観なのか。

しかし、現代での多様性の普及において重要かつ危険なのは、現代の世の中ではポリティカルコレクトネスや全く新しい価値観が力を持つことで、この多様性のあるべき姿が捻じ曲げられつつあり、アート/カルチャーの中からも「本質的な多様性」が失われつつあるということだ。
前述した通り、現代では多様性という言葉は広い認知を得、社会的通念として普及しつつある(あるいはその道の活動家からすればまだ黎明期の段階かもしれない)。その動きによってセクシャルマイノリティやレイシズムによって差別されてきた人達の理解が深まり、少しでも世の中に「本質的な多様性」をもたらすような結果になるのであれば非常に結構である。
しかし裏腹に、その概念が社会的通念となる過程の帯びる熱を、様々な方法で利用しようとする輩が存在することも確かだ。特にこの場で自分の政治的な思想を述べるつもりは一切ないが、自らの選挙活動の公約の中で多様性だの男女平等だのと掲げている人間の一体何割が本気で多様な世の中を望んでいるのか?ダイバーシティを推進する事業を行ったり、女性雇用を躍起になって増やそうとしている企業や法人の活動の一体どれくらいが、多様性の必要性について心から賛同しているのか?「君付け、ちゃん付け」を無理矢理やめることに、一体どのくらいの意味があるのか?本当は必要性よりも「とりあえずやっておかないと社会的にまずい」とか、「多様性に賛同しておけば支持率が上がる」とか、そういった邪な思いとともに「多様性」の立て看板を立てている人間は少なからずいるはずだし、感情論になってしまい申し訳ないが自分にはそうとしか思えない人間のほうが目につくのだ。そもそもそういった議論にすら及んでいなかった多様性、もしくはダイバーシティという話題が、そういった利用も含め表立って考えられるようになったこと自体は良かったのかもしれない。だがそれは本質的ではない。
そしてこの問題は政治や企業活動を超え、とうとうファッション、ひいてはアート/カルチャーまでをも虹色で染め上げようとしている。この二つのキャンペーンが本質的か否かの議論は別にして、冒頭のロエベやバーバリーのような異常なほどに虹色を前面に押し出した広告がある。
昨今アパレルの中に溢れている虹色は本質的なものなのだろうか?現代の洋服は多くの場合ユニセックスでなければならないのだろうか?メンズとウィメンズのコレクションをまとめて発表しなければならないのだろうか?

ファッションにはトレンドというものがあり、各ブランドがこぞって近しい要素を取り入れたランウェイを披露することは確かにある。しかし、トレンドとこのダイバーシティムーブメントが決定的に違うと思われるのは、昨今のアパレルに溢れる虹色には実は自由が存在せず、非常に政治的である点だ。
多くのブランドが社会の波に流されてダイバーシティムーブメントに参加し、社会からの批判に対してバリアを張る。この社会の流れは英語に直せばトレンドという単語があてがわれることになるが、我々がファッションを取り扱う上で用いられる意味とは全く違う。これはポリティカルコレクトネスがアート/カルチャーに対して突きつけてきている「正解」をなぞっているだけだ。
ポリティカルなものに限らず、コレクトネスはある行動を起こすことについて「正解」を押し付けてくる。この概念は確かに政治生活や企業生活の中では和を乱さないために重要な存在であることは間違いない。ある種の気遣いのようなもので、冒頭で既述の通り自分の主義主張が傷つくことを許せない=「分かり合えないことを前提にする」ことができない人がほとんどの世の中で、コレクトネスというルールは人間生活の中で何が許容されるべきか、またはされないべきかを誰が決めたかは知らないが、定めている。しかしそれは同時に自由を縛ってしまう。正解以外の回答は許されない。
もしそれがファッション、アート/カルチャーの世界線を越えようとしているのなら、自分は絶対にそれを許すことはできない。本質的な多様性が唯一存在する理想郷を虹色で塗りつぶすことは許されてはならない。そしてアート/カルチャー、ファッションというコミュニティの中でも世界的に名を知られているブランドのような、声の大きい者がダイバーシティを政治利用することは絶対にありえない。そういった社会通念の正解的用法について警鐘を鳴らし、皮肉り、時には称賛する、そういったアート/カルチャーの本来あるべき自由で多様な、正解など存在しない世界としての姿を、正解という概念をコミュニティに持ち込むことで捻じ曲げることになるからだ。
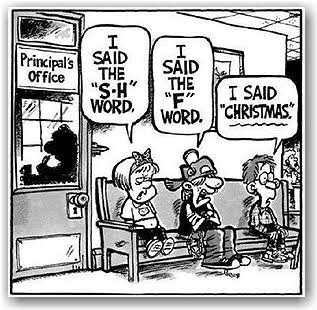
ファッションは、それぞれの時代から何かを解放することで発展を遂げてきた。ココ・シャネルは女性らしさという固定観念から女性を解放した。マルタン・マルジェラは世に溢れる様々な物体を与えられた役割や用法から解放した。エディ・スリマンは極端に細いスタイルでかつてのマスキュリンなイメージから男性を解放した。そういった服作りにおける既成観念や、一般的と考えられていたイメージを切り崩すことこそがファッションの発展であり、モードだ。そういったファッションの世界観、文化成長の構造は、自由な発想や表現が許されていなければ不可能だ。しかし、ポリティカルコレクトネスの流入や、社会通念への迎合はその自由を奪いかねない、すなわち、それを持ち込めばファッション、ひいてはアート/カルチャーはお終いかもしれない。

自分は1910年代から女性をかつての女性のイメージから解放したココ・シャネルのルックも、1948年に発表されたクリスチャン・ディオールのコルセットのルックも、両方が美しいと思う。
ディオールのコルセットは、女性の解放を自身の使命としてきたココ・シャネルにとってはありえないものだったはずで(もしかすると、現代から見てもすでに許されないものになってしまっているかもしれない)、当然シャネルはこれに対して反発した。しかし、結果として両者の作る服は互いに大いに影響を与え、1950年代に渡るまでファッションというカルチャーの成長に多大なる貢献を果たした。これは当時からファッションやアートではある種「何を主張してもいい」的な世界であり、女性をこれまでの社会観念から解放するシャネルの服も、かつての女性美という十字架に磔にするディオールの服も同時に成り立っていたという点で非常に多様であると言える。
シャネルもディオールもアウトプットだけを見れば相容れないが、かといって彼らの服作りはお互いを踏みにじるために作られているわけではなく、あくまでリスナーに対する主張だった。

そして、自分は最も本質的な多様性を体現する服作りをしているのはコムデギャルソンだと思う。1980年代のボロルックも、当時社会通念上きらびやかな者が良いとされていた時代に、質素な色使いでボロ布のようなコレクションを発表し波紋を呼んだ。このコレクションは「ヒロシマルック」などと揶揄され不謹慎だなどとされたが、むしろボロルックによって戦争や政治的な事柄についてファッションを通じて主張することを可能にし、ファッションをアート/カルチャーの存在する次元へとぐっと近づけたとすら思う。
1997年に発表されたこぶドレスはドレスというにはあまりにも歪で、まさに男性用でも女性用でもない、誰用でも何のためでもない服で、そもそも服なのかという見た目だが、自分はこれは最も多様性の本質に近い服だと思う。
性別ではなく、人かそうでないか、服なのかそうでないか、そういった次元の問いかけをこのコレクションは自分に投げかけてくる。ユニセックスの服とか、虹色の服とか、男女混合のコレクションとか、そんな甘ったれた問いかけで本物の自由が掴めるか、という川久保玲の怒りのようなものすら現代から見ると感じ取れてしまう。
本来ファッションの、アート/カルチャーの世界観=本質的な多様性が存在しうる世界では、こういった主張、クリエイションこそが価値のあるものではないかと自分は思う。(あくまで自分の中で、である。再三いう通りアート/カルチャーの中に正解や確実に価値のあるものなどは存在しない。)
自分が仮に今デザイナーだったとしたら、きっとポリコレまみれの多様性からファッションを解放出来るような洋服を作ると思う。実際には洋服を作れる技量はないが、文字を連ねることはできるので今回こういう記事を書いた。読んでくださる方の中には様々な考えを持つ人がいることも重々承知で、この記事の内容に怒りを感じる人ももしかしたらいるかもしれない。それでも自分は今のファッションの中での多様性の取り扱いは本質的ではないと主張したい。
本質的な多様性が生きるファッションやアートというキャンバス上では、何も虹色が最も美しい色だとは、自分は思わない。
