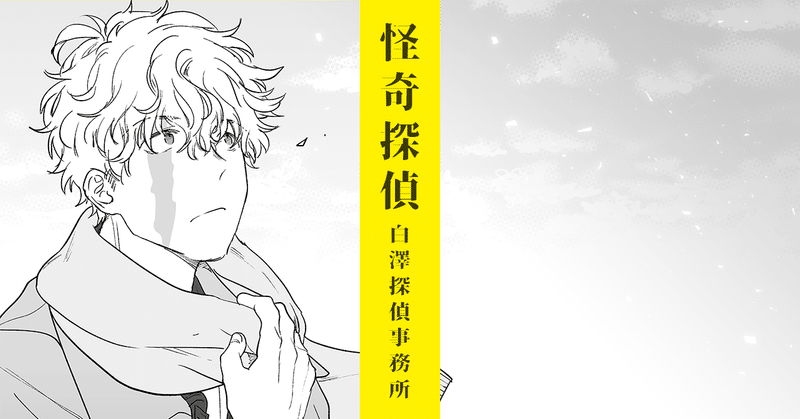
【小説】#7 怪奇探偵 白澤探偵事務所|春を呼ぶはなし
あらすじ:春の足音が聞こえ始めたある日、白澤から東北へ行く手配を受けた野田。どうやら毎年この時期に決まった場所へ行く依頼があるらしい。行先はまだ冬の気配が濃いのだが――。
シリーズ1話はこちら
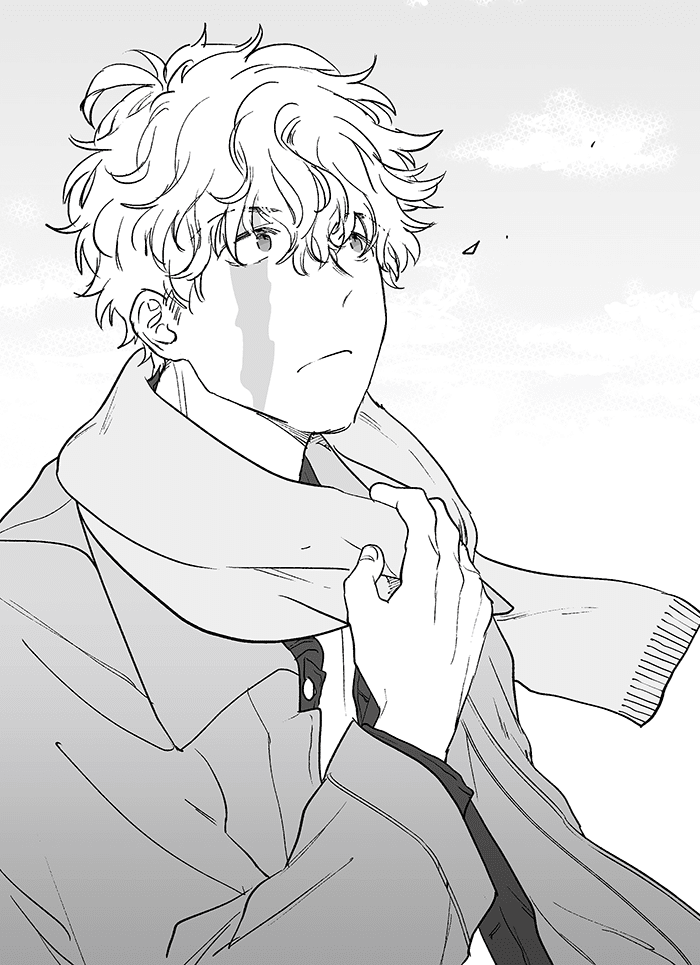
桜の開花予想がニュースで流れるようになると、春の訪れを感じる。例えば卒業式をモチーフにしたコマーシャルや、花粉症対策を歌う薬の広告なんかを見ても春を感じる。
白澤探偵事務所はといえば、特に変わりない日々が続いている。新しい年度に合わせてお札の発送処理をするとか、備品の発注とか、三階倉庫に一時保管されている荷物の整頓だとか、そんな具合だ。
「野田くん、新幹線とレンタカーの手配をお願いしたいんだけど」
対面の依頼がなければ忙しいこともないのだなと思っていた頃、オーナーから手配する便とレンタカー業者の電話番号を手渡された。行先には見慣れぬ土地の名前があり、日付は来週の半ばが書かれている。
「出張ですか?」
「うん、毎年恒例のものだから野田くんも一緒に」
行先となる場所の名前を見てもぴんとこない。知らない土地の名前を業務端末の検索窓に打ち込めば、東北地方のある都市であることがわかった。
最近の情報検索の便利なところは、土地の名前を調べると現地の天気やらバスの時刻表やらが紐づいて表示されるところだと思う。天気予報の示す最高気温は新宿より十度も低い。
「オーナー、ここって結構寒いですか? まだ冬?」
「行きは寒いけど、帰りは温かくなると思うよ」
「了解っす、帰りの切符は取ります?」
何時に終わるかわからないから行きだけで構わない、と言うオーナーに了解の返事をして、片道二人分の切符の予約と、レンタカーの手配業者へ連絡を済ませる。帰りは温かくなるというのは、単純に仕事で体が温まるからという意味なのか、季節の話なのか、聞き損ねてしまった。とりあえず冬のコートをしまいこむのは来週の仕事が終わってからにしようと、手元のカレンダーに印をつけておいた。
東北の地は、思いのほか春が遠いようだった。冬のコートにマフラーで十分だと思っていたが、手袋もあったほうが良かったかもしれないと目的地について手を擦り合わせた。口から漏れる吐息も薄っすら白く染まっている。もう日が昇っているのにだ。
「野田くん、足元気を付けてね」
「うっす……このへん、まだ雪残ってるんすね」
依頼人宅の駐車場にレンタカーを停め、周りを見渡す。市街地から少し離れた山の中腹あたり、山々はまだ雪化粧が濃く、人の通らない道路の脇に雪が積み上げられている。東京ではなかなか見られない光景だけに、少しはしゃいでしまった。
「まだ冬だからね、明日からは多少温かくなるよ」
「そうですかねえ……」
空気の冷たさにぶるりと震えがくる。オーナーは普段と変わらないコート姿で平気らしく、車を施錠して依頼人の家へ向かっていく。慌てて追いかけ、呼び鈴を押した。
「いらっしゃい、白澤さん……あら?」
出迎えてくれたのは、真っ白な髪を短く切りそろえた老婦人だった。肩掛けにセーターと、冬国の防寒を感じさせる暖かな装いだ。彼女はオーナーを見て、その後ろに立つ俺をじっと見つめた。視線を感じると、何となく目線を逸らしてしまう。
「ご無沙汰しております。こちらは部下の野田です」
「……野田ひろみです」
ぺこりと頭を下げる。ゆっくりと顔をあげると、穏やかな微笑みを浮かべた老婦人と目が合った。また目を逸らしかけて、堪えた。
「ひろみさん。素敵なお名前ね、今日はよろしくお願いします」
慌てて再び頭を下げると、依頼人にいつまでもお外にいては寒いでしょうと招き入れられた。家の中は当然温かく、フローリングの廊下を歩いてもひやりともしない。逆に、ほんのり温かいような気もする。断熱に関しての技術は寒い地方に集まるのかもしれない。
「お部屋の様子が変わりましたね」
「この夏に床暖房取り付けたの、もう石油を買いに行くのも大変でね……」
オーナーと依頼人の他愛無い会話を聞きながら、ついさっきの言葉を反芻する。自分の名前を笑われることはあれど、いい名前と褒められたことはなかった。特に、自身と比較したときに嫌な思いをすることが多かっただけに、素直に褒められたのは、何というか、拍子抜けしてしまった。
リビングのテーブルに案内され、オーナーの隣に座る。おやつの入った籠とポットが並ぶのを見ると、生活の様子が垣間見えるようだ。
「では白澤さん、いつも通りお願いしますね」
依頼人はにっこりと微笑み、テーブルの上に手のひらほどの柘植櫛を置いた。これを使って何をするのか、俺には全然ぴんときていない。そもそも、何の依頼でここまで来たのかも知らないのだった。
「野田くん、櫛を持って周りを視てくれる?」
「あ、はい」
テーブルの櫛をそっと拾い上げ、手のひらに乗せる。ポケットに突っ込んだままのお守りをオーナーに預けてから目を瞑ると、目線より上にぼんやりと明るいものがある。近くではなく、少し距離があるように感じた。どれくらい離れているかまではわからない。
「上の方ですね、家の上っていうかもっと上の……」
「裏山かな。野田くんは雪江さんとお留守番してて」
「あ、はあ……了解っす」
雪江さん、というのは依頼人の名前だろう。毎年決まった時期に会って仕事をこなす、というのを繰り返していると、親しく呼び合うようになるものなのかもしれない。他の仕事ではどうかわからないが、ここではきっとそうなのだろう。
オーナーは柘植櫛を持って部屋を出ていく。廊下を歩く足音が遠くなり、玄関がぱたんと閉まる音の後に、俺と依頼人――雪江さんが残された。
「ひろみさん、白澤さんが誰かを連れてきたのは初めてなの。色々お伺いしても良いかしら?」
「あんまりおもしろい話はできませんけど……」
「いつも一人だから、誰かと話すというだけで楽しいわ」
お茶を淹れるから待ってね、と声を弾ませる雪江さんがお茶の用意を始めるのを見ながら、何から話せばいいだろうと少し考えた。オーナーと長く付き合いがあるということはおそらく不思議な事柄も知っていると思うのだが、怖がらせるような話はしたくない。コインで迷子の話は詳細を濁せば愉快な話になる、気がする。
ふと、好奇心に溢れた目に見つめられても平気な自分がいることに気が付いた。名前を呼ばれてもとげとげした気持ちにならないし、もちろんこの場にいることも嫌ではない。人って変わるものだな、と思う。自分のことだからこそ、この変化が不思議に感じるのかもしれない。
オーナーが出て行ってから一時間ほど経った。探偵助手になった経緯だとか、今までどういう仕事をしたとか、その他にも最近の東京の様子も話した。もう梅の時期は終わって、桜の開花予報が始まったことだとか。
「このあたりは寒いでしょう? 春が遅い土地なのよ」
確かに、三月も半ばなのにまだ雪が残っているし、冬の重たい雲と冷たい空気で満ちている。久しぶりに冬用のコートを着たくらいだから、よっぽど寒い場所だ。
「裏山に冬将軍が住んでるんだって白澤さんが言ってたわ」
「冬将軍ですか?」
「ふふ、昔ねえ……白澤さんがその冬将軍を連れて家まで来たことがあったの。私にはよく見えなかったのだけれど、あの人に似てた気がするのよね」
雪江さんがちらっとテーブルの上にある写真たてをちらと見た。今より黒い髪が多い雪江さんと、年の近そうな恰幅の良い男性の仲がよさそうな写真だ。旦那さんだろうな、というのはすぐにわかった。
「あの人も話好きだったから、もしかしたら白澤さんと話し込んでいるのかもしれないわ」
「何のお話ですかねえ」
「きっとあなたのこともお話なさるわね」
白澤さんには今まで助手の一人もいなかったのだという。探偵助手という仕事を始めてから、この仕事量を今まで一人でやっていたのかと舌を巻いてしまうこともあるだけに、妙に可愛がられているというか、こうやっていろんなところに連れて行ってもらえるのが不思議に思うこともあるのだ。
「ひろみさん、白澤さんのことよろしくね」
あの方も長く一人だから、と言って雪江さんはにっこりと笑う。よろしくしてもらうのはどちらかというとこっちなのだが、と思いながらも、重々しく頷いた。
がちゃり、とリビングのドアが開く音がしてびくりと背が跳ねる。振り返れば、コートを片手に持ったオーナーが立っていた。どうやら話に夢中で、玄関の開く音に気が付いていなかったらしい。
「戻りました。伝言を預かっております」
「どんな伝言かしら」
「今年はあんまり寒くなかったから冬っぽくなくてすまない、と」
雪江さんは口元を押さえてくすりと笑う。オーナーも同じように、穏やかに微笑んでいる。
「いつもこれくらいでいいのにねえ……」
「あんまり温かくても雪が降りませんから」
オーナーは柘植櫛をテーブルへ置く。雪江さんはそれをそっと手に取り、愛おしむように撫でた。その手つきで、あの写真の中にある仲睦まじい空気が目に浮かぶようだった。
これは俺の想像でしかないが、このあたりにいる冬将軍というのは、あの旦那様なのだろう。雪江さんの名前とかけて、このあたりの冬を取り持っているのかもしれない。近くにいて、春になると去っていく存在というのは少し寂しいかもしれないけれど。
「ではまた来年の冬に」
「はい、またお願いしますね」
オーナーは椅子に着かず、もう帰り支度を始めている。俺も慌てて続き、コートを腕にひっかけて立ち上がった。雪江さんは急がなくてもいいのに、と残念そうにしている。
「お茶ごちそうさまでした! あの……また、来年も来ます」
オーナーが目を丸くして俺を見た。変なこと言ったかな、と少し焦る。雪江さんはと言えば、穏やかな笑みのままうんうんと頷いてくれていた。
「ひろみさんも、またいらしてね」
家の外へ出る。昼に到着して、オーナーのお仕事が一時間ほど。まだ日が高い時間だ。家に入る前は空気が冷えていたのに、なんとなく、さわやかな風が吹いている気がする。厚い雲を割り、日も差し込んできた。雪が溶けそうな、あたたかな日差しだ。
「明日は温かくなりそうですねえ」
「もうすぐ春だからね」
助手席から雪江さんに手を振る。明日はきっと、今日より温かくなるのだろう。春の足音がするような、そんな日だった。
閑話はこちら
