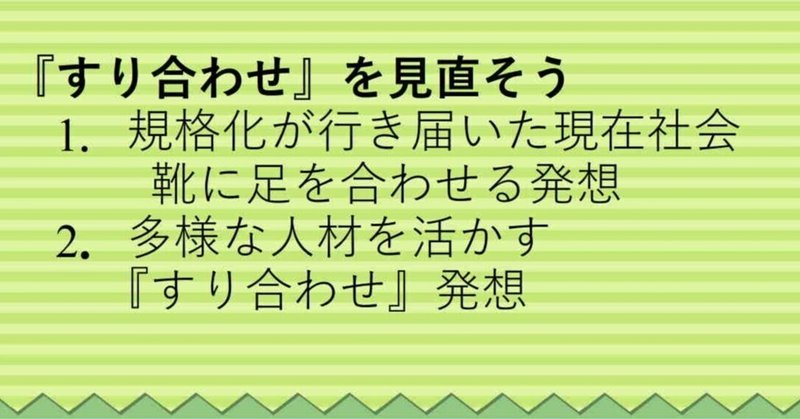
『すり合わせ』を見直そう
序
私たちは現在、学校社会などの規則化が強い社会に適応しています。そこでは、決められた規格に合ったものを、組み合わせることは、比較的簡単にできます。そのため、規格に合うものをそのまま使う便利さに、私たちは慣れてしまいました。しかし、現実の世界に存在するものは多種多様です。その複雑さに向き合うときには、現実の多様さ複雑さに対応して『すり合わせ』での適合を行う必要があります。
しかし、この『すり合わせ』に対して、私たちは、行き届いた学校教育に比較して、訓練した経験は少ないのです。それどころか、逃げようとして、現実の複雑さ、多様さに目を背けていることも少なくありません。実は、今までの我が国は、海外の影響などを避け、単調な経済成長路線をたどってきたので、このような現実逃避でも、生きていける人が多くいました。もっと言えば、現実に疑問を抱かずに、言われたことだけをきちんと行うだけの、いわゆる『優等生』が、教科書通りの世界に適応して生きていました。
さて現在の状況と、しっかりと向き合ってみましょう。
少子化・高齢化の波は人手不足を招き、パートタイマー等の多様な働き方をする人を戦力とする必要が出てきました。また、外国の人たちと仕事をする機会も増えています。このような状況では、仕事の管理においても、仕事と作業者の能力を、きちんと『すり合わす』必要があります。
また私たちの、自分自身の力を生かすためにも、人に教えられた知識だけでは不十分です。知識とスキルなどをきちんと『すり合わせ』て融合した生きた知恵を持たないと、AIやロボットにとってかわられます。
このように、『すり合わせ』の必要性は納得いただけたでしょう。しかし、実際の『すり合わせ』をどのように行うのか、これを教えてくれる機会はますます少なくなっていきます。
ここでは、『すり合わせ』はどのようなモノか、色々な経緯を含めてお伝えし、管理職としての『すり合わせ』の活用と、自己成長のための『すり合わせ』について説明します。なお、この記事を読むとき、多くの場面を想像してもらう必要があります。実は、このように自分が今置かれている環境以外の世界を想像する力が、『すり合わせ』を行うために必要な一つのスキルになります。
第一章 道具の誕生とすり合わせの発達
私たちは、現在は便利な道具に囲まれています。しかし、人類の歴史を遡ってみると、このような道具の誕生についてもいろいろな変遷があります。しばらく想像力を巡らして考えてみましょう。
例えば、私はいま椅子に座ってこの本を書いています。しかし、石器時代などを考えてみましょう。人は腰を掛ける時、どのような物に腰を掛けたでしょう。大きな石に平坦な部分があれば、そこに腰を掛けることもあったでしょう。または、折れた木の太い部分は、腰を掛けることができたでしょう。このように、自然にあるものを何とかして使う、これが始まりでした。このためには、人間が今あるものの都合に『合わせる』必要がありました。
次にもう少し進化すると、道具でいろいろ加工することができます。木を組み合わせて、椅子の形にする。このような加工ができるようになります。しかしながら、木にそれぞれ個性があります。そのため
「不揃いの木を組み合わせる」
などの『すり合わせる』加工が必要になります。
技術がもっと進化すると鉄など金属の時代になります。ここでは
「鉄は熱いうちに打て」
というように鍛造して形にはめることができるようになります。しかしながら、このように形にはめると言っても、その形自体が統一されるには、まだ時間が必要でした。
例えば、火縄銃の時代には、鉄砲それぞれに合わせて、鉛を溶かして弾丸を作っていました。つまり、鉄砲の銃口の形はそれぞればらついていたので、それに合わせた形枠に鉛を溶かし入れて、専用の弾丸を作る。このようなことが行われていたのです。また、火縄銃の銃身の端にはネジを使って閉じていました。ただしこのネジも、私たちが現在使っているような、規格に従ったネジではなく、個別の雄ネジと雌ネジを『すり合わせる』形で作りました。
このように個別の物を、『すり合わせて』調整することで、必要なものに作り上げていたのです。
第二章 標準品の誕生
さて、文明の進化は産業革命を迎えました。産業革命の結果、今までと比べて工作精度の高い、旋盤などのしっかりした機器が誕生します。一方、フランス革命の後、メートル法による計測尺度の標準化が進みます。このような流れを受けて、一八五一年にねじの標準規格が誕生します。こうして、現在のように、ボルトとナットは同じ規格番号なら、規格値から決められた公差の範囲に入るので、どれでも組み合わせることができるようになりました。
このようなことは当たり前と思うかもしれませんが、歴史を遡るとほんの三世紀前に実現したことです。例えば一八四一年の第一回万国博覧会で、複数の鉄砲を部品に分解して、元の銃と違うばらばらの部品から、新しい銃を組み立てるということが、パフォーマンスとして行われました。このように、部品の標準化ということが、万博で展示できるほど珍しかったのです。
こうした工業化に関連した標準化は、おもにアメリカで進みました。これは、銃に頼るアメリカ社会で、銃が故障したときに、他の銃の部品を組み合わせて現場で修理したい、という要求から発生したものです。この後、コルトの銃生産などで、標準化の効果が進んでいきます。ただし、このようなアメリカでも、名人の手作りの銃は、特別なものとして扱われていました。つまり標準品でも少しのばらつきがある。公差の範囲のがたつきは我慢して、並みの性能で使う。しかし、特別に良いモノは、名人が手作りする。このように、標準化によるモジュラーな物作りは、大衆化した廉価品を生み出しました。
こうしたアメリカの標準化を重視した物作りは、その後フォードシステムの大量生産による、自動車の普及に繋がっていきます。ベルトコンベアのラインで大量に作る。このためにも作業の標準化は必要でした。このような標準化を実行するためには、それを支える科学の進歩が必要でした。
なお、作業の標準化は、軍隊にも影響します。集団で戦うとき、個人の技より、皆が同じ動作ができることが優先されます。こうした軍隊を作るために、日ごろからの訓練で、同じ動作ができるように育てる考えが、軍隊の基本的な発想です。また
「足に合う靴でなく支給品に足を合わせろ」
という発想で、標準品に満足させえることも、標準化を進めていく効果がありました。
第三章 理論的な成果を産む科学技術
さて見方を変えて、科学技術の進歩を考えてみましょう。現在の西洋文明は、ギリシャの文明からの流れがあります。ギリシャ文明から、現在の科学に影響しているものの一つに、ユークリッドの幾何学の考え方があります。幾何学の誕生のためには、現実の図形の複雑さを無視した、理想的な直線や点を考える必要がありました。幾何学では
「太さがなくゆがみもない直線」
「広がりがない点」
と理想化したもので考えます。実際の土地の上では、地図上で直線でも少しぐらいの曲がりはあるでしょう。しかしそのような細部を無視し、抽象的なモノで考えるのが数学の始まりです。
このような現実を理想化するところに、標準化してモジュラー化するための糸口があります。具体的に言えば、幾何学の誕生を逆に戻って、現実の直線の太さやゆがみに対応する作業が、『すり合わせ』での実現になります。
さて、ギリシャの哲学は、それ以降の文明に、もう一つ大事な遺産を残しました。それは、プラトンが大著「国家」で示した
「詩人ではなく哲学者が指導する」
という考えです。これについては、マクルーハンなどが詳しく論じていますが、要するに
「詩人の師弟間の全人格的な伝承ではなく、論理的な書き物だけで学ぶべきである。」
と言っているのです。このように書き物という、抽象化した約束事の上で話を進める。ここに、細部を無視して、『すり合わせ』を排除する、モジュラー化の原点があります。逆に、プラトンが否定した、模範の実例を描いた叙事詩による、道徳感・国家感などの伝承は、一対一の個別伝承で行われるので、総合的に伝えることができます。この時、伝承を受ける側は、全体像を完成させるために、自分の心の中で色々な『すり合わせ』を行っていました。この発想を排除したのが、プラトンの文字による記述だけでの伝承です。このように見ると、『すり合わせ』を排除する発想は西洋文明の根底にあるのです。
このように、理想的な記号化した世界で考える発想は、その後ニュートンの力学などに結実します。ニュートンが力学を考えることができたのは、太陽系のモデルが貢献しています。そこでは、まず太陽と地球という一番目立つもので検討しました。その他の惑星の運動も、太陽と一対一の関係で考えます。その後、地球の運動なら、月の影響を加味するという風に、逐次的に情報を追加して精度を上げます。このように階層的に議論を進めて、力学を構成していきました。
産業革命では、このような力学に裏付けされた、機械の働きが大きく貢献しました。精密な機械による高精度の物作り、これができるようになれば、規格通りの物ができます。こうして標準化が実用になりました。しかし、標準化はまだネジのような部品の段階でした。その先の製品化に至る段階では、組み合わせたときに発生する種々の問題を職人技による『すり合わせ』で吸収していきました。
アメリカの工業化は、この『すり合わせ』を少なくしていくことで、大きく進んだのです。第二次大戦を前にしてヒトラーは
「アメリカには(すり合わせを行う)マイスターが少ないから、飛行機の生産は限られている。」
と甘く見ましたが、アメリカの工業の進化は既に、マイスターの技を使わずとも飛行機の大量生産に成功していました。この結果ドイツは大敗しました。なお当時の日本の物作りの力は、高精度の球形が必要なベアリングが、現在のパチンコ玉よりばらついている言う段階でした。パチンコの玉はランダムな動きとするため、わざとひずませてばらつかせています。当時の日本は、そのような低い精度の工作機器しか使えませんでした。それを、現場の職人芸で補って、何とか動くものにしていました。太平洋戦争中の日本のエンジン作りを、ある人は『制作』と言いました。物作りである『製作』ではなく、職人芸や芸術家により、『すり合わせる制作』でした。
第二次大戦後の日本の工業技術の進歩には、この反省が大きく影響しています。高精度の工作機械を使い、できる限り標準化した作業に持ち込む、これをきちんと実行しました。この中で、職人芸による『すり合わせ』をできる限り排除する向きに動きました。
また、二十世紀の後半には、電子回路技術が進歩しました。電子回路の技術は、理論が先にあって、それを理解した人間がものづくりを行っています。しかし、初期のトランジスタ回路では、実際の回路を組むときには、個別の部品のばらつきなどがあり、パラメーターの調整を現物に合わせておかなう、『すり合わせ』がありました。
このような、電子回路の『すり合わせ』を排除するためには、連続的な値でなく、両極端のオン/オフ値を利用する、ディジタル処理が使われるようになり、現在の計算機技術に継承されています。また、連続値を処理するアナログ回路でも、集積回路技術により、演算増幅器を使用して強力なフィードバックをかけることで、設計計算値通りの性能を、調整なしで得るようになりました。
現在の科学技術では、ある程度の物は『すり合わせ』なしの、理論計算値通りの物が動くようになっています。
第四章 人間的要素におけるモジュラー化
さて今までは『すり合わせ』要素を排除して、標準品のモジュラー化に向かう、機械の歴史的な流れを、振り返りました。次に、人間的な要素について、個々人のばらつきを吸収して規格的な扱いを行ってきた、色々な仕組みを見てみましょう。
個々人として人間を見ずに、人数で評価する、このような世界の一つは軍事です。例えば、関ケ原の戦いのとき、負けた側の西軍には、剣豪宮本武蔵もいました。しかし、兵力の大幅な違いは個人の技を超えます。そして、近代軍隊になれば、ますます個人の技でなく、集団で戦うことを重視するようになりました。
明治以降の日本の富国強兵の方針は、このような『標準的人材』を多く育てることを目標としたものです。そのために、まず学校教育という仕組みを作りました。そこでは、行進の仕方から教え訓練して、皆がそろって同じペースで進むようにします。徴兵制の軍隊でも、訓練を積むことで、均一な行動ができるようにしていきました。先ほども書きましたが、
「支給品の靴に自分の足を合わせる」
ことに従う人材を育てたのです。
このように、教育・訓練で皆が同じような行動ができるようにする。これが、人間の規格化の一つの手段です。
現在も残っている、新卒一括採用と企業内研修による育成は、この路線に従ったものです。
もう一つの人材均一化の手段は、人の選別です。この極端な例は、人材の使い捨てです。文化大革命後の中国の経済成長期に、日本のあるメーカーが、中国の某所に進出しようとしました。日本の担当者が
「この仕事は、手先の器用な人が必要です。XX歳からXX歳までの若い人が好いのですが。」
と言ったら、中国の役人は
「千人単位のご希望通りの人は直ぐ揃えます。交代要員もいくらでも補給できます。」
というような会話があったという伝説があります。
このように、自分たちの条件に合う人間を選別し、合わなければ辞めさせる。このような均質化もありました。その場合に、
「個人が規格に合わせる努力をする」
風土があれば物事は旨く流れていきました。戦後日本の、新卒一括採用での終身雇用制は、このような風土づくりにも役立っています。
第五章 すり合わせなしの世界
さて、二十世紀も末の方になりますと、工業技術は大きく進歩していきます。そこでは、理論的計算値で予測した通りの物作りができる。そして、組み上げたものがそのまま動く物が出てきました。このような状況では、『すり合わせ』が行われないままで製品化が行われます。
また、電子回路技術の進歩は、高集積度回路を実現しました。そこでは主要機能が、一枚の基板に収まってしまう。そこにケーブルとコネクタでつなぎこむだけで回路が完成し、それをケースに入れることが組み立てという、工程の簡略化も進みます。
このように簡略化した工程は、一人の人間が全て組み立てる、いわゆるセル生産が可能となりました。ここでは、作業は一人で行うため、他の人との協力関係は少なくなります。ラインでの工作なら、他の人との協力の場での『すり合わせ』が行われましたが、個人作業では不要です。確かに作業者個人の頭の中では、『すり合わせ』が行われましたが、それは外から見えなくなっています。
しかしながら、このような標準化が進んだモノづくりの世界でも、トラブル発生時には、現場・現物での詳細検討が必要であり、『すり合わせ』による作業が発生します。このような時に、『すり合わせ』の未経験者が多くなっていると、対応に困るという事態になっています。技能伝承問題の一側面は、このような『すり合わせ』能力の伝承です。
第六章 すり合わせの復権
さて、『すり合わせ』ということの、原点に返って考えてみましょう。『すり合わせ』が行われるのは、最初に計画したものと、実現したものに違いが生じるからです。理論的に予測した結果と、異なった結果になったときに、修正する働きです。これは現実の世界での多様性やばらつきが原因です。
もう一つ踏み込めば、現実にあるものの力を最大限に発揮させるときに、『すり合わせ』が有効になります。標準化したモジュラーなものの実現は、能力的な余裕を持つことで、標準に合わせることが多いのです。初期の電子回路では、トランジスタ一個の能力を、最大限に引き出すため、個別に調整していました。しかし、トランジスタを多数組み込んだ集積回路の演算増幅器なら、増幅率を抑えるネガティブ・フィードバック量という、計算できる値で増幅率を得ています。このように、『すり合わせ』なしのモノ作りは、性能面で限界のはるか下で、余裕を持った使い方が必要になります。
別の見方をすると、『すり合わせ』なしの世界は、安全側に偏って、性能の限界を引き出さない世界です。言い方を変えると、『すり合わせ』で得るものは、もっと多くの物を得ることができます。
さて、現在の経営環境は、少子化と国際化の両面から、多様な人材の有効活用が必要になっています。このような状況では、人材活用における『すり合わせ』が、重要な問題になります。もう一つ言えば、自然科学の場合と異なり、社会科学の予測の精度はそれほど良くありません。何を考慮すべきか、学者の間でも意見が分かれています。従って、理論的な予測も大きく違うことがあります。そのような状況でも、世界の急激な変化や、多様な人材を活用するためには、今までの延長による発想だけでなく、学問的な知見も活用する必要があります。
こうして管理職の主要スキルとしての、『すり合わせ』能力が問われるようになりました。
見方を変えれば、経営学などの文系分野でも、とりあえず理論的な予測がある程度形になる。これは物理学等を母体とした工学分野ほどではないが、ある程度のガイドができる。そこでそれに合わせる、『すり合わせ』が成立するように成熟したとも言えます。昔の管理は、経験的なモノで行っていましたから、理論がありません。従って『すり合わせ』すら行えなかったのです。
コラム すり合わせと全体像
『すり合わせ』の物作りを、インテグラルという場合もあります。この時に対になる概念は、モジュラーです。この「インテグラル」は「統合」という意味があります。全体的にまとめ上げる作業です。確かに全体としての最適なものを得るためには、色々な部分の要求を『すり合わせる』必要があります。
一方、『すり合わせ』を行うときには、全体を見ていないと、『すり合わせ』の進み具合、特に完了判定が難しくなります。基準値があるなら、その値になれば完了と言えるでしょう。しかし、『すり合わせ』の場合には、自分で判定する必要があります。そのため全体を見る必要があります。
実は、このような全体像の作成自体も『すり合わせ』的な作業になります。全体としてどこまで見るか、外部の環境をどこまで見るか?この判断を、作っているものと『すり合わせ』ながら行います。このような全体像の作成では、安定したという感触が一つの尺度になります。
第七章 大局的なすり合わせ
さて、今まで話していた、『すり合わせ』は、鉄砲と弾丸のように、個別の部品同士の『すり合わせ』でした。確かに『すり合わせ』の語源は、二つの部品面を合わせることから出ています。
しかしここで、『すり合わせ』という概念を広げてみましょう。これまで書きましたが、『すり合わせ』を不要にするモノ作りは、モジュラーな物の組み合わせです。これは標準品と言ってもよいのですが、もう一つ別の見方で言えば、
「理論どおりの物作り」
です。つまり教科書の値のとおりに物ができる。工場で言えば、設計者が机上で考えた通りに物ができることです。
しかしながら、現実の物作りでは、複雑なものは一気にできるわけではありません。色々な試行錯誤を繰り返しながら、物ができていくのです。これは、物だけではなく、設計の机上検討の段階でもいろいろな試行錯誤があります。
「設計CADシステムの操作は、アメリカでは専門のオペレーターに作業をさせるが、日本では設計者自身がCADを操作することが多い。」
という報告がありました。ここで大切なことは、CADシステムは、書き直しが比較的楽にできるということです。設計者が自分の考えを、一度図面という観える形にします。その上で、色々と反省し修正する、こうして試行錯誤ができるのです。つまり、日本の設計者は、理論的な構想を、一度は図面上の表現という形に展開します。これから色々と想像し、確認するのです。これは『すり合わせ』の設計なのです。
このように部品の段階以外でも、『すり合わせ』を行うことで、良いモノが生まれてくる。今までできなかったものが実現するようになる。この点にも注意してください。
第八章 自分の能力開発としてのすり合わせ
次に、私たち自身が、仕事などで有能と言われるようになる条件を考えて見ましょう。私たちの能力は色々な階層があります。一つの例は次のようなものです。
経験
基礎知識
スキル
意欲・価値観
体力・気力
この力の階層は、習得方法に違いがあります。例えば、経験は自分で体験できれば良いのですが、人の体験談を聞く、本を読むなどの場合もあります。一方、基礎知識は学校で学ぶことなどです。これも本などにより自分で学ぶこともあります。
スキルは、自分の体で覚えるものです。一般的に、繰り返して練習する必要があります。意欲や価値観は、今までの生活で身についたものですが、他人の成功した話などから教訓を得ると、大きな変化をすることがあります。
気力は、成功する見込みがあれば強化されます。一方、体力はスキルが向上すれば、消耗が少なく多くの仕事ができるようになります。このように階層構造の中でも、相互に関連しあい、下位でも上位からの影響で変化する、このような状況は、工業部品と大きく違います。外部の状況で、ネジの強度や形が変化するということは、工業製品では、大事故などでの破壊以外では、通常は考えないようにしています。しかし、人間の場合には、経験や知識が、気力・体力に影響することもあり大きな変化を生み出すことがあるのです。従って、全体を見て『すり合わせ』を行う必要があります。
このような『すり合わせ』を経て、自分が成長を感じる時は、この能力階層の全てに渡って、バランスが取れたと感じる時です。学校の成績のように他人に評価されるのではなく、自分で評価する時には総合的なモノが必要です。このように、自分の成長のためにも、『すり合わせ』を上手に行うことが必要です。
終わりに
私たちは、科学的な知識などは学びましたが、現場の力である『すり合わせ』を意識したことは、少ないでしょう。しかしながら、現在の多様化時代には『すり合わせ』が、大きな力を生み出します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
