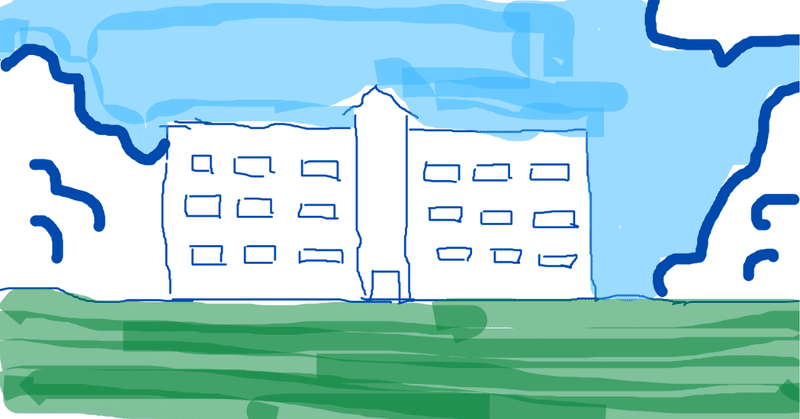
私の統合失調症と学歴コンプレックス
1994年、まだ冬の寒さが残る頃、私は地元の県立高校の玄関の前にいた。
受験の合格発表を見るためだ。
私の受けた県立高校は地元ではトップクラスの高校で、そこに入るのはエリートとされていた。地方では都会と違い私立より県立高校のほうがレベルが高いのだ。しかし、私はそんなに強くその県立高校に行きたいとは思っていなかった。私にとって高校とは野球をするところであり、その高校はサッカー部は強いが野球部は弱かった。では、なんでそんな高校を受けたかと言うと、私は中学時代、野球でイップスになり、野球が楽しめず、野球に絶望していたため、周囲が行けと言うこの優秀な県立高校を仕方なく受けたのだった。本当はもっと野球の強い高校に入学してレギュラーになり甲子園を目指すのが、私の人生で一番重要なことだったのに、その青春がもう望めなくなっていた。
結局、私はその県立高校に合格した。私は掲示板に私の番号があったことを見て安堵し、軽く握りこぶしを固めた。周りでは「やったー」などと、歓喜して抱き合って喜ぶ奴らもいた。一方で泣いている女の子もいた。きっと落ちたのだろう。私がひとり合格したためにひとり不合格者が出たのだ。私はその場にいるのが嫌になって、静かに家に歩いて帰った。
家に着くと母は、「どうだった?」と訊くので、「合格したよ」と私は静かに答えた。母がどんなリアクションをしたかは覚えていないが、喜んでいただろう。
それでも、私はその県立高校に行くかどうか迷っていた。もうひとついわゆる「滑り止め」で受けた私立高校に通うことも考えていた。理由は単純で、県立高校は家から近く、私立高校は家から遠いことが理由だった。県立高校は私の中学よりも近かった。中学を卒業したらもっと遠くへ行きたいのが少年の心理だ。歩いて十分程度の近くにある県立高校など魅力がなかった。やっぱり、高校に通う以上寄り道が楽しいだろうと思っていた。県立高校と自宅の間にはビデオレンタルが一軒あるだけだった。しかし、私のこの進路の迷いを決定づけたのは母の一言だった。
「県立高校ならばお小遣い月五千円、私立ならば三千円」中学時代のお小遣いは月二千円だったから、それが五千円になるか三千円になるかは私にとって非常に重大なことだった。
私は県立高校に入学した。
県立高校に入るとすぐに、担任が大学受験の話をしたのでうんざりした。私は大学になんぞ興味はなかった。その当時は高校を卒業したらマンガ家になりたいと思っていた。そのマンガあるいはアニメのことを考えながら、まだ未練があった野球部に入部した。野球部は練習がきつかった。頭の中はマンガやアニメで、肉体はグラウンドにいた。まだイップスは治らなかった。授業はほとんど聴いてなく、居眠りばかりして、午後の部活の時間のために体力を温存した。一学期の成績はどうだったか忘れたが、化学が8だったことは覚えている。ほとんど中学でやった内容だったため、勉強をしなくともその程度取れたのだ。私はこの優秀な子が集まる高校でも学業成績がそんなに悪い方ではないと感じていた。私は大学の偏差値がどうとかまったく知らなかったが、六大学野球や箱根駅伝などで常連の早稲田や慶応などのレベルが高いことを知った。正直、私はそのような大学を難しいと思わなかったが周囲がそれらの大学をエリートの行く大学だ、みたいに言うので、私は自分の能力がそんなに高いのかと、戸惑った。昔から東京大学は難しいというのは知っていた。そういう大学の象徴だった。しかし、六大学などが、難関校みたいに言われているのが驚きだった。私の当時の自己意識は自分が普通の人間だったために、普通に生きているとエリートになってしまう、と恐れのようなものを感じた。私の親しかった友達はもっと成績の悪い高校に行っているのである。私はエリートになりたい人達よりも、他の高校に進んだ友達のほうに価値観としては通ずるものがあった。中学生当時私は、『ドラゴンボール』に出てくる、「ベジータ」というキャラの真似をして、「俺はエリートだ」「ふん、ザコどもめ」などと言ったり、『スラムダンク』の「桜木花道」の真似をして、「俺は天才だ」などとふざけていたが、高校で件の県立高校に入ることになると、それが冗談ではなくなり、嫌味にすらなってしまうようになり、友達とのふざけ方も変えなければならなくなった。
とにかく私は自分が普通に勉強してエリートになることに抵抗するようになった。
私は、上記のようにマンガ家になることを夢見つつ、野球部に所属していた。しかし、高校一年も終わる頃、野球部を辞めた。理由はイップスが治らなかったからだ。野球をやっていても、何も楽しくないのだ。私は野球のない人生を生きることに決めた。
しかし、高校野球への未練は高校三年生の夏まであり、毎晩のように野球部に戻った夢を見た。夢から覚めると自分がイップスであることに気づき絶望した。そんな絶望感の中、高校に通った。頭の中はマンガ家になること、その後、アニメ映画の監督になることでいっぱいだった。ほとんどノイローゼだった。毎日、下校途中にビデオレンタルでビデオを借りて映画を観まくった。そして、自分の中に映画理論、物語論を形成していった。二年生になると野球部を辞め、肉体疲労がなくなると、勉強の成績が上がった。クラスでも良い方だったと思う。しかし、私は夢の中にいた。将来、マンガやアニメで大物になるまでの通過点として現在の高校時代を考えていた。
詳細は省くが、そんな将来ばかり考えて現在を疎かにする夢見る私は高校二年の秋に統合失調症を発症した。
そこからは地獄だった。
三年生では散歩ばかりして勉強を全くしなかった。狂気の中にいたが、とにかく周りから見て普通を装った。周囲からいじめられていることもわかっていたが、いじめる奴らを殺そうと、何度も妄想したが、将来、狂気が鎮まったとき、自分が殺人を犯した前科者であるか、それとも、何の罪もない普通の人であるかを考えて、普通であるためにそいつらを殺さなかった。殺すことが悪いという意識はなかった。ヤバい状態だろう。将来の自分のために犯罪をしなかった。心神耗弱といった状態だったと思う。それでも、自分の中の僅かな理性が自分の凶行を抑えていた。
大学受験ではひとつも合格しなかった。受験勉強を一年間一秒もしなかったのだから当然だった。私は予備校に通うことになった。「一年がんばって、大学に合格し、東京に出よう」そう思った。
私はマンガ家になりたかったため、地元の静岡県から出版社の多い東京に出ることが重要だと思っていた。そのために東京の大学ばかり受験した。早稲田や慶応は無理なように思われた。もちろん東京大学は論外だった。しかし、東京のなるべく偏差値の高い大学に行きたかった。理由は自己評価を高めるためだった。学部も何でもよかった。
受験前に母が「これ受けてみれば」と言って、私に勧めたのが、国学院大学の哲学科だった。私はそのときその大学の存在を初めて知った。だから、早稲田や慶応のように先入観がなかった。
結局、私は国学院大学の哲学科に入学した。他には日本大学の社会学部などが受かっていたが、日大はマンモス大学で騒がしいだろう、国学院大学は小さくて静かに過ごせるだろう。場所も渋谷という中央とは距離のある町だから良いだろう、などと思って決めた。当時私は渋谷がどんな街か知らなかった。
私にとって、受験の敵は、「レベルが高い」という周囲からのプレッシャーだったと思う。最初、早稲田や慶応が普通の大学と思っていたのは、知らぬが仏だろう。しかし、知ってしまえば仏はどこかに行ってしまう。私は早稲田や慶応の名にビビってしまった。東京の列車に乗ると、早慶という文字の入った予備校の看板が目立った。予備校の宣伝文句は、昨年度東大〇人、京大〇人、慶応〇人、早稲田〇人などと、大々的に書き上げている。あの受験戦争みたいなのは、統合失調症の私でなくても、多くの人がその狂気に晒されているだろう。自分の大学の偏差値はいくつだから、などと、卒業後もコンプレックスを引きずる人も多いだろう。コンプレックスとは劣等感だけではない、優越感も含む。だから、東大出の人も、「自分は東大を出ている」と強く意識することは、それ自体が不幸なことで、いらない自意識だ。国学院などは中堅の大学で、東大などから見れば全然大したことはないし、高卒や中卒の人から見たら充分高学歴だと思う。ああ、私も学歴の魔力にやられてしまっている。社会に出て学歴を振り回す奴はなんなのだ?四十代で自分の出た大学を自慢する奴、二十年前の学力じゃないか。私自身もこういう文章を現在書いている時点で学歴に振り回されている。
ただ、私は統合失調症の急性期、心神耗弱とも言える地獄の中で勉強し国学院に入れたことは誇りに思っていいと思う。それは国学院が優秀だとかそういうことではなくて、逆境の中でベストを尽くした証拠として、私はその大学を誇りたい。そういう努力を誇ることはコンプレックスとは関係なく、正常な心理だと思う。
しかし、東京大学も、早稲田大学も、国学院大学も大学であって私ではない。誇りとはどこに属していたかにあるのではない。どこのポジションにいたかではない。誇りとは大企業に勤めていたとか、大会社の社長だったとか、あるいは大臣経験者とかそういう類のものではない。何をしたかにあると思う。
これからは何を成し遂げたかを誇れるように生きて行きたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
