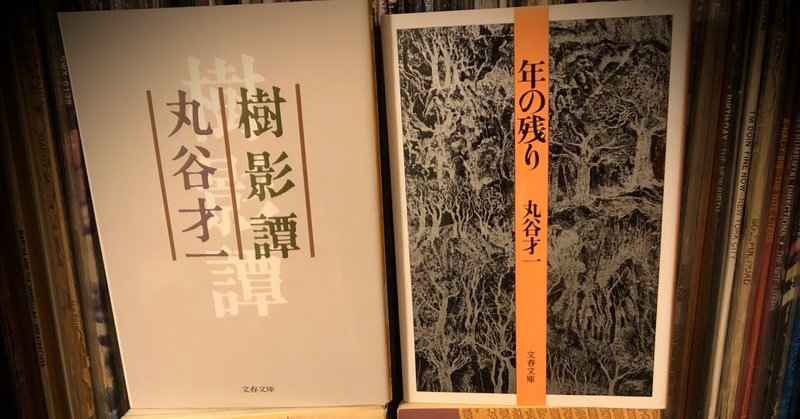
切り口が素敵な小説家・丸谷才一
2021年10月15日号のBRUTUSの
村上春樹特集で、
氏がお勧めする本の中にあったのがきっかけで
ぐいぐいハマってもう4冊読んでしまいました
そんな小説家・丸谷才一についてのレビューです
「年の残り」1968
「裏声で歌へ君が代」1982
「樹影譚」1988
「女ざかり」1993
読んだのはこの四冊
「樹影譚」1988
最初に読んだのは短編集「樹影譚」
この、村上春樹も勧めるタイトル作がまず素晴らしくてハマることになった。
作者自身の樹影に対する思い、ある種の木の影はどうしようもなく郷愁をそそるのは何故だろう?という自問から始まるエッセイ。。。かと思いきや、そこから小説が始まるのが素敵だった。村上春樹の表現によると「文章のスタイリスト」まさにそのスタイリストっぷりが発揮された短編。旧仮名遣いなのに何故か読みやすい。そもそも1988年に発表されたものなのに旧仮名遣いというところが、丸谷才一らしさでもある。
「年の残り」1968
次に読んだのが短編集「年の残り」
「樹影譚」は既に63歳ころと熟してきた頃の作品集なのに対して、これは40代のもの。驚くべくは、この頃は仮名遣いは普通のものだった。この短編集がまた素敵で、二度読みしてしまうほど。芥川賞受賞作でもあるらしい表題作などは69歳が主人公で、とにかくどんどん周囲の人があーだこーだで亡くなっていく話。そしてふと、「もし自分は最初に縁談のあったあの人と結婚してたらどうだったんだろうか?」と妄想していくうちに、ひょんな縁の積み重ねで驚きの、、、でもホッコリで終わる話。いやぁ素敵。
「思想と無思想の間」というのも良かった。これこそ丸谷才一の本領発揮というか、基軸となるような視点で描かれた小説だった。翻訳を生業にしている主人公が、昔たまたま翻訳したヒットラー伝のために、その種の人と思われてしまいがちで、かつ義理の父も右翼的な発言で一斉を風靡した人で、、、そうしたちょっとしたキャリアのせいで持たれがちな偏見から逃れるために色々と気をつけているのに、そこを目当てに現れたイケメンな学生、、、という話。
昨今の、「昔実はこういう発言をしてた」「親戚にこういう人がいる」というだけでその人自身の評価を色眼鏡で見てしまう、そうしたことへの軽い警鐘のような話にも思える。そうした話がどの短編にも凝縮されていて素敵だった。
「裏声で歌へ君が代」1982
そして、長編にも挑戦してみた。まずは
「裏声で歌へ君が代」
これがまた突拍子もない素敵な始まり方で、かつ壮大なテーマで素晴らしかった。
なにせエスカレーターを昇っていくときに、降りてくる側に、知り合ったばかりの女性を見つけて咄嗟に逆乗りをして追いかけていくとこから始まるからね。そして向かうはたまたま友達だった台湾系の男の「台湾民主共和国準備政府の大統領就任式」。そこから始まる駆け引きと共に「そもそも国家とは何か?」という話をあーだこーだ色んな登場人物が意見を出していく。
個人的に腑に落ちた考え方は
「蝶々も犬も目的なんてなくて、ただ存在している。日本という国はある時から国であることを諦めて、ただ存在している、というところになったのではないか?日本という国は現代国家の典型かもしれませんね。目的というものがなくてただ尊愛している国家の典型。~~どの国もなんか色々お題目を掲げていますがあれは間違いで、戦時中の「東洋永遠の平和のため」とか「アジアの盟主」とか八紘一宇とか、くだらないお題目が亡くなってから、ずっとマシになりました。
普通はよほど優秀な国でないと、そんなことできないんですがね。何しろ寂しいからな。国家目的がないと認めるのは。ところが今の日本がそれをやってのけたのは、これは偶然ですね。なんとなくこうなってしまった。別に寂しいのを我慢してじゃないらしい」
こんな壮大な話の中に男と女のエロティックな話も絡んでくるところが素敵な小説でした。
「女ざかり」1993
そして今しがた読み終えたのは
「女ざかり」
吉永小百合主演で映画化もされたらしいこの小説は、1993年に出たのがよく分かるフェミニズム〜女性の社会進出的なテーマが掲げられているようでありながらも、基本は「日本らしさとは何か?」これもまた色んな意見が登場人物を通して語られるが、通奏低音としてあるのは日本の価値観は「贈与〜物のやりとり」が軸である、と。お中元やお歳暮からお賽銭から、、、あらゆる形で贈与の形態を維持されている社会であって、、、ということを、新聞社の女性記者が記した一つの社説記事が問題を引き起こして、それと戦うという設定の中で示されていく小説。
もうどれも「うまい!」って手を叩く感じがありつつ
「なるほどなぁ」という思想や切り口も示される。
なかなか近所の本屋レベルだと最近は扱われていない小説家のような気がするのが残念だけど、個人的にはかなり好みな小説家でした。今後もちょいちょい読んでいこうと思います。
よろしければサポートをお願いします!収益はSWING-Oの更なる取材費に使わせていただきます!
