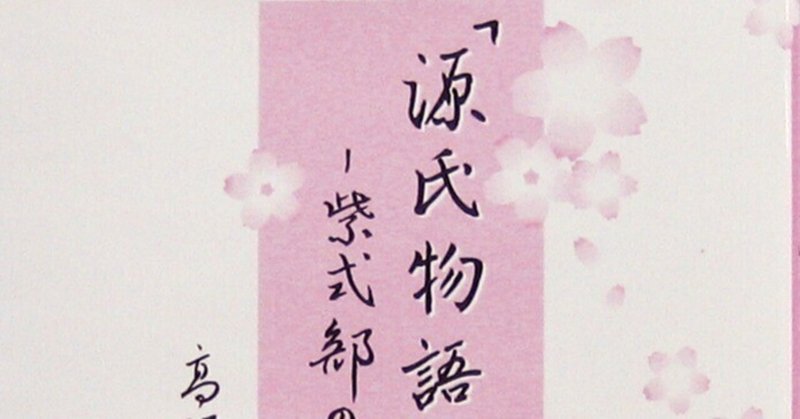
第91回 道長の野望、火を噴く
三条天皇が譲位した長和5(1016)年4月、70歳になった為時(香子の父)は三井寺で出家します。そして孫娘の18歳の賢子が彰子に呼ばれて女房となりました。為時が2年前まで越後守をやっていたので「越後の弁」と呼ばれました。(大弐の三位はだいぶ後年)
賢子は亡き父宣孝に似て明るかった様です。(母親の紫式部はどちらかというと陰キャ?)
さて、翌年3月、道長は摂政を1年余で辞し、長男で26歳の内大臣頼通が摂政となります。次代への布石というところでしょうか。
そして5月、余り身体が丈夫でなかった三条上皇が42歳で崩御します。
大変なのは皇太子であった、上皇の第一皇子敦明親王(24歳)です。皆、道長に忖度し、東宮御所へは寄り付きません。親王はだんだんノイローゼになってきます。
ここで動いたのが高松方の能信(23歳)です。近くに住んでいたという事もありますが、敦明親王の所へ参上すると、ひどく滅入っていて「こんな事なら東宮を辞めて気ままな暮らしがしたい」と言います。
能信は参内して早速、伯父の権大納言・源俊賢(母明子の異母兄)に相談すると「これは早く大殿(道長)に言った方がいい」という事で、道長に連絡すると「ほう!今日は悪い日ではない。早速、東宮辞退と、敦良の立太子の式を行おう」と言います。
そして敦明親王の母・皇后娍子方の邪魔が入らないように、いつも使いの女房が来る通路を塞いでしまいます。
その日の内に、敦明親王は東宮辞退という事で「小一条院」という上皇待遇の院号を与えます。これは『源氏物語』で光源氏が天皇になってないのに「六条の院」として上皇待遇を受けるのによく似ています。参考にした?
これで1日にして道長は二人の孫を1人は天皇、1人は皇太子とする事に成功します。後で、何も知らなかった娍子は知ってがっくりしましたが、どうしようもありません。3月に左大臣に昇進して喜んでいた、敦明親王の舅・藤原顕光も愕然とします。
思えばかつて、中の関白家の伊周が花山法皇と女性関係から襲った時も、道長はじっくり構えました。それだけではひょっとしたら流罪にできないと思ったのかも知れません。その内に伊周に不利な情報がどんどん出てきます。皇太后詮子を呪った事、臣下がしてはいけない呪いの術をしていた事など証言者が出てきます。そして待つ事3カ月。4月についに追い詰めて流罪にしたのでした。
今度は電光石火。1日にして行動しました。やはり道長の政治手腕でしょうか?
小一条院になった敦明親王を、道長は高松方の美貌の寛子(19歳)の婿として盛大にそして丁重に迎えます。敦良が東宮になったのですから、安いものです。まるで『源氏物語』終盤で、夕霧が六の君の婿として、匂宮をもてなすように。ただ、これは高松方、特に能信などは不満でした。「まるで捨て石の様な使い方ではないか。あちらは后となっているのに」
一生懸命、父の歓心を買おうとして能信は行動したのですが。
『大鏡』には道長を賛美しながら、この娍子方の女房を妨害したのを、
「可哀想な気もしたが、面白くもあったよ」と道長が言ったと批判しています。『大鏡』は『栄花物語』として随所に批判が見られます。
作者は不明ですが、能信も複数の作者候補に上がっています。
そしてこの小一条院の寛子との結婚はまた新たな悲劇をもたらすのでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
