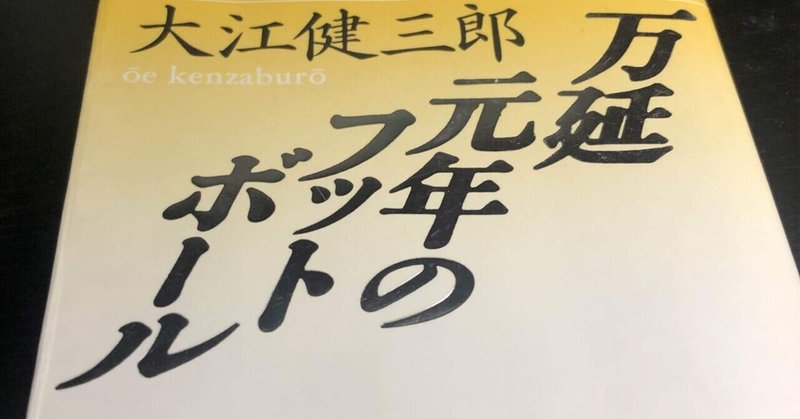
万延元年のフットボールの余韻
この本を東京駅横の丸善で買ったのが1月末で、読み終えたのが一昨日だから、3週間くらいかかったことになる。
良い小説だった。間違いなく読んで良かった。「百年の孤独」の読後感に似ていると思ったのは僕だけか。
今はカポーティの小説を読んでいるのだけど、これを読んでいる間も常に「万延元年」、いや大江健三郎の顔が頭にある。「万延元年」読後の後遺症として、次に読んだ本に対し「本ってこんなにスラスラ読んでいいんですか?」と思ってしまう。カポーティの小説も良いはずなのに、「万延元年」と比べると読み応えがなく感じる。僕は都会の、平凡な、孤独の主人公は大好きだ。なのに今は物足りない……
「万延元年」を読み終えて、舞台の村のイメージがかなり具体的に浮かんでいたことに気付いた。実際に見たわけじゃないのに、こういう村でこういう人が住んでいて、気温はこれくらいで、どこかねっとりした空気がある、と。
僕は毎日通勤で大阪駅を通る都会の人である。だから「万延元年」のような田舎の、しかも昔の小説は読みづらい。共感ポイントがないから。
しかし、2点が僕をグイグイ惹き込んだ。
1点は大江健三郎の挑戦的な姿勢。僕は大江健三郎が考えていることが本当に分からない。良い意味での「俗っぽさ」がない。村上春樹、谷崎潤一郎、フィリップ・ロス、サリンジャー、ヘミングウェイ、サガン、それから庄司薫。これらの都会派作家は、僕のようなどこにでもいる若者と響き合う「俗っぽさ」を持っている。そういうのは好感が持てる。好感が持てると、また読みたくなる。
でも大江健三郎は人間性というか、考えていることが本当に分からない。唯一わかるのは、この人が常に新しい文学を求め、1文1文挑戦していたということだけ。だからどれだけ内容が複雑で文体が硬くても、その野性を少しでも吸収するために、僕はこの本を読んだ。
2点目は「万延元年」の主役、鷹四と蜜三郎。この2人にはリアリティがある。鷹四は凶暴な男になりたい、普通の人間。そういう人間が何に好奇心を抱き、いつストレスを感じ、何を根底に考えているのかというのが、すごい分かる。「俺が本当のことを言うときは、死ぬときだ」というのは、大江健三郎がこの小説内で一番伝えたかったことだったんじゃないかな。多少極端だけど、僕もそういうふうに考えることがある。だから鷹四がどれだけ凶暴なことをしても、「あー、やってるやってる」という目で見られる。この小説はグロテスクであればあるほど面白い。やりすぎなように見えて、ちょうど良いのだ。
対する蜜三郎。平凡な人間に見えるが、誰よりもタフである。大人である。最後にアフリカへの仕事を選ぶ点など、その表れである。こういう人は静かだが、誰よりも前衛を好む。
ふと、大江健三郎がすでに他界していることを思い出す。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
