
2022年NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』(第20回)「帰ってきた義経」
1.義経北帰行
■『吾妻鏡』「文治3年(1187年)2月10日」条
文治三年二月小十日壬午。前伊豫守義顯日來隱住所々。度々遁追捕使之害訖。遂經伊勢美濃等國、赴奥州。是、依恃陸奥守秀衡入道權勢也。相具妻室男女。皆、假姿於山臥并兒童等云々。
(文治3年(1187年)2月10日。前伊予守・源義顕(義経→義行→義顕)は、最近(畿内の)あちこち(多武峰、鞍馬山、比叡山、洛中など)に隠れ住み、何度も追捕使(追手)から逃れていた。遂に(畿内に隠れ住むのは無理だと感じ)伊勢国(三重県)から美濃国(岐阜県)等を通って、奥州(東北地方)へ落ちた。これは、平泉の陸奥守・藤原秀衡の力を頼るためである。妻・郷御前、子、男女の従者も連れて行った。皆、山伏や稚児等に変装していたという。)
源義経の最後の実名は、義顕である。元服時、源氏ゆかりの通字「義」と、初代経基王の「経」で実名を「義経」としたが、「罪人変改名」(有名なのは和気清麻呂→別部穢麻呂(わけべのきたなまろ))により、九条良経と同じ「義経」から、文治2年(1186年)閏7月10日「義行」に変えさせられるも、「義行」は「よく逃げる」に通じるとして、文治2年(1186年)11月29日、「義顕」(よく顕れろ(早く現れろ))に改名させられた。
※「【義経伝説】源義経の奥州落ち」
https://note.com/sz2020/n/nb300500b5acd
2.郷御前
『鎌倉殿の13人』の源義経は、「郷御前は比企一族の娘だから人質に使える」と言っていたが、源頼朝はそんなに甘くない。父親が殺されている。
・河越重頼(郷御前の父):源頼朝の命令で、所領没収の後に殺害される。
文治元年(1185年)11月12日。享年不明。
・郷御前:文治5年(1189年)閏4月30日、源義経に殺害される。
『吾妻鏡』では源義経が殺害。『義経記』では自害。
■『義経記』
「北の方は如何に」と宣へば、「早御自害有りて御側に御入り候ふ」と申せば、御側を探らせ給ひて、「是は誰、若君にて渡らせ給ふか」と御手を差し渡させ給ひて、北の方に取り付き給ひぬ。兼房いとど哀れぞ勝りける。「早々宿所に火をかけよ」とばかり最期の御言葉にて、こと切れ果てさせ給ひけり。
3.義経北行説(北方伝説)/源義経生存説
「義経北行説(北方伝説)」(源義経生存説)の根拠は、「首」と「伝承地の存在」である。
(1)首
・焼身自殺したので首はないはず。(あっても黒こげ)
・平泉→鎌倉は20日程度なのに首は43日かけて運ばれた。(腐乱したはず)
・首検分は鎌倉ではなく、腰越で和田義盛と梶原景時が行った。
(6月9日の亡母の供養前に鎌倉に着いて穢れるのを避けた)
■『吾妻鏡』「文治5年(1189年)閏4月30日」条
文治五年閏四月卅日已未。今日、於陸奥國、泰衡襲源豫州。是、且任勅定、且依二品仰也。与州在民部少輔基成朝臣衣河舘。泰衡從兵數百騎、馳至其所合戰。与州家人等雖相防、悉以敗績。豫州入持佛堂、先、害妻(廿二歳)、子(女子四歳)、次自殺云々。
(文治5年(1189年)閏4月30日。今日、陸奥国で、藤原泰衡が源伊予守義経を襲った。これは、勅定(朝廷の命令)と源頼朝の命令に従ったのである。源義経は、藤原基成の衣川館にいた。藤原泰衡は、数百の騎馬武者でそこへ駆けて行き、合戦となった。源義経の家来たちは防戦したが、悉く負けた。防御しようと戦いましたが、皆全て負けてしまいました。源義経は、持仏堂に入り、先ず、妻(22歳)と娘(4歳)を殺害し、次いで自殺したという。)
■『吾妻鏡』「文治5年(1189年)5月22日」条
文治五年五月小廿二日辛巳。申剋、奥州飛脚參着。申云「去月晦日、於民部少輔舘、誅与州。其頚追所進也」云々。則爲被奏達事由、被進飛脚於京都。御消息曰「去閏四月晦日。於前民部少輔基成宿舘(奥州)、誅義經畢之由、泰衡所申送候也。依此事、來月九日塔供養、可令延引候。以此趣、可令洩達給、頼朝、恐々謹言」。
(「文治5年(1189年)5月22日。午後4時頃、奥州平泉から飛脚が到着し、「先月30日、藤原基成の館で、源義経を誅殺した。其の首は、追って送る」と伝えた。直ぐにこの事を後白河法皇に奏上するため、飛脚を京都へ遣った。その消息(手紙)には、「先月30日、奥州の藤原基成の宿館で、源義経軍を誅殺したと、藤原泰衡から申し送りがあった。この事により、(身内の死で穢れるのを避け)来月9日の(鶴岡八幡宮の)塔完成供養(亡母の供養)の儀式は、延期することにした。この内容で、後白河法皇にお伝えいただきますよう、頼朝、恐れ謹んで申し上げる」と書いた。)※導師が既に京都を出ていたので、予定通り行われた。
■『吾妻鏡』「文治5年(1189年)6月13日」条
文治五年六月大十三日辛丑。泰衡使者・新田冠者高平、持參豫州首於腰越浦、言上事由、仍爲加實檢、遣和田太郎義盛、梶原平三景時等於彼所。各着甲直垂、相具甲冑郎從二十騎。件首納黒漆櫃、浸美酒、高平僕從二人荷擔之。昔、蘇公者、自擔其糧。今、高平者、令人、荷彼首。觀者皆拭雙涙、濕兩衫云々。
(文治5年(1189年)6月13日。藤原泰衡の使者・新田高平が、源義経の首を腰越浦(神奈川県鎌倉市腰越)に持ってきたと言うので、首実検に和田義盛と梶原景時をその場所へ行かせた。2人とも鎧直垂(よろいひたたれ)を着て、甲冑を身に着けた部下20人を連れて行った。件(くだん)の首は、黒漆のお櫃(首桶)に入れて、高級酒で満たし、新田高平の下僕の2人が天秤棒にぶら下げて担いできた。昔、蘇武は、自分で食料を担いだ。今、新田高平は、人に源義経の首を運ばせている。見る人は、皆、涙を流して両袖を濡らしたという。)
※和田義盛と梶原景時は武将を並べ、礼を払って首実検を行ったが、新田高平は、礼に欠け、首桶を自ら担かず、従僕に担がせた。
『鎌倉殿の13人』(第20回)の「帰ってきた義経」というタイトルは、前回(第19回)のタイトル「果たせぬ凱旋」とセットである。生きて鎌倉への凱旋は出来なかったが、自害して首が帰ってきた。
『鎌倉殿の13人』では、鎌倉の大倉御所に届けられた源義経の首桶を前に「源平合戦の様子を詳しく聞かせてくれ」と、源頼朝が号泣するシーンが感動的でした。
源頼朝「九郎…よう頑張ったなぁ。さあ、話してくれ。一ノ谷、屋島、壇ノ浦。どのようにして、平家を討ち果たしたのか。おまえの口から聞きたいのだ。さあ…九郎…。九郎…。話してくれ…。九郎…。九郎ー!すまぬ…。九郎…九郎ー!」
これは、源義経が出陣する時(第14回「都の義仲」)、「木曽義仲と平家をいかにして滅ぼしたか、じっくりと教えてあげたい」と言った言葉を受けたからで、源義経は、平宗盛を連れて凱旋して語りたかったことであるが、それは叶わなかった(第19回「果たせぬ凱旋」)。
タイトルは「帰ってきた義経」
ですが、実際は首も鎌倉へは入れられず、源頼朝は源義経の首桶を見ていません。首実検は、和田義盛と梶原景時が腰越で行い、首は捨てられました。捨てられた首は、牛若丸時代の師・聖弘上人がもらいうけ、白旗神社(神奈川県藤沢市藤沢2丁目)付近に埋葬しましたが、その首塚は、今は均されて民家が建てられている。
話を戻すと、源義経生存説論者の論理の流れは、源義経の首を捨てる訳が無い(そんな礼を欠く扱いをしたら、怨霊になってしまう)→捨てたのは偽物だったからであろう→源義経は死んでいない、です。
(2)生存説
伝承地を線で結ぶと、北海道に渡ったとも、中国に渡ったとも。
いずれにせよ生存説は「源義経を怨霊にしない策」(生きていれば怨霊になれない)であろう。
源義経が生きていれば。奥州合戦に参陣したはずです。北海道に渡って、アイヌ人と組んで鎌倉を襲うという「義経=オキクルミ説」とか、シーボルトの「義経=成吉思汗説」(源義経は中国大陸に渡って成吉思汗となり、源義経(成吉思汗)の孫が、鎌倉幕府を倒そうとしたのが「元寇」)は荒唐無稽かと。両説に共通するのは「打倒鎌倉」であるが、『鎌倉殿の13人』の源義経は、「打倒鎌倉」の策を奥州藤原氏ではなく、いかに凄い策であるか理解出来る梶原景時に渡していた。梶原景時に渡したことは「打倒鎌倉を諦めた」ということ、奥州藤原氏に渡さなかったことは「自分の首で平泉を守ったと思っていたこと」を意味する。
『鎌倉殿の13人』には源義経が自害するシーンは無く、抜け道があることが示されたので、もしかしたら逃げたのではとは思いますが。
今回の脚本で気にいらなかったのは、源義経が目を輝かせて北条義時に「鎌倉攻め」の作戦を語るシーン。
源義経 「そこまで兄上にとって私は邪魔なのか。そう思うと、どうでもよくなった。この首で、平泉が守れるなら、本望だ。見せたい物がある。ここに来てから、いかに鎌倉を攻めるか、色々考えた。まずは定石通り、北から攻める構えを見せる。見せるだけだ。鎌倉勢は当然、鎌倉の北に兵を出して迎え撃とうとする。そこで、南側の海だ。平泉は北上川から直に船を出せる。まさか我らが船で攻めてくるとは思っていないだろう。ガラ空きの鎌倉の浜に乗りつける。北にいた兵が慌てて戻ったら、それを追い掛け、そのまま鎌倉全体を包囲。すべての切り通しを塞ぎ、袋の鼠にしてから、町に火を放つ。どうだ?」
北条義時「素晴らしい…。ただ…」
源義経 「どうぞ」
北条義時「船団が鎌倉の海に入る時、どうしても三浦の岬から丸見えになります。これはどうされますか?」
源義経 「三浦を味方につけておく。親父ではなく息子の方だ。あいつは損得の分かる奴だからな」
北条義時「恐れ入りました」
作戦の欠点を見つけた北条義時に、源義経が「どうぞ」と言うと、北条義時が「海から攻めたら三浦に見つかる」と指摘し、源義経が「三浦義村を抱き込んでおく」と答えた。「どうぞ」はないだろ。「落ち度があれば申してみよ」だろ。と言うか、「どうぞ」ではなく、「三浦の事だろ?」であれば、源義経の凄さが際立ったかと。答えも「三浦義村を抱き込む」ではなく、「鎌倉の海岸は砂浜で、(北条泰時が和賀江島を作るまでは)大きな港がなく、水軍も無いので上陸するまで襲われないから、奇襲にはならないだろうが、見つかってもかまわない」かと。
私が源義経なら「定石通り、7つの出入り口「鎌倉七口」から攻める構えを見せる。見せるだけだ。道無き道を越える。「鵯越の逆落し」だ。だが「一ノ谷の戦い」とは違う。海からも攻めて挟み討ちだ」って言うな。
ちなみに、鎌倉を攻略したのは、新田義貞「鎌倉攻め」と北条時行「中先代の乱」などである。なお、鎌倉幕府滅亡の日は、奇しくも689年前の今日(元弘3年(1333年)5月22日)である。
【雑談】「翔」と言えば、巨人軍の中田翔選手、いや、今話題のカジノプレーヤー・田口翔被告か。放送終了の数時間後、特大の日米通算150号HRを打ったMLBの大谷翔平選手の「翔」は源義経の「八艘飛び」、「平」は世界遺産「平泉」に由来するという。
■秘話 大谷翔平「二刀流の血脈」<第1回>「翔平」の由来は源義経だった
「義経が平泉にいたというのは、この辺りでは誰でも知っています。中国に渡ったとか、北海道に行ったとか、義経伝説もいろいろあって、歴史上のいいイメージがある。最初は「義経」でもいいかなと思ったんですけど、「大谷義経」では、いくらなんでもだいそれてるかなと(笑)・・・もともと「翔」という字が気に入っていて、「はばたく」というイメージがある。義経はなんかこう、身軽で美男子だったと聞いたこともありましたしね。「大谷翔」でもよかったんですけど、僕が「徹」でひと文字。これは僕自身が嫌で、上の子2人も、ふた文字にしたんです。ふた文字にすると、「翔平」とか「翔太」かなと。お兄ちゃんとお姉ちゃんは横浜で生まれたけど、あいつだけ岩手で生まれた。平泉も近い。なので平の字をもらって「翔平」と名付けたのです」(父・大谷徹氏談)
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/sports/158459
https://www.sekaken.jp/whinfo/blog/k178/
4.静御前
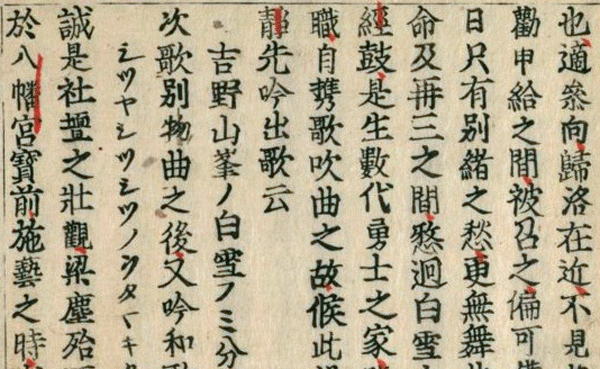
■『吾妻鏡』「文治2年(1186年)4月8日」条
文治二年四月大八日乙夘。二品并御臺所御參鶴岳宮、以次被召出靜女於廻廊。是依可令施舞曲也。此事去比被仰之處、「申病痾」之由不參、「於身不屑者者、雖不能左右、爲豫州妾、忽出揚焉砌之條、頗耻辱」之由、日來内々雖澁申之。彼既天下名仁也。「適參向、歸洛在近、不見其藝者無念」由、御臺所頻以令勸申給之間被召之。「偏可備大菩薩冥感」之旨、被仰云々。
「近日只有別緒之愁。更無舞曲之業」由、臨座猶固辞。然而貴命及再三之間、憖廻白雪之袖。發黄竹之歌。左衛門尉祐經鼓。是生數代勇士之家、雖繼楯戟之塵、歴一臈上日之職、自携歌吹曲之故也。從此役歟。畠山二郎重忠爲銅拍子。靜先吟出歌云。
吉野山峯の白雪ふみ分て入にし人の跡そこひしき
次歌別物曲之後、又、吟和歌云。
しつやしつしつのをたまきくりかはし昔を今になすよしもかな
誠是社壇之壯觀、梁塵殆可動。上下皆催興感。
(文治2年(1186年)4月8日。源頼朝と御台所(北条政子)は、鶴岡八幡宮を参詣した。そのついでに、静御前を(当時は舞殿がなかったので)回廊に呼び出した。これは、舞を奉納させるためである。この事は、前々から命じていたのであるが、「病気だ」と言って断っていた。「囚人なので、素直に言うことを聞かない訳にはいかないが、源義経の妾だとの掲焉(けちえん。目立つさま)は大きな恥辱である」として、日頃から渋っていたが、彼女は既に「名人」として天下に知られていた。「たまたま鎌倉へ来て、近いうちに京都へ帰るのに、その芸を見ないのでは残念である」と、御台所(北条政子)が頻りに言うので、承諾した。「絶対に(鶴岡八幡宮の)八幡大菩薩も気に入られるであろう」と言ったという。
「最近、人と別れるという悲しいことがあり、踊る気になれない」と、座に臨んだのに辞退した。しかし、何度も命令されたので、嫌々ながらも、白雪のような真っ白な袖をひるがえして、(北条政子がリクエストした穆王の)「黄竹詩」を謡った。工藤祐経が鼓を打った。彼は、数代続く武勇の家に生まれ、武芸を継いでいたが、一臈(六位の蔵人)として朝廷で勤務していた時、音楽に関わっていたので、この役を与えられたのであろうか。畠山重忠は、銅拍子(銅製の小型のシンバル)を打った。静御前は、先ず、
吉野山 峯の白雪 踏み分けて 入りにし人の 跡ぞ恋しき
と和歌を吟じ、次に
しづやしづ しづのおだまき 繰り返し 昔を今に なすよしもがな
と吟じた。
誠に社殿の有様は(八幡大菩薩が共鳴し)梁の塵が(振動で)殆ど全てが動いた。身分の高い人も、低い人も感動した。)
静御前のその後について、個人的には京都に戻って出家したのではないかと思うが、終焉の地は全国各地にある。『鎌倉殿の13人』の北条義時は、「青墓宿(岐阜県大垣市青墓町)の遊女になったという噂がある」と源義経に伝えた。それを盗み聞きしていた郷御前は「ざまぁみろ」と言い、土佐坊昌俊の「堀川夜討」は、郷御前が依頼した静御前暗殺未遂事件だと明かし、逆上した源義経に殺害された。(源義経は、土佐坊昌俊の「堀川夜討」は、兄・源頼朝が依頼した源義経暗殺未遂事件だと思い込み、兄の兄弟愛を信じきれずに挙兵したのだった。郷御前が依頼した静御前暗殺未遂事件だと知っていれば、兄の愛を信じて挙兵しなかったかもしれない。)
源義経「お前が…呼んだのか? 兄の策では、なかったのか?! お前が…呼んだのか。お前がー!」
▲「13人の合議制」のメンバー
【文官・政策担当】①中原(1216年以降「大江」)広元(栗原英雄)
【文官・外務担当】②中原親能(川島潤哉)
【文官・財務担当】③藤原(二階堂)行政(野仲イサオ)
【文官・訴訟担当】④三善康信(小林隆)
【武官・有力御家人】
⑤梶原平三景時 (中村獅童)
⑥足立遠元 (大野泰広)
⑦安達藤九郎盛長(野添義弘)
⑧八田知家 (市原隼人)
⑨比企能員 (佐藤二朗)
⑩北条四郎時政(坂東彌十郎)
⑪北条小四郎義時 (小栗旬)
⑫三浦義澄 (佐藤B作)
⑬和田小太郎義盛(横田栄司)
▲NHK公式サイト『鎌倉殿の13人』
https://www.nhk.or.jp/kamakura13/
▲参考記事
・サライ「鎌倉殿の13人に関する記事」
https://serai.jp/thirteen
・呉座勇一「歴史家が見る『鎌倉殿の13人』」
https://gendai.ismedia.jp/list/books/gendai-shinsho/9784065261057
・富士市「ある担当者のつぶやき」
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/fujijikan/kamakuradono-fuji.html
・渡邊大門「深読み「鎌倉殿の13人」」
https://news.yahoo.co.jp/byline/watanabedaimon
・Yusuke Santama Yamanaka 「『鎌倉殿の13人』の捌き方」
https://note.com/santama0202/m/md4e0f1a32d37
▲参考文献
・安田元久 『人物叢書 北条義時』(吉川弘文館)1986/3/1
・元木泰雄 『源頼朝』(中公新書)2019/1/18
・岡田清一 『日本評伝選 北条義時』(ミネルヴァ書房)2019/4/11
・濱田浩一郎『北条義時』(星海社新書)2021/6/25
・坂井孝一 『鎌倉殿と執権北条氏』(NHK出版新書)2021/9/10
・呉座勇一 『頼朝と義時』(講談社現代新書)2021/11/17
・岩田慎平 『北条義時』(中公新書)2021/12/21
・山本みなみ『史伝 北条義時』(小学館)2021/12/23
記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。
