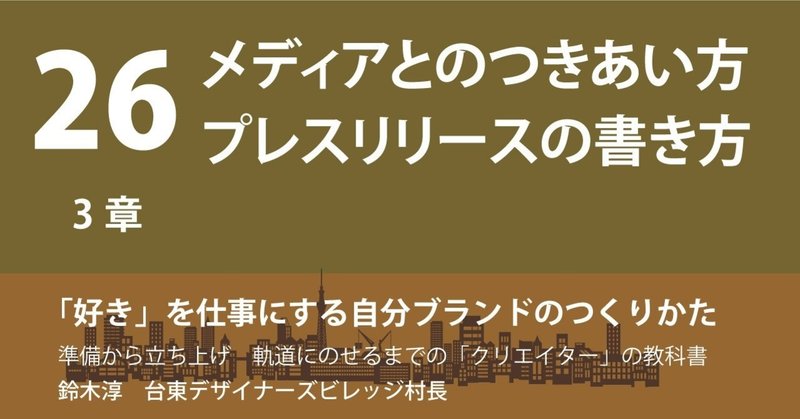
26終.メディアとのつきあい方。プレスリリースの書き方
連載も本稿で最後です。1ヶ月近くお付き合いいただきありがとうございました。最後はプレスリリースについて。現在はSNSでの発信が主力になっていますが、メディアの影響力は今でも大きいものです。また、プレスリリースを作る過程を通じて、自らの事業やブランドを客観的に見直すこともできます。ニュースや記事を読む人にとって、あなたの発信は意味あるものになるでしょうか?考え直すきっかけになるかもしれません。
◆マスコミとの付き合い方
バイヤーでも消費者でも、むりやり売り込まれると嫌になってしまうもの。しかし、マスコミやほかの人が「これはいい」と褒めてオススメするものは欲しくなります。「これはいい」と薦めてくれるマスコミは創業者の強い味方であり、マスコミに情報を伝えるプレスリリースは小さなブランドの武器なのです。
マスコミ掲載はブランドの信用を高め、チャンスをもたらします。
しかし、雑誌もビジネスですから、近年は広告重視。掲載してもらえるのは有名ブランドが中心です。お金がなくて広告が出せないクリエイターには厳しい時代。そんななかで紹介してもらおうと思えば、頭を使わなければなりません。
まずは相手の雑誌を知り、編集者の考え方や仕事を知ること。そこから、相手が求めているものを察する必要があります。こちらの都合による一方的な売り込みではダメなのです。
マスコミに掲載されるためには、掲載される理由を考え、読者にメリットがある材料を集め、取材したい、掲載したという気持ちを起こさせるきっかけを作ります。
デザビレでプレスの講師をしてくれたフリーランスのプレス鈴木清之さんは、メディアに対して、いつもおいしいお菓子を差し入れたり、電話では迷惑になることもあるのでファクスで連絡をしたり、バイヤーではなくマスコミだけを対象にしたプレスデーを設けて和やかに取材してもらう場を用意したり……。
プレスリリースも、どうすれば読みやすいか、文字組みや表記、レイアウト、写真などまで細かく考えているそうです。
取材してもらったときには、お土産としてそのブランドの携帯ストラップやミニポーチなどを渡し、スタイリストや編集者に使ってもらうと言います。そうすると、そこからまた取材の依頼が入ったりするのだとか。
気遣い→好意度形成→取材→お礼→2次取材というループができています。
「コム・デ・ギャルソンでも、特集を組んでもらったら、編集部にフラワーアレンジをお礼状とともに届ける。大手でさえ、そういう気配りをしているのに、小さなブランドが頑張らなくてどうするんですか!」。これは鈴木さんの言葉。本当にその通りです。
『JAPAN PRECIOUS』というジュエリー業界誌の記者・横内さんも、以前こんなことをおっしゃっていました。
「現在著名なジュエリーデザイナーでも、こまめにプレスリリースを送ってくる。月1回とか新商品が出るたびに。多い人は週1回くらい。そこまで送ってもらうと、たまには紹介しないと悪いかしらと思う」。
「ジュエリーというのは、宝石の材料の値段だけではなく、そこにデザイン・ブランドという高付加価値を与えている。創業期のブランドはプレスリリースをどんどん送ったり、展示会に出展するなどして知名度を高め、ブランド力を高めていくことが不可欠」。
「プレスリリースにつける商品写真、商品の脇にブランド名を入れて、ロゴも掲載してもらうような配慮が必要」。
「開発で一番苦労した部分が、こだわりや特長になるのだから、そこをしっかり伝えなくてはもったいない」。
「伸びていくブランドは、ナンバーワンの部分がある。ほかではやらない技術で差別化を図るのです」などなど……。
デザビレでは毎年『装苑』のニューカマーコーナー担当で、自分でもショップ・marmeloを経営する秋山美紀子さんにセミナー講師をお願いしています。
秋山さんいわく、「デザイナー側は自分のブランドツールのことだけ考えているのだけれど、受け取る側は何百通というDMが送られてくるなかから、どの展示会に行くか選ぶのだから、ブランドを伝えきる努力をしないとダメ」。
たくさんの競合ブランドのなかから選んでもらうためにはどうしたら良いか考えなくてはいけないのです。
たくさんのブランドとつきあう編集者の言葉はとても参考になります。
◆プレスリリースやブランド資料の送り方
プレスリリースを送付してマスコミに掲載してもらうことは、PR予算が少ない創業期のブランドには有効な手段です。ただし、掲載されるかどうかは、相手の判断次第。小さなブランドは話題性が低いと判断されやすいので、掲載してくれるのはとてもありがたいことです。
以下に、送る際に気をつけることとフォーマットを記しますので参考にしてください。
1)送り先を調べる
・送りたい雑誌や新聞の奥付や連絡先欄、webなどで送り先を調べる
・自分が掲載されたい特集記事の担当編集者やスタイリスト個人宛も効果的。できるだけ宛先担当者名を記入する。しないと捨てられることも
・業界紙:業界動向を紹介する役割があるので新商品・新ブランド情報を掲載してくれやすい
・ファッション誌:特集のテーマに合えば取り上げてくれることもある
・一般誌:社会性や話題性など掲載理由が明確な場合、まれに取り上げてくれる
2)送付する時期
・月刊誌掲載を希望するなら2ヶ月以上前、業界紙なら1~2週間前
・展示会に来場してほしいなら1~2週間前+数日前に電話プッシュ
3)送り方
・初めてのところには郵送。顔見知りになったらメールも可
4)送付するモノ
・挨拶文:挨拶、媒体を選んだ理由、相手にどうしてほしいか
・リリース本文:下記参照
・掲載用写真:記事に使ってもらう写真、雑誌の切り抜きなどは不可
・ブランド紹介資料:会社案内、パンフレット、カタログ、MD表などこれらがブランドらしくデザインされているほうが良い
5)送付状の注意
・展示会出展情報なのか新ブランド発表なのかコレクション発表なのかなど、リリースを送った理由を明確にする
・掲載して欲しいのか、来場して欲しいのかアクションを促す
◆プレスリリースのフォーマット例
プレスリリースは、記者・編集者に情報を提供し、その内容に対して興味をもってもらうことが目的。記者が興味を持ってくれて初めて記事として掲載されます。基本的にはニュース=新しいことを紹介する、ということを念頭においてください。
(1)報道資料
DMと区別するために書きます
(2)日付・発信人
20●●年●月●日 株式会社●●●●●●● 代表取締役●●●
(3)タイトルとサブキャッチ
例:「●●●なアパレルブランド●●●●がデビュー」例:「日本初●●●を使った新商品を●●●から発売」
・記者の関心を惹くようなタイトルと、サブキャッチを書くように注意。文字はやや大きく
(4)内容の要約
・とくに紹介して欲しい内容を150~300字程度で簡潔に要約
・商品特長や、他社商品との差別化ポイントを盛り込む
・「良質の素材」「こだわりのデザイン」「最高の品質」「消費者ニーズ」
「顧客志向」など抽象的な言葉は避けましょう。多くの企業がこれらの言葉を使うので特長が伝わりません。
・ほとんどの場合、タイトルと要約で掲載の可否が判断されます。記事にしたほうが良い理由、読者に伝えたほうが良い理由をお知らせするつもりで書きましょう
(5)本文(必須)
・記者が書く記事の材料なので客観的に書いてください
・新規性(どんな新しさがあるのか→報道としての役割)
・話題性(時事ネタや流行と関連付ける→読者が話題にしやすい)
・社会性(生活者にとってどのような恩恵があるか?→読者のメリット)
・経済性(どのような経済的なメリットを与えるか→市場の活性化)
・開発者の気持ちや主観はプレスリリースではなく、実際に取材してもらったときに話すようにするとよいでしょう
(6)商品の仕様
・商品名、アイテム名(品目)、価格、大きさ、素材など記事にした場合必要な項目を記載しておきます
・商品写真(裏にブランド名記載)かデータCD-ROMの添付も有効
(7)発信者の概要
・企業名・屋号・代表者名・資本金・事業内容・取引店舗等
・住所・電話番号(電話での連絡可能時間帯)・FAX番号・メールアドレス・担当者氏名(ふりがな)・ホームページのURL
・ここをきちんと書かないと、取材してくれません
(8)追伸
・手書きで書いておくと、目立つので読んでもらえます
(9)添付するブランドの紹介資料の例
以下のような内容を加えておくと理解してもらいやすいのですが、 内容がまとまっていないと、読むのに時間がかかるのも敬遠されます。
・ブランドコンセプト/デザイナーからのメッセージ
・イメージビジュアル
・商品のこだわりのポイント
・ブランドの経歴(創業から現在まで)
・デザイナーのプロフィール(学歴、職歴、受賞歴、メッセージ)
◆コラム:損得で対応を変えると人は離れ、変えないと人が集まる
連絡をマメに返してくれる人とそうでない人がいます。
返事をくれない人には、仕事のシステムよりも自分の能力や気持ちを優先して仕事をする、自分に得になるかならないかに敏感、あまり価値を生 まない作業が好きで目標を考えるのが嫌い、仕事をプロジェクトでするよ りも自分だけで完結させたいというような気質があるような気が。いきあ たりばったりでいつも余裕がないような感じです。事務連絡などは面倒な だけで自分の損になると思って、バカにしているのかもしれません。
いつもは連絡をおろそかにする人が、得になる話やマスコミには即効で 飛びついたりしているのを見るとがっかりするというよりも可哀想になり ます。自分の得になりそうな企業や仕事や人を嗅ぎ分け、そういう人には 媚びて、そうではなさそうな無名の企業や人を見下している人は、同じことを自分もされることになるから。
相手の立場で言えば、創業者と仕事をするのはあまり得策ではありませ ん。もっと実績や才能がある人を選べるのです。自分が相手によって態度 を変えているうちに、相手には人柄の浅薄さや余裕のなさ、人を見下して いる姿勢などが透けて見えてしまっています。
自分の損得や相手の企業規模などであざとく態度を変える人の周りから は徐々に人が減っていくのではないでしょうか。仕事の付き合いがあって も続かないことが多いようです。
逆に、損得関係なく人に対応できる人の周りには人が集まってきます。 面倒でもやるべきことをキッチリしている人や損に見えることでもわけ隔てなく行える人には、なぜかいい話とか協力者が。その結果、仕事がうまくいったりします。
周りの実例を見ていると、特に創業期の人の場合はかなり当てはまって いると言えそうです。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
このNOTEは、台東デザイナーズビレッジでの1年目~7年目ぐらいの活動や指導を書き続けたブログを基に再編集した著書「好きを仕事にする自分ブランドのつくりかた」から抜粋しています。
発行から10年が経ちましたが、内容的には今のクリエイターやブランドにも当てはまることが多いと思っています。
この本に書ききれなかったコンセプトの作り方、自分の生かし方、自分の思い込みを乗り越えて成果を出す方法などは、近著で紹介しています。「あなたの力を最大限に発揮して、人に喜ばれ、イキイキと仕事する」ためにどうするか、について書きました。よろしければぜひお読みくださいませ。
100ブランド以上を育ててきてわかったのは、「ビジネスを成長させるには、たったひとつの成功の法則があるのではなく、人それぞれの“自分の活かし方”を見つけることが大事だ」ということ。そんなことをツイッターでもつぶやいたりしています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
