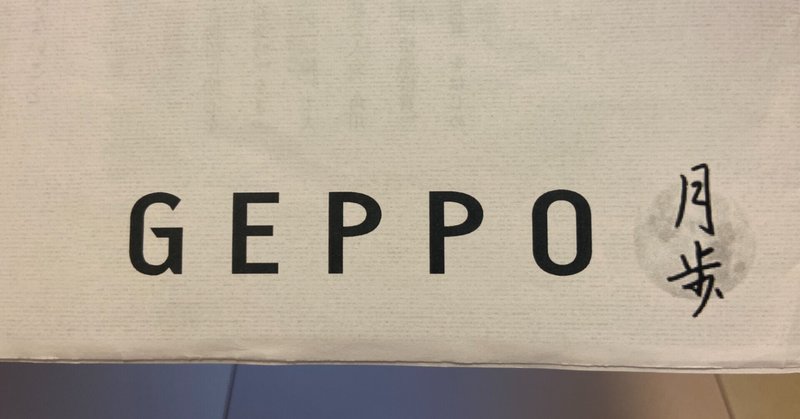
8/21(Sat) ネプリ「月歩」
10時、インターホンのチャイムに起こしてもらう。
宅配便で、たのしみにしていた伊勢宮忠の盛り塩器が届いた。

さすがヒノキ製。塩がこびりつかず圧倒的に盛りやすい!
歌集制作が本格化してから生活が不規則になり、寝つけない日々が続いたので、週2〜3回の盛り塩交換と玄関の掃き掃除を習慣にしてみた。体がすっと軽くなる気がしてなかなかよい。何かを信仰している、というわけでは全然ないのだけど、しばらく続けてみようと思う。
漬けるペースに消費量が追いついていないぬか漬けをつまみつつ、初校の戻しチェックや装幀・帯の色決めなど。デザインを任せている友人が、細かく相談に乗ってくれてありがたい。
*今日の一冊
遅ればせながら、先々月発足した短歌同人「月歩」のネットプリントを読んだ。以下、好きだった歌をいくつか。
サドルへと降りゆく蜘蛛のすらすらと四月の空はどこまで深き
/中野功一
自転車というとx軸(横の動き)を連想しがちだけれど、そのサドルに垂れてくる蜘蛛を描くことでy軸のイメージが加わり、景が際限なく広がっていくように感じる。「どこまで深き」という結句もその味わいを深めている。
君の歩く速度で自転車を押して行くタイヤに花弁巻き込みながら
/小島涼我
第三者には、想い人との楽しいひと時に映るかもしれないが、主体は必死で歩幅を合わせて歩き、そのせいで主体が押している自転車のタイヤはいくつもの花弁を巻き込み、潰している。だれかを想うことの壮絶な側面を匂わせる一首。
朝の陽のおすそわけです紙匙をりんごゼリーはするりとすべる
/ネコノカナエ
あったなあ、「紙匙」。給食でよく出てきた、自分で折って掬う面を作るタイプ。
↑
これ!!つるつるしていて舌に心地好いのです。
わたしは木匙の味がとても苦手なので、この紙匙に何度も救われた覚えがある。
りんごゼリーは朝の陽の色って感じがしますね。韻律も心地よい。
毎日の暮らしの上にラを乗せるラはやわらかくつまみ出される
/青海ふゆ
青海ふゆさんの7首どれもよかった。この歌が特に好き。
なんで「ラ」(=Aの音階)なんだろう?と色々考えて、明確な答えは出なかったけれど、オーケストラの楽器の調音で用いられる音階が確か「A」だったと思うので、「日常に調和をもたらすものや考え方」みたいな意味合いもあるのかなと思った。そういうものって簡単に排除されてしまうし。絶妙に腑に落ちる一首だった。
東京に凪を見つけて糖蜜を啜るロスタイムの四月あり
/宮下一志
都心の喧騒の中で偶然、ひと息つける静かなカフェなどを見つけた一幕だろうか。
「ロスタイムの四月」が面白い。多忙な冬〜初春を過ごしたあと、そこで奪われた余暇を取り返すように束の間の春を満喫している主体が思い浮かんだ。と思いきや、連作全体をみるとそうでもないようで、さらに深い解釈ができる気もしている。
思ひ出は抜け落ちぬ杭束にした線香花火に火を付けてゆく
/酒匂瑞貴
線香花火に着火すると、炎が小さく丸まり芯として安定する前に、大きくゆらぐ数秒がある。あの一時の炎って、なんとも言えない「だる〜い」感じがするんだよな…ということを思い出した一首。
途中で面倒くさくなったのか、今となっては思い出したくない夏の遺物なのか、本来なら一本ずつ楽しむはずの線香花火を束にして一気に着火する行為は地味に恐ろしい。
屋上で白く干されたシーツたち五月はきっと揮発する夏
/鈴木智子
五月にも本当は夏が来ているのだけれど、その夏が「何か」によって揮発してしまうから、まだ本格的には暑くならない。蝉も鳴かない。
…そう考えると五月が特別なものに思えてくる。また、そのあとに訪れる梅雨もその「何か」と関係していそうで想像が膨らむ。
五月の雰囲気を的確に捉えているとも言えるし、新たな視点を与えているようにも見える。干されているシーツも、刻々と移り変わる季節の層を表しているようで、下の句にうまく作用していると感じた。
十五時に今日の全てがいやになり豆を求めてコメダへ向かう
/丸山萠
コメダは珈琲店なのでこの「豆」はコーヒー豆のことと思う方もいるかもしれないが、多分違う。この「豆」は恐らく、コメダでお茶請けとして出される「豆菓子」のことである。あの「豆」、特段味付けされているわけでもないのにどうしてあんなに美味しいのか。ということを書いていたらまた食べたくなってきた…。「十五時」というのも絶妙。木曜日くらいかな。
行くあてのない夜のためいつまでも完成しない高速道路
/森山緋紗
もともと森山さんの短歌のファンだが、今回の「チャイナタウン」7首もとてもよかった。
高速道路と言っているけれど、上の句の語感からなんとなく夜の滑走路が浮かぶ。「未完成の道路」=「行き止まり」的な概念に繋げてしまいやすいところを「行くあてのない(=行こうと思えばどこへでも行けるけれどどこに行ったらいいかわからない)」としていることで、主体の状況や感情とより結びついているように感じる。
日陰から白い十字が空見上ぐ触れる者なきドクダミの花
/ゆり子
臭いなどから倦厭されがちなドクダミの花に着眼した、ハッとする一首。「白い十字」がドクダミのささやかながら凜とした佇まいを端的に表している。日陰に咲くから白が際立つんですよね。ドクダミには万能な薬効もあるし、主体の周りにこういう存在がいて、その人のことを暗に詠んでいるのかな、とも思った。
大変な思ひ違ひをしてゐたとだれかが言つて、夏の到来
/近藤あなた
すごく好きな歌。旧仮名にぴったり。
「ぼくは大変な思い違いをしていたみたいだ…!真犯人は…」と電話口で言いかけて殺される、クリスティの小説に出てきそうな人物が浮かんだ。でも、この歌においてその「重大な気づき」の後に来るのは夏。結句の抜け感がおしゃれ。この歌で始まる連作なら、何首でも読めてしまいそう。
同人誌には色々な形態があるようだけど、こうしてネットプリントで気軽に読めるものも今のご時世にはありがたいなと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

