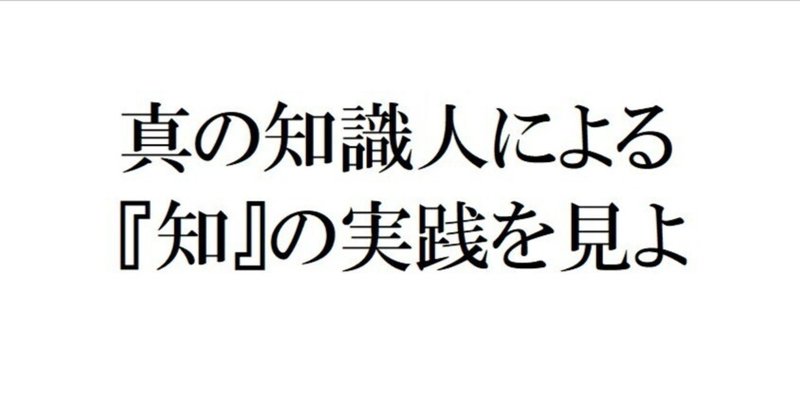
書評:『〈知〉の取り扱い説明書』(仲正昌樹著、作品社)
1.はじめに
正直侮っていたと言わざるを得ない。
著者はこれまで多くの思想家についての入門書・解説書を執筆しており、その著者が個別の「知」ではなく「知」そのものをいかに取り扱うかを教えてくれるというのは、強く興味を惹かれるものだった。
だが読み始めて私は落胆した。多少の勉強の仕方の他はバカな学生や大学、SNSを含めたネットへのグチが書き連ねられているばかりで、特筆すべき点のない凡庸な本だと失望した。
ところが中ほどまで読み進めたとき、突如としてソーカル事件批判がぶち上げられたことによって事情は一変した。
ソーカル事件とは「物理学者のソーカル(1955-)がインチキ科学哲学論文を書いて、社会思想系のそれなりに有名な雑誌に投稿して、採用され、後でそれを自分でバラし、だから、ポストモダン系はいい加減と煽ったことから起きた騒動」(p.98)のことである。その後、ソーカルはブリクモンとともに『「知」の欺瞞』を出版し、ポストモダン思想における理系概念の濫用を指摘、批判した。著者はこの『「知」の欺瞞』までを含めて批判している。
わずか2ページほどの分量ではあるが、そこには煮えたぎるマグマのようなパトスが噴き上がっていたのである。
するとどうだろう、それまで退屈だと思われていた記述の中に、まるで推理小説のように伏線が張り巡らされていたことに私は気が付いた。
この伏線はすでにタイトルから張られていたものであり、ソーカル事件への反論のみならず、本書の記述全体を律していたのである。
この緻密な構成こそが著者の言う「知」の実践なのかと私は感服した。そしての感動を少しでも多くの人と分かち合いたいと思い、この拙文をしたためた次第である。
2.真の知識人とエセ知識人
本書のタイトルは『〈知〉の取扱説明書』である。
手近にある取扱説明書を開いていただきたい。そこには正しい使用法と間違った使用法が記されている。これは「知」にも正しい使用法と間違った使用法があり、著者には何が正しく何が間違っているかの判断基準があり、かつその判断基準が正しいことを決定する権利があることを示している。
なぜ著者は自分の判断基準が正しいと決定することができるのか。結論を先に述べてしまうなら、著者が「真なる知識人である人文学者」だからである。
本文冒頭には次のように書かれている。
まず、「知」とは何か? そもそもそれを取り扱う「知識人」とは、何者か、その特性とは何か、を考えましょう。 私たちは、ほとんどの場合、テクストを通してしか「知識人」を知りません。「知識人」と呼ばれるような人と、個人的面識がある人はそんなにいないでしょう。「知識人」というのは、文字通りに受け取ると、「知」とはどういうものか実践し、模範を示してくれるはずの人です――その名に値しない〝知識人〟や自称〝知識人〟のことはとりあえず無視しましょう。「知識人」が示してくれる「知」のモデルを知るには、彼らの「テクスト」を読まねばなりません。(p.14)
実に含蓄に富んだ一節であり何度も熟読玩味すべきだろう。
ここで著者は真の知識人とその名に値しない〝知識人〟や自称〝知識人〟(仮にエセ知識人と総称する)を区別できると自負している。その自負は大したものだし、そのように自負する著者がまさかエセ知識人のわけがないだろう。
もちろん著者がエセ知識人でも構わないのだが、そうするとこの本はエセ知識人がエセ知識人を糾弾する自己批判の書ということになる。
真の知識人とエセ知識人の違いはどこにあるのか。われわれ一般人はいかにして見分ければいいのか。
著者は彼らの「テクスト」を読まねばならないと言う。だが、「テクスト」とは何を指すのだろうか。
大学の教授がツイートでやっているような放言と、その人が論文で書く内容は基本的に関係がありません。大学教授が紙やネットなどのマスコミ向けに書く文章も、正式の学術論文とは違います。(pp.99-100)
著者は奥ゆかしく「知」の範囲を学術論文に限定しているが、遠慮することはない。大学教授などの知識人の持つ「知」の実践は何も学術論文のみとは限らない。
「知」を学術論文として表すのも取り扱い方のひとつである。しかしひとつであって全てではない。ネットで放言するのも取り扱い方のひとつであり、マスコミ向けに書くのも取り扱い方のひとつである。そして全く取り扱わない(死蔵する)のもまたひとつの取り扱い方だろう。
そしてたとえ大学教授の放言と学術論文に関係がなくとも、大学教授の持つ「知」と放言には関係があるのだ。
ツイートやブログで発信される放言やマスコミ向けの文章も「テクスト」であり、知識人がどのように「知」を実践し、範を示しているかを知るには、それらのテクストが教えてくれることになる。
そしてこの一節は、「知」が必ずも人格の涵養に役立つわけではないことも教えてくれる。「知」が必ず人格を涵養してくれるのならば、ネットで放言を繰り返す大学教授が現れることもないだろう。
「知」が人格の涵養に必ずしも役立つわけではない(直接的な結びつきがない)のであるならば、「知」は何に役立つのだろうか。
それは真の知識人たる著者が、本書の全体を通して教えてくれることになるだろう。
3.真の知識人のランク付け
著者によると、真の知識人とは正式に学術論文を発表した大学教授だということになる。しかし真の知識人の中にもランクはある。
著者は次のような者達を完全に見下している。
Twitterで論争みたいな真似をやったり、自分のお仲間のツイートをいくつか孫引きして、○○がトレンド、世の中の常識だ、などと言いたがる人間は、本当に物事を知りたいのではなくて、相手を言い負かして「勝者」感を得たいだけだと思います。(p.74)
その辺の欲求不満なおっさんを言い負かして、あとで正体を知ったら惨めになるような相手に対して勝ったと言っているようだと、学者としての人生で負けています。(p.75)
あるいは
「老害」が出てくるのも、普段、学術的・教育的コミュニケーションができていないことに原因があるのだと思います。この場合の「老害」というのは、今テーマになっているのと関係ない、テーマについての自説を延々と語って、迷惑がられる、という人のことです。(p.150)
このように見下している連中のことを、著者は真の知識人として認めるのだろうか。「学者としての人生で負けています」「老害」とまで言い切っているのに?
しかし著者は知識人を知るにはテクストを読まねばならない、そのテクストはネットでの放言でもマスコミ向けの文章でもなく、学術論文であると言う。だとしたら知識人たる資格は学術論文を発表したか否かということになるだろう。
だとしたら、学者としての人生で負けていたり老害であったりしても、学術論文を発表していれば知識人だということになる。しかしその中でもダメな学者や老害がいるということは、質の良い知識人と質の悪い知識人がいるということになる。
そしてダメな学者や老害として一部の知識人を見下げているように、著者は自分を質の良い知識人に区分しているだろう。もちろん質の悪い知識人に区分している可能性もあるが、その場合、この本は質の悪い知識人が質の悪い知識人を糾弾している自己批判の書ということになる。
4.ソーカル事件批判
それではいよいよ著者によるソーカル事件批判を見ていくことにしよう。
これは、物理学者のソーカル(1955-)がインチキ科学哲学論文を書いて、社会思想系のそれなりに有名な雑誌に投稿して、採用され、後でそれを自分でバラし、だから、ポストモダン系はいい加減と煽ったことから起きた騒動です。(p.98)
ここにひとつ情報の歪曲がある。ソーカルとブリクモンはあくまで理系の概念の濫用を批判しているのであって、ポストモダン思想全体を否定しているわけではない。
該当する箇所をいくつか、私の手持ちの2000年発行版『「知」の欺瞞』(岩波書店)から引用しよう。
われわれの目的は、まさしく王様は裸だ(そして、女王様も)と指摘することだ。われわれは、哲学、人文科学、あるいは、社会科学一般を攻撃しようとしているのではない。それとは正反対で、われわれは、これらの分野がきわめて重要であると感じており、明らかにインチキだとわかる物について、この分野に携わる人々(特に学生諸君)に警告を発したいのだ。(p.7)
これらの著者たちの仕事の中の科学とは無関係な部分についてまでとやかくいう資格がわれわれにないことはいうまでもない。また、自然科学への「介入」が彼らの仕事の中心課題でないこともよくわきまえている。それでも、誰かの書いたものの中に、たとえそれが些細な一部分であろうとも、知的不誠実(あるいは極端な能力不足)の兆候が見いだされれば、その人の作品の他の部分もより批判的に読んでみようと考えるのが自然ではないか。そうやって批判的に分析した結果が白とでるか黒とでるか、ここで予断したくない。われわれは、学生が(そして教授たちが)そういう批判的な分析に踏み切るのを時として阻んできた、深遠さというオーラを取り除きたいだけなのだ。(p.10)
われわれはラカンの精神分析、ドゥルーズの哲学、あるいは、ラトゥールの社会学での具体的な業績の正しさを判定しようなどとはいっていない。われわれが問題にするのは、あくまでも、数理科学、物理科学、あるいは、科学哲学の基本的な問題に関連する主張だけなのだ。(p.16)
当然のことながら、二人の意図を越えてポストモダン思想全体を否定するのであれば、それこそ「知の濫用」のそしりを免れないだろう。
著者によるソーカル事件批判に戻ろう。
私からすると、その雑誌は、ポストモダン系の思想の代表というよりは、新左翼系のだし、仮にポストモダン系だとしてもその雑誌の査読体制が、科学論文系に関して緩すぎたからといって、ポストモダン思想全体を否定するなんて無茶な話です。(p.98)
ポストモダン系の思想の雑誌であることと新左翼系の雑誌であることは別に矛盾することではない。まさか現代思想がまったく法や政治に関わっていないとは著者も言わないだろう。
そこ(ブリクモンと共著の『知の欺瞞』/引用者注)に列挙されているのは、その人たちの主用著作の一番重要な箇所、論証の最重要部というよりは、周辺的なテクストで、それもたまたま理系っぽい喩えを、本当に言葉の彩として使っているという感じで、ポストモダン思想全体を否定するというよりは、揚げ足取りです。この程度の比喩なら、理系の学者でも使うだろう、という感じがします。(p.98)
言葉の彩なら適当なことを書いてもいいのかだろうか。そもそも言葉の彩になっていないというのがソーカルとブリクモンの主張である。
われわれの引用した部分は、正確な論理的な議論としてではなく、メタファー(比喩)として読まなくてはならないというわけである。確かに「科学」が疑いようもなくメタファーとして用いられている場合はある。だが、このようなメタファーは馴染みのない概念を馴染み深い概念と関連させることで説明するものであって、決して逆の状況では使わない。……ほとんど全員が科学者ではない読者のために、たとえメタファーのためだったとしても、自分自身あやふやにしか理解していない科学の概念を喚起する利点はまったく理解できない。(『「知」の欺瞞』p.14)
誤った知識をもとにした比喩が正しい理解を促すとは思えないのだがいかがなものか。
何をその人の主要著作とするかについては色々と意見があるだろうが、しかし例えばドゥルーズとガタリの『哲学とは何か』でときには数ページにわたる記述を、主要著作でも論証の最重要部でもない「周辺的なテクスト」とするのは無理がないだろうか。
さらには「この程度の比喩なら、理系の学者でも使うだろう、という感じがします」とはあまりにも曖昧な物言いである。「印象で「ダメ」は、ダメ」(p.78)と言ったのは著者自身ではなかったか。
無論、ミイラ取りがミイラにならないようにしないといけません。私も瞬間的に、他の人がそういうダメ人間だと判断し、心のなかでバカにすることはありますが、それを書いて公表してしまうと、なぜその人が「○○」なのか実証しなければいけなくなります。(p.78)
印象で語ってならないのはその通りである。であるならば、「~だろう、という感じがします」などという曖昧な印象で語るべきではないし、自分の言に従ってきちんと使ったところを実証すべきである。
ソーカルは、「それを読んだ人たちから、ポストモダンの思想の全体を知らないのに、揚げ足だと言われるだろう、しかし、……」という感じのことを書いています。 そんなのは普通に考えて、言い訳でしかありません。しかし、例えば、私がそれはドゥルーズやボードリヤールの著作の主要な部分ではないし、単に分かりやすい比喩として使っているだけで、論証に使っているわけではない。そんな揚げ足取りで論破したつもりになるのはおかしい、と指摘すると、ネットの安易な自称反ポストモダンの連中は、「ソーカルが予め釘をさしておいたことを言っている(笑)、この程度」、と勝ったつもりで騒ぐ。あらかじめ、相手の反応を予測して、言い訳しておいたら、論破したことになるのか。多分、彼らの喧嘩では、そういうルールがあるのでしょうが、なぜソーカルや彼らの勝手なルールに則って議論をしないといけないのでしょうか。(pp.98-99)
まず、ポストモダン思想の全体を知らないならポストモダン思想における理系概念の濫用を批判をしてはならないとはならない。著者もまた「理系のことを全部分かってる人間などいるはずないじゃないですか」(p.113)と述べているが、それでも後で検討するように理系批判を行っている。
次に、反論をあらかじめ予想し、それに再反論しておくことは悪いことではない。肝心なのはその再反論が理にかなっているかどうかであり、それに対して「言い訳」「揚げ足取り」としか返せないのだとしたらソーカルとブリクモンの図星だったことになる。
「あらかじめ、相手の反応を予測して、言い訳しておいたら、論破したことになるのか」は反語としては「論破したことにならない」だが、これは相手の再反論自体を無効化したいだけである。
例えば著者はレポートを提出してきた学生に質問し、それに対して答えられなかったらどうするのか。本作中で何度も繰り返したように「バカな学生」だと言って鼻で笑うのか。それともそもそも反論を許さないつもりなのだろうか。むしろ勝手に相手にルールを押しつけて相手の行動を規制しようとしているのは著者のほうである。
文中の「ネットの安易な自称反ポストモダンの連中」というのが具体的にどのような連中か具体的な記述はないが、ひとまず「ポストモダン思想の文章を読んでないのにポストモダン批判する連中」ということにしておこう。
ポストモダン思想にまつわる話でいうと、「文章を読んでいない人間がポストモダン批判をしても意味がないじゃないか」と私が言うと、「これだけ自然科学が発展して、その専門家たちが非科学的だと言っているんだからそうなんだ」と返ってくる。しかしその「専門家」の意見がどれだけ積み上がっても、「読んでないなら批判できない」ということは変わらないのですが、そのことが分からないみたいです。(p.57)
ソーカルとブリクモンの二人と、「ポストモダン思想の文章を読んでないのにポストモダン批判する連中」をしっかり分けないといけない。ソーカルとブリクモンは、きちんとポストモダン系のテクストを読んだのだから批判することができる。そして二人の理系の知識はその分野で大体確立された知識であるので、既成事実として信用させてもらうことができる。
人文系、社会科学系の知も、様々な分野が支え合うネットワークになっているので、全部を知るのは無理だし、その必要はありません。これとこれは、この分野で大体確立された事実のようになっているし、それは自分の専門でもないので、その既成事実を信用させてもらおう。しかし、ここから先は自分でちゃんと検討しないといけない、と分かっているのが「知を使う」ということです。自分の能力も踏まえながら、自分の知るべき範囲をわきまえることが前提です。(p.41)
しかし、これは何度でも強調しておくが、ソーカルとブリクモンの検証をもってポストモダン思想全体を否定する叩き棒とするのなら、それは二人の意図から外れるものであり、虎の威を借りる狐である。
ところで著者はソーカルとブリクモンの再反論を「言い訳」としているが、これは一つの印象操作である。「言い訳」とは、私の持っている『新明解国語辞典』によると、「自分のした失敗・過失などについて、そうならざるを得なかった事情を客観的に説明して、相手の了解を得ようとすること」である。
つまり著者は、ソーカルとブリクモンがなんらかの失敗を犯し、それに対して取り繕おうとしているとしたい、あるいはソーカルとブリクモンが「失敗した」ことにしたいと考えていることになる。だが、一体何が「失敗した」のだろうか。これは後ほど判明する。
ソーカルの意図的なデタラメを掲載してしまったような、そういうユルい雑誌が一つあったからといって、なぜ現代思想全体がデタラメだということになるのか。『ネイチャー』だってフェイク論文はいくらでも載せています(笑)。撤回もしょっちゅうやっている。雑誌に一回載せたら、なんでそんなに偉くなるのでしょうか。(p.99)
ポストモダン思想全体がデタラメかどうかは知らないが(ソーカルとブリクモンはそれについては言及していない)、しかし著者の記述を読む限り、そもそもポストモダン業界全体が緩いのだと言わざるを得ない。つまり、ソーカルの論文が採用されたからポストモダン思想がデタラメなのではなく、ポストモダン業界がデタラメだからソーカルが論文を投稿したのが正しい。因果関係が逆なのだ。ポストモダン業界がポストモダン思想の「言葉の彩」を許していたことが、ソーカルがパロディ論文を思いつくきっかけになったのだ。
著者は「その雑誌の査読体制が、科学論文系に関して緩すぎた」と言っているが、ということは当然だが査読の緩くない雑誌もあるはずである。しかしソーカルがパロディ論文を書こうとしたきっかけである各思想家の著作がそのまま世に出ているということは、業界全体のレベルがその程度だということになる。
著者はポストモダンにおける「言葉の彩」と『ネイチャー』に掲載されたフェイク論文を同列に置いているが、それならばそれ相応の対応をポストモダン側は取っているのだろうか。本書で言及されているSTAP細胞事件でも『ネイチャー』に載った論文は撤回され、関係者は処罰されているが、ソーカル事件の後にきちんと撤回されたポストモダンの著作はあるのだろうか。それがなされていないのなら、著者の対比に従う限り、「文系には学問の手続きが不要」だと思われても仕方ないだろう。
5.批判するは我にあり
それにしてもなぜ著者はこれほどの熱量をもってソーカル事件に対して反論を行うのだろうか。あたかも信ずる神の無謬性を傷つけられた信徒のようである。
もちろん不当な言いがかりに対して反論を行うのは正当な行為であるだろう。しかしソーカルとブリクモンのものは「ポストモダン思想の文章を読んだうえで批判している」のであるし、その批判内容はポストモダン思想の理系概念の濫用である。著者もポストモダン思想における理系概念の濫用自体は否定していない。ただその濫用を「言葉の彩」としてすませているだけである。
著者のこれほどの熱意を引き起こした原因は、おそらくソーカルとブリクモンの批判が著者にとって許しがたい越権行為だからだと思われる。
「大人になる」とは 1.ルールはそれぞれの環境で違う。 2.環境が変わった、自分に求められている基準が変わった。 以上のことが分かること。(p.89)
学問分野によって関心の中心が違い、それぞれに違ったルールがあると考えるべきです。馬鹿の一つ覚えの人は、ある分野でこの言葉はこう理解するのが正解だと言われると、それが同じ言葉、表現が出てくる全領域に通用すると思ってしまいます。(p.89)
一つの会社ではこうしている、というルールがあっても、同じ業界でも他の会社では違うということはよくあります。家族のなかのルールもそうでしょう。そこを勘違いして、自分の家族のなかで正しいことが世の中全部で通用すると思い込む人がいます。市や県が変わるだけで行儀作法が違うというのを経験すると、学問も、領域ごとにルールが違っていて、よそに口出しをするときは違うルールがあるんだろうなと推測することができます。そういうことを知っていることが大事ですね。(p.89-90)
「学問分野によって関心の中心が違い、それぞれに違ったルールがある」ことに気付かず、無粋な突っ込みをしてしまったソーカルとブリクモンは「大人」ではなかったらしい。「そういうことを知っていることが大事」なのである。
そもそも著者によると、人文系の学問は引用や注を疎かにしてもいいのである。
日本にはマルクスがどこで何を言ったかについてやたらにうるさいマルクス文献学者というか、マルクス・オタクの人たちがいますが、この手の人たちは、マルクス自身の引用の不正確さや事実誤認には結構甘いというか、神様は間違わないくらいに思っているのかもしれません。ハンナ・アーレントは、もっと引用とか注の付け方の間違いがひどいですが、アーレント・ファンの人たちも、神が間違えるはずないと思っているようです。こういうことを疎かにしないという姿勢がないと、人文系の学問をちゃんとやっていくことはできません。(p.19)
引用や注の間違いを疎かにしていたら人文系の学問ができないというのなら、そもそもマルクスやアーレントは人文系の学問をちゃんとできていないことになってしまう。しかし一般的に、マルクスやアーレントはちゃんと人文学をやっていることになっている。そうすると、その一般的な評価が実は間違っているか、引用や注の間違いを疎かにしていても人文学はちゃんとできるのだということになる。そしてマルクスやアーレントが実は人文学ができていないのだとしても、ちゃんとした人文学者として流通している以上、結局引用や注を疎かにしてもいいのだということになる。
ちなみにここのマルクスとアーレントをポストモダン思想にすると、まるきり著者に当てはまることを指摘しておこう。ソーカルとブリクモンに間違いを指摘されても「言葉の彩」ですませる著者は、「神様は間違わない」と思っているのだろう。
著者は文系のやり方に口をはさむ理系学者にも苦言を呈している。
(大学教員の就職について/引用者注)文化省もそうですが、理系から、文系も自分たちと同じ基準にしろといいう圧力もあるようです。外部資金獲得や査読付きの論文の点数、国際学会の発表などの条件を満たしていなかったら、偉い先生が推薦しても意味がないわけです――文系は外部資金を得られる当ては少ないし、そもそも理系ほど研究費はいらないし、発表媒体も限られている、といった事情の違いがあるのに、理系の人たちはそういう違いは一切無視して、「あんたたちは、怠けている」という思い込みで、攻撃してくる。(p.120)
だが、著者もまた理系のおかしいと思ったことには口を出している。そしてそれに対し社会の違いを持ち出されることには納得せず不満たらたらである。
自分が普段やっているようにやらせてもらうのが科学的。自分はプロとしてこのやり方でやってきた、自分は科学者だ、だからこれでいいんだ。他の研究機関、他分野の人から、うちではそんなことはありません、と指摘されると、「あんたたちは、科学的じゃない」、と言い始める。(p.114)
だとしたら文系の大学教員の就職について理系から「うちではそんなことはありません」と言われても納得するしかないだろう。それとも「あんたたちは、文系的じゃない」と言うつもりだろうか。
それでも、自分の身に付けたやり方だけが、「科学的」だと信じて疑わない人がいます。自分が、「科学」だと錯覚しているのかもしれません。そういうふうに思い込んでしまうと、何でも答えられる万能の専門家になってしまうのかもしれません。文系の学者に、「それはあなたの専門ではないでしょ。なんで人流抑制の効果が感染症学で分かるんですか」、と聞かれると、「科学的でない人間の感情的発言だ!」、と感情的に反応し、〝理系〟崇拝者を動員して、その疑問を強引に封じ込める。(p.115)
それはそうかも知れないが、だったら「よその社会に口を出すのは大人ではない」という話はどこへ行ったのだろうか。それでいいならソーカルとブリクモンがポストモダン思想の理系概念の濫用に口を出すことも正当だとなるし、それに対して文句を言うのは不当だということになる。なぜ大人がどうたらなんて話題を出したのか。
自分が他の社会に手口を出すのは正当だが、他から自分の社会に口を出されたときはことさら違いを強調し、攻撃されていると被害者意識を募らせれるのは公平とは言えないだろう。
しかもこの引用個所は、理系と文系を入れ替えると、そのままポストモダンとそれを擁護する著者に当てはまってしまう。
理系の学問を引用しまくるポストモダン思想家は「何でも答えられる万能の専門家」になったつもりだろうし、理系の学者(ソーカルとブリクモン)に「それはあなたの専門ではないでしょ」と聞かれると、「言葉の彩の分からない感情的発言だ!」と感情的に反応してその疑問を強引に封じ込めようとする。
さらに著者は理系に対し、それこそ「揚げ足取り」としか言いようのない口出しをしている。
実験室の長である教授に対して外から命令するな、実験に際しては無駄口をたたくな、学生は教授と話したかったらアポイントメントを取れ、電気の無駄遣いをするな、試薬の量をちゃんと計算しろ、換気をしろ、こういう指示は研究の本体とは関係のないことです。(p.117)
電気の無駄遣いをしないのは理系文系以前の一般常識だと思うのだが、文系の常識では違うのか。試薬の量をちゃんと計算するのは実験結果に関わるし、試薬を無駄に使っていいわけでもないだろう。換気をしっかりするのも安全上してしかるべきだ。また、それ以外のこともそれぞれの研究室(社会)のルールの違いの範囲である。著者も大人になるべきではないのか。
だが、そうではないのだ。文系の真なる知識人である著者は、大人になる必要などないのだ。次はそれについて述べる。
6.教養とは何か
それにしても、なぜ文系の著者は理系に対して口出しをしまくるのに理系の学者から文系への口出しは断固として許さないのだろうか。その理由は著者の文系の学問への関わり方、そして最終的には文系の学問の成り立ちそのものにある。
著者は「学問と自分が一体化してしまう困った人」(p.115)として次のように書いている。
学者のなかには、自分の研究をしている領域が、その学問分野全体を代表している、と思い込んでいる人が少なくありません。分子生物学者や疫学者が、「科学」全体を代表するかのように語るのが一番極端な例ですが、民法学者や刑法学者が「法学」を代表して、「法学的には……」と言うとか、ドイツ近代史の研究者が、「歴史学的には……」と言うとか。全く当該の学問に馴染みのない人に、「●●入門」的な話をするときに、大ぶろしきになるのは仕方ないことですが、「法的には……」と言って異論を封じ込めようとするのは、傲慢で有害です。
問題は、自分がその科学の実態になってしまい、自分のあり方が即・科学的だと、どこかで思ってしまうことです。これは何も大御所に限らず、学部四年生ぐらいで言い出す例もあります。「○○的に正しい」を自分が身に付けて体現していると思い込んでいる。(pp.115-116)
ここは著者自身が学問と一体化している例である。自分が法学的な思考ができていると考えないと、相手の思考が法学的に正しいか否かの判定ができないだろう。
この理屈は法学だけでなく、著者の挙げている分子生物学や疫学、歴史学の全てに当てはまる。そうでないなら、なぜ著者は相手の言っていることが科学的、歴史学的に正しいか否か判断できるのだろうか。分子生物学者や疫学者の言っていることが、科学全体に当てはまることもあるし、当てはまらないこともある。しかしそれを判断するには、自分がその判断基準を持っていなくてはならない。
また、ポストモダン思想と一体化していないと、ポストモダン学者の述べる、理系の学者でも意味の取れない専門用語の羅列を、「言葉の彩」「単に分かりやすい比喩」と判断することもできないだろう(「ポストモダン的には……」)。
しかしそういう学問と自分が一体化して異論を封じ込めようとするのは「有害」で「教養がない」のではなかったか。
自分と合意できない人間は法学的じゃない。
そういう人は端的に教養がないんだと思います。(p.116)
だとしたら、学問と一体化している著者は教養がないことになってしまうが、それでは本書は教養のない人間が教養のない人間を糾弾する自己批判の書になってしまう。まさか真の知識人である著者に教養がないわけがないだろう。この矛盾をどう解釈すればいいのか。
だが、これにも著者はちゃんとヒントを出している。著者が「学問と自分が一体化した人」と表現したことをよく考えなくてはならない。
一体化とは「いくつかのものがまとまって一つの組織となること」である。学問でないものが学問と一体化するから教養がないことになるのであって、そもそも学問自体であるのなら教養がないことにはならない。つまり、著者は学問のイデアであり教養そのものである。これならば矛盾は生じない。さすがである。
それではこの教養について、著者はどのように述べているのだろうか。
古代ローマのキケロのような思想家にとって、「人間」とは「市民」であり、市民として都市国家の公の領域で活動する際に身に付けるべき素養、弁論術、文法、論理学のようなものを「フマニタス」と呼んでいました。ルネサンスというのは、古代の「フマニタス」の研究を復興することを目指したという意味で、「人文主義=ヒューマニズム」とも呼ばれています。文学部で学ぶ科目のことを、「人文humanities」と呼ぶのも、この「フマニタス」という概念に由来します。(pp.22-23)
(特定の概念をめぐる/引用者注)そうしたこだわりが生まれるには、最低限、本や論文をよく読んで中身を把握し、どの領域で何がキーワードか把握する読解力、文脈把握力が必要です。自分も議論に加わるには、そうしたテクスト読解のなかから自分独自の考え方を見出し、それを、議論する相手に向かって表現する能力が必要です。こういう能力は、フマニタス以来、人文系の学問全般に共通する基礎ですし、学者、知識人になるつもりがない人でも、情報収集・精査、プレゼン、ディベートなど、言語に重きがある仕事や活動に関わっている人全てにとって、不可欠でしょう。(pp.23-24)
「こういう能力」は別に人文系の学問全般に限定する必要はなく、理系の学問にとっても必要なものだろう。なぜ著者は「人文系の」と限定しようとするのか。もちろん著者は理系の学問を全く無視しているわけではない。筆者は続けて「学者、知識人になるつもりがない人でも」と、人文系の学問以外でも必要だと述べている。だとしても、それは理系の学者は学者や知識人ではないことになるだろう。なぜ著者は理系の学者を学者・知識人から締め出そうとするのだろうか。
それはそもそも「フマニタス(humanitas)=教養」(p.22)だからである。
古代ローマのキケロのような思想家にとって、「人間」とは「市民」であり、市民として都市国家の公の領域で活動する際に身に付けるべき素養、弁論術、文法、論理学のようなものを「フマニタス」と呼んでいました。ルネサンスというのは、古代の「フマニタス」の研究を復興することを目指したという意味で、「人文主義=ヒューマニズム」とも呼ばれています。文学部で学ぶ科目のことを、「人文humanities」と呼ぶのも、この「フマニタス」という概念に由来します。(pp.22-23)
(特定の概念をめぐる/引用者注)そうしたこだわりが生まれるには、最低限、本や論文をよく読んで中身を把握し、どの領域で何がキーワードか把握する読解力、文脈把握力が必要です。自分も議論に加わるには、そうしたテクスト読解のなかから自分独自の考え方を見出し、それを、議論する相手に向かって表現する能力が必要です。こういう能力は、フマニタス以来、人文系の学問全般に共通する基礎ですし、学者、知識人になるつもりがない人でも、情報収集・精査、プレゼン、ディベートなど、言語に重きがある仕事や活動に関わっている人全てにとって、不可欠でしょう。(pp.23-24)
このフマニタスの伝統の価値観においては、人文系の学問(フマニタス)は「人間」、つまり国家運営に関わる市民にとって必須の教養であり、理系の学問はそうではない副次的なものである。だから人文系そのものである真の知識人である著者は、ナチュラルに理系の学者を学者・知識人の範疇から外してしまうのである。そして副次的な学問である理系の学者のソーカルとブリクモンによる指摘は分を弁えない「揚げ足取り」であるし、そういう揚げ足取りをしてしまったことは「失敗」であるのだ。
7.人文学パンテオン
こうして著者による人文学的ヒエラルキーの世界観が明らかになる。
まず頂質の良い人文学的知識人を頂点とし、その下に質の悪い人文学的知識人と理系の学者が位置する。この二者の上下関係は不明である。その下に学術論文を発表したことのない一般人が存在する。
この人文学パンテオンに君臨するのが学問のイデア、教養そのものである著者である。なぜならば、知識人の質が良いか悪いかを判定する権能を持っているのだから。
こうした世界観において、雲上人である著者からは地上にうごめくわれわれ一般人はどのように見えているのだろうか。
端的に言って「馬鹿」である。
人間の生きている社会は複雑なので、分かりやすいというのは本来おかしいのです。教科書が分かりやすいとすれば、馬鹿な自分たちにも分かるように、概念を固定して簡単にしてもらっているだけだと考えるべきです。(p.180)
「こういうふうに分かりやすくしてもらっているんだろうな」ということを忘れないこと。そういう意識があると、分からなくなったときにもう一度勉強し直してみようと思うことができます。(p.180)
光輝く人文知に浴することのできないわれわれ一般人にとって、真の知識人である著者によって与えられる数々の入門書・解説書は、まさに恵みの雨である。人々は「なるほどこれは分かりやすい。ありがたいことだ」と涙を流して喜ぶだろう。アマゾンレビューにもそのような感謝の言葉が数えきれないほど書き連ねられている。
そうした人々に対して著者が放つ言葉が「馬鹿」である。
本職の理系学者ですら意味不明と投げ出すポストモダンの難解な記述を、分かりやすい言葉の彩として読み解く著者からしたら、「馬鹿なお前たちにも分かりやすいように概念を固定して簡単にしてやっている」のだ。大変な手間をおかけしてしまい、申し訳ない気持ちでいっぱいである。
われわれ馬鹿な一般人は真の知識人である著者に「分かりやすくしていただいている」ことを忘れず、こうべを垂れて感謝しなくてはならないのだ。讃えよう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
