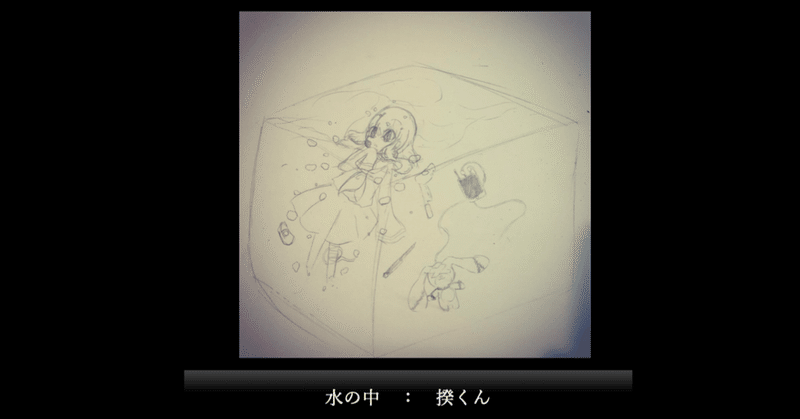
できる、できないは別にして、理想の教育制度を語ろう19
magenta-hikari様のコメント(3/31)
(前略)日本の教員は、相対的に志が高く、能力も高い方が多くていらっしゃるのに、
本来の職務にフォーカスできない勝手な押し付けが、日本の社会から教育現場に向けてあると思います。
文科省が推奨する「アクティブラーニング」は、従来(例えれば、“昭和な”授業スタイル)よりも遙かに高い指導力と、教材研究を要します。今一度、教員は「教科授業遂行」に専念させてあげたらいいんじゃないかな・・・。
そのためには、教員免許を持っている以外の人材をたくさん、教育現場に引き入れることが出来る制度を整えられるといいんじゃないのでしょうか。多様化する社会に対応するには、教育が担う役割は非常に大きいです。まずはその教育現場の“鎖国”を解いてやり、多様化することがスタートとなるのかもしれませんね。
*小鳥遊 樹のコメント
「日本の教員は、相対的に志が高く、能力も高い方が多くていらっしゃるのに、
本来の職務にフォーカスできない勝手な押し付けが、
日本の社会から教育現場に向けてあると思います。」とのことですが、
本当にそう思うのです。
これも、誰かが悪者なのではありません。
なんとなく今の状態に積み重なってしまって、
直しようのないものに思われているだけなのです。
学校の先生達の苦労を、
他人事ではなく、自分の子ども苦労のように捉えて、
一つ一つベストな制度になるために、
私たちが何をできるか考えていかなければならないと思います。
部活の負担を減らし、お休みを確保しているのは良い傾向ですね。
それは結局、未来を生きる子ども達の才能を伸ばし、
ひいては社会のためになるからです。
先生達のゆとりとリラックスは大事だと思います。
PTAの役員なども、生徒数が多い頃に作られて、
親も先生も負担が大きいのに、
なくならない委員会もあると思います。
時代が変わるとともに、
必要のなくなった制度の断捨離や、
子ども達の資質が変化しているために、
かかる先生達への負担を減らすために、
定期的に制度の見直しが必要です。
これらは、地域の慣習や気候に大きく関わってくることですから、
地方での決定権の権限が大きい方が良いですね。
日本の教員は、能力が高くないとなれない仕組みになっています。
特に教育学部で小学校や複数の免許をとる人たちは、相当な苦労をしています。
そのことがかえって、教員全体の質を多様性から遠ざけてしまい、
子どもたちの多様性に対応できない組織になっているのです。
能力が高い=偏差値が高いになってしまい、
偏差値が高い人たちというのは、
総じて決められたことを上手にこなす人たちです。
真面目で一生懸命。
頭の回転が早くて努力家。
それはとても素晴らしいことです。
けれど、同じ種類の人たちだけが、
指導者として居心地がいい場所を作ろうとしてしまうと、
未知の特異な才能を見過ごしがちです。
ですから、とんでもない先生のドラマなどは人気がありますね。
小学校であっても、
もっと専門的な教育の仕方であってよく、
同じ先生が全ての教科を教える必要なんてありません。
能力が高いからこなせてしまうかも知れないけれど、
子どもの立場に立ってみたら、
相性の合わない先生に全てのことを教えられたら、
好きになるものも、ならずに終わってしまいそうです。
子どもに何か教える人は、
教える分野が生きる喜びでなければならないと思うのです。
そのくらいの情熱がないと、教わる側に面白さが伝わらない。
カリキュラムがあるから教えるのではなく、
学問としてのテンションを子ども達に伝えられる教育の仕組みを考えた方がいいのです。
極端な例ですが、宇宙のことは宇宙飛行士さんに教えてもらい、
動物のことは動物学者や飼育員さんに教えてもらうのが良いと思うのです。
学校の先生が専門により特化していくのか、
それとも全体のチューター的役割を果たすのか、
これからの歩み方によっても変わりますが、
子ども達に、どの学びもワクワクする!を差し上げられる方法を、
模索するべきだと思います。
能力の高い先生達の志の高さが、
教育することからかけ離れた雑事に忙殺されて、
心が折れてしまうのは勿体無いことです。
「本来の職務にフォーカスできない、
社会からの勝手な押し付け」についてですが、
具体的に見ていくと、
*先生方への勝手な押し付け(1)
本来先生たちは子ども達の
生活の世話をするためにいるのではないのです。
学校は基本的な生活の保育をするのではなく、
教育をして才能を伸ばす場所です。
もしも先生たちが、
一人一人バラバラな育ち方をしている子ども達の面倒を、
全て理想的に救おうとすれば、それこそ大変な負荷がかかります。
大学で専門を学んでいるとはいえ、
まだまだ人間としては経験の浅い人たちが、
いっぺんに何十人もの子ども達を見ることになります。
学校というところは必ずしも子ども達が喜んで通っているところではありません。
苦手なところに無理矢理通わされて、
理解できないことを我慢して、椅子に座って聞いていなくてはならず、
勝手にテストをされて点数をつけられて、
順番をつけられたり批評をされたりする。
そんなストレスのかかった子ども達の世話をする、
先生たちの気持ちを考えてみましょう。
昔は良かったんです。
教育は教育を得ること自体が名誉なことでしたから。
誰も彼もが学校に行くようになったら、
「行かなければ」の強制よって、子供たちのやる気は削がれているのです。
そうであるにもかかわらず生徒の扱い方はそのまんま。
こんな無理矢理な話はありません。
全てがうまく噛み合っていないのです。
矛盾している。
システム自体が機能していない。
親は子どもに高学歴を授けたいと仕事に忙しく、
家庭でのゆとりあるしつけをすることができません。
よって子どもたちは「勉強しなさい」と言われるだけで、
勉強することの大切さや可能性と、面白さとが先に入ることなく、
やらなければならない、面倒くさくて嫌なものと言う部分が植え付けられてしまいます。
本来学びと言うのは、
自分が選んで喜んで学ぶから意味があるのであって、
十把一絡げに、興味があるものにもないものにも、
同じように同じことを同じ時期に分からせようとする。
こんな制度はそろそろ変えましょう。
時間もエネルギーも勿体無いって思いませんか?
人の才能は、もっともっと楽しいことをして伸ばすことができるんです。
間違いないんです。
子どもたちが、自分で能動的に頭を働かせたときの素晴らしさを、
枠を先に作ることによって全てロックしてしまっている。
そのことに、いい加減誰かが気がついて、
声をあげていかなくてはならないのです。
*勝手な押し付けその(2)
子ども達の登下校の安全を守ることは先生たちの役目でしょうか?
先生も同じ時間に帰らせてあげたいものです。
それは地域の人たちの仕事にすれば良いと思います。
*勝手な押し付けその(3)
先生たちの校外指導は必要なものでしょうか?
なぜ必要だと思いますか?
それは学校が、学校から帰った後の過ごし方も、休みの間の過ごし方も、
全て支配しようとするからです。
そんな必要がどこにあるんでしょうか?
そのことによって先生たちは、
放課後や休みの日に何か事故や事件が起きれば、
自分の休みを返上してその対応に当たらなければいけません。
それは警察や補導員さんのお仕事で良いと思います。
どうしてだれも、どの先生も、「それってどうして私たちの仕事なの?」
と声を上げる人っていないんでしょうか?
税金でお給料が出ているせいもありますね。
先生達にこそ、社会的に理想の生活をして欲しいのです。
なぜか?
それは子ども達に一番近い存在だから。
私は、保育士さんが学校にいても良いと思うのです。
保育士さんにも学校の先生方と同じ待遇を差し上げたいです。
それは結局子ども達のためになりますから。
中途半端ですが、日付が変わってしまうので、
また後日書かせて頂きます。
思考のキッカケに感謝いたします。
今日もおかげ様🙏
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
