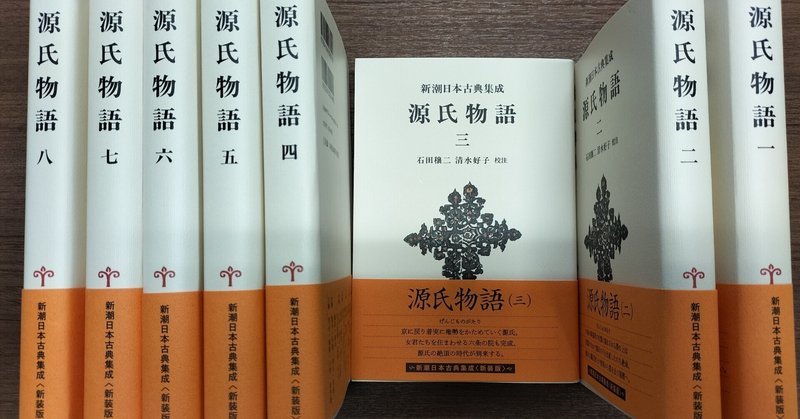
毎週一帖源氏物語 第十五週 蓬生
源氏が須磨と明石での不遇の日々を乗り越えて都への凱旋を果たすと、物語としても山を一つ越えたような感覚がある。それでちょっと気が抜けたというか、続きを読む意欲が弱まっているのを感じる。気をつけないと。
蓬生巻のあらすじ
源氏が須磨に退居すると、支えを失って困窮する人々もあった。常陸宮の君もその一人である。邸は荒れ放題だが、姫君は亡き父宮の思い出が詰まった邸も調度類も売り払わない。女房たちも少しずつ離れて行く。
その叔母は受領の北の方になっていたが、身分を落としたことで侮られていたのを根に持っており、姫君の苦境につけこもうとする。姫君の乳母子に当たる侍従を籠絡しつつ、「わが娘どもの使人(つかひびと)」(62頁)にしてやろうと企む。しかし、姫君は承知しない。
源氏は京に戻って来たが、常陸宮邸には寄りつかない。故院の御八講に呼ばれた兄の禅師が源氏の様子を伝えるにつけ、姫君は自分が省みられない現実を嘆くしかない。
叔母は、太宰大弐に任じられた夫とともに下る前に、もう一度姫君を説き伏せようとするが、叶わない。仕方なく、侍従だけを連れて行く。
年が改まり、源氏は「卯月ばかりに、花散里を思ひ出できこえたまひて」(72頁)出かけたところ、途中で見覚えのある木立を通り過ぎ、常陸宮の姫君を思い出す。惟光を遣わして様子を探ったあと、自ら対面しに行く。源氏は長い無沙汰を言葉巧みに詫びつつも、ここで一夜を明かすことはしない。それでも、二条の東の院に迎え入れる約束をする。二年後、実際にそのようになった。
大弐の北の方は、京に戻ってから姫君の境遇が激変していることに驚く。侍従は嬉しく思う一方で、「今しばし待ちきこえざりける心浅さをはづかしう」思うのだった。
末摘花、再び
末摘花巻は脇筋だと思っていたので、ここで再会を果たしたのは意外だった。蓬生巻も本筋から外れてはいるのだが、脇筋にも続編があったことに意表を突かれたのである。一度深い関係になった相手のことは見捨てないという源氏の態度が、読者に印象づけられる。
末摘花が報われたのは、源氏を一途に思い続けたからだろう。末摘花と対比的に描かれているのは、大弐の北の方(叔母)と侍従(乳母子)である。叔母は底意地の悪い人、侍従は辛抱の足りない人である。末摘花はその反対で、源氏を信じて待つことができた。源氏と末摘花が交わす歌で、「松」と「待つ」がかけられているのも、納得である。
後続の巻名が本文に
末摘花が住む常陸宮邸の荒れ果てたさまを描いた一節で、宇治十帖の巻名にもなっている「総角」という語句が使われている。その直後には、中盤の巻名「野分」も見える。
春夏になれば、放ち飼ふ総角(あげまき)の心さへぞめざましき。八月、野分(のわき)荒かりし年、〔……〕
もっと進むと、末摘花が侍従の長年にわたる奉仕に報いるため、見慣れ衣が汗じみているので代わりに自分の髪で作った鬘を与えるのだが、そのときに詠んだ歌には「玉かづら」という語句が含まれている。偶然だろうが、何となく気になった。
語りの枠
この巻の終わり方は、語りの構造という観点から興味深い。賢木巻の記事でも記したが、『源氏物語』は源氏の言行を見聞した人物による語りを、別の誰かが書き留めたという体裁を取っている。そのことが蓬生巻の末尾に現れているのだ。
今すこし問はず語りもせまほしけれど、いと頭(かしら)いたう、うるさく、物憂ければなむ。今またもついであらむをりに、思ひ出でてなむ聞こゆべきとぞ。
「もう少し話したいが、頭も痛いし、面倒だし、またの機会があれば思い出して話しましょう」と言って話を打ち切っているのが、見聞した語り手である。そして最後に「とぞ」すなわち「ということです」と付け加えているのが、語り手の話を聞いて書き留めた人である。見過ごしてしまいそうだが、「とぞ」という二文字があるからこそ、それまでの言葉が伝聞であることが明確になる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
