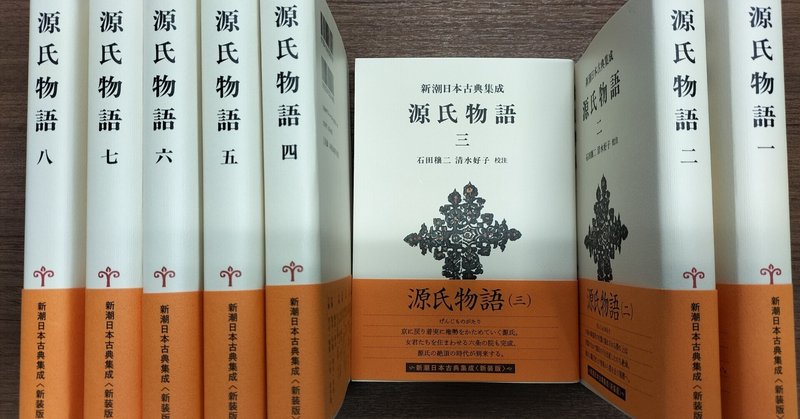
毎週一帖源氏物語 第十九週 薄雲
物語が大きく動くところは、やはり読んでいてもおもしろい。中だるみの危機をひとまず乗り越えられた。
薄雲巻のあらすじ
若君の袴着を立派に執り行いたいと願う源氏は、娘を手放すことになる女の気持ちを思いやりながらも、二条に引き取る。女も、娘のためにはそのほうがよいと自分に言い聞かせて我慢する。姫君は移ってきた初めのうちこそ大井の母君がいないことを寂しがったものの、すぐに二条の院の上になつく。源氏は年の内に大井を訪れるが、二条の「女君も、今はことに怨(ゑ)じきこえたまはず」(158頁)、かわいらしい姫君に免じて大井の人を赦す。年が改まってからも、源氏は近くの御寺や桂殿に行くのを口実に、山里を訪れる。
太政大臣が亡くなり、天文に異常が続く。源氏だけは凶事に心当たりがある。
三月、入道后の宮の病状が重くなる。三十七歳という厄年だが、大袈裟と思われないように、目立った祈禱はしていなかった。宮は「燈(ともしび)などの消え入るやうにて果てたまひぬれば」(168頁)、見舞いに訪れた源氏は嘆き悲しむ。二条の院の桜を眺めながら、「今年ばかりは〔墨染に咲け〕」(169頁)とつぶやき、薄雲に託して哀悼の歌を詠む。
法事が一通り済んだあと、故宮のもとに出入りしていた僧都が帝と差し向かいになった折に、言いにくそうに秘密を明かす。僧都が「くはしく奏するを聞こしめすに、あさましうめづらかにて、恐ろしうも悲しうも、さまざまに御心乱れたり」(172頁)。僧都は、このことを知っているのは自分と王命婦だけだと誓う。
帝は内外の事例を学び、臣籍に下った者が帝位に即いたためしがあることを知る。帝はそれとなく「おぼし寄する筋のこと漏らしきこえたまひける」が、源氏は滅相もないと譲位を断る。源氏は王命婦に質すが、帝に事の真相が伝わらないように故宮が気をつけていたと聞かされる。
秋頃、斎宮女御が二条の院に下がる。この季節に亡くなった方の思い出を語っていたのが、その娘の女御への気持ちを源氏は抑えられなくなる。あまりのことに、女御は言葉を返せない。源氏は話題を転じ、春秋の花や木をあしらった庭を造りたいという願いを述べ、春と秋のいずれを好むかと女御に尋ねる。女御は秋の風情をよしとするが、それが源氏の告白を誘い、女御は困惑する。源氏も自らの暴走を反省する。
源氏は山里の人を忘れてはおらず、念仏を口実に訪れることもある。
姫君をめぐる綱引き
直前の松風巻で浮上した明石の若君の養育問題が、この薄雲巻で決着を見る。三歳の姫は、母の明石の上の手を離れて、二条の院で紫の上によって育てられることになる。明石の上には娘を産んだという強みがあるものの、自らの身分の低さは如何ともしがたい。自分の手許に置いたままでは、娘の将来は開けない。一方の紫の上は高貴な血筋ではあるが、子宝に恵まれない。
姫を紫の上が預かることは、双方の弱点を補っているように見えるが、それは源氏の視点にすぎない。当事者二人は互いに協力するような関係ではなく、紫の上が相手を屈服させた形である。もっと言えば、紫の上の機嫌をとるために、源氏が肩入れしたも同然だ。
明石巻の頃から、明石の上との関係が他人の口を通して紫の上に知られることを、源氏は極度に恐れていた。その結果、先回りして白状することを繰り返している。紫の上の嫉妬を掻き立てないように腐心しているのだ。この姫君を入内させるためには、相応の教育を二条の院で授けなければならない。公的な理由としてはその通りだろうが、紫の上をなだめるという私的な動機も無視できないように思う。
紫の上は、機嫌を直したように見える。「遠方人(をちかたびと)のめざましさも、こよなくおぼしゆるされにたり」(161頁)という一文に、紫の上の勝ち誇った気持ちが現れている。明石の上を身のほど知らずと見下し、しかし今となっては大目に見てやろう、というわけだ。
この書き方だと私が紫の上に対して批判的であるように見えるかもしれないが、そういうつもりはない。むしろ同情的である。その代わりというか、源氏には共感しにくい。
藤壺の崩御と密通の露見
藤壺崩御のくだりは、源氏愁嘆の場となるのかと思いきや、意外とあっさりしていた。しかし、御念誦堂にこもって薄雲の歌を詠み、誰もそれに応えてくれないのが、源氏の孤独を際立たせているとも言える。
物語の展開としては、帝が桐壺院ではなく源氏の子であるという秘められた事実が夜居の僧都によって帝本人に明かされることが重要だ。振り返ってみると、若紫巻で源氏と藤壺が密通し、紅葉賀巻で皇子が生まれるが、それが不義の子であることは桐壺帝を含めて誰にも知られずに済む。その秘密が、ついにここで当の冷泉帝に知られる。冷泉帝は衝撃を受けるが、自分が桐壺院の子でないことよりも、実の父である源氏が臣下にとどまっていること、換言すれば実の父を臣従させていることのほうを、むしろ気にしているように読める。
冷泉帝に秘密を暴露したのは、源氏と藤壺のあいだを取りもった王命婦ではなく、藤壺のために祈禱していた僧都である。この人物の導入は、いささか唐突に映る。
秘中の秘とされるこの事実は、どのようにして『源氏物語』の語り手に伝わったのだろうか。薄雲巻のこの時点で知っていたのは、故人を含めて五人である。すなわち、当事者である源氏と藤壺、手引きをした王命婦、祈禱を仰せつかった僧都、この僧都から奏上された冷泉帝。一体誰が外に漏らしたのだろう。
譲位をめぐって
冷泉帝の譲位の意向は、二度にわたって示される。一度目は、出生の秘密を知った直後である。このときは「今は心やすきさまにても過ぐさまほしくなむ」(174頁)という一般論であり、誰に譲るつもりかは述べられていない。帝が秘密を知ったことに、源氏はまだ気づいていない。母の藤壺が亡くなったのを悲しんでいるだけだろうと思っている。
二度目は、時期は明確に示されていないが、帝が故事を研究したあとのことで、実の父である源氏に譲位したい旨がほのめかされる。源氏はここで、事が顕れたことを悟る。一度目の譲位の真意にも、思い至ったことだろう。「いとまばゆく恐ろしうおぼして、さらにあるまじきよしを申し返したまふ」(176頁)とあるように、源氏は恐怖に駆られ、譲位を固辞する。罪の意識は、生涯にわたって源氏につきまとうはずである。
墨染
巻名の「薄雲」は、藤壺の死を悼む源氏の歌にちなむ。自らの歌に先立って、源氏は「今年ばかりは」とひとりごつが、頭注が引く歌は「深草の野辺の桜し心あらば今年ばかりは墨染に咲け」(『古今集』巻十六哀傷、上野岑雄(かみつけのみねを))である。
京阪電車に墨染という駅がある。とくに深い考えもなく、百人一首の「おほけなくうき世の民におほふかなわが立つ杣に墨染の袖」に由来するのかと思っていたが、むしろ「墨染に咲け」の歌に由来することを知った。それなら、深草の次の次の駅が墨染であることも納得だ。
私の記憶にある墨染駅は、プラットフォームの外側の柵(線路のあるほうではなく、敷地の外との境)が少し変わっていて、鉄の棒が垂直ではなくやや斜めに傾いていた。あれは枝が風になびく様子を表しているのだろうか。それとも、とくに意味はないのだろうか。
母に続いて娘にも懸想する
源氏が斎宮女御に恋していることは、賢木巻ですでに語られていた。六条御息所もそのことに気づいていて、だからこそ死の間際に釘を刺したのである。そして源氏は斎宮を養女にして、帝に入内させた。にもかかわらず、源氏は斎宮女御に恋の告白をしてしまう。本当に困った人である。
それにしても、藤壺崩御のあとというタイミングが解せない。藤壺とよく似ている紫の上への思いが再燃したというなら分かる。なぜ、よりによってこの時期に斎宮女御に思いを打ち明けてしまったのだろう。
またしても宇治十帖の巻名
蓬生巻の記事で、後続の巻名が本文中に見えることに触れた。この薄雲巻でも、宇治十帖の巻名が二つ登場する。一つ目は源氏が大井の明石の上を訪ねたときで、すぐに帰らなければならない逢瀬のはかなさを「夢のわたりの浮橋か」(162頁)と嘆息する場面である。頭注によると、「世の中は夢の渡りの浮橋かうちわたりつつものをこそ思へ」という古歌をふまえているという。
もう一つは、この巻の最後の場面で明石の上が詠む歌に現れる「浮舟」である。大井川で行われる鵜飼のかがり火からの連想で水の上に漂う舟が持ち出され、「浮き」が「(身の)憂き」に掛けられている。偶然かもしれないが、明石の上との関連で夢浮橋と浮舟が登場している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
