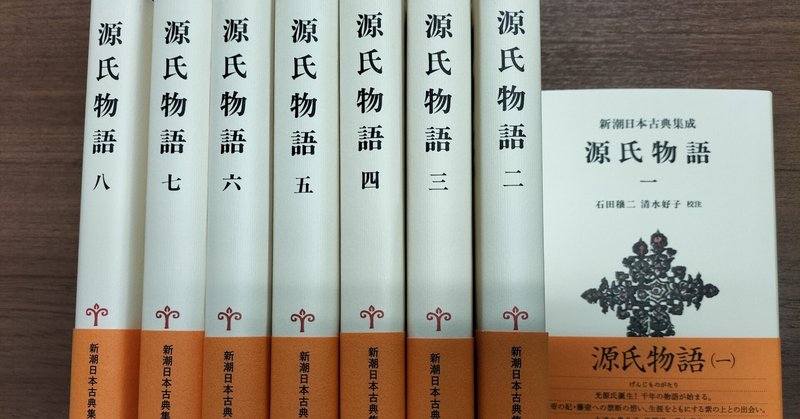
毎週一帖源氏物語 第六週 末摘花
古文を朗読する際、どんなイントネーションが適切なのだろうか。このところ、私は現在の京言葉を意識したイントネーションにしている。千年前と今では語彙だけでなくイントネーションも違っているだろうから、当時の口調からむしろ遠ざかっているのかもしれない。ただ、何となくやってみたくなったのだ。古文の「え何々ず」が今の関西弁の「よう何々せえへん」に当たるわけだから、まるで見当違いとも言えないのではないか、と自分勝手に得心している。
末摘花巻のあらすじ
夕顔を忘れられない源氏は、左衛門の乳母の娘である大輔(たいふ)の命婦から亡き常陸宮の娘の噂を聞きつけ、興味を抱く。すっかりうらぶれた暮らしを強いられているらしい。命婦の手引きで、源氏は春の十六夜にこの姫君が奏でる琴を聴く機会を得るが、その日はそれ以上近づくことはない。この忍び歩きを頭中将に見つけられ、源氏は抜け駆けされまいと競争心をかきたてられる。
源氏は常陸宮の姫君に文を送るが、まったく返事がない。八月二十余日、業を煮やした源氏は命婦をせっついて常陸宮邸に赴く。初めのうちは障子越しだったが、姫の言葉数があまりにも少なく、源氏は障子を押し開けて姫と契る。
忙しさにかまけて源氏は常陸宮邸に立ち寄らずにいたが、冬の雪の夜に久しぶりに姫のもとを訪れる。翌朝、源氏は帰りぎわに姫の姿を雪明かりのもとで見て、その醜い容貌にぎょっとする。胴長で、長い鼻の先が赤い。言葉に詰まりながらかろうじて歌を詠むが、姫は歌を返すこともできない。
それでも源氏は宮家の窮乏を見かねて、生活の面倒を見てやることにする。その年の暮れ、姫は命婦を介して源氏に正月用の晴れ着を送るが、濃い赤のそれは時代遅れで野暮ったい。添えられた歌も冴えない。源氏はすっかり紅色に嫌気が差してしまう。二条の院で紫の君と一緒に過ごすときも、自分の鼻先に紅をつけて戯れる。
強烈な読後の印象
以前に現代語訳で『源氏物語』を読んだとき、強い印象を受けた代表例がこの末摘花巻である。夕顔巻の内容などはすっかり記憶の彼方に去っていたが、末摘花の赤鼻は忘れようがない。「光君」と称されるほど見目うるわしく、知力と財力にも恵まれた源氏が、不器量の極みのように描かれる女を相手にする羽目になる。その落差たるや……。読者の私まで、見てはいけないものを見たような気にさせられた。
美しさは抽象的に、醜さは具体的に
末摘花の容貌の醜さは、詳細に語られる。
まづ居丈(ゐだけ)の高う、を背長(せなが)に見えたまふに、さればよと、胸つぶれぬ。うちつぎて、あなかたはと見ゆるものは、御鼻なりけり。ふと目ぞとまる。普賢菩薩の乗物とおぼゆ。あさましう高うのびらかに、先のかたすこし垂りて色づきたること、ことのほかにうたてあり。色は雪はづかしく白うて真青(さを)に、額つきこよなうはれたるに、なほ下(しも)がちなる面(おも)やうは、おほかたおどろおどろしう長きなるべし。
胴長で、象(=普賢菩薩の乗物)のように鼻が長く伸びていて、その先は垂れ下がって赤く、顔色は蒼白く(ということは鼻の赤は目立つだろう)、額は広く、顔が長い。「見えたまふ」や「見ゆる」という語が示すように、これは源氏の目に映じた通りの姿である。
その一方で、こうした残酷なまでに具体的な描写に接した私たち読者は、光源氏の眉目秀麗ぶりが抽象的にしか形容されていなかったことに気づく。たとえば、末摘花巻で探せば「男は、いと尽きせぬ御さま」(260頁)や「世にたぐひなき御ありさま」(262頁)といった具合である。他の巻でも事情は似たり寄ったりだ。
源氏の美しさに具体性が欠けている理由については、さまざまな説明が可能だろう。たとえば、何らかの特徴――切れ長の目をしているとか、体型がほっそりしているとか――を挙げてしまうと、そうした点に魅力を感じない読者をがっかりさせるので、作者としては曖昧にしておくしかない、といった説明だ。読者に想像の余地を残しておくには、美しさを抽象的に表現するしかないだろう。
上手くも詠めるし下手にも詠める――紫式部の詩歌の才
末摘花の詠んだ歌について、源氏は「さてもあさましの口つきや」(276頁)とその下手さ加減に呆れている。私には歌の良し悪しが分からないが、どうやらこの歌は出来が悪いらしい。しかし、作者の紫式部に和歌の才能がないわけではない。「さすがは源氏の君」と他の人物たちが褒めそやす歌もまた、紫式部が作ったものである。名優が「下手くそな演技」を見事に演じられるように、紫式部は歌を上手くも詠めるし下手にも詠める。
『源氏物語』は敷居が高いと感じられる理由の一つは、要所に配された和歌の解釈が難しいからだろう。詠み手の気持ちが、そこに至るまでの出来事をふまえて、さらには念頭に置かれている過去の歌(和歌に限らず漢詩も入って来るので大変だ)を射程に収めて、三十一文字に凝縮されている。『源氏物語』を読むということは、紫式部の詩歌の才を受け止めるということである。それは、かなりしんどい。しかし、分かってくると、おもしろい。
第一分冊読了
新潮日本古典集成の『源氏物語』は全八冊だが、この末摘花巻で第一分冊を読み終えたことになる。文字通り、第一関門突破だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
