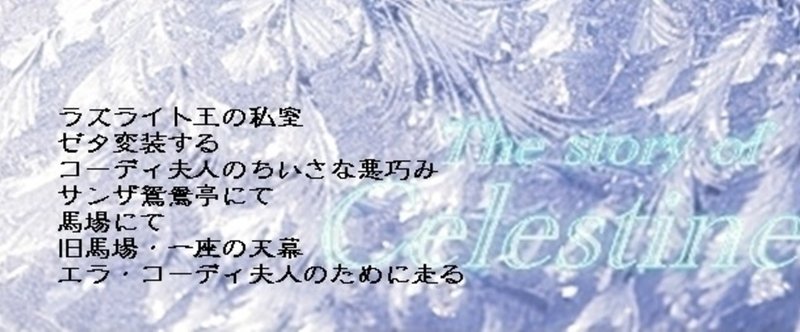
セレスタイン物語 3
3章
*** ラズライト王の私室 ***
早朝、パンひとつを大急ぎで囓ったあとで、ヴェンティは家を出た。朝政前の国王をとっ捕まえて質問攻め……否、空き時間を少しだけおわけくださるよう、お願い申し上げて、話をお聞きいただくためである。
王宮の門衛はヴェンティの顔を見ると、無言で通過を許可した。サンザ家では当主ノーヴェが隣国との交易を通して、しばしば国政に重要な情報を持ってくる。
国王ラズライト三世の指示で、ノーヴェとヴェンティは検問なしで、王宮の門をくぐれる、数少ない市民であった。城内に入って東へ進み、王が起居する涼楓殿と名付けられた建物に向かう。涼楓殿門前からは近衛兵がひとりつくが、王の居室へ入るときは、ヴェンティひとりだ。
王は居室にいなかった。卓上には朝食の支度が調っている。朝食前に、誰かが執務室での謁見を乞うたのだろうか、陛下は忙しい身だなと、ヴェンティは思った。
大きな盆の上に被せてある布をそうっと持ち上げてみる。堅焼きの小さなパンがふたつ、暖めた牛乳、濃い色合いの豆茶、小皿に干しぶどう十粒ほどと、林檎がひとつ。思いの外簡素な王の朝食に、ちょっと驚く。布をもとに戻して食卓から離れ、窓辺に寄って庭を眺めた。木立に囲まれているため、涼楓殿は王宮内にあるとは思えないほど、素朴な雰囲気を持っている。窓の外に小さな池があり、小鳥を呼ぶ給餌台には胸の赤いヒタキが一羽いて、ルル、リルル、と澄んだ声で鳴いていた。
ヴェンティが物心つくかつかぬかという年頃だったころ、父に連れられてこの涼楓殿へ来て、あの池に落ちたことがある。給餌台に止まった小鳥を捕まえようとして足を滑らせ、池にはまったのだ。池からヴェンティをすくい上げてくれたのが、当時、太子であった若きラズライト王子である。王や王子という概念を、まだ理解できなかったヴェンティは、王子になつき、優しくて格好いいお兄さん、くらいに思っていた。ヴェンティが王子に向かって何か言ったりしたりするたびに、父ノーヴェが青ざめて狼狽し、息子を叱りつけてみたり、それを王子が引き留めたりして、楽しかった記憶がある。
子どものころのヴェンティがこの涼楓殿で王子と会ったのはほんの数回だ。一度だけ、ほっそりとした綺麗なお姉さんがいたことがある。おしゃまなヴェンティが王子に、
「彼女?」
と、尋ねると、王子は首を左右に振り、
「そうではない」
答えながらも、彼女に優しい笑みを向けていた。
その後、王子は何かと忙しい身分になり、ヴェンティがこの涼楓殿に呼ばれることはなかった。
幼い頃に会った優しいお兄さんは、じつは王子であり、本来であればヴェンティが気安く訪ねていける相手ではないと知ったのは、それから少し経ってからのことだ。
やがて王子は即位し、ラズライト三世の治世が始まった。ヴェンティは商家の跡取り息子として、半ば遊び半ば学びながら少年期を過ごし、父も呆れるやんちゃぶりを発揮して、王都下を駆け回って成長した。
そして去年の年明け早々、宮殿の執務室に呼び出された。都下における学舎との喧嘩騒ぎを、王と父と、当時の学博から、こっぴどく叱られたのである。そのときのヴェンティの受け答えが、何故かはわからないが、王に気に入られたようだった。かつての王子、今や王であるラズライト三世は、ヴェンティを涼楓殿に呼び出した。
「気安い友に話すようにして話せ。気兼ねは無用だ。余も作法など無視でゆく」
そう言われているが、相手が王となると、父に対するようにざっくばらんにはいかない。一年のあいだに何度か涼楓殿を訪ねてみたが、そのうち二回は王が執務中だったため、会えなかった。必ず会うためには、早朝、朝政前にここへ来て、朝食を採る王と話すしかない。
前回、王に会ったのは、商団の出発前だから、じつに半年ぶりである。内ポケットに入れた青い宝石を、服の上からそっと撫でたとき、背後の扉が開く音がした。
「待たせたか」
王が足早に近づいてきて、食卓につく。
「ヴェンティ、朝食は?」
「パン一個、やっつけてきました」
王は盆の布をさっと取りのけ、皿の上の林檎を掴むと、ヴェンティに投げてよこした。
「いただきます」
遠慮せず、林檎にかぶりつく。王は居室内では格式張った作法を嫌うと、ヴェンティは察していた。
「麦か、旅か、姫か」
無駄なく核心を突いてくる王である。許された時間が少ないのだ。ヴェンティはすぐに服の中から、青い宝石を取りだした。
「リュー、というのだそうです。おわかりになりますか」
「東方の龍という名石だ。中の石は天青石。どこで手に入れた」
「王都領門前で、旅芸人一座から抜けたばかりのパルメという女から、金三百で買い取りました」
「女……どのような」
「目先の損得に踊りやすく、深慮はないと見ました」
「今、パルメはどこにいる」
「王都領門前のサンザ鴛鴦亭に足止めしてあります」
「サンザ家の客人として連れてきて、身柄を確保しておくように」
言いながら王は、食卓脇に置いてあった小箱を、開けよ、というように指で示した。
蓋を開けると、ヴェンティが持ってきたものとそっくり同じ方解石の中に、色合いだけがわずかに高濃度の宝石が抱かれた装飾品が入れられてあった。
「それも、東方の龍だ。中の石は天藍石。ふたつの石は余が父上から賜った。天藍石を余に、天青石を余の妻となる者に与えよと仰せになった」
感情をどこかへ消し去ったような声で王は説明した。
「事情があって、天青石のほうを十四年ほど前に手放した」
「パルメはそのあたり、まったく知らない……と、思います」
「彼女が王都直前までいた座は、ビョルケ一座か」
「話の前後からすると、そうなると思います」
「ビョルケ一座に、セレスティアという名の踊り子ないしは、セレスという名の、十二、三歳ほどの少年か少女がいないか。調べてほしい」
「名前はわかりませんが、その年頃の子どもはいます。大きな青い眼をしていて、綱渡りの練習をしてました」
「綱渡り?」
王は牛乳を飲むのをやめて、難しい顔になった。
「……そうか。綱渡り」
独り言を呟いて、何か納得した様子である。
「セレスティアとセレスという名前の芸人がいるかどうか、明日の初日を観に行って、調べてきます、陛下」
「頼む」
王は干しぶどうを一粒口に含んで、何かを思い出す表情である。
「陛下、セレスティア……という名の踊り子とは、どういう」
「答えない」
そうきたか。では、それが誰なのかは知らずにおいて調べるしかないと、ヴェンティは思った。
「では陛下、麦ですが」
「うん。値は抑えた。近々ルーシェ公に頼んで、王室から小作達に下賜麦として千人ぶん相当を、北峰領に運ぶことになっている」
「小作は六百人です、陛下」
「ほう」
王は満足そうに頷いた。
「どうして、それを知っている?」
「商人ですから。これでも商団の団統です」
ふふふと、王は楽しげになる。王の笑顔はどこか悪戯そうであり、ヴェンティもつり込まれて笑ってしまった。
「陛下、小作の租税を一部やめて、貨幣で徴税する方法に切り替えてはいかがですか」
「ほう。どうやって?」
「穀倉地域には大農家が二十家ほどあります。彼らは貴族の分かれで、広い土地を所有している地主ですけれども、農民の気持ちは理解していない」
「たしかに」
王は堅焼きパンをちぎって手に持ったまま、食べることも忘れた様子で頷いた。
「最初の一年は、国庫にも大農家にも、小作にも、儲けはありません。まずは投資です。今年収穫する麦については冬小麦、春小麦とも、租税免除とする。で、大農家が所有する土地のうち、人手が足りなくて耕作されていない土地を開拓せよと、陛下から小作へ命令を出していただいて」
「ふむ」
「新規開拓地の半分を大農家のものとし、残り半分を小作の所有地と認める。これで小作が自作農になれます」
この新規自作農の所有地からあがってくる収穫については、大農家と領主の中間搾取を禁じる法を出すのである。
そこへ、サンザ家が麦の買い取り専門の問屋を北峰領に数カ所置く。収穫した麦は農家が保存していると、領主の専横で巻き上げられてしまうので、サンザ家が穀物倉庫に保管し、農民の希望があれば、麦を買い取る。
「小作が自作農になって生産が安定し、サンザに麦を売り、サンザがその麦を市場に運んで売ったら、そこに課税するのです。税はサンザから陛下へ直納です。税率は一割を超えてはいけません。それ以上だと、麦を買う国民にしわ寄せがいきます」
「すなわち貨幣による徴税、か」
「租税で麦を徴収している限り、小作は浮かび上がれないんです、陛下。大農家と領主は、麦の出来高におかまいなしに一定量、取り上げてしまいますから」
しかも、領主の命令ひとつで価格が大きく変動する。小麦の価格は領主の欲と連動し、北峰領では相場の三倍の高値になった。
「小作はこれでは生きていけません。小作の棄農が続けば麦の収穫量は減ります。残った小作にはさらなる重労働と飢餓が襲いかかる。悪循環です」
「ほう。だが、小作の自作農化を、大農家が納得するか」
「新規開拓農地の半分からあがる麦がありますから、大農家の取得総量もあがります。同時に、小作達には、開拓すればするほど、自前の土地も増え、その麦は取り上げられないで済む。うまくいけば五年で小作は十分の一以下になるでしょう。ただし、問題がひとつ」
「領主か」
「そうです。この方法だと、領主は中間搾取ができません」
領主の儲けは減らないが、増えもしない。だが、もともと領主は私欲を持たず、領民を労るべき立場の人間だ。
起きもしなかった干ばつの噂を流して価格を操作し、私腹を肥やすようでは、領主の資格はない。
「今の北峰領の領主は農地農民を育てることができない人物です。陛下、領主って、クビにできないものなのですか」
「極端な落ち度があれば、問責という手もあるが」
「領主が穀倉地域から巻き上げた麦の総量から、領政に費やしたぶんと、国庫へ納めたぶんを差し引いて、着服した量が租税の半分以上であり、どう考えても健全な領政運営ではないと証明できれば、罷免できますか」
王は目を丸くし、持っていたパンを皿に置いた。
「ヴェンティ、どうしてそれを知っている」
「商人ですから」
「ふむ」
王は食卓に肘をつき、顎に手を当てて、渋い顔になった。
「陛下、お聞きしていいですか。領主が不当に蓄えた利益は、いったいどこへ消えたのでしょうか」
「学舎西館。と、余は見ている」
「あ、やっぱり……」
王と商人は揃って沈黙した。王は所在無げに干しぶどうを一粒つまんで口に入れた。
「で、陛下は俺に、姫を押しつけようって腹ですね」
「従兄の娘だから、大なたをふるうわけにはいかないのだよ」
「結婚話、お断りしますよ」
「やむをえまい。姫を牽制するための窮余の策だ。命令ではなく提案と言ったのはそのためでもある。しかし、どう言って断る?」
「姫に恥はかかせません。俺の爺は、姫の怒りを買って、縄でぐるぐる巻きにされて荷車もろとも崖から落とされるとか言って心配してますが」
「落とされずに済む方法があるか」
うふふ、と、ヴェンティは笑いながら、肩をすくめた。
「サンザ家ヴェンティには、熱烈に愛し合っている恋人がいるということにすれば、いいんですよ」
「ほう! 誰と恋愛していることにするのか」
「領兵長ゼタ、ってことで。どうでしょう、陛下」
ハハハハ、と王は大笑いし、食卓を手のひらで三度ほど叩いた。
「まったく、ノーヴェといい、ヴェンティといい、サンザの男は面白い」
「明日の夕方、ゼタと一緒に、ビョルケ一座の初日を観に行きます。さっきのこと、調べてきます」
「うんうん。頼む」
王はまだ笑いが収まらない様子で、しきりに肩を揺らしている。
「そうかそうか、ヴェンティがゼタと。あの生真面目な領兵長が……いや、素晴らしい。これはマージがどう出るか、面白いことになってきた」
「当面の災難を防いでおいて、姫の変な悪戯を封じる裏技を考えてみます。税法変更は俺から陛下へ宿題ということで」
「生意気なやつめ」
「可愛いでしょ?」
「可愛い」
王は満面の笑みでそう言って、食事を終えた。
*** ゼタ変装する ***
朝食を済ませるとすぐ、ゼタは領兵詰所へ向かった。
詰所の領兵はおのおのの任務をこなしながらも、ゼタの姿を認めると直立して礼を示した。
昨春、ゼタが領兵長に任命された直後には、兵の大多数に、
『若造が、何ができるというのだ、親の威力をかさにきて』
というような、半ば反発を含んだ視線が感じられたものだが、最近はすっかりなりをひそめている。
領兵らの態度が変わったのは、夏に行われた御前競技会のあとだ 弓術、馬術、剣術の三種目でゼタは優勝した。格闘技では腕力がいささか不足し、優勝を逃したが、決勝戦までは進出した。将器を試される戦略競技では、模擬兵五十名に捕虜なし、負傷兵なし、前線後退なし、敵陣旗奪取という、競技会始まって以来の好成績をおさめ、総合優勝を勝ち取った。その際、ゼタの父、領兵監オルクスは公平を期すため、採点に加わっていなかった。領兵達の信頼と支持を得ることができたのは、オルクスを審査から外した国王陛下の采配と、ゼタへの信頼のゆえである。
王国ではこの三十年間、対外戦争がなく、将軍と参謀に就いている将兵はいない。東西南北の各領、南西三島及び王都内に、領兵が配置されているが、戦時に比べれば兵の数は激減し、最多時の十分の一ほどになったというのが、父オルクスの弁である。領兵も兵士ないしは武官というよりも、警備専門の巡回が主な職務であり、中には武術に無縁な文官的業務、庶務専門の領兵もいる。領兵全般の傾向として武術の質は低迷気味だが、忠誠心は比較的保たれている。
ゼタは父の厳しい指導のもと、幼いころから修練してきた。領兵の中では最年少ながら、王都の兵を指揮する領兵長の地位についたのは、そうした理由があった。ゼタの父オルクスは領兵監であり、緊急時にはただちに将軍を拝命する立場にある。幸い、民間外交官とも言えるサンザ家ノーヴェの巧みな交渉のおかげで、隣国との関係は円満だ。戦は起きないだろうと父は考えており、陛下も満足しておられるのだった。
早朝の閲兵を済ませ、兵舎に入るとゼタは治安に関する訴事を担当する領兵を呼んだ。
「昨夜、市場の装身具店の店主コポルが私に面会に来なかったか」
「来ておりません、領兵長殿」
領兵は即座に答えた。
「やはり来ていないか。夕方には来ると思ったのだが。それと、市場で芸人一座の女と子どもを窃盗の疑いありと勘違いして捕縛しようとした兵はどこにいる」
「兵舎自室で謹慎中です」
「謹慎を解き、十日間の詰所内勤とせよ。今月は減俸十二分の一、ただし降格なし」
「はっ、ただちに」
「装身具店の店主に、再度出頭をするように……いや、私が直接出向こう。小隊長ビルト、同道せよ」
「かしこまりました」
ゼタより二歳年長のビルト小隊長を連れて、ゼタは領兵詰所を出た。
領兵詰所は武術訓練所とともに、王宮の西翼に隣接している。王宮の壁沿いに南の王宮門近くまで回り、そこから都下へ出て、川を渡り、大通りに入った。
大通りを進んでゆくと、
「領兵長殿、尾けられております」
小隊長ビルトが歩速を変えずに呟いた。
「何人だ」
「三人です。三人とも若い男のようです」
「サンザ商館に入り、変装して尾行をまく」
「わかりました」
そのまま早足で歩き続け、サンザ家の門を入って館へ直行した。いつもはヴェンティにヤモリのように張り付いている生え抜きの副統ティントが、
「これはこれは、どうなさいました、ゼタ若様」
いつもの笑顔で、だが急ぎ足で近づいてきた。
「市場へ行きたいのだが、正体不明の三人に追われている。市場へ向かう荷車はないか。荷運びに模して潜行したいので、変装の支度を頼む」
「ただちに」
ティント爺はすぐさまふたりを館内の一室へと案内した。見習いの商人がサンザで研修するときに使う小部屋である。棚にはサンザ家の使用人が着ている数種の衣類が吊されていた。
「最近、あちこちで、おかしな面々が何やら嗅ぎ回っておりますな」
「サンザ家ではどうだ?」
「商館に来ている連中には逆に監視をつけてあります。さきの商団にも五人、紛れ込んでおりましたわい。とりたてて悪さはせず、愚にも付かないことを書きまくっては鳩につけて飛ばしておるようです」
「やはり、学舎側から送り込まれた学生か」
「そのようです。何度か鳩を捕まえて通信筒の中身を見てみましたが」
「何が書かれていた?」
「ヴェンティ若が商売上手だと買いてありました。たいした内容ではありません」
ティント爺はゼタとビルトに、商団の若い者が着る地味な薄茶の揃い服を選んで差しだした。
「なので、こっちも便乗して、若の商売上手に打ちのめされた老齢の商人が、引退して若い者に店を譲った話を面白おかしく書いて、通信等に入れて送り出してやりましたわい」
ゼタの後ろでビルト小隊長が、着替えながら吹き出した。
「ヴェンティはどこかへ行っているのか」
「朝っぱらから難しい顔をして、陛下に会いに行かれました」
「例の結婚の噂の件か」
「ま、そのようでございますよ。まったく、災難とはこのことです」
「ノーヴェ殿はどうされてる? ヴェンティと一緒に王宮へ行かれたのか」
「今朝、若より早起きして東南の国境近くへ行かれました。東方との交易ですわ」
「そうか。お忙しいのだな」
「ありがたいことでございますよ。商人が暇ではろくなことがありません」
「領兵が暇だと平和だが」
軽口を叩きながらの着替えが済むと、ティント爺は二人に帽子を被せ、中身は空っぽの荷箱ふたつを担がせて部屋から出した。
商館の裏手から、市場へ向かう荷車が次々と出て行く。
「三つ目の、胡桃の袋を積んだ荷車がようございましょう。あれは市場の一番奥まで行きます。ここまでお召しになってこられた兵装のほうはどうされますか」
「兵装は私たちと似たような背格好の若い者に着せ、ヴェンティが王宮から戻ってきたら、三人一緒に馬で送り出してくれ。父の屋敷の馬場で馬術の練習のふりでもして待っていてほしい。私たちも調べが済んだら馬場に行き、ヴェンティと会って、服を交換する」
「承知いたしました」
「ありがとう、ティント爺」
「おやすいご用でございますよ。行ってらっしゃいませ」
荷担ぎに化けたふたりは市場へ向かう荷車脇につき、サンザ商館をあとにした。
*** コーディ夫人のちいさな悪巧み ***
目覚めたとき、コーディ夫人は自分がどこにいるのか、一瞬、わからなかった。起き上がって周囲を見回し、応接室に隣接する花部屋だと気づき、
「いけない、お客様を放りっぱなしだったわ」
慌てて長椅子から降りた。
部屋のすべて花を模した家具調度で埋め尽くした、夫人の趣味のお部屋である 小さな卓をはさんで向かいの長椅子には、昨夜、領門の外の宿屋で出逢ったパルメが、毛布を頭から被るようにして、眠っていた。
大きな窓からさんさんと光が差し込み、五月の美しい朝である。
昨夜遅く、コーディ夫人はパルメを屋敷に招待し、この部屋へ案内した。そのあと、彼女を相手に、娘マージの結婚について、少しばかり愚痴を並べてみた。望まぬ相手との娘の結婚、娘をどれほど大切に育ててきたか、娘の美点、娘の気高さ、その他にもあれこれ話して聞かせた。最初のうちは熱心に話を聞いて、相づちも打ってくれていたパルメが、次第に眠たげにうなだれてしまい、ついには寝入ってしまった。夜のうちに宿に帰りたいとパルメが言っていたことを思い出し、少し眠ったらパルメを起こして馬車で送ろうと思っていたのだが、じつは夫人もその前の夜から、寝不足であった。結局、パルメと同じように、花部屋で眠り込んでしまったのである。そして朝まで、二人揃って熟睡してしまったというわけなのだった。
夫人は足音をたてないよう、そうっと部屋から出て、使用人のエラを呼んだ。
「お客様に、朝食をお出しして。私にも、何か軽いものをね。それと、お客様はお食事のあと、すぐにお帰りになるから、馬車の支度をね」
あれこれ指示して花部屋に戻り、パルメの寝顔をのぞき込んだ。
昨夜、宿で会ったときは、彼女の野性的な容貌と、それとはうらはらに高貴な精神を感じて、感動してしまった夫人であったが、今朝になると、自分が何故、この女を屋敷にまで連れてきて歓待したかったのか、わからなくなっていた。
「どこの誰とも知らない人なのに、私、どうかしていたのだわ」
だが、具合が悪くて倒れそうだった自分を、親切に介抱してくれたことは事実である。それなりに礼をせねばならないと考えた。
花部屋を出てもう一度使用人のエラを呼び、入浴の支度を命じたあとで、夫人は自室へ入り、装身具の箪笥を開けた。嫁入りの際、実家の両親が持たせてくれた美しい装身具の数々だ。コーディ夫人と、夫人の母の趣味もあり、花を模した首飾り、イヤリング、指輪、腕輪、宝石付きの扇、ベルト、銀冠その他である。だが夫人がルーシェ公との結婚後、これらのもので身を飾ることはほとんどなかった。王の近裔としてのルーシェ公は、見事なまでに王統の精神の具現者であった。平素の装いはいたって質素である。装身具など、身につけたところを見たことがない。自身を飾ることに公は無関心だった。私的な財産を得ることにも、まったく興味を示さない。ただひたすら、国と民のために学究にいそしみ、研鑽してきたのである。いきおい、夫人も夫の流儀にしたがって、自らの行いを正さねばならなかった。貴族の夫人達はおおむね華やかな存在だが、コーディ夫人は着飾らなかった。結婚当初はそれが物足りなくて、つまらないと思ったこともある。けれども、今は王の従兄の妻として、何飾ることなく凛としてあれば、それが一番だと思えるほどになっていた。夫人の装身具は箪笥の飾りとしてこの二十余年を過ごしてきたことになる。
装身具の箪笥から、夫人は三連の真珠の首飾りを選んだ。棚の上から天鵞絨張りの小箱を取り出して、中に首飾りを入れる。それを持って花部屋へ戻った。パルメはまだ眠っていた。よくよく見れば、荒れた髪には細かな埃がまとわりつき、手入れをした様子も見られない。昨夜、宿の灯りのもとでは日に灼けた肌と見えたけれども、ただの汚れた顔である。
そういえば、と夫人は思った。
芸人一座から抜けて来たと、この人は言っていたわ。私、それを聞いて虐待から逃げ出してきたのに違いないと思い込んだのだけれど。でもどうみても、この人は三十歳くらいの大人の女。幼い子どもなら是が非でも保護しなければいけないけれど、大人なら自分で判断して行動できるはず。
私ったら、昨日はいったい何を考えていたのかしら……。
寝入っている女の胸元に、真珠の首飾り入りの箱をそっと置いた。足音を忍ばせて花部屋を出て、またまた使用人のエラを呼んだ。
「お客様が目を覚まされたら、私は急ぎの用事で出かけたと言いなさい」
エラは目を丸くした。
「ご入浴の支度ができておりますけれど?」
「入浴はします。でも、お客様には、不在と言ってほしいの。それと、昨夜、とてもよくしていただいたので、お礼に首飾りを、さしあげました。天鵞絨の小箱に入れて、お客様のそばに置いてきましたから、私が感謝していたとお伝えして、受け取っていただいてね。あとのことは、指示通りに」
「わかりました、コーディ様」
「お前に嘘をつかせてしまって、ごめんなさい」
「大丈夫です、コーディ様。うまくやります」
エラは実家から連れてきた長年の奉公人なので、こういうときは頼りになる。エラにあとを託して、夫人は急ぎ足でその場を離れ、浴室へと向かった。昨日、一日馬車に揺られて、顔や手にも砂埃がまとわりついているような気がしてならない。早く洗い流したかった。普通、貴族の夫人は衣類の着脱は使用人にさせるのだが、ここは王の従兄の屋敷である。入浴程度のことは自分ですべて、しなければならない。なので、浴室には夫人ひとりきりだ。天井近くの小窓から、日差しが浴室内に差し込んでいる。湯船には夫人の好きな薔薇の香油が少し垂らしてあった。清潔な浴槽にゆったりと浸かって、夫人は手足を伸ばした。
浴槽の横に小さな卓が寄せてあり、卓上には入浴しながらつまめるようにと、朝食が置かれていた。いつものお茶、小さくて柔らかなパンにはクリームがつけてある。薄焼きの焼き菓子の上に甘く煮た果物。夫人の大好きな、蜂蜜を溶かした牛乳。少しずつ、それらをつまみながら、再び考える。
マージをどうやって、無体な結婚から救い出せばいいのかしら。
考えることはやはり、それである。ふいに、夫人の記憶のどこかから、
……結婚ったって、すぐにすぐってわけじゃないんだろ? 婚約して、結婚式まで、間があるだろうさ……そのあいだに、時間稼ぎしてさ、向こうに落ち度がありゃ、それを理由に断れるんじゃないの……人間、誰だって叩けばホコリのひとつふたつは出るもんだって言うじゃない……それで、娘さんって年はいくつ? あ、十九? それじゃあたしが身代わりに化けるってわけにもいかないねえ、十若ければ、あたしが奥さんの娘さんになりすまして嫁いでやったけどね、アハハ……
昨夜のパルメの言葉が思い出された。
婚約、時間稼ぎ、落ち度探し、破談。それは素晴らしい策に思えた。さらに、身代わり、なりすまし。パルメという人は、なんと賢いのかしら、私にはそんなこと、まったく考えつかなかった。よく考えてみましょ、娘のためですもの。お湯を両手ですくって顔をそうっと撫でたとき、夫人の脳裏に、これ以上はなく素晴らしい策略が浮かんだ。と、夫人には思えた。
使用人の娘をひとり選んでサンザ家へ行かせる。商家のことを学ぶためとか、両家の親睦のためとか、マージとの結婚の支度を相談するためとか、理由をつけて。何日か通わせたら、サンザ家のヴェンティが、娘を誘惑しようとした……ということにしてしまう。そんな男のところへ、大事なマージを嫁がせられませんと陛下に申し上げて、縁談は白紙にしていただく。
私ったら、今まで気づかなかったけれど、悪女の素質があったのだわ。
コーディ夫人は自分で自分に驚いた。そうと決まれば湯に浸かっている場合ではない。あたふたと浴槽から出て大慌てで身体を拭き、新しいドレスを身につけて、全部の紐を留めつけるのももどかしい思いで、浴室から走り出た。
「コーディ様、どうかなさいましたか」
エラが驚いたように言って、急ぎ足で廊下を走ってきた。
「エラ、うちにいる使用人の中で、一番年若いのは誰?」
「庭師のコルグです、コーディ様、お髪をどうにかいたしませんと、ああ、滴が」
「男ではなく、娘は?」
「娘ですか……料理人の手伝いに、ジェンがおりますが、三十を超しております。コルグのほうが若いですよ」
「男ではだめなの。他に、誰かいない? マージと同じくらいの年頃の娘が」
コーディ様、と、エラは渋い顔をした。
「お屋敷に勤めさせていただいている使用人は、ルーシェ公様のご配慮で、年配の者が多いのでございますよ。若くて体力のある者は働き口がたくさんありますが、年がいきますと雇い手が見つかりにくいものなんでございます」
「え、そうなの?」
「ですから、ルーシェ公様は、使用人のために、私のような年の者でも、雇い続けてくださるのです。当然、お屋敷にいる使用人は、年かさの者ばかり。庭師は親子で働いてきましたが、息子が仕事を継いだので、若いのです」
「まあ……そうだったの」
「ジェンを呼びますか? ご用をお言いつけになるのでしたら、連れてきます」
「三十過ぎでは、いくらなんでも。サンザのヴェンティは十七、八だったわね……」
「コーディ様、何をお考えなのです」
「あ、いいの。ちょっと思いついたことがあったので、聞いてみたけれど、もう少し考えてみるわ」
「コーディ様」
使用人頭は少しだけ、怖い顔をした。
「お話しください。コーディ様がひどくお悩みでおいでだということは、このエラにもわかるのでございますよ。もしや、マージ姫様のことなのでは?」
コーディ夫人は驚き、四十年来仕えてきてくれたエラの顔をまじまじと見た。
「ええ、そう、そうなの。マージのことで」
「エラにお話しくださいまし。それがコーディ様のお為でございます。何を、どうしようとお考えだったのです?」
コーディ夫人はしばらく考え込み、なんとかしてごまかそうと笑顔で取り繕ってみようと試みたが、うまくいかなかった。
「じつはね。マージとサンザ家ヴェンティの、結婚のことなの」
「縁談を壊したいということですか」
「そう……え? どうしてわかったの、エラ」
「コーディ様のお考えになることは、このエラも考えることですから」
「まあ」
夫人は隠し事を諦めて、ついさっき、浴室で思いついた策略をエラに打ち明けた。
エラは難しい顔をして話を聞き、それがまた、あっという間に話が終わってしまったので、拍子抜けしたようだった。
「コーディ様、それだけ、ですか?」
「それだけって……ええ、これだけ」
「娘を誰かひとりサンザへやって、縁談を破談にすると」
「そう。いい考えではなくて?」
エラは今度は両手で顔を覆い、深いため息をついた。
「わかりました。このエラが、なんとかしてみましょう」
「だめよ。自分で言うのもなんですけれど、これは決して良い行いではないわ。エラにはさせられません。マージの母親は私よ。私がやります」
「コーディ様には無理です」
きっぱりと言われて、夫人はまた驚いた。
「エラが、いたします。コーディ様は、このエラが何をどうしようとしているのか、何もお聞きになってはいけません。そうすればエラも思い切った方法が取れます」
「エラ、思い切った方法って、どういうことなの?」
「エラをお信じください。縁談が壊れてことが解決するまで、コーディ様は何も知らず、何もせず、何も言わずに、ただただじっとしていてくださいまし。ようございますね」
「誰かを傷つけたり、困らせたりはだめよ、エラ」
「わかっております」
「マージは守りたいけれど、誰かを犠牲にしてはいけないのよ、大丈夫?」
「大丈夫です」
エラは力強く頷いた。
「ところでコーディ様、エラにお貸しいただきたいものがございます」
「あら、何を?」
「コーディ様がお持ちの、慈善院の院司印です」
「あ、慈善に行ってくれるのね。わかりました、すぐに持ってくるわ」
コーディ夫人は自室へ戻り、机の引き出しから院司印を取り出した 不遇な境遇の子どもを引き取るとき、この院司印を携帯して、保護が陛下の名の下で正しく行われていると示す、いわば証明印である。院司印所持者にはさまざまな特権があり、希望すれば裁判所の判事として司法的な権限をも持つことができた。ただし、コーディ夫人は一度も裁判には参加したことがない。ほとんど飾りの院司印だった。
エラは院司印を受け取ると、ちょっと出かけてきますと言って、上着をつけて出て行った。
エラを見送ったあとで、コーディ夫人はふと花部屋の客人のことを思い出した。
パルメは花部屋にはいなかった。真珠の小箱は消えていたので、持って行ってくれたらしい。馬番に尋ねると、ほんの少し前に、パルメは馬車に乗って領門へ向かったということだった。何かしらほっとした気分のコーディ夫人である。安心すると、急に喉の渇きを覚えた。朝食を途中でやめてしまったので、お腹のほうもやや物足りない。
厨房の料理人に、お茶をもう一度いれて果物をと、指示して、花部屋へ戻ろうとしたとき、屋敷の扉が開いて、ルーシェ公が、彼にしては慌てた様子で入ってきたのが見えた。
「ルーシェ公、どうされましたの?」
「大変なことになった」
公は動揺した様子で夫人に近づいてくる。
「急いで着替えを。学舎に行かねば」
「あら、今までどちらにおいででしたの?」
「陛下からお呼びがあり、お会いしてきた。夫人、マージとサンザ家ヴェンティの結婚のことだが」
「聞きたくありません」
「破談になった」
「ですから、聞きたくないと……えっ?」
夫人は両手で口元を隠し、意外といえばあまりに意外な夫の言葉と態度に、答える言葉を失った。
*** サンザ 鴛鴦亭(おしどりてい)にて ***
王都領門の外、サンザ鴛鴦亭でヴェンティは首を傾げていた。
ヴェンティに東方の龍を売りつけた旅の女パルメが、部屋にいないというのである。宿を任せている差配に聞くと、昨夜遅く、ルーシェ公夫人コーディが馬車で乗り付けてきてここでしばし休み、そのあと、パルメと夫人が揃って入領したという話だった。
「知り合い? ってことないよなあ、コーディ夫人と、パルメ……」
何もかも違うふたりである。念のため、パルメを泊まらせている部屋を調べると、ヴェンティが支払った金三百は寝台脇の物入れに、袋に詰め直した様子で置かれていた。旅道具らしきものは増えても減ってもおらず、粗末な作りの薄い上着一枚は寝台の上に放り投げられたままだ。
「どうしますか、若。行方不明と門兵に報せたほうがいいですか」
宿の差配は苦い顔だ。
「うーん、金を置いて行ってるからなあ……宿代はサンザ持ちと言ってあるから踏み倒してるわけじゃないし、最後に一緒だったのがコーディ夫人だし」
いったいどこに問題があるのかと聞かれたら、返事のしようのない状況だった。王の希望に添い、パルメをサンザで預かろうと、迎えにきたヴェンティである。ことのついでに、パルメがたしかにビョルケ一座から抜けたばかりなのかどうかを確認し、そうだとすれば座の内情を聞いてみようと考え、ここへ来てみたのだった。東方の龍の入手経路についても、パルメから詳しく聞きたかった。
東方の龍には、いくつかの謎がある。先王が、王子だったころのラズライト王に『妻となる者に与えよ』と下賜した、貴重な貴石である。そして、王室から盗まれたわけではなく、王が『わけあって手放した』のだ。巡り巡って、東方の龍は王の手元に戻った。そして王は『セレスティアという名の踊り子』と、『セレスという名の子ども』がビョルケ一座にいるかどうか調べよという。つまり、パルメが言うところの『小さい子どもを抱えて苦労していた元踊り子さん』が、セレスティアであり、王が求婚したのかどうかは定かでないものの、東方の龍を手渡した相手だった可能性がある。
パルメは宝石を持ち込んできたとき、『元踊り子さんからもらった』と言った。元踊り子さんが、小さな子どもを抱えて苦労していたにもかかわらず、売り飛ばさずに持っていた東方の龍を、『お礼よ』と言って、パルメに譲るだろうか。ここが怪しい。
それと、見逃せないのが、名前だ。
踊り子セレスティアと、セレスという名の子ども。
隠し子、と考えてから、慌てて否定する。
「……あり得ないな。天地がひっくり返っても」
とにかく、堅物王ラズライトである。
パルメを、どうあっても確保しないといけない。今は宿にいないけれど、金を置いて行っているから、きっと戻ってくるだろう。ヴェンティはパルメの泊まっている部屋の中を注意深く元通りにし、外へ出た。差配を呼んで、パルメが戻ってきたら、ヴェンティが会いたがっていると伝えるようにと指示して、宿を出た。
領門に近づくと、一台の馬車が都内から出てくるのに気がついた。紋章からすると、ルーシェ公の馬車である。旗が立っていないので、夫人が乗っているのかもしれない。呼び止めてコーディ夫人にパルメの所在を聞いてみようかと思ったが、やめた。サンザが夫人から蛇蝎のごとく嫌われていることは知っている。下手に声をかけて、余計な騒動になるのは避けなければいけない。馬車を見送ったのち、まっすぐ商館へ戻っていった。
何か食べようかなと食堂に入ろうとしたヴェンティの首根っこを、ティント爺が掴んできて、
「いったいどこをほっつき歩いていたんです、若」
そのままずるずると外へ引き出された。商門裏手には、領兵の制服を着たサンザの若手ふたりが馬に乗っている。
「何それ。うちの使用人だろ。なんで領兵の格好なんかしてるんだ。仮装大会でもあんの?」
「しのごの言わずに馬に乗って。ゼタ様の馬場へ行ってくだされ」
「なんで?」
「行けばわかります、さ、お行きなされ」
ティント爺はヴェンティを馬の背に無理矢理押し上げ、
「それっ」
かけ声も勇ましく馬の尻を叩いた。ヴェンティの乗った馬が素っ頓狂な速さで駆けだし、領兵の制服組ふたりもあとからついてくる。
「馬場って、どっちー!?」
ヴェンティは叫んだ。
「新馬場です」
後ろから返事がある。ということは、芸人が天幕を張っている旧馬場ではなく、領兵監オルクスの館脇の新馬場である。
「腹、減ってんだけどなあ、もう……」
ぼやきながらも、馬を走らせて馬場に向かったヴェンティだった。
*** 馬場にて ***
装身具店主のコポルの行方はつかめなかった。
ゼタが市場へ行ったときには、天幕がたたまれ、奥の店の扉は閉まり、使用人もいなかったのである。念のため、コポルの家族が暮らす家を訪ねていったが、コポルも家族もいなかった。隣人の話では、夜のあいだに、西府領のコポルの母親から、父親が危篤と報せが来て、さきにコポルが出かけ、家族もそれを追った、という話だった。何かしらうさんくさいものを感じて、ゼタは領門の門兵詰所へ調べに行った。コポルとその家族が出領した記録はなかった。
詳しく見ていくと、夜半に学舎西館からソロン序学士が、新任の序学士一名とともに、地理調査の名目で出領したと記録があった。そこで、ゼタは自分の失敗に気づいたのだった。
ソロン序学士は、装身具店前の金貨騒動の折り、ゼタの背後の人垣から少し離れたところに立っていた。兵を引き連れて帰舎するとき、ソロン序学士がいることに気づいたが、その場でどうするわけにもいかない。市場調査と言われたらそれきりである。なので、気にはなったが、放置したのだ。結果として、コポルは領外へ連れ去られた。おそらく口封じのためだろう。そしてコポルの家族のほうは、領内のどこかに監禁ないしは軟禁されて、身柄を拘束されている。いわば、人質だ。つまり、ビョルケ一座の芸人に、金貨泥棒の濡れ衣を着せて捕らえようとした学舎西館の勢力が、コポルをゼタから隠したと考えられる。
一連の事件の背後にソロン序学士がいる。彼が単独で行動するはずがないから、真の黒幕は学舎西館准学のマージ姫ということになるのだろう。領兵長であるゼタの立場では、詰問も取り調べもできない相手だ。マージ姫を喚問できるのは陛下とルーシェ公だけである。
この件を報告すべきかどうか。待ち合わせ場所の新馬場の、芝目を見ながら自問する。
陛下は多忙なかただ。朝、夜明け前から執務に就かれ、深夜まで政務をこなしておられる。町中の小さな事件の背後に、王室関係者がいるという報告は、陛下のお悩みを深めることになりはしないか。それが案じられた。それに、マージ姫が何故、芸人一座の踊り子と、見習いとおぼしき子どもを捕らえようとしたのか、理由がわからない。
ヴェンティに相談してみようかと考えたちょうどそのとき、
「領兵長殿、ヴェンティ殿が来られました」
小隊長ビルトの声が聞こえた。
「おー、いたいた。待ったー?」
いつものように、明るい声のヴェンティである。重苦しかった胸がすっと軽くなり、ゼタは手を振ってヴェンティを呼んだ。
「あ、なーんだ。ゼタはいつからうちの使用人になったんだ?」
ゼタの服を見てヴェンティは大笑いする。
「わけがあってな。ヴェンティ、厩舎へ入ってくれ。服を交換する」
「楽しそうだな、領兵って」
そうだよ、とゼタも笑う。兵士に偽装した商人二名と商人になりすました兵二名の、衣類の交換が済むと、ゼタは厩舎脇の管理人小屋へヴェンティを連れていった。
「なんだなんだ。馬場の小屋で密会とは、色気がなさすぎるぞ、ゼタ」
「すまない、人に聞かれたくないんだ」
「ま、秘密めいてて面白いけどな。で、なんだ? 告白が先かそれとも」
「ヴェンティ、芸人一座の女芸人ひとりと、子どもが危ない」
ヴェンティは真顔になり、口を閉ざした。ふざけていたときの笑顔が消え、真剣な表情になる。
「綱渡りする子どもか」
「そうだ。昨日、ビョルケ一座の女と子どもとで連れだって市場に買い物に行き、金貨泥棒の濡れ衣を着せられそうになった。もう少しで学舎西館の手に落ちそうになったんだ」
「西館? 市場の治安問題に西館が介入するか?」
「そうだ。おかしいだろう?」
「金貨泥棒……は口実で、目的は」
「そう、たぶん芸人と子どもだ」
「どうも最近、芸人やらその子どもやらに縁があるな」
「縁があるとは?」
「うん。別の話。それで、どうなったんだ、そのあと」
それがだ、と、ゼタは手にした鞭で軽く壁を叩いた。
「じつは、その騒動の仕掛け人と思われる装身具店の店主コポルが、おそらくは拉致されて、ソロン序学士の手で領外へ出されてる」
「コポルなら市場近くの家に女房と子どもがいるだろ?」
「家族は行方不明だ。近所の者の話では、西府領へ行くと言って家を出たということだが、領門に出領記録がない」
「なんだよ、詰めの甘い黒幕だな」
ヴェンティの言いぐさにゼタは思わず笑ってしまった。
「ヴェンティ、すまないが、今から一緒に一座へ行ってくれないか。昨日、連れ去られそうになったふたりを私が助けたから、私の顔と名前を覚えていると思う」
「あ、いいよ。保護してうちで預かるよ」
何も言わずとも察してくれる、賢いヴェンティである。
「では急ごう。何故かわからないが、西館の出方がここ数日、妙に強引だ」
ふたりは管理小屋を出た。兵士に変装していたサンザの商人は荷を負って遠ざかっていくところだ。ゼタに付き従ってきたビルトは兵装に戻って、管理小屋前に立っていた。
「小隊長、先に帰舎してくれ。私は寄っていくところがある」
ゼタは小隊長を帰らせ、ヴェンティと並んで歩き出した。
「そういえばさー、西館はどうも変だよな。羊毛に付け火もするし」
「領門前騒動か。あれも、故意か?」
「そうだろうよ。去年、俺が学舎と大喧嘩して、あっちこっちから叱られたことがあっただろ?」
喧嘩のしめくくりが夜空を彩る千発の花火で、都民は喜んだのだが。
「ヴェンティのせいであのあと花火が半年間、禁止になったな」
「そうそう、おかげで祭がつまんなくて……違う違う。あの喧嘩のあとにさ。サンザの商権を剥奪しろとか、商団を解体しろとか、陛下に迫った爺さんがいたの、覚えてないか」
「前学舎学博のガバン公だ。古王の四代孫だったか。たしか王裔だったな」
「そうそう。商団憎しで凝り固まってて、やりにくいジジイだった。ソロン序学士って、やりくちがガバン公にそっくりなんだよ。あー、やだやだ。あれがいると思うと、西館という名前を聞くのもいやだ」
「ガバン公の派閥か……」
ガバン公は王弟ファーディ公を、熱心に支持した一派の総帥だった。つまり、現在の王ラズライト三世の即位に猛反対した派閥である。ガバン公は昨年亡くなり、学博にはルーシェ公が就任した。ルーシェ公は派閥に無関心であり、ガバン公の影響は消え去ったかに見えた。ところが同じ時期、ルーシェ公の娘マージ姫が西館准学に就いた。そしてどうやらガバン公の率いていた派閥をそっくり抱き込んだ様子が見られるのである。秋から冬にかけて、マージ姫は学舎に新たな部を設立した。古衛研究と称して、武術に長けた学生を入学させ、研究とは名ばかりの、私兵増強に踏み切ったのだった。その折り、ファーディ公亡きあと離散していたガバン一派の貴族の子弟を、多数入学させている。彼らは学問ではなく武術鍛錬に余念がない。
「その連中が、何かっていうと、間者まがいにあちこち嗅ぎ回ったり、人を尾行したりしてて、もー、うるさいったら。ゼタも今日、尾けられたくちだろ?」
「そうだ」
「姫はいったい、何をどうしたいんだろうな」
「結婚して聞き出してみたらどうだ」
「あ、あれね。断った。俺にはゼタという生涯を誓った相手がいるからな」
「誓った覚えはない」
ゼタが冷たく突き放すと、ヴェンティは男殺しな流し目をよこした。
「陛下は喜んでいらしたけどな。机をバンバンバン! 三回も叩いた」
「呆れたやつだ、陛下に申し上げたのか」
「だからもう、俺とゼタは公認よ、公認」
「大丈夫なのか、ヴェンティ。あちらがどう出るかわからんぞ」
「行動に出てくれば、対策が取れるだろ。俺はさー、ゼタ。姫には学問に専心してもらいたいわけ。学舎は学問して、商人は商売をして、兵士は市井を守ってさ」
「そうだな」
「芸人は芸を、踊り子は踊りを、だ。そうやって世の中、丸く収まればさあ、陛下もご自分の幸せのことを考える時間ができるってもんだよ。なあ、そうだろ?」
ヴェンティの言葉は、ゼタの願いでもある。ゼタの父オルクスはもとより、派閥解体を目指して自ら退官した元将軍バライト、王族の抗争を避けるために王宮から去っていった親ラズライト派王裔達。皆、同じ気持ちなのだ。
「おっ、見えたぞ。あれだろ、ビョルケ一座の天幕」
ヴェンティが嬉しそうに声をあげる。
天幕の周辺には、噂を聞きつけて集まった見物人が、柵ごしに中をうかがってみたりして、なにやら楽しげな雰囲気である。柵のすぐ内側で、刃のない剣を綺麗に回して軽々と跳んだり跳ねたりして練習している男達がいて、子ども達が拍手を送っていた。
*** 旧馬場・一座の天幕 ***
「失礼。ビョルケ座頭にお会いしたいのだが。私は王都領兵長ゼタ、連れはサンザ商団統領ヴェンティだ」
ゼタが声をかけると、剣術舞をしていた男達は動きを止めた。すぐに近づいて来て、柵を開け、どうぞ、と中へ促した。別の一人が三つほど先の天幕へ走っていき、すぐに座頭とおぼしき男が姿を現した。座頭も何かの演目の練習中だったらしく、赤と緑の奇抜ないでたちである。
「ビョルケでございます、お見知りおきを」
人の良さそうな笑顔で近づいてきて、芸人らしい張りのある声で挨拶をよこした。
「私は王都領兵長ゼタ、座頭には初めてお目にかかる」
「あっ、これは、ゼタ様でいらっしゃいますか! 昨日は市場で私どもの芸人をお助けくださり、ありがとうございます。なんでございますか、たった一括で、他の兵隊様の背筋がぴーんと伸びたと。座の者どもも皆、話を聞いて驚くやら、感心するやらありがたいやらで」
「座頭、そのことで急ぎ、相談したいことがあるのだ。昨日私が市場で会ったふたりに会わせてもらえぬか」
「へ? ソフィとセレスにでございますか」
「そうだ。練習中なら少し待つ。子どもは見習いか」
「へい、さようでございます、ですがゼタ様、セレスはついさっき、ええ、本当に半時もたっておりませんが、院司様とおっしゃるご年配の奥様がお見えになって、慈善院へ出かけていったばかりでございます」
意外な言葉にゼタは一瞬、返す言葉を失った。
「慈善院とは何よ。ここで虐待の疑いでもあったのか」
代わりにヴェンティが問いかけた。ビョルケ座頭は目をぱちぱちさせ、
「それはいったい、なんのお話でございますか。院司様のおっしゃるには、慈善院には、芸人一座の興業を見に来られない子どもさんが大勢おいでだそうで」
その子ども達に、同じような年頃ながら、芸の練習を一生懸命して、頑張っている子どもがいると教えてあげれば励みになるという説明があったという。芸人達は興業を控えて仕上げにかかっているため、手が離せない。セレスは婦人に連れられて一人で慈善院へ向かった。帰りも必ず連れてきますからと、婦人は請け合ったという。
「ということですから、セレスは見習いですけれども、手玉を五つほど持って、慰問に行ったのでございますよ」
「しまった!」
ヴェンティが叫び、親方はその声に驚いて飛び上がった。
「院司の証明は受けたか、親方。名簿に院司印は?」
「は? いえ、ゼタ様、院司様は座の名簿に印を押してはおられません。私どもは印をお見せいただいただけで、はい」
ヴェンティがゼタの横で、ぶんぶんと首を振った。
「そいつは偽物だぜ、座頭」
「な、なんですと」
「ヴェンティ。院司印は滅多に目にしないものだ。院司が偽物か本物か、座頭にわからなくても無理はない。それより、慈善院に行ったという話のほうが怪しい。座頭、昨日、私が会った……ソフィといったか、彼女をすぐにここへ」
座頭の後ろで話を聞いていた剣術舞の男が一人、大天幕へと駆けだしていった。すぐさま大天幕から、昨日ゼタが市場で救った女が出て来た。舞踊の衣装を身につけ、手には羽根をどっさりつけた豪華な扇を持っている。
「あなたは、昨日の……ゼタ様?」
すぐにゼタの顔を思い出した様子で、しかし笑顔は見せなかった。その場の雰囲気を敏感に察したようだ。
「ソフィ、聞いてくれ。昨日、私と会う前に、装身具店に行ったな?」
「はい、扇を買いに」
「その店の主人が、家族もろとも行方不明になった」
「え?」
「昨日、私はふたりに、店主から事情を聞いたのち、ここへ説明しに来ると言ったのだが、そういうわけで、説明はできない。だが、信じてほしい。今から言うことを、座頭も、一座の者も、よく聞いてくれ」
座員が皆、押し黙ってしまった。ゼタはビョルケ座頭が、両手を握りしめて震えているのに気づいた。セレスという子どもが大事にされているのだと、その態度からわかる。
「金貨騒ぎは、罠だった可能性がある」
ゼタが言うと、横でヴェンティが、
「可能性どころか。ありありと、罠だよ」
混ぜっ返すな、ヴェンティ、とゼタは注意した。
「それと、院司は芸人一座から、子どもを慈善院へ、慰問と称して連れ出したりしない」
「で、ではうちのセレスは、セレスはどうなったのでございますか、いったいどこへ」
座頭は涙声である。ソフィが座頭の肩に手を回して支え、こちらも青ざめていた。
「今からただちに、私とヴェンティとで、セレスを探しに行く。だが、座の皆には、冷静さを保ってほしい。下手に騒ぐと、セレスが危険だ」
「危険って、どういうことです」
ソフィがとがった声で聞いてくる。
「理由はまだ、はっきりしない」
「これで二度目です! どうしてセレスばかりが危険な目に、あの子は」
「隠し子かもしれないからさ、さるおかたの」
ヴェンティがさらっと言い、ゼタはのけぞった。
「ヴェンティ……何を言い出すのだ」
「違うかも知れないけど、可能性はある。でも皆さん、これは口外しちゃだめだよ。わかった?」
芸人達は揃って真剣な顔をして頷いた。
「ソフィさん、セレスはこの座の誰かの子どもじゃないよね?」
「ええ、違います。五年前に、北峰領の村から加わった子です。食いつぶして逃げてきた農民の子という話でした」
「五年前、北峰領で食いつぶした農民なんていないよ」
「えっ、どうしてそんなことがわかるのですか」
「調べたもん。十年前まで。北峰領の農家の、大農家、自作農、全部。まずね、農民は食いつぶしたりしない。不作なら租税免除の上、下賜麦っていう保護法を陛下がお定めになったから。小作はまあ、逃げちゃったりするけどさ。でもね、小作は自分達のこと、農民とは言わないんだ。地主のところの奉公人だから、たとえ逃げたとしても、元奉公人って言うんだよ。わかる?」
「まあ、ではどうして、パルメはあんな嘘を」
「パルメ?」
今度はヴェンティが驚いた声になった。
「えと、待ってよ。それはつまり、五年前にパルメさんっていう人が、北峰領のあたりで、セレスを連れてきて、食いつぶした農民の子だと言って、ビョルケ一座に加わった。って、そういうこと?」
芸人達は全員、同じような渋い顔をして首を上下に振った。ビョルケの眉間には皺も寄っていた。
「で、パルメさんは、もしかして王都に入る直前に、座から抜けた?」
再び、全員が頷いた。
ゼタはヴェンティの肩に手を載せた。
「ヴェンティ、とりあえず慈善院に行ってくれ。そこにセレスがいなかったら、兵舎で落ち合おう。私は先に兵舎へ行って、セレスを捜索する兵を集めておく」
「慈善院より西館を洗っちゃったほうがいいんでないかい」
「陛下の許可なしにそれはできない」
「あ、そうか」
学博ルーシェ公、准学マージ姫とも、王裔である。領兵には捜査権がないのだ。
「では、私たちはこれで失礼するが。座頭も皆も、落ち着いてほしい。芸をするときは集中力が必要と聞いた。どうか、怪我などのないように。捜索の結果はできる限り頻回に、領兵を派遣してお知らせする。では」
「ゼタ様、お願いします! セレスを、セレスを無事にお返しください!」
ビョルケがかすれた声で言いながら何度も頭を下げた。
「必ず」
しっかり目を合わせてそれだけを言い、ゼタは一座の天幕前を離れた。
*** エラ、コーディ夫人のために走る ***
エラは全速力で走っていた。
コーディ夫人のお為に。ただそれだけが、エラの胸にあった。エラは十六歳で初めてコーディ夫人の実家に使用人として入った。エラが二十二歳のとき、お屋敷でコーディ姫が生まれた。それから今日までの三十八年間、ひたすら尽くしてきた。西府領で一番美しく優しく、清らかなコーディ様、エラの大切なコーディ様だった。王都へ嫁入りしたときはもちろん、付き従ってきた。
コーディ夫人の幸せはエラの幸せである。同様に、夫人に襲いかかる不幸の影は、エラがどうあっても、はらいのけなければならないと思っている。
ついさっき、芸人一座から連れて出て来た子ども、セレスという名の少年。おとなしくて、物静かなとても良い子だ。あの子にはなんの罪もない。
「おばさん、慈善院て、遠いのですか」
疑いのかけらもない、澄んだ目で見つめられて、エラはもう少しで泣いてしまいそうだったが、懸命にこらえた。
じつは、芸人一座から子どもを連れて出すこの方法は、コーディ夫人のお友達、つまり貴族の夫人で、同じように院司印を保有していたご婦人の真似である。芸人一座ではときとして大勢の子どもを育てながら旅をするが、その中に、どう教え込んでも、育った後に芸人にはなれそうもないという子どもがいたりする。芸をして稼がなければ、座のお荷物なので、どうかすると虐待を受ける。そうした子ども達を探し出して座から引き取るとき、子どもを虐待しているのかと、いきなり尋ねても、たいていは「していません」で済まされてしまう。そこで王都の貴族夫人達は、芸人一座の子ども達を慈善の名目で私邸に招いて食事をさせ、子ども達からこっそり聞き取りをしたのである。子どもの身体に傷跡があったり、子ども自身の話から日頃、座の中でひどい扱いをうけていたと判明したときは救出する。貴族婦人たちは院司の資格を持って保護し、慈善院へ集めて子どもを世話をするという活動を行ってきた。
コーディ夫人のご友人数人が茶会の席で、子どもを保護したときの方法を、手柄話のようにして披露していたのを、給仕しながらエラは聞いていた。
コーディ夫人は救出方法には関心がなかった。両親から大切に育てられた夫人は、子どもが虐待に遭うという現実を、はなから想像することができないからだった。その代わり、慈善院での子ども達の世話などは熱心に行った。子どもの身体を清潔にしてやって、衣類を着せ、食事をさせる。痩せて体力のなかった子どもや病気だった子が、次第に元気になって、夫人になついてくれるのが嬉しいらしく、去年の秋頃からは頻繁に慈善院に通っていた。
そうした話を茶会の席の後方で聞きながら、
……その程度のことなら私にもできそうだわね。と、エラは思ったことがある。だが、今日、実際に子どもを連れ出してみて、聞くのとやるのとでは、こんなに大きな違いがあるのかと痛いほどに感じた。芸人一座に子どもは大勢いるだろうと、見当をつけていったのだが、これがまず外れた。その上、セレスという子が優しい子で、慈善院へ慰問に行ってもらいたいというエラの嘘を疑いもせずに、快く引き受けてくれたのである。エラの良心は奥底で軋むような音をたてた。罪悪感で汗だくになりつつ、セレスをサンザ商館の荷車駐まりまで連れていき、
「ここで、ちょっと待っていてね、坊や。おばさんは用事を済ませて、すぐに戻ってくるから。迷子になるといけないから、ここにいるのよ」
そう言い聞かせたときも、セレスは無心に頷いただけだった。それがまた、エラの胸にひどく堪えた。しかし、これもコーディ夫人のため。やり通さなければ。自分を奮い立たせて、子どもを置き去りにした。
商人の館はその特性からして、門も扉もほぼ開けっ放しである。人通りも荷車も多く、エラとセレスにことさらな注意を向ける使用人はいない。子どもをここへ連れてきて入り口で待たせ、館内で商い向きの話をする親もあるはずだ。エラはそう思ったのだった。セレスを置き去りにしたあと、エラは敷地内を早足で突っ切って、サンザ館の前の大通りを渡った。
広い緑地の向こうに学舎がある。学舎の前庭に入るとエラは走った。
エラの筋書きは仕上げに入っていた。
これからマージ姫に会って、サンザ商館の使用人が、芸人一座の子どもを誘拐した、とお知らせする。
その子どもをマージ様に保護していただく。
子どもを狙った犯罪には厳罰がくだる。さきの陛下も、今の陛下も、子どものことになると厳しくて、さらったり虐待したりすれば、鞭打ちの刑である。
だが、ちゃんとした証拠がないから、サンザ家が罪に問われることはたぶんない。
子どもも無事に一座へ送り返されるだろう。
疑わしい噂だけは、隠しようもなく広がる。
そのような噂のあるサンザ家との縁談には応じられないと、コーディ様がルーシェ公を説得なさる。
誰かを傷つけたり、困らせたりはだめよと、コーディ様はおっしゃった。
大丈夫、立つのは噂だけで、誰も傷つかない。
コーディ様、エラが、やりとげます。もう少しです。エラは走りに走って、学舎西館の玄関へ飛び込んだ。
西館の大玄関にいた、受付の若い学生に、
「マージ様はどこですか、今すぐお会いしたいのですが」
息をきらしながら尋ねた。
「准学マージ様はお部屋においでですが。あなたはどなたですか」
「マージ様の母上、コーディ様の使用人で、エラです。急いで、とにかく大急ぎで、私が来たと、お話があると伝えてください」
エラの異様な訴えぶりに、学生は驚いた様子だったが、すぐに階段を上がっていった。
エラは波打つ胸を押さえ、一心に階段の上を見つめた。一瞬一瞬が、耐えがたく遅く過ぎる気がする。万が一、この策が失敗したら、と思うと、それだけで膝から崩れて座り込んでしまいそうだった。
ふいに、階段上で足音が聞こえ、さきほどの学生が下りてきた。
「お会いになるそうです。二階の応接室へどうぞ、お急ぎください」
ああ、助かった。エラは両手を胸の前で握りしめた。階段を上がり、学生に案内されて廊下を歩き、部屋へと入る。
「エラか。どうしたのだ」
コーディ夫人の宝物、マージ姫の声がエラを迎えてくれた。
「姫様……マージ様」
そう言ったあと、言葉が続かない。
ああ、よかった。おいでになった……。そう思ったとたんに、何をどう説明したらいいのか、わからなくなったのである。
「ずいぶんと汗まみれのようだが。母上に何かあったのか」
「はい。いえ、そうではなく、そうです。コーディ様が、大変なのです、マージ様」
「落ち着いて話すがよい。母上から伝言か」
エラは胸の動機がいっそう激しくなるのを感じた。この姫が幼い頃から異様なほど賢いことは知っていた。コーディ夫人のものやわらかな性格を、マージ姫は少しも受け継いでいない。少女のころから、マージ姫は独特の威厳を持っていたし、エラは彼女の前では自分が野ねずみほどに小さくなっていくように感じたものだ。
だが、もう後戻りはできない。ことは起こしてしまったあとである。
「マージ様。コーディ様は、ご結婚に反対でおいでです」
「知っている」
「なんとかして、この縁談を、なかったことにしたいと、お悩みでした」
「母が、何かしたのか」
「いえ! コーディ様は、何もご存じありません。すべて、すべてこのエラが、しでかしました。これを」
エラはコーディ夫人から借りた院司印を差しだした。受け取ったマージが、怪訝そうにそれを見る。
「院司印ではないか。これがどうしたのだ」
「お借りしました、コーディ様から」
「そうか。エラはこれを何に使った」
「馬場あとの天幕に、芸人一座が来ております。その一座の子どもをこれで、連れ出しました」
「虐待の疑いでもあったか」
「いえ。大事にされている様子でした。で、その子を」
マージの顔が厳しくいかめしくなるのをエラは見た。今までの人生で、これほど怖い人間に会ったことはないとまで、感じたのである。
「よもや殺してはいまいな」
「とんでもないことでございます!」
エラは叫び、頭に血が上って、卒倒しそうになったが、かろうじてこらえた。
「その子どもを、サンザ商館の、荷車駐まりへ置いてきました」
「サンザへ? それはまた、なんのためだ」
「サンザが、芸人の子どもをたぶらかしてさらってきた……マージ様がそれをお裁きに、院司印をお持ちになって商館へお出ましになれば」
ふいにマージは声をたてずに笑った。姫様は笑ったほうが怖い。エラはこの場に身を置いていることが耐えがたく、ついに両手で顔を覆った。
「そうすればサンザに多大な落ち度ありとして、縁談が壊れると考えたのか」
「そうです、その通りです」
「浅知恵だな、エラ」
エラの胸は潰れそうになった。すべてはコーディ夫人のため、そしてマージ姫のためである。それを浅知恵とひとことで切り捨てられた痛みは激しかった。
「案ずるな。縁談は、ついさっき、壊れたところだ」
「は? はい?」
「サンザ家から、断りの返事が来たということだ。父上からお話があった」
声はもう出なかった。ではこの一刻あまり、エラがしてきたことは、なんの益にもならなかったことになる。
「しかし、エラ。それで良い。このマージに考えがある」
「は、はい、姫様」
「ところで、子どもの名前はなんという」
「セレスと名乗っておりました」
マージの頬に、軽く赤みがさしたやに、エラには思えた。マージは椅子から立ち上がり、エラから離れて扉へ向かっていく。扉前で振り返った。
「院司印は預かる。早く帰るがよい」
「わ、わかりました」
エラはこれ以上、自分を保てそうになかった。よろよろと歩を進めて部屋を出る。マージの姿はもう廊下にはなかった。階下から、
「序学士並びに学生を呼べ! 全員、講堂へ!」
マージの、将軍のような号令が聞こえてくる。恐ろしさと安堵が複雑に入り交じったような、言い様のない気持ちを抱えて、エラは階段を降り、学舎前の緑地へ出た。
目の前を、大勢の学生が通り過ぎた。マージの号令を聞いたのだろうか。学生全員が、東西の学舎のあいだの講堂へ、足音高く駆けてゆく。
何か、恐ろしいことが起きそうな気がした。
サンザ家との縁談が壊れたのだから、コーディ夫人の悩みは消えたはずだ。だから安心していいのだ。自分に言い聞かせたが、手の震えが止まらない。やがて、すべての西館学生が講堂へ入ったらしく、あたりは静かになった。エラは自分を励まし、立ち上がった。自分がしたことの結末を知るために、講堂の扉へ向かった。講堂玄関の大扉は開いていた。講堂では大勢の学生が、整然と並んで立っている。学生が揃うと、序学士三十名が一列になって入堂した。
最後にマージが、壇上に進んだ。
「学生達よ」
准学マージの声が講堂に響く。
「私、マージのもと、日々の学業に励む学生達。今から、マージの指揮により、西館全学生による院司執行を行う」
臨時に司法権を行使して、不正をただすべく、マージを先頭に、市中へ学生総動員で出動するのである。
「皆も知っての通り、サンザ家は民への奉仕と称して、その実、数々の専横を行ってきた。我らは学舎学生として、国と民のために日々研鑽を怠らないが、サンザは違う。国と民のためでなく、商団と私欲のために肥大し、日ごとに横暴さを増している。今や、王都の民の命をいつでも脅かせるほどの力を持つに至った」
学生達は無言でマージの声を聞いていた。
「そのサンザでは、さきの陛下ヴォイド三世が禁じられた、十三歳未満の子どもを拉致誘拐したあげく、見習いと称して酷使している。私は王の近裔として、また王国の平和を担う学舎准学として、これを見逃せぬ。よって、今から全学生とともにサンザ商館へ向かい、強制労働させられている子どもを救おうと思う」
エラは仰天して後ずさり、扉の鉄環にしがみついた。これほど大げさなことになるとは思っていなかった。せいぜい、お付きの二、三人を連れてサンザへ行き、芸人の子どもを勝手に連れ出した濡れ衣を着せて、サンザを非難し、そのような商団の跡取りとは結婚できないと、破談を申し入れる手段にする……程度と考えていたのだ。
やがてマージが壇を降りてきた。その後ろに序学士が並び、よどみなく学生が続いた。
扉脇に身を隠していたエラの前を、学生が次々と通り過ぎていく。どの顔も怖いほど真剣な表情をしていた。
学生の集団はひとかたまりになって遠ざかっていく。
マージひとりを舳先にして濃い深緑の巨船が進んでゆく光景に、それは似ていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
