「ごはんが恋しい」 (とらばーゆ 1986)
外国を旅していると、日本食が食べたくなる。わたしは、嫌いな食べものはないのだが、辛すぎるもの、塩のききすぎたもの、油っこいものは苦手なのだ。だから、外国で、しつこい味のものばかり食べていると、さっぱりした日本食が恋しくなる。
去年の夏、ドイツのブレーメンの友だちの家に居候して、二ヶ月間、ドイツ語学校に通ったときは、せっせとお鍋でごはんを炊いては、生卵をかけて食べたものだ。
そのドイツ語学校には、日本人も十人以上いたが、日本食を自炊していたのは、わたし以外は、すべて男だった、女たちは、ドイツのパンやチーズはおいしいから、べつに不自由しないといっていた。しかし、男たちは、口をそろえて、「やっぱり、米のメシが食べたい!」。
男たちがごはんを食べたがるのは、パンよりお腹にたまるので、旺盛な食欲が満たされるからだろうか。それなら、おモチのほうがお腹にズッシリくるけど「おモチがなつかしくてたまらない」といったひとは、いなかった。
だいたい、男のほうが、自分が生まれ育った環境のなかではぐくんだものを守りたがるようだ。女のほうが、どんな環境にでも適応できる。男たちが、「米のメシ」食べたがるのは、それがいちばん馴れ親しんだ食べたものであるからではないだろうか。
わたしの知人のなかに、三食、かならずごはんを食べないと、気がすまない男がいる。じゃあ、パンやうどんはどうなるんだときいたら、そんなものはおやつだといった。彼の体格は、長年のごはん生活の結果、中年を待たずして、でっぷりしたものになった。海外旅行に行ったら、三食ごはんというわけにはいかないから、日本から一歩も出る気はないそうだ。
彼がいったセリフで、もうひとつ、忘れられないものがある。どうせ、人間死ぬのだが、どんな死に方いいかと、何人かで話していたときのことだ。長く病気で苦しむのはイヤだね。でも、あんまりあっけないのもどうかな、と現実感もないまま、各自が勝手なことをいっていた。すると、とつぜん、彼はマジにいったのだ。どんな死に方でもいいが、かならず、今、自分が毎晩寝ているとおり、畳に敷いた布団の上で死にたいと。病院のベッドの上や、飛行機事故では、死にたくないそうだ。
まあ、彼ほど極端なひともめずらしいけど、男のほうが、自分の現在の生活習慣を、一生守り通したいと思うものだ。女のほうが、その場に合わせて、臨機応変だ。
ドイツで会った日本人の女のコのなかには、特定の相手ができたわけでもないのに、ドイツは住宅環境がいいし、このままドイツで結婚して、こっちに住んでもいいなあといったひともいた。
それをきいた、ある男のコは、ドイツ人の女と結婚して、ドイツに住むなんて、とんでもないといった。仕事に疲れて帰ってきたときは、サッと熱い日本茶をだしてもらいたい。それには、やっぱり、よく気がつく日本人の女の人じゃなくちゃ、いけないそうだ。わたしは、彼が、まだ若い学生だったから、おどろいた。
彼は、お茶漬けを、自分と同じようにおいしいと思ってくれるひとでないと、いっしょに暮せないとも、いっていた。しかし、たとえ日本人同士で、同じお茶漬けを食べたとしても、はたして、同じ味がしているものだろうか。味覚の感じ方は、ひとそれぞれではないだろうか。
日本食好きのわたしには、日本食に固執する男たちについて、どうこういう資格はない。だけど、自分の好みを、相手に押しつける結果になるのは、よくないと思う。自分がどうしても食べたいものは、自分でつくって、食べればいいのだ。
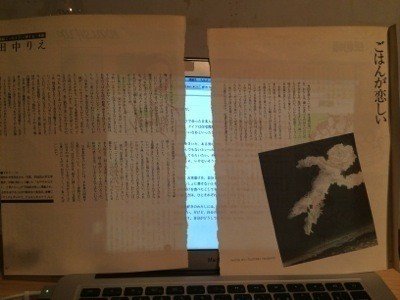
(投げ銭、よろしければお願いいたします)
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
