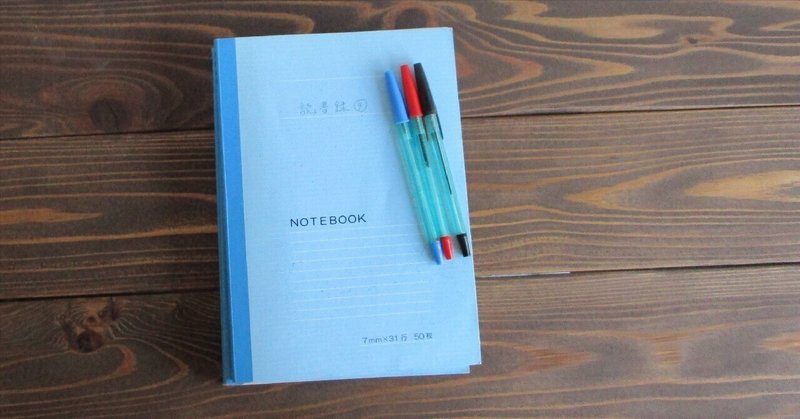
渡辺淳一「失楽園 上巻」読書感想文
渡辺淳一には、ずっと小さく興味があった。
2014年に死去したときのニュースを見てから。
「セックスは決してエロではない、人間がいとおしく見える」といった意味の生前の言葉が紹介されていたから。
それまでは、渡辺淳一とは「失楽園」というエロ小説を書いて、ノリが軽いスケべったらしい作家というイメージしかなかった。
この人、大真面目にエロを追求してたんだ・・・という以外さが、小さな興味に直結させていた。
たぶん、意外なイメージにさせたのは、石田純一が勝手に重なっていたのだろうけど。
2冊めの渡辺淳一
初めての渡辺淳一は、未決囚のときに「パリ行最終便」で済ませている。
が、この短編集は、実刑判決を挟んで読んだので、気持ちが動揺するわパリどころじゃないわで良く覚えてない。
気持ちが落ち着いた今は改めても読みたいし、別の本も読みたいとも思っていた。
2冊目の渡辺淳一は、この「失楽園」が無難だろう、と官本室で手に取った。
映画もテレビ放映で観ており、不倫が描かれているということも、結末も知っている。
詳しくは覚えてないのが、原作を読むのにはちょうどいい。
貸し出しのカゴに入れた。
すると刑務官が「なんだオマエ!こりゃ、スケべな小説じゃねえか!」と言ってきた。
せっかく、物思いに耽って選本したのに。
君は文学というものをわかってないのかね・・・と心のどこかで反論しながら「先生、たまにはこういうのも・・・」とショイショイで借りたのが残念だった。
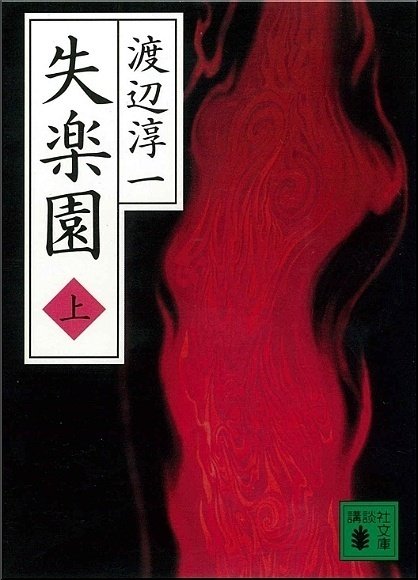
読み終えた直後の感想
大人になったのを感じた。
当時 “ 失楽園ブーム ” というのがあったけど、それがなんだったのか、わかるような年齢になったのだ。
感慨深い。
コンクリートの天井を見上げた。
すぐに読書録を書こう。
すぐに下巻を読もう。
失楽園ブームのときからすると
その失楽園ブームのときは、まだ自分は少年だった。
失楽園とは、ただのエロ小説という認識しかない。
自分にとって失楽園とは、ナンパのネタでしかなかった。
「失楽園しませんか?」みたいなノリで、よく意味がわからないけどブームに乗っかって使っていた。
檻の中にいる今となっては「もっと勉強しろよ!」と、当時の自分の頭を引っ叩いてやりたい。
渋谷のスクランブル交差点を左に渡ったところに「オカダヤ」という手芸の店があって、そこに出入りする30代や40代の人妻を狙う少年だった。
あと東急本店前の文化村通りもいい。
お出かけの装いの熟女を狙う。
当時はまだ “ 熟女 ” という言葉がない。
レンタルビデオ店にいくと、30代や40代の女性のAVは “ 年増モノ ” というジャンルで、棚の隅に数少なくSMなどの特殊性癖と同一に置かれていた状況。
少年の身で、ひと回り以上の年上の女性が好きと口にしたものなら “ マザコン ” か “ ヘンタイ ” の一言で済まされてしまう時勢だった。
だから当人にも、30代や40代の女性が好きというのは「普通じゃないんだ・・・」と重く圧しかかってもいたし「でも今さら普通もないしな・・・」という開き直りもあったが、いずれにしても公言はできない。
それでも「人妻が好き」と公言するのだったら、少年たちには非合法の気分で認められる。
この少年には罪はない。
童貞を奪われた35歳の大塚病院の看護婦(当時)が、そうさせた責任があると思われる。
それに、ネットが普及してない当時は、道端でのナンパは日常のことだった。
とにかくも、熟女攻略法である。
まず、綺麗どころに声をかける。
で、どこが綺麗なのかハッキリと口に出す。
どういうことかというと「カワイイ」に反応するか、「キレイ」に反応するかで最初の距離感が決まる。
「カワイイ」と「キレイ」は同じようでいて共存しづらい。
「カワイイ」に反応する女性は、受け身の姿勢ながらも可愛らしさを無責任にばらまく。
曖昧に距離をとらないと引いてしまう。
対して「キレイ」をまとう女性は、攻めの姿勢があって主張がある。
どこがどう「キレイ」だと大胆に口に出して、こちらも踏み込みこんでいくくらいでちょうどいい。
足を止めた女性から鼻の笑いが出たら、そこが橋頭堡。
さんざんと突撃した末の橋頭堡。
本来は、軽蔑の意味がある鼻の笑いだけど、好感が交じった鼻の笑いってのもある。
ただ、あきれているだけかもしれないけど。
そしたら、下の名前で呼び捨て攻撃。
ひと回り以上の年上の女性だけど、ものすごく大人に見えるけど、思い切って呼び捨てしてみる。
熟女ともなると下の名前でなかなか呼ばれないから、あえてやってみる。
こっちも精一杯だけど、向こうだって年下の少年に呼び捨てにされて精一杯になるのはわかっていた。
でもここは難しいところで、態度が無礼な人が呼び捨てすると、そもそもが無礼なのだから、やっぱり無礼となる。
だけど、自分のような自称ではあるが礼儀正しい人が呼び捨てをしたのなら、そもそもが礼儀正しいのだから、ナンパの距離感としては呼び捨てでもちょうどよくなる。
呼び捨てクリアしたら、あとは駄々。
熟女にこそ盛大に駄々をこねるべき。
どうせ、世代の違いで話も合わないのだから、駄々をこねるのは欠かせない。
それと息子を持つ熟女の匂いってあって・・・。
・・・話が飛んだ。
だいぶ。
なにがいいたのかというと、主人公が、37歳の人妻にのめり込む気持ちが「わかるぅぅ」といいたいのです。
登場人物 - プロファイリング風
久木祥一郎
都内にある出版社勤務の54歳、既婚者。
世田谷区桜新町住。
出版部長からの降格人事で、調査室へ移動となったばかり。
昭和史編纂が仕事内容となる。
その年、人妻の松原凛子と知り合い、不倫状態に陥る。
会社と家庭の往復のみだった久木氏を不倫にのめり込ませた原因のひとつとして、松原凛子の姿態が挙げられる。
松原凛子は、セックスには貪欲な姿をさらけ出す一方で、恥らいも忘れないというアンバランスさがある。
意図された姿態ではないが、これが久木氏をのめり込ませて、翌年の1月から、当該女性と渋谷区のマンションで同棲をはじめるにまで走らせる。
松原凛子
杉並区久我山住の37歳。
既婚者、誕生日は2月14日。
書道の講師。
久木氏からの接触により、当初は戸惑いながらも関係を持つに至る。
与えられた快楽には忠実な松原凛子だが、ミッション系大学卒が影響しているのか、不倫に罪悪感を抱いてもいたりと一般以上の良識も垣間みせる。
しかしながら、そういった、いわゆる “ 人妻ブランド ” が久木氏をして加虐にさせ、やがてお互いの破滅に向かわせた遠因なのも認められる。
松原凛子が自宅を逸出して、渋谷のマンションにて久木氏と半同棲になったときには、夫から「売女!」と罵られて暴力をふるわれたと言い訳されるが、そもそもが不倫が露呈したことが直接の原因でもある。
言い訳は、松原凛子を大胆にさせていく。
母親からは「身体におぼれたふしだら女!」と指弾されて縁を切られるに至るが、松原凛子の基本的な態度は被害者という域から出ることはない。
松原凛子が知らず知らずに見せつける、あざとさが含まれる立ち回りに、久木氏が引きずり込まれた感は否めない。
松原晴彦
松原凛子の夫。
48歳、医学部教授。
久木氏と松原凛子に敵視され悪人扱いされるが、よくよく考えてみると、とくに落ち度もない被害者的立場といえないこともない人物である。
衣川
久木氏の大学時代からの友人。
新聞社勤務から、カルチャーセンターに出向して所長をしている。
久木氏に、カルチャーセンター講師の松原凛子を紹介した。
あらすじ
降格人事があってからの出会いで
出版部長から、調査部へ降格人事となった久木だった。
5人の部署は、仕事らしい仕事はない。
閑職だった。
それでも久木は、気楽でもあった。
これからは、あくせくしないで、もっと自由に生きていこうと思っている。
ある日、友人の衣川からの依頼でカルチャーセンターで講演をした久木は、紹介された松原凛子を交えて食事をする。
彼女から貰った名刺を頼りに電話をかけ、食事に誘い、2人は関係を結ぶ。
当初こそは人目を気にしていた2人だったが、そのうちに気にかけなくなってくる。
鎌倉のホテル、箱根のホテル、横浜のホテルで2人は会い続けて、その度に性愛は深まっていく。
不倫にのめりこむ2人
不倫には戸惑いながらの松原凛子だったが、夫との行為を受け付けなくなったとも、化粧ノリが良くなったとも、恥ずかし気に話す。
敏感に「こわいわ・・・」とあえぎ、行為のあとには「わたし、おかしいのかしら・・・」と、のぼりつめた瞬間を「頭の先まで貫かれるような・・・」とためらいながらも話す。
良識として慎みを理解しているのだけど、身体が言うことをきかないほどに感度が高まっていくのだ。
そんな彼女に久木は満足を覚える。
お互いに外泊することも増えてきた。
久木は、友人とゴルフだ、仕事の出張だ、と嘘を重ねて外泊するが、妻は薄々と気がついているかのような言動をとるようになってきてもいる。
凛子は、友人と旅行、書道の授賞式などアリバイをつくるが、夫はすべてをわかっているような態度を取る。
お互いに状況はわるくなる一方だったが、会うのは止められない。
その日もベッドの上で過ごす。
事後、放心していた凛子は「電気が流れたようだった・・・」とつぶやいて身を寄せてくる。
久木はさらに抱き込んでいく。
一晩が終わる。
別れるときには、お互いにさびしくもなり辛くなっていく。
葬式の夜に喪服で
その年の暮れ、凛子がカルチャーセンターの常任講師を申し出ていることが衣川からの電話で知る。
彼女は家を出ようとしているのか。
それを確めようと自宅へ電話したのだったが誰も出ない。
夜になって彼女から電話があった。
彼女の父親が急死して、横浜の実家で葬儀の準備をしているという。
久木は嫉心した。
凛子が夫婦として葬儀に参加しているのが不満だった。
久木は、半ば命令するかのように、これから横浜のホテルまで来るように告げる。
電話の向こうで戸惑う凛子からの返事はなかった。
横浜のホテルで久木が待っていると、通夜の最中に抜け出した凛子が喪服で現れたのだった。
30分で帰る約束だったが、久木は喪服の裾をまくり上げて事に及ぶ。
あとは、なすがままの凛子だった。
さんざんと抱かれてから「こんな夜にこんなことして罰があたる・・・」と凛子は蒼ざめて帰っていった。
そのような状況に、ほのかに満足を覚えた久木だった。
年が明けてから
年が明けた。
1月3日の呼び出しに応じた凛子だった。
久木でないと満足できない身体にされた、操られているようで口惜しいと、首を絞めてきたりもする。
が、もう、夫になにをいわれても気にしないことに決めた、ときっぱりとした態度も見せる。
久木は、いつでも会えるようにと、渋谷に1LDKのマンションを借りる。
会社が終業するとマンションに直行して、2人で食事をして、それ以外はベッドで行為に耽る。
新婚生活のようであった。
無断外泊の末に
2月になる。
凛子の誕生日のプレゼント代わりにと、2人は日光の中善寺湖の温泉に小旅行をする。
この旅行が2人にとって、後戻りできない状況に追い込まれることになった。
大雪となったのだ。
翌日に、東京に戻ることができなくなる。
凛子は、夫方の姪の結婚式を無断で欠席することにする。
夫が怒るのは予想されたが、開き直ったかのように、2人はもう1泊する。
翌日に、2人は東京に戻る。
久木は出社しなければだが、凛子と別れることができない。
出社もせず、妻への連絡も放り、凛子と一緒にいることに決めて渋谷のマンションに向かう。
その日は、さらに2人は行為に耽る。
とはいっても、それぞれの家に帰らないわけにはいかない。
お互いに帰路についたときには、22時を過ぎていた。
