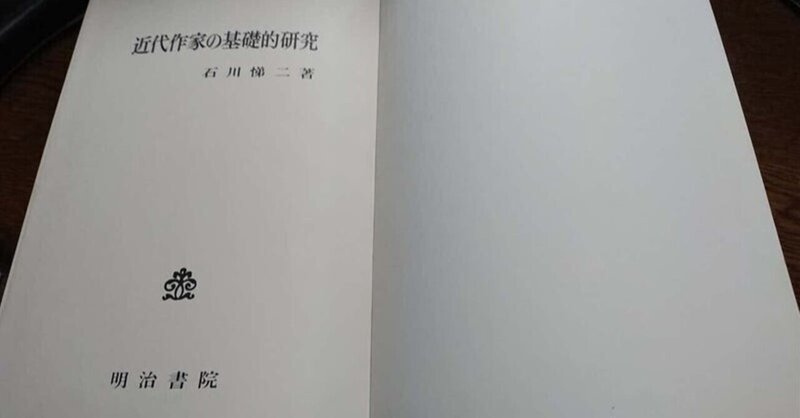
石川悌二著『近代作家の基礎的研究』(7)―樋口一葉と谷崎周辺(その3) 稲葉の風
春がすはみ立ち別れしはいつならん
いなばの風に雁のねぞする
この本には『一葉日記』から「稲葉ノ風」と題する一首が引用されていますが、ここに至るまでの経緯もこの本に記されています。
一葉の両親
樋口一葉の父母が山梨の故郷を駆け落ちして江戸に上ったのは安政四年四月六日で、母はすでに妊娠していました。江戸へ着いて過ごすうちに月満ちて女子(ふじ)を生みましたが、この子を里子に出して湯島三丁目の稲葉大膳正方という旗本の家に乳母奉公をすることになり、以後数年間仕えました。
一葉の母が乳を上げた赤ちゃんは、おこう(鑛)という名の女の子で、養女でした。生後半年ばかりで稲葉大膳にもらわれたことが書かれています。この子が後に家督を継いで牧野家から婿をもらい婿に家督を譲ることになりますが、一葉の母は稲葉家で政岡のように威風を帯びていたという故郷の人の伝え話を記した人もいることが書かれています。政岡は谷崎作品にも何かと埋め込まれるので、政岡というと目を留めてしまいます。
稲葉家の変転
一葉の父母は共働きでお金を貯めて頑張っていたわけですが、明治維新の社会変動で稲葉家の状況が変わります。
旧旗本の中でも、朝臣を願い出た者は一応安泰であったが、その多くは新政府に仕えるのをいさぎよしとせず、それらの人々は領地や屋敷を官収され、たちまち生活の方途を失った。そして多数の人々は静岡に移封された旧主徳川亀之助にたよって都落ちをしたが、稲葉大膳がその後静岡に移住したことを思わせる次のような記録がある。
と、明治3年2月9日に一葉の父が東京府長屋から府宛に提出した届書の内容が掲載されています。そして、
維新のさい、徳川家をしたって都落ちした人々の中でも、早く元年八月の徳川亀之助移封と行を共にした人々には、三千石以上は五人扶持、以下千石迄は四人扶持というように、わずかながらも扶持があたえられた。だが、明治三年にもなって、東京を食いつめて落ちていった人たちは全くの無禄移住であった。
ということで結局東京に戻るわけですが、知人が新政府の官員になって湯島の稲葉邸がその賜邸になっていたこともあり、明治9年にはその知人に稲葉正方を証人に一葉の父が大金を貸し付けている記録から、昔の抱え屋敷があったところに住んだらしいことが書かれています。その後本所相生町に転居して、明治14年7月、稲葉氏は父の勘気を受けた一葉の次兄の身柄を引き取り、同年10月に分籍届が出され、次兄は平民になります。このように、次兄が父の勘気を受けて無理やりのように分籍されたことが、後に一葉が女所帯を引き受けて苦労する一因になりました。
次兄は翌15年に稲葉正方および松岡徳善(芝大神宮祠掌)が保証人になって、陶工の成瀬誠至へ六か年の徒弟奉公に出されたのですが、その同じ年に稲葉正方が亡くなったと思われ、同年10月30日にお鑛様が戸主を相続し、その2年後の明治17年に小石川柳町士族牧野駒第父駒太郎の次男寛を養子に迎え、即日戸主を譲っていると書かれています。
牧野姓が登場しました。牧野姓は谷崎および周辺に大いに関係があるので要チェックです。しかも、牧野姓で駒ですか。御牧を思い浮かべますね。『細雪』の御牧から御牧姓についてもチェックしてみました。ツイログもご覧ください。
また、松岡徳善という名前も大変気になります。
一方、一葉の父則義は、家運挽回のために荷馬車会社設立を企て失敗し、憂悶のうちに明治22年に亡くなります。葬式に際しては稲葉夫婦が世話役をつとめ骨上げにも加わったこと、一葉が戸主となって、後見人の廃止届をしたときには、稲葉寛が親類の名義で連署していることが書かれています。この時の稲葉寛の住所は本郷菊坂町ですが、父則義の死後しばらく芝西応寺の次兄方へ寄寓した一葉、母、妹の三人は次兄との折合いが悪くて困り、女三人で本郷菊坂町に越した時の借家も同じ町に住む稲葉寛夫婦の斡旋によるものと思われると書かれています。この時は門や小庭のある独立家屋で長屋ではなかったとのことです。
ここまではまだ良かったんですねぇ。
菊坂町といえば谷崎も含め文豪が集まっていた地区。文京区ナビに記事がありましたので、こちらもご覧ください。
いよいよ悪化の度が極まってくるのが明治24年。一葉の日記から次のように引用されています。
朝より雨降る。昼少し過より稲葉君参る、いよいよ落はふれしかば、車引かばやと物語らる。かなしきこといと多かり。
その後も稲葉家はどんどん落ちぶれていき、樋口家にも迷惑をかけるようになり、ついに春は訪れず。寛亡き後、お鑛様とその長男の母子は寛の七十五日と共に牧野清三方に引き取られたとのことですが、その後この本の著者のところに稲葉氏の後裔を名乗る人の訪れがあり、お鑛様の孫の情報が届いています。手品の名人として東京に健在していると(当時)。
ムムッ、手品の名人! 『三つの場合』に登場する阿部徳蔵氏と繋がってくるのでしょうか。
下谷練塀町
その後は樋口一家の住んだところについてそれぞれ詳しく書かれているのですが、その中で1個所、谷崎との繋がりで非常に興味深い記述があります。下谷練塀町についてです。少し長いですが引用します。
東京府構内長屋から、樋口家は明治五年八月七日に、第五大区四小区下谷練塀町四十三番地の桜井重兵衛方に転居した。桜井重兵衛は何者か不明だが、則義はこの家屋の売却を頼まれて、七年二月末に百三十円で売った金額のうち、手附金三十円を取得した。(則義覚書)
連塀町四十三番地は、当時の第三大区取扱所(区務の取扱所で今日の区役所のようなもの)に隣接しており、この扱所を含めた四十三番地二百四坪の地主は江沢述明なる者であった。
この辺は当時も家屋がかなり建てこんでいたようだが、それより一年前の明治四年東京大絵図をみると、ほとんどが武家地で、町の北半分ほどは桑茶畑、南の相生河岸は火除地である。この火除地は、明治二年末の火事が神田一帯に延焼する大火になったのにかんがみて、焼跡の一万四坪を火除けの神様といわれる秋葉神社を勧請したので、秋葉原とよばれたが、秋葉神社は明治二十一年に下谷区入谷町に移されて、秋葉原を鉄道用地として秋葉原駅ができたものである。練塀町のその後の変化ははげしく、樋口家の居住した四十三番地は現在の青果市場の構内に入ってしまったようである。
今はその青果市場も大田市場に移りましたが。
ここで江沢述明という人物が登場します。実は『幼少時代』では、谷崎の伯父久兵衛と父倉五郎は玉川屋の遺児だったのを祖父久右衛門が引き取って婿にしたことになっていますが、この本の谷崎の生い立ちのところで掲載される明治26年に改写された谷崎家の戸籍によると、谷崎の父倉五郎は
明治十六年十二月十七日神田相生町二番地江澤秀五郎三男ニテ入
と書かれています。伯父は間違いなく玉川屋の住所から入っているのですが、倉五郎の住所はどうやら玉川屋新店だったようです。ということは、この江沢述明という人物は谷崎の父の親類の可能性が非常に高いと思われます。また、湯島に玉川屋藤右衛門の記載があるということで(谷崎の父の長兄は藤右衛門を襲名している)、湯島の稲葉家とも縁があったであろうと思われます。二代目久右衛門の妻の桜井姓も登場するところがまた興味深いところですが、このあたりはもう少し調べる必要がありそうです。
樋口一葉については思いのほか長くなりましたが、次回はいよいよ谷崎の生い立ちに入ります。
よろしければサポートをお願いします。いただいたサポートは資料収集等研究活動に使わせていただきます。
