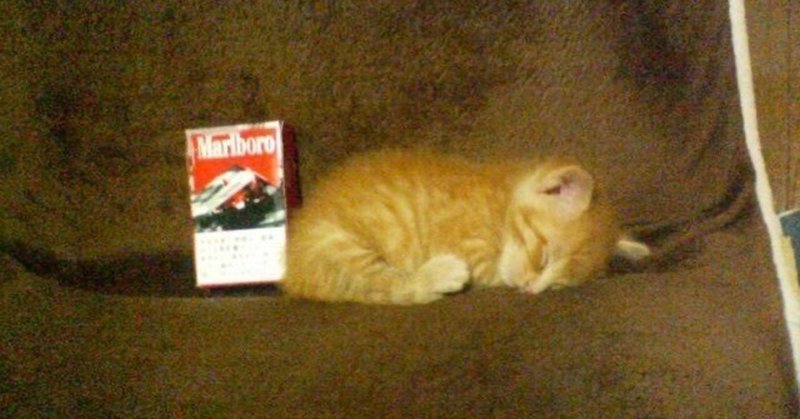
九十九日めの魚
魚は恐怖を感じるんかな。痛覚はどうなんやろ。たぶんやけどないんやろうな、あったら都合が悪いし、それにあったとしてもぼくが思うのとはきっと違うんやろう。
分厚いガラスの水槽のなか、泳ぐというよりこれは浮遊。ただただエネルギーを消費しないように懸命に務めている気がする。そんな一匹の鯛がこちらを見ている。 あ、いま目があった。かと思えばその焦点はぼくを捉えないまま、おそらく目線の先はぼくを通り過ぎて、そうして特異点もなにもない銀色の冷蔵庫に着地した。
奇しくも三枚に降ろされた同種の鯛が銀色のプレートの中、キッチンペーパーに包まれてラップを巻かれて手厚い扱いを受けた安置所の遺体みたいな状態で丁寧に保管されていて、ぼくは食べられるためだけに生かされてるあいつをもう一度振り返って見てみる。名前でもつけてやろうかしら。ぼくも大概やけどおまえもあれな。お互いしんどい場所にいて息苦しいところはほら、似てるかもな。うそうそ、生け簀が汚れるん避けたいからって餌も与えられてないもんな、おまえ。生きられる場所にいるだけの待遇で、身が痩せてしまってガリガリのチーぎゅうみたいなカーストで。美味しさからは遠ざかって、でも活け作り用やから、おまえ。ご愁傷様です。
「桜蓮根、持ってこい」
四つ年上の兄さんが包丁を研ぎながら怒鳴ってくる。桜の花に見えるようにピンク色に合わせた紫蘇酢と包丁細工は自信作やけど、基本的には怒られることが仕事。慌てて持っていくと、兄さんは包丁の刃を親指の爪に押しやって切れ味を確認している最中。ちらっとだけぼくの手元にある桜蓮根を一瞥し、うまくなったな、と言った。めずらしい。
「六方剥きは下手なんにな」
「はい」
「飯はできたんか? 休憩しようや」
「はい、もうできます」
かんてきにチャッカマンで火を放って味噌汁の鍋をペンチで掴んで乗せる。そういえばなんでコンロのことかんてきと呼ぶんやろ。確か上方言葉やったはずだけど誰も教えてくれんしこの世界はわからんことばっかり。鍋に取手がついてないんはガスの火が強過ぎて燃えてしまうから外しておくんやってことは予想ができるし、たぶん間違ってないはず。続いて菜の花の酢の物、鳥肉の代わりに柳鰆のハシっこを板場に貰ったから今日のまかないは柳鰆のあぶれた身をほぐした煮付け丼。テーブルに並べる。おやっさんは炊き立てごはんを少しだけやから困る。少食やから。
ちらちらと鍋を見る。単純な止め椀やけど鍋の周りがふつふつと沸く状態で火を止めんと味噌の風味が飛んでしまう、らしい。正直煮立ってしまわなければ些細すぎる繊細な味の違いはぼくにはよくわからんし、そもそも味わって食べる余裕がない。
仕事もまかないも手際良く準備できるようになるまで何度も怒鳴られた。何度も何度も怒鳴られるものだからわかったことがある。納得したときには一人吹き出しちゃったんやけど、人ってきっと否定され続けると思考を放棄しちゃう生き物なんや。DV被害にあっても依存から抜け出せない奥様の気持ちに似てるかも、もしくはブラック企業で働く社員特有の責任感かも。まああんまり料理には関係のないことやけど、最近では文句を言われることも少なくなった。
「お前ぐらいになったらもう味噌汁作ったらダメやで。端回してもらってあら炊きぐらいこしらえんと」
「はい」
生け簀の鯛がぼくを見ている、気がする。今度ははっきりと目線がぼくに向けられている気がするんやけど、見つめ返す気力が湧いてこないんはチクリと刺されたサボり癖を見透かされてしまったようでバツが悪いから。あんまり見んといてほしい、ぼくらはまだ友達じゃないやろう。
「ご馳走さん。ほな、帰ろうか」
おやっさんは食べるのが早い。少食やから。だから兄さん連中もぼくもおやっさんが食べ終えるまでに胃に放り込める量の米しか茶碗によそわんのやけど、炊いてから時間が経って黄ばんだ固いごはんやから噛むにも飲み込むにもコツがいる。板長であるおやっさんを待たせることなんてできないし、それにおやっさんは板前が味見をすることを嫌っとるからぼくはいつでも腹が減ったままの痩せっぽっち。味見は煮方の仕事で、最後の詰めがおやっさん。この前なんてお腹が空き過ぎてチャンバでこっそり水物とか甘味もののケーキをつまみ食いしとったのがバレて親の仇なの? ってぐらい兄さんに怒鳴りつけられた。まだ微妙に口をもぐもぐさせてたぼくも悪いけど、気がつくかな普通。
ご馳走さんの一言で一斉に立ち上がり慌ただしく片付けを終える。時間が本当にぜんぜん足りない、というか人手がぜんぜん足りないしお腹もぜんぜん膨れてない。今どき日本料理の板前になろうなんて奇特な奴がそもそも現れないことと、例え現れたとしてもすぐに辞めちゃうからいつまで経ってもぼくが一番の下っ端。でもやってることは十年選手。まだ二年しか経ってないけど下っ端の追い回しと盛り付けの八寸場と、それに焼き場と揚げ場もぼくの担当なんやから割合が完全におかしい、異常。でも今日は早く終わったからいつもより眠れそう。料理人になってからは朝六時から夜の十時まで働きっぱなし。休みは半年前に一度もらっただけなんやからせめて、少しだけでも自由がほしい。
まっすぐ部屋に帰ることはまずない。社員寮は誰かが誰かに依存し他人の人生に感傷し介入しようとする人間に都合のいい作りになっている。だからここにもぼくの居場所はない。
自室には生活を彩るものがなにも無い。キッチンの蛇口を捻ったこともないし、冷蔵庫と布団とが心細い距離感で互いを牽制しあっているよう。見たことはないんやけどきっと刑務所よりもなにもない。でもたまに疲れて部屋に帰ると彼女がいてくれることがある。
「遅くまで大変だね」退屈そうに待ってくれていたのかと考えると真っ直ぐに部屋に帰ればよかったなと申し訳ない気持ち。あと、いじらしくてかわいいし、いい子だなと胸が熱くなることある。二週間前に来てくれたときは、「本当いつ来てもなにもないね」って退屈そうにしてたけれど。今夜は小さなテレビとDVDプレイヤーを持ち込んで過ごしていたから笑ってしまった。きっと彼女はぼくなんかよりもずっと逞しい。ついでのように電気ケトルとインスタントコーヒー、それにマグカップをふたつプレゼントしてくれた。「ごめん、テーブルは忘れてたよ」
もしかしてここも水槽なんかも。そう思ったのはフローリングの床に直接マグカップを置いて隣り合ってコーヒーをすすっていた時のこと。彼女がレンタルショップで借りてきてくれた映画を見ていた時のことで、途中まではちゃんと見てたんやけど、行為が始まってしまったら保留になった。
かなり大きな声を出す彼女の口を塞ぎながらセックスをして、しっとりと全身が濡れたような彼女を腕枕で寝かしつけてから、ぼんやりとしたタイミングでもう一度考えてみた。深海から空を仰ぐ魚ってどんな気持ちなんやろうだとか、水槽から見上げるあいつは蛍光灯の光を太陽と錯覚してるんかなだとか。あとは魚は孤独を感じるんかなとか、つまりはそんなこと。
元々、誰かと一緒にいることが得意じゃなかった。一緒に食事をとることもそうで、自分が食べるところを見られるのも嫌だったし、見るのも好きじゃない。人間の三代欲求のうち睡眠欲や性欲が社会生活では隠されて恥ずべきことだと槍玉に上げられることが多いけれど、ぼくにとっては食欲もそう。「何かを食べることを想像している人間」と「性欲を満たすために舌舐めずりしながら異性を眺めている人間」ってきっとそんなに大差ない気がする。気がするだけでご飯も食べるしセックスもするんやから。だからたぶんぼくには自身に対しての羞恥心がないんやと思う。壊滅的に。
「もう寝た?」
「寝そう」
ぼくの腕のなかでまどろんでいる彼女は、幸せだー、とささやいた途端に寝息をたてはじめた。
もう少しだけ起きていてほしい気がしたけど、幼い横顔を眺めながら背中をぽんぽんと叩いていると、「魚も愛しさを感じたりするんかなあ」なんて、聞いてみたところで返ってくる返事は予想もつくようなありきたりでつまらないことなんだしと諦めた。
ぼくの頭は日を追うごとに退化していく。
ぼくの身体は日を追うごとに劣化していく。
歩き出すために右足を出せば左足が出るように、とても自然に湧き出てくる漠然とした不安でたまらない夜がある。子供が積み木で城を作るように積み上げた論理を、すべて崩してしまった先にこそ感覚がある。そんな気がする。そうして、感覚を頼りにしてしまう人種に向けた自分自身の感情に対しての苛立ちと焦燥感がある。
彼女にとってぼくは二度目の恋人で、初めてを捧げた大人の男らしい。だから耐えられるんかもしれん。普通の男女の付き合い方をまるで実践できていないぼくに、メールも電話もろくにできないぼくに。一人きりでぼくの帰りを待つ時間。彼女はなにを思ってなにを感じてなにを見つめてなにを考えながら待っていてくれているんやろ。
おうまがどきに冷たい雨が降っている。おうまがどき、オウマガドキ、逢魔ヶ時。なんやろうぼくのなかの中学二年生が反応する。別名は夕暮れ、他にはなにがあるんやろうって包丁を動かしながら考えたら大根の桂むきがスルスルまな板の上にたたまれていって黄昏時、薄暮時、宵の口。確かひともしころもあった気がするなあ。
とにかく火点す頃に雨が降っているはず。とびきり冷たいやつ。でも本当のところは朝から調理場で目の前の食材に向き合っている限りは外の様子なんてわからないしね。これはぼくの頭のなかの想像でしかないんやけど、雨が降っていてくれたらいいなとは思う。そう、とびきり冷たいやつ。
「仕事の話は終わりにしてさ、どう? 娘とはうまくいってる?」
年棒交渉のために一年に一度呼ばれる社長室で予定調和のまま契約書にサインを書いた。質素、倹約が叫ばれているホテルとは思えないほどに煌びやかな部屋。廊下の照明ひとつでさえ目の敵にしている彼の表情は、張り付いて取れなくなった能面のような笑顔を思わせて苦手。それに、娘ってなんのことやろう。
「娘さん、ですか?」聞き返してみた。
「君がいま付き合ってる女性は私の娘だよ」そう言い終えて大袈裟にため息をついた社長はソファの背もたれに倒れ込み、やっぱり言ってなかったか、と笑った。今まで遠巻きに見た分も合わせて、笑顔のままで喜怒哀楽をすべて見せてくれるんかと思った。
先日夕暮れ時に社員寮に入っていく社長の娘の姿を室長が発見したらしい。どこへ行くのかとこっそり後をつけてみるとぼくの部屋に入っていったのだと、つまりそういうこと。彼女には合鍵を渡してあるのだから、この前に待ってくれていた時のことやろうと思う。逢魔ヶ時とはよくいったもので、たぶんこの場合はぼくが魔物。社長にとってというより、ひとりの男親にとって。
「そういえば目元がよく似てますね」
「うん、目に入れても痛くないかわいい一人娘なんだよ」
別段、交際を反対されたわけでもない。部屋を出るときには見送ってくれて、大切にしてあげてほしい。そう笑顔でぼくの背中二回叩いていた。
刃物のなかで日本刀の切れ味を現代でも世襲しているのは和包丁だけだといつか二番の兄さんが話してくれたことを思い出す。薄刃、出刃、柳刃。ぼくの持っている三種類の和包丁のなかで柳刃包丁が一番きれい。機能美ってある。春の季節がぼくらの方向性を形作って、夏に熱く熱さられた鉄のようにドロドロになって型に流し込まれていくのだとしたら秋には固まってぼくらの形が出来上がるはずで、そうして、ぼくらはきっと形成途中のまま冬を迎えた。そんな風に、工程や手入れを怠ればすぐに使いものにならずに錆びついてしまう和包丁にぼくらの関係を重ね合わせてみる。外は雨。それもとびきりに冷たい。そうであれば、突然連絡がつかなくなった彼女のことにも納得ができる気がしていた。
「氷鉢を下げてくださーい」
すいませえーん下げてくださーい、ともう一度中居さんが大きな声で指示をくれたので竹松と呼ばれる座敷の個室に氷鉢を回収しにいった。大きな氷柱を削ってお造りの器にしたものだから女性には重すぎるし、それに白衣を着た板前が挨拶にくるとウケがいい。基本的にはお礼を言われるし、たまに心付けもくれるから好きな仕事。
襖を開けるとご年配の男女が二人向かい合って座っていて、いつまでも柔らかい笑みを絶やさないまま一瞥もくれない男と、ぼくと目が合ったタイミングで歪ませた表情を隠そうともしない女が視線を切ってうつむく。
「ねえ、板前さん」女性が顔をあげて今度はまっすぐにぼくの目を見る。なんやろう既視感がある。どこかで見たことのある目で思い出せんけどバツが悪くて逃げ出したくなってしまう表情と声色。ちょっと怖い。
「あのね、板前さん。私たちは今日この店の懐石料理を楽しみにしてきたの。主人の定年祝いでね。お疲れさまでした、今まで私たち家族を養うため守るために一生懸命働いてくれてありがとうって気持ちを込めて、おいしい食事をプレゼントしたくて最高級のプランを頼んだんです」
「それは、おめでとうございます」
「……なんなんですかこの料理は」
もしかしてお礼の言葉かなと思っていたから驚いた。瞳のなかに溜めた涙がつーっと溢れていて一筋から二筋に変わり、最初はおそらく虚しさに震えていた声にも怒気が混じりはじめてしまって、いよいよぼくはどうしたらいいかわからないまま女性の話に頷き続けている。
先付、煮物椀、造りと続いて焼物。氷柱を彫刻用の刀で削り器に成したお造りの受け皿はぼくが作った。よくできたと思ってはいるんやけど下っ端だし修行中だから不格好だったのかもしれんなとも思う。だけど目玉である氷細工の器の上、お造りが気に入らないのだという。煮物もありきたりなものであるし、そもそもがやっぱりお造りのネタが不満だし量が少ないし安っぽいのだという。
もう一度女性を見てみる。ゆっくりと。先程までの悲しみよりも怒りが色濃く反映された表情でぼくを見ている。左手側の男性は、「まあまあ」とでも言いたげに柔和な笑みを崩さずにいるのだからきっと、女性が怒ってくれているこの現状が嬉しいのかもしれん。
結局板場に戻って二番の兄さんに対応してもらったんやけど、こういうときに限って板長のおやっさんは出てこん。
「どうしておやっさんが対応しないんですかね?」と聞くと、板長が出ていくとお客さんに恥をかかせる場合がある。今回がそれや。と二番の兄さんが言う。
「あのお客さんはうちの懐石料理で一番高いコース『葵』を選んで来てくれはったんや。『橘』が六千円で、『葵』は九千円や。二つ並べたらそら違いは見てとれるほどやけどな」
「高いですよね」テリヤキマックセットが五百円か六百円だから、一回の食事にしては何倍も高い。
「普通に考えたらな。でも懐石料理の場合は大したもんは出せん金額やで。ご年配の夫婦やったな、入籍のための親族通しの顔合わせ、子供が生まれてお食い初め。一通り経験してしまえば日本料理の料金は頭んなかで固定される。ちょっとした小料理屋で一人五千円も支払えばウニでもトロでもそれなりのもんは食わしてもらえるからな。あの夫婦は、最高級のプランを頼んだと言うたんやろ? ただ、うちみたいなホテルの和食部門では確かに一番高いけど老舗の料亭になんていってみい、こんな金額では豆腐懐石しか食えん」
そう言いながら二番の兄さんは予定されていた献立の止め碗を、季節の炊き込みごはんを止めて寿司を握り、水菓子のメロンとオレンジを飾り切りで豪勢に盛り付けるのだった。
「おやっさんには内緒やで」
まっすぐに社員寮に戻った。真っ暗な部屋の電気をつける前に念のため「ただいま」と告げてみる。電気をつけてみたけどもちろん誰もいないし、何度携帯を確認してもメールも着信もない。地面にはこの前気晴らしに買ってきてマグカップに差したまんまのキンセンカ。花弁も枯れて茶色く濁って汚らしいけど、なんとなく片付けたくない。レンタルしたDVDケースは床と同化したように控えめに存在感を匂わせている。
「絶対に見て感想聞かせてほしい」そう彼女が言うからあれから何度どなく借りてみたのだけど、結局再生ボタンを押す気力もないままに返却してを繰り返している。
着替えることも面倒で立ち止まったまましばらくぼおーっとしてしまう。なんだかどっと疲れてしまったからこのまま布団に飛び込んでしまいたかったんやけど、次の休みにはやってくるかもしれない彼女に枕が臭いと思われたくないなとか、そもそも次があるんかなとか、ため息のでるような事ばかりが頭に浮かんでくる。振り払うようにぐわーっと気合をいれて風呂場に向かい、熱かったり冷たくなったりを繰り返すシャワーを浴びていると、妙に悲しい気持ちになってきた。
あの夫婦は定年祝いに相応しい料理を期待してた。そうして見事に裏切られた結末にやるせない気持ちになったんやろう。
想像してみる。柔和な笑みの穏やかな男と、哀しい怒りを下っ端の板前にぶつける女のことを。
夫婦で一杯ずつのお酒、男はビールで女は日本酒。普段から飲むタイプじゃないんやろう。泊まりの客やったんかな、いや違うな。服装が浴衣ではなくて私服やったし、宿泊代込みではなくて料理だけを食べにきたから値段に見合ってないと感じたんやろう。男の方は会社員かな、外仕事の男や職人が醸し出す雰囲気ではなかった。定年時期が六十代やとするとバブルの時代は二十代後半から三十の前半で、接待や社員旅行等で懐石料理を食うこともあったやろうに。
そうすると、もしかしたら奥さんのほうがサプライズで旦那をうちに連れてきたんかもしれん。旦那はなにも知らん状態で、優しい妻が連れてきてくれた料理を精一杯楽しむことに決めている。どんな料理が出てきてもさほど問題じゃないのは、妻の気持ちがうれしいからや。私たちと言ってたから結婚して子宝にも恵まれて、年代的には二人以上かも。子供の養育費と夢のマイホームのローンに追われる。
教育方針の違いで夫婦喧嘩も少なくない頃には不景気の煽りを受けた社会情勢に収入は上がらなずにいて、子供の友達の父親と見比べただろう妻の小言も増えてくるのだから益々家に帰るのが遅くなる。大事な仕事だとうそぶいて飲みに出掛けて火遊びにと立ち寄った風俗やキャバクラも一度や二度ではない。昇級も諦め同僚が出世していく様を眺め続けている内に、いつの頃からか身についていた諦めの笑顔と、腹の贅肉。
決して平坦ではなかった道のり。ただ彼は、走りきった。自分の人生は百点ではないにしろ折り合いをつけながら辿り着いた及第点なのだと。定年を迎えたその日、女性社員に花束を渡された時には走馬灯のように思い出が駆け巡ったはずで。そうして、いつもと同じように、いつもと違う帰り道を噛み締めて家に帰る。妻がサプライズを用意してくれていたことを知って今までの苦労が報われた気がした。妻は優しく微笑む、「長い間お疲れ様でした。夫婦二人きりでおいしいご飯を食べにいきましょう。贅沢しよう」と。
タオルで頭を拭きながら部屋に戻ってペットボトルの水を胃のなかに流し込んだ。
女はどうやろう。今日のことを誰かに話すんやろうか。あのホテルの日本料理屋は最低で、しょぼいもんしか出ないんやと拝聴して回るんやろうか。
あの時、もしも板長が頭を下げていたら、あの奥さんの溜飲は少しだけでも下がったかもしれん。だけど、ホテルの懐石料理を最高級プランで九千円も払ったのに大したもんが出なかったと、文句を言ったら謝ってくれたんやと、その話が通じるのは狭い世界のコミュニティだけで運が悪ければクレーマー女だと思われて恥をかいてしまう。年齢を重ね、子育てもひと段落し、酸いも甘いも噛み分けてきたはずだと確信している女の目は、直視できないほど、逃げ出したくなるほどに傲慢な、被害者ゆえの弱者の怒り。
もう一度水を飲む。喉が渇いて渇いて仕方がない。なんで飯を食っただけでこんなに惨めな思いをさせんといけんのやろう。これを惨めだと思うのはきっと、ぼくが板場という水槽の中にいる魚やからかもしれんなと、そう思った。ショボかったかもしれんけど大事な日なんやからせめて、おいしかったとそう感じていえ欲しかった。そうして、今日あったことを、感じたことを彼女に伝えてみたくなった。
だけど、慣れんことを器用にこなせるほど余裕のあるぼくではなかった。頭の中にはぐるぐると伝えたいことが踊るのに、それを伝えるはずの携帯をいくら睨んでみてもぼくの親指は一文字も打ち込めないまま。そのまま三十分もしないうちに睡魔が襲ってくる。夢の中でさえ結局ただの一文字も、打てなかった。
目覚まし時計に起こされてから洗面台の前に立つまでの間一切躊躇しちゃいけんのは、起きられなくなってしまうことだけじゃないってことをぼくは経験上知っとる。二度寝なんてもってのほかで、貴重な睡眠時間を確保するためにギリギリの時間にアラームを鳴らすことで、もうあと五分だけの甘い魔法を唱えなくて済むことと、同時に見たくないこと知りたくないことを考えなくて済む。
窓の向こうで雨音が聞こえて少し憂鬱になっても洗面台の前に立って笑顔を作ることが大切。夜にシャワーを浴びる前と、朝に歯を磨く前に鏡の前でふふーんと笑ってみる。何年間もずっと練習してきたんになんで目が笑わんのやろうって情けない気持ちになってもがんばる。この儀式があればスイッチが入って大抵のことは受け流せるようになるから不思議。「もしかして何年も何十年も何百年でも続けられるのかも知れんね」と、ばっしゃばっしゃ顔を洗って濡れた手で寝癖を治す。いつも通り手強いね。今朝も。
板場までは社員寮から車で五分。白飯と酢飯を別々の鍋で炊いて、水をはった寸胴に昆布を入れて火をつける。次にとシャケを網台に並べながら考えたのは最近は意図せずにたくさんの表情を見てしまったから怖いなって思ったこと。「こわいったらこわいんだよー」って心のなか平仮名で呟いてみても誰も聞いてないし聞かせる気がそもそもない。水槽の中の魚は生きていくことに夢中で口をパクパクさせるだけだけなんやけど、もしあのパクパクがぼくになにかを伝えようと懸命に動かしている類のものなら、今度こそ本当に友達になれるかもしれん。見てみてよ、バイキングの朝食用に甘い卵焼きを作る姿。かんてきを三つも同時に使えるぼくってすごいし偉いやろ。弱者の傲慢さも、強者の謙虚さも怖いけど、本当に一番怖いものがなにかおまえは知っとるか。ぼくは知らん。
「手が遅い! 何しとれん早よこいや!」
刺場の兄さんの怒号が飛んできて、ついでに食材のエビを投げつけられてぼくはこの板前の世界を考える。食べたい人と食べさせたい人がいる世界のことを。もちろん食材に敬意を払わないこの人は論外なんやけど気づいたことがある。
「おやっさんが毎日鯖を三尾捌けて言うたやろ!」
日本料理の世界のことを簡単に話そうと思うんや。
誰に。
決まってるやん。
誰に。
ぼくのことを好きやと言ってくれる彼女にや。
どうして。
伝えたいからや。
どうして。
どうしてやろそんなの考えたこともない。
なんで。
なんでって聞かれても。
わからんのか。
わからん。
わからんのか。
わからん。
わからん。わからんけど彼女とぼくの人生は交差したんやと思う。それが例え一瞬の瞬きで、口に出すと恥ずかしい種類の偽善に満ちた上辺を撫でる煙のようなもんやとしても。彼女はぼくを好きやと、幸せだと言った。
利き腕ってあるやろ。腕の右利き、足の左利き、目の右利き、耳の。そう、左右についてる器官。
それでぼく思うんや。心臓は片方にしかついてない。これがもはや欠陥の最たるものなんやなって魚を捌く時に思い出すんや。ぼくはどうして人を好きになるんかなって考えて、「顔かな、たしかにぼく面食いやしな、いや身体かもしれん、抱いてると気持ちがいいし。いやでもぼく、好きになったらその人のヨダレも飲みたくなるしな。ついでに言うと心臓も欲しいわ。左右対称にしたい。ダメダメ、こわいこわい引かれる」
血抜きで身割れせんようにやさしく腹を抑えてエラからこめかみに向けて包丁の先端を入れる。酷く跳ねる。背びれが左手の人差し指に刺さって血が出てしまったから水で洗って手早くサランラップをぐるぐるに巻きながら眺めるのはゆっくり動かなくなっていく魚。シンクの中からぼくを見上げていて、薄情かもしれんけどようやく思い出す。「こいつぼくの友達になれるかも知れんかった奴や忘れとった」ぼそっと口に出してみる。
「あのね、この世界は食べたい人と食べさせたい人がいて成り立っとるんや。言わば欲望の最終地点やね。やっぱりぼく性欲と似とるって思うよ。でも差別化されとるのは吐き出したいやつと受け入れたいやつがおることかね。たまに思うんや、ぼく。受け入れてほしいし押し付けたいと心が動いて、包み込んで迎えてあげたい、その代わり特別にしてほしいとねだる人がおる。身体の構造が違うからかと思ってたけどそんなに簡単なもんじゃないのかもしれんね」
背中から怒鳴り声がする。刺場の兄さんが食材を投げつけてくるかなと思ってたらオタマが飛んできた。さっさと終わらせて手伝いに来いとかなんとか叫びながらおかんむり。こわい人。
「あの刺場の兄さんは家に帰ってから包丁ひとつ握らんらしい。もちろん心情的にはわかるんや。考えてもみい。仕事で年がら年中料理作ってお客さん喜ばしてるんやから、家に帰ってから家族に手料理作るなんてことはプライベートとビジネスの線引きがわからんくなるやろ?」
おいこら、シカトできるほど偉くなったんかいい身分やな。と兄さん。
「でも、みんなどうやって折り合いをつけとるんやろうね。最初はみんなそれぞれの大事な人においしいって言ってもらいたくて包丁を握ったんやと思うんや。親とか兄弟とか恋人とか友達とか。おもしろいよね。配偶者ならば日々の惰性で。恋人ならば愛情で。友達ならば好意で。関係性が深まるに連れて日常に溶けていく特別だったはずの欲望。ぼくは、いつからか対価がないと動けんようになった」
空っぽになった水槽を見る。いつもはぶくぶく音を立ててる消える丸っこい空気の泡の水中ポンプも電源を落とされてる。そう、ここにこいつがいた。ぼくの唯一の理解者になれたかもしれんやつ。さよなら、せめておいしくするよ昆布締めで。バイバイ。
<今から行っていい?>と彼女からメールがきて、<いいよー>と返事をした。半月ぶりの連絡だったから、正直もうぼくの前に姿を見せんのかもと思ってた。彼女は電話が苦手でぼくはメールが苦手。だからぼくらの連絡はいつも次に会う日の約束をするためだけの最低限で終わる。
二十三時に部屋に上がり込んできた彼女に、「ごめんぼくまだ見てない」って伝えて二人で映画を見た。途中で行為が始まってしまいそうになったけど断ったのは彼女が珍しいことを口にしたから。「キスマークつけてほしい」って言う。
「つけたことない」と苦笑した。「つけ方もわかんないよ」
「つけたことないんだ」
「うん、あと昨日ちょっと変な夢見たから元気ないかも」
「どんな夢?」
「君、夢のなかで浮気してたぼくビックリしたよ」
「なにそれ」と彼女が笑う。「それでどうしたの?」
「謝ったよ。さみしくさせてごめんねって。あと浮気相手にも、この子が本当に好きなのはぼくだけだよ、ごめんねって」
たまにはコーヒー淹れてきてあげる。そう伝えてキッチンに向かう。マグカップを二つ手に取って戻ってきたときには彼女が泣いていたから、「だいじょうぶだいじょうぶ」って抱っこしてから頭を撫でて慰めた。「映画見ようよ」
彼女の好きな映画なんだから、彼女がどんな風に感想を語るのかを聞きたかった。ふふーんって笑ってみせるとふへへって彼女も笑う。綺麗な黒髪が濡れた頬に張り付いてて今にも口に入りそう。ぼくのなかで一番柔らかい指はどれだろうって考えながら結局親指と人差し指で摘んだ。
『昔、ある王様がパーティを開き国中の美しい女性が集まった。護衛の兵士が王女の通るのを見てあまりの美しさに恋に落ちた。だけど彼女と兵士では身分が違う。それでも諦めきれずに兵士は王女に詰め寄ってこう言った。
『あなたなしでは生きていけない』
彼女は兵士のまっすぐな目に驚いて告げる。『百日間、昼も夜も私のバルコニーの下で待っていてくれたらあなたのものになりましょう』
兵士は待つ。二日、十日、二十日。毎晩決まって彼女が覗くが兵士は微動だにしない。雨の日も雪の日も鳥が糞をしても蜂が刺しても名もなき兵士は動かない。九十日が過ぎた頃、兵士は干からびて真っ白になっていて目からは涙が滴り落ちる。涙を抑える気力もなかった。彼女はずっと見守っている。
九十九日目の夜、兵士は立ち上がってその場を去った。二度と戻って来なかった』
映画が終わってもう随分眠かったけど、お互いが同じタイミングで冷めてしまったコーヒーをすすっているのを確認できてちょっと癒された。
「どう思う?」って聞かれてぼくはしばらく考えてみる。ベランダに行ってタバコが吸いたいんやけど、我慢。きっと今夜は特別な日になる。ぼくは忘れないけど、彼女はすぐに忘れるはずで、そういうことってある。きっと逆も沢山あるはずで、あってほしいなって思う。
「愛してるって。言い続けたかったんやと思ったよ」
「……ん?」
「愛してた。じゃなくて、愛してる。この先の王女の人生はきっと長いけど、バルコニーからずっと見守っててくれんやから。ほら、影送りみたいな残影としてでも忘れてほしくなかったんじゃないんかな。身分も違うから兵士と一緒になっても幸せにさせてあげられん」
終わりたくなかったんやろうと、そう思った。だけどこれは言わないことにした。ね、愛されたい愛されたいって脅迫まがいに待つなんて、どら焼きみたいに甘いけど腐臭がするやん。成就してもしなくてもいつか終わるなんておもしろいよね。と、これも言わないことにする。
「きっと、王女はさ」と彼女。「耐えたい人だったんだよ」
「うん」
「耐えられる人だって、私は強いって。そう思ってたんだよ」
「うん」
「自分のこと、強いって思ってたんだよ」そう言って泣き出した彼女は、ぐええって変な泣き方をする。かわいい人。綺麗な人やなあって思う。
「ごめん。わたしは弱かった」
うん、いいよ。他のごはんが食べたくなっただけなんやよねって心の中で呟いて、「だいじょうぶだいじょうぶ」ってまた頭を撫でた。大丈夫やよ、一年半もありがとね。そう言いたかったけど言葉にしないほうがいいこともある。気付かなかったぼくが悪いってそう思うよ。きっとすべてが足りなかったから気がつかんかった。想像してた未来のぼくらはきっともっとかっこよかったはずやから、泣かせてしまってごめんって、そう思うんや。大丈夫やよ、泣かんでいいよ、大丈夫。
ダイレクトメールを掻き出して彼女からの手紙に気がついたのは別れてから一ヶ月経ってからで、ポストを開ける習慣がなかったから本当はもっと前から届いてたのかもしれんなと思った。
封筒のなかには合鍵と一緒に、沢山の思い出を綴られている手紙。ありがとうって何回も書かれていて、何回かふふーんって笑わなくちゃいけないタイミングがあって、嬉しかった。きっと彼女は水槽から抜け出せた魚だから「逃げて逃げて」って、「でも少しだけでも覚えててね」って切ない気持ち。彼女にとってはすぐに消したい過去になるんにね。
パサっと封筒から落ちてきたのは黄色いキンセンカの押し花で作った栞。裏面には『忘れないよ。あなたが好きだったお花』と書かれていた。
「違う」そう囁いて俯いて、社員寮の玄関口で動けんくなった。
「君の誕生花やったから」
これはきっと、声にならんかった。
お肉かお酒買いたいです
