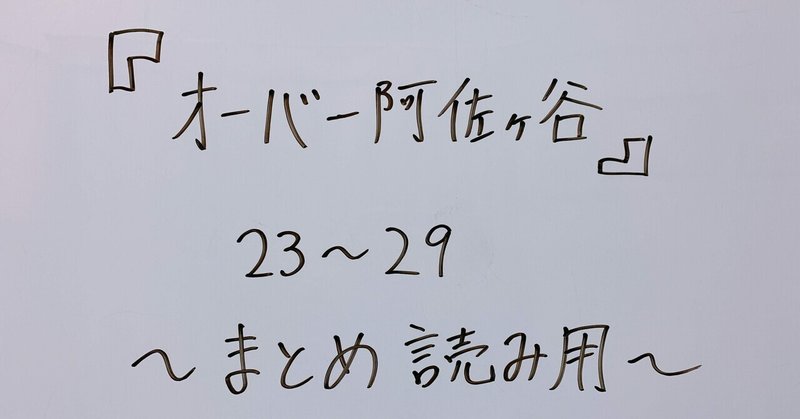
『オーバー阿佐ヶ谷』23〜29(まとめ読み用)
23.
通夜は環七にほど近い高円寺の寺で行われていた。私はそこまで歩いて行った。最近、生活の全てが阿佐ヶ谷から前後二駅で済んでしまっている。これが”中央線の呪い”というやつなのだろうか。一度、沼にハマると抜け出せなくなる。もがけばもがく奴ほどよく沈む。最後に渋谷のクラブでライブをしたのは一体いつだったのか、それすらもう思い出せなかった。
寺への道すがら、喪服姿の人間とすれ違う。意外と人が多かった。こうして偲ばれているところを見ると、界隈ではそれなりに有名人だったのかもしれない。あの呑んだくれのセクハラ演出家も。
寺の門柱にもたれるようにして、真妃奈が待っていた。先程のTシャツ姿とは違い、黒いシックなドレス様の喪服を着ている。首元には小振りなパールが光る。さすがは女優の卵。金のかけどころを知っている女だ、と思った。
「Yo,Wassup!」
「え?喪服とか着てこないんですか?」と真妃奈は言った。
私は自分を見下ろした。赤のジップアップパーカーがそこにはあった。背中にはSnoop doggの顔がプリントされている。2PACやnotorious BIGを見送った今やラップ界のレジェンドが。
「要は気持ちの問題だからね。忌野清志郎の葬儀に革ジャンで弔辞を読んだ甲本ヒロトみたいなものさ」
「まぁなんでも良いですけど、焼香の時は少しワタシから離れてくださいね」
寺の中では念仏と木魚のリズムがいい具合にグルーヴしていた。飛び入りでフリースタイルをかましたい欲を辛うじて抑えた。普通、親族が座る席には誰もいなかった。空のパイプ椅子が涙を誘った。
「弔問客の中に座長さんって人はいた?」と真妃奈に尋ねる。
「人が見てるとこで話しかけないでもらって良いですか?」
寺中の人間は皆、私の赤いジップアップパーカーに夢中だった。機嫌の悪い闘牛のように。
焼香の列に並ぶ。真妃奈は私より三人後ろに並んだ。仏花に囲まれて演出家は眠っていた。この世の最期に用意された舞台にて。遺影は今よりだいぶ若い頃のものを使っているらしい。あまり馴染みのない顔がそこにはあった。
前の人間の真似をすることで焼香をやり過ごした。作法に気を取られるあまり、哀悼の気持ちはどこかへ飛んでしまっていた。
*
入り口の傍に設られた灰皿のところで煙草を吸っていると、焼香を終えた真妃奈がやってきた。
「主催の顔見せて貰ったんですけど、人間、死ぬとなんか一回りくらい小さくなりますよね」
「魂が抜けるせいだろうな」
「いつかワタシも本当に死ぬ日が来るんだろうか。今はまだそんなこととても信じられない」
真妃奈は自分の手のひらを見つめた。生命線の残りでも確かめるように。
「あぁ。そいつがどんなに年若く、張りのある胸と股の間に光るパールを隠し持っていたとしても、死ぬ時は、そう。死ぬ」
「捻くれた寺の小坊主みたいなこと言ってる。馬龍丑。さんって一体何者なんですか?」
「何者に見える?」
「あなたと合コンごっこをするつもりはありませんよ。で?」
「RAPするラッパ吹きでもの書き」
「情報量、多っ!」
「そして、金も地位も名誉も名声も時間的自由も全部欲しい」
「一聞いて十返ってきた!」真妃奈は指折り数えた。でも、どう数えても”八”止まりだった。それはそれで末広がりで悪くはなかった。「強欲で傲慢なんだ、ということだけは分かりました!」
ーーーそれは良かったな。
「ただ、”ありあまる富”なんて自分には持てない、と思って諦める方が己の人生に対して傲慢だと思うけどね」と私は言った。
24.
燃えていく煙草は灰を落とすよりも早く風に散らされていった。私が煙草を揉み消すと同時に「あっちの部屋でお寿司食べていきましょ、お寿司」と真妃奈が言った。ここはディズニーランドかと錯覚するようなはしゃぎぶりだった。チュロス。
「来る前にピザ食ったから大丈夫」
「え、でも。お寿司ですよ?」
ーーー寿司は全てに勝る、とでも言いたげだった。
「生魚食うとお腹壊すタイプの遺伝子らしいんだ、おれ」語尾を柔らかく保つ為にひらがなで言った。
「まるで劣勢遺伝の塊みたい」
反論する術はなかった。
私がここに来たのは、なにも寿司を食う為でも、焼香をして最後の別れを惜しむ為じゃない。そんなことはバーの片隅でやればいい。そっちの方が随分とあの演出家には相応しいのだから。
「ところで、座長って奴はいたか?」
「どうやら見当たりませんねー。来ないのかなー。あっ」真妃奈の見回していた首が止まった。「芸能人だっ!」
真妃奈の指差す方向に目をやると、男がタクシーから降りてくるところだった。長身、細身の体型に張り付くようなスリムな喪服に、淡い色のサングラス。全体的にスタイリッシュ。ただ、メッシュ状に染めた茶髪がこの男が一昔前の世代に属することを示していた。
私のすぐ脇を男は風のように通り抜けていった。アフターシェーブローションとコロンの入り混じった匂いを残して。
「ねぇ!見ました?今の!」と真妃奈は言った。「やっぱ佇まいが渋いなぁ。あとでサイン貰っちゃおうかなー」
私は頭の中で今見た男の顔を反芻していた。真妃奈の考えていることとは別の意味で。草の中に混じった石ころのような遺物感を覚える。それは演出家から「怪物を見たうちの一人」として名前を挙げられていた俳優だった。通夜に顔を出した当初の目論見より良い当たりくじを引いたような気分だった。私は男が焼香を終えるのを待つことにした。
お寿司お寿司お寿司が食べたい、と喚く真妃奈をなだめながら男が出てくるのを待った。時間にして五分ほど。寿司屋ですらこれほど聞くことはないだろうと思うほどの『寿司』という単語を耳にし続け、その許容量が一日の限界値を超え、思考がオーバードーズし始めた頃、男は寺の中から出てきた。
「Hey!What’s up men!」
私は男の背中に声を掛けた。
「うわっ!バカ!やめなさい」
真妃奈は私のパーカーのフードを引っ張った。
俳優はこちらを振り返り、その頭の中の人名リストを辿っていた。でも、どこにも記載がないようだった。それはそうだ。初対面なのだから。怪物を媒介とした邂逅。
周りにいる人間達が遠巻きにそれとなしにこちらを意識している。これが一流芸能人の持てるオーラだろうか。これこそが怪物によって与えられた力なのか?もしくは葬儀の席に赤いパーカーで現れた、常識はずれのラッパー風情に絡まれる有名人を痛ましく思っているのかもしれない。
「何か?」と俳優は言った。当然の反応だった。
「サインなら、こんな場ですから控えてもらえませんか?」と横にいたマネージャーらしき男に制された。
「怪物の話を聞きにきたんだ」
「怪物?」と俳優は言った。
「そう。あんたのよく知っている怪物の話を」
「この人、タップするホラ吹きのボロ雑巾なんです!」真妃奈が割り込んできて慌てたように付け加える。
一つとして合ってなかったが、あながち間違いでもなかった。
*
俳優は我々二人を交互に眺めた。
「ここでは何ですからーーー」俳優はひとしきり頷いた。「ーーーいいバーがあるんです。お二人共ご一緒いかがですか?」
我々はタクシーに乗り込んだ。
25.
招待されたバーは西麻布のメインストリートからは外れた住宅街の一角にあった。会員制らしいが会員でもなければまずバーだとは分からない造りをしている。そう、全身で場末の飲み屋感を出している『ソルト・ピーナッツ』とは大違いだった。
隣り合った人間の顔が辛うじて分かるくらいに抑えられた照明。壁に備え付けられたライトは自動で回転を繰り返す仕組みのようで、ゆっくりと店内の有りようを照らしていく。
静かに流れるピアノの調べ。注意して聴くと、とても良いメロディだと思うのだが、二秒後には靄となって思い出そうにも辿れないような種類のメロディ。まさにキングオブBGM。
バーテンダーはきちんと正装をしている。赤のネクタイに黒いベスト。頭蓋骨に沿うように撫でつけられた髪の毛。これ以上ないくらいバーテンダーだった。
店内を見回しながら「わぁー。オシャレ〜」と真妃奈は言った。確かにデートの最後に連れてこられるバーとしては完璧だった。この後に辿り着くところは一つしかない。とはいえ、
ーーーこいつはここに来た意味を分かっているのか?不安だ。
芸能人と飲みに来た訳じゃないんだぞ、と小声で釘を刺す。
並べられたウィスキー瓶を可動式の間接照明が照らしていく。光が当たる度、鈍く光る琥珀の液体は美しい。オシャレ〜、と思った。
我々は俳優を間に挟んでカウンターに座った。各々の飲み物を注文し終わると、「主催に」と俳優は言った。「ウィスキーのストレートを」
酒が来るまでの間に改めて自己紹介の時間があった。俳優は小牧亨(こまき・とおる)といった。この度の通夜のメインアクトだった演出家の主催する阿佐ヶ谷の小劇団【演劇集団 暗愚裸座】にかつて所属しており、十七年ほど前にそこを辞め、紆余曲折あって今はテレビや映画などの映像の仕事をメインにしているそうだ。真妃奈曰く、「なんであんたそんなことも知らないのよ」らしい。
ソルティドッグとマティーニとアプリコットオレンジがカウンターに揃った。誰もいない席に誰も口のつけないウィスキーが置かれた。
「主催の繋げてくれた縁に」俳優はグラスを掲げた。「献杯」
掲げられた三つのグラスを可動式のライトが順に照らし、カウンターに置かれたウィスキーグラスのところで一旦停止した。全てが演出された賜物のような気がして気持ち悪かった。
各々、沈黙を噛み締めるようにしてグラスを口元に近づけた。酒の味はーーー。阿佐ヶ谷のみならず中央・総武線沿線のどの駅で飲む酒より酒だった。各酒造メーカーは中央・総武線と西麻布では下ろす酒の等級を変えているのかもしれない。そう思えるほどに酒が酒だった。ーーーそれ以上、私には判断出来かねた。
皆のグラスが空になり、ウィスキーグラスに注がれた0.0数%が蒸発した頃、リニアモーターカーのような滑らかさで俳優が口を開いた。
「では、本題といきましょうか」
私はバッグに忍ばせておいたアイスバーグ・スリム『PIMP』を取り出し、真ん中あたりのページを開いた。そこには黒い四本の毛が挟まっていた。ーーー増えていたら面白いのに、と思ったがその数はきっちり四本だった。
「なにそれ。汚い」と真妃奈は言った。
久々に見たそれは確かに益々、陰毛感に拍車が掛かっていた。
26.
「見覚えあるかい?」
私は毛の一本を摘んで、小牧の前にかざした。可動式のライトがゆっくり毛を照らし、小牧のその端正な横顔を照らした。
小牧は毛を受け取り、興味深そうに眺めてから「これは…なんでしょうね」と言った。
「分かってんだろ?俺が怪物からむしり取った体毛だよ」
小牧の奥から身を乗り出し、「小牧さん、困ってるじゃない!ちゃんと説明してあげてよ。そもそもワタシもその怪物のことなんてよく知らないし」と真妃奈は言った。ーーーこいつは一体、誰の味方なのだろう。少なくとも私ではないことは確かだった。
*
{仕方がないので、ことのあらましを説明した。今更もう一度書くのは面倒くさいので省く。各々、勝手に最初の方を読み返してくれやがれ}
*
「なんとも興味深い話ですね」と小牧は言った。
「教えてくれよ。あの怪物は一体なんなんだ。ーーーそれともこのまま知らぬ存ぜぬを通すつもりか?」
小牧は深くてのんびりとした溜め息をついた。もしその口にトランペットのマウスピースを当てがってやればLow-F♯ が出そうな息遣いだった。
「なんで僕がここまで有名になったか分かりますか?阿佐ヶ谷の小劇団の売れない役者だったこの僕が」
「怪物に会ったからじゃないのか?言ったんだろ?『俺を救ってください』って」
小牧は微笑した。それは女を戸惑わせる種類の淡いものだった。
「ーーーそれとも才能があったから、とでも言いたいのか」
「逆ですよ」小牧は微笑んだ。それは女をたらし込む時のそれだった。私は今宵このまま抱かれてしまうのだろうか。ーーー最悪、3Pならアリだなと思った。「自分に才能がないことをきちんと自覚出来ていたなら、他人の話を素直に聞ける。独りよがりにならずに、ね。才能なんてあればあるだけ邪魔なだけなんですよ。ーーーでも、それを認めることが一番難しい」
小牧の横で真妃奈が盛んに頷いている。釈迦の説法を聞く弟子みたいな姿勢で。
「小牧さん、今日はあんたの芸論を聴く会じゃないんだよ。そんなこと自分の講演会でやりやがれマザファカ」
「あぁ申し訳ない。僕も歳なのかな」と笑った。
小牧はバーテンダーに目で合図を送った。バーテンダーは仕事を始めた。よく調教された牧羊犬みたいに。
新しい酒が三つ届いた。ジントニック、ドライマティーニ、カルーアミルク。真妃奈の奥の席のウィスキーグラスが下げられ、そこには代わりにビールが置かれた。
「で、会ったのか?怪物に」
「会いましたよ。もちろん」
意外、というかあっさり認めた。その答えが来るとは思っていなかったので、私はジントニックを噴き出した。
「ーーー会ったの?」
「えぇ」
「阿佐ヶ谷の小劇団を辞めたっていう十七年前に?」と真妃奈が付け加えた。
「そうですね。あれはーーー」
小牧亨の一人語りが始まった。私と真妃奈は【小牧亨ひとり芝居】と題された舞台を眺める形となった。
27.
【小牧亨の場合①】
ーーーなんで僕は認められないんだろう。こんなにも努力して、こんなにも夢の為に全てを捧げて、こんなにもーーー。
月の綺麗な夜だった。僕の心とは真反対で、空には雲ひとつなく頭上には満月がただ浮いているだけ。銀色に光る表面は魔女の横顔のように怪しく、臼を撞く兎のように寓話的だった。
ーーー”何者か”になれない人生、コンビニでレジ打つだけの人生、舞台袖で主役を眺め続ける人生。
世界に、というか宇宙に一つしかない月を想うと、激しい嫉妬に駆られる。僕だってオンリーワンの人間になりたい。他の役者に代替が効かないような、「あなたじゃなきゃ駄目なんです」って言われるような、そんな俳優に。
ーーー舞台に立ち、観客の目が一斉に自分を見ているという愉悦を知ってしまった人間は、辞めたその後に続く静かな人生を耐え切れるのだろうか。
今日も主催を怒らせてしまった。なにより主催は、僕の演技というより僕自身のことが気に入らないみたいだ。やれ「台詞の言い回しが違う」から始まって「感情の」だの「姿勢が」だの、終いには髪型や服装のことまで。ことあるごとにいびられて、もうウンザリだ。僕はただ芝居をやりたいだけなのに、人間関係にまで気を回して疲弊して。いや、そもそもがもう古いんだ、考え方も演出方法も何もかも。あんな時代遅れの演劇論にはもうついてはいけない。こんなところで燻っている暇なんてないのに。親からは三十までに芽が出なければ帰ってきて家業を継げ、と言われている。三十歳まではあと二年。二年か。あと二年で何が出来る?
ーーー与えられる配役は僕の特性から大きく外れるものばかりで、得意な長所は何一つ活かせず終い。このままで終わっていいのか?それで満足なのか?僕は。
頭の中にはあらゆる可能性が散らばって渦を巻いている。それは川に落ちた木片のように、浮かんだり沈んだりを繰り返しながら誰かの手で拾われるのを待っている。英雄を孕んだ桃みたいに。
ーーー流れ去ってしまったものはもう二度と同じ川の流れには戻ってこない。だから早く、一刻も早く、掴み取らなければ。
僕は川辺に立ち、その木片の一つに手を伸ばす。水は冷たく、指先に刺すような痛みを覚える。拾い上げたそれは水を含んで重く、色も澱んでいたけれど、この”僕”がずっとずっと求めていたものだった。
ーーー今ならまだ間に合う。他の劇団に移ろう。僕の役者人生最後のチャレンジとして、有名な劇団のオーディションを片っ端から受けまくるというのもありかもしれない。
酒が足をもつれさせる。『ソルト・ピーナッツ』で飲んだ正体不明の酒がだいぶ廻ってるみたいだ。心拍数は普段の倍くらいあって、やけに喉が渇く。自分の中の血が沸騰して蒸発していくような感じだが、それは無性に心地が良かった。
28.
【小牧亨の場合②】
当時の僕のアパートは南阿佐ヶ谷にあって、『ソルト・ピーナッツ』から自宅へと帰る為には高架下をくぐる必要があった。ちょうどその曲がり角に差し掛かる時、僕は一人の娼婦と出くわした。戦後の闇市から抜け出てきたような出立ちの老娼婦と。
その女は界隈では有名な立ちんぼだった。夜な夜な阿佐ヶ谷のあちこちに出没しては一晩の飲み代程度で体を売る、と噂の。そういう人に付き物の「国に帰ったG.Iだか将校だかを今も待ち続けている」とか「実は各界の著名人を客に待つ」とか「友達の友達が梅毒をうつされた」とか、そういった清濁入り混じった伝説を目一杯に羽織って。
声を掛けられた訳じゃない。青白い街灯の下、娼婦はただじっとそこに立っていた。裸足に履いたパンプスから小指が突き出ていたことを今も覚えている。風でめくれたオーバーコートの隙間から見える足は細く、白く、喩えるなら地に生えた二本のネギみたいだった。ーーーこんな人を買う人間がいるんだろうか、少なくともその瞬間まではそう思っていたよ。
ーーー魔が差したのかもしれない。別に女に飢えていた訳じゃないことは確かだ。飢えていたとしても、だ。あれはそう、魔が差したとしか言えないな。
僕は財布の中の金の半分を使って、その娼婦を自宅に連れて帰った。道すがら、どちらも口を開かなかった。無言で歩く僕らの上を中杉通りの紅葉した並木だけが寒風に揺られ、ざわめいていた。
ーーー軽蔑するかい?それとも少しは同情してもらえるかな。その夜は寒く、お互い独りで過ごすには厳し過ぎたんだ。
*
無言で鍵を開け、無言でシャワーを浴びるように指示し、無言で抱いた。あれは僕の女性遍歴の中でも一番奇妙なセックスだったな。今思い出しても、背筋が鳥肌立ち、尻のあたりが強く内側に引き込まれるような感覚があるよ。
気持ち良くはなく、興奮もしていない。だけど、勃つには勃っていた。それはまるで誰か別の人間の”ブツ”を眺めているような気分だったな。それが出たり入ったりーーー。
イク時の感覚もなかったけど、その代わりに胸のあたりで何かが搾り取られるような感覚があった。搾乳機を心臓につけられて、心を根こそぎ吸引されるような。
あれ以前もあれ以降も二度と味わうことのない体験なんだろうな。
*
ことが済んだ後、その娼婦は言ったよ。「ごめんなさい。でも、ありがとう」って。謝られる理由もなければ、感謝される所以もない。(それが性欲を介さない屈折した形であっても)僕はただ金と精子を交換したに過ぎない。ーーーもしくは別の何か大切なものを。
朝靄に翳る娼婦の背中を見送りながら思ったんだ。もし自分に成功が用意されているとするならば、もうこんなところに居ちゃ駄目だ、って。
29.
話はそれで終わった。小牧はフォークに刺さったまま残されたオリーブを齧り、グラスをバーテンダーに返した。
「そいつが小牧さんの言う”怪物”なのか?」
「もしくは、単なるアゲ-マン売女」と真妃奈が付け加えた。
「そうですね。僕が成功の扉を叩いたのだとしたら、あの夜のあの出来事以外考えられませんね。もしそれを怪物と呼ぶのなら」
ーーー解せなかった。演出家から聞いていた話とだいぶ違う。確かに”すがりつく”という点では似たようなものかもしれないが。
「怪物は見る人によって姿形を変えるのか?俺が見た奴と全然違う」
「怪物も馬龍丑。さんには抱かれたくなかったんですよ、きっと。分かる〜」と真妃奈が言った。
ーーー今は冗談とかいいぜ、bitch。
「どうなんだろう。もしかすると、東京には怪物がたくさんいるのかもしれませんね。それは時代によって姿を変え、求めに応じて形を変えて、あちこちに生息しながら他人の夢を喰う機会を伺っている」
小牧は財布からカードを取り出し、支払いを済ませた。手出し口出し出来る隙もないほどのスマートさだった。
私は小牧の寂しげな横顔が気になった。演出家の通夜から怪物の話まで些か昔を思い出し過ぎたせいなのかもしれない。
「ーーー会って良かったんだろ?怪物に」
「どうかな。夢を追っていたあの頃の僕の方が、今よりもずっと輝いていたように思えて仕方ない」
「おい。成功者みたいなつまらないこと言うなよ」
小牧はバーテンダーからコートを受け取り、それを羽織った。上質そうな革のコートだった。
「君たちも東京という怪物に呑み込まれないように気をつけた方がいい」
我々の肩に手を乗せ、スツールから立ち上がった小牧は先程より一回り痩せて小さくなったように見えた。
ーーー照明の当たり具合のせいかもしれない。
ドアへと向かうその背中に声を掛ける。
「Hey!ちなみに梅毒は大丈夫だったのかよ、doggs?」
「幸い、今は良い薬があるんだぜ、坊主」とだけ小牧は言った。
*
残った酒を飲み干す。もう一杯頼むだけの余裕は肝臓にはあっても、財布には無かった。タイムリミットだけがあった。西麻布には駅がない。ここから阿佐ヶ谷へと帰るには六本木まで歩き、都営大江戸線を経由して代々木で総武線に乗り換えなければならない。終電が迫っていた。ヤれそうにもない女とのタクシーの相乗りなど言語道断だった。
「そろそろ帰ろうぜ」と私は言った。
「うーん。私もそのお店行ってみようかな。『モスト・デンジャラス』だっけ?今日の帰りにでも」
「『アルト・バイエルン』だよ」
!ーー正しくは『ソルト・ピーナッツ』。阿佐ヶ谷に存在する世捨て人のポケット。
「馬龍丑。さんも付き合ってくださいよ」
「俺は御免だね」
こんな良い酒を飲んだ後に、ドブ底をさらって仕込んだような低級酒なんて身体に入れたくはなかった。
*
真妃奈とは阿佐ヶ谷駅前で別れた。本当に『ソルト・ピーナッツ』に寄って帰るつもりらしい。まぁ自分のとこの主催が馴染みだった店だ。わざわざ止める筋合いもなかった。飲みたい奴は飲めばいいし、死にたい奴は死ねばいい。自由とはそういうものだろう。違うのか?
「もし場所が分からなかったら電話してくれ」と真妃奈にケータイの番号を渡した。それ以外の理由で掛かってくることなんて期待せず。
#阿佐ヶ谷 #西麻布 #バー #小劇団 #演出家 #演劇 #俳優 #通夜 #小説 #短編小説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
