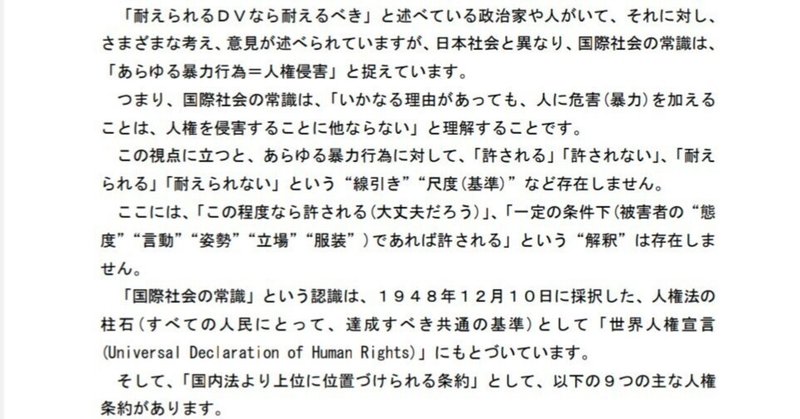
(コラム-5)耐えられるDVなど存在しない。国際社会の常識は、「あらゆる暴力行為=人権侵害」である! 日本には、なぜ、人権認識が定着しないのか、その歴史的背景を踏まえて。
「耐えられるDVなら耐えるべき」と述べている政治家や人がいて、それに対し、さまざまな考え、意見が述べられていますが、日本社会と異なり、国際社会の常識は、「あらゆる暴力行為=人権侵害」と捉えています。
つまり、国際社会の常識は、「いかなる理由があっても、人に危害(暴力)を加えることは、人権を侵害することに他ならない」と理解することです。
この視点に立つと、あらゆる暴力行為に対して、「許される」「許されない」、「耐えられる」「耐えられない」という“線引き”“尺度(基準)”など存在しません。
ここには、「この程度なら許される(大丈夫だろう)」、「一定の条件下(被害者の“態度”“言動”“姿勢”“立場”“服装”)であれば許される」という“解釈”は存在しません。
「国際社会の常識」という認識は、1948年12月10日に採択した、人権法の柱石(すべての人民にとって、達成すべき共通の基準)として「世界人権宣言(Universal Declaration of Human Rights)」にもとづいています。
そして、「国内法より上位に位置づけられる条約」として、以下の9つの主な人権条約があります。
これらの条約には、いずれの国家の立場からも独立である専門家からなる委員会が設置され、その内容を守ることを約束した国が、本当に守っているかどうかを監視しています。
・あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約、1965年12月21日)
・市民的および政治的権利に関する国際規約(自由権規約、1966年12月16日)
・経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(社会権規約、1966年12月16日)
・女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約、1979年12月18日)
・拷問および他の残虐な、非人道的な、または品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約(拷問等禁止条約、1984年12月10日)
・児童の権利に関する条約(子どもの権利条約、1989年11月20日)
・すべての移住労働者およびその家族の権利保護に関する条約(移住労働者権利条約、1990年12月18日)
・障害者の権利に関する条約(障害者権利条約、2006年12月13日)
・強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約(強制失踪者保護条約、2006年12月20日)
日本は、「移住労働者権利条約」以外の8条約について、「守る」と約束しています。
これらの条約は、「国際的な人権保障である」ことから、国際社会の常識となります。
したがって、「あらゆる暴力行為は人権を侵害する」と認識し、その判断基準は、上記「世界人権宣言」であり、「人権条約」となります。
なお、「あらゆる暴力行為」とは、児童虐待(ネグレクト、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待(面前DVを含む))の他、過干渉、教育的虐待、しつけ(教育)と称する体罰、養育者がアルコール・薬物・ギャンブルなどに依存し、不適切にかかわるなどを含む)、DV(身体的暴力/性的暴力/精神的暴力/社会的隔離/子どもを利用した精神的暴力/経済的暴力)、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメント、差別・迫害、戦争などの暴力行為を指します。
したがって、「耐えられるDVなら耐えるべき」と述べていたり、考えたりする人は、人権に対する認識が欠落している人ということであり、DVに限定されず、児童虐待を含めあらゆる暴力行為を容認している人といえます。
なお、子どもの視点に立つと、DVと児童虐待は密接な関係にあり、切り離すことができない問題です。
交際相手との間、夫婦間に子どもがいる“前提”で、「耐えられるDVなら耐えるべき」と述べているときには、「子どもの人権」を踏まえていないことになります。
なお、「DV=犯罪」として警察が介入するアメリカでは、子どものいる家庭におけるDV事件(子どもが面前DV=心理的虐待被害を受けている)では、児童保護局(CPS)に通報され、CPSが、「子どもに危険性がある」と判断したときには、子どもを裁判所の保護下に置き、加害者・被害者の親から分離させます。
その間に、両親(加害者と被害者)ともに、加害者プログラムやカウンセリングなどを受け、子どもを安全に育てる環境を整えなければなりません。
「子どもの人権」を優先する欧米諸国では、DV加害者だけではなく、DV環境下に留めたDV被害者も子どもに虐待を加えた“当事者”となります。
人として、人権を尊重し、守ることは、大きな責任を伴います。
(「人権意識」がない日本社会の現状認識のための“前置き”)
同じ敗戦国だった(西)ドイツと日本の大きな違いは、敗戦を反省し、学ばなかったことです。
日本は、経済復興という名の下で、高度経済成長を経て、1969年(昭和44年)6月10日、GNP、世界2位となりました。
それは、世界に秀でた物を造り、世界で売り、世界を席巻することで、負けた屈辱を晴らす国家プロジェクトでしたが、戦争トラウマを抱えた日本国民が、会社に忠誠を誓い、家庭を顧みず、身を削って働き続けることで達成したものです。
この仕組みは、武家が主君に忠誠を誓い、命を懸けて尽くした価値観と受け継いだものです。
つまり、戦後77年、日本社会の絶対的多数は、この精神論ともいえる価値観を美徳とし、受け継ぎ、異論を唱える者(ベトナム戦争に反対するウーマンリブ運動(ここからDV問題にとり組む芽が生まれた)としての婦人運動、安保反対を掲げた学生運動など)は叩き潰したり、仲間にとり入れ骨抜きにしたり、いまは、内閣府として監視社会を構築したりしてきました。
また、この間、いまの日本の礎となる社会保険、年金、社会福祉など、さまざまな社会保障制度がつくられましたが、その基礎は、欧米諸国の「個人主体」ではなく、「家族主体」に置くものです。
これは、女性を社会ではなく、家庭に留めおく重要な役割を果たしています。
日本が敗戦して2ヶ月後、10月24日、国際連合憲章の下、「国際連合」が51ヶ国の加盟国で設立され、その2年9ヶ月後に採択したのが「世界人権宣言」です。
第2次世界大戦直後に、人権にフォーカスした意義は大きく、国の再建に人権を優先させた国々とそうでない国々に別れ、日本は、後者、人権を優先させてこなかった国ということです。
そして、日本国民の多くが理解していないのは、経済活動と戦争・紛争はつながっているということです。
日本では、「戦争に負けたけども、日本の技術は世界一だった。だから、短期間で、奇跡的な経済復興を成し遂げられた」、「世界2位の経済大国となり、豊かな生活となった」ことを教えられ、「人生の負け組にならないために、勝ち組になれ!」と叱咤激励されるだけで、「その経済活動として国々の紛争の最終的な解決方法として、『国際法』は“合憲”と認めている(国連、各国が監視し、抑止している)」ことは教えず、「他国で紛争や戦争に至る背景となっている経済活動は、その日本をはじめ先進諸国を豊かにするため」と教えなかったり、知らせなかったりしてきました。
日本政府が、頑なに人権教育をとり入れないのは、さまざまな問題意識を持ち、政府批判をしないようにするためです。
例えば、昭和6年(1931年)-昭和7年(1932年)の「満州事変」は、世界恐慌の影響で大変な不景気となり、鉄鉱石や石炭などがとれる中国東北部の満州の権利拡大を目指した日本は、中国に攻撃を仕掛け、満州を占領したわけです。
翌昭和8年(1933年)、国際連盟を脱退し、太平洋戦争(第2次世界大戦)に進んでいきました。
アフリカの国々、アフガニスタンなどで続く紛争、そして、ロシアがウクライナに攻め込んだ(戦争を仕掛けた)の原因は、日本が「満州事変」をおこした構図とほぼ同じです。
そして、個々人の「人権」を主体にせず、日本社会が「家族」を主体にしているのは、日本社会が保守的な価値観を受け入れている、つまり、日本社会が、「男尊女卑」「内助の功」「良妻賢母」といった価値観を受け入れていることを意味します。
それでも、国際社会の動きに逆らえず、不完全ながらも、平成12年(2000年)に『児童虐待の防止等に関する法律』、平成13年(2001年)に『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律』が制定され、平成29年(2017年)、110年ぶりの刑法が改正(性犯罪の厳格化)され、令和2年(2020年)『男女雇用機会均等法(職場でのセクシュアルハラスメント防止対策)』が改正されてきました。
保守的な価値観を支持する社会で、その特権性を享受してきた人たちは、こうした「女性と子どもが獲得してきた権利」を疎ましく、鬱陶しく、忌々しく思っています。
いま、こうした人たちが、かつての権威(特権)をとり戻そうと、いまいちど「権利」を奪おうと目論む人たちのパワーが目立ってきています。
同じ敗戦国のドイツと異なり、戦時中、戦後を踏まえて日本政府が犯した大きな過ちがもうひとつあります。
それは、PTSDの存在を隠し、その治療体制を整備することを怠ったことです。
第1次世界大戦(1914-1918年)後のイギリスとアメリカでは、「砲弾ショック(シェルショック)」と「戦闘神経症」に対する研究としてPTSD研究がおこなわれていました。
その後の太平洋戦争(第2次世界大戦)では、日本政府は、この「砲弾ショック」「戦闘神経症」と呼ばれたPTSDの存在を隠し続けました。
なぜなら、当時の陸軍は、国民にその存在を知られると兵士を戦地に送るのに支障がでると考えたからです。
その日本では、1937年(昭和12年)の日中戦争から1945年(昭和20年)の終戦までに、療養施設に収容された戦場疾病者約6万人のうち精神疾患患者は約1万4千人でした。
そして、戦場体験などによる精神疾患で退院できずにいた患者は、高齢化で亡くなる人が増え、平成16年(2004年)には143人になり、戦後69年を経た同26年(2014年)には13人になっています。
戦争と障害者の問題を研究してきた清水寛・埼玉大名誉教授は、「戦争はおびただしい数の戦傷病者をつくる。特に戦争に行って精神疾患となった患者は家族から家の恥のようにいわれ、社会復帰できずに病院で亡くなるなど、“復員”が果たせないこともあった。悲惨な状況を繰り返さないために、戦傷病者の存在を忘れてはならない。」と述べています。
しかし、この精神疾患患者約1万4千人は、終戦後、日本にひきあげることができた日本軍の軍人・軍属約330万人の0.42%です。
これは、ベトナム帰還兵の30%がPTSDを発症し、18.7%が日常生活に復帰できない重篤なPTSDを発症し、戦争終了後40年以上経過しても約10%が慢性症状に苦しみ続けている現実からかけ離れた数値です。
終戦後の日本が、帰還した兵士が発症していたであろうPTSDに対し、いかに見て見ぬふりをしてきた(存在がなかったと黙殺してきた)かがわかります。
これは、日本政府が、国民を大切にしてこなかった証です。
日本政府の特徴は、なにごとにも非を認めず、隠し、そして、賠償は絶対に避けることです。
そして、日本社会、国民の一定数は、賠償を得た人を権利と解釈できず、泡銭を得た人と解釈し、時に、激しく非難します。
誰しも、戦地からの帰還兵、空爆を受けた国民が抱えた苦しみ、哀しき、絶望は、戦後の混乱期、アメリカだけではなく、戦地となったヨーロッパ、アジア、そして、日本で見られたものだったと察することができます。
アメリカでは、その後、イラク戦争だけで4千人を超える戦死者をだし、イラクからの帰還兵の2割にのぼる30万人がPTSDを発症し、その治療に少なくとも6,200億円(4-5年前で))が費やされています。
ここに、第2次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争などの補償(治療費)が加わります。
日本政府が、その存在を認めると膨大な費用が必要となります。
そうした人々に対する賠償金を支払うこともなく、国として非を認めなかった日本政府は、意図的に、こうした事実は消し去ったたといえます。
PTSDの存在を隠し、認めてこなかった日本政府のもとでの精神科治療、もしくは、医学教育には、PTSDの治療・研究機関は存在しない、つまり、表立ってPTSDを学び、治療法を身につける医学部学生はいない時期が長く続きました。
その結果は、日本に、PTSDの専門医が極端に少ない理由です。
しかも、日本社会では、PTSDやその併発症としてのうつ病などの症状は、精神論にかき消されてしまいやすく、いまだに、情報や医療につながり難い状況です。
戦後77年経ったいまでも、日本社会に残されたのは、「どこの家庭でも、暴力があたり前のように繰り返されていた」、「昔はどの家庭でもぶん殴られていた」という空しいことばとその消し去ることのできない事実です(令和4年(2022年)4月)。
(日本の「家族法」、なにが問題? その背景にある「保守的な価値観」とは)
DV問題や児童虐待問題は、個人や家庭の問題と認識していると、DV問題や児童虐待問題の本質を把握できません。
なぜなら、今日のDV問題や児童虐待問題は、その国の政府が、第2次世界大戦後の77年間、その対策として、どのようにとり組んできたのかが顕著に表れるからです(令和4年(2022年)10月現在))。
そして、ここには、その国で生活する国民の意識が深く表れます。
この問題に先進的にとり組んできた欧米諸国と比べると、日本は、四半世紀近く遅れています。
その背景になっているひとつは、「G7の中でもっとも遅れている。」、「G7の中で、これほどまでに後ろ向きな国は他にない。」と指摘される『家族法(民法)』です。
それは、世界で唯一、「夫婦同姓(民法750条、および、戸籍法74条1号)」と法で定め(令和2年(2020年)には、95.3%の夫婦が「夫の名字」を選択)、第2次世界大戦後、家父長制はなくなったが、その価値観は生活様式として根づいていたり、令和4年(2022年)10月14日に削除されるまで、「親の子どもに対する懲戒権(民法822条)」が明治29年(1896年)の制定から120年残り続けたりし、その流れで、2年前の令和2年(2020年)4月1日に『児童虐待防止法』が改正されるまで、「しつけ(教育)と称する体罰」を容認してきたことであり、また、日本の『社会保障制度』は、家族を優遇する制度設計となっていたりすることなどがあげられます(いずれも、令和4年(2022年)10月現在)。
こうした世界に例のない日本特有の問題は、「なぜ、DV被害者は、DV加害者から逃げたり、DV加害者と別れたりできないのか?」に看過できない影響を及ぼしています。
司法、福祉行政、警察の現場では、DV対策、児童虐待対策は、日本の法制度の下で考えることであり、欧米諸国と比べても仕方がないとの認識であり、その認識は、いまは変えようのない事実です。
とはいえ、上記例は、昭和60年(1985年)6月25日に批准(昭和56年(1981年)9月3日発効、20ヶ国目)した『CEDAW(女性差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)』、平成6年(1994年)4月22日に批准(平成2年(1990年)発効、158ヶ国目)した『児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)』と深くかかわります。
いうまでもなく、条約は国内法より上位です。
したがって、CEDAW委員会の勧告をあまり重視していない(と思われる)日本が、欧米諸国からどのくらい遅れているのかは関係がない、仕方がないではすまされないと考えます。
夫婦間にDV行為があるときには、子どもは、夫婦間の暴力を見たり、聞いたり、察したりする状況にあります。
この状況は「面前DV」と呼ばれ、『児童虐待防止法』の心理的虐待にあたります。
このことは、同法第2条(児童虐待の定義)の中で、「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力」と明記されています。
つまり、夫婦間にDV行為があるとき、子どもは、等しく虐待を受けていることになります。
したがって、一方の配偶者に対して、DV行為に及んでいる親(もう一方の配偶者)は、子どもに虐待を加えていることになり、「DV行為があっても、親と子どもの関係は別」という論理(主張)は成り立ちません。
ここで必要となる捉え方は、虐待を加えた親(加害者)と虐待を加えられた子ども(被害者)という関係性です。
この視点に立つと、虐待行為の加害者である親とその被害者である子どもとの面会交流の実施の判断は慎重でなければならず、また、虐待行為の加害者である親(一方の配偶者に対してDV行為に及んでいる親)が、被害者である子どもの親権や監護権(養育権)を得たりすることはあり得ません。
『児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)』の19条では、「子どもが両親のもとにいる間、性的虐待を含むあらゆる形態の身体的、または、精神的暴力、傷害、虐待、または、虐待から保護されるべきである。」と定め、「それが起こるとき、親権や監護権、面会交流の決定において、親密なパートナーからの暴力や子どもに対する暴力に対処しないことは、女性とその子どもに対する暴力の一形態であり、拷問に相当し得る生命と安全に対する人権侵害である。」、「また、子どもの最善の利益という法的基準にも違反する。」と規定しています。
平成26年(2014年)、CEDAW委員会は、「面会交流のスケジュールを決定するときには、家庭内暴力や虐待の履歴があれば、それが女性や子どもを危険にさらさないように考慮しなければならない。」と勧告しているが、日本政府は、この勧告に反し、その考慮は極めて限定的です(改善に消極的です)。
いうまでもなく、『条約』は、国際法です。
『日本国憲法』第98条2項は「条約を誠実に遵守する」と定め、同第73条第3号但書、同第98条2項により、『条約』は、『法律(国内法)』の上位に位置づけられますます。
家庭内暴力や虐待の履歴がある家庭で、子どもがいる夫婦が別居、あるいは、離婚に至るとき、その子どもが、虐待行為の加害者である一方の親と生活をともにすることは、子どもを危険にさらすことに他なりません。
この状況は、いうまでもなく、『児童虐待防止法』に準じると通報事案、つまり、そのこと自体が“一時保護”事案となり得るということです。
にもかかわらず、日本政府(国民が選んだ国会議員、その国会議員が所属する政党で、数がもっとも多い第1政党+他で、過半数を占める)が、こうした国連の勧告を拒み続けるのは、保守政党だからです。
そして、日本には、ほぼ保守政党しかありません。
それは、国会議員、地方議員の絶対的多数が保守派、つまり、日本国民の絶対的多数が保守派という意味です。
その絶対的多数が保守派の中でも、超に超がつく保守派の人たちが、「G7の中でもっとも遅れている。」、「G7の中で、これほどまでに後ろ向きな国は他にない。」と指摘される『家族法(民法)』を「さらに“保守的”、さらに遅れたものに、あるいは、危険な方向に働きかけている、それは、日本の危機だ!」というのが、ウニさんの指摘(問題提起)です(同解釈だといいのですが)。
危険な方向に働きかけているのは、いうまでもなく「共同親権」です。
実は、この日本社会総保守派ともいえる状況が、日本特有のDV問題、児童虐待問題を生みだしています。
代表的な“保守的”な価値観は、「女性の幸せは、結婚し、子どもを持つことであり、子どもにとっての幸せは、たとえ、暴力のある家庭環境(機能不全家庭)であっても、両親の下で育つことである」と考え方です。
この“保守的”な価値観が、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの問題を解決するうえで、大きな障壁として立ち塞がります。
アメリカ合衆国の保守基盤は、「キリスト教的家族主義(信仰)」ですが、個々人の人権をなによりも重んじているので、日本の保守派とは異なります。
いまから120年前の明治29年(1896年)に制定された「民法(家族法)」は、“家制度(家父長制)”を軸につくられました(令和4年(2022年)4月現在)。
日本における“保守的”な価値観とは、明治政府が、列強強国に対抗するために進めた“富国強兵”“国民皆兵”を国民に浸透させた価値観です。
それは、「男尊女卑」「内助の功」「良妻賢母」という概念です。
この概念は、日本社会における「男女の役割(ジェンダー観)」に大きな影響を及ぼし、日本特有の問題を生じさせています。
「男尊女卑」とは、「男性を重く見て、女性を軽く見る」ということです。
「男尊女卑」は、“儒教思想”に由来しますが、その初出は、中国古代の素朴な父系社会がそのまま反映されている春秋戦国時代(紀元前770年に周が都を洛邑(成周)へ移してから紀元前221年に秦が中国を統一するまで)に生まれた“老荘思想”と考えられています。
つまり、いまから2700-2200年前の中国社会の価値観です。
その“儒教”は、江戸時代の武家社会の礎となる思想です。
「内助の功」とは、「家庭において、夫の外での働きを支える妻の功績」のこと、つまり、「夫(男性)が働き、妻(女性)は家で家事をする」ということです。
「良妻賢母」とは、「良妻とは、夫(男性)に従い、サポートを惜しまない貞淑な妻のこと、賢母とは子どもの教育やしつけをしっかりできる賢い母のこと」をいいます。
性別にかかわらず、この「男尊女卑」「内助の功」「良妻賢母」という価値観を肯定する人と肯定しない人では、男女の役割(ジェンダー観)の捉え方は違ってきます。
この価値観を支持する“保守的”な人たちは、この価値観を「日本古来の」「昔からの」という表現をよく使いますが、この価値観は、明治政府が“富国強兵”“国民皆兵”、つまり、軍国化を進める国家的なキャンペーンにより国民に浸透させたもので、「日本古来の価値観」でも、「昔からずっとそうだった」わけでもありません。
例えば、江戸時代268年間(1603年-1868年/1871年)は、「夫を支える妻」という“構図”は、総人口約3000万人中、7%の210万人(江戸300藩、1藩平均700人程度)に満たなかった「武家」などに限られたものでした。
平安時代中期((900年ころ以降)/平安時代(794年-1185年))になると、官職や職能が特定の家系に固定化していく「家業の継承」が急速に進展し、軍事を主務とする官職を持った家系・家柄の総称を「武家」というようになりました。
約450年後の江戸時代では、「武家」は、武家官位を持つ家系のことを指します。
武家で求められた女性像は、家庭的であると同時に、男性よりも勇敢で、決して負けないというもので、武家の若い娘は感情を抑制し、神経を鍛え、薙刀を操って自分を守るために武芸の鍛錬を積むことになりました。
ところが、時代の変遷により、武家の女性たちが音曲・歌舞・読書・文学などの教育が施されたのは、父親や夫が家庭で憂さを晴らす助けとなること、つまり、普段の生活に“彩”と“優雅さ”を添える担う役割と変わっていきました。
「家庭で憂さを晴らす」役割には、男性を性的に喜ばす行為も含まれています。
それが、武家の妻が夫を「もてなす(待遇する、応対する、世話する)」ということです。
(豊臣秀吉が大阪に最初につくったとされる「遊郭」で、その後、日本独特の遊郭文化、つまり、遊女が歌を詠み(読み書き)、楽曲、歌舞ができたのは、政権交代で、身を落とした公家、武家の女性が遊女になったからです。主な政権交代は、安土桃山から江戸、江戸から明治の2回です。)
つまり、武家では、娘としては父親のため、妻としては夫のため、母としては息子のために、「献身的に尽くす」ことが女性の役割とされたのです。
「男性が忠義を心に、主君と国のために身を捨てる」ことと同様に、「女性は夫、家、家族のために自らを犠牲にする」こと求められたのです。
つまり、武家の女性には、自己否定があってこそはじめて成り立つような、夫を引き立てる役割を担わされました。
この役割が、武家の女性に求められた「内助の功」「良妻賢母」です。
これが、日本の文化「おもてなし」の悲劇的な背景です。
こうした背景のもと、いまから120年前の明治29年(1896年)に「民法(家族法)」が制定されました。
この120前に制定された「民法(家族法)」の中で、こうした背景の価値観が戦後も色濃く残る部分が、「G7の中でもっとも遅れている。」、「G7の中で、これほどまでに後ろ向きな国は他にない。」と指摘される「家族法」の問題点です。
一方で、個人主体ではなく、家族(家庭)主体の社会システムである日本でに導入するのは危ぶいと指摘されているのが、「離婚後の共同親権制度」にフォーカスした「家族法」の改正問題です。
いまだに、日本社会における“男らしさ”は、国と職場のために身を捨てては働くことを意味し、“女性らしさ”とは、男性、夫、子ども、家族のために自らを犠牲にして尽くすことを意味します。
これらは、“性差別”そのものを指すことばです。
そして、個々人の人権はなく、国家、会社、学校を第1に身を尽くす(自らを粉(犠牲)にして頑張る)であることを意味します。
女性の役割として、男性に「献身的に尽くさせる」ために、男性の威厳を示す(力を誇示する)暴力がひとつのDV行為の典型であることがわかると思います。
女性に向けられるこの性差別がいきつくと、女性を狙った殺人「フェミサイド」になります。
フェミサイドとは「女性であることを理由に、男性が女性を殺害する」ことを指します。
その「フェミサイド」の背後には、「ミソジニー(女性に対する憎悪・嫌悪・差別意識)」が存在します。
日本社会には、この「日本社会にミソジニーが存在することを隠したい、臭いものに蓋をしたい人」が数多く存在します。
このことは、日本社会が、女性差別社会であることを意味します。
そして、この人たちは、「女性と子どもが獲得してきた権利」を疎ましく、鬱陶しく、忌々しく思っている人たちと合致します。
アメリカでは「インセル」ということばが生まれましたが、このことばは、「不本意な禁欲主義者」を意味し、「俺が、恋愛やセックスをできないのは女が悪い」と女性を逆恨みして、憎悪を募らせる“一部”の男性を指します。
このインセルと呼ばれる“一部”の男性は、「男には、恋愛やセックスをする権利がある」、「女にケアされて性欲を満たされる権利がある」、「その権利を不当に奪われている」という強い被害者意識を持っています。
その被害者意識は、進学、就職、仕事、人間関係などで挫折したり、ストレスを覚えるできごとがあったりしたとき、「俺の人生がうまくいかないのはモテないから、つまり、女が悪い!」と女性に責任転嫁し、逆恨みする傾向があります。
日本社会においても、ネット上で自称「非モテの弱者男性」の一部が、「女を再分配せよ」と主張しているのを見かけますが、いうまでもなく、女性はモノではありません。
ここには、「男には、女を所有する権利がある」という“認知の歪み”が存在し、この“認知の歪み”を生みだしているのが、男性優位社会です。
「女を所有してこそ一人前」、「女をモノにできない自分は男社会で認められない」という劣等感から女を逆恨みするのも「ホモソーシャル」です。
女性を自分と対等な人間だと思っていない男性は、「女のくせに、俺を拒絶しやがって」、「女のくせに、幸せそうにしやがって」、「自分の思い通りにならない女が憎い、そんな女に復讐してやる」と憎悪を募らせます。
2014年(平成26年)、アメリカで、インセルを自称する22歳の男性が、「女への復讐」を宣言し、6人を殺害して14人を負傷させ、のちに自殺した事件がおきました。
この凄惨な事件をおこした「エリオット・ロジャー」は、インセルコミュニティで崇拝され、英雄視されました。
その後、インセルによる凶悪事件の連鎖が起きました。
例えば、2018年(平成30年)、「エリオット・ロジャーは不滅だ」とネットに書き込んでいた男性が、フロリダ州の高校で乱射し、17人を殺害しました。
同年、カナダでは、SNSに「インセル革命はすでにはじまっている! 最高紳士エリオット・ロジャー万歳!」と投稿した男性が、車で通行人に突っ込み、10人を殺害しています。
そして、日本社会においても、実際に、ネット上で女叩きをするコミュニティが存在しています。
彼らは、女性を狙い、嫌がらせや誹謗中傷を繰り返し、特に、フェミニストの女性に対する攻撃は過激化しています。
頑固にこびりついたミソジニーを「学び落とす」のは大変なことで、労力も、多くの時間も必要です。
したがって、重要なことは、子どもにミゾジニーをすり込まないことです。
子どもの周りにいる親、近隣住民(コミュニティ)、学校園の教職員といった大人が、ミゾジニーのことばやふるまい(態度)を見せたり、聞かせたりしないことです。
スウェーデンでは、保育園からジェンダー教育や人権教育を徹底しています。
世間やメディアに刷り込まれる前に、真っ白な状態で教えることによって、子どもたちは差別や偏見のない大人に育ちます。
日本では一貫して、「すべての人間にはオギャーと生まれた瞬間から人権がある、差別されない権利がある」というあたり前の人権教育をしてきませんでした。
その日本社会では、子どもにミゾジニーをすり込まないためには、大人が、まずジェンダーに就いて学ぶ必要があります。
なぜなら、いうまでもなく、子どもは、周りの大人を手本にして育つからです。
子どもは、家庭での両親の関係から男尊女卑を学んでしまったり、親や公園で一緒に遊んでいる子どもの親同士、学校園の教職員の些細なやりとり(会話)から歪んだジェンダー観を学んでしまったりします。
欧米諸国の多くでは、人権教育としての包括的性教育が成果をあげています。
人権意識にもとづく、愛情や親密性の育みを大切にする性教育によって、男の子たちは、楽しいセックスと健康的な恋愛関係は支配とコントロールではなく、敬意と双方の充足感から生まれるのだという意識を持つようになります。
人権教育として性教育を学ぶことは、「性犯罪の被害者、加害者にならない」、「低年齢の性体験、妊娠のリスクを回避できる」、「自分の性やからだに対して肯定的に捉えられるようになり、自己肯定感の高い人間に育つ」、「自分だけでなく相手も尊重できるので、幸せな人間関係を築く力の土台となる」など多くのメリットがあります。
しかし、日本は、世界のポルノの約60%が生産されている「性産業先進国」である一方で、人権教育としての性教育はかなり遅れています。
人権教育としての性教育が遅れる一方の日本社会は、「臭いものに蓋をしろ」「寝た子を起こすな」と主張するばかりで、国(政府)として、大人として、子どもを守る責任を果たしていません。
大人の責任を果たすために、フェミサイドから目を逸らすことは論外です。
自分の生き難さを女性のせいにして、女性を狙い、加害する男性が存在し、女性への憎悪や差別を強化するコミュニティがあるという現実にしっかり向き合い、「フェミサイドを許さない」という姿勢を強く示すことが必要です。
こうした“保守的”な価値観のもとでは、国と職場のために身を捨てて働く男性に対し、男性に自らを犠牲にして尽くすはずの女性が、男性とは異なる考えや意志を持つことは許されません。
その世界で、女性が自分の考えや医師を口にすると、「口ごたえした!」「文句があるなら、でて行け!(稼いでこい)」「偉そうなことをいうな、何様だ!」と否定したり、非難したり、「誰のおかげで生活ができている(学校に行けている)と思っているんだ!」と侮蔑したり、卑下したりすることばを浴びせる行為は、問題がないことになります。
つまり、こうした男性が女性に浴びせることばの暴力(DV行為としての精神的暴力)は、肯定(容認)されます。
こうした“保守的”な価値観を肯定する人は、妻(女性)は、夫(男性)を喜ばすためにもてなし、献身的に尽くす役割を担うのがあたり前と認識し、肯定する人が男性のときは、女性に対してあたり前のようにそれを求めたり、肯定する人が女性のときは、男性に対してあたり前のように尽くしたりします。
それができなければ、しつけとしてふるまいを正す行為、つまり、暴力(体罰)は認められて当然と考えます。
ここには、「男女の関係は対等である」という概念(価値観)は存在しません。
「男女の関係は対等でない」という概念(価値観)は、家庭内だけではなく、社会そのものの考えであることから、学校園、職場、スポーツ、芸術、政治、社会保障制度、就職・賃金などあらゆる“場”に存在します。
では、日本において、なぜ、「男女の関係は対等である」という概念(価値観)は存在しないのでしょうか?
それは、世界で唯一、日本だけが採用している「夫婦同姓強制制度」が関係しています。
これは、明治憲法・明治民法がつくりだした家父長制が、いまだに、日本の国民の暮らしの主体としての役割を果たしていることを意味します。
つまり、戦後の日本社会では、表面的に「家父長制」はなくなりましたが、「夫婦同姓強制制度」の名の下で、社会制度システムものものは「家・家族」に重きがおかれています。
明治31年(1898年)に施行された『民法』の家族法は、法律婚をした女性から法的能力を完全に奪いました。
既婚女性が仕事をするなどの経済行為をするには、夫の許可が必要でした。
自分の子どもについても、法的な権限を一切持てませんでした。
離婚すると、子どもは夫の家に置いていかなければならず、離婚自体も、自分の意志ではできませんでした。
こうした人権否定を止め、男女同権としたのが、昭和22年(1947年)に施行された『日本国憲法』です。
法の下の平等を保障し、結婚は両性の同意のみで成立すると決め、戸籍は結婚した夫婦が新しくつくることになりました。
しかし、姓はどちらか一方のものを選ばなければならず、現在でも96%の女性が夫の姓に改姓しています。
妻が結婚により夫の姓を名乗るよう誘導する制度が、戦後77年も経ったいまでも(令和4年(2022年)8月15日現在)、多くの女性とその周辺に「夫の家に入る」という家父長制時代の感覚を残しています。
こうした感覚を持つ人は、夫を「主人」「旦那」と呼び、妻を「嫁」と呼ぶことに疑問を覚えません。
この呼称を使う人は、この関係性は“対等ではない”という認識には至っていません。
ここで、日本社会特有の夫婦間で使われる3つの“呼称”について、触れておきたいと思います。
第1は、「主人」という呼称です。
「主人」の反対語は、「下女」「下男」です。
主人は男女に限らず、“上”の者で、上の者に従う“下”の者という関係性になります。
つまり、「僕(しもべ)・下僕」「従じる者」です。
この関係性を夫婦関係にあてはめると、「主人」である夫(男性)に対し、「下女」「僕(しもべ)・下僕」「従じる者」である妻(女性)ということになります。
しかし、妻(女性)は、夫のことを「主人が」と表現する一方で、妻(女性)は自分のことを「私は夫の下僕です。」、「私は夫の僕(しもべ)です。」、「私は夫に絶対服従している者です。」と表現しません。
では、夫婦関係における「主人」の対義語はなんでしょうか?
それは、「令室」です。
「主人」「令室」は、ともに、相手を敬う表現です。
しかし私たちは、日本社会において、日常的に、夫が妻のことを「令室は、…」と表現するのを見聞きしているでしょうか?
日本社会では、女性は、夫を敬う表現である「主人」を使う一方で、男性は、妻を敬う表現である「令室」を使うことはありません。
そもそも、男性だけでなく、女性も、妻を敬う「令室」ということばを知っているのは、ごく少数ではないでしょうか?
つまり、日本社会には、妻(女性)を敬う表現は存在しないのです。
このことは、暗黙裡に、日本社会は、妻(女性)は敬うに値する存在ではないと認めていることを意味します。
日本社会は、暗黙裡に、本来、対等である夫婦の関係性に主従、上下という立場を受け入れています。
第2は、「旦那」という呼称です。
「旦那」とは、サンスクリット語の仏教語ダーナに由来し、“与える”“贈る”といった「ほどこし」「布施」を意味します。
もともと僧侶に用いられてきたことばです。
その後、一般にも広がり、「パトロン」のように“生活の面倒をみる人”“お金をだしてくれる人”という意味として用いられるようになりました。
妾や生活の面倒を見てくれる人のことを旦那様と呼び、奉公人が生活の面倒を見てくれる人、住み込みで仕事を与えてくれる人のことを旦那様、ご主人様と呼ぶようになっていきました。
その妾や奉公人が使っていた呼称を、夫婦間の呼称として使っていることは、「嫁」という概念や妻という立場が、家庭の中、夫婦の間においては、それ同等の解釈(扱い)のもとで成り立っていることを意味します。
つまり、夫婦間で、妻が夫のことを「旦那(様)」と呼ぶその関係性は、本来、生活の面倒をみる人とみてもらう人くれる人、生活費をだしてくれる人とだしてもらう人ということになります。
第3は、“支配意識”下での呼称とは趣が異なりますが、子どものいる夫婦で、夫のことを「パパ」、妻のことを「ママ」と呼ぶ呼称です。
これは、戦後の日本社会特有の現象です。
いうまでもなく、「パパ=父親」、「ママ=母親」は、子どもから見た、つまり、子どもが使用する呼称です。
では、ひとつ考えて欲しいことがあります。
それは、実際は血のつながりはないとしても、「パパ」と呼ぶ男性、「ママ」と呼ぶ女性との性行為は「近親姦」であり、「性的虐待」です。
疑似的なことはいえ「近親姦」を避けるために、性行為を避け、セックスレスになるということなら、それは、人として正常です。
この観点にもとづくなら、日本社会特有の社会病理ともいえる「パパ」「ママ」と呼び合う夫婦間でセックスレスになるのは、至極あたり前のことです。
一方で、意図的に、「パパ」「ママ」と子どもという疑似的な関係性を演出し、性行為に及ぶ行為は、疑似的な近親姦を望んでいることから、パラフィリア(性的倒錯・性嗜好障害)が絡んできます。
明治政府が国家プロジェクトとして推し進めてから約150年経過した“いま(現在)”、居住し生活している都市(地域)の学校園の教職員、同級生、先輩(卒業生)や後輩、企業の経営者、職場の上司、同僚、先輩や後輩、友人、祖父母、きょうだい、父母、義父母、交際相手、配偶者が、この「男尊女卑」「内助の功」「良妻賢母」という概念(価値観)について、どのように捉えているかという問いは、DV(デートDV)や児童虐待、いじめ、(教師や指導員などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力行為をどのように捉えているか知るうえで重要な意味を持ちます。
なぜなら、「男尊女卑」「内助の功」「良妻賢母」を当然(あたり前のこと)と認識している人たちが多数派のコニュニティ、企業(組織)、学校、家庭では、男性から女性への暴力を容認しやすいからです。
「容認」とは、認める、受け入れるということです。
そして、「あたり前のこと」と容認している人は、男性から女性に対するあらゆる暴力行為のハードル(障壁)が低くなります。
(家族を主体とした日本社会が、男女間の教育格差、賃金格差を生みだし、DV被害から女性が抜けだせなる要因に。)
シングルマザーの数は、平成12年(2000年)86.8万人であったのが、5年後の平成17年(2005年)には107.2万人と激増しました。
平成22年(2010年)は108.2万人となっていることから、同12年から17年の5年間で、家庭のあり方が大きく変化している状況がわかります。
同時期、非正規雇用が増えるなど、雇用形態が様変わりしています。
以前であれば、ひとつの仕事(正規社員)で働いてなんとか子どもを育てられた女性が、派遣労働とアルバイトを2つかけ持たなければ子どもを育てることができ難くなっています。
そのため、母親と子どもが一緒に過ごしたり、一緒に食事をしたりする時間がとれないなどの問題が生じやすくなっています。
また、仕事を2つ3つかけ持つ生活を続けた結果、からだと心のバランスを壊して働けなくなるなどの事態を招いています。
日本は、平成29年(2017年)、OECD(経済協力開発機構)に加盟38ヶ国の中で、男女間の賃金格差が、韓国の34.6%に続いて、24.5%と2番目に高くなっています。
日本の男女間の賃金格差は、2005年(平成17年)は32.8%で、その後、緩やかな減少傾向にあるものの、欧米諸国は10%台なのに対して、韓国と日本の2ヶ国だけが突出しています。
この結果は、日本社会が、男性の自尊心を満たすために、女性が高収入を得られる仕事に就くことを奪っていると考えることができます。
もし、日本の男女間の賃金格差が、欧米諸国並みの10%台になったときには、交際相手や配偶者が、「男性は、世帯一の稼ぎ手でなければならない」という考え方であるとき、その考え方に女性が歯向かったり、女性が男性よりも稼いだりしたとき、暴力を加えられリスクが高くなることから、いま以上に、DV(デートDV)案件は増加すると考えられています。
男女間の賃金格差が、DV(デートDV)案件の抑止となっている日本社会は健全ではなく、これは、まっとうなDV対策ではないことから、男女間の賃金格差がなくなった瞬間、この均衡が崩壊する矛盾を秘めています。
ここには、均衡が崩壊したときのDV対策、女性と子どもの保護などのシステムの構築にまったくにとり組んでいない現実があります。
日本において、この男女間の賃金格差が社会問題化しない背景にあるのは、いうまでもなく、「男尊女卑」「内助の功」「良妻賢母」、つまり、「女性は家に!」という認識です。
その日本における男女間の賃金格差が大きい理由は、「正規・非正規の賃金格差と女性の非正規比率の高さ」と「性別役割の固定化と就社型雇用システム」の2つです。
終身雇用を前提とする正社員雇用を守るために、非正規雇用との処遇格差が大きくなります。
終身雇用と表裏一体の長時間労働・会社都合の転勤は、「男性は会社、女性は家庭」という男女分業(性別役割の固定化)を“前提”としていて、女性の多くが、非正規雇用で働いています。
非正規労働者の70%近くが女性です。
欧米においても、非正規雇用が少ないわけではないが、ヨーロッパでは、企業横断的に「同一労働同一賃金原則」が浸透していることから、日本と比べて、正規と非正規の賃金格差は大きくなっていません。
もうひとつの日本の男女間の賃金格差の原因である「性別役割の固定化」と「就社型雇用システム」は、根が深い問題といえます。
女性は、正社員として採用されたとしても、いまだに、結婚や出産を機に退職することが少なくなく、結果、昇格・昇給が抑制されています。
『改正男女雇用機会均等法』が施行され、採用や昇進・昇格においては表面上の差別はなくなったが、女性に対する会社の姿勢、社会の捉え方はほとんど変わっていません。
日本社会と日本企業に長年染みついた性別役割分業意識と女性の昇進などに対する「アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)」からは、簡単に抜けきれるものではありません。
さらに近年、女性の昇格・昇給が抑制されている日本の問題は、平成12年(2000年)と令和2年(2020年)の年間平均賃金額の比率を見ると1.02倍と、この20年間、実質賃金がほとんど上昇していなません。
一方で、他国の実質賃金の上昇を見てみると、韓国は1.45倍と非常に高く、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスは1.2倍程度となっています。
いまから22年前、平成12年(2000年)の日本の実質賃金は3万8085ドルで、世界第5位でした(令和4年(2022年)4月現在)。
日本の実質賃金は、アメリカの6万1048ドルよりはかなり低く(62.4%)、イギリスの4万6863ドル(81.3%)、ドイツの4万7054ドル(80.9%)、フランスの4万4325ドル(85.9%)と比べても低い一方で、韓国は3万6140ドル(105.4%)で、日本と大差はありませんでした。
ところが、20年後の令和2年(2020年)になると、日本の実質賃金は3万8515ドルで、アメリカの6万9391ドルに比べ55.5%と、さらに両者の差は、6.9ポイントと広まりました。
イギリスは4万7147ドル(81.7%)、わずか0.4ポイントの差が縮まったものの、ドイツは5万3745ドル(71.5%)で9.4ポイント、フランスは4万5581ドル(84.5%)で1.4ポイント差は広がり、韓国は4万1960ドル(91.8%)で、日本を逆転し、その差は実に13.6ポイントに及びます。
もはや日本は、OECD(経済協力開発機構;ヨーロッパ諸国を中心に日・米を含め38ヶ国の先進国が加盟する国際機関)の中で、日本より実質賃金が低い国は、旧社会主義国と、ギリシャ、イタリア、スペイン、メキシコ、チリぐらいしかなく、最下位グループに入ります。
では、なぜ、日本はこの20年間でここまで経済競争力を失ったのでしょうか?
それは、アベノミクスが、日本で技術革新が進まず、実質賃金があがらない中で、円安を主導し、賃金の購買力を低下させることで株価をひき上げてきた(一部の企業と株主だけに利益が得られるシステム)からです。
正常にマーケットが機能していれば、価格の安い日本製品の輸出が増え、円高になり、その状況は、不均衡がなくなるまで続き、輸出の有利性は減殺されます。
本来、企業は、円高を支えるために技術革新を実施し、生産性をひきあげなければならないが、アベノミクスでは、本質の問題を先送りし、円安を求めました。
その結果、日本の実質賃金はあがらなくなりました。
物価が低いことが問題なのではなく、賃金があがらなかったことが問題です。
賃金があがらず、しかも円安になったことから、日本の労働者は、国際的に見て貧しくなりました。
株価があがり、物価があがり、経済的な効果があるように見せかけたアベノミクスは、実際は、真逆の負の遺産をつくりあげただけです。
企業は、賃金を抑える中で、株価があがっているので、利益剰余金(内部留保)としての純資産が増加している中、技術革新を進める設備投資をおこなっていないことが大きな問題です。
利益剰余金は、株式配当に充てられています。
「お上のいう(やる)ことを信じ」、「皆が苦しいのだから、がまんする(耐え忍ぶ)」という戦時下に植えつけられた(洗脳された)思考・行動パターンは、いまだに、日本国民のものごとの本質を知ることの大きな妨げになっている、その典型的なできごとです。
GDP3位の日本の実質賃金が、OECDの中で最下位グループに入っていることを知り、なぜ、そうなったのかを理解している日本国民はどのくらいいるのでしょうか?
ちなみに、平成8年(1996年)、1人あたりGDPはG7で2位、世界17位だったが、25年後の令和3年(2021年)になると、1人あたりGDPは、G7では最下位で世界37位、物価変動の影響を除いた日本の実質経済成長率は約1.6%、世界157位と散々な状況となっています。
主要先進国のイギリスが7.4%、フランスが7.0%、アメリカが5.7%など、日本と異なり、大きく成長しています。
日本は、バブル経済崩壊後、「失われた10年」といわれてきたが、実は、「失われた30年」で、いまもその渦中にあります。
20年間、実質賃金があがらない中で、正規と非正規の賃金格差は大きく、勤務する女性の多くが非正規である社会がもたらしたものが、子どもの7人に1人が貧困という現実です。
日本社会は、いまだに、明治政府が推し進めた男性優位社会(男尊女卑)の下で、「内助の功」「良妻賢母」を支持する人が多数派であり、「女性の幸せは、結婚し、子どもを持つことであり、子どもが生まれたら仕事は辞めて育児に専念し、育児に余裕ができたらパートタイムの仕事をして家計を助ける」という価値観・人生観が“主流”です。
こうした“保守的”な価値観は、いまだに、男性だけでなく、多くの女性にすり込まれている価値観・人生観といえます。
そのため、これがあたり前、普通と問題意識なく受け入れるだけではなく、これが理想、こうでなければならないと強いる状況が至る所で生まれます。
例えば、職場における「マタニティハラスメント」などは、加害者となる女性が、いずれ妊娠・出産に至る可能性があるにもかかわらず、こうした価値観・人生観に捉われる中で、休職などに伴う負担を強いられる思いが敵意となり、ハラスメント行為を激化させます。
これは、企業側で、女性が出産・育児と仕事を両立させやすい職場環境、就労システムを構築することで、その多くは防ぐことができます。
にもかかわらず、日本の多くの企業はとり組んでいません。
家庭内や親族内で、男性である夫や祖父、叔父が、女性である妻や祖母、叔母よりも優位であるとき、その中で暮らし、育つ子どもは、この関係性を見て、聞いて、察して、すり込みます。
きょうだい間における男性の優位性は、同じきょうだいであっても、女の子より男の子の教育にお金をかけたり、常に、男の子の意見を優先して育てたりすることなどに見られます。
こうした家庭内や親族内での日々の体験は、子どもの心の成長に大きな影響を及ぼします。
子どものすり込みには、この関係性に潜む暴力性も含まれ、パワーを使い方、パワーの回避する方法など、この関係性下で生活する(生き延びる)“術”を学び、身につけます。
意識、無意識下にかかわらず、世代間でひき継がれていきます。
(「道徳教育」と「人権教育」の違い)
まず、おさえておきたいのは、「わたしは、他人に傷けられるような人(存在)ではない」という価値観(人権)です。
このことばは、自分は大切な存在と自覚する、つまり、自分の存在そのものを肯定することにつながることばです。
あえて、「知識として」としているのは、暴力のある家庭で暮らし、育った人には、「自分を大切にする」という感覚がわからない人が少なくないからです。
たとえ、感覚としてわからなくても、まず、ことば(知識)として、「誰であっても、他人(親などを含む)に傷つけられていい人はいない」ことは知っておく必要があります。
なぜなら、暴力行為により傷つけられることは、人権を侵害されることだからです。
日本社会には馴染みがなく、浸透していませんが、暴力で人を傷つける行為のすべては、人権問題ということです。
人権問題については、家庭だけでなく、学校教育でしっかりと教えることが重要です。
親からの暴力(虐待)被害について、第三者の大人に助けを求められる年齢であり、デートDV被害が起き得る年齢になる9歳(小学校4年生)から15歳(中学校3年生/思春期前期-後期)にかけて、体系的な人権教育(子どもの権利/デートDV/性教育)を継続的に実施することで、「誰であっても、他人(親などを含む)に傷つけられていい人はいない」ことを学ぶことができます。
しかし日本では、その肝心な学校教育の現場は、いまだに、“子どもの権利”を尊重しているとはほど遠い状況です。
しかも、日本の学校教育の現場では、男女という性別をめぐる固定観念・偏見から抜けだせていません。
“保守的”な「ジェンダー観」は、先に記しているとおり、家庭内のDV、虐待、(教師などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力行為の解決を困難にさせます。
また、日本社会においても、「性の多様性」ということばが浸透してきていますが、“保守的”な価値観にもとづく日本の学校文化、企業文化には馴染まず、まったく対応できていません。
ほかにも、日本の教育現場では、日本語指導が必要な外国にルーツを持つ子どもたち、また、さまざまな障害のある子どもたちが安心して学べる環境は、いまだに整備されておらず、多様性の尊重は実態を伴っていません。
それどころか、むしろ、このような子どもたちを普通学級から排除していく傾向が顕著です。
また、暴力のある家庭で暮らし、育つ子どもと関係性が深い「不登校」の問題(いじめを起因する不登校を含む)に対しても、「別の場所を用意するから無理して登校しなくていいよ」といった趣旨の『義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律』が、平成28年(2016年)に制定されたものの、教育現場では、子どもに問題があるかのように語られています。
無理しなければ行けなくなるような学校、あるいは、いじめの加害者にこそ問題があるはずです。
しかし、いじめの被害者である子どもが、転校を勧められています。
こうした学校から見て問題のある子ども(余計な手のかかる子どもと解釈)の「排除」は、教育現場では、「その子に合った指導を」ということばに都合よく置き換えてしまいます。
結果として、日本の子どもたちは、多様な出会いの機会はどんどん失われています。
人権の保障は、人々の「多様性」を否定したところでは成り立つものではありません。
問題は、日本社会では、こうした学校教育から排除される人たちは、“差別”の対象となっていることです。
そして、学校教育において、この「排除・差別」という問題は、「思いやり」や「やさしさ」といった心の問題として扱われています。
道徳の授業は、個人の「心のあり方」を問題としています。
一見すると、個人の道徳性のあり方から差別問題などの社会的な課題に対応していくことには、効果があるように思えます。
なぜ、そう思ってしまうのでしょうか?
さまざまな差別問題は、常に具体的です。
ある特定の誰かに起こる問題であり、そこでは、個人的な、ある人とある人との狭い範囲の関係のあり方が問われます。
しかし、そうした視点だけでは、「排除・差別」について十分に考えることはできません。
差別は、個人的な「人間関係」を超えた、より広い社会関係の中で起きるものです。
現行の道徳教育では、「狭い関係性」にばかり注意が集まってしまい、その関係の中に、社会的に仕組まれたより広い構造的課題が凝集していることを考えることができません。
「心のあり方」を問題とする道徳の枠組みでは、この社会的な構造は問い難いのです。
日本では、教育現場に限らず、排除・差別だけではなく、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力行為の問題も、個々人(特定の家庭、特定の職場、特定の学校)の「心のあり方」の問題と捉え、論議され、対策が講じられています。
しかし、個々人の「心のあり方」の問題として捉える限り、問題の本質に踏み込むことはできません。
そこで、必要とされるのは、「人権認識」と、そのための「人権教育」です。
『日本国憲法』の第14条にあるとおり、「差別は、政治的、経済的、または、社会的関係において発生」します。
したがって、この関係のあり方を分析し、変えていくことでしか、排除・差別、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師などによる)体罰、ハラスメントなどの問題は解決できません。
これは、「人権教育」でとり扱う問題です。
それは、「人が自らの権利を知り、権利の主体として、それを実現するために行動する」ことが、「人間性の回復であり、社会を変えることにつながる」ような教育です。
つまり、人権教育の目的は、構造的に問題を把握することであり、それにもとづく社会変革です。
これは、道徳が、「心のありよう」という個々人の内面にフォーカスし、その枠組みにおいて問題を把握するのとは大きく異なるものです。
「人権」は、人類の歴史において、市民自らの手(力)で“獲得”してきたものです。
それは、その時々の社会体制の中で虐げられ、人としての尊厳を踏み躙られてきた人たちが、自らの人間性の回復を「人権」や「権利」という概念で表現し、権力と闘うこと(市民的抵抗、レジスタンス)で勝ちとってきたものです。
人権や権利は、「社会的」で「争議的」なものです。
DV行為の防止と保護(配偶者からの暴力の防止及びに被害者の保護等の法律)、ストーカー行為の禁止(ストーカー行為等の規制に関する法律)、親の子どもに対する体罰の禁止(児童虐待の防止等に関する法律)、ハラスメント行為の防止(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)、そして、ヘイトスピーチ防止する条例などは、欧米で社会運動がおこり、遅れて日本で問題意識が高まったり、または、国連などが、日本の現状を問題視することで、法律の制定であったり、改正につながったりしてきました。
確かに、社会的な動きの中で、市民が勝ちとったものですが、日本では、法律の制定にあたり、その法律が社会システムにどのように適合するかという視点が欠けています。
そのため、日本社会の“保守的”な価値観である「男尊女卑」「内助の功」「良妻賢母」、同じく“保守的”な「家父長制」を軸にする家族制度、その家族制度を前提に構築されている「社会保障制度」、そして、その家族制度、社会保障制度で成り立っている企業風土の下では、これらの法律は、被害者が守られない。被害者が理不尽で、不合理を強いられてしまうなどの齟齬が生じています。
つまり、いまの日本では、法律はできても、社会システムとして機能し難くなっています。
「排除・差別」「DV(デートDV)」「児童虐待」「性暴力」「いじめ」「(教師などによる)体罰」「ハラスメント」などの問題が解消される“道筋”は、こうした動きの中で、社会的な制度や構造が変わる中で拓けてくるものであって、一方的な“温情”や“思いやり”といった個々人の「心のあり方」によってもたらされるものではありません。
歴代の法律を制定する国会議員、政党(政権)は、この視点が備わっていません。
それは、日本が人権教育を蔑ろにし続けてきた結果ともいえます。
人権教育は、いま、自らが生きている社会についての分析が不可欠です。
そこでの人々の暮らしをどう理解していくか、それを踏まえて、社会のどこに問題を見出し、どのように変革していくかを問うことが求められます。
例えば、人権や権利を守るためには、どのような法制度が必要なのかについて問うことになります。
ここには、国をどう位置づけるかという観点も含まれます。
“保守的”な価値観、“保守的”な家族制度を軸にした社会システムはそのままで制定された法律は、母屋に次々と部屋を増築し続けた結果、迷路に迷い込み、目的地に辿りつけ難く、路頭に迷うような状況になっています。
こうした日本の状況下で実施される「人権教育」では、子どもたちが上記のような本来の視点を獲得するのは困難です。
平成12年(2000年)に制定された『人権教育及び人権啓発の推進に関する法律』の第2条で、「人権教育は、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動である」と定義され、「人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除ク)をいう」となっています。
この法律における人権教育や啓発は、個人の精神を涵養し、理解を深めていくとされています。
つまり、この法律は、「心がけ」に重点が置かれているので、人権教育というよりも「道徳教育」の目的に近くなっています。
先に記しているとおり、人権に関する問題は、道徳では解決しません。
なぜなら、それは心の問題ではないからです。
人に危害を加える行為は、危害を加えられた人の人権を侵害することです。
したがって、排除・差別、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師などによる)体罰、ハラスメントなどの問題は、個々人の心の問題として道徳観に訴える限り解決することはできず、人権問題と認識し、解決していかなければならないテーマです。
これらの「暴力行為」に対する課題を個々人の心の問題として認識したまま「法律」を制定してしまうと、「法律」が限定的であったり、「法律」の解釈に抜け道があったり、「法律」が「社会制度」として機能しなかったり、「法律」が時代や現状にそぐわないまま放置されていたりする事態を招きます。
日本の人権や権利に関する教育の問題は、先の法律がそうであるように、個人の価値観や道徳性の涵養へと都合よく(容易に)置き換えられてしまうことです。
例えば、いじめなど人を傷つけてはいけないことを教える「命の授業」は、個々人の「心のあり方」の問題として道徳観に訴えて解決できるものではありません。
平成26年(2014年)7月、女子生徒が高校の同級生を殺害し「人を殺してみたかった。」と供述した「佐世保同級生殺害事件(事例139)*1」が発生したとき、例年5-7月のうち1週間を「命を大切にする心や思いやりの心の育成」を目的にした“命を大切にする教育”を10年間続けてきた長崎県の教育関係者に衝撃が走りました。
この“命を大切にする教育”は、平成16年(2004年)6月におきた小学校6年生の女子児童が同級生を殺害したショッキングな事件(佐世保小6女児同級生殺害事件(事例87)*2)後に、市内の小中学校で命の尊さを学ぶとり組みを続けてきました。
この命の尊さを学ぶとり組みは、長崎平和公園や原爆資料館を見学したり、佐世保空襲の体験者を招いて話を聞いたりすることで生命の尊さや戦争の悲惨さを学ばせようとするものでした。
その中で、悲劇が繰り返されたことに、長崎県の教育関係者はショックを受けたのです。
敢えて苦言を呈すると、長崎県の教育関係者は、この10年間、命の尊さを学ぶとり組みが、人を傷つける行為の減少につながっているのかを検証してきたのでしょうか?
検証の結果、人を傷つける行為は減少している中で、悲劇が繰り返されショックを受けたのであれば、教育関係者の葛藤は理解できます。
殺傷事件前の平成24年(2012年)の長崎県14歳-19歳人口1万人あたり少年犯罪の検挙数は62.56人(503人)で全国25位、また、非行発生率は、命の尊さを学ぶ授業がはじまる前の昭和60年(1985年)24.98で全国24位、平成2年(1990年)21.13で全国27位とほぼ横一線の状況が続いているように、命の尊さを学ぶとり組みが少年犯罪を減少させる“相関性(因果関係)”を確認できません。
しかし、10年間「命を大切にする教育」にとり組んできた長崎県の教育関係者は強いショックを受け、無力感にうちひしがれたのです。
この齟齬は、「命の授業」が、“思いやり”“やさしさ”といった個々人の「心のありよう」という個々人の内面にフォーカスして実施されている、つまり、道徳教育として実施されていることから生じています。
このことは、長崎県の教育関係者が、必死に考え、労力を惜しまず、一生懸命にとり組んでも、とり組むべき方向性を間違ってしまうと意味をなさないことを教えてくれます。
問題は、「心のありよう」という個々人の内面にアプローチ以外に、アプローチの仕方を知らないことです。
その理由は、いうまでもなく、「道徳教育」と「人権教育」の違いを学んでいないからです。
そして、こうした社会問題に対する道徳的なアプローチ、つまり、個々人の「心のもちよう」による解決、個人的関係の中での解決というアプローチは、自己救済を強調し、国などの公的機関がしなければならない諸施策を免責する危険性をも孕んでいます。
日本において、人権教育が根づかないのは、国(政権)や権力者にとって都合が悪い教育だからです。
人々が自らの権利を学び、知識を得ることは、「声をあげる活動的な市民をつくりだす」ことに他ならないのです。
それはおかしい、間違っている、正さなきゃならないと「声をあげる活動的な市民になる」ために、一人ひとりが、自らの権利を学び、知識を得ることはとても大切なことです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
