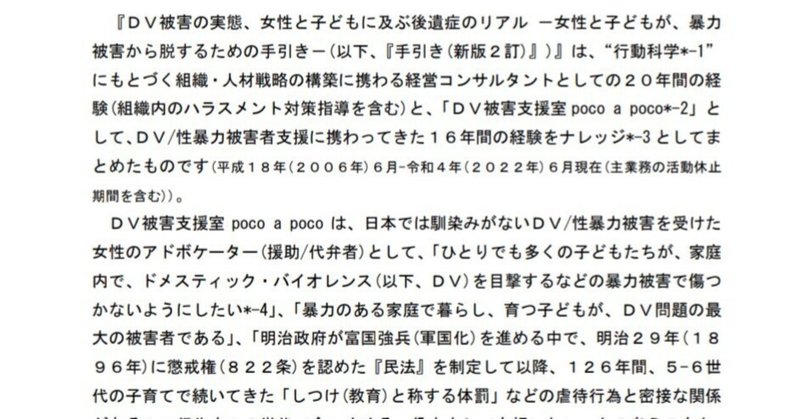
(手引き-1) はじめに。
** この「はじめに。」の中で表記されている「事例№」「判例№」については、すべての章の改訂作業が終了後、修正します。
なお、文面内では、*1.2‥と印がついています。
(年号の表記)
この『手引き(新版2訂)』における年号の表記は、日本のできごとについては「元号」表記で、( )づけで「西暦」を表記しています。
これは、家庭裁判所、地方裁判所などに提出する書面などは、「元号」が使われていることにもとづいています。
なお、家庭裁判所、地方裁判所などに、弁護士などが作成し、提出する書面では、( )づけで「西暦」を表記することはありません。
(被虐待体験(逆境的小児期体験)の表記)
この『手引き(新版2訂)』では、『児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)』で定める児童虐待行為(ネグレクト、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待(面前DV、スケアード・ストレートを含む)、しつけ・教育と称する体罰など)を受けて育った人を「被虐待体験(逆境的小児期体験)(逆境的小児期体験)をしてきた人」「被虐待者」「被虐待児」と表記しています。
「逆境的小児期体験(Adverse Childhood Experience:ACE)」は、神経発達不全や社会的・情緒的・認知的障害のリスクを高めること、薬物乱用、対人間の暴力、自殺未遂などが起きやすいこと、さらに、次世代の養育にも大きくかかわってくること(世代間伝達・連鎖)など、歳月の経過によって自然に癒されることができない影響をもたらすことから、「被虐待体験(逆境的小児期体験)(逆境的小児期体験)をしてきた人」が示す症状や傾向は、「C-PTSD(複雑性心的外傷後ストレス障害)」、「発達性トラウマ症候群」、「アダルト・チルドレン(AC)」、「被虐待症候群/被虐待女性症候群(バタード・ウーマン・シンドローム)」で示される症状や傾向と同意と捉え、表記しています。
また、「アダルト・チルドレン」は、「アダルト・サバイバー」と同意と捉え、表記しています。
『DV被害の実態、女性と子どもに及ぶ後遺症のリアル -女性と子どもが、暴力被害から脱するための手引き-(以下、『手引き(新版2訂)』)』は、“行動科学*-1”にもとづく組織・人材戦略の構築に携わる経営コンサルタントとしての20年間の経験(組織内のハラスメント対策指導を含む)と、「DV被害支援室poco a poco*-2」として、DV/性暴力被害者支援に携わってきた17年間の経験をナレッジ*-3としてまとめたものです(平成18年(2006年)6月-令和5年(2023年)6月現在(主業務の活動休止期間を含む))。
DV被害支援室poco a pocoは、日本では馴染みがないDV/性暴力被害を受けた女性のアドボケーター(援助/代弁者)として、ⅰ)「ひとりでも多くの子どもたちが、家庭内で、ドメスティック・バイオレンス(以下、DV)を目撃するなどの暴力被害で傷つかないようにしたい*-4」、ⅱ)「暴力のある家庭で暮らし、育つ子どもが、DV問題の最大の被害者である」、ⅲ)「明治政府が富国強兵(軍国化)を進める中で、明治29年(1896年)に懲戒権(822条)を認めた『民法』を制定して以降、126年間、5-6世代の子育てで続いてきた「しつけ(教育)と称する体罰」などの虐待行為と密接な関係があるDV行為をこの世代で食い止める一役を少しでも担いたい」との考えのもと、DV/性暴力被害者への支援活動をしています。
DV被害支援室poco a poco の支援活動は、交際相手や配偶者、そして、1)親や近親者からの理不尽な暴力(DV/性暴力/虐待(性的虐待を含む)など)を受け苦しんでいる人たち、2)家庭内で行使される暴力に支配される関係性を断ち切り、生活の再構築を望んでいるDV(デートDVを含む)を受けている人たち、3)レイプなどの性暴力被害を受けた人たちに対し、a)暴力行為で傷ついた女性と子どもの心のケア(カウンセリング)*-5と、b)-ア)「婚姻破綻の原因は、配偶者のDV行為である」として申立てる離婚・監護権者指定調停(審判)や裁判(民事事件)、-イ)『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下、配偶者暴力防止法)』に準じた「保護命令」の申立て、-ウ)DV(デートDV)や性暴力事件において、「暴行罪(刑法208条)」、「傷害罪(同204条)」、「殺人未遂罪(同203条)」、「強制性交等罪(同177条)」、「強制性交等致傷罪(同181条2項)」、「強制わいせつ罪(同176条)」、「強制わいせつ致傷罪(同181条1項)」、「強要罪(刑法223条)」、「侮辱罪(同231条)」を適用した立件や示談(刑事事件)などで、加害者のDV/性暴力行為に対する証拠能力を高めるために、被害者のアドボケーターとして、DV/性暴力被害の事実を書面化(『レポート(被害の事実と後遺症、その経過)』のとりまとめ)する支援(サポート)の実施です*-6。
ここでいう「暴力」は、a)交際相手や配偶者によるDV行為(身体的暴力、性的暴力、精神的暴力、社会的隔離、子どもを利用した精神的暴力、経済的暴力)に加え、b)親や養育者、近親者による虐待行為(ネグレクト、性的虐待、身体的虐待、心理的虐待(面前DV、スケアード・ストレートを含む)に加え、過干渉・過保護、いき過ぎた教育(教育的虐待)、しつけ(教育)と称する体罰(体罰を含む厳しいしつけ)を含む)、c)親や養育者がアルコール、薬物(白砂糖、ニコチン、カフェインを含む)、ギャンブルなどの依存に加え、d)宗教に対する信仰、新興宗教やカルトの教え(教義)、スピリチュアル、占いなどへ傾倒し、家庭を顧みなくなっていたり、その信仰や教え(教義)がDV行為や虐待行為と結びついていたりするなど、交際相手や配偶者、子どもに対する不適切なかかわりを指します。
こうした「暴力」のある家庭環境で暮らし、成長した人は、ア)その後の人生で、対人関係に苦しみ、生き難さを抱え、困難な状況(不登校、ひきこもるようになるを含む)に陥りやすいだけでなく、イ)PTSD(心的外傷後ストレス障害)、その併発症としてのうつ病、解離性障害、パニック障害などを発症するなどの後遺症に長く苦しんだり(暴力に起因せず、事故、火災、自然災害で被災したとき、PTSD、うつ病を発症するリスクが高く、しかも重篤化しやすい。PTSD発症者は、同じ「海馬」のダメージが発症要因となるアルツハイマー型認知症の発症リスクが高くなるを含む)、ウ)統合失調症や双極性障害を発症したり、キ)破壊的行動障害(行為障害)、反抗挑戦性障害、性的サディズム、窃視症、性的マゾヒズム、ペドファリア(小児性愛)、窃触症(さわり魔、痴漢)、露出症などのパラフィリア(性的倒錯/性嗜好障害)、ボーダーライン(境界性)、サイコパス(反社会性)、妄想性、自己愛性などの人格障害を発症するなどの精神的なトラブルを抱えたり、エ)C-PTSD(複雑性心的外傷後ストレス障害)の覚醒亢進(過覚醒)の自己投薬といわれるアルコール依存、薬物依存(白砂糖、ニコチン、カフェインを含む)に加え、ギャンブル、ポルノ、セックス、買い物、仕事に依存したり、オ)自傷行為(リストカット、OD(大量服薬)、過食嘔吐など)に及んだり、カ)スピリチュアル、占い、新興宗教・カルトに傾倒したり、ク)いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメント、デートDV・DV、性暴力(トラウマの再演、性的自傷を含む)の被害者になったりしやすかったり、逆に、「加害トラウマ」を起因として、ケ)暴行・傷害、いじめ、体罰、ハラスメント、デートDV・DV、性暴力、子どもへの虐待の加害者になったり、コ)非行、他の犯罪に手を染めたりするなど、対人的(対外的)なトラブルをひき起こすリスクが高くなります。
ア)世帯主が生活を支えていることから、貧困とかかわる問題として直接論じられないのが、内閣府が23.6万人、広義を含めると69.6万人と推計している「子どものひきこもり」の問題です。
親の立ち位置から子どものひきこもりは、「自室からもほとんどでない」、「普段は家にいるが、近所のコンビニなどにはでかける」、「自室からはでるが、家からはでない」、「普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」といった段階で認識され、前者の3つが狭義のひきこもり、最後の1つが広義のひきこもりとなります。
広義のひきこもりとされる「普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事のときは外出できる」ことは、「仮面うつ病(気分障害に該当しない「非定形うつ病」、「新型うつ病」)」と総称で呼ばれる人たちに共通する特性に合致します。
精神科、心療内科の受診において、時に、この「仮面うつ病(気分障害に該当しない「非定形うつ病」、「新型うつ病」)」に対し、気分障害の「うつ病」と診断し、精神治療薬が処方され、また、出社できない理由を示す診断書が作成されています。
一番の問題は、気分障害の「うつ病」でないにもかかわらず、精神治療薬が処方されている危険性です。
内閣府の調査とは異なり、疫学調査でひきこもり数を25万5000世帯(広義のひきこもり数は46万人)と算出した厚生労働省は、『95%以上に診断名がついたとし、25%以上を発達障害が占めた。』と発表しています。
この調査では、『アスペルガー症候群の人が不安障害になったり、ADHDの人がうつ病になったりすることがよくある。』、『アスペルガー症候群などのひきこもり当事者の中には、なぜ、ひきこもりから抜けださなければならないのかを理解し難い場合が多い。』と説明しています。
さらに、『後発性の発達障害との関係性も深いパーソナリティ障害(人格障害)、例えば、「回避性」は、人の前でなにかをするのが怖く、「依存性」は、他人に頼らないと生きていくことができず、責任は絶対に負わない、「強迫性」は、完全主義者で失敗は認められない、「受動攻撃性(拒絶性)」は、どうせなにをやっても認められないからなにもやらない、「自己愛性」は、自分に自信がないため、無理やり自分はすごいと思い、傷つくことを恐れる、「境界性(ボーダーライン)」は、虐待を受けた経験者が多く、自分探しをして、これが私だという土台を築くことができなかった。人にしがみつき、自分の思い通りに操作し続けないと、自分が空っぽで無力な価値のない存在に思えてしょうがない。「シゾイド性」は、ひとりでいるのが大好きな人たち、「妄想性」は、非常に過敏で被害的で、迷信深く、魔法のような世界にいる、といったそれぞれの特性が、ひきこもりの要因となっている。』と説明し、『ひきこもりとの親和性(物事を組み合わせたときの、相性のよさ。結びつきやすい性質)がとても高い。』と指摘しています。
そして、ひきこもりの状態を、「統合失調症、気分障害、不安障害などの精神疾患の診断がつくひきこもりで、薬物などの医療的治療の優先が不可欠となるものを「第1群」、発達障害の診断がつくひきこもりで、特性に応じた精神療法的アプローチや教育的な支援が必要となるものを「第2群」、パーソナリティ障害(人格障害)や薬では効果のない不安障害、身体表現性障害(PTSDの症状のひとつの「身体化」。痛みや吐き気、しびれなどの自覚的ななんらかの身体症状があり、日常生活が妨げられており、自分でその症状をコントロールできない)、同一性の問題などによるひきこもりの人たちで、精神療法やカウンセリングが中心となるものを「第3群」と分類」しています。
不安障害やうつ病(気分障害)、総称としての仮面うつ病(非定型うつ病)、そして、後発性の発達障害の一部の人格障害(パーソナリティ障害)の人たちに共通しているのが「低い自尊心と自己肯定感」であることから、否定と禁止のメッセージを含むことばの暴力(過干渉・過保護、教育的虐待を含む精神的虐待)を浴びせられている、つまり、暴力のある家庭環境で暮らし、育ってきたことが発症原因となり、同時に、子どものひきこもりの原因となっています。
ウ)の自傷行為をすると、脳では、痛みを和らげるドーパミンが分泌されます。
このドーパミンは快感をもたらすので、自傷行為はちょっとした気持ちよさを覚えます。
しかし、自傷行為を続けるとドーパミンが分泌され難くなり、より深く自分を傷つけなければ快感を得られないようになります。
一時、ODで気持ちよくなったとしても、ODを繰り返すと内臓はダメージを受けます。
ODを繰り返すほど快感は得られ難くなり、快感を得られないのに、大量の薬に手をださずにはいられない中で、慢性的な体調不良に苦しみ、最悪、死に至ります。
日本では、ア)イ)ウ)エ)カ)キ)の治療のためサ)精神病院で長い入院生活を余儀なくされます。
入院患者約26万人、10年以上の入院患者約4万6千人の日本は、世界の中で「精神科病院大国」として知られ、日本の精神科病院の入院ベッド数は、OECD(経済協力開発機構)加盟38ヶ国にある精神科の入院ベッド数の約4割を占めています。
平成26年(2014年)、厚生労働省の患者調査では、認知症を含む精神疾患を抱える患者は全国で約392万人と推計されています。
この数字は、同年10月1日現在の人口1億2708万人の3.09%、人口1万人あたり309.81人(54.3人の増加)、100人に3.10人(0.54人の増加)です。
うつ病、双極性障害(躁うつ病)などの気分障害、統合失調症(精神分裂病)、不安障害、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、てんかん、薬物・アルコール依存症などの患者数は、顕著な増加傾向にあり、6年前の平成20年(2008年)に比べて68.7万人と激増し、その増加率は1.21と約20%に及びます。
うつ病や双極性障害(躁うつ病)などの気分障害がもっとも多く112万人(16.2万人の増加、増加率1.26)で、続いて、統合失調症(精神分裂病)で77万人(5.7万人の増加、増加率1.08)となっています。
なお、全体の精神疾患患者の約40%(156.8万人)が、「子育て世代」ともいえる25-54歳が占めています。
エ)コ)では、『犯罪白書(2020年版)』で、覚醒剤の使用歴がある受刑者を対象にした実態調査の結果、女性の72.6%が「交際相手や配偶者からDV被害を受けたことがある」と回答しています。
DV被害と覚醒剤の使用の関係性については、これまでも、「宿カレを起因とするデートDV/デートレイプに伴う売春を強いられる性的搾取」の問題として指摘されてきたことですが、平成29年(2017年)に、厚生労働省所管の国立精神・神経医療研究センターと法務省法務総合研究所が共同で実施し、具体的な数値が明らかになりました。
このことは、「女性は、男性(交際相手/配偶者)からDV被害を受けなければ、女性の覚醒剤の使用を大きく減らすことができる」ことを意味します。
ア)イ)ウ)エ)ク)は、仕事を続けられなくなったり、仕事に就けなくなったりする直截的な要因となり得て、結果、シ)貧困につながります。
交際相手や配偶者からのDV被害を減らすことができれば、イ)シ)で苦しむ人が少なくなり、DV行為のある家庭で暮らし、育つ(面前DV=心理的虐待を受ける)子どもが減ると、ア)-カ)、サ)シ)のすべてが減ります。
しかし日本は、国として、明治29年(1896年)に「懲戒権(822条)」を認めた『民法』を制定して以降、126年間、「しつけ(教育)と称する体罰」などの虐待行為を認めてきました。
このことは、日本国民の一定数が、「しつけ(教育)と称する体罰(虐待行為)」を5-6世代の子育てで行ってきたことを意味します。
この「日本国民の一定数」は、戦前、昭和の話しではなく、平成30年(2018年)、子ども支援の国際的NGO「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」が2万人の日本人を対象に実施した調査では、しつけ(教育)に伴う子どもへの体罰を約6割-7割が容認し、体罰(虐待行為)を加えていることから、いまの問題です。
日本国民の70%-60%が、子どもに虐待(しつけ(教育)と称する体罰)を加えている異常な状況は、日本を蝕む社会病理といえます。
このア)-カ)、サ)シ)の問題は、この『手引き(新版2訂)』の「第2部(Ⅱ)虐待(面前DVを含む)の後遺症。子どもを加害者、被害者にしないために」で詳述します。
「暴力(DVと密接な関係にある児童虐待)」の“世代間連鎖”を食い止め、「暴力被害(DVと密接な関係にある児童虐待)」を“起因”とするさまざまな影響を防ぐには、いま、「DVと児童虐待」のある家庭に対して適切なアプローチとケアにとり組む(早期発見と早期介入、早期治療)ことが必要不可欠です。
*-1 行動科学のひとつの「行動分析学(Behavior Analysis)」では、人や動物などの行動を分析します。
人や動物を「行動」という切り口で、「行動の制御変数」を実験的な手法により、主に環境(独立変数)との相互作用の中に見つけていきます。
「制御変数」とは、相関関係で終らず、因果関係を見つけることです。
「環境との相互作用」とは、行動の“見かけ”ではなくて環境に及ぼす効果、環境が行動に及ぼす効果、つまり、“機能”に注目するものです。
環境をどのように変えれば、行動の頻度が変化するのかがわかるので、望ましい行動を増やしたり、望ましくない行動を減らしたりする方法を考えることができます。
つまり、行動の「原理」や「法則」を導きだす考え方です。
これを、「実験的行動分析(Experimental Analysis of Behavior)」といい、これにより、行動の「予測」と「制御」が可能になります。
例えば、出会いのきっかけ、交際のいきさつを明らかにし、検証したり、被害者と加害者のやり取り(携帯電話やパソコンに保存されているメール文、録音された会話)から被害者の心理的状況の変遷、加害者の思考パターンの特徴などを分析したりすることで、いまの状況、いまの段階が、被害者の身に危険が及ぶリスク、つまり、加害者のストーキングリスク(「行動」)の程度を「予測」し、どのような対応をとることが有効であるか(「制御」)を判断することに役立てることができます。
環境と行動間のこのような分析は、「機能分析(functional analysis)」とよばれ、環境と行動の数量的関係をとり扱う数量的行動分析として、「マッチングの法則」、「行動経済学」、「行動調整理論」などが確立されてきています。
この成果は、人間や動物のさまざまな問題行動の解決に応用されています。
このことを「応用行動分析(Applied Behavior Analysis)」といいます。
この応用行動分析は、発達臨床として、発達障害や挑戦的行動、自閉症スペクトラム障害を持つ人に用いられています。
例えば、「臨床法」の「行動療法(behavior therapy)」は、不安症、恐怖症、PTSD、うつ病、摂食障害などを発症した人たち、自閉症やADHDなど、発達障害や学習障害を持った人たちを、主に「学習理論」にもとづいて治療したり、支援したりするいろいろな方法論に包括的につけられている“総称”で、最近では、「認知行動療法」と呼ばれることが一般的です。
禁煙サポートやソーシャルスキルトレーニングの実施など、生活改善や社会適応の支援も行われます。
他にも、「行動」という切り口で捉えることができるならすべてが対象となることから、一般臨床、医療措置、重篤な精神障害、エイズ予防、老年医学、産業安全、職場活性、学校教育、スポーツなどに活用されます。
スポーツにおける活用例をあげると、いまから50年前、ソビエト連邦(ロシア)のバスケットボールチームで得点力をあげるためにシュミレーショントレーニングを導入するなど、シュートスキルの改善のためのコーチング法に活用されました。
また、刑事ドラマで描かれる『分析官が、「犯罪者プロファイリング」を駆使し、犯人像を絞り込み、事件を解決するシーン』として描かれる「プロファイリング(Offender profiling、criminal profiling)」は、行動科学にもとづいています。
犯罪捜査で用いられる犯罪者プロファイリングでは、犯罪の性質や特徴から、行動科学的に分析し、犯人の特徴を推論していきます。
行動分析学の基本的な“原理”は、「レスポンデント条件づけ(古典的条件づけ、パブロフ型条件づけ)」と「オペラント条件づけ(道具的条件づけ)」の2つです。
例えば、「オペレント条件づけ」にもとづく実験例は、「Ⅰ-A-4-(3)学習した無力感」で説明し、「DV被害者が、なぜ、暴力のある環境から逃れることができなくなるのか」を踏まえて説明しています。
つまり、DV/性暴力被害者や加害者の行動特性を知るうえで、行動分析は有効な手法といえます。
*-2 DV被害支援室poco a pocoの事務局は、東京都23区内ですが、詳細な所在地(住所)については、緊急一時保護施設(行政や民間のシェルター)などと同様に“非公表”です。
事務局の携帯電話番号は、メールでの相談・依頼を受けてから別途通知し、お知らせいただいた携帯電話を事前登録させていただいたのち、電話での対応、カウンセリングがスタートします。
これらは、DV加害者との接触を避け、相談をしている被害者とその援助をする者(アドボケーター)に対する加害行為を防ぐ(加害者との接触そのものを避ける)意図によるものです。
女性センターや市区町村役場など、DV/デートDV被害の相談機関(窓口)では、対応した職員の氏名を告げないのもこうした意図があるからです。
*-3 「ナレッジ」とは、知識・経験・事例・ノウハウなど付加価値のある情報のことです。
*-4 子どもが、家庭内で、両親間のDVを目撃する、つまり、父親と母親の間(あるいは親の交際相手との間)の暴力を目撃したり、聞いたり、察したりすることを「面前DV」といい、『児童虐待の防止等に関する法律』では、心理的虐待となります。
したがって、DV問題には、暴力のある関係性に子どもがいるときには、少なくとも面前DV=心理的虐待被害が存在する、つまり、児童虐待問題として捉える側面があります。
つまり、「家庭内におけるDVと児童虐待は、密接な関係」にあり、DV問題、児童虐待問題のいずれにしても、この“視点(捉え方)”は必要不可欠です。
*-5 DV(デートDV)、性暴力では、多くの男性の被害者がいますが、DV被害支援室poco a pocoでは、DV被害者、性暴力被害者の中で、「女性に限定した支援」を行っています。
なぜなら、第1に、日本の社会システムが男性優位であることから、その対策、対応のあり方の一つひとつ微妙に異なること、第2に、男性ホルモンと女性ホルモンの分泌の違いにより、暴力に対する反応、行動変容のあり方が異なることから、男性対応も女性対応と同じ、一律とならないからです。
*-6 どのようなアプローチで、『レポート(被害の事実と後遺症、その経過)』をとりまとめていくかについては、DV被害支援室poco a pocoの支援活動の概略として、この『note』の2つ目の記事「DV被害支援室poco a pocoとしての活動の経過」にまとめています。
なお、DV/性暴力被害者のアドボケーターとして、『レポート(被害の事実と後遺症、その経過)』をとりまとめるサポートは無償です(有償となると、弁護士法に抵触する可能性があるからです)。
(DV問題における重要な視点、この『手引き』で重視していること)
この『手引き(新版2訂)』では、DV問題における重要な視点を以下のように捉えています。
第1は、いかに親しい関係にあっても、いかなる理由があっても、「本来、対等の関係にある交際相手間、配偶者間において、上下の関係性、支配と従属の関係性を成り立たせるためにパワー(力)が行使されることは、決して許されるものではない」ことです。
国際社会の常識は、「あらゆる暴力行為=人権侵害」と捉えています。
つまり、国際社会の常識は、「いかなる理由があっても、人に危害(暴力)を加えることは、人権を侵害することに他ならない」と理解していることです。
この視点に立つと、あらゆる暴力行為に対して、この“程度”なら「許される」「許されない」、この“程度”なら「耐えられる」「耐えられない」という“線引き”“尺度(基準)”など存在しません。
ここには、「この程度なら許される(大丈夫だろう)」、「一定の条件下(被害者の“態度”“言動”“姿勢”“立場”“服装”“性別”“年齢”“職業”など)であれば、暴力行為は許される」という“解釈”は存在しません。
「国際社会の常識」という認識は、1948年12月10日、賛成48票、反対0、棄権8(ソビエト連邦、ウクライナ、ベラルーシ、ユーゴスラビア、ポーランド、南アフリカ連邦、チェコスロバキア、サウジアラビア)、欠席(イエメン、ホンジュラス)で採択された「人権法の柱石(すべての人民にとって、達成すべき共通の基準)」となる『世界人権宣言(Universal Declaration of Human Rights)』にもとづいています(以上、国名は当時)。
なお、敗戦国である日本が80番目の国連加盟国となったのは、それから8年後の昭和31年(1956年)12月12日であるため、この『世界人権宣言』に賛成票を投じていません。
第2は、暴力のある家庭(機能不全家庭)で暮らし、育った人(被虐待体験(逆境的小児期体験)(逆境的小児期体験)をしてきた人)が、再び、交際相手や配偶者からDV被害を受けるとき、その被害は、日常化、長期化、深刻化しやすく、その関係を断ち切る(別れる、逃げる)のは容易でないことです。
そのため、被害者の心身に及ぶダメージ、つまり、発症したPTSDは重篤化し、その併発症としてのうつ病を発症するなど、その後遺症は重く、長期化します。
第3は、被虐待体験(逆境的小児期体験)によりアタッチメント(愛着形成)の獲得に問題があり、渇望感と空虚感、見捨てられ不安を抱える者が加害行為に及んでいるときには、被害者が暴力のある関係を断ち切ろうとする(別れる、逃げる)とき、「見捨てられ不安」が起因となり、これまで以上の苛烈なDV行為に及んだり、復縁を求める執拗なストーキングに及んだりするリスクが高くなることから、理不尽であっても、被害者の身(命)を守ることを最優先にしなければならない判断(決断)が必要になることです。
第4に、被害者が、DV行為に及ぶ交際相手や配偶者との関係を断ち切る“場面”では、加害者のDV行為、ストーキングについて、被害者自らが、加害者の暴力行為を立証(事実経過を明らかに)しなければならないことです*-7。
その「場面」とは、被害者が、ア)加害者のDV行為で加療を要する傷害(骨折、裂傷、打撲など)を負った傷害事件で、所轄警察署に被害届・告訴状を提出したり*-8、イ)地方裁判所に、『配偶者暴力防止法』にもとづく“保護命令”の発令を求める申立てをしたり、ウ)DV被害を所轄警察署や女性センターに訴え(相談し)、『配偶者暴力防止法』にもとづく“一時保護”の決定を受け、母子生活支援施設に入居したり、エ)家庭裁判所に、「婚姻破綻の原因は、配偶者のDV行為である」と夫婦関係調整(離婚)調停、監護権者指定調停(審判)を申立てたり*-9、オ)家庭裁判所に、「暴力被害により精神的苦痛を被ったとして損害賠償金(慰謝料)」を請求したりする(した)ときです。
このとき重要になるのが、被害者が、自身が受けたDV行為としての暴力の事実と、暴力被害による後遺症の症状を正確に訴えられる(主張できる)かどうかです。
「正確に訴える(主張する)」とは、根拠(裏づけ)にもとづき、暴力被害と後遺症の因果関係を立証できることまでを指します。
とくに、被害者が、被虐待体験(逆境的小児期体験)をしてきて、再び、交際相手や配偶者から暴力被害を受けたときに、被虐待体験(逆境的小児期体験)トラウマ(心的外傷)、暴力の捉え方、トラウマ反応の表れ方が異なります。
このとき、暴力被害の事実や後遺症の症状(精神的に不安定になっていることを含む)を正確に訴える(主張する)ことができず、結果、加害者に有利に働き、理不尽な思いをさせられる事態に陥ることがあります。
加えて、このア)イ)ウ)エ)オ)の「場面」に加え、被害者は、カ)女性センターや市区町村役場のDV被害相談窓口に被害を相談したり、キ)警察にDV被害や性暴力被害を訴えたり、ク)代理人となる弁護士に相談し、依頼したりするときに、繰り返し、DV被害や性暴力被害を説明しなければなりません。
DV被害者、性暴力被害者にとって、何度も被害の事実を説明することは、トラウマを「追体験」することになり、大きな精神的な負担となります。
つまり、被害者は、第3者に被害を口にしなければならない「場面」があるたびに、トラウマを追体験することになり、PTSDの侵入によるフラッシュバックや悪夢、パニックアタックをひき起こし、結果、覚醒亢進(過覚醒)状態に陥り、そのダメージが残る中で、再び、トラウマの追体験を繰り返します。
このことは、被害者に大きな精神的な負担をもたらすだけではなく、PTSDなどの治療を阻害し、精神的に不安定をもたらし、疲弊させるなどの大きなリスクを伴います。
第5は、交際相手や配偶者との関係に子どもが加わるときのDV行為は、子どもの視点に立つと、「面前DV=心理的虐待(虐待行為)」になり、子どもの一方の親が、DV行為としての身体的暴力を受けているときには、その子どもの70%以上が身体的虐待を受けているなど、DVと児童虐待は密接な関係にあること、第6に、この「両親間のDVを目撃する(暴力を見たり、聞いたり、暴力の痕跡を察したりする(面前DV=心理的虐待))」ことは、他の虐待行為とともに、子どもの発達期の脳に大きなダメージが及び、将来にわたり、心身の健康を損なうリスクがあることです。
子どもは、暴力のある家庭環境で暮らし、成長する(被虐待体験(逆境的小児期体験)をして育つ)中で、暴力に順応する考え方の癖(認知の歪み)を身につけ、その認知の歪みによる思考・行動パターンは、将来、いじめ、DV(デートDV)、性暴力、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの加害行為につながったり、逆に、暴力行為の被害者になったり、C-PTSDの自己投薬といわれるアルコール、薬物、ギャンブル、セックスなどに依存したりするリスクを高めます*-10。
第7は、慢性反復的(常態的、日常的)なDV被害は、PTSDの発症、その併発症としてのうつ病、解離性障害、パニック障害などを発症させたり、被虐待女性症候群(バタード・ウーマン・シンドローム)の傾向などの後遺症をもたらしたり*-11するリスクが高く、その中での子育ては、統合失調症、うつ病、双極性障害などの精神疾患者の子育てと同様に、子どもの養育が困難になったり、同じく暴力で心にダメージを負った子どもに不適切な行為に至ったりする(2次加害を及ぼす)可能性があり、同時に、その子どもは、ヤングケアラーとなり得る可能性も高くなります。
そこで、重要になるのは、児童虐待と密接な関係にあるDV家庭を早期に発見し、適切に介入(支援)し、適切な治療につなげることです。
そのためには、複合的で、継続的なシステム(仕組み)としての支援が必要です。
*-7 離婚調停・離婚裁判(民事事件)で離婚を求めたり、『配偶者暴力防止法』にもとづく一時保護の決定や保護命令の発令を求めたり、負った傷害を刑事事件としての立件を求めたりするとき、暴行の状況を説明(立証)するうえで、a)裂傷や鬱血痕の写真を撮ったり、b)病院に行き、-ア)どのようにして骨折、裂傷、鬱血などの傷害を負ったのかという経緯と-イ)「・・週間(・・ヶ月)の加療を要する」と傷害の程度が明記された診断書を受けとっておくことが重要です。
ただし、イ)の診断書は、診断名、どのような治療を行い、どのような処方を行ったのかの記載だけではなく、その診断に至ることなった原因はDV行為、虐待行為であるとの因果関係(裏づけ、根拠)を明記してもらう必要があります。
*-8 「DV行為により加療を要する傷害を負った」として所轄警察署に訴える、つまり、刑事事件とするときには、所轄警察署に「被害届」「告訴状」を提出します。
ただし、「被害届」には捜査の強制力はないので、速やかに捜査にとり組んでもらうには、「告訴状」を受理してもらうことが必要です。
*-9 家庭裁判所に、「婚姻破綻の原因は、配偶者のDVである」として夫婦関係調整(離婚)調停については、「Ⅰ-C-10.夫婦関係調整(離婚)調停、離婚裁判での判決」で詳しく説明しています。
*-10 第6の視点は、この『手引き』の核となるもので、第2部(Ⅱ.虐待(面前DVを含む)の後遺症。子どもを加害者、被害者にしないために)で、詳しく説明しています。
*-11 「PTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状や被虐待女性症候群(バタード・ウーマン・シンドローム)の傾向などの後遺症」については、「Ⅰ-B-7.被害者に見られる傾向-暴力被害の後遺症という視点-」で詳しく説明しています。
(この『手引き』で重視していること)
この『手引き(新版2訂)』では、児童虐待と密接な関係にあるDVとはどのようなものか、子どもが暴力のある家庭環境で育つということはどういうことかを理解するうえで、以下の5点を重視し、繰り返し説明しています。
第1は、DV行為としての暴力の“本質”は、「本来、対等である夫婦の関係性を破壊し、上下の関係性、支配と従属の関係性を成り立たせたり、その関係性を維持したりするためにパワー(力)を行使する」ことです。
つまり、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力行為のすべては、この視点に立ち、人と人との“関係性”で認識します。
第2は、交際相手や配偶者など、近しい人に対して加えられる暴力行為には、ⅰ)衝動的な暴力で、いわゆる「破壊的行動障害(行為障害)」「反抗挑戦性障害」と診断し得る特性による暴力行為、ⅱ)自己愛が高く、反社会性が高いサイコパス的な特質(サイコパス(精神病質者、反社会性人格障害)*-12、自己愛性人格障害、MNPD(悪性の自己愛性人格障害)、パラノイア(偏執病、被愛妄想)の特性を持ち、支配性の高い暴力行為、ⅲ)ボーダーライン(境界性人格障害)の感情の激しさ、人やものごとを白か黒かにわける極端さ、自己否定と他者不信、怒りと恨みの激しさがトリガー(ものごとをひき起こすひきがね)となり、執着する暴力行為、ⅳ)パラフィリア(性的倒錯・性嗜好障害)を背景とする性的サディズム、性的マゾヒズム、ペドファリア(小児性愛)、窃視症、窃触症(さわり魔、痴漢)、露出症にもとづく暴力行為、ⅴ)統合失調症の幻視(幻聴幻覚)、双極性障害の躁状態(性的高揚)にもとづく暴力行為、ⅵ)ADHD(“2次障害”としての自己正当化型ADHDを含む)の「多動性」や「衝動性」、アスペルガー症候群*-13などの「コミュニケーション・社会性の障害」による“特性”が、結果として、DV(デートDV)やハラスメントなどとなる暴力行為、ⅶ)高次脳機能障害、ジストニア、レビー小体型認知症、レム睡眠行動障害、農薬・PCBなど汚染化学物質、覚醒剤や違法ドラックなどの薬物、アルコールの摂取による神経障害、低血糖症(ペットボトル症候群)などを起因となる暴力行為、ⅷ)家父長制を背景にもとづく家族観、男尊女卑、内助の功、良妻賢母という保守的な概念、価値観、考え方にもとづく暴力行為、ⅸ)(外国人との交際、結婚であるとき)人種や国に対する偏見、差別、侮蔑・卑下意識(価値観)にもとづく暴力行為、ⅹ)アメリカの保守基盤である「キリスト教的家族主義」の信仰、イスラム教の厳格な戒律などの宗教観(信仰)、新興宗教やカルト集団の教え(教義)に準じる暴力行為など、さまざまなタイプ(属性)があり、その違いの見極めが、第1の関係性の背景にある被虐待体験(逆境的小児期体験)をしているのか、していないのかを判断するうえで重要であることです。
ⅰ)ⅱ)ⅲ)ⅳ)に加え、ⅴ)の一定数、ⅵ)の自己正当化型ADHDに共通しているのは、被虐待体験(逆境的小児期体験)をし、思春期後期(12-15歳)、青年期(前期15-18歳/18-22歳)に達し、デートDV、DVの加害者になったことです。
この『手引き』では、このⅰ)-ⅹ)の暴力行為に及ぶ者、つまり、DV加害者の属性として捉えています。
このⅰ)-ⅹ)の属性の中で、第1の「人と人の関係性」に準じると、「同じ暴力行為であっても、DV行為としての暴力に該当しない」と考えられるのがⅴ)とⅶ)の一部です。
「DV行為に該当しない」と考えられるⅶ)は、投薬などの医療的な治療が必要です。
また、ⅱ)ⅲ)ⅳ)など、“認知の歪み”が軽度ではなく、その人そのもの(人格)となっているとき、「認知行動療法」をとり入れた『加害者更生プログラム』や精神的な医療は意味を持ちません(無力です)。
DV加害者属性ⅰ)-ⅹ)の人物特性、行動特性を正確に把握することは、別れ話が起因となる復縁を求めるストーキングに及ぶリスク、そのときのストーキングが最悪の事態を招くリスクを判断するうえで重要で、また、その人のものごとの捉え方や考え方(価値観/概念)という“認知”にアプローチする『加害者更生プログラム*-14』の受講が効果的なのか(意味があるのか)の判断には、必要不可欠なアプローチといえます。
この第1、第2の視点は、この『手引き(新版2訂)』の「第1部(Ⅰ)暴力に怯え、支配される関係を終わらせるために。」の「Ⅰ-A.DVの規定と加害者のタイプ・特性、思考行動パターンを知る」の「Ⅰ-A-1.DVとは、どのような暴力をいうのか(*)」、「Ⅰ-A-2.加害者属性による判断。暴力の後遺症によるDV -加害トラウマ。世代を超えてひきつがれる暴力-(*)」、「Ⅰ-A-3.第5のDV行為。別れ話が発端となるストーキング(つきまとい)*」、「Ⅰ-A-4.傷めつけ、被害者を負い込むマインドコントロール術*」、「Ⅰ-A-5.関係を断ち切るために必要(ⅰ)。加害者に共通する行動特性の理解」、「第3部(Ⅲ) DV環境下にある子どもの早期発見と支援、欠かせない母親へのケア」の「Ⅲ-27.DV加害者更生プログラム-「ケアリングダッド」を実施するうえでの原則-(*)」、「Ⅲ-28.『加害者更生プログラム』の受講効果の真意*」の“主”となります。
第3は、第2のⅰ)-ⅹ)のタイプ(属性)の特性を知ることは、DV行為としての暴力を受けた被害者の異なる後遺症の表れ方を知るうえで重要であることです。
例えば、ⅵ)のアスペルガー症候群の障害の“特性”がDV(デートDV)となるとき、その被害者は、一般的なPTSDの症状の回避の傾向をあまり示さず、「カサンドラ症候群」をいう傾向を示します*-15。
なぜなら、アスペルガー症候群の“特性”としてのDV行為は、支配を意図していないことから、恐怖の覚え方が違うからです。
仮に、アスペルガー症候群の交際相手や配偶者からの暴力行為で、被害者が恐怖を覚え、PTSDの回避行動が認められるときには、加害者の交際相手や配偶者が、被虐待体験(逆境的小児期体験)をしている(2次被害を受けている)か、あるいは、被害者が被虐待体験(逆境的小児期体験)をしているかのどちらかです。
また、ⅷ)家父長制的で男尊女卑、内助の功、良妻賢母という保守的な価値観の父母や祖父母の言動や態度、ふるまいに嫌悪感を覚えている人と、この背景のもとで暴力を加えられ、嫌悪感に加え恐怖心を覚えている人とは、後遺症の表れ方、ものごとの捉え方、考え方など認知のあり方などはまったく異なります。
このように、DV加害者属性のⅰ)-ⅹ)を正確に理解することは、暴力を受けた被害者が、その暴力を加える交際相手や配偶者に対し、恐怖の覚え方が異なり、結果、後遺症の表れ方も違ってきます。
このことは、被害者の後遺症に対する治療のあり方も一律ではなく、それぞれ違ってくることを意味します。
この第3の視点は、この『手引き(新版2訂)』の「Ⅰ-B.逃れることの難しさと暴力被害による深刻な後遺症を知る*」の「Ⅰ-B-6.デートDV。別れられず、暴力が長期化する原理」、「Ⅰ-B-7.被害者に見られる傾向-暴力被害の後遺症という視点-*」の“主”となります。
第4は、子ども(胎児期を含む)が、暴力(面前DV、過干渉・過保護、いき過ぎた教育(教育的虐待)、しつけ(教育)と称する体罰、スケアード・ストレートなどを含む)のある家庭環境で暮らし、育つことが、脳の発達に与える影響とともに、その環境に順応するために身につけたものごとの捉え方、考え方、どのような価値観、モノサシ(判断基準)を形成し、それがどのような行動パターンとなり、その後の対人関係、人生に、どのような影響を及ぼすのかを知ることです。
そのためには、胎児期を含め、人の脳がどのように発達し、その発達段階ごとに、暴力被害のダメージがどのように及ぶのかを正確に知ること、加えて、「C-PTSD(複雑性心的外傷後ストレス障害)」、「アダルト・チルドレン」、「発達性トラウマ症候群」が示す症状や傾向を正確に知るためには、暴力(ストレス)が、「ASD(急性ストレス障害)」、「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」、その併発症としての「うつ病」を発症したり、腹痛など「身体化(身体表現性障害)」をもたらしたりする科学的(医学的)なメカニズムに対する理解は必要不可欠です。
第5は、子どものいるDV被害者にとって、その事実は、ツラく、苦しく、やるせない現実となり得ることですが、第4の理解の“前提”となるのが、子どもが、両親間のDV行為としての暴力を見たり、聞いたり、察したりする状態は面前DVとなり、それは、子どもに心理的虐待を加えていることになることです。
子どもが、ア)幼少期に頻繁に両親間のDVを目撃する(面前DV=心理的虐待)と、視覚野の一部が約16%(平均4.1年間DVを目撃して育った人の平均値)萎縮し、イ)幼少期に暴言(否定、非難、侮蔑、卑下するなどのことばの暴力)による虐待(心理的虐待)を受けると、強い自己否定の気持ちを植えつけ、会話や言語を司る「聴覚野」の一部(上側頭回灰白質)が14.1%拡大します。
この「視覚野」が萎縮すると、他人の表情を読めず、対人関係がうまくいかなくなり、「聴覚野」が萎縮すると、聞こえ方、会話やコミュニケーションがうまくできなくなります。
つまり、夫婦間にDV行為があり、その夫婦間に子どもがいるときには、その子どもは等しく、視覚野、聴覚野に深刻なダメージを及ぼす(児童)虐待行為(心理的虐待)を受けていることなります。
この「第5」の理解は、子どもの暴力による後遺症に対する治療には時間的な期限があることから、それは1日も早く、暴力のない安全で、安心できる環境で、治療をはじめる必要があることを知ることにつながります。
ベストは、胎児期、コルチゾールの曝露による脳形成期の中枢神経系の発達に影響を及ぼすリスクを考えると、妊娠5週目までに、暴力のない安全で、安心できる環境で妊娠期を過ごし、出産・育児にあたることです*-16。
この第4、第5の視点は、「ひとりでも多くの子どもたちが、家庭内で、ドメスティック・バイオレンス(以下、DV)を目撃するなどの暴力被害で傷つかないようにしたい」、「暴力のある家庭で暮らし、育つ子どもが、DV問題の最大の被害者である」、「少しでも世代間の暴力(DV・虐待)の連鎖を食い止める一役を担いたい」というDV被害支援室poco a pocoの活動テーマの“骨格”であると同時に、被虐待体験(逆境的小児期体験)をしてきた子どもが背負う十字架の数々にフォーカスしたこの『手引き(新版2訂)』の「第2部(Ⅱ)虐待(面前DVを含む)の後遺症。子どもを加害者、被害者にしないために」の“主(本論)”となるものです。
この「第2部(Ⅱ)」で扱うテーマは、「Ⅱ-13.脳と子どもの発達*」、「Ⅱ-14.トラウマと脳*」、「Ⅱ-15.慢性反復的トラウマの種類(児童虐待分類)と発達の障害*」、「Ⅱ-16.暴力のある家庭で育った子ども。発達段階で見られる傾向-乳幼児の心を育むのは、暴力のない安全で、安心できる環境-*」、「Ⅱ-17.思春期・青年期の訪れとともに(*)」、「Ⅱ-18.抑圧。凶器の刃となり、人を殺める」、「19.PTSDとC-PTSD、解離性障害*」、「Ⅱ-20.パラフィリア(性的倒錯・性嗜好障害)」、「Ⅱ-21.ACという考え方と人格障害(パーソナリティ障害)」です。
この“本論(第2部(Ⅱ))”で示される「被虐待体験(逆境的小児期体験)がもたらす後遺症」の数々は、子どもがいる親(DV被害者)にとっては、「知らない方がよかった」と感じるほどの残酷な事実となり得るものです。
*-12 「自己愛と反社会性が高い」人物の特性については、「Ⅱ-21-(11)人格障害(パーソナリティ障害)とは」で、A群(奇妙で風変わりな行動:妄想性人格障害、統合失調質人格障害(シゾイド)、統合失調型人格障害(スキゾタイバル))、B群(演技的で移り気な行動:演技性人格障害、自己愛性人格障害、反社会性人格障害、ボーダーライン(境界性人格障害))、C群(不安や抑制を伴う行動:回避性人格障害、依存性人格障害、強迫性人格障害)として、それぞれの人格障害(パーソナリティ障害)を詳述しています。
加えて、「サイコパス」については、「Ⅰ-A-2-(5)サイコパス(精神病質者、反社会性人格障害)」で詳しく説明しています。
*-13 「自己正当化型ADHD」「アスペルガー症候群」については、「Ⅰ-A-2-(3)発達障害などの“障害”の特性が結果として暴力となる」、「Ⅱ-23-(8)自己正当化型ADHD・アスペルガー症候群とAC」で詳しく説明しています。
*-14 『加害者更生プログラム』については、「Ⅰ-B-8-(7)危険な「きっと、加害者更生プログラムで変わってくれる」との考え」、「Ⅳ-27.DV加害者更生プログラム。「ケアリングダッド」を実施するうえでの原則」、「28.『加害者更生プログラム』の受講効果の真意」において詳しく説明しています。
*-15 「カサンドラ症候群」については、「Ⅰ-B-7-(5)カサンドラ症候群」で事例を踏まえて詳述しています。
*-16 詳細は、「Ⅱ-13-(10)脳の機能を発達させないリスク-暴力のある環境で育つ子どもの脳では、なにがおきているか-*」で詳述します。
・被虐待体験(逆境的小児期体験)をしてきた子どもに対する治療という視点
一方で、「暴力のある家庭環境で暮らし、育っている子どもの治療には、時間的な期限がある」ことから、この事実を正確に知ることは重要です。
そこで、重要となるのが、以下の6つの視点です。
第1は、妊娠5週目以降の母体のDV被害は、胎児に濃度の高いコルチゾールなどの曝露をもたらし、結果、胎児の「中枢神経系」の発達が損なわれ、出生後、ADHD、自閉スペクトラム症、LD(学習障害)などの発達障害、さまざまな精神疾患を発症する高いリスクを負うことです。
しかも、胎児が女児であるときに限り、母体のコルチゾールの濃度が高いと、古代脳(古皮質)の「扁桃体」が絡む神経ネットワークの結びつきが強くなり、また、出生後、抑うつ的な行動が増えるという結果がでています。
この事実は、特に重要で、胎児期に濃度の高いコルチゾールに曝露した女児は、同じ状況で生まれた男児に比べ、生まれながらにして、強い不安、恐怖を覚えやすく、将来、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、うつ病、不安障害、パニック障害などの精神疾患に発症しやすくなることを意味します。
第2は、子どもが受ける虐待(面前DV、過干渉・過保護、いき過ぎた教育(教育的虐待)、しつけ(教育)と称する体罰、スケアード・ストレートを含む)、貧困、差別・排除、いじめがもたらす強烈なストレス(脅威・危機)は、先の「第5」で指摘したような脳の一部の発達を阻害し、脳自体の機能や神経構造に永続的にダメージを与えることです。
第3は、その永続的なダメージは、胎児期以降、脳の発達段階に準じてゆっくりと致命的なダメージとなりながら、少しずつ症状や傾向として表れ、思春期前期(10-12歳)を前にした8歳-9歳で、自己と他の境界線があいまいなことを起因とする問題が顕著な姿を表すことです。
第4は、2歳10ヶ月までに脳の主要となる部分(90%)できあがる中で受ける虐待は、3-4歳ごろに育つ「海馬」が深刻なダメージを受けることです。
「海馬」は、大脳辺緑系に位置し、長期の記憶、空間学習能力にかかわる部位で、虚血(血流量が不足し、血液が十分に供給されない)に非常に脆弱です。
また、ストレスホルモンのコルチゾールが長期間にわたり分泌されると、「海馬」の神経細胞は破壊され、萎縮し、そのことが、PTSD、その併発症としてのうつ病の発症原因となります。
そして、「海馬」は、PTSDの発症者の発症率が高いとされるアルツハイマー型認知症の病変部位です。
つまり、乳幼児期に受けた「海馬」のダメージは、PTSDの発症、その併発症のうつ病の発症、そして、アルツハイマー型認知症の発症など、人生全般に及ぶ影響をもたらします。
第1-第4の視点にもとづくと、胎児期(妊娠5週目以降)-2歳10ヶ月まで期間の1日も早く、(妊娠初期の)女性に対するDV行為と子どもに対する虐待を発見し、速やかに介入(支援)し、1日も早く治療につなげることが重要です。
第5は、第4の時期で、子どものいるDV被害にあっている女性、被虐待体験(逆境的小児期体験)をしている児童を発見できず、介入(支援)に至らず、また、就学する(6歳に達する)まで発見し支援につなげることができなかったとしても、小学校就学時の6歳、あるいは、後遺症が顕著な姿を表しはじめる7-8歳(言語を司るブローカー野の発達が止まる9歳まで)までに、虐待を発見し、速やかに適切な治療につなぐことができたとき*-17には、「脳梁(9-10歳で境界性人格障害(パーソナリティ障害/ボーダーライン)や解離性障害の発症原因となる)」、「前頭前野(感情や理性を司り、14-16歳でダメージを受ける)」の障害を軽減できる可能性があると信じることです。
このとき、子どもの支援者であり、治療の伴走者となる親は、少しでも早く適切な治療につなげ、同時に、第3者である専門機関の助けを借りて、子どもに対し、脳の発達過程で獲得できなかった脳機能を補う方法について順を追って学ばせる覚悟が必要です。
なぜなら、被害を受けた時間に比例するように、多くの時間をかけて習得させる(学び直しをする)必要があるからです。
ベストの判断は、交際相手や配偶者から最初の暴力を受けたとき、直ちに別れることで、その機会を逃したときには、妊娠が判明したとき、直ちに別れることです。
それができなかったとしても、できる限り、第4-第5にフォーカスすることです。
子どもの親であるDV被害者が、暴力に怯えない、安全な環境で、暴力で傷ついた自身と子どもの治療にとり組むのを妨げているのは、ひとつは、日本国民には、「いかなる理由があっても、すべての暴力行為は許されない」との人権意識が生活の一部になっていないことを起因として、知識がないことです。
もうひとつは、日本社会は、女性で、子どものいるDV被害者が離婚し難く、しかも、シングルマザー(ひとり親世帯)として生活を再建し難い社会システムになっていることです。
子どもの発達段階にフォーカスすると、対人関係が、親やきょうだいと過ごす日々から、友人と共通の楽しみ、塾や習いごと、クラブ活動などのコニュニティへと社会的な広がりを見せはじめるのは、思春期前期(10歳-12歳)前の「8-9歳」からです。
「8-9歳」は、2人称を獲得しはじめる時期です。
ところが、アタッチメントの獲得に問題があり、母子分離ができず、自己(一人称)と他(二人称)の境界線があいまいなまま成長していると2人称の概念がわからず、自分は他の人たちとは違うと自覚しはじめ、対人関係のトラブルがこれまでとは異なるレベルで表面化してきます。
親として、子どもの手が少しずつ離れ、仕事に就きやすいと考え、12歳の子どもが中学校に進学するタイミングで離婚を考え、それを子どもに切りだすときには、子どもが、離婚を考える親の思惑に意を反する言動、態度、ふるまいに至ることがあります。
日々、暴力の恐怖に怯え、「助けて!」、「早く、逃げようよ。」と願い続けていた子どもにとって、親が離婚を決めたタイミングは、「なにをいまさら!」と、既に過去のことです。
思春期前期の10-12歳になると、親の都合での転居に伴い、小学校を転校したり、友人たちが進学する中学校とは別の中学校に進学したり、まったく土地感もなく、知っている人もいない中で生活したりしなければならないことに対し、強い不安感、そして、強烈な拒否反応を示すことがあります。
例えば、このとき、第1子がこの思春期前期(10-12歳)、中学校進学前の小学校5-6年生で、第2子が7-8歳、小学校2年以下だと、転居し転校したくない第1子と、転居し転校してもいい第2子、子どもの意志が異なる事態が生じます。
このとき、同じDV被害者である親と第1子との関係において、再構築し難い軋轢、亀裂、破綻が生じるリスクが高まります。
加えて、このとき、DV被害者である親には、隠し切れなくなった顕著な後遺症としての症状や傾向、行動パターンが表れていることが少なくなく、一方の、第1子、第2子においても、自己と他の境界線のあいまいさが招くトラブルが表れはじめています。
しかし、DV被害者の母親は、自分のことが精一杯で、子どもの表れた変化に気がついていないことが少なくありません。
面前DV下にある子ども、つまり、被虐待体験(逆境的小児期体験)をしてきた子どもは、思春期後期(12歳-15歳)の後半から「青年期前期(15歳-18歳)にかけて、a)人との適切な距離感がわからず葛藤し、苦悩の日々を送ったり、b)「消えたい」衝動からの自傷行為(リストカット、OD(大量服薬)、過食嘔吐など)に及んだり、c)幼少期からの頭痛、腹痛に加え、起立性調節障害やうつ症状に伴う体調不良が顕著となったり、いじめ被害がきっかけとなったりしてひきこもりになったり、d)家出をきっかけとして宿カレなどからの性暴力被害やデートDV被害を受けたり、e)アタッチメントのやり直しを求めて、自分が乳幼児期だったときの父母と年齢が近い年齢の異性と交際したり、不特定多数との異性と性的関係を持ったり(援助交際、パパ活を含む)、f)アルコール、薬物を乱用したり、ギャンブルに依存したりするようになったり、g)暴力沙汰を起こすなど非行行為が目立つようになったり、g)自身の言語化できなかった不可思議な感覚(離人感、金縛り、幻覚、幻聴など)がスピリチュアルと結びつくなど、占い、新興宗教やカルトに傾倒したりするなどの行動が顕在化しはじめ、「青年期後期(18歳-22歳)」にかけて、h)不安障害(パニック障害)、統合失調症、解離性障害などの精神疾患(人格障害(パーソナリティ障害)を含む)を発症しやすい状態になり、i)自死リスクも高まったりします。
このa)-i)の背景にあるのは、いうまでもなく、被虐待体験(逆境的小児期体験)です。
DV被害者である親が、子どもを連れて家をでて、やっと生活の再建をはかれると考えていた矢先に、子どもにa)-i)の問題が次々表面化してくると、「暴力のある家庭環境に留まるのも地獄、家をでるのも地獄」となり得ます。
DV被害者である親が、この事実を受け入れるのは容易ではありません。
あまりにも残酷な事実であることら、その現実から逃げだしたい思いに駆られることがあります。
このとき、その現実から逃げだしたいDV被害者である親もまた、ア)後遺症としてのPTSD、その併発症としてのうつ病、身体化の症状などで心身ともに疲弊し、精神的に極限状態になったり、イ)ア)を起因として、仕事に就けなかったり、仕事を続けられなかったりして経済的に困窮したり、破綻に陥ったり(結果、性風俗業界に身を置くことを含む)、ウ)アルコールや薬物、ギャンブルに依存したり、エ)出会い系サイトなどで異性に心の拠り所を求めたり(性風俗業界のリクルーティングで、働くことを強要されたり、写真や動画を撮られ、脅され、管理売春させられたり(性的搾取されたり)を含む)、オ)新興宗教やカルト、スピリチュアル、占いに傾倒したりするリスクが高まります。
子どもに対し、親やコミュニティが被虐待体験(逆境的小児期体験)をさせなかったり、子どもが胎児期・乳幼児期のときに親が家をでることができていたりしたときには、こうした社会病理といえるa)-i)の問題、それに派生する新たな親の問題ア)-オ)は、劇的に改善できます(減少します)。
日本社会では、現在も、「しつけ(教育)と称する体罰(虐待行為)」を国民の70-60%が容認しています。
この状態は、明治29年(1896年)に制定された『民法』で、親による子どもに対する懲戒(民法822条)を認めたことに由来し、126年間、6-5世代の子育てで「しつけ(教育)と称する体罰(虐待行為)」を続けてきた結果です。
日本社会では、この社会病理といえる深刻な状況に気づき難く、表立って論じられることはありません。
しかし、この視点に立たなければ、日本で生まれ、生活する子どもは、これからもひき続き、被虐待体験(逆境的小児期体験)をしながら成長し、大人になります。
いまできることは、第1に、被虐待体験(逆境的小児期体験)をしている(きた)子どもに対し、できる限り後遺症を残さないために、1日も早く発見し、介入し、治療につなげること、第2に、DV被害を受けている女性に対する早期に介入し、速やかに支援につなげること、第3に、子どものいる親は、虐待行為はいうまでもなく、まず、子どもに対するいっさいの「しつけ(教育)と称する体罰」をしないことです。
DV被害を受けている女性、被虐待体験(逆境的小児期体験)をしている(きた)子どもに対し、どのタイミングでかかわるかにより、どのような治療が必要となり、どのような支援が必要となるのかは違ってきます。
被虐待体験(逆境的小児期体験)をしている(きた)子どもに対する治療に欠かせないのは、生活をともにする親の心(精神)が安定していることです。
したがって、子どもと同じように、暴力の後遺症を抱えている可能性の高い親に対する治療はとても重要です。
また、支援する者(転居などに伴い子どもとかかわることになる学校園の教職員を含む)、治療する者には、上記のような葛藤を抱えたり、症状や行動が表面化したりしている子どもは、大人を信じる、信用することができなくなっている“前提”でかかわることが必要です。
大人がかかわろうとしてきた子どもは、この人は信じるに足りる大人かどうかを確かめるために、嫌がること、怒らせること、甘えることなどの“試し行動(リミットテスティング)”を嫌というほど繰り返します。
これらの「リミットテスティング」は、「子どもが、相手(大人)の時間を奪い、自分に尽くしてくれる時間だけを求める行為」とことばを置き換えるとわかりやすいと思います。
したがって、この子どものリミットテスティングに対して、「いま、忙しいからあとで。」ということばは、「自分を拒絶、拒否した」と受けとることを理解する必要があります。
そして、子どもは、この「いま、忙しいあとで。」のことばの「あとで。」は存在しないことは身を持って知っています。
この被虐待体験(逆境的小児期体験)をしてきた子どもの「リミットテスティング」を理解し、どのように対応したらいいのかなど専門的なトレーニングを受けていない人が、上記のような葛藤を抱えたり、症状や行動が表面化したりしている子どもとかかわると、子どもの信頼、信用を得ることは困難となり、結果、子どもの治療に支障をもたらします。
また、被虐待体験(逆境的小児期体験)をしてきた子どもの一定数は、カラカラに乾いたスポンジのような渇望感、心の中にぽっかりと空いた大きな穴のような空虚感、底なし沼のような寂しさ(見捨てられ不安)を埋めようとする、つまり、親から得られなかったアタッチメントの再獲得を、自身が乳幼児期だったときの父母と年齢が近い大人の異性に求めようとすることがあります。
この行動が、援助交際、パパ活、ホスト依存につながります。
*-17 両親間に身体的暴力がある60-70%の家庭では、子どもも身体的暴力(虐待)被害を受けていると報告されています。
・被虐待体験(逆境的小児期体験)をしてきた子どもの支援者に必要不可欠な資質
また、就学前後の性的虐待被害を受けてきた(いる)子どもには、齢に見合わない強い性的関心や言動を示したり、例えば、保健室の性教育資料などに異様に関心を示したり、それを先生や友だちに見せて露骨なことば遣いをしたりする「性化行動」が見られることがあります。
このとき、先生に甘えてきて、自分の股間をすりつけたり、相手の股間や胸に強い関心を示したりすることがあり、子どもの「性化行動」を受けた教師や支援機関の職員が、その行為に触発されてしまい、性的行為に及ぶ「2次加害」に至ることもあります。
こうした性的虐待被害を受けてきた(いる)子どもが、かかわった大人からの「2次被害」を受けないためにも、子どもの支援にかかわる者(子どもが通学する学校園の教職員を含む)、子どもの治療にかかわる者は、子どもを性的対象としないこと、被害を受けた子どもの症状、特性、傾向について十分な知識を持っていることが必要です。
性的虐待を受けた(ている)子どもは、そのときには気づけなくても、数年、10-15年とかなりの時間をおいて、自分の行動は「性化行動」であったり、トラウマの「再演(再犠牲者化/投影性同一視)」、「性的自傷」であったことを気づいたり、知ったりします。
一方で、ずっと知らないままの人もいます。
自己と他の境界線があいまいなまま成長し、人との距離感がわからず、極端にペタッとへばりつくように接してくる子ども、極端に離れて近寄ろうとしない子どもは、「ふわふわと地に足がついていない危うさ」を抱えています。
被虐待体験(逆境的小児期体験)をしてきて、上記のような状況にある子どもとかかわる人(支援者)は、こうした危うさを抱えている子どもをターゲットに、性的な関係を求めたり、管理売春(ソープランド、AVのスカウトを含む)の世界に招き寄せたりする大人から守る役割もあります。
ところが、被虐待体験(逆境的小児期体験)をし、自己と他の境界線があいまいなまま成長した人が支援(教育や指導者として相談に応じる機会のある人も含む)にまわる(かかわる)とき、相談する人、助けを求める人と支援者という境界線はあいまいになりやすく、不適切な性的な関係に至るリスクがあります。
しかも、一度、不適切な性的な関係になると、より支配(独占)するための性的関係を強いるリスクもあります。
特に、権威・権力志向が高いときには、この傾向はより顕著になります。
上下関係を利用したセクシャルハラスメント、グルーミング、エントラップメントを利用した性暴力をきっかけとした継続的に性的な関係を強いるようになります。
支援界隈に留まらず、被害者や子どもとかかわることの多い学校園の教職員、塾や習いごと、クラブ・サークル活動の教師や指導者とその範囲を広げると、無意識下で、上下関係が表れやすく、相談(不平や愚痴、共通の趣味などを話すなどを含む)などがきっかけとなり、不適切な性的な関係が生じやすいことが知られています。
このときの成功体験は「うまみ」となりやすいことから、その「うまみ」が忘れられず、意図的に、問題を抱える女性や子どもに近づき(グルーピング)、同様の行為を繰り返します。
典型的な例は、カトリック教会、特に孤児院や学校、神学校など司祭や修道者、施設関係者と子どもたちが、共同生活を送る施設で繰り返された性的虐待です。
グルーミングを利用し、恋愛関係と思い込ませ、そのまま結婚に至る典型的な例は、女子高の教師と生徒、指導者と生徒の結婚です。
問題は、交際中、結婚後も対等な男女の関係ではなく、教師や指導者と生徒の関係性、つまり、上下の関係性が継続しやすいことです。
このまま継続された上下の関係性は、意図せずとも、DV行為としての暴力が生じやすくなります。
つまり、教師や指導者と生徒との結婚、上司と部下の結婚では、生徒や部下をリスペクトし、生徒や部下と対等な関係性を構築していない限り、構造上、DV行為としての暴力が生まれやすくなります。
加えて、顕著なアタッチメントの問題を抱える被虐待体験(逆境的小児期体験)としてきた人は、強く承認欲求を求め、自身が望む高い評価が得られないとき、「こんなに頑張っているのに報われない」と苛立ち、驕り、慢心があると、「自分はこれぐらいのことはしてもいい(当然、許される(報われるべきだ))」との考えに至り、不正行為に及ぶリスクがあります。
そこで、少し、被虐待体験(逆境的小児期体験)をし、自己と他の境界線があいまいな成長してきた人が、支援(援助)や教育に携わるときのリスクマネジメントに触れておきます。
支援する者と支援を受ける者との間にも、構造上、無意識下で、上下の関係性、支配と従属の関係性になりやすいことから、不適切な性的な関係、ハラスメントが生じやすいという前提で、その仕組みを厳格に整える必要があります。
被虐待体験(逆境的小児期体験)をし、自己と他の境界線があいまいで、「見捨てられ不安」を抱える人が、自身の被虐待体験(逆境的小児期体験)を当事者として語るのとは異なり、被害者支援にまわるときには、自身の被害と関係するさまざまな感情を自覚し、専門的なケアを受けているのかなどのリスクマネジメントは重要です。
それは、被虐待体験(逆境的小児期体験)をし、自己と他の境界線があいまいで、「見捨てられ不安」を抱える人自身が、無力感、恥・屈辱感、劣等感、嫌悪感、罪悪感、負い目・後ろめたさ、哀しみ、寂しさ、不安、怒り、憎しみ、悔しさ、嫉妬心、喪失感・妬み、憧れ、羨望、期待、渇望感、空虚感などの感情を人(第3者)に隠していたり、秘めていることに無自覚であったりして、その感情に対し専門的なケアしていないときのリスクです。
例えば、「子どものときに安定感が形成されずに育った母親に「乳児部屋のおばけ」という現象がおき、それが、虐待行為につながる」とセルマ・フライバーグが指摘したように、保育(ベビーシッターを含む)、看護、支援の現場では、これまで、自分がして欲しかった支援をあたり前のように受けている人(乳幼児を含む)に対し、ことばで説明ができないさまざまな感情が沸きあがり、虐待やハラスメントにつながることがあります。
被虐待体験(逆境的小児期体験)としてのトラウマに加え、幼児期に抱いたさまざまな感情は、発達過程の中で、専門的なケアを受けていないとき、人生のどこかのタイミングで、突然、激しいトラウマ反応が表出する可能性があります。
重要なことは、組織として、被虐待体験(逆境的小児期体験)をし、自己と他の境界線があいまいで、「見捨てられ不安」を抱える人が、被害者支援にまわるときのリスクを正しく評価し、自身も自覚することです。
ここには、感情労働となる援助者、教育者が精神的に疲弊し、燃え尽きることを防ぐケア、サポートの仕組みが含まれます。
被害者や子どもとかかわる支援機関、保育・教育機関で生じやすい不適切な性的な関係を防ぐときの視点は、「厳格である」ことで、「少しでも油断、隙(綻び)、過信が入る余地をなくす」ことです。
では、日本では馴染みのない(敢えて避けている)「ペドファリア(小児性愛)」の視点で、この問題に触れておきます。
ペドファリアは、「13歳未満の小児」を対象とします。
しかし、同じペドファリアであっても、「幼児期期(3-6歳)」、「学童前期(6-10歳)」、「思春期前期(10-12歳)」のいずれかを主ゾーンとするように、この時期の体型が重要なファクターとなります。
つまり、ペドファリアは、「幼児体型を好む者」、「学童児体型を好む者」、「第2次性徴前の体形を好む者」に分かれ、この主ゾーンはほぼ破られることはありません。
そのため、欧米社会では、小児を狙ったペドファリアの犯罪が発生したときには、前歴リストの中から、対象となったゾーンに沿った捜査が進められます。
ただし、生物学的な区分(4大人種)として、モンゴロイド(黄色人種群)のアジア系の人々は、ネグロイド(黒色人種群)、コーカソイド(白色人種群)、オーストラロイド(黒褐色人種群)の人々に比べ幼く見られるため、時として、ペドファリアの対象は15-16歳まで広げる必要があります。
このペドファリアではないけれども、性的経験のない、あるいは、性的経験の浅い年齢(15-20歳前後)だけを主ターゲットとする捕食者もいます。
また、ゲイやレズビアンであることを隠し、異性と交際したり、結婚したりすることがあるように、ペドファリアであったり、性的経験のない、あるいは、性的経験の浅い年齢だけを主ターゲットとする捕食者であったりすることを隠し、大人の異性と交際したり、結婚したりしていることもあります。
このとき、家庭内で起きるのが、子どもに対する性的虐待、しかも、性交を伴う深刻な性的虐待です。
性交を伴うレイプの74.4%は、顔見知り、つまり、よく知っている人による犯行で、そのうち、父母・祖父母・叔父叔母・いとこが11.9%となっています。
つまり、性交を伴うレイプのうちの11.9%が、性交を伴う性的虐待ということになります。
また、いまから41年前の1981年(昭和56年)、シアトル・タイムズ紙が、「あなたのお嬢さんのクラスにこの次出席するとき、不特定の15人の女の子に目を留めてください…少なくとも1人、おそらく、2-3人は、近親姦の犠牲者であると考えて差し支えありません。」と報じています(令和4年(2022年)10月現在)。
つまり、家庭内での性的虐待は、特別なことではなく起き得る、しかも、かなり高い確率で起きている前提に立つ必要があります。
同様に、被害者支援(カウンセリングを含む)、保育・教育の場においても、不適切な性的な関係(性暴力)は起き得る前提に立ち、対策を講じ、厳格な仕組みをつくりあげる必要があります。
このとき、日本では馴染みのないことばかも知れませんが、性的サディズム、窃視症、性的マゾヒズム、ペドファリア(小児性愛)、窃触症(さわり魔、痴漢)、露出症などの「パラフィリア」の視点、つまり、パラフィリアが示す「性的興奮のパターン」は、第1に、思春期前の幼児期・学童期の前半の6-8歳ころまでには(小学校1-3年生までには)、既に発達を終える(確立される)ということ、第2に、その性的興奮のパターンがいったん確立されると、その多くは一生続く」という視点で捉えることが必要不可欠です。
「思春期前の幼児期・学童期の前半の6-8歳ころまでには(小学校1-3年生までには)、既に発達を終える(確立される)」というのは、「6-8歳以前(乳幼児期、学童期前期)に、性的興奮がパターン化されるほど、繰り返し性的虐待など心的外傷体験している」ことを意味します。
つまり、このパラフィリアが見せる「性的興奮のパターン」の発達には、①不安、または、早期の心的外傷が正常な精神性的発達を妨げていたり、②性的虐待を受けるなど、本人の性的快楽体験を強化する強烈な性体験に早期にさらされることにより、性的興奮の標準的パターンが他のものに置き換わっていたりする。
さらに、③「性的興奮のパターン」として、性的好奇心、欲望、興奮と偶然に結びつくことによって、そのフェティッシュが選択されるなど、しばしば象徴的な“条件づけ”の要素を獲得しているといった3つのプロセスが関係しています。
つまり、人は、就学前の0-6歳の間に、被虐待体験(逆境的小児期体験)による刺激を「うまみ(快感)」として、脳の快感中枢が「性的興奮のパターン」として認識し(覚え)、確立すると、それは一生続くことになります。
被虐待体験(逆境的小児期体験)をしていない子どもは、こうした「パラフィリア」としての「性的興奮のパターン」を身につけません。
したがって、リスクマネジメントとして、被虐待体験(逆境的小児期体験)をし、自己と他の境界線があいまいで、「見捨てられ不安」を抱えている人が、支援(カウンセリングを含む)にまわったり、保育・教育に携わったりするときには、個人活動はいうまでもなく、組織に所属していてもひとりで対応するのではなく、必ず複数のチームで対応するなどの厳格な仕組みが必要です。
「ひとりで対応できないことは、信用・信頼されていない」のではなく、「間違いを防ぐための仕組み(システム)」です。
この視点は、日本社会に欠落しています。
被虐待体験(逆境的小児期体験)をし、自己と他の境界線があいまいで、「見捨てられ不安」を抱えている人が、専門的なケアを受け、自身の特性と傾向を正しく学んでいないときには、被害者支援(カウンセリングを含む)に携わったり、学校園(低学年の)教職員、塾や習いごと、クラブやサークルの指導者になったりすることは、自らの意志で避ける(諦める)勇気が必要です。
この「第5」の視点に必要不可欠な「治療には時間的な期限がある」ことに対し、重要な視点としてあげた「第1-第4」は、この『手引き(新版2訂)』の「第3部(Ⅲ)DV環境下にある子どもの早期発見と支援、欠かせない母親へのケア」の「Ⅲ-22.慢性反復的なトラウマ体験からの回復」、「Ⅲ-23.DV被害者の抱える心の傷、回復にいたる6ステップ」、「Ⅲ-24.暴力被害女性と子どものためのプログラム -コンカレントプログラム-」、「Ⅲ-25.虐待する親の回復の視点-MY TREEペアレンツ・プログラム-」、「Ⅲ-26.性暴力被害者支援の連携体制-SART(性暴力被害支援チーム)-」、「第4部(Ⅳ)学校・福祉施設の現場で、児童虐待・DVとどうかかわるか」の「Ⅳ-29.児童虐待の定義」、「Ⅳ-30.初期対応としての緊急性の判断」、「Ⅳ-31.性的虐待への初期対応」、「Ⅳ-32.子どもの心理的援助-トラウマ反応について学ぶ-」、「Ⅳ-33.児童相談所への「通告」と連携」、「Ⅳ-34.子どもや家庭に対する主な関係機関」、「Ⅳ-35.通告後の児童への対応。子どものケア、回復のプロセス」、「Ⅳ-36.児童虐待・DV事件、保護者の苦情の捉え方」、「Ⅳ-37.母子生活支援施設の機能と役割」、「Ⅳ-38.児童相談所における児童青年期のメンタルヘルスの問題」、「Ⅳ-39.援助者(支援者)・教職員のメンタルケア」の“主”となります。
・被害者が専門機関につながり難いその背景とつながることを避ける被害者
「子どもの治療には、時間的な期限がある」ことを知るうえで重要となる視点の第6は、自分だけで解決しようと考えず、速やかに、専門機関とつながり、サポートを受けることです。
しかし、日本社会では、第3者に助けを求めることは容易ではなく、大きなハードル(障壁)があります。
心理的障壁(防衛機制)のひとつは、日本社会は、家庭内での心の問題(家庭に暴力があること、精神疾患の家族がいたり、ひきこもりの家族がいたりすることなど)を世間に知られないように、必死に隠そうとする傾向があることです。
心理的障壁(防衛機制)のもうひとつは、いまから約2070年前、シーザー(ユリウス・カエサル)が、「人は、自分の考えに固持しがちで、自分の都合のよいように世界を見る傾向があることを知る。」、「人間はみな自分の見たいものしか見ようとしない。」と指摘したことに真意があります(令和4年(2022年)10月現在)。
デートDV・DV被害を受けている人が、交際相手や配偶者と別れたくない(離婚したくない)と強く思っているときには、子どもの訴え、「助けて!」のサインは耳に入らず、子どもの体調不良と暴力の関係性に気づくことは容易ではありません。
ときには、ツラく苦しい現実から目を背けるために、敢えて、気づかないようにふるまい、いまの関係性に固執します。
この状況は、被虐待体験(逆境的小児期体験)をしてきて「見捨てられ不安」を抱える人が、再び、交際相手や配偶者からDV行為を受けたときに認められる傾向のひとつです。
カラカラに乾いたスポンジのような渇望感、心の中にぽっかりと空いた大きな穴のような空虚感、底なし沼のような寂しさを伴う「見捨てられ不安」は、人に固執(執着)し、自分の意志だけでは手放すことができません。
そのため、交際相手や配偶者と別れない(離婚をしない)方法はないか、交際相手や配偶者が暴力を加えなくなる方法はないかと必死に考え、その情報を必死に探し、自分が望む(自分の期待に応えてくれる)情報・ノウハウを提供してくれる人や機関とつながろうとします。
敢えて、「DV環境下に留まる危険性とその影響を踏まえて、DV問題解決の最善策は加害者と別れる(離婚する)こと」と考える人や支援機関は避けます。
中には、交際相手や配偶者からの苛烈な暴行被害を受け、その傷みと恐怖に耐え切れず、警察署に助けを求めたDV被害者が、『配偶者暴力防止法』に準じ“一時保護”の決定を受け、「母子生活支援施設(母子棟、行政のシェルター)」に入所したとき、「施設の職員が、私は別れるつもりはないのに、別れさせようとする!」、「携帯電話をとりあげ、連絡をできないようにする!」と非難し、「一時保護は、自らの意志によるものではない」として、交際相手や配偶者が待つ家に率先して戻っていくことがあります。
私は、こうした一時保護を受け、直ぐに、家に戻る行為を6度繰り返しているDV被害者を担当する福祉事務所の職員に、「その被害者の心理を教えて欲しい」と相談されたことがあります。
DV被害者は、交際相手や配偶者から苛烈な暴力を受けた瞬間は、二度と暴力は加えられたくないと思っていても、必ずしも加害者と別れる(離婚する)ことを第1に考えているわけではありません。
これは、DV被害者のひとつの姿です。
日本で、DV被害者支援に携わる人たちの一定数は、画一的に、「DV被害者が、DV加害者から逃げない(別れない)のは、共依存だから」と認識しています。
しかし、それは、ごく一部のDV被害者像に過ぎません。
ごく一部のDV被害者像に固執していると、DV問題の本質の理解を妨げることになります。
DV問題の本質の理解がないと見落としかねないのが、DVと密接な関係にある子どもに対する虐待行為です。
被虐待体験(逆境的小児期体験)をしてきた人が、再び、交際相手や配偶者から暴力行為を受けるとき、暴力に順応するために身につけてきた考え方、行動パターンが前面にでることが少なくないことです。
それは、被虐待体験(逆境的小児期体験)をしてきた人のプライオリティ(優先順位)に表れます。
常に、暴力行為に及ぶ交際相手や配偶者の顔色をうかがい、自身に暴力行為が及ぶのを避ける(回避する)ために、暴力行為に及ぶ交際相手や配偶者の機嫌を損ねないように、自ら率先して、意に添うことをしたり、喜ばせたりします。
このことは、虐待行為に及んだ親と同様に、絶対的な力を持つ交際相手や配偶者に、従順で、異を唱えることなく、服従し続けることを意味します。
時に、この恐怖と痛みを回避する、つまり、被害者が自分の身(命)を守る言動や行動は、子どもを犠牲にすることがあります。
「子どもを犠牲に」とは、自身に向けられる交際相手や配偶者からの暴力を回避するために、交際相手や配偶者からの暴力の矛先を「子どもに向ける」、つまり、子どもを身代わりすることです。
それは、子どもを生贄に差しだすことです。
このことは同時に、自身に向けられるDV被害が凄まじく、耐え切れなくなった分岐点といえます。
捕虜などに繰り返される苛烈な拷問は、傷みに耐え切れずに仲間を売るように、徹底的にからだと心を傷みつけますが、慢性反復的(常態的、日常的)に繰り返されるDV(デートDV)、児童虐待の被害者は、捕虜と変わらないほどからだと心を傷みつけられ、被害者が覚えるストレスの程度は、戦地からの帰還兵と同等といわれます。
平成30年(2018年)3月、東京都目黒区で船戸結愛(ゆあ)ちゃん(当時5歳)の虐待死事件が発生し、5歳児が書いたと思えないような「反省文」が、連日、ニュースで報道された児童虐待事件がありました。
母親(妻)は、帰宅した父親(夫)に、その日に、「娘は、なにができなかったか」など詳細に報告していました。
このことが、父親から娘に対するしつけ(教育)と称する苛烈な虐待行為のモチベーション(動機)のひとつになっていました。
この帰宅した夫に、その日のことを報告するという妻(娘の母親)の行動の背景にあったのが、日常的に繰り返された夫から暴力により植えつけられた恐怖心でした。
夫からDV被害を受けている妻が、夫に対し、夫の子どもへの虐待行為を止める言動やふるまいは、夫の意に反する(逆らう)ことから、それがきっかけとなり、妻が苛烈なDV被害につながります。
「俺のやることに口だしをするな!」、「でしゃばったマネをするな! 俺の教育方針に文句があるのか!」、「お前は、俺のやり方に従っていればいい。役立たずが!」といった罵倒とともに、苛烈な暴力を加えられます。
DV被害者にとって、自身の苛烈なDV被害(恐怖と痛み)を回避するには、その“きっかけ”をつくらない、つまり、DV加害者による子どもへの虐待行為を止めない、虐待行為を批判しない、ただ見て見ぬりをして嵐が過ぎ去るのを待ちます。
時には、自らが率先して、DV加害者の意図する言動・ふるまいに参加する、つまり、子どもに対する虐待行為に加担し、従順である(運命共同体)ことを示すことが必要です。
結果として、この言動・行動バターンは、子どもに対する虐待行為を容認したり、虐待行為を正当化したりする“働き”を持ちます。
この“働き”は、DV被害者が「暴力行為は不当である、許されるものではない」と声をあげる(意に反する、逆らう、口ごたえする)ブレーキとなる(障壁となったり、躊躇させたりする)のを心理的に妨げます。
この自身の行動、つまり、回避行動を正当化できなければ、心の安定を保つことができず、精神の破綻に向かうリスクが高まります。
その結果、「お父さんはあなたのこと(将来)を思って、…」などということばを伴って、父親からの子どもに対する虐待行為を正当化し、そのことばを繰り返すことで、DV被害者である母親も「自分は間違っていない」と心に刻み込みます。
夫の怒りの琴線に触れる前に、子どもの火種を解決しておかなければならないという強迫観念は、子どもに過剰に干渉するか、夫の代わりに率先して虐待行為に及ぶか極端な選択に及びます。
後者の状況は、DV被害者である妻が、DV加害者であり、子どもに対し虐待行為に及ぶ夫に「子どもに手をあげないで! それは、虐待よ。」などと口にすると、「お前だって、子どもに手をあげているじゃないか!」と指摘(非難)されることで、口を噤(つぐ)まざるを得ない状況をもたらします。
つまり、自ら逃げ道を閉ざすことになりますが、“いま、この瞬間”の傷みと恐怖を回避する行動には、合理的選択を伴いません。
なぜなら、PTSDの症状のひとつの「回避行動」は、つまり、外敵(脅威)に出会うと生存本能として「闘うか、逃げるか(Fight or Flight)」の状況判断は、「前頭前野」での思考、判断でもたらされるものではなく、すべての脊椎動物に備わる古代脳のひとつ「扁桃体」の働きによるものだからです。
つまり、DV被害者の行動を理解するには、「Ⅰ-B-7-(4)暴力の後遺症としてのPTSD」で述べる人の脳がストレスを覚えると、どのような脳内物質が分泌され、どの部位に、どのような反応をもたらすのかといったメカニズム、そして、それぞれの部位はどのような役割を担うのかなどの最低限の知識が必要です。
一方で、「私も子どもに手をあげている」という“罪悪感”は、第3者に、配偶者からの自分へのDV行為、夫(父親)の子どもへの虐待行為を相談することを思い留まらせ、第3者に助けを求める機会を逸しさせます。
DV被害者が、自身のふるまいがブレーキとなり、自身に対するDV行為、子どもに対する虐待行為について口を閉ざしている状況は、加害者にとって、第3者に告げ口(家の秘密をばらす)したり、逃げだしたりする心配(怖れ)がない、つまり、被害者をずっと自分のもとに留めておけるので、好都合です。
DV被害者である妻が、DV加害者である夫とともに、子どもに虐待行為を加える状況は、仲間として運命共同体となり、それに反する行為は「裏切り」となります。
つまり、「いうことに従わないと、お前は、どういうことになるかわかっているな!」という“暗黙の了解”のもとで、敢えて「お前もやれ!」と命じたり、指示したりしなくても、自ら率先して応じられるように、意図的に、仕込まれた行為です。
DV被害者が限界まで追い込まれる精神状況は、自ら体験しない限り理解することは難しいかも知れませんが、この理解に役立つのが、「Ⅰ-A-4.傷めつけ、被害者を負い込むマインドコントロール術」で述べる「新潟少女監禁事件」、「北九州連続監禁事件」、「東京・綾瀬女子高生女子高生コンクリート詰め殺人事件」、「北海道・東京連続少女監禁事件」のような監禁・虐待事件で、これらの監禁・虐待事件の理解に役立つのが、ミルグラムの「アイヒマン実験」、つまり、「権威者への服従実験」です。
日本で起きた凄惨な殺人事件を例にとると、「伊予市17歳少女殺人事件」では窪田恵が、「堺市傷害致死・死体遺棄事件」では岩本孝子が、「尼崎連続変死事件」では角田美代子が、「北九州連続監禁殺人事件」では松永太が、古くは、「連合赤軍山岳ベースのリンリ事件」の森恒夫(初公判前に東京拘置所で首を吊り自殺)、永田洋子(脳腫瘍の手術を受けた22年後、死刑執行されることなく多臓器不全で死亡)などが、この「権威者」にあたり、DV(デートDV)加害者の交際相手や配偶者、虐待加害者の親は、この「権威者」にあたります。
この「権威者」の言動や態度、ふるまいを理解するには、新興宗教やカルト集団などで用いられるマインドコントロールの技法を正確に知る必要があります。
この理解にもとづくと、児童虐待(その環境下でのきょうだいと間で)、いじめ(加害者が、観衆、傍観者を仲間にとり込むとき)、(教師や指導者などによる)体罰(教師や指導者がターゲットにしている児童に対し、他の児童がという構図で)、ハラスメント(経営者や上司がターゲットにしている社員に対し、他の社員がという構図で)などの暴力行為、いじめと同じ構図で、窃盗、恐喝、集団レイプ、オレオレ詐欺、悪徳商法などで、程度の差はあれ、同様の状況が意図的につくられていることがわかります。
つまり、この行為は、グループ、組織にとり入れ、グループ、組織から離れられなくする常套手段です。
確かに、船戸結愛ちゃん虐待死事件での母親は、子どもに対して虐待行為をしたり、見て見ぬふりをしたりした当事者ですが、その背景にあるのは、夫からの苛烈な暴力があり、PTSDの主症状である回避行動が結果として虐待行為になっています。
この認識に立つことができれば、この事件の主要因は、「夫からのDV行為による恐怖に支配されている状況」となり、最悪の事態に至る前に、警察、女性センター、保健センター、福祉事務所が主となり、児童相談所、保育園などと連携し、この状況をとり除く(母親と娘を父親から離す)ことができていれば、子どもに対する虐待行為はなくなり、結果として、船戸結愛ちゃんは亡くならなかった可能性がでてきます。
このとき、児童虐待事案(『児童虐待防止法』『児童福祉法』の適用)として、子どもを一時保護し、父親と母親から離す対応ではなく、DV事案(『配偶者暴力防止法』の適用)として、一時保護として、母親(妻)と子どもを「母子生活支援施設」などに入居させることで、父親と離し、双方に適切な治療につなげる(一定期間、母親と子どもを離し、専門的な治療を実施したあとで生活をともにさせる(母親にPTSD、その併発症としてのうつ病などの後遺症が表れている中で、子どもの世話や治療は困難という考えで、一定期間、治療に専念してもらう配慮)を含む)という視点が必要でした。
こうしたケースは珍しいことではなく、児童虐待の一定数に認められます。
したがって、児童虐待案件では、ミスリードを防ぐためには、密接な関係にある配偶者間のDV行為の存在にフォーカスすることは重要です。
このように、DV事案では、ア)(子どもがいるとき)児童虐待の視点、イ)被害者(交際相手や配偶者、子ども)の後遺症の症状とその治療のあり方に対する視点、ウ)被害を受けると、人はどういう心理状態に陥り、どういう行動に至るのかといった視点、エ)別れ話がきっかけとなり、復縁を求めるストーキングリスクの分析と評価の視点、オ)『配偶者暴力防止法』に準じ一時保護を求め、「母子生活支援施設」に入所後、どこで、どのように生活の再建をはかっていくのかといった視点、カ)家庭裁判所における「夫婦関係調整(離婚)調停」や「監護権者指定調停(審判)」で、どのようにDV行為や虐待行為を立証していくのかといった視点、キ)そのDV事案や児童虐待事案は日本特有の問題を背景にしているのか、そうでないのかといった視点など、さまざまな視点が存在することから、それぞれの視点に併せて、正確で、科学的な根拠に裏づけられた知識(情報)が必要です。
・日本のDV問題や児童虐待問題にとり組む姿勢の背景(歴史観)
DV問題や児童虐待問題は、その国の政府が、第2次世界大戦後の77年間、その対策として、どのようにとり組んできたのかが顕著に表れます(令和4年(2022年)10月現在))。
ここには、その国で生活する国民の意識が深く表れます。
いま、日本は、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力(人権)問題に先進的にとり組んできた欧米諸国と比べると、50年-25年ほど遅れています。
その背景になっているひとつは、「G7の中でもっとも遅れている。」、「G7の中で、これほどまでに後ろ向きな国は他にない。」と指摘される『家族法(民法)』です。
日本は、世界で唯一、「夫婦同姓(民法750条、および、戸籍法74条1号)」と法で定め、令和2年(2020年)には、95.3%の夫婦が「夫の名字」を選択しています。
このことは、第2次世界大戦後、家父長制はなくなったものの、「家に嫁ぐ」「嫁に行く」などの考えなど、その概念は、いまだに生活様式として深く根づき、その概念と深くかかわる「内助の功」「良妻賢母」という“保守的”な価値観は、多くの日本国民に支持されています。
この“保守的”な価値観は「男尊女卑」につながり、日本社会における「ジェンダー観(男女の役割)」に大きな影響を及ぼし、日本特有の問題を生じさせています。
そのひとつが、明治29年(1896年)の制定から令和4年(2022年)10月14日に削除されるまでの126年間、「親の子どもに対する懲戒権(民法822条)」です。
「懲戒」とは、不正、または、不当な行為に対して制裁を加え、懲らしめることで、「懲戒権」は、親は子どもに対し、その権利を有することです。
「懲戒権(民法822条)」が削除される2年前の令和2年(2020年)4月1日に『児童虐待防止法』が改正され、体罰が禁止されました。
しかし、懲戒権の残る限り、その効果は限定的なままでした。
日本政府は126年間、親は、「家父長制」にもとづき、子どもに対し、「しつけ(教育)と称して体罰(主に身体的虐待)」を加えるお墨付きを与えてきたわけです(令和4年(2022年)10月現在)。
つまり、日本社会では、5-6世代の多くの子育ての一定数において、親は、子どもに対し、「しつけ(教育)と称する体罰」を加え続けてきました。
また、日本の『社会保障制度』は、家族を優遇する制度設計になっています。
いうまでもなく、家族を優遇する考えの根底にあるのは、家父長制です。
このことが、女性が離婚し難くなったり、ひとり親世帯(シンブルマザー)が貧困に陥りやすくなったりする大きな要因となっています。
こうした世界に例のない日本特有の問題は、「なぜ、DV被害者は、DV加害者から逃げたり、DV加害者と別れたりできないのか?」に看過できない影響を及ぼしています。
DV問題、児童虐待問題と同じテーマであったとしても、被害者の立ち位置と支援する者の立ち位置、しかも、それぞれ、“保守的”な価値観を支持する人と指示しない人では、ものごとを捉えたり、考えたりする価値観、モノサシ(判断基準)はまったく異なります。
また、同じDV被害者であっても、被虐待体験(逆境的小児期体験)をしてきた人とそうでない人、子どもがいるDV被害者と子どもがいないDV被害者では同じ立ち位置ではなく、しかも、子どもがいても、子どもの数、年齢、性別によっても、同じ立ち位置ではありません。
加えて、支援する人の知識と経験が、いまの日本より50年-25年先を行く欧米諸国の知識、ナレッジに更新されているのか、更新されずに50年-25年遅れたままなのかは、ひきだしの多さにつながり、それは、ストーキングリスクの判断や助言に大きな差となって表れます。
DV問題や児童虐待問題に携わるとき、その暴力行為だけの問題(知識)に留まらず、法律、税、福祉行政、社会保障制度、就労や賃金、後遺症(医療)、歴史的背景にもとづく地域性などの知識に加え、支援(援助)者としての技能など幅広く、奥行きのあるひきだしが必要です。
DV問題や児童虐待問題と、歴史的背景にもとづく地域性などは関係ないように見えますが、とても重要な知識です。
・新政府軍、明治政府がつくりあげたストーリー、3つの嘘
ⅰ)江戸幕府を倒した新政府軍、その後の明治政府は、国民に討幕した正当性を示すこと、加えて、富国強兵を進める国家キャンペーンとして、嘘のストーリーをつくりあげ、その嘘のストーリーは、いまだに、日本社会に息づいています。
江戸時代には、「士農工商」という身分制度は存在せず、明治政府は、意図的に、「われわれは、身分制度をなくし、身分の差をなくした」という嘘のストーリーをつくりあげ、自分たちのなし得た功績を称えました。
「四民平等」は、中国の古典で使われていたもので、そこでは、「士農工商の四民は石民なり」とあり、「石民」とは「国の柱石となる大切な民」、つまり、「国を支える職業」「すべての職業」「民衆一般」といった意味です。
「士農工商」は平成12年(2000年)度以降、「四民平等」は平成17年(2005年)度以降の教科書からその記述は消えました。
教科書から削除された理由は、存在していない、事実でない、つまり、嘘・つくり話だからです。
明治政府が「国民皆兵(明治6年(1873年)の徴兵令発布)」を進め、欧米の国々に対抗するため、経済を発展させ、軍隊を強くする「富国強兵」を目指し、一気に「軍国化」を進めるためには、この教えを自分たちに都合のいいストーリーに仕上げる必要がありました。
この国家キャンペーンを先導したのが、佐賀藩出身で日本の法典編纂を主導した江藤新平です。
このときにつくられた学制、兵制、税制は、現代の基礎となっています。
ⅱ)明治政府が目指した「国民皆兵」「富国強兵」には、学制、兵制、税制改革は不可欠で、そのうえで大きな役割を果たしたのが「家父長制」です。
その「家父長制」のもとで、武家社会の思想の「男尊女卑(儒教思想)」、武家の女性に求められた「内助の功」「良妻賢母」を浸透させました。
つまり、男性は皆兵、女性は家を守るという家庭内での役割の明確化にすることで、国民に「国民皆兵」「富国強兵」のために一致団結、士気高揚を目論んだわけです*-18。
江戸時代の総人口約3000万人中、武家の人口は、「7%」の210万人でした。
明治政府は、僅か「7%」の武家社会の思想の「男尊女卑(儒教思想)」、武家の女性に求められた「内助の功」「良妻賢母」という価値観を、軍国化を進める中で、国家プロジェクトとして大々的なキャンペーンを通して、国民に浸透させていきました。
結果、家父長に絶大な権力が与えられました。
第2次世界大戦の敗戦後、「家父長制」の廃止は、家父長にとっては、絶大な権力を奪われたことになります。
そして、“保守的”な価値観を強く支持する人たちにとっては、家父長に意を唱えたり、意に添わなかったりした妻や子どもに対し「懲罰(しつけ(教育)と称する体罰)」を加える(DV行為、児童虐待行為、性暴力行為)ことを禁止する法律(配偶者暴力防止法、児童虐待防止法、強制性交等罪、強制わいせつ罪の成立要件の緩和)を制定したり、支援する仕組みを構築したりすることは、本来、認めたくないことです。
そのため、女性と子どもが獲得してきた権利(法などの整備を含む)を疎ましく、鬱陶しく、忌々しく思っている“保守的”な価値観の持ち主たちが、その「権利」を奪い、かつての権威(特権)をとり戻そうと政治的に強く働きかけています。
そのひとつが、「共同親権」です。
そもそも明治政府は、イギリスのアヘンマネーを背景に、薩長の下級武士が皇室を「錦の御旗」に政治利用し、徳川幕府から政権を奪取したクーデターを経て構築されました。
その後も日本政府とアヘンは結びつきが深く、満州国*-19の財政を支え、しかも、機密費の主な資金源になりました。
日本政府は、満州や蒙古各地でケシを栽培させ、ペルシャなどから密輸した大量のアヘンを満州国に流し込みました。
アヘンは膨大な利益を生み、軍の謀略資金となりました*-20。
この「アヘン密売」で絶大な権力を得たとされるのが、安倍晋三元総理の祖父で、満洲国総務庁次長(当時)、その後、昭和の妖怪と呼ばれ、統一教会(現、世界基督教統一神霊協会)と連携して自主憲法制定運動やスパイ防止法制定運動に尽力した岸信介元総理です。
昭和43年(1968年)、統一教会(現、世界基督教統一神霊協会)は、“反共産主義”を掲げる政治団体「国際勝共連合」を創設し、「国際勝共連合」は、岸信介元首相、自民党右派、戦後最大のフィクサーと呼ばれた児玉誉士夫、日本財団の創始者である笹川良一と深く結びついていました。
そのため、「自由民主党」が進める憲法改正、同性婚の反対などは、「国際勝共連合」の政治理念と一致しています。
このことは、「自由民主党」の考え(思想)は、カルトの統一教会(現、世界基督教統一神霊協会)の考え(思想)と一致していることを意味します。
この憲法改正などの動きを加速させるきっかけとなったのが、平成15年(2003年)9月、安倍晋三が幹事長に就任し、平成16年(2004年)4月、自民党史上初の全国的な候補者公募を実施(このとき、公募に合格し、当選を果たしたのが、「共同親権制度」推進をはかる柴山昌彦である)するなど、「憲法改正に賛成する」といった意に添う人物を登用しはじめたことです。
「安倍チルドレン」と呼ばれる平成24年(2012年)の総選挙で初当選した自民党議員119人の2回生議員は「魔の2回生」「魔の3回生」と呼ばれ、さまざまな問題をひき起こしました。
岸信介が「アヘン密売」で得た膨大なマネー、統一教会(現、世界基督教統一神霊協会)」を母体とする政治団体「国際勝共連合」との関係は、岸信介、佐藤栄作(総理/実弟)、安倍晋太郎(外相/長女の夫、安倍晋三の父)、岸信夫(防衛相/安倍晋三の実弟)と3世代にわたり、日本政治の中枢を担い、4世代目として、岸信夫の長男である岸信千世が衆議院議員に当選するなど、過去の話ではなく、いまに続く話です。
そして、この統一教会(現、世界基督教統一神霊協会)を母体とする政治団体「国際勝共連合」を支援母体とするのが、平成22年(2010年)4月に結成された「大阪日本維新の会(現.日本維新の会)」で、地方議員、国会議員と議席数を拡大させています。
国民会議と神道政治連盟、統一教会(現.世界平和統一家庭連合)と深い関係にある「自由民主党」の保守派閥に属する安倍晋三が銃弾に倒れたあと、祖父の岸信介元総理以降、「自由民主党」と統一教会(現.世界平和統一家庭連合)の深い関係が明るみにでると、「日本はカルト国家になった」と嘆く人々が表れましたが、その解釈は的外れで、日本は、明治政府以降、一貫してカルト国家で、安倍晋三元総理が、「自由民主党」の幹事長になってから、より強固なカルト国家として突き進んでいると解釈するのが妥当だと思います。
在任日数の1位は安倍晋三の3188日(第2次2012年12月26日-2020年8月24日の2822日)と8年半に及び、その間、安倍チルドレンとともに、「日本維新の会」は台頭し続けています)、2位は桂太郎(長州藩)の2886日、3位は佐藤榮作(長州藩)の2798日、4位伊藤博文(長州藩)の2720日、5位は吉田茂(土佐藩)の2248日、6位は小泉純一郎(薩摩藩)の1980日、7位は中曽根康弘の1806日、8位は池田勇人の1575日、9位は岸信介(長州藩)の1241日、10位は原敬(盛岡藩)の1133日で、上位4人は「長州藩」で9位の岸信介の在任日数を加えると9645日(26年5ヶ月、明治18年(1885年)以降137年の1/5(19%))を占め、「岸家」の在任日数は実に7277日(19年11ヶ月、戦後77年の1/4(25%))に及んでいます。
安倍晋三元首相が銃弾に倒れたあと、朝日新聞が、令和4年(2022年)8-9月に実施した「都道府県議の他、国会議員、知事ら3333人を対象に教団との接点の有無やその内容などを尋ねたアンケート」に対し、都道府県議は9割にあたる2314人が回答し、292人(12.62%)が統一教会(現、世界基督教統一神霊協会)と接点を持っていました。
令和5年(2023年)4月9日、同4月23日の地方統一選挙において、カルトの統一教会(現.世界平和統一家庭連合)との接点を認めていた都道府県議で、立候補した228人のうち206人(90.35%)が当選しています。
落選したのは僅か22人です。
また、同選挙の結果、「日本維新の会」の全国の自治体の長と地方議員が非改選も含めて774人になりました。
投票(指示)するという視点に立つと、日本国民は、カルト教団の統一教会(現.世界平和統一家庭連合)を受け入れていることになります。
日本国民が、カルト教団である「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」を母体とする政治団体「国際勝共連合」の深い関係にある「自由民主党」の保守派に加え、「日本維新の会」に拒否反応を示さず、受け入れてしまうのには、理由があります。
なぜなら、日本は、明治政府以降、カルト国家だからです。
カルト国家に馴染み過ぎて、拒否反応を示すことができないのです。
この「日本は、明治政府以降、神話国家(カルト国家)」というのが、明治政府(新政府軍を含む)の3つ目の嘘、つくり話です。
ⅲ)大日本帝国(江戸時代末期(幕末)に外交文書に使用されて以降、終戦から2年経過した昭和22年(1947年)まで使用された日本国の国号)は、神話に基礎づけられ、神話に活力を与えられた「神話国家」です。
例えば、古代ギリシャより語り伝えられ、多くの神々が登場し、愛憎劇を繰り広げる物語の「ギリシャ神話」に基礎づけられ、神話に活力を与えられた国家建設と置き換えてみたらどうでしょうか?
その神々が発したことばが、『第日本帝国憲法』や『教育勅語』に使われていたら、あなたはどう思いますか?
「ギリシャ神話」は、「ローマ神話」の体系化と発展を促進し、古代ギリシャの哲学や思想、ヘレニズム時代の宗教や世界観、キリスト教神学の成立など、多方面に影響を与え、西欧の精神的な脊柱のなっていき、中世を経て、ルネサンス期、近世、近代の思想や芸術にとって、「ギリシャ神話」は“霊感(「神により、息吹きだされた」の意)”の源泉となりました。
この「ギリシャ神話」は、ギリシャ市民の教養となり、いまでも、ギリシャの小学校では、歴史教科のひとつになっています。
この視点に立つと、ギリシャ市民の教養としての神話、日本市民の教養としての神話は似通っていますが、決定的な違いは、日本市民は、その教養が「神話」にもとづいていることを認識していないことです。
しっかり教養として身につき、浸透しているが、神話とは認識していないことが、日本社会の危うさを示しています。
では、肝心の日本の神話の話です。
江戸幕府を倒した新政府軍のスローガンは「神武天皇の時代に戻れ!(神武創業)」でした。
「天照大神(あまてらすおおみかみ)の神勅」を抜きに、『大日本帝国憲法』と『教育勅語』の文面は成り立ちません。
「神武天皇」とは、「多くの神々を統合した日本国の創始者」とされていますが、実在した人物ではなく神話です。
江戸時代まで、京都御所にあった天皇家の仏壇(御黒戸(おくどろ))には、神武天皇の位牌はなく、神武天皇を含む初期の天皇たちは、天皇家の祖先供養の対象になっていませんでした。
つまり、突如として、天皇家に「神武天皇」が表れたのは、明治政府以降です。
「天照大神の神勅」とは、天照大神が孫の瓊瓊杵尊らに下した「天壌無窮の神勅(葦原千五百秋瑞穂の国は、是、吾が子孫の王たるべき地なり。爾皇孫、就きて治らせ。行矣。宝祚之隆えまさむこと、当に天壌と窮り無かるべし。)、「宝鏡奉斎の神勅(吾が児、此の宝鏡を視まさむこと、当に吾を視るがごとくすべし。与に床を同くし殿を共にして、斎の鏡となすべし。)」、「斎庭(ゆにわ)の稲穂の神勅(- 吾が高天原に所御す斎庭の穂を以て、亦吾が児に御せまつるべし。)」の“3つの神勅(三大神勅)”に加え、同段で天照大神が臣下の天児屋命・太玉命に下した「侍殿防護の神勅(願はくは、爾二神、また同じく殿の内に侍ひて、善く防ぎ護ることをなせ。)」、「高御産巣日神の下した神籬磐境の神勅(吾は則ち天津神籬た天津磐境を起樹てて、まさに吾孫の御為に齋ひ奉らむ。汝、天児屋命・太玉命、宜しく天津神籬を持ちて、葦原中国に降りて、また吾孫の御為に齋ひ奉れと。)」を加えた「五大神勅」のことをいいます(『日本書紀』の天孫降臨の段)。
日本軍将兵は、古代の軍事氏族である「大伴氏(天忍日命(あめのおしひのみこと)の子孫)」になぞらえられていました。
「天忍日命」とは、日本の建国神話「神武東征神話」で、神武天皇と東征に同行した軍隊である久留郡を率いて活躍した武将です。
「自由民主党」の保守派閥と深い関係にある国民会議と神道政治連盟にとって、日本軍将兵を祭る「靖国神社」は特別な意味を持ちます。
日本軍将兵が神(天忍日命)であることは、日本の精神医療のあり方にも大きな影響を及ぼしました。
陸海軍病院などの一部を除き、日本の精神科医療において、PTSD研究が致命的に遅れたのは、神の子孫である日本軍の将兵は、特異な精神疾患とされた「PTSD(当時「砲弾ショック」呼ばれていた)」を発症してはいけないのです。
つまり、日本では、「砲弾ショック(PTSD)」の存在は隠され続けたのです。
「砲弾ショック(PTSD)」は存在しないので、治療は必要がないのです。
そのため、日本国内におけるPTSD研究は、欧米諸国から遅れることになりました。
いまだに、PTSD発症者は、専門医につながり難いだけではなく、PTSDの症状や傾向に理解のない精神科医による不適切な治療がおこなわれたり、2次加害として、心ないことばを投げつけられたりすることが少なくありません。
また、「親の子どもに対する懲戒権(民法822条)」は、明治29年(1896年)の制定から令和4年(2022年)10月14日に削除されるまでの126年間、日本政府がお墨付きを与えてきたわけですから、被虐待体験(逆境的小児期体験)をしてきた人に対する治療、つまり、C-PTSD、解離性障害などの治療体制も整備されていません。
軍や国民学校(昭和16年(1941年)3月、「国民学校令」を公布し、初等科6年、高等科2年の8年を義務教育)で、体罰が横行したのは、薩摩藩の“郷中”、会津藩の“什”という武士階級子弟の教育法(少年集団をつくり研鑽し合うもので、この両藩は、その厳しさが際立っていた)の流れを汲むものです。
例えば、戊辰戦争後の明治政府では、薩摩藩士(新政府軍)は軍の上層部、会津藩士(幕府軍)は軍の下士官と立場が大きく異なりましたが、“郷中”“什”の精神は、相通じるものがあり、組織統一に大きな役割を果たしました。
日本社会が、いまだに「気持ちで頑張れ!」「気合で乗り切れ!」「弱音を吐くな!」「歯を食いしばれ!」と精神論、根性論を支持するのは、国民1人ひとりに、この“郷中”“什”の流れを汲む精神教育が深く浸透していたことを物語っています。
この精神教育は、家庭内教育だけではなく、教師や指導者などによる「しつけ(教育)と称する体罰」、職場などでの「ハラスメント」を容認する“礎”となっています。
明治政府のもとで、学校教育に従事してきたのは、いうまでもなく武家出身者で、その武家出身者には、儒教思想にもとづく「男尊女卑」、家父長制にもとづく「内助の功」「良妻賢母」の価値観が叩き込まれています。
とくに、裕福な子女に実施された女子教育は、「内助の功」「良妻賢母」の醸成でしかなく、この流れは、戦後、「家政科(高校、短期大学、大学)」としてひき継がれました。
女性の大学進学率があがる一方で、その多くが「家政学」を学ぶことになり、「家政学」を学んだ女性の多くが、高度成長期以降の日本社会の中で、「内助の功」「良妻賢母」を支持する大きな役割を果たしました。
結果、交際相手や配偶者からDV行為を受けても、子どものために耐え忍び、一方で、家を守り私が、しっかり子育てをしなければならないと、「しつけ(教育)と称する体罰」が横行していきます。
太平洋戦争で喧伝されたスローガンのひとつは、神武天皇が唱えたとされる「八紘一宇」でした。
「八紘一宇」とは、天下をひとつの家のようにすること、全世界をひとつの家にすることで、「天皇総帝論」、「唯一の思想的原動力」を意味します。
では、日本の国家「君が代」の歌詞は、「君が代は 千代に八千代に さざれ石の巌と なりて こけのむすまで」で、現代和訳すると、「男性と女性がともに支えているこの世は 千年も 幾千年もの間 小さな砂がさざれ石のように やがて大きな盤石となって 苔が生じるほど長い間栄えていきますように」なり、「八紘一宇」を表していることがわかります。
この「君が代」の歌詞は、平安時代中期の905年(延喜5年)に奏上された『古今和歌集』に収録されていた「読み人知らず」の歌が元となっています。
「詠み人知らず」とは、「誰が歌詞を書いたのかわからないが、ずっと昔から歌われていた歌」ことです。
国体、神国、皇室典範、万世一系、男系男子、天壌無窮(てんじょうむきゅう)の神勅、教育勅語、靖国神社、君が代、軍歌、唱歌などは、すべて「神話」と関係しています。
神話、教育勅語にもとづいて学校教育がなされた戦前の日本教育の幾つかは、日本国民に根づき、学校で、地域で、日常生活で、いまもひき継がれています*-21。
「教育勅語」の全文は、「朕惟(ちんおも)ふに、我が皇祖皇宗(くわうそくわうそう)、国を肇むること宏遠(こうえん)に、徳を樹(た)つること深厚なり。我が臣民克(よ)く忠に克く孝(かう)に、億兆心(おくてふこころ)を一にして世々其の美を済(な)せるは、此れ我が国体の精華にして教育(けふいく)の淵源亦実(えんげんまたじつ)に此(ここ)に存す。爾臣民父母(なんじしんみんふぼ)に孝に、兄弟(けいてい)に友(いう)に、夫婦相和(ふうふあいわ)し、朋友相信(ほういうあいしん)じ、恭倹己(きょうけんおのれ)を持(ぢ)し、博愛衆(はくあいしゅう)に及ぼし、学を修め、業(げふ)を習ひ、以て知能を啓発し、徳器を成就し、進んで公益を広め、世務(せいむ)開き、常に国憲(こくけん)を重んじ、国法に遵(したが)ひ、一旦緩急(いったんくわんきふ)あれば義勇公(ぎゆうこう)に奉じ、以て天壌無窮(てんじょうむきゅう)の皇運(こわううん)を扶翼(ふよく)すべし。是の如きは、獨り朕が忠良(ちゅうりゃう)の臣民たるのみならず、又以て爾祖先(なんじそせん)の遺風を顕彰(けんしゃう)するに足らん。斯(こ)の道は、実に我が皇祖皇宗(くわうそくわうそう)の遺訓にして、子孫臣民の倶(とも)に遵守すべき所、之を古今に通じて謬(あやま)らず、之を中外(ちゅうぐわい)に施して悖(もと)らず、朕爾臣民(ちんなんじしんみん)と倶(とも)に拳拳服庸(けんけんふくよう)して咸(みな)其の徳を一にせんことを庶幾(こいねが)ふ。」とあり、辻田真佐憲著『「戦前」の正体 愛国と神話の日本近現代史』によると、この「教育勅語」は、天皇の祖先、当代の天皇、臣民の祖先、当代の臣民の四者で構成され、この四者が、「忠」と「孝」という価値観で固く結びついていると説明しています。
忠とは、君主に対する臣民の誠であり、孝とは、父に対する子の誠ことです。
つまり、「 歴代の臣民は、歴代の天皇に忠を尽くしてきた。当代の臣民も、当代の天皇に忠を尽くしている。また、これまでの臣民は自らの祖先に対して孝を尽くしている。当代の天皇もまた過去の天皇に孝を尽くしている。
ほかの国では、君主が倒され、臣民が新しい君主になっており、忠が崩壊している。それはまた、そのときどきの君主が徳政を行わず、結果的に祖先からひき継いだ王朝を滅ぼしたという点で、孝も果たせていない。ところが、日本は忠孝がしっかりしているので、万世一系が保たれている。」という意味です。
「教育勅語」の内容は知らなくても、日本人の仕事観(自らを犠牲にしてでも、会社のため、組織のため、学校のため、恩師のためと自己犠牲をいとわない。結果、休暇をとらない、長時間労働・低賃金に不満をいわない)、日本人の道徳観(親の孝行を善とし、強要する(学校園の行事(親宛の手紙を書かせるなど)で「育ててくれて、ありがとう」「産んでくれて、ありがとう」といわせるなど)など、身近な価値観として醸成されています。
海外の人が、日本人の特性を示す「礼儀正しい」「親切」「勤勉」「盾突かない」「規律的」などは、「教育勅語」の教えがいまも国民にひき継がれ、“国民性”と呼ばれるほど、無自覚な価値観であり、行動規範となっています。
権力者には、賞賛し、褒め称え、「盾突かず」、辛抱し、忖度するなど、「忠義」に徹します。
一方で、この行動規範から外れる者、例えば、病気や障害を負い働けない者、学校に通学しない者、親に心配をかけたり、親の面倒をみたりしない者、社会が定めた枠組みから外れる者、権力者に従順ではなく、歯向かったり、意を唱えたりする者などに対し、非常ともいえる冷酷な態度をとるのも日本人の特徴です。
「自分たちもこの行動規範に従っている。はみ出ること(例外)は絶対に許さない!」、「やり直し、再チャレンジも許さない!」と徹底的に叩き、排除します。
実際、第2次世界大戦後、新政府軍、明治政府が構築したような神話国家をつくりあげた国家があります。
それは、カルト教団の統一教会(現.世界平和統一家庭連合)が日本の信者から集めた膨大な資金を送り、その資金が、軍事国家を支えている北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)です。
岸信介元総理以降、「自由民主党」の保守派閥と深い関係にある統一教会(現.世界平和統一家庭連合)が日本の信者から集めた膨大な資金が、北朝鮮の神話国家を成り立たせ、核開発を支えています。
つまり、国民会議と神道政治連盟、統一教会(現.世界平和統一家庭連合)と深い関係の「自由民主党」の保守派閥が目指す国家像は、北朝鮮のような国民が反対の声をあげることのできない独裁国家、あるいは、中国(中華民国)のような一党国家(共産党)です。
独裁国家、一党国家では、人権は存在しなかったり、軽視されたりします。
この視点に立ち、「自由民主党」をはじめとする保守政党が目指す政策の数々には、戦前の憲兵隊を思わせる秘密警察をかかえる北朝鮮、習近平国家主席下の中華民国、プーチン政権下のロシアのような国家を構築したい思いが滲みでています。
表面的ではなく、実質的に人権が認めていないような国において、人権宣言にもとづく「いかなる理由があっても暴力は許されない」といった考え方は受け入れられない、つまり、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力(人権)を受けた被害者の存在は、軽視されます。
令和5年(2023年)6月9日、強制送還の対象となった外国人の長期収容解消をはかることを目的とし、難民認定の申請中は強制送還を停止する規定を改め、難民認定の申請で送還を停止できるのは原則2回までとする「改正出入国管理及び難民認定法(案)」は、参院本会議で可決し、成立しました。
「出入国管理及び難民認定法」は、安倍政権以降、平成11年(1999年)の改正で、不法在留罪の創設、退去強制された者に係る上陸拒否期間の伸長、再入国許可の有効期間の伸長など、平成13年(2001年)の改正で、サッカーワールドカップの開催に向けたフーリガン対策等としての上陸拒否事由及び退去強制事由の整備など、平成16年(2004年)の改正で、在留資格取消制度の創設、仮滞在許可制度の創設、出国命令制度の創設、不法入国罪等の罰則の強化など、平成17年(2005年)の改正で、人身取引議定書の締結に伴う人身取引等の定義規定の創設等、密入国議定書の締結等に伴う罰則・退去強制事由の整備など、平成18年(2006年)改正で、上陸時における個人識別情報の提供義務付け、自動化ゲートの導入、一定の要件に該当する外国人研究者及び情報処理技術者を在留資格「特定活動」により受け入れる規定の整備など、平成21年(2009年)の改正で、在留カード・特別永住者証明書の交付など新たな在留管理制度の導入、外国人登録制度の廃止、在留資格「技能実習」の創設、在留資格「留学」と「就学」の統合、入国収容所等視察委員会の設置など、平成26年(2014年)の改正で、在留資格「高度専門職」の創設、船舶観光上陸許可の制度の創設、自動化ゲート利用対象者の拡大、在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」の統合、在留資格「投資・経営」から「経営・管理」への変更、PNR(Passenger Name Record;航空会社が保有する旅客の予約情報)に係る規定の整備など、平成28年(2016年)の改正で、在留資格「介護」の創設、偽装滞在者対策の強化のための罰則・在留資格取消事由の整備など、平成30年(2018年)の改正で、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設などと、年々、難民(外国人)の管理を強化し、難民(外国人)の排除姿勢を鮮明に打ちだしてきました。
安倍政権以降、「出入国管理及び難民認定法」を改正し続け、監視を強化し、排除姿勢を鮮明にしてきたのは、新政府軍のスローガン「神武天皇の時代に戻れ!(神武創業)」は、神武天皇からはじまる日本の建国に立ち返ることから、そこには、難民(外国人)は存在しないからです。
日本は、強固な神話国家に立ち返る、いよいよ危ない域に達してきました。
*-18 この目論見は、太平洋戦争で、日米両軍が激突した「南太平洋ソロモン諸島・ガダルカナル島の戦い(昭和17年(1942年)8月-10月)」の激しい消耗戦により、戦死者だけでなく兵員に多数の餓死者を発生させたうえ、軍艦、航空機、燃料、武器等多くを失ったにもかかわらず、その後、3年余りにわたり、国民・軍人に敗戦濃厚の事実を隠して戦争を続けたように、ロシアからの賠償金目的に開戦した「日露戦争(明治37年-同38年(1904-1905年))」においてもみられます。
日露戦争末期、日本は戦闘を優位に進めていた一方で、国力をほとんど使い果たし、ロシアも世相混沌とし、ロマノフ王朝による君主制が崩壊の動きを示していた中で、アメリカを介して和睦し、「日露講和条約(ポーツマス条約)」を締結しました。
日本が、ロマノフ王朝の崩壊が間近で開戦に及んだ構図は、崩壊寸前の清王朝と戦った「日清戦争(1894年(明治27年)7月-1895年(明治28年)3月)」と同じです。
「ポーツマス条約」では、ロシアが満州や朝鮮から撤兵し、遼東半島の租借権や東清鉄道を日本に譲渡し、樺太の南部を日本に割譲することになりましたが、日本は、ロシアから賠償金を得ることはできませんでした。
ロシアからの賠償金目的で開戦した日本にとって、賠償金を得ることができなかったことは、敗戦に等しいといえます。
戦争が長期化すれば敗戦していた日本に対し、アメリカが「痛み分け」と助け船をだし、敗戦を免れたに過ぎない戦争でした。
アメリカが日本を助けたのは、アジア進出の足掛かりをするためでした。
しかし日本は、国民に「国民皆兵」「富国強兵」のために一致団結、士気高揚を目論み、「大国ロシアに大勝利した!」と大キャンペーンを実施しました。
*-19 昭和6年(1931年)、日本の関東軍が柳条湖事件を契機に中国軍との戦闘に突入、満州を占領し、翌昭和7年(1932年)、満州国を建国しました。
そして、5年後の昭和12年(1937年)、全面的な日中戦争に突入しました。
*-20 人の戦争には、幾つかの仕組みが存在します。
戦場で戦う兵士の恐怖心を麻薬でとり除くために、麻薬(たばこを含む)の精製と配布(販売)を国が担い、重要が拡大した戦争が終わると、軍(国)の需要が減り、余った麻薬は一般社会に流れ、結果、麻薬汚染が進むという構図です。
この需要が拡大する構図に目を向けると、武器(軍事産業)、化学薬品産業も同じです。
戦争が終わると戦争国の需要が減るので、新たな戦争国に供給するか、戦争国がないときには、新たな戦争・紛争を起こし供給するかといった構図、農薬などの化学物質に規制が入り、国が使用禁止を決定すると、その分をどこかの国がひき受けることになるなどといった構図です。
例えば、子どもの脳の発達に悪影響を及ぼし、発達障害発症の原因となり、さまざまな環境問題につながることから、2018年(平成30年)4月27日、ネオニコチノイドと呼ばれる農薬のうちの3種、「クロチアニジン」、「イミダクロプリド」、「チアメトキサム」を主成分とする薬剤(以下、対象薬剤)は、すべての作物に対して屋外での使用を禁止した一方で、日本はその流れに反し、安倍政権の下で、ネオニコチノイド系農薬の食品の残留基準を緩和しています。
*-21 例えば、5月5日の「こどもの日」にも神話(信仰)が深く結びついています。
「こどもの日」は、もともとは病気や災いを避けるための行事であった「端午の節句」でした。
「節句」とは、季節の節目を表す日のことで、中国の「陰陽五行説」をもととし、日本では奈良時代ごろに伝来し定着したといわれています。
主に、宮廷において季節の節目に実施された「節会(せちえ)」という伝統的な行事が、日本の稲作文化や信仰とうまく結びつき、庶民の季節行事としても深く根づいていきました。
「節句」は「節供」ともいい、その季節の旬の供物を神に捧げ、祈り、そのお下がりを皆で食するというのが本来の祝い方です。
日本では宮廷や貴族社会において、薬草を丸め、飾って使う薬玉を送り合う習慣がありました。
平安時代になると、邪気払いとして、菖蒲の葉を枕の下に敷いて寝る習慣が生まれました。
これは、菖蒲には特別な力があり、神様がそれを目印にしていると信じられていたからです。
武家が台頭してくる鎌倉時代になると、「菖蒲」と「尚武(武道、軍事を尊ぶこと)」の読みが同一であること、また、菖蒲の葉が刀の切っ先を連想させることから、端午の節句は男子の節句とされるようになり、鎧、甲、鯉のぼり、五月人形などを飾り、男子の成長と健康、一族の繁栄を願う重要な行事になっていきました。
端午の「端」には、「初め」という意味があり、5月の初めの午(うま)の日が端午の節句とされていましたが、後に「午=五(読みが同じ)」ということで5月5日に定着していきました。
昭和23年(1948年)に定められた『国民の祝日に関する法律』には、「こどもの日」は、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」と記載されています。
興味深いのは、子どもの「人権」ではなく、子どもの「人格」と記述し、「子どもの権利」を明確にしていないことです。
「人権」は、「人間が人間らしく生きるための権利で、生まれながらに全員が持っている権利のこと」です。
人間であれば、誰もが持っている権利です。
つまり、どのような人であっても、出生後、決して否定されない権利です。
一方で、「人格」とは、個人の心理面での特性、人柄のことで、あるいは、人としての主体(中心となるもの)を意味します。
「人格権」は、「個人の名誉など人格的利益を保護するために必要な権利のこと」ですが、人格権自体には、権利として具体的に保障されているわけではありません。
同年12月10日、国際連合(以下、国連)は、人権法の柱石(すべての人民にとって、達成すべき共通の基準)として『世界人権宣言(Universal Declaration of Human Rights)』を採択しました。
この『世界人権宣言』では、第1条「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」、第3条「すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。」と記述しています。
第1条の「尊厳と権利とについて平等」ですが、日本では、第2次世界大戦後、家父長制はなくなったものの、「家に嫁ぐ」「嫁に行く」などの考えなど、その概念は、いまだに生活様式として深く根づき、その概念と深くかかわる「内助の功」「良妻賢母」という保守的な価値観は、多くの日本国民に支持されています。
この保守的な価値観は、子どもを育てる(子どもの育児)は、母の務めとして、明確に「母に感謝する」という記述に表れています。
つまり、多くの日本国民は、「尊厳と権利とについて、不平等」を支持していることになります。
この保守的な価値観は「男尊女卑」につながり、日本社会における「ジェンダー観(男女の役割)」に大きな影響を及ぼし、日本特有の問題を生じさせています。
日本は、明治29年(1896年)の制定から令和4年(2022年)10月14日に削除されるまでの126年間、「親の子どもに対する懲戒権(民法822条)」を認めてきました。
いまから6ヶ月前までです(令和5年(2023年)5月現在)。
「懲戒」とは、不正、または、不当な行為に対して制裁を加え、懲らしめることで、「懲戒権」は、親は子どもに対し、その権利を有することです。
親や教師(指導者)、上司による懲戒は、「しつけ(教育)と称する体罰」と加えられます。
さらに、軍国化が進む中で、一部の家父長は、家父長としての男性の権利として、子どもだけに留まらず、妻や女性に対して懲罰(懲戒)も認められると自分に都合のいいように解釈していきました。
「懲戒権(民法822条)」が削除される2年前の令和2年(2020年)4月1日に『児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)』が改正され、体罰が禁止されましたが、懲戒権の残る限り、その効果は限定的なままでした。
つまり、日本政府は126年間、親が、子どもに対し、しつけ(教育)と称して体罰を加えるお墨付きを与えてきたわけです。
その結果、日本国民の一定数では、5-6世代にわたる子育てにおいて、「しつけ(教育)と称する体罰」は加え続けてきました。
この「日本国民の一定数」は、戦前、昭和の話しではなく、平成30年(2018年)、子ども支援の国際的NGO「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」が2万人の日本人を対象に実施した調査では、しつけ(教育)に伴う子どもへの体罰を約6割-7割が容認し、体罰(虐待行為)を加えていることから、いまの問題です。
日本国民の70%-60%が、子どもに虐待(しつけ(教育)と称する体罰)を加えている異常な状況は、日本を蝕む社会病理といえます。
「親に対し、しつけ(教育)と称する体罰(懲戒権)を認めた」ままで、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかる」と、「こども日」に、鎧、甲、鯉のぼり、五月人形などを飾り、柏餅を食べ、GWを楽しみ、遊び惚けている日本国民、怖さを覚えます。
親に懲戒権を認める一方で、子どもの権利(人権)を認めてしまうと齟齬が生じることになります。
懲戒権を認めてきた親を「加害者」「犯罪者」とすることはできないので、「被害者」である“子ども”を存在させてはいけません。
結果、日本では、「いかなる理由があっても、人に危害(暴力)を加えることは、人権を侵害することに他ならない」という考えに立てる人は、ごく少数という“いま”がつくられました。
また、『児童の権利に関する条約(CRC)(以下、子どもの権利条約)』と『女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(CEDAW)(以下、女性差別撤廃条約)』が禁止している「児童婚(18歳未満での婚姻)」について、日本は、13ヶ月前の令和4年(2022年)4月1日に民法の一部を改正するまでは、「児童婚」を認めていました。
この民法の一部改正では、明治9年(1876年)の『太政官布告』を引き継ぐかたちで、成年年齢を20歳と定めて以降、147年続いた成年年齢を18歳に引き下げ、婚姻開始年齢は16歳と定められていた女性も18歳と引き上げられ、ようやく男女の婚姻開始年齢が統一されました。
婚姻開始年齢が男女で異なる状況は、『世界人権宣言』の第1条「尊厳と権利とについて平等である」に反し、日本は、この状況を75年間にわたり放置し続け、しかも、昭和60年(1985年)6月25日に『女性差別撤廃条約』、平成6年(1994年)4月22日に『子どもの権利条約』に批准した日本は、37年間、同条約が禁止する「児童婚」を認め続けてきました。
そして、5月5日のこどもの日から1週間は、「児童福祉週間」です。
「児童福祉週間」は、「子どもの健やかな成長、子どもや家庭をとり巻く環境について、国民全体で考える」ことを目的に定められたもので、児童福祉の理念の普及・啓発のための各種行事が行われています。
ここでも、日本では、児童福祉の向上に不可欠な子どもの権利(人権)を表現していません。
1954年(昭和29年)11月20日、国連は、世界の子どもたちの相互理解と福祉の向上を目的として、「世界子どもの日」と制定しました。
以降、毎年、11月20日には、「子どもの権利の認識向上」と「子どもの福祉の向上」を目的として、世界中で子どもたちが主体となって参加する催しが実施されています。
そして、1959年(昭和34年)11月20日、国連総会で『子どもの権利宣言』を採択し、これから30年経過した1989年の11月20日、国連総会において、すべての子どもに人権を保障するはじめての国際条約である『子どもの権利条約』を採択しました。
以降、34年間、世界中で、子どもに関わるすべての人が、『子どもの権利条約』にうたわれている権利の実現に向けてとり組むことはもちろん、子どもたち自身が、自分たちの持つ権利について知り、学び、声をあげてきました(令和4年(2022年)11月20日現在)。
一方で、日本政府は、子どもの権利(人権)、女性の権利(人権)だけではなく、国民一人ひとりに対して、一貫して、国民に対し「人権の保障」を明確に示そうとしません。
日本基準ではなく、国際基準、グローバルスタンダードな基準にもとづいて、「子どもの人権」を考える必要があります。
・性犯罪、児童ポルノに寛容な日本社会の背景にあるのは「遊郭」と「神話」
イギリスのアヘンマネーに支えられてクーデターを起こした新政府軍、「国民皆兵」「富国強兵」を進めた明治政府がつくりあげた家父長制にもとづく「民法」や「刑法」の解釈には、明治政府にとって都合のいいストーリーを意図的に仕上げた背景が数多く存在します。
その典型的なものが『家族法』であり、『性犯罪』の軽い処罰、制約の多い適用(成立)要件です。
日本社会は、世界に例がないほど、交際相手や配偶者の男性の買春行為に寛容です。
日本社会では、男性の買春行為は、「性風俗店に行った」、「派遣型性風俗を利用した」など表現し、あたかも性風俗店以外のサービス業を利用しているのと変わらない表現、反応を示します。
その一定数は、交際相手や配偶者が性風俗で、女性を買春しても、女性も同様の反応を示すように、日本社会では、男女の区別なく性売買に寛容で、あまり問題視していません。
買春行為は、18歳未満に金銭を支払った性行為等に及んだ(児童買春罪『児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律』)とき、その性行為等の裸や下着などを撮影した(児童ポルノ製造罪『児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)』)とき以外、処罰されることはありません。
買春や売春は『売春防止法』で禁止されていますが、「売春する者は、保護しなければならない弱い立場」とみなされているので罰則はありません。
一方の買春する者は、この「保護しなければならない弱い立場」でないにもかかわらず、売春する者と同様に罰則はありません。
ここには、終戦してから13年後の昭和33年(1958年)に『売春防止法』を施行するまで、「公娼制度」は存続し続けたこと、「内助の功」「良妻賢母」で示される武家の女性が男性をもてなす保守的な価値観が深く関係しています。
鎌倉幕府が、公的な宴席での接待役に遊女を招集し、管理する「遊君別当」を設け、室町幕府は、「傾城局」を置き、宿駅などの傾城(遊女)を統轄しようとしたことが、日本の「公娼制度」のはじまりです。
その後、豊臣秀吉が大阪に最初につくったとされる「遊郭」などは、公的に認められた特定の場所に設け、その営業権を保証したことで、「公娼制度」は制度的に確立しました。
「公娼制度」とは、特定の売春、接待行為を公的に保護し、特別の権益を与える制度のことです。
日本独特の遊郭文化、つまり、遊女が歌を詠み(読み書き)、楽曲、歌舞ができたのは、政権交代で、身を落とした公家、武家の女性が遊女になったからです。
武家の女性に求められた「内助の功」「良妻賢母」は、武家の枠をでた「遊郭」で、女性が、男性をもてなし、喜ばすという「日本特有のおもてなし文化」をつくっていきました。
つまり、武家(家父長である男性)の客人を武家の妻と女性がもてなす作法が、「遊郭」で客(男性)をもてなす作法となり、それが、宿屋や店で客をもてなすようになりました。
家父長的で、保守的な価値観を支持する人にとって、それは、いうまでもなく、「女性が男性をもてなす」ことです。
それに反する女性は、「女性らしくない」「生意気だ」「女性のくせに、態度がでかい」などと非難されます。
武家の女性が「遊郭」に流れた主な政権交代は、安土桃山から江戸、江戸から明治の2回です。
明治政府は、この「公娼制度」を廃止することなく、太平洋戦争(第2次世界大戦)後も赤線地帯として残り、終戦してから13年後の昭和33年(1958年)に『売春防止法』を施行するまで、「公娼制度」は存続し続けました。
古今東西、勝利した剣闘士、功績をあげた兵士に奴隷(敗戦した国々)の女性をあてがったように、明治、大正、昭和前期にわたり、日本政府は、明治政府が進めた「国民皆兵」としての兵士(男性)に女性をあてがう仕組みを残し続けたことになります。
驚愕なのは、太平洋戦争の敗戦から僅か3日後の昭和20年(1945年)8月17日、組閣された組閣された東久邇内閣の国務大臣に就任した近衛文麿は、直ちに、警視総監の坂信弥に「米軍相手の売春施設をつくるように。」と命じたことです。
2週間後に40万人の占領軍上陸を控える中で、「国策売春組織」、すなわち「特殊慰安施設協会(RAA)」が設立され、RAAは、使命を忠実に達成するため、真先に開業したのが「慰安所」です。
「慰安」とは、本来、セックスを意味することばではなく、心をなぐさめ、労をねぎらうことです。
つまり、武家(家父長である男性)の客人を武家の妻と女性がもてなす作法(おもてなし)は「慰安」そのものです。
ところが、日本政府の考える慰安、つまり、RAAが、忠実に達成しなければならない使命とは、「進駐軍将兵の慰安で、なによりも重視したのが、セックスで満足させる」ことでした。
つまり、家父長制、軍事国家下で日本の男性が求める「慰安」は、セックスで満足させることがなにより重視されるようになりました。
敗戦国日本は、「左側通行から右側通行に替えるには、全国に設置されているバス停を移動させる必要があり、いまの日本にはその金はない」とGHQ(正確には、連合国軍最高司令官(マッカーサー)=SCAP(Supreme Commander for the Allied Powers)に付属する組織である総司令部(General Headquarters)のことであるので「連合国軍最高司令官総司令部」)に回答するほどの財政難であったにもかかわらず、霞が関、つまり、外務省・内務省・大蔵省・運輸省・東京都・警視庁などの主要官庁が動き、3300万円(現在の価格に換算すると10億円を超える)をだしたのです。
このときの座長役は、大蔵省主税局長の池田勇人(のちの首相で、在任日数8位)です。
同じ敗戦国のドイツ、イタリア、あるいは、ソ連に占領された東ヨーロッパの国々では、占領軍を相手にする売春婦は大勢いましたが、国が号令を発し、莫大な予算を投じ、官僚がプロジェクトを組み、「国体護持」のために女性を犠牲にするという“理想”を高らかに掲げた国は、世界の中で日本だけです。
そして、組閣から10日後、ポツダム宣言の受諾(8月14日)から13日後の同年8月27日、RAAは、占領軍の上陸地点に近い品川の大森海岸に「慰安所第1号」として、「小町園」を開店しました。
このとき、「小町園」に集められた女性は、50人です。
豊臣秀吉が「遊郭」を設けたのを機に確立した日本の「公娼制度」は、敗戦から13年後の昭和33年(1958年)に『売春防止法』の制定で、その歴史に幕を下ろしましたが、家父長制のその概念・価値観は残り続けてきたように、この流れは、トルコ風呂(ソープランド)にひきつがれました。
いまでこそ、宿泊先のホテルにコールガールを派遣することが主流になりましたが、料亭での会食やゴルフの接待と同様に、「トルコ風呂(そーブランド)」は、取引先への接待として利用されるなど、「遊郭」が担ってきた一部の役割はいまも残り、デリバリー型性風俗など、その形態は多様化しています。
日本では、金品を支払い性行為する買春行為は、『売春防止法』でとり締まられますが、罰則はなく、逮捕されることはありません。
唯一の例外は、平成11年(1999年)11月26日に制定された『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』の対象となる児童、つまり、18歳未満の児童に対し金銭を支払い、性行為等を行ったときは、同法の「児童買春罪」、「児童福祉法」違反、「青少年保護育成条例」違反などが適用できます。
また、18歳未満の児童を買春し、裸や下着などの写真を撮影したときには、同法の「児童ポルノ製造罪」を適用できます。
この撮影には、買春者が撮影するケースに加え、18歳未満の児童に撮影させ、送信させることも含まれます。
また、出会い系サイトなどのSNSに、18歳未満の児童に対し、売春を促すような書き込みをしたときには、性行為に至らなくても、『インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)』)を適用できます。
日本では、買春行為が法的に禁止されているのは、あくまでも18未満の児童に対する買春行為に限定されています。
一方で、欧州では、スウェーデン、ノルウェー、アイスランド、北アイルランド、フランスが採用している「北欧モデル」の他、イギリスが、買春を禁止、買う側は罰せられます。
「北欧モデル」とは、根本的な人権侵害である売買春の社会的廃絶に向けた法体系で、a)売春店の経営、売買春の周旋、売買春から第3者が利益を得ることなどを禁止すること、b)買春行為をも処罰の対象とすること、c)売春者を処罰せず、離脱(足抜け)に向けて社会的・医療的・経済的等々の支援を提供することという3つの柱にもとづいています。
例えば、「北欧モデル」を採用しているフランスでは、性関連サービスに対価を払った者には罰金1500ユーロ(約18万円)、再犯者に対しては最大で3750ユーロ(約46万円)の罰金を科し、性労働者の窮状について学ぶ講習会への出席を義務づけています。
また、売春産業から抜けだしたい外国人の性労働者には、半年間の在留許可を与え、売春防止のために補助金を拠出しています。
人権解釈の乏しい日本では、こうした「北欧モデル」とほど遠い状況です。
いまの日本に通じる国の礎をつくりあげたのは、いうまでもなく明治政府で、そのメンバーは反政府軍の薩摩藩、長州藩の主流2藩に加え、肥前藩(佐賀藩)、土佐藩の4藩がほとんどでした(藩閥政治)。
このように、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力(人権)事案、そして、これらの暴力(人権)事案とかかわる法律や制度は、歴史的な背景の理解なく語ることができません。
日本社会では、この歴史的な背景は、過去の問題ではなく、いまの問題としてひき継がれています。
差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力(人権)事案の解決に向けてとり組むとき、障害となるのは、この歴史的背景を起因とする保守的な価値観、この保守的な価値観の背景である神話、そのもとで制定された法律、そして、制度です。
歴史的背景は、県(藩)の歴史、文化はいうまでもなく、子育てに虐待をとり入れる教えを受け継いできた隠れキリシタンの流れを汲む一部の地域(その出身者を含む)、長く差別・排除の対象となってきた同和地区、そして、明治政府の意向を汲む政治団体など、地域コミュニティ、組織に至るまでかかわりがあります。
教育行政は、その地域コミュニティの歴史的背景に影響を受け、その地区の教育を受けた人は、当然、歴史的背景にもとづく価値観の形成に大きな影響を受けています。
差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力(人権)事案とかかわるとき、地域コミュニティの歴史的背景を知らないと、個々人の価値観の背景、組織風土としての文化を理解することができず、対応を誤る可能性があります。
この第5は、この『手引き(新版2訂)』の「Ⅰ-C.暴力に支配される関係を断ち切る(一時保護と離婚、被害者の土俵で闘うために)」の「Ⅰ-C-8.思いを断ち切るために、必要な判断と覚悟」、「Ⅰ-C-9.一時保護の決定、保護命令の発令。「身を守る」という選択」、「Ⅰ-C-10.夫婦関係調整(離婚)調停、離婚裁判での判決」、「Ⅰ-C-11.DV離婚を考えたとき、事前に確認しておくこと」、「Ⅰ-C-12.加害者がDV行為を認めない中で、DV行為を立証する」の“主”となります。
ただし、あくまでもバックグランドであることから、これらの章で説明すると流れ、構成を損なうことから、この『はじめに。』の中(次の「日本特有のDV問題」、5つの切り口)で説明します。
(日本特有のDV問題)
1.日本社会は、いまだに保守的な価値観が主流
日本において、「暴力」のある家庭に対して適切なアプローチとケアにとり組む(早期発見と早期介入、早期治療)には、日本特有の問題があります。
それは、「女性の幸せは、結婚し、子どもを持つことであり、子どもにとっての幸せは、たとえ、暴力のある家庭環境(機能不全家庭)であっても、両親の下で育つことである」という“保守的”な価値観です。
この“保守的”な価値観が、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの問題を解決するうえで、大きな障壁として立ち塞がります。
“保守的”な価値観とは、明治政府が、列強強国に対抗するために進めた「富国強兵」「国民皆兵」を国民に浸透させるためにとり組んだ「家父長制度」を軸にしたさまざま価値観です。
「家父長制」は、第2次世界大戦(太平洋戦争)の敗戦後に法的にはなくなりましたが、日本は、世界で唯一、「夫婦同姓(民法750条、および、戸籍法74条1号)」と法で定め、令和2年(2020年)には、95.3%の夫婦が「夫の名字」を選択しています。
このことは、第2次世界大戦後、家父長制はなくなったものの、「家に嫁ぐ」「嫁に行く」などの考えなど、その概念は、いまだに生活様式として深く根づき、その概念と深くかかわる「内助の功」「良妻賢母」という保守的な価値観は、多くの日本国民に支持されています。
この保守的な価値観は「男尊女卑」につながり、日本社会における「ジェンダー観(男女の役割)*-16」に大きな影響を及ぼし、日本特有の問題を生じさせています。
それは、DV(デートDV)、児童虐待などの女性や子どもに対する暴力行為を容認しやすく、一方で、被害者が被害を認識し難く、その暴力行為のある環境から離れる選択をするのが容易でなくなる状況を生みます。
被害者の視点に立つと、個々人の問題で、加害者から逃れたり、別れたりできないのではなく、こうした日本社会に色濃く残る保守的な価値観が逃れたり、別れたりするのを妨げていることになります。
つまり、DV問題や児童虐待問題は、個人や家庭の問題と認識していると、DV問題の本質を把握できなくなります。
なぜなら、今日のDV問題や児童虐待問題は、その国の政府が、第2次世界大戦後の77年間、その対策として、どのようにとり組んできたのかが顕著に表れるからです(令和4年(2022年)10月現在)。
ここには、その国で生活する国民の意識が深く表れます。
では、この視点に立ち、保守的な価値観について説明します。
「男尊女卑」とは、「男性を重く見て、女性を軽く見る」ということです。
「男尊女卑」は、“儒教思想”に由来しますが、その初出は、中国古代の素朴な父系社会がそのまま反映されている「春秋戦国時代(紀元前770年に周が都を洛邑(成周)へ移してから紀元前221年に秦が中国を統一するまで)」に生まれた“老荘思想”と考えられています。
つまり、いまからおよそ2800年-2250年前に生まれた思想です(令和4年(2022年)10月現在)。
この“儒教”は、江戸時代、武家社会の礎となった思想です。
明治29年(1896年)に制定された「民法」は“家制度”にもとづき、戦後、日本国民が理想としたアメリカ社会の家族像は、キリスト教にもとづく“家父長制”でした。
「内助の功」とは、「家庭において、夫の外での働きを支える妻の功績」のこと、つまり、「夫(男性)が働き、妻(女性)は家で家事をする」ということです。
「良妻賢母」とは、「良妻とは、夫(男性)に従い、サポートを惜しまない貞淑な妻のこと、賢母とは、子どもの教育やしつけをしっかりできる賢い母のこと」をいいます。
日本社会において、性別にかかわらず、この「家父長制」「男尊女卑」「内助の功」「良妻賢母」という価値観を肯定する人と肯定しない人では、男女の役割(ジェンダー観)の捉え方は大きく違ってきます。
この“保守的”な価値観を支持する人たちは、この価値観を「日本古来の」「昔からの」という表現をよく使いますが、この価値観は、先に記したとおり、明治政府が「富国強兵」「国民皆兵」、つまり、軍国化を進める国家的なキャンペーンにより国民に浸透させたもので、「日本古来の価値観」でも、「昔からずっとそうだった」わけでもありません。
この国家的なキャンペーンの期間は、いまから149年前の明治6年(1873年)の徴兵令発布の制定から、いまから77年前の昭和20年(1945年)8月15日の太平洋戦争の敗戦までの約70年です(令和4年(2022年)10月現在)。
つまり、約70年間続いた国家的なキャンペーンの影響が、77年経ったいまも残り続けていることになります。
その国家的なキャンペーン、つまり、思想教育が凄まじいものだったのかがわかります。
江戸時代268年間(1603年-1868年/1871年)は、「夫を支える妻」という“構図”は、日本の総人口約3000万人中、「7%」の210万人(江戸300藩、1藩平均700人程度(実際は大小かなりの差がありました))に満たなかった「武家」などに限られたものでした。
つまり、2,790万人の人々には、「夫を支える妻」という“構図”はありませんでした。
明治政府以降の国家的なキャンペーンは、時間軸が少し違いますが、この2,790万人に対する思想教育と捉えることができます。
では、「武家」について、少し説明します。
平安時代中期((900年ころ以降)/平安時代(794年-1185年))になると、官職や職能が特定の家系に固定化していく「家業の継承」が急速に進展し、軍事を主務とする官職を持った家系・家柄の総称を「武家」というようになりました。
約450年後の江戸時代では、「武家」は、武家官位を持つ家系のことを指すようになりました。
当初、武家で求められた女性像は、家庭的であると同時に、男性よりも勇敢で、決して負けないというものでした。
武家の若い娘は感情を抑制し、神経を鍛え、薙刀を操って自分を守るために武芸の鍛錬を積むことになりました。
ところが、時代の変遷により、武家の女性たちが音曲・歌舞・読書・文学などの教育が施されるようになり、それは、父親や夫が家庭で憂さを晴らす助けとなること、つまり、武家の女性が担う役割は、普段の生活の中に、女性たちが音曲・歌舞・読書・文学などで“彩”と“優雅さ”を添えることに変わっていきました。
武家の女性が、「家庭で憂さを晴らす」という役割には、男性を性的に喜ばす行為も含まれています。
それが、武家の妻が夫を「もてなす(待遇する、応対する、世話する)」ということです。
つまり、武家では、娘としては父親のため、妻としては夫のため、母としては息子のために、「献身的に尽くす」ことが女性の役割とされました。
「男性が忠義を心に、主君と国のために身を捨てる」ことと同様に、「女性は夫、家、家族のために自らを犠牲にする」こと求められました。
つまり、武家の女性は、自己否定があってこそはじめて成り立つような、夫を引き立てる役割を担わされました。
この役割が、武家の女性に求められた「内助の功」「良妻賢母」です。
いまだに、日本社会における“男らしさ”は、国と職場のために身を捨てて働くことを意味し、“女性らしさ”とは、男性、夫、子ども、家族のために自らを犠牲にして尽くすことを意味します。
これらの認識は、“性差別”そのものです。
この視点に立つと、女性の役割として、男性に「献身的に尽くさせる」ために、男性の威厳を示す(力を誇示する)暴力が、DV行為としての暴力、レイプなどの性暴力、職場などでのセクシャルハラスメントであることが理解できると思います。
女性に向けられるこの性差別がいきつくと、女性を狙った殺人「フェミサイド」になります。
フェミサイドとは「女性であることを理由に、男性が女性を殺害する」ことを指します。
その「フェミサイド」の背後には、「ミソジニー」が存在します。
ミソジニーとは、「女性に対する憎悪、嫌悪、差別意識」のことです。
日本社会には、自分がミソジニーであることを隠したり、女性を臭いものとして蓋をしようとしたりする男性が数多く存在します。
このことは、日本社会が、女性差別社会であることを意味します。
アメリカでは「インセル」ということばが生まれましたが、このことばは、「不本意な禁欲主義者」を意味し、「俺が、恋愛やセックスをできないのは女が悪い」と女性を逆恨みして、憎悪を募らせる“一部”の男性を指します。
このインセルと呼ばれる“一部”の男性は、「男には、恋愛やセックスをする権利がある」、「女にケアされて性欲を満たされる権利がある」、「その権利を不当に奪われている」という強い被害者意識を持っています。
その被害者意識は、進学、就職、仕事、人間関係などで挫折したり、ストレスを覚えるできごとがあったりしたとき、「俺の人生がうまくいかないのはモテないから、つまり、女が悪い!」と女性に責任転嫁し、逆恨みする傾向があります。
日本社会においても、ネット上で自称「非モテの弱者男性」の一部が、「女を再分配せよ」と主張しているのを見かけますが、いうまでもなく、女性はモノではありません。
ここには、「男には、女を所有する権利がある」という“認知の歪み”が存在し、この“認知の歪み”を生みだしているのが、男性優位社会で、そこに、母親による被虐待体験が加わると、女性に罰を与える使命が生まれることがあります。
「女を所有してこそ一人前」、「女をモノにできない自分は男社会で認められない」という劣等感から女を逆恨みするのは、「ホモソーシャル」です。
女性を自分と対等な人間だと思っていない男性は、「女のくせに、俺を拒絶しやがって」、「女のくせに、幸せそうにしやがって」、「自分の思い通りにならない女が憎い、そんな女に復讐してやる」と憎悪を募らせます。
2014年(平成26年)、アメリカで、インセルを自称する22歳の男性が、「女への復讐」を宣言し、6人を殺害して14人を負傷させ、のちに自殺した事件がおきました。
この凄惨な事件をおこしたエリオット・ロジャーは、インセルコミュニティで崇拝され、英雄視されました。
その後、インセルによる凶悪事件の連鎖が起きました。
例えば、2018年(平成30年)、「エリオット・ロジャーは不滅だ」とネットに書き込んでいた男性が、フロリダ州の高校で乱射し、17人を殺害しました。
同年、カナダでは、SNSに「インセル革命はすでにはじまっている! 最高紳士エリオット・ロジャー万歳!」と投稿した男性が、車で通行人に突っ込み、10人を殺害しています。
そして、日本社会においても、実際に、ネット上で女叩きをするコミュニティが存在しています。
彼らは、女性を狙い、嫌がらせや誹謗中傷を繰り返し、特に、フェミニストの女性に対する攻撃は過激化しています。
頑固にこびりついたミソジニーを「学び落とす」のは大変なことで、労力も、多くの時間も必要です。
したがって、重要なことは、子どもにミゾジニーをすり込まないことです。
子どもの周りにいる親、近隣住民(コミュニティ)、学校園の教職員といった大人が、ミゾジニーのことばやふるまい(態度)を見せたり、聞かせたりしないことです。
いまから43年前の1979年(昭和54年)、世界で最初に体罰を禁止したスウェーデンでは、保育園からジェンダー教育や人権教育を徹底しています(令和4年(2022年)10月現在)。
つまり、ジェンダー教育や人権教育を実施していない日本とは異なり、スウェーデンでは、2-3世代にわたり、ジェンダー教育や人権教育を受け、人権意識は社会にしっかり根づいています。
世間やメディアに刷り込まれる前に、真っ白な状態で教えることによって、子どもたちは差別や偏見のない大人に育ちます。
日本では一貫して、「すべての人間にはオギャーと生まれた瞬間から人権がある、差別されない権利がある」というあたり前の人権教育をしてきませんでした。
その日本社会では、子どもにミゾジニーをすり込まないためには、大人が、まずジェンダーに就いて学ぶ必要があります。
なぜなら、いうまでもなく、子どもは、周りの大人を手本にして育つからです。
子どもは、家庭での両親の関係から男尊女卑を学んでしまったり、親や公園で一緒に遊んでいる子どもの親同士、学校園の教職員の些細なやりとり(会話)から歪んだジェンダー観を学んでしまったりします。
日本とは異なり、戦後、人権問題にとり組んできた欧米諸国の多くでは、人権教育としての包括的性教育が成果をあげています。
人権意識にもとづく、愛情や親密性の育みを大切にする性教育によって、男の子たちは、楽しいセックスと健康的な恋愛関係は支配とコントロールではなく、敬意と双方の充足感から生まれるのだという意識を持つようになります。
このことは、「性的同意」を前提にした性行為のあり方を学ぶことから、「性的同意」を無視した性暴力を減らす大きな役割を果たします。
人権として「性的同意」を学んでいない日本では、交際相手や配偶者が求めてきたら応じなければならないと嫌でも応じる「性暴力(デートDV/DV)」が数多く存在します。
日本では論じられることはほぼありませんが、男性の交際相手や配偶者に対するDV行為としての性的暴力を減らすことで、DVだけではなく、性感染症、望まない妊娠に伴う人工中絶に至ったり、妊娠したことで結婚に至り慢性反復的(常態的、日常的)なDV被害を受けたり、面前DV=心理的虐待が継続したり、未成年での離婚や後遺症で働くことができずに貧困に至ったり、アルコールや薬物依存に陥ったり、管理売春(性的搾取)や性犯罪に巻き込まれたりするなど、多くの社会病理といえる問題を減らすことができます。
人権教育として性教育を学ぶことは、「性犯罪の被害者、加害者にならない」、「低年齢の性体験、妊娠のリスクを回避できる」、「自分の性やからだに対して肯定的に捉えられるようになり、自己肯定感の高い人間に育つ」、「自分だけでなく相手も尊重できるので、幸せな人間関係を築く力の土台となる」など多くのメリットがあります。
日本社会は、世界のポルノの約60%が生産されている「性産業先進国」であり、性別に関係なく、性風俗を利用(に通う)と表現し、女性を買うと表現したりしない中で、いまだに、人権教育としての性教育をほぼ実施していません。
人権教育としての性教育の実施を拒む人たちは、「臭いものに蓋をしろ」「寝た子を起こすな」と主張するばかりで、国(政府)として、大人として、子どもを守る責任を果たしていません。
大人の責任を果たすために、フェミサイドから目を逸らすことは論外です。
自分の生き難さを女性のせいにして、女性を狙い、加害する男性が存在し、女性への憎悪や差別を強化するコミュニティがあるという現実にしっかり向き合い、「フェミサイドを許さない」という姿勢を強く示すことが必要です。
日本のように、“保守的”な価値観のもとでは、国と職場のために身を捨てて働く男性に対し、男性に自らを犠牲にして尽くすはずの女性が、男性とは異なる考えや意志を持つことは許しません。
その世界で、女性が自分の考えや意志を口にすると、「口ごたえをした!」、「文句があるなら、でて行け!(稼いでこい)」、「偉そうなことをいうな、何様だ!」と否定したり、非難したり、「誰のおかげで生活ができている(学校に行けている)と思っているんだ!」と侮蔑したり、卑下したりすることばを浴びせる行為は、問題がない、至極あたり前となります。
つまり、こうした男性が、女性に浴びせることばの暴力(DV行為としての精神的暴力、児童虐待、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメント)は、肯定(容認)されます。
日本のように、“保守的”な価値観を肯定する人は、妻(女性)は、夫(男性)を喜ばすためにもてなし、献身的に尽くす役割を担うのがあたり前と認識し、肯定する人が男性のときは、女性に対してあたり前のようにそれを求め、肯定する人が女性のときは、男性に対してあたり前のように尽くします。
それができなければ、夫(男性)は、しつけ(教育)としてふるまいを正す行為、つまり、妻に対する暴力(体罰)は認められると、「懲戒権(民法822条)」を拡大解釈した明治中期から太平洋戦争に敗戦した当時と同様に、認められて当然と考えます。
ここには、「男女の関係は対等である」という概念(価値観)は存在しません。
DV被害者支援の現場では、「本来、男女の関係は対等である」との考え(声)は、時々、DV被害者の女性に「男女の関係は対等ではない。男性が上」と否定されます。
この否定のことばは、いま受けているDV被害にもとづく関係性を示しているのではなく、そもそも「男性が上で、女性が下」、つまり、「男尊女卑」の価値観がベースになっています。
「男女の関係は対等でない(女性蔑視)」という概念(保守的な価値観)は、家庭内だけではなく、日本社会そのものの考えであることから、学校園、職場、スポーツ、芸術、政治、入試、就職、就労形式・賃金制度、社会保障制度などあらゆる“場”に存在します。
では、日本において、なぜ、「男女の関係は対等である(女性蔑視)」という概念(保守的な価値観)は存在しないのでしょうか?
それは、世界で唯一、日本だけが採用している「夫婦同姓制度」が関係しています。
これは、明治憲法・明治民法がつくりだした家父長制が、いまだに、日本の国民の暮らしの主体としての役割を果たしていることを意味します。
戦後の日本社会では、表面的に「家父長制」はなくなりましたが、「夫婦同姓制度」の名の下で、社会制度システムものものは「家・家族」に重きがおかれています。
明治31年(1898年)に施行された『民法』の家族法は、法律婚をした女性から法的能力を完全に奪いました。
既婚女性が仕事をするなどの経済行為をするには、夫の許可が必要でした。
自分の子どもについても、法的な権限を一切持てませんでした。
離婚すると、子どもは夫の家に置いていかなければならず、離婚自体も、自分の意志ではできませんでした。
こうした人権否定を止め、男女同権としたのが、昭和22年(1947年)に施行された『日本国憲法』です。
法の下の平等を保障し、結婚は両性の同意のみで成立すると決め、戸籍は結婚した夫婦が新しくつくることになりました。
しかし、姓はどちらか一方のものを選ばなければならず、令和2年(2020年)には、95.3%の夫婦が「夫の名字」を選択、つまり、女性が夫の姓に改姓しています。
妻が結婚により夫の姓を名乗るよう誘導する制度が、戦後77年も経ったいまでも、多くの女性とその周辺に「夫の家に入る」、「・・家に嫁いだ(・・家の嫁になった)」という家父長制時代の感覚を残しています(令和4年(2022年)10月現在)。
こうした感覚を持つ人は、夫を「主人」「旦那」と呼び、妻を「嫁」と呼ぶことに疑問を覚えず、この呼称を使う人は、この関係性は“対等ではない”という認識には至っていません。
ここで、日本社会特有の夫婦間で使われる3つの“呼称”について、触れておきたいと思います。
第1は、「主人」という呼称です。
「主人」の反対語は、「下女」「下男」です。
主人は男女に限らず、“上”の者で、上の者に従う“下”の者という関係性になります。
つまり、「僕(しもべ)・下僕」「従じる者」です。
この関係性を夫婦関係にあてはめると、「主人」である夫(男性)に対し、「下女」「僕(しもべ)・下僕」「従じる者」である妻(女性)ということになります。
しかし、妻(女性)は、夫のことを「主人が」と表現する一方で、妻(女性)は自分のことを「私は夫の下僕です。」、「私は夫の僕(しもべ)です。」、「私は夫に絶対服従している者です。」と表現しません。
では、夫婦関係における「主人」の対義語はなんでしょうか?
それは、「令室」です。
「主人」「令室」は、ともに、相手を敬う表現です。
しかし私たちは、日本社会において、日常的に、夫が妻のことを「令室は、…」と表現するのを見聞きしているでしょうか?
日本社会では、女性は、夫を敬う表現である「主人」を使う一方で、男性は、妻を敬う表現である「令室」を使うことはありません。
そもそも、男性だけでなく、女性も、妻を敬う「令室」ということばを知っているのは、ごく少数です。
つまり、日本社会には、妻(女性)を敬う表現は存在しないのです。
このことは、暗黙裡に、日本社会は、妻(女性)は敬うに値する存在ではないと認めていることを意味します。
日本社会は、暗黙裡に、本来、対等である夫婦の関係性に主従、上下という立場を受け入れています。
第2は、「旦那」という呼称です。
「旦那」とは、サンスクリット語の仏教語ダーナに由来し、“与える”“贈る”といった「ほどこし」「布施」を意味します。
もともと僧侶に用いられてきたことばです。
その後、一般にも広がり、「パトロン」のように“生活の面倒をみる人”“お金をだしてくれる人”という意味として用いられるようになりました。
妾や生活の面倒を見てくれる人のことを旦那様と呼び、奉公人が生活の面倒を見てくれる人、住み込みで仕事を与えてくれる人のことを旦那様、ご主人様と呼ぶようになっていきました。
その妾や奉公人が使っていた呼称を、夫婦間の呼称として使っていることは、「嫁」という概念や妻という立場が、家庭の中、夫婦の間においては、それ同等の解釈(扱い)のもとで成り立っていることを意味します。
つまり、夫婦間で、妻が夫のことを「旦那(様)」と呼ぶその関係性は、本来、生活の面倒をみる人とみてもらう人くれる人、生活費をだしてくれる人とだしてもらう人ということになります。
第3は、“支配意識”下での呼称とは趣が異なりますが、子どものいる夫婦で、夫のことを「パパ」、妻のことを「ママ」と呼ぶ呼称です。
これは、戦後の日本社会特有の現象です。
いうまでもなく、「パパ=父親」、「ママ=母親」は、子どもから見た、つまり、子どもが使用する呼称です。
では、ひとつ考えて欲しいことがあります。
それは、実際は血のつながりはないとしても、「パパ」と呼ぶ男性、「ママ」と呼ぶ女性との性行為は「近親姦*-17」であり、「性的虐待」です。
疑似的なことはいえ「近親姦」を避けるために、性行為を避け、セックスレスになるということなら、それは、人として正常です。
この観点にもとづくなら、日本社会特有の社会病理ともいえる「パパ」「ママ」と呼び合う夫婦間でセックスレスになるのは、至極あたり前のことです。
一方で、意図的に、「パパ」「ママ」と子どもという疑似的な関係性を演出し、性行為に及ぶ行為は、疑似的な近親姦を望んでいる(無意識下を含む)ことから、パラフィリア(性的倒錯・性嗜好障害)が絡んできます。
明治政府が国家プロジェクトとして推し進めてから約150年経過した“いま”、居住し生活している都市(地域)の学校園の教職員、同級生、先輩(卒業生)や後輩、企業の経営者、職場の上司、同僚、先輩や後輩、友人、祖父母、きょうだい、父母、義父母、交際相手、配偶者が、この「家父長制」「男尊女卑」「内助の功」「良妻賢母」という概念(保守的な価値観)について、どのように捉えているかという問いは、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導員などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力行為をどのように捉えているか知るうえで重要な意味を持ちます。
なぜなら、「家父長制」「男尊女卑」「内助の功」「良妻賢母」を当然(あたり前のこと)と認識している人たちが多数派のコニュニティ(国、地域)、企業(組織)、学校園、家庭では、男性から女性への暴力を容認しやすく、暴力に対する抑制は効き難くなります。
令和3年(2021年)3月、オーストラリア統計局が10年以上かけて実施した調査結果をまとめた論文を発表しました。
この論文では、「男性のパートナーより収入が高い女性は、身体的な家庭内暴力を受ける確率が35%高くなる」、「カップルの収入の半分以上を女性が稼ぐようになった瞬間、その女性が感情的な虐待を受ける確率も20%高くなる」、「感情的な虐待を受けるリスクは、女性が占める収入の割合が大きくなるにつれて高くなる」と述べています。
調査員のロバート・ビリングと研究所特別会員のインユンジー・チャンは、「年齢、収入、居住国にかかわらず、男性のパートナーより稼ぐ女性は、家庭内暴力を受けるリスクが大幅に高くなる」、「家庭における女性の収入の割合が高くなっても、それが世帯収入の半分以下なら、身体的、及び、感情的な虐待を受ける確率はあがらない」、「男性が不満を感じるのは、世帯一の稼ぎ手になれないときだけ」と指摘し、「一家の大黒柱は男性というジェンダーに関する社会の標準から外れたときだけ、身体的な暴力と感情的な虐待を受けるケースが多くなる」、「この標準に対する意識は非常に強く、広範な人口学的特性にわたり一貫して見受けられる」、「しかし、男性に対する身体的暴力や感情的虐待のケースは増えない」と述べています。
この論文で示されているのは、「男性が、世帯一の稼ぎ手でなければならない」という考え方であるとき、「それに女性が反する、つまり、女性が男性よりも稼ぐと暴力を加えられるなどのトラブルが生じる」ということです。
この傾向は、日本社会にもあてはまります。
そして、日本社会で、女性の賃金格差が解消され、女性が配偶者の男性より稼ぐようになると、いま以上に、配偶者の男性から暴力、時に、身体的暴力を加えられる数は激増することを示唆しています。
日本は、OECD(経済協力開発機構)に加盟38ヶ国の中で、男女間の賃金格差が、韓国の34.6%に続いて、24.5%と2番目に高くなっています(2017年(平成29年))。
日本の賃金格差は、2005年(平成17年)は32.8%で、その後緩やかに減少傾向にあるものの、欧米諸国は10%台なのに対して、韓国と日本の2ヶ国だけが突出しています。
日本の男女賃金格差が大きい理由は、①正規・非正規の賃金格差と女性の非正規比率の高さ、②性別役割の固定化と就社型雇用システムの2つです。
終身雇用を前提とする正社員雇用を守るために、非正規雇用との処遇格差が大きくなります。
終身雇用と表裏一体の長時間労働・会社都合の転勤は、「男性は会社、女性は家庭」という男女分業(性別役割の固定化)を“前提”としており、女性の多くが、非正規雇用で働くことになります。
非正規労働者の70%近くが女性です。
欧米諸国においても、非正規雇用が少なくないが、ヨーロッパでは、企業横断的に同一労働同一賃金原則が浸透していることから、日本と比べて正規と非正規の賃金格差は大きくありません。
もうひとつの日本の男女賃金格差の原因である性別役割の固定化と就社型雇用システムは、根が深い問題です。
なぜなら、女性は、正社員として採用されたとしても、いまだに、結婚や出産を機に退職することが少なくなく、結果、昇格・昇給が抑制されているからです。
『改正男女雇用機会均等法』が施行され、採用や昇進・昇格においては表面上の差別はなくなりましたが、日本における女性に対する会社の姿勢は変わっていません。
日本企業に長年染みついた性別役割分業意識と女性の昇進などに対するアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)は、簡単に抜けきれるものではありません。
日本社会は、いまだに、「男尊女卑」の下で、「内助の功」「良妻賢母」を支持する人が多数派であり、「女性の幸せは、結婚し、子どもを持つことであり、子どもが生まれたら仕事は辞めて育児に専念し、育児に余裕ができたらパートタイムの仕事をして家計を助ける」、「子どもにとっての幸せは、たとえ、暴力のある家庭環境(機能不全家庭)であっても、両親の下で育つことである」という価値観・人生観が主流です。
こうした“保守的”な価値観は、いまだに、男性だけでなく、多くの女性にすり込まれている価値観・人生観です。
家庭内や親族内で、男性である夫や祖父、叔父が、女性である妻や祖母、叔母よりも優位であるとき、その中で暮らし、育つ子どもは、この関係性を見て、聞いて、察して、すり込みます。
きょうだい間における男性の優位性は、同じきょうだいであっても、女の子より男の子の教育にお金をかけたり、常に、男の子の意見を優先して育てたりすることなどに見られます。
この家庭内や親族内での日々の体験は、子どもの心の成長に大きな影響を及ぼします。
仮に、男性が優位で、絶対君主的な家庭で育った男性が、男性を過剰に敬わない女性と交際したり、結婚したりしたとき、その男性は、男性の優位性が損なわれたと感じます。
ここでいう優位性とは、男性が上で女性は下である、男性が支配し女性は従属するといった保守的な価値観です。
この優位性が損なわれた(脅威、危機)と感じた男性は、パワー(力)でこの関係性(いまの状況)を破壊しようと試みます。
これが、男性から女性に対する暴力、つまり、DV(デートDV)、ハラスメントのひとつの形です。
こうした“保守的”な価値観は、男女の区別はなく、差別・排除、DV(デートDV)、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力被害を受けた者が、学校園の教職員、同級生、先輩(卒業生)や後輩、会社の経営者、職場の上司、同僚、先輩や後輩、友人、祖父母、きょうだい、父母、義父母、つまり、身内や近しい人たちに、被害を相談したり、助けを求めたりしたとき、大きな障壁となるだけでなく、2次加害を受ける大きな要因となります。
こうした“保守的”な価値観のもとでは、「虐待の世代間連鎖」、「DVの世代間連鎖」が起きやすくなり、また、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントを容認する組織風土を醸成します。
2.126年間、懲戒権、しつけ(教育)と称する体罰を認めてきた日本
しつけ(教育)と称する子どもへの体罰や女性へのDV行為を肯定する人たちに共通するのは、自分たちも親などから体罰を受けたり、父親から母親へのDV行為を目撃したりした経験があることです。
問題は、子どもが、「暴力」のある家庭で暮らし、育つことは、人とのかかわり方としての「暴力」を見て、聞いて、察して、「暴力」で人を操る“術”や「暴力」を回避する“術”を学び、その“術”を思考・行動習慣として身につけてしまうリスクが高いことです。
無意識下に、人とのかかわり方に「暴力」的なやりとりが組み込まれてしまいます。
子どもが虐待を受けたトラウマ(心的外傷)は、単なる暴力の後遺症に留まらず、その後の人生における思考・行動習慣に影響を及ぼし、しかも、「分子の傷跡」として、子どものDNAに刻み込まれるという事実です。
カナダのリティッシュコロンビア大学などの研究チームが、児童虐待の被害者を含む成人男性34人の精子細胞を詳しく調べた結果、「精神的、身体的、性的な虐待を受けたことのある男性のDNAの12の領域に、トラウマによる影響の痕跡がしっかりと残されていることがわかった。」、「虐待を受けた子どもは、そのトラウマを示す物質的特徴が細胞の中に刻み込まれている可能性がある。」とする研究論文を発表しています。
研究チームは、「未来の児童虐待容疑の捜査において、「メチル化」として知られるこのDNAの改変を捜査当局は調べることになるだろう。」と予想しています。
ブリティッシュコロンビア大学遺伝医学部の博士号取得候補者のニコル・グラディシュは、「遺伝子を電球とみなすと、DNAメチル化は、それぞれの光の強度を制御する調光スイッチのようなものだ。そして、これは細胞がどのように機能するかに影響を及ぼす可能性がある。」、「ここで得られる情報から、児童虐待が長期的な心身の健康にどのように影響するかをめぐる、さらなる情報が提供される可能性がある。」と述べています。
この実験は、発達のさまざまな段階で遺伝子を「オン・オフ」するものについて調べる「後成遺伝学(エピジェネティクス)」の範疇に入ると考えられます。
これまで、「遺伝子は、受精時において、既にプログラムが完了している」と考えられていましたが、いまでは、「環境要因や個人の人生経験によって活性化・非活性化される遺伝子も一部に存在する」ことが知られています。
精神医学専門誌「トランスレーショナル・サイキアトリー(Translational Psychiatry)」に論文を発表した研究チームは、メチル化が、個人の長期的な健康にどのような影響を与えるかについてはまだ不明だとしています。
統計的に見ると、女性は、児童虐待の被害者となる確率が男性に比べてはるかに高いものの、卵細胞の抽出が困難なことから、今回の実験を女性で再現する予定は考えられていません。
今回の研究結果によると、「子どものときに虐待を受けた男性のゲノム(全遺伝情報)の一部は、虐待を受けていない男性と比較して29%異なっていた。」とし、研究チームは、「DNA領域における調光スイッチの影響は、予想以上に高かった。」と述べています。
この痕跡は、二重螺旋の塩基配列自体は変わらないものの、化学基が修飾することによって変化する、くっつくような感じだということです。
これは、食生活や運動などの外部環境で変化します。
ラットを使った実験では、塩分を多く摂った個体は高血圧になりやすく、その情報は、遺伝子に修飾され、生まれてくる子どもにも血圧が上がりやすい体質が遺伝する可能性があることが示されています。
メチル化の度合いには経時変化が見られることから、被験者の男性の細胞を調べることにより、虐待が行われた大まかな時期を明らかにしています。
このことについて、グラディシュは「医療従事者が活用したり、法廷で用いられる証拠として使用されたりする可能性のある検査方法を開発する助けになるかも知れない。」と指摘しました。
2021年(令和3年)11月、福井大の友田明美教授(小児発達学)らの研究チームは、「虐待などの不適切な養育を受けた子どもは、遺伝子に変化が生じ、その度合いが強いほど脳の機能にも影響する」との研究成果を発表しました。
その研究では、虐待やネグレクトなどを経験した24人(平均12.6歳)と、経験していない31人(同14.9歳)から唾液を採取し、愛着や絆、信頼の形成に関連する「オキシトシン遺伝子」のDNA15ヶ所を解析して比べています。
その結果、「虐待やネグレクトなどを経験した子どもは、経験していない子どもに比べて、遺伝子の一部にメチル基という分子が付着するメチル化が1.7倍だった」、さらに、磁気共鳴画像(MRI)検査で子どもの脳を調べると、「オキシトン遺伝子のメチル化が多いほど、脳の一部の容積が減り、機能が低下する」ことも確認されました。
この脳の部位は、「他者の視線認知と自身の眼球運動との連携にかかわることから、容積の低下により人と目を合わせられないなどの影響がでる可能性がある」、「脳機能の低下は意欲や喜び、やる気を感じる活動の低下につながる怖れがある」と指摘しています。
さらに、虐待を受けた(暴力のある家庭で暮らし、育った)人は、攻撃性と関係のある「MOMA遺伝子」の“スイッチ”を入れることなど、遺伝子レベルでひき継がれることがわかってきました。
2002年(平成14年)、イギリスのロンドン大学のリサーチセンターのカスピ博士らにより、人の攻撃性(暴力的な反社会的行動)に関係しているといわれる「MOMA」と呼ばれる遺伝子が、暴力のある家庭で暮らし、育つこととの関係性を調べた研究結果がまとめられました。
この研究は、MOMA遺伝子の活性が低いタイプは攻撃性が高く、MOMA遺伝子の活性が高いタイプは攻撃性が低いとされていることを踏まえ、MOMA活性が低いタイプのグループと、MOMA活性が高いタイプのグループが、それぞれ3-11歳のころの虐待の略歴を調べ、さらに、26歳になったときの攻撃性について、精神科・心理学的な調査や警察の逮捕歴などで調べたものです。
カスピ博士らは、「MOMA活性が低いタイプでも、暴力のない家庭で暮らし、育っている(子ども時代に虐待を受けていない)ときには、攻撃性は見られず、一方で、暴力のある家庭で暮らし、育っている(子ども時代に虐待を受けて育っている)ときには、高い攻撃性が見られた。」、「MOMA活性が低いタイプの子どもは、虐待を受けることで過度の恐怖を感じ、常習的に虐待を受け続けることで、神経伝達物質システムと呼ばれる脳の働き自体が変わってしまい、強い攻撃性を見せるようになったと考えられる。」、「攻撃性が高いと思われるMOMA活性が低いタイプであっても、虐待を受けなければ、活性が高いグループに比べても攻撃性はむしろ低いくらいであった。」、「MOMA活性が高いタイプは、虐待によって脳の機能を変えられることから、自分を守る力を遺伝的に持っているかもしれない。」との研究結果を発表しています。
この研究結果は、「子どもが、暴力のある家庭環境暮らし、育つ(虐待を受けて育つ)ことによって、“攻撃性(暴力的な反社会的行動)のスイッチ”が入る」ことを示すものです。
一方で、“従順さ”など後天的に獲得された「形質」や「学習行動」は、遺伝子やRNA(DNAと同じ核酸で、ヌクレオチドと呼ばれるリン酸・塩基・糖から成る基本構造を持ち、ヌクレオチドが連なった構造(ポリヌクレオチド)をとる)を介して、母親から子ども、孫に受け継がれる(遺伝する)という研究報告があります。
このことは、遺伝子学的に見れば、猪、牛などの家畜、騎馬(競走馬)、戦車などの役割を担った馬、象、ペットとなった犬や猫など、人の生活に密接にかかわってきた動物たちは、人に牙をむけず、おとなしい種同士を掛け合わせ、さらに、人に懐き、従順な種同士を掛け合わせ、いまに至る事実があります。
家畜やペットなど、動物が人に懐くことを「能動的従順性」といい、例えば、犬では9番染色体上にART1とART2の遺伝子領域が「能動的従順性」と深くかかわっていることが明らかになり、この遺伝子領域には、神経伝達物質のセロトニンの量を調節する遺伝子が含まれています。
このことを踏まえると、「人を殺す人」と定義されるホモサピエンス(人)の種においても、国々が積み重ねてきた歴史と人の残虐さ、勇敢さ、献身さ、秩序さ、堅実さ、従順さなどには顕著な関係性があることが理解できると思います。
精神科医の本田秀夫は、「体罰は一種の洗脳である」と指摘しています。
この「一種の洗脳」という表現は、親の行為を「見て、聞いて、学び、身につけた思考・行動習慣」とのことばに置き換えることができます。
しつけ(教育)と称する体罰を繰り返し受けて育った子どもが、大人になったときの特徴は、「自分がここまで成長できたのは体罰のおかげだと信じ込み、疑わない」ということです。
これは、厳しい指導を受けてきたスポーツ選手だった人にも多く見られる傾向です。
そのため、児童に加えた体罰が発覚したスポーツ強豪校では、父兄が体罰を隠ぺいしたり、教師(監督やコーチ)にひき続き指導を懇願したりします。
それだけでなく、被害を訴えた児童や父兄を誹謗中傷するなど、敵意を顕わにすることもあります。
「自分がここまで成長できたのは、体罰のおかげだ」と信じ込み、疑わない人が、自分の“信念”を否定されたり、非難されたりすると、自分がツラい仕打ちを受けた現実と向き合わなければならなくなります。
そのため、後ろめたい感情を見透かされないように、以前に増して、自身の行為、つまり、体罰を肯定し、正当化しようとします。
この「体罰」を肯定し、正当化しようとする行為は、それを指摘されたときに(報道やSNSの投稿などを見たり、聞いたりしたときを含む)、人に対する加害行為に至らせます。
その加害行為は、第1に、「そんなことはない!」と否定したり、「あの人はそんなことするはずがない!」と加害者を擁護したり、第2に、「被害者に落ち度(問題)があったに違いない!」と批判したりする行為です。
SNSには、こうした加害行為(誹謗中傷)が溢れています。
こうした加害行為は、親の虐待行為としての「(しつけ(教育)と称する)体罰」だけでなく、「性的虐待」などの指摘に対しても顕著に表れます。
子どもをしつける(教育する)うえで、親や教師による体罰や暴言(脅しのことば)には、一見、効果があるように見えますが、実は、「恐怖により子どもをコントロールしている」だけです。
恐怖によるコントロールを「スケアード・ストレート」といいます。
「スケアード・ストレート」は、子どもに恐怖を感じさせる(スケアード)ことで、子どもに正しい行動(ストレート)をとることの必要性を学ばせる教育法のひとつです。
この「スケアード・ストレート」は、『ランダム化比較試験』などにより、「意味がない」どころか、「逆効果を生む」ことが明らかになっています。
『ランダム化比較試験』とは、研究の対象者を2つ以上のグループにランダムにわけ(ランダム化)、治療法などの効果を検証することです。
ランダム化により、検証したい方法以外の要因がバランスよくわかれることから公平に比較することができます。
「スケアード・ストレート」は、例えば、親が、「早く寝ないとお化けがでるよ!」といい、子どもを怖がらせて寝かしつけようとしたり、「いうことをきかないと、押し入れに閉じ込めるぞ!」、「いうことをきかないと、もう買わないからね!」、「早くこないと、置いて行っちゃうよ!」といい、怖がらせ、脅して、いうことをきかせようとしたり、学校などで、人が交通事故にあった映像を見せ、「道路を飛びだしてはいけない」と教えたりする行為を指します。
こうした子どもに恐怖を与え、従わせようとする行為は、日本社会では、家庭だけでなく、学校園による教育、部活動などの指導など、大人が、子どもとかかわるあらゆる“場”や“機会”で、日常的に見られる光景です。
私たち大人は、親や教師などが、子どもを怖がらせること、つまり、子どもに恐怖を与えることは、プラスに働くことはなにもなく、すべてマイナスに働くことを理解する必要があります。
そして、この「スケアード・ストレート」には、「いい子にしない(いうことをきかない)と、お巡りさん呼ぶぞ!」などと、親が、子どもにいうことをきかせる(コントロールする)ための“嘘”という側面を伴うことがあります。
この側面の問題は、「スケアード・ストレート」と同様に、子どものときに親に嘘をつかれたことが多い人ほど、成長に伴い、親や教師、上司などに嘘をついたり、心理的な問題を抱えたりすることが多くなる傾向があることがわかっています。
これは、シンガポールのナンヤン工科大学(南洋理工大学;NTU)が、カナダのトロント大学と米カリフォルニア大学サンディエゴ校、中国の浙江師範大学との協力のもと実施された調査で、子どものころに嘘をつかれたことが多い人ほど、大人になって自分も親に嘘をついている」、「攻撃的になったり、規則を破ったり、過干渉な行動をとったりするなど、社会的に好ましくない問題を発達させてしまうリスクが高くなる」ことが明らかになりました。
そして、「親は、子どもになにかをさせたいときに、嘘をつく方が簡単だと思うかも知れないが、親が子どもに対して「正直でいることが一番」と教えているにもかかわらず、「親自身が嘘をつき、正直でない」という“相反する”言動やふるまいを子どもに見せてしまうと、子どもに矛盾したメッセージを発することになる。」、「子どもの親(大人)を信頼する心を損ない、正直さを欠いてしまう可能性がある。」と指摘しています。
相反する言動やふるまいのことを「ダブルバインド」といい、この行為は、人にどちらが正しいのかという“混乱”をもたらします。
加えて、「親の子どもにいうことをきかせる(親の権力行使として、子どもをコントロールするため)ための嘘が、スケアード・ストレートの側面が強くなるほど、つまり、子どもを怖がらせ、脅したりする要素が加わるほど、子どもの心理的な問題をひき起こす可能性が高くなる。」、「子どもに対して、親が権力を使おうと嘘をつくことで、子どもは自主性を持ち難くなったり、拒絶されたと感じたりする可能性があり、その結果、究極的に、子どもの情緒面での健康が損なわれる。」と説明しています。
心理的虐待としての「スケアード・ストレート」については、親や祖父母、親戚に加え、コミュニティ(生活圏)の人々、教師や保育士、医師、看護師、弁護士(司法関係者)、警察官、福祉事務所や保健センター、児童相談所の職員など、子どもとかかわるすべての人に必要不可欠な知識といえます。
しつけ(教育)と称する体罰が、「子どもや大人、そして、社会にとって有害である」という科学的な証拠はかなりの数存在し、250以上の研究で関連性が論証されています。
一方で、体罰のメリットを立証している研究はありません。
16万927人の子どもたちの、過去50年間の75の研究を使用したメタ分析では、身体的虐待としては軽度とされる「お尻を叩く」という体罰も、「低い規範の内面化」「攻撃性」「反社会的行動」「学校での破壊的行動」「外在化問題行動」「内在化問題行動」「心の健康問題」「否定的な親子関係」「認知能力障害」「低い自己肯定感」「親からの身体的虐待のリスク」「大人になってからの反社会的行動」「大人になってからの心の健康問題」「大人になってからの叩くことへの肯定的な態度」という有害な結果と関連することが明らかになっています。
身体的虐待により「前頭前野」が萎縮すると、感情や理性、思考をコントロールし難くなり、「前帯状回」が萎縮すると、集中力が欠け、自分で決めたり、共感したりでき難くなり、「感覚野」への神経回路が細くなると、痛みに対して鈍感になり、心理的虐待により「聴覚野」が拡大すると、聞こえ方、会話やコミュニケーションがうまくできなくなります*-18。
人は、社会活動の中で、周りの人たちと協力し、時に支え合いながら生きていきます。
子どもが、体罰などの身体的虐待の影響を受け、脳の部位が萎縮することは、子どもの将来に重大な損害(損失)を与えることになります。
体罰をはじめとする「虐待行為」は、「小児性愛(ペドファリア)」などの「パラフィリア(性的倒錯・性嗜好障害)」の発症につながります。
なぜなら、体罰をはじめとする「虐待行為」は、性的興奮のパターンに影響を及ぼすからです。
この「性的興奮のパターン」は、思春期前の幼児期・学童期の前半、つまり、10歳前に発達し、いったん確立されるとその多くは一生続きます。
「小児性愛(ペドファリア」などの「パラフィリア(性的倒錯・性嗜好障害)*-19」は、再発性の(常習的で)強い性的興奮をもたらす空想、強い衝動、または行動で、苦痛や障害を伴い、無生物、小児、その他合意の成立していない成人を巻き込み、または自分自身や相手に苦痛や屈辱をもたらすものです。
小児性愛者には、特有の脳の活動、脳の特徴があることがわかっていて、異性愛の男性が通常興奮するような性的な刺激画像を見ても、小児性愛者は興味を示さないことが脳の活動レベルから報告されています。
*-16 世界の政財界の指導者が集うダボス会議で知られる世界経済フォーラム(WEF)が、2019年(令和元年)12月に発表した『男女格差(ジェンダーギャップ)報告書』では、男女平等度で日本は過去最低の153ヶ国中121位、主要7ヶ国(G7)では最下位です。
報告書は経済、教育、健康、政治の4分野14項目でどれだけ格差が縮まったかを指数化し、国別に順位をつけるもので、153ヶ国の平均は68.6%で、日本は65.2%でした。
いま、経済学の世界では、男女の社会的役割に関する固定観念を覆すような研究が相次いでいます。
例えば、これまで、男女の賃金格差が生まれる背景のひとつとして、「女性は、生まれつき男性より競争を回避する傾向がある」といわれてきましたが、インドにある母系社会、つまり、女性優位社会での心理学実験では、「女性の方が男性よりも強い競争心を示す」という結果がでています。
これは、「女性が競争を回避したとしても、それは、社会の中で身につけるものである」ということを意味します。
つまり、「子育ては母親がすべきだ」というような、従来の「男らしさ」「女らしさ」の考え方はあてにならないということです。
にもかかわらず、男性が多い社会では、露骨な女性差別でなくても、同性の男性を選びがちだという無意識のバイアス(差別・偏見)があり、格差の解消を難しくしています。
*-17 「近親相姦」という表現ではなく、相互行為の意味が含まれる「相」の文字を省き、「近親姦」と表現します。
「相姦」の相互行為には“性的同意”の意味があり、性的虐待を受けた当事者とっては、文脈や用途にかかわらず、「近親相姦」という表現に触れたとき、「相互ではなく一方的」、「同意していない」と反応し、2次加害(セカンドレイプ)にあったと認識することもあります。
*-18 体罰など、親からの暴力行為による脳の部位の損傷が、MRI検査などで「視覚化」できるようになったことについては、この「はじめに。」の中の「支援活動16年。脳科学の発展と関連法の改正、とり巻く状況の変化」の“第1”で詳しく説明しています。
*-19 「パラフィリア(性的倒錯・性嗜好障害)」については、「Ⅱ-20-パラフィリア(性的倒錯・性嗜好障害)」で詳しく説明し、交際相手や配偶者との間での性暴力とパラフィリアの関係性については、「Ⅰ-A-2-(9)パラフィリア(性的倒錯・性嗜好障害)の夫による性暴力」で、事例を交えて説明しています。
3.DV被害も「子どもがいるから別れない」という選択
「1」で示した日本社会特有のジェンダー観、家族観は、子どものいる家庭におけるDV被害者にとって、暴力に支配される関係性を断ち切るうえで大きな障壁になります。
このことは、平成24年(2012年)4月、内閣府男女共同参画局が実施した『男女の暴力に関する調査』において明らかになっています。
この調査(回答者227名)で、「DV被害を自覚している被害女性が、配偶者と別れなかった理由」の第1位は、130名(57.27%)が回答した「子どもがいるから、子どものことを考えたから」です。
これは、第2位の43名(18.94%)が回答した「経済的な不安があったから」とは、実に38.33ポイントの差があります。
つまり、日本では、DV被害を自覚している状況の中で、実に76.21%(173名)の被害女性が、「子どもがいる」「子どものことを考えて」「経済的に不安」という理由で、DV加害者である配偶者と別れられないでいる(別れる選択を避ける)ことになります。
このことは、結果として、子どもを暴力のある家庭環境に留める(面前DV下におく=心理的虐待を与え続ける)“選択”をしていることを意味します。
問題は、日本社会の多くが、この選択を正しいと認識し、その判断を支持していることです。
このことは、DV被害者の相談・援助者となる得る親やきょうだい、親族、友人、子どもが通う学校園の教職員、勤務する会社の経営者、職場の上司や同僚、そして、加療を要する傷害の治療にあたる医師や看護師、被害の相談を受ける行政機関の職員、支援機関のメンバー、警察官、弁護士なども、この選択が正しく、その判断を支持していることが少なくないことを意味します。
したがって、この選択を正しいと支持している人に、DV被害を相談したり、助けを求めたりすると、当然のように、「子どもがいるんだから、がまんしたら」、「離婚したら、子どもがかわいそう」、「子どもをひとりで育てるつもり」、「どこの家庭でも、暴力はあるわよ」と、暴力のある家庭に留まるように助言されたり、「あなたにも至らないことがあったんじゃない。そこを直さないと」と非難されたりするリスクがあります。
上記のような本人は助言したと認識していることばの数々は、否定、非難でしかなく、最後の非難のことばとともに、DV被害者にとって2次加害となります。
ところが、DV被害者自身が、この非難であるはずのことばを「そのとおり」と認識し、その選択を望むときには、「交際相手や配偶者が暴力をふるわなくなる方法」を必死に探し求めます。
このとき、DV被害者は、相談、支援、民間資格のカウンセラー、自己啓発セミナーという名を借りて、「夫が右脚をだしたら、靴下を履かせなさい」などと、「内助の功」「良妻賢母」という概念(教え)、古典的な家族主義を唱える「キリスト教」、「天理教」「創価学会」などの新興宗教、「エホバの証人」「旧統一教会(世界平和統一家庭連合)」「幸福の科学」「国家神道」「アレフ」などのカルト、非科学的な親学、スピリチュアル、占い、そして、加害者の自助グループ(共同親権など)につながることがあります。
「あえて夫婦に上下、支配と従属の関係性を推奨する教え」の下で、暴力を避けるために、より従順に、意に添うようにふるまう術を学んでいきます。
こうした「交際相手や配偶者が暴力をふるわなくなる方法」を必死に探し求めるDV被害者の中には、一般的なDV被害の相談機関に相談したものの、期待していた回答を得られず、つまり、暴力をふるわなくなる方法を教えてもらえず、逆に、離れる(別れる)ことを勧められたと腹を立て、非難したりする人もいます。
結果、DV被害を長期化(常態化)させ、被害女性とその子どもは、暴力による心身のダメージは重く、深刻になります。
また、「暴力行為はいけない」との考えであっても、意識の中に、「たった一度くらいなら」、「よほどの理由があるのなら仕方がない」、「夫婦の間ならただのケンカだろう」、「しつけ(教育)のためだから、子どもへの体罰は認められる」など、“一定の条件下”であれば、暴力行為を認める(容認する)考え方が潜んでいる可能性があります。
日本社会では、いまだに、人権意識にもとづく「いかなる理由があっても、いっさいの暴力行為は許されない」との人権認識の下で、「子どもをDV・虐待のある家庭環境に留めて(育てて)はならない」という考え方に立つ人は少数派です。
「女性の幸せは、結婚し、子どもを持つことであり、子どもにとっての幸せは、たとえ、暴力のある家庭環境(機能不全家庭)であっても、両親の下で育つことである」という保守的な価値観(概念)が主流であり、しかも、日本の「児童福祉」における“子の利益(福祉)”の判断、そして、戦後の「社会保障制度」の“中核”に位置づけられています。
4.被害者が孤立しやすい。相談、助けを求め難い社会風土
離婚後のひとり親家庭(シングルマザー)における子どもが貧困に陥りやすい要因のひとつが、「G7の中でもっとも遅れている」、「G7の中で、これほどまでに家族法に後ろ向きな国は他にない」と指摘される「家族法(民法)」です。
日本では、家庭の問題に対し、家族内に紛争があっても公的機関はほとんど介入しません。
世界に類がなく、日本における離婚の90%を占める「協議離婚」では、養育費の支払いや離婚後に子どもとどうかかわるかなどは、離婚する夫婦間でとり決められ、そのとり決めには法的義務は生じません。
そのため、離婚後、養育費は70%以上が支払われず、結果、ひとり親家庭のシングルマザーと子どもは困窮しやすくなります。
さらに、「婚姻破綻の原因が、配偶者である夫からのDV行為である」ときには、DV被害の後遺症で精神的に不安定になり、働くことができず、困窮を極めるなど、経済的に破綻に至るリスクが高くなります。
一方、欧米諸国では、離婚、離婚後のとり決めには、裁判所が関与し、離婚給付や養育費が算定され、執行されます。
加えて、公的機関が、養育環境が子どもにとって適切かを判断し、必要があれときは、子どもは速やかに保護されます。
この日本の「家族法の不備」と次に述べる「家族を優遇する社会保障制度」は、DV問題・児童虐待問題の解決を困難にする大きな要因となっています。
日本の「社会保障制度」は、個人よりも家族に重点が置かれている、つまり、家族を優遇する制度設計になっています。
このことは、欧米諸国に比べて、女性や子どもを家に縛りつけやすい構造を伴うことを意味します。
つまり、日本社会では、女性は、結婚し、嫁として家族に属し、子どもを設けたとき、その関係性を維持し続けなければ、国の制度として、経済的に不利を被りやすくなります。
この家族に重点が置かれた日本の「社会保障制度」では、ひとり親家庭(シングルマザー)では生活が困窮しやすくなります。
加えて、社会保障制度として、DV行為に及ぶ配偶者と別れ難い側面には、被害者が、暴力のある環境から逃れたあとにも不自由な生活を強いられるという不合理さが含まれます。
それは、「被害者は、加害者の暴力から自分の命(身)を守る」ために“逃げる(身を隠して生活をする)”という重い選択をしたときに顕著になります。
この「被害者が、加害者から自分の身(命)を守る“選択”」は、加害者は、これまでと同じ生活(仕事、学校を含む)を送ることができるのに対し、被害者は、これまでの生活(仕事、学校を含む)を捨て、一から生活を再建しなければならないなど、不合理さ、理不尽さがつきまといます。
女性センターや所轄警察署は、『配偶者暴力防止法』に準じ、被害者の「一時保護」を決定したり、地方裁判所が、被害者の申立てにより接近禁止を含む「保護命令」を発令したりできますが、『ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)』を含めて、現実として、加害者から被害者の命(身)を完全に守ることはできません。
それだけ、加害者は、時に、常軌を逸した行動にでる可能性があります。
DV対策で重要なことは、被害者自身、被害者の親やきょうだい、被害者の近しい人たち(友人、教師、同僚や上司など)、そして、DV相談機関や福祉行政の職員、弁護士、医師や看護師、子どもが通う学校園の教職員など、いずれの立場であっても、加害者認識に、一般的・常識的な考え方や解釈を持ち込むことは大きなリスクとなります。
そのため、DV問題や児童虐待問題の解決には、DV問題や児童虐待問題に精通した専門機関のサポートが必要です。
ところが、日本社会では、DV被害者(デートDV被害を含む)の多くは、先の記述のとおり、DV問題や児童虐待問題に精通した専門機関につながり難く、結果、被害を相談したり、助けを求めたりすることが困難です。
ここには、「日本社会が、ソーシャル・キャピタルが極めて低い」という問題が絡みます。
「ソーシャル・キャピタル」とは、「家族以外のネットワーク(社会的なつながり)」を意味し、ボランティアや地域活動への参加など、地域社会での「人との信頼関係や結びつき」を示す概念です。
2018年(平成30年)、英国シンクタンク「レガタム研究所」は、149の国や地域に対して、繁栄の度合いを経済、教育、安全などの9項目に分けて数値化した「繁栄指数」を発表しました。
日本の繁栄指数は、健康や安全性などの項目が高い指数を示しましたが、「ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)」の充実度は、149の国や地域の中で99位、OECD(経済協力開発機構)に加盟する先進国31ヶ国の中では、下から2番目の30位です。
最下位のギリシャが、アメリカのRussell Investmentsにより発展途上国に範疇替えさせられているので、事実上、日本は先進国31ヶ国中では最下位です。
日本は、決して豊かとはいえないガーナなどのアフリカ諸国を下回っています。
「日本社会が、ソーシャル・キャピタルがきわめて低い」という現実は、日本では、「圧倒的多数の人が、家族などのコミュニティ以外に居場所を持たない」ことを意味します。
このことは、日本社会は、一緒に暮らす家族はいても、家族以外に居場所がなく、相談できる人がいない状況であることを示しています。
つまり、日本社会は、家族が当事者であり相談そのものが不可能な状況にあるDV(デートDV)、児童虐待に加え、家族に相談し難いレイプなどの性暴力、差別・排除、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力被害にあったとき、被害者は、誰にも相談できず、孤立しやすい深刻な問題を抱えています。
性的な被害、児童虐待、DV、ストーカー、交通事故、殺人や傷害などの暴力被害を受けたとき、自治体の相談窓口について、「被害にあう前から知っていた」のは7.0%に留まり、「被害にあったあとに知った」の12.2%を加えても僅か19.2%です。
つまり、自治体の相談窓口を知らない人が80.8%に及んでいる、それが、日本の現実です。
このデータは、平成28年(2016年)1月、性的な被害、児童虐待、DV、ストーカー、交通事故、殺人や傷害などの暴力被害の6種に対して、警察庁が、20歳以上に実施したインターネットによるアンケート調査で、被害を受けた経験のある被害者本人とその家族917人から回答を受けたものです。
また、はじめて被害にあったとき、誰にも相談していない人の割合が最も多かったのは、児童虐待の74.3%で、その理由(複数回答可)は、「低年齢だったため、相談を思い至らなかった」が73.1%を占めています。
このことは、児童虐待被害を受けた人(子ども)の3/4は、誰にも被害のことを話せず、警察や児童相談所、保健センター、福祉事務所の助けを受けられなかったことを意味します。
次に多かったのは、性的な被害で、誰にも相談していない人は52.1%に及び、「他人に知られたくなかった」などの理由が多く、DV被害では、32.8%が相談をしていませんでした。
さらに、警察に通報・相談しなかったのは、「警察に相談するほどの被害ではないと思った」と理由と回答した人は、DVで46.0%、ストーカーで39.4%、交通事故で35.3%でした。
この結果は、被害者が相談窓口の存在を知らないことに加え、暴力被害を他人に知られたくないとの思いが働いたり、家庭内の暴力被害を矮小化したりする被害者心理が強く影響することを示しています。
加えて、被虐待体験をしてきた人は、これまで、ずっとそうであったように、「ツラい、苦しい、哀しい、やるせない」、「助けて!」という思い・感情を押し殺し、心の奥にしまい込むことで、ツラい記憶はなかったことにしてしまい、結果として、「助け」を求めなくなっていることがあります。
被虐待体験をしてきた人は、親の日々の言動や態度などにより、幼児期に「家の“秘密”を他の人に話してはならない」と自ら察したり、親にそう思い込まされたりしてきたことが、人に困っていると訴えたり、人に助けを求めたりするブレーキとなっていることです。
被虐待体験をしてきて、人に助けを求められない人は、子どものときに、親から呪文のように、ア)「人に謝ることは、負けを認める」こと、イ)「人にツラい、苦しい、哀しいと話すことは、人に弱みを見せる」こと、ウ)「人に助けを求める=人に頼ることは、人に迷惑をかける」こと、エ)「人に迷惑をかけることは、親に迷惑をかける」こと、オ)「親に迷惑をかけることは、親の期待を裏切る」こととして、徹底的に、「だから、してはいけない(禁止)」と教え込まれ、まるで新興宗教やカルトの教義(教え)のように、その後の人生を縛りつけます。
幼児期に、こうした価値観を身につけてきた人は、大人になっても、人に弱みを見せたり、負けを認めたり、人に頼ったりすることができず、時には、攻撃的だったりします。
それは、強迫観念的で、時に病的です。
人に自分の心内(本心)を話したらどう思われるのだろうと強烈な不安(恐怖というべき)に襲われるだけでなく、そもそも人に頼るにはどうしたらいいのか、その方法(術)を知りません。
「困ったときには、人に頼ってもいい」という認知とその認知に伴う行動の背景には、親に守られ、安全で、安心できる体験をしていないことから、本質的に、乳児期の自分を親(養育者)に委ねることから学ぶ、人を信じること、成長過程の自分を親(養育者)に信じて見守られることから身につく、自分を信じることを獲得できていません。
エリク・H・エリクソンによる「発達段階」では、心理的課題として「基本的信頼-不信」をとり込むのは0-2歳で、導かれる要素は「希望」です。
つまり、0-2歳(乳幼児期の前半)で「基本的信頼」が得られず、「基本的不信」が主体となると「確信的な希望」を持つことができなくなります。
確信的な希望は、チャレンジすること、前に進もうとすることの意欲となるものです。
親(養育者)からの暴力体験は、拒絶のメッセージを心に刻み込むため、人に拒絶されることが恐怖(見捨てられ不安)となることから、人に拒絶されることにつながる行為すべてから逃げようとします。
自分の思いや考えを口にしたり、行動に移したりしたときに、相手の反応(相手にどう思われたか)が怖く、口にしたり、行動に移したりすることを避けます。
つまり、思考・行動のモノサシ(判断基準)は、「人に拒絶され、自分が傷つくのを避ける」ことです。
このモノサシ(判断基準)は、拒絶されることに対する恐怖、その恐怖のもとは暴力であることから、この回避行動はPTSDの症状です。
つまり、被虐待体験をしてきた人(無自覚な人を含む)に、こうしたものの捉え方、考え方があり、回避行動が認められるときには、医療機関を受診せず(診断されず)、治療を受けていないとしても、その背景には、PTSDを発症するほどのトラウマ体験があります。
この被虐待体験者の典型的な特徴ともいえる拒絶されることに対する恐怖心、つまり、「見捨てられ不安」は、カラカラに乾いたスポンジのような渇望感、心の中にぽっかりと空いた大きな穴のような空虚感、底なし沼のような寂しさを伴い、一度できた人との関係性には強く固執します。
その固執(執着)が強く、感情の起伏が激しく、激情を示すときには、(C-)PTSDの併発症としての「ボーダーライン」が疑われます。
また、人を信じたり、自分を信じたりする概念を獲得できていないので、人とのやりとりには、善意(行為)はなく、必ず裏がある(悪意がある)と認知(間に画った考え方の癖=認知の歪み)しています。
人に頼っても、人は善意で動かないので、人に頼るには相当の対価が必要と考えます。
暴力のある家庭環境が嫌になったり、愛想を尽かしたりして家出を繰り返す中高生の少女たちが、泊めてもらう対価としてセックスを強いられたり、宿カレが売春行為を強いたりするのを安易に受け入れてしまうのは、対価を求めない“善意”という存在を信じていないからです。
また、「人に助けを求める」ことは、「人に迷惑をかける」との認識と深く結びついています。
この「人に迷惑をかけてはいけない」は、「人と接しない」につながり、それは、人との関係性を閉ざすことで迷惑をかけない状況をつくります。
一方で、SNSなど急速に広まったネットワークの中で、どこにもつながることができなかったり、相談したり、助けを求めたりしたときに2次加害を受けた多くの被害者が、その被害にあった苦しみ、ツラさ、哀しみ、やるせなさを書き綴り、感情を吐きだし、理解して欲しい思いなどを訴えています。
5.欠落している「あらゆる暴力行為は人権侵害である」との認識
では、DV(デートDV)被害者が、女性センターなどの相談機関や警察署に相談したり、助けを求めたりし難い理由、背景について、もう少し踏み込んでいきたいと思います。
DV被害者が、DV被害を相談したり、助けを求めたりし難い理由は、a)交際相手や配偶者からDV被害を受けている被害者自身が、日々自分がされている暴力行為がDVだと認識できていない、あるいは、DV行為だと確信が持てないこと、b)一度は信頼し、好きになり、親密な関係にある交際相手や配偶者をDV加害者と思いたくない(認めたくない)心理が働くことです。
a)は、知識の問題です。
DV(デートDV)や児童虐待、差別・排除、いじめなどの暴力行為、妊娠、性感染症などの人権教育で、正しい情報が伝わり、知識が深まることは、被害を少なくしたり、被害が長期化したりするのを防ぐ大きな助けになります。
次に、DV被害者にb)の思いがあるとき、DV被害者は、自分がDV被害を受けていることを認めたくない(受け入れたくない)心理が働き、DVということばに過剰に反応し、ことばにすることができず、第3者から指摘されたり、心配されたりすると「DVは受けていない!」と強く否定します。
この状況は、DV加害者が、自身の暴力行為を受け入れ(認め)なかったり、アルコール依存者が、自身がアルコールに依存していることを認めなかったりするのと同じで、「否認の病」的なものです。
したがって、DV被害者が、自身が交際相手や配偶者からDV行為を受けていることを認める(受け入れる、否認しない)ことが最初のステップです。
ただし、DV被害者自身が、被虐待体験をしているときには、別の意味が含まれてことがあります。
それは、c)「交際相手や配偶者が暴力をふるうのは、自分のことが嫌いだから」との認識、つまり、「人が、意地悪をする(嫌なことをする)=その人は、自分のことを嫌い」という“論理(理由づけ)”での解釈です。
暴力行為は、好き嫌いといった感情がトリガー(引き金)となるのはごく一部に過ぎず、その多くは、人(被害者)の“態度”“言動”“姿勢”“立場”“服装”が気にいらない、つまり、自分の意に反する、意を汲んでいない、自分に対する敬い、怖れを感じられない、生意気、誘っているなど自己中心的な認知がトリガーとなります。
トリガーのモノサシ(判断基準)は、加害行為に及ぶ者のそのとき(瞬間)の気分、雰囲気に左右され、一定ではないことから、この前は大丈夫でいまはダメ、この前はダメだったのにいまは大丈夫と状況(ダブルバインド)が生まれ、被害者は混乱します。
「嫌われると捨てられる可能性がある=死に値する恐怖である」、「その死に値する恐怖を回避するためには、嫌われてはならない」、「嫌われないためには、嫌われることはしない、喜ばれることをしなければならない」という思考・行動パターンは、アタッチメントが形成され母子分離が進む3-4歳までにつくられます。
「死に値する恐怖」とは、乳幼児・学童期の子どもは、親の庇護がなければ生きていけない(生存できない)ことに起因しています。
この思考・行動パターンを身につけていることは、乳幼児期に「拒絶メッセージ」を含むことばや態度を伴った虐待を受けて育っていることを意味します。
そのため、c)の傾向のあるDV被害者は、「暴力を加えるのに好き嫌いの感情は関係ない」という事実を知り、理解することと、被虐待体験をしてきて抱えるトラウマ(心的外傷)に対する治療が重要です。
交際相手や配偶者から最初のDV被害を受けたとき、a)の「知らない」ではなく、「知っている」であれば、DV被害を長期化させ、事態を深刻化させずに、暴力のある環境(暴力を加える人)から離れることができるので、その国が、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力行為に対し、どう向き合い、どのような対策を講じてきたのかと深くかかわります。
b)はc)と深くかかわることから、b)とc)は、被虐待体験をしない家庭環境で育ち、成長することで、暴力のある環境(関係性)に留まり、被害が長期化し、深刻化することを防ぐことができます。
つまり、被虐待体験をしていると、交際相手や配偶者から暴力をDV行為だと認識し難く、DV行為だと確信が持てないまま、あるいは、DV行為だと認めたくない思いの中で、ずるずると暴力に屈し、暴力に支配される関係を続けてしまいやすくなります。
したがって、DV被害を長期化、深刻化させないためには、第1に、人権教育をいまの親の世代と学校教育を受ける機会が多い24歳以下の子どもに対し一斉(一定期間、時期を空けず)に実施すること、第2に、子どもに対ししつけ(教育)と称する体罰をはじめとする虐待行為(厳格な基準)を認めず、その環境下で子どもを育てないことです。
暴力行為に対する人権解釈は、「いかなる理由があっても、人に暴力を加えることは許されない」ということです。
いま(これまで)、交際相手や配偶者からDV被害を受けている(きた)人が、知識として学んでおく必要があるのは、「私は、他人に傷けられるような人(存在)ではない」ということばです。
このことばは、「自分は大切な存在」と自覚する、つまり、「自分の存在そのものを肯定する」ことにつながります。
あえて、「知識として」としているのは、被虐待体験をしている(きた)人は、実体験として「自分を大切にする」という感覚がわからない人が少なくないからです。
たとえ、感覚としてわからなくても、まず、ことば(知識)として、「誰であっても、他人(親などを含む)に傷つけられていい人はいない」ことは知っておく必要があります。
「人からの暴力行為で、自分が傷つけられることは人権を侵害される」ことです。
暴力で人を傷つける行為のすべては、人権侵害です。
差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力は、人権を侵害する行為、つまり、人権問題です。
人権問題については、学校教育だけではなく、家庭内でしっかりと教えることが重要です。
しかし、人権教育をしてこなかった日本社会では、学校教育の現場、コミュニティ、家庭で、人権教育を教えられる人がほとんどいません。
肝心な学校教育の現場では、いまだに、“子どもの権利*-20”を尊重しているとはほど遠く、男女という性別をめぐる固定観念・偏見に満ちています。
先の記述のとおり、“保守的”な「ジェンダー観」は、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力行為の解決を困難にさせます。
「性の多様性」ということばは、日本社会でも徐々に知られてきましたが、“保守的”な価値観にもとづく日本の学校文化、企業文化には馴染まない状況です。
日本の教育現場では、日本語指導が必要な外国にルーツを持つ子どもたち、また、さまざまな障害のある子どもたちが安心して学べる環境は、いまだに整備されておらず、多様性の尊重は実態を伴っていません。
それどころか、むしろ、このような子どもたちを普通学級から排除していく傾向が顕著です。
また、被虐待児童と関係性が深い「不登校(ひきこもり)」の問題(いじめを起因する不登校を含む)に対しても、「別の場所を用意するから無理して登校しなくていいよ」といった趣旨の『義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律』が、平成28年(2016年)に制定されたものの、教育現場では、子ども、そして、家庭(親の教育)に問題があるかのように語られています。
家庭(親の教育)に問題があり、それがDV・虐待問題なら女性センター、保健センター、児童相談所、警察、医療など、それが貧困やヤングケアラーの問題なら保健センターや福祉事務所など、子どもの心(精神疾患、発達障害を含む)の問題なら保健センターや医療などに、それぞれの専門機関に速やかにつなげ、連携することが、教育機関としてしなければならないことです。
しかし、欧米諸国とは異なり、日本の教育現場で重視しているのは、「児童が登校し、不登校でない」ことです。
そのため、「登校できない子ども」が問題視されることになります。
このとき、いまの学校教育、いまの教育制度の仕組みに、子どもが登校できなくなる原因があるのでは?といった視点は、自己批判となることから疑う思考すら存在せず(組織内で否定され)、排除されます。
本来は、無理しなければ行けなくなるような学校、あるいは、いじめの加害者にこそ問題があるはずです。
しかし、いじめの被害者である子どもが、転校を勧められています。
こうした学校から見て問題のある子ども(余計な手のかかる子どもと解釈)の「排除」は、教育現場では、「その子に合った指導を」ということばに都合よく置き換えられます。
結果として、日本の子どもたちは、多様な出会いの機会は失われています。
「人権の保障」は、人々の「多様性を否定」しては成り立ちません。
問題は、日本社会では、こうした学校教育から排除される人たちは、“差別”“排除”の対象となっていること、そして、その「差別・排除意識」に対し、日本社会が無自覚、無頓着であるということです。
日本の学校教育において、この「差別・排除」という問題は、「思いやり」や「やさしさ」といった心の問題として扱われています。
それは、「人権教育」ではなく、「道徳教育」を実施することに示されています。
道徳の授業は、個人の「心のあり方」を問題とします。
一見すると、個人の道徳性のあり方から差別問題などの社会的な課題に対応していくことには効果があるように思えます。
なぜ、そう思ってしまうのでしょうか?
さまざまな差別問題は、常に具体的です。
ある特定の誰かに起こる問題であり、そこでは、個人的な、ある人とある人との狭い範囲の関係のあり方が問われます。
しかし、そうした視点だけでは、「差別・排除」について十分に考えることはできません。
なぜなら、差別・排除は、個人的な「人間関係」を超えた、より広い社会関係の中で起きるからです。
現行の道徳教育では、「狭い関係性」にばかり注意が集まってしまい、その関係の中に、社会的に仕組まれたより広い構造的課題が凝集していることを考えることができません。
「心のあり方」を問題とする道徳の枠組みでは、この社会的な構造は問い難いのです。
日本では、教育現場に限らず、差別・排除だけではなく、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力行為の問題も、個々人(特定の家庭、特定の職場、特定の学校)の「心のあり方」の問題と捉え、論議され、対策が講じられています。
しかし、個々人の「心のあり方」の問題として捉える限り、問題の本質に踏み込むことはできません。
そこで、必要とされるのは、「人権認識」の醸成と、そのための「人権教育」の実施です。
『日本国憲法』の第14条にあるとおり、「差別は、政治的、経済的、または、社会的関係において発生」します。
したがって、この関係のあり方を分析し、変えていくことでしか、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力問題は解決できません。
なぜなら、これらの暴力問題は、「人権教育」でとり扱う問題だからです。
人権教育は、「人が自らの権利を知り、権利の主体として、それを実現するために行動する」ことが、「人間性の回復であり、社会を変えることにつながる」ようにするものです。
つまり、人権教育の目的は、構造的に問題を把握することであり、それにもとづく社会変革です。
これは、道徳が「心のありよう」という個々人の内面にフォーカスし、その枠組みにおいて問題を把握するのとは大きく異なるものです。
「人権」は、人類の歴史において、市民自らの手(力)で“獲得”してきたものです。
それは、その時々の社会体制の中で虐げられ、人としての尊厳を踏み躙られてきた人たちが、自らの人間性の回復を「人権」や「権利」という概念で表現し、権力と闘うこと(市民的抵抗、レジスタンス)で勝ちとってきたものです。
人権や権利は、「社会的」で「争議的」なものです。
a)DV行為の防止と保護(配偶者からの暴力の防止及びに被害者の保護等の法律)、b)ストーカー行為の禁止(ストーカー行為等の規制に関する法律)、c)親の子どもに対する体罰の禁止(児童虐待の防止等に関する法律、懲戒権(民法822条)の削除)、d)ハラスメント行為の防止(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)、そして、e)ヘイトスピーチ防止する条例などは、欧米諸国で社会運動がおこり、遅れて日本で問題意識が高まったり、または、国際連合などが、日本の現状を問題視することで、法律の制定であったり、改正につながったりしてきました。
確かに、社会的な動きの中で、市民が勝ちとったものですが、日本では、法律の制定にあたり、その法律が社会システムにどのように適合するかという視点が欠けています。
そのため、日本社会の“保守的”な価値観である「男尊女卑」「内助の功」「良妻賢母」、同じく“保守的”な「家父長制」を軸にする家族制度、その家族制度を前提に構築されている「社会保障制度」、そして、その家族制度、社会保障制度で成り立っている企業風土の下では、これらの法律は、被害者が守らず、被害者が理不尽で、不合理を強いられてしまうなどの齟齬が生じています。
“保守的”な価値観、“保守的”な家族制度を軸にした社会システムはそのままで制定した日本の法律は、母屋に次々と部屋を増築し続けた結果、迷路に迷い込み、目的地にたどり着き難く、路頭に迷うような状況になっています。
つまり、いまの日本では、法律はできても、社会システムとして機能し難くなっています。
差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力問題が解消される“道筋”は、人々の意識が変わり、行動を起こし、社会的な制度や構造(仕組み)が変わる中で拓けてくるものであって、一方的な“温情”や“思いやり”といった個々人の「心のあり方」によってもたらされるものではありません。
歴代の法律を制定する国会議員、政党、政権は、この視点が備わっていないというよりも、国民が人権意識に目覚め、こうした動きにつなげること妨害し、排除することに長けています。
それは、「民は愚かに保て!」の政治原則にもとづいています。
日本が導入を拒み続けている「人権教育」は、いま、自らが生きている社会についての分析が不可欠です。
そこでの人々の暮らしをどう理解していくか、それを踏まえて、社会のどこに問題を見出し、どのように変革していくかを問うことが求められます。
例えば、人権や権利を守るためには、どのような法制度が必要なのかを問うものです。
ここには、国をどう位置づけるかという観点も含まれます。
平成12年(2000年)に制定された『人権教育及び人権啓発の推進に関する法律』の第2条では、「人権教育は、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動である」と定義し、「人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く)をいう」としています。
この法律における人権教育や啓発は、個人の精神を涵養し、理解を深めていくと規定しています。
つまり、この法律は、「心がけ」に重点が置かれていることから、人権教育というよりも「道徳教育」の目的に近くなっています。
先に記しているとおり、人権に関する問題は、道徳では解決できません。
なぜなら、それは心の問題ではないからです。
人に危害を加える行為は、危害を加えられた人の人権を侵害することです。
したがって、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの問題は、個々人の心の問題として道徳観に訴える限り解決することはできません。
これらの問題は、「人権問題」と認識し、解決していかなければならないテーマです。
これらの「暴力行為」に対する課題を個々人の心の問題として認識したまま「法律」を制定すると、「法律」が限定的であったり、「法律」の解釈に抜け道があったり、「法律」が「社会制度」として機能しなかったり、「法律」が時代や現状にそぐわないまま放置されていたりする事態を招きます。
日本の人権や権利に関する教育の問題は、時に法律がそうであるように、個人の価値観や道徳性の涵養へと都合よく(容易に)置き換えられてしまうことです。
例えば、いじめなど人を傷つけてはいけないことを教える「命の授業」は、個々人の「心のあり方」の問題として道徳観に訴えて解決しようと試みています。
平成26年(2014年)7月、女子生徒が高校の同級生を殺害し「人を殺してみたかった。」と供述した「佐世保同級生殺害事件(事例282/事件研究49)*1」が発生し、例年5-7月のうち1週間を「命を大切にする心や思いやりの心の育成」を目的にした“命を大切にする教育”を10年間続けてきた長崎県の教育関係者に衝撃が走りました。
この“命を大切にする教育”は、平成16年(2004年)6月におきた小学校6年生の女子児童が同級生を殺害したショッキングな事件(佐世保小6女児同級生殺害事件(事例227/事件研究30)*2)後に、市内の小中学校で命の尊さを学ぶとり組みを続けてきました。
この命の尊さを学ぶとり組みは、長崎平和公園や原爆資料館を見学したり、佐世保空襲の体験者を招いて話を聞いたりすることで生命の尊さや戦争の悲惨さを学ばせようとするものでした。
その中で、悲劇が繰り返されたことに対し、長崎県の教育関係者はショックを受けました。
敢えて苦言を呈すると、長崎県の教育関係者は、この10年間、命の尊さを学ぶとり組みが、成長した子どもたちが人を傷つける行為の減少につながってきたのかを検証してきたのでしょうか?
検証の結果、人を傷つける行為は減少している中で、悲劇が繰り返されショックを受けたのであれば、ある程度、教育関係者の葛藤は理解できます。
この殺傷事件前の平成24年(2012年)の長崎県14歳-19歳人口1万人あたり少年犯罪の検挙数は62.56人(503人)で全国25位、また、非行発生率は、命の尊さを学ぶ授業がはじまる前の昭和60年(1985年)24.98で全国24位、平成2年(1990年)21.13で全国27位と順位はわずかに下回り、非行発生率は少し改善した(全般的にほぼ横一線)状況が続いているように、命の尊さを学ぶ10年間のとり組みが少年犯罪を減少させる相関性(因果関係)を確認することはできません。
しかし、10年間にわたり、「命を大切にする教育」にとり組んできた長崎県の教育関係者は強いショックを受け、無力感にうちひしがれました。
長崎県に限らず、「命の授業」の多くは“思いやり”“優しさ”といった個々人の「心のありよう」にフォーカスして実施、つまり、道徳教育の一環として実施されています。
こうした社会問題に対する道徳的なアプローチ、つまり、個々人の「心のもちよう」による解決、個人的関係の中での解決というアプローチは、自己救済を強調し、国などの公的機関がしなければならない諸施策を免責する危険性も孕んでいます。
つまり、国や公的機関には非(責任)はなく、それは、個人の問題と片づけるのに役立ちます。
一方で、本来、国や公的機関がしなければならないことを、個人の努力や民間機関の仕組みでなにかを成し遂げたときには、国(政権、政党、政治家)は褒め称え、政治利用します(感動ポルノ)。
人権意識が根づかない国々では、人権意識は、国(政権)や権力者にとって都合が悪い、目障りなものです。
そのため、政権や権力者に従順ではなく、反旗の声をあげる人々をつくりかねない「人権教育」をとり入れようとしません。
それはおかしい、間違っている、正さなきゃならないと「声をあげる活動的な市民になる」ために、一人ひとりが、自らの権利を学び、知識を得ることはとても大切なことです。
「いかなる理由があっても、暴力行為は許されない」という人権意識にもとづく規定=モノサシ(判断基準)がないとき、そのモノサシは、その人の感覚や認識に大きく左右されます。
“疑わしきは罰せず”を採用している日本の法律の解釈においても、このモノサシがなかったり、あいまいなモノサシであったりすることで、警察や検察の解釈、加害者・被害者の弁護士の解釈(腕)に大きく左右され、結果は一律ではありません。
例えば、「強制性交等罪(刑法177条)」が適用されたレイプ事件において、その成立要件となる「暴行・脅迫」「恐怖・驚愕」「地位利用」「心身に障害を生じさせる」などの行為で被害者を「拒絶困難」な状態にさせた場合に処罰する」という基準があいまいなことから、起訴された加害者(被告人)の弁護士の「被害者の抵抗は、著しく困難とはいえない。したがって、強制性交等罪は成立しない。」との主張が採用され、無罪判決が相次いでいます。
このように、人権解釈がなかったり、法律があっても基準があいまいだったりすると、不合理で、理不尽な思いにさせられるのは、常に、被害者や社会的に立場の弱い人(社会的弱者)です。
「声をあげる活動的な市民」が増えることで、はじめて人権意識にもとづき、「差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力(人権)問題は、決して許さない社会がつくられ、そうした社会では、適用にあいまいな基準を残さない法律が制定されます。
*-20 国連で、1989年(平成元年)11月20日に採択された『児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)』は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。
18歳未満の児童(子ども)を、権利を持つ主体と位置づけ、大人と同様にひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利を定めています。
前文と本文54条からなり、「子どもの生存」「発達」「保護」「参加」という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。
1989年(平成元年)の第44回国連総会において採択され、1990年(平成2年)に発効し、日本は、1994年(平成6年)に批准しました。
6.援助者にも暴力に対する感度、認識に大きな違い。判断に影響
自身が受けた暴力被害を直ちに、明確に、DV行為と認識できる人とできない人がいます。
そこで、「暴力被害を認識できる人は、暴力行為に対する感度の高い人」、「暴力被害を認識できない人は、暴力行為に対する感度が低い人」と置き換えてみます。
暴力行為に対する感度が低い人には、幾つかの特徴があります。
ひとつは、その人が、「暴力」のある家庭で暮らし、育ってきたことです。
ここでいう「暴力」は、冒頭で述べたように、a)交際相手によるデートDV行為(デートレイプを含む)、配偶者によるDV行為に加え、b)親や養育者、近親者による虐待行為(ネグレクト、性的虐待、身体的虐待、心理的虐待(面前DVを含む)だけでなく、過干渉・過保護、いき過ぎた教育(教育的虐待)、体罰を含む)、c)親や養育者がアルコールや薬物(白砂糖、ニコチン、カフェインを含む)、ギャンブルなどの依存に加え、d)宗教に対する信仰、新興宗教やカルトの教え(教義)、スピリチュアル、占いなどへ傾倒し、家庭を顧みなかったり、その信仰や教えがDV行為や虐待行為に至っていたりするなど、交際相手や配偶者、子どもに不適切なかかわりを指します。
つまり、「暴力のある家庭」には、両親間の暴力と親子間の暴力の両方、あるいは、どちらか一方という“関係性”が存在します。
暴力のある家庭で暮らし、育ってきた人は、家庭が、暴力のある関係性(上下の関係性、支配と従属の関係性)で成り立っていることについて、ア)「それがあたり前」、「どこの家庭でも同じ」、「特段、問題があるように思わない」と家庭内の暴力行為に無自覚、鈍感(無頓着)な人、イ)ア)の中で、交際相手や配偶者から受けたDV行為に対して、親から受けていた凄惨な虐待被害と比べ、「(暴力があることが前提で)この程度ならたいしたことはない。耐えられる(がまんできる)」と暴力行為の程度、悲惨さをモノサシに耐えられる(がまんできる)かどうかにフォーカスする人と、逆に、ウ)「うちは、他の家とは違った」と家庭内の暴力行為を自覚している人、エ)ウ)の中で、「ドアや扉を閉めるとき大きな音を聞いたり、大声で騒いでいる人がいたりするとドキドキと動悸がはじまる」といった不安感や恐怖心が身体症状(PTSDの身体化(身体表現性障害))となって表れる人など、家庭内の暴力行為に敏感な人に分かれます。
エ)は、敏感の範疇を超え、暴力行為を連想させる音、匂い、光、人の立つ位置などがトラウマを想起させ、恐怖でしかない人です。
この家庭内における暴力行為に感度が低い人と敏感な人の違いは、被害を第3者に相談したり、訴えたりしたときにも、その後の対応に大きな差となって表れます。
つまり、相談・支援を受ける者の暴力行為に対する感度のことです。
では、その暴力認識の感度の差が顕著に表れたー例を見ていきます。
それは、ネグレクトの傾向が見られた小学校2年生の女児の保護・支援の“場”において、小学校の教師に見られた反応の違いです。
女児が小学校1・2年生のときの担任は、両親間の苛烈なDV行為を見て、聞いて、察して育った、つまり、被虐待体験をしてきた女性でした。
この女児の担任は、38歳のときに、アダルト・チルドレンのカウンセリングにつながり、自身が抱える生き難さや心身の不調の原因が、面前DV、被虐待体験であること、高校のときの部活動の顧問から受けた性暴力(グルーミングにより交際関係に、その下での性的行為)であることを自覚しました。
この女児の担任は、「小学校のときの担任がもう少し踏み込んで話を聴いてくれたら、きっと私は、母親が父親から暴力を受けていること、自分も父親から暴力を受けていること、兄から性的虐待を受けていたことを話すことができた」との思いがあったことから、夏休み、土日の休日などに、民間機関が実施している児童虐待やDV対策の研究会(宿泊型の研修を含む)などに参加し、勉強を重ねていました。
前任校では、保育園のときにシングルマザーのネグレクトで、児童相談所が介入し、児童養護施設で生活していた女児が、小学校入学を機に母親のもとに帰り、暮らしはじめた女児の担任を務め、その女児が小学校2年生の冬休み前に、小学校と児童相談所が連携し、再び、その女児を児童養護施設で生活する事案に携わる経験をしていました。
女児の担任は、女児が、入学早々にだした「助けてのサイン」を見逃しませんでした。
この女児の担任は、女児が見せる担任との距離感(ペタッとへばりつく)に気づきました。
からだが一体化してしまうようにペタッと寄り添うようにへばりつく行為は、アタッチメント(愛着形成)の獲得に問題を抱えている人に認められる特徴のひとつです。
適切な成長過程で“母子分離”ができずに育つと、自己と他の境界線があいまいなまま成長してしまいます。
自己と他の境界線があいまいなまま成長した人の距離感は、他人との距離感が“極度に近い”か、“極度に遠い”かに顕著に表れます。
からだが一体化してしまうようにペタッとへばりつくか、どこにいるのかわからないほど離れているかのどちらかです。
この女児の担任は、時に、自分にペッタとへばりつき離れない女児を抱っこしたまま、膝のうえにのせたまま授業をしていました。
その女児の家庭訪問では、女児の母親から「女児の父親は、覚醒剤で逮捕歴があり、刑期を終え出所し、女児が就学する数年前に、再び、女児の母親との2人で生活している」こと、「母親が妊娠していること」のことなどの基礎情報を得ました。
休憩時間や下校前の女児とたわいのない会話で、「女児の父親が女児の母親と自分(女児)に、時々、暴力を加えている」との話がでました。
そこで、この女児の担任の上司にあたる学年主任の女性教諭とこの事実を共有しました。
このとき、女児の担任と学年主任の女性教師との間で、「家庭内における暴力行為」に対する認識の違いが生じました。
この学年主任は、「どこの家庭でも、少なからず、親は子どもを叩いている」という認識(感覚)でした。
そのため、学年主任は、日本の多くの教員がそうであるように、「しばらく様子を見ましょう。」と述べ、問題を先送りしようとました。
この学年主任の父親は高校の教師、母親は中学校の教師で、この学年主任は、母親方の祖母に厳しく育てられていました。
日本社会では、「うちの家庭はしつけに厳しかった(親に厳しくしつけられた)」と表現するとき、その多くは、「しつけ(教育)と称する体罰」を加えられています。
学年主任は、日本社会では珍しくない無自覚な「教育的虐待(いき過ぎた教育)」を受けて育った、つまり、暴力のある家庭で暮らし、育ってきた人(被虐待体験をしてきた人)でした。
日本では、いまでも、しつけ(教育)と称する体罰を容認し、加えている(加えてきた)人が60-70%に上ります。
そのため、“厳しいしつけ”“いき過ぎた教育”と表現される「教育的虐待」の被虐待体験をしてきた人は、親が、公務員(裁判官、検事、教師、警察官、消防士などを含む)、大学などの教員、医師、弁護士・公認会計士・税理士などの士業者、スポーツ選手、バレエダンサー、音楽家など、高学歴であったり、専門性が求められたりする職種に就いている人にも、同様に、ほぼ同数存在します。
学年主任は、多くの「教育的虐待」の被虐待体験をしてきた人と同様に、この事実に対して無自覚でした。
このとき、女児の担任が、学年主任の考えに従っていたら、この事案に対する対応は遅れ、より深刻な事態に至っていたと考えられます。
しかし、女児の担任は、ルールに反するかも知れませんが、教頭を通じ、校長と直に、粘り強く女児に対する早期介入の重要性を説きました。
その結果、小学校として、女児と家庭を注視することになりました。
その後、夏休み中に、女児の父親が、行方を告げずに家をでて行き、帰宅しなくなったという事件が起きました。
すると、第2子を妊娠中の女児の母親は、精神的に不安定になり、時々、椅子を投げるなど暴れるようになりました。
母親が暴れている間、女児は、布団を被って騒ぎが収まるのを待ち続けました。
そして校長は、担任とともに、女児の母親を見守る一方で、小学校(校長と教頭、担任、養護教諭)、スクールカウンセラー、保健センター(保健師)、児童相談所、管轄の警察署との協議会を開くことになりました。
校長もまた、無自覚の教育的虐待(いき過ぎた教育)を受けて育った被虐待体験のある人で、「どこの家庭にも多少の暴力はある」との考え方でしたが、数年前に、勤務する小学校で、虐待が疑われる児童に対する対応で、いまでも「あのとき、他の対応があったのではないか」との思い(後悔)がありました。
この経験があったので、校長は、女児の担任から女児に対する早期介入の必要性を求められたときに、担任の確かな知識に裏づけられた説明を受け、当時、自分が至らなかった視点を認識し、「今回は対応を誤らない」、「最善を尽くしたい」との強い思い(決意)がありました。
校長は、女児の担任のDV・児童虐待問題に対する知識の深さを頼り、その話に耳を傾け、速やかに動きました。
そして、少しずつ陽が暮れるのが早くなってきたとき、20時過ぎ、帰宅途中の保健師が「女児が、真っ暗な道をひとりで歩いている」のを目撃し、女児を保護する事件が起きました。
女児は、女児の母親が運転する自家用車で買い物に行き、母親が、女児をスーパーにおいて帰ってしまった、つまり、女児は、母親にスーパーに置き去りにされ、自宅に歩いて帰っていたのでした。
連絡を受けた女児の担任と校長が、保健師が保護していたコンビニエンスストアに駆けつけました。
「置き去り」は、児童虐待事案なので、児童相談所は、これまでの経緯を踏まえて、直ぐに児童相談所が動きました。
児童相談所の職員が到着するのを待ち、職員と校長が女児の自宅を訪問し、母親の同意のもとで、児童相談所が女児を一時保護することになりました。
女児は、女児の祖母(女児の母親の母。女児の母親の妹と同居)の家で暮らすことになり、そこから通学できる小学校に転校することになりました。
この女児は、定期的に児童相談所でのカウンセリングを受け、母親と定期的に面会交流をしながら、祖母の家から通える小学校を卒業、寮のある公立の中高一貫校に進学し、いま高校生です(令和4年(2022年)4月現在)。
子どもと接することの多い学校園の教職員、学童の職員、塾や習いごとの教師や指導者、近隣住民、医師や看護師などの大人が、子どもが発している“助けて”のサインを察知し(受けとり)、どのように対応する(動く)かによって、子どもの将来は大きく違ってきます。
差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力被害を受けた人から相談を受けた(被害をうち明けられた)とき、相談された(被害をうち明けられた)者が、暴力行為に敏感か、敏感でないか、暴力に対する認識如何で、被害をどう受けとり、どのようなことばをかけ、どのように動くかは大きく異なります。
それは、被害を相談した(うち明けた)人の“いま”と“これから”は大きく異なり、結果、その後の人生を左右します。
この女児のケースで、女児とかかわった小学校の教職員(担任、校長、教頭、養護教諭)、スクールカウンセラー、保健センターの保健師、児童相談所の職員(ケースワーカー)、警察官のほとんどが、「子どもにとっての幸せは、たとえ、暴力のある家庭環境(機能不全家庭)であっても、両親の下で育つことである」という“保守的”な価値観にもとづき判断を下す人たちで構成されていたときには、速やかに女児を保護し、養護施設で暮らさせるか、祖母のもとで暮らさせるかの2択での判断に至ることはなかった可能性があります。
つまり、日本では、「いかなる理由があっても、暴力行為は許されない」という厳格なモノサシ(判断基準)で統一されていないことから、こうした重要な判断を下すときに、判断を下す側にいる人たちが重視する価値観(家庭観)、考え方、つまり、個々人のありようで、その解釈、判断は異なります。
日本では、対応にあたる機関の組織のトップが変わると、あたり前のように、その解釈、判断が変わってしまいます。
人がかかわることなので、一定でないのは仕方がないことですが、日本は、その差が激しいといえます。
本来、相談する(被害をうち明ける)ことは、“賭け”であってはならないのです。
しかし、現実は違います。
(支援活動16年*。脳科学の発展と関連法の改正、とり巻く状況の変化)
* 平成18年(2006年)6月-令和4年(2022年)5月の16年。ただし、DV/性暴力の立証のためのレポート作成については、平成28年(2016年)4月1日-令和2年(2020年)3月31日の4年間の活動休止期間を含む。
最初に、私が、DV/性暴力支援に携わるようになった平成18年(2006年)以前のDV問題、児童虐待問題の歴史を見ていきたいと思います。
では、第2次世界大戦後、日本を統治下に置き、その後、同盟国となったアメリカ合衆国の歴史とともに、日本が『配偶者暴力防止法』を制定するまでの経緯を見ていきます。
アメリカ社会は、白人の入植者が、先住民であるインディアンを迫害した過去があります。
イギリスでの宗教弾圧を逃れてマサチューセッツ州のプリマスに住み着いた入植者(ピルグリム・ファーザーズ)は、作物を栽培できず、飢えそうになっていました。
このとき、その地の先住民であったワンパノアグ族(Wampanoag)は、食物を分け与え、栽培の知識を与えました。
生き延びることができた入植者は、収穫が多かった翌年、ワンパノアグを招いて宴会をおこないました。
これが、アメリカ合衆国における“感謝祭”のはじまりといわれています。
しかしその後、白人の入植者らは、自分たちを救ってくれたワンパノアグ族の土地を奪い、女性や子どもを奴隷として売り飛ばしました。
しかも、抗議した酋長を毒殺し、後続の酋長が抵抗の戦いを挑んだときにはワンパノアグ族を虐殺し、壊滅させました。
勝利した白人入植者は、酋長の頭を槍のうえに刺し、見せしめとして飾りました。
このときに惨殺されたインディアンは、他の部族も含めて約4,000人といわれています。
その後も白人たちは、アメリカ全土でインディアンから土地を奪い、虐殺し、奴隷にし、作物が採れない場所に追いやりました。
このことが、その後のアメリカ社会におけるインディアン・黒人の人々が、貧困、アルコール依存、DVといった問題につながるルーツといわれています。
つまり、アメリカ社会の抱える貧困、アルコール依存、DVの根本的な原因(バックグランド、背景)は、過去の血みどろの歴史です。
こうした迫害、虐殺された人々(民族・人種)の子孫が、その後、貧困、アルコール依存、DVといった社会問題を抱える事実は、アメリカ合衆国だけでなく、「アイヌ民族を迫害(民族)」した日本をはじめ多くの国々、地域に存在しています。
しかも、現在も紛争・テロ行為を繰り返すなど、血みどろの歴史を積み重ねています。
建国後、先住民族を虐殺するなど血みどろの歴史を抱えるアメリカ合衆国における女性や子どもへの暴力や黒人など人種差別の根絶を目指すとり組みのきっかけは、「ベトナム戦争(1960年代初頭から1975年4月30日)」です。
ベトナム戦争が長引き、泥沼化する中で、アメリカ国内では、反戦運動や女性の開放運動が盛んになりました。
女性の開放運動の中で、女性解放運動家たちが、DV(ドメスティック・バイオレンス)ということばをはじめて使いました。
当時のアメリカでは、親しい男女間の暴力は、個人の問題であり、社会問題、人権問題といった意識はありませんでした。
なぜなら、社会的な背景として、「男だから女性への暴力は、許される」、「女性は、男性の暴力に耐えなければならない」、「親の子どもへの暴力は、許される」といった暴力行為を正当化しようとする考え方が世代間で受け継がれてきたからです。
ここには、アメリカ合衆国の保守基盤である「キリスト教的家族主義」の信仰が大きく関連しています。
こうした中、女性解放運動家たちは、「緊急一時避難所(シェルター)を被害者に提供した」ことに端を発して、アメリカでのDV活動がはじまりました。
1990年代になり、「DVとは、女性の基本的人権を脅かす重大な犯罪である」と認識されるようになりました。
ここに至るまで、実に、20数年の歳月を要しています。
1986年、合衆国最高裁判所は、ヴィンソン対メリター・セービングス・バンクの裁判で、「セクシュアルハラスメント行為が人権法に違反する性差別である」と初めて認めました。
1989年には、北米の炭鉱でセクシュアルハラスメント行為に対する労働者による集団訴訟で勝訴し、「性的迫害から女性を守る規定」を勝ちとり、その後、全米の企業に、「セクシュアルハラスメント防止策の制定」「産休の保障」などが適用されることになりました。
そして、1993年、国連総会で「女性への暴力撤廃宣言」が採択されました。
女性に対する暴力には、夫やパートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアルハラスメント、ストーキングの他、女児への性的虐待も含まれます。
「女性への暴力撤廃宣言」が国連で採択された6年後の1999年(平成11年)12月、国連総会は、「11月25日」を「女性に対する暴力撤廃国際日」と定めました。
これを受けて、日本の内閣府の男女共同参画推進本部は、「女性に対する暴力は、女性への人権を侵害するものであり決して許されるべき行為ではない」とし、平成13年(2001年)、アメリカの『女性に対する暴力防止法』にあたる『配偶者からの暴力の防止ならびに被害者の保護に関する法律』が施行されました。
この法律の目的は、直接、配偶者からの暴力を禁止する規定はなく、被害者の保護と暴力の防止です。
ただし、配偶者間であっても、暴力行為は、被害者の告訴により「暴行罪(刑法208条)」、「傷害罪(刑法204条)」、「脅迫罪(刑法222条)」、「強要罪(刑法223条)」、「強姦罪(刑法177条/現強制性交等罪)」などの罪を問う(法を適用する)ことができるとしています。
この「配偶者暴力防止法」が制定された平成13年(2001年)以降、毎年11月12日-25日は、「女性に対する暴力をなくす運動期間」と定め、他団体との連携、協力の下、意識啓発活動にとり組むことになり、現在に至ります。
3年後の平成16年(2004年)の法改正で、制定前から問題視されていた対象者が「被害者だけ」に限定されていた問題は、ア)「被害者の子どもの保護」が加わり、イ)配偶者には事実婚、DV行為の後に離婚(事実婚解消)したケースも含まれ、ウ)対象となる暴力は、「身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすもの」に加え、「これに準する心身に有害な影響を及ぼす言動」が加わり、「精神的暴力」「性的暴力」も対象となりました。
ただし、警察の介入については、身体に対する暴力のみが対象です。
平成19年(2007年)の法改正で、保護命令の発令の対象が、「身体に対する暴力」だけでなく、「脅迫により、生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときにも発する」ことができるようになりました。
それから7年後の平成26年(2014年)、改正新法として、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)」となり、「婚姻関係になくとも同じ居住地で生活を営んでいる者(元を含む)」に対して、同法が適用されることになりました。
また、「家庭での親密な関係における暴力を犯罪と認める」という考え方の背景には、国際連合の『子どもの権利委員会』において、「体罰を撤廃することは、社会のあらゆる形態の暴力を減少させ、かつ防止するための鍵となる戦略である。」と明確に示された人権解釈が存在しています。
この人権解釈は、つまり、『児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)』は、1989年(平成元年)11月20日、第44回国連総会において採択され、1990年(平成2年)に発効しました。
日本政府は、発効から4年後の1994年(平成6年)に批准しました。
では続いて、日本で、『児童虐待防止法』が制定されるまでの流れを見ていきたいと思います。
日本では、昭和22年(1947年)、「児童福祉法」の制定に伴い、昭和8年(1933年)に制定された「(旧)児童虐待防止法」が統合・廃止されました。
日本社会では、1990年代(平成2年-)に入るまで、マスコミをはじめとする国民の多くが、児童虐待にほとんど関心を持っていませんでした。
しかし1990年代以降、都市化・核家族化が進む中で、児童虐待は増加し、深刻化していると報告されるようになり、平成12年(2000年)、家庭での親密な関係における暴力を“犯罪”と認め、深刻化する児童虐待の予防および対応方策とするために、『児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)』が制定されました。
小児精神科医の池田由子が、アメリカでの虐待研究をもとに、1979年(昭和54年)に『児童虐待の病理と臨床』、1987年(昭和62年)に「児童虐待―ゆがんだ親子関係」を出版したことを受け、児童虐待が社会問題として認知されるようになりました。
池田氏は、児童虐待を2つに区分しました。
ひとつは、“貧困”や“人権無視”といった「社会病理」としての児童虐待で、もうひとつは、平和で、飢餓による食料不足もなく、人間の権利が尊重される先進国で、親個人の「精神病理」、あるいは、「家族病理」としての虐待です。
高度成長を成し遂げた当時の日本は、「社会病理」としての虐待は減少している一方で、親の「精神病理」、あるいは、「家族病理」としての児童虐待は増加しつつあると述べています。
つまり、後者の児童虐待は、戦前から戦後直後の1950年代(昭和25年-同34年)まで問題とされてきた「社会病理」としての児童虐待とは異なる様相を示すものでした。
その特徴は、第1に、児童虐待の加害者が、ほぼ親に限定されていることです。
昭和8年(1933年)の『児童虐待防止法』では、「保護者が虐待をしたときは、処分をする」と規定している一方で、児童虐待を保護者による行為とは定義していませんでした。
ところが、平成12年(2000年)に制定された『児童虐待防止法』の第2条で、「児童虐待とは保護者がおこなう行為である」と規定しています。
この「保護者」には、未成年後見人、その他現に子を監護するものが含まれますが、そのほとんどが継父母、養父母を含む親です。
このことは、貧しい時代の親は子どもを虐待しなかったが、いまの親は虐待するようになったという意味ではありません。
第2次世界大戦後、高度成長を経た日本社会では、家の家計を支えたり、助けるために、女中、子守、芸妓、丁稚、工員として働きにだされる子どもがいなくなったことで、子どもを虐待したり、酷使したりする親以外の保護者がほとんどいなくなり、残ったのが親による虐待であるということです。
時代背景の結果として、虐待は、親がおこなうものとなったということです。
このことは、家庭の中で、親が子どもを一人前になるまで育てることがあたり前の社会となったことを意味します。
子どもの養育と教育を家族の重要な役割・機能と見なす「子ども中心主義」の「教育家族」は、近代社会において形成されたものです。
近代家族のあるべき規範が、日本社会に広く定着していく中で、児童虐待が社会問題化していったことになります。
親が責任を持って子どもを育てることがあたり前の社会になったからこそ、そこから逸脱した親の言動やふるまいが「虐待」と捉えられるようになり、家族の「病理」と認識されるようになりました。
そのため、かつての虐待と今日の虐待では、意味や概念が異なります。
かつての虐待は、「人身売買や児童労働、酷使、暴力など、様々な大人による子どもに対する残虐な行為(cruelty)」を意味していましたが、現在の虐待は、「親の権限の濫用(abuse)」であり、「親による不適切な子どもの扱い(maltreatment)」を意味します。
平成25年(2013年)、『子ども虐待の手引き(厚生労働省)』には、諸外国で一般的に使われているマルトリートメント(不適切な養育)という概念が、日本の児童虐待に相当すると記載しています。
今日の虐待の基準は、親の言動が残酷かどうかではなく、適切かどうかであり、虐待の範囲は、親としてふさわしくない言動や不適切な子どもの養育方法へと大幅に拡大しています。
第2に、虐待の原因や責任がもっぱら親や家族に求められ、社会的な背景や要因がほとんど問題にされないことです。
池田氏の調査において、虐待を受けた子どもの「家族の問題」としてもっとも多いのが「経済的問題」であり、次に、「家族関係の不和」「父親の転職の多さ」と続いていたことから、池田氏は、「概括的にみれば、日本でも外国でもやはり経済的に困窮している階層の割合が高い。」と指摘していました。
にもかかわらず、池田氏は、親の学歴や社会階層を問わず、「どんな家庭でも虐待は起こる」として、貧困や階層などの社会的問題を切り捨て、虐待を親個人の病理や家族病理と見なしました。
そのため、社会的な背景や要因がほとんど問題にされなくなってしまいました。
しかし、児童虐待の背景に経済的な問題があることは、多くの調査で明らかにされています。
平成17年(2005年)、東京都福祉保険局の「児童虐待の実態Ⅱ」では、虐待をする家庭では「経済的困難」「ひとり親」「孤立」「就労の不安定」「育児疲れ」などが、離れがたく結びついていることを明らかにしています。
アメリカで虐待調査を実施してきたリーロイ・H・ペルトンは、「児童虐待やネグレクトが貧困や低収入に結びついているという事実を超える事実はひとつもない。」と述べ、「親の監護力が十分か否かは、環境が十分か否かによる。」と断言しています。
『子ども虐待の手引き(厚生労働省)』は、「養育環境のリスク要因としては、家庭の経済的困窮と社会的孤立が大きく影響している。」と指摘しています。
にもかかわらず、日本の経済的支援の拡充は、虐待対策には位置づけられていません。
「経済的支援」は、児童扶養手当など、既存の制度の「周知」だけに留まっています。
その理由は、現代の児童虐待問題では、経済的困窮は虐待をひき起こす社会的要因や背景ではなくて、個々の家庭が抱える様々な「リスク要因」のひとつとして捉えているからと考えられます。
つまり、虐待家庭の背景に存在する貧困は、それぞれの家庭の問題に過ぎないとされ、社会が解決すべき問題としては位置づけられていません。
第3は、概念の拡大とその広さです。
昭和8年(1933年)制定の『児童虐待防止法』、昭和22年(1947年)制定の『児童福祉法』のどちらも、「なにが虐待であるか」を規定していませんでした。
その中で、親による家庭内の虐待として想定していたのは、「身体的虐待」と「監護の怠慢・懈怠(けたい;ネグレクト)」で、しかも、子どもにひどいケガを負わせるなどして生命に危険が及んだり、刑罰法令に触れたりするような重大な行為に限っていました。
それに対し、いまから22年前の平成12年(2000年)制定の『児童虐待防止法』は、「身体的虐待」と「ネグレクト」に加え、「性的虐待」と「心理的虐待」の4つを虐待として規定し、その範囲を大幅に拡大しました(令和4年(2022年)10月現在)*-21。
いまから18年前の平成16年(2004年)に改正された『児童虐待防止法』では、子どもが、両親間のDVを目撃する、つまり、面前DVは、「心理的虐待にあたる」と位置づけました(令和4年(2022年)10月現在)。
「DVは、直接被害を受けた女性のみならず、それを目撃している子どもたち(面前DV被害下にある子どもたち)は、恒常的なストレス状態の中で暮らしていることになり、その恒常的なストレス状態は、子どもの心(精神)までも破壊する可能性のある犯罪である」と認められました。
しかし、日本社会では、いまだに、子どもが暴力のある家庭環境で暮らし、育つこと、つまり、「子どもが、両親間のDV行為を見たり、聞いたり、察したりすること(面前DV)が、子どもには心理的虐待にあたる」という認識には至っていないのが現状です。
国際連合の「女性及び女児に対するあらゆる形態の暴力の撤廃と防止」に対する積極的なとり組みは、パープルリボン(女性に対する暴力の撤廃)、ホワイトリボン(DV防止の願い)、オレンジリボン(未来を切り開く子どもへの希望を込めて)などのキャンペーン運動へとつながり、女性や子どもへの暴力の根絶を願う思いが、徐々に社会に広がるうえで大きな役割を担っています。
「パープルリボン」とは、国際的な女性への暴力根絶を訴えるキャンペーンです。
1994年(平成6年)、米国のベルリンという小さな町のサバイバー(被虐待者・DV被害者)による集まりからはじまった「インターナショナル・パープルリボン・プロジェクト(IPRP)」が代表的で、現在40ヶ国以上に知られ、国際的なネットワークに発展しています。
第2次世界大戦後55年—56年と長い時間を要して、家庭や親密な関係での暴力に関する法律(『児童虐待防止法』『ストーカー規制法』『配偶者暴力防止法』)が制定されたことにより、これまで法律が入り難かったプライバシーの問題、「女性や子どもに対する暴力」に対し、人々の関心が向けられるようになり、公の場で、漸くこの問題が語られるようになりました。
*-21 児童虐待の定義については、「Ⅱ-15.慢性反復的トラウマの種類(児童虐待分類)と発達の障害」、「Ⅳ-29-(1)児童虐待の定義」で詳しく説明しています。
では、私がDV/性暴力被害者支援に携わることになった平成18年(2006年)の少し前からいまに至るまでの18年間で起きた“6つ”の大きな変化、つまり、「法律の制定/改正」や「画期的な判決」を見ていきたいと思います。
第1は、先に少し触れましたが、私が支援活動をはじめる2年前、いまから18年前の平成16年(2004年)、改正『児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)』に「子どもが、両親間(マムズボーイフレンドとの間を含む)のDV行為を目撃すること(面前DV)が、心理的虐待になる」と明記されたことです(令和4年(2022年)4月現在)。
「面前DV」とは、子どもが、両親間のDVを目撃する(両親間の暴力行為を見たり、聞いたり、察したりする)ことです。
この『児童虐待防止法』の改正により、面前DVは「心理的虐待」とされました。
この法改正により、DVは、単に交際相手や配偶者間の問題ではなく、児童虐待と密接な関係にあることを明確にしました。
しかし、実際の実務の現場では、「DVと児童虐待は密接な関係にある」との前提に立つことは少なく、そのため、各機関の連携はスムーズではありません。
この法改正以降、子どもが、両親間のDVを目撃している(面前DV)として、警察が児童相談所に通告するケースが多くなりました。
2019年(平成31年/令和元年)、警察が、虐待の疑いがあるとして児童相談所に通告した9万7842品のうち、7万441人が心理的虐待で、そのうちの6割(約4万2千人)が面前DVです。
このことは、DV被害を受けている一方の配偶者であっても、最初に、児童相談所が介入すると、子どもに対する心理的虐待(面前DV)を加えた当事者(親)として扱われる可能性があることを意味します。
なぜなら、児童相談所の『児童虐待防止法』にもとづく介入は、虐待被害を受けた子どもに対するサポートが“主”だからです。
DV被害者の女性(交際相手や配偶者(いずれも元を含む))が、女性センターなどの相談機関や警察、弁護士に対し、「加害行為に及んでいる交際相手や配偶者から逃げたい」と助けを求めたときには、直ちに、『配偶者暴力防止法』にもとづく“一時保護”を決定し、DV被害を受けている女性と子どもを「母子生活支援施設(母子棟、いわゆるシェルター)」に入所させる手続きができます。
ところが、a)近隣住民などが、「あそこの家でDVがあって、子どもが泣いている」と警察に通報し、警察がその児童を保護したあと、児童相談所に通告したり、b)DV被害を受けている妻が、夫の暴力によりケガ(傷害)を負った子どもを病院に連れていったとき、医師や看護師が「傷害を負った子どもは、虐待が疑われる」として児童相談所に通告したりしたときには、児童相談所が“児童虐待案件”として介入し、時に、DV被害者であっても、児童虐待の加害者(当事者)として扱われることがあります。
後者の結果は、ときに、家庭裁判所に「婚姻破綻の原因は、配偶者のDV行為である」と夫婦関係調整(離婚)調停を申立てた離婚事案において、子どもの親権者、監護権者の決定に大きな影響を及ぼします。
この問題は、「Ⅰ-A-4-(2)-②無自覚な間違った考え方の癖(認知の歪み)」の「事例179(分析研究15)*3」で詳しく説明しています。
この事例は、家庭裁判所に、「監護権者指定調停(審判)」を申立てた「DV加害者である夫(子どもの父親)が、子どもの監護権者」となる判決を受けたものです。
夫から苛烈な暴行を受け、加療を要する傷害を負った妻が、警察の指導にもとづいて、子どもを連れて妻の実家に帰りましたが、夫から繰り返し「二度と暴力はふるわない。やり直したい」と懇願され、夫の『DV加害者更生プログラム』を受講するという約束を信じ、実家に帰ってから4ヶ月後、両親や妹の反対を押し切る形で夫の待つ家に戻りました。
夫のもとに戻り、夫の母(義母)が用意していたアパートに子どもと住み、夫婦の再建をはかりました。
直ぐに、夫は「妻と子どもが暮らすアパートにはこない」との約束を破り、仕事が終わるとアパートに立ち寄り、夕食を食べてから帰宅するようになり、しばらくするとそのまま泊まっていくようになり、1ヶ月後には、夫と生活していた家に戻ることになりました。
夫と同居することになった妻は、再び、夫から苛烈な暴行を受けるようになり、精神的に不安定になりました。
妻は育児に不安を覚え、自ら「児童相談所」に子どもの保護を求め、児童相談所は、その訴えを聞き入れ子どもを保護しました。
夫の離婚を決意した妻は、翌日、朝一番の飛行機で駆けつけた妻の母とともに、一時的に保護してもらった(と認識)子どもを「児童相談所」に迎えにいきました。
しかし、児童相談所は、「夫と一緒でなければ、子どもを帰宅させられない。」と応じました。
妻は、夫と接触するのが怖く、やむなく、母とともに実家に帰りました。
一方の夫は、直ぐに、家庭裁判所に対して、「監護権者指定の調停(審判)」を申立て、結果として、「2歳の子どもの監護権者を父親とする」との判決が下されました。
この事例は、仮に、『配偶者暴力防止法』にもとづく“一時保護”を求め、母親が子どもとともに「母子生活支援施設」に入所し、「婚姻破綻の理由は、配偶者である夫からのDVである」として、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停を申立てていれば、2歳の男児の監護権(親権)は妻となり、子どもとともに、新たな生活を送ることができた可能性がありました。
このように、いまの日本では、DV被害のある家庭に子どもがいるときには、最初に、そのDV被害を「どこに相談するのか」、その事案に対して「誰が」「どのようにかかわるのか」によって状況は一変し、時に、上記の事例のような悲劇がおきます。
この事例のように、どの機関が介入するかによって異なる結果になり得るとしても、『児童虐待防止法』に「子どもが、両親間(マムズボーイフレンドとの間を含む)のDV行為を目撃すること(面前DV)が、心理的虐待になる」と明記されたことには、大きな意義があります。
なぜなら、『児童虐待防止法』に、「面前DVが心理的虐待になる」と明記されたのは、子どもが、両親間(マムズボーイフレンドとの間を含む)のDV行為を目撃する(見たり、聞いたり、察したりする)ことは、「子どもの脳の発達に大きなダメージを与え、将来にわたり心身の健康を損なうことになり、同時に、自己規定・自己規範となる価値観に認知の歪みを生じさせるリスクが高くなる」という考え(判断)にもとづいているからです。
(MRI画像診断で、脳の傷が見えるように)
では、面前DV=心理的虐待が、「子どもの脳の発達に、どのような大きなダメージを与える」のでしょうか?
この16年で急速に発展した脳科学の分野の成果を見ていきます。
これまで、「心が傷つく」といっても、「心(脳)の傷は見えない」といわれてきました。
このことは、「見えないのだから、わからない」とダメージの深刻さを理解しようとされなかったり、「見えない=わからないのだから、暴力行為の事実も疑わしい」と疑念を持たれたり、嘘つき呼ばわりされたりする要因になるなど、2次加害の温床となってきました。
しかし、いまでは、「MRI(磁気共鳴断層撮影)検査」や「光ポグラフィー検査」などの画像診断により“脳の傷(萎縮や肥大化)”が視覚化(見える化)できるようになりました。
この分野は、日々、急速な発展を遂げています。
ここでは、日本の研究者におけるMRI検査を利用した先駆的な研究に触れておきます。
いまから15年前の平成19年(2007年)3月16日、東北大学の松沢大樹名誉教授(総合南東北病院・高次脳機能研究所 所長)は、MRI検査による画像診断により、「深刻ないじめによっても、子どもたちの扁桃核に傷が生じている」と発表しました(令和4年(2022年)4月現在)。
それは、「過去3年間で、総合南東北病院・高次脳機能研究所に、深刻ないじめを原因に心の不調を訴えて来院してきた300人以上の子どもたちすべてに、扁桃核の傷が認められた」というもので、松沢名誉教授は、「扁桃核に傷がつくことで、精神疾患が起きる」と説明しています。
「扁桃核(扁桃体)」は、人を含む高等脊椎動物の側頭葉内側の奥に存在するアーモンド(扁桃)形の神経細胞の集まりで、大脳辺縁系の一部とされ、情動反応の処理と記憶において主要な役割を果たします。
「うつ病」や「統合失調症」と診断されたケースで、それぞれ特有の傷が見つかり、その後、画像診断を重ねた結果、どの患者にも「返答核(扁桃体)」に傷(萎縮)があることが明らかになりました。
「統合失調症」よりも「うつ病」の病状が優勢なときには、「扁桃核」の傷のほか、「海馬」の萎縮も表れます。
いじめ被害などで、脳内の神経伝達物質の「ドーパミン」と「セロトニン」のバランスが崩れることで傷(萎縮)が生じる、つまり、精神の安定や睡眠に関わるセロトニンが減少し、快感や運動調節に関するドーパミンが過剰になって毒性が表れるのが、傷(萎縮)が生じる原因としています。
その後、松沢名誉教授は、平成23年(2011年)3月11日に発生した東日本大震災後、東北大学の一部の大学生にMRI検査を実施しています。
その結果は、検査を受けた大学生ほとんどに脳の萎縮が認められました。
これにより、いじめ被害など「慢性反復的トラウマ」だけでなく、「単回性トラウマ」に位置づけられる震災被害のストレスが、脳に傷(萎縮)を残すことが明らかになりました。
次に、「慢性反復性トラウマ」に位置づけられる親による子どもへの虐待行為が、脳に傷を残すことを詳細に検証したデータです。
その脳の目に見える傷は、福井大学の友田明美教授(研究発表時は熊本大学准教授)が、アメリカ合衆国のハーバード大学との共同で、2003年-2012年(平成15年-同24年)に、18-25歳の約1500人に対して知能検査とMRI検査を実施した研究で明らかにしたものです。
その結果は、a)幼少期に激しい体罰(身体的虐待)を長期にわたり受けると、感情や理性を司り、思考をコントロールする「前頭前野」が約19%萎縮し、集中力や意思決定、共感などと関係の深い前頭葉の「前帯状回」が萎縮し、さらに、脳の一番外側に広がる大脳皮質の「感覚野」へ痛みを伝えるための神経回路が細くなる、b)幼少期に暴言(否定、非難、侮蔑、卑下するなどのことばの暴力)による虐待(心理的虐待)を受けると、強い自己否定の気持ちを植えつけ、会話や言語を司る「聴覚野」の一部が約14%拡大する、c)幼少期に性的虐待を受けると、視覚を司る大脳後方の「視覚野」が約18%萎縮する、d)幼少期に頻繁に両親間のDVを目撃する(面前DV=心理的虐待)と、視覚野の一部が約6%萎縮し、e)幼少期にネグレクトを受けると、喜びや快楽を生みだす「線条体」の働きを弱め、左右の脳をつなぐ「脳梁」を萎縮させるというものでした。
面前DV(心理的虐待)による「視覚野」の萎縮については、身体的暴力の目撃では3.2%の萎縮だったのに対し、ことばの暴力に接してきたときには19.8%の萎縮が認められ、前者に比べて6.19倍もダメージが大きい結果となっています。
身体的虐待により「前頭前野」が萎縮すると、感情や理性、思考をコントロールし難くなり、「前帯状回」が萎縮すると、集中力が欠け、自分で決めたり、共感したりでき難くなり、「感覚野」への神経回路が細くなると、痛みに対して鈍感になり、心理的虐待により「聴覚野」が拡大すると、聞こえ方、会話やコミュニケーションがうまくできなくなり、性的虐待や面前DV(心理的虐待)により「視覚野」が萎縮すると、他人の表情を読めず、対人関係がうまくいかなくなり、ネグレクトにより「線条体」の働きが弱まると、心地よい、楽しい、嬉しい、喜びなどの感覚が損なわれ、「反応性愛着障害」をひき起し、「脳梁」が萎縮すると、「境界性人格障害(ボーダーライン)」をひき起します。
こうした「子どもの脳の変形」は、「外部からのストレスに耐えられるように情報量を減らす」ための“脳の防衛反応”と考えられています。
ストレスの影響を最も受けやすいのは、脳中央にある「海馬」と「扁桃体」、脳前方の「前頭葉」です。
大人であっても、職場でハラスメントを受けたり、東日本大震災などの自然災害に襲われたりするなど大きなストレスを受けると、適応障害やうつ病、PTSDを発症したり、身体的不調に陥ったりするのは、そのストレスが、「海馬」や「扁桃体」を刺激して脳にダメージを及ぼすからです。
「扁桃体」は、情動と深く関係している感情の中枢で、好き嫌いや快・不快を判断したり、敵か味方かの判断をしたりする場所で、「危険(脅威)」と結びつく情報には強く反応します。
「海馬」は、大脳から送られてくる情報を処理して、それらをもとに記憶をつくって保管する働きをしますが、「扁桃体」と近いところにあることから、感動や興奮、恐怖などの強い情動を伴うできごとを記憶しやすいという特徴があります。
この「扁桃体」と「海馬」の働きをコントロールし、「扁桃体」が危険や恐怖に過剰反応しないよう適度にブレーキをかけているのが「前頭葉」です。
また、「扁桃体」の働きは、うつ病とかかわりがあります。
うつ病になると、怒りや不安を司る「扁桃体」が過剰に働くようになります。
「扁桃体」が過剰に働くと、通常は扁桃体の活動をコントロールしている「大脳皮質」の働きが弱くなり、不安や気分の憂鬱が強くなります。
そうなると、仕事だけではなく、日常生活も難しくなります。
つまり、うつ病は、「扁桃体」が暴走した状態といえます。
この感情の中枢である「扁桃体」は、刺激を受けるとストレスホルモンを分泌するよう副腎皮質に指令をだします。
過度の暴力を受けると、「扁桃体」は常に興奮をし、大量のストレスホルモン「コルチゾール」を脳内に放出させます。
このことが、脳に重大な傷を負わせます。
こうした状況を回避するために、脳は「外部から入ってくる情報量を減らす」ことを選択する、つまり、脳は「変形する」のです。
見たくないものを見続けないように「視覚野」が萎縮したり、痛みを感知したり、起こっていることを認識したりしないように「前頭前野」が萎縮したりすることは、脳が自らを守ろうとする“自己防衛反応”です。
暴言を受けることで変形する「聴覚野*-22」は、萎縮をするのではなく、シナプスの「刈り込み」が止まってしまうことから“肥大”します。
シナプスの「刈り込み(剪定)*-23」とは、いらないところを刈り込んで整えていく過程です。
その剪定がストップし、シナプスが伸び放題になり、雑木林のような状態になっているのが、変形した「聴覚野」です。
これも、聞きたくないことを聞かなくていいように、音が拾えない状態に自らを変えてしまったものです。
いずれの部位の変形は、脳が暴力による苦しみに必死に適応しようとした結果といえます。
これらのことが教えてくれるのは、「人の脳は、生まれ育った環境(胎児期を含む)でつくられる*-24」、つまり、「人は、育つ家庭環境やコミュニティで生存するために必要な(求められる)脳の機能を発達させ、必要ない(求められない)脳の機能は発達させない」、そして、「胎児期・乳幼児期に暴力を加えられる(面前DVを含む)など、不適切な刺激により脳の部位は、各々異常をきたす」ということです。
人間の脳は、生存している環境にあった脳の機能がつくられます。
人類は、脳や身体を進化させてきた一方で、必要のなくなった機能、つまり、必要のない生存環境では、進化させてきた脳や身体の機能を捨て去るだけでなく、生存のために異常を示すことになります。
「生存のために異常を示す」とは、正常な脳機能を守るために、別の正常な脳機能を破壊し異常をおこすということ、あるいは、異常な脳機能を補う(正そうとする)ために、新たな異常を生みだすということです。
つまり、「脳が脆弱な乳幼児期に、ある特定の入力(インプット)が欠けたり、過剰に入ってきたりすると、そのインプットに関連する情報を感じ、気づき、理解し、判断し、それに従って行動するという脳のシステムの発達に異常(問題・障害)が生じる」ということです。
子どもの脳の発達に影響を与える時期は、出生後の環境だけでなく、出生前の妊娠期、つまり、胎児期の母体環境からはじまります。
妊娠中のDV被害は、母体の被害だけでなく、早産や胎児仮死、児の出産時低体重をひきおこし、セロトニン・ドーパミンなどの神経伝達物質の分泌に影響を及ぼすなど初期の脳形成に重大な影響を及ぼします。
発達期の脳に対する強い精神的衝撃は、脳の神経伝達物質の分泌にも影響を与えます。
例えば、ストレスを調節するホルモンである「コルチゾール」、重要な神経伝達物質である「エピネフィリン」、「ドーパミン」、「セロトニン」などに変化が生じます。
これら神経伝達物質のバランスに問題が生じると障害がおきます。
脳システムの発達に異常(問題・傷害)をもたらすのは、人が、暴力(性暴力を含む)行為を眼で見たり、耳で聞いたり、身体的暴力や性的暴力(セックスを含む)をからだで受けたり、アルコール、薬物(白砂糖、ニコチン、カフェインを含む)、激辛などの薬品や食品(白砂糖は薬品に分類される)をからだに摂り入れたりする行為と深く関係します。
つまり、人の脳が、眼で見る(視覚)、耳で聴く(聴覚)、肌に触れる(触覚)、舌で味わう(味覚)といった行動に加え、体内にとり組むことで得られる“刺激”は、快感中枢が反応する「うまみ」となります。
この快感中枢が反応する「うまみ」となり得る“刺激”には、「一度強い刺激を受けると、より強い刺激を求める」ようになる“特性”があります。
このより強い刺激を渇望するようになることを「中毒」、「依存」といいます。
この50年ほどで、乳幼児期から白砂糖を大量に含む炭酸飲料などのジュース、ジャム、生クリーム、精製された小麦や米、それを粉にして加工されるパン、蕎麦、うどん、ラーメン、パスタなどの依存性の高い“糖質”の食品に急速に馴染んだ人の脳は、その食品を見ただけで、脳では大量のドーパミンが分泌され、「欲しくてたまらない欲求」に満たされます。
小麦や米などを摂取し、脳の唯一の栄養分となるブドウ糖で満たされた脳は、コカイン中毒者の脳と類似した状態になることがわかっています。
そして、これらの食品(白砂糖は薬品分類)は、脳の「快感中枢」が反応し、常に、依存に陥りやすい“特性”を持っています。
つまり、浸透性の高い精製され、加工された“糖質”に馴染んだ近代人、特に、ここ40年-30年の間に子ども時代を過ごした人の脳は、とても、“脆弱化”しています。
中脳には、神経細胞の集まり「A10神経核」があります。
なんらかの行動などで、ここが活性化すると、「前頭前野」「運動野」「海馬」、そして、「側座核」の神経細胞にまで伸びる「軸索」の末端から神経伝達物質「ドーパミン」が放出され、それぞれが活性化します。
「側座核」は、人が快感を覚えるときに血流が増します。
これらの領域すべての活性化が、再び、A10神経核を活性化させ、さらにドーパミンを分泌させるという「快感循環」をもたらします。
人のどのような行動であれ、積極的に繰り返しているときには、この循環が起きています。
差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、レイプなどの性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力行為に加え、アルコール、薬物(白砂糖、ニコチン、カフェインを含む)、激辛などの食品を摂取したり、リストカットやOD(大量服薬)、過食嘔吐などの自傷行為に及んだりする行為が、慢性反復的(継続的、日常的)に繰り返されている時には、既に、脳が快感を覚え、「快感循環」が起きています。
つまり、人の脳の快感中枢が反応する行為は、一度、その「うまみ(快感)」を覚えると繰り返す特性があるということです。
例えば、リストカットを行うと、脳から痛みを和らげるためにドーパミンが分泌されます。
このドーパミンは、快感をもたらします。
しかし、リストカットを続けるとドーパミンが分泌され難くなることから、より深く自分を傷つけなければ快感を得られなくなります。
繰り返しリストカットしていて、「命にはかかわらない」と安堵している中で、突然、死に至るほど深く傷つけてしまうことがあるのは、こうした理由からです。
人の脳が快感を覚えていたり、行動していたりすることに対して、やみくもに、あるいは、正論を振りかざして、「お願いだから、もう止めて!」と訴えたり、「その行為は間違っている。直ぐに止めるべきだ!」と叱ったりしても、効果はほとんど見込めません。
また、MRI画像診断により脳の萎縮を診る他に、ストレスの負荷の状態は、血液検査によるセロトニン値などの把握により数値化できます。
(被虐待体験は、内臓にも傷をもたらし、免疫系にダメージを及ぼす)
私が、被害者のアドボケーターとなるときには、被害者に対し、「少なくとも、血液検査で、「コルチゾール、ACTH(以上、ストレス状態を見る)、TSH、T3、T4、rT3(以上、甲状腺の機能低下、うつ傾向を見る)の値は必要で、可能であれば、白血球の一種「好中球数」を知りたい」と伝えています。
なぜなら、これらの数値は、いま、からだや脳がどのような状態なのかを知る手がかりになるからです。
暴力行為によるストレスは、脳の萎縮をもたらすだけではなく、内臓にも傷をもたらし、免疫系にも大きなダメージを及ぼします。
虐待死した子どもと高齢者の司法解剖により、虐待死した人には、「胸腺」の萎縮が認められることがわかっています。
「暴力を受けて亡くなった生後2ヶ月-8歳の子ども13人と66-84歳の高齢者11人を司法解剖し、心臓、肺、肝臓、腎臓を調べた調査報告では、子どもは、すべての臓器で、好中球の数が虐待死でない場合に比べ、1.7倍-7.6倍増加し、高齢者では、肺や肝臓で1.9倍-4.8倍増えていた」という報告があります。
注目されるのは、慢性反復的(長期間、継続的、日常的)に虐待を受けた子どもに共通して見られる傾向が、免疫に関わる「胸腺」の重さが同年代の子どもの平均の数分の1だったこと、つまり、萎縮していたことです。
虐待を受けた子どもや高齢者は、正常な内臓も攻撃してしまう白血球の一種「好中球」を増加させ、その結果、肺や肝臓などの臓器にも障害を生じさせます。
このことは、仮に外傷の痕跡が目立たない場合であっても、司法解剖で内臓を調べることで、虐待死を発見することができるということ、同時に、生存中の血液検査で、コルチゾール値に加え、「白血球数」、ならびに、「好中球数」を把握することができれば、虐待被害(ストレス)の可能性の高さを判断できるということを意味します。
では、トラウマ体験によるストレスが、免疫力の低下を招くことが、潰瘍や消化器系の炎症を生じさせ、臓器に傷害をおこすメカニズムを説明します。
「好中球」は「白血球」のひとつです。
白血球は好中球・好酸球・好塩基球・リンパ球・単球で構成され、血液中の白血球の約半数は顆粒球です。
その大部分が中性の色素でよく染まる好中球で、酸性色素で染まる好酸球、塩基性色素で染まる好塩基球に分けられます。
好中球は、細菌などの異物を処理し、生体を外敵から防ぐ働きをします。
つまり、生体に交感神経が優位になりアドレナリンが分泌されると、好中球は増加します。
ストレスは、薬物(薬品分類としての白砂糖、ニコチン、カフェインを含む)などと同様に、体内に入ると毒蛇の2倍の毒素を持つといわれるアドレナリンを分泌させます。
好中球の増加と関連する疾患として、「細菌感染・血管炎」、「梗塞など組織の炎症」、「壊死を伴う疾患」、「尿毒症」、「がん・リンパ腫などの腫瘍」、「急性出血・溶血」があげられます。
また、好酸球は、顆粒から特殊な蛋白を放出して寄生虫やその虫卵を傷害したり、「喘息」や「薬物アレルギー」などのアレルギー反応をひきおこしたりします。
好塩基球の増加は、「骨髄増殖性疾患」、「潰瘍性大腸炎」をひきおこします。
さらに、白血球には顆粒球以外にリンパ球と単球がありますが、リンパ球は、外敵の侵入からからだを守る免疫機能を担い、副交感神経が優位になると増加します。
人のからだは、強いストレスにさらされて交換神経が優位になると、好中球は増加し、リンパ球は減少します。
リンパ球が減少すると、体内にウイルスなどが侵入したときに撃退することができず、疾病に罹患する(発病する)リスクが高くなります。
慢性反復的(日常的)なトラウマ体験は、継続的に長期間にわたりコルチゾール(副腎皮質から分泌されるストレスホルモン)を分泌させ、脳の海馬や視床下部などにダメージを与えるだけでなく、免疫力の低下を招きます。
その免疫細胞は、正常な脳細胞の維持、損傷後の修復のプロセスに重要な役割を担っています。
重要な役割とは、脳機能の損傷に続く修復プロセスの各段階に決まったタイプの免疫細胞がかかわり、それらのスイッチが、順番どおりタイミングよく入ったり切れたりすることです。
つまり、免疫系には、生化学的なバランスをとり戻す役割があり、免疫系が機能しない状態を放っておくと、長期的な精神機能障害につながりかねないことになります。
継続的に長期間にわたりコルチゾールが分泌される状態、つまり、免疫系が機能しない状態になると、認知や情緒が損なわれたり、脳機能の損傷後の再生がうまくいかずに「神経変性疾患」の進行を促したりします。
「神経変性疾患」とは、脳や脊髄にある神経細胞の中で、ある特定の神経細胞群(例えば、認知機能に関係する神経細胞や運動機能に関係する細胞)が徐々に障害を受け脱落してしまう疾患です。
脱落してしまう細胞は疾患により異なりますが、大きく分けると、a)スムーズな運動ができなくなる「パーキンソン病」、「パーキンソン症候群(多系統萎縮症、進行性核上性麻痺など)」など、b)からだのバランスがとり難くなる「脊髄小脳変性症」、「一部の痙性対麻痺」など、c)筋力が低下してしまう「筋萎縮性側索硬化症」など、d)認知能力が低下してしまう「アルツハイマー病」、「レビー小体型認知症」、「皮質基底核変性症」などの疾患があげられます。
トラウマとなり得る体験により「免疫力の低下」を招き、免疫系が内臓に及ぶすダメージについては、「Ⅱ-19-(1)-③身体化の障害(身体表現性障害)」で述べていますが、トラウマとなり得る体験(心の傷)は、脳に傷をもたらすだけでなく、内臓に傷を残します。
(アタッチメントを損なうと「愛着障害」を発症させる)
そして、乳幼児期の「ある特定の入力」の代表的なものは、“愛着(アタッチメント)”です。
「愛着理論」を確立したジョン・ボウルビィは、アタッチメント(愛着)は、「特定の対象者との情緒的な結びつきを指し、子どもが特定の対象者との相互的な情緒的な作用を通じて形成される確固たる絆である」としました。
アタッチメントの形成は、子どもの人間に対する基本的信頼感を育み、その後の心の発達、人間関係に大きく影響し、乳幼児期に愛着にもとづいた人間関係が存在することが、その後の子どもの社会性の発達には重要な役割を持つと考えます。
乳幼児期の心の発達には、アタッチメントの形成が大前提です。
つまり、アタッチメントの形成が子どもの心の発達の基盤となります。
一方で、子どものアタッチメントの形成を損なう家庭環境やコミュニティ環境(生存環境)は、子どもの心の発達に支障を生じさせます。
子どものアタッチメントの形成を損なう環境とは、親(養育者)による子どもへの虐待行為(両親間のDV行為を目撃を含む)が存在している、つまり、機能不全家庭における養育ということになります。
苛烈な被虐待体験でアタッチメントを損ない、子どもが発症しやすくなるのが、「Ⅱ-16-(7)反応性愛着障害(RAD)」で詳述する「愛着障害」です。
虐待を受けるなどを起因として、親に愛着を感じられない「愛着障害」がある子どもの脳では、特定の機能が低下していることがわかっています。
そのひとつが、「ほめられる」といった“報酬”について喜ぶ機能の低下です。
「愛着障害」の子どもは、自己肯定感が低く、ほめられることばを投げかけられたとしても心に響かず、同時に、感情を制御することができないことから、問題をおこしやすい傾向があります。
「愛着障害」の子どもと感情を制御することができずに問題をおこしやすい「ADHD(注意欠陥/多動性障害)」の子どもとの違いは、「愛着障害」の子どもは“報酬”に反応しないのに対し、「ADHD」の子どもは、得られる“報酬”が多くなると活性化することです。
胎児期を含めた発達期の脳に対する強い精神的衝撃は、脳の神経伝達物質の分泌にも影響を及ぼします。
報酬を喜ぶ機能は、神経伝達物質の「ドーパミン」が関係していることから、「愛着障害」の子どもは、ドーパミンが不足している可能性が指摘されています。
また、ドーパミンの不足は、パーキンソン病と関係していることが知られています。
この『手引き(新版2訂)』では、「子どもの脳の発達」「子どもが受ける脳のダメージ」を考えるとき、“乳幼児・学童期”だけではなく、“胎児期”を含んだ脳の発達、ダメージまでを網羅します。
つまり、女性が妊娠期に暴力を受けると、その影響(ダメージ)は、「胎児」にも及ぶという理解です。
DV被害のリスクが疑われる妊産婦は、少なくとも14%以上存在しているといわれます。
この数字を、令和3年(2021年)に生まれた日本人の子ども842,897人にあてはめると、117,999人の子どもの母親が、妊娠中にDV被害にあっていたことになります。
妊娠中のDV被害は、母体の被害だけでなく、早産や胎児仮死、児の出産時低体重をひきおこしたり、「セロトニン」、「ドーパミン」などの神経伝達物質の分泌に影響を及ぼしたりするなど、胎児の初期の脳形成に重大な影響を及ぼします。
そのため、アメリカのサウスダコタ州やウィスコンシン州では、胎児を人として捉え、胎児虐待を「児童虐待」に含み、刑事罰の対象としています。
日本では馴染みのない「胎児虐待」とは、胎児の生命を脅かしたり、深刻な健康被害をもたらしたりする怖れのある行為をいいます。
日本では、妊娠中のDV被害などの「胎児虐待」が確認されても、妊婦に適切な対応やサポートは行われず、胎児への深刻な影響が放置されています。
日本において「胎児虐待」に対する対応の論議が進まない理由は、日本の刑法(判例)では、人の始期が一部露出説を採用しているからです。
「一部露出説」とは、胎児の体の一部が母体から体外にでた段階で、刑法の対象の「人」となることです。
日本では、「胎児虐待」の法的な“定義”がないことが、行政機関や臨床現場で議論されてこなかった大きな要因となっています。
平成28年(2016年)10月、『児童福祉法』が一部改正され(平成28年法律第63号)、「支援を要する妊婦等を把握した医療機関や学校等は、その旨を市町村に情報提供するよう努めるものとする。」と明記されました(第21条の10の5)。
これを受けて、医療機関から自治体の保健・福祉に情報提供することが努力義務となり、本人の同意がなくても特定妊婦や産後に養育不全や児童虐待が懸念される場合には市町村の情報提供が可能であるとされました(雇児総発1216第2号・雇児母発1216第2号)。
「胎児虐待」は、DV被害下にある妊婦支援のために関係機関が情報共有し、積極的に介入し、対応しなければなりません。
日本周産期メンタルヘルス学会の診療ガイド『周産期メンタルヘルス コンセンサスガイド2017』の「CQ6.メンタルヘルス不調で支援を要する妊産褥婦についての、医療・保健・福祉の情報共有及び同意取得・虐待や養育不全の場合の連絡の仕方は?」のAnswerでは、「児童虐待・胎児虐待が疑われた場合は、医療機関から保健・福祉機関に情報提供を行い、医療・保健・福祉機関が連携して、母子の支援を行う。」と明記しています。
この「胎児虐待への対応」に言及した『診療ガイド』の記載は、受診した妊婦に胎児虐待やその疑いがあるとき、関係機関と連携して、妊婦をサポートし、胎児を守っていくための母子保健における胎児虐待対応を整備することを目的にしています。
しかし、日本では、このガイドから5年経過したいまも、妊婦に対し、適切な対応やサポートは行われず、胎児への深刻な影響が放置され続けています(令和4年(2022年)4月現在)。
そうした中、令和4年(2022年)6月25日、一般社団法人「日本乳幼児精神保健学会」は、離婚後の子どもの養育のあり方について声明を発表しました。
その冒頭で、「人間の脳は、乳幼児期・児童・思春期にもっとも発達し、とりわけ、受胎という命の誕生から最初の数年の間に、急激な回路の発達を遂げる。この時期に形成された人としての土台が人生全体へ強く影響を及ぼすことは、いまや発達科学の常識として良く知られたことである(ユニセフは、発達阻害を防ぐには、妊娠から2歳の誕生日を迎えるまでの3年間-人生の最初の約1000日-への関心を高め、集中的にとり組む必要があることを強調している。)」と記し、最後に、「以下、当学会は、乳幼児・児童・思春期の精神医学の観点から、子どもの権利を最大限尊重するという理念を基本に、最新の科学的研究および豊富な臨床現場の知見に基づき、離婚後の子どもの養育に関して声明を発する‥」と記しています。
この“声明”は、ⅰ)離婚後の子どもに必要なことは、子どもが安全・安心な環境で同居親と暮らせること、ⅱ)子どもには意思がある、ⅲ)面会交流の悪影響、ⅳ)同居親へのサポート、ⅴ)離婚後の共同親権には養育の質を損なうリスクがあるとしています。
そして、「離婚後の子どもの養育に関する法制度の改正には、子どもの視点に立った慎重な議論を求めるものである。」と締めくくっています。
発達期の脳に対する強い精神的衝撃は、脳の「神経伝達物質の分泌」に影響を与えます。
ストレスを調節するホルモンである「コルチゾール」や重要な神経伝達物質である「エピネフィリン」、「ドーパミン」、「セロトニン」等に変化が生じます。
これら神経伝達物質のバランスに問題が生じると、障害が起きます。
神経発達症(発達障害)には、「自閉症」、「双極性障害」、「統合失調症」、「学習障害」、「脳性麻痺」など、脳や神経系の発達に関連する疾患が該当します。
「妊娠期を含め、被害親子の精神健康は相互に影響している」という視点に立ち、両者のケアがリンクすることは、重要なテーマであり、被害親子のケアにあたっては、安全な居場所の確保が最優先事項です。
にもかかわらず、日本政府や国会議員(支援する団体、支援者を含む)、警察、司法、医療、福祉行政、教育に携わる人たちなど、日本社会において、女性と子どもに対する人権意識の低さを起因とする大きな“遅れ”は、暴力行為に及んだ者に対する精神的治療に結びつくのを難くしています。
結果、日本では、欧米諸国のような警察、司法、福祉行政、医療、教育などの機関との連携体制も構築できません。
『児童虐待防止法』において、「面前DV」を「心理的虐待」と規定したことは大きな意味がありますが、面前DV(心理的虐待)などの虐待行為がもたらす“子どもの脳の発達”と“子どもの脳のダメージ”に対する視点は、司法関係者に留まらず、医療関係者、教育関係者、福祉行政関係者にもほとんど知られておらず、まして、妊娠期のDV被害(胎児虐待)の視点は、日本社会には見あたりません。
子どもに対する虐待行為(面前DVを含む)が、脳のシステムの発達に異常(問題・傷害)が及ぶメカニズムと、その異常(問題・障害)がもたらすさまざまなトラブルを知ることはとても重要なことです。
*-22 令和3年(2021年)4月、福井大学医学部の西住裕文准教授らの研究グループは、幼少期の嗅覚刺激が、その後の社会行動に影響を及ぼす「においすり込み」の仕組みを解明したと発表しました。
「すり込み」は、幼少期に外界から受ける嗅覚や触覚、聴覚などの刺激により、脳内の神経回路が変化し、生涯にわたって影響を及ぼす現象のことで、アヒルの後追い行動やサケの母川回帰は、よく知られています。
西住准教授らは、平成28年(2016年)から哺乳類の嗅覚系のすり込みをマウスで研究し、「生後1週間までに脳内のタンパク質「セマフォリン7」「プレキシンC1」が結合し、においに関する神経回路が増強する」、「この時期に鼻をふさいでいたマウスは、本来興味を示すべき仲間のにおいを避け、自閉症と同様の行動をとるようになる」ことを確認し、「愛情ホルモンとして知られるタンパク質「オキシトシン」が、この時期に接したにおいを“心地よく、安心感のあるにおい”として認識させる」ことを明らかにしました。
西住准教授は「この研究を人に応用することで、いつ、どのような感覚刺激を与えると、より心豊かに育まれるのかが分かってくるのではないか。愛着障害、発達障害が発症する原因の究明にもつながる可能性も高い」と説明しました。
オキシトシン投与は、既に、自閉症の治療法として研究されており、「投与時期の最適化など、治療の改良にも役立つのではないか」と今後の展開に期待しています。
*-23 「シナプスの刈り込み(剪定)」については、「Ⅱ-13-(7)学童期(6-12歳)」で説明しています。
*-24 さまざまな生活習慣病は、胎児期に兆候が表れます。
人の体内時計は、胎児期に基礎がつくられ、乳児期の終わりにほぼ完成し、その後、生涯にわたり健康に影響を及ぼします。
体内時計の形成とは、概日リズム(おおむね「1日=24時間」を刻む身体のリズム)形成の原点である「超日リズム(数10分から数時間単位(20時間まで)繰り返されるリズム)形成」のことです。
この胎児期における体内時計の形成のあり方が、その後の生活習慣病の発症に影響を及ぼします。
生後、1日を2-4時間ごとの超日リズムによる睡眠・覚醒リズムで過ごしていた乳児は、新生児期が終わると、かなり速いスピードで、夜は睡眠、日中は覚醒・活動という、概日リズム体内時計の形成を進めます。
そのとき、胎児期につくられた各臓器に独立して存在する概日リズムを持つ末梢時計系群を統合する中枢時計が、脳の視交叉上核に形成されていきます。
このとき統合される概日リズムは、新生児期の超日リズムを基盤としていますが、もとは、超日リズムも全身の細胞・臓器の概日リズムも、体内ですでにつくられたものです。
当然、母体の影響を強く受けます。
乳児は、胎児期に母親とともにつくった自分の固有の超日リズムと、各臓器に散在する概日リズムをもって生まれきます。
生後は、実際の日常生活の夜(暗)と昼(明)のリズムを経験することで、概日リズムを1つにまとめる中枢時計をつくりあげます。
その完成時期は、1-2歳ごろまでです。
このあと、概日リズム中枢時計は次第に固定していきますが、固定されるわけではなく少し柔軟性を残しています。
つまり、その後の人生での過ごし方が、体内時計をずらしてしまうこともあれば、あるいは、ずれた体内時計を修復することもできます。
ただし、ずらすのも、修復するのも、それ相応の時間を要します。
重要なことは、ずれや混乱は、重症化すると修復が困難になるということです。
ホモサピエンス(人類)が出現してから20万年をかけて「共同養育システム」をつくりあげていく中で、暗くなったら眠り、明るくなったら起きて活動する生活リズムをつくりあげていきました。
700万年前の北アフリカ、乾燥化により熱帯雨林が縮小しできたサバンナでの生活で、肉食獣に襲われるリスクが高く、生存率が低下したサピエンスは、人類生存の戦略として、毎年出産して、多くの子どもを残すようになりました。
出産後子育てに従事する5年間は次の子どもを妊娠しないチンパンジーと違い、猿人から分化した人類は、600万年という年月をかけて毎年出産できるように進化しました。
出産後10年以上の歳月をかけて大脳をゆっくりつくりあげるホモサピエンス(人類)が、育児中に次の子どもを妊娠し出産することを可能にしたのが、女性同士が育児と労働を助け合い、男性が育児に加わる「共同養育」というシステムでした。
現代社会では、「共同養育システム」が崩壊する一方で、正確な24時間の繰り返しで営まれる学校・社会という生活リズムに適応なしに生活を送ることはほぼ不可能です。
しかし年齢層に関係なく、夜ふかしや不規則な生活は、中枢時計がずれたり揺らいだりして、学校・社会との間にさまざまな程度の時差が生じることにより、全身体内時計の歯車のかみ合わせの狂いや不安定さが生じます。
つまり、系統的に体内時計に混乱が生じるのです。
胎児期からの生得的な素質に加えて、日常生活の夜型化(ずれ=シフト)や不規則性などは、極めて重大な健康被害を及ぼします。
これは、ひとつの「生活習慣病」といえます。
「共同養育システム」のもとで子育てができるようにインプットされているホモサピエンス(人類)が、「共同同養育システム」がほぼ機能しなくなった現代社会で、深刻化し、社会問題化しているのが「産後うつ」です。
第2は、いまから2年前の令和2年(2020年)4月1日、親による「体罰」を禁止する『改正児童虐待の防止等に関する法律(改正児童虐待防止法)』が施行されたことです(令和4年(2022年)10月現在)。
「体罰」は、子どもの成長や発達に悪影響を与えることが、科学的にも明らかになっていることから、世界では、日本が法改正をする前に、58ヶ国が法律で体罰を禁止してきました。
一方で、国連児童基金(ユニセフ)は、「2017年(平成29年)時点で2-4歳の子どもの約63%(約2億5000万人)が、尻を叩く体罰が認められている国に住み、保護者から定期的に体罰を受けている」と報告しています。
アメリカ合衆国では、全50州で親による子どもへの体罰は合法とされ、そのうち19の州では、法律で学校内での体罰が認められています(これらの州の一部の学区では体罰を禁止している)。
一方で、スウェーデンが、世界で初めて体罰禁止を法制化したのは、第2次世界大戦が終戦してから34年後、いまから43年前の1979年(昭和54年)のことです(令和4年(2022年)10月現在)。
そのスウェーデンでは、1960年代に55%の親が体罰を肯定的に捉え、95%の親が体罰をおこなっていました。
しかし、体罰禁止を法制化してから34年経過した2018年(平成30年)、親の体罰は1-2%に激減しています。
一方で、日本政府(日本社会)では、スウェーデンが体罰を禁止してから43年間(終戦後77年間、「懲戒権(民法822条)」の制定から124年間)、体罰は、「しつけ(教育)」の一環として容認してきました(令和4年(2022年)10月現在)。
「しつけ(教育)」なので、親は、虐待とは認識していません。
スウェーデンが体罰を禁止してから39年経過、第2次世界大戦が終戦してから73年経過した平成30年(2018年)3月、東京都目黒区で船戸結愛(ゆあ)ちゃん(当時5歳)の虐待死事件が発生し、5歳児が書いたと思えないような「反省文」がメディアでとりあげられ、連日、ニュースで報道されました。
この虐待死事件は、政府を動かし、同年7月には、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」が示され、2年後の令和2年(2020年)4月1日、『改正児童虐待防止法』が施行されました。
スウェーデンが体罰を禁止してから41年、世界で59番目のことでした。
同法では、「親は、児童のしつけに際して体罰を加えてはならない」としています。
施行される前、メディアなどで議論されたのは、親の子どもへの体罰(虐待行為)に対して、「どのような行為が許されないのか」よりも、「どこまでだったら、許されるのか」という“線引き”“尺度(基準)”でした。
職場での「セクシュアルハラスメント」や「パワーハラスメント」が禁止されたときにも、メディアなどで議論されるのは、「どのような行為が許されないのか」よりも、「どこまでだったら、許されるのか」という“線引き”“尺度(基準)”でした。
そもそも、暴力(虐待)行為に対して、“線引き”“尺度(基準)”を持ちだすことは、間違っています。
なぜなら、暴力を加える(加えられる)ことに、「許される」「許されない」という“線引き”“尺度(基準)”など存在しないからです。
つまり、「いかなる理由があっても、人に危害を加える、つまり、人に暴力をふるう行為は許されない」という立ち位置(人権認識)であることが求められます。
「この程度なら許される(大丈夫だろう)」、「一定の条件下であれば許される」という“解釈”を残してはならないのです。
「人に危害を加えられることは、人権を侵害されることに他ならない」と理解しなければならないのです。
しかし日本では、いまだに、この「いかなる理由があっても、人に危害を加える行為は許されない(人権侵害)」という“概念”は浸透していません。
この“概念”が備わっていない人の多くは、例えば、「性暴力(レイプ、痴漢、セクシュアルハラスメントなど)被害を受ける女性は、このような人/タイプ/年齢/服装」などといったステレオタイプ的な考え方に影響を受けやすくなります。
それは、被害を訴えた(話した)とき、その被害を信じるか、信じないかに影響を及ぼし、2次加害(セカンドレイプ)を招く可能性を高めます。
2021年(令和3年)、米非営利団体ストップ・ストリート・ハラスメントは、「数年前、職場で何らかのセクシュアルハラスメントを経験していた女性の割合は81%にも上る」との衝撃的な調査結果を発表しました。
これには、ことばによるハラスメントから性的暴行まで含まれており、女性が職場で直面する問題の規模を浮き彫りにしています。
セクシュアルハラスメントに対する対応は、その内容にもとづいて実施される必要があります。
しかし、ワシントン大学は、4,000人以上が参加した研究結果として、「実際は、そうなってはいない」、「セクシュアルハラスメントの訴えは、年齢が若く、振る舞いや見た目が女性らしい、一般的に魅力的とされる女性の方が、はるかに信じてもらいやすい」と発表し、「セクシュアルハラスメントは、“典型的”な女性のみの問題だとする認識が強いこと」、「典型的な女性像にあてはまらない女性は、たとえセクシュアルハラスメントを受けても実害はないと考えられがちなこと」を示し、「それがもたらす結果は、セクシュアルハラスメント被害者の狭い定義に入らない女性にとって非常に深刻である」、「こうした女性たちは、セクシュアルハラスメントを受けたことを信じてもらえないだけでなく、セクシュアルハラスメントを受けても害がないと思われ、加害者が罰を受ける必要もないとみなされていた」と指摘しています。
このことは、職場でのセクシュアルハラスメントは、あらゆるタイプの女性が被害を受けているにもかかわらず、こうした条件にあてはまらない女性たちは、被害を信じてもらえず、結果、被害を証明し難い状況にあることを示しています。
日本では、職場での上司と部下、取引先と担当者などの関係性で生じる「ハラスメント」、教育現場などで、教師や指導者と生徒の関係性で生じる「体罰」、「ハラスメント」だけでなく、家庭内での夫婦の間(交際相手との間)における「DV(デートDV)」、親子間における「児童虐待」においても、「一定の条件下での暴力行為は許される」と考える人が圧倒的多数を占めます。
平成30年(2018年)、子ども支援の国際的NGO「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」が2万人の日本人を対象に実施した調査では、しつけに伴う子どもへの体罰を約6割が容認していました*-25。
しかし、「体罰はすべきではない」と回答した人でも、「お尻や手の甲を叩く」ことは容認していることから考えると、実際は、約7割の人が、しつけに伴う体罰を容認していることになります。
日本では、「この“程度”のことは体罰ではなく、しつけのうち」と自身の基準(モノサシ)で判断したり、「手加減すればよい」、「子どものふるまいを正すにはやむを得ない」、「一度だけなら大丈夫だろう」と自身の体罰行為を正当化したりする人が多いことが示されています。
平成28年(2016年)に実施された他の調査では、「約70%の親が、子どもを叩いたことがある」と回答しています。
その調査は、20-30歳代の社会人男女200人(男女100人ずつ)に対し、「過去に、親からどのようなしつけを受け、罰を与えられたことがあるか?」を訊くアンケート(12項目、複数回答可)で実施されました。
「過去に親からしつけとして与えられた罰」に対し、①叩かれる(53.5%)、②長時間のお説教(32.0%)、③押入れ・ベランダなどに閉じ込められる(22.0%)、④ゲーム・おもちゃなどをとりあげられる(21.0%)、⑤おやつ抜き(12.5%)、⑥正座(11.0%)、⑦ご飯抜き(8.5%)、⑧お小遣いの減額、とりあげ(6.5%)、⑨置き去り(6.5%)、⑩強制お勉強(5.5%)、⑪誕生日・クリスマスのプレゼントなし(2.5%)、⑫反省文(2.5%)と回答しています。
加えて、「とりわけ衝撃的だった(“最も衝撃的だった”親からしつけとして与えられた罰)もの」についても同じ項目からひとつ選んでもらうと、男性では、①叩かれる(30.5%)、②長時間のお説教(13.0%)、③押入れ・ベランダなどに閉じ込められる(12.0%)、④ゲーム・おもちゃなどをとりあげられる(4.0%)、⑤おやつ抜き(3.0%)と回答し、女性では、①叩かれる(35.0%)、③押入れ・ベランダなどに閉じ込められる(12.0%)、②長時間のお説教(6.0%)、④ゲーム・おもちゃなどをとりあげられる(6.0%)、⑨置き去り(3.0%)と回答しています。
そして、「最も衝撃的だったしつけ体験について、いま、ふり返ってみて、どのように思うのか」を訊くと、①「叩かれる」ことについては、「よいと思う。誰かが痛みを教えないといけない(33歳・男性)」、「多少トラウマになったようで“自分は決して暴力を他人にふるうものか”と思うようになりました(38歳・男性)」、「本気で叩いてないし、しつけだから問題ない(29歳・男性)」、「掃除機の柄で叩かれて肩が外れかけました。いくらなんでもやりすぎだと思います(37歳・女性)」、「叩くのは親がすっきりしたいからだと思う(34歳・女性)」、②「長時間のお説教」については、「気が遠くなるほどやられた(33歳・男性)」、「無駄話が多かった(26歳・男性)」、「やはり自分が悪いことをして罰を受けているので、当時はすごい嫌で覚えているが適切な判断だったと思う(32歳・男性)」、「怖かった(27歳・女性)」、「特別不適切に思ったことはない(25歳・女性)」、③「押入れ・ベランダなどに閉じ込められる」ことについては、「自分が悪いことをしたのだから適切(38歳・男性)」、「閉所恐怖症だったのでキツかった(37歳・男性)」、「過激だったとは思わないが、悲しかっただけでしつけとして効果的だったかどうかは微妙(28歳・女性)」、「思いだすだけでも嫌になるが、もし自分に子どもができたとき、頭を冷やせという意味で同じことをすると思う(31歳・女性)」、④「ゲーム・おもちゃなどをとりあげられる」については、「詳しくは覚えていないが、なにか悪いことをしたせいだから仕方ないと思います(33歳・男性)」、「ゲームをやり過ぎていた自分も悪かったが、とりあげられて余計にイライラしてしまった(24歳・女性)」、⑤「おやつ抜き」については、「一番効くと思う(26歳・男性)」、⑨「置き去り」について、「山の中に置き去りにされて動くことができず、泣いたのを覚えています。捨てられる恐怖を覚えて、いまもトラウマです(30歳・女性)」と回答しています。
調査対象は、20-30歳であることから、平成7年-昭和60年(1995年-1985年)の生まれです(平成28年(2016年)現在)。
父母が20-35歳ときに生まれたと仮定すると、父母は昭和40年-25年(1965年-1950年)生まれの40歳-65歳、同様に、祖父母は昭和20年-大正14年(1945年-1925年)の70歳-95歳ということになります(いずれも平成28年(2016年)現在)。
調査対象者の70%が子どもを叩いているので、祖父母まで遡ると4世代となります。
明治政府が「懲戒権(民法822条)」を定めたのが明治29年(1896年)なので、この4世代の前に、1-2世代の子育てがおこなわれていたことになります。
上記の体罰の“%”は、「昭和40年-25年生まれ(1965年-1950年)の40歳-65歳の53.5%の親は、平成7年-昭和60年(1995年-1985年)に生まれの20-30歳の子どもを叩いていた(身体的虐待を加えた)」ことを意味します(いずれも平成28年(2016年)現在)。
そして、「53.5%の子どもを叩いていた親の下で育った20-30歳の子ども(平成7年-昭和60年(1995年-1985年)の生まれ)は、親となったとき、その約70%が自身の子どもを叩いている」ことを意味します(平成28年(2016年)現在)。
このことは、「叩かれて(身体的虐待は受けて)はいない体罰を受けて(被虐待体験をして)育つと、親になったとき叩く(身体的虐待を加える)行為が増加している」こと、「1-2世代前の親はみな叩いていたのではなく、しつけ(教育)と称する体罰を容認している中で増加した」、「しつけ(教育)と称する体罰を受けて育つと、その被虐待体験は抑止に向かわない」ことを示しています。
同様に、32.0%が長時間の説教(心理的虐待)、22.0%が押入れ・ベランダなどに閉じ込め(身体的虐待)、21.0%がゲーム・おもちゃなどをとりあげ(心理的虐待)、12.5%がおやつを抜き(身体的虐待)、11.0%が正座をさせ(身体的虐待)、8.5%が食事を与えず(ネグレクト)、6.5%がお小遣いを減額したり、とりあげたりし(心理的虐待)、6.5%が置き去りにし(身体的虐待)、5.5%が勉強を強制し(教育的虐待)、2.5%が誕生日・クリスマスのプレゼントを贈らず(わたさず)(心理的虐待)、2.5%が反省文(心理的虐待)を書かせています。
( )書きしているように、上記の体罰行為は、『児童虐待防止法』では、すべて「虐待行為」です。
親からこうした体罰を加えられて育った20-30歳の子ども(平成7年-昭和60年(1995年-1985年)の生まれ)は、叩く(身体的虐待)ことは、「痛みを教えないといけない」「しつけだから問題ない」、長時間説教する(心理的虐待)ことは、「適切な判断だった」「特別不適切に思ったことはない」、押入れ・ベランダなどに閉じ込める(身体的虐待)ことは、「悪いことをしたのだから適切」「子どもができたとき、頭を冷やせという意味で同じことをすると思う」、おやつ抜くことは、「一番きくと思う」などと親の体罰(虐待行為)を受け入れ、容認している、つまり、虐待行為を肯定しています。
こうした虐待行為を容認(正当化)する認知が、70%の親が子どもを叩くなどの虐待行為につながっています。
そして、子どもに対する暴力(虐待行為)だけでなく、差別・排除、DV(デートDV)、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力行為に対して容認しやすくなります。
こうした暴力行為(体罰)を容認し、肯定する人たちに共通する“いい回し”があります。
それは、「暴力はダメだ。しかし…」、「戦争はダメだ。しかし…」、「差別はダメだ。しかし…」、「いじめはダメだ。しかし…」、「ハラスメントはダメだ。しかし…」、「DVはダメだ。しかし…」、「児童虐待はダメだ。しかし、」と“逆説の接続詞”をつけて語ることです。
“逆説”とは、「前文の内容と反対となる内容が後文にくる」ことです。
「逆説の接続詞」とは、「しかし/しかしながら/だが/だけど/だけども/でも/それでも/ところが/とはいえ/けれど/けれども/なのに/それなのに/ですが/とはいうものの/にもかかわらず」のことです。
上記の「しかし、」のあとに続くことばは、「相手にも非があったに違いない」、「暴力(差別、いじめ)をふるわれるだけのことをした(理由がある)」と、“一定の条件下”であれば、暴力は正当化されるという考え方にもとづく内容です。
この“一定の条件下”であれば、暴力を容認してしまう考え方や価値観は、DV(デート)や児童虐待という問題に限定されるものではなく、差別・排除、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力問題に共通するものです。
これらの暴力行為に及ぶ者に共通しているのは、“一定の条件下”、例えば、「妻(女性)」「子ども」「部下」「生徒」「特定の人種、出身者」の態度や言動、服装、状況などを、暴力行為の“理由づけ(いい訳)”として使い、自らの暴力行為を正当化しようと試みることです。
加害者(DV/性暴力)を対象として実施される『加害者更生プログラム』の基本姿勢では、この“一定の条件下”、つまり、“態度”“言動”“姿勢”“立場”“服装”などを暴力行為(暴力行為をエスカレートさせたを含む)の理由づけとする考え方(認知)をいっさい認めていません。
つまり、『加害者更生プログラム』では、受講者に対して、「暴力行為の責任に関して、飲酒やストレス、被害女性の態度や服装などが暴力行為の理由づけに用いられるが、それらのことがあっても暴力を用いない人が多い」こと、「あくまでもそうした方法を選択しているのは、加害者の自分に都合のいい(自分勝手な)考えでしかない」ことを示し、「暴力行為を選択した責任は100%加害者にある」ことを示します。
問題は、こうした自分勝手な(自分だけに都合のいい)主張、つまり、“いい訳”を聞いた者の多くが、「一定の条件下であれば、仕方がない(容認される)」という立ち位置であるとき、大人と子ども、男性と女性の区別はなく、被害者の声(訴え)は、「否定・非難され、黙殺される」ことです。
こうした自分本位で身勝手な考え方の人たちによって、被害者の声(訴え)が否定・非難され、黙殺されることは、あってはならないことです。
しかし、この16年間、この理不尽な状況は変わりませんでした。
逆に、法が整備され、被害者が声(訴え)をあげ、行動に移しはじめる中で、加害者や加害者の考えや行為を支持する人たちによる被害者叩き(被害者を支援する人を含む)は激しく、執拗になっているように感じます。
第2次世界大戦後、日本政府は、明治29年(1896年)の制定から49年経過していた「懲戒権(民法822条)」を削除せず、74年7ヶ月、3世代にわたり、「しつけ(教育)と称する体罰」を認めてきた。
日本政府は、平成12年(2000年)に『児童虐待防止法』を制定しているので、「懲戒権」を削除した令和4年(2022年)までの22年間は2枚舌といえ、「児童相談所」や警察の介入を妨げる要因となってきた。
問題は、この126年間、5-6世代にわたり、国が認め、国民に深く沁み、ごく自然な行為となっている「しつけ(教育)と称する体罰」を減らすのは容易ではなくなったことです。
もはや、日本国民の大多数は、子どもの「しつけ(教育)」に対するアプローチとして、「体罰」を使わない方法を身につけていません。
法律で、「しつけ(教育)と称する体罰は加えてはいけない」としても、いまの日本社会には、その代替となる方法を教えられる人が極端に少ないという現実があります。
いま日本社会に必要なのは、パラダイムシフトの転換とも呼べるダイナミックな変革です。
私は、いまの日本は、例えば、脳卒中死亡者を減らすために、福祉行政(保健師)と医療(医師、看護師)が連携し、住民一人ひとりの食事の改善、運動習慣に地道にとり組んだように、スウェーデンやフィンランドをはじめとする北欧諸国で、しつけ(教育)と称する体罰やスケアード・ストレートをしない子育ての仕方と高い人権意識を身につけるために、大量の日本人家族が移住し、そのコミュニティで子育てをする中で、社会システムとともに、その子どものしつけに対するアプローチの数々について、身を持って学び、習得し、それを持って帰国し、その日本人家族が各都道府県に複数組み移住し、伝承させていくような国家プロジェクトなくして、しつけ(教育)と称する体罰をなくすことなどあり得ないほどの状況と危惧しています。
同時に、社会保障制度そのものを再設計し直し、時に、法体系の見直しも必要になります。
いまの日本社会において、いまの世代で、「しつけ(教育)と称する体罰」や「スケアード・ストレート」を使わないで子育てをする、つまり、子育てにおいて、いっさいの虐待を加えなくなることは非現実的です。
いまの現実をどう考えるか、この深刻な状況を受け止め、見て見ぬふりをしないか、国民一人ひとりの課題です。
*-25 2021年(令和3年)3月、国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」は、同年1月に20歳以上の男女2万人を対象に実施した「体罰等に関する意識調査」の結果を発表しました。
それによると、子どもへのしつけのための体罰を「容認」する回答者は41.3%で、前回の平成20年(2007年)の意識調査結果から15.4ポイント減少したものの、「体罰を決してすべきではない」と回答した1万1752人の29%(3408人)が、「しつけでお尻を叩く」と体罰を容認しています。
つまり、実数としては、60-70%がしつけと称する体罰を容認していることになります。
体罰を容認している人は、性別では男性が、年代では40-50歳代が相対的に高いことも明らかになりました。
第3は、いまから5年前の平成29年(2017年)3月7日、政府が、『性犯罪の厳罰化をはかる刑法改正案』を閣議決定し、同年6月2日、この性犯罪を厳罰化する刑法改正案は、衆院本会議で審議入りし成立、7月13日施行したことです(令和4年(2022年)10月現在)。
この刑法改正では、家庭内の性的虐待も厳罰化し、親や養父が監護者としての影響力により18歳未満の子と性行為をした場合について、新たに、『監護者性交等罪(刑法179条2項)』、『監護者わいせつ罪(刑法179条1項)』を設け、「暴行や脅迫要件は撤廃」されました。
これは、加害者が親などの監護者であるとき、子どもの生活を把握・管理する立場であることから、暴行や脅迫を行使しなくても、「性交に応じなかったら、お前の居場所はなくなる」と思わせたり、「これは誰でもやっていることだ」といいくるめたりすることは容易いと想定できるからです。
そして、「被害者の告訴がなくても処罰できることになった」ことは意味のあることです。
つまり、『監護者性交等罪』、『監護者わいせつ罪』は、暴行や脅迫、被害者の告訴がなくても適用されます。
また、この刑法改正により、『強姦罪(刑法177条)』、『強制わいせつ罪(刑法176条)』の法定刑が、以下のように強化されました。
被害者の告訴がないと起訴できない「親告罪」の規定がとり除かれ、改正案は付則で、改正法施行前の時効が成立していない事件についても、告訴なしに原則立件可能と定めています。
そして、強姦罪は『強制性交等罪』と改められ、被害者を女性に限らず、強制わいせつ罪に含めていた一部の「性交類似行為」と一本化されました。
「性交類似行為」とは、望まない肛門への性器挿入、口腔への性器や性具等の挿入等を伴う行為のことです。
これまでの『強姦罪』は、「陰茎の腟内への挿入(姦淫)」のみが対象でしたが、『強制性交等罪』では、“口腔性交(口腔内に陰茎を入れる行為)”と“肛門性交(肛門内に陰茎を入れる行為)”も構成要件に含まれるようになりました。
したがって、被害者が男性器を無理やり口に入れられたというケースもレイプ(強姦)と同じ扱いになります。
顔や口腔に射精された被害女性が、その後、食事や水分が摂取できなくなったり、自分の顔やからだへの幻臭に苦しんだりすることがあるように、「性交類似行為」は、深刻なトラウマになりうる行為です。
交際相手間、夫婦間におけるレイプ(同意のない性行為)、性交類似行為は、被害者の心身に与えるダメージは深く、長く苦しむことになります。
にもかかわらず、警察に「交際相手からのレイプ被害(デートレイプ)」「配偶者からのレイプ被害」を訴え、逮捕に至ったとしても、『強制性交等罪(刑法177条/旧強姦罪)』、『強制わいせつ罪(刑法176条)』どころか、『傷害罪(刑法204条)』でもなく、『暴行罪(刑法208条)』に留まることが少なくないのが現状です。
交際相手や配偶者に対し、「同意のない性行為」に及んだり、「望まない性行為」を強いたりすることは、「(DV行為としての)性的暴力」に該当すると『配偶者暴力防止法』で規定しています。
しかし、日本の警察は、平成13年(2001年)に同法が施行されて19年間(令和2年(2020年)9月現在)にわたり、夫婦間レイプ(強姦)について、ほとんど対応していません。
配偶者からの暴力事案の検挙状況(平成25年度)のうち、強姦(レイプ)による検挙はわずか2件です。
そういった意味でも、交際相手や配偶者が、「同意のない性行為」に及んだり、「望まない性行為」を強いたりする行為は、『配偶者暴力防止法』が規定する「(DV行為としての)性的暴力」に該当することが広く知られることは、性暴力被害を防ぐという意味でとても重要です。
また、今回の厳罰化で、強姦(レイプ)は被害、加害両者の性別に関係なく処罰可能となり、法定刑の下限を懲役3年から5年、致死傷罪の場合も5年から6年にそれぞれひきあげ、強盗や殺人と同等となりました。
懲役6月以上10年以下の強制わいせつ罪の一部もこれに含められ、刑罰は強化されます。
準強姦罪も『準強制性交等罪』に改められ、懲役4年以上とされている集団強姦罪の規定は削除されます。
また、強盗を伴う場合の刑罰が統一されます。
現行法(当時)では、強盗が先だと『強盗強姦罪』として「無期または7年以上」が科される一方、強姦が先なら強姦と強盗の併合罪で「5年以上30年以下」でしたが、改正において、新たに、『強盗・強制性交等罪(刑法241条1項)』を設け、犯行の前後にかかわらず「無期または7年以上」となります。
ただし、『傷害罪』、『強制性交等罪(旧「強姦罪」)』などで起訴され、実刑の判決が下った事件であっても、その傷害に対する損害賠償金(慰謝料)を求めるときには、別途、民事事件として提訴する必要があります。
この110年ぶりに改正された“性犯罪刑法”では、「公訴時効の廃止、または、停止」、「配偶者間におけるレイプの明文化」、「暴行・脅迫要件の緩和、もしくは、撤廃」、「性交同意年齢のひきあげ」などが見送られるなど、被害者にとって不合理な幾つかの重要な課題が残ったままです*-26。
いまから5年前の2017年(平成29年)、性暴力被害者支援の草の根活動のスローガンとしてはじまった「♯Me Too」は、同年10月5日、ニューヨーク・タイムズが、性的虐待疑惑のあった映画プロデューサーのヴェイ・ワインスタインによる数十年に及ぶセクシュアルハラスメントを告発したことをきっかけに、世界中に広まりました(令和4年(2022年)10月現在)。
この気が遠くなるほどの長い間、DV(デートDV)被害者、性暴力被害者たちの声(訴え)は、社会に、多くの男たちに黙殺されてきました。
その間、女性は、一歩一歩、一つひとつ、暴力被害から身を守る権利を勝ちとってきました。
そして、#MeTooが世界的なムーブメントなり、世界中で、性暴力やセクシュアルハラスメント対する体制や法の厳罰化などが見直されてきました。
スウェーデンでは、これまでの「No means No」という「不同意性行為はレイプ」という法律から「Only Yes means Yes」と「積極的な同意がなければ性暴力にあたる」とする法律に改正されました。
しかし、日本では、合意の有無ではなく、被害者への著しい暴行、脅迫され抵抗できなかったことの証明を求める「暴行・脅迫要件」は改正されずに残されたままです。
これまで、被害者を追い詰めてきた「なぜ抵抗できなかったの?」、「逃げられたはずでしょう!」といった問いかけのことばは、本来、あってはならないことです。
スウェーデンの調査では、「性暴力を受けたとき、約7割の人がショックで体が硬直した」という結果が報告されています。
この「人がショックで体が硬直する」、つまり、人が殴られたり、レイプされたりした瞬間に、「助けて!」と声をだせなかったり、逃げたりできなくなる、いわゆる「フリーズ現象」については、「Ⅰ-B-7-(4)暴力の後遺症としてのPTSD」で、ASD(急性ストレス障害)、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、PTSDの併発症としてのうつ病を発症するメカニズムとともに、「HPA機能」として科学的に説明し、「Ⅱ-19-(3)-③-カ)転換性障害」では、PTSDの侵入としてのフラッシュバックに襲われたとき、歩けなくなったり、声をだせなくなったりする症状として根拠を示しています。
日本では、フラワーデモのきっかけのひとつとなったのが、平成31年(2019年)3月、名古屋地裁岡崎支部が、平成29年(2017年)に19歳の娘に性的暴行を加え、『準強制性交等罪(刑法178条)』に問われた父親(49歳)に対し、「娘は抵抗できない状態ではなかった」として無罪判決を下したことです。
その後、令和2年(2020年)3月12日、名古屋高等裁判所の堀内満裁判長は、一審の無罪判決を破棄し、「被害女性は当時、抵抗することが困難な状態だった」として求刑通り懲役10年の判決を下しました。
この裁判で争点となったのは、『準強制性交等罪』の成立要件のひとつである「女性が事件当時、身体的、心理的に抵抗することが著しく困難な「抗拒不能」の状態だったのか」です。
「抗拒不能」とは、身体的、または、心理的に抵抗することが著しく困難な状態のことで、『準強制性交等罪』は、性行為への同意がなく、「心神喪失もしくは抗拒不能」により抵抗できなかった状態であることが成立要件となります。
抗拒不能は、「薬や酒を飲まされて、意識を失った」「騙され、信じ込まされた」など、暴行や脅迫がなくても、それらがあったときと同じようにからだや心の自由を奪われた場合に認められるものです。
一審判決では、「父親は、女性が小学生のころから虐待し、中学2年生のころに性的虐待を加えはじめていることなどから、女性に性行為の同意はなく、長年の虐待で、父親の精神的支配下に置かれていた」と認める一方で、「過去に拒めたことがあったなどとして、抗拒不能の状態だったと認定するには合理的な疑いが残る」と判断していました。
一方の高等裁判所判決では、女性が性行為を拒んだときに痣ができるほどの暴行を受けたことなどをあげ、「一審判決が抗拒不能状態を否定した事情は、むしろ肯定する事情となり得る」などと指摘し、一審判決について「父親が実の子に対し、継続的に行った性的虐待の一環だという実態を十分に評価していない」と批判し、父親に対し、「実の娘を性欲のはけ口としてもてあそんだ卑劣な犯行」と指摘したうえで、「被害者が受けた苦痛は加害者が、実の父親であることからも極めて甚大で深刻」と述べています。
そして、同年11月4日、最高裁判所は、父親を無罪とした1審判決の上告を棄却する決定を下し、2審判決が確定しました。
日本の刑法に「同意がなければ、性的暴行」と明記されていたら、被害女性をはじめとする性暴力被害者の長く苦しい道のりは違うものになります。
加えて、日本では、現在も、相手の同意があったかどうかにかかわらず性交した時点で犯罪になるという、「性交同意年齢は13歳」のままです。
日本と同じ「性行同意年齢が13歳」だった韓国は、いまから2年前の2020年(令和2年)5月、大量の被害者を出した『n番部屋事件』を受け、「13歳から16歳」にひきあげました(令和4年(2022年)10月現在)。
フランスやスウェーデンが15歳、カナダやイギリスが16歳です。
しかし日本では、いまだに、「同意があった」と主張すれば、中学生以下の児童と性交すること自体を犯罪として罰することができません。
ここには、たとえ、法律上成人と見なされる大人が13歳以下の児童と性的行為に及んだとしても、「自由恋愛なのだから、法律で守られるべきだ」という論調がまかり通っている背景があります。
しかし、「性交同意年齢」を考えるとき、“恋愛”云々を論議するのではなく、14歳以下の幼児・小児を対象とした性愛・性的嗜好は、「パラフィリア(性的倒錯・性嗜好障害)」としての「ペドファリア(小児性愛者)である」という“前提”に立つ必要があります。
重要なことは、15歳以上に性的行為を及ぶ者は、「ペドファリア」から外れますが、アジア諸国以外の国々の人から見ると、日本をはじめアジア人は体形を含め年齢より幼く見えることから、青年期後期(18歳-22歳)くらいまでは、捕食者の「ペドファリア」の“餌食(ターゲット)”と考えていいと思います。
たとえ、恋愛であっても、大人は児童を守る義務があり、性的欲求を抑えなければならないと考えます。
いうまでもなく、日本における「児童」とは、「18歳以下」の子どもです。
『監護者性交等罪』、『監護者わいせつ罪』は、18歳未満の子どもとの性行為を禁じているのに対し、『強制性交等罪』、『強制わいせつ罪』は、性的同意年齢を13歳以下のままなのは、どう考えても不合理、異常です。
*-26 現行の刑法では、「暴行・脅迫」を使えば『強制性交等罪』、アルコールや薬を飲ませて「心神喪失・抗拒不能」にしたときには『準強制性交等罪(178条)』となります。
しかし、その基準があいまいで、「被害者の抵抗が著しく困難でないと成立しない」と解釈され、無罪判決が相次いでいます。
そうした中で、令和3年(2021年)11月以降、性犯罪をめぐる刑法の規定の見直しを検討してきた法制審議会(会長・井田良中央大大学院教授)の部会は、令和5年(2023年)1月17日、『強制性交罪(刑法177条)』の成立要件で、「暴行・脅迫」「恐怖・驚愕」「地位利用」「心身に障害を生じさせる」など8項目の行為で被害者を「拒絶困難」な状態にさせた場合に処罰する」の「拒絶」を「同意しない」と文言を換えました。
これは、被害者の「「拒絶困難」では、被害者に拒絶の義務を課している」との訴えを踏まえたもので、8項目を前提とした基本構造は維持され、また、「意思に反して」という点だけで処罰する『不同意性交罪』とは異なります。
同年2月17日、法制審議会は、答申した「性犯罪規定改正の要綱」の中で、性的行為について自分で意思決定ができるとみなす「性交同意年齢」を13歳から16歳にひき上げ、16歳未満との行為を処罰対象にすると改めました。
これにより、16歳未満への行為は、同意の有無にかかわらず処罰対象となります。
ただし、近い年齢同士なら罰せず、13-15歳との行為は、加害者が5歳以上年上のケースを対象と限定するなど課題は残っています。
また「暴行・脅迫」といった『強制性交等罪』などの処罰要件で、「同意しない意思の表明などが難しい状態にして性的な行為をした」ことと改めました。
他に、性的部位や下着を盗撮する『撮影罪』を新設します。
同年2月24日、法務省は、刑法の『強制性交等罪(177条)』を『不同意性交等罪』に、『強制わいせつ罪(176条)』を『不同意わいせつ罪』に罪名変更する方針を固めました。
性犯罪規定は2021年に始まった法制審議会(法相の諮問機関)などで見直し議論が進められてきた。
法制審議会が、先の同年1月17日に答申した「法改正要綱」では、『強制性交等罪』などの成立要件について、現在の「暴行・脅迫」だけではなく、「虐待」や「経済的・社会的地位の利用」など計8種類の行為や状況によって、「同意しない意思の表明などが困難な状態になった被害者に性行為をした」ときには処罰すると明記しました。
つまり、被害者が「同意しない意思」を「形成し、表明し、もしくは、まっとうする」ことを困難にさせる状態にして性交したときには処罰できるようになります。
一方で、「意志に反して」という要件については、「内心だけの問題がある」として見送られています。
第4は、いまから10年前の平成24年(2012年)7月24日、最高裁判所が、暴力被害を原因とし、加療を要するPTSDの発症について、「監禁行為やその手段等として加えられた暴行、脅迫により、一時的な精神的苦痛やストレスを感じたという程度に留まらず、いわゆる再体験病状、回避、精神的麻痺症状及び過覚醒症状といった医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現していることなどから精神疾患の一種である外傷後ストレス障害(以下「PTSD」)の発症が認められる」こと、つまり、「精神的機能の障害を惹起した場合も刑法にいう傷害にあたるとするのが相当である。」との判断を示したことです(令和4年(2022年)10月現在)。
続けて、平成25年(2013年)2月27日、広島高等裁判所岡山支部は、平成15年の強制わいせつ致傷事件の被害者が事件後に発症した「パニック障害」が刑法の傷害にあたるかについて、伝田喜久裁判長は「パニック障害も傷害にあたる」と判断した1審の岡山地方裁判所の判決を支持し、控訴を棄却しています。
以上のことから、『傷害罪(刑法204条)』は、暴力行為が原因で、PTSD、うつ病、適応障害、不安障害(パニック障害)を発症した(傷害を負った)ときにも適用できるようになりました。
民事事件と違い厳格な暴力行為とPTSDの発症の因果関係を立証しなければならない刑事事件では、起訴に持ち込むことは難しいと思われがちですが、令和3年(2021年)7月には、「部下の女性職員にパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント行為を続け、PTSDを発症させた」として、男性職員を傷害と暴行の疑いで書類送検しています。
この事件は、「被害女性と加害男性がともに勤務する職場などで、女性が、上司の男性に手や腕をつかまれたり、複数回にわたり「デートしよう」、「水着の写真を送れ」といったメッセージを送られたり、帰り道にストーキングをされたりしてPTSDを発症した」というもので、加害男性は、勤務先で減給の他、課長から係長へ降格する処分を下されています。
さらに、平成17年(2005年)7月、神奈川県厚木市で高校1年生(当時16歳)の女性に加えた性的暴行事件では、その性的暴行によりPTSDを負わせたことを根拠に、『強姦致傷罪(刑法181条2項)』の公訴時効(15年)成立直前の平成31年(2019年)1月に起訴に持ち込みました。
そして、令和3年(2021年)7月、横浜地方裁判所小田原支部(佐脇有紀裁判長)は、この性的暴行事件の被告(43歳)に対し、懲役8年の判決を下しました。
この裁判では、争点となった「事件から14年後に診断のPTSDが事件で負った傷害」と認め、実刑判決を下しました。
『強姦罪(刑法177条)』の公訴時効は10年なので、先の性的暴行によりPTSDを発症した(加療を要する傷害を負った)ことを以って『傷害罪(刑法204条)』を適用できることが、「強姦罪の公訴時効10年+傷害罪の公訴時効5年(強姦致傷罪)」として、時効前に起訴することができ、それを裁判所が認定したわけです。
こうした暴力被害で発症したPTSD、うつ病などの診断時期の解釈で、「20年の公訴時効に風穴を開ける画期的な判決」がありました。
それは、近親者(おじ)による性的虐待被害を受けた被害女性(提訴時30歳代)がPTSD、離人症性障害、うつ病などを発症し、最後の性的虐待被害を受けた小学校4年生の夏休みから20年以上を経過した平成23年(2011年)4月、30歳代(提訴当時)の女性が、おじに約4,170万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、平成26年(2014年)9月25日、札幌高等裁判所の岡本岳裁判長は、「30年前の性的虐待の損害を認定」し、加害者に対して治療費(性的虐待行為により被った過去及び将来10年間の治療関連費)919万余円、慰謝料2,000万円他の支払いを命じたものです*-27。
2審の札幌高等裁判所の判決では、精神科医の尋問を踏まえ、原告(被害女性)は被告(おじ)から性的虐待行為を受けたことにより、昭和58年(1983年)ころ、PTSD及び離人症性障害、高校在学中に摂食障害を発症し、平成18年(2006年)9月ころ、うつ病を発症した」ことを認定しました。
一方で、PTSD及び離人症性障害、摂食障害を発症したことを理由にした損害賠償請求権は、被害女性(原告)が訴訟をおこした平成23年(2011年)4月には除斥期間が経過していましたが、「平成18年9月ころに発症したうつ病は、PTSD及び離人症性障害、摂食障害にもとづく損害とは質的にまったく異なるものである。また、うつ病の損害は、性的虐待行為が終了してから相当期間が経過した後に発生したものと認められるとして、除斥期間の起算点は、損害の発生したとき、つまり、うつ病が発症した平成18年9月ころというべきだ」と解釈しました。
「PTSDは昭和58年ころに発症しており、20年が経過しているが、うつ病は平成18年に発症したもので、20年は経過していない。そして、そのうつ病の発症の原因は性的虐待にあったことを本人が知ったのは平成23年2月であり、訴訟を起こした平成23年4月の時点で3年も経過していない。したがって、時効・除斥期間は成立しない。」との考えを示し、被害女性の損害賠償請求を認めました。
そして、「控訴人(被害女性)が、被控訴人(加害者の叔父)から本件性的虐待行為を受けたことで、極めて重大、深刻な精神的苦痛を受けたことは、当該行為を受けてから、子供時代、就職、進学、結婚といったライフステージを通じて、…生活上の支障、心身の不調に悩まされたほか、妊娠、出産、育児に対する不安感、恐怖感を感じていたことから容易に想定できる。また,控訴人(被害女性)は、本件性的虐待行為を受けた後、…生活上の支障、心身の不調に悩まされながらも、…やりがいを持って働いていたが、うつ病を発症したことにより、…勤務だけでなく、身の回りのこともできなくなったものである。…現時点では症状が軽快したものの、辛うじて日常生活が営める状態になった程度にとどまるものであり、発症から約8年が経過しても、いまだ相当期間の治療を余儀なくされる状況で、寛解の見通しも立っていない。このような事情のほか、本件性的虐待行為の内容、期間及び頻度、平成23年3月17日における話合い以降現在に至るまで何ら謝罪の姿勢を示していない被控訴人(加害者の叔父)の対応など、本件訴訟で現れた事情を総合考慮すると、控訴人(被害女性)の精神的苦痛を慰謝するための慰謝料は、2000万円とするのが相当である。」と損害賠償額の根拠を示しています。
こうした判例に示されたように、暴力行為により加療を要するPTSD、うつ病、適応障害、不安障害(パニック障害)などを発症したときには、適切に『傷害罪(刑法204条)』を適用・起訴し、実刑判決を下したり、「精神的苦痛を被った」ことに対する損害賠償請求が認められたりする事例が増えることを強く希望します。
そして、加害者の逮捕・起訴は、直接、被害者との関係を断ち切ることにはなりませんが、そのきっかけにはなります。
こうした判決の理解は、交際相手や配偶者からのDV行為により「加療を要する障害を負った」とするPTSD、うつ病の発症に対する刑事事件、民事事件のあり方につながります。
DV事件における刑事事件化とは、①被害者自らが、DV被害を警察に届けたり、②近隣住民が、DV被害を警察に通報したり、③DV被害で負った傷害(骨折や裂傷、打撲などのケガ)の治療で訪れた病院が、警察に通報したりして、警察が、加害者に事情招集(逮捕後の捜査を含む)をしたうえで、被害状況を鑑み、加害者に事情聴取を実施、拘束・逮捕し、起訴に至ることです。
つまり、DV行為が、『刑法(主に、暴行罪、傷害罪)』に該当するとき、刑事事件として、捜査や逮捕の対象となり、罰金や懲役などの処分(刑罰)が必要と判断されたときには、『刑事訴訟法』に則り、起訴の手続きがとられ、その後、裁判が実施されます。
加害者の逮捕、起訴(刑事事件化)には、性暴力事件で被害者が躊躇う理由とは違う特有の被害者心理(心の問題)が働きます。
それは、好きになり交際に至り、生活をともにしたり、結婚したりした人が、または、子どもの親である人が、逮捕され、『傷害罪』で起訴され、実刑判決(罰金刑を含む)を受け、犯罪者となる(前科がつく)ことを躊躇したり、望まなかったりすることです。
また、猶予のつかない懲役刑が下されたとしても、刑期を終え、出所したときに、仕返しにくるかも知れない、子どもをとり戻し(連れ去り)にくるかも知れないとの怖れから、敢えて、事件化を望まない被害者も少なくありません。
一方で、加害者にとっては、「加療を要する傷害を負わせても、逮捕されない、起訴されない」ことは、示談や証拠不十分で不起訴とされた性暴力加害者と同様に、ひとつの成功体験となります。
その成功体験は、“うまみ”です。
ひとりの女性に執着しないタイプの加害者が、こうした成功体験として“うまみ”を得ると、新たな交際相手や配偶者に対し、再び、加療を要する傷害を負わせるような暴力行為に及ぶことは少なくない、それも、ひとつの現実です。
*-27この札幌高等裁判所が下した画期的な判決については、「Ⅱ-19-(3)性暴力被害と解離性障害」の中でとりあげている「判例4*4(事件研究36)*5」で説明しています。
第5は、平成12年(2000年)に施行された『ストーカー行為等の規制に関する法律(ストーカー規制法)』は、いまから11年前の平成23年(2011年)に逗子市でおきた離婚後の凄惨なストーカー殺害事件*-28をきっかけに、同25年(2013年)7月23日の「一部法改正」で、「電子メールを送信する行為の規制」が加わったことです(令和4年(2022年)10月現在)*-29。
この改正では、対象がTwitterやLINEといったSNS、ブログのコメント欄への執拗な書き込みなど、インターネット上でのつきまといを規制対象にし、加えて、緊急の必要がある場合に警察が警告なく禁止命令を発令できるようになりました。
さらに、令和3年(2021年)5月26日の「一部法改正(同年6月15日施行)」で、「住居、勤務先、学校など通常いる場所に加え、あなたが、実際にいる場所の付近において見張る、押し掛ける、みだりにうろつく行為」「電話、FAX、電子メール、SNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為」が規制対象となり、同年8月26日以降、「GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等」が規制対象となり、「禁止命令等に係る書類の送達に関する規定が整備され、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、都道府県公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる」ようになりました。
ちなみに、以下の8類型のつきまとい行為(ストーキング)を連続して同じ人に行う人のことを「ストーカー」といいます。
① つきまとい・待ち伏せ・押しかけ、うろつき
尾行する、通勤ルートなどで待ち伏せする、自宅や職場などで見張りをしたり、うろついたりする、一方的に押しかけたりするなど、
② 「監視している」と本人に告げる行為
「何月何日にこういう行動をしていた」、「この人と会っていたね」などと告げて、相手の行動を監視していたことに気づかせたり、帰宅後に「おかえりなさい」と連絡したりするなど
③面会・交際の要求
嫌がっているのに「会ってほしい」と執拗に繰り返す、断っているのに復縁や交際を求める、断っているのに贈り物などを送るなど
④著しく粗野、または乱暴な言動
ドアを激しく叩いて家の中に入れるように迫る、「復縁しないなら殺す」などと相手に危害を加えるような言動を浴びせるなど
⑤ 無言電話や連続した電話・文書の送付・Fax、電子メール、SNSなどによる連絡
無言電話などを何度もかけて不安にさせる、会社、自宅などに電話を何度もかける、メールやSNSで連続的にメッセージを送るなど
⑥ 名誉を傷つけるような内容を他人に広める
汚物や動物の死骸などを送付する、人前やオンライン、文書などで相手を中傷するなど
⑦ 相手が嫌がっているのにわいせつな動画や写真などを送りつける
⑧ 電話で卑猥なことばを投げかけ、性的に羞恥心を呼び起こさせる行為
加えて、平成13年(2001年)に施行された『配偶者からの暴力の防止及びに被害者の保護に関する法律(配偶者暴力防止法)』は、その3年後の平成16年(2004年)の改正で、「被害者の子どもの保護」、「精神的暴力(ことばの暴力など)」が加わりました。
さらに、同26年(2014年)には、改正新法として、「保護」が「保護等」になり、「同じ所載地で居住するも者(同棲生活をしている者)で、元を含む」と対象が広がりました。
この改正新法により、「一定の条件はあるものの交際相手(元を含む)が、一時保護の決定、保護命令の発令の対象者」となり、『ストーカー規制法』で対応できない一時保護の決定が可能になりました。
DV行為(デートDVを含む)のある関係性下で別れ話や別居がきっかけとなり、復縁話を求める行為がエスカレートし、執拗につきまとう(ストーキング)は、“一連のDV行為”と認識し、的確に対応する必要があります。
「一連のDV行為」とは、『配偶暴力防止法』に規定される「身体的暴力」「性的暴力」「精神的暴力(ことばの暴力/社会的隔離/子どもを利用した精神的暴力を含む)」「経済的暴力」の4つに加え、「ストーキング(つきまとい)」を“第5のDV行為”とする考え方です。
しかし、メディアだけでなく、対応の遅れなどが問題視されることが少なくない警察を含めて、ストーカー事件では、上記の“第5のDV行為”としてのストーキングと、アイドルや歌手、俳優、スポーツ選手に対する一方的な恋愛感情、そして、報われない怒りを起因とするストーキングを一色単に捉えた情報を発信しています。
このことは、大きな問題です。
なぜなら、対応のあり方は、「似通って異なるもの」だからです。
夫婦間に子どもが生まれ、その後、離婚したときの元配偶者によるストーキングでは、相談し、対応する警察署の警察官は「元配偶者と合わない(接触しない)ように」と助言します。
しかし、その警察官は、離婚という民事事件、特に、親権、監護権者、面会交流の実施に伴うとり決め(とり決めされた面会交流の実施を拒むなどの行為に対し、家庭裁判所への申立てにより、応じなければ罰金を科すとする「間接強制」を発令されるなど)に関する民事事件に関する知識が乏しかったり、仕事を辞め、身を隠して(居所を知られずに)アパートを借りるなど、生活を再建するときに利用する「生活保護制度」に詳しくなかったりします。
そのため、警察官では、被害者が抱える八方塞がり的な苦悩に思いを寄せることができず、凄惨な事態を招いてしまうこともあります。
元交際相手や元配偶者に対して復縁を求めるストーキングの一部が殺害に至ってしまうリスク、そして、デジタルタトーと呼ばれるリベンジポルノとしてネットに晒され一生つきまとう知っている人に見られるかも知れない恐怖ついては、『ストーカー規制法』の強化、そして、『私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ被害防止法)』だけでは払拭できないのが現実です。
暴力で支配する関係性、つまり、DV行為のある関係性で、もっとも危険で、凄惨なDV行為が生じる瞬間のひとつは、別れ話(離婚話)を切りだしたときです。
もうひとつは、黙って家をでたものの居場所を特定され、連れ戻しにきたときです。
このとき、リスクが高いのが苛烈な身体的暴力とレイプ(性的暴力)です。
「Ⅰ-A-2.加害者属性による判断。暴力の後遺症によるDV-加害トラウマ。世代を超えてひきつがれる暴力-」、「Ⅰ-A-3.第5のDV行為。別れ話が発端となるストーキング(つきまとい)」、「Ⅲ-28.『加害者更生プログラム』の受講効果の真意」で詳述しているように、『配偶者暴力防止法』、『ストーカー規制法』などの法律があっても、自身(子どもを含む)の身(命)を守るために、その法を適応し得るのか、あるいは、その法は有効なのかを判断する(リスク分析をして行動を選択する)には、DV行為だけでなく、加害者1人ひとりの特性を知ることが不可欠です。
あらゆる暴力行為について、正しく理解するうえで重要なことは、その“関係性”に着目することです。
自分と他の人という“関係性”です。
「他の人」には、父、母、きょうだい、親族、配偶者、交際相手、友人、知人、同僚、上司、取引先の担当者、教師などが該当します。
例えば、性交を伴うレイプの74.4%は、顔見知り、つまり、よく知っている人による犯行です。
よく知っている人の「内訳」は、父母・祖父母・叔父叔母・いとこが11.9%、配偶者・元配偶者が9.9%、そして、友人や知人(学校の教職員、先輩、同級生、クラブやサ-クル指導者や仲間、職場の上司や先輩、同僚、取引先の関係者)が53.1%です。
この“関係性”の理解は、どのような行為がDV(デートDV)に該当するのか、どのような行為が児童虐待に該当するのか、どのような行為が(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントに該当するのかを知ることよりも重要な意味を持ちます。
なぜなら、これらの“関係性”には、上下の関係性、支配と従属の関係性が成り立ちやすいからです。
この「上に立とう(支配しよう)とする者」と「下におかれる(支配され、従属させられる)者」という“関係性”で加えられる暴力行為の典型が、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力行為です。
つまり、上下の関係性、支配と従属の関係性を成り立たせたり、支配したりするため(目的)の“手段”が、「・・に該当する行為」ということになります。
「・・」に入ることばは、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどです。
ただし、DV(デートDV)といじめ以外の暴力行為の関係性には、大きな違いがあります。
それは、“関係性”のスタート(開始)です。
親と子どもの間、上司と部下の間、取引先と担当者、教師と生徒との間の関係性は、その関係性のスタートとともに、既に、立ち位置として、あるいは、敬う存在として、上下の関係性が成り立っています。
しかし、DV(デートDV)においては、交際相手との間、配偶者との間の関係性のスタートは、(本人の意識の問題は別として、)“対等”な関係ではじまります。
「本人の意識の問題は別」と( )づけで記述したのは、被害を受ける女性が、“保守的”な価値観として「家父長制」「男尊女卑」「内助の功」「良妻賢母」という“概念(価値観)”を受け入れているときには、関係性のスタートから“対等”ではないケースとなります。
人権教育を受けていない日本では、「彼の女性を見下すことは気になるけれど、彼のことが好きだから。」と問題から目を逸らし、見て見ぬふりをすることが少なくありません。
しかし、その瞬間(当事者は無意識ですが)、その女性は、「彼の女性を見下すことばやふるまい」を受け入れた(容認した)ことを意味し、両者の間には、暗黙裡に上下の関係性が成立します。
交際をはじめた男女、結婚をした男女が、ともに、「家父長制」「男尊女卑」「内助の功」「良妻賢母」といった“保守的”な価値観に対し疑問を覚えず、DV行為としての暴力がなければ、2人の関係性は上手くいく可能性があります(ただし、この関係性に子どもが生まれたときには、この“保守的”な価値観にもとづく厳しいしつけ、しつけ(教育)と称する体罰を加えるなど、虐待リスクはあります)。
しかし、交際をはじめた男女、結婚をした男女の一方が、こうした“保守的”な価値観(概念)に対して、疑問を感じ、受け入れたくないと行動を起こした(ことばにしたり、態度に示したりする)とき、問題(トラブル)が生じることになります。
その多くは、“対等”の関係性を求めることばやふるまいを破壊する行為として表れます。
つまり、“対等”の関係性を求めることばやふるまいを破壊する暴力が、最初のDV行為になります。
この交際相手や配偶者が、これまで身につけてきたものごとの捉え方や考え方、価値観、モノサシ(判断基準)、行動パターンなどを「破壊」し、新たな「ものごとの捉え方や考え方、価値観、モノサシ(判断基準)、行動パターンなどを「教え込む(わからせる)」行為が、DV行為の本質でが、この「これまでを破壊」し、「新たに教え込む」行為は、新興宗教やカルトの勧誘などで実施するマインドコントロールの手法そのものです*-30。
この「交際相手や配偶者の“これまで”を破壊する行為」が、身体的暴力であったり、性的暴力であったり、精神的暴力であったり、経済的暴力であったり、交際のきっかけとなる偶然を装う出会いを演出するストーキングであったりするわけです。
特に、人権教育を受けず、性的同意、避妊などを学ばず、交際相手や配偶者に求められたら嫌でも(気乗りしなても)応じなければならないと認識している多くの日本の女性は、このときの「性行為」を「DV行為としての性的暴力」、つまり、DV被害と認識できないことが少なくありません(同じ構図は、上司や仕事関係者との性行為(セクシャルハラスメント)にも認められます)。
しかし、DV被害と認識できていないけれども、彼と過ごす週末になると気が重たくなったり、頭痛や腹痛が起きたりするなど身体的な不調として、性行為(性的暴力)に対する拒否反応が表れていることが少なくありません。
そして、この俺とお前は「対等の立場ではない」ことを思い知らせるDV行為としての暴力は、「しつけ直しとして」「罰(こらしめ)を与えるため」と正当な行為との認識の下で実行に移されます。
第1で、子どものとき、両親間のDV行為を見たり、聞いたり、察したりする(面前DV=心理的虐待)だけではなく、親から身体的虐待やことばの暴力(心理的虐待)を受けて育つと、第1で記しているとおり、『脳の傷の影響で、a)他人の表情を読めず、対人関係がうまくいかなくなり、b)集中力が欠け、自分で決めたり、共感したりでき難くなり、c)感情や理性、思考をコントロールし難くなり、d)痛みに対して鈍感になり、聞こえ方、会話やコミュニケーションがうまくできなくなり、その結果として、自己規定・自己規範となる価値観に認知の歪み(間違った考え方の癖)を生じさせるリスクが高くなる』ことを説明しています。
この「俺とお前は、対等の立場ではない」という“自己規定(自分は何者であるのか)”、「思い知らせる」「しつけ直す」「罰を与える」という“自己規範”は、暴力のある家庭環境で暮らし、育つ中で身につけたものです。
「自己規範」とは、その人のモノサシ(判断基準)となる自己の価値を価値のあるもとの自身で認めることです。
この“これまで”の破壊を目論む最初のDV行為を受けた者(被害者)が、直ちに、その関係性を終わらせる(別れる)ことができないと、一方の加害行為に及んだ者(加害者)は、パワー(力)を行使し、成り立たせようと目論み、なし得た上下の関係性、支配と従属の関係性を維持しなければならなくなります。
その対象者が、対等の関係に戻そうとすることばを吐いたり、態度を示したりしたときには、自身にとって、その行為は脅威、恐怖となることから、より激しい破壊行為が必要になります。
この「はじめに。」の最初に、被虐待体験をしてきた人の一定数は、『 虐待を受けた(暴力のある家庭で暮らし、育った)人は、攻撃性と関係のある「MOMA遺伝子」の“スイッチ”を入れることなど、遺伝子レベルでひき継がれることがわかってきました。 』、『 この子どもが虐待を受けたトラウマ(心的外傷)は、思考・行動習慣に影響を及ぼすだけでなく、「分子の傷跡」として、子どものDNAに刻み込まれるということです。 』と、「MOMA遺伝子」の活性化について説明しているように、暴力がなく安全で、リラックスできる家庭環境で暮らし、育った人と比べて、攻撃的になりやすくなります。
暴力のある家庭環境で暮らし、育つ状況は、日々に抱く強い不安、脅威、恐怖が、攻撃性と関係のある「MOMA遺伝子」の“スイッチ”となります。
DVの本質は、「本来、対等であるはずの交際者間、夫婦間の関係性に、上下の関係、支配と従属の関係を持ち込み、成り立たせ、維持するためにパワー(力)を行使すること」です。
そして、暴力のある家庭で暮らし、育ったことで身につけた“自己規定”と“自己規範”にもとづき、「お前とは、対等な関係ではない」、「お前とは、同じ立場ではない」ことを思い知らせる暴力行為が、DVです。
思い知らせる行為は、自分と他者が対等であること、同じ立場であること、自分より優秀であること、自分のもとを離れることに対して過敏で、“不安”“脅威”“恐怖”を覚える者が、その不安、脅威、恐怖を、自分から排除する行為といえます。
この構図は、DV加害者だけではなく、差別・排除、児童虐待、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力行為に及ぶ加害者すべてにあてはまります。
加害行為に及ぶ者の背景を知るうえで、「Ⅰ-A-2.加害者属性による判断。暴力の後遺症によるDV-加害トラウマ。世代を超えてひきつがれる暴力-」でとりあげる「加害トラウマ」の視点と先の遺伝子学的の「MOMA遺伝子」の視点は、必要不可欠です。
この加害者が、「不安・脅威・恐怖を覚える」は、「男(親/上司/教師)として、威厳を示さなければ(思い知らせなければ)ならない強迫観念」、「親(上司/教師)として、失格の烙印を押される強迫観念」などと置き換えることができます。
この「強迫観念」は、暴力のある家庭環境で暮らし、育つ中で身につけた“自己防衛機能”といえます。
安全な暴力のない家庭環境で暮らし、育った人にも、当然、“自己防衛機能”は備わっていますが、その違いは、その不安・脅威・恐怖を覚えた人から離れる(距離を置く)のではなく、その関係性に執着(固執)することです。
つまり、「見捨てられ不安」を抱える被虐待体験をしてきた人に見られる特性ということです。
いうまでもなく、「自らの立場が脅かされる」という不安・脅威・恐怖は、強烈なストレスを及ぼします。
その強烈なストレス(危機)は、生物としての生存本能として、不安、脅威、恐怖を排除するか、回避するかの選択を迫るものです。
その排除・破壊行為に及んだ者(加害者)は、自身の暴力行為を正当化するための理由について、同じ表現(ことば)を使います。
それは、「悪いことをした」から、「態度が悪かった」から、「やれということをしなかった(できなかった)」から、「同じ失敗を繰り返した」から、「いうことをきかなかった」から、「指示通りのことができなかった」から、「期待した成果をあげられなかった」から、「気分を害する(怒らせる)ことをした」からという表現で、「しつけ」「教育」「指導」と称して、立場をわからせる“罰”を与えます。
こうした決まり文句(常套句)は、暴力のある家庭で暮らし、育つ中で、身を持って体験して学んだ「自己規定」「自己規範」です。
立場をわからせる“罰”を与える人物の“認知”は、「自分は、あなたに“罰”を与えられるだけの絶対的(特別)な存在である」と自称する人物から「被虐待体験」として学び、身につけたものです。
絶対的(特別)な存在から学び、見つけた“認知”にもとづき、「自分も、それだけの(威厳のある)人物であることを態度で示さなければならない」と強迫観念的な思いにつき動され、自らの正しさを示すために“罰”としての暴力を与えます。
その思いが強くなると、絶対的な忠誠心を求めます。
問題は、被虐待体験による見捨てられ不安を抱え、自尊感情(自己肯定感)が低い人ほど、不安、脅威、恐怖を覚えやすく、被虐待体験で学び、見つけた自己規定と自己規範にもとづき、負けない強さ(男らしさ)を示さなければならない(わからせなけれんばならない)強迫観念的な承認欲求が、暴力行為につながっていることです。
すべての欲求を凌駕する承認欲求に囚われてしまうと、もはや自分の意志ではコントロールは不可能です。
カラカラに乾いたスポンジのような渇望感、心の中にぽっかりと空いた大きな穴のような空虚感、底なし沼のような寂しさを“埋める”ことができる、つまり、承認欲求を満たすのが、人が自分を怖れ、ひれ伏すように恐怖を与える暴力行為、人を自分に意をとなえず、従順に意に添うようにしつけ(教育)直す暴力行為、人が自分に逆らったり、指示(期待)通りにできなかったときに罰(こらしめ)を与える暴力行為です。
自分の立場をわからせたい相手に、自分の立場をわからせる(認めさせる)ことで、渇望感、空虚感、寂しさを満たす、つまり、承認欲求を満たすことができます。
この瞬間、はじめて、自分(心の安定)を保つことができます。
この瞬間は、自分の存在意義を感じられる、なにごとにも代えられない至福のときです。
自分が絶対的な存在と感じ、高揚感を覚える(快感中枢が反応する)のは、自分を怖れている相手の姿や表情を見て(視覚)、声を聞いて(聴覚)、からだで感じている(触覚/臭覚/味覚)ときです。
問題は、高揚感を味わえる強烈な刺激となる暴力行為(うまみ)に、脳の“快楽中枢”が反応することです。
暴力行為による強烈な刺激(高揚感)を覚えた脳の“快楽中枢”は、再び(繰り返し)、高揚感を得るために暴力行為を求めます。
なにか不安になることがあったり、脅威・恐怖を覚えたりしたとき、その不安・脅威・恐怖を払拭し、心の安定(均衡)を求めて、もう一度、あのときに怯えた姿や表情を見たり、声を聞いたり、からだで感じたりしたい衝動(欲求)に駆られます。
つまり、脳の“快楽中枢”が強烈な刺激を得られる暴力行為は、中毒化(慢性反復化)しやすいという特性があります。
差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの中毒化しやすい暴力行為の代替となるのは、ア)ケンカとしての暴行、略奪の暴力行為であったり、イ)危険な運転行為、窃盗(万引き)などスリルを満たしたり、ウ)レイプ、痴漢、盗撮、のぞき、体液をかけるなどの支配欲を満たしたりする性的な行為(性暴力)であったり、エ)薬物(白砂糖、ニコチン、カフェインを含む)、アルコール、ギャンブル、セックス、仕事、買い物、過食(炭水化物の大量摂取によるブドウ糖)であったり、オ)リストカットやOD(大量服薬)、過食嘔吐などの自傷行為であったりします。
これらの行為に走らせる衝動的な欲求に襲われるのは、不安、脅威、恐怖を覚えたとき、渇望感、空虚感、不安を払拭したいとき、つまり、自分の立場が脅かされる危険(ストレス)を感じたときです。
日常生活で生じるさまざまな心理的苦痛、否定的感情に遭遇したとき、つまり、脅威を覚え、危機(ストレス)にさらされたとき、満たされてこなかった承認欲求、傷ついた自尊感情、劣等感、孤独感が反応し、一時でもその苦痛を紛らわしてくれる行為に心の安定を求め、そして、溺れるようになります。
溺れる状態は、一時、苦痛を紛らわしてくれる行為による刺激に対し、脳の快感中枢が反応し、高揚感を覚え、再度、その刺激を求めるようになる、つまり、依存・中毒化している状態のことです。
つまり、「依存」とは、生き難さに対する自己治療的な対処行動あり、その人が生き延びるための手段といえます。
問題は、人(の脳)は、脅威を覚え、危機にさらされたときに、心の安定(均衡)をとり戻すために、a)差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなど暴力行為とb)ア)-オ)の行為に加え、c)親、きょうだいなどの親近者、友人、交際相手、配偶者などの中で、安心とリラックスをもたらしてくれる人に抱きしめて(守って)もらったり、d)そこ(その状態)から逃げたりすること以外、脅威・危機にさらされたときの対処方法(ストレス・コーピング)を持っていないことです。
アタッチメントに問題があり、「見捨てられ不安」を抱える被虐待体験者にとって、交際相手や配偶者が、自分に別れを告げたり、自分のことから逃げたりするふるまいこそが、自分の立場がもっとも脅かされる瞬間です。
被害者が、「見捨てられ不安」を抱えていると、DV行為としての暴力で支配されていても、その特徴が固執(執着)であることから、その関係を断ち切ることは容易ではなく、一方の加害者が、「見捨てられ不安」を抱えていると、同じくその特徴は固執(執着)であることから、被害者が暴力行為に支配された関係を断ち切ろうとすることを決して許さず、「復縁を求める」ために、常軌を逸したストーキングに及ぶことがあります。
被虐待体験により、好きか嫌いか、白か黒か、生か死かなど、極端な“二元論(二者択一)”でものごとを捉え、考え、判断する人は、「裏切り者には、罰を与える(死で報いろ)」、あるいは、特殊な信仰観を持ち込み、「一緒に死んで、永遠に魂で結ばれる」との考えに執拗に囚われ、死に至らす行為に及ぶことがあります。
「Ⅰ-A-3.第5のDV行為。別れ話が発端となるストーキング(つきまとい)」、「Ⅲ-28.『加害者更生プログラム』の受講効果の真意」で詳述していますが、ストーキング・DV対策で、なにより優先しなければならないのは、被害者である女性の身(命)の安全、子どもの身(命)の安全を守ることです。
このことは、DV問題には、「被害者は、すべてを捨ててでも、加害者(交際相手や配偶者)の暴力から自分の命(身)を守るという選択をしなければならない」という重い決断が存在することを意味します。
DV被害者が、加害者である交際相手や配偶者による上下、支配と従属関係を断ち切るには、主に、2つの方法があります。
ひとつは、加害者である交際相手や配偶者と「別れる(逃げる)」ことです。
このストーキング・DV特有の問題は、被害者は、「どこに逃げるか」、「別れたあとどこに住むか(どこで生活するか)」です。
被害者が、加害者である交際相手や配偶者に逃げた居場所、新たに生活をはじめた住居を特定されると、苛烈な暴力やレイプを加えられたり、逆に、泣いて謝られたりして連れ戻され、再び、慢性反復的(常態的、日常的)に暴力を加えられるリスクがあります。
加害者である交際相手や配偶者が、直ぐに訪問したり、待ち伏せしたりする、つまり、ストーキングに及ぶリスクが高いのは、被害者の父母が暮らす家(実家)、きょうだい、親戚、友人の家に加え、被害者の勤務先、通学している学校、子どもが通っている学校園、塾、習いごとの教室やスポーツ施設、スーパーなどの商業施設、利用していた理容室や飲食店などです。
そのため、被害者が、加害者である交際相手や配偶者から逃げ、連れ戻されたり、見つけだされたりしないためには、父母、きょうだい、親戚、友人との連絡を断つ必要があったり、仕事や学校、塾、習いごとなどを辞めたり、勤務先を替えたり(転職、退職し、新たに就職)、通学している学校を転校したり、退学したりしなければならないときがあります。
加害者である交際相手や配偶者が見つけ難いのは、資金的に余裕があれば、一端、少し離れた土地(他の都道府県)のホテルなどに宿泊し、アパートなどの賃貸契約を結び、新たな生活をはじめることです。
それは、大きな決断を伴います。
連れ戻される危険を避けるには、女性センターへのDV相談を介し福祉事務所とつながっておき、『配偶者暴力防止法』に準じ、一時保護の決定を受け、「母子生活支援施設(母子棟、行政のシェルター)」などの入居することです。
警察経由ではなく、女性センター、福祉事務所とつながっておくことで、「母子生活支援施設」に入居する前に、職員同行で所轄警察署に立ち寄り「捜索願の不受理届」を提出します*-31。
これは、警察が、加害者である交際相手や配偶者に代わり、被害者を見つけ(探し)だす役割を担うことを避けるためです。
提出する「理由」は、「交際相手や配偶者からのDV被害で、母子生活視線施設に入居するため」となりますが、女性センター、福祉事務所の職員が同行することで、手続きがスムーズに運びます。
また、自己資金に余裕がないときには、福祉事務所の職員が、入居とともに、直ちに「生活保護受給」の手続きをします。
生活の破綻しない状況下で、転宅手続き(アパートなどの賃貸契約)がとられたり、優先的に公共住宅への入居の手続きをしてもらえたり、医療機関の受診で「保険証」を使うリスクがある(理由は下記のカ))ので、福祉事務所発行の「医療券」で無料で受診できたり、「住民基本台帳事務における支援措置」、「社会保険」や「年金」など変更手続きにおける住居の非表示(黒塗り)などさまざまの行政手続きのサポートを受けることができます。
とはいっても、DV被害者の新たな生活では、ア)仕事を辞めて転職したり、イ)子どもが転校したり、退学したり、ウ)親やきょうだい、友人、同僚との連絡ができ難くなったり、エ)いま使用している携帯電話を使えなかったり(通話記録をもとにその相手と接触したり、GPSで場所を特定されたりするリスクがある)、オ)安易にSNSに投稿(特に写真)できなくなったり(近隣地区、学校などを特定されるリスクがある)、カ)健康保険証を使えなくなったり(保険者から受診記録が通知され、どこの医療機関を利用したのか特定されるリスクがある)するなど、さまざまな“制限”のある不便な生活を強いられます。
日本では、平成13年(2001年)、女性センターや所轄警察署が、被害者の「一時保護」を決定したり、地方裁判所が、被害者の申立てにより接近禁止を含む「保護命令」を発令したりできるように『配偶者暴力防止法』を制定しました。
しかし、『配偶者暴力防止法』制定の前年、平成12年(2000年)に制定された『ストーカー規制法』を含めても、DV加害者である交際相手や配偶者からDV被害者の命(身)を完全に守ることはできないのが現実です。
それだけ、DV行為に及ぶ加害者である交際相手や配偶者は、時に、「復縁(「別れを納得できず、理由を知りたいので話したい」を含む)」を求めて、執拗なストーキングを繰り返して被害者を殺害したり、性行為などを撮影したりした写真や映像をSNSなどに投稿(リベンジポルノ)したりするなどの常軌を逸した行動を伴うことがあります。
もうひとつは、DV/ストーキングの加害者が「暴力行為で逮捕・起訴される」こと、つまり、交際相手や配偶者からのDV/ストーキング行為が、刑事事件として「事件化(起訴)」することです。
交際相手や配偶者に対する「DV行為としての身体的暴力」に対して“適用”できる『刑法』は、「暴行罪(同208条)」、「傷害罪(同204条)」、「殺人罪(同199条)」、「殺人未遂罪(同203条)」、同「性的暴力」に対しては、「強制性交等罪(同177条)」、「強制性交等致傷罪(同181条2項)」、「強制わいせつ罪(同177条)」、「強制わいせつ致傷罪(同181条1項)」、同「精神的暴力」に対しては、「脅迫罪(刑法222条)」、「強要罪(刑法223条)」、「侮辱罪(同231条)」、「暴行罪(同208条)」などです。
同「経済的暴力」に対する「窃盗罪(同235条)」、「横領罪(同252条1項)」、「不動産侵奪罪(同235条2項)」は、配偶者(以下の①)には適用できません。
「親族間の犯罪に関する特例(親族相盗例)(同244条1項)」があり、その適用範囲は、①配偶者、②直系血族、③同居の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)です。
したがって、上記②③にあてはまらない交際相手(元を含む)には、「窃盗罪(同235条)」、「横領罪(同252条1項)」、「不動産侵奪罪(同235条2項)」を適用できます。
夫婦の関係下での「強制性交等罪(刑法177条)」の適用については、いまから36年前、昭和61年(1986年)12月17日、鳥取地方裁判所は、「婚姻関係が破綻している場合、夫婦間でも婦女暴行は成立する。」と懲役2年10月の有罪判決を下し、同62年(1987年)6月18日、広島高等裁判所松江支部の控訴審は控訴を棄却し、刑が確定しています(令和4年(2022年)10月現在)。
これらのDV行為としての暴力は、「民法709条」のDV加害者の不法行為であることから、民事訴訟、あるいは、「婚姻破綻の原因は、配偶者からのDV行為である」として申立てた夫婦関係調整(離婚)調停において、損害賠償金(慰謝料)、逸失利益を求めることができます。
加えて、そのDV行為としての暴力による後遺症として、「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」、「その併発症としてのうつ病」、「パニック障害」などを発症しているときには、その後遺症に対し別途「傷害罪(同204条)」が適用できます。
これは、いまから28年前の平成6年(1994年)1月18日、名古屋地方裁判所は、「傷害について、人の生理的機能を害することを含み、生理的機能とは精神的機能を含む身体の機能的すべてをいうとし、医学上承認された病名にあたる精神的症状を生じさせることは傷害に該当する。」との判断を示したことにもとづきます(令和4年(2022年)10月現在)。
以降、暴力被害でPTSDなどの精神疾患を発症し、加療を要するケースでは『傷害罪』が適用され、賠償、逸失利益を認め、慰謝料の支払いを命じています。
また、このときの公訴時効の“起算点”は、「加療を必要とする傷害を負わせた暴力行為」に適用される「傷害罪(同204条)」とは別となり、基本的に、その診断を受けて治療を開始した日(状況によっては、その症状を自覚したとき)となります。
法的根拠は、いまから8年前の「平成26年(2014年)9月25日、札幌高等裁判所は、幼少期におじに性的虐待を加えられた被害女性が、性的虐待被害に対し、公訴時効を経過後に損害賠償請求を求めた民事事件の控訴審で、「除斥期間の開始時期を、精神障害の発症時期と解釈する。」との判決を下し、平成27年(2015年)7月8日、最高裁判所第2小法廷が加害者の上告を退ける決定をし、確定していることです。
加えて、交際相手や配偶者(いずれも元を含む)による裸体や性行為を写した画像や動画をSNSに投稿する行為に及んだときには、『リベンジポルノ被害防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)』、『ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制に関する法律)』に“抵触”、あるいは、“違犯”する行為として、同法を適用できます。
法の適用はあるものの、リベンジポルノは、「デジタルタトゥー」と表現されるように、一度インターネットに投稿された画像や動画は、次々にコピーされ保管されたり、拡散されたりするリスクが高く、完全に消し去ることはできない、つまり、永遠に画像や動画を消し去ることができないと考えるのが現実的です。
DV(デートDV)事案では、怒られたり、不機嫌になったりすることを避けるため、仕方なく(嫌でも)、裸の写真を撮ったり、性的な行為を動画に残したりする行為に応じなければならない状況(DV行為としての性的暴力)がつくられることが一定数存在します。
この問題は、知らない間にnetに投稿されていたり、別れ話がでたときに脅される道具(切り札)にされたりすることになるなど、リベンジポルノ被害のリスクを抱えることになります。
ネット上には、許可を得ていないと思われる交際相手や配偶者との性行為などを撮影した動画や写真が無数に(想像を絶するほど多く)投稿され、閲覧できるようになっています。
無断でnetに投稿されていると思われる交際相手や配偶者の性的な写真や動画の一定数には、身体的暴力受けたと思われるうっ血痕(打撲痕)、タバコを押しつけられたと思われる傷痕のある女性が含まれています。
ここには、交際相手や配偶者を管理売春(性的搾取)としてグループセックスなどに派遣しているケースなどが含まれます。
また、未成年者のデートDVとして、被害(性的暴力のきっかけとなること含む)が多いのが「セクスティング」です。
「セスクティング」とは、sex(性的な)+ texting(メッセージのやりとり)からの造語で、スマートフォンなどを介し、性的なメッセージや画像をやりとりする行為のことです。
出会い系サイトで知り合った異性とのセスクティング、恋人同士のポジティブなコミュニケーションの中でのセクスティングは、リベンジポルノ、無許可(盗撮・隠し撮りを含む)の性的動画・写真のSNS投稿、いじめ、ハラスメントまでさまざまなリスクを伴います*-32.33。
現実問題として、知らない間に撮影(盗撮)され、知らない間にnetに投稿され、知らない間に拡散され、知らない間に不特定多数の人の眼にさらされ、そして、画像や映像が保存されています。
カナダのカルガリー大学の研究者が、18歳未満(平均年齢15.16歳(11.9-17.0歳).男性47.2%)の11万0380人に対して調査をおこない、解析結果として、「①18歳未満の男女の7人に1人(約1万5800人)が性的な画像やメッセージ「セクスティング」を送信、②4人に1人(約2万7600人)が「セクスティング」を受信し、③8人に1人(約1万3800人)が相手の同意を得ずに「セスクティング」を転送していた。」と報告しています。
同調査によるセクスティングの平均発生率は、送信が14.8%、受信が27.4%、同意なしの転送が12.0%、事前の同意なしにセクスティングを転送されたケースは8.4%となっています。
セクスティングの発生率は、年齢とともに上昇し、パソコンよりもスマートフォン利用者のセクスティング率が高いことが示されています。
問題は、人権教育を実施していない日本社会で育ち、家庭でしつけ(教育)と称する体罰などの虐待を受け、自尊感情(自己肯定感)が育まれていない多くの10歳代の若者は、男女を問わず、「性的な画像が欲しい(送れ!)」という“圧力”に抗うのは難しいということです。
なぜなら、一時の相手であっても、承認欲求を満たすために「気を惹きたい」という思い、見捨てられ不安(底なし沼のような寂しさ)からくる「嫌われたくない(別れを切りだされたくない)」という思いが強く働くからです。
しかも、悪意のある人物が、親しさを装って近づき(接触を試み)、手懐け(グルーミング)、個人情報を手に入れたあとに“脅す”ことで、接触を持った10歳代の子どもは、逃れるのが難しい状況がつくられるという問題があります。
独立行政法人・情報処理推進機構(IPA)が、13歳以上のスマートフォン利用者(男女5,000人)を対象に行ったアンケート調査では、10歳代の7.5%、20歳代の11.3%が、「恋人など親密な間柄なら、自分の性的な姿の写真や動画をSNSで共有しても構わない」と回答していますが、「一度手を離れた写真は、ネット上で独り歩きするリスクがある」と認識する必要があります。
自分の手を離れた画像は、いとも簡単にコントロールを失い、あっさり拡散するリスクがあり、一方で、安易な転送で自分が加害者になるリスクがあります。
また、SNSに投稿した写真にはGPS情報(位置情報)が残っているため、そこから居所を特定されるリスクがあります*-34。
令和4年(2022年)12月19日、東京地方裁判所で、元交際相手に対する「殺人罪(刑法199条)」で懲役9年の判決を受けた女性(6歳年上の元交際相手と高校3年生のときに交際を開始)は、元交際相手に撮影された性行為の動画を何度も削除するよう求め、応じてもらえない中で犯行に及んだものです。
「性犯罪行為などを隠し撮り(盗撮)したビデオの原本は没収できる」と最高裁判所は判断していることから、交際相手や配偶者(いずれも元を含む)による性行為などを同意なく撮影した動画をSNSなどに投稿されたり、ビデオ(動画)や写真の存在をネタに復縁を強いられたり、復縁に応じない腹いせに勤務先や親族に送り付けられたりするストーキングリスクを回避するという意味で、交際相手や配偶者との性行為などを撮影したビデオ(動画)、写真などの原本を没収したり、デジタル機器に保存されているデータを削除することは重要です。
しかし、交際相手や配偶者に撮影された性的な動画や写真の削除は、先の殺人事件のように容易ではありません。
まして、その交際相手や配偶者が、DV行為としての暴力に及んでいるときにはなおさらです。
交際相手が撮影した性的な動画は、平成12年(2000年)11月、『ストーカー行為等の規制に関する法律(ストーカー規制法)』の制定のきっかけとなった「桶川ストーカー殺人事件(平成11年(1999年)10月26日/事例113、事件研究1*)」、平成26年(2014年)11月、リベンジポルノへの罰則を盛り込んだ『リベンジポルノ被害防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)』を成立させるきっかけとなった「三鷹ストーカー殺害事件(平成25年(2013年)10月8日/事例116*6、事件研究4*7)」など、デートDV事件、ストーキング事件と深く関係し、一方で、性的な動画や写真の存在が、DV行為としての暴力に及ぶ交際相手や配偶者と別れるのを躊躇させる大きな要因となっていることは広く知られる必要があります。
高性能なカメラ機能がついた携帯電話(スマートフォンなど)、盗撮機器が普及したことにより、集団レイプ、ドラックやアルコールを使用したレイプなどの性暴力事件において、その様子を動画や写真に収めるケースも増えています。
立場を利用したセクシャルハラスメント(レイプなど)などの性暴力事件に加え、デートDVでは、その動画や写真の存在を持って、脅され、別れることを許されず、性的関係を強要されることも少なくありません。
*-28 「Ⅰ-A-3-(3)-③逗子ストーカー殺人事件(事例115*8/)事例研究3*9」で詳しく説明しています
*-29 令和3年(2021年)5月18日、「GPS(全地球測位システム)を悪用し、相手の承諾なく位置情報を把握する行為などを規制対象」に加える法案が衆院本会議で可決成立し、同年8月に施行されるようになりました。
*-30 「Ⅰ-A-4.傷めつけ、被害者を負い込むマインドコントロール術」で詳述しています。
*-31 「捜索願の不受理届け」については、「Ⅰ-B-9.一時保護の決定、保護命令の発令。「身を守る」という選択」の冒頭で触れています。
*-32 『総務省情報通信政策研究所の調査(2019年度)』の中で、10歳代の63%、20歳代の65.9%がSNSを利用していると報告しています。
SNSの平均利用時間(休日)は、いずれも80分を超え、他の世代よりも大幅に長くなっています。
90%以上が無料通信アプリ「LINE」を使い、70%が「Twitter」、60%が写真共有アプリ「インスタグラム」を利用し、動画投稿サイト「ユーチューブ」の視聴は90%を超えています。
内閣府の意識調査では、「ほっとできる場所」として、13-29歳の56.6%が「インターネット空間」をあげています。
2021年度に内閣府が、10-17歳の全国5千人を対象に実施した調査では、ネットで知り合った「同性と会ったことがある」「異性と会ったことがある」の回答率の合計が中学生は3.5%、高校生は9.8%となっています。
警察庁のまとめによると、令和2年(2020年)、1年間にSNSの利用をきっかけに事件に巻き込まれた18歳未満の子どもは1819人(前年比12.6%減)でした。
そのうち、略取誘拐の被害は6割増の75人、殺人未遂が2人でした。
被害者の内訳は、高校生が917(127人減)、中学生が695人(152人減)で、全体の9割近くを占め、小学生は84人(12人増)で、5年間で2倍に増えています。
背景には、スマートフォンの普及があります。
罪種別でみると、淫行などの『青少年保護育成条例』の違反が738人、裸の写真の撮影など『児童ポルノ禁止法』の違反が597人、児童買春が311人、略取誘拐が75人、『強制性交等罪』が45人などで、少女が男に首を絞められるなど殺人未遂も2件ありました。
被害者が利用したSNSは、多い順に(警察庁は被害の多い5つを公表)、「ツイッター」が642人、「インスタグラム」が221人、学生限定のチャット型交流サイト「ひま部」が160人、動画アプリ「TikTok」が76人、音声でやり取りする「KoeTomo」が63人でした。
特定のアプリの使用制限などができる「フィルタリング」の利用の有無がわかった1151人のうち、8割以上が被害時に利用していませんでした。
一方、SNSを使ったかどうかにかかわらず、警察が摘発した児童ポルノ事件は2757件(9.9%減)あり、被害にあった子どもは1320人(15.3%減)でした。
また、児童買春関連の摘発は8.4%減の2409件、被害の子どもは12.7%減の1531人でした。
前年比で減少した原因は、コロナ禍で、子どもも大人も外出を控えたことが影響していると思われます。
そして、子どもの性的虐待の画像・動画を扱ういわゆる「違法児童ポルノ」の問題は、既に、「世界的な公衆衛生上の危機」といえる状況ですが、この閲覧者の驚くべき実態を、フィンランドの人権団体「プロテクト・チルドレン」がアンケート調査を実施し、その調査結果を公表しています。
アンケート調査の目的は、閲覧者の思考や感情、行動パターンを把握し、自助プログラムを開発するためでした。
インターネット上に投稿されている子どもの性的虐待の画像・動画を視聴した人の3分の1が、その内容に影響を受け、実際に子どもに実際に接触を試みていました。
このアンケート調査は、こうした類の画像・動画の閲覧者に匿名で広く回答してもらうため、(令和2年)2020年12月に「ダークウェブ」上に投稿されました。
「ダークウェブ」は、通常の検索では見つけられない特別なネットワークに構築されたウェブサイトで、違法性の高い情報やコンテンツが掲載されています。
アンケート調査をまとめた報告書では、回答者の70%が、「はじめて子どもの性的虐待の画像・動画を見たのは18歳未満」、40%が「13歳未満」と回答し、50%以上が「意図せずに閲覧してしまった」と回答しています。
「どのようなコンテンツを探しているか?」という問いに対しては、45%が「4-13歳の少女」と回答し、少年の画像・動画を探している人は18%でした。
ネット上の違法コンテンツの撲滅を目指す英団体「インターネット・ウォッチ・ファウンデーション」のスージー・ハーグリーブス代表は、この報告書の内容について、「これほど多くの人が13歳未満で有害な動画・画像を見ているという事実は驚くべきこと。子どもの性的虐待のコンテンツを見ることは被害者のいない犯罪だと思われていますが、被害者である子どもたちは実際に残酷な性的虐待に苦しんでいます。しかも彼・彼女らは、画像・動画がネット上でシェアされ続ける恐怖とともにこれから生きていかなければなりません」とコメントしました。
団体側は、当初、アンケートの回答者は200人ほどだろうと予想していましたが、すぐに約5000人から回答があり、それをもとに報告書が作成されました。
令和3年(2021年)9月現在、回答者の総数は1万人を超えています。
回答者の中には、「自分の頭の中で繰り返される問題をはじめて文字にした。」とコメントした人がいたことに対して、「プロテクト・チルドレン」の法律専門家アンナ・オバスカは、「回答者たちは、(自分の抱える問題について)話す必要を感じているのだと思います。つまり、こうしたアンケート調査自体に、問題に介入する働きがあるといえます。」と述べている一方で、同団体の事務局長ニーナ・バーナエネン=バルコネンは、「残念ながら、こうした違法コンテンツを閲覧し、シェアしている人の大半は永遠に逮捕されません。」と嘆いています。
回答者の大多数が、子どもの性的虐待を扱うコンテンツの視聴を恥に感じ、なんとか止めたいともがき苦しんでいたこと、およそ半数の回答者が、こうしたコンテンツを見てしまうことがきっかけで、自殺や自傷を考えたことがあると回答しています。
幼いころに性的虐待を受けた成人を支援する心理学者でもあるバーナエネン=バルコネンは、「回答者のこうした傾向から、心理的なセラピーによって閲覧者たちの行動は変えられる。」、「ネット上の子どもへの虐待は世界的規模で拡大しており、公衆衛生上の危機と言えます。解決には、地域や公私の保健機関を挙げてのアプローチが必要です。」と述べています。
*-33 2014年(平成26年)、フィリピンで国外の高齢男性をターゲットに犯行を繰り返していた組織が逮捕されたり、日本国内においても平成27年(2015年)辺りから被害が増えはじめ、2022年(令和4年)5月、アメリカのカリフォルニア州で、17歳の男子高校生が自殺したりするなど、FBIなどが注視しているのが、デジタル性犯罪の「セクストーション」です。
セクストーションとは「セックス(性的)」と「エクストーション(脅迫・ゆすり)」を合わせた造語で「性的脅迫」のことです。
それは、マッチングアプリなどで出会った異性とSNSでやり取りをはじめ、「ビデオ通話で話をしない?」と持ち掛け、「ビデオ通話」に応じると、突然、衣服を脱ぎマスターベーションをはじめ、「あなたもしましょう」、「互いの恥ずかしい姿を見せ合おう」と誘い、それに応じた途端、その様子を録画した画面に切り替わり、「Facebook、Instagramの友人(フォロワー)にこの動画をバラまくぞ!(この恥ずかしい姿バラまくぞ!)」と脅し、「動画を消してほしければ、・万円を払え。でなければ」といったメッセージを送りつけ、金を騙しとる手口です。
*-34 リベンジポルノに限らず、DV被害から逃れた(加害者と別れた)あと、居所を知られずに生活をしなければならないときには、GPS情報(位置情報)が残っている写真をSNSに投稿してはならないのです。
また、使用している携帯電話(スマートフォン)に、無断で、遠隔操作してメールや通話履歴を見たり、無音で写真や動画を撮影したりできるアプリ(盗難・紛失対策に開発)をインストールされ、居場所や行動を知られていることもあるので、家をでる前に、インストールの有無を確認していくことが必要です。
第6は、いまから11年前の平成23年(2011年)6月3日、民法等の一部を改正する法律が成立し、『民法766条』の“子の監護”について必要な事項の例として、「父、または、母との面会やその他の交流、子の監護に要する費用の分担」が明示されるとともに、「父母がその協議で、子の監護について必要な事項を定めるときには、子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と規定されたことです(令和4年(2022年)10月現在)。
「子どもの監護」とは、「子どもの養育」という意味で、「監護者」となると「養育者」のことです。
したがって、「子の監護に要する費用の分担」とは、子どもの監護者(養育者)ではないもう一方の親とともに、養育費を分担し合うということです。
つまり、離婚後、子どもの養育費の負担を子どもの監護者(養育者)だけが担うことなく、もう一方の親が「養育費の支払う」ことで、分担し合う状況が成立するということです。
この『民法766条』の“改正”の背景には、日本政府が、1983年(昭和58年)12月1日に発効した国境を越えての子どもの連れ去りを禁止する『ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)』の批准*-35を強く迫られていたことがあります。
なぜなら、当時84ヶ国が加盟し、主要国で未加盟なのは日本とロシアだけだったからです。
つまり、日本政府は、『ハーグ条約』の批准にあたり、世界各国が採用している共同親権制度の考えを反映させる意向を示す必要性がありました。
このことは、国家間の「条約」は、国内法よりも優先されるため、日本が、これまでの単独親権から共同親権に則る考え方を主流にしていく意思表示と捉えることができます。
先に述べたように、日本社会の家族観(家制度)のもとで、子どもは養育者の家に帰属すると養育費の支払いがされていないことが、シングルマザーの貧困問題の背景のひとつになっています。
ここには、離婚全体の約9割を占める「協議離婚制度」は、他国にはない特殊な制度であることから、一方的な届け出が可能であったり、夫婦間で、「面会交流」「養育費の分担」など、文書(離婚協議書)としてとり決めをまとめて、公証役場で公正証書にしていなかったりする現実が存在します。
夫婦関係調整(離婚)調停で、離婚後の養育費の支払いを約束して離婚が成立した案件であっても、離婚後に子どもの養育費の支払いは30%程度に留まり、しかも、離婚後3年を経過すると15%ほどに低下しているのが、日本の現状です。
こうした中で、いまから2年前の令和2年(2020年)4月、養育費を回収しやすくする『改正民事執行法』が施行されました(令和4年(2022年)10月現在)。
この改正により、離婚後に子どもを養育している親が、養育していない親の「銀行口座」「勤務先」などの情報を取得しやすくなりました。
こうした情報が取得しやすくなることの意義は、養育費が未払いになったときに、速やかな差し押さえ(強制執行)につなげられることです。
つまり、夫婦関係調整(離婚)調停において、離婚が成立したときに作成される「調停調書」に養育費について定めた条項、離婚訴訟の判決などの債務名義にもとづく“差し押さえ(強制執行)”が、これまでよりもやりやすくなりました。
それは、「監護親」について、新たに、①金融機関から預貯金の情報を取得できる、②登記所(法務局)から土地建物に関する情報を取得できる(令和元年(2019年)5月17日から2年を超えない範囲内で、政令で定める日から運用が開始される)、③市町村・日本年金機構から給与債権、つまり、勤務先の情報を取得できるようになりました。
このことは、例えば、養育費の支払いが滞り、ひき続き支払いを求めたいと思ったとき、非監護権者が離婚後に転職をしていて、いまの勤務先がわからず、養育費の支払いを諦めるしかなかった事態を防げる、つまり、養育費の支払いを諦めずにすむということです。
ただし重要なことは、夫婦関係調整(離婚)調停において、離婚が成立したときに作成される「調停調書」や、離婚訴訟の判決(判決文)などの「債務名義に、養育費について定めた条項が記載されている」ことが“前提”です。
つまり、夫婦関係調整(離婚)調停において、このことについて、前もって主張し、「離婚調書の覚書」として文書化しておく必要があります。
そして、「婚姻破綻の原因は、配偶者によるDV行為である」ときの離婚では、「被虐待女性症候群(バタードウーマン・シンドローム)」、「PTSD」、「うつ病」、「解離性障害」などのDV被害の後遺症に苦しみ、仕事ができなかったり、日常生活に支障が生じたりすることがあることから、離婚後の生活が破綻しやすいリスクを抱える被害女性が多くいます。
シングルマザーの貧困は、深刻な社会問題であることから、生活保護の受給を受け入れることも踏まえて、離婚後の生活を破綻させないことは重大テーマです。
離婚後、子どもの親権者に対する「養育費の支払い」において、この“法改正”は、被害女性の大きな支えになります。
一方で、この『民法766条』の“改正”は、『配偶者暴力防止法(同16年改正)』が施行された平成13年(2001年)以降の子どもとの面会交流に対する司法判断を一転させました。
DV行為の後遺症としてのPTSD、その併発症のうつ病などの症状に苦しむ被害者にとって、離婚後(離婚調停/裁判期間を含む)、恐怖心を拭い去ることができない加害者である配偶者(元を含む)と子どもとの面会交流は、大きな精神的な負担になります。
しかも、この夫婦間にDV行為があったことは、子どもは心理的虐待(面前DV)を受けてきた被虐待児です。
この夫婦間のDV行為に「身体的暴力」が認められ、その夫婦間に子どもがいるときには、その子どもの70%以上が「身体的虐待」を受け、また、夫婦間に「性的暴力」が認められるときには、厳格な解釈にもとづくと、ほとんどの子どもは「性的虐待下である」ことを踏まえると、夫婦間にDV行為があり、心理的虐待(面前DV)を受け続けてきた子どもが、そのDV加害者である父親と面会交流をすることはあり得ないことです。
しかし、日本の司法は、「子どもが、両親間のDV行為を見たり、聞いたり、察したりする家庭環境にあるとき、その子どもは被虐待児である」という視点が欠落しています。
DV行為のある夫婦間に子どもがいるときには、その子どもは、等しく面前DV=心理的虐待被害を受け、その被害を持って、『児童虐待防止法』、『児童福祉法』が適用できます。
この「面前DV」が、『児童虐待防止法』の「心理的虐待」にあたることは、同法第2条(児童虐待の定義)の中で、「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力」と明記されています。
したがって、一方の配偶者に対して、DV行為に及んでいる親(もう一方の配偶者)は、子どもに対し、少なくとも心理的虐待を加えていることになり、「両親間にDV行為があっても、親と子どもの関係は別だから、親と子どもの面会交流は問題なく実施できる」という論理(主張)は成り立ちません。
ここで必要となる捉え方は、虐待を加えた親(加害者)と虐待を加えられた子ども(被害者)という関係性です。
「Ⅲ-28.『加害者更生プログラム』の受講効果の真意」の中で、「アメリカでは、DV=犯罪として、重罪か軽罪かにかかわらず、また、DV(犯行)があったと疑われるときには、警察官は、逮捕令状なしで加害者と疑われる者を逮捕できる。」一方で、「アメリカでは、子どものいる家庭におけるDV事件では、児童保護局(CPS)に通報される。」、「このとき、加害者逮捕に至らなくても、CPSが、「子どもに危険性がある」と判断したときには、子どもを裁判所の保護下に置き、加害者・被害者の親から分離させる。」、「その間に、両親(加害者と被害者)ともに、加害者プログラムやカウンセリングなどを受け、子どもを安全に育てる環境を整えなければならない。」と述べている通り、アメリカでは、DV被害者であっても、子どもに対する虐待行為(面前DV)の状況を放置した当事者となります。
したがって、日本においても、DV被害者である子どもの母親は、子どもに対し、子どもを安全で安心できる環境を整えるという意味で、配偶者から受けたDV行為によるダメージ(後遺症)のケア(治療)を最優先にとり組むことが必要です。
この視点に立つと、配偶者からDV行為を受けた子どもの母親の治療には、DV行為に及んだ子どもの父親との接触(面会交流)は、トラウマの追体験となり、PTSDの症状が悪化する要因となり得ることから、治療上、避ける必要があります。
このように、虐待行為の加害者である父親とその被害者である子どもとの面会交流の実施の判断は慎重でなければならず、また、虐待行為の加害者である親(一方の配偶者に対してDV行為に及んでいる親)が、被害者である子どもの親権や監護権(養育権)を得たりすることはあり得ないことです。
国連で、いまから33年前の1989年(平成元年)11月20日に採択された『児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)』の19条では、「子どもが両親のもとにいる間、性的虐待を含むあらゆる形態の身体的、または、精神的暴力、傷害、虐待、または、虐待から保護されるべきである。」と定め、「それが起こるとき、親権や監護権、面会交流の決定において、親密なパートナーからの暴力や子どもに対する暴力に対処しないことは、女性とその子どもに対する暴力の一形態であり、拷問に相当し得る生命と安全に対する人権侵害である。」、「また、子どもの最善の利益という法的基準にも違反する。」と規定しています(令和4年(2022年)10月現在)。
いまから8年前の平成26年(2014年)、CEDAW(女性差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約))委員会は、「面会交流のスケジュールを決定するときには、家庭内暴力や虐待の履歴があれば、それが女性や子どもを危険にさらさないように考慮しなければならない。」と勧告しています(令和4年(2022年)10月現在)。
しかし、日本政府は、この勧告に反し、その考慮は極めて限定的です(改善に消極的です)。
いうまでもなく、『条約』は、国際法です。
『日本国憲法』第98条2項は「条約を誠実に遵守する」と定め、同第73条第3号但書、同第98条2項により、『条約』は、『法律(国内法)』の上位です。
家庭内暴力や虐待の履歴がある家庭で、子どもがいる夫婦が別居、あるいは、離婚に至るとき、その子どもが、虐待行為の加害者である一方の親と生活をともにすることは、子どもを危険にさらすことに他なりません。
この状況は、いうまでもなく、『児童虐待防止法』に準じると通報事案、つまり、そのこと自体が“一時保護”事案となり得ます。
また、子どもへの「身体的虐待」に対しても、同様に、「暴行罪(同208条)」、「傷害罪(同204条)」、「殺人罪(同199条)」、「殺人未遂罪(同203条)」、同「性的虐待」に対しては、「監護者性交等罪(同179条2項)」、「監護者わいせつ罪(同179条1項)」、同「心理的虐待」に対しては、「強要罪(刑法223条)」、「侮辱罪(同231条)」、その虐待行為による後遺症として、「PTSDやその併発症としてのうつ病」「パニック障害」「C-PTSD(複雑性心的外傷後ストレス障害)」などを発症したときには、その後遺症に対し別途「傷害罪(同204条)」が適用できます。
一般的な常識で考えると、こうした『刑法』に抵触する虐待行為に及んだ子どもの親が親権を得たり、監護権者となったり、もう一方の親(DV被害者)と暮らす子どもと面会交流を実施することはあり得ないことです。
一方で、いまだに“保守的”な価値観を支持する人たちが主流の日本社会においては、「虐待を加えてきた人であっても親、人を殺した人であっても親、肉親の絆は切れるものではない」、つまり、「子どもにとって、どんな親でも親であることには変わらない」と、親と会ったり、親と過ごしたり、親と暮らしたりするのは子どもの義務、責任との考えを子どもに押しつけ、決まりごとと行動を押しつけます。
子どもの思いや考え、意志、子どもの人権を尊重することはなく、ほとんど大人の都合で決められます。
それでも、平成13年(2001年)に『配偶者暴力防止法』が施行されると、「婚姻破綻の原因は、配偶者のDV行為である」として、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停を申立てたり、その後、調停不調となり提訴し裁判となったりした民事事件で、「被害者であり、親権を得た、あるいは、監護者となった母親と暮らすことになる子どもが、DV加害者である父親と面会交流をおこなうことは、加害者に対する恐怖心を拭えない母親の精神的苦痛となり、相互の意思疎通ができない中での子どもの面会交流は子の福祉に反する(その後、「子の利益」に変更)」と、「加害者である父親と子どもとの面会交流が及ぼすリスクと悪影響」を主張することで、離婚後、加害者である父親と子どもの面会交流を拒むことができました。
例えば、平成19年(2007年)8月22日、東京高等裁判所は、「子の監護に関する処分(面会交渉)審判に対する抗告事件」で、「子の福祉の面から恐れが高い」として、面接交渉の申立を却下しました。
この審判は、「父(相手方)から母(抗告人)に対して、面接交渉を求めた事案の抗告審において、母には、父が未成年者らを連れ去るのではないかと強い不信感があり、面接交渉に関する行動につき信頼が回復されているといいがたく、未成年者らも将来はともかく、現在は相手方との面接を希望しない意思を明確に述べているような状況においては、未成年者らと相手方との面接交渉を実施しようとするときには、未成年者らに相手方に対する不信感に伴う強いストレスを生じさせることになるばかりか、父母との間の複雑な忠誠葛藤の場面にさらすことになる結果、未成年者らの心情の安定を大きく害するなど、その福祉を害する恐れが高く、未成年者らと相手方の面接交渉を認めることは相当ではないとして、面接交渉を認めた原審判をとり消し、面接交渉の申立を却下した」ものです。
この時期、東京家庭裁判所(平13.6.5審判)、横浜家庭裁判所(平14.1.16審判)、東京地方裁判所(平14.5.21審判)など、同等の解釈による判決が多数下されました。
ところが、いまから10年前の平成24年(2012年)4月に改正された『民法766条』が施行されると、この「離婚後の面会交流のあり方」は、「父親を怖れている子どもとの面会は、子の利益(福祉)の観点から好ましくないので実施しない」との主張は認められ難くなり、「夫婦間にどのような経緯・懸案事項があろうとも、父親と子どもとの面会は子の利益(福祉)の観点から必要不可欠であり、家庭問題情報センター(FPIC)などの第3者機関を介することで、面会は可能である」との考え方に大きく舵を切りました(令和4年(2022年)10月現在)。
しかし、先に記しているとおり、被害者にとって、子どもを加害者である父親と面会交流させるには、大きな精神的負担を伴います。
なにより、父親が、母親にDV行為としての暴力を加えるのを見たり、聞いたりしてきた子どもが、その父親と面会交流するのは、大きな精神的負担となります。
このことは、被害者である元配偶者の暴力被害による後遺症(PTSD、その併発症のうつ病)の治療と心身の回復に大きな影響を及ぼし、同時に、加害者である父親と面会せざるを得ないもうひとり被害者である子どもの治療と心身の回復にも大きな影響を及ぼします。
父親ともうひとりの被害者である子どもとの面会交流は、仮に、FPIC立ち合い。時間が限られたものであっても、暴力的ではない外面のよい父親を演じ切る可能性があることから、「民法733条」の改正前と同様に、「加害者である父親と子どもとの面会交流が及ぼすリスクと悪影響」を主張し、面会交流を認めないことです。
面会交流に臨む子どもが、被虐待児という視点に立つと、父親が暮らす家に行ったり、その家に宿泊したり、旅行に行ったりすることはあり得ないことです。
したがって、DV被害者支援室poco a pocoの活動は、平成24年(2012年)4月に『民法766条』が施行されて以降、大きな舵を切った裁判所の方針に抗い続けた10年となりました。
大きな舵を切った裁判所の方針に抗うためには、武器が必要です。
それが、被害者のアドボケーターとしてまとめる『レポート(被害の事実と後遺症、その経過)』であり、その中での記述の裏づけ・根拠となる情報をまとめた『別紙1.2.3』などの資料です。
*-35 「ハーグ条約」については、「Ⅰ-B-10-(6)-⑥国際結婚における離婚問題。子どもの連れ去りとハーグ条約」で説明しています。
(追記)
『民法766条』の“子の監護”が問題となるのは、いうまでもなく、民事事件として、加害者(配偶者)と「離婚する(した)」ときです。
『配偶者暴力防止法』に準じて“一時保護”が決定されたり、“保護命令”が発令されたりしても、その時点で、離婚は成立しません。
また、加療を要するような傷害を負うような暴行・傷害事件として、加害者である配偶者が逮捕され、その後、起訴され、懲役刑が確定したとしても、その行為によって、離婚は成立しません。
したがって、婚姻関係にある夫婦が離婚するには、民法が定めるア)夫婦が同意して署名し、協議離婚届書を戸籍係に提出する方法(協議離婚)、イ)家庭裁判所の調停の場で離婚の合意をする方法(調停離婚)、ウ)調停でまとまらず、家庭裁判所が離婚の審判をする方法(審判離婚)、エ)家庭裁判所の判決で離婚が命じられる方法(判決離婚)のいずれかの方法で成立させる必要があります*-36。
離婚全体の約9割を占める「協議離婚」は、他国にはない、日本独自の特殊な制度です。
「協議離婚制度」は、夫婦が離婚に合意しているとき、それぞれが署名、押印した離婚届を自治体に提出すると離婚が成立する制度です。
しかし、本人が提出する必要はなく、役場の窓口で、著名の真偽などは確認されないことから、一方的な届け出が可能です。
一方の配偶者が、離婚にあたり、「親権者は自分」として離婚届を自治体に提出するのを防ぐ必要があるのが、「婚姻破綻の原因は、配偶者からのDV行為である」ときです。
それは、一方の配偶者が、一方の配偶者の同意なく離婚届を提出してしまう前に、自治体に「離婚届の不受理申出書」を提出することです*-37。
この手続きにより、仮に、DV被害者が離婚する意思があったとしても、夫婦の合意として、財産分与、暴力行為により精神的苦痛を被り、PTSDなどの後遺症に対する治療費の支払いなどに対する損害賠償金(慰謝料)の支払い、子どもの親権者、監護権者の決定、子どもの養育費の支払いなどをとり決めることなく、DV加害者である配偶者が一方的に離婚届を提出するのを防ぐことができます。
イ)の「調停離婚」は、一方の配偶者が、家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)調停」を申立て、2名の調停委員を介して合意を目指し話し合います。
婚姻による夫婦関係は、「お互いに助け合う(協力し合う)」、「お互いに扶助し合う」といった“前提”に立っています。
例えば、一方の配偶者が病気や事故の後遺症、失業などで働けないときには、もう一方の配偶者が働き、生計を成り立たせることが求められます。
子どもや年老いた両親や親族などを養育する、扶養することは、「民法752条」で定める「扶養の義務」です。
その「民法752条」では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」としています。
お互いの話し合いで合意に至り離婚(協議離婚)できないときには、婚姻とは違い、簡単に離婚を成立させることができません。
なぜなら、「お互いに助け合う(協力し合う)」、「お互いに扶助し合う」義務を果たしてきたかが問われるからです。
一方の配偶者が申立てた「夫婦関係調整(離婚)調停」において、家庭裁判所が離婚を認めるか否かの判断は、「民法770条」で定める離婚事由に該当するかどうかです。
民法770条に定める離婚事由は、次の5つです。
a)配偶者に不貞行為がある、b)配偶者から悪意で遺棄された(「同居義務、協力義務、扶助義務を負う」に対し、不当に違反する行為)、c)配偶者の生死から3年以上明らかでない、d)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない*-38、e)その他、婚姻を継続し難い重大な理由がある、つまり、ア)配偶者からの暴力・暴言、その他の虐待行為を受けた、イ)夫婦間の性関係がない(セックスレス)、ウ)性格の不一致、エ)配偶者が某宗教団体に入会し、布教活動に熱中し家庭を顧みない、オ)配偶者と両親との不仲などの認定が必要となります。
したがって、「婚姻破綻の原因は、配偶者によるDV行為にある」として離婚を求めることは、e)「その他、婚姻を継続し難い重大な理由がある(民法770条第1項5号)」の中のア)「配偶者からの暴力・暴言、そのほかの虐待行為を受けた」が、法律上の離婚事由になります。
重要なのは、離婚を求める側は、上記の離婚事由(配偶者からの暴力・暴言、そのほかの虐待行為を受けた)に該当していることを、事実にもとづいて立証しなければならないということです。
例えば、「民法770条第1項4号」のd)として、配偶者が回復の見込みのない精神病に罹患していたり、レビー小体型認知症、レム睡眠行動障害などの発症が暴力の原因であったりするときは、治療にとり組むなど「手を尽くせることはすべてやった」事実が必要です。
重要なことは、夫婦間の協議で離婚できず、「夫婦関係調整(離婚)調停」での話し合いとなるときには、「婚姻破綻の原因が、精神疾患や人格障害、発達障害などを起因とする暴力(DV)であった」としても、「配偶者がうつ病(統合失調症)を発症したから離婚したい」、「配偶者は自己愛性人格障害(または、境界性人格障害)だと思われるから離婚したい」、「配偶者はアスペルガー症候群*-39だから離婚したい」など、 “病名”を離婚理由とするのではなく、暴力という“行為”だけにフォーカスして主張することです。
なぜなら、その主張が、離婚する配偶者を誹謗中傷し、貶める行為として、離婚を求めるもう一方の配偶者の人となりを疑われる怖れがあるからです。
つまり、「夫婦関係調整(離婚)調停」に携わる調停委員、裁判所調査官、裁判官(審判員)、そして、自身の代理人(弁護士)の心証が悪くなります。
「婚姻破綻の原因が、配偶者からのDV行為である」として臨む「夫婦関係調整(調停)調停」では、主張する“離婚事由”としての「DV行為の事実」にフォーカスし、その事実が、夫婦関係を破綻させた重大な原因であり、修復する可能性がないことを明確に示す必要があります。
このときのポイントは、被害の事実と意見(思い、感情表現)をわけることです。
「書面」での主張は、被害の事実だけにフォーカスし、いかにツラく、苦しく、哀しく、やるせなかったについては、最後にまとめることが重要です。
なぜなら、被害の事実を示すときに感情表現が加わると、被害の事実ではなく、思い中心の文章になり、被害の事実が正確に伝わらないリスクがあるからです。
代理人の弁護士が「長いと読まれないので、陳述書は、簡潔にまとめてください」と話す(指示する)ことがありますが、その理由は、感情表現が主となり、被害の事実が明確でないからです。
司法に携わる人たち(裁判官、検察官、弁護士、書記官、裁判所調査官など)は、長文の「判決文(判例)」に慣れているので、先の弁護士の話(指示)は真実ではないことは明らかです。
つまり、彼らが読みやすい事実主体の文章で、論理構成がしっかりしていれば(論理破綻だらけのハチャメチャな文章でなければ)、信じられないほどの長文であってもきちんと読んでもらえます。
その「夫婦関係調整(離婚)調停」を家庭裁判所に申立てるとき、家庭裁判所では、「申立書」を用意しています。
「申立書」とは、訴訟法上、当事者が、裁判所に対して特定の内容の訴訟行為を求める旨の意思表示を記載して提出する書面のことで、一般的な「申請書」のようなものです。
この「申立書」の“別紙”として、離婚を申立てるに至った経緯を詳細にまとめた書面を提出することができ、その提出は、家庭裁判所が用意している「申立書」を提出したあと(後日)でも可能です。
その家庭裁判所が用意している申立書の「申立ての動機欄」には、13の項目が記載されています。
「動機」とは、離婚を申立てる理由ということです。
では、その申立書の「申立ての動機欄」に記載されている13項目と『配偶者暴力防止法』で規定しているDV行為との相関性を見てみます。
「3.暴力をふるう」は身体的暴力、「8.精神的に虐待する」「13.その他(束縛する・育児に協力しない・子どもを乱暴に扱う)」は精神的暴力、子どもへの虐待、「3.異性関係」は性的暴力、「12.生活費を渡さない」「6.浪費する」は経済的暴力ということになり、13項目のうち6項目は、DV行為としての暴力です。
では、離婚調停に臨んだ女性が、離婚理由としてあげた1-10位までを順を追って見ていきたいと思います。
1位の「性格が合わない」は、抽象的な表現となっています。
「夫婦関係調整(離婚)調停」では、具体的に、詳細に、「夫婦間で、どのようなことが合わないのか」についての説明を求められます。
「なにが合わないのか」について、具体的に、詳細に話す中で、「行為」にフォーカスしていると、その「行為」が、これまで自覚できていなかった「DV行為としての暴力」であったことにはじめて気がついたり、代理人の弁護士や調停委員に「その行為は、DVですよ。」と指摘されたりすることがあります。
2位は「暴力(身体的暴力)をふるう」です。
婚姻破綻の原因である以前に、身体的暴力は、「暴行罪(刑法208条)」「傷害罪(刑法204条)」などで立件される可能性のある犯罪行為です。
また、夫婦間の身体的暴力を子どもが見たり、聞いたり、察したりする状況にあるときには、「面前DV」となり、子どもにとって「心理的虐待」となります。
夫婦間で「身体的暴力」などのDV行為が加えられているときには、身の安全を確保することを優先させ、安全が担保されている状況下で、「夫婦関係調整(離婚)調停」を進める必要があります。
そこで、「婚姻破綻の原因が、配偶者からのDV行為である」ときの「夫婦関係調整(離婚)調停」では、加害者である配偶者と被害者であるもう一方の配偶者とが顔を合わせないように部屋を分け、2名の調停委員がそれぞれの部屋を相互に訪れて話をしたり(仲介する)、その調停が終わったあとは、加害者である配偶者が帰ったのを確認したことを被害者であるもう一方の配偶者に伝え、退出してもらったりするなどの対応がとられます。
ただし、小規模な家庭裁判所や支部では、部屋を分けることができないこともあります。
3位の「生活費を渡さない」は、「経済的暴力」になるので、2位の身体的暴力とともにDV行為となり、同時に、「民法752条(同居、協力及び扶助の義務)」に反する行為です。
「生活費を渡さない」ことで、一方の配偶者が努力しても、子どもの養育に支障がでるような状況に至っているときには、子どもにとっては「ネグレクト」となり得えます。
4位の「精神的に虐待する」は、「精神的暴力」のことですから、いうまでもなくDV行為であり、子どもが見たり、聞いたり、察したりする状況であれば「面前DV」となり、子どもにとって「心理的虐待」となります。
5位の「異性関係」は、女性関係が不特定多数であったり、愛人に子どもを設けたり、性風俗店やデリバリー型の性風俗店で買春したりするなどが該当します。
こうした行為のすべては、「性的暴力」としてDV行為に該当します。
また、不特定多数の人物と性行為に及び、そのとき、避妊具を使用しないことは、性感染症に罹患するリスクがあり、性感染症に罹患したことを知りながら夫婦間の性行為に及び、配偶者に性病を罹患させたときには「傷害罪(刑法204条)」、HIV感染者のときには「殺人罪(刑法199条)」の適用対象となります。
6位は「浪費する」で、ギャンブルに入れ込んだり、遊興や趣味に散財したり、贅沢品や洋服などを必要以上に購入したり、多額の借金をしたりする行為が含まれます。
家庭の家計を顧みず、日々の生活に支障がでるような浪費や散財がおこなわれたり、多額の借金をしていたりするのであれば、3位の「生活費を渡さない」と同じ「経済的暴力(精神的暴力に含まれる)」ということになり、DV行為に該当します。
7位の「家庭を捨てて省みない」は、a)「愛人などの家で生活して帰ってこない」だけでなく、b)「毎日飲んで帰ってくる」、c)「仕事をできない理由がないのに仕事をしない」、d)「子どもの面倒をまったく見ない」など、健全な結婚生活を続けることが困難だと思われる状況も該当します。
a)愛人などの家で生活して帰ってこないは、DV行為としての「性的暴力」に該当すると同時に、「民法752条(同居、協力及び扶助の義務)」に反する行為となり、b)飲んで帰ってきて大声で怒鳴りつけたり、罵倒したりするのであれば「精神的暴力」になり、c) 仕事をしなかったり、生活費を入れなかったりするのは「経済的暴力」で、「仕事をして欲しい」との訴えに激怒して、暴行を加えたときには、「身体的暴力」になり、d)「少しは子どものことを見てほしい」の訴えに、不機嫌になったり、無視したり、子どもが乳幼児で手がかかるときに、休日にひとりで遊びに行ってしまったりするのは「精神的暴力」になります。
b)c)d)のDV行為を、子どもが見たり、聞いたり、察したりし得るときには、「面前DV」となり、子どもにとっての「心理的虐待」となり、a)d)を踏まえ、「家庭を捨てて省みない」ことは、子どもに対する「ネグレクト(育児放棄)」となります。
そして、同居・協力・扶助義務を正当な理由なく拒否する状況は、「悪意の遺棄」に該当し、離婚原因となります(民法770条1項2号)。
このように、細かく落とし込んでいくと、その多くがDV行為、子どもに対する虐待行為に該当します。
8位の「異常性格」は、a)配偶者に対して、慢性反復的(常態的、日常的)にDV行為としての暴力を加えたり、b)子どもに対して、慢性反復的(常態的、日常的)に虐待行為としての暴力を加えていたりする他、c)パラフィリア(性的倒錯/性嗜好障害)として、グループセックスやSM行為など望まない性行為を強いたりするなど、性的サディズム、窃視症、性的マゾヒズム、ペドファリア(小児性愛)、窃触症(さわり魔、痴漢)、露出症の傾向があったり(これらの行為は「性的不調和」にも該当)、d)日常生活に支障を及ぼす重度の「統合失調症(精神分裂病)」、「双極性障害(躁うつ病)」などの精神疾患の発症などが想定されています。
他に、e)「極度のマザコン(マザーコンプレックス)、ファザコン(ファザーコンプレックス)」も該当すると解釈されています。
極度のマザーコンプレックス、ファザーコンプレックスとは、裏返せば、親の過干渉や過保護、いき過ぎた教育(教育的虐待)という“支配”のための暴力を受けて育ってきて、いまだに、親の支配下にある状況を意味します。
そのため、「親のいうなり」、「親の指示(同意)がなければ、なにも決められない」などと不満が溜まり、あまりにもひどいと感じたときには、“異常”と認識することになります。
それだけでなく、配偶者である妻が、母親がしてくれていたとおりにできないと「母親はこうだった。なぜ、お前はできないんだ!」と母親と比べて否定したり、非難・批判したり、侮蔑したり、卑下したりすることばの暴力を浴びせるなど、「精神的暴力」が加えられます。
激怒する配偶者であるときには、「しつけ(教育)のし直し」と称した(自身の行為を正当化する)殴る蹴るといった苛烈な「身体的暴力」が加えることもあります。
「しつけ(教育)のし直し」とは、「僕は、本当は殴りたくないんだ! でも、君が僕を傷つけたんだから仕方ない!」、「僕は、君に変わってほしいだけなんだ!」という自分勝手な(自分だけに都合のいい)理屈で加えられる暴力行為です。
また、実家に帰省したとき、親の前で、妻が自分の意見や考えを口にしたのを発端に、「俺に恥をかかせやがって!」とDV行為の引き金になることもあります。
“親に認められたい”、“立派に家庭を築いていることを親に示したい”といった強迫観的な感情が、実家で、自分を敬い、奉り、至れり尽くせりで接しない落ち度を咎め、苛烈な暴力行為に至ります。
こうした状況下でのDV行為は、夫婦内で解決しようとしても、絶対君主として君臨している父親(義父)、一見、好意的に耳を傾けてくれているようであっても、「息子は悪くない」という“前提”で、後始末(尻拭い)役を買ってくる加害者である配偶者の母親(義母)によって、事態が複雑化していきます。
しかも、息子が精神的な問題を抱えていることを自覚していても、その事実を認められない母親(義母)には、息子の生贄としての妻(女性)をあてがっておきたい心理が潜んでいるときもあります。
ここには、義母の他、配偶者のきょうだいも含まれます。
なぜなら、息子、きょうだいの暴力的な言動やふるまいに恐怖を覚えていて、自分に向かう怖れを回避する狙いがあるからです。
そのときの母親(あるいは、きょうだい)は、主に2つの回避行動を示します。
ひとつは、息子の機嫌を損ねず、怒りださないための方法を伝授するなど、「あなたが変わることで、夫婦関係は継続できる」といい含めることです。
その結果、「私はあなたの味方である」ことを装う姑(時に、姉や妹)と、その姑(時に、姉や妹)を頼りにする嫁という構図といった新たな関係が構築されます。
もうひとつは、「息子は、母親思いの優しい子で、これまで、暴力的な行為におよんだことはない。」、「あなたと結婚してから息子は変わった! あなたに問題がある」と非難したり、侮蔑したり(以上、ことばにださなくとも、無視するなど態度やふるまいで感じることを含む)することで、息子に従順である姿勢を見せることです。
「しつけ(教育)のいき届いていない」息子の妻を、息子との“共通の敵”という位置づける関係が構築されます。
このとき、家の嫁としてふさわしくなるための「嫁のしつけ(教育)のし直し」をする役割の主体が、息子から母親(義母)にバトンタッチされます。
その結果、妻は、義母に対して強い反発心や怒りの感情を示すようになり、夫のDV問題が、嫁と姑の問題にすり替わっていることがあります。
配偶者間のDV問題であるはずが、加害者である配偶者の親が絡み、問題をより複雑にしていることがあります。
9位の「酒を飲み過ぎる」は、7位の「家庭を顧みない」の毎日のように飲み歩いて泥酔して帰宅する、家庭内でも家計に負担を与えるほど飲むことと重なります。
また、飲むと暴れる、いわゆる「酒乱」による暴言や暴行に至っているときには、DV行為そのものです。
そして、子どもが、親が飲むと暴れる姿を見たり、聞いたり、察したりする状況は「面前DV」となり、子どもにとって「心理的虐待」となり、その飲むと暴れる行為が子どもに向かうときには、その時の状況によって、「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」になります。
ただし、「アルコール依存症=酒乱」ではなく、アルコール依存症にもとづくDV行為(身体的暴力)は、全体の8%程度といわれています。
ただし、阪神淡路大震災や東日本大震災などの自然災害にあい、長い避難生活を余儀なくされると、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、自殺が増加することがわかっています。
このとき、その背景にあるのが、被災者のアルコール飲酒量が増え、その結果、暴力行為に至っている事実があります。
つまり、被災地域では、アルコール依存症が増加し、その増加に比例するように、DV、児童虐待、性暴力(、自殺)が増加し、その結果、離婚も増加する傾向があります。
10位の「性的不調和」は、セックスレスを想定していますが、望まない性行為を強要したり、特異な性的嗜好を強要したりする行為も含まれます。
レックスレスの原因はさまざまですが、7位の「家庭を捨てて省みない」のa)愛人などの家で生活して帰ってこない、b)毎日飲んで帰ってくるが関係していたり、また、不倫関係にある異性(同性)がいたり、性風俗店やデリバリー型の性風俗店で買春行為に至っていたり、8位の「異常性格」のc)パラフィリア(性的倒錯/性嗜好障害)として、グループセックスやSM行為など望まない性行為を強いたりするなど、性的サディズム、窃視症、性的マゾヒズム、ペドファリア(小児性愛)、窃触症(さわり魔、痴漢)、露出症の傾向があったり(これらの行為は「性的不調和」にも該当)することが、その背景にあることがあります。
これらの行為は「性的暴力」そのものですから、DV行為ということになります。
以上のように、妻が離婚理由としてあげている上位10(1位は不明確なので対象外)は、すべてDV行為に含まれ、ときに、子どもに対する虐待行為にあたります。
ところが、夫婦関係調整(離婚)調停を介して離婚をした女性であっても、2位-10位にあげた離婚理由について、「DV行為としての・・」と正確に理解している人は少ないかも知れません。
例えば、「婚姻破綻の原因は、配偶者からのDV行為である」との離婚事由で、家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)調停」を申立てたり、「DV行為で精神的苦痛を被った」ことに対する“損害賠償金(慰謝料)”を請求したり*-40するとき、被った精神的苦痛の程度(「傷害罪」が適用される加療を要する傷害を負った、つまり、PTSDを発症したり、その症状が重篤化し、併発症としてのうつ病を発症したりするなど)は、どのようなDV行為としての暴力を、どれくらいの期間、どれくらいの頻度で受けてきたのかで判断されます。
つまり、どのような行為がDVにあたるのかを正確に知らなければ、被った精神的苦痛の程度を正確に示すことができません。
DV被害者のアドボケーター(援助/代弁者)としての経験では、かかわったDV事案のほとんどで、「被害者と代理人の弁護士が認識してきた(いま、離婚調停で主張している)DV被害では、ここまで重篤なPTSD、その併発症としてのうつ病などの症状などは表出し難い」といえるDV被害でした。
このことは、第1に、被害者自身が、まだ認識できていないDV被害が隠れている、第2に、第1に起因して、DV被害を言語化できていなかったり、無意識下で、トラウマとなり得たDV被害の追体験によりPTSDの症状が悪化するのを避け、結果、DV被害を言語化できなかったりする問題が存在する、第3に、被害者自身が、認識できていなかったり、認識していても、第3者には隠したかったりする性的暴力が存在していることを意味します。
DV被害者の代理人(弁護士)を含めて、「婚姻破綻の原因が、配偶者からのDV行為である」とする「夫婦関係調整(離婚)調停」にかかわる人は、慢性反復的(常態的、日常的)なDV被害の後遺症、つまり、PTSD、その併発症としてのうつ病などの症状はどのようなものなのか、その症状が、“これまで”と“いま”、そして、“これから”の生活にどのような影響を及ぼすのかなどについて正確に理解していない限り、DV被害の事実と後遺症の状況を正確に把握することは困難です。
中には、PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、その名称のとおり“後発性”が特徴であるにもかかわらず、別居してから時間が経過したり、医師の治療(カウンセリングを含む)を受けてから症状が重くなったりしたとき、DV被害者が、新たに訴える症状に疑心暗鬼になり、「治療を受けて、症状がひどくなったのね。」と嘲笑した女性の代理人(弁護士)もいました。
これは、DV被害者の代理人となった女性の弁護士の無知(知らないこと)による無理解が招いた「2次加害」でした。
この女性の弁護士は、そのDV被害者が生活する都市では、DVやセクハラ事件に精通している弁護士として名を馳せている人でした。
DV加害者の配偶者との出会い、交際期間を含めて結婚後の日々の生活について、DV被害者に一つひとつことばにしてもらうことで、「いま示している症状や傾向の根底には、このDV行為としての暴力がある」という“原因”を見つけることができ、結果、これらの因果関係を示すことができます。
DV行為としての暴力の正確な理解なくして、DV被害を正確に主張することはできません。
正確に主張できないと、被った精神的苦痛、後遺症としてのPTSD、併発症としてのうつ病の症状や苦しみは理解されず、認定されません。
この『手引き(新版2訂)』では、理不尽なDV被害を受けたあとも、頼った人たちから理不尽な思いをさせられないために、多くの事例を通じてDV行為としての暴力を正確に知ることと、その後遺症としてのPTSDの症状*-41、その併発症としてのうつ病をもたらすメカニズム、被虐待女性症候群(バタード・ウーマン・シンドローム)*-42の傾向などの被害者の特徴、さらに、DV加害者の属性ごとの特性を正確に理解していただくために、多くの頁を割いています。
*-36 平成15年(2003年)2月5日、法制審議会は「離婚訴訟を家庭裁判所の管轄にする」という法案要網が発表され、これにもとづいた法改正により、エ)地方裁判所でおこなわれていた離婚裁判についても家庭裁判所でおこなわれるようになりました。
*-37 「離婚届けの不受理申出書」の提出については、「Ⅰ-C-11-(4)役場(市役所や区役所など)での手続き」の中で説明しています。
*-38 ただし、措置入院などの公的保護を受けて、療養できる体制を整えたり、治療費等の金銭的な手当てをしたりするなど具体的な方法を尽くしていないと、離婚が認められないことがあります。
なお、「配偶者の精神疾患が原因となる暴力行為」に対しては、「Ⅰ-A-1-(10)加害者の属性で判断。DVでない暴力、DVそのものの暴力」で詳しく説明しています。
*-39 「アスペルガー症候群などの発達障害の“特性”が、結果として暴力行為となる」ことについては、「Ⅰ-A-2-(3)発達障害などの障害の“特性”、結果として暴力」で詳述しています。
*-40 離婚成立時に慰謝料(損害賠償金)請求をしていないときの「配偶者に対するDV行為に対する慰謝料(損害賠償金)請求の時効は5年(民法改正で3年から5年に延長)」で、起算日は離婚が成立した日です。
なお、配偶者が不貞行為などの不法行為に至ったとき、配偶者、ならびに、その相手に対する損害賠償請求権は、不法行為発覚後3年で時効となりますが、この不貞行為が原因で離婚に至ったときには、配偶者との離婚事由として損害賠償できることから、離婚時に慰謝料(損害賠償金)を請求できます。
また、慰謝料(損害賠償金)請求をせずに離婚に至っているときには、その慰謝料(損害賠償金)請求権は、離婚が成立した日から3年で時効となります。
*-41 「PTSDの症状」については、「Ⅰ-B-7-(4)暴力の後遺症としてのPTSD」で詳述しています。
*-42 「バタード・ウーマン・シンドローム(被虐待女性症候群)」については、「Ⅰ-B-7-(2)被虐待女性症候群(バタード・ウーマン・シンドローム)」で詳述しています。
私は、令和2年(2020年)3月、COVID-19(新型コロナウイルス)の流行を受け、休校や外出自粛が叫ばれ、失業が懸念され、阪神淡路大震災、東日本大震災などの震災後、DVや児童虐待、レイプなどの性暴力が増加したことから、4年半余り休止していた支援活動を再開しました。
その支援活動を再開して感じたことは、「DV(デートDV)」「児童虐待」「性暴力」「ハラスメント」ということばは広く知られるようになってきた一方で、「どのような行為が、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントにあたるのか」の知識は、いまだに不確かな人が多く、これらの暴力行為は「人権問題」という認識はほとんど浸透していないと再認識したことでした。
知識が不確かな人が多い社会は、被害を相談したり、訴えたりし難くなります。
そればかりか、被害を理解されなかったり、被害を信じてもらえなかったり、被害を否定されたり、非があると責められたりする2次加害をもたらします。
被害を相談したり、助けを求めたりする行為が、2次加害を生み、誰も助けてくれないと絶望感を覚えさせてしまいます。
例えば、「婚姻破綻の原因は、配偶者からのDV行為である」とする「夫婦関係調整(離婚)調停」では、DV加害者であるはずの配偶者(夫)が、逆に、「私がDVをするはずがない。被害者は私の方だ。」と主張したり、被害者が、「配偶者(夫)の身体的暴力により加療を要する障害を負った」と診断書を提出しても、「それは、嫉妬深く、怒りっぽい妻が興奮し、暴れたのを止めようとしたらからであって、不可抗力だ。」と反論したりすることがあります。
このとき、この離婚事件を扱う調停委員のバックボーンに、「女性の多くは、嫉妬深く、怒りっぽく、興奮すると厄介だ」、「暴力をふるわれるだけのことをしたのなら、暴力は仕方ない」という考え方(“保守的”な価値観)があるとき、DV加害者の夫の主張を「あり得るな」と受け入れてしまうリスクがあります。
つまり、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力事件では、暴力被害の訴えを聴く者の価値観というバックボーンに大きく左右されてしまいます。
時には、暴力被害という事実そのものが歪められてしまいます。
被害者の多くは、無知(知らないこと)がもたらす無理解という暴力による2次加害に苦しめられます。
人は、自分の意思に反し、望まない性的行為を強要されたり、暴力行為を受けたりすると、つまり、「人的侵害」を受けると、この“わたし”というアイデンティティが破壊され、粉砕されます。
つまり、「自分が、自分でなくなる(同一性拡散の危機)」状態に陥ります。
「自分が、自分でなくなる」ことは、自尊感情(自己肯定感)が破壊され、粉砕されている状態です。
「自尊感情(自己肯定感)」とは、自分は存在価値があると感じられる、自分を好きだと感じられる、自分を大切に思える気持ちがあることです。
つまり、自尊感情(自己肯定感)が破壊され、粉砕されると、自分の存在価値を認められなくなる、自分を好きになれなくなる、自分を大切に思えなくなります。
自尊感情(自己肯定感)が破壊された被害者にとって、近しい人の間違った価値観や解釈にもとづく言動やふるまいは、ときに、ナイフのように心を切り裂きます。
なぜなら、脳は、「再び、人的侵害された」と認識してしまうからです。
暴力被害を受けると、被害者はなにに苦しむようになるのでしょうか?
それをまとめたのが、以下に示す『被害者の私にかかわるすべての人たちに、7つのお願い』です。
(被害者の私にかかわるすべての人たちに、7つのお願い)
* この「被害者の私にかかわるすべての人たちに、7つのお願い」は、被害者のアドボケーター(援助/代弁者)として、離婚調停(民事事件)や提訴・示談交渉(刑事事件)などで、加害者のDV/性暴力行為に対する証拠能力を高めるために、DV/性暴力被害を継続的な事実としての記録(事実経過)を書面化( 『レポート(被害の事実と後遺症、その経過)』のとりまとめ)し、この『レポート(被害の事実と後遺症、その経過)』の幾つかの記述について、その裏づけ・根拠となる情報として、『レポート(被害の事実と後遺症、その経過)』に添付する『別紙1 DV/性暴力被害者の私にかかわるすべての人たちに7つのお願い+α(32頁)』に記載しているものです。
この「はじめに。」では、『別紙1 DV/性暴力被害者の私にかかわるすべての人たちに7つのお願い+α(32頁)』に記載している記述をそのまま引用していることから、「である調」となっています。
なお、『別紙1 DV/性暴力被害者の私にかかわるすべての人たちに7つのお願い+α(32頁)』の他、『レポート(被害の事実と後遺症、その経過)』に添付するのは、『別紙2 性暴力、DVと面前DVの影響、後遺症としてのPTSD(268頁)』、『別紙3 DV行為による恐怖。その支配の構造と仕組みと加害者の属性と特性(150頁)』で、これらの『別紙1.2.3』の記載内容は、この『手引き(新版2訂)』から引用したものです。
日本では、他の先進諸国に比べて、「心が傷ついたといっても、見えないから、わからない。気持ちの問題だろ!」、「随分時間が経ったんだから、いい加減、忘れなさい(立ち直りなさい)!」などと“精神論”で語り、本気で、精神論の「気持ちでなんとかなる(できる)と思っている人が圧倒的に多い」という哀しい現実がある。
しかし、この考え方は間違っている。
この「間違い」による言動やふるまいは、「2次加害」として、被害を受けた当事者を追い詰め、自死に至らしめるなど、多くの悲劇を招いている。
DV(デートDV)や性暴力/性的虐待の被害者に対して、“精神論”を持ちだすなど、無知(知らないこと)からくる無理解は、偏見、差別を生み、2次加害・3次加害となって、DV(デートDV)や性暴力/性的虐待の被害者を追い詰めている。
「知らないこと」からくる無理解が生みだす“偏見”や“差別”という暴力は、時には、自死を選択させるほど、被害者を徹底的に追い詰める。
精神論で片づけてしまったり、人づてに聞いた話を鵜呑みにしてしまったりせずに、科学的な知識やデータにもとづき、「正しく知る」ことが重要である。
「正しく知る」ことは、時に、これまで正しいと信じていたこと、これまでの価値観を根底から覆すことになり(パラダイムシフト)、簡単には、受け入れられないかも知れない。
人は、無理強いされたと感じると、激しく抵抗する。
それでも、DV(デートDV)や性暴力/性的虐待の被害にあった当事者の“これから”の回復のためには、家族や親族、友人、上司や同僚、教師や同級生、そして、被害者とかかわる弁護士、医師や看護師、行政機関の職員の方々には、受け入れていただく必要がある。
直ぐに受け入れられなくとも、知ろうとする、理解しようとする姿勢を持っていただきたい。
1.暴力を受けた被害者に対し、「時間がすべてを癒してくれる。」、「すぐによい方向にむかうよ。」といった耳触りがよく、楽観的なことばは、その後の被害者の人生に、多くの悪影響を及ぼすことになることを知ってください。
2.多くの暴力被害者が、暴力による心の傷を長い間ひきずり、もがき続けていることそのものに強いストレスを抱えていることを知ってください。
そして、
3.多くの暴力被害者は、その苦しみの原因がおきたのが、まるで、昨日のように感じていることを知ってください。
4.多くの暴力被害者は、逆境を乗り越え、立ち直るのに必要なサポートを受けなければ、時間が過ぎてもなお、苦しみ続けることになることを知ってください。
つまり、「時間は、解決しない」ことを知ってください。
アリゾナ州立大学の研究チームによる最新の研究によって、「人には、それほどの自然治癒力はなく、自然災害や長期の失業など、人生を変えるようなできごとを経験した場合、回復するまでに予想以上の時間がかかる可能性がある。」、「人生にストレスをもたらす要因は、健康状態を大幅に悪化させることがあり、その状態は、数年にわたって続くこともあり得る。」とし、「時間が人を癒す効果はない」ことが確認されている。
いまだに、「ほとんどの人には、回復力がある」、「時間が解決してくれる」と信じられていることは、多くの暴力被害者が、より効果的な回復に必要な支援につながることを妨げてきた。
東日本大震災後の平成25年(2013年)4月以降、福島県相馬市で2,000人以上の被災者の診察を続けていた蟻塚亮二医師は、戦後68年経った平成25年(2013年)、日本で唯一地上戦が繰り広げられた沖縄戦の体験が、胎児を含めた各世代がのちに統合失調症やうつ病、不安や不眠をひき起こすとした「晩発性PTSD」の研究結果をまとめている。
蟻塚医師は、平成25年(2013年)4月に福島県南相馬に赴任する前、沖縄の病院で精神科医として9年間勤務していた。
そのとき、「終戦時に幼少で、68年経過した高齢者359人(平均年齢82歳)を対象に調べた結果、141人(39.28%)にPTSDの症状が認められた」と報告した。
それまで、沖縄の高齢患者が一般的なうつ病と診断されていたのは、「入眠困難(眠りに入れない)」や「中途覚醒(夜中に目が覚める)」という不眠ではなく、「夜中に何度も目が覚める不規則なタイプ」であったからである。
しかし、蟻塚医師は、不眠以外の症状を丹念に聴いていった結果、一般的なうつ病ではないと考えるようになった。
このとき、蟻塚医師が見つけたのは、アウシュビッツ収容所からの生還者の精神状態を調査した米国の研究者の論文であった。
その論文に紹介されている「奇妙な不眠」と酷似する症例を体験したことが、調査にとり組むきっかけとなった。
その結果、この調査まで一般的なうつ病と診断されていた沖縄の高齢患者の多くが、「沖縄戦に伴うPTSD」であることが次々に判明したのである。
この調査結果は、戦争・震災・DV(デートDV)・虐待・いじめ・ハラスメント・性暴力などでトラウマ(心的外傷)を負った人は、早期に適切な治療を開始し、逆境を乗り越え、立ち直るのに必要なサポートを受けなければ、時間が過ぎてもなお、苦しみ続けること、つまり、「時間は、解決しない」ことを裏づけている。
続けて、重要な指摘がある。
それは、「ストレス耐性」が、大人の脳(青年期後期(18-22歳)以降)と10歳代の脳で、顕著な違いを示すことである。
人は、ストレスを感じると、脳内で「THPホルモン」が分泌される。
この「THPホルモン」は、不安を抑えるブレーキの役割を果たす。
しかし、10歳代の脳では、「THPホルモン」は逆にアクセルとなり、不安を増幅させてしまう。
日本における15-19歳、20-24歳の死因の原因の第1位は「自殺」で、第2位が不慮の事故、25-29歳、30-34歳、35-39歳も死因の第1位は「自殺」で、第2位は癌である。
10歳代-20歳代前半の暴力被害者は、「時間が解決するどころか、その時間の経過とともに、自死に至るリスクが高くなる」のである。
子どものときに虐待を受け、その結果、あたり前のように死ぬ現実がある中で、生き残って成人に達した人たちのこと「アダルト・サバイバー(adult survivors)」という。
つまり、「アダルト・サバイバー」とは、虐待被害の中、なんとか生きて、思春期、成人期に達しながらも、かつてのトラウマ体験の影響を心身に色濃く残している人々のことである。
同様に、DV(デートDV)、レイプなどの性暴力などの暴力被害後、その後遺症に苦しみながら生き残った人たちを「サバイバー」という。
「時間が解決する前に、自死に至るリスクが高くなる」こと、「なんとか生き残ったとしても(時間が経っても)、苦しみは、消えない」ことを知ってください。
加えて、
5.「このころまでに回復している」との時間枠を定めるのは、危険な行為であることを知ってください。
被害者がなかなか回復しないと感じたとき、自分自身を厳しく批判してしまう可能性が非常に高くなり、また、同じような体験をした人たちも長期にわたって苦しんでいることに対しても共感できなくなってしまう危険性がある。
回復力(レジリエンス)を高めるために、計画的なサポートを受けることで、現実的に考え、感情をコントロールし、生産的な行動を心がけることが、困難を乗り越え、回復することに向けての“鍵”となり、結果として、あらゆるストレス要因に対しての抵抗力を高めることができる。
このことが、暴力被害者の心の傷を癒す能力を高めることを知ってください。
6.適切な治療と適切なサポートを受ける機会を逸した暴力被害者の多くは、暴力による心の傷を長い間ひきずり、もがき続けていることそのものにさえ強いストレスがかかることを知ってください。
アメリカ合衆国オレゴン州のビルズボロ警察が、「DV被害を受けている職員のうち74%が、仕事中に加害者からハラスメントを受けている」、「DV被害者の28%が仕事を早退したことがある」、「DV被害者の56%が仕事に遅刻したことがある」、「DV被害者の96%が、その暴力・虐待行為によって仕事に支障をきたした経験がある」と、DV被害が、DV被害者の仕事の効果性や効率性を損なうなど、職場においてもDV被害の影響が及んでいる状況をまとめている。
日本社会では、職場における社員、学校における生徒・学生のDV(デートDV)被害や性暴力被害の影響に対する意識は、皆無といえる。
DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、ハラスメントなど暴力被害によるPTSDやうつ病、パニック障害の発症は、「傷害罪(刑法204条)」を適用できる「加療を要する傷害を負う」もので、その精神的苦痛は、非常に重い。
例えば、性暴力被害に適用し得る「強制性交等罪(刑法177条)」、「強制性交等致傷罪(刑法181条2項)」、「強制性交等致死罪(刑法181条2項)」、「強制わいせつ罪(刑法176条)」、「強制わいせつ致傷罪(刑法181条1項)」、被害者が18歳以下の児童であるときは「児童福祉法違反(34条1項6号、60条1項)」に加え、「リベンジポルノ被害防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)」、都道府県の「迷惑防止条例違反」とは別に、その被害によりPTSDやうつ病、パニック障害などを発症したときには「傷害罪(刑法204条)」が適用でき、これらの「疾患を発症した」と診断がされた日が公訴時効の起算点となる。
そして、DV(デートDV)、性暴力、いじめ、ハラスメントなど暴力被害による後遺症としてのPTSDやうつ病、パニック障害の発症は、勉強や仕事のパフォーマンスを著しく低下させ、家族、友人、教師、同僚、上司などとの対人関係を壊しかねない。
『別紙2』の「1.PTSDの症状(解説)」「2.被虐待体験、慢性反復的な暴力被害による脳の傷の視覚化(解説)」「3.虐待被害が子どもの心身の成長に与えるダメージ 」「4.面前DV=心理的虐待被害を受けた子どもの心身のダメージ」「5.C-PTSD、解離性障害(解説)」「6.アダルト・チルドレン。思春期・青年期の訪れとともに」のそれぞれの章で詳述しているように、慢性反復的(常態的)なトラウマ体験となる交際相手や配偶者、親、近親者による「同意のない性行為、意に反する性行為の強要、望まない性行為の強要」や「性的虐待」、面前DV=心理的虐待、DV(デートDV)、いじめ、ハラスメントなど暴力被害は、後遺症として、うつ症状やパニック症状を伴う「PTSD」の発症、「解離性障害」、「不安障害」、「適応障害」、「うつ病」の発症、「身体化障害」として、頭痛、背部痛などの「慢性疼痛」、「食欲不振」や「体重減少」、「機能性消化器疾患」、「高血圧」、「免疫状態の低下」の症状をもたらし、「自殺傾向」を示す。
DV(デートDV)、児童虐待、性暴力などの被害者の多くは、こうした後遺症に長く苦しみ続け、学校に通学できなくなったり、仕事を続けられなくなったり、職に就くことができなかったりする問題と直結する。
7.暴力被害者が、適切な治療と適切なサポートを受けるためには、安全で、安心できる環境が必要不可欠であることを知ってください。
暴力被害者にとって、安全で、安心できる環境は、暴力被害者の回復を信じて、適切な距離感で見守られていることである。
距離が近すぎると、ときに脅威と感じる。
不安が強まり、苛立ち、怒りをぶつける。
頼り切ると、なにもできない自分が情けなく、申し訳なさで消えたい衝動に襲われる。
距離が遠すぎると、見放されていると感じ、孤立感が強まる。
自暴自棄に陥り、自傷行為、依存行為に走るリスクが高まる。
近すぎず、遠すぎず、加減のいい距離感が必要である。
加減のいい距離感は、暴力被害者抜きで判断することなく、暴力被害者の意志を尊重することが重要である。
そして、暴力被害者に「加減のいい距離感で接する」ことは、簡単なことではないことを知ってください。
特に、暴力被害者と「加減のいい距離感で接する」ことを求められる被害者家族、友人、教師、上司や同僚、医師や看護師、行政機関の職員、弁護士は、被害者の伴走者の一役を担うことを知ってください。
暴力被害者は、安全で、安心できる環境で、長期間にわたるPTSD、その併発症としてのうつ病などの治療に加え、伴走者といえるサポートを必要としている。
暴力被害者の伴走者には、専門的な知識と幾つかのトレーニングが必要となる。
長期間にわたるPTSDと、その併発症のうつ病の治療にかかる「治療費」は、暴力被害者のこれからの人生に大きな負担になることを知ってください。
差別・排除、DV(デートDV)、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力被害は、誰にもおきること、身近で、深刻な問題です。
人が、差別・排除、DV(デートDV)、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力被害にあったとき、その被害が、ショッキングなできごとであればあるほど、向き合えないほどツラい現実であればあるほど、人は、「あのDV(デートDV)、性暴力なんて、なかったんだ」、「あの人は、そんなことをするはずがない」と被害(事件)そのものを否定したり、「それほどたいしたことじゃなかった」と被害(事件)を矮小化したりします。
この「なかったことにする(否認)」は、「防衛機制」と呼ばれるものです。
被害者の心に、こうした“否認”のフィルターをかけずに、「あれはDV(デートDV)だった」、「あれは虐待だった」、「あれは性暴力だった」、「あれはハラスメントだった」と気づくには、典型的な被害者像を知ることが必要です。
なぜなら、典型的な被害者は、私たちが、日常の世界で想像している被害者像から大きくかけ離れているからです。
重要なことは、「深く傷ついた人がとる行動のリアル」を知ることです。
最後に。
DV被害者支援の現場では、「ツラい、苦しい、哀しい、やるせない」、「助けて欲しい」、「でも、人に頼ることはできない。だって、どうしたらいいのか知らない」、「本当に、信じて、頼っていいのだろうか?」、「また裏切られないだろうか?」と葛藤し、身構えているDV被害者には、安全を担保することで、安心して相談でき、適切な支援を受けられ、速やかに治療につながることが重要と考えます。
しかし近年、女性と子どもが獲得してきた権利(法などの整備を含む)を疎ましく、鬱陶しく、忌々しく思っている“保守的”な価値観の持ち主たちが、その「権利」を奪い、かつての権威(特権)をとり戻そうと目論む人たちのパワーが目立ってきています。
第2次世界大戦の終戦から3年3ヶ月、国際連合が「世界人権宣言」を採択し、その宣言にもとづく9つの条約を批准しながらも、国民に人権意識を醸成しようとはせず、政治政府が「富国強兵」「国民皆兵」を成し遂げるために国をあげて構築した“保守的”な価値観は、終戦後77年経ったいまも日本社会の主流であり続けています。
特に、国として、126年にわたり「懲戒権(民法822条)」と認めてきたことで、5-6世代の子育てで、しつけ(教育)と称する体罰(虐待行為)はひき継がれてきました。
その日本社会で、いま、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力行為が大きく減少する要素を見つけだすことができません。
いまから11年前、東日本大震災のあった平成23年(2011年)1月に受けたDV事案の被害者とのやりとりで、私は、「暴力被害を受けずに育った人はどのくらいいるのですか?」と訊かれ、「3-4割、いるかいないかです。」と応じたことがあります。
平成20年(2008年)の1億2,808万人をピークに減少に転じ、第2次ベビーブーム(昭和46年(1971年)-同49年(1974年))後の昭和50年(1975年)以降、出生数は減少し続け、平成28年(2016年)の出生数は97万6979人と明治32年(1899年)に統計をとりはじめてはじめて100人を割り込み、さらに、令和4年(2022年)の出生数は79万9728人で、はじめて80万人を割り込みました。
死亡者数は、過去最多で158万2033人となり、人口の自然減は78万2305人、これは、政令指定都市の静岡県浜松市の人口78万3573人(令和元年(2019年)5月1日現在)が消滅するほどの人口減です。
人口が減少し、出生数が減り中で、DV(デートDV)相談件数、児童虐待相談対応件数は増加し続けていることは、人口対比で考えると、DV/児童虐待のある家庭の比率は増加し続けていることになります。
このことは、DV/児童虐待のない家庭は年々少なくなることを意味します。
つまり、虐待(面前DV)被害によるさまざまな影響を受ける子ども、DV被害の後遺症を抱えた親と生活する子どもが増加し続けることは、当然、その後の人生において、その十字架を背負い続ける人(被虐待体験をしてきた人)が増え続けることになります。
日本は、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力(人権)問題に対し、先進的にとり組んできた欧米諸国から50年-25年ほど遅れています。
日本社会が、これらの暴力行為を減らす舵を切るには、この深刻な事態を受け入れることが必要で、見て見ぬふりをして舵を切らなければ、増加傾向に歯止めをかけることはできません。
この16年間は、その瀬戸際に立たされた16年でした。
これらの暴力行為を防ぎ、加害と被害にかかわる人を減らすには、第1に、a)家庭内における「しつけ(教育)と称する体罰」をはじめとする虐待行為、b)学校園、塾や習いごと、サークル活動などにおける教師や指導者などによる「体罰」や性暴力、c)生徒間の「いじめ」、教師による生徒に対する「いじめ」、d)職場などにおける「ハラスメント」などの暴力行為に対し、ア)被害を早期に発見し、速やかに介入し、治療につなげる、イ)加害行為に対しては見て見ぬふりをせず厳格に対処し、ウ)その暴力行為があった家庭、学校園、職場などに対して直ちに介入し、適切な対応と厳格な改善策を講じさせるなどを、エ)国の責任で、関係機関を連携させる仕組み(社会保障制度の見直し、大改革を含めて)としてつくりあげることが必要です。
そして、第2に、いまの児童と親、祖父母、つまり、3世代に対し、国のとり組みとして道徳教育ではなく、直ちに「人権教育」を実施することです。
ここには、時間的な猶予は存在しません。
しかし、第1の厳格な対応とそれを支える仕組みができたり、第2の人権意識が国民に醸成されたりしても、近年、女性と子どもが獲得してきた権利などを一瞬で破壊するのが、戦争であり、自然災害・環境破壊による飢餓・飢饉、貧困です。
第2次世界大戦後に長く続いた東西冷戦下では、地政学的に、ソビエト連邦(現ロシア)、北朝鮮、中華民国、ベトナム、ラオスなどがあり、ヨーロッパ(東欧と西欧、中欧)の要所のトルコと同様に、アジア太平洋の要所は、フィリピン、台湾、韓国、日本で、その状況は、いまも変わりません。
いまから21年前の2001年(平成13年)9月11日のアメリカ同時多発テロ以降、日本政府は、『テロ対策特別措置法』を制定し、自衛隊をインド洋での補給艦による給油活動を実施し、平成15年(2003年)には、『イラク人道復興支援特別措置法』を制定し、自衛隊をイラクに派遣し、イラクでの人道復興支援活動に従事させました。
こうした自衛隊の海外での活動が広がる中で、平成27年(2015年)、『安全保障関連法』を成立させ、集団的自衛権の行使の一部を容認するなど、近年、日本政府は確実に軍事化を進めてきました。
一方で、自衛隊の海外での活動が広がる中で、派遣先からの帰還兵(自衛隊員)、東日本大震災の津波被害後の遭難活動に従事した自衛隊員(他に消防隊員など)の多くが、アメリカ軍や多国籍軍の帰還兵と同様に、PTSDを発症し、その併発症としてのうつ病を起因とする自殺者がでています。
戦争・紛争に自衛隊を派遣する機会が多くなることは、PTSDを発症する帰還兵(自衛隊員)が多くなり、その家族などがDV(デートDV)、児童虐待、性暴力に巻き込まれる機会が増えるリスクが高くなります。
日本政府は、再び、軍備増強を目指し、行使・保持する防衛力を必要最小限とする「専守防衛」を否定し、抑止力としての反撃能力(敵基地攻撃能力)保有することを明記した「安全保障関連3文書」と閣議決定しましたが、日本には、54基(福島第一、第二原発を含む)の原子力発電所、131ヶ所米軍基地、約160ヶ所の自衛隊の駐屯地があり、これらが標的(攻撃目標)となると、幾ら追撃システムなどの防衛力を高めたとしても、近距離から複数の弾道ミサイルの攻撃を受ければ防ぎようがなく、攻撃を受けると被害は甚大となります。
つまり、日本は、昭和30年(1955年)、『原子力基本法』が成立し、いまから56年前の昭和41年(1966年)、商業用原発として、日本原電の東海発電所が茨城県那珂郡東海村に建設し、運転を開始し、昭和48年(1973年)の第1次オイルショック、昭和53年(1978年)の第2次オイルショック以降、「エネルギーの安定供給」が重要な国家課題となる中、昭和48年(1973年)、首相の田中角栄(当時)は、国会で「原子力を重大な決意をもって促進をいたしたい。」と述べ、昭和49年(1974年)、「原子力発電所の立地地域への交付金を定める法律」を整備したことで、原子力発電所建設が一気に進みました。
この間、1962年(昭和37年)10月、ソ連がキューバにミサイル基地建設を進めた「キューバ危機」が起きました。
このとき、ソ連がキューバに配備しようとしたミサイルは、射程約1800kmの準中距離弾道ミサイル「R-12」、射程約4000kmの中距離弾道ミサイル「R-14」で、ともに、広島に投下された原爆の60倍以上の1メガトンの爆発力を持つ核弾頭を装着できるもので、配備されたときには、ハワイ州とアラスカ州を除く米本土のほぼ全域を攻撃することが可能でした。
樺太(その海域を含む)がソ連の領土であり、北朝鮮、中華民国(いずれも海域を含む)との距離を踏まえると、この時点(太平洋戦争終結後17年)で、日本は、攻撃目標となり得る原子力発電所の建設の有無にかかわらず、「専守防衛」すら成り立たない国家になっています。
多くの原子力発電所が建設され、運用をはじめて以降は、日本は専守防衛だろうが、反撃能力を持とうが、いったんことが起これば火だるま、あのときのように焼け野原になります。
つまり、日本は、「専守防衛」は不可能な国家、「反撃能力」を持つことはあり得ない国家で、地政学的に東西冷戦時もいまも、地政学的に東側の盟主のアメリカの要所でしかありません。
ロシアがウクライナに侵攻したように、中国が台湾に侵攻したときには、「抑止力としての反撃能力(敵基地攻撃能力)保有する」ことなど意味がなく、米軍基地、自衛隊の駐屯地などあらゆる土地が攻撃のターゲットとなり、再び、戦火に巻き込まれ、海路は閉ざされ、食料、燃料などあらゆる物資がなくなります。
また、戦時下では、化学物質による「環境汚染」は深刻になります。
大気汚染、水質汚染などは、発達障害の発症、不妊の原因となっているなど人体や生態系に深刻な影響を及ぼし、温暖化とともに「自然破壊」を促進させ、気候変動は、自然災害をひきおこすだけではなく、生物の生存環境に影響を及ぼし、それは、食料・水源破壊につながり、結果、貧困・飢饉をもたらします。
近年、日本において、多くの被災者が長期間の避難生活を余儀なくされた自然災害の典型例は、いまから27年前の平成7年(1995年)1月17日の阪神淡路大震災、いまから11年前の平成23年(2011年)3月11日の東日本大震災、いまから6年前の平成28年(2016年)4月14日の熊本地震です。
これらの自然災害後の被災地では、殺害を伴うような略奪行為はおきませんでしたが、避難先で生活をしている人たちの全壊、半壊の家屋、コミュニティで避難し住民がいなくなった地域の家屋での窃盗被害は相次ぎました。
そして、自然災害後の被災地では、差別・排除(避難所でのADHDやアスペルガー症候群などの発達障害の子どものいる家庭、視覚や聴覚、肢体に傷害のある人、ペットを飼っている人、乳幼児の子どものいる母親、女性、老人などの弱者に対して)、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、自殺が、顕著に増加しました。
阪神淡路大震災における避難所・被災地でおきた数々の性暴力、女性に対する配慮のない避難生活などの「負の教訓」は、その後の東日本大震災では生かし切れず、熊本地震で漸く生かされはじめました。
しかし、こうした大きな自然災害で被害が増加する差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力などの暴力被害に対する早期発見、早期介入、そして、速やかな治療につなげたり、自殺者の家族などに対する心のケアやフォローにつなげたりすることに対する重要性は見過ごされてきました。
平成7年(1995年)1月17日の阪神淡路大震災から19年経過した平成26年(2014年)、神戸では、過去5年で心理的虐待(面前DVを含む)での通告は25倍に増加しました。
平成26年(2014年)、阪神淡路大震災当時3歳だった保育園(幼稚園)児は22歳になり、当時6歳だった小学校1年生は25歳になり、当時12歳だった中学校1年生は31歳になっています。
つまり、神戸では、大震災後に増加した両親間のDVを見たり、虐待を受けたりして育った子どもたちが、結婚し、親となりはじめた時期に、再び、DVと児童虐待が顕著に増加しました。
以降、神戸では、DV、児童虐待件数は増え続けています。
この事実は、当時の被災者に対する心のケアなどのアプローチがなされなかったこと、暴力被害者に対して、早期発見、早期介入、そして、速やかな治療につなげることができなかったことを意味しています。
阪神淡路大震災から16年後におきた東日本大震災では、原発事故により避難生活を余儀された人々も多く、被爆した子どもに対する甲状腺検査などが継続され、子どもに対する心のケアにもフォーカスされました。
十分とはいえないものの、東日本大震災(原発事故)から10年後、令和3年(2021年)4月、福島県福島市(福島学院大学内)に「ふくしま子どもの心のケアセンター」は、東日本大震災後の福島の子どもたちへの支援活動を目的として設立され、震災後の発達の気になる子どもとその保護者への支援、地域の母子保健体制整備に関連するサポート、ペアレントプログラムなどによる保護者支援などを実施していることは、ひとつの成果です。
重要な視点は、大きな自然災害に巻き込まれた被災者のストレスは、子どもの発達に影響を及ぼすという“前提”に立ったとり組みになっている、つまり、この事実から目を背けなかったことです。
ただし問題は、子どもやその保護者をケアしたり、サポートしたりできる絶対数が足りないということです。
これらの問題は、「Ⅰ-A-2-(2)PTSDの症状(攻撃防御の機能不全)に端を発した暴力 -東日本大震災後の児童虐待とDVの増加。戦争体験によるPTSDの発症から学べることはなにか-」で詳述していますが、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力(人権)問題を考えるうえでは、避けて通ることができない重要な視点です。
重要なことは、これらの問題に対し、ひとごと(他人ごと)とではなく、自分ごとと認識することです。
この『手引き(新版2訂)』の“事例”を通じて示される「典型的な被害者像」、そして、「深く傷ついた人がとる行動のリアル」が、ひとりでも多くの被虐待体験をしてきた人、DV(デートDV)、性暴力などの暴力被害者、そして、暴力被害を受けた人の親やきょうだい、親族、いま(これから)の配偶者、いま(これから)の交際相手、友人、クラブ活動や習いごとの仲間、同僚、上司、福祉行政に携わる職員、学校園の教職員、医師、看護師、カウンセラー、警察官、弁護士、調停委員、裁判所調査官など夫婦関係調整(離婚)調停、監護権者指定調停(審判)に携わる司法関係者、年齢、性別、職業など関係なく、すべての人たちに届くことを切に願います。
平成25年11日12日(改訂:平成28年2月28日/新版:同年10月10日/新版2訂:令和5年 月 日)
DV被害者支援室poco a poco 代表 庄司薫
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
