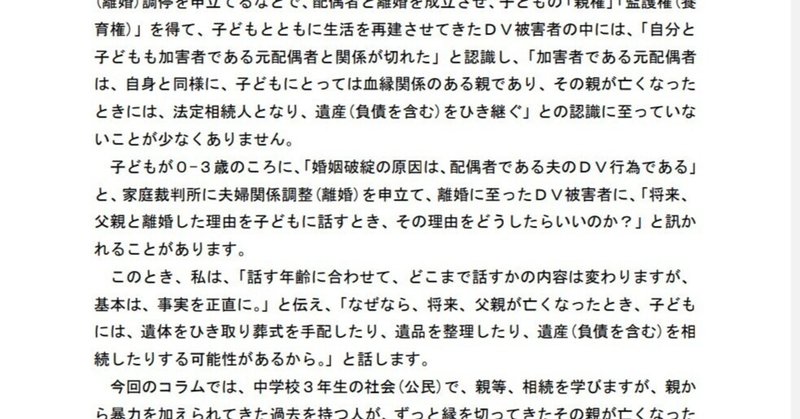
(コラム-13) 被虐待体験をしてきた子どもが、ずっと音信不通だった親の遺体のひき取らず、遺品の整理をせず、相続を放棄するための手続き
「婚姻破綻の原因は配偶者からのDV行為である」と、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停を申立てるなどで、配偶者と離婚を成立させ、子どもの「親権」「監護権(養育権)」を得て、子どもとともに生活を再建させてきたDV被害者の中には、「自分と子どもも加害者である元配偶者と関係が切れた」と認識し、「加害者である元配偶者は、自身と同様に、子どもにとっては血縁関係のある親であり、その親が亡くなったときには、法定相続人となり、遺産(負債を含む)をひき継ぐ」との認識に至っていないことが少なくありません。
子どもが0-3歳のころに、「婚姻破綻の原因は、配偶者である夫のDV行為である」と、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)を申立て、離婚に至ったDV被害者に、「将来、父親と離婚した理由を子どもに話すとき、その理由をどうしたらいいのか?」と訊かれることがあります。
このとき、私は、「話す年齢に合わせて、どこまで話すかの内容は変わりますが、基本は、事実を正直に。」と伝え、「なぜなら、将来、父親が亡くなったとき、子どもには、遺体をひき取り葬式を手配したり、遺品を整理したり、遺産(負債を含む)を相続したりする可能性があるから。」と話します。
今回のコラムでは、中学校3年生の社会(公民)で、親等、相続を学びますが、親から暴力を加えられてきた過去を持つ人が、ずっと縁を切ってきたその親が亡くなったときに発生する相続について考えます。
したがって、このコラムのテーマは、第1に、被相続人が亡くなったあと、法定相続人にはなにが求められ、なにを相続することになるのかなどを知ること、第2に、被相続人である親から被虐待体験のある相続人が、a)被相続人の遺体のひき取り、埋葬したり、b)遺品の整理をしたり、c)遺産を相続し、相続税を支払ったりしたくないときにはその方法があることを知ることです。
特に、第2のテーマである「被相続人である親から被虐待体験のある相続人」という“特殊事情”にフォーカスし、親の死に伴う子どもの相続の発生について考えていきます。
なお、第1のテーマについては、「別紙2.被相続人の死後、相続人がすること」、「別紙3.被相続人としての基礎知識」としてまとめています。
これらは、親(被相続人)が亡くなったあと、その家族は、葬式の手配、保険証の返却、年金、銀行の解約、不動産の名義変更、財産調査、相続人の確定、遺産分割、相続税の支払いなどさまざまな手続きをしなければなりません。
そのための基礎知識です。
1.
親(以下、被相続人)が亡くなってから埋葬(火葬)までの流れについて、幾つかの要件により異なるそのプロセスを見ていきたいと思います。
その要件とは、以下のようなものです。
第1に、いま(これから)、被相続人がどこに住んでいるかです。
それは、a)被相続人が、配偶者や子どもと同居している、b)被相続人がひとり住まいをしている、c)被相続人が病院に入院し、治療を受けている、d)被相続人が高齢者向け介護施設に入居している、e)被相続人が、上記以外の場所にいる(で生活している)などです。
この住居は、被相続人がどこで亡くなり、誰がその死を見届けるのか、あるいは、誰がその遺体を発見するのかにかかわります。
また、ア)誰が被相続人の遺体をひき取り、埋葬(火葬)を行うのか、イ)誰が、被相続人の遺品(財産)の整理を行うのか、ウ)誰が、被相続人が生前に利用していたさまざまサービスの解約などの手続きを行うのかにかかわってきます。
第2に、被相続人に配偶者、子ども、親やきょうだいがいるのか、いないのかです。
これは、第1の4文にもかかわり、加えて、被相続人の遺産(財産)の相続人がいるのか、いないのかにかかわります。
それは、生前の被相続人とこれらの相続人とが、良好な関係性を築いていようが、長く疎遠になっていたり、音信不通になっていたりしていようが、血縁関係がある限り、被相続人の法定相続人(直系尊属の2親等)、扶養義務者(3親等の叔父・叔母、甥、姪)となります。
例えば、ⅰ)被相続人が、「離婚した配偶者との間にひとり子どもがいるが、もう30年ほど会っていない。どこで、なにをしているのかも知らない。」と話していたり、ⅱ)被相続人の相続人となる子どもが、「母は父からずっと暴力(DV行為)を受けていた。その暴力から逃れるために、母は、幼い私を連れてシェルターに入り、知らない土地で、苦労して私を育ててくれた。父のことは、父とも思っていないし、会うつもりもない。」と思っていたり、ⅲ)被相続人の相続人となる子どもが、「私に虐待を繰り返してきた親は殺してやりたいほど憎んでいる。親のきょうだい、いとことは会ったこともないし、そもそもいるのかも知らない。」と怒りに満ちていたりしても、それぞれの考えや思いは関係なく、被相続人の法定相続人(ⅰとⅱ)、あるいは、扶養義務者(ⅲ)となります。
「身寄りはいない」と話していたり、親族や子どもと音信不通であったりする被相続人が第1のa)b)c)d)e)のどこで亡くなっても、被相続人の遺体をひきとるなど緊急連絡ができないときには、被相続人の死亡を確認した病院や所轄の警察署は、被相続人の居住していた「市区町村役場」に、被相続人が「死亡した」ことを連絡します。
なぜなら、ひとつは、被相続人を「戸籍」から除籍するため、もうひとつは、「葬儀社」に連絡し、「葬儀(火葬)」を行うために必要不可欠だからです。
そして、被相続人が「死亡した」との連絡を受けた市区町村役場は、「戸籍」からの除籍に加え、被相続人が出生から死亡までのすべての「戸籍謄本」などを調査し、法定相続人がいないのか、いるのかを調査し、『別紙2.被相続人としての基礎知識』の1-(2)に該当する第1順位から第3順位に該当する法定相続人が見つかったときには、必ず、その法定相続人に連絡をし、遺体のひき取りを求めます。
このとき、連絡を受けた法定相続人には、2つの選択肢があります。
ひとつは、「遺体をひき取る」と応じ、葬儀を行い、遺品の整理をすることです。
もうひとつは、遺体のひき取りを拒否する」と回答し、葬儀を行ったり、遺品の整理をしたりしない意志を示すことです。
ただし、上記「遺品の整理(ひき取り、処分など)」は、被相続人の財産を相続することにつながります。
なぜなら、遺品は、被相続人が所有していた物、つまり、財産だからです。
つまり、「“形見分け”として、被相続人が身に着けていた物(時計や指輪、宝石、貴金属など)を幾つか欲しいが、遺産を相続はしない。」という論理は成り立ちません。
ここで気をつけなければならないことは、第1に、「遺体のひき取りは遺産相続と別問題」ということ、第2に、市区町村役場や警察から「被相続人が亡くなった」ことを知らせる連絡があったときが、法定相続人には相続が発生したことになるということです。
(1) 遺体のひき取りを拒否したとき
法定相続人が、被相続人の遺体のひき取りを拒否したときは、市区町村が火葬費用を立て替え、被相続人の遺産から支払い、不足がでたとき、遺体のひき取りの有無は関係なく、法定相続人にその費用が請求されます。
その請求は、法定相続人の第1順位、第2順位、第3順位、3親等の親族(扶養義務者)の順となり、すべての法定相続人、扶養義務者が、費用の支払いが困難であるとき、最終的に、市区町村が負担することになります。
(2) 遺産放棄するとき
法定相続人が、被相続人から受ける“遺産(財産)”は、ア)現金、イ)銀行預金、ウ)不動産(土地建物)、エ)車、オ)株式(有価証券)、カ)債権、キ)投資信託、ク)生命保険、ケ)美術品、コ)貴金属、サ)仮想通貨、シ)各種ローン、ス)負債(借金)などがあります。
注意が必要なのは、シ)各種ローン、ス)負債(借金)も法定相続人が相続する遺産(財産)に含まれることです。
法定相続人が、被相続人の遺産(財産)を相続する意志がないときには、『別紙3.被相続人の死後、相続人がすること』の4-③のとおり、「相続のあることを知った日から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをしなければならないということです。
つまり、上記ⅰ)ⅱ)ⅲ)のようなケースであっても、被相続人に負債(借金)があり、3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをしなければ、法定相続人は、被相続人の負債(借金)を弁済しなければならなくなります。
加えて、法定相続人は、被相続人が居住していた家の「退去費用」、つまり、家財やゴミの処分などの遺品整理費、壁紙の張り替えや床の修復などの原状回復費、1ヶ月分の家賃などを負担することになります。
なぜなら、生前に被相続人が着ていた衣服、使用していた家具や携帯電話などもすべて遺品(財産)になるからです。
では次に、市区町村役場から連絡を受けた「被相続人の遺体はひき取らない。」と応じた相続人に対し、その後、市区町村役場が火葬費用など請求する法的根拠を説明します。
2.
「自分には、身寄りがない」と話し、ひとり住まい(ホームレス、生活保護受給者を含む)の被相続人が亡くなったとき、市区町村役場は、「行旅病人及行旅死亡人取扱法(住所、居所もしくは氏名が知れず、かつ、ひき取る者がいない死亡人は行旅死亡人(1条2項))」に則り、被相続人の遺体をひき取り、遺留金品をひき継ぎます。
その後、ⅰ)市区町村役場で「戸籍謄本」などの調査で直系尊属(法定相続人)が明らかになり、連絡した法定相続人が、「遺体と遺留金品のひき取りを拒否した」ときには、『行旅病人及行旅死亡人取扱法』の9条、『戸籍法』の第92条第3項にもとづいて火葬手続きをし、ⅱ)『墓地埋葬法』の9条(死体の埋葬、または、火葬を行う者がないとき、または、判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない)、同4条1項の規定により、都道府県知事の許可を受けた墓地で、無縁仏として埋葬します。
このときの費用、つまり、市区町村が火葬等の費用を肩代わりしたときは、『行旅病人及行旅死亡人取扱法』の第7条と第11条にもとづき、被相続人の遺留金品を火葬等に要した費用に充当します。
遺留金品を充当しても、十分に費用の弁償を得ることができないときは、『行旅病人及行旅死亡人取扱法』の第11条にもとづき、被相続人の相続人、扶養義務者の順に費用の弁償を求めます。
「扶養義務」とは、『民法第877条第1項』で、直系血族、および、兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があると定められ、『民法第752条』で、夫婦の相互協力扶助義務の一環として扶養義務があると解され、加えて、『民法第877条第2項』で、直系血族、および、兄弟姉妹が揃って経済的に困窮しているなど特別の事情があるときには、家庭裁判所の審判により、被扶養者と3親等内の親族に対しても、扶養の義務が課されるとあることから、「扶養義務者」は、直系血族(直系尊属)、兄弟姉妹、配偶者の相続人に加え、3親等以内の親族となります。
そのため、相続人とは別に、扶養義務者が加えられています。
例えば、亡くなった被相続人が生活保護を受給していたときは、『生活保護法』の第18条にもとづき、葬祭等に要した費用を生活保護法の「葬祭扶助」として支給し、同法76条では、「同法第18条第2項にもとづき「葬祭扶助費」を支給したときは、亡くなった方の遺留の金銭や有価証券など(以上、遺留金品)を葬祭扶助費に充当し、なお足りないときは、その方の遺留の物品(遺留物品)を売却してその代金を充当することができる」とあります。
そして、市区町村は、法定相続人や扶養義務者からその費用の弁償を得ることができなかったときは、『行旅病人及行旅死亡人取扱法』の第15条にもとづき、直ちにその遺留物品を売却し、それでもなお、十分に費用の弁償を得ることができないときは、市区町村が繰替支弁し、都道府県に不足分の負担を求めることになります(指定都市・中核市は、自市で負担)。
つまり、法定相続人の第1順位、第2順位、第3順位、3親等の親族(扶養義務者)の順となり、すべての法定相続人、扶養義務者が、費用の支払いが困難であるとき、最終的に、市区町村が負担することになります。
では、このコラムの主要テーマ、第2に、被相続人である親から被虐待体験のある相続人が、a)被相続人の遺体のひき取り、埋葬したり、b)遺品の整理をしたり、c)遺産を相続し、相続税を支払ったりしたくないときの方法について考えていきます。
3.
上記、第2のⅱ)に該当する親から被虐待体験をしてきた人は、主に次の3パターンが考えられます。
ア)その家庭環境で虐待行為(面前DV、親がアルコールや薬物、ギャンブルの依存者、親が新興宗教やカルト、スピリチュアルの傾倒者などを含む)に耐え続け、成長した人、イ)児童虐待事案として、児童相談所に保護され、18歳まで児童養護施設で生活し、その後、自立した人、また、ウ)一方の親が、一方の親のDV行為から逃れるために、DV被害を受けていた一方の親とともに家をでて、『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下、配偶者暴力防止法)』に準じ“一時保護”として母子生活支援施設(行政のシェルター)を経たり、実家に帰ったりして、生活の再建する中で暮らし、成長してきた人(自身に対する虐待行為に加え、両親間のDV行為を見たり、聴いたり、察したりしてきた(面前DV)心理的虐待を含む)などが該当します。
その被虐待体験(逆境的小児期体験)をしてきた人の中には、自分、自分と生活をともにしてきた一方の親に暴力を加えてきた一方の親、あるいは、双方の親に対し、いっさいのかかわりを避け続け、怒りや憎しみの感情を抱き続けている人も少なくありません。
ところが、「いっさいのかかわりを断ち切ってきた自分に加害行為を繰り返してきた被相続人に、配偶者(再婚して)やその配偶者などとの間に子どもがいない、いわゆる身寄りがない状態で亡くなった」とき、突然、市区町村役場や警察から「あなたの親が亡くなりました。遺体をひき取って欲しい。」と連絡が入ります。
この事態を予期していないとかなりのショック、心が揺さぶられることになります。
なぜ、市区町村役場や警察から連絡がはいるのでしょうか?
それは、被相続人から見て、子どもは第1親等にあたり、法定相続人の第1順位に該当するからです。
例えば、生活をともにしてきた親は、「婚姻破綻の原因は、配偶者からのDV行為である」として離婚が成立した一方の配偶者(子どもにとって親)とは、法律上、縁が切れますが、子どもは、法律上、暴力行為を加えていた親との関係は切れません。
それは、離婚成立時、暴力被害を受けてきた親が「親権」「監護権(養育権)」を得ていたとしても、血縁関係にある事実には関係ありません。
つまり、血縁関係にある子どもや親、兄弟姉妹などは、『別紙1.被相続人としての基礎知識』の1-(2)のとおり、被相続人の法定相続人になることから、市区町村や警察から連絡が入ります。
その被相続人の子どもは、法定相続人の第1順位であることから、最初に、連絡が入ります。
人が亡くなると、遺族は、医師が作成した「死亡診断書(身元が不明のときは、「遺体検案書」を作成し、警察に連絡)」を受け取り、市区町村役場に「死亡届」を提出し、「火葬許可証」をもらい、葬儀社に連絡し、埋葬(火葬)の手続きをします。
さらに、人が亡くなると、『別紙3.被相続人の死後、相続人がすること』のとおり、葬式の手配、保険証の返却、年金、銀行の解約、不動産の名義変更、財産調査、相続人の確定、遺産分割、相続税の支払いなど、さまざまな手続きが必要となります。
身寄りがない人が亡くなると、その人が居住していた市区町村が、遺体のひき取りと遺留金品(その人の財産)をひき継ぎますが、市区町村役場では、遺体をひき取り、埋葬し、遺留金品を受け取る(相続する)法定相続人を「戸籍謄本調査」などで探します。
その結果、生存している法定相続人が見つかったときには、連絡し、遺体などのひき取りをお願いします。
以上のように、人が亡くなると、a)誰が被相続人の遺体をひき取り、埋葬(火葬)を行うのか、b)誰が、被相続人の遺品(財産)の整理を行うのか、c)誰が、被相続人が生前に利用していたさまざまサービスの解約などの手続きを行うのかという事態が生じます。
つまり、被相続人の法定相続人の第1順位にあたる子どもには、必ず、このa)b)c)という事態が生じます。
そこで、縁を切り、疎遠となっている被相続人がいる被虐待体験(逆境的小児期体験)をしている人は、心の準備として、予め市区町村役場や警察からこの突然の連絡がきたときにどうするのか、あるいは、どうすることができるのかを知っておくことがとても大切です。
なぜなら、この突然の連絡がきてから3ヶ月以上放っておくと、生前の被相続人に負債(借金)があるとき、その負債(借金)を相続することになり、弁済しなければならなくなるからです。
縁を切り、疎遠であった被相続人の遺体や遺留金品(財産、預金や有価証券などに留まらず、生活していた家に残された物品すべて)などひき取りたくもないときに、最低限、知っておかなければならないことは以下の3点です。
それは、法定相続人として、第1に、a)には、市町村役場や警察に「遺体のひき取りはしない。」と意思表示ができ、第2に、b)c)には、まず、『別紙3.被相続人の死後、相続人がすること』の4-③のとおり、相続が発生したことを知った日(市区両村役場や警察から「亡くなった」との連絡があった日)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」の手続きを行うことができます。
仮に、被相続人がギャンブル依存で、消費者金融会社から多額の借り入れ(負債(借金))をしていて亡くなったとき、この負債(借金)も相続する遺産(遺産)となるので、上記の「相続放棄」の手続きをしないと、この負債(借金)の弁済義務を負うことになります。
「知識は身を救う」とあるように、知らないと、自分を苦しめた親が亡くなったあとに苦しむことになります。
そして、第3に、法定相続人として、市区町村役場に「遺体のひき取りはしない」と回答し、火葬などを市区町村役場が実施したとき、その火葬費などは、遺留金品を売却し充填したのち、不足が生じたときには、法定相続人や3親等の親族(扶養義務者)に請求されます。
ただし、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課/厚生労働省社会・援護局保護課/法務省民事局商事課/法務省民事局参事官室が作成した『身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引(令和3年3月)』には、「墓埋法及び行旅法にもとづく事務は自治事務であり、自治体の判断として、亡くなった方からDV被害を受けていた相続人や扶養義務者など、費用弁償先としてふさわしくないケースについては、その方から求めるべき費用分を負担することとし、当該相続人又は扶養義務者を費用弁償先から除外する取扱いを行うことも可能となる。」と記述されています。
したがって、この手引きの引用し、「自分に虐待を加えてきた親の遺体を引き取ったり、遺産(遺留金品)を受けとったりするつもりはない」と、“自分に虐待を加えてきた親”と明確に表現し、伝えることができます。
なぜ、この手引きを引用することが重要になるのかは、担当する(連絡を受けた)市区町村役場の職員が、この手引きの記述を知らない可能性があるからです。
そして、両親間にDV行為のある家庭環境で暮らし、育っている人は、この状況が、自身(子ども)にとって、心理的虐待(面前DV)であることを理解しておくなど、正確に、どのような暴力行為が、『児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)』に定める虐待にあたるのか正確に知っておくことが大切です。
また、配偶者からDV被害を受け、『配偶者暴力防止法』に準じ“一時保護”の決定を受け、母子生活支援施設などのシェルターに入居してきた人は、そのときに発行された『DV被害証明書(配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書)/女性センター(婦人相談所)』は、また、「婚姻破綻の原因は、配偶者からのDV行為である」として、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停を申立てたときの「申立書」「第1準備書面」「答弁書」「陳述書」などは、上記の「DV被害を受けていた相続人である」ことを示す証拠ともなるので、捨てずに、子どもが高校や大学進学、就職したり、成人(18歳)を迎えたりしたときなどに、将来(上記のような事態)に備え、子どもにわたし、説明しておくことはとても大切です。
別紙2.被相続人の死後、相続人がすること
被相続人の死後、葬式の手配、保険証の返却、年金、銀行の解約、不動産の名義変更、財産調査、相続人の確定、遺産分割、相続税の支払いなどさまざまな手続きが必要です。
なお、年金、銀行預金、株(有価証券)、不動産、その他の手続きには、「戸籍」等が必要です。
① 死亡者(被相続人)の戸籍、出生から死亡までのすべての戸籍類が必要
役所の窓口で、「出生から死亡までの戸籍をください。」と伝えます。
② 相続人は、現在の戸籍のみ必要
(1) 死亡から7日以内
① 死亡診断書の受け取り
「死亡診断書」は、死亡を確認した医師が勤務する病院が発行し、「死亡診断書」にもとづき「火葬」「埋葬」を行うことができます。
「死亡診断書」は、その後の手続きに必要となることがあるので、コピーをとっておきます。
死亡理由が明らかでないときは、「死体検案書」が作成され、これが、死亡の証明となります。
② 死亡届の提出
「死亡届」は「死亡証明書」と一体で、用紙の右側が死亡証明書、左側が死亡届です。
「死亡届」の必要事項に記入後、「死亡届」と「火埋葬許可申請書」を市区町村市区町村役場に提出し、「火葬許可証」をもらいます。
「火葬許可証」を葬儀社に持っていくと火葬の申し込みができます。
(2) 死亡から10日以内
① 葬儀
葬儀社に火葬許可証を提示し、葬儀の申込み、通夜や葬儀などの法要を行い、墓・仏壇を用意します。
なお、葬儀費用は、相続財産から控除できることから、領収書を保管しておきます。
* 葬式後、市区町村役場に「葬祭費申請」をすると最大5万円ほど還付されます。
② 年金受給停止の手続き
被相続人が「年金受給者」のとき、「年金の受給停止手続き」を住民票の住所地管轄の社会保険事務所で行います。
「厚生年金」の受給停止手続きは死亡後10日以内、「国民年金」の受給停止手続きは死亡後14日以内に行います。
なお、年金の受給停止手続きには、「年金証書」「死亡診断書、または、火葬許可書」、「戸籍謄本、または、除籍謄本」、「故人と年金請求者の住民票写し」が必要です。
(3) 死亡から14日以内
① 健康保険の資格喪失届の提出(保険証の返却)
被相続人が「国民健康保険」に加入しているときは、死亡から14日以内に「国民健康保険資格喪失届」を市区町村役場に提出します。
また、被相続人が75歳以上のときは、「後期高齢者医療資格喪失届」を提出します。
なお、喪失届を提出するときに「保険証」を返却します。
被相続人が会社員で「健康保険」に加入しているときは、死亡から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を会社経由で年金事務所に提出します。
残された家族が、「被相続人の健康保険の扶養に入っている」ときは、「保険証」が使えなくなるので、国民健康保険に加入するか、他の家族の健康保険の扶養に入るかを決めます。
また、被相続人が「介護保険の被保険者」であるとき、「資格喪失届」を市区町村市区町村役場に提出します。
② 介護保険の資格喪失届の提出
「要介護認定」を受けているときは、14日以内に「介護被保険者証」を返還します。
なお、「未納保険料がある」ときは相続人に請求され、納め過ぎていたときは相続人に還付されます。
資格喪失届の必要書類は「介護保険の資格喪失届」と「介護保険被保険者証」です。
③ 世帯主変更届の提出
被相続人が世帯主であるときは、死亡後14日以内に「世帯主変更届」を市区町村役場に提出します。
一般的には、「死亡届」の提出時に、「世帯主変更届」を一緒に提出します。
なお、残された世帯員が1人、もしくは、残された世帯員が15歳未満の子どもとその親権者であるときは、世帯主変更の手続きは必要ありません。
④ 生命保険金の受け取り
被相続人が「生命保険」に加入しているとき、受取人は生命保険会社に連絡をして「保険金受け取りの手続き」をします。
なお、生命保険金は受取人固有の財産となることから、受取人が単独で申請をして受け取ることが可能です。
⑤ 金融機関への連絡
金融機関に「口座名義人の死亡」を連絡し、口座の入出金を止めます(凍結する)。
被相続人の銀行口座が凍結されると公共料金や各種サービスの自動引落が止まることから、支払い方法の変更や解約の手続きをします。
⑥ 公共料金や各種サービスの変更と解約
被相続人が名義人となっている電気、ガス、水道、固定電話、携帯電話、NHKの使用料の引き落とし先の変更が必要です。
なぜなら、有料サービスは、解約しない限り、料金を払い続けなければならないからです。
サブスクリプションやインターネット回線は解約忘れが多いので注意が必要です。
また、クレジットカード、ガソリンカード、Suica、nanacoなどの電子マネーなどの解約が必要です。
年会費がかかるものがあるときには注意が必要です。
(4) 死亡から3ヶ月以内
「遺言書」は、相続人全員で話し合う「遺産分割」より、優先して効力が発揮されます。
したがって、「遺言書がある」ときは、「遺言書の記載内容」にしたがい遺産を分けますが、「遺言書がない」ときは、相続人全員で集まり、遺産の分け方を決めます(遺産分割協議)。
「遺言書がない」ときは、遺産分割協議をおこなうために、a)相続人が誰かを調査したり、b)相続財産を調査したりする必要がありますが、この事案は、「遺言書を残す」ことを“前提”としているので、割愛します。
* 被相続人が「遺言書」を金庫以外に保管先として、被相続人が公証役場で「公正証書遺言」をしているときは、公正役場で遺言書の検索をすると見つけることができます。
① 遺言書の検認
「遺言書」は、勝手に開封することはできず、「検認」をせずに開封すると5万円以下の過料が科せられることがあります。
したがって、被相続人の居住地を管轄している家庭裁判所に「検認」を申立てます。
「検認」を申立てると家庭裁判所から相続人に検認の期日の連絡があり、その期日に家庭裁判所で出席した相続人の前で遺言書の開封と確認がおこなわれます。
確認後、「検認済証明書」が発行され、「遺言書」に“添付”できます。
② 相続財産の調査
ア) 現金
イ) 銀行預金
ウ) 不動産(土地建物)
エ) 車
カ) 株式(有価証券)
キ) 債権
ク) 投資信託
ケ) 生命保険
* 生命保険は、死亡時の受取人が指定されているとき、相続の財産には含まれないので注意が必要です。
「生命保険」には相続税の非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
例えば、法定相続人が3人のときは、500万円×3人で1,500万円が非課税です。
コ) 美術品
サ) 貴金属
シ) 仮想通貨
ス) 各種ローン
セ) 負債(借金)
* 相続する財産には負債(借金)も含まれます。
したがって、負債(借金)を抱える被相続人の財産を相続するときには、相続人がその負債(借金)を弁済することになります。
③ 相続放棄
被相続人に多額の負債(借金)があり、負債(借金)を相続したくないとき、相続人は、「相続放棄」や「限定承認」という手続きができます。
「相続放棄」とは、資産や負債の一切を受け取らないことです。
「限定承認」とは、相続した遺産の中から債権者に借金を返し、残金があるときに受け取ることができる手続きです。
遺産よりも負債(借金)の方が上回っているとき、不足分を返済する必要はありませんが、「限定承認」は相続人全員でおこなう必要があります。
「相続放棄」と「限定承認」は、相続のあることを知った日から3ヶ月以内です。
それまでに家庭裁判所で手続きをしないと、「単純承認をした」ことになり、負債(借金)を弁済しなければいけなくなります。
(相続放棄の手続き)
申述する法定相続人の状況により、必要な書類が異なり、また、条件により、関係者の法定相続人の戸籍謄本、除籍謄本、または、改製原戸籍謄本の提出が必要です。
① 相続放棄の申述書
② 亡くなられた方の住民票除票、または戸籍附票
③ 申述される方の戸籍謄本
④ 収入印紙書;申述する法定相続人1人につき800円
・被相続人についての戸籍
・本来の相続人の中で、死亡している人についての戸籍
なお、「相続放棄申述書」と「記述例」は、下記、家庭裁判所のHPhttps://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html(相続の放棄の申述)からダウンロードできます。
(相続放棄の手続きの流れ)
① 相続放棄にかかる費用を準備する
ア)収入印紙代:800円
イ)郵便切手代:裁判所によって金額が異なる
* 弁護士、司法書士に、「相続放棄手続きの代行」を依頼するときには、別途費用が必要です。
依頼費用は、弁護士は5万円程度、司法書士は3万円程度が相場です。
法定相続人同士で揉めているときなどでは、弁護士が間に入り交渉してくれます。
② 相続放棄に必要な書類を用意する
ア)相続放棄申述書(相続放棄の意思表示を記した書類)
イ)被相続人の住民票除票または戸籍附票
ウ)申立てる相続人の戸籍謄本
上記ア-ウの書類の他、「誰が申立てているのか」により、以下の書類が必要です。
エ)申立人が被相続人の配偶者のときは、上記ア-ウに加えて、「被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」が、オ)申立人が被相続人の子どもや孫(代襲者)のときは、上記ア-ウに加え、「被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」が、カ)申立人が孫のときは、「本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」が、キ)申立人が被相続人の両親や祖父母(直系尊属)のときは、上記ア-ウに加え、「被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」「被相続人の子供で死亡者がいれば、その子供の出生時から死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」「被相続人の直系尊属に死亡者がいれば、その者の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」の3点が、ク)申立人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪のときは、上記ア-ウに加え、「被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」「被相続人の子供で死亡者がいれば、その子供の出生時から死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」「被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」の3点が、ケ)申立人が甥姪のときは、「本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」が必要です。
③ 財産調査を行う
相続においては、「1-(4)-b)相続財産の調査」に記している預貯金など(動産)、土地建物など(不動産)に対する調査をする必要があります。
預貯金は預金通帳や金融機関からの郵送物などで確認でき、不動産は「固定資産税通知書」、「名寄帳」などで確認できます。
特に重要な“負債”については、郵便物、預金通帳などで確認できます。
④ 家庭裁判所に相続放棄を申立てる
財産調査をした結果、被相続人には負債(借金)があり、それが、負債以外の遺産(財産)より多く、「相続を放棄する」ときには、被相続人の住民票の届出のある都市を管轄する家庭裁判所に相続放棄を申立てます。
* 相続放棄は、相続人本人が申立てるのが原則ですが、相続人が未成年のときは、その親などの法定代理人が申立てます。
* 相続放棄の申立ては、相続がはじまったことを知ってから3ヶ月以内です。
⑤ 相続放棄申立後に照会書が届く
家庭裁判所に相続放棄を申立てると、約10日後に家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送付されます。
送付書には、回答の記入欄があるので、必要事項を記入後、家庭裁判所へ再送します。
⑥ 相続放棄が許可されれば相続放棄申述受理通知書が届く
再送後10日ほどすると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
これにより、相続放棄が認められたことになります。
(5) 死亡から4ヶ月以内
① 所得税の準確定申告
1月1日-死亡日までに得た収入については、死亡日から4ヶ月以内に「準確定申告」が必要になります。
* 年金受給者で、年金以外の収入があったり、就労者、自営業者で収入があったりするときには、税務署で「確定申告」をします。
(6) 死亡から10ヶ月以内
① 遺産分割協議書の作成 *「遺言書」があるとき、必要ありません。
誰がどうひき継ぐのか話し合い、決まったことを「遺産分割協議書」として作成し、相続人全員で著名押印(実印)と印鑑証明書を添付します。
② 各種の相続手続き
「遺言書」の内容、もしくは、遺産分割協議書の内容にしたがい自分(相続人)が取得した遺産の相続手続きをおこないます。
「預貯金」を相続するときは払い戻し手続き、「不動産」を相続するときは名義書換手続きが必要です。
不動産の名義書換手続きには期限はありませんが、名義書換をしないまま相続人が死亡すると次の相続人の相続手続きが複雑で大変になるので、不動産を相続するときに速やかに手続きをします。
③ 相続税申告と納付手続き
相続税の「基礎控除」は、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」です。
この「基礎控除」を超えるときには、相続税申告と納付手続きをします。
「相続税申告」と「納税の期限」は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内で、10ヶ月を過ぎると延滞税などがかかります。
遺産分割協議が終わっていないとき、法定相続人が法定相続分で取得したものとして相続税申告と納税をおこない。遺産分割協議がまとまったあとで、その内容に応じて相続税の計算をおこない、税務署で手続きをおこないます。
相続税を払い過ぎていたときは還付を受け、相続税が不足していたときは追加で支払います。
なお、相続税を支払えないときは、遺産そのものを支払う物納や分割で相続税を支払う分納が可能です。
* 生命保険、退職金があるときは、「相続税の計算」に加算され、相続人1人あたり、500万円が控除されます。
(相続税の速算表) 平成27年(2016年)以降
相続税の課税対象となる金額 税率 控 除 額
1,000万円以下 10% -
1,000万円超-3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超-5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超-1億円以下 30% 700万円
1億円超-2億円以下 40% 1,700万円
2億円超-3億円以下 45% 2,700万円
3億円超-6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
(7) 死亡から1年以内
① 遺留分減殺請求の手続き
「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の相続人のために、法律で保障されている一定割合の相続分のことです。
(8) 死亡から2年以内
① 葬祭費、埋葬料の申請手続き
被相続人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していると、喪主に対して葬祭費が支給されます。
金額は、自治体により異なりますが2-7万円ほど支給されます。
請求期限は葬儀をおこなった日の翌日から2年です。
国民健康保険の資格喪失届を提出するときに、一緒に手続きをおこないます。
また、被相続人が会社員で健康保険に加入しているときには、喪主に対して埋葬料として5万円が支給されます。
請求期限は死亡した日から2年です。
健康保険の資格喪失届を提出するときに、一緒に手続きをおこないます。
(9) 死亡から3年以内
① 税務調査への対応
税務調査とは、相続税の申告内容について税務署が調査することです。
税務調査が入るのは全体の20%-25%ですが、税務調査が入ったうち追徴課税が発生する確率は80%以上です。
税務調査が入ると相続税が増額する可能性が高いことから、事前に税理士に相談するなど税務調査対策が必要です。
なお、相続税の税務調査の時期は申告をした翌年、もしくは、翌々年の夏から秋の間が一般的です。
(10) 死亡から3年10ヶ月以内
① 相続税軽減の手続き
相続税には、さまざまな軽減措置がありますが、遺産分割協議が長引き、未分割で申告と納税をおこなったときは、「配偶者軽減」や「小規模宅地等の特例」などの税額軽減が適用されません。
未分割で申告と納税をおこなったあと、遺産分割協議がまとまり、相続税の修正申告や更正の請求の手続きをおこなうときに税額軽減を受けるには、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出する必要があります。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を当初申告時に提出し、亡くなってから3年10ヶ月以内に遺産分割協議をまとめ、その後4ヵ月以内に税務署に更正の請求をおこなうと、配偶者控除や小規模宅地等の特例を受けることが可能です。
(11) 死亡から5年10ヶ月以内
① 相続税の還付請求の手続き
相続税申告書の内容を見直し、相続税の金額を減額できるときには、税務署に払い過ぎていた分を返金してもらうことが可能です(相続税還付)。
相続税還付の期限は亡くなってから5年10ヶ月以内です。
・戸籍類は「市区町村役場」
・年金は「年金事務所」
・準確定申告は「税務署」
・不動産の名義変更は「法務局」
・相続放棄は「裁判所」
* 市区町村役場以外は、事前に連絡し予約が必要です。
別紙3.被相続人としての基礎知識
被相続人に、配偶者、子ども、親、きょうだいが生存しているとき、どこで亡くなったのかは関係なく、2-(1)-②のとおり、相続が発生し、その法定相続人には、第1順位、第2順位、第3順位があります。
法定相続分については、2-(1)-③で述べます。
「遺言書」には、「財産目録」を添付しますが、その対象となる“遺産(財産)”は、ア)現金、イ)銀行預金、ウ)不動産(土地建物)、エ)車、オ)株式(有価証券)、カ)債権、キ)投資信託、ク)生命保険、ケ)美術品、コ)貴金属、サ)仮想通貨、シ)各種ローン、ス)負債(借金)などが該当します。
これらの財産の一覧をまとめたものが、「財産目録」です。
この「財産目録」にもとづいて、金銭でないものについては、その評価額を明確にして、財産を金銭に換算し、「2.相続税の「基礎控除」」に記述している「相続税の速算表」のとおり、その金額にもとづいて、相続人の相続税が決まります。
なお、遺産(財産)には、シ)各種ローン、ス)負債(借金)などが含まれ、『1-(4)-③相続放棄』のように、相続がはじまったことを知った日から3ヶ月以内に「相続放棄の手続き」をしないと、弁済しなければならなくなります。
また、被相続人が、法定相続人の法定相続分とは異なる遺産の分け方を『遺言書』に残していたとしても、2-(1)-④のとおり、法定相続は最低限取得できる権利(遺留分)があります。
このことは、『遺言書』において、法定相続人が相続する遺産(財産)の遺留分を超えない範囲で、「世話になった人など、法定相続人ではない人に財産を譲ることが可能である」ことを意味します。
さらに、2-(3)-②-a)のとおり、贈与した金額が1年間で、110万円以下であれば、贈与税を支払う必要はなく、生前贈与は、2-(3)-②-b)のとおり、誰に、どの財産を、どのくらいわたすかを決めることができます。
しかし、2-(3)-③ーd)のとおり、「死亡前3年以内に被相続人から相続人に実施された生前贈与は、死亡時に相続人の相続財産に加算され(生前贈与加算)、相続税が課税される」ことから、節税対策としての「生前贈与」は、被相続人の年齢などを踏まえ熟考が必要です。
最後に、ア)「財産目録」を作成し、イ)誰に、どの財産を、どのくらいわたすのか、ウ)喪主、葬儀を誰が執り行うのか、エ)遺言執行者を誰にするのか(2-(2)-②)が決まれば、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないことから、「公正証書遺言」が便利です。
つまり、経営する企業の大株主であり、多くの不動産を有するなど、多額の財産があり、法定相続人が複数で、複雑でない限り、「遺言書」の作成は、それほど難しくはありません。
なお、公証人に支払う手数料については、2-(5)-①-c)のとおり、相続財産の価額により手数料は異なりますが、概ね2万円-5万円程度です。
(1) 遺言書と法定相続人
「遺言書」は遺産の分け方を示した法的な書類で、「遺書」は死ぬ間際に自分の気持ちを伝えるための手紙のことです。
「遺書」に自分の財産の分け方について書いても法定効力はありません。
ただし、「遺書」が「遺言書」としての要件を満たしているときは法的効力が発生します。
民法では、「遺言の方式」「遺言の効力」「遺言の失効」「遺言の取消」など遺言について、さまざまな規定を定め、同法第960条に「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と定めています。
つまり、「遺言書」は、民法の規定にしたがい作成されていないと法的効力はありません。
① 遺言書の有無
法的に有効な「遺言書」があるときは、原則として、「遺言で指定された人が遺産を取得する権利を有し、法的に有効な「遺言書」がないときには、法定相続人が財産を相続する権利を有します。
② 法定相続人とは
民法で定められている「法定相続人(遺産を相続する権利のある人)」は、「配偶者」と「血族相続人」に分けられます。
内縁者や離婚した元配偶者は、法定相続人にはなりません。
例えば、被相続人に配偶者と子どもがいるときには、配偶者と子どもが法定相続人になります。
法定相続人の第1順位は「子(代襲相続、再代襲相続、ともにあり)」、第2順位は「直系尊属(もっとも親等の近い者で、代襲相続はなし)」で、第3順位は「兄弟姉妹(代襲相続あり、再代襲相続はなし)」です。
第1順位の血族相続人(子、および、その代襲者)がいないとき、第2順位の直系尊属(父母や祖父母のように直系の親族(直系尊属)で、前の世代の人)が相続人となり、第2順位の直系尊属がいないときには、第3順位の「兄弟姉妹」が相続人となります。
つまり、子どもがいるときは子どもが、子どもがいないときは第2順位の両親が、子どもも両親もいないときは第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。
「代襲相続」とは、例えば、被相続人が死亡する前に被相続人の子Aが死亡したときに、Aに代わりAの子B(被相続人の孫)が法定相続人になり、「再代襲相続」では、子B(被相続人の孫)の子C(被相続人のひ孫)が法定相続人となります。
ただし、「相続放棄」した人の子(被相続人の孫)は代襲相続人となることはできません。
なお、血族には、血縁関係がある自然血族のほかに、養親子などの法定血族が含まれまれ、相続権が発生しますが、配偶者の血族(舅・姑など)や、血族の配偶者(妻や夫)のように、婚姻関係によって成り立つ姻族は血族には含まれず、相続権は発生しません。
③ 法定相続分とは
法定相続人は、法律で、相続できる割合(法定相続分)が決まっています。
相続割合は、以下のように、相続人の構成によって異なります。
法定相続人 法定相続分
配偶者のみ 配偶者 遺産のすべて
配偶者と子ども 配偶者 遺産の1/2
子ども 遺産の1/2を均等に分割
子どものみ 子ども 遺産のすべてを均等に分割
配偶者と親 配偶者 遺産の2/3
親 遺産の1/3を均等に分割
親のみ 親 遺産のすべて
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 遺産の3/4
兄弟姉妹 遺産の1/4を均等に分割
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹 遺産のすべて
④ 遺留分とは
「遺言書」で、誰に、どの財産を、どのくらいわたすのかを決められますが、それが完全に実現できるとは限りません。
なぜなら、一定の範囲の法定相続人には、遺産を最低限取得できる権利が認められているからです。
この遺産を最低限取得できる権利のことを「遺留分」といいます。
例えば、「遺言書」に「遺産のすべてを愛人Bにわたす。」と記述したとしても、妻の「遺留分」は遺産の2分の1なので、妻は、愛人Bに対して「遺留分として遺産の2分の1をもらう権利がある。」と主張し、「遺産の2分の1をわたしなさい。」と請求できます。
このような遺留分が侵害されたとき、他の相続人に不足分を請求することを「遺留分減殺請求」といいます。
遺留分の対象となる財産は、被相続人の死亡時の財産だけではなく、被相続人の生前の贈与等も遺留分の対象に含まれます。
遺留分算定の基礎となる財産は、「相続財産+贈与分-負債(借金)」です。
つまり、相続開始時に被相続人が有していた財産に、条件付の権利や遺贈、死因贈与、生前贈与、不相当な対価をもってした有償行為、特別受益などを足した額が遺留分算定の基礎となる財産となります。
贈与分にあたる財産には、以下のものが含まれます。
ア) 相続開始から遡って1年以内の贈与
イ) 遺留分権利者に損害を与えることを知っていて行った贈与(過去1年以内にはとらわれない/第3者に対して行われた贈与も含む)
ウ) 相続人への特別の贈与
そして、法定相続人の遺留分は以下のようになります。
相続人 遺留分合計 配偶者 子ども 親 兄弟
配偶者のみ 1/2 1/2 - - -
配偶者と子ども 1/2 1/4 1/4 - -
配偶者と親 1/2 1/3 - 1/6 -
配偶者と兄弟 1/2 1/2 - - -
子どものみ 1/2 - 1/2 - -
親のみ 1/3 - - 1/3
兄弟のみ - - - - -
⑤ 遺言書の効力
「遺言書」には、できることとできないことがあります。
a) 誰に、どの財産を、どのくらいわたすのか指定できる
「遺言書」で、誰に、どの財産を、どのくらいわたすのか指定できます。
世話になった人など、法定相続人ではない人に財産を譲ることも可能です。
b) 相続する権利を剥奪できる
「遺言書」を作成する被相続人が、特定の相続人から虐待や侮辱などの暴力被害を受けていたとき、その相続人から相続する権利を剥奪することができます。
c) 隠し子を認知することができる
隠し子を遺言書で認知することができます。
遺言書で認知された子どもは、被相続人の子どもとして認められることから、法定相続人として財産を相続できます。
d) 遺言執行者を指定できる
「遺言書」に記載した内容を執行する人(遺言執行者)を指定できます。
「遺言執行者」を指定しておくと、相続手続きを速やかに進められます。
なお、「遺言執行者」については、「2-(4)遺言執行者」で詳述しています。
e) 保険金の受取人を変更できる
保険金受取人を「遺言書」で変更できます。
ただし、生命保険は、死亡時の受取人が指定されているとき、相続の財産には含まれないので注意が必要です。
一方で、「生命保険」には相続税の非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
例えば、法定相続人が3人のときは、500万円×3人で1,500万円が非課税です。
⑥ 遺言書の書き方
「遺言書」には、「普通方式」の遺言書と「特別方式」の遺言書があります。
普通方式の遺言書は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
「秘密証書遺言」と「自筆証書遺言」は、勝手に開封することができず、家庭裁判所での“検認”が必要です(「1-(4)-①遺言書の検認」を参照ください)。
特別方式の遺言は、「一般危急時遺言」、「難船危急時遺言」、「一般隔絶地遺言」、「船舶隔絶地遺言」の4種類に分かれます。
ここでは、普通方式の遺言書について説明します。
a) 自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、被相続人が、「遺言書」のア)全文、イ)日付、ウ)氏名を自筆し、エ)押印します。
ア)イ)ウ)エ)の成立要件が欠けていると、その「遺言書」は“無効”となります。
* 平成31年(2019年)の法改正で、「遺言書」に添付する「財産目録」は、自筆でなくてもよくなりました。
自筆以外とは、ワープロ、パソコンでWordなどワープロソフトを利用して作成したものをいいます。
b) 公正証書遺言
「公正証書遺言」は、2人以上の証人の立会いのもと、公証人が、被相続人から遺言内容を聴き取りながら作成します。
「公正証書遺言」は、a)遺言者(被相続人)本人であることを証明するための「実印」と「印鑑証明書」を用意し、b)2人以上の証人と一緒に公証役場に行き、c)公証人に遺言の内容を伝え、d)公証人が正確に文章にまとめ、e)その文章を読み聞かせて内容を確認してから、f)遺言者・証人・公証人が署名をして、遺言書を作成するので、方式の不備で無効になることはありません。
「公正証書遺言」は、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないので、被相続人が死亡後、最寄りの公証役場に行き、「遺言書」の内容を確認し、相続手続きを進めます。
なお、公証人に支払う手数料については、「5-(1)「遺言書」作成の費用(概算)」に記載しています。
* 被相続人が「遺言書」を金庫以外に保管先として、被相続人が公証役場で「公正証書遺言」をしているときは、公正役場で遺言書の検索をすると見つけることができます。
c) 秘密証書遺言
「秘密証書遺言」は、遺言者(被相続人)が作成した遺言(自筆、自筆以外でも可)を2人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらうものです。
その流れ(手順)は、ア)遺言者(被相続人)が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をしたうえで、イ)これを封じ、ウ)遺言書に押印した印章と同じ印章で封印したうえ、エ)公証人、および、証人2人の前にその封書を提出し、オ)自己の遺言書である旨およびその筆者の氏名および住所を申述し、カ)公証人が、その封紙上に日付および遺言者の申述を記載したのち、キ)遺言者および証人2人とともに、その封紙に署名押印する、となります。
「秘密証書遺言」は、遺言者(被相続人)が署名と押印をすれば、「遺言書」をパソコンで作成したり、代筆してもらったりすることができます。
「遺言書」は、被相続人が保管します。
(2) 相続税の「基礎控除」
「相続人の相続税」については、別紙1『死後、相続者がすること』の「4-③相続税」に記述しているとおり、a)相続税の支払いは、死亡日から10ヶ月以内、b)相続税の「基礎控除」は、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」となっており、c)この「基礎控除」を超えると申告が必要です。
(相続税の速算表) 平成27年(2016年)以降
相続税の課税対象となる金額 税率 控 除 額
1,000万円以下 10% -
1,000万円超-3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超-5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超-1億円以下 30% 700万円
1億円超-2億円以下 40% 1,700万円
2億円超-3億円以下 45% 2,700万円
3億円超-6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
(3) 生前贈与
「生前贈与」とは、被相続人が生存中に保有する財産の一部、あるいは、全部を、特定の誰かに贈与することです。
「遺言」は、被相続人自身で作成できますが、「贈与」は“契約”となることから「贈与を受ける側(受贈者の承諾が必要」です。
なぜなら、受贈者は贈与された分が“利益”となり、「贈与税がかかる」からです。
しかし、子や孫などの親族への贈与については、「贈与税の非課税枠」が設けられています。
つまり、非課税枠内であれば、贈与税がかからずに贈与できます。
しかし、上記「相続税の速算表」と下記「贈与税の速算表」を比較すると「贈与税の方が税率は高い」ことがわかります。
したがって、節税対策として安易に生前贈与をすると、かえって相続人が支払う税金が高くなることがあるので注意が必要です。
① 生前贈与の受け取り方
a) 暦年課税
「暦年課税」とは、受贈者が1月1日-12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えると、その超過分に対し贈与税が課税される制度です。
受贈者が、「相続時精算課税の申請をしない」と“暦年課税を選択”したことになります。
b) 相続時精算課税
「相続時精算課税」は、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫へ贈与するときに選択できます。
「相続時精算課税」を選択すると受け取った額の合計が2,500万円を超えるまで「贈与税は無税」ですが、相続時に受け取った分に対して「相続税が課税」されます。
② 生前贈与で相続税の節税対策をするメリット
「生前贈与」で、相続税の節税メリットは主に以下の2点です。
a) 相続財産を減らすことができる
3-(1)-①で示した「暦年課税」での生前贈与は、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税が課税されません。
したがって、生前贈与を110万円以下にすると、贈与税が課税されることなく相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
例えば、現金が1,000万円あるとき、死亡すると1,000万円に対して相続税が課税されますが、生存中に、110万円を子どもに贈与すると贈与税が課税されないので、現金1,000万円は890万円に減ります。
つまり、この現金890万円に対して相続税が課税されます。
b) 財産を自由に贈与することができる
民法では、被相続人の遺産を誰が相続するかについて定められています(法定相続人)が、生前贈与は、誰に、どの財産をわたしても自由です。
つまり、第1順位-第3順位となる親族以外に対して生前贈与ができます。
「遺言書」においても、誰に、どの財産を、どのくらいわたすのか指定できますが、生前贈与の方が手続きは簡単です。
③ 生前贈与で相続税の節税対策をするデメリット
「生前贈与」で、相続税の節税デメリットは主に以下の4点です。
a) 税務署に否認されるリスクがある
生前贈与を成立には、贈与者(被相続人)と受贈者の双方の意思表示が必要です。
生前贈与では、「贈与契約書」を作成すると生前贈与を立証しやすくなります。
なお、現金手渡し、名義預金、へそくり等は、税務署に否認されることがあります。
b) 定期贈与とみなされるリスクがある
年間の贈与額が110万円以下であるとき、贈与税が課税されませんが、毎年同じ金額を贈与し続けると「定期贈与」とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されるリスクがあります。
「定期贈与」とは、毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与のことで、「定期贈与の取り決めをした年」に、「定期金に関する権利」の贈与を受けたとして贈与額の合計金額に対して贈与税が課税されます。
例えば、「毎年100万円を10年にわたり贈与する。」という取り決めがおこなわれたとき、取り決めをおこなった年に1,000万円の定期金に関する権利を贈与したとして1,000万円に対して贈与税が課税されます。
c) 贈与者の生活を圧迫するリスクがある
多くの財産を生前贈与することで、贈与者(被相続人)の生活を圧迫してしまうリスクがあります。
d) 死亡前3年以内の贈与は相続税の対象
死亡前3年以内に被相続人から相続人に実施された生前贈与は、死亡時に相続人の相続財産に加算され(生前贈与加算)、相続税が課税されます。
④ 贈与税の計算方式
贈与税の基礎控除額は、年間110万円です。
贈与した金額が1年間で、110万円以下であれば贈与税を支払う必要はありませんが、「2-(3)-④死亡前3年以内の贈与は相続税の対象となる」ことに留意が必要です。
贈与税の計算方法は、以下のとおりです。
a) 贈与税の課税対象となる金額
1年間の贈与額-110万円=贈与税の課税対象となる金額
b) 贈与税額の計算式
贈与税の課税対象となる金額×税率-控除額=贈与税額
税率と控除額は課税対象となる金額に応じて異なるので、下記「速算表」を参照にします。
「速算表」とは、課税対象の金額に応じた税率と控除額がわかる表のことで、「直系尊属」とは親や祖父母などの直系の親族のことです。
(生前贈与の速算表①) 平成27年(2016年)以降
20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けたときの贈与税の税率と控除額
贈与税の課税対象となる金額 税率 控除額
200万円以下 10% -
200万円超-400万円以下 15% 10万円
400万円超-600万円以下 20% 30万円
600万円超-1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超-1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超-3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超-4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
(生前贈与の速算表②) 平成27年(2016年)以降
上記以外の場合の贈与税の税率と控除額
贈与税の課税対象となる金額 税率 控除額
200万円以下 10% -
200万円超-300万円以下 15% 10万円
300万円超-400万円以下 20% 25万円
400万円超-600万円以下 30% 65万円
600万円超-1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超-1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超-3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
⑤ 節税効果の高い贈与額
贈与税の基礎控除額である110万円以上の金額を贈与する方が節税となることがあります。
下記の表は、贈与税と相続税の節税額を比較したもので。相続税の税率は20%、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けたときの贈与税で計算しています。
贈与税と相続税の節税額の比較
年間の贈与額 ①贈与税額 ②相続税節税額 節税効果②−①
110万円 0円 22万円 22万円
200万円 9万円 40万円 31万円
500万円 48.5万円 100万円 51.5万円
510万円 50万円 102万円 52万円
600万円 68万円 120万円 52万円
800万円 117万円 160万円 43万円
1,000万円 177万円 200万円 23万円
年間110万円を贈与したときは、相続財産を110万円減らせるので110万円×0.2で相続税を22万円減額できます。
年間200万円を贈与したときは、(200万円-110万円)×0.1で贈与税が9万円課税されますが、相続財産を200万円減らせるので200×0.2で相続税を40万円減額できます。
したがって、贈与税が9万円課税されますが、相続税を40万円減額できるので、40万円-9万円で31万円の節税効果が得られます。
以下、同様の計算になります。
(4) 遺言執行者
遺言執行者は、「遺言書」の内容にしたがい、被相続人の意思を実現する役割を担います。
一般的に、被相続人の逝去により相続は開始します。
「遺言書」がなければ、法定相続分にしたがい遺産分割の協議が行われ、「遺言書」があれば、遺言内容にしたがい財産が受け継がれます。
この財産の引き渡しを行うのが、「遺言執行者」です。
遺言執行者は、「遺言書」で指定できます。
なお、遺言執行者となる方が見つからず、「遺言書」に指定がないとき、利害関係者が家庭裁判所に申立てをすると、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。
① 遺言執行者になれる人
被相続人が死亡したときに、未成年者(満18歳以下)や破産者でなければ、遺言執行者になることができます(民法1009条)。
遺言執行者は、個人に限らず法人も指定することができます。
また、法定相続人や受遺者といった利害関係者も含まれます。
しかし、遺言執行の手続きには、さまざま手続きが必要で、相応の時間と手間、専門的な知識を要することも少なくないことから、弁護士、司法書士(遺産に不動産がある)、行政書士、税理士などの専門家に依頼することが少なくありません。
また、信託銀行で取り扱っている遺言信託は、遺言書の作成から保管、執行までをトータルでサポートしています。
このサービスは、普段から財産の管理を依頼しているなど信託銀行と取り引きがあるとき、遺言執行者に選んでいます。
② 遺言執行者の役割
たとえ遺言執行の手続きに複雑な事項がなくても、財産の確認や整理、相続人や受遺者への連絡、財産の引き渡しの手続きなど、遺言執行には相応の時間と手間を要します。
また、不動産の遺贈では、不動産登記などの専門的な知識を要します。
遺言執行は、以下のように進められます。
相続が開始されると、相続人・受贈者に対して、ア)遺言執行者就任の通知と遺言者の開示し、イ)遺産の調査、財産目録の作成・交付、相続・受遺の意思確認を行い、ウ)財産の引き渡しを行い、エ)業務終了の報告を行います。
③ 執行報酬と費用
遺言執行の費用は、民法1021条で、「相続財産から負担する」と定めています。
具体的には、遺言執行者の報酬のほか、各種手続き(自筆証書遺言の検認、相続財産の目録、預貯金解約など)の費用となります。
こうした費用が、相続時に財産から控除され各個人・法人に分配されます。
遺言執行者の報酬については、おおよその相場はありますが、各士業の方、各金融機関により異なります。
(5) 費用(概算)
① 「遺言書」作成の費用(概算)
a) 弁護士・行政書士
「遺言書」の作成を弁護士に依頼すると、その費用は概ね10万円-20万円程度で、遺言の内容が複雑なときには20万円を超えることもあります。
「遺言書」の作成を行政書士に依頼すると、その費用は概ね10万円前後です。
弁護士は「遺言書がないケース」や「遺言書の内容が不適切であるケース」で生ずる紛争事案(民事事件)をとり扱っていることから、事案を担当した経験がある弁護士には、それらにもとづいたアドバイスを受けることができます。
行政書士は紛争事案をとり扱いできないので、それが、弁護士と行政書士の違いです。
b) 銀行・信託銀行
銀行・信託銀行は、遺言信託というサービスを提供していることから、遺言書作成に加え、遺言書の保管や遺言の執行など、総合的にサポートできます。
遺言書作成だけでなく、「2」の遺言の執行まで含めた費用は、最低でも140万円-150万円前後です。
c) 公証役場
「1-(6)遺言書の書き方」に記述しているとおり、「遺言書」には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があり、そのうちの「自筆証書遺言」は自筆なので費用はかかりませんが、「遺言書保管制度(法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度)」を利用するときに、1件3,900円の手数料がかかります。
公証役場に行き作成してもらう「公正証書遺言」では、公証人に支払う手数料がかかります。
遺言の対象とする相続財産の価額により手数料は異なりますが、手数料は、概ね2万円-5万円程度です。
また、疾病などで公証人に出張してもらうときには、手数料が1.5倍になり、他に、交通費や日当(1日2万円、4時間まで1万円)の費用がかかります(詳細は、日本公証人連合会のホームページhttps://www.koshonin.gr.jp/business/b10で確認することができます)。
② 遺言執行者に対する報酬(専門家や銀行に遺言の執行をしてもらう費用)
a) 弁護士・行政書士
旧日本弁護士連合会報酬等基準では、例えば、相続財産の総額が300万円-3,000万円未満のときは「2%+24万円」、3,000万円超-3億円のときは「1%+54万円」となっていて、多くの弁護士、法律事務所がこの報酬基準で依頼を受けています。
例えば、上記報酬基準に準じると、相続財産が1,000万円のときは44万円、相続財産が3,000万円のときは84万円、相続財産が1億円のときは154万円が、遺言執行者に対する報酬となり、これらは、相続人が相続財産で支払います。
行政書士についても、同様の報酬基準を採用している事務所が多い一方で、固定報酬としている事務所もあります。
b) 銀行・信託銀行
銀行や信託銀行も相続財産の総額の1-2%前後で報酬を設定しています。
ただし、最低報酬額が定められているので(プランによって異なるものの概ね30万円-150万円程度)、相続財産が3,000万円を下回るときには、弁護士や行政書士と比較すると割高になります。
* 遺言執行者を弁護士に依頼するときには、そのまま弁護士に「遺言書」の作成も依頼する方法があります。
ただし、5-(1)(2)のとおり、依頼する弁護士に対する(遺言執行者に対する)報酬(相続人が相続財産から支払う)、「遺言書」の作成に対する報酬は、それぞれ別です。
ここには、「公正証書遺言」のように、直ぐに、公証役場で「遺言書」を受け取ることができる“保管”は含まれていません。
そのため、別途、「遺言書」の保管費用が発生します。
法律事務所によって異なりますが、その費用は年間1万円前後です。
弁護士に「遺言書」の作成と保管を依頼したときは、「2-(5)-①「遺言書」作成の費用(概算)」に準じると、「遺言書」の作成報酬が10万円-20万円程度+保管費用が1万円/年×年数です。
また、2-(1)-⑥のとおり、「公正証書遺言」以外の遺言書は、家庭裁判所での“検認”が必要です。
(3) 「死後事務委任契約」に対する報酬
被相続人が、家や介護施設、病院で亡くなったあと、『別紙2.被相続人の死後、相続人がすること』のようなさまざまな手続き』のようなさまざまな手続きは必要になります。
そこで、身寄りがなかったり、遺族(法定相続人)に面倒をかけたくないとの思いがあったりする被相続人には、「行政書士」が実施している「死後事務委任契約」を利用する方法があります。
「死後事務委任契約」とは、被相続人が生きている間に、亡くなったあとの諸手続き、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等(死後事務)について委任しておく契約のことです。
例えば、死後事務として、ア)関係者への死亡の連絡、イ)死亡届の提出、ウ)火葬許可証の申請・受領、エ)葬儀・火葬に関する手続き、オ)埋葬・散骨等に関する手続き、カ)供養に関する手続き、キ)社会保険・国民健康保険・国民年金保険等の資格喪失手続き、ク)病院・施設等の退院・退所手続き・精算、ケ)住居の管理・明渡し、コ)勤務先の退職手続き、サ)車両の廃車手続き・移転登録(名銀行)、シ)運転免許証の返納、ス)遺品整理の手配、セ)携帯電話はパソコン等に記録されている情報の抹消、ソ)各種サービスの解約・精算手続き、タ)住民税や固定資産税等の納税手続き、チ)遺産や生命保険等に関する手続き、ツ)ペットの引渡しなどを委任することができます。
また、①連絡代行サービス(家族や知人への緊急時の連絡など)、②葬儀サービス(家族に代わり葬儀を執り行う)、③納骨サービス(葬儀のあとの納骨や散骨、供養など)、➃行政手続きなど代行サービス(死亡後の行政手続きや、生前利用していたサービスの解約手続きなど)、⑤遺品整理サービス(死後の遺品整理、家財道具や生活用品の処分・ひき取り)、⑥相続サービス(遺言執行者指名の受託)をひとつのパックとして受注する「終活代行業務」を行っている団体もあります。
ただし、のHPでは料金体系は示されていないので、資料請求など具体的なアクションを起こさないと実情は把握できません。
* 仮に、「自分には、身寄りがない」と話していたり、長く疎遠になっている親族に迷惑をかけたくないと思ったりしている被相続人が、別紙5『高齢者向け介護施設に入居すると』のように、介護施設に入居し、行政書士と「死後事務委任契約」を締結するときには、いまの財産からⅰ)介護施設の入居費、ⅱ)(介護施設の月額使用料-年金)で不足分が発生するときは×月数、ⅲ)ⅱ)以外の生活費等、ⅳ)「死後事務委任契約」にかかわる費用が賄われることになります。
つまり、「いまの財産-(ⅰ+ⅱ+ⅲ+ⅳ)=相続対象の遺産」となります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
