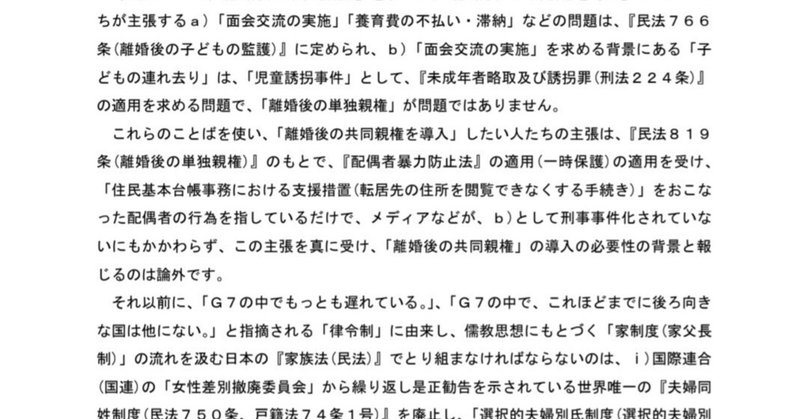
(コラム-17(Ver2))(改訂版)主体は親で子どもは客体と位置づける「共同親権制度改正案」-「子の意見の尊重(子の意思表明権)」の不記載は、「子の最善の利益」を脅かす-
少し長いはしがき
いま、「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が、本国会の衆議院を通過し、参議院の法務委員会で参考人質疑が行われています。
『民法819条(離婚後の単独親権)』を改正し、「離婚後の共同親権を導入」したい人たちが主張するa)「面会交流の実施」「養育費の不払い・滞納」などの問題は、『民法766条(離婚後の子どもの監護)』に定められ、b)「面会交流の実施」を求める背景にある「子どもの連れ去り」は、「児童誘拐事件」として、『未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)』の適用を求める問題で、「離婚後の単独親権」が問題ではありません。
これらのことばを使い、「離婚後の共同親権を導入」したい人たちの主張は、『民法819条(離婚後の単独親権)』のもとで、『配偶者暴力防止法』の適用(一時保護)の適用を受け、「住民基本台帳事務における支援措置(転居先の住所を閲覧できなくする手続き)」をおこなった配偶者の行為を指しているだけで、メディアなどが、b)として刑事事件化されていないにもかかわらず、この主張を真に受け、「離婚後の共同親権」の導入の必要性の背景と報じるのは論外です。
それ以前に、「G7の中でもっとも遅れている。」、「G7の中で、これほどまでに後ろ向きな国は他にない。」と指摘される「律令制」に由来し、儒教思想にもとづく「家制度(家父長制)」の流れを汲む日本の『家族法(民法)』でとり組まなければならないのは、ⅰ)国際連合(国連)の「女性差別撤廃委員会」から繰り返し是正勧告を示されている世界唯一の『夫婦同姓制度(民法750条、戸籍法74条1号)』を廃止し、「選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)」を導入すること、ⅱ)令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」と深くかかわり、「離婚」の87.8%を占める世界で唯一の特殊な『協議離婚制度(民法763条)』を廃止し、すべての「離婚」に家庭裁判所がかかわることです。
ⅱ)は、日本を除く他国と同様に、「離婚後の子どもの監護(民法766条)」に沿い、子どもの父母(共同監護者)として、養育費、面会交流、医療行為、教育(進学、習いごと)、転居、就職などのとり決めを「文書化(公正証書(強制執行認諾条項付きの公正証書))」することで、離婚後の協議による合意(同意)形成に至るプロセスによる係争事件の多くは減少させることができ、同時に、「離婚」の87.8%を占める世界で唯一の特殊な『協議離婚制度(民法763条)』があるために、現在、まったく機能していない「養育費の滞納」に速やかに強制執行の手続きができる『改正民事執行法(令和2年(2020年)4月1日に施行)』を有効に機能させることができます。
そして、「離婚時」に家庭裁判所がかかわることで、現在、家庭裁判所で実施される「夫婦関係調整(離婚)調停」「監護者指定の調停・審判」の役割を担うことができることから、ここで、配偶者間のDV行為、親子間の虐待行為の事実があれば、この事実を持って、面会交流の禁止、接近禁止などを踏まえたとり決め(文書化)に至ることができます。
また、「離婚後の共同親権制度」を導入しなくても、国連の「子どもの権利委員会」の「共同監護のための法整備」に対する是正勧告に抵触することはありません。
なぜなら、この是正勧告は、「共同親権」ではなく「共同監護」に対するもので、しかも、国連の「子どもの権利委員会」の審議における「離婚後の子どもの状況に関する質問」に対し、日本政府代表団は、意図的(政治的)に、「現法の『民法766条』で対応できる」との回答をすることなく勧告に至った経緯があるからです。
つまり、是正勧告に至るプロセスに問題があります。
加えて、パラダイムシフトを招く大改革となりますが、明治政府が進めた「軍国化(国民皆兵、富国強兵)」に不可欠な「家」を基軸に制度設計され、太平洋戦争敗戦後もそのまま継承した「税制度(社会保障制度(年金制度を含む)を含む)」を、日本を除く他国と同様に、「個人」を基軸に制度設計し直すことです。
この「家」を基軸に制度設計された「税制度(社会保障制度(年金制度を含む)を含む)」のもとでは、現在、「個人」を基軸に制度設計され、同時に、「離婚後の共同監護(一部、共同親権)制度」の他国(世界の圧倒的多数の国々)とはまったく異なる運用になります。
この日本の「家」を基軸に制度設計された「税制度(社会保障制度(年金制度を含む)を含む)」は、シングルマザーや未婚女性の貧困問題の原因となっています。
つまり、“女性”は結婚し「家」に入り、離婚せずに夫婦揃って老後を迎える(受給開始年齢を迎える)ことで生活が成り立つように制度設計された「女性差別制度」です。
「離婚後、子どもの共同親権者になる」ことは、「婚姻中、子どもの共同親権者である」という状況と同じで、違うのは、居住地が異なることと子どもは父母どちらかと生活することです。
婚姻中は、「家」を基軸に制度設計された「税制度(社会保障制度(年金制度を含む)を含む)」を意識することは少ないかも知れませんが、「離婚後、子どもの共同親権者となる」ことは、あたり前のことですが、子どもには父母2人の「親」がいることになり、婚姻期間中と同様に、「家」の収入は父母2人の合算となります。
しかも、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」には、養育費の「養育費の支払い義務」は課せられておらず、強制徴収の仕組みもありません。
このことは、子どもの監護者の親が、子どもの監護者でない一方の親(共同親権者)より収入が少なく、後者からの「養育費」が“不払い”であったり、“未払い”があったりしても、子どもの親の収入は父母2人の合算であることから、「育児手当」「就学支援金」「児童手当」「児童扶養手当」「障害年金」などの手当ての対象外になったり、収入の多い共同親権者の預貯金口座に振り込まれたりする(父母ともに働いているときは、恒常的に所得が高い方が受給者となる)可能性があります。
つまり、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が成立・施行されると、これまで、ひとり親家庭の生活基盤を支えていた制度を根こそぎ奪いとることになります。
まるで、「結婚し「家」に入り、出産した女性が、離婚し、子どもの監護者(親権者)となった」ことに対する“罰則規定”のようです。
令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が成立・施行すると、女性と子どもに深刻な人権侵害問題をもたらす世界に恥ずべき法制度となります。
つまり、『家族法(民法)』、「税制度(社会保障制度(年金制度を含む)を含む)」など、あらゆる社会システムが「家」を基軸に制度設計されている日本では、同じ名称の離婚後の共同監護(共同親権)制度」を導入しても、他国の「離婚後の共同監護(共同親権)制度」にはなり得ず、結果、まったく異なる運用となります。
にもかかわらず、なにがなんでも「離婚後の共同親権制度を導入」したい人たちがいます。
それは、ア)「律令制(男子専権離婚)」、儒教思想にもとづく「家制度(家父長制)」の流れを汲み、世界で唯一の特殊な『協議離婚制度(民法763条)』を廃止し、「現法」を有効に機能させる(家庭裁判所がすべての「離婚」事件に関与し、離婚後の子どもの監護のとり決めを書面化(公正証書(強制執行認諾条項付きの公正証書))する)ことが不都合な実質的な「家」の家父長(権威者)を自認する人たちであり、同時に、イ)『日本国憲法』の「9条(戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認)」を無力化し、「専守防衛原則」を捨て、「集団的自衛権」を行使し、「敵基地攻撃能力」を具現化し、“再軍備”を実健したい人と武器輸出で懐を潤したい人たちです。
「再軍備」に不可欠なのは「税制度(税制改革を含む)」で、日本は、戦前の「家(家制度(家父長制))」を基軸に制度設計された「税制度(社会保障制度(年金制度を含む)を含む)」を継承していることから、その「家」を定義した『家族法(民法)』とは相関関係があります。
つまり、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」は、「律令制」に由来し、儒教思想にもとづく「家制度(家父長制)」の流れを汲む『家族法(民法)』の規定であり、「離婚した子どもの父母もひとつの“家”とするための共同親権である」と捉えています。
この子どもの父母がひとつの「家」であることは、「再軍備」の“要”である「子どもの愛国心の醸成(満州事変・太平洋戦争時の『戦時家庭教育指導要項』に通じる『家庭教育支援法案』の成立・施行にもとづく)」には不可欠と考えています。
令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」の質疑の中にでてきた「子どもの養育計画」は、満州事変・太平洋戦争時の『戦時家庭教育指導要項』の「あるべき家庭教育を国が定め、国家が家庭での教育を統制する」という考えにもとづいています。
この視点を持つと、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」には、日本が批准・締結している『児童の権利に関する条約(以下、子どもの権利条約)』に規定している「子どもの意見の尊重(子の意思表明権)」の記載がなく、「子どもの利益を最優先」にする“前提”が示されていない理由が見えてきます。
本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」の“構造”は、「主体は親で、子どもは客体」となっています。
これは、『子どもの権利条約』に反する致命的な欠陥です。
国連で採択され、批准・締結した『人権条約』の規定に準じた法の制定、法の改正に至らないことが、国として「反する行為」となるのは、『国際法』『条約』は、「国内法」よりも上位に位置づけられているからです。
日本で、「「離婚後の共同親権制度の導入」のための『家族法(民法)』の改正」を“主導”してきたのは、ア)極右・超保守の超党派「共同養育支援議員連盟(前.親子断絶防止議員連盟)」、イ)自由民主党の議員連盟「日本の尊厳と国益を護る会」などの議員連盟、そして、ウ)「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)、「桜の会」など、(元)配偶者が『配偶者暴力防止法』の適用を受け、子どもと面会交流ができないDV加害者グループ、そして、エ)右翼団体「日本財団」、カルト教団「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」を母体とする「国際勝共連合(共産主義に勝利するための国際連盟)」、「親学」を主導する日本最大の超国家主義・極右主義団体「日本会議」、役員の多くが「日本会議」の役員・幹部を兼務する「神道政治連盟」などの後ろ盾を受けるオ)極右・超保守の政権、政党、政治家たちです。
エ)と日本の政治のかかわりでは、例えば、『子ども家庭庁』の設立は、安倍晋三元首相や極右議員らが傾倒した「親学」を提唱した高橋史郎氏が中心メンバーの日本最大の超国家主義・極右主義団体「日本会議」が主導し、『こども基本法』は、自由民主党の支持母体の右翼団体であり、カルト教団「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」と深い関係にある「日本財団」の肝入りで成立させています。
これは、安倍晋三元首相が会長となり発足させた「親学推進議員連盟」が立法化を目指した肝いりの政策で、第3次安倍晋三政権で、国会提出を見送った満州事変・太平洋戦争中の『戦時家庭教育指導要項』に通じる『家庭教育支援法案』を成立させるためです。
この『家庭教育支援法案』は、家父長主義的な思想で、男女共同参画や性の多様性を否定している「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」に共鳴した内容(教義そのもの)となっています。
「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」の“教義”は、極右・超保守の政権、政党、政治家が支持する「伝統的な家族観」に沿い、離婚を実質的に否定しているという意味で、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」に合致します。
加えて、極右・超保守の政権、政党、政治家、彼らと“共同体”といえる関係を構築しているエ)の政治団体は、「再軍備」のために、戦前の『国家総動員法』に匹敵する「緊急事態条項」を『日本国憲法』に創設しよう(『日本国憲法』に「緊急事態条項」を創設するための『日本国憲法』の改正)と目論み、関連法案として、『特定秘密保護法』を拡大する『重要経済安保情報保護法(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律)』の本国会での成立を目指しています。
この『家庭教育支援法案』とこの「法案」を成立させるための『子ども家庭庁』『こども基本法』、そして、『日本国憲法』に「緊急事態条項」を創設するための『日本国憲法』の改正、『重要経済安保情報保護法(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律)』の成立を目指している状況を踏まえると、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」の意図(目論見)が見えてきます。
このように、エ)の政治団体は、単なる政治団体ではなく、日本の極右・超保守の政権、政党、政治家との“共同体”、あるいは、エ)の政治団体のメンバーが同時に、日本の極右・超保守の政権、政党、政治家ということもできます。
自由民主党、日本維新の会の支持母体が、カルト教団「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」を母体とする「国際勝共連合(共産主義に勝利するための国際連盟)」で、この「国際勝共連合」と「日本財団」「日本会議(神道政治連盟を含む)」と密接につながっていることは、メディアも伝えないことから、「公明党の支持母体は、創価学会」のように、わかりやすい構図が見えないことが、狡猾で、厄介なところです。
“保守”と位置づけられる立憲民主党と国民民主党、“極右・超保守”と位置づけられる自由民主党・日本維新の会、公明党のオール保守の大きな違いは、エ)の政治団体との関係が深いか浅いか、関係の深い議員が多いか少ないかの違いです。
つまり、日本には、極右・超保守、保守に加え、太平洋戦争敗戦後の地政学的に左派(日本社会党、日本共産党)はありますが、正当な「リベラル政党」は存在しません。
「リベラル」は、「人権」を背景にした「個人」の意思を尊重し、「よい考えがあれば、たとえ急でも、古い昔からのやり方は捨てて、一からやり直し、社会を変えて行こう」と考え、行動する人のことです。
太平洋戦争敗戦後の日本は、極右・超保守、保守、地政学的な左派の中で、「リベラル」は育ちませんでした。
欧米諸国の「保守」と「リベラル」の構図では、ナチスドイツの反省から、超国家主義・極右主義、超保守は小さな政党で、少しでも議員数が増えるなどの動きが見えると、市民は抑止の機能を果たしますが、太平洋戦争敗戦後もその超国家主義・極右主義、超保守が政権を担い続けている日本は、異様な国家といえます。
唯一、超国家主義・極右主義、超保守を“規制”する役割を果たしてきたのが、『日本国憲法』の9条((戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認)です。
そして、日本に正当な「リベラル政党」が存在しなかったことが、上記の「律令制」に由来し、儒教思想にもとづく「家制度(家父長制)」の流れを汲む『家族法(民法)』を放置し、「再軍備」に不可欠なのは「税制度(税制改革を含む)」で、日本は、戦前の「家(家制度(家父長制))」を基軸に制度設計され、太平洋戦争敗戦後もそのまま継承した「税制度(社会保障制度(年金制度を含む)を含む)」を廃止し、「個人」を基軸した制度設計に変更しなかったこと、そして、これらの思想・イデオロギーに大きな影響をもたらす「人権意識」が日本社会に根付かなかった大きな要因となっています。
超国家主義・極右主義、超保守の人たちは、『世界人権宣言』『人権条約』の「人権」と馴染まない(真逆の)思想・イデオロギーにもとづく政治姿勢で、批准・締結した『女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約)』『子どもの権利条約』を“背景(各「委員会」による是正勧告)”に進められた『男女雇用機会均等法』、『児童虐待の防止等に関する法律(以下、児童虐待防止法)』と『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(当時)(以下、配偶者暴力防止法)』の制定、「子どもを懲戒する権利(民法822条)」の削除、110年ぶりの刑法改正(性犯罪の厳格化)で『強姦罪(刑法177条)』を『強制性交等罪』に、6年後の「刑法改正(性犯罪規定の見直し)」で『不同意性交等罪』への変更、「性交同意年齢のひき上げ」、「女性(児童婚)の婚姻年齢のひき上げ(民法731条)」など、「女性と子どもが獲得してきた権利」が、疎ましく、鬱陶しく、忌々しいと思っています。
「ナショナリズム」の民族主義と「超保守」の自国のことを極端に優れているとの認識が結びつくと、自分の人種が最上であると考え、他の人種を見下し、公平に扱おうとしない「レイシスト(人種差別主義者)」として、苛烈な「ヘイト(憎悪)スピ-チ」に至ります。
性差別的な態度が強い権威的な男性に対し、男女平等を訴えると女性により攻撃的になり、女性に向けられるこの性差別がいきつくと、女性を狙った殺人「フェミサイド」となり、この「ミソジニー」が存在します。
ミソジニーとは、「女性に対する憎悪、嫌悪、差別意識」のことです。
この人たちは、「女性と子どもが獲得してきた権利」を疎ましく、鬱陶しく、忌々しく思っている人たちと合致します。
日本社会で、性差別的な態度が強く、自身が、「家」の家父長(権威者)と自認している男性は、女性に対するDV行為、子どもに対する虐待行為を「懲戒」と認識しています。
この「懲戒」との認識は、明治政府が進めた「軍国化(国民皆兵、富国強兵)」を支えた「家制度(家父長制)」のものでの「子どもに懲戒する権利(民法822条)」の拡大解釈した「家」の「家父長」が、子どもだけではなく、配偶者の妻に加えてきた認識にもとづき、彼らは、その時代は許されてきたので、いまも許されると認識し、同時に、あとからできた「DV」「児童虐待」は存在しない(受け入れない)と認識しています。
この視点に立つことができると、ア)DV加害者の一定数が、交際相手や配偶者に自身の行為を暴力、DVと指摘したとき、そのことばに過剰反応を示し、「暴力じゃない」「DVじゃない」と否定し、自己弁護に走ったり、イ)極右・超保守の超党派「共同養育支援議員連盟(前.親子断絶防止議員連盟)」代表の柴山昌彦元文部科学大臣が、令和5年(2023年)1月、北日本放送の番組で、「被害者とされる方々の一方的な意見により、子どもの連れ去りが実行されてしまうことが本当に問題ないのかどうか。公正な中立な観点から、DVの有無とか、本当に耐えられるものか耐えられないものであるかということを判断する仕組みの一刻も早い確立が必要だ」との発言に至ったりする“背景”には、この「DVではなく、懲戒」との認識があることがわかると思います。
このレポート『主体は親で子どもは客体と位置づける「共同親権制度改正案」-「子の意見の尊重(子の意思表明権)」の不記載は、「子の最善の利益」を脅かす-』では、「G7の中でもっとも遅れている。」、「G7の中で、これほどまでに後ろ向きな国は他にない。」と指摘される「律令制」、儒教思想にもとづく「家制度(家父長制)」の流れを汲む日本の『家族法(民法)』の背景と深い関係にある極右・超保守の政権、政党、政治家、彼らと“共同体”ともいえる密接な関係を構築している日本財団、国際勝共連合、日本会議、神道政治連盟の政治姿勢(思想・イデオロギー)を踏まえ、ⅰ)「共同親権法案」の問題点(懸案事項)、ⅱ)「家制度(家父長制)」が支えた「軍国化(国民皆兵、富国強兵)」との関係性を踏まえ、「再軍備」のための『日本国憲法』の改正に向けた関連法案を整理しました。
あいさつ
政治(国を治める)の主な役割は、「法律」を制定(法改正を含む)したり、国を治めるために必要な「予算」を決定したりするために審議し、決定することです。
「法律の制定」や「法改正」は、制定・改正に至るプロセスを踏まえて、極めて政治的、つまり、実権を握る政権、政党、政治家、その政治支援団体の政治的な姿勢・意図の影響を強く受け、議員数というパワーの論理が明確に示されます。
本国会で、審議入りしている「法案」の幾つかは、平成15年(2003年)9月、「清和会」の小泉純一郎元首相のもとで、ナショナリストで極右・超保守の安倍晋三元首相が、当選3回(当時49歳)で自由民主党の幹事長に就任して以降、実権を握り続ける極右・超保守の政権、政党、政治家、以下に示す彼らと“共同体”ともいえる強固な関係にある政治団体ア)イ)ウ)エ)が、虎視眈々と、着実に、用意周到に準備を進めてきたものです。
日本の“極右”“超保守”の政治が、どのような思想・イデオロギーのもとで、「法律」を制定(法改正を含む)したり、「予算」を決定したりしているのかを知らずに、成立させてしまうと危険です。
なぜなら、日本の“これから)”に致命的な影響を及ぼす「法案」だからです。
本国会で、審議入りしていない「法案」を含めて、直接、ⅰ)敗戦後、日本の“復興”としての悲願である「再軍備」のための『日本国憲法』の改正、ⅱ)「再軍備」に欠かせない「家制度(家父長制)」と「子どもに対する愛国心の醸成教育」の実質的な強化につながるものです。
つまり、日本の“これから”に致命的な影響を及ぼしかねないこと踏まえると、令和6年(2024年)の本国会は、日本の“これから”を決めかねない重大な局面であることを意味します。
そのためには、日本で、実権を握り続ける極右・超保守の政権、政党、政治家、その政治支援団体の実態を正確に知ることが不可欠で、それには、日本の歴史的背景にもとづく彼らの思想・イデオロギーを知る必要があります。
令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」と深く関係する日本の『家族法(民法)』は、欧米諸国から「G7の中でもっとも遅れている」、「G7の中で、これほどまでに後ろ向きな国は他にない」と指摘されています。
この“指摘”を考えることは、なぜ、日本で女性として生まれると生き難いと感じるのか? なぜ、夫婦共働きでも女性だけがあたり前のように自己犠牲(家事の分担)を求められるのか? に対する“解”を導きます。
その“解”は、日本の『家族法(民法)』は、「律令制」「儒教思想」の影響を強く受けていることです。
なぜなら、「儒教思想」は、中国の「春秋戦国時代(紀元前770年に周が都を洛邑(成周)へ移してから、紀元前221年に秦が中国を統一するまで)」の儒学者(諸子百家(孔子・老子・荘子・墨子・孟子・荀子など))の教え(儒教)にもとづくことから、女性蔑視・男尊女卑(男を尊び女を卑しめる)が色濃く示されているからです。
女性蔑視・男尊女卑(男を尊び女を卑しめる)が色濃く示される「儒教思想」は、男女平等を“前提”とするグローバルスタンダードな「人権」とは対極に位置づけられるからです。
この「儒教思想」は、日本社会で、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力(緊急避妊薬、中絶薬の導入を含む)、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力問題は、人権侵害問題であるとの認識に立つことができない要因となり、その認識の大きな心理的障壁(防衛機制)となっています。
この「儒教思想」は、日本では、例えば、江戸時代では人口の7%に過ぎなかった「武家」の教育・規範でしかなく、「家制度(家父長制)」も「武家」だけの制度でした。
しかし、明治政府が進めた「軍国化(国民皆兵、富国強兵)」には「税制改革」が不可欠で、その「税制改革」には「家」を基軸とする徴収が必要で、そのために設けたのが「家制度(家父長制)」、その「家父長」に与えたのが「親権」です。
そのため、日本の『家族法(民法)』に定められている「親権」には、「親(家父長)」の権利の行使という意味合いが強くなっています。
つまり、「親権者」は、子どもについての重要事項を決定する権利を持ちます。
そして、江戸時代の「寺請制度」で仏教の説話に親しんでいた一般市民(ほとんどが農民)に儒教思想にもとづく「家制度(家父長制)」を定着させるために実施したのが「道徳教育」です。
「道徳」は、「子どもは父母に孝行しなさい」という儒教思想にもとづいています。
日本の戦前の「道徳」では、ここに、日本神話を祖とする天皇の神格化を踏まえた「神道(思想)」が加わります。
そのため、儒教思想にもとづく家族像(観)は、「男性は、忠義を心に、主君と国のために身を捨てる」、「女性の幸せは、結婚し「家」に入り、子どもを持ち、「家」の繁栄に尽くし、父母に孝行すること」であり、「子どもの幸せは、厳しい「懲戒(しつけ(教育)と称する体罰)」があっても、両親の下で育ち、両親を敬い、孝行する」ことです。
この「家」における女性の役割は、「武家の女性」のように、自己犠牲なくして成り立たない「内助の功」「良妻賢母」に徹することです。
極右・超保守の人たちは、この儒教思想にもとづく家族像(観)を「伝統的家族像(観)」、この“精神”で、主君と国に忠誠を誓い、主君と国、家のために尽くすことを「愛国心」と呼びます。
また、明治政府により構築された儒教思想にもとづく家族像(観)について、「いままでの伝統や文化や考え方」なので、この「家族像(観)にもとづく社会を維持していく。それがあたり前」との考えは、「保守的」な価値観となります。
OECD(経済協力開発機構)に加盟38ヶ国の中で、「儒教思想」の国家は、大韓民国(韓国)と日本の2ヶ国で、この2ヶ国で際立っているのが、男女間の賃金格差、男女間の家事労働時間格差です。
この『レポート』では、このように、一見、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」とは関係がないように見える「律令制」「儒教思想」「家制度(家父長制)」が、日本の『家族法(民法)』を理解するうえでは不可欠であり、また、「共同親権法案」に至っては、この「共同親権法案」の成立・施行を目指している人たちの思想・イデオロギーを理解することが不可欠であることから、「ナショナリスト」「極右」「超保守」「神武創業」「八紘一宇」「日本神話」「安保闘争」「岸信介元首相」「安倍晋三元首相」「日本財団」「国際勝共連合(統一教会)」「日本会議」「親学」「神道政治連盟」「共同養育支援議員連盟(親子断絶防止議員連盟)」「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)」「国連(国際連合)」「世界人権宣言」「子どもの権利条約」「女性差別撤廃条約」などの表記(キーワード)が幾つもでてきます。
また、「人権」と「人格」、「人権」と「儒教思想にもとづく道徳」、「親権」と「監護権」、「親の権利」と「親の務め(義務)」など、ことばが似ていても意味がまったく異なることば、対極にあることばが幾つもでてきます。
この理解は、日本の法の解釈、日本政府の政治姿勢を理解するうえで、重要な意味を持ち、この理解は、ことばは似ていても異なることばを使う人とのやりとりは成り立つのかという問題の解を示します。
例えば、「女性の幸せは、結婚し「家」に入り、子どもを持ち、「家」の繁栄に尽くし、父母に孝行すること」であり、「子どもの幸せは、厳しい「懲戒(しつけ(教育)と称する体罰)」があっても、両親の下で育ち、両親を敬い、孝行する」ことと理解し、その「家」における女性の役割は、「武家の女性」のように、自己犠牲なくして成り立たない「内助の功」「良妻賢母」と考える保守的な価値観の人と、保守的な価値観を支持しないリベラルな人のやり取りは噛み合うでしょうか? 女性蔑視・男尊女卑の「儒教思想にもとづく道徳」を背景にした主張と、男女平等を前提とした「人権」を背景にした主張は噛み合うでしょうか? 「親権を親の権利(親権の主体は親)」と認識している人と、「親権を親の務め(親権の主体は子ども)」と認識している人のやり取りは噛み合うでしょうか? 自分は、実質的な「家」の家父長(権威者)で、妻や子どもに対する「懲戒(しつけ(教育)と称する体罰(身体的虐待、DV行為としての身体的暴力)」は正しい行為と認識している人と、それは人権侵害行為と認識している人のやり取りは成り立つでしょうか?
これは、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」に賛成している人と「共同親権法案」に反対の声をあげている人の考え方の違いを示しています。
いままで、「日本はどういう国なのかなどあまり考えたことがなかった」と人権・社会問題と距離を置いていたり、政治に無関心だったりした人にこそ、ぜひ、一読していただければと思っています。
なぜなら、“これから”の日本で生活する人には、直接関係することだからです。
“これから”の日本で生活する人が、気がついたときには、戦前のように、「軍国化されていた」、「結婚し、子どもを持ったら離婚できなくなっていた」、「子どもの教育の方針を国が決めていた」、「皆で国の政策に意を唱える声をあげたら、国に逮捕・拘束されるようになっていた」とならないために、いま、社会問題(人権問題)と距離を置かず、政治に関心を持っていただけることを切に願います。
令和6年(2024年)4月8日
(改訂版)同年4月22日
DV被害支援室poco a poco 庄司薫
少し長いはしがき
あいさつ
はじめに。
・用語説明。極右・超保守・保守、左派、リベラル、ナショナリスト
・日本は儒教社会。いまも、実質的な「家制度(家父長制)」であることに無自覚
・「神武創業」とファンタジーストーリー「日本神話」、男尊女卑の由来
・『教育勅語』『八紘一宇(君が代)』と「皇民化教育」
・軍国化と教師による「懲戒」。がまんし、耐え抜くことを美徳する精神論・根性論
・岸信介元首相とアヘンマネー、フィクサー、カルト教団、暴力団と
の結びつき
・日本には、政治に影響力のある市民運動が存在しない
・リベラルが育つ土壌と意思表明権。人権教育と道徳教育の違い
1.「律令制」「家制度(家父長制)」の流れを汲む『家族法(民法)』
(1) 夫婦同姓制度(民法750条、戸籍法74条1号)の日本の税制度 ① 女性差別撤廃委員から繰り返されている是正勧告
② 戦前の「家」を基軸に制度設計された「税制度」を継承
・軍国化と「税制」、「税制」を支えた「家制度(家父長)」
・日本の男女間の賃金格差。OECD(経済協力開発機構)に加盟38ヶ国の中で37位
・男女間の賃金格差と「ジェンダーギャップ指数」
・負の遺産をつくりあげた「アベノミクス」
・相対的貧困率。7人に1人の子どもが貧困
(2) 協議離婚制度(民法763条)と離婚事由(民法770条)の規定
(3) 単独親権(民法819条)と養育費の不払い
・母子家庭の養育費と面会交流のとり決めの現状
2.第1の「法案」 『家族法(民法)』の改正(離婚後の共同親権制度) 64
(1) 「離婚後の共同親権制度の導入」を主導してきたのは
・「親子断絶防止議員連盟」の議員連盟案『共同養育支援法』
・柴山昌彦元文部科学大臣の「本当に耐えられないDVか発言」の背景にある「懲戒」認識
・ナショナリストで、極右・超保守な人に極めて邪魔な『配偶者暴力防止法』
(2)「家制度」を継承。「単独親権(民法819条)」は核家族化で変化
① 新しい構図のもとで新たな「単独親権制度」がはじまるまでの経緯
② 核家族化のもとでの新たな「単独親権制度」。父母の立ち位置
③ 新しい構図のもとでの新たな「単独親権」。都合が悪くなった人々
(3) 欧米諸国。フレンドリーペアレント(FP)を見直し、法改正の動き
(4) 「子どもの意見の尊重(子どもの意思表明権)」の未記載
・『世界人権宣言』と9つの主な『人権条約』
・126年間続いた「子どもを懲戒する権利」。いまも7割が「体罰」を容認する異常
(5) 子どもの「人権の尊重」と「人格の尊重」の決定的な違い
① 似通っていて、まったく異なる意味の「人権」と「人格」
② 「道徳教育」では、人権・社会問題にとり組む視点は育たない
③ DV・虐待問題、先進的なとり組みが進む欧米諸国と遅れる日本
(6) 子どもを懲戒する権利。被虐待体験と精神疾患発症との深い関係
① 被虐待体験(小児期逆境体験)と深い関係にあるひきこもり
② 数字に示される被虐待体験(小児期逆境体験)を起因する社会病理
3.「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」の懸案事項-ⅰ)ⅱ)ⅲ)
(1) 日本で「離婚」するには
① 離婚方法と離婚事由
・離婚調停・裁判離婚における「離婚事由」はすべてDV事案に絡む
② 離婚後の氏(姓)の変更
(2) 離婚後の親権の決定
・「離婚条件」として、「共同親権」の選択を強いられる可能性
(3) 親権と監護権
(4) 「共同親権法案」の懸案事項-ⅰ) 離婚した父母の合意
・「共同親権法案」の成立・施行で、増加が予想される係争事件。逆に裁判所職員を削減
・「同意」の名の下で懸念されるレイプ被害
(5) 「共同親権法案」の懸案事項-ⅱ) 明確さに欠ける「急迫の事情」
(6) 離婚理由「性格の不一致」は、離婚後の話し合いを困難に
(7) DV・児童虐待の“規定”が「単独親権」の判断に
① 『配偶者暴力防止法』の致命的な欠陥-ⅰ)
② 『配偶者暴力防止法』の致命的な欠陥-ⅱ)見せかけの適用の拡大
a) 『配偶者暴力防止法』の適用の拡大は見せかけで、適用を困難に
b) 「保護命令の申立て数」と「保護命令の申立てに対する発令数」
c) 令和5年(2023年)5月12日の「法改正」
③ 『配偶者暴力防止法』の致命的な欠陥-ⅲ)適用対象外の「性的暴力」
➃ 配偶者殺人。3.44日に1人、妻は夫に殺される
⑤ 「共同親権」と婚姻関係にない子どもの父親の「子どもの認知」
⑥ DV加害者の主張と「子どもの連れ去り」の2パターン
⑦ 虐待被害とDV被害の経済的損失
⑧ ユニセフの「提言」と日本乳幼児精神保健学会の声明
(8) 「共同親権法案」の懸案事項-ⅲ) 面会交流が祖父母まで拡大
(9) 「共同親権法案」の懸案事項-ⅳ)「共同親権」で収入は父母合算に
4.「離婚後の共同親権制度」の法制化に至る経緯
(1) 離婚後の子の監護(民法766条)。面会交流と『人権条約』
① 「女性差別撤廃委員会」の日本政府に対する是正勧告
② 『民法766条』の改正と面会交流調停の推移
③ 全米法曹協会は「片親疎外症候群」はエセ科学、信用性否定
(2) 共同監護のための法整備に対する「子どもの権利委員会」の勧告
(3) 家族法制部会の『家族法制の見直しに関する中間試案』
(4) 離婚後の子の養育をめぐる制度の見直しに向けた民法改正要綱案
5.第2の「法案」 家庭教育支援法
・「日本財団」「日本会議」が主導。『こども基本法』、『子ども家庭庁』の設立の経緯
6.第3の「法案」 『日本国憲法』に創設「緊急事態条項」
・アメリカの保守政党「民主党」と“ネオコン”。日本の極右・超保守と“共鳴”
・地政学的に、日本は「専守防衛」は不可能で、「反撃能力」を持つことはあり得ない暴挙
7.第4の「法案」 重要経済安保情報保護法
最後に。
はじめに。
いまから20年6ヶ月前の平成15年(2003年)9月、ナショナリストで、極右・超保守の安倍晋三元首相は、当選3回(当時49歳)で、自由民主党の幹事長に就任し、党内ではじめて「国政選挙における候補者選考に公募制度」を導入しました(令和6年(2024年)4月15日現在)。
ここで、思想・イデオロギーを同じくする人、つまり、ナショナリストで、戦前の日本をとり戻し、「再軍備」のための「憲法改正」を支持する(志を同じくする)人を採用し、党内で仲間を増やし、同時に、母方の祖父でナショナリストの岸信介元首相以降の日本の政治と深くかかわってきた極右・超保守の政治団体と“共同体”ともいえる強固な体制をつくりあげました。
「思想」とは、人生や社会についてのひとつのまとまった考えや意見のことで、政治的、社会的な見解を示し、「イデオロギー」とは、社会のあり方などに対する考え方、人の行動を左右する考え方や信条のことです。
つまり、人が政治、経済、司法、福祉、教育などの人権・社会問題を考えたり、見解を述べたり、行動したりするときのモノサシ(判断基準)なるのが思想・イデオロギーで、「極右」「超保守」「保守」「左派」、「リベラル」といった政治姿勢の根幹となるものです。
日本の政治と深くかかわってきた極右・超保守の政治団体とは、保守的な日本の大手企業を中心に構成された経済団体「日本経済団体連合会」に「日本商工会議所」「経済同友会」を加えた「経済3団体」ではなく、主に、ア)安倍晋三元首相の母方の祖父で、ナショナリスト、『日米安保条約(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約)改訂案』を強行採決し、「安保闘争」を招いた岸信介元首相以降の自由民主党を支え続けている笹川良一(子ども番組の時間帯を狙いテレビ広告を流し続けた「お父さん、お母さんを大切にしよう。一日一善!」の人)が創設した「日本財団(日本船舶振興会)」、イ)日本海を挟み、ソビエト連邦(社会主義)、中華人民共和国(共産主義)、東シナ海の台湾、資本主義と社会主義で分断された朝鮮半島と南シナ海に面するインドネシア半島(ベトナム)といった地政学上、左翼や新左翼の運動家が参加した反政府・反米運動(安保闘争など)に警戒心を強めたCIA(アメリカ中央情報局)主導の下で、岸信介(元首相)、戦後最大のフィクサーと呼ばれた児玉誉士夫、「日本財団」の創始者である笹川良一らが創設したカルト教団「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」を母体とする「国際勝共連合(共産主義に勝利するための国際連盟)」、ウ)「安保闘争」の活動を経て創設され、「生長の家」関連団体の在籍時に「親学」を提唱した高橋史郎氏が中心メンバーの日本最大の超国家主義・極右主義団体「日本会議」、エ)役員の多くが「日本会議」の役員・幹部を兼務する「神道政治連盟」などです。
「第1次安保闘争(昭和35年(1960年)5-7月)を経て、「第2次安保闘争(昭和45年)」直前の昭和44年(1969年)刊行の『創価学会を斬る(藤原弘達)』の中で、「自由民主党と公明党の連立が実現したら、自由民主党のタカ派的、右翼的、ファシズム的要素と、公明党の母体となる「創価学会」の宗教的ファナティックな要素が結合して、日本はとても怖ろしい方向に進む」と指摘していますが、それから30年を経た平成11年(1999年)、野中広務官房長官(当時)が、小渕恵三政権で、公明党との連立政権として実現します。
いまから24年前のことです(令和6年(2024年)4月15日現在)。
「ファナティック」とは、熱狂的、狂信的な状況を意味します。
「怖ろしい方向に進む」との指摘は、この「宗教的ファナティック」が、「ポピュリズム(populism)」と結びつきやすいからです。
葛藤、悩み、苦しみ、哀しみ、不満、憎しみ、怒りなどの思い(感情)を秘めている人は、短く、わかりやすく、力強いことばでその思いを訴えられると、そのメッセージは、心に響き、共感しやすいという傾向があります。
「ポピュリズム」は、人の持つこの傾向を巧みに利用します。
つまり、「ポピュリズム」は、政治指導者、政治活動家、革命家が、不満を募らせていたり、利得を求めていたりする大衆に対し、大衆の不満や利得など一面的な欲望に迎合して大衆を操作する方法です。
「大衆を操作する」とき、不満を募らせていたり、利得を求めていたりする大衆は、短く、わかりやすく、力強いことばで訴え、聴衆の心を捉えることだけにフォーカスします(この『レポート』とは対極です)。
このとき、正しいことを選択する理性よりも、気持ち(感情)に響き共感できること、つまり、承認欲求が満たされることが優先されます。
そのため、その訴えの内容や実現のための方法が正しいかどうかは問題ではなく、大衆の欲望に沿うことができれば、聴衆の心を捉え、聴衆が大挙を成すシュプレヒコールを意図的に扇動することができます。
新政府軍(明治政府)による天皇の「神格化」と「国民皆兵」「富国強兵」はポピュリズムを駆使した国家的なキャンペーンの下で進められ、また、ヒトラーの独裁は、ナチス政権が1933年(昭和8年)に創設した「宣伝省」のもとで、ヒトラーのカリスマ性を前提としたナチスのポピュリズムを効果的に演出することで成し遂げました。
また、小泉純一郎政権での「郵政民営化」での「自由民主党をぶっ壊す!(単なる党内の反対勢力の排除)」はポピュリズムの典型です。
2016年(平成28年)、アメリカ合衆国の大統領選で、共和党のドナルド・トランプ元大統領が掲げたスローガンは「America First(アメリカ第一主義)」で、反グローバリズムとポピュリズムが勝利をもたらしています。
ポピュリズムの表現は、テレビニュースや討論番組などで、定められた時間で、(視聴者受けのいい)テンポがよく、力強く(過激で、大げさ)、短いことばが求められるのと同じです。
そのため、正確な解説は求められず(嫌われ、興味を持たれず)、正確性に欠けている、根拠(裏づけ)がないことは問題(失言で炎上だけは避けたい)にはなりません。
大阪圏のテレビ番組では、平成20年(2008年)1月27日、「大阪府構想」を掲げた橋下徹弁護士が大阪府知事選挙に当選すると、以降、吉本興業に在籍する芸人とのコンビで、これまで以上にポピュリズム化が進み、極右・超保守政党「大阪維新の会(日本維新の会)」は議員数を拡大し続けています。
しかし、この極右・超保守政党「大阪維新の会(日本維新の会)」の政治母体が、自由民主党の政治母体であるカルト教団「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」を母体とする「国際勝共連合(共産主義に勝利するための国際連盟)」であること理解している人はどのくらいいるのだろうか?
突然、“ボッ”と火の手があがるように、極右・超保守の政治家が増えているのが、ポピュリズムの怖いところです。
また、自由民主党とカルト教団「創価学会」との関係は、安倍晋三元首相の母方の祖父であり、ナショナリストの岸信介元首相と、「創価学会」の第2代会長の戸田城聖(昭和33年(1958年)4月2日没)と関係に遡ります(フランスでは、「創価学会」はカルトと認定されています)。
岸信介元首相は、首相時に招かれた「創価学会の儀式」に、妻(良子)、3女(岸洋子)、岸洋子の夫の安倍慎太郎元外相を出席させ、その後、岸信介元首相の3女岸洋子と安倍慎太郎元首相の長男、つまり、安倍晋三元首相が、首相時に参加した公明党の大会に参加しています。
そのとき、安倍晋三元首相は、「御党と岸家の関係は、自分の祖父の代にまでさかのぼる」と述べています。
その後、岸信介元首相は、児玉誉士夫、笹川良一とともに、昭和43年(1968年)4月1日、カルト教団「世界基督教統一神霊協会(統一教会)」を母体とする「国際勝共連合(共産主義に勝利するための国際連盟)」を創設させています。
岸信介元首相とカルト教団との結びつきを見ると、ファンタジーストーリー「日本神話」をもとに、明治政府の国造りの礎となった「神武創業(神武天皇の時代に戻れ!)」を祖とするナショナリズムは、カルト教団「創価学会」「世界基督教統一神霊協会(統一教会)」との親和性が極めて高いこと裏づけています。
『日本国憲法』では、「国家が特定の宗教と結びつくと、国家が正しい判断ができなくなる怖れがある」と戦前の反省を踏まえて、「政教分離(20条1項後段、20条3項、89条)」を定めていますが、太平洋戦争敗戦後も「神道」と結びつくナショナリズムは、タカ派、右翼、ファシズムと「神道」を主とするカルトは深く結びついています。
この「自由民主党のタカ派的、右翼的、ファシズム的要素は、「創価学会」「世界基督教統一神霊協会(統一教会)」の宗教的ファナティックな要素と結びつきやすい」という視点に立つことができると、イ)ウ)エ)との“共同体”ともいえる密接な関係性は必然であることが理解できると思います。
イ)の戦後最大のフィクサーの「フィクサー」とは、通常、社会生活では、正規の手続きを経て意思決定を進めていきますが、資金、政治力、人脈を駆使し、正規の手続きを経ることなく、意思決定プロセスに介入する人のことです。
ウ)エ)が役員・幹部が兼務している政治団体「神道政治連盟」の「神道」には、キリスト教の「聖書」、イスラム教の「コーラン」に該当する「正典」は存在しませんが、『古事記』『日本書紀』『古語拾遺』『先代旧事本紀』『宣命』といった「神典」と称される古典群が、神道の聖典とされています。
つまり、ファンタジーストーリー「日本神話」を思想・イデオロギーとしています。
「神道」では、森羅万象に神が宿ると考え、また、偉大な祖先を神格化し、天津神・国津神などの祖霊を祭り、祭祀を重視します。
そのため、日本軍将兵(明治以降の日本の戦争・内戦において政府・朝廷側で戦歿した軍人ら)を祀る「靖国神社(明治2年(1869年)6月29日創建の「招魂社」に由来する)」、神々を統一し日本を建国(紀元元年・約2680年前)した神武天皇を祀る「橿原神宮(明治23年(1890年)4月2日創建)」は特別な意味を持ちます。
なぜなら、「日本軍将兵」は、日本の建国神話「神武東征神話」で、神武天皇と東征に同行した「武将の大判氏(天忍日命)の子孫」と崇められたからです。
この「日本軍将兵は、神(天忍日命の子孫)である」ことは、戦前・太平洋戦争敗戦からいまに至るまで、日本の精神医療と福祉行政、学校園などの教育の現場にも大きな影響を及ぼしています。
日本の精神科医療において、「第1次世界大戦(大正3年-同7年(1914年-1918年))」「第2次世界大戦(昭和14年-同20年(1939年-1945年))」に参戦した欧米諸国と異なり、「砲弾ショック(PTSD)研究」が致命的に遅れたのは、神の子孫である日本軍の将兵は、特異な精神疾患とされた「砲弾ショック(PTSD)」を発症するはずがない(発症してはいけない)からです。
そのため、戦時中の日本では、日本軍将兵の指揮にかかわるとして、「砲弾ショック(PTSD)」の存在そのものが隠され続け、結果、「砲弾ショック(PTSD)」に対する治療のための研究は封印されました。
第2次世界大戦後(太平洋戦争後)の同じアジアで、朝鮮戦争、ベトナム戦争の帰還兵の多くがPTSDを発症し、研究・治療が進む中で、敗戦後の日本政府は、「軍人(帰還兵)に対する補償(軍人恩給)問題」が絡むことからこの問題にとり組むことなく封印したことは、旧帝国大学系の大学におけるPTSD研究の遅れにつながり、先進的にとり組んできた欧米諸国から致命的な差が生まれました。
アメリカ政府は、平成16年(2004年)時点で、ベトナム戦争から帰還した元兵士でPTSDの症状に苦しむ21万7,893人に対して補償を続けていますが、この政治姿勢の違いが、医療、福祉行政、司法などのとり組み、市民の理解などの大きな差となっています。
日本で、PTSD発症した人は、いまだに、専門医につながり難いだけではなく、PTSDの症状や傾向に理解のない精神科医による不適切な治療がおこなわれたり、時に、PTSDに疑心暗鬼な精神科医による2次加害として、心ないことばを投げつけられたりすることが少なくありません。
存在が隠された「砲弾ショック(PTSD)」は、日本の司法、警察、福祉行政、学校教育、そして、一般市民に至るまで、同様の問題をもたらしています。
精神疾患者・身体障害者、からだの弱い者に対する偏見・差別は、「神(天忍日命)である日本軍将兵」になれない者(徴兵検査に受からない者)に対する否定・卑下(見下す)に由来します。
少なくともベトナム戦争(1960年代初頭から1975年4月30日)の終戦から48年11ヶ月経過している中で、PTSDの症状に理解を示さず、PTSDを発症した人に対し肝要でない日本社会は異常です(令和6年(2024年)4月15日現在)。
また、日本最大の超国家主義・極右主義団体「日本会議」が主導する「親学」は、もともと、パナソニック(松下電工)創業者の松下幸之助が創設した「PHP研究所」の教育改革の中で、「親学アドバイザーの配置」として提唱されたものです。
この「PHP研究所」は、多くの国会議員を輩出した「松下政経塾」とは姉妹関係で、「松下政経塾」出身の国会議員は、令和5年(2023年)12月1日現在35名で、衆議院議員26名(自由民主党11名、立憲民主党10名、国民民主党2名、日本維新の会1名、無所属2名)、参議院議員9名(自由民主党5名、立憲民主党3名、日本維新の会1名)、同首長(知事)は2名(宮城県、滋賀県(いずれも無所属))となっています。
20年6ヶ月前の平成15年(2003年)9月をターニングポイントとして、日本の政治は、これまで以上に極右化・超保守化し、同時に、極右・超保守を含めた保守(政党・政治家)が圧倒的多数の議席を確保し続けていることから、その政治姿勢は、強権化しています。
ナショナリストで、極右・超保守の安倍晋三元首相は、平成18年(2006年)9月29日、第1次安倍晋三政権の「所信表明演説」で、新政府軍の倒幕スローガン「神武創業(神武天皇の時代に戻れ!)」、太平洋戦争のスローガン「八紘一宇(君が代)」と同意といえる「美しい国創り」を宣言し、「教育再生実行会議」をつくるなど、極右・超保守の政治姿勢の背景にある思想・イデオロギーを前面にだした政策(「法」の制定・改正)を進めました。
平成19年(2007年)、第1次安倍晋三政権は、『日本国憲法』の改正(9条(戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認)の削除)に向けて、『国民投票法』を強行採決しました。
その後、この『国民投票法』は、令和3年(2021年)5月7日、菅義偉政権のもとで、改憲のための手続きを定めた「改定案」が、衆院憲法審査会で修正のうえ可決しています。
続けて、第1次安倍晋三政権は、政府の意に反する者の声を排除し、従順に従う者を登用するために、平成20年(2008年)、『国家公務員制度改革基本法(国家公務員法等の一部を改正する法律)』、『独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律』、『行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』の3つの法律を成立させました。
『国家公務員制度改革基本法』は、その後の与野党の反対で、なかなか前に進めることができませんでしたが、平成26年(2014年)、反対勢力を押さえ込むことに成功した第2次安倍晋三政権は、『国家公務員法等の一部を改正する法律(『内閣法』の改正)』を成立させ、同年5月30日、内閣官房に『内閣人事局』を設置しました(内閣法21条1項)。
これにより、首相官邸、つまり、安倍晋三政権は、「審議官級以上の国家公務員の人事権を掌握する」ことに成功しました。
このことは、首相官邸、つまり、政権(日本政府)が望む(目論む)法案の作成を官僚(国家公務員)に命じることができることを意味します。
政治家・政党の主な仕事は、法案をつくり、その法案を国会で通すことです。
法務省で「審議官級以上の国家公務員」は、官房長、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官6人(国際・人権担当、民事局担当、刑事局担当、矯正局担当、訟務局担当(2人)です。
この「審議官級以上の国家公務員の人事権の掌握」は、実権を握る政権の意のままに法案をつくることができ、国会で過半数をとることができれば、賛成多数で、その法案を容易に成立させることができます。
つまり、平成26年(2014年)5月30日、首相官邸は、独裁に通じる絶対的な権力を得たことを意味します。
例えば、「法案」を検討する「法務審議会」は、法務大臣が命じるので、法務省の問題ではなく、政治的なもので、その「審議官」の人事を首相官邸が握っているので意に添う方向で進めることができます。
「法」を制定したり、「法」を改正したりするのは、「法務省」の移行ではなく、極めて政治的であることがよくわかる事例があります。
それは、他国にはない、世界で唯一の『夫婦同姓制度(民法750条、戸籍法74条1号)』に関するものです。
第2次世界大戦終戦から3年後の1948年(昭和23年)12月10日、国際連合(国連)は、人権法の柱石(すべての人民にとって、達成すべき共通の基準)として『世界人権宣言(Universal Declaration of Human Rights)』を採択しました。
この『世界人権宣言』では、第1条「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」、第3条「すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。」と記述しています。
日本は、太平洋戦争敗戦後、『日本国憲法』の24条(法の下の平等など)に反するとして、「家制度(家父長制)」を廃止しましたが、「律令制」、儒教思想にもとづく「家制度(家父長制)」の流れを汲む世界で唯一の制度の『夫婦同姓制度(民法750条、戸籍法74条1号)』、『協議離婚制度(民法763条)』に加え、『離婚後の単独親権制度(民法819条)』を継承しました。
そのうち、『夫婦同姓(民法750条、および、戸籍法74条1号)』は、この『世界人権宣言』の第1条の「人は、尊厳と権利とについて平等」に反する(違反する)として、国連の「女性差別撤廃委員会」は、『女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(以下、女性差別撤廃条約)』の批准・締結国(昭和60年(1985年)6月25日)である日本政府に対し、繰り返し改善勧告をだしています。
いまから32年前の平成3年(1991年)、法務省の法制審議会民法部会(身分法小委員会)は、「婚姻制度等の見直し」の審議を行い、その5年後の平成8年(1996年)2月、法制審議会が答申した「民法の一部を改正する法律案要綱」では、「選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)の導入」を提言しています(令和6年(2024年)4月15日現在)。
この答申を受け、法務省は、平成8年(1996年)と平成22年(2010年)に「改正法案」を準備しましたが、日本政府は、いずれも国会に提出しませんでした。
令和2年(2020年)12月、閣議決定した『第5次男女共同参画基本計画』では、この「夫婦の氏に関する具体的な制度のあり方」について、「司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める」と見解を示していますが、日本政府は、依然として「民法の改正」にとり組む姿勢を示していません。
つまり、法制審議会の答申を受け、「改正法案」を準備しても、政府が、「改正法案」を成立させる意思がなければ、幾らでもお蔵入りさることも容易にでき、逆に、政府肝入りの「法案」であれば、強行採決に持って行くことができます。
そして、極右・超保守の政権、政党、政治家、彼らと“共同体”ともいえる強固な関係を築いている上記ア)イ)ウ)エ)の政治団体は、第3次安倍三政権で国会提出を見送った『家庭教育支援法』の成立のために、令和4年(2022年)6年15日(同5年(2023年)4月1日施行)に『こども基本法』を成立させ、令和5年(2023年)年4月1日に『子ども家庭庁』を創設させました。
いま、その総仕上げともいえる同じ方向を向き、同じ線上で密接につながる4つの「法案」、つまり、ⅰ)『家族法(民法)』の改正(共同親権法案)、ⅱ)満州事変・太平洋戦争中の『戦時家庭教育要項』に通じる『家庭教育支援法』、ⅲ)戦前の『国家総動員法』に匹敵する「『日本国憲法』に新たに創設する「緊急事態条項」」、ⅳ)『特定秘密保護法』を拡大する『重要経済安保情報保護法(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律)』の成立を目指して(目論んで)います(令和6年(2024年)4月15日現在)。
「再軍備」のための『日本国憲法』の改正、「再軍備」にかかせない実質的な「家制度(家父長制)」と「子どもに対する愛国心の醸成教育」という同じ方向を向き、同じ線上で密接につながるこの「4つの「法案」」が可決・成立し、施行されると、“これから”の日本で生活する人たちにとって、極めて危険な「法律」・「制度」となります。
・用語説明。極右・超保守・保守、左派、リベラル、ナショナリスト
「超保守」とは、自国のことを極端に優れていると考えている人たちのことで、超保守派、右翼、極右、国粋主義者、タカ派、排外主義者、右派と表現されます。
「極右(far right, extreme right)」、「急進右翼(radical right)」、「超右翼(ultra-right)」とは、過激な保守主義、超国家主義、権威主義の傾向がある政治思想で、民族主義的傾向も示し、「極右」は、ファシズム、ナチズム、ファランギズムの経験を表現するために使われ、「極右政治」は、これまで、集団に対する弾圧、政治暴力、同化の強制、民族浄化、大量虐殺をひき起こしてきました。
現代的な定義には、ネオ・ファシズム、ネオナチ、オルタナ右翼、人種至上主義、その他の権威主義、超国家主義、排外主義、外国人嫌悪、神権主義、人種差別主義、同性愛嫌悪、トランスフォビア、反動的な見解を特徴とするイデオロギーや組織が含まれます。
「保守」とは、「いままでの伝統や文化や考え方、社会を維持していく」、つまり、「昔からのやり方に従うのがあたり前だ!」と考え、行動する人たちですが、同じ「保守」であっても、「人権」を背景にした「個人」の意思を尊重する他国(世界の圧倒的多数の国々)の「保守」と、「(儒教思想にもとづく)道徳観」を背景にした「家」「集団(組織)」の意思を尊重する日本の「保守」はまったく異なります。
同じ「保守」であっても、日本の「保守」は世界的に異質で、独得です。
「左派(左翼)」は、通常、より平等な社会を目指すための社会変革を支持する人たち(層)のことですが、太平洋戦争敗戦後の日本では、地政学上、「安保闘争(左翼や新左翼の運動家が参加した反政府・反米運動)」を踏まえ、「資本主義」と「共産主義」「社会主義」の対立構図であったことから、日本には、「保守」と「左派」の構図はありますが、「保守」と正当な「リベラル」の“構図”は存在しません。
例えば、平成5年(1993年)8月、日本新党代表の細川護熙(元首相)のもとで、日本社会党、新生党など非自民・非共産8党派の連立政権を樹立し、昭和30年(1955年)の結党以来38年間単独政権を維持し続けた自由民主党が下野することになりました。
いわゆる「55年体制の崩壊」ですが、日本の政治は、以降も保守に対抗するリベラル(革新)が台頭することはなく、立憲民主党・国民民主党を含め、保守内部の権力闘争(政権を握るための主導権争い)として少数政党が数多くできただけでした。
そして、安倍晋三元首相が幹事長に就任すると、極右・超保守の勢力が大きくなり、自由民主党の支援政治団体であるイ)のカルト教団「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」を母体とする「国際勝共連合(共産主義に勝利するための国際連盟)」を政治母体とする極右・超保守政党「日本維新の会」が台頭し、極右・超保守、保守の巨大勢力ができあがりました。
つまり、日本の政治体制は、「極右・超保守の政権(自由民主党・公明党)+極右・超保守(日本維新の会)+保守(立憲民主党、国民民主党)」と「左派(日本共産党)」の構図で、「中道左派」として「社民党(国会議員3名)」があります。
安倍晋三元首相が銃弾に倒れたことがきっかけで、自由民主党・日本維新の会をはじめとする政党とカルト教団「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」との密接な関係について、連日、メディアは報じましたが、肝心の政治団体「国際勝共連合(共産主義に勝利するための国際連盟)」にはまったく触れることはありませんでした。
この日本のメディアの報道姿勢もまた、異常です。
一方で、“これまで”の「(儒教思想にもとづく)道徳観」を背景にした「家」「集団(組織)」の意思を尊重するのではなく、“これから”は『人権法』の“柱石”である『世界人権宣言』に沿い、「人権」を背景にした「個人」の意思を尊重する社会に変えて行こうと考え、行動する人が、「リベラル」です。
つまり、「リベラル」は、「人権」を前提に、「よい考えがあれば、たとえ急でも、古い昔からのやり方は捨てて、一からやり直そう」と考える人たちです。
日本で「リベラル」が育たない理由については、後述の「日本で、政治に影響力のある市民運動が存在しない」「リベラルが育つ土壌と意思表明権。人権教育と道徳教育の違い」で述べています。
「ナショナリスト」とは、「ナショナリズム」を信奉する者のことです。
「ナショナリズム」とは、自己の所属する民族のもと形成する政治思想や運動を指す用語で、国家主義、国民主義、国粋主義、国益主義、民族主義とも呼ばれます。
「ナショナリズム」の民族主義と「超保守」の自国のことを極端に優れているとの認識が結びつくと、自分の人種が最上であると考え、他の人種を見下し、公平に扱おうとしない「レイシスト(人種差別主義者)」として、苛烈な「ヘイト(憎悪)スピ-チ」に至ります。
2015年(平成27年)の研究では、「性差別的な態度が強い男性は、男女の平等を促進するメッセージを読んだあと、女性に対してさらに攻撃的になった」ことが示されています。
つまり、性的な攻撃性を持つ男性は、男女平等や暴力防止のメッセージに逆らう行動をとる傾向が高くなります。
その理由として、性差別的な態度が強い男性、性的な攻撃性を持つ男性は、「自分には望む女性と性交渉をする権利があると認識している」ことをあげています。
女性に向けられるこの性差別がいきつくと、女性を狙った殺人「フェミサイド」になります。
フェミサイドとは、「女性であることを理由に、男性が女性を殺害する」ことを指します。
その「フェミサイド」の背後には、「ミソジニー」が存在します。
ミソジニーとは、「女性に対する憎悪、嫌悪、差別意識」のことです。
家制度(家父長制)を背景にした家族観に馴染み、内助の功、良妻賢母を求める保守的な価値観が色濃く残る日本社会には、自分がミソジニーであることを隠したり、女性を臭いものとして蓋をしたがったりする男性が数多く存在します。
この人たちは、「女性と子どもが獲得してきた権利」を疎ましく、鬱陶しく、忌々しく思っている人たちと合致します。
アメリカでは「インセル」ということばが生まれましたが、このことばは「不本意な禁欲主義者」を意味し、「俺が、恋愛やセックスをできないのは女が悪い」と女性を逆恨みして、憎悪を募らせる“一部”の男性を指します。
このインセルと呼ばれる“一部”の男性は、「男には、恋愛やセックスをする権利がある」、「女にケアされて性欲を満たされる権利がある」、「その権利を不当に奪われている」という強い被害者意識を持っています。
この被害者意識は、「女が悪い!」と女性に対する責任転嫁、逆恨みにつながり、それが、女性に対する暴力行為に表れます。
・日本は儒教社会。いまも、実質的な「家制度(家父長制)」であることに無自覚
いまだに、「家に嫁ぐ」「嫁に行く」などのことばが使われるなど、その概念は生活様式として深く根づき、その概念と深くかかわる「内助の功」「良妻賢母」という儒教思想は、「女性の幸せは、結婚し「家」に入り、子どもを持ち、父母に孝行すること」であり、「子どもの幸せは、厳しい「懲戒(しつけ(教育)と称する体罰)」があっても、両親の下で育ち、両親を敬い、孝行すること」であるという保守的な価値観として、いまも多くの日本国民に支持されています。
儒教思想は、江戸時代、人口の7%に過ぎなかった「武家」に限られていた教育です。
「儒教」は、高等学校の授業で学ぶ『漢文』の「孔子いわく、…」、つまり、「論語」のことで、「諸子百家」とは、中国の「春秋戦国時代(紀元前770年に周が都を洛邑(成周)へ移してから、紀元前221年に秦が中国を統一するまで)」の学者・学派の総称です。
「諸子」とは、孔子・老子・荘子・墨子・孟子・荀子などの人物を指し、これらの儒学者のことば(教え/論語)は、江戸時代の人口の7%に過ぎなかった「武家」の教育の根幹となっていましたが、これは、紀元前の中国社会(春秋戦国時代)の価値観が反映されているので、「男尊女卑(男を尊び女を卑しめる)」が際立っています。
その「武家」以外の一般市民は、特に、江戸時代の一般市民は、経、説法、説話などを介し、仏教に親しみ、その教えを学んでいました。
なぜなら、江戸幕府は、すべての人々がいずれかの仏教寺院(寺)の「檀家」となることを強制する「寺請制度」を設けたからです。
その仏教寺院(寺)は、その檀家の葬祭供養を執り行い、「檀家(住民)」の動向や戸籍上の管理を請け負う義務が生じました。
「説話」では、仏教に関する話が語られ、その内容は、「発心(悟りを得ようと仏の道に志すこと)」「遁世(俗世の煩わしさを捨てて静かな生活に入ること)」「往生(この世を去って極楽に生まれ変わること)」「霊験(仏の霊力によって起こる不思議なできごと)」などで、「説法」とは、仏教の宗教の教義を説き、聞かせることです。
明治政府は、軍国化(国民皆兵、富国強兵)に必要不可欠な「学制」「税制」「兵制」を進めるうえで、「律令制」の流れを汲み、儒教思想の「公家」「武家」にひき継がれてきた『家制度(家父長制)』を設けました。
しかし、経、説話、説法などを介し、「仏教」に親しみ、学んできた一般市民には、この儒教思想の『家制度(家父長制)』には馴染みはありませんでした。
そのため、明治政府は、軍国化(国民皆兵、富国強兵)に必要不可欠な「学制」「税制」「兵制」を進めていくには、一般市民に、儒教思想を教えることで、『家制度(家父長制)』を浸透させ、定着させる必要がありました。
そこで、とり入れたのが、「儒教思想にもとづく道徳教育」で、その後、5-6世代にわたりこの「道徳教育」を受けてきたことから、いまの日本の社会規範として定着しています。
これは、学校教育だけではなく、童話・昔話などあらゆるものを含み、いまも続いています。
例えば、中国の三国時代(黄巾の乱の勃発(184年)-西晋による中国再統一(280年))描いた『三国志』は、いくつもの演目『三国志演義』が創作されましたが、江戸時代は活躍した武将が英雄として人気がありましたが、明治政府は、劉備の軍師(宰相)の諸葛孔明を「忠義の人」と英雄視するキャンペーンを実施しました。
なぜなら、劉備は、諸葛孔明に「跡を継ぐ子どもの劉禅が無能であるなら、とって代わり国を治めるように」と遺言した(そう伝わる)とにもかかわらず、諸葛孔明は、忠義に徹し、その愚息劉禅を支え続けたからです。
正確に言語化できないけれど、日本は生き難いと感じている女性は、数多くいるのではないでしょうか?
それは、日本の人々は、5-6世代にわたり「(儒教思想にもとづく)道徳」を学び、あまりにも長く日本社会の規範と根づいていることから、生まれてきた子どもは、幼児期からその規範の中で育ち、4-5歳に達することには、既に、ア)「女性の幸せは、結婚し、子どもを持ち、父母に孝行すること」であり、イ)「子どもの幸せは、厳しい「懲戒(しつけ(教育)と称する体罰)」があっても、両親の下で育ち、両親を敬い、孝行すること」である、そして、ウ)女性は、「武家の女性」のように、自己犠牲なくして成り立たない「内助の功」「良妻賢母」を身につけることが、ステレオタイプとなっています。
いまでも、就学前の女児の3割は、男児の4割は、既に、「女性は家庭に」という価値観を支持しています。
結婚式では、「家制度」の概念が持ち込まれ、控室にはそれぞれ「・・家様」と表記され、祝辞では「両家の皆さま、おめでとうございます。」などとあたり前のように「家制度」を表現しています。
また、婚姻した女性が、一方の配偶者の夫を「旦那」「主人」と表現する呼称は、「家制度(家父長制)」をそのままひき継いだもので、主従関係を示します。
「主人」の反対語は「下女」「下男」で、「主人」の対義語は、「令室」です。
「主人」「令室」は、ともに、相手を敬う表現です。
しかし、日本社会では、女性は、夫を敬う表現である「主人」を使う一方で、男性は、妻を敬う表現である「令室」を使うことはありません。
つまり、「家制度(家父長制)」のもとで、妻(女性)を敬う表現はなくなっていきました。
「旦那」とは、サンスクリット語の仏教語ダーナに由来し、“与える”“贈る”といった「ほどこし」「布施」を意味し、もともと僧侶に用いられてきたことばです。
その後、一般にも広がり、「パトロン」のように“生活の面倒をみる人”“お金をだしてくれる人”という意味として用いられていきます。
妾や生活の面倒を見てくれる人のことを旦那様と呼び、奉公人が生活の面倒を見てくれる人、住み込みで仕事を与えてくれる人のことを旦那様、ご主人様と呼ぶようになっていきました。
その妾や奉公人が使っていた呼称を、夫婦間の呼称として使うことは、「家制度(家父長制)のもとでは、「「嫁」という概念や妻という立場が、家庭の中、夫婦の間において、妾や奉公人と同等の扱いをされていた」ことを意味します。
また、「人工妊娠中絶に配偶者の同意が必要」な国は、203ヶ国の中で、日本、台湾、インドネシア、トルコ、サウジアラビア、シリア、イエメン、クウェート、モロッコ、アラブ首長国連邦、赤道ギニア共和国の11ヶ国・地域に留まり、192ヶ国は、配偶者同意の規定は存在しません。
日本では、明治2年(1869年)に『堕胎禁止令』が公布され、明治13年(1880年)の『刑法』の制定で、『堕胎罪(刑法212−216条)』として犯罪となり、現在の『刑法』にひき継がれました。
一方で、太平洋戦争に敗戦直後の昭和23年(1948年)に制定された『母体保護法』による一定の条件を満たすことで人工妊娠中絶が可能となり、同年に施行された『優生保護法』において、日本は、世界に先駆けて、人工妊娠中絶の実質的合法化を実現しました。
しかし、その日本は、避妊をめぐる政策は極めて「保守的」で、平成5年(2023年)4月、「経口中絶薬」が承認されましたが、これは、1988年(昭和63年)、世界で初めて「経口中絶薬」が導入されてから35年経過しています。
日本で、この「経口中絶薬」の承認が遅れた背景にあるのが、人工妊娠中絶を「女性の罪」とする『堕胎罪(刑法212−216条)』の存在です。
『税制』『社会保障制度(年金制度を含む)』、『家族法(民法)』で定める婚姻・離婚、人工妊娠中絶に必要となる配偶者の同意の必要性、「緊急避妊薬」の導入、「中絶薬」の導入など、女性の妊娠・出産に絡む制度や法に加え、社会的な慣習として、結婚式の「・・家」、妻の「主人」「旦那」と夫を呼ぶ呼称に至るまで、家制度(家父長制)はいまも、日本の隅々まで浸透し、残っています。
少し厄介なのは、一般市民が5-6世代にわたり、学んできた「道徳」は、慣れ親しんだ仏教を基軸に、儒教思想に加え、ファンタジーストーリー「日本神話」を背景とした「神道」が交わった異質な(なんでもありの)価値観が社会規範となっていること、そのなんでもありの状況が、日本が、大韓民国(韓国)・朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)と同じ儒教国家(男尊女卑で家制度(家父長制))であることをわかり難くしていることです。
・「神武創業」とファンタジーストーリー「日本神話」、男尊女卑の由来
新政府軍の倒幕スローガン「神武創業(神武天皇の時代に戻れ!)」の「神武天皇」は日本の神々を統一して日本を建国したとする日本神話(ファンタジーストーリー)に登場する架空の人物です。
もともと、京都御所にあった天皇家の仏壇(御黒戸(おくどろ))には、神武天皇を含む初期の天皇たちの位牌はありませんでしたが、明治政府は、天皇家に、「現人神(あらひとがみ)」としての「神武天皇」を誕生させました。
645年6月12日の「乙巳の変」にはじまる一連の“国政改革(狭義には大化年間(645年-650年)の改革のみを指し、広義には大宝元年(701年)の『大宝律令』の完成までに行われた一連の改革を含む)”が『大化の改新』です。
この改革により、豪族中心の政治から天皇中心の政治へと移行したと考えられ、このとき、「日本」という国号、「天皇」という称号が正式なものになったとされています。
この改革の中心人物の中大兄皇子と中臣鎌足が、皇極天皇を退位させ、皇極天皇の弟(孝徳天皇)を即位させ、この孝徳天皇即位を持って、新たな時代のはじまり、つまり、日本ではじめての元号「大化」が定められました。
つまり、日本国としての天皇史がはじまりは、孝徳天皇以降となります。
その後、「葦原中つ国を天皇が支配する」ことの“正当性”を示す歴史書としてまとめられたのが、『古事記(712年)』と『日本書紀(720年)』です。
『日本書紀』は、中国の歴史書のスタイルに則り、純粋な漢文でまとめられています。
中国をはじめ国外に対して、日本の歴史、つまり、「天地開闢(てんちかいびゃく)」といわれる世界のはじまり、神々の手によって日本の国が築かれていった神代から第41代の天皇に数えられる持統天皇(女性天皇)の時代までの歴史をアピールする意図でまとめられました。
「国家の歴史書」としての『日本書記』に対し、『古事記』は、変体漢文、つまり、仮名がまじった日本ならではの文章で書かれています。
このことから、『古事記』は、国内の読者を想定し、「天皇家のための歴史書」としてまとめられたと考えられています。
新政府軍は、「新政府軍が、江戸幕府を倒し、新政府を打ち立てる“正当性”を示すために、「葦原中つ国を天皇が支配する」ことを示す『古事記』『日本書記』で記した「天地開闢といわれる世界のはじまり、そして、その神々をひとつにまとめた神武天皇」を倒幕スローガンにしました。
それが、「神武創業(神武天皇の時代に戻れ!)」です。
その日本神話では、「女性は穢れた存在」とし、いまに至る「女性蔑視(男尊女卑)」につながっているので、その経緯に触れておきます。
日本神話では、国を生んだ神は、イザナミです。
イザナミは、天地開闢において神世七代の最後にイザナギとともに生まれ、そのイザナギと夫婦になり、オノゴロ島におりたち、国産み・神産みにおいてイザナギとの間に、淡路島・隠岐島、そして、日本列島を生み、さらに、山・海など森羅万象の多数の神々(子ども)を生みました。
その後、妻イザナミは、夫イザナギよりも先に亡くなります。
そこで、夫イザナギは、妻イザナミに会いに、死後の世界である黄泉の国を訪れますが、妻イザナミは死のケガレ(穢れ)にとりつかれて、腐っていました。
その姿に驚いた夫イザナギは逃げだします。
妻イザナミは追いかけていきますが、命からがら夫イザナギは脱出します。
そして、ケガレたからだを清めたときに生まれたのがアマテラスです。
日本神話を基礎とする「神道」では、死をケガレとし、その血もケガレとします。
そのため、日本神話を基礎とする「神道」では、「女性は穢れている」として、神社に入れなかったり、大相撲の土俵にあがれなかったり、さまざまな制限を設けています。
この「女性は穢れている」との認識が、“女性蔑視”、“男尊女卑(男を尊び女を卑しめる)”につながっています。
女性の「生理(血)」を穢れとし、生理をタブーとすることは、男性の「生理」に対する無知(知らないこと)による無理解を生み、ステレオタイプとして、生理周期による女性ホルモンの影響を受け心身に示される傾向を「生理中の女性は感情的(ヒステリー)」と、女性を侮蔑し(バカにする)、卑下する(見下す)発言や態度、つまり、ハラスメントをつくりだしています。
この視点に立つと、日本政府をはじめとする極右・超保守の人たちが、「人権解釈」にもとづく「性教育」を頑なに実施しようとしない理由がわかると思います。
地方都市の神舎で行われる祭りの中には、いまでも、男児だけが立ち入る(参加する)ことができ、女児が参加できない(立ち入りが禁止されている)祭りがあります。
幼い子どもに、「なぜ、女性が参加できないのか(その場に立ち入れないのか)?」と問われ、「女性はケガレているから」と応じれば、このことばは、子どもたちのステレオタイプとなり、ものごとの価値判断(モノサシ)となっていき、無意識下で「女性蔑視」「男尊女卑」がすり込まれていきます。
このファンタジーストーリー「日本神話」にもとづく新政府軍の倒幕スローガン「神武創業(神武天皇の時代に戻れ!)」は、「天皇の神格化」を柱に、『大日本国憲法』『教育勅語』を制定しました。
この『レポート』の主人公ともいえる「極右・超保守の政権、政党、政治家、彼らと“共同体”ともいえる「はじめに。」で示したア)イ)ウ)エ)の政治団体」の世界観(思想・イデオロギー)には、ファンタジーストーリー「日本神話」の世界に対する「復古(主義)」があります。
「復古主義」とは、「情勢や体制などが現在よりも過去の方が優れている」との考えで、「その当時の状況に戻すことにより、社会がよりよくなる」ことから、「復古させよう(昔に戻そう)」という主義のことです。
この「復古主義」にもとづく「ナショナリズム」の民族主義、「超保守」の自国のことを極端に優れているとの思想・イデオロギーで活動しているのが、「はじめに。」で示したア)イ)ウ)エ)の政治団体であり、彼らの後ろ盾を得て、“共同体”ともいえる極右・超保守の政権の政権、政党、政治家です。
そして、このファンタジーストーリー「日本神話」の影響を強く受けているのが、国家観としての“家族像”で、日本の『家族法(民法)』に明確に示されています。
・『教育勅語』『八紘一宇(君が代)』と「皇民化教育」
「神武創業」を礎とする『教育勅語』の全文は、「朕惟(ちんおも)ふに、我が皇祖皇宗(くわうそくわうそう)、国を肇むること宏遠(こうえん)に、徳を樹(た)つること深厚なり。我が臣民克(よ)く忠に克く孝(かう)に、億兆心(おくてふこころ)を一にして世々其の美を済(な)せるは、此れ我が国体の精華にして教育(けふいく)の淵源亦実(えんげんまたじつ)に此(ここ)に存す。爾臣民父母(なんじしんみんふぼ)に孝に、兄弟(けいてい)に友(いう)に、夫婦相和(ふうふあいわ)し、朋友相信(ほういうあいしん)じ、恭倹己(きょうけんおのれ)を持(ぢ)し、博愛衆(はくあいしゅう)に及ぼし、学を修め、業(げふ)を習ひ、以て知能を啓発し、徳器を成就し、進んで公益を広め、世務(せいむ)開き、常に国憲(こくけん)を重んじ、国法に遵(したが)ひ、一旦緩急(いったんくわんきふ)あれば義勇公(ぎゆうこう)に奉じ、以て天壌無窮(てんじょうむきゅう)の皇運(こわううん)を扶翼(ふよく)すべし。是の如きは、獨り朕が忠良(ちゅうりゃう)の臣民たるのみならず、又以て爾祖先(なんじそせん)の遺風を顕彰(けんしゃう)するに足らん。斯(こ)の道は、実に我が皇祖皇宗(くわうそくわうそう)の遺訓にして、子孫臣民の倶(とも)に遵守すべき所、之を古今に通じて謬(あやま)らず、之を中外(ちゅうぐわい)に施して悖(もと)らず、朕爾臣民(ちんなんじしんみん)と倶(とも)に拳拳服庸(けんけんふくよう)して咸(みな)其の徳を一にせんことを庶幾(こいねが)ふ。」です。
辻田真佐憲著『「戦前」の正体 愛国と神話の日本近現代史』では、この『教育勅語』は、天皇の祖先、当代の天皇、臣民の祖先、当代の臣民の四者で構成され、この四者が、「忠」と「孝」という価値観で固く結びついていると説明しています。
「忠」とは、君主に対する臣民の誠であり、「孝」とは、父に対する子の誠ことです。
つまり、『教育勅語』は、「歴代の臣民は、歴代の天皇に忠を尽くしてきた。当代の臣民も、当代の天皇に忠を尽くしている。また、これまでの臣民は自らの祖先に対して孝を尽くしている。当代の天皇もまた過去の天皇に孝を尽くしている。ほかの国では、君主が倒され、臣民が新しい君主になっており、忠が崩壊している。それはまた、そのときどきの君主が徳政を行わず、結果的に祖先からひき継いだ王朝を滅ぼしたという点で、孝も果たせていない。ところが、日本は忠孝がしっかりしているので、万世一系が保たれている。」という意味です。
極右・超保守の政権、政党、政治家の『教育勅語』に対する肯定発言は、この時代への“復古”を意味し、「第2の「法案」家庭教育支援法」で示している満州事変・太平洋戦争時の『戦時家庭教育指導要項』に通じる『家庭教育支援法案』につながっています。
満州事変・太平洋戦争時の『戦時家庭教育指導要項』に通じる『家庭教育支援法案』は、安倍晋三元首相が会長となり発足させた「親学推進議員連盟」が立法化を目指した肝いりの政策で、第3次安倍晋三政権で、国会提出を見送った経緯があります。
しかし、「はじめに。」で示したア)イ)ウ)エ)の政治団体が主導し、この『家庭教育支援法』の成立のために、『こども基本法』を成立させ、『子ども家庭庁』を創設させ、地方議会で、同じ趣旨の『家庭教育支援条例』を制定させ、とても危険な状況です。
この「神武創業」「八紘一宇」「教育勅語」は、国のために身を捧げることを求める「皇民化教育」そのもので、「軍官民共生共死思想」として、沖縄戦における集団自決につながっています。
「皇民化教育」とは、満州事変から太平洋戦争までの戦時中、日本(大日本帝国)の統治地域の朝鮮や台湾などに加え、沖縄で実施した日本語の常用、神社の建設や参拝、日の丸の掲揚、君が代の斉唱など、強制的な同化教育です。
「沖縄戦」における一般住民の「集団自決」は、「皇土防衛」「国体護持」作戦の犠牲であることから、沖縄戦は、天皇制を守る戦いでした。
「国民皆兵」「富国強兵」を突き進めた明治政府は、天皇を「神聖にして侵すべからず」と神格化し、国民に対し、自らの生命を喜んで天皇に捧げるという「皇民化教育」を徹底しました。
沖縄では、方言廃止、標準語励行を強要し、方言札をつくるなど、日本化(=皇民化教育)を進めました。
日本軍は、「沖縄は民度が低く、殉国思想がなく信用できない」と考え、皇土防衛として総力戦に臨むにあたり、「軍官民共生共死の一体化方針」を示しました。
「軍官民共生共死の一体化方針」とは、「沖縄にいる軍官民(軍人、公務員、民間人)は、日本軍とともに生きるか死ぬかのどちらかの道しかない」というものです。
追い詰められた日本軍は、「捕虜になれば、男は戦車でひき殺され、女は辱めを受けて殺される。」と米軍への恐怖心を煽り、死を選ぶように導き(「共死」という名の「軍事的他殺」)、一般住民の「集団自決」をもたらしました。
安倍晋三元首相が「美しい国創り」と宣言し、愛国心を醸成する道徳教育に力を入れ、成立を目指す「第2の「法案」」である満州事変・太平洋戦争中の『戦時家庭教育指導要項』に通じる『家庭教育支援法』は、この「皇民化教育」を指します。
『教育勅語』「皇民化教育」の内容は知らなくても、ア)自らを犠牲にしてでも、会社のため、組織のため、学校のため、恩師のためと自己犠牲をいとわない、「壊れても死んでもかまわない」とケガを負うほど頑張ることをいとわない、結果、休暇をとらない、長時間労働・低賃金に不満をいわない日本人の価値観、イ)学校園の行事で、親宛に「育ててくれて、ありがとう」「産んでくれて、ありがとう」などと感謝の気持ちを手紙に書かせるなど、親の孝行を善とし、強要する日本人の儒教思想にもとづく道徳観など、身近な至るところに、『教育勅語』の“教え”が行き届いています。
海外の人が、日本人の特性を示す「礼儀正しい」「親切」「勤勉」「盾突かない」「規律的」などは、『教育勅語』の“教え”が、いまも国民にひき継がれていることを意味し、日本人の“美徳”とされています。
この日本人の特性は、“国民性”と呼ばれるほど、無自覚な価値観であり、行動規範となっています。
権力者には「盾突かず」、賞賛し、褒め称え、辛抱し、忖度するなど、「忠義」に徹します。
一方で、権力者が、「盾突かず」、賞賛し、褒め称え、辛抱し、忖度するなど、「忠義」に徹することを求めるとき、それに応じられないときの「叱責(懲戒)」、つまり、「しつけ(教育)と称する体罰」は、その“対象”が、交際相手や配偶者であればDV(デートDV)、子どもであれば児童虐待、生徒間や職場などであれば、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、パワーハラスメントという暴力(人権侵害)行為につながっています。
ただし、冒頭の「少し長いはじがき」で述べているように、「復古主義」にもとづく「ナショナリズム」の民族主義、「超保守」の自国のことを極端に優れているとの思想・イデオロギーを持つ人、つまり、自身が実質的な「家」の家父長(権威者)であると自認している人は、「懲戒」と認識しているので、泥沼化するベトナム戦争に対する「反戦運動」「女性解放運動」を介し進んだ女性と子どもに対する非暴力として生まれた「DV(ドメスティック・バイオレンス)」「児童虐待」という新たな用語は存在しないことになります。
この権力者には「盾突かず」、賞賛し、褒め称え、辛抱し、忖度するなど、「忠義」に徹するといった“行動規範”から外れる者(「徴兵検査」の通らず国の役に立てなかったり、国の姿勢に反発したりする者)、例えば(現代では)、病気や障害を負い働けない者、学校に通学しない者、親に心配をかけたり、親の面倒をみたりしない者、社会が定めた枠組みから外れる者、権力者に従順ではなく、逆らったり、意を唱えたりする者などに対し、非常ともいえる冷酷な態度をとったり、時に残忍な行動に至ったりするのも日本人の特徴です。
ここにも、戦前に叩き込まれた『教育勅語』の影響が示されています。
令和5年(2023年)6月、障害者の就労を支援する『ゼネラルパートナーズ(東京)』は、多様な人材が個性や能力を発揮できるようにする考え方「ダイバーシティー&インクルージョン(多様性と包摂)」についてインターネット調査を実施し、20歳代-70歳代の129人から回答を得た結果、「障害者の112人(86.82%)が、社会で普及していないと感じ」、「98人(75.97%)が、自身への差別や偏見がある」と回答し、企業で働く際に求める配慮事項(複数回答)で、65%が「同僚や上司からの理解と協力」、43%が「仕事量の調整」、36%が「キャリアアップの機会」、33%が「ハラスメントの防止」、30%が「福利厚生の充実」と回答していることから、障害者らへの理解、共生社会の実現に向けたとり組みが不十分であることが明らかになっています。
日本の人たちは、「自分たちもこの行動規範に従っている。はみ出ること(例外)は絶対に許さない!」、「やり直し、再チャレンジも許さない!」と徹底的に叩き、排除します。
この日本人の「国民性」の背景にあるのが、「日本神話」にもとづく『教育勅語』の“教え”です。
日本社会では、「よい考えがあれば、たとえ急でも、古い昔からのやり方は捨てて、一からやり直そう」と考えるリベラル(革新)的な価値観の人は、徹底的に叩かれ、排除されます。
この「リベラル(革新)」的な価値観の根底にあるのが、「人権」です。
「人権」は、日本の極右・超保守、保守が絶対に認めようとしない価値観です。
なぜなら、極右・超保守、保守が求めているのは、日本神話の家族像と儒教思想に示される「伝統的家族像」のもとでの「愛国心」だからです。
それは、「男性は、忠義を心に、主君と国のために身を捨てる」、「女性は家で、夫、家、家族のために自らを犠牲にする(内助の功、良妻賢母)」と考え、「家族(男性と女性、子ども)はひとつ、家父長に従い一致団結する」というものです。
日本神話、儒教思想のいずれも「女性蔑視」「男尊女卑」が示されていることから、「人権」とは真逆に位置づけされます。
実質的に「人権」を認めていない日本の極右・超保守の政権は、『世界人権宣言』にもとづく「いかなる理由があっても暴力は許されない」との認識に立つことはありません。
このことは、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力(人権侵害)を受けた被害者の存在は、軽視されることを意味します。
例えば、令和5年(2023年)6月9日、岸田文雄政権は、強制送還の対象となった外国人の長期収容解消をはかることを目的とし、難民認定の申請中は強制送還を停止する規定を改め、難民認定の申請で送還を停止できるのは原則2回までとする『改正出入国管理及び難民認定法』を成立させました。
『出入国管理及び難民認定法』は、平成11年(1999年)の改正で、不法在留罪の創設、退去強制された者に係る上陸拒否期間の伸長、再入国許可の有効期間の伸長など、平成13年(2001年)の改正で、サッカーワールドカップの開催に向けたフーリガン対策等としての上陸拒否事由及び退去強制事由の整備など、平成16年(2004年)の改正で、在留資格取消制度の創設、仮滞在許可制度の創設、出国命令制度の創設、不法入国罪等の罰則の強化など、平成17年(2005年)の改正で、人身取引議定書の締結に伴う人身取引等の定義規定の創設等、密入国議定書の締結等に伴う罰則・退去強制事由の整備など、平成18年(2006年)改正で、上陸時における個人識別情報の提供義務付け、自動化ゲートの導入、一定の要件に該当する外国人研究者及び情報処理技術者を在留資格「特定活動」により受け入れる規定の整備など、平成21年(2009年)の改正で、在留カード・特別永住者証明書の交付など新たな在留管理制度の導入、外国人登録制度の廃止、在留資格「技能実習」の創設、在留資格「留学」と「就学」の統合、入国収容所等視察委員会の設置など、平成26年(2014年)の改正で、在留資格「高度専門職」の創設、船舶観光上陸許可の制度の創設、自動化ゲート利用対象者の拡大、在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」の統合、在留資格「投資・経営」から「経営・管理」への変更、PNR(Passenger Name Record;航空会社が保有する旅客の予約情報)に係る規定の整備など、平成28年(2016年)の改正で、在留資格「介護」の創設、偽装滞在者対策の強化のための罰則・在留資格取消事由の整備など、平成30年(2018年)の改正で、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設などと、年々、難民(外国人)の管理を強化し、難民(外国人)の排除姿勢を鮮明に打ちだしてきました。
これらは、すべて、安倍晋三政権以降のできごとです。
つまり、安倍晋三政権以降、『出入国管理及び難民認定法』を改正し続け、監視を強化し、排除姿勢を鮮明にしてきたのは、新政府軍のスローガン「神武天皇の時代に戻れ!(神武創業)」が、神武天皇からはじまる日本の建国に立ち返ることから、そこには、「難民(外国人)は存在しない」からです。
自由民主党の杉田水脈衆院議員(比例中国)が、ネット上にアイヌ民族を侮辱する内容の投稿をしたことに対し、令和5年(2023年)9月、札幌法務局は「人権侵犯の事実があった」と認定しましたが、その後もアイヌ民族を侮蔑する投稿を続けています。
「人権侵犯の事実」が認められた杉田水脈衆院議員を処分しない「自由民主党」には、「人権」という判断基準(モノサシ)は存在せず、同時に、杉田水脈衆院議員の発言は、自由民主党の思想・イデオロギーそのものなので、処分する概念(根拠)は存在しません。
遺伝子学(骨格など)では、本土日本人は、大陸や南シナ海経由で日本島に辿りつき、住みついた人類(原アジア人)が、縄文・弥生時代(弥生人)を経て、いまに繋がる本土日本人となったことがわかっています。
弥生人は、アイヌ、琉球人(沖縄人)と別れ、本土日本人は、大宝元年(701年)、『大宝律令』の完成前の4-7世紀ごろに住み着いた多くの渡来人(朝鮮半島(主に百済)、中国/原アジア人から大陸に住みついた北東アジア人)と交わり、いまに繋がる本土日本人ができあがりました。
遺伝子学では、弥生人の流れを汲むのはアイヌ、琉球人(人)で、彼らは、オーストラリアのアボリジニ、北アメリカ大陸のインディアン、エスキモー、アレウトなどの先住民族と同じ凄惨な迫害・殺戮の被害を受けました。
ファンタジーストーリー「日本神話」の神武天皇が日本建国の祖と考える人たちは、この事実を否定し、純粋の日本人でない人たち、つまり、外国人(難民)を受け入れようとせず、差別・排除しようと躍起になります。
ここにあるのは、「復古主義的な情緒主義」です。
「情緒主義」は、「各々の道徳判断は、信念ではなく一種の感情の表現であり、そうした表現を通じて相手の感情に訴えるための道具である、つまり、道徳判断は、個々人の好みや感情の表明に過ぎない」との立ち位置です。
非認知主義、表現主義の一形態と見なされ、口語的には“万歳・くたばれ説”として知られています。
つまり、非科学的で、エビデンス(証拠、根拠、裏づけ)は無視します。
日本は、神話国家に立ち返るカルト国家に向け、いよいよ危ない域に達してきました。
・軍国化と教師による「懲戒」。がまんし、耐え抜くことを美徳する精神論・根性論
日本で「軍国化」が進むと、「国の役に立つ人材育成のため」という「懲戒権(民法822条)」の目的を同じくする学校教育で、教師による生徒に対する「懲戒」が一般化していきます。
その役割(生徒指導)を担ったのが、軍人経験者の「体育教師」で、大正時代には、「体育教師」の半数は軍人経験者が占めていました。
「軍人」の“精神論”“根性論”は、「軍」の実験を「薩摩藩」が握っていたことと深く関係しています。
なぜなら、江戸時代は、武士階級子弟が少年集団をつくり研鑽し合う教育法が「各藩」にあり、その中で、会津藩の“什”と薩摩藩の“郷中”の2藩はその厳しさが際立っていたからです。
これが、いまの「教師(指導者などによる)による体罰(身体的暴力)の問題」、職場などでの「パワーハラスメントの問題」につながっています。
しかし実は、明治12年(1879年)に発せられた『教育令』で、「凡学校二於テハ生徒二体罰(殴チ或ハ縛スルノ類)ヲ加フヘカラス(46条)」と規定しています。
これは、世界的に見ても、かなり早い時期に体罰禁止を明文化したことを意味します。
そして、この「体罰禁止規定」は、『小学校令』、『国民学校令』に一教員の懲戒権規定の但し書にひき継がれていましたが、軍国化(国民皆兵、富国強兵)をする中で「日清戦争」「日露戦争」と突き進む中で、形骸化していったことになります。
「形骸化」とは、事物や制度、行為が本来の機能や役割を失い、形だけの存在となるこ戸を示します。
太平洋戦争敗戦後の昭和22年(1947年)に制定された『学校教育法』で、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない(11条)」と規定しています。
しかし問題は、「懲戒を加えることができるが、体罰を加えることはできない」と規定していても、戦前の『教育令』、敗戦後の『学校教育法』や関連法令で、「体罰の定義を明確に定めていない」ことです。
この定義(解釈)を不透明にしたままにしておくのは、日本政府の得意技、常套手段です。
そして、「5.第2の「法案」家庭教育支援法」で示したように、満州事変・太平洋戦争時には、『戦時家庭教育指導要項』を発令し、「はじめに。」の中の「『教育勅語』『八紘一宇(君が代)』と「皇民化教育」」で示しているように、沖縄戦における集団自決につながった「皇民化教育」を実施していきます。
平成13年(2001年)4月、国連の「子どもの権利委員会」は、「教育の目的」に関する最初の一般的意見を採択し、体罰が条約と両立しないことをあらためて指摘しました。
そこでは、「…子どもは校門をくぐることによって人権を失うわけではない。したがって、たとえば教育は子どもの固有の尊厳を尊重し、第12条1項にしたがって子どもの自由な意見表明や学校生活への参加を可能にするような方法で提供されなければならない。教育はまた、第28条2項に反映された規律の維持への厳格な制限を尊重する方法で提供され、かつ学校における非暴力を促進するような方法で提供されなければならない。委員会は、総括所見のなかで、体罰を使用することは子どもの固有の尊厳も学校の規律に対する厳格な制限も尊重しないことであるとくりかえし明らかにしてきた。……」と指摘しています。
いまから23年前のことです(令和6年(2024年)4月15日現在)。
「家」、「軍」、「学校」、「職場」で「しつけ(教育)と称する体罰(身体的虐待)」が横行し、その理不尽さに対して、意を唱えず(被害を訴えず)、「がまん」し、「耐え抜く」ことが求められる社会が構築された日本社会は、この「がまん」し、「耐え抜く」ことを“美徳”とし、“精神論”、“根性論”を美化します。
この精神論、根性論を美徳とする価値観と、女性の自己犠牲なく成り立たない「内助の功」「良妻賢母」は、ともに、「がまん」し、「耐え抜く」ことを前提としています。
これらの保守的な価値観を肯定し、支持する人は、「(その人たちの判断基準(モノサシ)に過ぎない)ある程度のDV行為は、(夫、男性に従順に尽くし、支える女性の鏡、母親の鏡となる行為として)耐えるのが好ましい」と認識します。
同時に、極右・超保守の人は、「家制度(家父長制)」の価値観を持ちだすので、家父長による子どもに対する身体的虐待行為は「懲戒(しつけ(教育)と称する体罰)」、家父長である夫による配偶者の妻に対する身体的暴力行為(DV)は「懲戒(教育)と称する体罰)」と認識しているので、意を唱える人には、「懲戒(しつけ・教育)は認められている」と応じたり、声を荒げ、「他人が、懲戒(しつけ・教育)に口を挟むな!」と非難したりします。
平成12年(2000年)に『児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)』が制定され、続いて、平成13年(2001年)に『配偶者暴力防止法』が制定されると、これまで、親の子どもに対する「懲戒」、夫から妻に対する「懲戒」が、「虐待行為」「DV行為」と呼ばれるようになりましたが、彼らにとっては、所詮「懲戒」に過ぎないと認識しています。
そのため、「懲戒が耐え切れなくなり、所属する「家」から逃げだす」のは、根性がなっていない、性根が腐っていると考えます。
そのツラくても、がまんし、耐えることを美徳とする“精神論”“根性論”は、男尊女卑(男を尊び女を卑しめる)である「儒教思想」にもとづく「道徳」と同様に、「人権」とは真逆に位置する(相反する)社会規範です。
彼らにとって、「人権条約」である『子どもの権利条約』『女性差別撤廃条約』の批准・締結の流れで、『児童虐待防止法』『配偶者暴力防止法』が制定され、「女性と子どもが獲得した権利」は、疎ましく、鬱陶しく、忌々しいものです。
極右・超保守の超党派「共同養育支援議員連盟(前.親子断絶防止議員連盟)」代表の柴山昌彦元文部科学大臣が、令和5年(2023年)1月、北日本放送の番組で、「被害者とされる方々の一方的な意見により、子どもの連れ去りが実行されてしまうことが本当に問題ないのかどうか。公正な中立な観点から、DVの有無とか、本当に耐えられるものか耐えられないものであるかということを判断する仕組みの一刻も早い確立が必要だ」と発言には、この疎ましく、鬱陶しく、忌々しい思いが滲みでています。
・岸信介元首相とアヘンマネー、フィクサー、カルト教団、暴力団との結びつき
倒幕スローガン「神武創業」を掲げた新政府軍の軍資金は、イギリスの「アヘンマネー(アヘン戦争がもたらした莫大な利益)」で、明治政府は、満州や蒙古各地でケシを栽培させ、ペルシャなどから密輸した大量の麻薬アヘンを満州国に流し込むことで、膨大な利益(アヘンマネー)を生み、それは、軍の謀略資金、機密費の主な財源になり、満州国の財政を支えるなど、明治政府の財政を支えました。
当時の総務庁の次長として、このアヘン政策をとり仕切っていたのが、東条英機元首相に近く、その後、東条英機内閣の商工大臣を務め権力の中枢に位置し、A級戦犯で逮捕されたナショナリストの岸信介元首相(安倍晋三元首相の母方の祖父)です。
昭和27年(1952年)に公職追放を解除された岸信介元首相は「日本再建連盟」を結成、昭和28年(1953年)3月、「自由党」に入党し、翌月の総選挙で当選して政界復帰を果たすと、「保守政界」の中で急速に頭角を現し、憲法調査会長として「憲法改正・再軍備」を唱道しました。
自由党を離党して「民主党」を立ちあげた鳩山一郎と行動をともにし、民主党の初代幹事長に就任し、昭和30年(1955年)、自由党と民主党が統合し「自由民主党」を立ち上げると、ひき続き幹事長に就任、昭和31年(1956年)12月、自由民主党総裁選において、7票差で石橋湛山に敗れましたが、外務大臣として入閣を果たします。
このとき、「昭和天皇は、東条英機よりも太平洋戦争の中心人物であった岸信介が、外務大臣就任することに強く反対した」とのちに侍従長だった人物が述べています。
そして、その2年後の昭和32年(1957年)、首相の座に就きます。
政界復帰後、わずか4年のことです。
太平洋戦争敗戦後の日本政治において、特筆すべきことは、この岸信介元首相が、戦後最大のフィクサーと呼ばれた児玉誉士夫、日本財団の創始者である笹川良一らとともに、カルト教団「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」を母体とする「国際勝共連合(共産主義に勝利するための国際連盟)」を創設し、しかも、「大規模デモ運動(安保闘争)」を押さえ込むために暴力団とも手を組んだことです。
岸信介元首相は、昭和35年(1960年)5月、『日米安保条約改定案』を強行採決したことで過激になった大規模デモ運動(安保闘争)に対し、「警察と右翼の支援団体だけでは抑えられない」と判断し、戦後最大のフィクサーと呼ばれた児玉誉士夫を頼り、自由民主党内の「アイク歓迎実行委員会(第34代アメリカ合衆国大統領のドワイト・アイゼンハワーの略称で、歓迎とはアイクの訪日に対して、安保反対者が、訪日に向けて過激なデモに及ぶ可能性があることに対する対策部隊)」の委員長の橋本登美三郎(朝日新聞社の記者として満州で活動し、その後、政治家となり「南京大虐殺」については否定的な証言をしている)を使者に立て、暴力団関係者の会合に派遣しました。
そして、「松葉会」の藤田卯一郎会長、「錦政会」の稲川角二会長、「住吉会」の磧上義光会長、「新宿マーケット」のリーダーで「関東尾津組」の尾津喜之助組長、「極東関口組」の初代会長である関口愛治ら全員が、アイゼンハワー大統領の訪日に対するデモ隊を抑えるために手を貸すことに合意しました。
つまり、岸信介元首相は、自由民主党内の「アイク歓迎実行委員会」を窓口にし、暴力団を実働部隊としてとり込むことに成功しました。
自由民主党内の「アイク歓迎実行委員会」は、主流の暴力団だけではなく、数十人の博徒やテキヤの親分衆にも協力を打診し、多数の親分集の協力を得ています。
そして、50人近くのテキヤの親分集が集まり、部隊の名称を「全日本神農憂国同志会」と決定し、「警視庁との打合せ」で、動員する1万5000人のテキヤについて、3000人を1個部隊として5個部隊編成し、配置先を決定しました。
右翼と暴力団で構成された「全日本愛国者団体会議」、戦時中の超国家主義者もいる「日本郷友会」、岸信介元首相自身が、昭和33年(1958年)に組織し、木村篤太郎が率いる「新日本協議会」の右翼連合組織にも行動部隊になるように要請、住吉一家3代目総長の阿倍重作は、関東中の博徒の親分衆に動員をかけ、「アイク歓迎対策実行委員会」の勢力は、稲川組などの博徒1万8000人、テキヤ1万5000人、旧軍人、消防関係、宗教団体など1万人、右翼団体4000人、その他5000人を動員することが可能なほど膨れ上がりました。
結果、「安保闘争・学生運動」は、ナショナリストの岸信介元首相により叩き潰されました。
ナショナリストの安倍晋三元首相は、母方の祖父である岸信介元首相宅に父の安倍晋太郎元外相(当時、朝日新聞記者)と母(岸信介元首相の3女)とともに同居し、そこで、育ち、父の安倍晋太郎元外相が膵臓がんで急逝すると、その祖父岸信介元首相の意志をひき継ぎ、「再軍備」、そのための「憲法改正」を目指します。
いま、パーティー収入不記載5年で数億円のキックバックが指摘され、世間を賑わしている「安倍派」、いわゆる「清和会」は、昭和54年(1979年)、岸信介元首相の岸派の人脈を引き継いいだ福田赳夫元首相により創設されましたが、「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」との深い関係も引き継がれました。
「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」の教祖は、韓国人の文鮮明で、文鮮明の悲願は「南北統一」であることから、日本市民から巻きあげた「統一教会」の多額のカルトマネーは北朝鮮に流れ、軍備費に充てられています。
その軍備費で長距離弾道ミサイルがつくられ、国会内で、軍事費増大の議論が盛んなときを狙い、日本海の排他的経済水域外に着弾するように発射され、それに対し、日本はアメリカ製の兵器(地政学的に、着弾時間を踏まえると「弾道ミサイル追撃システム」は役に立たない)を購入しています。
また、岸信介元首相の三女の夫で、安倍晋三元首相の父である安倍慎太郎元外務大臣は、山口県在日本朝鮮人商工会会長などを務めた朝鮮総聯系の呂成根、パチンコ業界大手の七洋物産創業者の吉本章治などからの支援を受けています。
下関と韓国・釜山を結ぶ「関釜フェリー」の物流の拠点として、山口県下関市には「リトル釜山」と呼ばれるコリアンタウンがあり、この地域性が、安倍信太郎元外務大臣と日本朝鮮人商工会、パチンコ業界との深い関係につながっています。
昭和63年(1988)の「リクルートコスモス(現.コスモスイニシア)」の非公開株を巡る「リクルート事件」に関与し、妻(岸信介元首相の三女で、安倍晋三元首相の母)に「顧問料」の名目で、同年8月までの2年7ヶ月間にわたり月30万円、合計約900万円が支払われ、安倍信太郎元外相の妻(岸信介元首相の三女)と二男で秘書の安倍晋三、その妻とともに住んでいた超高級マンションは、リクルートコスモス社の所有でした。
父・安倍慎太郎元外相のパチンコ業界と深い関係が、安倍晋三元首相の「カジノ特区構想」にひき継がれています。
パチンコ業界は、カジノ実現に向けて、政界に働きかけを続けてきました。
パチンコ業界と深い関係のある安倍晋三元首相が政権・実権を握る前に近づいたのが、業界大手のセガサミーホールディングスの里見治会長です。
その一連の流れを経て、観光立国推進閣僚会議の観光立国推進ワーキングチームが中間報告をまとめるなど、『カジノの事業法案(特定複合観光施設区域整備法案)』の提出準備を着々と進めていきます。
平成28年(2016年)12月、『特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(カジノ事業法/IR推進法)』」を成立させ、平成30年(2018年)7月、『特定複合観光施設区域整備法(IR実施法)』を成立させました。
そして、令和5年(2023年)4月14日、日本政府は、大阪府・市が申請していた「カジノを含む統合型リゾート施設(IR)の区域整備計画」を認定しました。
施設の建設や運営を手掛けるIR事業者は、アメリカMGMリゾーツ・インターナショナルの日本法人とオリックスが中心となって設立した「大阪IR株式会社」で、2029年秋以降の開業を目指しています。
カジノ誘致で、問題が指摘されたギャンブル依存についてとり組む姿勢を見せないのは、母方の祖父、岸信介元首相が、当時の総務庁の次長として、軍の謀略資金、機密費の主な財源になり、満州国の財政を支えるなど、明治政府の財政を支えたアヘン政策をとり仕切っていたことが、日本の薬物問題(覚醒剤・大麻などの所持・使用のいずれも刑罰が異常に軽い)の軽視につながっていることと同じです。
新政府軍の倒幕資金となったイギリスのアヘンマネーの当事国の中華民国(中国)では、死刑です。
・日本には、政治に影響力のある市民運動が存在しない
太平洋戦争敗戦後の30年、つまり、昭和50年(1975年)辺りまでは、社会主義国家、共産主義国家を理想とする人たちの活発な政治活動があり、「安保闘争・学生運動」の終わり、高度経済成長で生活にゆとりができはじめると、生活苦からの不満をぶつける政治批判の声は少なくなり、日本で生活する市民の多くは人権・社会問題から距離を置き、政治に無関心になっていきました。
その背景にあるのは、革命の声をあげ「安保闘争・学生運動」に興じた、圧倒的な政治力に屈した男性リーダーたちの価値観が、自身は、「家」を基軸とした家父長(権威者)であり、「女性は家に」と考え、一歩下がって歩く女性を好み、その女性には、女性の自己犠牲ではじめて成り立つ「内助の功」「良妻賢母」を求めていたからです。
そのため、ベトナム戦争が泥沼化する中で、アメリカを発端に世界中に広まった「反戦運動」「女性解放運動(ウーマンリブ運動)」は、日本では、「安保闘争・学生運動」でともに戦った男性リーダーたちが去ったあとの一部の女性リーダーを中心の市民運動となりました。
そして、日本社会とメディアは、欧米社会と異なり、「女性解放(ウーマンリブ)」の声をあげる女性たちに対し冷ややかで、侮蔑・蔑視的に扱いました。
日本社会とメディアが一体となり、女性の声を押さえ込みました。
そして、「6-(1)夫婦同姓制度(民法750条、戸籍法74条1号)」の「日本の男女間の賃金格差。OECD(経済協力開発機構)に加盟38ヶ国の中で37位」の中で述べているように、第1次オイルショック(昭和48年(1973年))、第2次オイルショック(昭和53年(1978年))が起きたことをきっかけに、欧米諸国における「母親が育児に専念できる時代」は終わりました。
しかし、日本社会では、女性の社会進出は進みませんでした。
なぜなら、超保守派の政権、政党、政治家、その政治支援団体は、「女性に家庭責任を負わせる」と誘導したからです。
つまり、日本政府は、所得税の扶養控除を設け、昭和60年(1985年)5月、『男女雇用機会均等法』を制定する一方で、サラリーマン・公務員の妻で、専業主婦なら国民年金を払わなくても受給でき『第3号被保険者制度』を発足させ、昭和61年(1986年)、『労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)』を施行し、ア)サラリーマン・公務員の妻の「専業主婦化」をはかり、イ)サラリーマン・公務員の妻が働くなら非正規雇用という“構図”をつくりあげました。
このことが、男女の賃金格差を生みました。
ここにあるのは、「女性は家に」という保守的な価値観で、しかも、結婚した女性の多くが「専業主婦」となり、「寿退社」と用語も生まれました。
欧米諸国と異なり、女性の社会進出が進まなかった日本社会そのものが、「リベラル」が育つ土壌にはなり得ず、結果、「リベラル」の人たちが政治の役割を担う構造をつくることができませんでした。
その後の約50年間、「リベラル」の人たちによる人権・社会問題に先進的にとり組んだ欧米諸国と異なり、日本では、政治的な影響力を持つ市民運動は育たず、「女性と子どもの権利」に関する法の整備し、制度を充実させるとり組みは、欧米諸国から、50年-30年遅れることになりました。
・リベラルが育つ土壌と意思表明権。人権教育と道徳教育の違い
加えて、日本で「リベラル」が育つ土壌がないもうひとつの理由は、「人権」を踏まえた教育体制が存在しないことです。
日本では、「律令制」、儒教思想にもとづく「家制度(家父長制)」は、江戸時代の人口の7%に過ぎなかった「武家・公家」の人たちの教えでした。
江戸時代の一般市民は、江戸幕府が、すべての人々がいずれかの仏教寺院(寺)の「檀家」となることを強制する「寺請制度」を設けたことから、葬祭供養などの場を通じて、仏教の説話などを社会規範としてきました。
そのため、明治政府は、「軍国化(国民皆兵、富国強兵)」を支えた「家制度(家父長制)」の普及・定着に向けて、「家制度(家父長制)」のもととなる「儒教思想」を広めることが急務となり、国家的なとり組みとして実施したのが、いまに続く「(儒教思想にもとづく)道徳教育」です。
「儒教思想にもとづく道徳」は、グローバルスタンダード(世界人権宣言、人権条約にもとづく)な「人権」とは、対極(真逆に位置する)なものです。
しかし、一般市民が親しんだ「仏教」に「儒教思想」が加わり、一般市民の社会規範となったことから、大韓民国(韓国)の市民と異なり、自国が「儒教思想」であること認識していない人が圧倒的多数という問題を抱えています。
このことは、日本社会では、圧倒的多数の人たちが、自国が、儒教思想にもとづく女性蔑視・男尊女卑、「家」を基軸とする家父長制であることに気づくことなく、社会生活を営んでいることを意味します。
つまり、日本社会には、身近な人権・社会問題に気づき難い社会風土があります。
令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」において、「子どもの人権の尊重」ではなく「子どもの人格の尊重」と表記されています。
「人権」は、人間が、人間らしく生きるための権利で、生まれながらに全員が持っている権利のことです。
人間であれば、誰もが持っている権利です。
つまり、どのような人であっても、出生後、決して否定されない「権利」です。
そして、英語の「rights(権利)」には、「自然で、あたり前のこと」という意味があります。
つまり、「権利」は、人としてあたり前に持っているものです。
出生した新生児が発する(訴える)「あー」、「うー」に対し、(養育の有無にかかわらず)ケアする大人が、「どうしたの?」などとことばをなげかけるやり取りは、新生児(相手)の立場で、新生児の要望を聴きとろうとする行為です。
この新生児と大人のやり取りは、この新生児が、「権利のある存在」として社会に認められたことを意味します。
一方の「人格」とは、「人の心のあり方」を問う「道徳」に通じるもので、個人の心理面の特性、人柄、あるいは、人としての主体(中心となるもの)を意味し、「人格権」は、「個人の名誉など人格的利益を保護するために必要な権利のこと」ですが、人格権自体には、権利として、具体的に保障されていません。
つまり、「人権」と「人格」は似通っていますが、意味はまったく異なるものです。
そして、「道徳教育」は、「人の心のあり方」にフォーカスし、「個々人の心を育むための教育」であることから、子どもたちは、「私たち一人ひとりが問題意識を持ち、‥」と個人の問題としてとり組むと思考終結することから、人権・社会問題につなげる(巻き込む)思考習得は困難です。
不適切な表現になってしまいますが、「メタ認知」を育めず、短絡的な思考習得となります。
「メタ認知」とは、自分の認知活動を客観的に捉えること、つまり、自ら考えたり、感じたり、記憶したり、判断したりする(認知)ことについて、自分を客観的に捉える(認識できる)ことです。
一方の「人権教育」は、社会のあり方を考えさせる、つまり、物事の構造、仕組み、つくりに起因する問題を把握し、その問題解決につながる社会変革を考える中で、自らの権利を知り、権利の主体として、社会変革を実現するための行動につながるように導くものです。
例えば、欧米諸国の授業(家庭においても)では、「あなたの考えはどう?」「あなたの意思はどう?」「あなたはどうしたい?」となげかけることに重きをおくのは、「人権」を背景にした「個」の意思を尊重する社会だからです。
「あなたの考えはどう?」「あなたの意思はどう?」「あなたはどうしたい?」のとなげかけることは、子どもが意思表明(権)を学び、身につけることを意味します。
一方で、「いわれたことをしなさい」「与えられたものを覚えなさい(解きなさい)」という全体主義的な日本の学校教育(家庭を含む)に加え、保守的な価値観の家庭やコミュニティに所属し、乳幼児期までに、「女性は家に」などの保守的な価値観をステレオタイプとしてすり込み、しかも、「子どもは大人の話に口出しするな(黙っていろ)」「女だてらに」「生意気だ」とすり込まれて育ってきた日本の子どもと女性の多くは、意思表明する習慣が極端にすくなくなっています。
しかも、日本社会では、大人や男性の顔色を伺い、期待する返答を心がけたり、口を噤いだりする(口を閉じて話さない/黙る)思考・行動習慣を身につけている子どもや女性が数多く存在します。
例えば、交際相手との男女、夫婦の男女のペアで街頭インタビューを受けたときに、男性が意見を述べ、隣の女性は頷き、マイクを向けられると「同じです。」と応える構図が映しだされます。
こういう場で、女性が、「私はこう考える」と男性と異なる意見を述べることは稀です。
このことは、人の異なる意見も尊重し、受け入れるという相手をリスペクトする「人権認識」が育まれていない、身につけていない社会を意味します。
中には、男性の10cmほど後ろに下がって、男性の話に相槌を打つ女性の姿が映されます。
この映像などを見て、「ここには、日本の女性の慎ましさが表れている(美徳)」と容認している社会には、「女性の意志表明権は存在していない」ことを意味します。
家庭教育・学校教育で、(日常のあり前のこととして)習慣として、自分の意思表明をするトレーニングをしていない日本で生まれ、育ってきた人(子どもを含む)にとって、「離婚」するときに、「共同親権」「単独親権」の選択、「養育費」「面会交流」、「教育(進学・就職など)」など「子どもの最善の利益」のために、「意見表明」し、「自己決定権」を持つ(政策側としては委ねる)ことは、大きなリスクを伴います。
なぜなら、スタートが対等の関係で成り立っていないからです。
欧米諸国では、グローバルスタンダードな「人権教育」のもとでは、子どものときからこうした「意見表明」し、「自己決定権」の大切さを学び、身につけていきます。
このとき、「意見表明」「自己決定権」は、基本的に、自身が所属するコミュニティの「家」「親」「祖父母」「きょうだい」「学校」「クラス」「サークル・クラブ」「職場」「上司」「同僚」の考えに影響を受けないことから、個人の「意見表明」「自己決定権」に影響が及んでいるときは、このコミュニティとの間に、“力学(力関係)”が発生していることを意味します。
個人の「意見表明」「自己決定権」を学んでいない日本社会では、このコミュニティとの間で生じる“力学(力関係)”が見え難く、表面化し難い顕在的な問題を抱えます。
このことが、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力(緊急避妊薬、中絶薬の導入を含む)、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなど暴力問題、つまり、人権侵害問題において、欧米諸国とは異なる日本特有の難しさの要因となっています。
日本の法律では、「人権」と「人格」、「共同親権」と「共同監護」など似ているけれどもまったく異なる表記を意図的にとり入れることに、政治姿勢、意図、目論見が示されています。
似ていても、意味がまったく異なることは、まったく異なる結果をもたらします。
日本政府は、「人権」を尊重するのではなく、「人格」を尊重する、つまり、社会問題・人権問題ではなく、すべて、「個人の心のあり方」、個人の問題と考えています。
この考え方が「自己責任」につながり、政治姿勢としての「自助」に示されます。
この「自助」のもとで「自己責任」を集約する場が「家」です。
この視点で、「女性と子どもの権利」にかかわる法律やその法律の下で構築された制度の捉えてみると、日本の仕組み(国造り)、日本の政治が少しずつわかってきます。
そして、第2次世界大戦終戦から3年後の昭和23年(1948年)12月10日、国連総会で、人権法の柱石(すべての人民にとって、達成すべき共通の基準)となる『世界人権宣言』を作成し、採択できることは、「人権」を学び、身につける土壌が既に構築されていた国々が多数あったことを意味しています。
この視点に立つと、日本の「人権解釈」は100年近く遅れていることが理解できます。
1.「律令制」「家制度(家父長制)」の流れを汲む『家族法(民法)』
「G7の中でもっとも遅れている。」、「G7の中で、これほどまでに後ろ向きな国は他にない。」と指摘されている日本の『民法』は、「日清戦争(明治27年7月-明治28年3月(1894年7月-1895年3月)」直後の明治29年(1896年)に制定され、その後、『家族法』が、明治31年(1898年)に公布・施行され、1,050条のうち725条以降の第4編「親族編」、第5編「相続編」を指します。
この指摘のキーワードは、日本の『家族法(民法)』が「G7の中でもっとも遅れている」ことと、この「太平洋戦争敗戦前から継承し続ける家族法(民法)を削除したり、改正したりするのに後ろ向きな歴代の日本政府の政治姿勢」です。
(1) 夫婦同姓制度(民法750条、戸籍法74条1号)と日本の税制度
① 女性差別撤廃委員から繰り返されている是正勧告
「G7の中でもっとも遅れている」と指摘される『家族法(民法)』のひとつは、『夫婦同姓制度(民法750条、および、戸籍法74条1号)』です。
この『夫婦同姓制度』は、世界唯一の制度で、『日本国憲法』の24条(法の下の平等など)に反するとして廃止された「家制度(家父長制)」の流れを汲みます。
日本の「家制度(家父長制)」は儒教思想にもとづき、646年以降進められた政治改革、いわゆる「大化の改新」で示された4つの施策方針のひとつとして、公家・武家に引き継がれてきました。
この「大化の改新」に強い影響を与えたのが、中国(唐時代)の「律令制」です。
世界で唯一の制度で、「律令制」、儒教思想にもとづく「家制度(家父長制)」の流れを汲む『夫婦同姓制度(民法750条、および、戸籍法74条1号)』は、『世界人権宣言』の第1条前段「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」に反する「夫婦同姓」と定められています。
そして、「日本の夫婦同氏制は、実質的に女性に不利益を強いる制度として機能している」ことが、昭和60年(1985年)に日本が批准した『女性差別撤廃条約』に違反します。
そのため、国連の「女性差別撤廃委員会」は、条約締結国である日本政府に対し、平成15年(2003年)、同21年(2009年)の2回勧告し、そして、同28年(2016年)2月、「女性差別撤廃委員会」の63会期において、同21年(2009年)の勧告に対する日本審査が行われています。
その課題リストで、a)制度的枠組み、b)暫定特別措置、c)ステレオタイプおよび有害な慣行、d)女性への暴力、e)売春の搾取と人身売買、f)政治的・公的機関への参画、g)教育、h)雇用、i)健康、j)災害、k)不利な立場にある女性、l)結婚および家族関係、m)『(女性差別撤廃条約)選択議定書』への批准といった13の分野における情報を提供するよう政府に求めています。
同30年(2018年)12月、「女性差別撤廃委員会」は、同28年(2016年)2月の日本側の報告に対し、さらなる行動に関する情報を求める見解を示しました。
しかし日本は、昭和60年(1985年)6月25日『女性差別撤廃条約』の批准・締結から38年9ヶ月、平成15年(2003年)の勧告から20年、平成28年(2016年)の勧告から8年、国連の「女性差別撤廃委員会」の勧告などに対し、頑なに対応を拒んでいます(令和6年(2024年)4月15日現在)。
② 戦前の「家」を基軸に制度設計された「税制度」を継承
太平洋戦争敗戦から76年経過した令和3年(2021年)に婚姻した夫婦の501,138組のうち「夫の名字」を選択したのが476,088組(95.0%)です。
この「夫の名字」を選択した95.0%の夫の多くが、「税制度」「社会保障制度(年金制度を含む)」に加え、「契約書」などの書類で続柄として記載を求められることが多い「世帯主」「扶養者」となっています。
これは、家庭内(夫婦間/親子間)で、「世帯主」と「家」に所属する人の関係、「扶養者」と「被扶養者」の関係という夫婦間の役割の位置づけに差が設けられていることを意味します。
夫婦間の役割の位置づけに差が設けられていることは、1947年(昭和22年)、国連で採択された『世界人権宣言』の第1条前段「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」に反します。
日本の「税制度」「社会保障制度(年金制度を含む)」は、「家」を基軸に制度設計されています。
なぜなら、太平洋戦争敗戦後も、日本政府は、明治政府が進めた軍国化(国民皆兵、富国強兵)」を支えた「税制度」をそのまま継承したからです。
この「税制度(軍国化のための税制改革)」を支えたのが、「家制度(家父長制)」です。
“呼称”としての「世帯主」「扶養者」は、「家父長」のいい換えに過ぎないといえます。
つまり、日本の「税制度」「社会保障制度(年金制度を含む)」などの社会システムは、太平洋戦争敗戦後も、その呼称も含めて、実質的な「家制度(家父長制)」を継承しています。
同じひとりの女性であるにもかかわらず、女性が結婚し「家」に入り、「家」に所属する人となったり、離婚し「家」から離れたり、または、結婚せず、正規労働者(正社員)として就労していたりすると、「所得税」「住民税」や「社会保険料」などの支払い、年金受給額などで違いが生じます。
しかも、男女の差は甚だしく、極めて不適切な制度となっています。
例えば、昭和60年(1985年)、国際連合(国連)加盟国の日本は、期限ぎりぎりで『女性差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)』を批准・締結した日本政府は、同年5月、『男女雇用機会均等法』を制定しなければならない状況に追い込まれました。
そこで、極右・超保守の政権は、「女性は家に」との基本姿勢として、女性の雇用機会を奪い、日本の結婚した女性の「専業主婦化」を進める政策に打ってでました。
それが、同年に発足させた『第3号被保険者制度』です。
サラリーマン・公務員の妻で、国民年金を払わなくても受給できる『第3号被保険者制度』を利用するには、結婚後、専業主婦であり続ける必要があることから、『男女雇用機会均等法』の適用は、結婚する前の女性(未婚の女性)だけに限られることになります。
つまり、その効果を限りなく無効にできます。
当時、つまり、昭和55年(1980年)の女性の未婚率4.45%、昭和60年(1990年)の女性の未婚率4.33%なので、『第3号被保険者制度』の発足による専業主婦化政策、『男女雇用機会均等法』の無力化政策はかなり有効でした。
それだけでなく、問題は、納付期間や収入により年金受給額は違いますが、厚生労働省の『令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、月の受給額は、「共働き世帯」では、夫16万3,000円に妻10万5,000円を加え、26万8,000円で、「夫婦のどちらかが専業主婦の世帯」では、夫16万3,000円に妻5万4,000円を加え、21万7,000円となり、その差は5万1.000円です。
国民年金の平均月額は、男性が約5万9,000円、女性が約5万4,000円なので、サラリーマン・公務員の妻で、国民年金を払わなくても受給できる『第3号被保険者制度』の優位性は、月額3,000円となります。
つまり、国民年金の支払い期間と受給期間の違いはありますが、支払いと受け取りの月額3,000円の違いは、共働きで賃金を得た方が、所得として優位であることは一目瞭然です。
男性の独身者の1年間の平均年金受給額は、厚生年金が207万円(月額約17万2,500円)、国民年金が70万円(月額約5万8,300年)、一方の女性の独身者の1年間の平均年金受給額は、厚生年金が130万円(月額約10万8,300円)、国民年金が64万円(月額約5万3,300円)です。
まるで、詐欺商法のようです。
「厚生労働省 統計情報(生涯未婚率の推移)」によると、生涯未婚率は、昭和35年(1960年)で男性が1.26%、女性が1.88%、昭和45年(1970年)で男性が1.70%、女性が3.33%、昭和55年(1980年)で男性が2.60%、女性が4.45%、平成2年(1990年)で男性が5.57%、女性が4.33%、平成12年(2000年)で男性が12.57%、女性が5.82%、平成22年(2010年)で男性が20.14%、女性が10.61%、令和2年(2020年)で男性が28.25%、女性が17.81%となっています。
20歳-24歳の女性の未婚率は、昭和55年(1980年)は80%を下回っていましたが、その後上昇し、平成2年(1990年)に86.0%、平成27年(2015年)になると91.4%になっています。
25歳-29歳の女性の未婚率は、昭和55年(1980年)は20%台半ばで、平成2年(1990年)に40.4%、平成27年(2015年)になると61.3%に上昇し、晩婚化の傾向が示されています。
平成27年(2015年)の30歳-34歳の女性の未婚率は34.6%、同年35歳-39歳の未婚率は23.9%、同年40歳-44歳の未婚率は19.3%、同年45歳-49歳の未婚率は16.1%、同年50歳-54歳の未婚率は12.0%と、晩婚化に加え、生涯未婚率が上昇しているのがわかります。
この生涯未婚率の上昇と、高齢女性の貧困化には一定の相関関係があります。
日本の「家」を基軸に制度設計されている「税金」「社会保障制度(年金制度を含む)」は、例えば、年金では、受給年齢になったとき夫婦が揃っていて生活できる額を支給する制度設計となっていることから、ア)「被扶養者」で「専業主婦」となった女性が離婚し、「家」を離れたり、イ)未婚(独身)で、男性の「家」に入らなかったりした女性は、受給年齢になったとき、生活苦に陥る高いリスクがあります。
また、「社会保険(健康保険)」の扶養対象となる「収入基準額は、年間130万円未満(被扶養者が60歳以上であったり、障害があったりするときは、180万円未満)と定められている(判断は、社会保険(健康保険)は月々の収入)」ことも同様の仕組みといえます。
例えば、59歳未満の配偶者の妻が、夫の扶養に入っているときには、妻の年間の収入は130万未満、これを月給に換算すると108,333円未満となります。
このことは、夫の扶養に入っている限り、月給108,334円以上の収入を得られる職に就けない(避ける必要がある)、つまり、非正規雇用であり続けることを意味します。
この制度の背景にあるのは、家制度(家父長制)で、「妻は夫を支える役割として、夫が困っているときには、内職をして家計を助ける」との価値観、つまり、「内助の功」「良妻賢母」にもとづいています。
例えば、アルバイトなどのパートタイム労働による収入は、通常、給与所得となり、給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。
給与所得控除額は最低55万円であることから、アルバイトなどのパートタイム労働による収入金額が103万円以下(給与所得控除額55万円に所得税の基礎控除額48万円を加えた金額)で、他に所得がなければ所得税はかかりません(令和元年(2019年)以降)。
そして、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、納税者本人(配偶者を扶養に入れている者)は、所得税の配偶者控除を受けることができます。
つまり、配偶者の収入がアルバイトなどのパートタイム労働による収入だけで、その収入が103万円以下であるとき、給与所得控除額の55万円を差し引くと所得金額は48万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
収入を一定以内に収める「扶養内勤務」で、税金や社会保険料の負担を抑えることが“賢い妻”という役割は、「良妻賢母」「内助の功」そのものです。
この「良妻賢母」「内助の功」として夫を支えるのが妻の役割、賢い妻と認識している女性は、意識、無意識にかかわらず、家制度(家父長制)、そして、男尊女卑社会を受け入れていることになります。
国税庁のホームページに掲載されているデータ(平成10年度)では、給与所得者数は4,274.8万人、配偶者数は1,292.3万人(30.23%)で、1年を通じて勤務した給与所得者4,545万人のうち年末調整を行った者は4,275万人(94.1%)です。
このうち、配偶者控除、または、扶養控除の適用を受けた者は1,823万人(42.6%)で、扶養人員のある者1人あたりの平均扶養人員は2.21人です。
配偶者控除のある者では、扶養人員3人(配偶者、及び、扶養親族2人)の者が394万人(30.5%)でもっとも多く、一方、配偶者控除のない者についてみると、扶養人員1人(扶養親族)の者が256万人(48.3%)でもっとも多くなっています。
1年を通じて勤務した給与所得者で年末調整を行った者のうち、「配偶者特別控除」の適用を受けた者は1,148万人(26.85%)で、そのうち、「配偶者控除」と併せて受けている者は1,092万人(95.12%)で、配偶者特別控除のみを受けている者は56万人(4.88%)です。
配偶者数は1,292.3万人なので、「配偶者特別控除」の適用を受けた1,148万人は、88.83%に該当し、「配偶者控除」と併せて受けた1,092万人は、84.50%に該当、配偶者特別控除のみを受けている者56万人は、4.33%に該当します。
つまり、配偶者数は1,292.3万人のうち1,148万(88.83%)は、収入金額が103万円以下(給与所得控除額55万円に所得税の基礎控除額48万円を加えた金額)のアルバイトなどのパートタイム労働で、配偶者特別控除のみを受けている者56万人(4.33%)は、1年間の合計所得金額が48万円-133万円未満の就労者で、134万円以上の収入を得て、扶養に入っていない配偶者は、わずか144.3万人(11.17%)です。
同じく社会保険料控除、生命保険料控除、及び、損害保険料控除の適用を受けた者は、それぞれ3,805万人、3,395万人、及び、1,715万人で、1人あたりの平均控除額は、50.5万円、5.9万円、及び、0.6万円です。
したがって、収入金額が103万円以下(給与所得控除額55万円に所得税の基礎控除額48万円を加えた金額)のアルバイトなどのパートタイム労働者1,092万人(84.50%)、1年間の合計所得金額が48万円-133万円未満の労働者56万人(4.33%)が、DVなどが原因で離婚に至ると、ひとり親家庭(シングルマザー)では生活が困窮しやすくなります。
このように、日本の「家」を基軸に制度設計された「税制度」「社会保障制度(年金制度を含む)」は、「個人」を基軸に制度設計されている欧米諸国に比べて、女性や子どもを家に縛りつけやすい構造を伴います。
日本で暮らす女性は、結婚し、嫁として「家」に属し、子どもを設けたとき、その関係性を維持し続けなければ、国の制度として、経済的に不利を被りやすくなります。
このことは、日本の「家」を優遇する「税制度」「社会保障制度(社会保障制度)」は、離婚したくても、離婚後の経済的困窮を避け、思い留まらせる足枷となっていることを意味します。
また、昭和60年(1985年)に成立した『男女雇用機会均等法』を無力化するための「専業主婦化政策」として、同年、にサラリーマン・公務員の妻で、専業主婦なら国民年金を払わなくても受給できる『第3号被保険者制度』を発足させてからは、女性の身分をハードワークの総合職、所得が低く不安定な非正規雇用、専業主婦に分断することになり、女性の経済格差、男女の賃金格差の拡大をもたらしました。
・軍国化と「税制」、「税制」を支えた「家制度(家父長)」
明治政府が「国民皆兵(明治6年(1873年)の徴兵令発布)」を進め、欧米の国々に対抗するため、経済を発展させ、軍隊を強くする「富国強兵」を目指し、一気に「軍国化」を進めるには、この教えを自分たちに都合のいいストーリーに仕上げる必要がありました。
この国家的なキャンペーンを先導したのが、佐賀藩出身で日本の法典編纂を主導した江藤新平です。
このときにつくられた学制、税制、徴兵制は、徴兵制を除き、いまの学制、税制(社会保障制度、年金制度)の基礎となっています。
明治政府が目指した「国民皆兵」「富国強兵」には、学制、兵制、税制改革は不可欠で、そのうえで大きな役割を果たしたのが「家制度(家父長制)」です。
そして、儒教思想に馴染みのない「武家(江戸時代の人口の7%)」以外の「寺請制度」で仏教の説話に親しんできた一般市民(ほとんどは農民)に進めたのが「(儒教思想にもとづく)道徳教育」です。
・日本の男女間の賃金格差。OECD(経済協力開発機構)に加盟38ヶ国の中で37位
日本は、ひとり親家庭(シングルマザー)が、なぜ、貧困に陥りやすいのか? その背景にあるのが、男女間の賃金格差です。
この「男女間の賃金格差」の背景にあるのは、いうまでもなく、日本の「扶養」という制度です。
平成29年(2017年)、日本の男女間の賃金格差は24.5%で、OECD(経済協力開発機構)に加盟38ヶ国の中で、韓国の34.6%に続き2番目に高くなっています。
日本の男女間の賃金格差は、2005年(平成17年)は32.8%で、その後、緩やかな減少傾向にあるものの、欧米諸国は10%台なのに対して、韓国と日本の2ヶ国だけが突出して高くなっています。
韓国と日本に共通しているのは、「儒教社会」であること、実質的な「家制度(家父長制)」であることですが、韓国の人々は、このことを認識していることに対し、日本の人々は認識していないことです。
アメリカでは、泥沼化するベトナム戦争に対する「反戦運動」、「ウーマンリブ運動(女性解放運動)」が「権利擁護運動」の組織を生み、ボランティアが自宅をDV被害者用の避難所をとし、危機対応のサービスを提供したことが「DV活動」のはじまりで、「DV介入プロジェクト(DAIP)」の構築につながりました。
同時期に、第1次オイルショック(昭和48年(1973年))、第2次オイルショック(昭和53年(1978年))が起きたことをきっかけに、欧米諸国における「母親が育児に専念できる時代」は終わりました。
しかし、日本社会では、女性の社会進出は進みませんでした。
なぜなら、超保守派の政権、政党、政治家、その政治支援団体は、「女性に家庭責任を負わせる」と誘導したからです。
つまり、日本政府は、この「被扶養者」を増やし、結婚した女性の「専業主婦化」を進めました。
日本において、この男女間の経済格差をもたらす「男女の賃金格差」が拡大した要因については、第1に、昭和60年(1985年)、日本が『女性差別撤廃条約』を批准・締結し、同年5月、『男女雇用機会均等法』を制定すると同時に、サラリーマン・公務員の妻で、専業主婦なら国民年金を払わなくても受給でき『第3号被保険者制度』を発足させる一方で、結婚した女性の「専業主婦化」を促進させたこと、第2に、昭和61年(1986年)、『労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)』を施行したことです。
つまり、『第3号被保険者制度』の発足は、同年に制定した『男女雇用機会均等法』を無力化する意図で構築し、翌年に施行となった『労働者派遣法』は、非正規雇用であることから、ア)サラリーマン・公務員の妻の「専業主婦化」をはかり、イ)サラリーマン・公務員の妻が働くなら非正規雇用という“構図”をつくりあげたことになります。
この1980年代、日本は、「低金利政策」を背景に地価が高騰し、株価も急伸したことが、バブル経済につながっていきます。
その後、平成2年(1990年)3月、「大蔵省(当時)通達」で、不動産向け融資を抑制する総量規制を導入したことを契機に、資産価格は急落し、バブルは崩壊しました。
この期間で、女性の身分をハードワークの総合職、所得が低く不安定な非正規雇用、専業主婦に分断することになり、女性の経済格差、男女の賃金格差の拡大をもたらしました。
日本で、『男女雇用機会均等法』が機能しなかった理由はここにあります。
バブル経済の崩壊で、加速したのが、女性の派遣社員・契約社員、非正規雇用・パートタイム労働です。
男女間の賃金格差は、一般労働者の平均賃金に顕著に表れています。
「一般労働者」とは、常用労働者のうち、パートタイム労働者、つまり、非正規雇用者を除いた労働者のことです。
令和4年(2022年)、厚生労働省の『賃金構造基本統計調査』では、一般労働者の平均賃金は月31万1800円で、男性が34万2000円、女性が25万8900円で、その差は83,100円です。
男性賃金を100として女性の賃金を数値化する「男女間賃金格差」は75.7です。
韓国と日本に共通しているのは、儒教思想にもとづく道徳観と家父長制です。
家父長制が色濃く残る日本は、女性が高収入を得られる仕事に就くことを嫌い、望まず、奪う社会です。
家父長制の下での男性は、女性や子どもから敬われる存在、女性が高収入を得られる仕事に就き、自立できる状況は、男性の自尊心が傷つき、損なわれます。
男性が自尊心をとり戻すためには、女性が高収入を得られる仕事に就けなくする必要があります。
つまり、「女性は家に!」という考えをもとに政策を考え、実行するのが、極右・超保守の政権、政党、政治家、彼らと“共同体”ともいえる強固な関係を築いている「はじめに。」で示したア)イ)ウ)エ)の政治団体、そして、圧倒的多数の保守の人たち(企業の経営者などを含む)です。
・男女間の賃金格差と「ジェンダーギャップ指数」
この男女間の賃金格差と「ジェンダーギャップ指数」は深い関係があり、同時に、その国(政権)の姿勢が顕著に表れます。
ジェンダーギャップ指数で14年連続1位の「アイスランド」は、日本が、1972年(昭和47年)2月の「あさま山荘立てこもり事件」後、若者が社会問題と距離を置き、政治に無関心になっていったのとは異なり、1975年(昭和50年)、国内女性の約90%が参加したといわれるストライキを機に、ジェンダー平等のとり組みが活発になりました。
そして、男女ともに、企業役員や公共の委員会の構成員について40%を下回ることを禁ずる「クオータ制(割り当て制)」などが、雇用機会の不平等改善に大きく寄与しています。
この雇用機会の不平等改善の実現には、誰でもすぐ入園できる保育園や幼稚園などのインフラの充実が支えています。
いまから7年2ヶ月前の2017年(平成29年)1月、世界で最初に、『ジェンダー(性別)による賃金格差を禁止する法律』を施行し、「男女の同一労働同一賃金を守ること、その証明をし、認証取得することを企業や団体に義務づけ、違反したときには罰金を科す」ことができます(令和6年(2024年)4月15日現在)。
2位の「ノルウェー」は、「充実した福祉社会を維持するには、男女かかわらず国民一人ひとりが自立して納税すること」が最重要事項と考え、「男女ともに就労者である」と認識しています。
そのため、就労者である男女を支えるシステムが充実しています。
ノルウェーの企業は、遅くとも16時ころには勤務時間が終了します。
男性の育児休暇制度も浸透し、家庭では夫婦が分担して家事をし、夫婦で子どもの面倒を見るのが常識となっています。
介護は政府と自治体が担い、女性の就労継続をサポートするなど、女性の就労継続を阻む「育児」や「介護」などの問題を解消するための制度や意識改善が進んでいます。
一方の日本における男女間の賃金格差が大きい理由は、ア)正規・非正規の賃金格差と女性の非正規比率の高さと、イ)性別役割の固定化と就社型雇用システムの2つです。
終身雇用を前提とする正社員雇用を守ろうとすると、非正規雇用との処遇格差が大きくなります。
終身雇用と表裏一体の「長時間労働」や「会社都合の転勤」は、「男性は会社、女性は家庭」という男女分業(性別役割の固定化)を“前提”としていて、女性の多くが、非正規雇用で働いています。
非正規労働者の70%近くが女性です。
欧米においても、非正規雇用が少くありませんが、ヨーロッパでは、「企業横断的に同一労働同一賃金原則」が浸透していることから、日本と比べて、正規と非正規の賃金格差は大きくありません。
もうひとつの日本の男女間の賃金格差の原因である「性別役割の固定化」と「就社型雇用システム」は、根が深い問題です。
女性は、正社員として採用された企業において、いまだに、結婚や出産を機に退職せざるを得ない職場風土の企業が少なくなく、しかも、出産後、職場に復帰してからは、昇格・昇給が抑制されます。
『改正男女雇用機会均等法』が施行され、採用や昇進・昇格においては表面上(上辺だけ)の差別はなくなりましたが、女性に対する会社の姿勢、社会の捉え方はほとんど変わっていません。
なぜなら、家父長制が色濃く残る日本社会と日本企業に長年染みついた性別役割分業意識に加え、女性の昇進などに対する根深い「アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)」があるからです。
近年の日本は、平成12年(2000年)と令和2年(2020年)の年間平均賃金額の比率を見ると1.02倍と、この20年間、実質賃金は上昇していません。
一方で、他国の実質賃金の上昇を見てみると、韓国は1.45倍と非常に高く、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスは1.2倍程度となっています。
平成12年(2000年)の日本の実質賃金は3万8085ドルで、世界第5位でした。
日本の実質賃金は、アメリカの6万1048ドルよりはかなり低く(62.4%)、イギリスの4万6863ドル(81.3%)、ドイツの4万7054ドル(80.9%)、フランスの4万4325ドル(85.9%)と比べても低い一方で、韓国は3万6140ドル(105.4%)で、日本と大差がありませんでした。
ところが、20年後の令和2年(2020年)になると、日本の実質賃金は3万8515ドルで、アメリカの6万9391ドルに比べ55.5%と、さらに両者の差は、6.9ポイント広がりました。
イギリスは4万7147ドル(81.7%)、わずか0.4ポイントの差が縮まったものの、ドイツは5万3745ドル(71.5%)で9.4ポイント、フランスは4万5581ドル(84.5%)で1.4ポイント差は広がり、韓国は4万1960ドル(91.8%)で、日本を逆転し、その差は実に13.6ポイントに及びます。
・負の遺産をつくりあげた「アベノミクス」
いま、日本より実質賃金が低い国は、OECD(経済協力開発機構;ヨーロッパ諸国を中心に日・米を含め38ヶ国の先進国が加盟する国際機関)の中で、旧社会主義国、ギリシャ、イタリア、スペイン、メキシコ、チリぐらいしかなく、日本は最下位グループに入ります。
では、なぜ、日本はこの20年間でここまで経済競争力を失ったのでしょうか?
その原因は、第2次安倍晋三政権での「アベノミクス」の実施です。
なぜなら、「アベノミクス」は、日本企業の技術革新が進まず、実質賃金があがらない中で、円安を主導し、賃金の購買力を低下させることで株価をひき上げてきたからです。
つまり、「アベノミクス」の問題は、一部の大企業と株主だけに利益が得られるシステムということです。
正常にマーケットが機能していれば、価格の安い日本製品の輸出が増え、円高になり、その状況は、不均衡がなくなるまで続き、輸出の有利性は減殺されます。
本来、企業は、円高を支えるために技術革新を実施し、生産性をひきあげなければなりませんが、「アベノミクス」では、本質の問題を先送りし、円安を求めました。
その結果、日本の実質賃金はあがらなくなりました。
物価が低いことが問題なのではなく、賃金があがらなかった(政府主導の下で、企業側が賃金をあげるつもりがなかった)ことが最大の問題です。
賃金があがらず、しかも円安になったことから、日本の労働者(一般市民)は、国際的に見て急激に貧しくなりました。
大企業は、賃金を抑える中で株価があがっているので、利益剰余金(内部留保)としての純資産は増加しています。
大問題は、純資産が増加している中で、技術革新を進める設備投資を怠ったことです。
技術革新を進める設備投資ができる状況であるにもかかわらず、技術革新を進める設備投資を怠ったことは、今後、日本経済の衰退を加速させます。
では、第2次安倍政権以降、大企業の利益剰余金は、なにに使われてきたのでしょうか?
それは、株式配当に充てられてきました。
そのため、「過去最高の利益をだした」「株高が過去最高を更新した」とニュースが伝えていますが、社員の給与には反映されていません。
自社株を所有している経営陣と株主だけが懐を潤し、その潤ったお金が、支持政党、支持する政治家に流れます。
株価があがり、物価があがり、経済的な効果があるように見せかけた「アベノミクス」の実態は、真逆の負の遺産をつくりあげただけです。
それも、日本経済の将来に致命的なものです。
この状況は、多少経済学を学んだ者には容易にわかることで、「アベノミクス」の問題点を指摘することなく放置し続けた日本の経済紙・ビジネス誌、メディアは怠慢であるだけでなく、大きな罪を負っています。
加えて、日本は、令和5年(2023年)1年間のGDP(国内総生産)は3位から4位に転落しました。
日本の経済規模は、昭和43年(1968年)にGNP(国民総生産)で、当時の西ドイツを上回り、アメリカに次いで世界2位となり、その後、平成22年(2010年)にGDPで中国が2位、日本は3位となり、令和5年(2023年)、人口がほぼ2/3のドイツに抜かれ、4位となり、数年後にはインド、シンガポールに抜かれる予定です。
その日本の実質賃金は、OECDの中で最下位グループに入っていることを知り、なぜ、そうなったのかを理解している人は、どのくらいいるのでしょうか?
平成8年(1996年)、1人あたりGDPはG7で2位、世界17位でしたが、25年後の令和3年(2021年)になると、1人あたりGDPは、G7では最下位で世界37位、物価変動の影響を除いた日本の実質経済成長率は約1.6%、世界157位と散々な状況です。
日本と同じ主要先進国(G7)では、イギリスが7.4%、フランスが7.0%、アメリカが5.7%などと大きく成長しています。
1人GDPが世界17位(平成8年(1996年))、G7では最下位で世界37位(令和3年(2021年))で、GNP世界2位(昭和43年(1968年)-)からGNP世界3位(平成22年(2010年))に転落後、なんとか令和4年(2023年)まで3位を維持できたのは、「低賃金」、「長時間労働」で穴埋め、辻褄を合わせてきたからです。
日本は、バブル経済崩壊後、「失われた10年」といわれてきましたが、実は、「失われた30年」で、いまもその渦中、その衰退から抜けだす光をどこにも見つけることができない深刻な状況です。
第2次安倍晋三政権以降、「アベノミクス」により、20年間、実質賃金があがらない中で、正規と非正規の賃金格差は大きく、勤務する女性の多くが非正規である現実がもたらしたのは、子どもの7人に1人が貧困という現実です。
「子どもの7人のうち1人が貧困」となっている日本の「ひとり親世帯貧困率」は50.8%で、主要41ヶ国の中で4番目に高く、G7ではもっとも高く、改善の見通しはまったく立っていません。
この状況を生みだしたのは、紛れもなく歴代の保守政権と第2次安倍晋三政権以降の自由民主党、自由民主党に加担する保守政党すべて、彼らと“共同体”ともいえる強固な関係を築いている「はじめに。」で示したア)イ)ウ)エ)の政治団体、そして、日本の大手企業を中心に構成された経済団体「日本経済団体連合会」に「日本商工会議所」「経済同友会」を加えた「経済3団体」です。
・相対的貧困率。7人に1人の子どもが貧困
厚生労働省の『国民生活基礎調査』によると、「貧困線」は、直近の2021年(令和3年)の127万で、「相対的貧困率」は15.4%で、30年前より1.9ポイント高く、日本人口の6人に1人は相対的貧困となっています。
「相対的貧困率」とは、国や地域の中での経済格差を測る代表的な指標のひとつで、生活状況が自分の所属する社会の大多数よりも、相対的に貧しい状態にある人の割合を指します。
所得が、集団の中央値の半分にあたる「貧困線」に届かない人の割合を指し、税金や社会保険料を除いた手取りの収入を世帯の人数で調整した「等価可処分所得」が比較の物差しになります。
先進国の指標となる「OECD(経済協力開発機構)」では、「世帯の所得がその国の等価可処分所得(手取り収入を世帯人数の平方根で割って調整した額の中央値の半分(貧困線)に満たない人々の割合」と定義し、先進国ではこのタイプの貧困が多く見られます。
一方、「絶対的貧困率」は、国や地域における生活レベルとは関係なしに、衣食住といった必要最低限の生活水準が満たされていない人の割合のことを指し、「世界銀行」が定めた国際貧困ラインでは、「1日1.90アメリカドル未満で生活する人の割合」と定義しています。
2022年(令和4年)末までに絶対的貧困に該当する人々は、全世界で6億8,500万人と推定されており、そのうちの70%以上がサブサハラ・アフリカ地域に集中し、中東と北アフリカ地域で上昇傾向にあります。
OECD(経済協力開発機構)によると、アメリカは2021年に15.1%、英国は2020年に11.2%で、日本の状況は、アメリカ・イギリスと比べると国内の経済格差が大きくなっています。
日本における「子どもの相対的貧困率」は、2012年(平成24年)16.3%、2015年(平成27年)は15.7%、2018年(平成30年)は15.4%とわずかな改善傾向を示し、これがピークで、2021年(令和3年)には11.5%まで下がりました。
ひとり親世帯は44.5%で、大人が2人以上いる世帯の8.6%と比べると実に35.8ポイントの開きがあります。
このことは、ひとり親世帯は、経済的に著しく苦しいことを意味しています。
相対的貧困に該当する人々の手取り所得は、「貧困線」の127万円を下回ります。
つまり、月々約10万円で、家賃、光熱費、食費などすべてを賄うので、病気の治療費、子どもの進学費を払うことも難しくなります。
平成30年(2018年)、17歳以下の子どもの貧困率は13.5%で、7人に1人の子どもが貧困となっています。
そのため、子どもが進学をあきらめ、就職せざるをえなかったり、親が多くの仕事をかけもちするダブルワーク、トリプルワークをしなければならなかったりする状況が生まれています。
このいまの日本の状況は、2021年(令和3年)のOECDの相対的貧困率では、先進国38ヶ国の中でもっとも高く、G7(主要7ヶ国)でワースト1位です。
相対的貧困率の高さは、国内における経済的な格差の大きさを示します。
日本の相対的貧困は、65歳以上の高齢者世帯や単身世帯、ひとり親世帯が多く、令和3年(2021年)に生活保護を受けた世帯の55.3%が高齢者世帯、50.8%が単身世帯となっており、高齢になるにつれて、男性より女性の貧困率が高くなります。
この理由は、日本の「税制度」「社会保障制度(年金制度を含む)」が、戦前の「家」を主軸にした制度設計が継承されているからです。
(2) 協議離婚制度(民法763条)と離婚事由(民法770条)の規定
G7の中でもっとも遅れている「家族法」のもうひとつは、日本の離婚全体の87.8%を占め、他国にはない特殊な『協議離婚制度(民法763条)』です(「離婚」に占める%は、平成21年度厚生労働省「離婚に関する統計」による)。
この他国にない特殊な離婚制度は、「律令制(男子専権離婚/江戸時代の「三行半」などにひき継がれてきた)」、儒教思想にもとづく「家制度(家父長制)」の流れを汲んでいます。
日本では、「離婚」は、ア)夫婦が同意して署名し、「協議離婚届書(離婚届)」を戸籍係に提出する方法(協議離婚)、イ)家庭裁判所の調停の場で離婚の合意をする方法(調停離婚(家事事件手続法268条)/9.7%)、ウ)調停でまとまらず、家庭裁判所が離婚の審判をする方法(審判離婚(家事事件手続法284条・同法297条)/0.03%)、エ)『民法770条1項』に定める「離婚事由」があるとき、家庭裁判所の判決で離婚が命じる方法(判決離婚(人事訴訟法37条)/2.4%)のいずれかの方法で成立させる必要があります。
家庭裁判所のもとで離婚の有無が合意・判断されるイ)ウ)エ)では、『民法770条1項』で定める「離婚事由」に該当していることが必要となります。
ア)の「協議離婚制度」は、江戸時代、「三行り半(みくだりはん)」と呼ばれる3行と半分の文章で『離縁状』を書き、妻に渡すことで、いつでも妻を追いだすことができた「追出し離婚」の流れを汲むものです。
日本では、離婚そのものは認められてきたものの、「律令制」のもとで定められた「七出」や「三不去」、のちには、「三行半の交付」による『追い出し離婚』など、いずれも「男子専権離婚」の法制でした。
時代背景としては、孝徳天皇や中大兄皇子が、646年以降進めた政治改革、いわゆる「大化の改新」で4つの施策方針を示していますが、それは、中国の「律令制」の強い影響を受けたものです。
「七出」とは、『唐律令(等の律令制度)』に定められた「夫の一方的な意思により離婚できる7つの事由」の戸令のことで、ア)舅姑に従わない、イ)子ができない、ウ)姦通、エ)いい争いが多い、オ)盗み、カ)嫉妬深い、キ)たちの悪い病気の7つで、「三不去」とは、「(七出に該当していても)離婚できない3つの事由」のことで、ア)舅姑の喪に3年間服した、イ)貧しいときに嫁いで、のちに豊かになった、ウ)帰る所がないの3つです。
先の「七出(離婚できる7つの事由)」と、『明治民法813条』の「10の具体的離婚原因」という考えは、現『民法』の「離婚事由(770条)1項」にひき継がれています。
『民法770条1項』に定める離婚事由は、a)配偶者に不貞行為がある、b)配偶者から悪意で遺棄された(「同居義務、協力義務、扶助義務を負う」に対し、不当に違反する行為)、c)配偶者の生死から3年以上明らかでない、d)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない、e)その他、婚姻を継続し難い重大な理由があるの5つで、e)の「その他、婚姻を継続し難い重大な理由」には、ア)配偶者からの暴力・暴言、その他の虐待行為を受けた、イ)夫婦間の性関係がない(セックスレス)、ウ)性格の不一致、エ)配偶者が某宗教団体に入会し、布教活動に熱中し家庭を顧みない、オ)配偶者と両親との不仲などといったおこないが該当します。
「婚姻破綻の原因は、配偶者からのDV行為である」として、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停を申立てるときには、e)-ア)、つまり、『民法770条第1項5号』の「その他、婚姻を継続し難い重大な理由がある」の中の「配偶者からの暴力・暴言、そのほかの虐待行為を受けた」が、法律上の離婚事由になります。
本国会に提出されたⅰ)の「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」では、ア)の「協議離婚」において、父母間の協議(話合い)で共同親権とするか、どちらか一方の単独親権とするかを決めるのが基本で、夫婦間の協議(話合い)で、意見が異なり、決まらないときには、家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が、親子の関係などを踏まえて決定するとしています。
しかし、このア)の「協議離婚」は、「離婚後の共同親権制度」を採用している他国(世界の圧倒的多数の国々)にはない制度であることから、他国(世界の圧倒的多数の国々)では、離婚をする当事者だけで話し合い、「単独親権」か、「共同親権」かを決めることができず、すべて「家庭裁判所」の判断となります。
ここに、「離婚後の共同親権制度」を採用している他国(世界の圧倒的多数の国々)との決定的な違いがあり、日本の問題は、「家庭裁判所」が介入しないア)の「協議離婚」での離婚が、離婚全体の87.8%を占めることです。
令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」では、このとき、一方の親にDV行為があったり、子どもに対する虐待行為があったりして、「子どもの利益が害される怖れがある」ときには「単独親権」とするとしています。
「本来、対等の関係にある夫婦間で、上下の関係性、支配と従属の関係性を成り立たせるためのパワー(暴力)の行使がある」、つまり、「夫婦間にDV行為としての暴力がある」とき、この『協議離婚制度(民法763条)』にもとづく協議(話し合い)では、この夫婦(父母)関係の力関係により、対等な話し合いができずに「共同親権」を強いられる高いリスクが存在します。
(3) 単独親権(民法819条)と養育費の不払い
「2-(2)-①新しい構図のもとで新たな「単独親権制度」がはじまるまでの経緯」で示しているとおり、日本の産業構造・就労構造が大きく変わる中で、「家族のあり方」も大きく変わり、離婚後の子どもの「親権」は、「家」から「子どもを連れて家をでた女性(子どもの母親)」が得るようになりました。
そのプロセスで生まれた『離婚後の単独親権制度』の“新しい構図”で問題となったのは、離婚後、子どもの監護者でない一方の親による養育費の不払いです。
『離婚後の単独親権制度』は、「家制度(家父長制)」の流れを汲みます。
「家制度」に準じると、子どもは「父親の家」と「母親の家」の両方に所属するのではなく、一方の「家」に所属することから、子どもの養育にかかわる費用のすべては、子どもが所属する「家」が担います。
日本では、この「子どもは家に所属する」という考えが、「離婚したとき、子どもの父母がともに養育にかかわる費用を負担する」、つまり、「子どもの監護者の親に対し、もう一方の親が子どもの養育費を支払う」という習慣が根付かなかった大きな要因となっています。
厚生労働省が実施した『養育費、面会交流の取り決め状況等(平成28年度全国ひとり親世帯等調査)』では、「養育費」のとり決めをしている世帯(「とり決めをしている」、「子によって違う」)は44.6%で、「受けたことがあるが、現在は受けていない」が11.6%で、「いまも養育費を受けている」は27.0%となっていますが、ア)養育費のとり決めをした母子世帯で、養育費を現在も受けているのは53.3%であるのに対し、イ)養育費のとり決めをしていない母子世帯で、養育費を現在も受けているのは僅か2.5%です。
他の調査では、夫婦関係調整(離婚)調停で、離婚後の養育費の支払いを約束して離婚が成立した案件であっても、離婚後に子どもの養育費の支払いは24.3%で、しかも、離婚後3年を経過すると15%ほどに低下しています。
これが、日本の現状です。
離婚後の「養育費」は、『民法766条1項』の「子の監護に要する費用」に該当し、「子を監護していない親から、子を監護している親に対して支払われる未成熟の子の養育に要する費用である」と規定しています。
また、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子の面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担、その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と規定しています(民法771条で裁判上の離婚に準用)。
未成熟な子ども(成人に達していない子ども)に対する親の扶養義務は、親と同程度の生活を保障する「生活保持義務」として、親子関係そのものから生じるものであるとし、離婚後も父母は親権の有無にかかわらず、それぞれの資力に応じて子どもの養育料を負担すべき義務を負います(昭和52年(1977年)12月20日「福岡高等裁判所」による判決(家月30巻9号75頁参照))。
つまり、「養育費の支払義務」は、自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務(生活保持義務)で、「養育費請求」の根拠は、親子間の扶養義務(民法877条)です。
そして、「養育費の支払い」について、当事者間で協議が調わないとき、または、協議することができないときは、家庭裁判所に調停、または、審判の申立てをすることができます(民法766条2項、家事事件手続法別表第2の3項、同法244条)。
平成24年(2012年)4月1日以降、『協議離婚制度(民法763条)』による「離婚」では、『ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)』の批准・締結に備え、その2年前の平成23年(2011年)6月3日に法改正された『民法766条1項』の施行に伴い、「離婚届用紙」には、「養育費の分担」「面会交流取り決め」の有無についてチェックする欄が設けられています。
法務省によると、平成27年度(2015年度)の未成年の子どもがいる夫婦が離婚したとき、養育費の「とり決めしている」にチェックした割合は62.6%程度で、平成28年度(2016年度)は64-65%となっています。
しかし、この数字が、実態を表しているかはわかっていません。
「とり決め」が口頭での約束なのか、「合意書」や「公正証書(強制執行認諾条項付きの公正証書)」を作成しているのなど、法務省はまったく把握できていません。
こうした中で、令和2年(2020年)4月、養育費を回収しやすくする『改正民事執行法』が施行されました。
この改正により、離婚後に子どもを養育している親が、養育していない親の「銀行口座」「勤務先」などの情報を取得しやすくなりました。
こうした情報が取得しやすくなることの意義は、養育費が未払いになったときに、速やかな差し押さえ(強制執行)につなげられることです。
つまり、夫婦関係調整(離婚)調停において、離婚が成立したときに作成される『調停調書』に「養育費について定めた条項」を盛り込むことで、離婚訴訟の判決などの債務名義にもとづく「差し押さえ(強制執行)」が、これまでよりもやりやすくなりました。
それは、「監護親」について、新たに、ア)金融機関から預貯金の情報を取得できる、イ)登記所(法務局)から土地建物に関する情報を取得できる、ウ)市町村・日本年金機構から給与債権、つまり、勤務先の情報を取得できるようになりました。
例えば、養育費の支払いが滞り、ひき続き支払いを求めたい監護者が、被監護者が離婚後に転職をし、新たな勤務先がわからず、養育費の支払いを諦めるしかなかった事態を防ぐことができる、つまり、養育費の支払いを諦めずにすむということです。
シングルマザーの貧困は、深刻な社会問題であることから、生活保護の受給を受け入れることも踏まえて、離婚後の生活を破綻させないことは重大テーマといえます。
しかも、「婚姻破綻の原因は、配偶者からのDV行為である」ときの離婚では、DV被害者が、暴力被害の後遺症として「被虐待女性症候群(バタードウーマン・シンドローム)」、「PTSD」、「うつ病」、「解離性障害」など症状や傾向に長く苦しみ、仕事ができなく退職したり、就職できなかったり、日常生活に支障が生じたりすることが少なくないことから、離婚後の生活が破綻しやすいリスクを抱えます。
そのため、離婚後、子どもの親権者に対する「養育費の支払い」において、この『民事執行法』の“改正”は、DV被害者の大きな支えになります。
しかし問題(欠陥)は、ア)協議離婚であっても、「面会交流」「養育費の分担」など文書(離婚協議書)としてとり決めをまとめて、公証役場で公正証書(強制執行認諾条項付きの公正証書)にすること、イ)夫婦関係調整(離婚)調停での『調停調書』や離婚訴訟の『判決(判決文)』が作成されるときに、「債務名義に、養育費について定めた条項が記載されている」ことが“前提”となっていることです。
つまり、この『改正民事執行法』の上記のような“前提条件”は、「離婚」の87.8%を占める、他国にはない特殊な『協議離婚制度(民法763条)』の下では、その効果はほとんど期待できません。
なぜなら、「協議離婚」に至った夫婦で、『調停調書』に準じる「覚書」を作成し、公証役場で『公正証書(強制執行認諾条項付きの公正証書)』にしていることはほとんどないからです。
つまり、家庭裁判所に、「夫婦関係調整(離婚)調停」を申立て「離婚」に至る「調停離婚(家事事件手続法268条)/9.7%」、「審判離婚(家事事件手続法284条・同法297条)/0.03%」、「判決離婚(人事訴訟法37条)/2.4%」の12.13%で、しかも、上記条件を『調停調書』に残すことに合意したり、『判決文』に明記したりしていなければ、この『改正民事執行法』は意味をなさないことになります。
この『改正民事執行法』を有効にするためには、離婚全体の87.8%を占め、他国にはない特殊な『協議離婚制度(民法763条)』を廃止することが必要です。
つまり、「2-(2)- ③新しい構図のもとでの新たな「単独親権」。都合が悪くなった人々」の中で述べているように、「養育費の不払い」については、子の監護の規定を定めた『民法766条』の「1項」で対応できることから、日本政府が、この「離婚後の養育費の不払い」に対応するつもりであれば、世界で唯一の『協議離婚制度(民法763条)』の廃止にとりかかります。
世界で唯一の『協議離婚制度(民法763条)』を廃止することで、すべての離婚事件は、家庭裁判所を介することになり、結果、夫婦関係調整(離婚)調停での『調停調書』や離婚訴訟の『判決(判決文)』の作成に伴い、「債務名義に、養育費について定めた条項が記載される」ことになれば、この令和2年(2020年)4月1日に施行した『改正民事執行法』が有効に機能するようになります。
いい改正ですが、使えない改正にしたのは、いうまでもなく日本政府です。
しかも、「3-(4)「共同親権法案」の懸案事項-ⅰ)離婚した父母の合意」の「「共同親権法案」の成立・施行で、増加が予想される係争事件。逆に裁判所職員を削減」で示しているように、日本政府は、令和5年(2023年)2月7日、「判事補に因数を減少するとともに、裁判所の事務を合理化し、効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少させる」とした『(裁判所職員定員法の一部を改正する法律案』を国会に提出し、同年4月7日に成立(同14日施行)しています。
このことからも、令和6年(2024年)、「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」を本国会に提出する根拠とした「離婚後の養育費の不払い問題」に対応する意思はない、つまり、眼中になかったことは明らかでした。
・母子家庭の養育費と面会交流のとり決めの現状
「1-(3)単独親権(民法819条)と養育費の不払い」の中でとりあげた「厚生労働省が実施した『養育費、面会交流の取り決め状況等(平成28年度全国ひとり親世帯等調査)』」では、母子家庭の養育費のとり決めをしない理由は、「相手とかかわりたくない」が31.4%、「相手に支払う能力がないと思った」が20.8%、「相手に支払う意思がないと思った」が17.8%、「とり決めの交渉が煩わしい」が5.4%、「とり決めの交渉をしたが、まとまらなかった」が5.4%、「相手から身体的・精神的暴力を受けた」が4.8%などとなっています。
また、母子家庭の母で、「面会交流のとり決めをしている」のは24.1%、「面会交流のとり決めをしていない」のは70.3%で、「面会交流のとり決めを文書にしている」のは90.8%で、これは、判決離婚、審判離婚、調停離婚など家庭裁判所におけるとり決め、「強制執行認諾条項付きの公正証書」が96.6%で、その他の文書は0.2%となっています。
つまり、「面会交流のとり決めを文書にしている」のは、判決離婚、審判離婚、調停離婚など家庭裁判所を介した「離婚」で、離婚の87.8%を占める「協議離婚」では、ほとんどが「面会交流のとり決めを文書にしていない」ことになります。
つまり、日本の「養育費の不払い」、「面会交流の未実施」の背景にあるのは、離婚時にとり決めを文書(公正証書(強制執行認諾条項付きの公正証書))にしていないことです。
その要因は、「律令制(男子専権離婚)」、儒教思想にもとづく「家制度(家父長制)」の流れを汲む世界唯一の特殊な『協議離婚制度(民法763条)』にあります。
母子家庭の母が、「面会交流のとり決めをしていない理由」は、「相手とかかわりたくない」が25.0%、「とり決めをしなくても交流できる」が18.9%、「相手が面会交流を希望しない」が13.6%、「子どもが会いたがらない」が7.3%、「相手が養育費を支払わない、または、支払えない」が6.3%、「とり決めの交渉が煩わしい」が5.9%、面会交流をすることが子どものためにならないと思う」が6.3%、「相手から身体的・精神的暴力を受けた」が3.1%などとなっています。
DV事案の有無は関係なく、養育費、面会交流ともに「とり決めをしていない理由」の1位は、「相手とかかわりたくない(25.0%)」です。
つまり、離婚事由はさまざまですが、離婚に至るプロセスで、離婚後には「相手とかかわりたくない」という状況が生まれています。
日本の「離婚」の87.8%を占める『協議離婚』で、この「とり決めを文書化していない」「相手とかかわりたくない」といういまの状況は、仮に、「離婚後の共同親権制度」が導入されたときには、DV事案の有無は関係なく、父母の話し合い、合意に至ることは容易でないことを示唆しています。
2.第1の「法案」 『家族法(民法)』の改正(離婚後の共同親権制度)
第1の「法案」は、いま開催されている令和6年(2024年)の本国会に提出されたもので、『家族法(民法)』を改正し、導入を目指す「離婚後の共同親権制度」です。
この「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が成立・施行すると、身(命)が危険にさらされるリスクの高い人たちがいます。
それは、DV被害者が、女性センター(婦人相談所、男女共同参画センター)、所轄警察署にDV被害を訴え、同機関が、『配偶者からの暴力の防止及び被害者等の保護に関する法律(以下、配偶者暴力防止法)』に準じ「一時保護」を決定し、DV被害者が子どもとともに「母子生活支援施設」に入居し、福祉行政の支援を受けて転宅(アパートの賃貸契約をし、転居する)するとき、同法の「住民基本台帳事務における支援措置(転居先の住所を閲覧できなくする手続き)」をし、その後、「離婚」を成立させ、「支援措置」の更新を繰り返し、身を隠して避難生活をしているDV被害者とその子どもです。
つまり、『配偶者暴力防止法』の適用を受けた、その後、「離婚」を成立させ、同時に、居所を隠し生活をしているDV被害者とその子どもです。
なぜなら、「共同親権法案」が成立・施行したとき、18歳未満であるとき、改めて、18歳未満の子どもの監護者である親とその子どもの監護者でないもう一方の親は、「単独親権」を継続するか、それとも「共同親権」に変更するかの判断が求められるからです。
そして、18歳未満の子どもの父母による話し合い(協議)で、合意が得られないとき、その判断は、家庭裁判所が下すことになります。
このとき、家庭裁判所は、「共同親権を認めると子どもに対する虐待行為、元配偶者に対するDV行為などが生じ、子の利益を害する」と認められるときには、父母の一方を親権者(単独親権)と定めなければならない」とあるので、「単独親権」を継続したいときには、“いま”も“これから”も「共同親権を認めると子どもに対する虐待行為、元配偶者に対するDV行為などが生じ、子の利益を害する可能性が高い」ことを示す必要があります。
これは、子どもに対する虐待行為、(元)配偶者に対するDV行為の有無は関係なく(離婚理由は関係なく)、「共同親権法案」が成立・施行する前に、子どものいる夫婦が「離婚」に至り、施行時に、その子どもが18歳未満であるとき、同様に、「単独親権」を継続するか、それとも「共同親権」に変更するかの判断が求められ、上記の理由がないときには、「共同親権」となることです。
そして、「共同親権法案」が成立・施行したあとの「離婚」はすべてこの適用になります。
(1) 「離婚後の共同親権制度の導入」を主導してきたのは
この「「離婚後の共同親権制度の導入」のための『家族法(民法)』の改正」を主導してきたのが、極右・超保守の超党派「共同養育支援議員連盟(前.親子断絶防止議員連盟)」、自由民主党の議員連盟「日本の尊厳と国益を護る会」、そして、「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)」、「桜の会」など、(元)配偶者が『配偶者暴力防止法』の適用を受け、子どもと面会交流ができないDV加害者グループであることを踏まえると、この「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」の背景にあるのは、『配偶者暴力防止法』の存在で、狙いは『同法』の無力化、機能不全に持っていくことです。
「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)」は、DV加害者である元配偶者たちが連携するようになり、『配偶者暴力防止法』が最初の改正で、その対象者に「子ども」を加えてから4年後、いまから15年8ヶ月前の平成20年(2008年)7月に設立されました(令和6年(2024年)4月15日現在)。
「桜の会」は、「子どもの連れ去り(実子誘拐)、虚偽DV、親子断絶を経験した」と訴えるDV加害者が集い、できた団体です。
DV被害を訴える一方の配偶者が、「離婚後の単独親権制度(民法819条)」のもとで、『配偶者暴力防止法』に準じ、「保護命令」の発令を受けたり、「一時保護」の決定を受け、子どもを連れて「母子生活支援施設」に入居したあとの転居先で、「住民基本台帳事務における支援措置(転居先の住所を閲覧できなくする)」を手続きしたりする、つまり、『配偶者暴力防止法』の適用を受けた「子連れ別居」で、居所が不明で、子どもに会えないことは、実質的な「家」の家父長を自認するDV加害者には、到底、許す(受け入れる)ことのできない重大な問題です。
『配偶者暴力防止法』の“適用”は、重大な問題と認識している人たち、つまり、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正(共同親権法案)」に示されているのは、「結婚して「家」に入り、子ども出産した女性は、子どもを連れて離婚し難くなる」ことです。
これは、実質的な「家制度(家父長制)」の再興を意味する「法案」です。
そして、再興した実質的な「家制度(家父長制)」のもとで運用したいのが、満州事変・太平洋戦争時の『戦時家庭教育指導要項』に通じる「第2の「法案」」、つまり、の子どもに愛国心を醸成するための『家庭教育支援法案』です。
『家庭教育支援法』は、満州事変・太平洋戦争時の『戦時家庭教育指導要項』に通じるものであることから、その目的は、「再軍備」で、そのために、「第3の「法案」の戦前の『国家総動員法』に匹敵する「緊急事態条項」を『日本国憲法』に創設するための『日本国憲法』の改正を目指しています。
これらは、まったく関係のない法律のように見えますが、実は、同じベクトル上にあり、密接につながっています。
以下、この視点で補足して説明します。
日本の『家族法(民法)』は、「律令制」、儒教思想にもとづく「家制度(家父長制)」の流れを汲んでいることから、女性蔑視・男尊女卑、女性の自己犠牲で成り立つ「内助の功」「良妻賢母」を踏まえた“家族像(観)”が示されています。
戦前の「家制度(家父長制)」では、女性は結婚し「家」に入り、産まれてきた子どもはその「家」に所属します。
その「家」は、「君が代(八紘一宇)」が示すように“ひとつ(一致団結)”です。
「君が代」の歌詞は、「君が代は 千代に八千代に さざれ石の巌と なりて こけのむすまで」で、現代和訳すると、「男性と女性がともに支えているこの世は 千年も 幾千年もの間 小さな砂がさざれ石のように やがて大きな盤石となって 苔が生じるほど長い間栄えていきますように」となり、この「君が代」は、太平洋戦争のスローガンとなった「八紘一宇(天下をひとつの家のようにすること、全世界をひとつの家にすること、つまり、「天皇総帝論」)」を示しています。
その「家」のもとで、「男性は、忠義を心に、主君と国のために身を捨てる」、「女性は家で、夫、家、家族のために自らを犠牲にする(内助の功、良妻賢母)」ことを理想的な“精神”としました。
この“精神”が、極右・超保守の考える「愛国心」です。
つまり、この“精神”と「愛国心」を「復古」させ、戦前の日本に戻すことが、極右・超保守の考える日本の国造りで、「再軍備」とその再軍備を支える「税制度」と「家制度(家父長制)」は、その“根幹”だと考えています。
ここに、「律令制」「家制度」を継承してきた「公家・武家」の教育、つまり、儒教思想を加えると、極右・超保守の考える理想的な家族像は、「女性の幸せは、結婚し「家」に入り、子どもを持ち、「家」の繁栄に尽くし、父母に孝行すること」であり、「子どもの幸せは、厳しい「懲戒(しつけ(教育)と称する体罰)」があっても、両親の下で育ち、両親を敬い、孝行する」こととなります。
この「家」における女性の役割は、「武家の女性」のように、自己犠牲なくして成り立たない「内助の功」「良妻賢母」に徹することです。
「内助の功」とは、「家庭において、夫の外での働きを支える妻の功績」のこと、つまり、「夫(男性)が働き、妻(女性)は家で家事をする」ということで、「良妻賢母」の「良妻とは、夫(男性)に従い、サポートを惜しまない貞淑な妻のこと」で、「賢母とは、子どもの教育やしつけをしっかりできる賢い母のこと」をいいます。
「愛国心」は、個々人の価値観の上位にあると考え、国のために命を捨ててもそのように務めるのが国民の義務となります。
この“精神”と考えを踏まえて、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正(共同親権法案)」はできています。
つまり、「共同親権法案」には、結婚し「家」に入り、出産した女性は、ⅰ)「家」の繁栄のために、「家」に所属する子どもを連れて「家」を離れることは許さない、ⅱ)「家」の繁栄のために、夫に従い、尽くし、子どもの教育やしつけをするのが女性(妻)の務め(役割)、離婚して「家」を離れ、その役割を放棄することは許さないとの考えのもとで、それを“実現”する仕組みが施されています。
日本の国造り、再軍備の根幹が、「家」のもとで、「男性は、忠義を心に、主君と国のために身を捨てる」、「女性は家で、夫、家、家族のために自らを犠牲にする(内助の功、良妻賢母)」ことを理想的な“精神”とし、この“精神”と「愛国心」を養うのが、国が定める教育を担うのが「家庭」と位置づけています。
このことを踏まえると、実質的な「家制度(家父長制)」の構築のための「共同親権法案」と「再軍備」は、同じ1本の線上にあり、同じベクトルを向いていることになります。
この視点に立つと、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」に、『子どもの人権条約』に定める「子どもの意思を尊重する(子の意思表明権)」との記述がなく、「同法案」が、「子どもの最善の利益が優先されない」リスクの高い内容になっていて、「同法案」の意図が、「離婚後、子どもの監護者でないもう一方の親が、“共同親権者”として、子どもに親権(権利)行使できるようにすること」にあることを理解できるのではないでしょうか?
つまり、この「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」は、「主体は親で、子どもは客体」と位置づけらえています。
これは、『子どもの人権利約』に反するもので、この「共同親権法案」のもとでは、 「子どもの最善の利益」は優先されません。
「親権」とは、「未成年の子どもを成人まで育てあげるために親が背負う一切の権利・義務」のことで、「親権を行う者は、子どもの利益のために子どの監護及び教育をする権利を有し、義務を負う(監護権)」と『民法820条』で規定されていますが、この問題は、この「権利を有する」と「義務を負う」のどちらにフォーカスして捉えるかの問題といえます。
日本では、令和4年(2022年)10月14日(同年12月16日に施行)に削除されるまでの126年間、5-6世代の育児において、「親権」の「子どもを懲戒する権利(懲戒権(民法822条))」を行使してきました。
子どものしつけ(教育)と称して、懲戒(体罰)を加えることは、「義務」ではなく、「権利」の行使です。
そのために、日本では、「親権」は子どもに対し行使する権利と認識している人が圧倒的に多いように感じます。
一方で、「共同監護(共同親権)」は、「子どもが主体(子どもの最善の利益)で、親は客体」という位置づけで捉えている『児童の権利に関する条約(以下、子どもの権利条約)』で定める「子どもの権利(4原則)」は、「親の子どもに親権を行使する権利」ではなく、「親権は子どもに与える親の義務」という位置づけです。
日本は、「国内法」よりも上位に位置づけられる『子どもの権利条約』、『女性差別撤廃条約』を批准・締結しているので、前者の立ち位置(解釈)ではなく、後者の立ち位置(解釈)にもとづく法の制定、法の改正でなければならないことから、この「共同親権法案」は、『子どもの権利条約』に違反しています。
そして、日本国内で制定される法、改正される法は、日本が批准・締結した『人権条約』の“規定”がすべての判断基準(モノサシ)となる、つまり、『世界人権宣言』『人権条約』の“規定”にもとづいて、適切か、不適切かを見極める視点が必要となります。
・「親子断絶防止議員連盟」の議員連盟案『共同養育支援法』
「「離婚後の共同親権制度の導入」のための『家族法(民法)』の改正」を主導している極右・超保守の超党派「親子断絶防止議員連盟(現.共同養育支援議員連盟)」の考え・目論見を知るうえで重要なのが、平成28年(2016年)12月13日の「親子断絶防止議員連盟」の総会で承認された議員連盟案『共同養育支援法(父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する法律案)』です。
この『共同養育支援法(案)』の目的を1条で、「父母の離婚等の後においても子が父又は母との面会及びその他の交流を通じて父母と親子としての継続的な関係を持つことができるよう、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等に関し、基本理念及びその実現を図るために必要な事項を定めること等により、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進を図り、もって子の利益に資すること」と示しています。
この動きに合わせるように増加したのが、家庭裁判所に申立てた「子の引き渡しを求める調停・審判」です。
最高裁判所の調べでは、「子の引き渡しを求める調停と審判」の申立件数は、令和4年(2022年)が3,592件で、これは、10年前の平成22年(2010年)の2,710件の約3割増加し、調停で合意できず審判に至ったケースでは約4割増加しています。
ここには、審判の平均期間が、平成22年(2010年)に6.3ヶ月だったのが、令和4年(2022年)になると9.1ヶ月と長くなっていることにも示されています。
これらの「子の引き渡しを求める調停と審判」において、その多くは、この引き渡しを求められた配偶者(元)が、子どもの引き渡しはできず、同時に、面会交流の実施は困難とする“根拠”として、配偶者との間には、DV行為があり、子どもに対する虐待行為(夫婦間にDV行為がある(面前DV)ことは、子どもに対する心理的虐待に該当する)の事実を示し、認定され、この引き渡しが認められないケースとなっています。
この状況に納得できない、許せないのが、「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)」、「桜の会」であり、「共同養育支援議員連盟(前.親子断絶防止議員連盟)」です。
後者の代表は柴山昌彦元文部科学大臣です。
1年延期された東京オリンピックの開催直前、令和3年(2021年)7月、フランス人の夫が「子どもを妻に連れ去られ、子と断絶させられた」と訴えハンガーストライキを行い、日本外国特派員協会で会見したり、動画投稿サイトを使ったりした「子どもの連れ去り事案」に飛びつき、「日本に共同親権制度の導入を!キャンペーン」として利用したのが、この「親子ネット」と「共同養育支援議員連盟(前.親子断絶防止議員連盟)」です。
この事案は、この5年前、離婚を求める夫と距離をとるために、都内の自宅をでて子連れで別居したことに起因し、「(夫妻の子が)自宅のガレージから車のトランクに入れられている」とする動画を公開し、「母親が子どもを誘拐した」と訴えたものです。
しかし、この動画は、女性(子どもの母親)が家をでた日とは別の日に撮影されたもので、汚れたチャイルドシートを自宅ガレージに戻って交換していた様子を、このフランス人の夫が隠し撮りしたものでした。
つまり、このフランス人の夫の訴えは虚偽でした。
このフランス人の夫は、妻が子どもを連れ別居を開始してからの5年間、家庭裁判所に「面会交流調停」の申立てをすることなく、虚偽の動画を根拠にハンガーストライキに至ったわけです。
その後の離婚訴訟で、家庭裁判所は、夫が「妻に連れ去られた」と訴えた2人の子どもの親権は、2人の子どもと同居する妻とするとの従来通りの判決を下しています。
このフランス人が訴えた「子どもとの面会交流」、そして、『共同養育支援法(案)』の1条で示されている「子どもとの面会交流のあり方」については、「4-(1)離婚後の子の監護(民法766条)。面会交流と『人権条約』」で示しているように、平成25年(2013年)5月22日、日本政府が、『ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)』の批准・締結するにあたり、共同親権制度の他国と単独親権制度の日本との国際結婚における離婚問題(特に、子どもの監護について)に対応するために、その2年前の平成23年(2011年)6月3日、「民法等の一部を改正する法律」を成立し、改正した『民法766条(離婚後の子の監護)』で対応が可能です。
・柴山昌彦元文部科学大臣の「本当に耐えられないDVか発言」の背景にある「懲戒」認識
極右・超保守の超党派「共同養育支援議員連盟(前.親子断絶防止議員連盟)」代表の柴山昌彦元文部科学大臣が、令和5年(2023年)1月、北日本放送の番組で、「被害者とされる方々の一方的な意見により、子どもの連れ去りが実行されてしまうことが本当に問題ないのかどうか。公正な中立な観点から、DVの有無とか、本当に耐えられるものか耐えられないものであるかということを判断する仕組みの一刻も早い確立が必要だ」と発言したことに対し、「第1の「法案」『家族法(民法)』の改正(離婚後の共同親権制度)」の「懸案事項のⅱ)」では、『この柴山昌彦元文部科学大臣の「被害者とされる方々の一方的な意見により、子どもの連れ去りが実行されてしまうことが本当に問題ないのかどうか」は、『配偶者暴力防止法』の“適用”に対する疑問視(非難)であり、「DVの有無とか、本当に耐えられるものか耐えられないものであるか」は、実質的な「家」の「家父長(権威者)」である夫の妻に対する「懲戒」は正しい行為であるとの認識にもとづいています。』と記述しています。
「軍国化(国民皆兵、富国強兵)」に不可欠な“税制改革”を進めるうえで設けられた「家制度(家父長制)」のもとで、「子どもを懲戒する権利(民法822条)」は、都合よく拡大解釈されるようになり、「家」の家父長(権威者)は、子どもだけではなく、配偶者に対し懲戒を加えるようになっていきました。
ナショナリストで、極右・超保守であり、復古主義にもとづくと、戦前の「家」の家父長(権威者)を“前提”とする認識となることから、平成13年(2001年)に制定された『配偶者暴力防止法』でいうDV(ドメスティック・バイオレンス)は存在せず、すべて、配偶者に対する懲戒に過ぎないと認識しています。
したがって、この発言の後段「DVの有無とか、本当に耐えられるものか耐えられないものであるか」というDV行為に対する疑問視(非難)は、「耐えられるDV」「耐えられるDVはない」というキーワードで、SNSで大きな議論を巻き起こしましたが、この発言の背景にあるのは、ナショナリストで、極右・超保守であり、復古主義者に共通認識である実質的な「家」の「家父長(権威者)」である夫の妻に対する「懲戒」という認識です。
DV加害者の一定数が、交際相手や配偶者に自身の行為を暴力、DVと指摘したとき、そのことばに過剰反応を示し、「暴力じゃない」「DVじゃない」と否定し、自己弁護に走る背景には、この「懲戒」との認識が存在しています。
・ナショナリストで、極右・超保守な人に極めて邪魔な『配偶者暴力防止法』
先の疑問視(非難)している『配偶者暴力防止法』の“適用”、つまり、「離婚後の共同親権制度の導入」を主導してきた極右・超保守の超党派「共同養育支援議員連盟(前.親子断絶防止議員連盟)」、自由民主党の議員連盟「日本の尊厳と国益を護る会」、そして、「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)」の訴える『子どもの連れ去り』は、DV被害者が、「離婚後の単独親権制度(民法819条)」のもとで、女性センター(婦人相談所)・警察署に相談することで、「一時保護」が決定され、子どもとともに「母子生活支援施設」に入居し、福祉行政の支援を受けて転宅(アパートの賃貸契約をし、転居する)、そのとき、同法の「住民基本台帳事務における支援措置(転居先の住所を閲覧できなくする手続き)」をすることを指しています。
それは、『配偶者暴力防止法』の適用により、(元)妻(子どもの母親)と子どもの居所がわからず、連絡もできず、子どもと会うことができない(子どもと面会交流できない)という状況が生まれ、同時に、「離婚後の単独親権制度(民法819条)」のもとで、子どもの「親権者」「監護者」は、圧倒的に、その子どもを連れ去った一方の配偶者に決定される状況を認めるわけにはいかないとの認識です。
この認識は、令和5年(2023年)の本国会に提出した『請願書(別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する請願)』と、令和6年(2024年)の本国会で成立を目指す「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」の「主体は親で、子どもは客体」という位置づけに明確に示されています。
しかも、「共同養育支援議員連盟(前.親子断絶防止議員連盟)」、「日本の尊厳と国益を護る会」、「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)」、「桜の会」の訴える『子どもの連れ去り』と『子どもに会えない(面会交流できない)』との訴え(主張)には、決定的な根拠(裏づけ)が欠けています。
彼らが主張するⅰ)「子どもの連れ去り」は、「離婚後の単独親権」「離婚後の共同親権」の問題ではなく、「3-(7)-⑥DV加害者の主張と「子どもの連れ去り」の2パターン」で示しているように、「児童誘拐事件(未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条))」であり、ⅱ)「子どもに会えない(面会交流できない)」は、『民法766条(離婚後の子どもの監護)』で解決でき、「離婚後の単独親権」「離婚後の共同親権」の問題ではありません。
ⅰ)の「一方の(元)配偶者に子どもを連れされた」が、上記の『配偶者暴力防止法』の“適用”によるものでなければ、「未成年者の子どもの連れ去り」は、いうまでもなく「児童誘拐事件(未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条))」となります。
つまり、「一方の(元)配偶者に子どもを連れされた(元)配偶者」は、通常、所轄警察署に直ちに通報したり、証拠とともに「告訴状」を提出したりすると考えられます。
したがって、「一方の(元)配偶者に子どもを連れされた」けれども、「いま、(元)配偶者のもとに、連れ去られた子どもが戻ってきていない」という事実は、a)所轄警察署に「児童誘拐事件」を通報したり、被害を訴えたりしたが、その時点で、刑事事件として扱えないとの説明を受け、刑事事件とならなかったか、b)「告訴状」が受理され、捜査はされたが、「児童誘拐に該当しない」と判断されたか、c)そもそも所轄警察署に通報したり、被害を訴えたりしていないかのいずれかということになります。
ⅰ)-a)b)については、その事実に対し納得できていないときには、自身こそが被害者認識が強くなり、自分の訴え(主張)が認められなかった悔しさ、怒りの感情が加わり、そこに、被害を訴えるモチベーション(動機づけ)となっていると考えられます。
つまり、「一方の配偶者に、子どもを連れ去られた」と訴えて(主張して)いますが、「児童誘拐事件(未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条))」ではないことになります。
次に、ⅱ)では、「子どもを連れ去った」一方の配偶者、「子どもとの面会交流を許さない」一方の配偶者との関係性を考える必要があります。
民事事件として、家庭裁判所での「夫婦関係調整(離婚)調停」で、a)離婚が成立しているか、b)調停中か、あるいか、まだ、c)家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)調停」を申立てていないかで、配偶者か、元配偶者かにわかれます(「離婚調停」は、調停委員を介し合意を目指すので、司法判断とは異なり、「離婚調停」で合意に至らないときには不調となり、その後の審判・裁判で司法判断を求めることになります)。
ⅱ)-b)c)の状況のとき、d)家庭裁判所に「監護者指定調停・審判」、e)「面交流調停」を申立てることが多くなります。
したがって、「一方の(元)配偶者が子どもを連れ去った」、「子どもと会えない(子どもとの面会交流ができない)」と訴える(元)配偶者の状況は、ⅱ)-a)の「離婚」が成立したときに、「親権者」は一方の配偶者に、「子どもとの面会交流は実施できない」との合意されている(あるいは、司法判断が下されている)中での訴え(主張)となり、ⅱ)-b)c)とⅱ)-d)で、まだ、判断が示されていないときには、「監護者」は決まっていない中での主張となり(ⅱ)-ア))、ⅱ)-d)で、「監護者」は一方の配偶者にとの判断が示されたときには、自身が「監護者」でない中での訴え(主張)となります(ⅱ)-イ))。
そして、ⅱ)-ウ)として、ⅱ)-ア)の状況で、ⅱ)-e)の判断が示されていない中での訴え(主張)と、ⅱ)-エ)として、ⅱ)-イ)の自身が「監護者」でなく、ⅱ)-e)の判断が示されていない中での訴え(主張)と、ⅱ)-オ)として、ⅱ)-イ)の自身が「監護者」でなく、ⅱ)-e)で、「面会交流の実施はできない」と判断を示された中での訴え(主張)となります。
つまり、①ⅰ)-ア)イ)ウ)エ)の状況で、「一方の(元)配偶者が子どもを連れ去った」、「子どもと会えない(子どもとの面会交流ができない)」と訴える(元)配偶者は、既に、「夫婦関係調整(離婚)調停」、「監護者指定調停・審判」、「面会交流調停」おいて、まだ、自身が「監護者」の指定を受けられるのか判明していない、しかも、「子どもとの面会交流」が認められるのかが判明していない中での訴え(主張)となります。
②ⅱ)-a)、ⅱ)-オ)の状況で、「一方の(元)配偶者が子どもを連れ去った」、「子どもと会えない(子どもとの面会交流ができない)」と訴える(元)配偶者は、既に、「夫婦関係調整(離婚)調停」、「監護者指定調停・審判」、「面会交流調停」おいて、自身が、「親権」「監護権」を得られない理由、「面会交流の実施」できない理由を示されていることになります。
ⅰ)-a)b)の状況と同様に、その事実に対し納得できていないときには、自身こそが被害者認識が強くなり、そこに、自分の訴え(主張)が認められなかった悔しさ、怒りの感情が加わり、被害を訴えるモチベーション(動機づけ)となっていると考えられます。
したがって、「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)」、「桜の会」で、「一方の(元)配偶者が子どもを連れ去った」、「子どもと会えない(子どもとの面会交流ができない)」と訴える人のほとんどは、ⅰ)-a)b)、ⅱ)-a)、ⅱ)-オ)の状況であると類推できます。
つまり、「一方の配偶者による子どもの連れ去り」は、「児童誘拐事件(未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条))」ではなく、「夫婦関係調整(離婚)調停」「監護者指定調停・審判」で、「親権者」「監護者」の指定を受けられず、そして、「夫婦関係調整(離婚)調停」「面会交流調停」で、「子どもとの面会交流を実施が許されない理由」を示されている状況下で、「一方の(元)配偶者が子どもを連れ去った」、「子どもと会えない(子どもとの面会交流ができない)」と訴えて(主張して)いる人ということになります。
こうした背景の人たちの訴え(主張)をもとに、「子どもの連れ去り禁止」を求める『請願書(別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する請願)』を作成し、令和5年(2023念)の本国会に提出することは、異常といえます。
それほど、彼らは、『配偶者暴力防止法』の存在が邪魔ということです。
つまり、「離婚後の共同親権制度の導入」の目的は、監護者でない一方の親の子どもに対する権利を行使するために、『配偶者暴力防止法』を“無力化”し、“機能不全”に陥らせることです。
それは、『請願書(別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する請願)』、そして、柴山昌彦元文部科学大臣の発言にその意図(目論見)が明確に示され、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」では、「単独」で行使できる「急迫の事情」を定めていますが、この「急迫の事情」に、『配偶者暴力防止法』の適用(一時保護)を該当すると明確にしないことで具現化しました。
いうまでもなく、『配偶者暴力防止法』に準じた「一時保護」を「急迫の事情」と認めると、「離婚後の共同親権制度の導入」の本来の目的を達成できなくなります。
ナショナリストで、極右・超保守で、復古主義者が目指している世界観は、DVは存在せず、「家」の家父長による「懲戒」であり、その「懲戒」は正しいと行為であるとの考えが常識になること、そうなると、邪魔な『配偶者暴力防止法』は必要なくなり、その世界観のもとで、国家として戦前のように強力な軍事力を支える子どもの教育を進めることができる(満州事変・太平洋戦争中の『戦時家庭教育指導要項』に通じる「家庭教育支援法案」)というものです。
(2)「家制度」を継承。「単独親権(民法819条)」は核家族化で変化
① 新しい構図のもとで新たな「単独親権制度」がはじまるまでの経緯
太平洋戦争敗戦後、日本政府が、明治民法で制定した「律令制」に由来し、儒教思想にもとづく「家制度(家父長制)」の流れを汲む『夫婦同姓制度(民法750条、戸籍法74条1号)』と『協議離婚制度(民法763条)』ともに『離婚後の単独親権制度(民法819条)』を継承したのは、実質的な「家制度(家父長制)」を継承するためです。
日本政府は、太平洋戦争敗戦後、昭和22年(1947年)、『日本国憲法』の24条(法の下の平等など)に反するとして廃止した「家制度(家父長制)」を廃止しましたが、日本で生活する市民の価値観に「家制度(家父長制)」が残り続けただけではなく、もともとは、上記のように『家族法(民法)』に「律令制」「家制度(家父長制)」は継承され、また、その「家制度(家父長制)」なく成り立たなかった「軍国化(国民皆兵、富国強兵)」に不可欠だった「税制度」もそのまま継承しました。
いま(戦後)の日本の「税制度」「社会保障制度(年金制度を含む)」が「家」を基軸に制度設計されているのは、「家制度(家父長制)」の継承を意味します。
つまり、日本政府は、『日本国憲法』の24条(法の下の平等など)に反するとして「家制度(家父長制)」を廃止する一方で、『家族法(民法)』、「税制度」「社会保障制度(年金制度を含む)」などの社会システムそのものは、実質的な「家制度(家父長制)」で構築されています。
この実質的な「家制度(家父長制)」で構築されている社会システムの中で、「家制度(家父長制)」を継承した『単独親権制度』を、「家」の実質的な家父長(権威者)を自認する人たちは、『家族法(民法819条)』を改正して、離婚した父母の「単独親権」から「共同親権」に変更する必要があるのでしょうか?
その理解のためには、太平洋戦争敗戦後の日本の社会構造が変化したことが、実質的な「家制度(家父長制)」から離れる要因になり、逆に、実質的な「家制度(家父長制)」をとり戻すために、離婚した父母の「共同親権」が必要になったからです。
以下、その経緯を説明します。
「軍国化(国民皆兵、富国強兵)」を支えた「家制度(家父長制)」は、「家」のもとで、「男性は、忠義を心に、主君と国のために身を捨てる」、「女性は家で、夫、家、家族のために自らを犠牲にする(内助の功、良妻賢母)」ことを理想的な“精神(愛国心)”のもとに、「家」はひとつ、一致団結する象徴でした。
ここに、「律令制」「家制度」を継承してきた「公家・武家」の教育、つまり、儒教思想を加えると、理想的な家族像は、「女性の幸せは、結婚し「家」に入り、子どもを持ち、「家」の繁栄に尽くし、父母に孝行すること」であり、「子どもの幸せは、厳しい「懲戒(しつけ(教育)と称する体罰)」があっても、両親の下で育ち、両親を敬い、孝行する」こととなります。
「家制度(家父長制)」のもとでは、女性は結婚すると妻・嫁として「家」に入り、生まれた子どもは「家」に所属します。
その「家」に入り、子どもを出産した女性が離婚し、「家」を離れる(「家」の所属者でなくなる)とき、「家」に所属する子どもは、母親とともに「家」を離れることはできません。
つまり、女性(母親)だけが「家」は離れ、主に、「実家」に戻ります。
この状況は、いまでも「出戻り」と表現され、女性にのみ使われ、男性には使われません。
この“構図”のもと、つまり、実質的な「家制度(家父長制)」のもとで“適していた”のは、『離婚後の共同親権制度』ではなく、『離婚後の単独親権制度』です。
そのため、「家制度(家父長制)」は、『日本国憲法』の24条(法の下の平等など)に反するとして廃止されましたが、日本政府は、「家制度(家父長制)」に通じる『離婚後の単独親権制度(民法819条)』を継承しました。
このとき、『離婚後の共同親権制度』への変更が議論されていますが、「日本は、共同親権は馴染まない」との判断で、『離婚後の共同親権制度』を継承しています。
ところが、“朝鮮戦争(昭和25年-同28年(1950年-1953年))”による特需により経済の立て直しに成功、“高度経済成長(実質経済成長率が年平均で10%前後を記録した昭和30年-同48年(1955年-1973年)ころまで)”に伴い、日本社会は、「工業化」「都市化」「核家族化」が急速に進みました。
「工業化」とは、国の産業構造として、農業などの第1次産業から、第二次産業、特に工業の占める割合が高まることで、「都市化」とは、都市に人口が集中することに伴い、都市近郊の農村地帯に住宅・工業用地が拡張され、その付近の土地利用や生活様式が、徐々に都市同様に変わっていくことです。
「都市化」により、工場が増加し、生産活動がさかんになる一方で、産業公害がもたらされました。
近郊住民が健康被害を受けたり、農村から都市への通勤者が増加したりする一方で、人口増加に伴うアパート経営を営むなど、農家の兼業化が進みました。
「核家族」とは、1950年代、アメリカ合衆国の文化人類学者G.P.マードックが命名したもので、「親と未婚の子ども」の家族形態をいい、ここには、「夫婦のみの家族やひとり親世帯」も含まれます。
日本社会で圧倒的多数を占める「家」の世帯主、扶養者であり、長時間労働勤務の男性(父親)は、都市化、核家族化が進む社会で、ひとり親(シングルファーザー)の親権者として子どもをひき取り、子育てを担うのは実質的に困難です。
そのため、女性(母親)が、ひとり親(シングルマザー)の親権者となり、子どもをひき取る構図が生まれ、そして、その割合は増加し続けました。
「厚生労働省の人口動態統計」によると、令和4年(2022年)の離婚数は17万9099組で、未成年の子どもがいる夫婦の離婚は9万4565組(52.80%)です。
その8割以上で、母親が子どもの親権者となり、子どもの育児にあたっています。
つまり、子どものいる夫婦が離婚したとき、実質的な「家」の家父長(世帯主)が子どもの親権者となり、「家」で父母(子どもの祖父母)・親族などの協力を得て、子どもの育児にあたることができていましたが、「工業化」「都市化」「核家族化」が急速に進み、日本の産業構造・就業構造が大きく変わる中で、「家」で父母(子どもの祖父母)・親族などの協力を得て、子どもの育児にあたることができなくなり、結果、子どもの母親が子どもとともに「家」を離れ、その母親が子どもの親権者となり、子どもの育児にあたるようになりました。
したがって、日本では、日本の社会構造が変わるとともに、「家」のあり方も変わるという“新しい構図”のもとで、新たな「離婚後の単独親権制度」がはじまったことになります。
② 核家族化のもとでの新たな「単独親権制度」。父母の立ち位置
この“新しい構図”のもとで、新たな「離婚後の単独親権制度」のもとでの「離婚」は、「1-(3)単独親権(民法819条)と養育費の不払い」で述べる「離婚後、子どもの監護者(親権者)に対する一方の親による養育費の不払い」の問題を除き、表立っては、大きな問題になりませんでした。
なぜなら、「1-(2)協議離婚制度(民法763条)と離婚事由(民法770条)の規定」で示した日本の「離婚」の87.8%を占めるのが『協議離婚(民法763条)』だからです。
つまり、母親が子どもの「親権者(監護者)」として、子どもを連れて「家」をでることは2面性があり、ひとつは、子どもと離れたくない母親の意思が尊重されたケースと、もうひとつは、表面的には、夫婦間の“合意”に見えていても、実質的な「家」の家父長(世帯主)の意思として、「子どもはおいていけ!」というのか、それとも、「子どもはお前が育てろ!」というのかで決まっていたケースがあります。
後者は、婚姻時の「家」の中での上下関係、支配と従属関係にもとづく合意を強いられていたものです。
また、「1-(2)-①新しい構図のもとで新たな「単独親権制度」がはじまるまでの経緯」で、『 「家制度(家父長制)」のもとでは、女性は結婚すると妻・嫁として「家」に入り、生まれた子どもは「家」に所属します。その「家」に入り、子どもを出産した女性が離婚し、「家」を離れる(「家」の所属者でなくなる)とき、「家」に所属する子どもは、母親とともに「家」を離れることはできません。つまり、女性(母親)だけが「家」は離れ、主に、「実家」に戻ります。 』と記述しているように、「家制度(家父長制)」のもとでは、子どもは「家」に所属するので、子どもの養育にかかわる費用は、所属する「家」が負担します。
子どもの監護者でないもう一方の親の「養育費の不払い」の背景にあるのが、この「家制度(家父長制)」のもとでの、「離婚後、子どもとともに「家」を離れた子どもに対する養育にかかわる費用は、負担しなくてもいい」との解釈です。
離婚後、子どもの監護者(親権者)に対する一方の親による「養育費の支払い」の根拠は、『民法877条1項』の「扶養義務」で、その「養育費」は、『民法766条1項』の「子の監護に要する費用」に該当し、「子を監護していない親から、子を監護している親に対して支払われる未成熟の子の養育に要する費用である」と規定されています。
つまり、離婚後の子どもの監護を定める『民法766条』にもとづくと、離婚後の共同監護は可能で、「親権」の有無は関係なく、子どもの扶養義務として、「養育費の支払い」は生じます。
『ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)』の批准・締結に備え、その2年前の平成23年(2011年)6月3日に法改正された『民法766条』にもとづき、平成24年(2012年)4月1日以降、『協議離婚制度(民法763条)』による「離婚」では、『民法766条1項』の施行に伴い、「離婚届用紙」には、「養育費の分担」「面会交流取り決め」の有無についてチェックする欄が設けられています。
開始は、いまから12年前のことですが、「未記入」でも離婚届は受理されます(令和6年(2024年)4月15日現在)。
ところが、子どもの監護者でないもう一方の親の中には、親の義務としての「養育費の支払い」は果たさず、「養育費」は、離婚後の子どもの監護(民法766条)としての「面会交流を実施したら支払う」と“条件(脅迫要件)”とする人もいます。
この“条件(脅迫要件)”を突きつけるなど、自分にとって都合のいい解釈をし、その解釈を強引に押しつける人たちが、令和6年(2024年)の本国会に提出した「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」の成立・施行を望んでいます。
この婚姻時の「家」の中での上下関係、支配と従属関係にもとづく合意、つまり、意思決定が成り立つ原因は、「2-(1)-①離婚方法と離婚事由」で示しているように、他国にはない特殊な『協議離婚(民法763条)』による「離婚」が、日本の離婚全体の87.8%を占めることです。
しかも、「2-(2)離婚後の親権の決定」で、『 離婚後の親権は、a)「父母の協議(協議離婚(民法763条))で、双方または一方を親権者と定める」と規定 』と示しているように、日本以外の他国とは異なり、家庭裁判所が介入することなく、離婚する父母の当事者だけ(「離婚」の87.8%を占める『協議離婚(民法763条)』)で、「単独親権」「共同親権」のどちらかを選択することになります。
つまり、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が成立・施行すると、“後者”の婚姻時の「家」の中での上下関係、支配と従属関係にもとづく合意を強いられるリスクが残る運用となります。
③ 新しい構図のもとでの新たな「単独親権」。都合が悪くなった人々
いまから19年10ヶ月前の平成16年(2004年)6月2日、「家」の中での上下関係、支配と従属関係による「家父長(世帯主/扶養者)」の“意思”で決まっていた『協議離婚制度(民法763条)』に大きな影響を及ぼす事態がおきました(令和6年(2024年)4月15日現在)。
そのできごとは、実質的な「家」の家父長(権威者)を自認し、妻や子どもに対する「懲戒(しつけ(教育)と称する体罰)」を家父長の権利として加えてきた人にとって、『離婚後の単独親権制度』は極めて不都合な制度となることを意味しました。
それは、いまから22年11ヶ月前の平成13年(2001年)4月6日に成立した『配偶者暴力防止法』の最初の「法改正」が平成16年(2004年)6月2日にあり、同法の適用者に「子ども」が加えられたことです(令和6年(2024年)4月15日現在)。
最初の『配偶者暴力防止法』で、適用者(対象者)に「子どもを外した」のは、極右・超保守勢力が激しく反対したからです。
しかし、平成13年(2001年)4月に『同法』が制定されてわずか2年4ヶ月後の同15年(2003年)8月、国連の「女性差別撤廃委員会」は、締結国である日本政府に対し、「ドメスティック・バイオレンスを含む女性に対する暴力の問題に対し、女性に対する人権の侵害としてとり組む努力を強化すること」、「『配偶者暴力防止法』を拡大し、様々な形態の暴力を含めること」との是正勧告を示しました。
「子どもを外した」ことに対し、制定前から「同法を無力化させるもの」と非難されていた日本政府は、この是正勧告により、法改正に応じざるを得なくなりました。
『同法』の最初の「法改正」で、この「子どもが加えられた」ことで、DV加害者である一方の配偶者には、極めて不都合な状況が生じることになりました。
それは、DV被害者が、女性センター(婦人相談所)・警察署にDV被害を訴え、『配偶者暴力防止法』に準じ「一時保護」が決定され、子どもとともに「母子生活支援施設」に入居し、福祉行政の支援を受けて転宅(アパートの賃貸契約をし、転居する)するとき、同法の「住民基本台帳事務における支援措置(転居先の住所を閲覧できなくする手続き)」をすることで、DV被害下にあった(主に)妻と子どもが、DV加害者である配偶者(主に夫)に、転居先・居所を知られず、安全な生活を送ることができるようになったことです。
また、『配偶者暴力防止法』に準じ、DV被害を訴える一方の配偶者が、地方裁判所に「保護命令」の発令(同法10条)を申立て、認められると、その旨が警察、配偶者暴力相談支援センター(女性センター/婦人相談所)に通知されます。
この「保護命令」の発令で、DV加害者である一方の配偶者が、ア)申立人(DV被害を訴え、保護命令を申立てた一方の配偶者)への接近禁止命令(1項1号)、イ)退去命令(2ヶ月間の退去、住居付近の徘徊近位)(1項2号)、ウ)申立人への電話禁止(2項)、エ)申立人の子への接近禁止命令(3項)、オ)申立人への親族等への接近禁止(4項)です。
つまり、DV加害者である一方の親は、『同法10条3項』により、子どもとの接近することが禁止されるので、子どもとの面会交流ができません。
ただし、「保護命令」の発令は、「一時保護(緊急避難)」するための準備期間と位置づけられています(アメリカのようにDV=犯罪と位置づけられていない日本では、DV被害者が逃げるしか解決策がないのが実情です)。
このことは、子どもを連れて家をでた一方の配偶者である妻と子どもの居所がわからず、妻(元)と「復縁」のための話し合いをしたり、子どもと会ったり(面会交流したり)することが困難となることを意味します。
なりより、子どもの監護者でない一方の親、つまり、(元)配偶者に子どもを連れて逃げられた(離婚された)DV加害者である親(実質的な「家」の家父長(権威者)を自認する親)が、子どもに「親権(権利)」を行使できない状況がつくられることを意味します。
つまり、実質的な「家」の家父長(権威者)を自認し、妻や子どもに対する「懲戒(しつけ(教育)と称する体罰)」を家父長の権利として加えてきた人が、『離婚後の単独親権制度』のもとで『配偶者暴力防止法』の適用を受け、子どもの親権者として、「親権(権利)」を行使できない状況は、到底、受け入れられない、許すことができないことになります。
この視点に立つと、子の監護の規定(共同監護)を定めた『民法766条』の運用など意味を持たず、ⅰ)邪魔な『離婚後の単独親権制度』を「共同親権」に変えること、ⅱ)『配偶者暴力防止法』の適用を無力化、機能不全に陥らせることが重要課題となりました。
この実現を目指してきたのが、いわゆる「共同親権推進派」の人たちです。
一方で、この最初の「法改正」は、『配偶者暴力防止法』の制定されてからの3年間、「子どもを家に残して、『配偶者暴力防止法』の適用を受けることはできないと躊躇していたDV被害者である配偶者」が、子どもとともに『配偶者暴力防止法』の適用を受け、DV行為のある家庭環境から逃れる決心と子どもと生きる覚悟の背中を押す役割を果たしました。
そして、この『配偶者暴力防止法』に準じ「一時保護」の決定を受け、「母子生活支援施設」に入居し、福祉行政の支援を受けて転宅(アパートの賃貸契約をし、転居する)するとき、同法の「住民基本台帳事務における支援措置(転居先の住所を閲覧できなくする手続き)」をすることで、DV被害者が、DV加害者であるもう一方の配偶者に、転居先・居所を知られず、安全な生活を送ることができるようになりました。
『配偶者暴力防止法』の適用を受け妻と子どもの行方が分からず、子どもに会えないDV加害者である一方の(元)配偶者は、この状況を「(元)妻が子どもを連れ去った」、「子どもの居所がわからず、子どもに会えない(面会交流できない)」と表現します。
つまり、彼らのいう「(元)妻が子どもを連れ去った」、「子どもの居所がわからず、子どもに会えない(面会交流できない)」は、『配偶者暴力防止法』の適用を受け緊急避難しているに過ぎません。
つまり、日本社会の変遷を踏まえて、直近の約20年間で、『離婚後の単独親権制度』が極めて不都合になったのは、DV被害を訴える一方の配偶者が、ア)『配偶者暴力防止法』に準じ「一時保護」が決定され、子どもとともに「母子生活支援施設」に入居し、転居先で「住民基本台帳事務における支援措置」の手続きをされたり、イ)『同法』に準じ「保護命令」が発令され、子どもと接近すること、面会交流が禁止されたりするのが許せない人たち、つまり、DV加害者である一方の配偶者、そして、ウ)「1-(3)単独親権(民法819条)と養育費の不払い」で述べている「離婚後、一方の親による養育費の不払いが続く監護者(親権者)」です。
ウ)は、「2-(2)-②核家族化のもとでの新たな「単独親権制度」。父母の立ち位置」で示しているとおり、子の監護の規定を定めた『民法766条』の「1項」で対応でき、加えて、世界で唯一の『協議離婚制度(民法763条)』を廃止し、すべての離婚事件に家庭裁判所を介することで、夫婦関係調整(離婚)調停での『調停調書』や離婚訴訟の『判決(判決文)』が作成されるときに、「債務名義に、養育費について定めた条項が記載される」ことになります。
これは、「1-(3)単独親権(民法819条)と養育費の不払い」の中で示しているように、令和2年(2020年)4月1日に施行した『改正民事執行法』が有効に機能するようになり、仮に、とり決められた養育費が滞ったとしても、強制執行として養育費を回収しやすくなります。
つまり、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」の成立・施行は、この問題の解決策にはならず、「現法」が有効に機能していない仕組み(法制度)に原因があります。
(3) 欧米諸国。フレンドリーペアレントを見直し、法改正の動き
問題は、「ナショナリズム」の民族主義と「超保守」の自国のことを極端に優れているとの認識が結びついた自分の人種が最上であると考え、他の人種を見下し、公平に扱おうとしない「レイシスト(人種差別主義者)」であり、性差別的で、女性に対する憎悪意識も高い権威者(ミソジニー)で、「復古主義」と結びついた人、つまり、実質的な「家」の家父長と自認し、女性を上下関係、支配と従属関係におこうとする人たちは、『世界人権宣言』『人権条約』、そして、人権・社会問題に先進的にとり組んでいる北欧諸国、欧米諸国の考え、制度には興味を示しません。
令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」にもその姿勢が顕著に示されています。
それは、「共同監護(共同親権)」のあり方を見直し、法改正の流れに至っている欧米諸国の現在のとり組みを無視していることです。
デンマークは、いまから26年前の1997年(平成9年)、『親の監護権/権限ならびに面接交渉権法改正法』の1条に、「子どもはケアおよび安全に対する権利を有する。子どもは、その人格を尊重して扱われ、かつ、体罰または他のいかなる侮辱的な扱いも受けない」と、監護権、面会交流で、「子どもはケアおよび安全に対する権利を有する」と明記しました(令和6年(2024年)4月15日現在)。
デンマークなどの北欧諸国とは異なり、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなどは、「フレンドリーペアレント(FP)」の考え方を導入していきました。
「フレンドリーペアレントルール」は、アメリカのカリフォルニア州などで採用された基準で、「子どもの親としての関係で、他方の親と友好的な関係を築くことができる方の親が親権者にふさわしい」と考える、例えば、他方の親と子どもの面会交流に許容的か、他方の親の悪口などを子どもにいっていないか、他方の親に寛容的かなどを考慮要素にして親権を判断することをいいます。
この「フレンドリーペアレントルール」にもとづくと、親権(監護権)獲得に不利になることを怖れ、(元)配偶者からのDV、子どもに対する虐待に対し、事実を訴えるのを躊躇せざるを得ない状況をもたらします。
別のいい方をすると、DV被害者を黙らせる、口を噤(つぐ)ませる役割を果たすのが、「フレンドリーペアレントルール」です。
この状況を危惧した国連の「女性差別撤廃委員会」は、国連で採択した『児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)』の19条にもとづき、「面会交流のスケジュールを決定するときには、家庭内暴力や虐待の履歴があれば、それが女性や子どもを危険にさらさないように考慮しなければならない。」との是正勧告をだしました。
日本に対する是正勧告は、平成26年(2014年)です。
その『子どもの権利条約』の19条では、「子どもが両親のもとにいる間、性的虐待を含むあらゆる形態の身体的、または、精神的暴力、傷害、虐待、または、虐待から保護されるべきである」と定め、「それが起こるとき、親権や監護権、面会交流の決定において、親密なパートナーからの暴力や子どもに対する暴力に対処しないことは、女性とその子どもに対する暴力の一形態であり、拷問に相当し得る生命と安全に対する人権侵害である」、「子どもの最善の利益という法的基準にも違反する」と規定しています。
国連の「子ども権利委員会」は、この規定に準じ、とり組みが進んでいない国(政府)に対し速やかな是正に向けた勧告しています。
そして、「フレンドリーペアレント(FP)」の考え方を導入してきたアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなどは、近年、一方の配偶者に対するDV行為、子どもに対する虐待行為の履歴のあるとき、「共同監護(養育)」ではなく、「子どもとその子どもと同居する親(監護者)の安全確保を最優先」する方向に転換し、「法制度」を見直しています。
オーストラリアでは、離婚後の交流に肯定的な親が子どもの養育を担うのに相応しいと考え、制定した「フレンドリーペアレント(FP)条項」を開始後5年、2011年(平成23年)に廃止し、「離婚後の父母と子どもとの交流の継続よりも、子どもの安全を優先」する法改正に至っています。
アメリカでは、2017年(平成29年)、子どもとの面会交流や監護を検討するとき、子どもの安全を最優先する必要があり、家族間暴力(DVと児童虐待)が訴えられているときの裁判所審理の改善を求める勧告を下院が決議し、イギリスでは、2020年(令和2年)、司法省の専門委員会が「DVの可能性のある親と子どもの交流の危険性」を指摘し、「離婚後も父母が子とのかかわりを継続することが、この健全な成長につながるという推定規定の見直し」を勧告しています。
また、カナダでは、2021年(令和3年)、『離婚法』を改正し、「フレンドリーペアレント(FP)」の考え方にもとづく規定を見直し、子どもの安全と健全な生育が確保できることを条件に、父母と子どもの関係の継続について考慮するという考え方に変更しました。
「離婚後の共同親権制度の導入」を主導してきた極右・超保守の超党派「共同養育支援議員連盟(前.親子断絶防止議員連盟)」は、令和5年(2023年)の本国会に提出した『請願書(別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する請願)』では、主に、ア)監護者でない一方の親と2週間に1度は泊りがけで会えるようにすること(親子交流の権利性を明確化)、イ)年間、100日以上は会えるようにすること(面会交流の拡充)、ウ)主たる養育親の決定は、フレンドリーペアレント(他方の親により多くの頻度で子どもを会わせる親)ルールによることを求めています。
つまり、欧米諸国で見直し、法改正を進めている中で、「フレンドリーペアレントルール(友好親原則)の導入」を求めています。
この政治姿勢が示しているのは、「親権」の主体は親で、子どもは客体であるという考えで、「子どもの利益を最優先する」という視点が欠落していることです。
そして、この『請願書(別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する請願)』は、上記『子どもの権利条約』の19条に反し、「女性差別撤廃委員会」の是正勧告などによる欧米諸国の「フレンドリーペアレント(FP)」を見直し、「離婚後の父母と子どもとの交流の継続よりも、子どもの安全を優先」する動きを無視し、逆行するものです。
この離婚後、子どもの「監護者」でないもう一方の親を「共同親権者」とし、子どもに対する権利(親権)を行使できる仕組みをつくる「共同親権法案」の背景にある思想・イデオロギーは、「第2の「法案」」の安倍晋三元首相の肝いりで、満州事変・太平洋戦争中の『戦時家庭教育指導要項』に通じ、成立を目指す『家庭教育支援法案』に通じるものです。
『戦時家庭教育指導要項』は、「あるべき家庭教育を国が定め、国家が家庭での教育を統制する」というものでした。
仮に、「第2の「法案」」の『家庭教育支援法』が成立し、「あるべき家庭教育を国が定め、国家が家庭での教育を統制する」ことができたとしても、家庭で子どもに教育をする親(彼らの認識は家父長なので父親を指す)の子どもに対する権利が弱ければ(子どもに主体があると)、実効性に欠けることになります。
そのため、離婚後、監護者でない一方の親の権利の強化として、「主体は親(共同親権者)」でなければならないことになります。
(4) 「子どもの意見の尊重(子どもの意思表明権)」の未記載
令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」には、いまから36年前の1989年(平成元年)11月20日に、国連で採択された『子どもの権利条約』に規定している「子どもの意見の尊重(子の意思表明権)」の記載がありません(令和6年(2024年)4月15日現在)。
『民法820条(親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う)』において、「親権」は、「子の利益のため」のものであることが明示されています。
しかし、「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」の国会提出前の審議会では、子どもの利益に直結する福祉分野の議論はほとんどありませんでした。
そのため、子どもが、「(生活を同じくしていない共同親権者であるもう一方の)親と会いたくない(面会交流したくない)」、「進学先は、・・にしたい」との意思が尊重されず、「嫌でも、決まりだから無理やり会わなければならない」、「親が決めた進学先に進学しなければならない」といった悲惨な事態を招く怖れがあります。
「1-(1)離婚後の共同親権制度の導入」を主導してきたのは」で示したように、「離婚後の共同親権制度の導入」を主導してきた極右・超保守の超党派「共同養育支援議員連盟(前.親子断絶防止議員連盟)」は、令和5年(2023年)の本国会に提出した『請願書(別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する請願)』では、主に、ア)監護者でない一方の親と2週間に1度は泊りがけで会えるようにすること(親子交流の権利性を明確化)、イ)年間、100日以上は会えるようにすること(面会交流の拡充)を求めています。
したがって、本国会で、「子どもの意見の尊重(子の意思表明権)」の記載がない「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が成立し、「離婚後の単独親権制度が導入」されると、子どもが、「(生活を同じくしていない共同親権者であるもう一方の)親と会いたくない(面会交流したくない)」と主張しても、監護者でない一方の親の意思が尊重され、ア)2週間に1度は泊りがけで会う、イ)年間、100日以上は会うなどと決まる可能性もあります。
『子どもの権利条約』の19条では、「子どもが両親のもとにいる間、性的虐待を含むあらゆる形態の身体的、または、精神的暴力、傷害、虐待、または、虐待から保護されるべきである」と定め、「それが起こるとき、親権や監護権、面会交流の決定において、親密なパートナーからの暴力や子どもに対する暴力に対処しないことは、女性とその子どもに対する暴力の一形態であり、拷問に相当し得る生命と安全に対する人権侵害である」、「子どもの最善の利益という法的基準にも違反する」と規定しています。
いまから9年前の平成26年(2014年)、「女性差別撤廃委員会」は、締結国である日本政府に対し、「面会交流のスケジュールを決定するときには、家庭内暴力や虐待の履歴があれば、それが女性や子どもを危険にさらさないように考慮しなければならない。」と勧告しています(令和6年(2024年)4月15日現在)。
これは、日本で実施される離婚後(夫婦関係調整(離婚)調停や監護者指定の調停・審判の実施中を含む)に実施されている「子どもと同居していないもう一方の親と子どもとの面会交流」は、「女性や子どもを危険にさらさないよいに考慮されていない」ことを示し、この状況は、いまも改善されていません。
このことは、「1.第1の「法案」『家族法(民法)』の改正(離婚後の共同親権制度)」で示しているように、「離婚後の共同親権制度の導入」の目的が、「離婚後、子どもの「監護者」でない一方の親の子どもに対する権利の強化」であることから、北欧諸国・欧米諸国の「離婚後の父母と子どもとの交流の継続よりも、子どもの安全を優先」する動きと逆行します。
・『世界人権宣言』と9つの主な『人権条約』
第2次世界大戦終戦から3年後の1948年(昭和23年)12月10日、国際連合(国連)は、人権法の柱石(すべての人民にとって、達成すべき共通の基準)として『世界人権宣言(Universal Declaration of Human Rights)』を採択しました。
この『世界人権宣言』では、第1条「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。」、第3条「すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。」と記述しています。
以降、国連は、9つの主な『人権条約』を採択しました。
『国際法』『条約』は、「国内法」より上位に位置づけられることから、国連で採択された『条約』を批准・締結した国連加盟国は、その『条約』に準じ、法を制定したり、法を改正したりする義務を負います。
これらの『条約』には、いずれの国家の立場からも独立した専門家からなる「委員会」を設置しています。
この「委員会」は、その内容を守ることを約束して批准・締結した国が、本当に守っているかどうかを監視し、守られていないときには、当該国宛に改善を求める「勧告書」を送付します。
「守られていない」とは、国連加盟国の国が、批准・締結した『条約』にもとづき、自国の「国内法」を改正したり、新たに「国内法」を制定したりする義務に対し、その義務を怠っている、つまり、対応していないことです。
本来、国民の「人権」や「権利」を“守る”ことは、国をどう位置づけるか、どのいう法制度が必要なのかが問われます。
つまり、国連加盟国は、常に、その国での人々の暮らしをどう理解し、それを踏まえて、社会のどこに問題があるのかを見出し、どのように変革していくのかが求められます。
同時に、これらの問題は、国任せ、つまり、政党、政治家、支持者任せではなく、市民一人ひとりが問い、考え、行動しなければならないことです。
なぜなら、国、政党、政治家、支持者が、日本で生活している市民(国籍は問わない)の「人権」や「権利」を認めなかったり、約束ごとを守らなかったり、誤った方向に進もうとしたりすることがあるからです。
問題は、日本で生活している市民(国籍は問わない)は、国際的なとり決めである『条約』での約束ごとを守らなかったり、間違った方向に向かったりしないように監視する役割があることに無関心で、無頓着なことです。
無関心で、無頓着であったり、見て見ぬふりをしたりすることも、市民の一人ひとりの意志、市民一人ひとりが選択したものです。
つまり、国、政党、政治家、支持者が、国民の「人権」や「権利」を認めなかったり、約束ごとを守らなかったり、間違った方向に向かったりするのを見て見ぬふりをする、知らずにやり過ごし、やりたい放題を許すのも、市民の一人ひとりの意志、市民一人ひとりが選択したことになります。
ただし、それは、日本で生活する市民としての義務を果たさず、権利を捨てることを意味します。
国連が採択した9つの主な『人権条約』は、
ⅰ) あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約、1965年(昭和64年)12月21日)
ⅱ) 市民的および政治的権利に関する国際規約(自由権規約、1966年(昭和41年)12月16日)
ⅲ) 経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(社会権規約、1966年(昭和41年)12月16日)
ⅳ) 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約、1979年(昭和54年)12月18日)
* 女性差別撤廃条約選択議定書(1999年(平成11年)10月6日)
ⅴ) 拷問および他の残虐な、非人道的な、または品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約(拷問等禁止条約、1984年(昭和59年)12月10日)
ⅵ) 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約、1989年(平成元年)11月20日)
* 児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する選択議定書(2000年(平成12年)5月)
* 武力紛争における児童の関与に関する選択議定書(2000年(平成12年)5月)
* 通報手続きに関する選択議定書(2011年(平成23年)12月)
ⅶ) すべての移住労働者およびその家族の権利保護に関する条約(移住労働者権利条約、1990年(平成2年)12月18日)
ⅷ) 障害者の権利に関する条約(障害者権利条約、2006年(平成18年)12月13日)
ⅸ) 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約(強制失踪者保護条約、2006年(平成18年)12月20日)
です。
日本は、ⅶ)の『移住労働者権利条約』以外の8条約について批准・締結、つまり、その『条約』の規定を「守る」と約束し、そのうち、6つに日本人の委員が選出されています。
ところが、ⅳ)の『女性差別撤廃条約』は批准・締結していますが、『女性差別撤廃条約選択議定書』は24年5ヶ月を経たいまも未批准、ⅵ)の『児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)』、『児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する選択議定書』、『武力紛争における児童の関与に関する選択議定書』は批准・締結していますが、『通報手続きに関する選択議定書』は未批准のままです(令和6年(2024年)4月15日現在)。
『選択議定書』とは、条約の内容を補うためにつくられる文書で、条約と同じ効力を持ちます。
歴代の日本政府の姿勢が示されているのは、批准・締結した8つの『人権条約』に対し、6人の委員をだしているにもかかわらず、9つの『人権条約』すべてに成立している「個人通報制度」をひとつも受諾していないことです。
この意味は重要です。
なぜなら、日本政府が、「個人通報制度」を受諾しない理由が、「第3の「法案」」で、本国会での成立を目指している『国家総動員法』に匹敵する「緊急事態条項に関する憲法改正」に不都合だからです。
ⅶ)の『移住労働者権利条約』を批准・締結していない日本政府は、ア)平成5年(1993年)に導入された「技能実習制度(Technical Intern Training Program)」、つまり、『出入国管理及び難民認定法』の別表第1の2に定める「技能実習」の在留資格により日本に在留する外国人が報酬を伴う実習を行う制度における実習生の低賃金、長時間労働、劣悪な居住施設を放置し続け、イ)名古屋出入国在留管理局に収容されていたスリランカ出身のウィシュマ・サンダマリさん(33歳)が死亡したとき、適切な医療を提供しなかったことが大きな問題となる中で、ウ)令和5年(2023年)6月9日、強制送還の対象となった外国人の長期収容解消をはかることを目的とし、難民認定の申請中は強制送還を停止する規定を改め、難民認定の申請で送還を停止できるのは原則2回までとする『改正出入国管理及び難民認定法』を参院本会議で可決し、成立させました。
日本政府が、ⅶ)の『移住労働者権利条約』を批准・締結しないのは、批准・締結すると『出入国管理及び難民認定法』にもとづく「技能実習制度」を実施できないからです。
ここには、日本政府の「人権」を蔑ろにする政治姿勢が示されています。
・126年間続いた「子どもを懲戒する権利」。いまも7割が「体罰」を容認する異常
明治29年(1896年)に制定された『子どもを懲戒する権利(民法822条)』は、令和4年(2022年)10月14日削除、同年12月16日に施行されました。
この間、歴代の日本政府は、126年間、5-6世代の育児において、『子どもを懲戒する権利(懲戒権(民法822条))』の下で、「しつけ(教育)と称する体罰(身体的虐待)」にお墨つきを与えてきました。
「懲戒」とは、不正・不当な行為に対して「制裁」を与えることで、子どもを殴ったり、叩いたり、蹴ったりするなどからだに対する(人権)侵害する行為、正座を強いたり、直立不動で立たせたりするなど、からだに苦痛を与える行為などが、「体罰」に該当します。
世界で初めて「体罰禁止」を法制化したのはスウェーデンで、第2次世界大戦が終戦してから34年後、いまから45年前の1979年(昭和54年)のことです(令和6年(2024年)4月15日現在)。
スウェーデンの『子どもと親法6章1条』では、「子どもはケア、安全および良質な養育に対する権利を有する。子どもは、その人格および個性を尊重して扱われ、体罰または他のいかなる屈辱的な扱いも受けない」と規定していますが(1983年改正)、これは、『世界人権宣言(昭和23年(1948年))』の第1条「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。…」に添ったものです。
「子どもが両親のもとにいる間、性的虐待を含むあらゆる形態の身体的、または、精神的暴力、傷害、虐待、または、虐待から保護されるべきである(19条)」と定めた『子どもの権利条約』が、国際連合(国連)で採択されたのは平成元年(1989年)11月20日、いまから36年4ヶ月前のことです(令和6年(2024年)4月15日現在)。
つまり、スウェーデンは、国連で『子どもの権利条約』を採択する10年前に、『世界人権宣言』にもとづいて「体罰」を禁止しています。
その『子どもの権利条約』には、「体罰を撤廃することは、社会のあらゆる形態の暴力を減少させ、かつ防止するための鍵となる戦略である。」と明確に示された人権解釈の存在があります。
国連の「子どもの権利委員会」は、「どんなに軽いものであっても、有形力が用いられ、かつ、なんらかの苦痛または不快感をひき起こすことを意図した罰」を「体罰」として定義し、続けて、「その多くは、手、道具(鞭、棒、ベルト、靴、木さじなど)で、子どもを叩くという形で行なわれる。しかし例えば、蹴ること、子どもを揺さぶったり、放り投げたりすること、ひっかくこと、つねること、かむこと、髪を引っ張ったり、耳を打ったりすること、子どもを不快な姿勢のままでいさせること、やけどさせること、薬物等で倦怠感をもよおさせること、強制的に口に物を入れること(例えば、子どもの口を石鹸で洗ったり、辛い香辛料を飲み込むよう強いたりするなど)を伴うこともあり得る。」としています。
「子どもの人権委員会」の見解では、「体罰は、どのようなケースであっても、子どもの品位を傷つける行為であり、加えて、同様に残虐かつ品位を傷つけるもの、つまり、体罰以外の形態をとる罰も存在する」として、その罰の例として、「子どもを貶(おとし)めたり、辱(はずかし)めたり、侮辱したり、身代わりに仕立てあげたり(責任を押しつけたり)、脅迫したり、怖がらせたり(スケアード・ストレート)、笑いものにしたりするような行為」をあげています。
126年間、5-6世代にわたり、「子どもを懲戒する権利(民法822条)」が削除されなかった日本の育児で日常化されているのが、「子どもを脅すなどして、恐怖を与え(terrorizing)、生活習慣を身につけさせる(心理的虐待)」ことです。
親やきょうだいなど生活をともにする人に脅され、恐怖を与えられて身につけた行動習慣は、恐怖を回避するための生存本能としての行動、つまり、PTSDの症状としての回避行動です。
子どもが、親の機嫌(顔色)を伺い、意に反しないように気を遣い、危害を避けるために意に添うように行動したり、喜ばせるように行動したりする行為は、恐怖を回避するための生存本能としての行動、つまり、回避行動です。
この恐怖によるコントロールは、「スケアード・ストレート」と呼ばれます。
子どもに恐怖を感じさせる(スケアード)ことで、子どもに正しい行動(ストレート)ととることの必要性を学ばせようとする行為です。
しかし、この「スケアード・ストレート」は、「ランダム化比較試験」などにより、「意味がない」だけではなく、「逆効果を生む」ことが明らかになっています。
「スケアード・ストレート」の例としては、ア)親が、「早く寝ないとお化けがでるよ!」といい、子どもを怖がらせて寝かしつけようとしたり、イ)「いうことをきかないと、押し入れに閉じ込めるぞ!」、「いうことをきかないと、もう買わないからね!」、「早くこないと、置いて行っちゃうよ!」といい、怖がらせ、脅して、いうことをきかせようとしたり、ウ)学校などで、人が交通事故にあった映像を見せ、「道路を飛びだしてはいけない」と教えたり、エ)「いうことをきかないと、レギュラー(配役、採用)から外す(内申点に影響する)」と脅すことばを伴って指導したり、オ)職場で、「いうことをきかないと、査定に響く(他の部署に飛ばす、辞めてもらう)」と脅すことばを伴って命じたりする行為があげられます。
こうした子どもに恐怖を与え、従わせようとする行為は、日本社会では、家庭だけでなく、学校園による教育、部活動などの指導など、大人が、子どもとかかわるあらゆる“場”や“機会”で、日常的に見られる光景です。
親や教師などが、幼児期の子どもを怖がらせること、つまり、子どもに恐怖を与えることはプラスに働くことはなにもなく、すべてマイナスに働きます。
一定の恐怖を与え、いうことをきかなくなると、さらに、強度を高めた恐怖を与えなければならなくなるという負のスパイラルをもたらします。
重要なことは、親が、子どもに対し「いい子にしない(いうことをきかない)と、お巡りさん呼ぶぞ!」といい、いうことをきかせる(コントロールする)ための「スケアード・ストレート」には、“嘘”という側面を伴っていることです。
この“側面”の問題は、「スケアード・ストレート」と同様に、子どものときに親に嘘をつかれたことが多い人ほど、成長に伴い、親や教師などに嘘をついたり、心理的な問題を抱えたりすることが多くなる傾向が示されています。
例えば、子どもが嘘をつくと、「嘘をつくと、エンマ大王に舌を抜かれるぞ!」とさらに“嘘”を重ね、いうことをきかせようとします。
つまり、「スケアード・ストレート」を使った生活習慣を身につけさせる行為は、子どもを嘘つきに育てたり、心理的な問題を抱えさせたりする深刻な側面を持ちます。
にもかかわらず、この「スケアード・ストレート」は、日本では、「なまはげ」などの伝統文化、仏教、儒教思想にもとづく道徳観として「昔話」、「童話」として日本社会の隅々まで浸透し、家庭だけでなく、学校園の催しごと、クラブ活動や塾、習いごとでの指導、職場での部下指導などいたるところであたり前のように行われ、しかも、実施したり、世襲したりする人だけではなく、それを見たり、聞いたり、学んだり、見守ったりする人たちもそのことに無自覚という、実に根が深い問題となっています。
そして、この恐怖によるコントロールの「スケアード・ストレート」は、オレオレ詐欺や投資詐欺、結婚詐欺、占い・スピリチュアルなどの詐欺商法、新興宗教やカルド団体の勧誘活動(さび商法を含む)の“常套手段”で、恐怖によるコントロールの「スケアード・ストレート」で育ってきた、つまり、心理的虐待を受けて育ってきた(被虐待体験をしてきた)人は、スッと騙されやすい傾向があります。
つまり、恐怖によるコントロールの「スケアード・ストレート」で育った被虐待体験をしてきた人は、人の嘘、つくり話、戯言に対する心理的な障壁が低く、人を騙したり、人に騙されやすかったりする傾向があります。
それだけではなく、性暴力に及ぶ者の主な手口であるⅰ)親しさを装い、手懐け、断り難い状況をつくりだす手法としての「グルーミング」、ⅱ)ことばでの威圧や借りをつくらせるなどの圧力(パワーハラスメントなど)により、不平等・非対等な関係を巧みに築き、あらがえない状況に追い込んで、性行為に持っていけるように罠を仕掛ける「エントラップメント」、ⅲ)短期間に猛烈なアプローチをし、まるで、相手が自分のことを「ひとめぼれ」したように見せかける「ラブボミング」に対する障壁が低く、慢性反復的(常態的、日常的)な性暴力被害を受けやすくなります。
同時に、グルーミング・エントラップメント・ラブボミングを駆使し、性暴力行為に至る加害者となり得ます。
なぜなら、乳幼児期から、「脅す」ことは人の心をコントロールできる有効な手段(術)であることを、親や近親者・保育士、所属するコニュニティの人たちからの「スケアード・ストレート」で叩き込まれているからです。
日本政府が、平成12年(2000年)に制定した『児童虐待防止法』を改正し、世界で59ヶ国目に「体罰」禁止したのは、令和2年(2020年)4月1日(施行)で、明治29年(1896年)に制定された『子どもを懲戒する権利(民法822条)』は、令和4年(2022年)10月14日削除、同年12月16日に施行されました。
このことは、日本政府が、『児童虐待防止法』で体罰を禁止し、『子どもを懲戒する権利(民法822条)』を削除するまでに、1979年(昭和54年)にスウェーデンが体罰を禁止してから44年を要したことを意味します。
そのスウェーデンでは、1960年代に55%の親が体罰を肯定的に捉え、95%の親が体罰を加えていたといわれていますが、体罰禁止を法制化してから34年経過した2018年(平成30年)、親の体罰は1-2%に激減しています。
その大きな要因は、そのときに生まれた子どもはいま44歳、つまり、自身が親となっているときには、既に育児はほぼ終わり、まもなく(早いと)その子どもが親となり、その子どもは自身の孫となっていることです。
つまり、自身の親の育児から2世代を経て、3世代目の育児で、体罰を加えない育児が継承されています。
一方で、日本は、明治29年(1896年)に制定された『子どもを懲戒する権利(民法822条)』にもとづく「しつけ(教育)と称する体罰(身体的虐待)」を126年間、5-6世代の育児で継承してきました。
「スケアード・ストレート(心理的虐待)」に至っては、江戸幕府が、すべての人々がいずれかの仏教寺院(寺)の「檀家」となることを強制する「寺請制度」を設け、葬祭供養などの場を通じて、仏教の説話などまで遡ることができます。
全宗派と寺院を全面的に統制する法度をつくり、住職の資格や寺領を規制するとともに寺檀制度の大綱を定めたのが、寛文5年(1665年)とあるので、そこを基準とすると、実に358年経過しています。
このことは、この期間の育児で、「しつけ(教育)と称する体罰(身体的虐待)」を加えたり、「スケアード・ストレート(心理的虐待)」でコントロールしたりしない方法を学び、習得する機会はありませんでした。
つまり、日本社会には、『児童虐待防止法』で体罰を禁止したり、『子どもを懲戒する権利(民法822条)』を削除したりしても、「しつけ(教育)と称する体罰(身体的虐待)」を加えたり、「スケアード・ストレート(心理的虐待)」でコントロールしたりしない“お手本”がほとんどいない(教えることができる人が存在しない)という深刻な問題を抱えています。
平成29年(2017年)、子ども支援の国際的NGO「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」が全国2万人の大人を対象に実施した「子どもに対するしつけのための体罰等に関する意識調査」と、1030人の子育て中の親と養育者を対象に実施した「体罰等に関する意識実態調査」にもとづき、『子どもに対するしつけのための体罰等の意識・実態調査結果報告書』をまとめ、発表しました。
実に68.2%の親が、子どもを叩くことを容認し、子育て中の家庭の70.1%が、過去にしつけ(教育)の一環として体罰を加えていたました。
問題は、「子どもに対して決して体罰をすべきではない」と回答した43.3%の一定数が、お尻を叩く、手の甲を叩く(以上、身体的虐待)、怒鳴りつける、睨みつける(以上、心理的虐待)などの子どもの心を傷つける体罰を容認していたことです。
つまり、「しつけ(教育)と称する体罰」に対する認識には、大きなギャップが存在しています。
そして、子育て中の家庭の70.1%が、過去にしつけ(教育)の一環として体罰を加えていました。
平成28年(2016年)に実施された他の調査では、「約70%の親が、子どもを叩いたことがある」と回答し、同様な結果がでています。
「しつけ(教育)と称する体罰」が、5-6世代の子育てで繰り返されてきたことを踏まえ、この70%を単純計算すると、調査年度の平成28年(2016年)の日本人の人口は1億2502万人なので、その70%は、8751万4千人が「しつけ(教育)と称する体罰」に関係する当事者となります。
当事者である8751万4千人とは、子どもに「しつけ(教育)と称する体罰」を加えたことのある親や養育者、親に「しつけ(教育)と称する体罰」を加えられた被虐待体験者(小児期逆境体験者)の総数です。
この深刻な日本を蝕む社会病理について、日本で生活する多くの一般市民は無自覚で、深刻で、重大な問題と認識に至っていません。
慢性反復的(常態的、日常的)で、苛酷な被虐待体験をしてきた人の一定数に認められる 「反応性愛着障害(RAD)」に求められる「不安型(囚われ型)」は、親のそのときの気分(気まぐれ)でかわいがられたり、突き放されたりするなどムラのある接し方をされている「ダブルバインド」「制限(条件)つきの優しさ」に起因します。
日本では、10人-8人に1人の子どもや大人が、この「不安定型(囚われ型)」の「反応性愛着障害(RAD)」に見られるような傾向が見られる(問題を抱えている)と指摘されています。
「10人-8人に1人」という数字を、小学校の1クラス35人学級にあてはめてみると、1クラスに3.50人-4.38人の児童が該当しますが、この「反応愛着障害(RAD)」が示す特徴と傾向が、「ADHD(注意欠陥多動性障害)」の特徴と傾向が酷似しています。
そのため、専門医でもその診断が難しいといわれています。
つまり、日本社会では、70%の人が「しつけ(教育)と称する体罰(身体的虐待)」を容認していることを踏まえると、1クラス35人のうち、実に21人-24.5人の児童が、少なくとも、お尻を叩く、手の甲を叩く(以上、身体的虐待)、怒鳴りつける、睨みつける(以上、心理的虐待)などの「しつけ(教育)と称する体罰」を加えられていて、そのうちの3.50人-4.38人の児童は、「反応愛着障害(RAD)」が示す特徴と傾向を示している(慢性反復的(常態的、日常的)で、苛酷な被虐待体験をしている(きた)児童)ことになります。
この虐待の連鎖問題とかかわるのが、「暴力のある家庭環境で育つ子どものMOMA遺伝子は活性化する」ことです。
出生後、人の暴力性を目覚めさせるか、目覚めさせないかは、攻撃性と関係のある「MOMA遺伝子」の“スイッチ”を入れる体験、つまり、被虐待体験、戦争や紛争による虐殺体験(目撃を含む)が大きく影響しています。
虐待を受けた(暴力のある家庭で暮らし、育った)人は、攻撃性と関係のある「MOMA遺伝子」の“スイッチ”を入れることなど、遺伝子レベルでひき継がれることがわかってきました。
2002年(平成14年)、イギリスのロンドン大学のリサーチセンターのカスピ博士らにより、人の攻撃性(暴力的な反社会的行動)に関係しているといわれる「MOMA」と呼ばれる遺伝子が、暴力のある家庭で暮らし、育つこととの関係性を調べた研究結果がまとめられました。
この研究は、「MOMA遺伝子の活性が低いタイプは攻撃性が高く、MOMA遺伝子の活性が高いタイプは攻撃性が低い」とされていることを踏まえ、MOMA活性が低いタイプのグループと、MOMA活性が高いタイプのグループが、それぞれ3-11歳のころの虐待の略歴を調べ、さらに、26歳になったときの攻撃性について、精神科・心理学的な調査や警察の逮捕歴などで調べたものです。
カスピ博士らは、「MOMA活性が低いタイプでも、暴力のない家庭で暮らし、育っている(子ども時代に虐待を受けていない)ときには、攻撃性は見られず、一方で、暴力のある家庭で暮らし、育っている(子ども時代に虐待を受けて育っている)ときには、高い攻撃性が見られた。」、「MOMA活性が低いタイプの子どもは、虐待を受けることで過度の恐怖を感じ、常習的に虐待を受け続けることで、神経伝達物質システムと呼ばれる脳の働き自体が変わってしまい、強い攻撃性を見せるようになったと考えられる。」、「攻撃性が高いと思われるMOMA活性が低いタイプであっても、虐待を受けなければ、活性が高いグループに比べても攻撃性はむしろ低いくらいであった。」、「MOMA活性が高いタイプは、虐待によって脳の機能を変えられることから、自分を守る力を遺伝的に持っているかもしれない。」との研究結果を発表しています。
この研究結果は、「子どもが、暴力のある家庭環境暮らし、育つ(虐待を受けて育つ)ことによって、“攻撃性(暴力的な反社会的行動)のスイッチ”が入る」ことを示すものです。
このⅰ)「MOMA遺伝子の活性化」とⅱ)「3-(7)-⑤「共同親権」と婚姻関係にない子どもの父親の「子どもの認知」」で示した「乳幼児期の被虐待体験を起因とする6-8歳ころ(小学校1-3年生まで)には、「パラフィリア」の性的興奮のパターンは発達を終え、その性的興奮のパターンがいったん確立される」こと、加えて、ⅲ)成育歴で、「扁桃体」の興奮を「前頭葉」でコントロール(抑制)する脳機能を獲得できているかなどの視点が、被虐待体験と暴力性との因果関係示す「エビデンス」となります*1。
また、こうした成育歴が、ア)世界に類を見ないほど多くの認知症患者数(アルツハイマー型認知症は、同じ海馬の萎縮が認められる(C-)PTSDの発症者が高い発症リスクを抱える)、イ)自殺者数(子どもの死因の第1位は自殺です)、精神疾患患者、ひきこもり者(多くは精神疾患(発達障害を含む)の発症を起因としている)、ウ) リストカット・OD(大量服薬)、過食嘔吐などの自傷行為、エ)アルコール・薬物・ギャンブル依存((C-)PTSDの自己投薬としてされている)、オ)再演・性的自傷としての性暴力被害(援助交際・パパ活、管理売春などの性的搾取被害)を生みだしている根本の要因です*2。
*1.2 この重要なテーマは、レポート『別紙2d(簡易版)DV・虐待・性暴力被害。慢性反復的トラウマ体験に起因する後遺症(A4版192頁)』で詳述しています。
(5) 子どもの「人権の尊重」と「人格の尊重」の決定的な違い
① 似通っていて、まったく異なる意味の「人権」と「人格」
『配偶者暴力防止法』の制定に大きな影響を及ぼした平成12年(2000年)6月、国連の「北京プラス5会議」でした。
日本が批准・締結した『女性差別撤廃条約』では、「DVが、女性に対する人権の侵害とする」と規定していることを受けて、平成7年(1997年)2月、橋本龍太郎政権(自由民主党、社民党、さきがけの連立政権で、2党首が土井たか子と堂本暁子)が発表した『男女共同参画2000年ビジョン』では、国内のほとんどすべての解決しなければならない暴力問題が含まれていました。
しかし、その後、「現行法制度でDV対応可能だ」と考える極右・超保守の政治家たちが圧力をかけ、変更に追い込んだ「プラン(計画)」では、「女性に対する暴力を人権問題として考慮していない」など、幾つかの点で大きく後退させる状況が生まれました。
この大きな後退に対し、意を唱えたのが、国連の「北京プラス5会議」で、日本政府は、「親密なカップルにおける暴力に国家が介入するようなDV政策をアジェンダに載せる必要がある」と迫られたことを受けて、日本の内閣府の「男女共同参画推進本部」は、改めて、「女性に対する暴力は、女性への人権を侵害するものであり決して許されるべき行為ではない」との立場を示し、平成13年(2001年)4月6日、「清和会(現安倍派)」の小泉純一郎政権が、5人の女性大臣を交えて成立する20日前に『配偶者暴力防止法』を成立させました。
この前置き文に、極右・超保守の政治家が認めない重要なキーワードがあります。
それは、「女性と子どもには、「人権」を認めない」ことです。
しかし、「女性と子どもには、「人権」を認めない」ことは、『世界人権宣言』、日本が批准・締結している8つの『人権条約』、そして、『日本国憲法』に反することから、歴代の日本政府は、まるで人々を欺くかのように、「人権」の代わりに「人格」という表記を使います。
令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」の衆議院・参議院における小泉龍司法務大臣、法務省の答弁の中に、この「人権」ではなく、「人格」という表現が頻繁にでています。
この「人格」の表記は、本国会で成立を目指す「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」でも、「子どもの人権の尊重」ではなく、「子どもの人格の尊重」と表記されていることから、この似通っているけれど、まったく意味が異なる「人権」と「人格」について正確に理解することはとても重要です。
以下、「はじめに。」の「リベラルが育つ土壌と意思表明権。人権教育と道徳教育の違い」の記述を引用します。
「人権」は、人間が、人間らしく生きるための権利で、生まれながらに全員が持っている権利のことです。
人間であれば、誰もが持っている権利です。
つまり、どのような人であっても、出生後、決して否定されない「権利」です。
そして、英語の「rights(権利)」には、「自然で、あたり前のこと」という意味があります。
つまり、「権利」は、人としてあたり前に持っているものです。
出生した新生児が発する(訴える)「あー」、「うー」に対し、(養育の有無にかかわらず)ケアする大人が、「どうしたの?」などとことばをなげかけるやり取りは、新生児(相手)の立場で、新生児の要望を聴きとろうとする行為です。
この新生児と大人のやり取りは、この新生児が、「権利のある存在」として社会に認められたことを意味します。
一方の「人格」とは、「人の心のあり方」を問う「道徳」に通じるもので、個人の心理面の特性、人柄のこと、あるいは、人としての主体(中心となるもの)を意味し、「人格権」は、「個人の名誉など人格的利益を保護するために必要な権利のこと」ですが、人格権自体には、権利として、具体的に保障されていません。
「人権」は、「どのような人であっても、出生後、決して否定されない権利がある」ことを保障するもので、グローバルスタンダードな「人権教育」は、社会のあり方を考えさせる、つまり、物事の構造、仕組み、つくりに起因する問題を把握し、その問題解決につながる社会変革を考える中で、自らの権利を知り、権利の主体として、社会変革を実現するための行動につながるように導くものです。
つまり、「人権」と「人格」は似通っていますが、意味はまったく異なるものです。
日本政府は、「人権」を尊重するのではなく、「人格」を尊重する、つまり、社会問題・人権問題ではなく、「個人の心のあり方」、個人の問題と考えています。
1989年(昭和62年)11月20日、国連で『子どもの権利条約』を採択してから5年後の1994年(平成6年)4月22日、日本は20ヶ国目の批准国になりました。
しかし、令和元年(2019年)に『児童虐待防止法』において、「親権者等による体罰の禁止(令和2年(2020年)4月1日施行)」するまでに、『子どもの権利条約』の批准・締結から25年を要し、「親権」の「子どもを懲戒する権利(懲戒権/民法822条)」を削除する(令和4年(2022年)10月14日(同年12月16日に施行))までに2年、併せて、27年を要しています。
つまり、日本では、この27年間の2世代の子育てを含めて、126年間、5-6世代の子育てで、日本政府の公認(子どもを懲戒する権利(民法822条)のもとで、親は子どもに対し、「懲戒(しつけ(教育)と称する体罰(身体的虐待))」を加えることが許されてきました。
この『児童虐待防止法』では、「体罰の禁止」について、どのように記述しているのでしょうか?
同法第14条第1項で、「児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。」と記述しています。
ここには、『世界人権宣言』『子どもの権利条約』に添った子どもの「人権」、「尊厳」、「保障」などの文言は一切記述されていないだけではなく、「監護及び教育に必要な範囲を超える行為でなければ、体罰を加えてもいい」と解釈できたり、「親権の適切な行使に配慮」とどのような行為が“適切”なのか不明確であったりします。
つまり、「体罰を禁止」としながら、「体罰」の規定を示すことで、一定の範囲であれば体罰を加えても問題ないとの考えを示しています。
ここに、親の子どもに対する「懲戒」「体罰」に対する日本政府の姿勢が明確に表れています。
日本政府は、本国会で成立を目指す「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」においても不明確な条文を多々設けています。
規定を明確に示さない(不明確にする)ことは、どのようにでも解釈できることを意味します。
どのようにでも解釈できるようにしておくことは、厳しく法を適用し、意に反するものを排除したり、責任を回避したりする(予め逃げ道を用意しておく)ことができ、権力を握る者にとって、とても都合がいいのです。
次に、『子どもを懲戒する権利(民法822条)』を令和4年(2022年)10月14日に削除(同年12月16日施行)したことに伴う関連法の条文を見ていきます
「民法820条(監護及び教育の権利義務)」で、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」、「同822条(懲戒)」で、「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」との規定が、この「同822条(懲戒)」は削除され、「同821条(子の人格の尊重等)」の後段が追加され、「親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」と規定しました。
つまり、日本の『家族法(民法)』における「親権」では、「子どもの人権を尊重する」ではなく、「子どもの人格を尊重する」と表記(規定)しています。
このことは、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」において、『子どもの権利条約』で規定している「子どもの意見の尊重(子の意思表明権)」の表記を外したことにつながっています。
この『民法』の一部改正に伴い、『児童福祉法』と『児童虐待防止法』も以下のように改正されました。
「児童福祉法33条の2の②」で、「児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を採ることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」、「同47条の③」で、「児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」との規定が、「同33条の2の②」で、「児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。この場合において、児童相談所長は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」、「同47条の③」で、「児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親(以下この項において「施設長等」という。)は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。この場合において、施設長等は、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」と改正されました。
「児童虐待防止法14条(親権の行使に関する配慮等)」で、「児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。」との規定が、「同14条(児童の人格の尊重等)」で、「児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」と改正されました。
「親権」としての『子どもを懲戒する権利(民法822条)』を削除したことを受け“改正”した『児童福祉施設』『児童虐待防止法』のいずれも、「児童の人権を尊重する」ではなく、「児童の人格を尊重する」と表記(規定)しています。
子どもに対する法律で、「人権」ではなく「人格」と記述する日本政府の姿勢は、第2次世界大戦(太平洋戦争)敗戦から3年後、日本政府が、昭和23年(1948年)に国連で『世界人権宣言』が採択された同じ年に定めた『国民の祝日に関する法律』にも示されています。
その『国民の祝日に関する法律』には、「こどもの日」は、「こどもの人格を重んじ、・・」と「人権」ではなく「人格」と記述しています。
② 「道徳教育」では、人権・社会問題にとり組む視点は育たない
平成12年(2000年)に制定された『人権教育及び人権啓発の推進に関する法律』の第2条では、「人権教育は、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動である」と定義し、「人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く)をいう」と規定しています。
しかし問題は、この法律における人権教育や啓発は、「個人の精神を涵養し、理解を深めていくこと」と規定していることです。
つまり、この法律は、「個人の精神」と“人柄”“心がけ”という「人格」に重点が置かれていることになります。
したがって、この法律で実施される「人権教育」は、「人格教育」であることから「道徳教育」といえます。
「はじめに。」の「リベラルが育つ土壌と意思表明権。人権教育と道徳教育の違い」で述べているように、人権に関する問題は、人格教育、道徳教育は解決できません。
なぜなら、それは個々人の心の問題ではないからです。
例えば、学校の「人権教育」でとり扱われるテーマの「いじめ問題」、その虐める行為の背景にある「差別・排除」について考えてみます。
『日本国憲法』の第14条にあるとおり、「差別は、政治的、経済的、または、社会的関係において発生」します。
ところが、日本社会、あるいは、学校教育において、この「差別・排除」という問題は、「道徳」として、人の“思いやり”“優しさ”“心がけ”といった心の問題として扱われています。
つまり、「道徳」の授業は、「個人の心のありよう」を問題とします。
一見、個人の道徳性のあり方から差別・排除問題などの社会的な課題に対応していくことには効果があるように思えます。
さまざまな差別問題は、常に具体的です。
ある特定の誰かに起こる問題であり、そこでは、個人的な、ある人とある人との狭い範囲の関係のあり方が問われます。
しかし、そうした視点だけでは、「差別・排除」について十分に考えることはできません。
なぜなら、差別・排除は、個人的な「人間関係」を超えた、より広い社会関係の中で起きるからです。
道徳教育では「狭い関係性」にばかり注意が集まり、その関係の中に、社会的に仕組まれたより広い構造的課題が凝集していることを考えることは困難です。
つまり、「心のあり方」を問題とする道徳の枠組みでは、この社会的な構造を問うことは難しくなります。
例えば、いじめなど人を傷つけてはいけないことを教える「命の授業」は、個々人の「心のあり方に問題がある」として、「個々人の道徳観の育成による解決」を試みています。
平成26年(2014年)7月、女子生徒が高校の同級生を殺害し「人を殺してみたかった。」と供述した「佐世保同級生殺害事件」が発生し、例年5-7月のうち1週間を「命を大切にする心や思いやりの心の育成」を目的にした“命を大切にする教育”を10年間続けてきた長崎県の教育関係者に衝撃が走りました。
この“命を大切にする教育”は、平成16年(2004年)6月におきた小学校6年生の女子児童が同級生を殺害したショッキングな「佐世保小6女児同級生殺害事件」をきっかけに、市内の小中学校で命の尊さを学ぶとり組みを続けてきたものです。
この命の尊さを学ぶとり組みは、長崎平和公園や原爆資料館を見学したり、佐世保空襲の体験者を招いて話を聞いたりすることで生命の尊さや戦争の悲惨さを学ばせようとするものでした。
その中で、悲劇が繰り返されたことに対し、長崎県の教育関係者はショックを受けました。
敢えて苦言を呈すると、長崎県の教育関係者は、この10年間、命の尊さを学ぶとり組みが、成長した子どもたちが人を傷つける行為の減少につながってきたのかを検証してきたのでしょうか?
検証の結果、人を傷つける行為は減少している中で、悲劇が繰り返されショックを受けたのであれば、ある程度、教育関係者の葛藤は理解できます。
この殺傷事件前の平成24年(2012年)の長崎県14歳-19歳人口1万人あたり少年犯罪の検挙数は62.56人(503人)で全国25位、また、非行発生率は、命の尊さを学ぶ授業がはじまる前の昭和60年(1985年)24.98で全国24位、平成2年(1990年)21.13で全国27位と順位は下回り、非行発生率は少し改善した(全般的にほぼ横一線)状況が続いているように、命の尊さを学ぶ10年間のとり組みが少年犯罪を減少させる相関性(因果関係)を確認することはできません。
つまり、いじめ問題、非行など少年犯罪は、「道徳」にもとづく「個々人の心のありよう」にフォーカスする限り、解決に至る方向性を示すことはできず、「人権」にもとづく、社会問題としてとり組む必要があります。
しかし、10年間にわたり、「命を大切にする教育」にとり組んできた長崎県の教育関係者は強いショックを受け、無力感にうちひしがれました。
長崎県に限らず、「命の授業」の多くは、“思いやり”“優しさ”といった個々人の「心のありよう」にフォーカスした道徳教育の一環として実施されています。
日本では、「道徳の授業」は、明治政府が構築した「(教育勅語にもとづく)教育制度」で実施さしてきた「道徳」の授業、昔話(絵本、童話)などに組み込まれた「道徳観」により、日本国民の隅々まで根づいています。
そのため、「差別・排除」といった人権・社会問題だけではなく、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力(緊急避妊薬、中絶薬の導入を含む)、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力(人権侵害)問題に加え、暴力被害に起因する精神疾患(PTSD、その併発症としてのうつ病、解離性障害など、リストカット・OD(大量服薬)、過食嘔吐などの自傷行為、アルコール・薬物、ギャンブル、セックス依存などのさまざまな後遺症を含む)、貧困、進学、就職(性風俗業界での就労を含む)、ひとり親家庭、ヤングケアラーとしての生活などの人権・社会問題も、すべて、「個々人(特定の家庭、特定の職場、特定の学校)の心のあり方の問題」、つまり、「個人の問題」と捉え、論議され、対策が講じられています。
個々人の心の問題として道徳観に訴える限り、これらの問題は、解決にむけた対策を講じることは不可能です。
これらの「人権侵害(暴力)問題」「人権・社会問題」に対する課題を個々人の心の問題として認識したままで、法を制定したり、法改正に至ったりすると、「法律」が限定的であったり、「法律」の解釈に抜け道があったり、「法律」が「社会システム」として機能しなかったり、「法律」が時代や現状にそぐわないまま放置されていたりする事態を招きます。
まさに、太平洋戦争敗戦から78年7ヶ月経過したいまの日本の現状を示しています(令和6年(2024年)4月1日)。
日本の人権や権利に関する教育の問題は、時に法律がそうであるように、個人の価値観や道徳性の涵養へと都合よく(容易に)置き換えられてしまうことです。
さらに、こうした人権侵害問題、人権・社会問題に対する道徳的なアプローチ、つまり、個々人の「心のもちよう」による解決、個人的関係の中での解決というアプローチは、自己救済(自助)を強調し、国などの公的機関がしなければならない諸施策を免責する危険性も孕んでいます。
つまり、国や公的機関には非(責任)はなく、それは、個人の問題と片づけるのに役立ちます。
一方で、本来、国や公的機関がしなければならないことを、個人の努力や民間機関の仕組みでなにかを成し遂げたときには、国(政権、政党、政治家)は褒め称え、「その貢献に感謝する」と表彰し、まるで「感動ポルノ」のように政治利用します。
「感動ポルノ(Inspiration porn)」とは、主に、身体障害者が健常者に同情・感動をもたらすコンテンツ(懸命になにかを達成しようとする場面)として消費されることを批判的に表現したものです。
「まじめで、頑張り屋」、「清く、正しい障害者」など特定のステレオタイプなイメージを押しつけられた障害者や、余命宣告者などの同情を誘いやすい立場の人を使い、視聴者を感動させようとする「お涙頂戴」のコンテンツを指します。
「感動ポルノ」においては、障害を負った経緯や障害による負担・障害者本人の思いではなく、積極的、前向きに努力する姿(障害があってもそれに耐え、負けずに、乗り越えようと頑張る姿)がクローズアップされます。
しかも、紹介されるのは、常に、「テレビ受け」する身体障害者に限られ、一見、健常者と判別困難である精神障害者・発達障害者がとりあげられることはほとんどありません。
国(政権、政党、政治家)が褒め称え、「その貢献に感謝する」と表彰し、まるで「感動ポルノ」のように政治利用するのは、同じように「自助」で国に貢献してくれる人を増やそうとの目論見があるからです。
これは、日本で生活する一般市民の「善意を搾取する行為」です。
この政治姿勢を示した発言が、令和6年(2024年)1月1日に発生した「能登半島地震」の復旧が遅れていることに対し、石川県馳浩知事は「3月末までに被災地に派遣された災害ボランティアは延べ4万6000人あまりで、同じ期間では東日本大震災でおよそ44万人、熊本地震ではおよそ10万人とボランティアが不足している」と嘆いています。
市民の善意(自助)を“前提”に対策案を講じるのは、根拠(裏づけ)ないあてずっぽう政策であり、それは、政策とはいえません。
しかも、復旧の遅れを市民の善意(自助としてのボランティア)が足りないと責任転嫁するのが論外です。
この市民の善意は、「個々人の心のありよう」にもとづいているので、彼らは「道徳教育」の強化が必要と訴えます。
③ DV・虐待問題、先進的なとり組みが進む欧米諸国と遅れる日本
一方、「人権教育」は、「人が自らの権利を知り、権利の主体として、それを実現するために行動する」ことが、「人間性の回復であり、社会を変えることにつながる」ようにするものです。
つまり、人権教育の目的は、「構造的に問題を把握することであり、それにもとづく社会変革」です。
「構造」とは、ひとつのものをつくりあげている部分部分の材料の組み合わせ方、また、そのようにして組み合わせてできたもの、仕組み、ものごとを成り立たせている各要素の機能的な関連のことで、「構造的」とは、ものごとの構造、仕組み、つくりに起因するありようのことです。
つまり、「人権教育」は、物事の構造、仕組み、つくりに起因する問題を把握し、その問題解決につながる社会変革を考え、行動につながるように導くものです。
決して、個人の問題にフォーカスするものではありません。
この視点に立つと、「人権」は、人類の歴史において、市民自らの手(力)で“獲得”してきたことを理解できると思います。
それは、その時々の社会体制の中で虐げられ、人としての尊厳を踏み躙られてきた人たちが、自らの人間性の回復を「人権」や「権利」という概念で表現し、権力と闘うこと(市民的抵抗、レジスタンス)で勝ちとってきたものです。
つまり、人権や権利は、「社会的」で「争議的」なものです。
例えば、女性に対するDV問題は、アメリカで、泥沼化するベトナム戦争に対する「反戦運動」「女性解放運動(ウーマンリブ運動)」に起因しますが、その1970年代以前のアメリカは、日本と同様に、男性から女性に対する暴力が正当化されていました。
しかし、1970年前半に、その状況に「No」と声をあげたアメリカの女性たちは、人権にフォーカスし、社会変革にとり組むことができたことを意味します。
その人権にフォーカスし、社会変革にとり組む動きは、ヨーロッパ諸国に広がり、世界的な運動となっていきました。
欧米諸国の高い人権意識は、「2-(4)「子どもの意見の尊重(子どもの意思表明権)」の未記載」の「『世界人権宣言』と9つの主な『人権条約』」で示しているように、1960年代-1980年代に、国連で『世界人権宣言』を踏まえた『人権条約』を数多く採択させる重要な役割を果たしました。
人権意識の高い欧米諸国は、国連で『世界人権宣言』を踏まえた『人権条約』の採択を主導してきたのに対し、日本は、国連で採択された『人権条約』を仕方なく(不本意ながら)批准・締結してきました。
そのため、日本は、「反戦運動」「女性解放運動(ウーマンリブ運動)」から50年以上経過した“いま”も、「人権」「権利」を“前提”にものごとを捉え、考え、考え、判断することができ難い社会です。
日本社会では、社会変革にとり組む動きは、徹底的に叩き、潰そうとする強烈なパワーが働きます。
その中心にいるのが、太平洋戦争敗戦後、日本の政治を担い、日本の再興を目指してきた人たち、つまり、ナショナリストで、極右・超保守の政権、政党、政治家、「はじめに。」の中で示した彼らと“共同体”といえる強固な関係を築いてきた政治支援団体、局ウイ・超保守の一般市民です。
問題は、ナショナリストで、極右・超保守の人たちは、一貫して、戦前の日本の再興(再軍備)を目指してきたことです。
ナチスを生んだドイツでは、第2次世界大戦(基本の構図はドイツ・ロシア戦争)に敗戦後、「同じ過ちはしない(二度とナチス(ヒトラー)を生みださない)」との“反省”を踏まえた国造り(政治)にとり組んできたのに対し、日本では、この“反省”なく、戦前の再興(再軍備)ありきで突き進んできた国です。
日本で、この“反省”をしてこなかった理由は、「軍国化」を進めてきたナショナリストで、極右・超保守の人たちが、ひき続き、太平洋戦争敗戦後の日本の国造りを担ってきたからです。
このことが、欧米諸国とは異なり、日本に「人権」が根づかなかった大きな要因となっています。
ナショナリストで、極右・超保守の人たちの政治姿勢、その政治姿勢の背景にある思想・イデオロギーは、「人権」と結びつきません。
一方で、アメリカの「暴力を振るわれた女性たちの運動」には、共通の“ビジョン”にもとづく、固有の“基本理念”がありました。
それは、a)被害者とその子どもの安全を確保すること、b)虐待するパートナーのもとに留まるか、去るかについての決定を含む被害者の自己決定権を確保すること、c)社会的および刑事上の制裁を通じ、DV加害者に責任を負わせること、d)被害者に対する社会的抑圧と闘い、被害者の権利を推進するための制度改革を実施することです。
b)の「被害者の自己決定権」は、子どもを守る、つまり、子どもの安全をはかることを第1にする仕組み(CPS)があってはじめて成り立つものですが、それ以前に、女性と子どもは、「家」の家父長の支持に従う前提で育てられているので、このb)の「被害者の自己決定権」をそのまま日本の仕組みにとり入れることは、被害女性と子どもの命の危険をもたらします。
日本では、(元)交際相手や(元)配偶者、職場の上司や同僚、学校の先輩や友人による執拗なストーキング被害にあったとき、警察に相談する一方で、「被害届」「告発状」の提出を躊躇し、その後、殺害されるという悲惨な事件に発展することは少なくありません。
アメリカでは、子どものいる家庭におけるDV事件では、児童保護局(CPS)に通報されます。
このとき、加害者逮捕に至らなくても、CPSが、「子どもに危険性がある」と判断したときには、子どもを裁判所の保護下に置き、加害者・被害者の親から分離させます。その間に、両親(加害者と被害者)ともに、加害者プログラムやカウンセリングなどを受け、子どもを安全に育てる環境を整えてきました。
アメリカのフェミニスト、地域活動家、性的暴行やDVを克服した被害者たちは、この共通の“ビジョン”にもとづく、固有の“基本理念”のもと、主に、「3つの目的」を掲げて対応しました。
それは、ア)被害者とその子どものための避難所と支援の確保、イ)法的および刑事司法分野での対応の向上、ウ)DVに対する一般の人々の意識改革です。
ウ)の「DVに対する一般の人々の意識改革」のとり組みのもと、DV行為は、「成人または青少年が親密なパートナーに対して行使する身体的、性的、精神的あるいはことばによる攻撃および経済的支配を含む、威圧的で攻撃的な行動パターン」と定義しました。
その後、一般の人々のDV行為に対する認識は、「親密なパートナーを支配しようとする者が、日常的に入念な方法でそのパートナーを脅迫、どう喝、操作し、身体的な暴力を加えること」、「虐待する者は、特定の方法で、あるいは、複数の方法を組み合わせて、パートナーに恐怖心を植えつけ、支配する」、「虐待する者の戦略の目的は、被害者を自分の思い通りに行動させ、その行動パターンを確立すること」、「加害者はしばしば、被害者の特定の行動を虐待の理由、または、原因とすることから、加害者によることばや身体的虐待は、そうした特定の行動を改めたり、制限したりすることを目的とする」とDVの“本質”にまで至っています。
このように、アメリカにおける「配偶者からの暴力(DV)」に対する認識は、日本の捉え方とは大きく異なり、配偶者からの虐待(DV)問題について、虐待(DV)が女性に及ぼす影響だけではなく、他の人々や社会機関にも計り知れない結果を及ぼすと先進的に捉えています。
それは、DVは、誰もが直面しうる社会、経済、健康面の問題であると捉え、全米の地域社会が、暴力の撲滅とDV被害者に安全な解決策を提供する戦略の策定を達成しつつあります。
このDVの“本質”の理解に至っていない限り、DV問題の解決はほど遠いものになります。
この視点に立つと、いま、日本に暮らす一般の人々、ならびに、保守派の政治家のDV行為に対する認識は、アメリカをはじめとする欧米諸国から少なくとも40-50年遅れていることがわかります。
極右・超保守の政治家は、「DV」的な行為は、実質的な「家」の家父長(権威者)による「懲戒」であり、「DV」は存在しないと認識しているので、論外です。
いまだに、子どもの安全をはかることを第1にする仕組み(CPSなど)が整っていない日本では、「家」を中心とする「道徳観」で、ものごとの判断基準とする人が圧倒的に多い中で、先に示したように、このb)の「個人」の「人権を尊重する」ことを“前提”に成り立つ「被害者の自己決定権に委ねる」ことは、DV被害者である女性(母親)と子どもの安全を脅かしかねない事態を招くリスクが高いというジレンマを抱えます。
欧米諸国の授業(家庭においても)では、「あなたは考えはどう?」「あなたの意思は?」「あなたはどうしたい?」に重きをおくのは、「人権」を背景にした「個」の意思を尊重する社会だからです。
「あなたは考えはどう?」「あなたの意思は?」「あなたはどうしたい?」のと意思表明(権)を学び、身につけさせない日本の教育で育ち、保守的な価値観の家庭やコミュニティなどで、「女だてらに」「生意気だ」とすり込まれて育ってきた日本の女性や子どもは、意思表明する習慣がなく、しかも、口を紡ぐ(口を閉じて話さない/黙る)ことが行動習慣となっていることが少なくありません。
こうした特殊な背景を持つ日本のDV被害者とその子ども(被虐待体験してきた児童)に「自己決定権に委ねる」ことは、大きなリスクを伴います。
しかも、DV被害者とその子ども(被虐待体験してきた児童)が意思表明をするとき、その相手が、「子どもの父親を犯罪者にするつもりですか(犯罪者にしてもいいですか)?!」、「子どもがいるんだから、がまんしたら」、「離婚したら、子どもがかわいそう」、「子どもをひとりで育てるつもり」、「どこの家庭でも、暴力はあるわよ」、「あなたにも至らないことがあったんじゃない。そこを直さないと」などと、保守的な価値観で助言(批判)し、その助言が判断を躊躇させたり、誤らせたりすることが少なくありません。
日本教育の致命的な欠陥ですが、極右・超保守の人たちにとっては、とても都合のいい状況です。
つまり、「人権」の“前提”のない日本で、「人権」を“前提”に構築している欧米諸国のDV対策にとり組むとトラブル・エラーが生じます。
そして、このことに気づいていない、支援機関、支援に携わる人たちが多く存在します。
DV/性暴力被害者支援に携わる者として、とても大きなジレンマです。
また、これは、国連で採択された『人権条約』を加盟国として批准・締結し、その『人権条約』の規定に準じ、「国内法」を制定したり、改正したりするときにも同様のトラブル・エラーが生じやすいという現状にも通じることです。
つまり、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」においても、同様のトラブル・エラーが生じやすくなっています。
(6) 子どもを懲戒する権利。被虐待体験と精神疾患発症との深い関係
① 被虐待体験(小児期逆境体験)と深い関係にあるひきこもり
平成27年(2015年)の生活保護世帯数1,623,576に対し、高齢者世帯数が802,492(49.43%)、母子世帯数が104,917(6.46%)、障害者世帯数が190,316(11.72%)、傷病者世帯数が253,374(15.61%)、合せて1,351,099(83.22%)です。
これは、全国の世帯総数(同年10月15日現在)53,331,797世帯の25.34%(全国の世帯総数の1/4)です。
障害者世帯は、82.9%が単身(世帯主の平均年齢は52.4歳)で、世帯主の障害の種類は、精神障害が49.4%、知的障害が8.1%、身体障害が42.5%で、世帯主の9.1%が入院、4.3%が施設入所です。
傷病者世帯は、78.1%が単身(世帯主の平均年齢は54.5歳)で、世帯主の傷病は、精神病が33.9%、アルコール依存症が2.8%、その他が63.4%で、世帯主の6.3%が入院、1.5%が施設入所です。
a) ヤングケアラーとひきこもり
国内で、精神疾患患者は約420万人といわれていますが、ヤングケアラーとして、その精神疾患患者の子どもたち、つまり、ヤングケアラーとなり得る子どもたちも多くの悩みを抱えています。
海外の研究結果では、「精神疾患の親を持つ子どもは、そうでない家庭と比べて精神疾患になる確率が2.5倍高い」と指摘されていますが、日本社会では、支援体制がほとんど整えていません。
精神疾患に関する否定的な意見を耳にする機会が多い子どもの多くは、「人(友人、学校園の教職員、近隣者など)に、絶対に知られたくない(「知られてはならない」と強迫観念的に)」という考えに陥ります。
つまり、ヤングケアラーとなり得る子どもは、「差別や偏見につながる意見を耳にするうち、スティグマ(負の烙印)を負ってしまう」ことが少なくありません。
この差別や偏見は、いじめにつながり、不登校・ひきこもりの大きな要因となります。
諸外国では、精神疾患の親を持つ子どもは7人に1人という研究結果もありますが、日本では実情が明らかになっていません。
アメリカでは、家族全員で精神疾患患者向けの家族会に参加し、イギリスでは、学校医が家族や兄弟のケアを担うヤングケアラー、厳しい家庭環境にいる子どもたちを把握するためのスクリーニング検査を実施しています。
b) ひきこもりと精神疾患の深い関係性
世帯主が生活を支えていることから、貧困とかかわる問題として直接論じられないのが、内閣府が23.6万人、広義を含めると69.6万人と推計している「ひきこもり」の問題です。
ひきこもりは、「自室からもほとんどでない」、「普段は家にいるが、近所のコンビニなどにはでかける」、「自室からはでるが、家からはでない」、「普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」と段階で認識され、前者の3つが狭義のひきこもり、最後の1つが広義のひきこもりとなります。
広義のひきこもりとされる「普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事のときは外出できる」ことは、「仮面うつ病(気分障害に該当しない非定形うつ病、新型うつ病)」と総称で呼ばれる人たちに共通する特性に合致します。
精神科の受診ではなく、心療内科の受診では、この「仮面うつ病(気分障害に該当しない非定形うつ病、新型うつ病)」に対し、気分障害の「うつ病」と診断し、精神治療薬が処方され、また、出社できない理由の診断書が作成されています。
内閣府の調査とは異なり、疫学調査でひきこもり数を25万5000世帯(広義のひきこもり数は46万人)と算出した厚生労働省は、「95%以上に診断名がついたとし、25%以上を発達障害が占めた」と発表しています。
この調査では、「アスペルガー症候群の人が不安障害になったり、ADHDの人がうつ病になったりすることがよくある。」、「アスペルガー症候群などのひきこもり当事者の中には、なぜ、ひきこもりから抜けださなければならないのかを理解し難い場合が多い。」と説明しています。
さらに、「発達障害も深くかかわるパーソナリティ障害(人格障害)、例えば、「回避性」は、人の前でなにかをするのが怖く、「依存性」は、他人に頼らないと生きていくことができず、責任は絶対に負わない、強迫性は、完全主義者で失敗は認められない、「受動攻撃性(拒絶性)」は、どうせなにをやっても認められないからなにもやらない、「自己愛性」は、自分に自信がないため、無理やり自分はすごいと思い、傷つくことを恐れる、「境界性(ボーダーライン)」は、虐待を受けた経験者が多く、自分探しをして、これが私だという土台を築くことができなかった。人にしがみつき、自分の思い通りに操作し続けないと、自分が空っぽで無力な価値のない存在に思えてしょうがない。「シゾイド性」は、ひとりでいるのが大好きな人たち、「妄想性」は、非常に過敏で被害的で、迷信深く魔法のような世界にいる、といったそれぞれの特性が、ひきこもりの要因となっている。」と説明し、「ひきこもりとの親和性(物事を組み合わせたときの、相性のよさ。結びつきやすい性質)がとても高い。」と指摘しています。
そして、ひきこもりの状態を、「統合失調症、気分障害、不安障害などの精神疾患の診断がつくひきこもりで、薬物などの医療的治療の優先が不可欠となるものを「第1群」、発達障害の診断がつくひきこもりで、特性に応じた精神療法的アプローチや教育的な支援が必要となるものを「第2群」、パーソナリティ障害(人格障害)や薬では効果のない不安障害、身体表現性障害(痛みや吐き気、しびれなどの自覚的ななんらかの身体症状があり、日常生活が妨げられており、自分でその症状をコントロールできない)、同一性の問題などによるひきこもりの人たちで、精神療法やカウンセリングが中心となるものを「第3群」と分類」しています。
不安障害やうつ病(気分障害)、総称としての仮面うつ病(非定型うつ病)、そして発達障害の一部、人格障害(パーソナリティ障害)の人たちに共通しているのが、「低い自尊心と自己肯定感」であることから、否定と禁止のメッセージを含むことばの暴力(過干渉・過保護、教育的虐待を含む精神的虐待)を浴びせられている、つまり、暴力のある家庭環境で育ってきたことが発症原因となり、同時に、ひきこもりの原因となっています。
国の政策として、DV対策、児童虐待対策を放置してきた結果が、認知症患者数世界1位、15歳以上人口の3.77%が精神疾患者で、生活保護世帯、高齢者世帯、母子世帯、障害者世帯の合計は、全世帯数の1/4を占め(平成27年(2015年))、ひきこもり数は69.6万人(疫学調査による46万人の95%以上に診断名がつき、25%が発達障害)、3.44日に1人、男性に女性が殺害され、国民の70%程度が子どもに対する「しつけ(教育)と称する体罰」を容認しているという“いまの日本”をつくってきたことになります。
こうした深刻な社会病理をつくりだしてきた日本政府の姿勢と施策は、国家犯罪に類するといえます。
② 数字に示される被虐待体験(小児期逆境体験)を起因する社会病理
日本では、明治29年(1896年)の制定から令和4年(2022年)10月14日に「子どもに懲戒する権利(民法822条)」が削除されるまでの126年間、5-6世代の育児で、「しつけ(教育)と称する体罰(身体的虐待)」が繰り返されてきました。
「1.第1の「法案」『家族法(民法)』の改正(離婚後の共同親権制度)」の「126年間続いた「子どもを懲戒する権利」。いまも7割が「体罰」を容認する異常」の中で述べているように、グローバルスタンダードの規定に沿うと、程度の差はあれ、日本で生活する市民の約7割は、被虐待体験者(小児期逆境体験者)となり、同時に、「加害トラウマ」として、5-6世代の世代間でひき継がれてきました。
これは、国が、「子どもに懲戒する権利(民法822条)」のもとで、親の子どもに対する体罰(身体的虐待)を認めてきた虐待の世代間連鎖です。
以下の記述の根拠(エビデンス)となる「長期間、慢性反復的(常態的、日常的)な被虐待体験」が、どのようなメカニズムでPTSD、その併発症としてのうつ病、パニック障害、解離性障害など発症させるのか、虐待行為としての「ネグレクト」「身体的虐待(しつけ(教育)と称する体罰を含む)」「性的虐待」「心理的虐待(面前DVを含む)」が、脳のどの部位にダメージ(萎縮・肥大)をもたらし、そのダメージがどのような影響をもたらすのか(妊娠期の女性がDV被害を受け、胎児期の中枢神経系の発達にもたらす影響を含む)については、レポート『別紙2d(簡易版)DV・虐待・性暴力被害。慢性反復的トラウマ体験に起因する後遺症(A4版192頁)』で詳述しています。
ここでは、「子どもを懲戒する権利(民法822条)」にもとづく「被虐待体験」が要因となる「精神疾患者数」「認知症患者数」「生活保護世帯数」「ひきこもり数」を示します。
日本は、ⅰ)認知症患者数は世界1位(PTSDの発症者に認められる「海馬」の萎縮は、アルツハイマー型認知症の高い発症リスクをもたらします。妊娠している女性がDV被害を受け、脳の血管の血液脳関門が未発達な胎児が曝露し、中枢神経系の発達を阻害させる「コルチゾール」は、長期間、慢性反復的(常態的、日常的)な虐待被害、DV被害は、大きな発症リスクとなります)で、ⅱ)15歳以上人口の26.50%(15歳人口の国民の4人に1人)が精神疾患者で、ⅲ)生活保護世帯、高齢者世帯、母子世帯、障害者世帯の合計は、全世帯数の1/4を占め(平成27年(2015年))、ⅳ)ひきこもり数は69.6万人で、疫学調査による46万人の95%以上に精神疾患、そのうち25%が発達障害(器質性障害をもたらす妊娠した女性がDV被害を受け、脳の血管の血液脳関門が未発達(生後6ヶ月まで)な胎児はコルチゾールに曝露し、中枢神経系の発達が阻害されることが発症のひとつの要因となっている)と診断されています。
a) 精神疾患の患者数
平成26年(2014年)、厚生労働省の患者調査では、認知症を含む精神疾患を抱える患者は全国で約392万人と推計されています。
この数字は、同年10月15日現在の人口1億2708万人の3.09%、人口1万人あたり309.81人(54.3人の増加)、100人に3.10人(0.54人の増加)です。
うつ病、双極性障害(躁うつ病)などの気分障害、統合失調症(精神分裂病)、不安障害、アルツハイマー型認知症、血管性認知症、てんかん、薬物・アルコール依存症などの患者数は、顕著な増加傾向にあり、6年前の平成20年(2008年)に比べて68.7万人と激増し、その増加率は1.21と約20%に及びます。
うつ病や双極性障害(躁うつ病)などの気分障害がもっとも多く112万人(16.2万人の増加、増加率1.26)で、続いて、統合失調症(精神分裂病)で77万人(5.7万人の増加、増加率1.08)となっています。
「気分障害(うつ病、躁うつ病、気分変調症等)」の総患者数は、各年で実施される労働厚生省の『患者調査』によると、平成8年(1996年)は43.3万人、平成11年(1999年)は44.1万人でしたが、平成14年(2002)年に71.1万人、平成17年(2005年)に92.4万人、平成20年(2008年)に104.1万人となり、9年間で2.4倍に激増しました。
その後、平成26年(2014年)に111.6万人、平成29年(2017年)に127.6万人と増加し、令和2年(2020年)には、172.1万人に激増しました。
つまり、「気分障害(うつ病、躁うつ病、気分変調症等)」の総患者数は、26年間で、約4倍(3.98倍)に激増しました。
令和2年(2020年)の総患者数172.1万人は、同年15歳以上人口11,111.5万人の1.55%です。
なお、全体の精神疾患患者の約40%(156.8万人)が、「子育て世代」ともいえる25-54歳が占めています。
このことは、「ヤングケアラー」の問題と深く関係します。
かつて、「一度入院すると、生きてでられない」と比喩されるなど、日本の精神病院では長い入院生活を余儀なくされます。
入院患者約26万人、10年以上の入院患者約4万6千人の日本は、世界の中で「精神科病院大国」として知られ、日本の精神科病院の入院ベッド数は、OECD(経済協力開発機構)加盟38ヶ国にある精神科の入院ベッド数の約4割を占めています。
また、平成9年(1997年)に1,789億円だった「精神神経疾患治療剤」の市場は、平成16年(2004年)には3,127億円と1.75倍に膨れあがっています。
ここには、日本で心と脳の研究が盛んになったこと、加えて、病院経営として利益追求のために、不必要な薬を処方しているという背景があります。
b) 摂食障害(拒食症・過食症)の患者数
死亡率は、精神疾患の中でもっとも高い約5%の「摂食障害(拒食症・過食症)」の患者数は、国立精神・神経医療研究センターの推計で、230万人といわれる一方で、医療機関を受診している患者数は1年間で推計22万人(9.57%)に留まっています。
c) 自殺者数
日本における15-19歳、20-24歳の死因の原因の第1位は「自殺」で、第2位が不慮の事故、25-29歳、30-34歳、35-39歳も死因の第1位は「自殺」で、第2位は癌です。
令和4年(2022年)の自殺者数は21,881人、19歳以下796人で、そのうち、小中高生の自殺者数は514人です(19歳の自殺者数282人)。
平成25年(2013年)- 令和4年(2022年)の10年間で年間自殺者は5千人近く減少した一方で、10歳代の自殺者数は、平成25年(2013年)546人から令和4年(2022年)の782人と1.43倍に増加しています。
平成30年(2016年)に日本財団が行った「自殺意識調査」によると、過去1年以内に53.5万人(男性26.4万人、女性27.1万人)が自殺未遂を経験しています。
女性の49%、男性の37.1%が「4回以上、自殺未遂を経験した」と回答しています。
そして、25.4%が「本気で自殺したいと考えたことがある」と回答し、そのうちの6.2%が「現在も自殺を考えている」と回答しています。
対象年度は異なりますが、自殺者数2.2万人に自殺未遂者53.5万人を加えると、1年間に55.7万人が自殺企図したことになります。
d) アルコール・薬物、ギャンブル依存者数
平成25年(2013年)に実施された「成人の飲酒行動に関する全国調査」では、「国際疾病分類第10版(ICD-10)」の診断基準にもとづく「アルコール依存症者」の有病率は、男性の1.9%(94万人)、女性の0.2%(13万人)、全体で0.9%と推定され、推計数は男女合わせて107万人となっています。
しかし患者数は、外来9万6千人、入院2万6千人、合計12.2万人(以上、平成28年(2016年))なので、治療に至っているのは11.4%です。
厚生労働省は、ギャンブル依存症は70万人と推計しています。
しかし、患者数は、外来3千人、入院260人、合計3260人(以上、平成28年(2016年))なので、治療に至っているのは、僅か0.47%です。
平成29年(2017年)に実施した一般住民を対象とした全国調査では、覚醒剤や大麻といった薬物を少なくとも1回以上使ったことがある国民(15歳から64歳が対象)は、全国で約216万人と推計されています、
もっとも多いのが大麻で、使用者人口は、全国で約133万人(61.57%)と推計されています。
薬物依存症の患者数は、外来6.5千人、入院1.4千人、合計7.9千人(以上、平成28年(2016年))で、治療に至っているのは、僅か0.37%です。
その大きな要因は、もっとも多い大麻使用者が治療に至っていないからです。
平成30年(2018年)に発表された『全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査』は、過去1年以内に使用歴がある1149例を対象に実施された調査で、39.3%(453例)が覚醒剤、29.9%(344例)が睡眠薬・抗不安薬、9.1%(105例)が一般用医薬品(咳止め、風邪薬など)、5.9%(68例)が多剤、5.6%(64例)が大麻、4.3%(49例)が揮発性溶剤、1.2%(14例)が危険ドラッグ、0.7%(8例)が鎮痛薬(非オピオイド系)、0.6%(7例)が鎮痛薬(処方オピオイド系)、0.4%(5例)がADHD治療薬、0.3%(3例)がヘロイン、0.3%(3例)がヘロイン、2.4%(28例)がその他となっています。
e) 認知症患者数
令和2年(2020年)の認知症の患者数は、約630万人で、世界1の患者数となっています。
「認知症」は、記憶の働きや思考力、判断力をはじめとする認知機能が低下し、日常の生活に支障をきたす症状のことで、ア)脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など脳の血管におこるもの(脳血管性)、イ)アミロイドβたんぱくや、タウたんぱくという異常たんぱく質が脳に蓄積し、脳の神経細胞にダメージを与えるもの(アルツハイマー型)、ウ)パーキンソン病をひきおこす物質でもあるレビー小体という異常なたんぱく質が神経細胞にたまるもの(レビー小体型)があります。
厚生労働省が実施し、公表した『2019年国民生活基礎調査』によると、介護保険制度で要介護になった原因は、「認知症」が18%ともっとも多く、「脳血管疾患(脳卒中)」が16.0%、「高齢による衰弱」「骨折・転倒」が13%となっています。
男性でもっとも多いのが、「脳血管疾患(脳卒中)」の24.5%で、女性でもっとも多いのは、「認知症」の19.9%です。
3.「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」の懸案事項-ⅰ)ⅱ)ⅲ)
(1) 日本で「離婚」するには
① 離婚方法と離婚事由
日本では、ア)世界で唯一の特殊な制度である夫婦が同意して署名し、「協議離婚届書(離婚届)」を戸籍係に提出する方法(協議離婚(民法763条)/「離婚」の87.8%)、イ)家庭裁判所の調停の場で離婚の合意をする方法(調停離婚(家事事件手続法268条)/同9.7%)、ウ)イ)の夫婦関係調整(離婚)調停でまとまらないとき、家庭裁判所が離婚の審判をする方法(審判離婚(家事事件手続法284条・同法297条)/同0.03%)、エ)イ)の夫婦関係調整(離婚)調停でまとまらず、『民法770条1項』に定める「離婚事由」があるとき、家庭裁判所の判決で離婚が命じる方法(判決離婚(人事訴訟法37条)/同2.4%)のいずれかの方法で、「離婚」を成立させます。
家庭裁判所のもとで離婚の有無が合意・判断されるイ)ウ)エ)では、「1-(2)協議離婚制度(民法763条)と離婚事由(民法770条)の規定」で示している『民法770条1項』で定める「離婚事由」に該当していることが必要となります。
・離婚調停・裁判離婚における「離婚事由」はすべてDV事案に絡む
『協議離婚制度』では、離婚事由は必要ない(問われない)ので、他国と異なり、日本では、離婚事由として、「DV行為としての暴力」がどの程度の割合を占めるのか正確なデータは存在しません。
日本では、上記のとおり、離婚する夫婦の僅か約1割が、家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)調停(以下、離婚調停)」を申立てることになるが、家庭裁判所が用意している『申立書』に記述されている「申立ての動機欄」には13の離婚動機(項目)が用意されています。
「動機」とは、離婚を申立てる理由、つまり、『民法770条』の離婚事由のことです。
そこで、その動機の13項目について、『配偶者暴力防止法』で規定する「DV行為としての暴力」をあてはめてみると、「3.暴力をふるう」は身体的暴力、「8.精神的に虐待する」「13.その他(束縛する・育児に協力しない・子どもを乱暴に扱う)」は精神的暴力、子どもへの虐待、「3.異性関係」は性的暴力、「12.生活費を渡さない」「6.浪費する」は経済的暴力(精神的暴力に含まれる)となります。
つまり、『離婚届』に記載されている「離婚動機」の13項目のうち6項目は、そのまま「DV行為としての暴力」を示しています。
次に、家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)調停」を申立てた女性が、離婚理由としてあげた1-10位までを順を追って見ていきます。
1位は、「性格が合わない(性格の不一致)」です。
この抽象的な「性格が合わない(性格の不一致)」は、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正(共同親権法案)」が成立・施行されると、この「性格が合わない(性格の不一致)」で離婚した子どもの父母は、「2-(2)離婚後の親権の決定」のa)「父母の協議(協議離婚(民法763条))で、双方または一方を親権者と定める」との規定による話し合いが成り立たず、b)「父母が合意できないときには、家庭裁判所が判断する」ことになることが想定されます。
そして、「性格が合わない(性格の不一致)」で離婚理由は、同c)b)では、「共同親権を認めると子どもに対する虐待行為、元配偶者に対するDV行為などが生じ、子の利益を害する」と認められるときには、父母の一方を親権者(単独親権)と定めなければならない」との定めに該当しないことから、b)により、家庭裁判所は、「共同親権」と判断することになります。
そして、この「共同親権法案」が成立・施行すると、共同親権下で、子どもの父母の話し合い(協議)が、DV行為のトリガーとなり得て、DV被害の増加も懸念されることから、別途「2-(5)離婚理由「性格の不一致」は、離婚後の話し合いを困難に」で説明します。
2位は、「暴力(身体的暴力)をふるう」です。
婚姻破綻の原因である以前に、身体的暴力は、「暴行罪(刑法208条)」「傷害罪(刑法204条)」を適用できる犯罪行為です。
夫婦間で、一方の配偶者に「身体的暴力」が加えられているときには、身の安全を確保することを優先させ、安全が担保されている状況下で離婚調停を進める必要があります。
そこで、婚姻破綻の原因が、「配偶者からのDV行為である」ときの離婚調停では、申告により、双方の部屋を分け、それぞれの部屋を2名の調停委員が相互に訪れて話をしたり(仲介する)、調停が終わったあとは、加害者である配偶者が帰ったのを確認してから被害者が退出したりするなどの対応がとられます。
この措置は、「精神的暴力」「性的暴力」があり、DV被害者である配偶者が、もう一方のDV加害者である配偶者に恐怖を覚え、直接の話し合いが困難と判断されたときにも適用されますが、小規模な家庭裁判所や地方都市の支部では、部屋を分ける対応ができないこともあります。
3位の「生活費を渡さない」は、「経済的暴力(精神的暴力に含まれる)」になるので、2位の身体的暴力とともにDV行為です。
4位の「精神的に虐待する」は、「精神的暴力」となるので、DV行為です。
5位の「異性関係」は、不特定多数の人物と性的関係にあったり、特定の人物との性的関係に至っていたり、愛人に子どもを設けたり、性風俗などを利用する(買春行為に至る)などが該当します。
こうしたふるまいは、「性的暴力」としてDV行為に該当します。
また、不特定多数の人物と性行為に及び、その性行為時に避妊具を使用しないことは、性感染症に罹患するリスクがあります。
そのため、夫婦間の性行為において、一方の配偶者が、性感染症に罹患していることを知りながら一方の配偶者と性行為に及び、性感染症を罹患させたときには、『傷害罪(刑法204条)』を、HIV感染者のときには『殺人罪(刑法199条)』を適用(いまは治療薬の発達で完治できる疾患になってきているので、上記の『傷害罪』の適用と考えるのが妥当です)できます。
感染者数が急速に拡大している「梅毒」に感染していることを知りながら、コンドームをつけない性交、オーラルセックス(フェラチオ)は、感染原因となることから『傷害罪(刑法204条)』、AV(アダルトビデオ)の影響の大きい顔射は『暴行罪(刑法208条)』、その顔射で精液が眼や口腔内にはいったときには『傷害罪(刑法204条)』の適用ができます。
また、「子宮頸がん」の発生原因となる性交によるHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染は、同様に、オーラスセックス(フェラチオ)が「喉頭がん」の発症原因となります。
6位は「浪費する」で、ギャンブルに入れ込んだり、遊興や趣味に散財したり、贅沢品や洋服などを必要以上に購入したりする行為が含まれます。
家庭の家計を顧みず、日々の生活に支障がでるような浪費や散財がおこなわれているのであれば、3位の「生活費を渡さない」と同様に、「経済的暴力(精神的暴力に含まれる)」ということになり、DV行為に該当します。
7位の「家庭を捨てて省みない」は、a)愛人などの家で生活して帰ってこないだけでなく、b)毎日飲んで帰ってくる、c)子どもの面倒をまったく見ない、d)仕事をできない理由がないのに仕事をしないなど、健全な結婚生活を続けることが困難だと思われる状況も該当します。
a)愛人などの家で生活して帰ってこないは、DV行為としての「性的暴力」に該当し、b)飲んで帰ってきて大声で怒鳴りつけたり、罵倒したりするのであれば「精神的暴力」になり、d)「仕事をして欲しい」との訴えに激怒して、暴行を加えたときには、「身体的暴力(暴行)」になり、b)「少しは子どものことを見てほしい」の訴えに、不機嫌になったり、無視したり、子どもが乳幼児で手がかかるときに、休日にひとりで遊びに行ってしまったりするのは「精神的暴力」になり、また、d)仕事をしなかったり、生活費を入れなかったりするのは「経済的暴力(精神的暴力に含まれる)」になります。
細かく落とし込んでいくと、その多くがDV行為に該当します。
8位は「異常性格」です。
ア)「民法770条1項」に定める「離婚事由」の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」の「精神病」は、「精神障害者保健福祉手帳(傷害者手帳(精神))」の対象となる日常生活に支障を及ぼす重度の「統合失調症(精神分裂病)」「気分障害(双極性障害(躁うつ病)、うつ病など)」「中毒精神病(精神作用物質の摂取を起因)」「てんかん」「器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害、発達障害)」などの精神疾患の発症などを想定しているのに対しているのに対し、この「異常性格」のひとつの想定は、イ)ペドファリア(小児性愛)、性的サディズム、性的マゾヒズム、窃視症(のぞき、盗撮)、窃触症(さわり魔、痴漢)、露出症などの「パラフィリア(性嗜好障害)」です。
「パラフィリア」を起因とする「DV行為としての性的暴力」は、グループセックスへの参加、SM行為など望まない性行為を強いたり、売春を強要したり、盗撮をしていたり、盗撮した画像や映像をネットの掲示板などに投稿したり、ポルノ中毒で、ポルノ映像で行われている顔射に及んだり、性具を使用したりするなど、意に反する性行為を強要するなどが該当します。
つまり、DV行為としての「性的暴力」は、「性的不調和」に該当します。
「異常性格」のもうひとつの想定は、極度の「マザコン(マザーコンプレックス)」、「ファザコン(ファザーコンプレックス)」で、これらも「性的不調和」に該当すると解釈されます。
極度のマザーコンプレックス、ファザーコンプレックスとは、裏返せば、親の過干渉や過保護、いき過ぎた教育(教育的虐待)という“支配”のための暴力を受けて育ち、いまだに、親の支配下にある状況を意味します。
そのため、配偶者には、「親のいうなり」、「親の指示(同意)がなければ、なにも決められない」などと不満が溜まり、あまりにもひどいと感じたときには、親子関係は“異常”と認し識します。
一方で、一方の配偶者である妻が、自分の母親がしてくれていたようにできないと「母親はこうだった。なぜ、お前はできないんだ!」と母親と比べて否定したり、非難・批判したり、侮蔑したり、卑下したりすることばの暴力を浴びせる(精神的暴力)、激怒して、物を投げたり、叩きつけたりするのは、いうまでもなく、DV行為としての精神的暴力(一部、身体的暴力)です。
マザコンだけれど、実質的な「家」の家父長(権威者)を自認する配偶者であるときには、「懲戒」としての正しい行為、つまり、「しつけ(教育)と称する体罰」として、殴る蹴るといった苛烈な「身体的暴力」が加えることが少なくありません。
自身の配偶者に対するDV行為を「懲戒」と認識しているDV加害者は、「僕は、本当は殴りたくないんだ! でも、君が僕を傷つけたんだから仕方ない!」、「僕は、君に変わってほしいだけなんだ!」という自分勝手な(自分だけに都合のいい)理屈で、自身の行為を正当化します。
背景にあるのは、母親による過干渉・過保護による「支配された」という被虐待体験(小児期逆境体験)で、これも、重篤なトラウマ体験となり、その重篤なトラウマ体験が、ミソジニー(女性に対する憎悪、嫌悪、差別意識)をもたらし、女性に対する加害行為(DV行為としての性的暴力を含む、レイプなどの性暴力)にいたる大きな要因となります。
この加害行為の背景となるトラウマは、「加害トラウマ」と呼ばれます。
自身が、慢性反復的(常態的、日常的)に、親から「しつけ(教育)と称する体罰」を加えられ、その行為について、親に「お前の(将来の)ため」、つまり、「お前に対する愛情」といいきかされて育っています。
そのため、自分は、愛情を持った親と同じことをしている、つまり、愛情にもとづく正しい行為と認識していると認識しています。
この認識は、暴力のある家庭環境で生き延びるために身につけた思考・行動習慣、つまり、暴力のある家庭環境でしか通用しない論理であることから、「認知の歪み(間違った考え方の癖)」と呼ばれます。
子どもに対して「懲戒(しつけ(教育)と称する体罰)」、つまり、身体的虐待を加えている親の多くも、同様に認識しています。
この問題は、126年間、5-6世代の育児において、「親権」としての「子どもを懲戒する権利(民法822条)」を認めてきた歴代の日本政府の重大な責任といえます。
また、実家に帰省したとき、親の前で、妻が自分の意見や考えを口にしたのを発端に、「俺に恥をかかせやがって!」とDV行為のトリガー(ひき金)になることも少なくありません。
「家庭を築き、家の主(あるじ)として立派に家を指揮っていることを親に示したい(見せたい)」、つまり、「親に認められたい」といった強迫観的な感情(承認欲求)が、帰省中の些細なことば遣いやふるまいが「なっていなかった!(恥をかかせた)」と苛烈な暴力行為につながります。
こうした状況下でのDV行為は、夫婦内で解決しようとしても、絶対君主として君臨している父親(義父)、一見、好意的に耳を傾けているように見えても、「息子は悪くない」という“前提”で、「家」の面子・世間体を考え離婚騒ぎにならないための後始末(尻拭い)役、暴力回避の助言者役を担おうとしてくるDV加害者である配偶者の母親(義母)やきょうだいにより、DV事案は、事態が複雑になり、深刻になっていきます。
息子が精神的な問題を抱えていることを自覚していても、その事実を受け入れない母親には、息子の生贄としての妻(女性)をあてがっておきたい心理が働くことが少なくありません。
なぜなら、息子の暴力的な言動やふるまいに恐怖を覚えていて、自分に向かう怖れを回避したいからです。
このときの母親と同じ回避行動は、絶対君主化したきょうだい(特に、兄や弟)に対する母親と同性の姉や妹(異性の兄や弟は、放っておけ、関係ないと同じ回避であっても距離を置く姿勢を示します)にも認められ、主に2つの回避行動を示します。
ひとつは、自身が、夫からのDV行為に耐えてきた経験を踏まえ、息子の機嫌を損ねず、怒りださないための方法を伝授するなど、「あなたが変わることで、夫婦関係は継続できる」といい含めることです。
「それで、怖い(痛い)思いをしなくてすむのなら」と救いの声に聞こえたDV被害者は、「私はあなたの味方である」ことを装う姑(時に、姉や妹)と、その姑(時に、姉や妹)を頼りにする嫁という構図の新たな関係が構築されます。
もうひとつは、「息子は、母親思いの優しい子で、これまで、暴力的な行為に至ったことはない。」、「あなたと結婚してから息子は変わった! あなたに問題がある。」と非難したり、侮蔑したりする(以上、直接ことばで表現しなくても、無視するなど態度やふるまいを含む)つまり、嫁を標的(共通の敵)とする行為を示すことで、息子に従順である姿勢を見せることです。
「問題(悪いの)は嫁(妻)のあなた!」と徹底的に糾弾したり、さまざまな嫌がらせに及んだりします。
そのため、家の嫁としてふさわしくなるための「嫁のしつけ直しをする役割」の主体が、息子から母親(義母)にバトンタッチされるときがあります。
その結果、「DV事案」では、妻は、義母に対して強い反発心や怒りの感情を示すようになり、夫のDV問題が、嫁と姑の問題にすり替わっていることがあります。
日本特有のDV問題として、配偶者間の個人の問題ではなく、「家」の問題として、DV加害者である配偶者の親が絡み、問題をより複雑にしていることが少なくありません。
このことを踏まえると、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」で、面会交流の対象者が、「子どもの監護者でないもう一方の親に加え、その「親の祖父母」まで拡大されていることは、大きな問題といえます。
9位の「酒を飲み過ぎる」は、7位の「家庭を顧みない」の毎日のように飲み歩いて泥酔して帰宅する、家庭内でも家計に負担を与えるほど飲むことと重なります。
また、飲むと暴れる、いわゆる「酒乱」による暴言や暴行に至っているときには、DV行為そのものといえますが、アルコール依存症=“酒乱”ではなく、アルコール依存症にもとづくDV行為(身体的暴力)は8%程度とされています。
ただし、「阪神淡路大震災(平成7年(1995年)1月17日)」や「東日本大震災(平成23年(2011年)3月11日)」などの自然災害にあい、長い避難生活を余儀なくされると、DV、児童虐待、レイプなど性暴力(被災地・避難所ではグルーミング、エントラップメント型の性犯罪が増加します)、自死、アルコール依存・ギャンブル依存が増加します。
なにもかも失ったやるせなさ・哀しみ、怒りの感情は、時に、配偶者である妻や子どもに向かいDV行為・児童虐待行為となり、なにもかも失ったやりきれない思いを忘れようとアルコール飲酒量が増え、また、避難先で、知人も少なく、なにもすることがないことがパチンコ店に入り浸るきっかけとなります。
そして、アルコールの飲酒量が増えたことで、からだを心配するひとこと、パチンコ店に入り浸り家庭を顧みなくなったこと、お金の浪費がひどくなったことに対する苦言・非難するひとことが、苛烈なDV行為を招くトリガー(ひきがね)となります。
そのため、被災地域では、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の自己投薬といわれるアルコール依存症・ギャンブル依存症が増加し、その増加に比例するように、DV、児童虐待が増加し、その結果、離婚の増加、10-30年後の糖尿病の増加につながります。
グルーミング、エントラップメント(型)は、性暴力に及ぶ者の主な手口のことで、ⅰ)親しさを装い、手懐け、断り難い状況をつくりだす手法を「グルーミング」、ⅱ)ことばでの威圧や借りをつくらせるなどの圧力(パワーハラスメントなど)により、不平等・非対等な関係を巧みに築き、あらがえない状況に追い込んで、性行為に持っていけるように罠を仕掛ける「エントラップメント(型)」といいます。
ⅰ)ⅱ)の性暴力は、主に、ア)13歳以下の幼児・児童を狙う「ペドファリア(小児性愛者)」によるもの、イ)学校園や塾・習いごとなどに通う児童・生徒を狙う教師や指導者によるもの、が、その児童・生徒を狙うもの、ウ)イ)の学校園や塾・習いごとの教師や指導者に加え、先輩、職場の上司や取引先、宗教(伝統・新興、カルトの区別なく)の教祖や指導者によるものに分かれます。
デートDVでは、ⅰ)とともに、DV加害者が、交際初期に巧妙に仕掛ける罠として、ⅲ)ラブボミング(愛の爆弾)があります。
「ラブボミング」は、短期間に猛烈なアプローチをし、まるで、相手が自分のことを「ひとめぼれ」したかのように仕向けていくものです。
結婚詐欺師は、このⅲ)とⅰ)を駆使しますが、「加害トラウマ」としてDV行為に至る交際相手や配偶者の一定数にも、同様の手口が使われ、ⅱ)はその仕上げとして駆使し、逃げられない状況をつくりだしていきます。
心理的虐待としての「脅すしつけ(教育)」「恐怖による支配」、つまり、「スケアード・ストレート」は、「1.第1の「法案」『家族法(民法)』の改正(離婚後の共同親権制度)」の「126年間続いた「子どもを懲戒する権利」。いまも7割が「体罰」を容認する異常」の中で述べているように、「恐怖によるコントロールの「スケアード・ストレート」で育った被虐待体験をしてきた人は、人の嘘、つくり話、戯言に対する心理的な障壁が低く、人を騙したり、人に騙されやすかったりする傾向があり、「グルーミング」「エントラップメント」「ラブボミング」に対する障壁が低く、慢性反復的(常態的、日常的)な性暴力被害を受けやすくなります。
10位の「性的不調和」は、セックスレスが想定されていますが、8位の「異常性格」の中で示しているように、望まない性行為を強要されたり、特異な性的嗜好を強要されたりする行為も含まれます。
これらの行為は「性的暴力」そのもので、DV行為です。
このように、離婚調停に及んだ妻が離婚理由としてあげている上位2-10位はすべてDV行為に含まれ、1位の「性格が合わない性格の不一致」は、DV行為を招くトリガー(ひきがね)となります。
調停・裁判を介して離婚をした女性であっても、1位-10位にあげた離婚理由について、「DV行為としての暴力」、「DV行為を招くトリガー(ひきがね)」と正確に理解している人はどのくらいいるのでしょうか?
例えば、家庭裁判所に「婚姻破綻の原因は、配偶者からのDV行為である」との離婚理由で夫婦関係調整(離婚)調停を申立て、「DV行為で精神的苦痛を被った」ことに対する“損害賠償金(慰謝料)”を請求するとき、被った精神的苦痛の程度は、どのようなDV行為を、どれくらいの期間、どれくらいの頻度で加えられてきたのかなどで判断されます。
つまり、どのような行為が、「DV行為としての暴力」に該当するのか、なにが、「DV行為を招くトリガー(ひきがね)」になっていたのかなどを正確に知らなければ、被った精神的苦痛の程度を主張できません。
また、夫婦間に子どもがいるときの「監護者指定の審判(調停)」においても、どのような行為が、「DV行為としての暴力」に該当するのか、なにが、「DV行為を招くトリガー(ひきがね)」になっていたのかなどを正確に知ることは重要な意味を持つ。
なぜなら、子どもから見て、両親間に「DV行為としての暴力」があるとき、つまり、子どもが両親間のDV行為を見たり、聞いたり、察したりする状況は、「面前DV」といい、『児童虐待防止法』で定める「心理的虐待」に該当することになるからです。
つまり、両親間(夫婦間)にDV行為があるときには、その子どもは等しく「被虐待体験者(児)」となります。
このことは、本国会で成立を目指している「離婚後の共同親権導入」の「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」において、重要な意味を持ちます。
なぜなら、「2-(2)離婚後の親権の決定」のc)で、b)の家庭裁判所は、「共同親権を認めると子どもに対する虐待行為、元配偶者に対するDV行為などが生じ、子の利益を害する」と認められるときには、父母の一方を親権者(単独親権)と定めなければならない」とし、同d)で、既に、離婚に至っている父母に対しても適用される、つまり、「いま、離婚し、子どもの監護者(単独親権者)でない一方の親との間で、c)を除き、a)b)で、子どもの監護者でない一方の親が、子どもの「共同親権者」となる可能性があるからです。
「DV行為としての暴力」「児童虐待行為としての暴力」、それらの暴力行為を招くトリガー(ひきがね)を正確に知ることで*3、「子どもに虐待行為としての暴力を加えた加害者は、監護者・親権者として不適切である」とその正当性を主張することができます。
*3 「DV行為、虐待行為の規定に対する正確な知識に加え、適用できる刑法、判例などの知識」については、レポート『別紙4b(簡易版) 「DV・虐待行為としての暴力」の規定と適用される法律(A4版・・頁)』で詳述しています。
② 離婚後の氏(姓)の変更
日本は、世界唯一の『夫婦同姓制度(民法750条、および、戸籍法74条1号)』があり、令和3年(2021年)に婚姻した夫婦の501,138組のうち「夫の名字」を選択したのが476,088組(95.0%)です。
離婚すると、原則、「原則復氏(旧姓に戻る)」ことになります(民法767条)。
ただし、離婚の日から3ヶ月以内に、市区町村役場に「婚姻時の氏を称する届け」を提出することで、婚姻時の姓を名乗り続けることができます。
次に、離婚後の子どもの姓です。
父母が離婚し、父母のいずれかが、婚姻前の名字(旧姓)に戻ったときでも、子どもの名字は、父母の婚姻時のままです。
離婚後、子どもの監護者が婚姻前の名字(旧制)に戻り、子どもの名字を子どもの監護者に合わせて変更するときには、家庭裁判所の許可が必要となります。
(2) 離婚後の親権の決定
令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)改正案(共同親権法案)」では、離婚後の親権は、a)「父母の協議(協議離婚(民法763条))で、双方または一方を親権者と定める」と規定し、b)「父母が合意できないときには、家庭裁判所が判断する」と定め、c)b)では、「共同親権を認めると子どもに対する虐待行為、元配偶者に対するDV行為などが生じ、子の利益を害する」と認められるときには、父母の一方を親権者(単独親権)と定めなければならない」と定めています。
加えて、d)既に、離婚に至っている父母に対しても適用される、つまり、「いま、離婚し、子どもの監護者(単独親権者)でない一方の親との間で、c)を除き、a)b)で、子どもの監護者でない一方の親が、子どもの「共同親権者」となる可能性があります。
つまり、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)改正案(共同親権法案)」は、“いま”婚姻関係にある夫婦、“これから”婚姻関係に至る可能性のある人たちだけの問題だけではなく、“これまで”に離婚し、同法の施行時に未成年(18歳未満)の子どものいるひとり親すべての人にかかわる問題です。
・「離婚条件」として、「共同親権」の選択を強いられる可能性
DV事案で、『協議離婚(民法763条)』であるとき、「共同親権に応じなければ、離婚しない」と脅され、離婚するために、意に添わない共同親権に至る可能性があります。
DV被害者が、「いまこの瞬間、殴られたり、蹴られたりするからだの痛み、絶望的な精神的な苦しみから逃れられるなら(離婚できるなら)、共同親権でもなんでもいい」と判を押し、結果、DV加害者が、「お前が自分の意志で判を押した(共同親権に合意した)」と正当性を主張することは容易に想像がつきます。
この点については、議論すらされていません。
DV事案では、子どもを守るために離婚を決意したはずが、子どもは、面会交流の実施など、離婚後も延々と続く父母の紛争に巻き込まれることで、子の福祉(利益)も害されるリスクがあります。
なぜなら、DV加害者の一定数は、離婚後もあらゆる機会を捉え、子どもを通じた加害を繰り返すからです。
この行為は、『配偶者暴力防止法』で規定される「DV行為としての精神的暴力」に含まれる「子どもを利用した暴力」に該当します。
この問題は、アメリカでは、「ポスト・セパレーション・アビューズ(別離後の虐待)」、「リーガル・アビューズ(法的虐待)」として知られています。
離婚しても、元配偶者と子どもに対する支配を続ける(影響力を維持する)ためだけの訴訟が続き、被害者である配偶者と子どもは、精神的、経済的に疲弊していきます。
例えば、家庭裁判所に「婚姻破綻の原因は、配偶者からのDV行為である」と夫婦関係調整(離婚)調停を申立て、その調停で「養育費算定表」にもとづく「養育費の支払額が決定した」としても、毎月、「養育費が支払われるのか?」という不安を覚え続けることがあります。
そして、その夫婦関係調整(離婚)調停において、「養育費の支払い」が決定されていたとしても、「強制執行認諾条項付きの公正証書」を作成していない中で、約束していた「養育費が振り込まれていない」ときには、『改正民事執行法』による強制執行の手続きをとることができないことから、別途、「強制執行」の申立てをする必要がでてきます。
そのため、「1-(3)単独親権(民法819条)と養育費の不払い」で述べているように、離婚時に、離婚後の子どもの監護にかかわるとり決めを文書にまとめ、「強制執行認諾条項付きの公正証書」にしておく必要があります。
とはいっても、「1-(3)単独親権(民法819条)と養育費の不払い」の中で、『厚生労働省が実施した『養育費、面会交流の取り決め状況等(平成28年度全国ひとり親世帯等調査)』では、「養育費」のとり決めをしている世帯(「とり決めをしている」、「子によって違う」)は44.6%で、「受けたことがあるが、現在は受けていない」が11.6%で、「いまも養育費を受けている」は27.0%となっていますが、ア)養育費のとり決めをした母子世帯で、養育費を現在も受けているのは53.3%であるのに対し、イ)養育費のとり決めをしていない母子世帯で、養育費を現在も受けているのは僅か2.5%です。他の調査では、夫婦関係調整(離婚)調停で、離婚後の養育費の支払いを約束して離婚が成立した案件であっても、離婚後に子どもの養育費の支払いは24.3%で、しかも、離婚後3年を経過すると15%ほどに低下しています。』と示しているように、DV事案では、「離婚後、子どもの養育費の支払い」を期待した生活設計しないのも選択のひとつです。
それは、離婚後も、「こどもの養育費(子どもの生活費)」を盾にした経済的な影響力が及ぶ(DV行為としての経済的暴力の支配下にある)ことを断ち切る重要な意味もあります。
しかし、「3-(9)「共同親権法案」の懸案事項-ⅳ)「共同親権」で収入は父母合算に」で示しているように、「家」を基軸に制度設計されている日本の「税制度」「社会保障制度」のもとで、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が成立・施行(運用)となり、子どもの監護者(同居親)でないもう一方の親が共同親権者となると、子どもの親の所得が父母の合計となることから、生活を破綻させないための「生活保護の受給」ができないリスクもでてきます。
このことは、子どもの安全だけではなく生命そのものを危うくします。
また、この問題は、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」と絡み、もうひとつの側面を持ちます。
それは、DV被害者の配偶者が、家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)調停」を申立てたケースでは、調停委員を介す、鬱陶しいやり取りに嫌気がさし、養育費の支払いなどのとり決め、そして、離婚に応じたDV加害者の一定数に、離婚後、意図的に養育費の振り込みをせず、元配偶者からの連絡を待ち、目論見通りに連絡があると「直接会ってわたす」と応じ、その面会で、復縁を迫ることがあります。
このとき、望む回答(復縁に応じる)を得られないと激怒し、苛烈な暴力に至ったり、レイプしたりすることがあります。
こうした要素のあるDV加害者には、「3-(4)共同親権法案」の懸案事項-ⅰ) 離婚した父母の合意」の「「同意」の名の下で懸念されるレイプ被害」で述べているように、「共同親権」の下で、「サイン」に応じる“条件”として、性行為を強いられる可能性があります。
(3) 親権と監護権
「親権」とは、「未成年の子どもを成人まで育てあげるために親が背負う一切の権利・義務」のことです。
「親権を行う者は、子どもの利益のために子どの監護及び教育をする権利を有し、義務を負う(監護権)」と『民法820条』で規定され、この内容を具現化させる権利として、以下のイ)エ)オ)カ)の行為が定められています。
このア)イ)エ)オ)カ)の行為は、父母が話し合い(協議し)、“共同”の意思として行使します。
この「親権」を行使する親を「親権者」といいます。
また、子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする権利・義務を負う親を「監護者」といいます。
父母が婚姻関係にあるときは、「親権者」と「監護者」が行使する権利はほぼ同じです。
ところが、子どものいる夫婦が別居生活(一部、単身赴任を含む)をしているとき、「子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親」と「子どもの近くにいることができず、子どもの世話や教育にあまりかかわらない(まったくかかわらない)親」という“構図”が生まれます。
このとき、「前者の親(監護者)」は、以下の「親権」のうちア)イ)エ)の行為を行使します。
ア)子どもに監護や教育をする権利義務(民法820条)、イ)子どもの居所を定める権利(民法821条(居所指定権))、ウ)子どもを懲戒する権利(民法822条(懲戒権))、エ)子どもの就職について許可をする権利(民法823条(職業許可権))、オ)財産を管理する権利(民法824条(財産管理権))、カ)契約などの法律行為を代理する権利(同条)です。
なお、「子どもを懲戒する権利(民法822条)」は、令和4年(2022年)10月14日、『民法(家族法)』の改正で削除、同年12月16日に施行されていることから、法的に、子どもに対する「懲戒」は禁止されています。
敢えて、ウ)として表記しているのは、この「親は子どもに懲戒できる」との認識が、日本で生活している市民の「親権」は親の権利であるとの認識に至っている大きな理由となっているからです。
この認識にあるとき、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」の「主体は親で、子どもは客体」に位置づけられているという致命的な欠陥を理解できない可能性があります。
しかし、日本が批准・締結している『子どもの権利条約』では、真逆の「監護権(親権)」の「主体は子ども(子どもの最善の利益のために、子どもの意思(意見)を尊重する)で、親は客体(子どもの最善の利益のために、子どもの意思(意見)を尊重する義務を負う)」と位置づけています。
この視点に立つと(期待を込めて)、「親は、子どもを懲戒する義務を負う」という解釈となり、いかに、日本の定める「親権」が、「親の権利」としていることの問題を理解できるのではないでしょうか?
父母が離婚したとき、子どもはどちらか一方の親と生活することになります。
つまり、子どもの監護者の親と子どもの監護者でない一方の親に分かれます。
前者の子どもの監護者である親が、上記のア)イ)エ)オ)カ)について、「単独」で行使できるのが、「現法」の『単独親権(民法819条)』です。
これに対し、子どもの監護者である親と、子どもの監護者でない一方の親がともに「(共同)親権者」となり、ア)イ)エ)オ)カ)について行使できるのが『共同親権』です。
令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正(共同親権法案)」は、この『民法819条』を改正し、「単独親権」の規定について、一部を除き「共同親権」に変更するものです。
(4) 「共同親権法案」の懸案事項-ⅰ) 離婚した父母の合意
現法では、『単独親権(民法819条)』では、「離婚」すると、子どもの監護者の親が、「(単独)親権者」として、「3-(3)親権と監護権」で示した「親権」のア)イ)エ)オ)カ)の行為を単独で行使することができます。
それに対し、令和6年(2024年)に本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が成立・施行されると、「2-(2)離婚後の親権の決定」のa)で「共同親権」を選択したり、b)d)の家庭裁判所で「共同親権」の決定を受けたりして、子どもの監護者の親と子どもの監護者でないもう一方の親(共同親権者)は、「3-(3)親権と監護権」で示した「親権」のア)イ)エ)オ)カ)の行為について、結婚時と同様に話し合い(協議し)、共同(合意・同意のもと)で行使することになります。
話し合い(協議)で、合意に至らない(同意を得られない)ときには、「家庭裁判所」にその判断を仰ぐ係争事件となります。
例えば、子どもの監護者である親が、もう一方の親(共同親権者)との合意(同意)が必要となるのは、ア)「3-(1)-②離婚後の氏(姓)の変更」の子どもの監護者が婚姻前の名字(旧制)に戻り、子どもの名字を子どもの監護者に合わせて変更するとき(家庭裁判所の許可を得る前に)、イ)幼稚園・保育園、小学校など子どもが学校園に就学したり、転校したり、進学したりするとき、ウ)子どもが通う高校の修学旅行が海外のとき、パスポートを申請するとき、エ)子どもの就職先を決めるとき、オ)医療機関で治療を受けたり(一部、「急迫の事情」に該当し、単独で行使できる)、任意のワクチンの接種を受けたり、歯の矯正を受けたり、療育支援を受けたり、カウンセリングを受けたりするときなど、子どもの意思決定に親が関与し得る日々の決めごとです。
例えば、子どもの監護者である親が、子どもが通学する幼稚園でプールに入る時間があり、幼稚園のプ-ルカードに許諾のサインをしても、子どもの監護者でないもう一方の親(共同親権者)が、幼稚園に電話をし「子どもをプールに入れないでくれ」と伝えると、父母の合意のない子どもはプールに入れなくなります(法務省の見解では後出しの決定が優先されることになっています)。
「合意」に至らなかったり、「同意」を得られなかったりして、「家庭裁判所」に判断を仰ぐ係争事件となると、その判断まで時間を要することになります。
そのため、当事者である子どもは、長期間、父母間の紛争下におかれるだけではなく、ときに(タイミングとして)、進学できなかったり、修学旅行に行けなかったり、療育を受けられなかったり、治療を受けられなかったりする可能性がでてきます。
とくに、子どもの意思決定に親が関与し得る日常の決めごとの中で、子どもの命にかかわることもある医療機関の受診、将来に多大な影響を及ぼす子どもの進学や就職では、その医療機関、教育機関が子どもの監護者でないもう一方の親(共同親権者)の同意が確認できないときの医療行為、入学の許可における訴訟を避ける可能性があります。
なぜなら、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」では、「監護」、「教育」にかかわる“日常の行為”や“急迫の事情”があるときには、子どもの監護者である親が、「単独」で、親権を行使できるとしていますが、「日常の行為」や「急迫の事情」の判断基準が示されていません。
つまり、なにが、「急迫の事情」に該当するかが明確に示されていません。
また、この「単独」の行使の理解で注意したいのは、子どもの監護者(同居親)の有無は関係ないということです。
・「共同親権法案」の成立・施行で、増加が予想される係争事件。逆に裁判所職員を削減
共同行使の例外、つまり、一方の配偶者に対するDV、子どもに対する児童虐待の事実が認められるときには「単独親権」とするし、協議で合意できないときには、家庭裁判所が決定するとしていますが、本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が成立・施行されると、その家庭裁判所は、これまで以上に大きな役割を担うことになります。
その新たな負担はあまりにも大きく、相当数の増加が見込まれる「子どもの監護に関する民事事件」をはじめとする各種家事事件に対応する(適正で、迅速に判断する)には、裁判官、家庭裁判所調査官、書記官、調停委員などの人的強化を含めた体制整備が必要となります。
しかし、日本政府は、令和5年(2023年)2月7日、「判事補に因数を減少するとともに、裁判所の事務を合理化し、効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少させる」とした『(裁判所職員定員法の一部を改正する法律案』を国会に提出し、同年4月7日に成立(同年同月14日施行)しています。
この事態に対し、令和5年(2023年)10月5日、日本弁護士連合会の人権擁護大会シンポジュウムにおける「提言」で、「裁判官、家庭裁判所調査官、司法職員(書記官、調停委員など)の増員は急務である」と発表しています。
つまり、日本政府は、本国会に「「離婚後の共同親権制度の導入」のための『家族法(民法)』の改正」の「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」を提出するちょうど1年前に、相当数の増加が見込まれる「子どもの監護に関する民事事件」をはじめとする各種家事事件に対応する裁判所の職員を減少させる『改正裁判所職員定員法』を成立させています。
このことは、本国会に提出した「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」を運用する体制の構築ではなく、家庭裁判所が、適正で、迅速に判断することを遮る(妨害する)、機能させないための伏線を意味します。
極右・超保守の政権、政党、政治家、彼らと“共同体”ともいえる強固な関係を築いている「はじめに。」で示したア)イ)ウ)エ)の政治団体が、本国会で、「「離婚後の共同親権制度の導入」のための『家族法(民法)』の改正」をなし遂げるために、緻密に、計画的に、用意周到にコトを進めてきたことがわかります。
・ 「同意」の名の下で懸念されるレイプ被害
子どもの「親権者」として、父母間で承諾を得るとき、この父母間に上下の関係性、支配と従属の関係性が成り立っているとき、この「権利」の行使を悪用すると、「こうして欲しければ、こうしろ!」と協議(交渉)と称する“脅す(脅迫)”することが可能となります。
DV/性暴力被害者支援に携わってきた経験を踏まえると、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が成立・施行されると、離婚した子どもの父母間で、「サイン(同意)が欲しけれれば、性交させろ!」などと性暴力が頻発する可能性があります。
OECD(経済協力開発機構)の加盟国(加盟38ヶ国)に国籍のある男性と結婚(国際結婚)し、夫の母国での結婚生活で、鞭で叩かれるなどの日々のDV被害から逃れるためには子どもを連れて帰国するしかないと追い詰められた女性は、帰省するには、「1年間、源氏名のもとで、グループセックスに応じる」という条件をつけられました。
2年後、子どもを連れて帰省することが許されたその女性は、帰国後、離婚に向けて準備をはじめましたが、重篤なPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症するだけではなく、解離性同一性障害(多重人格)を発症していました。
(5) 「共同親権法案」の懸案事項-ⅱ) 明確さに欠ける「急迫の事情」
「急迫の事情」に該当する「緊急の医療行為」では、具体的に、どのレベルの医療行為が該当するのか基準が不明確であることから、治療が必要な子どもが医療機関を受診したとき、医療機関は、「子どもへの対応(治療)」に対するトラブルを避けるために、「共同親権者である父母双方の署名」、あるいは、「単独親権であることを示す書類」を求める機会が増加することが予想されます。
例えば、家庭裁判所に子どもとの面会を禁止する判断を下されていた父親が、滋賀医科大学に対し、「3歳の娘の手術について、事前の説明や同意を求められなかった」として損害賠償請求を求めた民事訴訟で、令和4年(2022年)11月、大津地方裁判所は、その訴えを認めています。
こうした判例がある以上、医療機関は、訴訟を避けるために医療行為を控えざるを得なくなる可能性があります。
このことは、治療が必要な子どもが、適切なタイミングで治療を受ける機会を逸する可能性を意味し、子どもが亡くなったり、子どもが(後遺症として)重篤な障害を負ったりするリスクが高くなる可能性を示唆します。
また、児童とかかわる教育機関は、受験の願書をだしたり、入学園先に必要書類を提出したり、宿泊を伴う学校行事に参加したり、部活動などで長距離の移動を伴う遠征したり、大会に参加したりするときに、子どもの監護者でない一方の親(共同親権者)の同意が必要な児童(家庭)なのか、子どもの監護者である親が単独親権者で、一方の親の同意は必要ない児童(家庭)なのかを正確に把握しておく必要がでてきます。
例えば、子どもの監護者である親が、学校園・塾・習いごとなどに「単独親権」と伝えていて、それが事実に反し、子どもの監護者でない一方の親(共同親権者)が、「許可(同意)していない」と訴訟に至る可能性があります。
このことは同時に、受験の願書が無効になり、子どもが入学園できなったり、進学できなかったり、宿泊を伴う学校行事や大会に参加できなかったりするなど、子どもが大きな損害を被ることになります。
このように、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が成立・施行されると、医療機関や教育機関は、訴訟リスクを怖れ、萎縮し、父母双方のサインのない子どもに対する医療行為や教育を断ることも十分に考えられます。
これは、「子どもの最善の利益」の原則に反し、「子どもの安全」が担保されていないことを意味します。
令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正(共同親権法案)」には、『子どもの権利条約』に定める「子どもの意思(意見)の尊重(子どもの意見表明権)」の記載がありません。
この「子どもの意見の尊重(子どもの意見表明権)」の不記載は、「(生活を同じくしていないもう一方の親(共同親権者)親と)会いたくない(面会交流したくない)」、「進学先は、・・にしたい」、「‥に就職したい」、「・・の宿泊合宿に参加したい」「パスポートを取得し、修学旅行に参加したい」との子どもの意思が尊重されず、「嫌でも、決まりだから無理やり会わなければならない」、「歯の矯正をしたいけれど、親が必要ないとからと歯の矯正ができない」、「親が決めた進学先に進学しなければならない」、「親がパスポートの取得に反対だから、修学旅行に参加できない」といった悲惨な事態を招く高いリスクがあります。
つまり、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正(共同親権法案)」の「主体は親で、子どもは客体」と位置づけられています。
このことは、この「共同親権法案」が、世界に類のない恥ずべき悪法であることを意味します。
(6) 離婚理由「性格の不一致」は、離婚後の話し合いを困難に
「2-(4)「共同親権法案」の懸案事項-ⅰ)離婚した父母の合意」の「離婚調停・裁判離婚における「離婚事由」はすべてDV事案に絡む」で示した「調停離婚(家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)調停」を申立て、調停委員を介して合意に至った離婚)における「離婚事由」の1位は、「性格が合わない(性格の不一致)」です。
この抽象的な「性格が合わない(性格の不一致)」は、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正(共同親権法案)」が成立・施行されると、この「性格が合わない(性格の不一致)」で離婚した子どもの父母は、「2-(2)離婚後の親権の決定」のa)「父母の協議(協議離婚(民法763条))で、双方または一方を親権者と定める」との規定による話し合いが成り立たず、b)「父母が合意できないときには、家庭裁判所が判断する」ことになることが想定されます。
そして、「性格が合わない(性格の不一致)」で離婚理由は、同c)b)では、「共同親権を認めると子どもに対する虐待行為、元配偶者に対するDV行為などが生じ、子の利益を害する」と認められるときには、父母の一方を親権者(単独親権)と定めなければならない」との定めに該当しないことから、b)により、家庭裁判所は、「共同親権」と判断することになります。
この「性格が合わない(性格の不一致)」は、生まれ持った気質、育ってきた家庭環境、地域(国を含む)・コミュニティが違いなどから生じる、ものごとの捉え方や考え方、価値観の違いなどを指します。
生まれ育った家庭環境、地域(国を含む)・コミュニティで構築(形成)される生活習慣の違いは、ものごとの捉え方や考え方、価値観の違いをもたらし、なにを重視し、優先するかといったプライオリティの違い、つまり、金銭感覚、食事の好みやルール、衣服の好み、住まいの希望、家庭生活での男女(夫婦)の役割、父母・きょうだい・親族・友人・勤務する会社関係者などとのかかわり方(交流のあり方)、子どもの有無、子どものしつけ(教育)、習いごと、進学・進路方針、職業選択などの教育観・職業観、宗教観など多岐にわたります。
このことは、「2-(3)親権・監護権」で示したア)子どもに監護や教育をする権利義務(民法820条)、イ)子どもの居所を定める権利(民法821条(居所指定権))、エ)子どもの就職について許可をする権利(民法823条(職業許可権))、オ)財産を管理する権利(民法824条(財産管理権))、カ)契約などの法律行為を代理する権利(同条)に対し、ものごとの捉え方や考え方、価値観の違いが生じることを意味します。
結婚相手のものごとの捉え方や考え方、価値観の違いをリスペストすることできずに、「性格が合わない(性格の不一致)」として離婚に至った父母が、離婚後、子どもの「共同親権者」としての話し合い(協議)は、それぞれの考え方・意見が異なり、それぞれの主張は噛み合わないことは容易に想像できます。
したがって、「性格が合わない(性格の不一致)」として離婚に至った父母が、「子どもの意思を尊重(子の意思表明権)」しながら、「子どもの最善の利益」のために、子どもの離婚した父母が話し合い(協議し)、合意に至ることは困難を極めます。
結果、係争に至る事案が激増することになります。
日本を除く世界の国々が、離婚にあたり、家庭裁判所を介し、子どもいる夫婦では、養育費、面会交流など、「2-(3)親権・監護権」で示したア)子どもに監護や教育をする権利義務(民法820条)、イ)子どもの居所を定める権利(民法821条(居所指定権))、エ)子どもの就職について許可をする権利(民法823条(職業許可権))、オ)財産を管理する権利(民法824条(財産管理権))について、詳細にとり決め、文書化しておくのは、あとから生じる係争を防ぐ重要な役割があります。
「2-(2)離婚後の親権の決定」の中で述べている令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が示したa)の「(離婚後の親権は)父母の協議(協議離婚(民法763条))で、双方または一方を親権者と定める」との規定、b)「父母が合意できないときには、家庭裁判所が判断する」と定める規定により、子どもの監護者でない一方の親が「共同親権者」となったときには、離婚後の係争の増大、離婚後のDV行為を招くという意味でも、『協議離婚制度(民法763条)』を廃止せずに、「共同親権法案」を運用することは、致命的な欠陥といえます。
しかも、この生まれ育った家庭環境、地域(国を含む)・コミュニティで構築(形成)される生活習慣の違いがもたらす「ものごとの捉え方や考え方、価値観の違い」は、暴力のトリガー(ひきがね)となります。
共通言語、共通認識を持てない人との交渉(話し合い・協議)は、トラブルに発展したり、決裂しやすかったりし、合意に至るにはパワーの論理(力でねじ伏せる)が働くことになります。
なぜなら、本来、対等な男女の関係、夫婦の関係に、上下の関係性、支配と従属の関係性を成り立たせる(一度構築したその関係性を維持するを含む)ためには、パワー(暴力)を行使し、「生まれ育った家庭環境で構築(形成)される生活習慣」を“破壊”する必要があるからです。
この「破壊」は、支配(マインドコントロール)の最初のステップとなります*4。
つまり、「性格が合わない(性格の不一致)」は、直接的な「DV行為としての暴力」には該当しませんが、DV行為としての暴力をもたらすトリガー(ひきがね)となっていることから、「性格の不一致」で離婚した父母が、「共同親権」のもとで、離婚後の話し合う(協議する)ことは、十分にパワー行使のトリガーとなり得ることから、離婚後のDV行為が増加するリスクがあります。
そのときは、“元配偶者”は、『配偶者暴力防止法』の適用となります。
そのDV被害が、子どもに対する虐待行為に至っている(そのDV行為を子どもの面前で加えられたとき、面前DV(心理的虐待)となる(児童虐待防止法))ときには、「親権者による身体的、心理的虐待、性的虐待など、親権者による親権の行使が困難または不適当であることにより、子の利益を害する」として、家庭裁判所に「親権停止(最長2年、親権が停止される)」を求め、提訴することができます。
ただし、「親権停止」は、親族による申立てに対し、家庭裁判所は却下との判断を示すことが多く、その児童相談所長による申立てに対し、家庭裁判所は却下することはほとんどないことから、「女性センター(婦人相談所、男女共同参画センター)」の“主導”のもとで、児童虐待事案として「児童相談所」に関与してもらうことが有効です。
重要なことは、必ず、「女性センター(婦人相談所、男女共同参画センター)」の主導のもとでの対応であることです。
「面前DV」とは、18歳未満の子どもの前で配偶者や家族に対して暴力をふるうことで、「直接的に暴力を受けなくても、両親間のDV行為を見聞きして育つ子どもは心身に深い傷を負い、成長後もフラッシュバックや悪夢(侵入)に苦しむなどのPTSDを発症することが少なくなく*5、早期のケア(治療など)が必要として、平成16年(2004年)、『児童虐待防止法』の改正で、心理的虐待のひとつと認定されたものです。
つまり、子どものいる夫婦間で、DV行為があるときには、その子どもは等しく「心理的虐待」を受けていることになります。
そして、自身のDV被害に加え、子どもに対する虐待被害を訴えるには、DV行為、虐待行為の規定に対する正確な知識に加え、適用できる刑法、判例などの知識も必要になってきます*6。
「親権喪失」は、子どもの利益を著しく害したときに親権を失効(喪失)させるもので、停止のように期限はなく、その対象となった親は、とり消しとならない限り、親権は戻りません。
また、「離婚後の親権」と「離婚後の養育費の支払い」は別の問題であることから、「親権停止の決定」が下されたとしても、子どもの監護者でないもう一方の親であることには変わりがないので、「養育費の支払い」の義務を負うことになります。
*4 DV事案としての「支配(マインドコントロール)」については、レポート『別紙3 DV行為による恐怖。その支配の構造と仕組みと加害者の属性と特性(A4版165頁)』の中で詳述しています。
*5 面前DV(心理的虐待)がもたらす後遺症については、レポート『別紙2d(簡易版)DV・虐待・性暴力被害。慢性反復的トラウマ体験に起因する後遺症(A4版192頁)』で詳述しています。
*6 「DV行為、虐待行為の規定に対する正確な知識に加え、適用できる刑法、判例などの知識」については、レポート『別紙4b(簡易版) 「DV・虐待行為としての暴力」の規定と適用される法律(A4版・・頁)』で詳述しています。
(7) DV・児童虐待の“規定”が「単独親権」の判断に
昭和60年(1985年)に『女性差別撤廃条約』、平成元年(1989年)に『子どもの権利条約』を批准・締結した日本は、平成12年(2000年)、『児童虐待の防止等に関する法律(以下、児童虐待防止法)』、同年11月、『ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下、ストーカー規制法)』、同13年(2001年)4月、『配偶者暴力防止法』を制定しました。
『児童虐待防止法』は、平成16年(2004年)、令和2年(2020年)、令和4年(2022年)の3回改正、『ストーカー規制法』は、平成25年(2013年)、令和3年(2021年)の2回改正に加え、平成26年(2014年)11月、リベンジポルノへの罰則を盛り込んだ『リベンジポルノ被害防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)』の制定、『配偶者暴力防止法』は、平成16年(2004年)、平成19年(2007年)の2回の改正を経て、平成25年(2013年)改正新法の制定、令和5年(2023年)の改正(令和6年(2024年4月1日))を経ていまに至っています。
令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)改正案(共同親権法案)」と関連する条約と法改正は、平成25年(2013年)に『ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)』の批准・締結するにあたり、共同親権制度の他国と単独親権制度の日本との国際結婚における離婚問題(離婚後の子どもの監護)に対応するために、その2年前の平成23年(2011年)に改正したのが『民法766条(離婚後の子の監護)』です。
令和6年(2024年)に本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が成立・施行すると、「2-(2)離婚後の親権の決定」のc)家庭裁判所で「共同親権を認めると子どもに対する虐待行為、元配偶者に対するDV行為などが生じ、子の利益を害する」の認定を受け、子どもの監護者が「単独親権」を得るうえで、重大で、深刻な問題となり得るのが、平成13年(2001)年に制定された『配偶者暴力防止法』は骨抜きで、不備だらけで、しかも、日本政府は、敢えて(意図的に)放置していることです。
つまり、「2-(2)離婚後の親権の決定」のc)家庭裁判所で「共同親権を認めると子どもに対する虐待行為、元配偶者に対するDV行為などが生じ、子の利益を害する」の認定を受け、子どもの監護者が「単独親権」を得るには、ⅰ)『児童虐待防止法』『配偶者暴力防止法』『ストーカー規制法』『リベンジポルノ防止法』に定められている“規定”に加え、児童虐待行為やDV行為に適用できる『刑法』の“規定”に対する正確な知識、そして、ⅱ)長期間、慢性反復的(常態的、日常的)な被虐待体験、被DV体験により生じる(C-)PTSD、その併発症としてのうつ病、パニック障害など後遺症に対する正確な医学的知識(症状だけではく、重要なのは発症メカニズム)に加え、ⅲ)その後遺症を発症した人が、トラウマ反応をもたらすできごとに遭遇し、パニックアタックを起こしたり、トラウマの追体験がその後遺症を重篤化させたりするなどの根拠(裏づけ)のある医学的知識が、これまで以上に必要になってきます*7。
『配偶者暴力防止法』の規定の不備・欠陥を凌駕する正確な知識と根拠(裏づけ)のある医学的知識が必要になります。
それは、家庭裁判所の判断で、DVとの認定を受けられず、DV加害者である(元)配偶者と「共同親権者」となり得る最悪の事態を防ぐためです。
*7 「児童虐待」に該当する暴力、「DV行為」に該当する暴力については、レポート『別紙4b(簡易版) 「DV・虐待行為としての暴力」の規定と適用される法律(A4版・・・頁)』で詳述し、加えて、長期間、慢性反復的(常態的、日常的)な虐待被害、DV被害がもたらすPTSDなどの後遺症については、レポート『別紙2d(簡易版)DV・虐待・性暴力被害。慢性反復的トラウマ体験に起因する後遺症(A4版192頁)』で詳述しています。
①『配偶者暴力防止法』の致命的な欠陥-ⅰ)既定のダブルスタンダード
『配偶者暴力防止法』には、致命的な欠陥が3つあります。
第1の致命的な欠陥は、『配偶者暴力防止法』の第二条の三にもとづいて作成される『都道府県(市町含む)基本計画』の中で、「配偶暴力防止法で対象とする暴力として、身体的暴力、性的暴力、精神的暴力(社会的隔離、子どもを利用した精神的暴力を含む)、経済的暴力がある」と“規定”していますが、『同法』に準じて、地方裁判所に申立て発令される「保護命令」と、女性センター長、警察署長名で決定する「一時保護」の対象となる暴力の“適用要件”では、「身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすもの(身体的暴力の一部)」、「自由、名誉、財産」に対する加害の告知による脅迫を受けた者(精神的暴力の限定された一部)」と限定的で(絞り込まれ)、しかも、「性的暴力」は適用外になっていることです。
日本では、『配偶者暴力防止法』のもとで、この広報と運用のダブルスタンダードの規定が存在します。
この状況に対し、平成15年(2003年)8月、国連の「女性差別撤廃委員会」は、締結国である日本政府に対し、「ドメスティック・バイオレンスを含む女性に対する暴力の問題に対し、女性に対する人権の侵害としてとり組む努力を強化すること」、「『配偶者暴力防止法』を拡大し、様々な形態の暴力を含めること」と是正勧告を示しています。
しかし日本政府は、平成13年(2001)年に『同法』を制定以降、敢えて(意図的に)、この重大な欠陥(骨抜きで不備だらけ)を放置しています。
『都道府県(市町含む)基本計画』にもとづき、防止啓発活動として作成される「リーフレット(パンフレット)」では、「具体例をあげてDV行為を説明したうえで、『配偶者暴力防止法』による“一時保護”の決定、“保護命令”の発令の仕組みを伝え、最後に、「どのような理由があっても暴力は犯罪です。悪いのは暴力を振るう側です。一人で抱え込まず、相談してください。」と記述しているにもかかわらず、DV被害者が相談窓口を訪れ、「苦しくて、もう耐えられない」と訴えた「(命の危険性がないと判断される)身体的暴力」「精神的暴力」「性的暴力」に対し、担当職員から「保護命令をだせないし、一時保護の対象にもならない。」とにべもない対応をされます。
つまり、DV被害支援の現場では、「このような行為がDVに該当する」と広報(防止啓発活動)している一方で、DV被害者が意を決し、窓口を訪れて助けを求めると「一部の身体的暴力、精神的暴力、性的暴力は保護対象にはならない。」と応じています。
結果、藁にもすがる思いで、「ここに行けば、助けてもらえる」と相談に訪れたDV被害者は、一転して、「誰にも助けてもらえない。」と打ちのめされます。
これは、平成15年(2003年)8月、国連の「女性差別撤廃委員会」が、締結国の日本政府に対する是正勧告、つまり、「ドメスティック・バイオレンスを含む女性に対する暴力の問題に対し、女性に対する人権の侵害としてとり組む努力を強化すること」、「『配偶者暴力防止法』を拡大し、様々な形態の暴力を含めること」に反しています。
日本政府は、22年11ヶ月間にわたり、この「いっていることとやっていることがまったく違う二枚舌の状況」を放置したままで、相談に訪れるDV被害者に混乱と絶望を覚えさせています(令和6年(2024年)4月15日現在)。
②『配偶者暴力防止法』の致命的な欠陥-ⅱ)見せかけの適用を拡大
第2と第3の致命的な欠陥は、平成15年(2003年)8月、国連の「女性差別撤廃委員会」が、締結国の日本政府に対する是正勧告、つまり、「『配偶者暴力防止法』を拡大し、様々な形態の暴力を含めること」に該当する『同法』の適用する暴力に、「精神的暴力」と「性的暴力」を加えようとしない日本政府の政治姿勢です。
a) 『配偶者暴力防止法』の適用の拡大は見せかけで、適用を困難に
第2の致命的な欠陥は、『配偶者暴力防止法』を適用する暴力に、「精神的暴力」を加えたように見えて、実質的な問題として「精神的暴力」を加えていないだけでなく、適用を難しくしていることです。
平成16年(2004年)の最初の「法改正」で、「身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすもの」に加え、「これに準する心身に有害な影響を及ぼす言動」と“ことばの暴力(精神的暴力)”を加えました。
問題は、「生命または身体に危害を及ぼすほどの(に準する)、心身に有害な影響を及ぼす言動」と、立証するのが極めて難しい“条件”をつけたことです。
しかも、「心身に有害な影響を及ぼす言動」の基準を定めていませんでした。
当時、この基準を定めていないことが問題になりましたが、以降の「法改正」で、基準を限定したことにより、逆に、適用が難しくなりました。
2年後の平成19年(2007年)の「法改正」では、保護命令の発令の対象が、「脅迫により、生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときにも発する」としました。
この「適用要件」は、広義の「言動」を「脅迫」に限定した、つまり、絞り込んだことになります。
「脅迫」と限定することで、適用要件を狭くすることができます。
つまり、「法改正」で、同法の適用できるDV事案を少なくすることができます。
これは、実際の「保護命令の申立て数」と「保護命令の申立てに対する発令数」に明確に示されています。
b) 「保護命令の申立て数」と「保護命令の申立てに対する発令数」
平成13年(2001年)10月に『配偶者暴力防止法』が施行されてから令和2年(2020年)12月末までに終局した「保護命令事件」は4万9,019件です。
令和2年(2020年)に終局した「保護命令事件」は1,855件のうち、「保護命令が発令された件数」は1,465件(78.96%)とかなり低くなっています。
「保護命令が発令された件数」は1,465件のうち、ア)被害者に保護命令が発令されたのは382件(26.1%)、イ)被害者に保護命令が発令され、その子どもに接近禁止命令が発令されたのは592件(40.4%)、ウ)被害者に保護命令が発令され、その子どもと親族等に接近禁止命令が同時に発令されたのは307件(20.9%)、エ)生活の本拠をともにする交際相手に保護命令が発令されたのは141件(9.6%)です。
「保護命令の処理数(認容(保護命令発令)、却下、取下げなど)」は、平成20年(2008年)にはじめて3千件(3,143件)を超え、平成27年(2015年)までの8年間は3千件前後で推移していましたが、「改正新法(平成25年(2013年)6月16日)」として成立した『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)』が、平成26年(2014年)1月3日に施行され、平成28年(2016年)12月13日に議員連盟案『共同養育支援法(父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する法律案)』が、「親子断絶防止議員連盟」の総会で承認されると急激に減少に転じます。
平成28年(2016年)が2,632件(前年比88.62%)、平成29年(2017年)が2,293件(前年比87.12%)、平成30年(2018年)が2,177件(前年比94.94%)、平成31年/令和元年(2019)年が1,998件(前年比91.78%)、令和2年(2020年)が1,855件(前年比92.84%)、令和3年(2021年)が1,732件(前年比93.37%)、令和4年(2022年)が1,453件(前年比83.89%)と、毎年1割前後、減少しています。
令和4年(2022年)の1,453件は、平成27年(2015年)の2,970件の48.92%に過ぎず、8年間で、保護命令の申立て数は、実に1/2に減少しています。
しかも、直近の3年間の「保護命令」の申立てに対し、「保護命令」が発令された件数は、令和2年(2020年)が1,465件(78.96%)、令和3年(2021年)が1,335件(77.08%)、令和4年(2022年)が1,111件(76.46%)と申立てた1/4は発令されていません。
この令和4年(2022年)の1,111件は、「保護命令」の発令数がもっとも多かった平成26年(2014年)の2,528件の43.95%です。
この間、「改正新法」で、「婚姻関係になくとも同じ居住地で生活を営んでいる者(元を含む)」と『配偶者暴力防止法』の適用となる対象者が拡大され、しかも、DV被害の相談件数は約1割増加し、直近の2年は横這い状態が続いています。
これは、DV被害の相談件数が減少したことに比例して減少したのではなく、『配偶者暴力防止法』の適用要件の「脅迫」を厳しく運用する動きに転じたこと、その背景に政治的な働きがあったことが類推できます。
その「配偶者暴力相談支援センター」における相談件数は、平成27年度(2015年度)が111,172件(前年比107.97%)、平成28年度(2016年度)が106,367件(前年比95.68%)、平成29年度(2017年度)が106,110件(前年比99.76%)、平成30年度(2018年度)が114,481件(前年比107.89%)、平成31年/令和元年度(2019年度)が119,276件(前年比104.19%)、令和2年度(2021年度)が129,491件(前年比108.56%)、令和3年度(2022年度)が122,478件(前年比94.58%)、令和4年度(2022年度)が122,211件(前年比99.78%)となっています。
平成27年度(2015年度)の111,172件と令和4年度(2022年度)が122,211件を比較すると109.39%、8年間で約1割(+9.39%)増加しています。
相談件数は増加・横這いであるにもかかわらず、保護命令の申立て件数が1/2に激減し、しかも、保護命令を申立てた1/4は発令されない状況は、もはや『配偶者暴力防止法』が体をなしていないことを意味します。
c) 令和5年(2023年)5月12日の「法改正」
こうした状況で、令和5年(2023年)5月12日に成立(一部を除き令和6年(2024年)4月1日施行)した「法改正」では、加害者のつきまといなどを禁止する「保護命令」の要件として、「物理的な暴力だけでなく、ことばや態度による精神的な危害(害悪を告知することにより畏怖させる行為)」が加えられました。
接近禁止命令等の申立てをすることができるDV被害者(『配偶者暴力防止法』の適用対象者)は、これまでのⅰ)配偶者からの身体に対する暴力を受けた者、ⅱ)「生命又は身体」に対する加害の告知による脅迫を受けた者に加えて、ⅲ)「自由、名誉又は財産」に対する加害の告知による脅迫(『脅迫罪(刑法222条第1項)と同じ文言)を受けた者が適用となりました。
ⅲ)の「「自由、名誉又は財産」に対する加害の告知による脅迫」のア)「自由に対する脅迫」は、「‥するまで、‥ができるまで外出は禁止だ!」といった言動を指し(社会的隔離)、イ)「名誉に対する脅迫」は、「指示に従えない(いうことをきけない)なら、この(裸体や性行為を撮影した)画像(映像)をネットに拡散するぞ!」を脅す言動を指し、ウ)「財産に対する脅迫」は、いうことをきかなかったり(指示に従わなかったり)、失敗(判断基準はDV加害者)したりしたことに対する“罰”として、「クレジットカードをとりあげる」「生活費をわたさない」などの経済的暴力を指します。
問題は、ⅰ)ⅱ)ⅲ)-ア)イ)ウ)の対象者が、『配偶者暴力防止法』の適用、つまり、接近禁止令などの「保護命令」の発令を受けるには、ⅰ)ⅱ)ⅲ)-ア)イ)ウ)の行為により、「更なる身体に対する暴力または生命・身体・自由に対する脅迫により、心身に重大な危害を受ける怖れが大きいとき」という「保護命令」の“発令要件”を満たす必要があります。
「更なる」は、「一層」、「ますます」を示すので、「これまでの暴力被害以上の」という条件設定を意味し、「心身に重大な危害を受ける怖れ」は、少なくとも『傷害罪(刑法204条)』の適用となる「加療を要する傷害」を受ける怖れがあるという意味で、しかも、「大きい」とあるので、そのリスクが極めて高いことを示す(立証する)必要があります。
『傷害罪(刑法204条)』の適用となる「加療を要する傷害」については、平成6年(1994年)1月18日、名古屋地方裁判所が、「傷害について、人の生理的機能を害することを含み、生理的機能とは精神的機能を含む身体の機能的すべてをいうとし、医学上承認された病名にあたる精神的症状を生じさせることは傷害に該当する。」との判断を示しているので、DV被害の後遺症として、PTSD、うつ病、パニック障害、不安障害、身体化障害(身体表現性障害)などの後遺症を発症しているときには、『傷害罪(刑法204条)』を適用でき、同時に、「心身」の「心(精神)への重大な危害」を意味します。
つまり、「更なる」「大きい」という“条件”を踏まえると、DV被害の後遺症として、既に、PTSD、うつ病、パニック障害、不安障害、身体化障害(身体表現性障害)を発症し、通院加療(治療)を受けていて、今後、その症状が悪化する可能性があることを示す(申立て時に、「医師の意見書としての診断書」の提出する)必要があります。
令和6年(2024年)4月1日に施行(令和5年(2023年)5月12日成立)され、『配偶者暴力防止法』の“適用要件”となった「自由、名誉又は財産」に対する加害の告知による脅迫」に対し、メディアなどは、「精神的暴力」が加わり、「適用要件が拡大された」と報じていますが、“脅迫要件”が絞り込まれ、「更なる」「大きい」など細かな“条件”が書き加えられたことから、むしろ『同法』の適用を受け難くなり、『同法』は「後退した」といえます。
この令和6年(2024年)4月1日に施行された『(改正)配偶者暴力防止法』の適用基準は、平成15年(2003年)8月、国連の「女性差別撤廃委員会」が、締結国の日本政府に対する是正勧告、つまり、「ドメスティック・バイオレンスを含む女性に対する暴力の問題に対し、女性に対する人権の侵害としてとり組む努力を強化すること」、「『配偶者暴力防止法』を拡大し、様々な形態の暴力を含めること」に反しています。
極右・超保守の日本政府の目論見は、「DV被害者が、家庭裁判所に申立てた保護命令の発令をさせ難くする」、つまり、「保護命令の申立てを棄却する」こと、「保護命令の申立てを少なくする」ことです。
「保護命令の発令をさせ難く」したり、「保護命令の申立てをし難く」したりすることができれば、その後のア)つきまといの禁止期間は6月から1年に延長したり、既に、『ストーカー行為等の規制に関する法律(ストーカー規制法)』で規定しているイ)禁止行為に、緊急時以外の連続した文書送付・SNS送信、性的羞恥心を害するメール送信、位置情報の無承諾取得などを追加したりしたことは、重要な意味を持たなくなります。
しかも、「被害者と同居する未成年の子どもに対する接近禁止命令の要件」として創設された「当該子への電話等禁止命令」となる対象行為は、ア)監視の告知等、イ)著しく粗野乱暴な言動、ウ)無言電話、エ)緊急時以外の連続した電話となっていますが、イ)言動として「著しく粗野粗暴」の定義はなく、ウ)非通知での無言電話は、録音した音源での「音声/声紋分析による人物特定」が困難で、エ)なにを持って「緊急時」といえるのかの定義はなく、しかも、“連続”という条件まで設定されているのなど、被害者と同居する15歳未満の子どもとの電話などの禁止を求めるときの立証は、かなり難しくなっています。
つまり、法を先に進めているように見せているだけで、運用するうえでは、前に進んでいません。
内容を精査すると、DV加害者である(元)配偶者のストーキング(つきまとい行為)を規制するのではなく、黙認するかのように構築されているのがわかります。
不備・欠陥だらけの『配偶者暴力防止法』『ストーカー規制法』を放置し続ける 日本政府の政治姿勢は、常軌を逸した行為といえます。
③『配偶者暴力防止法』の致命的な欠陥-ⅲ)適用対象外の「性的暴力」
第3は、2度の刑法改正(性犯罪の厳格化、性犯罪規定の見直し)に至りながら、日本政府は、「DV行為としての性的暴力」について、『配偶者暴力防止法』による“一時保護”の決定、“保護命令”の発令の対象にしていないことです。
「同居している交際相手や配偶者からのレイプ(同意のない性行為、意に反する性行為)」は、「レイプ被害者が、レイプ被害後に、レイプ加害者が暮らす家で、生活をともにしなければならない」、「しかも、その家から逃げない限り、繰り返しレイプ被害を受ける」ことは、想像を絶する過酷な状況です。
「夫婦間レイプ」は、いまから37年前の鳥取地方裁判所の昭和61年(1986年)12月17日判決、同事件の控訴審(広島高等裁判所松江支部の昭和62年(1987年)6月18日)判決が、「夫婦間での強姦罪の成立を認めた判決」として広く知られています。
このDV・レイプ事件は、「配偶者である夫の繰り返される暴力に耐え切れなくなり、実家に逃げ帰った妻に対し、夫が友人と共謀して妻を輪姦(集団レイプ)した事件」ですが、この裁判により、それまでは夫の暴力や横暴に泣き寝入り状態だったものが、「夫婦の間でも、その夫婦生活が事実上破綻しているときには、強姦罪は成立する」との法的に基準が示された。
この裁判では、「婚姻関係が破綻しているのに、暴力をふるって妻と性交渉をもとうとする夫に対する婦女暴行罪が成立するのかどうか」が争われ、それまでの「夫は妻に性交渉を要求する権利があるから、夫の婦女暴行は成立しない」という通説を覆すはじめての司法判断で、「婚姻関係が破綻しているとき、夫婦間でも婦女暴行(夫婦間レイプ)は成立する」と有罪判決(懲役2年10月)を下したものです。
広島高等裁判所松江支部の控訴審(古市清裁判長)では、「法律上は夫婦であっても、婚姻が破綻して名ばかりの夫婦に過ぎない場合に、夫が暴行または脅迫をもって妻を姦淫したときは、強姦罪が成立する」との一審の事実認定に加え、「夫婦生活が事実上破綻しているときには、互いに性を求める権利・義務はない。」とし、控訴を棄却(昭和62年6月18日)、刑が確定しました。
DV事案では、同意のない性行為、意に反する性行為の強要(性暴力)は、少なくありません。
特に、配偶者である夫による慢性反復的(常態的、日常的な)なDV行為としての暴力に耐え切れなくなり、実家に逃げ帰ったり、『配偶者暴力防止法』に準じ「一時保護」の決定を受け、「母子生活支援施設」に入居したり、『同法』に準じ「保護命令」の発令により、家に残ったりしたDV被害者に対し、上記「DV・レイプ事件(夫婦間レイプ)」のように、DV加害者が「復縁」を求めたり、状況の改善を求めたりするときの接触では、苛烈な暴力行為が加えたり、レイプしたりすることは、DV加害者の常套手段のひとつです。
この状況の改善を求めたり、「復縁」を求めたりするときの接触で行使される「レイプ」は、「DV行為としての性的暴力」の典型的な「暴力後に、セックスに持ち込む行為」の延長線上にあります。
交際相手や配偶者からの性暴力における重要なポイントは、a)性行為の強要と性行為の拒否に対する暴力、b)暴力に対する和解の強要としての性行為です。
この「暴力後に、セックスに持ち込む行為」は、この「b」に該当します。
DVの“本質”は、「本来、対等な関係にある交際相手との間、夫婦との間に、上下の関係性、支配と従属の関係性を成り立たせたり、その関係性を維持したりするためにパワー(力)を行使する」ことです。
つまり、交際相手との間、夫婦との間に、「b」の性暴力が存在するとき、既に、この関係性には、上下の関係、支配と従属の関係が成り立っていることになります。
このb)の「暴力に対する和解の強要としての性行為」は、「暴力後の“仲直り”としての性行為」のことで、基本的に加害者の一方的な仲直りで、結果、日本特有のDV(デートDV)問題として、一方的な“仲直り”、つまり、このb)の「暴力に対する和解の共用としての性行為」が常態化しています。
こうした想像を絶するほど過酷な「DV行為としての性的暴力」は、DV被害者の「身体に重大な危害を受ける怖れ」、「心身に重大な危害を受ける怖れ」のある暴力行為以外のなにものでもありません。
この状況の放置は、先の「女性差別撤廃委員会」の是正勧告に加え、平成29年(2017年)6月2日に成立(同年7月13日施行)した110年ぶりの「刑法改正(性犯罪を厳罰化)」、その6年後の令和5年(2023年)6月16日に成立(同年7月13日施行)した「刑法改正(性犯罪規定の見直し)」で、日本政府が見送ってきたⅰ)平成20年(2008年)10月、「国際人権(自由権)規約委員会(市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」は、締結国の日本政府に対し、抵抗したことを被害者に証明させる負担をとり除き、強姦や他の性的暴力犯罪を職権で起訴するべきであるとの要請(是正勧告)、ⅱ)平成21年(2009年)8月、「女性差別撤廃委員会」が、最終見解(勧告)として、締結国の日本政府に対し、a)被害者の告訴を性暴力犯罪の訴追要件とすることを刑法から撤廃すること、b)身体の安全及び尊厳に関する女性の権利の侵害を含む犯罪として性犯罪を定義することとの要請(是正勧告)と深く関係するものです。
しかし、いまだに、この保守的な価値観を支持する人が圧倒的に多い日本社会では、「交際相手や配偶者が性行為を求めてきたら、応じなければならない(求めたら、応じるのが当然だ)」とのステレオタイプ的な固定観念が常識化し、フェミニストを名乗る人たちでさえ、「レイプ被害者が、レイプ加害者と同じ家に住み、生活をともにしなければならない異常さ」に対し、声をあげたり、問題を提起したりする人はほとんどいません。
このことも異常です。
➃ 配偶者殺人。3.44日に1人、妻は夫に殺される
日本社会は、世界的に見ても殺人事件が少なく、国連のUNODC(国連薬物・犯罪事務所)のデータでは、平成30年(2018年)の10万人あたりの殺人率は0.26、これは、ある程度の人口規模のある国の中では、シンガポールの0.16に次ぐ少なさで、殺人件数の長期推移をみても年々減少しています。
銃社会のアメリカの10万人あたりの殺人率は4.96です。
その殺人事件の少ない日本社会における殺人事件の50%以上は、「親族間の殺人」です。
つまり、日本における殺人事件の50%以上は、親族同士の殺し合いです。
少し古い数字ですが、平成25年(2013年)の殺人事件は858件で、そのうち「親族間の殺人」は459件(53.5%)で、その内訳は、親144件(31.37%)、子98件(21.35%)、配偶者155件(33.77%;夫106件(68.39%)・妻49件(31.61%))、兄弟姉妹36件(7.84%)、その他の親族26件(5.66%)となっています。
殺人・傷害・暴行など、家族が被害者である事件の数は、平成12年(2000年)は2,819件だったのが、21年後の令和3年(2021年)は12,630件と、実に4.5倍に増えています。
「親族間殺人」の1/3(33.77%)を占めるのが、「配偶者間殺人」です。
平成13年(2001年)に『配偶者暴力防止法』が制定されてから10年ほどは、年間130-120人の妻が夫に殺害されていましたが、徐々に減少していく一方で、殺人事件における配偶者間殺人の割合は、平成9年(1997年)の14%から21年後の平成30年(2018年)には19%まで増加しています。
「配偶者間殺人」のうち、夫が妻を106人(68.39%)殺害しています。
つまり、妻は3.44日に1人、夫に殺害されています。
平成26年(2014年)、同傷害2,697件のうち2,550件(94.55%)、同暴行2,953件のうち2,775件(93.97%)が、夫が加害者、妻が被害者です。
傷害・暴行事件では、男女の圧倒的な力の差となって表れます。
一方、圧倒的に力が劣る妻が、夫を殺害するときには、その多くが刃物などを使用します。
それは、平成25年(2013年)に妻が夫を殺害したのが49件(31.61%/7.93日に1人)と、傷害・暴行事件295件(5.22%)と違い殺害した件数、殺害率が高さに表れています。
不適切な表現かも知れないが、男性に比べ、圧倒的に力が劣る(圧倒的な体格差のある)女性は、刃物を使い確実に仕留めなければ、反撃にあい、殺されてしまうリスクがあります。
ここには、そうしなければならないという自身の恐怖体験、つまり、切実なDV被害者の実情が一定数存在し、加害女性が中高齢のときには、これまで虐げられてきた苦しみが恨みとなり、それが、殺害動機となっているケースが少なくありません。
それは、長期間、慢性反復的(常態的、日常的)なDV被害を受けてきた女性(配偶者や交際相手)が、精神が極限状態に陥り、殺されるのを回避する、つまり、「このままでは、殺されてしまう・・」との切実な思いで、苛烈な暴行を受けたあと、加害者が寝静まったときに刃物を使い殺害したり、自身や子どもが苛烈な暴行を受け、その対抗手段として刃物を持ちだし、殺害に至ったりするケースです。
つまり、傷害・暴行事件の検挙件数の多さから、夫による妻の殺害は、慢性反復的(常態的、日常的)な苛烈な暴行(身体的暴力)の延長線上で殺害に至る暴行があった(不適切な表現ですが、たまたま、今回は打ち所が悪く死亡した)のに対し、妻による夫の殺害は、必殺の一撃であるという異なる傾向を読みとることができます。
このことは、日本の不十分な『配偶者暴力防止法』であっても、制定後、顕著に夫による妻の殺害が減少した事実を踏まえると、長期間、慢性反復的な暴行の延長線上で殺害に至る暴行(不適切な表現であるが、たまたま、今回は打ち所が悪く死亡する)を加える前に、第3者が適切に介入し、DV被害を受けている妻(子どもがいるときには、子どもも)を保護し、加害者である夫と離すことが重要であることを示しています。
「離婚後の共同親権制度」が導入されると、『配偶者暴力防止法』に準じ「一時保護」の決定を受け、子どもを連れて「母子生活支援施設」に入居(避難)することが、“急迫の事情”に該当するのかが明確に示されていない(安全が担保されていない)ことから、この状況が大きく変わる可能性があります。
それは、一方の配偶者による苛烈な身体的な暴行により殺されるケースの増加だけではなく、DV被害者が、「避難できないなら、殺される前に殺す」と一方の配偶者を殺害するケースの増加です。
⑤ 「共同親権」と婚姻関係にない子どもの父親の「子どもの認知」
日本の『家族法(民法)』には、「家制度(家父長制)」に由来する致命的な欠陥、不備が幾つかあります。
そのひとつが、結婚の有無は関係なく、しかも、子どもの母親や未成年の子ども(出生前を含む)の同意は必要なく、子どもの父親は、本籍地のある市区町村役場に「認知届」を提出することで、子どもを認知することができる(任意認知)ことです。
例えば、未成年者の女性がレイプで妊娠し、親など周りの大人が妊娠を知ったときには人工妊娠中絶ができない時期で出産に至ったとき、そのレイプした男性が、本籍地のある市区町村役場に「認知届」を提出し(任意認知)、家庭裁判所の「共同親権」申立てをして認められると、そのレイプした男性は、子どものもう一方の親として「共同親権者」となります。
家庭裁判所が「共同親権」を認めなかったとしても、その申立てに対応するだけでも大きな負担になります。
また、レイプされ妊娠した女性が、人工妊娠中絶ができる時期であったときには、女性が人工妊娠中絶に至る前に、レイプした男性が、本籍地のある市区町村役場に「認知届」を提出すると、女性は、レイプした男性の同意なく人工妊娠中絶をすることができなくなります。
なぜなら、日本では、人工妊娠中絶には、配偶者(子どもの父親)の同意が必要だからです。
国際NGO「リプロダクティブ・ライツ・センター」の調査などでは、「中絶に配偶者(子の父親)の同意が必要な国」は、203ヶ国の中で、日本、台湾、インドネシア、トルコ、サウジアラビア、シリア、イエメン、クウェート、モロッコ、アラブ首長国連邦、赤道ギニア共和国の11ヶ国・地域に留まり、192ヶ国は、配偶者(子の父親)同意の規定は存在しません。
その結果、日本では、望まない妊娠(予期しない妊娠)をして、人工妊娠中絶を望んでも、同意が得られず(相手の居所がわからず、同意を得られる状況でないを含む)、誰にも相談できる状況にもなく、ひとりで出産し、出生児を殺害する(自然死・放置死を含む)といった悲劇もおきています。
この「人工妊娠中絶に配偶者(子どもの父親)の同意が必要」という問題には、配偶者である夫からのDV行為に耐えられず、家をでたあとに(『配偶者暴力防止法』に準じ“一時保護”の決定を受け、「母子生活支援施設」に入居し、福祉行政の支援を受けて転宅(アパートの賃貸契約をし、転居する)するときに、同法の「住民基本台帳事務における支援措置(転居先の住所を閲覧できなくする手続き)」をし、一方の配偶者と子どもの居所がわからない中で、新たな生活がはじめたなど)、妊娠がわかるケースもあります。
つまり、交際相手や配偶者(いずれも元を含む)からのDV被害から避難している状況で、DV加害者である交際相手や配偶者から「人工妊娠中絶」の同意を得るのは、困難を極めます。
「女性にレイプを加えた男性が、子どもを認知することは稀なこと、ほとんどない」と思われるかも知れません。
しかし、「性的行為には相手の同意(意思表示)が必要」との認識が極端に低い日本社会では、DV事案の一定数は、交際相手、あるいは、交際に至っていない先輩や同級生、同僚などのよく知っている人による「同意のない性行為(避妊に応じない性行為を含む)」「意に反した性行為」、つまり、レイプをきっかけに交際に至っていたり、レイプで妊娠したりしたことがきっかけで結婚に至っています。
これは、予期しない妊娠、望んでいない妊娠と呼ばれます。
性交を伴うレイプの74.4%は、顔見知り、つまり、よく知っている人による犯行です。
よく知っている人の「内訳」は、父母・祖父母・叔父叔母・いとこが11.9%、配偶者・元配偶者が9.4%、友人や知人(学校の教職員、先輩、同級生、クラブやサ-クル指導者や仲間、職場の上司や先輩、同僚、取引先の関係者)が53.1%です*8。
そして、同じ人(交際相手や配偶者、親・祖父母・叔父叔母・きょうだい・いとこなどの親族)から、生活をともにする家(一定期間、一緒に過ごす家や宿泊先を含む)で、もっとも多くレイプ(同意のない性行為、意に反する性行為)被害を受けるのが、DV被害者の女性と虐待被害者の子ども、そして、伝統・新興・カルトの区別なく宗教施設で生活している人です。
1981年(昭和56年)、『シアトル・タイムズ紙』は、「あなたのお嬢さんのクラスにこの次出席するとき、不特定の15人の女の子に目を留めてください…少なくとも1人、おそらく、2-3人は、近親姦の犠牲者であると考えて差し支えありません。」と報じています。
アメリカの人口約100万人の区域における近親姦の事例は、1971年(昭和46年)には30件でしたが、1973年(昭和48年)3月29日までにアメリカ軍がベトナムから撤退すると、1977年(昭和52年)には、500件以上に増加しています。
この事実を踏まえると、日清・日露、第1次世界大戦、太平洋戦争から帰還した日本兵の家庭で、相当数の性的虐待が加えられていたことは容易に類推できます。
この意味は重要で、性的虐待・体罰(身体的虐待)が、性的サディズム、性的マゾヒズム、ペドファリア(小児性愛)、窃視症(のぞき、盗撮)、窃触症(さわり魔、痴漢)、露出症など「パラフィリア(性的倒錯/性嗜好障害)」と深く関係しているからです*9。
「パラフィリア」の中で、性的な加害行為に及ぶ可能性のある者が見せる「性的興奮のパターン」の発達には、①不安または早期の心的外傷が正常な精神性的発達を妨げていたり、②性的虐待を受けるなど、本人の性的快楽体験を強化する強烈な性体験に早期にさらされることにより、性的興奮の標準的パターンが他のものに置き換わっていたり、③性的興奮のパターンとして、性的好奇心、欲望、興奮と偶然に結びつくことによって、そのフェティッシュ(物神崇拝、特殊な細部や部分対象への偏愛)が選択されるなど、しばしば象徴的な“条件づけ”の要素を獲得していたりするといった3つのプロセスが関係しています。
そして、「パラフィリア」が見せる「性的興奮のパターン」は、思春期前の幼児期・学童期の前半、つまり、6-8歳ころに(小学校1-3年生までには)既に発達を終え、その性的興奮のパターンがいったん確立されると、その多くは一生続きます。
その要因は、第1に、性的虐待・体罰(身体的虐待)などで得られる強烈な刺激は、依存症の発症メカニズムと同様に、脳の“快感中枢”がその強烈な刺激を「うまみ」して覚えてしまい、次の刺激を求め続けること、第2に、人は、耐えられない“苦痛(自身に対する罪悪感、嫌悪感も含む)”を覚えると、脳内ではモルヒネの6.5倍もの鎮静作用をもたらす「オピオイド(βエルドルフィンなど)」が分泌され、苦痛を和らげ、麻薬同様に、幸福感や爽快感をもたらし、この脳内麻薬「オピオイド(βエルドルフィンなど)」を求めて、敢えて苦痛を求める脳内麻薬依存脳がつくられることです。
つまり、「パラフィリア」の要因は、性的虐待・体罰(身体的虐待)などの被虐待体験で、その被虐待体験が、「加害トラウマ」として、性的虐待・体罰(身体的虐待)をもたらすことです。
太平洋戦争の帰還兵、空爆・沖縄戦の被災者を起因とする性的虐待・体罰(身体的虐待)、DVの世代間連鎖は、いま、4-3世代目を迎えています。
戦災孤児を含め戦時下・戦後の苦しい時代を生き延びた子どもが成長し、高度経済成長を踏まえ職を得て、収入が安定するまでの期間、生活困難からレイプに加え、盗みが加わる「強盗強姦」が数多く発生しましたが、経済復興が進み、国民所得が上昇しはじめると、レイプだけに留まらず、刑法犯罪は一気に減少に転じます。
一方で、帰還した日本兵、空爆・沖縄戦の被災者が結婚し、家庭を持つようになると、表面化し難い家庭内でのDV(夫婦間レイプを含む)、性的虐待・体罰(身体的虐待)が増加していきます。
ベトナム戦争反対運動、ウーマンリブ運動とともに、ピッピ―、フリーセックスなどの影響を受けたレイプ犯罪は、少しずつ現代型の性犯罪に様相を変えていきます。
それは、いまから62年前、北朝鮮への帰国事業が1シーン*10として収められている映画『キューポラのある街(昭和37年(1962年))』では、いま問題となっている「レイプドラッグ」、つまり、「飲み物に粉末の薬を入れられる集団レイプ未遂」の1シーンも描かれています(令和6年(2024年)4月15日現在)。
つまり、経済成長とともに、「やみくもに襲う性犯罪から、狙いを定めて計画的に襲う性犯罪」に変化していきます。
「レイプドラッグ」の問題は、いまの問題ではなく、60年以上も続く、レイプなどの性犯罪の温床となっていたことになり、歴代の日本政府、ならびに、日本の警察は、60年以上もの間、この「レイプドラッグ」の問題を放置し続けたことになります。
一方で、過激派、暴力団などの活動資金となった写真、ブルーフィルムが、生産設備、流通の整備などを背景に、大量生産が可能となり、1970年代末-1980年第初頭に「ビニール本」、昭和56年(1981年)以降、アダルトビデオ(AV)が市場に出回るようになりました。
性犯罪は、昭和40年(1965年)辺りから一気に減少傾向を示していることから、AVの普及と性犯罪の抑止には因果関係はありません。
逆に、そこで表現される性描写が多様化、過激化、暴力化する中で、その影響を受け、交際相手や配偶者との性行為そのものが多様化する一方で、交際相手や配偶者に対する性的暴力は、過激化し、暴力化し、女性のモノ化(性道具化)が顕著になっていきました。
ここには、性的虐待・体罰(身体的虐待)などの被虐待体験をしてきた人の「加害トラウマ」として、「パラフィリア」としての「性的サディズム」を結びついていたり、「ペドファリア」を結びついていたりする問題が絡んでいることが少なくありません。
*8 8人に1人が強制わいせつ被害(痴漢被害は3人に1人といわれているので実数ははるかに多い)を受け、15人に1人がレイプ被害にあっている日本で、被害を受けた人に向けられる2次加害(セカンドレイプ)の背景には、“精神論”とステレオタイプ的な理解、つまり、DVや性被害そのものに対し、無知(知らないこと)による無理解があり、DV/性暴力被害者とかかわる人が必要最低限、知っておく必要がある情報は、『別紙1b DV/性暴力被害者の私にかかわるすべての人たちに7つのお願い+α』にまとめています。
*9 性的虐待・体罰(身体的虐待)などの被虐待体験と「加害トラウマ」「パラフィリア」の問題は、レポート『別紙2d(簡易版)DV・虐待・性暴力被害。慢性反復的トラウマ体験に起因する後遺症(A4版192頁)』で詳述しています。
*10 映画『キューポラのある街(昭和37年(1962年))』には、もうひとつ、いまに至る人権・社会問題が描かれています。
それは、岸信介政権下の昭和34年(1959年)にはじまったのが、日本と北朝鮮の赤十字社により進められた在日朝鮮人とその家族による日本から北朝鮮への集団的な永住帰国・移住を進めた「帰国事業」です。
在日朝鮮人は、朝鮮半島の日本統治時代(1910年-1945年(明治43年-昭和20年))に、さまざまな事情で日本本土へ移った人、韓国政府による虐殺(済州島4・3事件)から逃れた人も一部いましたが、大多数は、太平洋戦争後に出稼ぎや朝鮮戦争の勃発などにより自ら密入国し、そのまま日本に居留した人でした。
そうした人々の中には、日本人と同様に、朝鮮特需などによる恩恵を享受した人もいましたが、依然として生活に困窮していた人も少なくありませんでした。
特に、昭和31年(1956年)の生活保護費の削減、同32年(1957年)-同33年(1958年)にかけての「なべ底不況」は、貧困層の生計を直撃しました。
在日朝鮮人の間では、朝鮮戦争による荒廃からの復興が進まず、また、政情不安を理由に、韓国への帰国を不安視する一方で、「社会主義体制のもとで、千里馬運動により急速な復興を実現した」とされた北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)への憧れがありました。
当時、社会主義国の北朝鮮と資本主義国韓国の体制間競争では、北朝鮮が優位に立っていました。
昭和30年(1955年)5月に結成された「在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)」と「日本共産党」は、北朝鮮を「地上の楽園」「差別がない」「衣食住の心配がない」と宣伝しました。
それに呼応した日本の進歩的文化人、日本共産党、帰国3団体は、繰り返し北朝鮮の経済発展の様子を伝え、在日朝鮮人に帰国の決意を促し、北朝鮮を訪問し、礼賛した日本共産党員寺尾五郎の『38度線の北(日本共産党の下部出版社である「新日本出版社」)』は、帰国希望者に大きな影響を与えたといわれています。
太平洋戦争敗戦後の「日本共産党」の党員の1/3は、「コミンテルンの一国一党の原則」により、在日朝鮮人でした。
昭和30年(1933年)に結成された「在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)」は、「日本共産党」から枝分かれた組織、つまり、元日本共産党員の集合体でした。
「帰国3団体」と呼ばれた朝鮮総連、日朝協会、帰国協力会のうち、日朝協会、帰国協力会の事務局は、日本共産党員で占められていました。
当時の日本における民族差別、子どもの教育や将来を見据えたときに、北朝鮮への帰国・移住を選択させる一因となりました。
これらの社会的な背景が、爆発的な運動の拡大をもたらしました。
ナショナリストの岸信介政権下の昭和34年(1959年)にはじまったのが、日本と北朝鮮の赤十字社によって行われた在日朝鮮人とその家族による日本から北朝鮮への集団的な永住帰国・移住を進めたのが「帰国事業」です。
昭和34年(1959年)-昭和59年(1984年)まで、中断を挟んで行われた「帰国事業」により、約9万3000人が、帰国船に乗って北朝鮮に渡ったとされており、その中には少なくとも7000人の日本国籍所有者がいたとされています。
この日本国籍所有者の多くが、在日朝鮮人の配偶者と子どもで、この「帰国事業」で、在日朝鮮人の夫とともに北朝鮮にわたった配偶者たちは「日本人妻」と呼ばれ、1,831人とされています。
また、在日朝鮮人の多くは朝鮮半島の南部、つまり、韓国(大韓民国)の出身であり、異郷への帰還でした。
日本の政党やメディアが「地上の楽園」「差別がない」「衣食住の心配がない」と宣伝した北朝鮮では、「帰国事業」で北朝鮮に降り立った人々は、「資本主義圏からきた危険分子である」として厳しい差別と監視のもとにおかれることになりました。
特に、日本人妻のいる世帯への監視は厳しいものでした。
「日本人妻たちは3年経ったら帰郷できる」という話を信じ、帰国船に乗り込んでいましたが、日本への自由帰国が許されることはありませんでした。
この北朝鮮への「帰国事業」は、在日朝鮮人と日本人の女性や子どもに対する非人道的行為であったにもかかわらず、その検証は、反省を含めてほとんど行われていません。
⑥ DV加害者の主張と「子どもの連れ去り」の2パターン
一般的に、問題になる実の親による「子どもの連れ去り」は、2つのケースです。
第1は、同居している夫婦と子どもが、離婚をしたいと考えている一方の配偶者が、子どもを連れて家をでて行き、そのまま別居状態となるケースです。
一方の配偶者の実家に帰省して、そのまま帰ってこないケースも含まれます。
DV加害者が、「一方の配偶者が子どもを連れ去った」「子どもと会えない(子どもと面会交流できない)」と訴える(主張する)のが、この第1のケースです。
それは、一方の配偶者が「離婚をしたい」と考える理由が、配偶者の自身に対するDV被害に耐え切れなかったり、配偶者の子どもに対する虐待行為を見るに耐え切れなかったりして、『配偶者暴力防止法』に準じ、「一時保護」の決定を受け、「母子生活支援施設」に入居し、福祉行政の支援を受けて転宅(アパートの賃貸契約をし、転居する)、そのとき、同法の「住民基本台帳事務における支援措置(転居先の住所を閲覧できなくする手続き)」をし、一方の配偶者と子どもの居所がわからない中で、別居状態がはじまったケースが該当します。
第2は、一方の配偶者が、子どもとともに一方の配偶者の実家などで別居生活をしている状況下(別居後、離婚が成立している状況も含む)で、子どもと離れて生活をしている(元)配偶者が、その別居先を訪れたり、子どもの通園・通学している学校園に迎えに行ったりして、子どもを自分のもとに連れ戻してしまうケースです。
DV被害者が訴える(主張する)のが、この第2のケースで、「児童誘拐事件(未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条))」に該当します。
『未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)』は、未成年者を、これまでの生活環境から離脱させて、自分や第3者の支配下に置くという犯罪行為です。
例えば、離婚に向けて実家で、一方の配偶者である母と生活をともにしていた2歳の長男が、長男が通園している保育園のお迎えで、自転車に乗せようとした長男の祖母の一瞬の隙を突いて、子どもと離れて暮らしている夫が、子どもを抱きかかえて連れ去り、自家用車で逃亡した事件がありました。
この夫は、発生した約6時間半後に通常逮捕されています。
この事件では、平成17年(2005年)12月6日、最高裁判所は、「長男の監護養育上、そのような行為に特段の事情もなく、たとえ親権者によるものでも正当とはいえず、未成年者略取にあたる」と判断し、『未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)』の成立を認めています。
一方で、第1のケースに該当する『配偶者暴力防止法』に準じ「一時保護」の決定を受けたDV被害者が、子どもとともに「母子生活支援施設」に入居し、福祉行政の支援を受けて転宅(アパートの賃貸契約をし、転居する)、そのとき、同法の「住民基本台帳事務における支援措置(転居先の住所を閲覧できなくする手続き)」をし、一方の配偶者と子どもの居所がわからないことに対し、一般的に、『未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)』の適用はありません。
なぜなら、第1のケースは、「自身の子どもが連れ去られた事件」ではなく、「自身の暴力行為が『配偶者暴力防止法』に該当し、配偶者の妻が『同法』の適用を受け、子どもとともに避難している事件」だからです。
少し厄介な問題は、第1の「『配偶者暴力防止法』の“適用”を子どもの連れ去り事件」と認識し、「離婚後の単独親権制度の導入」を目指して活動している極右・超保守の超党派「共同養育支援議員連盟(前.親子断絶防止議員連盟)」、自由民主党の議員連盟「日本の尊厳と国益を護る会」に所属する国会議員が、第2の「子どもの連れ去り事件(未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条))」のDV被害者の相談に親身に応え、強く「離婚後の共同親権制度の導入」を訴え、とり込んでいることです。
この行為は、新興宗教やカルト教団の勧誘(「自己啓発セミナー」などを隠れ蓑にマインドコントロールを仕掛けてくる)と同様に、実に狡猾で、とても厄介です。
⑦ 虐待被害とDV被害の経済的損失
ユニセフ(国際連合児童基金)は、平成27年(2015年)6月2日、「子どもへの厳しいしつけ(虐待)が子どもの人生を破壊し、多大なる経済的損失を生じさせる。」、「東アジア・太平洋地域においては、全地域のGDPの2%に相当する2,090億ドル(年間)、日本円に換算すると約26兆円にものぼる。」、「暴力をふるって体に危害を加える身体的虐待、性的な行為を強要したり見せたりする性的虐待、養育や保護の責任を放棄するネグレクト、暴言を浴びせるなどの心理的虐待(DVを目撃することを含む)の4分類の中で、このうち、経済的損失がもっとも高いのが心理的虐待である。」との報告を発表しました。
発達段階に日常的におこなわれる虐待は、子どもから積極性、自主性、意欲などを奪うことから、自信を喪失させ、自己肯定できなくさせるなど、本来獲得できるであろう能力(脳機能)を獲得し、十分に生かす機会を奪われる慢性反復的なトラウマ(心的外傷)体験となります。
特に、心理的虐待によって他者に恐怖心や敵意を抱くようになり、社会性・協調性の欠如、精神不安、自傷行為、自殺願望などという重荷を背負わされているにもかかわらず、本人は虐待を受けて育ったという自覚がないまま、「虐待を受け能力や将来を削りとられた自分」を「本来の自分」だと思い込んでいることが少なくありません。
しかし、ロバート・アンダ、ヴィンセント・フェリッティらの研究チームが、面前DVや虐待、ネグレクトといった幼児期の悲惨な体験が成人後にもたらす影響について調査した結果、「子ども時代のそうした体験が、成人してからの病気や医療費の多さ、うつ病や自殺の増加、アルコールや麻薬の乱用、労働能力や社会的機能の貧しさ、能力的な障害、次世代の能力的欠陥などと相関関係があるとわかった。」と、ユニセフが指摘している経済的損失について、「成人後にもたらされる影響」として問題視しています。
「親のいい分としての「厳しいしつけ(教育)」などの心理的虐待によって、子どもの将来の可能性を踏みにじれば、いずれその結果が社会にももたらされる」、つまり、「保健医療の負担増」、「暴力や犯罪の増加」について懸念を示しています。
令和4年(2022年)10月14日に削除(同年12月16日施行)されるまでの126年間、「子どもを懲戒する権利(民法822条)」を認めてきた日本は、政府公認のもとで、親子の関係性にパワー(力)を行使し、子どもを支配し、子どもの人生に悪影響を及ぼしてきました。
親が、子どもに対しパワー(力)を行使するのは、虐待行為です。
日本社会で、子どもに対する虐待行為としてあまり認識されて表現は、「しつけ(教育)と称する体罰(身体的虐待)だけでなく、a)過干渉、過保護、b)いき過ぎた教育(教育的虐待)、c)厳しいしつけ(教育)などです。
c)の厳しいしつけ(教育)の「厳しい」の意味は、①厳格で少しの緩みも許さない、厳重である、②いいかげんな対処が許されない、困難が多くて大変、③物事の状態が緊張・緊迫している、④すきまがなく密であるなどです。
つまり、「厳しいしつけ(教育)」とは、ア)子どもに厳格で、子どもに少しの緩みも許さないしつけ(教育)、イ)子どもにいい加減な対処を許さないしつけ(教育)、ウ)極度の緊張・緊迫状態のもとでおこなわれるしつけ(教育)、エ)子どもに逃げ道(親と異なる考えや行為)がないほど関係が密な中でおこなわれるしつけ(教育)のことです。
ユニセフは、「2017年(平成29年)時点で2-4歳の子どもの約63%(約2億5000万人)が、尻を叩く体罰が認められている国に住み、保護者から定期的に体罰を受けている」と報告しています。
この時点では、「親権」としての「子どもを懲戒する権利(民法822条/令和4年(2022年)10月14日に削除、同年12月16日に施行)」が削除されていないので、日本の子どもはこの約63%に含まれます。
また、DV被害者、ハラスメント被害者にも経済的な損失が生じています。
このことについては、アメリカ合衆国オレゴン州のビルズボロ警察が、「DV被害を受けている職員のうち74%が、仕事中に加害者からハラスメントを受けている」、「DV被害者の28%が仕事を早退したことがある」、「DV被害者の56%が仕事に遅刻したことがある」、「DV被害者の96%が、その暴力・虐待行為によって仕事に支障をきたした経験がある」と、DV被害が、被害者の仕事の効果性や効率性を損なうなど、職場においてもDV被害の影響が及んでいる状況をまとめています。
ところが、日本社会では、職場における社員、学校における生徒・学生のDV(デートDV)被害や性暴力被害の影響に対する意識は、皆無といえます。
日本社会は、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ(ジェンダーとしての差別を含む)、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなど、女性や子どもに対する暴力行為(人権侵害行為)が、大きな経済的損失を招いているという視点は皆無です。
国として126年間、「子どもを懲戒する権利(民法822条)」として、子どもに対する「しつけ(教育)と称する体罰(身体的虐待)」を認めてきた日本では、自身が、被虐待体験者と認識し難いことが背景となり、治療につながり難く、結果、差別・排除、DV(デートDV)、児童虐待、性暴力、いじめ、(教師や指導者などによる)体罰、ハラスメントなどの暴力行為に及ぶ加害者は、野放し状態です。
⑧ ユニセフの「提言」と日本乳幼児精神保健学会の声明
平成24年(2012年)4月に『民法766条』が改正されてから10年後の令和4年(2022年)6月25日、一般社団法人『日本乳幼児精神保健学会』は、離婚後の子どもの養育のあり方について発表しました。
この声明の冒頭で、「ユニセフの提言」を引用し、強調しています。
ユニセフの「提言」とは、「人間の脳は、乳幼児期・児童・思春期にもっとも発達し、とりわけ、受胎という命の誕生から最初の数年の間に、急激な回路の発達を遂げる。この時期に形成された人としての土台が人生全体へ強く影響を及ぼすことは、いまや発達科学の常識として良く知られたことである」、「発達阻害を防ぐには、妊娠から2歳の誕生日を迎えるまでの3年間-人生の最初の約1000日-への関心を高め、集中的にとり組む必要がある*11」というものです。
声明の最後で、「以下、当学会は、乳幼児・児童・思春期の精神医学の観点から、子どもの権利を最大限尊重するという理念を基本に、最新の科学的研究および豊富な臨床現場の知見に基づき、離婚後の子どもの養育に関して声明を発する‥」と目的を明確に示したうえで、ⅰ)離婚後の子どもに必要なことは、子どもが安全・安心な環境で同居親と暮らせること、ⅱ)子どもには意思がある、ⅲ)面会交流の悪影響、ⅳ)同居親へのサポート、ⅴ)離婚後の共同親権には養育の質を損なうリスクがあるとして、「離婚後の子どもの養育に関する法制度の改正には、子どもの視点に立った慎重な議論を求めるものである。」と締めくくった声明を発表しました。
この声明は、日本政府が、この問題に背を向け続けているだけではなく、極右・超保守が「離婚後の共同親権の導入」に向けて活動を活発させるなど、世界の流れに逆行しかねない中で大きな意味を持ちます。
しかし、極右・超保守の日本政府は、医師会のこうした声明、加えて、各都市の弁護士会の「反対声明」には耳を傾けることはありませんでした。
このユニセフの「提言」で、重要なことは、「発達阻害を防ぐには、妊娠から2歳の誕生日を迎えるまでの3年間-人生の最初の約1000日-への関心を高め、集中的にとり組む必要がある」は、「いまや発達科学の常識として良く知られたことである」という記述です。
「発達科学の常識」として、「妊娠から2歳の誕生日を迎えるまでの3年間」で、妊娠している女性がDV被害を受けたり(日本では、その概念が知られていない「胎児虐待」に該当します)、出生した子どもが、両親間のDV行為を見たり、聞いたり、察したりする状況(面前DV=心理的虐待)に置かれたり、子どもが親から虐待行為を受けたりすると、その子どもには、どのような発達阻害がもたらされるのかについて正確に知る必要があります。
つまり、DV・虐待事案のある父母間の離婚では、離婚後の面会交流において、「子どもは安全に対する権利を有する」、「女性や子どもを危険にさらさないように考慮しなければならない」ことが“前提”となります。
このことは、離婚後の面会交流の実施の“前提”は、「父母間にDVがあっても、親と子どもの関係には関係がない(影響が及ばない)」といった“非科学的”な考えを踏まえた「親の権利」に準じるのではなく、子どもの面前DV(胎児虐待を含む)・被虐待体験の影響(心身の発達に及ぼす深刻なダメージ)を踏まえ、「子どもの安全」を第1にしなければならないことを意味します。
加えて、妊娠している女性に対するDV被害を防ぐ、つまり、妊娠5週目以降の胎児の中枢神経系の発達阻害を防ぐ視点に立つ必要があります*12。
ユニセフの提言としての「発達科学で常識とされる事実」は、世界に類を見ない日本の社会病理としての「認知症患者数((C-)PTSDの発症者はアルツハイマー型認知症を発症する高リスクがある)」「精神疾患の患者数」「摂食障害(拒食症・過食症)の患者数」「自殺者数」「アルコール・薬物、ギャンブル依存者数」「ひきこもり者数」などに明確に示されています。
*11.12 長期間、慢性反復的(常態的、日常的)な被虐待体験がもたらす影響については、レポート『別紙1b DV/性暴力被害者の私にかかわるすべての人たちに7つのお願い+α(A4版47頁)』、レポート『別紙2d(簡易版)DV・虐待・性暴力被害。慢性反復的トラウマ体験に起因する後遺症(A4版192頁)』で詳述しています。
特に、妊娠5ヶ月に達した女性がDV被害を受けると、母体の「コルチゾール」は、未成熟な胎盤の血管を経て、からだ(内臓)や生後6ヶ月まで未熟な「血液脳関門」を介し中枢神経系(脳と脊髄)の発達にダメージを及ぼす事実を医学的(科学的)な根拠にもとづき知ることは特に重要です。
(8) 「共同親権法案」の懸案事項-ⅲ) 面会交流が祖父母まで拡大
令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」では、「一方の親」に限定していた「面会交流の対象者」を「その一方の親の祖父母」まで拡大しています。
例えば、「2-(7)-⑥DV加害者の主張と「子どもの連れ去り」の2パターン」の中で示している「別居中、保育園のお迎え時におきた子どもの父親による「子どもの連れ去り事件」に対し、平成17年(2005年)12月6日、最高裁判所が「長男の監護養育上、そのような行為に特段の事情もなく、たとえ親権者によるものでも正当とはいえず、未成年者略取にあたる」と判断し、『未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)』の成立を認めてからは、学校園は、在籍していたり、転校してきたりした児童のDV事案に対応するようになりました。
DV被害を訴え、子どもを連れて実家に帰った一方の配偶者が、実家の近くの学校園に転園・転校したとき、「DV被害を受けて実家に帰ってきたこと、「夫婦関係調整(離婚)調停」や「監護者指定調停・審判」で、子どもとの面会交流は認められないと決まっていること」などを学校園に伝えることで、DV加害者である一方の配偶者(子どもにとっての一方の親に加え、その親の祖父母、きょうだいなどの親族を含む)が、ⅰ)子どもを迎えにきたり、ⅱ)学校園の運動会・学芸会などの行事に参加したりしないように協力を得ることができるようになりました。
その結果、DV加害者である一方の親や祖父母、きょうだいなどの親族が、子どもを迎えにきたときには、子どもと接触させずに校長室や保健室で待機させたり、警察に通報し、警察官に駆けつけてもらったりすることができました。
しかし、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が成立・施行され、「2-(2)離婚後の親権の決定」のb)の家庭裁判所で、c)の「共同親権を認めると子どもに対する虐待行為、元配偶者に対するDV行為などが生じ、子の利益を害する」に“該当しない”と判断し、DV事案・虐待事案でありながら、子どもの監護者でないもう一方の親が「共同親権者」となったとき、子どもが通う学校園は、“これまで”の対応が一転することになります。
それは、ⅰ)では、ア)一方の親が、「子どもの共同親権者である」ことを盾に、子どもを迎えにきて連れて帰ったり、イ)祖父母が行事に「面会交流が認められている」と迎えにきて連れて帰ったり、ⅱ)では、一方の親とその祖父母が学校園の行事に参加したりすることに対し、学校園は、「共同親権者」である一方の親、「面会交流」が認められている一方の親の祖父母に対し、断ったり、警察に通報したりする根拠(理由)を失うことです。
また、DV加害者のいう『配偶者暴力防止法』に準じた「一時保護」の決定を受け、子どもとともに「母子生活支援施設」に入居したことに対する「子どもの連れ去り(子連れ別居)」ではなく、子どもの監護者でないもう一方の親が「共同親権者」となり、次は、子どもの監護者であろうとする可能性がでてきます。
このとき考えられるのは、第1に、子どもの監護者であろうとする共同親権者であるもう一方の親は、家庭裁判所に「子の監護者指定の調停・審判」を申立ててくることと、第2に、「共同親権者」であるもう一方の親との面会交流が開始されたことを受け、子どもの監護者でないもう一方の親(共同親権者)との面会交流に加え、その祖母との面会交流においても、そのまま子どもを返さない可能性があることです。
第2は、「2-(7)-⑥DV加害者の主張と「子どもの連れ去り」の2パターン」の第2のパターンの「子どもの連れ去り」に該当しますが、「2-(7)-⑥DV加害者の主張と「子どもの連れ去り」の2パターン」で示しているように、『 平成17年(2005年)12月6日、最高裁判所は、「長男の監護養育上、そのような行為に特段の事情もなく、たとえ親権者によるものでも正当とはいえず、未成年者略取にあたる」と判断し、『未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)』の成立を認めている 』ことを根拠に、子どもの監護者でないもう一方の親が、共同親権者となったとしても、面会交流の対象者にその共同親権者となった一方の親の祖母が加わったとしても、『未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)』を適用できます。
ただし、警察に直ちに通報し通常逮捕に至ったケースではなく、一定の時間を経て、警察に相談したとき、警察が、「被害届」「告発状」の受理を躊躇する可能性があります。
その間、家庭裁判所に「子の監護者指定の調停・審判」を申立て、家庭裁判所の判断を仰ぐにしても、連れ去れた子どものひき渡しは簡単ではありません。
「DV事案」における「離婚後の子どもの連れ去り事案」の解決は容易ではありません。
なぜなら、家庭裁判所に「監護者指定の調停・審判」を申立て、「監護者と指定され、子どもの引き渡しが決定」されても、その指定の日時に、家庭裁判所に子どもを連れてこない可能性があります。
子どもを連れてこない(子どもを引き渡さない)とき、子どもの引渡しを実現するためには、別途、「直接的な強制執行の手続き」をする必要があります。
「直接的な強制執行」は、債務者の住居等で実施されますが、債務者が住居等にいることが必要で、例えば、子どもが祖父母宅に預けられているときは、子どもは、債務者が占有する住居等以外の場所で居住していることになることから、祖父母の同意が必要となります。
万一、祖父母の同意が得られないときには、別途、家庭裁判所から占有者(この場合、祖父母)の同意に代わる許可を得る必用があります。
しかも、実際に、その住居(この場合、祖父母の家)で直接的な強制執行を実施するかの判断は、執行官に委ねられます。
執行官の判断により、「直接的な強制執行」を実施しても、留守を装ったり、子どもを引き渡すことを拒否したりすることもあります。
また、正当な手続きを経ずに拘束されている者の救済を求める手段の『人権保護法』にもとづく「請求」で、請求から1週間以内を目処に実施される審問で「相手側の行動に違法性がある」と認定されると、「子どもの引渡しを命じる判決」が得られますが、その後の効果は、「監護者指定の調停・審判」の決定を受けた「直接的な強制執行」と同じです。
中には、転職し、子どもを連れて転居していることもあります。
海外に転居しているときには、『ハーグ条約(国際的な子どもの奪取についての民事上の側面に関する条約)』にもとづく『国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律』に準じた「子どもの返還決定手続き」をする必要があります。
先の警察署が、「告発状」を受理し、「児童誘拐事件(未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条))」となったときには、直ちに捜査が開始されます(「被害届」には捜査の強制力はありません)。
しかし、「共同親権」の有無は関係なく、子どもを連れ去った子どもの監護者でない一方の配偶者(子どもにとっての一方の親)が、国籍が日本以外の国で海外に住んでいたり、子どもを連れ去ったあとに海外に転居していたりするときには、「居住している国が、アメリカ合衆国、大韓民国(韓国)の2ヶ国か」、「それ以外の国か」という問題がでてきます。
なぜなら、日本政府は、この2ヶ国としか『犯罪人引渡し条約』を締結していないからです。
因みに、アメリカ合衆国は69ヶ国、フランスは96ヶ国、イギリスは115ヶ国、韓国は25ヶ国と『犯罪人引渡し条約』を締結しています。
つまり、日本で犯罪に及び、『犯罪人引渡し条約』を締結していない国に逃亡すると、基本的に、逃亡先で逮捕されたとしても、その国の法律にもとづき裁判が実施され、身柄を引き渡してもらわない限り、日本の法律にもとづき裁判を実施することはできないわけです。
これらの条約にもとづく引き渡し請求がなされたときの日本国内の手続きは、『逃亡犯罪人引渡法』で定められています。
日本国民を縛るさまざまな法を制定したり、法を改正したり一方で、2ヶ国としか『犯罪人引渡し条約』を締結していない日本政府の姿勢は、日本国民を大切にしていないことを示すものです。
(9)「共同親権法案」の懸案事項-ⅳ)「共同親権」で収入は父母合算に
いまの日本で、「離婚後の共同親権制度を導入」するなら、廃止しなければならない制度が2つあります。
ひとつは、「2-(2)『協議離婚(民法763条)』と「共同親権法案」」、「2-(5)「性格の不一致」を起因とする離婚は、離婚後の話し合いを困難に」の中で、“致命的な欠陥”と示した「律令制(男子専権離婚)」、儒教思想にもとづく「家制度(家父長制)」の流れを汲み、「離婚」の87.8%を占める世界で唯一の特殊な『協議離婚制度(民法763条)』です。
もうひとつは、戦前の「家(家制度)」を基軸に制度設計されている「税制度」「社会保障制度(年金制度を含む)」を廃止し、日本以外の世界の国々と同様に、「個人」を基軸とした制度設計に構築し直すことです。
これは、いうまでもなくパラダイムシフトを伴う大改革となります。
この問題は、日本が、他国が採用している「離婚後の共同親権(実際は、共同監護)」を導入したとしても、社会システムが、「個人」を基軸とした制度設計している他国(世界の圧倒的多数の国々)と「家」を基軸に制度設計されている日本とでは、その運用は、まったく異なること意味します。
日本の「税制度」「社会保障制度(年金制度を含む)」は、戦前の税制度を継承し、「家(家制度)」を基軸に制度設計されているので、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正(共同親権法案)」が成立・施行され、離婚した父母が「共同親権」を選択したり、家庭裁判所が「共同親権」と決定したりすると、いうまでもなく、子どもの親権者は父母2人となります。
つまり、子どもの親権者の所得は、婚姻時と同じ、父母2人の所得の合算となります。
例えば、収入が910万円未満であるとき利用できた「高校の無償化」が、ひとり親家庭の子どもが、父母2人が共同親権者となると利用できなく可能性があります。
「高等学校等就学支援金(高校の無償化)」の受給における保護者の定義は、「子に対して親権を行う者」と定められていることから、「離婚後の共同親権」を選択すると、子どもの親権者は父母2人となり、その所得は、父母2人の所得の合算で判定されることになります。
つまり、父母2人の収入が910万円を超えると「高校無償化」の対象外となることから、共同親権者となった子どもの監護者でない一方の親が、「高校」に進学する費用の相当分を負担しないと、監護者と生活している子どもは、高校に進学できない可能性もでてきます。
しかも、「2-(2)『協議離婚(民法763条)』と「共同親権法案」」の中で示している「離婚後の親権を定める」のd)で、「既に、離婚に至っている父母に対しても適用される、つまり、「いま、離婚し、子どもの監護者(単独親権者)でない一方の親との間で、c)を除き、a)b)で、子どもの監護者でない一方の親が、子どもの「共同親権者」となる可能性があります。」と述べているように、過去の離婚に遡及して適用されます。
このことは、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が成立・施行されると、親が離婚し、ひとり親家庭で、「高校の無償化」を利用し、高校進学を考えている子どもが、一転して、高校に進学できなくなる可能性があることを意味します。
また、令和元年(2019年)10月、幼稚園・保育所は、すべての3-5歳児(就学前3年間)と住民税非課税世帯の0-2歳児の利用料が無料になり、令和2年(2020年)4月、私立高校の授業料の実質無償化が全国でスタートし、同年同月、大学生などへの「給付型奨学金」「授業料減免」について、対象者・金額ともに大幅拡充してきましたが、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が成立・施行すると、同じ理由から、これらの制度の利用が限定的になる可能性があります。
ひとり親の実収入は「範囲内」であっても、子どもの監護者でない一方の親が「共同親権者」となり、子どもの親の収入が父母2人の合算となることで、上記の例のように、「高校の無償化」を利用できなくなるだけではなく、「就学支援金」「児童手当」「児童扶養手当」「障害年金」などの手当ての対象外になったり、収入の多い共同親権者の預貯金口座に振り込まれたりすることになります。
また、同じ理由で、ひとり親家庭が、生活保護の受給を受けられなかったり、法テラスの利用ができなかったりします。
所得制限で影響が及ぶ可能性のある「27の支援策」は、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、補装具費支給制度、小児慢性特定疾病児童等への医療費助成制度、幼児教育・保育の無償化、幼稚園等における副食費免除、保育所等における副食費免除、就学援助制度、特別支援教育就学奨励費、高校無償化(高等学校等就学支援金制度)、高校生等奨学給付金、大学無償化(高等教育の就学支援新制度)、貸与型就学金、まごころ奨学金、母子・父子自立支援プログラム策定事業、自室支援教育訓練給付金事業、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援制度、高等職業訓練促進給付金等事業、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業、ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業、訴訟上の援助、訴訟費用執行免除、代理援助及び書類作成援助、セーフティーネット登録住宅の家賃低廉化支援、セーフティーネット登録住宅の家賃債務保証料等低廉化支援、セーフティーネット登録住宅への住み替え支援です。
一方で、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正(共同親権法案)」には、「養育費の支払い義務」は課せられておらず、強制徴収の仕組みもありません。
このことは、子どもの監護者の親が、子どもの監護者でない一方の親(共同親権者)より収入が少なく、後者からの「養育費」が“不払い”であったり、“未払い”があったりしても、子どもの親の収入は父母2人の合算であることから、「育児手当」「就学支援金」「児童手当」「児童扶養手当」「障害年金」などの手当ての対象外になったり、収入の多い共同親権者の預貯金口座に振り込まれたりする(父母ともに働いているときは、恒常的に所得が高い方が受給者となる)可能性があります。
まるで、「結婚し「家」に入り、出産した女性が、離婚し、子どもの監護者(親権者)となった」ことに対する“罰則規定”のようです。
この“罰則規定”と「3-(5)「共同親権法案」の懸案事項-ⅱ)明確さに欠ける「急迫の事情」で示している『配偶者暴力防止法』の適用(保護決定の発令、一時保護の決定)が単独で行使できる「急迫の事情」に定められていないことから、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正(共同親権法案)」は、結婚し、出産した女性を離婚でき難くする「離婚禁止法」との指摘が生まれています。
「家」を基軸にした「税制度」「社会保障制度(年金制度を含む)」の日本において、令和6年(2024年)の本国会に提出した「家族法(民法)の家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」が可決・成立することは、これまで、ひとり親家庭の生活基盤を支えていた制度を根こそぎ奪いとることになります。
それは、ひとり親とともに生活する子どもの将来を奪いかねないだけでなく、子どもの安全に生活する基盤そのものを破壊しかねないものです。
つまり、令和6年(2024年)の本国会に提出した「家族法(民法)の家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」は、『子どもの権利条約』で定めている「子どもの権利」、つまり、ア)差別の禁止(差別のないこと)、イ)子どもの最善の利益(子どもにとってもっともよいこと)、ウ)生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)、エ)子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)という4つの原則のすべてに反していることになります。
そして、戦前の「家(家制度)」を基軸とする「税制度」を継承する日本の「税制度」「社会保障制度(年金制度を含む)」のもとで、「離婚後の単独親権制度を導入」することは、明治政府が「軍国化(国民皆兵、富国徴兵)」を進めるために実施した「税制改革」に通じるものです。
その「税制改革」を支えたのが「家制度(家父長制)」です。
令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」には、ⅰ)社会保障費の支出を削減する、つまり、これまで、離婚後のひとり親が利用できた社会保障制度を利用でき難くすることで社会保障費の支出を削減する意図(目論見)が示されています。
同時に、ⅱ)離婚後に社会保障制度を利用でき難くすることで、結婚し「家」に入り、出産した女性は離婚を選択し難くすることもできます。
日本の女性の高齢者の貧困の要因が、「支給される年金受給額」が男性よりも低く設計され、このことが、女性の高齢者の生活保護受給者の増加の要因となっています。
日本の「年金制度」は、夫婦揃った「家」に支給することで生計が成り立つように制度設計されています。
つまり、受給年齢になったとき、夫婦揃っていないと、日本の「年金受給額」で生活は成り立たないように設計されていることが、高齢女性の貧困につながり、高い「生活保護受給率」の要因となっています。
つまり、ⅱ)の結婚し「家」に入り、出産した女性は離婚を選択し難くなることは、結果として、「社会保障」としての「生活保護受給者」の削減につながります。
さらに、「生活保護受給者(特に医療扶助費)」の削減につなげる政策が、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案」に含まれています。
それは、「2-(1)日本で「離婚」するには」で述べた『民法770条1項(離婚事由)』の改正で、d)の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」の削除することです。
このd)は、「人権侵害」として問題視されてきた離婚事由ですが、極右・超保守の日本政府の意図(目論見)は別にあり、それは、「重度の精神病に罹患した人の生活保護受給者(特に、医療控除)の削減」を意図しています。
これは、極右・超保守の政権、政党、政治家、その政治支援団体の政治姿勢は、「家」を基軸とした「自助」を“前提”としていることです。
つまり、日本の政治姿勢は、社会保障費を増大させる「公助」は否定しています。
日本政府の認識、つまり、高齢女性の貧困、重度の精神病疾患者は社会保障費を増大させ、国の財政負担を招いているとの認識は、福祉行政の支援が必要な人たちに対する偏見・差別的な発言などに示されています。
・「マイナンバーと預貯金口座との紐づけ」も税制改革の一環
先の『戦前の「家(家制度)」を基軸とする日本の「税制度」「社会保障制度(年金制度を含む)」のもとで、「離婚後の単独親権制度を導入」することは、明治政府が「軍国化(国民皆兵、富国徴兵)」を進めるために実施した「税制改革」に通じる』との視点を持つことで、マイナンバー制度の位置づけがはっきりしてきます。
安倍晋三政権は、平成25年(2013年)5月、『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)』を成立させ、同28年(2016年)1月1日、「社会保障・税番号制度(国があらゆる個人情報を紐づけ、12桁の個人番号で管理する「マイナンバー(個人番号)制度)」」が導入しました。
令和3年(2021年)5月19日に『預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(口座管理法)』が成立(令和6年(2024年)4月1日施行)させ、預貯金口座への個人番号(マイナンバー)付番が決まりました(マイナンバーと預貯金口座との紐づけ)。
同年9月に「デジタル庁」を発足させ、「健康保険証」機能を「マイナンバーカード」に統合するなど、全国民に「マイナンバーカード」の発行を進めています。
このマイナンバーと預貯金口座との紐づけについて、日本政府は、令和2年(2020年)4月27日時点の住民基本台帳の記載者に実施した「一律で1人10万円を支給する特別定額給付金」をはじめとする幾つかの給付金を支給しました。
結果、日本政府は、多くの市民の預貯金口座の把握をしています。
4.「離婚後の共同親権制度」の法制化に至る経緯
(1) 離婚後の子の監護(民法766条)。面会交流と『人権条約』
日本政府は、『ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)』の批准・締結(平成25年(2013年)5月22日)するにあたり、「離婚後の共同監護(親権)制度」を採用している他国(世界の圧倒的多数の国々)に国籍のある人と「離婚後の単独親権制度」を採用している日本(他にトルコとインド)に国籍のある人との国際結婚における「離婚後の子どもの監護」などの問題に対応するために、その2年前の平成23年(2011年)6月3日、『民法766条』を改正しました。
この『民法766条』では、“子の監護”について必要な事項の例として、「父、または、母との面会やその他の交流、子の監護に要する費用の分担」を明示したうえで、「父母がその協議で、子の監護について必要な事項を定めるときには、子の利益をもっとも優先して考慮しなければならない(親権・監護権の決定時に「子の利益をもっとも優先して考慮しなければならない)」と規定しています。
平成元年(1989年)11月20日、国連で採択され、日本政府が、平成6年(1994年)4月22日に批准・締結(平成2年(1990年)発効)した『子どもの権利条約』の19条では、「子どもが両親のもとにいる間、性的虐待を含むあらゆる形態の身体的、または、精神的暴力、傷害、虐待、または、虐待から保護されるべきである」と定め、「それが起こるとき、親権や監護権、面会交流の決定において、親密なパートナーからの暴力や子どもに対する暴力に対処しないことは、女性とその子どもに対する暴力の一形態であり、拷問に相当し得る生命と安全に対する人権侵害である」、「子どもの最善の利益という法的基準にも違反する」と規定しています。
日本の「親権」は、「3-(3)親権と監護権」で示しているように、ア)子どもに監護や教育をする権利義務(民法820条)、イ)子どもの居所を定める権利(民法821条)、ウ)子どもを懲戒する権利(民法822条/令和4年(2022年)10月14日に削除、同年12月16日に施行)、エ)子どもの就職について許可をする権利(民法823条)」で、「財産管理」として、オ)財産を管理する権利(民法824条)、カ)契約などの法律行為を代理する権利(同条)を指します。
① 「女性差別撤廃委員会」の日本政府に対する是正勧告
昭和54年(1979年)12月18日、国連総会で成立し、日本政府が、昭和60年(1985年)6月25日に批准・締結した『女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約)』の「女性差別撤廃委員会」は、平成26年(2014年)、締結国である日本政府に対し、「面会交流のスケジュールを決定するときには、家庭内暴力や虐待の履歴があれば、それが女性や子どもを危険にさらさないように考慮しなければならない。」と勧告しています。
国連の「子どもの権利委員会」から是正勧告を受けながらも放置し続けた日本政府は、漸く、批准・締結から16年8ヶ月経った平成28年(2016年)6月3日、『児童福祉法』の一部を改正し、その1条で「すべての児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること‥」、同2条で「児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない」と規定しました。
この条文は「国内法」として重要な意味を持ちます。
なぜなら、改正前、子どもは「福祉の対象」であったものが、この法改正で、『子どもの権利条約』に準じ、子どもは「福祉を受ける権利の主体」と子どもの位置づけが変わっているからです。
一方で、本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」には、子どもは「福祉を受ける権利の主体」であるという視点はなく、同時に、同法2条に反しています。
同時に、本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」には、「2-「改正案」の懸案事項-ⅱ)」で示したように、『子どもの権利条約』に規定している「子どもの意見の尊重(子の意思表明権)」の記載がありません。
この「子の利益(権利)」を主体としていない「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」は、『子どもの権利条約』の「子どもの最善の利益(3条)」、「自由に意見をいう権利(12条)」に反するものです。
② 『民法766条』の改正と面会交流調停の推移
日本では、いまだに、保守的な価値観を支持する人たちが主流で、「虐待を加えてきた人であっても親、人を殺した人であっても親、肉親の絆は切れるものではない」、つまり、「子どもにとって、どんな親でも親であることには変わらない」と、親と会ったり、親と過ごしたり、親と暮らしたりするのは子どもの義務、責任との考えを子どもに押しつけ、決まりごとと行動を押しつけます。
子どもの思いや考え、意志、子どもの人権を尊重することはなく、ほとんど大人(家)の都合で決められます。
それでも、平成13年(2001年)に『配偶者暴力防止法』が施行されると、「婚姻破綻の原因は、配偶者のDV行為である」として、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停を申立てたり、その後、調停不調となり提訴し裁判となったりした民事事件で、「被害者であり、親権を得た、あるいは、監護者となった母親と暮らすことになる子どもが、DV加害者である父親と面会交流をおこなうことは、加害者に対する恐怖心を拭えない母親の精神的苦痛となり、相互の意思疎通ができない中での子どもとの面会交流の実施は子の福祉に反する(その後、「子の利益」に変更)」、「加害者である父親と子どもとの面会交流が及ぼすリスクと悪影響」を主張することで、離婚後、DV加害者である父親と子どもの面会交流を拒むことができました。
平成13年(2001年)に『配偶者暴力防止法』が施行されると、東京家庭裁判所(平13.6.5審判)、横浜家庭裁判所(平14.1.16審判)、東京地方裁判所(平14.5.21審判)など、「子の監護に関する処分(面会交渉)審判に対する抗告事件」において、「子の福祉の面から恐れが高い」との解釈で、面接交渉(面会交流)の申立を却下する判決が多数下されました。
平成19年(2007年)8月22日、東京高等裁判所で行われた「子の監護に関する処分(面会交渉)審判に対する抗告事件(父(相手方)から母(抗告人)に対して、面接交渉を求めた事案の抗告審)」では、「母には、父が未成年者らを連れ去るのではないかと強い不信感があり、面接交渉に関する行動につき信頼が回復されているといいがたく、未成年者らも将来はともかく、現在は相手方との面接を希望しない意思を明確に述べているような状況においては、未成年者らと相手方との面接交渉を実施しようとするときには、未成年者らに相手方に対する不信感に伴う強いストレスを生じさせることになるばかりか、父母との間の複雑な忠誠葛藤の場面にさらすことになる結果、未成年者らの心情の安定を大きく害するなど、その福祉を害する恐れが高く、未成年者らと相手方の面接交渉を認めることは相当ではない。」として、面接交渉(面会交流)を認めた原審判をとり消し、面接交渉(面会交流)の申立を却下しています。
ところが、「7-(1)-④全米法曹協会は、「片親疎外症候群」はエセ科学、信用性否定」で示しているように、2006年(平成18年)、「全米法曹協会(ABA)」は、1980年代初めにリチャード・A・ガードナーが提唱した「片親疎外症候群(PAS)は、根拠のない独断的な主張である」、「エセ科学(junk science)として、その信用性を否定」と批判(提言)しているにもかかわらず、細矢郁判事らは、『面会交流が争点となる調停事件の実情及び審理の在り方―民法766条の改正を踏まえてー(家庭裁判月報、2012年7月/49-50頁)』)の中で、このガードナーの所説を引用し、「子どもが一方の親と過剰に強く結びつき、もう一方の親を激しく非難・攻撃するなどして接触も拒絶する現象を「片親疎外症候群」として概念化」し、この概念は、「一方の親の操作(洗脳)によって生じる病理的現象」として提示しました。
この細矢郁判事らの提示により、「離婚後の面会交流のあり方」は、大きく舵を切ることになりました。
それは、DV被害者である(元)妻の「父親を怖れている子どもと父親の面会は、子の利益(福祉)の観点から好ましくないので実施しない」との主張は認められ難くなり、「夫婦間にどのような経緯・懸案事項があろうとも、父親と子どもとの面会は子の利益(福祉)の観点から必要不可欠であり、家庭問題情報センター(FPIC)などの第3者機関を介することで、面会は可能である。」との考えにもとづく判断が下されるようになったことです。
そのため、これまで以上に、第3者機関を介しても面会交流は不可能であることを医学的な根拠(裏づけ)を持って主張する(示す)ことが必要になりました。
全米法曹協会が、「根拠のないエセ科学と信用性を否定」したガードナーの所説を引用し、「離婚後の面会交流のあり方」を劇的に変えた細矢郁判事は、平成30年(2018年)4月1日に東京高等裁判所の判事、同年8月27日に東京家庭部総括判事を経て、令和5年12月12日、静岡家庭裁判所所長に就いています。
そして、この民事事件の方向転換に伴い、FPICなど限られていた第3者機関は、規制緩和された事業のように新たに面会交流支援機関が参入してきました。
しかし、先に記しているとおり、DV被害者にとって、子どもをDV加害者である父親と面会交流させるには、大きな精神的負担を伴います。
なにより、父親が、母親にDV行為としての暴力を加えるのを見たり、聞いたりしてきた慢性反復的(常態的、日常的)な被虐待体験(小児期逆境体験)をしてきた子どもが、その父親と面会交流するのは、父親の機嫌を損ねないように顔色を伺い、率先して意に添うようにふるまうなど気を遣い、時に、トラウマの追体験となり苛烈なトラウマ反応(PTSDの侵入によるフラッシュバック・悪夢、パニックアタック(発作)、解離、中途覚醒による断眠・不眠、疼痛、不定愁訴、身体化(気管支喘息、反復性腹痛、起立性調節障害、偏頭痛、チック、夜尿、アトピー性皮膚炎、慢性蕁麻疹、円形脱毛症、抜毛、夜驚症、吃音、心因性発熱、めまいなど)、赤ちゃん返りの傾向を示すなど))を示すなど、大きな心身の負担を伴います。
このことは、DV被害者である元配偶者の暴力被害による後遺症(PTSD、その併発症のうつ病、パニック障害など)の治療と心身の回復に大きな影響を及ぼし、同時に、DV加害者である父親と面会せざるを得ないもうひとり被害者である子どもの治療と心身の回復にも大きな影響を及ぼします。
司法、特に、家庭裁判所の調査官が作成する『調査報告書』では、この問題に言及することがほぼなくなりました。
父親ともうひとりの被害者である子どもとの面会交流は、仮に、FPIC立ち合い、時間が限られているときには、暴力的ではない外面のよい父親を演じ切ります。
面会交流に臨む子どもが、慢性反復的(常態的、日常的)な被虐待体験をしてきたという視点に立つと、父親が暮らす家に行ったり、その家に宿泊したり、旅行に行ったりすることはあり得ないことです。
この日本の状況を危惧した「女性差別撤廃委員会」は、平成26年(2014年)、締結国の日本政府に対し、「面会交流のスケジュールを決定するときには、家庭内暴力や虐待の履歴があれば、それが女性や子どもを危険にさらさないように考慮しなければならない。」と是正勧告をだしています。
にもかかわらず、日本の家庭裁判所では、この「女性差別撤廃委員会」の是提勧告に反し、「FPICなどの第3者の立ち合いなどで、面会交流は可能である」との判断を示し続けました。
この司法判断は、『子どもの権利条約』の19条では、「子どもが両親のもとにいる間、性的虐待を含むあらゆる形態の身体的、または、精神的暴力、傷害、虐待、または、虐待から保護されるべきである」と定め、「それが起こるとき、親権や監護権、面会交流の決定において、親密なパートナーからの暴力や子どもに対する暴力に対処しないことは、女性とその子どもに対する暴力の一形態であり、拷問に相当し得る生命と安全に対する人権侵害である」、「子どもの最善の利益という法的基準にも違反する」との規定を無視するものでした。
③ 全米法曹協会は「片親疎外症候群」はエセ科学、信用性否定
DV加害者が、「片親疎外」と表現するようになったのは、『配偶者暴力防止法』に準じ「一時保護」の決定を受け、子どもとともに「母子生活支援施設」に入居し、祉行政の支援を受けて転宅(アパートの賃貸契約をし、転居する)、そのとき、同法の「住民基本台帳事務における支援措置(転居先の住所を閲覧できなくする手続き)」をしたDV被害者が、夫婦関係調整(離婚)調停などで、面会交流に応じられない根拠として、「子どもは父親のことを怖がっている」、「子どもが会いたくないといっている」、「精神的に不安定になるから会わせられない」と述べたことに対し、DV加害者が「片親引き渡し症候群」をひきあいにし、「妻が子どもを洗脳(虐待)している」と反論しはじめたことがきっかけです。
このDV加害者の動き(反論)を支え、勢いづけたのが、「4-(1)-②『民法766条』の改正と面会交流調停の推移」の中で示している細矢郁判事らが『面会交流が争点となる調停事件の実情及び審理の在り方―民法766条の改正を踏まえてー(家庭裁判月報、2012年7月/49-50頁)』)の中で、このガードナーの所説を引用し、「子どもが一方の親と過剰に強く結びつき、もう一方の親を激しく非難・攻撃するなどして接触も拒絶する現象を「片親疎外症候群」として概念化」し、この概念は、「一方の親の操作(洗脳)によって生じる病理的現象」と提示したことです。
「片親引き離し症候群/片親疎外症候群(Parental Alienation Syndrome;PAS)」とは、1980年代初めにリチャード・A・ガードナーによって提唱され、「洗脳虐待」と訳されることもあります。
両親の離婚や別居などの原因により、子どもを監護している方の親(監護親)が、もう一方の親(非監護親)に対する誹謗や中傷、悪口などマイナスなイメージを子どもに吹き込むことでマインドコントロールや洗脳をおこない、子どもを他方の親から引き離すようし向け、結果として、正当な理由もなく片親に会えなくさせている状況を指します。
また、子どもをひきとった親に新しい交際相手ができたときに、子どもに対してその交際相手を「お父さん(お母さん)」と呼ぶようにしつけ、実父・実母の存在を子どもの記憶から消し去ろうとする行為も該当します。
このガードナーの所説を引用し、「子どもが一方の親と過剰に強く結びつき、もう一方の親を激しく非難・攻撃するなどして接触も拒絶する現象を「片親疎外症候群」として概念化」し、この概念は、「一方の親の操作(洗脳)によって生じる病理的現象」として提示したのが、細矢郁判事らです(『面会交流が争点となる調停事件の実情及び審理の在り方―民法766条の改正を踏まえてー(家庭裁判月報、2012年7月/49-50頁)』)。
勢いづいたのは、DVに耐え切れず、子どもを連れて家をでていった(元)妻を持つDV加害者たちです。
配偶者からのDV行為に耐え切れず、子どもを連れて家をでて避難したDV事案で、DV加害者が「自分こそが被害者である!」と訴える(主張する)ときの常套句(キーワード)が、「子どもを連れ去った」、「片親疎外(片親疎外は、子どもの心身の成長に弊害をもたらす虐待行為だ!)」、「離婚後の共同親権制度の導入(主目的は子どもとの面会交流の実現)」です。
この「片親疎外症候群(PAS)」に対し、「全米法曹協会(ABA:American Bar Association)」は、2006年(平成18年)、『Childrens Legal Rights Journal』の中で、「PASの証拠能力が認められるものではなく、根拠のない独断的な主張である。」と批判をし、「アメリカの法廷で、20年間にわたり、PASの証拠能力が認められてきたことは、証拠法の歴史における恥ずべき一幕である。このことは、法的手続をエセ科学(junk science)による汚染から保護しようとする証拠法則を委託された法律家たちが、大失態を犯したことを示す。」と論じています。
この批判は、ガードナーが作成した資料集(同業の専門家による審査を経た23の論文、及び、「『PAS』が科学的に正当性であり法的証拠能力を有する」という彼の主張を裏付けるために引用している50の法的判断を含む)について実証的に分析したうえで、これらの資料が、「PAS」の法的証拠能力、ならびに、その存在自体さえも裏づけていないとの判断に至っています。
そして、「科学・法律・政策のすべての観点から、現在、及び、将来にわたって、『PAS』は証拠として容認できない。」と結論づけています。
加えて、「法的問題としてPASを捉えるときには、この理論が、科学的正当性と信頼性を欠いていることを踏まえ、その証拠能力を認めないことが適切であると考えるのである。また、同協会は、PASの主唱者が、依然として、PASの科学的及び法律的地位について、(PASの呼称を変えて証言することで、意図的に法的規制を回避することも含めて)虚偽の陳述を続けていると指摘する。このような対応に対しては、「根拠のない仮説をアメリカの法廷に持ち込もうとする相次ぐ企てを警戒し、法的な専門家を置くべきである。」と述べています。
また、「全米法曹協会(ABA)」は、歴史的にPAS理論が証拠法上採用されてきた経緯について、「離婚・親権・児童虐待の事案を委ねられた裁判所にとって魅力的であったのかもしれない。」と分析し、その理由として、「PASが、複雑で、時間がかかり、苦渋に満ちた、医学的診断に対する証拠調べを軽減することを主張するものであるからである。PASの起源、及び、法的に採用することにつき固有の着眼点は、人間の複雑な問題に対して、疑いもせずに、短絡的な答えをあてはめる、政策的なリスクを実証している。機能不全に陥った家庭に独特の力学が、型にはまった診断通りとなる可能性は低い。」と述べています。
「全米法曹協会(ABA)」の批判(提言)は、細矢郁判事らが、『「面会交流が争点となる調停事件の実情及び審理の在り方―民法766条の改正を踏まえてー(家庭裁判月報、2012年7月)』で、ガードナーの所説を引用する6年前のことです。
司法判断として、精神医学領域の概念が用いられる代表的な「PTSD」「うつ病」は、『DSM(「アメリカ精神医学会」の「精神障害の分類と診断の手引き(The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)』、『ICD((世界保健機関(WHO)の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)」)』において、その診断基準が確立されていますが、「片親疎外症候群(PAS)」は、『DSM』と『ICD』のいずれにも掲載されていません。
平成18年(2006年)、「少年裁判所及び家庭裁判所の裁判官による全国評議会」が公表した『DV事案における親権と面接の評価:裁判官のガイド(第2版)』では、「全米法曹協会(ABA)」の提言と変わらず、「親権を争う事案において当事者がPASに悩まされているという証言は、法的証拠として認められないと判断されるべきである。」と指摘しています。
その根拠として、「特に、DV事案における調査が困難である」と言及しています。
そこでは、「親権に関わる事案においては、子が時折、父母の一方に対して表す恐怖心や不安、嫌悪や怒りといった感情が、他の一方の引き離し行為によって助長・促進された可能性がある。その一方で、(子が疎遠になったと感じる親との間で生じた、子自身の経験に基づく不安への反応も含めて)調査を要する事項もある。DV事案では、その特殊性から、調査が困難であるため、事実に基づく注意深い調査が必要とされる。事案解決のために単にPASの「レッテル」を貼るのではなく、父母に関する子の意思に注意しつつ、子の抱える不安が事実にもとづくものか、親に関する子の認識形成に関して父母それぞれの役割はいかなるものであったか等を注意深く事実調査することで、その調査結果に証拠能力が認められると指摘する。(355-356頁)」、「高葛藤ケースや交流を求める別居親が過去に不適切な監護(虐待等)を行っていた場合などにおいて、安易にPAS理論を採用し、直接的な交流を認めてしまえば、将来的な親子間の愛着形成といった子の福祉以前に、現実的な子の身体的・情緒的福祉を危険にさらす可能性は否定できない(374頁)」と記述しています。
このように、「片親疎外症候群理論」を生みだしたアメリカにおいて、2006年(平成18年)、「全米法曹協会(ABA)」は、「片親疎外症候群はエセ科学として、その信用性を否定」し、同年、日本の「少年裁判所及び家庭裁判所の裁判官による全国評議会」が「PASに悩まされているという証言は、法的証拠として認められないと判断されるべきである。」と指摘しました。
にもかかわらず、その6年後の平成24年(2012年)、細矢郁判事らが『「面会交流が争点となる調停事件の実情及び審理の在り方―民法766条の改正を踏まえてー(家庭裁判月報、2012年7月)』において、ガードナーの所説を引用し、「子どもが一方の親と過剰に強く結びつき、もう一方の親を激しく非難・攻撃するなどして接触も拒絶する現象を「片親疎外症候群」として概念化」し、この概念は、「一方の親の操作(洗脳)によって生じる病理的現象」として提示したことには、大きな疑問を覚えます。
結果、18年経過したいまでも、日本の司法の現場では、DV事案における「面会交流のあり方」に大きな影響を及ぼしています(令和6年(2024年)4月15日現在)。
その恩恵を受けているのは、いうまでもなく、DV加害者と、「離婚後の共同親権制度」の導入を目論む極右・超保守の政治家、彼らと“共同体”ともいえる強固な関係を築いている「はじめに。」で示したア)イ)ウ)エ)の政治団体で、彼らは、「片親疎外」をひきあいにだし、「子どもの連れ去り」「面会交流が実施されない状況」を問題視し、DV被害者である母親を非難し続けています。
(2) 共同監護のための法整備に対する「子どもの権利委員会」の勧告
平成31年(2019年)2月7日、「子どもの権利委員会」は総括所見(勧告)を公表しました。
その「総括所見」では、多岐にわたる勧告を列挙し、特に、緊急措置をとるべき分野として、ア)差別の禁止、イ)子どもの意見の尊重、ウ)体罰、エ)家庭環境を奪われた子ども、オ)リプロダクティブヘルス(性と生殖に関する健康)、および、精神保健、カ)少年司法に関する課題をあげました。
「リプロダクティブヘルス」とは、性や子どもを産むことに関わるすべてにおいて、身体的にも精神的にも社会的にも本人の意思が尊重され、自分らしく生きられることで、「リプロダクティブ・ライツ」は、自分の身体に関することを自分自身で決められる権利のことです。
加えて、キ)差別の禁止として、包括的な差別禁止法の制定、非婚の両親から生まれた子どもの地位に関する規定をはじめとする子どもを差別しているすべての規定の廃止、および、アイヌ民族など民族的マイノリティ、被差別部落出身者の子ども、在日コリアンなど日本人以外の出自の子ども、移住労働者の子ども、LGBTIである子ども、婚外子、障害のある子どもなどに対する差別防止の措置の強化を求めています。
また、ク)子どもへの暴力、性的な虐待や搾取が高い頻度で発生していることに懸念を示し、子ども自身が虐待被害の訴えや報告が可能な機関の創設を速やかに進めることを政府に求め、虐待事件の捜査と、加害者に対する厳格な刑事責任追及を要請し、ケ)「女子高生サービス(JKビジネス)」など子どもの買春、および、性的搾取の促進、または、これにつながる商業的活動を禁止すること、コ)出生登録、および、国籍に関する課題として、非正規の移住者を含むすべての子どもが適正に登録され、無国籍から保護されるよう関連法規の改正、サ)教育に関する勧告のひとつとして、高校授業料無償化制度を朝鮮学校に適用するための基準の見直しとともに、大学・短大入試へのアクセスについて差別しないよう促しています。
「子どもの権利委員会」による「離婚後の共同監護を認めるための法整備を進めるべき」との勧告は、イ)とエ)に関することです。
具体的な勧告の内容は、ⅰ)仕事と家庭生活との適切なバランスを促進することなどの手段により、家族の支援や強化をはかり、また、とりわけ児童の遺棄や施設措置を防止するため、困窮している家族に対して十分な社会的援助、心理社会的支援や指導を提供すること、ⅱ)児童の最善の利益であるとき、外国籍の親も含めて児童の共同監護を認めるため、離婚後の親子関係について定めた法令を改正し、また、非同居親との人的な関係、及び、直接の接触を維持するための児童の権利が定期的に行使できることを確保すること、ⅲ)家庭争議(例えば、児童の扶養料に関するもの)における裁判所の命令の法執行を強化すること、ⅳ)「子及びその他の親族の扶養料の国際的な回収に関する条約」、「扶養義務の準拠法に関する議定書」、及び、「親等の責任及び子の保護措置に関する管轄権」、「準拠法、承認、執行及び協力に関する条約」の批准を検討することとなっています。
ⅰ)は、主に日本が抱えるライフワークバランス問題の解消、家庭支援への財源確保など、社会的な環境整備をすることを求める内容で、ⅲ)ⅳ)は、養育費不払い問題を解消することを求める勧告です。
ⅱ)が、離婚後の親子関係に関するもので、ここには、「共同監護(shared custody of children)」ということばはでてきますが、「親権(parental authority)」ということばはでてきません。
このことは、重要な意味を持ちます。
共同親権を求める人たちは、この「子どもの権利委員会」の勧告は、「日本に共同親権を求めるもの」と主張していますが、事実は、「共同親権」は勧告されていないということです。
「勧告されたのは、共同監護である」という視点に立つと、『民法766条(父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める)』で、以下のア)-オ)のように十分に対応が可能ということです。
ア)「共同監護(shared custody)を認めない規定?」に対し、「親権(parental authority)」は、離婚後は単独行使でも、「監護(custody)」は、両親が共同で実施することが可能で、『民法766条』には、「監護のとり決めができる」と記載され、共同監護は否定されていません。
イ)「単独監護の場合に非監護親と意義のあるコンタクトを維持できるようにする?」に対し、「面会交流の仕組み」は、既に法制化され、「非監護親が子どもと面会交流することが可能です。
ウ)「父母が離婚した場合にいずれか一方の親が子との関係を断絶され永遠に引き離される?」に対し、離婚後も法的な親子関係は切れない、つまり、離婚後に親子関係が断絶され永遠にひき離されるような仕組みにはなっていません。
エ)「親子関係のすべてが失われてしまい、別居親の同意がなく養子にすることも可能?」に対し、「普通養子縁組」をしたとしても、実親と子どもの親子関係は残り、遺産を相続する権利、面会交流をする権利もあります。
オ)「生物学的な親との連絡を完全に奪うことになる?」に対し、子どもは非監護親との連絡を維持する権利を持ち、面会交流も制度としてあり、子の利益を最善に検討し、原則、実施する決定(判決)がでています。
また、「戸籍」には認知した親の名前が残り、親との連絡を完全に奪うということはありません。
そして、この国連の「子どもの権利委員会」の勧告に至るプロセスには、重大な問題(欠陥)があり、それは、日本政府の政治的な働きがけがあったことです。
それは、「子どもの権利委員会」の審議、つまり、「離婚後の子どもの状況に関する質問」に対し、日本政府代表団の返答は、「国民の間にはさまざまな意見が見られる・・」などと、上記ア)-オ)のような説明(回答)に至っていないことです。
つまり、現状の法制度の『民法766条』で、問題提起された内容については十分に対応可能という上記のような回答を踏まえた審議が一切なく、勧告に至ったことです。
「法律の改正」「(新たな)法律の制定」は、極めて政治的です。
この勧告には、その極右・超保守政権の政治的な意図を読みとることができます。
それは、敢えて(意図的に)、国連の「子どもの権利委員会」から勧告を受けるように持って行き、「条約批准・締結国として、勧告に従う必要がある」として、「共同親権制度の導入を強行してしまおう」という目論見です。
「子どもの権利委員会」から「共同監護を勧告された」と捉える以前に、日本では、両親の協議と合意によって共同監護することも可能であり、そうしている家庭も多数存在します。
(3) 家族法制部会の『家族法制の見直しに関する中間試案』
この国連の「子どもの権利委員会」からの是正勧告を受けて、日本では、離婚後の共同親権に対する議論が大きく加速しました。
令和3年(2021年)以降、法務省の「法制審議会(家族法制部会)」において検討が進められ、令和4年(2022年)11月15日、『家族法制の見直しに関する中間試案』がとりまとめられ、公表されました。
中間試案では、ア)共同親権を原則としたうえで、一定の要件を満たす場合に限り、父母間の協議か家庭裁判所の判断で単独親権を認める案と、イ)単独親権を原則としたうえで、一定の要件を満たす場合に限り、父母間の協議か家庭裁判所の判断で共同親権を認める案があげられ、他に、ウ)ケースバイケースで、共同親権か単独親権かを決定すべきという案もあげられています。
親権は、「子どもの利益のために、親に認められた権利」であり、義務です(民法820条)。
子どもは、社会的に自立することができるように、周囲に見守られながら自立に必要な能力を養い、成長していく必要があり、親権者は、子どもが自立に必要な能力を養うことができるように、子どもに対する監護や教育を行うとともに、子どもが成人に達するまで、後見的な役割も担う「義務」を負います。
そして、親権者は、(裁量の逸脱がない範囲内で、)自らの裁量により、子どもに対し、どのような監護・教育をするかなどを決めることができる「権利」を持ち、「親権」は、こうした「義務」、「権利」の総称といえます。
したがって、共同親権の議論は、子どもに対し、社会的自立のために必要な能力を養う機会を与え、子どもが成人に達するまで後見的な役割を担い、子どもの利益を守っていくために、離婚後も父母が共同して親権者となることが適当か(あるいは、限定的な範囲で共同して親権を認めることが適当か)、それとも、父母の一方のみが親権者となることが適当かを問うものです。
次に、「親権」の内容は、大きく「身上監護」と「財産管理」に分かれます。
「身上監護」としての親権は、「子どもに監護や教育をする権利義務(民法820条)」、「子どもの居所を定める権利(民法821条)」、「子どもを懲戒する権利(民法822条/令和4年(2022年)10月14日に削除、同年12月16日に施行)」、「子どもの就職について許可をする権利(民法823条)」で、「財産管理」としての親権は、「財産を管理する権利(民法824条)」、「契約などの法律行為を代理する権利(同条)」です。
つまり、「親権者」とは、未成年の子どもに対し親権、つまり、子どもの財産を管理し(財産管理権)、子どもを監督、監護、教育する(身上監護権)義務を行う者のことで、「監護者」とは、親権者の役割のうち、実際に子どもを監督、監護する者のこと、つまり、実際に子どもを育て、教育をする権利を有する者のことです。
そして、子どもの親権者をめぐり、夫婦間で合意に至ることが困難なときには、親権者と監護者を別に定めることがあります。
親権の「子どもが社会的に自立するために必要な能力を養う機会を与える側面」は、「身上監護」としての親権に親和的で、「未成熟な子どもが経済的・法律的な不利益を負うことから保護する後見的な側面」は、「財産管理」としての親権に親和的です。
そのため、共同親権の議論においても、「身上監護」としての親権については、監護者を定めて単独で行うことを原則とすべきか、それとも、共同で行うことを原則とすべきか、あるいは、ケースバイケースにより判断すべきかで、意見が対立しています。
中間試案では、監護者は、ア)必ず、一方に定めなければならないものとする案と、イ)監護者を一方に定めることも、監護者を定めずに父母双方で身上監護についての親権も行うことができるものとする案があげられています。
イ)については、さらに、監護者を定めることを原則とすべきか、監護者を定めないことを原則とすべきか、いずれも原則とせずに解釈に委ねるべきかについての議論があり、加えて、父母双方で身上監護についての親権を行う場合において、「主たる監護者」を定めるべきかどうかという議論もあります。
監護者が一方に指定されている場合は、監護者が「身上監護」についての親権を行うことになります。
身上監護以外の親権については、ア)父母間で事前に協議したうえで行うことを原則とするかどうか、イ))協議を原則とした場合は協議がととのわない場合にどうするか(監護者が親権を行えるものとするか、家庭裁判所に親権を行う者の決定を委ねるか)、ウ)監護者が協議なく単独で行えるものとしたうえで、もう1人の親権者への事後の通知のみ義務づけるかなど、さまざまな議論があります。
監護者が、子どもの最善の利益に反するような行動にでたときには、もうひとりの親権者からそれを差し止める制度を導入するかどうかについても、議論があります。
親権については、父母が共同で行うことを原則とした場合において、父母間で親権の行使に関する重要な事項について協議が整わないときは、家庭裁判所が親権を行う者を決定する案が示されています。
父母の協議により監護者を定めることができないときに家庭裁判所が決定することも認める規律とする場合、「家庭裁判所が、どのような要素を考慮するのか」が問題になります。
中間試案では、考慮要素の例として、ア)子どもが生まれてから現在までの生活・監護の状況、イ)子どもの発達状況・心情、子の意思、ウ) 監護者となろうとする者の適性、エ)監護者となろうとする者以外の親と子との関係をあげ、他に、「子どもの連れ去り事例として、連れ去り後の事情について考慮することを認めるかどうか」、「監護者とならない親と子どもの交流が子にとって最善の利益になる場合に、その交流に対して監護者となろうとする者が積極的か消極的かを考慮要素に入れてよいかどうか」などの議論があります。
子どもの居所については、監護者が定めることができるという案と、父母の双方が関与するものとする案が示されています。
(4) 離婚後の子の養育をめぐる制度の見直しに向けた民法改正要綱案
令和5年(2023年)8月29日、法制審議会の家族法制部会は、「離婚後の子の養育をめぐる制度の見直しに向けた民法改正要綱案のたたき台」を示しました。
その「たたき台」では、離婚後も父母双方が親権者となる「共同親権」の導入を認める一方で、DVや虐待があったときには、例外としています。
「民法改正要綱案のたたき台」の主な内容は、以下のア)-オ)となっています。
ア) 単独親権か共同親権かを選択できる
現行制度は、離婚後は父母どちらかにしか親権を認めない「単独親権」となっていますが、父母双方に親権を認める「共同親権」の選択も可能としました。
ただし、DVや虐待などを想定し、親権について父母の協議が整わないときには、親子や父母の関係を考慮して家庭裁判所が親権者を決めたり、一定の条件を満たせば、親権者を決めたりしなくても、「協議離婚できる」としています。
イ) 親権者は変更できる
親権者の決定後も、DVや虐待などにより子どもの安心安全が脅かされるときには、家庭裁判所の判断で親権者を変更できるとしています。
ウ) 子どもの身の回りの世話をする「監護者」の判断を優先する
共同親権では、子どもの進路や大きな病気や怪我をしたときの治療方針などの重要事項については、父母双方の合意で決定することになります。
ただし、親権を持つ父母のうち一方を、子どもの身の回りの世話をする「監護者」に定めることで、監護者は、日常的な教育や居所指定を単独で決定できるとしています。
エ) 養育費の協議をせずに離婚しても、「法定養育費」を請求できる
養育費の不払い対策として、養育費の協議なしに離婚したときにも、養育する親がもう一方の親に、最低限の経済的支援の請求を可能とする「法定養育費」を創設します。
養育費の支払いが滞ったときには、財産の差し押さえ手続きをしやすくするため「先取特権」を定めています。
オ) 家庭裁判所が面会交流の試行を促す
子どもと別居する親と子どもとの面会交流については、家庭裁判所が試行を促せる規定を新設したうえで、子どもの安心安全に留意し、第三者の立ち会いといった条件を付けています。
「たたき台」として示されたア)-オ)は、『民法766条』などの現行法で十分に対応可能で、「離婚後の子の養育をめぐる制度の見直しに向けた民法改正」は必要ありません。
現行法で十分に対応可能であるにもかかわらず、日本政府は、共同親権制度の導入ありき、つまり、なんとしても共同親権制度を導入しようと考えているようです。
この政府の姿勢は、平成29年(2017年)の110年ぶりの刑法改正(性犯罪の厳罰化)に先立つ『法制審議会』において、「改正案の「強制性交等罪(177条)」「準強制性交等罪(178条2項)」の規定を柔軟に解釈すれば、相手の意に反する性交を処罰することは可能なのだから改正の必要ない。」との結論に至り、見送られた経緯とは、真逆です。
なんとか『不同意性交等罪』の採用を先延ばしにしようとした極右・超保守の日本政府は、「離婚後の共同親権制度」は、なんとしても導入したいようです。
この『レポート』で述べているように、法律の制定や法改正は極めて政治的なものです。
つまり、政治の中枢にいる権力者が講じたい政策の実現のためには、数さえ揃えれば、自由に法律を制定したり、法改正をしたりすることができます。
だからこそ、政治には、市民の監視(権力者の自由にさせない)が必要です。
5.第2の「法案」 家庭教育支援法
第2の「法案」は、『家庭教育支援法』です。
『家庭教育支援法案』は、平成24年(2012年)4月、安倍晋三元首相が会長となり発足させた「親学推進議員連盟」が立法化を目指した肝いりの政策です。
日本最大の超国家主義・極右主義団体「日本会議」などの保守系団体に加え、「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」を支持母体とする「国際勝共連合(共産主義に勝利するための国際連盟)」などの後押しを受け、第3次安倍晋三政権は、平成29年(2017年)の国会提出を目論みましたが、野党の反対により見送られました。
問題は、この『家庭教育支援法』は、満州事変・太平洋戦争中の『戦時家庭教育指導要項』に通じるということです。
満州事変・太平洋戦争中の『戦時家庭教育指導要項』は、「あるべき家庭教育を国が定め、国家が家庭での教育を統制する」というものです。
この『戦時家庭教育指導要項』に通じる『家庭教育支援法(案)』には、女性の社会進出の視点はなく、第1の「法案」で述べた「伝統的家族像(「男性は、忠義を心に、主君と国のために身を捨てる」、「女性は家で、夫、家、家族のために自らを犠牲にする(内助の功、良妻賢母)」と考え、家族(男性と女性、子ども)はひとつ、家父長に従い一致団結する)」が“前提”となっています。
これは、女性と子どもは「家」に所属し、意思決定は「家父長」にあるという「家制度(家父長制)」そのものです。
安倍晋三元首相の肝いりながら、第3次安倍晋三政権が、平成29年(2017年)の国会提出を見送った『家庭教育支援法(案)』は、その後、47都道府県に本部を置く、「親学」を主導する日本最大の超国家主義・極右主義団体「日本会議」などが連動し、地方議会から中央に意見書をださせ、法整備を働きかけています。
根強い批判を受ける中で、地方では、その目論見通りに、同じ趣旨の『家庭教育支援条例』を制定する動きが進んでいます。
統一教会(現.世界平和統一家庭連合)を母体とする「国際勝共連合」の月刊誌『世界思想(平成30年(2018年)2月号)』の特集「「今こそ家族を守れ」「『家庭教育支援条例・基本法』で絆を取り戻せ」」が組まれたのは、神奈川県内の議会で、法制定を求める陳情が相次いでだされていた時期と重なります。
その記事では、家庭について、「人間の心に腹の底からの幸せ感を体験させることができるようにする『愛の学校』なのだ。」などと説明し、家庭教育支援の重要性を強調し、一方で、「国家による家庭への介入だとの法案への批判は的外れ!」と断じ、「法制定を急ぐべきだ」と主張しています。
令和4年(2022年)6月までに、『家庭教育支援条例』を制定したのは、熊本県(平成24年(2012年)、議員提案)、鹿児島県(平成25年(2013年)、議員提案)、静岡県(平成26年(2014年)、議員提案)、岐阜県(平成26年(2014年)、議員提案)、徳島県(平成28年(2016年)、議員提案)、宮崎県(平成28年(2016年)、議員提案)、群馬県(平成28年(2016年)、議員提案)、茨城県(平成28年(2016年)、議員提案)、福井県(令和2年(2020年)、議員提案)、岡山県(令和4年(2022年)、議員提案)、石川県加賀市(平成27年(2015年)、市長提案)、長野県千曲市(平成27年(2015年)、議員提案)、和歌山県和歌山市(平成28年(2016年)、市長提案)、鹿児島県南九州市(平成28年(2016年)、市長提案)、愛知県豊橋市(平成29年(2017年)、議員提案)、埼玉県志木市(平成30年(2018年)、市長提案)の「全国10県6市」です。
また、令和4年(2022年)6年15日(同5年(2023年)4月1日施行)に成立した『こども基本法』、令和5年(2023年)年4月1日に発足した『子ども家庭庁』は、『家庭教育支援法(案)』を実現(成立)させるために動いたものです。
ア)『子ども家庭庁』の設立は、安倍晋三元首相や極右議員らが傾倒した「親学」を提唱した高橋史郎氏が中心メンバーの日本最大の超国家主義・極右主義団体「日本会議」が主導し、イ)『こども基本法』は、自由民主党の支持母体の右翼団体であり、カルト教団「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」と深い関係にある「日本財団」の肝入りで成立させたものです。
安倍晋三元首相の肝いりの『家庭教育支援法案』は、家父長主義的な思想で、男女共同参画や性の多様性を否定している「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」に共鳴した内容となっています。
つまり、『家庭教育支援法案』は、「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」の“教義”そのものです。
「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」の“教義”は、極右・超保守の政権、政党、政治家が支持する「伝統的な家族観」に沿い、離婚を実質的に否定しているという意味で、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」に合致します。
そして、『家庭教育支援法』の成立目的で成立・施行された『こども基本法』の1条を要約すると、「日本国憲法および児童の権利に関する条約に則り、すべての子どもが自立した個人としてひとしく健やかに成長できるよう、子どもの権利を守る」と目的が示されています。
「日本国憲法および児童の権利に関する条約に則り、‥」と記述されていますが、『子どもの権利条約』とほど遠い内容になっています。
『子どもの権利条約』で定めている「子どもの権利」には、ア)差別の禁止(差別のないこと)、イ)子どもの最善の利益(子どもにとってもっともよいこと)、ウ)生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)、エ)子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)という4つの原則があります。
一方、『こども基本法』における「こども施策」は、「日本国憲法の精神に則り、『教育基本法』を頂点とする教育法体系の下で行われるもので、こども基本法の目的・基本理念は、『教育基本法第1条』に定める「心身ともに健康な国民の育成」という「教育の目的」と通ずるもの」としています。
この「『こども基本法』における「こども施策」は、『教育基本法』を頂点とする教育法体系の下で行われる」ことは、『子どもの権利条約』で定めている「子どもの権利」のイ)子どもの最善の利益、エ)子どもの意見の尊重が損なわれる可能性があります。
同様の問題は、本国会で成立を目指している第1の「法案」、つまり、「離婚後の共同親権制度の導入」のための『家族法(民法)』の「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」にも認められ、この「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」には、『子どもの権利条約』で定めている「子どもの権利」のエ)の「子どもの意見を尊重する」との文言がなく、イ)の「子どもの最善の利益」が保証されていないことが問題視されています。
岸田文雄首相は、令和3年(2021年)10月31日に実施された衆議院選挙の公約として「『家庭教育支援法』の制定に向けたとり組みを推進します。」と明記しました。
『家庭教育支援法案』と『家庭教育支援条例』は、支援という名の下で、特定の家族像に合うように「親の教化」を目論むもので、「子どもを権利の主体ではなく、客体」と捉えています。
「主体」とは、私だったり、自分だったり、なにか物事をなしている中心のことで、一方の「客体」とは、「主体の対象となるもの」を指します。
例えば、「私は、美しい桜の樹を見ている」とき、「私」が主体で、「桜の樹」は客体となります。
つまり、「子どもが権利の主体ではなく、客体」という意味は、「権利の主体は親であり、客体は家庭教育を受ける子ども」ということになります。
この構図は、第1の「法案」で示しているように、本国会に提出された「「離婚後の共同親権制度の導入」のための『家族法(民法)』」の「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」に認められるものであり、また、『家庭教育支援法』の成立のために成立・創設させた『こども基本法』『子ども家庭庁』も同じ構図、つまり、「主体は親であり、客体は子ども」という構図になっています。
『家庭教育支援法案』では、家庭教育を「父母その他の保護者の第一義的責任」とし、「子に生活のために必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努める」としています。
このことは、満州事変から太平洋戦争下の『戦時家庭教育指導要項』と同様に「あるべき家庭教育を国が定め、国家が家庭での教育を統制する」というものです。
さらに、「法案」では、国と自治体が家庭教育支援のための「施策」を策定することを義務づけ、学校や保育所、地域住民等はこの「施策」に協力する努力義務を課しています。
この「施策」で活用させようとしているのが、日本最大の超国家主義・極右主義団体「日本会議」が主導し、安倍晋三元首相や極右議員らが傾倒した「親学」です。
「親学」は、第1の「法案」の中で述べているように、「子どもが幼い間は、母親が家にいるべき」という家父長制的家族観・ジェンダー観にもとづき、「いじめ、不登校、子どもの自殺の責任は親の教育にある」、「親が変われば子も変わる」などと考え、特に、母親の責任を強調するものです。
「親学」の提唱者で、日本最大の超国家主義・極右主義団体「日本会議」で活動する高橋史朗氏は、『こども庁』創設のために設けられた有識者会議において必要性が強調された「包括的性教育」に対して問題視し、「過激な性教育に他ならない。」と指弾しました。
ユネスコが提唱している「包括的性教育」とは、日本が遅れている人間関係、価値観、人権、文化、セクシュアリティ、ジェンダーの理解、暴力と安全などをキーコンセプトに、「子どもたちの健康とウェルビーイング(幸福や喜び)や、子どもたちの尊厳を実現する」、「個々が尊重された社会的、性的な関係を育てる」ために必要な知識やスキル、態度、価値観を身につけさせることを目的としています。
この『家庭教育支援法案』に定める「国と自治体が家庭教育支援のための「施策」を策定することを義務づけ、学校や保育所、地域住民等はこの「施策」に協力する努力義務を課している」ことが、令和6年(2020年)に本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」の質疑の中で述べられた「子どもの養育計画」と深く結びついています。
つまり、満州事変・太平洋戦争時の『戦時家庭教育指導要項』に通じる『家庭教育支援法案』において、努力義務としながらも『家庭教育支援法案』で、学校や保育所、地域住民等はこの「施策」に協力させることを踏まえると、「共同親権法案」で、離婚する父母に「子どもの養育計画」を作成させたいという思いの背景にあるのは、「あるべき家庭教育を国が定め、国家が家庭での教育を統制する」という考えです。
・「日本財団」「日本会議」が主導。『こども基本法』、『子ども家庭庁』の設立の経緯
『こども基本法』の制定、『子ども家庭庁』の設立には、いわくがあります。
令和元年(2019年)、ナショナリストで「憲法改正」「再軍備」を目指した岸信介元首相、戦後最大のフィクサーと呼ばれた児玉誉士夫らとともに「統一教会(現. 世界平和統一家庭連合)」を支持母体とする「国際勝共連合(共産主義に勝利するための国際連盟)」を創設した笹川良一が創始者である「日本財団」は、「日本には、『児童福祉法』や『母子保健法』、『児童虐待防止法』など、子どもに関する個別の法律はあるが、子どもに主体を置き、権利そのものを保障する法律がない」として、「子どもの権利を保障する法律(こども基本法)および制度に関する研究会」をスタートさせました。
そして、令和2年(2020年)9月に「提言書」を発表するなど、『こども基本法』の制定の必要性を訴える強力なロビー活動を展開し、令和4年(2022年)6年15日に『こども基本法』は成立、令和5年(2023年)4月1日に施行されました。
「ロビー活動(ロビイング(lobbying))」ともいい、もともとアメリカの議会用語で、圧力団体の利益のために、議会で立法の促進や阻止にあたったり、その立法の促進や阻止に役立つ影響力を行使したりする院外活動のことです。
もともと議員が院外者と面会する控室のことを「ロビー」といい、運動員(ロビイスト)が、主に、ここを活動の舞台として活動したことからこの議員用語が生まれました。
この『こども基本法』は、自由民主党の支持母体である右翼団体であり、「統一教会」と深い関係にある「日本財団」の肝入りの法律で、しかも、「親学」に傾倒、極右団体の「日本会議」が主導した「子ども家庭庁の設立」とのセットで制定されました。
『こども基本法』の1条を要約すると、「日本国憲法および児童の権利に関する条約に則り、すべての子どもが自立した個人としてひとしく健やかに成長できるよう、子どもの権利を守る」と目的が示されています。
しかし、その内容は、『子どもの権利条約』とほど遠いものです。
『子どもの権利条約』で定めている「子どもの権利」には、ア)差別の禁止(差別のないこと)、イ)子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)、ウ)生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)、エ)子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)という「4つの原則」があります。
『こども基本法』における「こども施策」は、「日本国憲法の精神に則り、『教育基本法』を頂点とする教育法体系の下で行われるもので、こども基本法の目的・基本理念は、『教育基本法第1条』に定める「心身ともに健康な国民の育成」という「教育の目的」と通ずるもの」と規定しています。
つまり、『こども基本法』は、“教育法”です。
この“教育法”との位置づけは、満州事変・太平洋戦争時の『戦時家庭教育指導要項』に通じる『家庭教育支援法案』につなげるものです。
令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」の質疑の中にでてきた「子どもの養育計画」は、満州事変・太平洋戦争時の『戦時家庭教育指導要項』の「あるべき家庭教育を国が定め、国家が家庭での教育を統制する」という考えにもとづく、つまり、『家庭教育支援法案』の意図(目論見)につながります。
そして、令和3年(2021年)9月15日、自民党会合で、少子化対策や子育て支援といった子ども政策の司令塔として2023年度の設立が予定されていた「こども庁」の名称が、「こども家庭庁」へと変更する提案が提出され、翌週の同月21日、名称を含めた同庁の基本方針が閣議決定されました。
僅か6日間のどんでん返しでした。
この僅か6日間のどんでん返しとなった「名称変更」には、自由民主党の支援母体である「親学」を主導する「日本会議」の「イデオロギー(社会のあり方などに対する考え方、人の行動を左右する考え方や信条)」が深く関係しています。
当初の名称は「子ども家庭庁」でした。
しかし、令和3年(2021年)3月、自民党議連が実施した「子ども行政に関する勉強会」で、虐待サバイバーであり、No More Abuse Tokyo代表の風間暁氏が「虐待を受けている子どもにとって、家庭とは、毎日生きることに必死な戦場を指すことばである」と指摘し、「「家庭」ということばを抜いて『こども庁』にして欲しい。」と訴えたことで、「家庭は温かい場所でなければいけないという固定観念とのギャップに苦しむ人がいることを考慮」した結果として「こども庁」に改称されました。
過去にLGBTQ+に対し差別的な発言をした山谷えり子元拉致問題担当相(当時)は、「家庭的なつながりのなかで子どもは育っていく。」、加藤勝信前官房長官(当時)は「子どもは家庭を基盤に成長する。家庭の子育てを支えることは子どもの健やかな成長を保障するのに不可欠。」と述べるなど、自由民主党の極右・超保守派に加え、公明党、日本維新の会、立憲民主党、国民民主党の議員も「家庭」を含めた名称変更を支持しました。
この名称変更を進めた保守派の政治家たちに影響を及ぼしたのが、極右教育理論の提唱者で、「親学」を提唱する高橋史郎氏です。
「親学」は、戦前の家父長制的家族観をベースに、子育ての責任を家庭、特に、母親だけに過大に押しつける考え方で、例えば、「児童の2次障害は、幼児期の愛着の形成に起因する。」、「子どもを産んだら、母親は、常に子どもの傍にいて育てないと発達障害になる。だから、仕事をせずに家にいなさい」と主張します。
この「親学」の提唱者である高橋史朗氏は、「生長の家」系組織で活動をおこない、現在は、自由民主党の支援母体である政治団体「日本会議」の中心メンバーをつとめる極右活動家です。
「生長の家」は、昭和5年(1930年)、「人間は神の子である」という悟りを得て、その喜びを伝えるために、月刊誌『生長の家』を発刊したのがはじまりで、「神・自然・人間は、本来一体である」との教えにもとづき、“新しい文明”の基礎づくりを進める活動をしています。
「日本会議」は、平成9年(1997年)、「日本を守る会」と「日本を守る国民会議」を統合し、設立された日本最大の保守主義・ナショナリスト団体で、会員数3万8000人、47都道府県に本部、241の市町村支部があり、関連団体は議員連盟「日本会議国会議員懇談会」、「日本会議地方議員連盟」、女性団体「日本女性の会」があります(平成27年(2016年)現在)。
「日本会議」は、「美しい日本の再建と誇りある国づくり」を掲げ、政策提言と国民運動をしていますが、この「美しい日本の再建と誇りある国づくり」という「日本会議」の政策提言は、平成18年(2006年)9月29日、第1次安倍政権の「所信表明演説」で、安倍晋三元首相が述べた「美しい国の繁栄には安定した経済成長が必要」、「美しい国の実現には子どもや若者の育成が必要」に反映されました。
この「親学」の提唱者である高橋史朗氏に共鳴する安倍晋三元首相をはじめとする自由民主党の極右・超保守議員に加え、公明党、日本維新の会、立憲民主党、国民民主党の保守議員(一部、極右・超保守議員)は、日本最大の保守主義・ナショナリスト団体「日本会議」の強力な後ろ盾をもとに設置したのが「子ども家庭庁」です。
このことが示しているのは、安倍晋三元首相が自由民主党の幹事長に就任し、党内の実権を握り、安倍晋三政権を発足させてからの日本の政治は、超がつくほど極右化していったことです。
この「日本財団」が主導して制定させた『こども基本法』、「日本会議」が主導して設立させた『子ども家庭庁』は、「親学」がベースとなる『家庭教育支援法案』が一気に進む危険性を孕んでいます。
『家庭教育支援法案』は、平成24年(2012年)4月、安倍晋三元首相が会長となり発足させた「親学推進議員連盟」が立法化を目指した肝いりの政策です。
第3次安倍晋三政権は、「日本会議」などの保守系団体に加え、「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」を支持母体とする「国際勝共連合(共産主義に勝利するための国際連盟)」などの後押しを受け、平成29年(2017年)の国会提出を目論みましたが、野党の反対により見送られました。
『家庭教育支援法案』は、平成18年(2006年)12月15日(同月22日施行)、第1次安倍政権が、昭和22年(1947年)に制定された『教育基本法』を改正し、その『改正教育基本法』で示した家庭の教育力の低下を“根拠”に、家庭教育を支援する施策の推進を目指し、国や学校、地域住民の責務や役割も盛り込み、「保護者が子の教育に第一義的責任を有する」とし、国や地方自治体に家庭教育の支援施策に努めるよう定めています。
この『家庭教育支援法案』には、女性の社会進出の視点が欠け、伝統的家族像が前提となっています。
これは、家長主義的な思想で、男女共同参画や性の多様性を否定している「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」に共鳴した内容といえます。
「共鳴」とは、他人の考えや感情をよいものと感じて、同じ考えを持つようになることです。
つまり、安倍晋三元首相の肝いりの『家庭教育支援法案』は、「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」の教義そのものです。
6.第3の「法案」 『日本国憲法』に創設「緊急事態条項」
第3の「法案」は、『日本国憲法』を改正し、『日本国憲法』に新たに創設する「緊急事態条項」です(緊急事態条項に関する憲法改正)。
「条文案」では、「①武力攻撃、②内乱・テロ、③自然災害、④感染症のまん延、⑤その他、これらに匹敵する事態の発生を前提に、国民生活及び国民経済に甚大な影響が生じている場合又は生ずることが明らかな場合において、当該事態に対処するために国会の機能を維持する特別の必要がある場合には、原則内閣による発議と国会による事前承認を条件に、閉会禁止・解散禁止・憲法改正禁止の効果が発生する」と定めています。
つまり、この「緊急事態条項」は、「国民」を守るためではなく、ア)「国家」「体制」を守るためであり、イ)政権に都合のいい解釈(自由裁量)で「憲法の規定をストップ(無力化)」し、「国民を犠牲にする」ことを厭(いと)わないものです。
大災害が起きたときの対応については、既に、『日本国憲法』に定めています。
ひとつは『日本国憲法54条2項』で、衆議院の解散時に災害が発生したときには、参議院の緊急集会を開き法律や予算を審議・決議できます。
もうひとつは『同法73条8号』で、参議院を開くことも難しいとき、内閣が法律の範囲内で罰則付きの政令をだせます。
また、『災害対策基本法(緊急政令)』では、緊急時、内閣に対して、生活必需品の配給や物の価格の統制など、4つの事項に限定して立法権を認めています。
「人権」を制限する規定については、都道府県知事の強制権として、救助のための従事命令、施設管理や物資の保管・収用命令など罰則付きで命令できます。
市町村長の強制権としては、設備物件の除去命令、他人の土地・建物・その他の工作物の一時的な使用・収用、現場の工作物または物件を除去させるなど多々あります。
つまり、現行の範囲内で十分対応可能で、「緊急事態条項に関する憲法改正」は必要ないものです。
現行の『日本国憲法』などで十分対応が可能で、改正など必要がないにもかかわらず、ナショナリストで復古主義的情緒主義、極右・超保守の政権、政党、政治家、彼らと“共同体”ともいえる強固な関係を構築している「はじめに。」で示したア)イ)ウ)エ)などの政治団体、つまり、ア)安倍晋三元首相の母方の祖父で、ナショナリスト、『日米安保条約(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約)改訂案』を強行採決し、「安保闘争」を招いた岸信介元首相以降の自由民主党を支え続けている笹川良一(子ども番組の時間帯を狙いテレビ広告を流し続けた「お父さん、お母さんを大切にしよう。一日一善!」の人)が創設した「日本財団(日本船舶振興会)」、イ)日本海を挟み、ソビエト連邦(社会主義)、中華人民共和国(共産主義)、東シナ海の台湾、資本主義と社会主義で分断された朝鮮半島と南シナ海に面するインドネシア半島(ベトナム)といった地政学上、左翼や新左翼の運動家が参加した反政府・反米運動(安保闘争など)に警戒心を強めたCIA(アメリカ中央情報局)主導の下で、岸信介(元首相)、戦後最大のフィクサーと呼ばれた児玉誉士夫、「日本財団」の創始者である笹川良一らが創設したカルト教団「統一教会(現.世界平和統一家庭連合)」を母体とする「国際勝共連合(共産主義に勝利するための国際連盟)」、ウ)「安保闘争」の活動を経て創設され、「生長の家」関連団体の在籍時に「親学」を提唱した高橋史郎氏が中心メンバーの日本最大の超国家主義・極右主義団体「日本会議」、エ)役員の多くが「日本会議」の役員・幹部を兼務する「神道政治連盟」などの政治団体は、なぜ、「緊急事態条項に関する憲法改正」をしようとするのでしょうか?
その理由は、以下の自民党改憲案の「緊急事態条項」の条文に明確に示されています。
自民党改憲案の「緊急事態条項」の第98条(緊急事態の宣言)第1項には「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。」、「法律の定めは、法律の定めるところにより、事前、または、事後に国会の承認を得なければならない。」と記述しています。
「内乱等による社会秩序の混乱」に対し「緊急事態宣言」をだせることは、極右・超保守の政権に反する考えの人たちが、反対の声をあげ「デモ活動」を実施したときには、社会秩序を混乱させる内乱にあたると容易に関係者を罰することができるようになります。
しかも、「緊急事態宣言」は、「事後承認でもよい」ことから、政権がだしたいと思えばだすことができ、しかも、「承認の期限がない」ことから、その宣言に正当性がないときには放置(知らんぷり)も可能となります。
第99条(緊急事態の宣言の効果)第1項では、「緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。」と記述しています。
これは、「国会を無視し、内閣だけで人権を奪う法律をつくることができる」もので、政令を制定できる対象事項の範囲が決められていません。
第3項では、「何人も、~国その他公の機関の指示に従わなければならない。」と記述しています。
これは、「国民は、罰則付きで、内閣の政令に従わなければならなくなる」ことを意味します。
このことが意味するのは、この「緊急事態条項」は、戦前のナチスドイツの『全権委任法』、戦前の大日本帝国の『国家総動員法』に匹敵するということです。
1933年(昭和8年)、ドイツで制定された『全権委任法』のもとで、アドルフ・ヒトラーと国民社会主義ドイツ労働者党の政府は、憲法改廃権を含む権力を手中にしました。
日本では、昭和13年(1938年)4月1日、第1次近衛文麿内閣の下で公布され、同年5月5日に施行した『国家総動員法』では、“国家総動員”を、「事変を含む戦時に際し、国の全力を最も有効に発揮せしむる様人的及物的資源を統制運用する」ことと定義し、「国家総動員上必要と認められる事柄について、政府が広範な統制を行える」と定めています。
『日本国憲法』に「緊急事態条項」を創設する(「緊急事態条項に関する憲法改正」が実現する)と、日本政府は、ア)気に入らない政党を禁止にすること、イ)都合が悪い言論・出版物を禁止にすること、ウ)政府に対して批判的な番組・新聞社を潰すこと、エ)労働組合を解散させること、オ)政府を批判する者を裁判にかけずに刑務所に入れること、カ)労働者を戦争に強制的に動員させること、キ)戦争のために国民から財産を奪うことや外出禁止にすることができます。
そして、ケ)このア)イ)ウ)エ)オ)カ)キ)に意を唱える声をあげると、いつでも、いくらでも、「緊急事態宣言」をだせます。
大規模なデモやストライキを口実に「緊急事態宣言」をだすことも可能です。
例えば、本国会で成立を目指す「「離婚後の共同親権制度の導入」のための『家族法(民法)』の改正」に対し、反対の声をあげ、大規模なデモを呼びかけると、「緊急事態宣言」をだし、その反対の声を押さえ込むことが可能です。
しかも、「法案」には、「衆議院解散中」などの時期の限定が示されていないので、いつでも「緊急事態宣言」をだせます。
つまり、「緊急事態条項に関する憲法改正」は、戦前のように、政権、内閣の「独裁」を可能とします。
それは、満州事変・太平洋戦争時と同様に、国民には、政府を批判する正しい情報がまったく入ってこなくなり、政府をチェックすることもできなくなり、どんどん政府が暴走していく可能性を意味します。
その政府の暴走が戦争であっても、それに意を唱えると弾圧され、その声は完全に封じられます。
第2次安倍晋三政権が発足して間もない平成25年(2013年)7月29日、安倍晋三元首相を支える麻生太郎元首相(副総理・財務大臣)は、「憲法改正をめぐるシンポジウム」で、「憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法がいつの間にか変わっていて、ナチス憲法に変わっていたんですよ。」、「誰も気づかないで変わった。あの手口を学んだらどうかね。」、「ワーワー騒がないで。本当に、みんないい憲法と、みんな納得して、あの憲法変わっているからね。」と述べています。
この麻生太郎元首相が語った「ナチスの手口を学べ」こそが、ナチス独裁への道を開き、ホロコーストを招いた「緊急事態条項」です。
その“手口”とは、「誰も気づかないように、しかも、皆にいい憲法と納得させたうえで、憲法を変えてしまう」ことです。
この麻生太郎元首相の発言には、政治(権力者)の基本姿勢である「民は愚かに保て!」が明確に示されています。
そして、アドルフ・ヒトラーによるホロコーストは、ヘイトスピーチ、言論弾圧からはじまりました。
日本では、いまから4年8ヶ月前の令和元年(2019年)の衆議院選挙中の7月15日、JR札幌駅近くで街頭演説をしていた安倍晋三首相(当時)に対し、北海道県警が「安倍辞めろ!」、「増税反対!」とヤジを飛ばした市民を拘束し排除した行為として、既に、立派な言論弾圧行為がおこなわれています(令和6年(2024年)4月15日現在)。
これは、戦時中のような言論弾圧です。
安倍晋三政権、特に第2次安倍晋三政権を樹立後、日本政府の政策、国家運営(報道規制など)の極右・超保守化が一気に加速し、報道規制も進みました。
報道規制は、報道とは関係がない一般市民の声(訴え)、つまり、反対意見、反対声明に対する規制につながるとても危険なものです。
第2次安倍晋三政権以降の顕著な報道規制の状況は、国際NGO「国境なき記者団(Reporters Without Borders;RWB.本部はフランスのパリ)」が発表する『報道の自由度ランキング』に示されています。
『報道の自由度ランキング』は、平成21年(2009年)に民主党政権が誕生すると、平成20年(2010年)に17位から11位にランキングをあげましたが、平成24年(2012年)、自由民主党が政権を奪取し、第2次安倍晋三政権を樹立すると、報道規制がはじまりました。
すると、この状況は一転し、ランキングは一気に下落しました。
平成24年(2012年)-令和2年(2020年)8月28日までを見ると、平成24年(2012)年は22位、同25年(2013年)は53位と就任(12月26日)して僅か4ヶ月で31位下落しました。
安倍晋三首相(当時)は、自分の「言論の自由」を口にする一方で、メディアを恫喝し、国会での虚偽答弁や公文書改ざんが明らかになった「森友・加計学園問題」、招待者リストの破棄まで行われた「桜を見る会疑惑」など、政権を揺るがすスキャンダルが続出する中で、安倍晋三首相(当時)の側近の萩生田光一筆頭副幹事長(当時)、菅義偉官房長官(当時)、高市早苗総務相(当時)などが、報道機関に干渉・監視を強化していきました。
同26年(2014年)は59位、同27年(2015年)は61位、同28年(2016年)は72位となり、就任前の22位から順位を50位落とし、同29年(2017年)は72位、同30年(2018年)は67位、同31年(2019年)は67位、令和2年(2020年)は66位で、主要7ヶ国(G7)の中で最下位です。
その後、菅義偉前首相(令和2年(2020年)9月16日-)の下では、同3年(2021年)は67位、岸田文雄首相(令和3年(2021年)10月4日-)の下では、同4年(2022年)は180ヶ国中71位、同5年(2023年)は180ヶ国中68位で、いずれも主要7ヶ国(G7)の中で最下位です。
日本政府は、報道規制を強化する中で、「ナチスの手口」と同様に、多くの一般市民が気に留めない中で、「緊急事態条項に関する刑法改正」に向けて虎視眈々と、着実に、用意周到な準備を進めてきました。
もうそこまで、恐怖政治は忍び寄ってきています。
ⅰ)「再軍備」を目的とする戦前の『国家総動員法』に匹敵する第3の「法案」の「緊急事態条項の憲法改正」は、ⅱ)その「再軍備」“要”である「子どもの愛国心の醸成」を目的とする満州事変・太平洋戦争時の『戦時家庭教育指導要項』に通じる第2の「法案」の『家庭教育支援法案』、ⅲ)その「子どもの父母がひとつの「家」として再構築させる意図(目論見)のある第2の「法案」の「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」とともに、絶対に成立させてはならない法案です。
・アメリカの保守政党「民主党」と“ネオコン”。日本の極右・超保守と“共鳴”
日本の歴代の首相の中で、アメリカ大統領と良好な関係を築くことができたのは、ア)中曾根康弘とロナルド・ウィルソン・レーガン(グラナダ侵攻、反共主義運動を支援)、イ)小泉純一郎とジョージ・W・ブッシュ(アメリカ同時多発テロ後、ネオコンの後ろ盾にフセイン政権打倒としてのイラク戦争)、ウ)安倍晋三とドナルド・ジョン・トランプ(ポピュリスト・保護主義者・ナショナリスト、厳格な移民政策、疑惑だらけ)の3組、非科学的で情緒主義、思想、思考が似たり寄ったりの3人です。
つまり、極右・超保守政権の日本が、アメリカと良好な関係を築くことができたのは、アメリカも保守政党である「民主党」、中でも非科学的で情緒主義の大統領が政権を担っているときです。
ただし、その良好な関係は、同じ同盟国のアメリカとイギリスの関係のように対等な関係ではなく、上下の関係、支配と従属の関係です。
結果は同じですが、そのプロセスとしては、日本側からご機嫌とりで武器などをいい値で買ったり、規制緩和をしたりする状況と、アメリカ側から強い圧力をかけられて、武器などをいい値で買わされたり、買ったり、規制緩和に応じたりする状況の違いという感じでしょうか。
明確なのは、極右・超保守政権の日本は、リベラル政党の「共和党」とは、論理的な話し合いができないことです。
その日本の極右・超保守の政権、政党、政治家の“復古主義”は、アメリカの保守政党「民主党」の「ネオコン」と共鳴しやすい特徴があります。
1990年代後半から、アメリカの「共和党」の内部で活発に活動していた「ネオコン」と呼ばれる新保守主義者たちは、「9.11事件」以降、積極的にイラクのサダム・フセイン政権打倒を主張するようになりました。
「ネオコン」とは、アメリカ合衆国における「新保守主義(Neoconservatism;ネオコンサバティズム)」の略で、自由主義や民主主義を重視し、アメリカの国益や実益よりも思想と理想を優先し、武力介入も辞さない思想です。
1970年代以降、アメリカの「民主党」のリベラルタカ派から独自の発展をした政治イデオロギーの「ネオコン」は、共和党支持に転向し、「共和党」のタカ派外交政策姿勢に非常に大きな影響を与えることになりました。
ナショナリストで、極右・超保守の安倍晋三政権と「日本財団」「日本会議」などの超国家主義・極右主義団体は、復古主義として、戦前の国家の再建を目指し「再軍備(軍備増強)」を進め、戦争のできる体制整備として戦前の『国家総動員法』に匹敵する「緊急事態条項に関する憲法改正」の成立を目指しています。
この政治姿勢は、この「ネオコン」の思想と「共鳴」します。
アメリカのネオコンは、「イラクが化学兵器や核兵器などの大量破壊兵器の開発を進めて保有している」、「アルカイダとつながっている」とイラクを非難する一方で、イラクは、いずれの疑惑も否定し続けました。
しかし、2003年(同15年)3月20日、アメリカ合衆国のG.W.ブッシュ政権は、イラクが大量破壊兵器を保持しているとして空爆および地上軍によって侵攻しました。
この「イラク戦争」は、アメリカ合衆国が、国連安保理決議にもとづかず、「テロとの戦争」の一環として、イギリス、オーストラリア、工兵部隊を派遣したポーランドの4ヶ国でなる「有志連合軍」とともにイラクへ侵攻したことではじまった軍事介入です。
この軍事介入は、イラク武装解除問題の進展義務違反を理由とする「イラクの自由作戦」の名の下で進められました。
日本の小泉純一郎首相(当時)は、攻撃開始直後の談話で、「我が国の同盟国である米国をはじめとする国々によるこの度のイラクに対する武力行使を支持します。」との立場を示しています。
同年5月には戦闘が終了、その後、フセイン大統領を拘束し、新たなイラン政府を成立させました。
その後もイラン情勢は安定せず、テロ活動がやまずに戦闘は続行し、アメリカ軍・イギリス軍などが駐留を続けるなど、問題は長期化しました。
一方で、開戦理由となった「大量破壊兵器」は見つかりませんでした。
2004年(同16年)10月、イラクの大量破壊兵器の捜索を担当していたアメリカの調査団は、「イラクには大量破壊兵器は存在せず、開発計画もなかった」と結論づけた最終報告書を議会に提出しました。
その後、アメリカ兵によるイラク人への虐待や性暴力といった非人道的な行為も次々に暴かれました。
そして、この「イラク戦争」では市民10万人以上が犠牲となっています。
・日本は、地政学的に「専守防衛」は不可能で、「反撃能力」を持つことはあり得ない暴挙です。
第2次世界大戦後に長く続いた東西冷戦下では、地政学的に、ソビエト連邦(現ロシア)、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)、中華民国(中国)、ベトナム、ラオスなどがあり、ヨーロッパ(東欧と西欧、中欧)の要所のトルコと同様に、アジア太平洋の要所は、フィリピン、台湾、韓国、日本で、その状況は、いまも変わりません。
「地政学」とは「地理学」と「政治学」を合わせた用語で、自分達の住んでいる国の地理的条件をもとに、隣国する国など他国との関係性や世界経済を国際的な視点で捉える視点です。
いまから22年6ヶ月前の2001年(平成13年)9月11日のアメリカ同時多発テロ以降、日本政府は、『テロ対策特別措置法』を制定し、自衛隊をインド洋での補給艦による給油活動を実施し、平成15年(2003年)には、『イラク人道復興支援特別措置法』を制定して自衛隊をイラクに派遣し、イラクでの人道復興支援活動に従事させました(令和6年(2024年)4月15日現在)。
自衛隊の海外での活動が広がる中で、日本政府は、平成27年(2015年)、『安全保障関連法』を成立させ、集団的自衛権の行使の一部を容認するなど、近年、確実に軍事化を進めてきました。
一方で、自衛隊の海外での活動が広がる中で、派遣先からの帰還兵(自衛隊員)、東日本大震災の津波被害後の遭難活動に従事した自衛隊員(他に消防隊員など)の多くが、アメリカ軍や多国籍軍の帰還兵と同様に、PTSDを発症し、その併発症としてのうつ病を起因とする自殺者がでています。
戦争・紛争に自衛隊を派遣する機会が多くなることは、PTSDを発症する帰還兵(自衛隊員)が多くなり、その家族などがDV(デートDV)、児童虐待、市民などがレイプなどの性暴力、殺傷事件に巻き込まれる機会の増加が懸念されます。
日本政府は、再び、軍備増強を目指し、行使・保持する防衛力を必要最小限とする「専守防衛」を否定し、抑止力としての反撃能力(敵基地攻撃能力)保有することを明記した『安全保障関連3文書』を閣議決定しました。
しかし、日本には、54基(福島第1、第2原発を含む)の原子力発電所、131ヶ所米軍基地、約160ヶ所の自衛隊の駐屯地があり、これらが標的(攻撃目標)となると、幾ら追撃システムなどの防衛力を高めたとしても、近距離から複数の弾道ミサイルの攻撃を受ければ防ぎようがなく、攻撃を受けると被害は甚大となります。
日本は、昭和30年(1955年)、『原子力基本法』が成立し、いまから57年前の昭和41年(1966年)、商業用原発として、日本原電の東海発電所が茨城県那珂郡東海村に建設して運転を開始し、第1次オイルショックがおきた昭和48年(1973年)、首相の田中角栄(当時)は、国会で「原子力を重大な決意をもって促進をいたしたい。」と述べ、昭和49年(1974年)、『原子力発電所の立地地域への交付金を定める法律』を整備しました(令和6年(2024年)4月15日現在)。
そして、昭和53年(1978年)の第2次オイルショック以降、「エネルギーの安定供給」が重要な国家課題となる中で、原子力発電所建設が一気に進みました。
このことは、日本が「核」を持つことを意味しました(日本政府が、東日本大震災で福島原発事故を招いたにもかかわらず、原子力発電に執着するのは、「核」を手放したくないからです)。
この間、1962年(昭和37年)10月、ソ連がキューバにミサイル基地建設を進めた「キューバ危機」が起きましたが、このとき、ソ連がキューバに配備しようとしたミサイルは、射程約1800kmの準中距離弾道ミサイル「R-12」、射程約4000kmの中距離弾道ミサイル「R-14」で、ともに、広島に投下された原爆の60倍以上の1メガトンの爆発力を持つ核弾頭を装着できるものです。
キューバに中距離弾道ミサイルが配備されたときには、ハワイ州とアラスカ州を除く米本土のほぼ全域を攻撃することが可能でした。
樺太(その海域を含む)がソ連の領土であり、北朝鮮、中華民国(いずれも海域を含む)との地理的な距離を踏まえると、いまから61年前の時点(太平洋戦争終結後17年)で、日本は、攻撃目標となり得る原子力発電所の建設の有無にかかわらず、「専守防衛」すら成り立たない国家です(令和6年(2024年)4月15日現在)。
多くの原子力発電所が建設され、運用をはじめてからは、日本は専守防衛だろうが、反撃能力を持とうが、いったんことが起これば火だるま、太平洋戦争の戦時下のように焼け野原になり、多くの市民が亡くなります。
例えば、北朝鮮が日本に向けて「弾道ミサイル」を発射すると、2-3分後にイージス艦のレーダーが信号を捉え、Jアラートが流れ、その4分後には目標に着弾します。
つまり、日本は「専守防衛」は不可能な国家、「反撃能力」を持つことはあり得ない国家といえ、地政学的に、東西冷戦時もいまも、日本は東側の盟主のアメリカの要所(軍事標的)でしかありません。
沖縄を含め日本本土は焼け野原で、潜水艦だけで反撃することしかできません。
現在、「軍事偵察衛星」を保有する国は、およそ10ヶ国と推定されています。
この「軍事偵察衛星」は、ロケットに搭載し、打ち上げられます。
「ロケット」と「弾道ミサイル」は、技術的に同じです。
第2次世界大戦で、ドイツが開発した弾道ミサイル「V2」の技術は、終戦後、同じ技術者の手で、アメリカ初の人工衛星開発に生かされました。
「弾道ミサイル」は、一般的に放物線を描いて宇宙空間を飛翔しつつ大気圏に再突入して標的を攻撃する兵器で、一方の「ロケット」は、宇宙空間の地球周回軌道に偵察衛星など人工衛星を乗せるところで役割を終えます。
「弾道ミサイル」は爆弾、「ロケット」は人工衛星などを搭載する違いがあるだけで、エンジン、切り離しを行う段間部、誘導、姿勢制御のための搭載機器などで構成されるつくりは共通し、推進部の大型化や分離、姿勢制御に必要となる技術も共通しています。
つまり、ロケットの打ち上げを弾道ミサイルの技術向上につなげることができます。
ロシアがウクライナに侵攻したように、中国が台湾に侵攻したときには、「抑止力としての反撃能力(敵基地攻撃能力)保有する」ことなど意味がなく、米軍基地、自衛隊の駐屯地などあらゆる土地が攻撃のターゲットとなり、再び、戦火に巻き込まれ、火だるまになります。
そして、海路は閉ざされ、食料、燃料などあらゆる物資がなくなり、国民は飢えます。
また、現代の戦時下では、化学物質による「環境汚染」は深刻になります。
大気汚染、水質汚染などは、発達障害の発症、不妊の原因となっているなど人体や生態系に深刻な影響を及ぼし、温暖化とともに「自然破壊」を促進させます。
気候変動は、自然災害をひきおこすだけではなく、生物の生存環境に影響を及ぼし、それは、食料・水源破壊につながり、結果、貧困・飢饉をもたらします。
そして、貧困・飢餓は、なにより生存が優先されることから、人類の英知として獲得してきた「人権」という概念を無力化させ、無法化させるリスクを高めます。
7. 第4の「法案」 重要経済安保情報保護法
第4の「法案」は、本国会に提出し、成立を目指している『特定秘密保護法(特定秘密の保護に関する法律)』を拡大する『重要経済安保情報保護法(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律)』です。
この『重要経済安保情報保護法(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律)』は、第3の「法案」の「『日本国憲法』を改正し、『日本国憲法』に新たに創設する「緊急事態条項」(緊急事態条項に関する憲法改正)」と深くかかわるものです。
第2次安倍晋三政権は、平成25年(2013年)、『日本国憲法』の「9条(戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認)」を無力化する「集団的自衛権行使」を規定した3大安全保障文書を決定しました。
このことは、「専守防衛」の建前さえ捨て去り、他国のために戦争する「集団的自衛権」を容認することを意味します。
つまり、安倍晋三元首相は、日本を「戦争する国造り」のための法整備を段階的に進めました。
その後、令和4年(2022年)の改正を通じて、日本は「専守防衛」原則から脱し、「敵基地攻撃能力」まで具体化し、2027年までに防衛予算をGDP(国内総生産)の2%水準までひきあげる予定で、アメリカの先端武器を日本で共同生産・輸出することを決めました。
この動きは、母方の祖父で、ナショナリストの岸信介元首相の悲願のひとつ「再軍備(軍備増強)」の実現を進めたものです。
この「集団的自衛権」については、多くの憲法学者・弁護士が「憲法違反」と訴えたにもかかわらず、日本政府は、その声(訴え)を無視しただけではなく、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃に対し、自国が直接攻撃されていなくても実力を以って阻止する権利」と都合よく解釈し、強行しました。
ナショナリストで、極右・超保守の安倍晋三元首相は、第2次安倍晋三政権を樹立すると、平成25年(2013年)12月に『特定秘密保護法(特定秘密の保護に関する法律)』、同27年(2015年)9月に『平和安全法制整備法(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律)』と『国際平和支援法(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律)』、いわゆる『安保法制(戦争法)』を捻じ込み、同29年(2017年)6月には『共謀罪(テロ等準備罪)』を押し通しました。
『重要経済安保情報保護法(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律)』は、平成25年(2013年)12月に成立した『特定秘密保護法(特定秘密の保護に関する法律)』を強化するものであることから、その『特定秘密保護法(特定秘密の保護に関する法律)』の成立に至る経緯と内容を見ていきます。
日本政府は、平成22年(2010年)9月7日に発生した「尖閣諸島沖漁船衝突映像のインターネット流出」を受けて、「従来の法律では、国の安全にかかわる秘密の漏えいを防ぐ管理体制が不十分」として、『秘密保護法(特定秘密の保護に関する法律)』の立案にとりかかったとしていますが、この事件は、「国家秘密の流出」といえるものではありませんでした。
そして、国民が反対の声を強めると、日本政府は、十分な審議時間を確保することなく採決を強行し、平成25年(2013年)12月6日、『特定秘密の保護に関する法律(以下、特定秘密保護法)』を成立させました(同26年(2014年)12月10日施行)。
この「尖閣諸島中国漁船衝突映像のインターネット流出事件」でできたのが、保守系の超党派「国家主権と国益を守るために行動する議員連盟」で、議員連盟がまとめた「要望書」には、国境に近い離島の振興強化、民有地である尖閣諸島の国有化、領海侵犯罪の新設、領海警備を自衛隊に行わせるなどのための新法制定・法律改正も含まれていました。
『特定秘密保護法』は、「防衛」「外交」「スパイ防止」「テロ防止」の4分野で、秘密が漏洩すると「日本の安全保障に著しい支障の怖れがある情報」を特定秘密に指定しています。
この『特定秘密保護法』が、「極めて危険である」されたのは、日本政府が、「特定秘密の取扱者から秘密を漏洩する一般的リスクがあると認められる者をあらかじめ排除する仕組み」と説明する「適性評価制度」が設定されているからです。
「適性評価(セキュリティー・クリアランス)」は、本人の同意を得たうえで、国の行政機関が、ア)家族や同居人の生年月日や国籍、イ)犯罪歴、3)薬物乱用、4)精神疾患、5)飲酒の節度、6)経済状態などを調査するものです。
この『特定秘密保護法』のもとで、令和4年(2022年)末時点で、評価保有者は13万人、大半は国家公務員で、民間人は、主に防衛産業で3%となっています。
この「適性評価(セキュリティー・クリアランス)」の対象になるのは、官僚をはじめとする公務員だけではなく、役所から委託を受けている下請け業者、その関係者まで広がります。
例えば、原子力発電に関する情報が「特定秘密」としてとり扱われるとき、原子力発電所の設計担当者、施工業者とその関係者、原子力発電所で働く作業員に至るすべての人が秘密を漏らす怖れがあるとして、適性評価の対象に含む可能性がでてきます。
「適性評価(セキュリティー・クリアランス)」では、まず、特定有害活動(スパイ活動)やテロリズムとの関連を調査されますが、これは、主義・主張、思想の調査に結びつきます。
日本政府と異なる主義・主張をする人の発言・行動は「テロリズム」であるとして、「合法的」にとり締まることができます。
第3の「法案」の中で、既に、戦時中のような言論弾圧が行われている例として、『いまから4年8ヶ月前の令和元年(2019年)の衆議院選挙中の7月15日、JR札幌駅近くで街頭演説をしていた安倍晋三首相(当時)に対し、北海道県警が「安倍辞めろ!」、「増税反対!」とヤジを飛ばした市民を拘束し排除した行為として、既に、立派な言論弾圧行為がおこなわれています(令和6年(2024年)4月15日現在)。』と述べていますが、これは、『特定秘密保護法』が、この事件の5年前の平成25年(2013年)12月6日に成立、同26年(2014年)12月10日施行に施行していることを踏まえると、この「安倍辞めろ!」、「増税反対!」といった“ヤジ”は、懸念されている「適性評価(セキュリティー・クリアランス)」を拡大解釈すると、「日本政府と異なる主義・主張をする人の発言・行動」として、この“ヤジ”は「テロリズム」であるとして、「合法的」にとり締まることができます。
加えて、性格、素行、異性関係、精神疾患の有無や病歴、酒癖、特異な行動、経済状況まで調べます。
こうしたつながりを調べることは、評価対象者だけではなく、家族、親族、交際関係者などに調査対象が広がることにつながります。
つまり、『特定秘密保護法』のもとでは、個人のプライバシーを侵害(人権侵害)したとしても問題にはなりません。
この「適性評価制度」を拡大し、適用すると、国民をひとり残らず監視できるシステムになり得るという意味で、極めて危険です。
そして、『特定秘密保護法』が成立してから10年3ヶ月経過した令和6年(2024年)3月22日、国が指定した経済安全保障上の機密情報を扱う民間事業者らへの身辺調査導入などを柱とする『重要経済安保情報保護法案(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案)』が、本国会で審議入りしました。
この『重要経済安保情報保護法案』は、『特定秘密保護法』の国家機密のとり扱いを有資格者に限る「適正評価(セキュリティー・クリアランス)」を経済安全保障に関わる情報にも広げるものです。
このことは、「適正評価(セキュリティー・クリアランス)」の対象となる民間人(一般市民)が実質的に拡大することを意味し、これまで(特定秘密保護法)以上に、「国民の知る権利」に加え、「プライバシーが侵害される」という懸念が高まります。
『重要経済安保情報保護法案』では、『特定秘密保護法』で指定された「防衛」「外交」「スパイ防止」「テロ防止」の4分野に加え、新たに「サイバー」「規制制度」「調査・分析・研究開発」「国際協力」の4分野で、漏洩すると安全保障に支障怖れがある情報を「重要経済安保情報」に指定し、対象は、防衛産業以外の幅広い民間事業者や大学を含む研究者などになります。
日本政府は、その情報の機密度をコンフィデンシャル(秘)級とし、より高いトップシークレット(機密)やシークレット(極秘)級を対象とする『特定秘密保護法』と区分しているとしています。
日本政府は、G7(先進7ヶ国)でコンフィデンシャル級を含め情報保全制度がないのは日本だけと説明し、「法案」の必要性を強調していますが、既に、イギリスとフランスでは、「コンフィデンシャル級の秘密指定」は廃止され、アメリカも情報保全監督局が廃止を勧告しています。
これは、「2.第1の「法案」『家族法(民法)』の改正(離婚後の共同親権制度)」の中で示している『「フレンドリーペアレント(FP)」の考え方を導入してきたアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなどは、近年、一方の配偶者に対するDV行為、子どもに対する虐待行為の履歴のあるとき、「共同監護(養育)」ではなく、「子どもとその子どもと同居する親(監護者)の安全確保を最優先」する方向に転換し、「法制度」を見直しているにもかかわらず、「改正案(離婚後の共同親権)」では、「フレンドリーペアレントルール(友好親原則)の導入」を求めている』という状況と同じです。
日本政府は、こうした指摘には耳を貸さず、「法案」の成立に突き進みます。
また、日本政府は、「国会が関与しない機密指定に関し、内閣府の独立公文書管理監がチェックを担当する」と説明していますが、依然として、機密指定基準などは曖昧なままです。
しかも、安倍晋三政権下で、報道規制を進めた高市早苗経済安保担当相は、「具体的な指定要件は、法案成立後に政府内で決める運用基準で示す」との考えを述べています。
具体的な指定要件、運用基準を決めずに「法案」を成立させようとする政治姿勢は、強権政治そのものです。
最後に。
令和5年(2023年)12月10日、『世界人権宣言』の採択から75年を迎えましたが、日本は、包括的な『差別禁止法』や救済制度を持つ「人権機関」をつくり、『人権条約』の「個人通報制度」を受諾し、世界基準の人権教育を実践し、人権侵害当事者を支援する仕組みをつくりあげられなければ、日本の「人権対応」は、ますます世界から遅れ、とり残されていきます。
その大きな要因は、日本には、「左派政党」はありますが、正当な「リベラル政党」が存在せず、極右・超保守な政権、政党、政治家、彼らと“共同体”ともいえる強固な関係を築いている「はじめに。」で示したア)イ)ウ)エ)の政治団体共同体が、日本の政治を担い続け、保守的な価値観を圧倒的多数の人が支持し続けてきたからです。
この「極右・超保守を含めた保守に圧倒的多数の議席を与えている」という“構図”を支えているのは、いうまでもなく「国政選挙」です。
その「国政選挙」で、誰に投票するかは有権者の意思表示です。
つまり、政治的には、極右・超保守を含めた保守に圧倒的多数の議席を与えている(「国政選挙」で当選させている)「有権者」は、極右・超保守を含めた保守が進める(進めたい)政策、国造りを支持していることを意味します。
しかし私には、この国の有権者の多くは、この『レポート』で示す「法案」背景にある極右・超保守の政権、政党、政治家に加え、「はじめに。」で示す彼らと“共同体”ともいえる強固な関係にある政治団体ア)イ)ウ)エ)の思想・イデオロギーを正確に理解したうえで、「国政選挙」で当選させているのだろうか? との思いがあります。
知らずに「国政選挙」で当選させていたのであれば、今後、その行為を正せるチャンスはあり、知っていて「国政選挙」で当選させてきたのであれば、今後、彼らの目指す国に近づいていきます。
例えば、平成29年(2017年)6月2日の110年ぶりの「刑法改正(性犯罪を厳罰化)」、令和5年(2023年)6月16日の「刑法改正(性犯罪規定の見直し)」では、同じ女性という括りとして女性議員は大きなパワーになりましたが、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」では、同じ女性という括りの女性議員は大きなパワーにはなりません。
なぜなら、保守的な「伝統的家族像(観)」を支持する女性の訴え(声)や女性議員の数は、「共同親権法案」の賛成票でしかないからです。
つまり、女性議員の数だけを増やすのではなく、保守的な「伝統的家族像(観)」を支持するのか、しないのかの“踏み絵”が必要になります。
それは、男性議員に対しても同じです。
その“踏み絵”は、どの政党に所属しているのかで直ぐにわかります。
これまで、人権・社会問題とは距離をおき、政治には無関心だったけれども、令和6年(2024年)の本国会に提出された「家族法(民法)の改正案(共同親権法案)」の是非を考えることで、人権・社会問題に対する意識が変わった、高まった人に必要な“視点”は、単なる「女性議員を増やそう」ではなく、「保守的な伝統的家族像を支持しない女性議員を増やそう!(そして、男性議員も増やそう!)」との姿勢です。
つまり、極右・超保守、保守、左派の政党はあっても、正当な「リベラル政党」のない日本には、既存政党に期待するのではなく、無党派層で、人権意識にもとづく「リベラル」な人たちによる市民政党が必要です。
唯一の期待は、令和5年(2023年)9月に実施されたNHKの世論調査では、「特に支持している政党はない」と回答した「無党派層」は42.8%で、「無党派層」は、第2次安倍晋三政権が発足した平成24年(2012年)以降、30%を超えるようになり、令和3年(2021年)7月には35%を超え、現在の岸田文雄政権になり、遂に40%を超えたことです。
「無党派層」42.8%は、支持政党としての「自民党」が34.1%、「立憲民主党」が4.0%、「日本維新の会」が5.8%、「公明党」が2.2%、「国民民主党」が2.9%と保守政党の総計49.0%に対抗し得るものです。
「無党派層」42.8%は流動的で、多くの保守的な価値観の人が含まれているとはいえ、リベラル的な価値観の人が社会問題・人権問題に声をあげ、政治に参加することで、いまの危険な動きの重要なブレーキの役割を担うことができます。
いま、この市民的な動き(市民運動)が生まれることが唯一の期待ですが、戦前の『国家総動員法』に匹敵する「緊急事態条項」を『日本国憲法』を改正し、同法に創設したり、『重要経済安保情報保護法(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律)』が成立したりすると、この市民的な動き(市民運動)の声は、国家権力(警察機関など)により押さえ込まれ、そして、叩き潰されます。
平成6年(2024年)の本国会は、“これから(未来)”の日本の方向性を決めかねない重大な局面をむかえています。
それは、日本の“これから(未来)”に及ぼす致命的な影響の大きさを示します。
20240408
20240422改訂版
無断転載・転用厳禁(他案件での使用・引用を含む)
*Twitter(X)@de90899284でフォローいただいている方(ただし、離婚後の共同親権導入を推進する活動・投稿している人は除く)で、PDF(レポート『主体は親で子どもは客体と位置づける「共同親権制度改正案」-「子の意見の尊重(子の意思表明権)」の不記載は、「子の最善の利益」を脅かす-(A4版155頁)』を希望される方は、これまでと同様に、「アカウント名」「PDF希望」と記述し、下記アドレス宛にお送りいただければと思います。 poco_a_poco_marine_s@yahoo.co.jp
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
