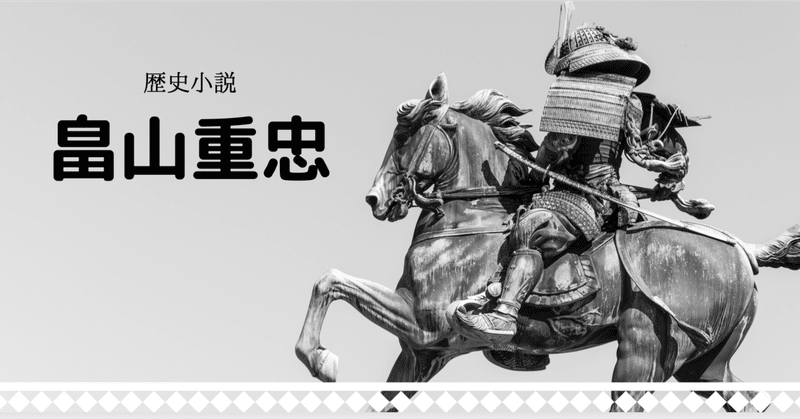
歴史小説 畠山重忠 その6
北条時政の館は名越の山の中にあった。涼しい海風の吹き込む一室で、時政は息子の義時、時房と対していた。
「どうしても畠山重忠殿を討つというのですか。」
「武蔵の国を我が手におさめるには重忠は取りのぞかねがならん。」
義時の問いに時政が答える。
この時期、武蔵の守は平賀朝雅であった。朝雅は時政の後妻、牧の方の娘婿である。重忠は代々武蔵の国の総検校職をつとめる家なのだから、色々な点で朝雅とぶつかることも多かった。在地の領主と名目上の領主との対立である。
「といっても、重忠殿は治承四年以来、ただただ忠勤を励んできました。頼朝公でさえ、死に際して、畠山の家は後々まで守るべし、と言い残したほどの武者です。」
「だからこそ取りのぞかねばなるまい。」
「しかも、先日の比企能員の乱に際しても、頼家将軍と昵懇だったにも関らず我らの味方に参じてくれました。これは、重忠殿の奥方が我らの姉君で、父子の礼を重んじてのことです。重忠殿はあなたの婿なのです。まさかお忘れではありませんな。」
時政は答えに窮した。
「粗忽の誅戮を加えるようなことがあれば、それこそ我らのほうがこの鎌倉に居場所をなくしましょう。」
時政が重忠を討つことに固執するのは、後妻牧の方の意向が強くはたらいていたからだった。
「継母上がそれほど畠山をにくんでいるとは。」
時房の言葉に時政が舌打ちする。
「わしは北条の家の繁栄をのみ考えている。一時の情に流されて言っているのではない。」
「しかし、継母上が、昨年の一件を未だに忘れずにいることは明らか。」
昨年の一件とは次のようなたわいもない事件のことだった。 元久元年【一二〇四年】八月、実朝将軍の妻になるべき坊門姫君を京から迎えるために、鎌倉から容姿端麗な若武者たちが派遣された。その中に重忠の息子、重保がふくまれていたのだが、その重保が、京都守護職にあった平賀朝雅と口論になり、お互いに太刀に手をかけるまでに至ったことがあった。
背景には、国の守として思うとおりにしたい平賀朝雅に取って、代々在地の領主として武蔵の国に力を持つ畠山重忠が目障りだということがあったのだろう。日頃のいらだちが、ちょっとしたことで大きな諍いになった原因なのだろう。
「とにかく、我ら兄弟は畠山重忠殿を討つことには賛成できませぬ。」 義時と時房はそのまま席を立った。
その義時を追って、牧の方の兄、大岡時親が義時の屋敷にやって来た。時親も牧の方の兄と言うことで時政に取り立てられた人物だった。
「ご用件を承りましょう。」
「私は、牧の方の使者として参りました。牧の方がおっしゃるには、夫時政が私に言うには、畠山重忠の謀反は私の讒言によるものと義時殿が申したとのこと。」 義時は何も答えなかった。
「重忠が謀反を企てていると言うことは既に発覚しているのであって、幕府のため、天下のため、私は時政殿にそのことを伝えたのだ、そうおっしゃっています。義時殿。貴殿がそのように畠山討伐に反対されるのは、牧の方に対して何かふくむところがおありだからでしょうか。」
「継母として尊敬こそすれ、他意はありません。」
「それならば何故反対されるのです。」
義時はしばらく考えていたが、「わかりました。そうまでおっしゃるなら従いましょう。」 と返事をした。
翌日、鎌倉は良く晴れた。 畠山重保の館は由比ヶ浜に近い所にあった。 重保は、数日前に菅谷の館から鎌倉に出てきたばかりだった。稲毛重成によって呼び出されたのだ。稲毛重成の妻も時政の娘であり、重成の父は、重忠の父重能の弟でもあった。
とかく不穏な空気が鎌倉には流れている。重保殿を鎌倉にのぼらせて、様子を見られた方がいいのではないか、そう重成から知らせてきたのだ。 その日、重保は波の音に目を覚ましたばかりだった。すると、何やら騒々しく若宮大路を騎馬武者が駆けていく。
「何事か見て参れ。」 重保はすぐに郎従をみせにやる。
「若殿、謀反人が由比ヶ浜に逃げたとのことです。」
「よし、すぐに馬を引け。」
重保は郎従三名を連れて由比の浜辺に馬を駆けさせる。 重保は三浦義村を見つけて近づいていく。 「謀反人はいずこに。」 義村は黙ったまま手で合図をした。とたん、義村の背後にいた佐久間家盛をはじめとした三十騎ほどの武者が重保主従を囲んだ。 「謀反人はそなたよ。」
重保は驚いたが、つぎの瞬間には矢が飛んできて、何かを考えている間もなかった。幸い、合戦支度をして出てきている。鎧の大袖で矢を防ぎながら太刀を抜くと馬を駆けさせた。
郎従たちも重保に続く。一瞬ひるんだ三浦勢の囲みを破って西に駆ける。が、あちこちから重保主従を目指して、十騎、二十騎と武者が駆けてくる。 重保はもはや逃げることはかなわないと、立ち止まって弓に矢をつがえて放つ。三本ほど射たところで、咳が出た。咳は重保の持病だった。最期の時になって咳の止まらぬ自分を重保は恨めしく思った。
そんな重保に矢が一本、二本と刺さり、数人の武者に馬乗りにされて首を掻かれてしまった。名乗りもないままの最期だった。 畠山重忠謀反。鎌倉中の御家人たちがその知らせに凍り付いた。重忠が謀反を起こしたならば大きな合戦になるに違いない。重忠はすでに軍を催して鎌倉に向かっているという。
将軍のいる鎌倉を合戦の場にするわけにはいかない。御家人たちはありったけの兵力を拠出した。大手の大将軍には義時が任じられ、葛西義清、境常秀、小山朝正、波多野忠綱、結城朝光、宇都宮頼綱、等従う武将三十六人、総勢一万三千騎。搦め手の大将軍は時房で、和田義盛と共に二千騎で関戸を目指す。
時政は四百人の壮士を引き連れて実朝の御前に伺候し、幕府の四門を厳しく固める。 三善善信、大江広元等は、それでも時政に言った。遠く朱雀院の御時、都から遠く離れた東国で平将門の乱があった際、土門だった門に扉をつけて厳しく守ったという。この度はあの畠山重忠の謀反であり、すでに鎌倉に向かっているとのこと。この程度の防備では全く足りるはずもない。 時政はさらに四百人の騎馬武者を御所の南御門前に集め、いざというときに備えさせた。 雲霞のような大軍は鎌倉街道を北上した。
その頃、重忠は武蔵の国と相模の国の境にある二俣川のあたりにいた。重忠はそれほどのことはないだろうが、重保一人を鎌倉にやることに不安を感じ、十九日に菅谷の館を出て鎌倉を目指していたのだ。 重忠に従うのは、重保の弟小次郎重秀、郎従本田次郎近常、半沢六郎成清等百三十四騎。みな、軽装である。 そこに、鎌倉の重保の郎従が急を告げた。何と、早朝に重保は由比ヶ浜で討たれたというのだ。
「何故、重保は討たれた。」
「わかりません。名乗りもないまま、三浦義村の軍勢に囲まれて最期を遂げられたご様子。また、鎌倉より軍勢がこちらに向かっております。鎌倉中の御家人たちが雲霞のように列を成して進んでおります。もう半刻もすればこのあたりまでやってくるはず。早く菅谷の館にお戻りください。」
「わっ、はっはっはっはっ。」 突然重忠は笑い出した。
「わずか百三十四騎の我らのために鎌倉中の御家人が出張ってくるとは。」
成清が近づいてきて言う。
「殿。こうなりましたら菅谷の館に戻り、一身、一家をあげて鎌倉の軍勢を迎え撃ちましょう。菅谷に戻れば策も立つというもの。一合戦して奥州に逃れる手もございます。」
ちょうどこの時、重忠が頼りとする弟、長野重清は信濃の国へ、同じくもう一人の弟の六郎重宗は奥州へと、それぞれ地頭に任じられている所領の検分に武者を引き連れて出かけていた。だから、菅谷の館に戻ったとしてもそれほどの兵力を集められるものではなかった。
「父上、いずれにしても、この二俣川の地で大軍を迎え撃つのは不可能です。」 重秀が進言する。確かに、比較的開けたこの鶴ヶ峰のあたりの地形は、大軍を迎え撃つには適していないことは確かだった。
「よいか、みなの者。この度のことは我らは全く知らぬ事。我らには謀反の意志など毛ほどもなく、何者かによって讒せられたことは明らか。大事なことは、我らの真っ白な心を天に示すことだ。」 重忠の言葉に皆が真剣に耳を傾ける。
「先日、梶原景時が誅せられた。景時は一宮の本拠を捨て、一族あげて京に上る途中で殺された。結果、景時は以前から謀反を企て、陰謀を企んでいたかのように言われることとなった。これは、一時の生命を惜しんだからのことである。この景時のことは、我らの戒めとすべきであろう。」
「それでは、この地で鎌倉からの大軍を迎え撃つと仰せですか。」
「重保がすでに亡き今、我らに残されたのはここで戦うことのみ。」
重忠の決断に異を唱える者は一人もいなかった。
「大串次郎はいるか。」
「はい。ここにおります。」
「よいか、次郎。これからわしがそちに命ずることに異を唱えてはならんぞ。」 「はい。」
「そちはこれから一人菅谷の館に戻れ。」
「それは出来ません。」
「異を唱えてはならん、と申したはず。そちは菅谷の館に戻り、わが妻どもにわしの言葉を伝えるのだ。」
「誰か他の者をお命じください。」 大串次郎は必死に訴える。
「次郎、お前でなくてはならん。よいか、重忠、重保、重秀が死んだと知れば、妻どもは後を追うやも知れん。だが、決して後を追って死んではならん、と伝え、そちが必ずそばにいて見届けるべし。そして、幼き子らを育て、畠山の家が向後も続くように取りはかれ、そのように伝えるのだ。」
大串次郎は泣きながらその場を離れて菅谷の館を目指した。 覚悟を決めた重忠主従は鶴ヶ峰に陣し、鎌倉の大軍を待ち受けた。しばらくして、続々と討手の大軍が、あちこちの峰に陣をし始める。その数、一万数千騎。 だが、彼らの誰もが目を疑った。畠山の軍勢はどう見ても百騎余り。しかも、鎧さえも身につけぬ軽装で待ちかまえている。畠山重忠の謀反、ということで鎌倉中の御家人は奮い立ってここまで来たのだった。
重忠の勢威はそれほど高く、少なくとも数千騎の軍勢で鎌倉を目指しているものと考えていたのだ。それがたった百騎余りの軽装の姿である。みな、謀反は何者かの讒訴によるものであり、事実無根であると理解した。が、こうしてお互いに陣を構えてしまってはどうにもならない。合戦に及ぶしかなかった。それでも重忠に同情し、誰も攻めようとはしなかった。 そんな中、安達藤九郎景盛が、野田興一、鶴見平次、秋間太郎等の剛の者として名高い従者七騎を率いて重忠の陣の前に進んだ。景盛は自ら鏑矢を弓につがえ、重忠の陣に向かってひょうど放つ。
「景盛はわしの旧来の友だ。しかも、その剛勇は誰もが知るところ。重秀、相手に不足はない。ひと当て合戦して参れ。」
重忠の命に、重秀は五騎ほどを率いて駆けていく。遠矢を射、接近しては太刀を取って戦い、また離れては騎射する。その馬上での技の数々は見る者を感嘆させた。 まるで絵巻物を見ているようであった。畠山勢は、五騎から十騎が一塊りとなり、あちこちで善戦する。それを取り囲んだ一万数千騎の軍勢は、同じように十騎、二十騎が一塊りとなって畠山勢と合戦する。そうすることを喜んでいるかのように、喜々としてみな合戦に興じた。
二時ほどそのような合戦が続いたが、愛甲三郎季隆が放った征矢が、重忠の喉を射きった。重忠はどっと馬から落ち、その首を季隆に掻ききられた。 それを知った畠山勢は、そこかしこで自死した。重秀も、半沢成清も自らの太刀で喉を掻ききって死んでいった。一万数千の兵はその姿をみな目に焼き付けた。 謀反の罪を着せられながらも、正々堂々と戦い、最期を遂げていった畠山勢に対して、鎌倉の諸勢はすがすがしいものを感じていた。そして、そうした畠山党を滅ぼし、二俣川を血に染めたことに後味の悪い思いをいだいた。
鎌倉に戻った義時は、重忠の首を持って時政の名越の館に参上した。
「よくやった。合戦はいかがであった。手こずったか。」
「重忠の弟や一族の多くは他所に出かけており、二俣川の重忠の率いる手勢はわずか百余騎に過ぎませんでした。重忠が謀反を企てていたというのは全くの虚偽で、何者かに陥れられたに違いなく、不憫でなりません。ここに持参した首を見るに及び、治承以来の思い出がわき出してきて涙が止まれません。」
義時の痛烈な批判に時政は黙ってしまうしかなかった。 その夜、酉の刻、鎌倉は再び騒々しくなった。稲毛重成の館を三浦義村の手勢が急襲し、その首を討ったのだった。また、重成の子である重政も、大河戸三郎によって討たれた。
確かに、親類であるにも関らず、重成は奸計を廻らして重保をおびき出し死に追いやった。また、重忠が誅殺されるきっかけを作ったともいえる。 しかし、それらはすべて北条時政の意志の上であるし、その背後には牧の方がいてのことであった。重成ひとりに罪をかぶせることはできない。 だが、時政は御家人たちの目をごまかすために、罪を稲毛重成一人に押しつけて、今回の件を終わりさせようとしたのだ。そうした意味では重成も犠牲者といえるだろう。
さて、重忠が誅殺されてわずか二ヶ月後、今度は牧の方の陰謀が露見する。牧の方は、実朝将軍を廃し、平賀朝雅を将軍職に就けようと画策したのだ。すんでのところで実朝将軍は時政の名越の館から義時の館へ移された。 この時、時政の側に立つ御家人はほとんどなく、鎌倉中の御家人は皆、義時の側に立った。義時は尼御台政子と実朝将軍を掌中においていたからだが、二ヶ月前の畠山重忠誅殺を、時政、牧の方の陰謀だと、誰もが理解していたからだった。
時政は落飾し、牧の方をともなって伊豆に落ちていった。平賀朝雅は追討使によって討たれてしまう。 結果、義時が執権として、実権を掌握することになった。 重忠の妻、時政の娘は、その後、足利義兼の次男岩松義純に嫁ぎ、一男をもうける。この男の子が畠山家を継ぎ、畠山三郎泰国と名乗るようになる。この泰国の子孫が、後に足利幕府の管領家である畠山氏へとつながっていく。
また、重忠の残した幼い子は、大串次郎に大切に育てられ、その子孫は新田義貞の鎌倉攻めに従って奮戦する。二俣川に散った重秀の子孫も、後に小田原北条氏に仕える事となる。 無念の思いをいだいたまま、由比ヶ浜に生涯を終えた重保の墓は、若宮大路の由比ヶ浜近くに今も残されている。そのりっぱな五輪塔は、せきに苦しむ人々によって長い間信仰され続けてきた。持病のせきのため、精一杯戦えなかった重保を多くの人々が哀れに思ったのであろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
