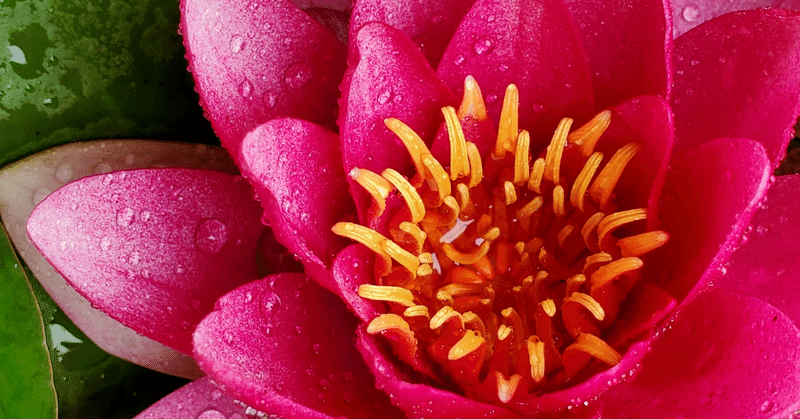
長編連載小説 Huggers(57)
裕子は激しく動揺する。
裕子 9(つづき)
しつこく食い下がろうとする男をなんとか振り払い、玄関のドアを閉めて急いで鍵をかけた。
冷え切った室内を暖めるためにとりあえず暖房のスイッチをいれ、コートも脱がないで男に渡されたコピーに目を走らせる。
その記事には、最近のミアの奇行の数々――取材や打ち合わせへの遅刻が目立つ、用意された弁当や差し入れを食べず、傍目にわかるほどやせた、インタビューでインタビュアーの問いに答えずただ微笑むだけだったり、相手を煙に巻くような返答をしたりする、瞑想と称して、ツアーにでかけてもバンドメンバーやスタッフと接触せず、一人でホテルに閉じこもっていることが多い、歌詞に今まで以上にスピリチュアルな色彩が色濃くなり、ついていけないファンが離れ、ファン層が変わり始めている――が、身近な関係者の話として書かれていた。
読んでいるうちに部屋の寒さにもかかわらず変な汗が出てくるのを感じた。ビールのあと、飲みなれない日本酒を少し飲んだのがいけなかったのか、気分が悪い。
ページをめくると、ミアは最近「一回のハグで悟りが開ける」と主張する奇妙な団体に入会し、そのせいで多くの友人知人が彼女の周辺から去っていて、このままでは芸能活動の継続も危うくなるだろうと書かれてあった。
時計を見てギリギリ大丈夫と判断し、永野に電話をした。二回ほどかけたが話中で、三回目にかけてやっとつながった。
「あ、西野さん、ちょうどかけようと思っていました。今小倉さんとお話ししていて、認定証の――」
「すみません、永野さん」話しかけた永野をさえぎって、裕子は言った。「ミアのことなんですけど。何か大変なことになってるみたいで」
「ああ、その件ですか」
即座の反応に、裕子は少しほっとした。
「永野さんは状況を把握されているんですね」
「まあ、だいたいは。西野さんはどうしてお知りになったんですか。まだメディアには出ていないと思いますが」
裕子がかいつまんでさきほどのルポライターの一件を話すと、永野は絶句した。
「その人なら、電話で一度話しました。そうですか、自宅にですか。どうやって知ったんでしょう。申し訳ありません。住所が漏れるはずはないのですが」
「ある程度は覚悟してました。自宅でセッションしてますから」
「では受講者が話したということですか? まさか。それは考えにくいですが」
「ないことはないと思いますよ。興味があるとか話が聞きたいとか言えば、善意で教えてしまうかも。そんなに悪い人ではなさそうだったし」
「西野さん」永野はあきれたとも感嘆したともつかぬため息をついた。「あなたの肝の据わり方には時々驚かされます。でも用心したほうがいい」
「私のことより、ミアはどうしたんです? 何が起こっているんですか? 本人には連絡がとれないんですか」
「いや、直接会いました。話もしました。結論から言いますと、何も問題ありません」
「そうなんですか?」裕子は驚いた。「でも記事を読むと、とてもそうは思えません」
「いや、あくまでも私の目から見て問題ないということです。世間的にはそうではないと思います」
「どういうことですか?」
「彼女には急激な覚醒体験が起こっています。ときどき、そういう方がいらっしゃるのは西野さんもご存じですよね」
「本で読んだことはありますけど。実際にそんなことがあるんですか?」
「言われているほど珍しい話ではないようです。その体験を他人に話す人が少ないだけで。ただ、ハグをきっかけにというのは、私の知る限りでは初めてです」
「え? ハグが? きっかけ?」
聞き間違いであることを祈った。
「本部に問い合わせをしてみましたら、ごくまれにそういう例があるそうです。初期化をきっかけに、深い覚醒体験が起こり、本人の顕在意識がそれについていけず、一時的に通常の社会生活に支障を来す」
「じゃあ、私のせい……なんですね。何かやり方を間違えたんでしょうか?」
「西野さんには責任はありません」
「でも」
「虚偽申告がありました」永野はあくまで冷静に言った。「彼女は学生時代に、ある種の麻薬の使用歴がありました。それを隠していたんです」
「麻薬? 本当ですか?」
「本人から聞きました。アメリカではそんなに珍しいことではないようです。それに常用していたわけではなく、何回か興味本位で使用しただけだそうです。音に対する感覚が非常に鋭くなるので、面白くて試してみた。申告したら、選考に通らないと思ったから黙っていた。そう言ってました」
「それが原因ですか?」
「たぶん間違いないと思います」
「本人は、いま、どうしているんですか」
「いたって幸せそうです。今の状況を喜んでいます。引退してもかまわないそうです。もう芸能活動に魅力は感じないと」
「待ってください。そんなわけありません」
裕子は叫んだ。
「あの子は歌を愛してます。歌うことが生きがいといってました。歌うことで、人々に生きる力を与えていきたいと。それが自分の生きる理由だっていってました。その人たちを放り出すわけありません。彼女の音楽を愛している人がたくさんいるんです」
「大丈夫」
永野はのんびりと言った。
「一時的に世俗的なことに興味を失っているだけです。覚醒がじゅうぶん熟し、そのとき彼女が必要と感じたらまた活動を再開するでしょう。彼女ほどの実力があれば、またやる気になればいくらでもチャンスはあります。よくいるじゃないですか、休養宣言して、また復帰する芸能人なんて」
「よくいるなんて簡単に言わないでください。それに、ほんとに覚醒体験かどうかなんて、どうしてわかるんです? 精神に変調をきたして、もうもとに戻れなかったらどう責任を取るつもりですか?」
「そんなことはありません。目を見ればわかります。覚者の目でした。話にも矛盾はありません」
「では――何もしないつもりですか? このままほっとくんですか?」
「したくても、私達にできることはありません。それとも、西野さんのところの精神神経科に連れて行って、入院させます?」
「そんな言い方……」
「彼女はセッションに専念したいと言っています。私としてはむしろ歓迎です」
まったくかみ合わない会話に永野ではらちが明かないと思い、電話を切った。動揺していた。一人の人間の運命を自分が変えた。そう思った。確かに覚醒体験は素晴らしいものなのかも知れない。でもあまりにも急激な変化、社会生活からの脱落は、ミアにとって決して望ましいことではないような気がした。周囲からは心を病んだとしか思われないだろう。
震える指で、スマートフォンの画面に電話帳を呼び出す。今すぐ小倉に共振してもらって、気持ちを立て直そうと思った。
とにかく、小倉の声が聞きたかった。
ずっと我慢して連絡を控えていたけれど、今はどうしても彼の声が聴きたかった。いつにもまして、顔が見たかった。
小倉さんなら、きっと、私の気持ちをわかってくれる。
裕子は思った。
きっと、一緒に事務局に腹を立て、一緒にミアを心配して、どうしたらいいか考えてくれる。
そして、いつもの穏やかな声を聴き、笑顔を見て、共振をしてもらえば、私はすぐに自分を取り戻せる。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
