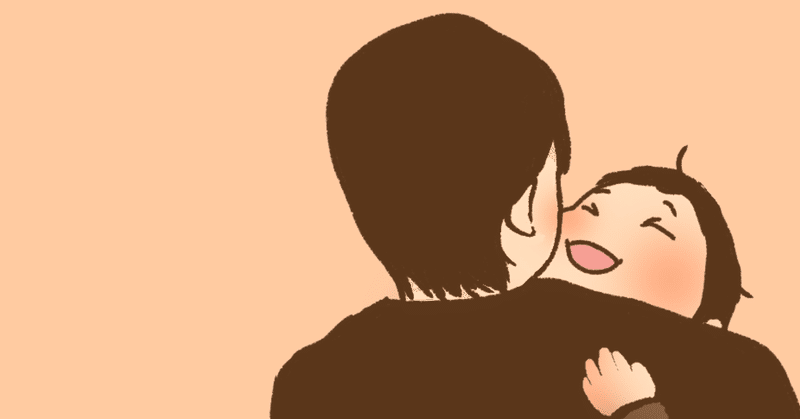
長編連載小説 Huggers(9)
失踪した妻の手がかりを探して、沢渡はある人物に会いにいく。
沢渡2
目当ての人々はすぐに見つかった。
代々木公園の、原宿駅方面からの入り口に近い小さな一角に数人の若い男女が陣取り、各自が白地にFREE HUGSと手書きの文字で描かれた、A3用紙くらいの大きさのボードを手に持って、道行く人たちに見せていた。
まだ高校生くらいに見えるワンピース姿の女の子二人組が、ニコニコしながら寄り添うようにして立っている。
その隣には大学生くらいの男子3人組が、お互いにわちゃわちゃとじゃれあうようにしながら「フリーハグやってまーす」と呼びかけている。うちひとりは撮影係のようで、スマートフォンで仲間を撮影している。
そして少し離れたところに白いシャツに、ジーンズ姿の髪の長い女性が立っていた。年齢は30代前半くらいだろうか。
彼女は声は出さず、ただどこか張り詰めた表情をして、両手で顔より少し高い位置にボードを掲げている。
あの人が清水美香に違いない、と沢渡は思った。
詩帆の動画を見て、沢渡はすぐにFREE HUGSという語を検索した。
そしてそれが、詩帆がやっていたようにFREE HUGSと書いたボードを持って街頭に立ち、通りすがりの見知らぬ人とただ抱擁する、という活動であると知った。
元々は、アメリカ人の1人の青年が亡き母親を追悼する目的で始めた行為だったが、オーストラリアの男性が動画を作ったことがきっかけで今では世界中に広がっていて、日本でも様々な人々がグループで、あるいは個人で実践しているという。
沢渡も見たその動画では、長髪に眼鏡の外国人の男(ホアン・マンという名だと後で知った)がボードを持ち、ハグの相手を求めてショッピングモールを歩いていた。
背景には優しく繊細に語りかける英語の歌が流れている。
最初は無視されたり、好奇の目にさらされたりするが、めげずに歩いていると、やがてハグに応じてくれる最初の相手が現れる。
二人が抱き合うと白黒画面がカラーになり、それが呼び水になったように、次から次へとハグの相手が現れ……という展開で、抒情的な音楽と短編映画のような構成も相まって、確かに人の心に訴えかける動画ではあった。
この活動は今では世界各国に広がり、様々な国で、年齢も性別もまちまちな人たちが同様の内容を動画サイトに投稿しているようだった。
清水美香に連絡をとったのは、失踪する少し前、日曜出勤の沢渡が帰宅したときに詩帆が「今日、代々木公園に行ってきた」と言ったことがあるのを覚えていたからだった。
そのときは「へえ、楽しかった?」などとのんきに聞いていただけだったが、今思えば何か目的があったのかもしれないと思い、Facebookでフリーハグをやっているグループを探した。
そして代々木公園を主な活動場所にしている美香のグループを見つけたのだ。
しばらくすると、参加者たちは休憩に入り、ベンチに集まってお茶を飲んだりおにぎりを食べたりしながら楽しそうにおしゃべりを始めた。
沢渡は、髪の長い女性に近寄っていったが、驚かせないように少し距離をとって声をかけた。
「すみません、あなたが清水美香さんですか?」
「あ、はい。清水です。沢渡さんですね? メッセージをくださった」相手は驚いた様子もなく言った。
「そうです。お返事くださってありがとうございます」
「すわりましょうか?」
美香は言ってすぐ近くのベンチを指し示し、二人は並んですわった。
「お知り合いの方を探していらっしゃるんですよね?」
「はい、この人なんですけど」
沢渡はスマートフォンを取り出す。
「見覚え、ありますか?」
「可愛い方ですね」
そう言って、沢渡が画面に呼び出した一番最近の詩帆の写真をしばらくじっと眺めていた美香は、やがて申し訳なさそうに首を横に振った。
「ごめんなさい、私が主催したイベントには、参加されてないと思います。いらっしゃった方のお名前は、たいてい把握してるんですけど。ちょっと、待っててくださいね」
美香はそう言って沢渡のスマートフォンを持って近くのベンチにいたほかの参加者たちに見せに行ったが、やがて肩を落として帰ってきた。
「ごめんなさい、誰も会ったことがないそうです」
「そうですか」
何気ない様子を装ったつもりだったが、落胆は隠すことができなかった。美香は一瞬迷ってから「もしかして、パートナーの方ですか」とたずねた。
「ええ。実は、出て行かれちゃったんです」
努めて軽い調子で言ったのだが、相手は予想通りの気の毒そうな顔をした。
「そうなんですか……。大変ですね」
「ただ、事件に巻き込まれたとか、自殺の心配があるとかじゃないので、それが救いっていうか」
そう言いかけてから、本当にそうだろうか、という何度も頭の中で打ち消してきた疑念がまたむくむくと湧いてきて、沢渡は中途半端に黙り込んだ。
「あのう、原因は、わかっているんですか?」美香がためらいがちにたずねる。
「いや。何も、はっきりこれっていう心当たりがなくて」
「そうですか」
美香はそれきり何を言っていいのか分からない様子で黙り込み、それは沢渡も同じで、原宿駅の方から途切れなく流れてきて目の前を通り過ぎていく人々をぼんやり眺める。日曜日だけあって、家族連れが多い。
「そういえば」
美香に話しかけられ、沢渡は我に返った。
「奥様がフリーハグに参加されていたんじゃないかって、どうして思われたんですか」
「実は、妻が、自分が一人でフリーハグをしている動画のURLを、僕あてに残していったんです」
沢渡は妻が残していった動画の話をした。
「その動画のなかでは妻は一人だったんですけど、少なくとももう一人、撮影していた仲間がいたはずです。だからもしかして、妻は僕が知らないうちにこの活動に参加していたのかもしれない。一緒に参加していた人たちに聞けば、何か妻についての手がかりが見つかるかもしれないって、そう思ったんです」
「なるほど」
美香は真剣な顔でうなずいた。
「動画、見られますか?」と沢渡は言ったが、美香は首を振った。
「いえ、今のお話だけで」そして、申し訳なさそうに、眉を寄せた。
「お役に立てなくて、ごめんなさい。奥様、早く見つかるといいですね」
美香はそう言って立ち上がりかけたが、沢渡の「あの」という声で再びすわった。
「清水さんは、なぜこういう活動をしているんですか?」
「ああ」美香は言って、ジーンズの足を組み、上になったほうのひざの上に片ひじをおいてあごを乗せた。
「うーん。なぜでしょうね」
そして困ったように視線を遠くにさ迷わせる。
「自分でもよくわかりません。私の場合は……たぶん、人の肌に触れたいんだと思います。変な意味じゃなくて。体温を感じると、安心するんです。最初にあのホアン・マンさんの動画を見たとき、なんかぞわって寒気がしたんですよ。これだ、私の求めていたものは、みたいな。それで急いで直近のイベントに参加してみたんですけど、最初は恥ずかしくてなかなか勇気が出なくて、中途半端な気持ちでボードを持ったままうろうろしてたんです。そしたらみんなにじろじろ見られて、変な人って感じでよけられて。でもそのうちだんだん、胆がすわってきたっていうか、別に見られても指さされてもいいや。ただ自分が楽しもうって思い始めたら、初めてハグに応じてくれる人が現れたんです。うれしかったぁ。そのときの気持ち、安心感、つながってる感じ、それが忘れられなくて、クセになっちゃったんです」
「でも知らない人とって、抵抗なかったですか? どんな人がくるかわからないし」
「私あんまり、何かする前に考えないたちなんですよね。思い立ったらぱっとやっちゃう。まあそれで失敗することもよくありますけど。もし色々考えちゃってたら、始められなかったでしょうね。だけど、もう二年くらいやってますけど、そんなに嫌な思いをしたことはありません。基本、おおぜいの人が見ている前でやりますし、一応ガイドラインがあって、みんなそれを守ってやってるし」
「なるほど」
「ただ、みんなが私みたいに感じているわけじゃないと思うし、奥様には奥様なりのスタンスがあると思いますよ。参加する動機は人それぞれですし、集まるメンバーだって毎回違うし。一度だけ来て二度と来ない人もいる、というかそっちのほうが多い。でも私はそれでいいと思ってます。……こんなところかな」
「ありがとうございます。ほんの少しだけ、理解できたような気がします。妻が考えていたこと」
「沢渡さん、よかったら体験してみません?」
上目遣いに沢渡の顔をのぞきこみ、美香は言った。
「ボードは余分に用意してきたんです。飛び入り参加される方がときどきいらっしゃいますので。奥様の気持ち、もっとよくわかるかもしれませんよ。ね、やりましょう」
勢い込んで立ち上がり、今にもボードを取りに行きそうな彼女を、沢渡はあわてて押しとどめた。
「いや……、今日のところは。心の準備ができてませんので」
「そうですかあ。こういうのは考えてるより、まずやってみることから入るのがいいんですけどね」
美香は心底残念そうな顔をした。
「気が向いたらぜひまた来てくださいね」
「ありがとうございます」
頭を下げると、美香は子供のようにバイバイと手をふって、仲間たちのほうへ戻っていった。さきほどの高校生も男子三人組も、そろそろ休憩を終えてハグを再開する様子だ。
沢渡は少し離れた木陰に立って美香を眺めていた。
詩帆の気持ちが理解できたような気がする、と言ったのは、嘘だった。
ただ率直に話してくれた美香に対しての礼儀としての言葉だった。
本当は、沢渡は詩帆がフリーハグに参加していたことに、ほとんど生理的な嫌悪感を抱いていた。
なぜ見知らぬ相手と抱き合おうなどと思うのか。
彼には想像もつかなかった。
清水美香は頭の上にボードを掲げ、微笑みながら道行く人に見せていた。大抵の人は、物珍しそうにボードと彼女の顔を見比べてから、少し迂回して通り過ぎていく。まったく無関心に通り過ぎる人もいる。十五分過ぎ、二十分過ぎても、ハグの相手は現れなかった。沢渡はこの運動が考えていたよりもずっと地味な行為であることに気がついた。
ホアン・マンの動画では、ハグの相手を探して歩き回ったり、無視されたりしている場面は、前半にモノクロ画面で短くまとめてある。そして誰かハグに応じてくれる人が現れたとたん、画面がカラーに変わって音楽も盛り上がり、映画のクライマックスのようにドラマチックな抱擁シーンが続く。だが現実にはBGMもなく、次々に相手が現れるわけでもない。
それでもまったく気落ちせず、むしろ楽しそうに道行く人たちに笑顔を送り、倦むことなくボードを持って立ち続ける彼女を見ていると、「痛々しい」という形容詞が頭に浮かぶ。同時に、ひとつの疑問が沢渡をとらえる。
「痛々しい」というとき、痛みを感じているのは誰なのだろう?
それは彼女ではなく、見ている沢渡自身だ。きっと彼女の姿に、自分のなかの目をそむけたくなるような何かを見るからなのだろう。そうでなければこんなに苦しいはずがない。それが、たった今親しく言葉を交わしたことで美香がただの他人以上の存在になったからなのか、一人で路上に立つ彼女に詩帆の面影を投影しているだけなのか、それと自分でも気づいていなかったような内面の痛々しい部分が、むき出しになって人目にさらされているからなのか。
ぞっと寒気がして、突然、美香にフリーハグをやめさせたいという激しい衝動にかられた。それ以上見ていると、本当に彼女に走り寄ってボードを奪い取ってしまいそうな気がして、沢渡は目を逸らし、急いでその場から歩み去った。
入ってきた原宿方面の入り口から遠ざかるように歩いた。あの感覚――西野裕子のアパートに行った日以来、時々唐突に彼をとらえる、心と体が中表にされているような完全に無防備な感覚がよみがえってくる。
なぜ関わろうとする?
枯れて茶色い芝生の上を、地面に這うように枝を伸ばす木々の間を抜け、何かから逃げるように彼は歩いた。革靴がほこりっぽい土と踏みしだかれた枯葉のかけらにまみれ、みるみる汚れていく。
なぜ自分に無関心な世界を抱きしめようとするんだ? 美香も、詩帆も。
「人の肌に触れたいんだと思います」
先刻の美香の言葉が脳裡によみがえり、どこか胸の奥深くにあった記憶を呼び起こした。
沢渡は詩帆と手をつないで立っていた。二人並んで立って、水面を眺めていた。あれはどこだったろう。詩帆の実家の近くの小さな沼のほとりか。不妊治療がうまくいかず、彼女が精神的に不安定になって、しばらく実家に帰っていた時期だった。
沢渡の手を痛いほど強く握りしめ、彼女は言ったのだ。
「ねえ、哲ちゃん。体って、何のためにあるんだろうね」
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
