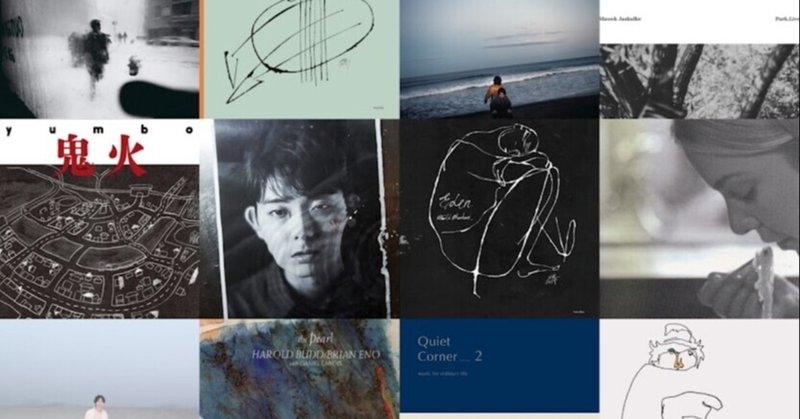
2021年マイベストアルバム
2021年を共に生きた大切なアルバム作品を10枚選びました。去年、一昨年といわゆる「新譜」と「旧譜」を交互にカウントダウンする形式を取っていましたが、今年はごちゃ混ぜ、発表された時代はフリーとしています。完全な自分オリジナルとして自信を持っていた去年までの形式。少し未練はあるけれども自分の中でのベストなフォームというのは変わり続けるものです。
皆さまより少しだけ先回りして、自分が選んだ10枚を眺めてみます。このリストに何かタイトルをつけるならば、『心に寄り添う作品集』といったところでしょうか。2021年、無意識に心を鎮めたいと願いながら音楽を聴いていたように思います。だけど音楽が心を鎮めてくれない時間も長かった。(そこで、音楽以上に私を救ってくれたのが料理することでした。)
このリストは私の鎮まらぬ、かといって明らかに騒がしいわけでもないドロッとした心に対して、白でもなく黒でもなく(晴れでもなく雨でもなく)ただそこに共に居てくれた作品集。
同じ心を共有し、2021を共に乗り越えたような、そんな気持ちを持っている作品ばかりが自然と集まってできたものなのです。
10. Tsuki No Wa『Ninth Elegy』 (2000)

アルバムは「On Mother's Day」で幕を開けます。ぽつぽつと爪弾かれるピアノ、続いてベース、しばらくはその2重奏。ほどなくして密かに紛れるノイズ、そして遠くから少しずつ近づいてくるように震えるソウルフルなボーカル、寄り添うサックス。プロデューサーのAmephoneによる幻想的なサウンドスケープは私を酩酊させ、どこか遠く暗転した天井の高い音楽ホールへと連れていきます。
しばらくそのサウンドスケープに身を任せた私の耳に飛び込んでくるのはボーカルFuminosukeによる、地の底までも震えるようなシャウト。その振動はまるで稲妻となって一時、闇に包まれていた広い広いホールや演奏家たちの全貌を照らし出すようです。
終盤、ふいにドラムスティックを床に落としたようなSE、その瞬間私は如何に彼らが作り出す音に意識を集中していたと同時にまどろんでいたか、ハッと我に返るのです。
9. Sam Gendel『Fresh Bread』 (2021)

今年の春先にこれまでスルーしていたサム・ゲンデルの作品をふと聴き始めてから、すっかりその音の虜となりました。主要な音源を聴き漁り、ありえないペースでリリースされる新作音源を追い、レコードを集めました。Sam Wilkesが屋台骨を整えてくれているおかげで、輪郭を掴みやすい『Music for Saxofone & Bass Guitar』を始めとしたSam Wilkesとの共演シリーズや、サム自らの手による嬉しい発掘音源「Inga 2016」、笹久保伸との共演作など、ここに選びたいものはたくさんありましたが、私の中で最もサム・ゲンデルらしい作品ということで、選んだのは『Fresh Bread』です。
3時間半を超える膨大な録音を集めた音源集。この作品がサム・ゲンデルのディスコグラフィの中でも一番空っぽの音楽が鳴っているような気がするから好きです。
空っぽだけどサムの生み出す音色は暖かく、おいしいところだけが次々と通り過ぎては消えていくような小品の数々はニュートラルな気品に溢れていてクールだなと感じたのでした。
8. 澁谷浩次『Lots of Birds』 (2021)
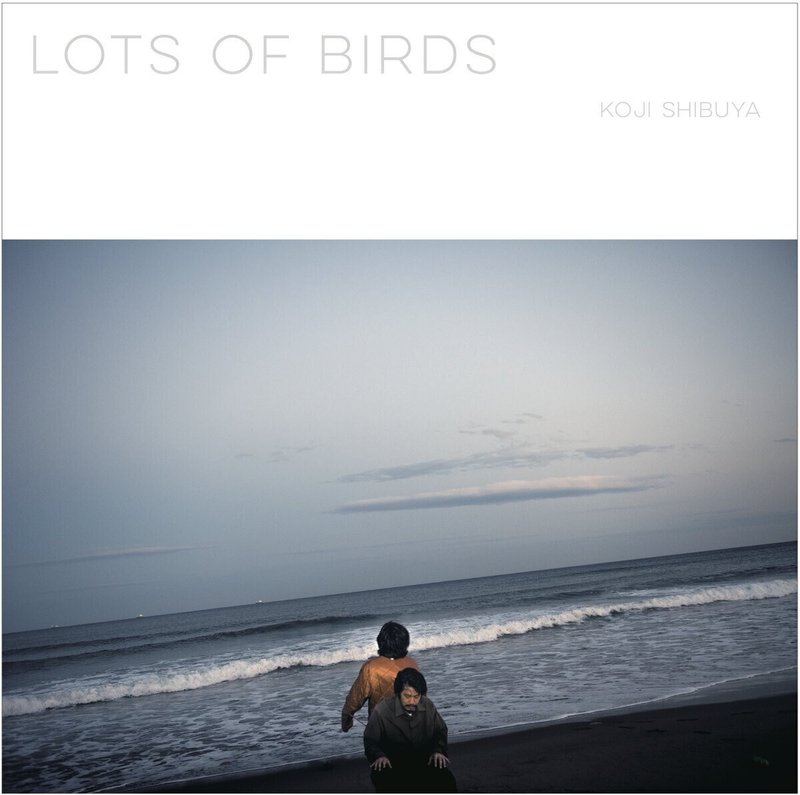
仙台のバンドyumboのコンポーザー 澁谷浩次のソロ作。自らが演奏するギター、シンセ、ヴィブラフォン等複数の楽器に、瀬川雄太のドラムスが加わったサウンドは晴れでもなく雨でもなく、どこか曇がかった優しさがあります。それはまるでこのレコードの美しい盤面の色のような。そしてフレーズを一つ一つ、そっと置いていくような朴訥とした歌唱は、聴き手の懐に馴染みよく入り込んできて、どこか親密な感情を持ってしまうような、そんなレコード。
本人による全曲の歌詞解説で、オープニングの「In a Limited Time (限られた時間内に)」について以下のように語られています。
長らく会っていない友人にあてて書いたもので、最初にこれを書いたことで、このアルバム全体のストーリーが一気に決定づけられた。時間が限られている、というのは最初に宣言しておきたかったことで、自分自身が50才になろうとしていた気分がそのまま出ている。
アルバムを通して目立つのは、長らく会っていない、もう会うことはないかもしれない友人や知人をポツポツと思い出しながら、彼らにあてて書いた手紙の中、思い出話の断片のような歌。本人は50歳になろうとしていた気分がきっかけと語っていますが、友人やこれまで出会った人から多かれ少なかれ切り離された、パンデミックの時代を生きる私たちの心が映し出されたアルバムとしてもこのアルバムを捉えられはしまいか。少なくとも私はそう感じていて、何だかそれがとても心強かったのです。
7. Caoimhín Ó Raghallaigh & Thomas Bartlett『Caoimhín Ó Raghallaigh & Thomas Bartlett』 (2019)
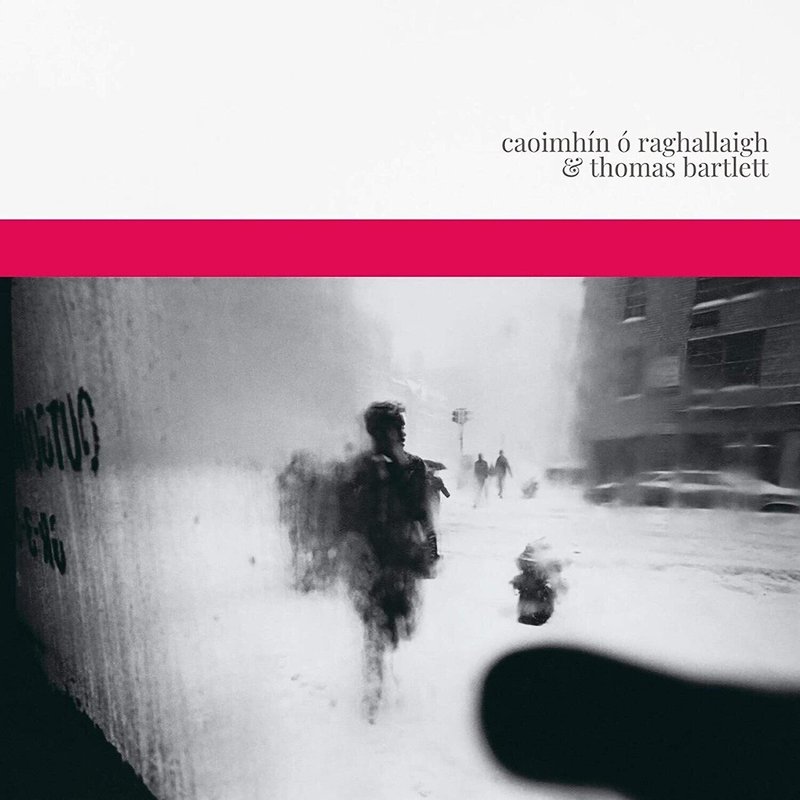
今年自分の中で大きかったこととして、山本勇樹氏による『Quiet Corner』というディスクガイドとの出会いがあります。7年前に刊行された1巻のサブタイトルは『心を静める音楽集』、そして今年刊行の続編のそれは『日常に寄り添う音楽集』というのを今確認したうえで、この年間ベストの前書きを振り返ると、図らずもあまりになぞった感が出ていて、なんとも恥ずかしい。
少し弁明させてもらいましょう。『Quiet Corner』というディスクガイドと出会う前から、僭越ながら私も"セルフクワイエットコーナー"をやっていたのだと。去年の暮れにそれとは関係なくCaoimhín Ó Raghallaigh & Thomas Bartlettによる本作に出会ってから何度も繰り返し聴きました。そして夏、新刊として目に入ってきた書影で、本作(とこのあと4位に選んだ作品)を表紙に選ぶディスクガイドなんてものが存在するのか…!?と驚いたのが『Quiet Corner2 日常に寄り添う音楽集』との出会いでした。すぐに購入してページを開いてみると、私にとって非常に大切な作品が、国や年代、ジャンルを超越して随所に並ぶ紙面。それは親近感どころかもはや他人のアウトプットとは思えないような域に達していて、嬉しくなると同時にある種の悔しさすら湧いてきたのでした。
私の頭の中にぼんやりあったのとごく近いイメージ (つまり"セルフクワイエットコーナー") に著者の山本勇樹氏は「Quiet Corner」と美しい名を付け、2冊の名著を編んだのです。Caoimhín Ó Raghallaigh & Thomas Bartlettによるピアノとフィドルの2重奏はそんなQuiet Cornerと私を繋いだ作品。
6. Harold Budd & Brian Eno 『The Pearl』 (1984)
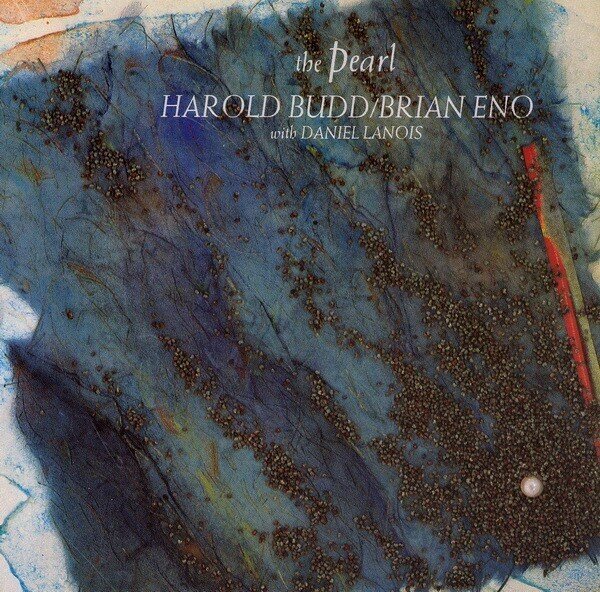
私のApple Musicアカウントによると、この一年ストリーミングで一番聴いたのはこの作品らしいです。夏くらいに初めて聴いて「イーノ関連でこれが一番なのでは?」と驚いてから、あらゆる場面で聴きまくりました。特に一日の終わりに。二日に一日くらいはこのアルバムで入眠していたような気がします。
「凪」の音楽、まずはこのアルバムをそう称してみることから始めたいと思います。凪とは<風がやんで、波がなくなり、海面が静まる>こと。この音楽の持つ底知れぬ虚無は、付かず離れずいつもただそこにあり、私の心は心地よく凪に近づくのでした。でも何か違う気がする。凪は海面の状態を指す言葉ですが、この音楽が鳴っているのは海上ではない。むしろ海中深くな気がするのです。状態としては凪にかなり近いのに。海中での凪に相当する言葉ってないのでしょうか?もどかしい。
しかも、もう一度海中での様子を観察してみると、浮遊感たっぷりのシンセサイザーは媒質となり、ハロルド・バッドによるミニマルなピアノの音色はその中を振動するような、何か波紋に近しいそんなゆっくりとした動きが存在しているようにはみえてこないでしょうか。
さらにこのアルバムを言い当てる言葉が分からなくなってきました。そしてこの言い当てられなさが、音楽の一つの本質なのかもしれないとふと思ったのでした。
5. ROTH BART BARON『無限のHAKU』 (2021)

このリストは私の鎮まらぬ、かといって明らかに騒がしいわけでもないドロッとした心に対して、白でもなく黒でもなく(晴れでもなく雨でもなく)ただそこに共に居てくれた作品集。
と、もう一度自らの前書きの言葉を振り返ってみます。「白でもなく黒でもない」ときたら、大半が次に思い浮かべるのは両者混じりあった曇りの色、グレーなんじゃないかと思います。でも三船雅也は違った。彼はなんと白のレイヤーを描こうとしたのです。その慧眼、それだけでもうすっかり痺れてしまう。
白、そこにはまっさらであるがゆえの緊張感が宿ります。
今の世界はシンプルに見える純白の裏側で虫のように何かがたくさん蠢いています。
日本を洗濯したいという有名な言葉がありますがこの音楽はあなたの心を静寂でまっさらにし滅び、蘇生する物語です。
とは三船雅也によるアルバムのデジタルリリース時のステイトメント。ステイトメントの中にも、そしてもちろん音楽にも、もっと優しく、傷ついた我々を抱擁と共に蘇生せんとする側面もありました。でも私がこの作品を聴いて何より感じたのは、三船雅也個人のパーソナルな混乱や、はたまた純粋でプリミティブであるがゆえの切れ味の鋭さ。そこにはある種の聴き手を突き放そうとするような、そっけなく、神聖な雰囲気さえ感じはしないでしょうか。それはまるで、人智を越えた存在である山や砂漠といった大自然のように。
例えば『化け物山と合唱団』であったり、初期の頃からロットの描くサウンドスケープの大きさには稀有なところがあったけれど、今作ではそんな過去作とほど近い到達点に対して、劇的に刷新された真逆に近しいアプローチでもって辿り着ているような、そんな印象を覚えます。
ずっと千利休の本を読んでいました。千利休って茶室の空間デザイナーでもあって。たった2畳のほとんど何もないデザインされたスペースで、人間が身分の垣根を超えて1対1でお茶を嗜む。そこには緊張感があるんだけど、心がチューニングされていく場所でもあって。
https://numero.jp/interview286/p3
茶室のように縮こまって入る小さな世界。縮こまって縮こまって、(あるいは潜って潜って)、その結果広大な裏側まで辿り着いてしまったようなイメージ。
『霓と虹』という曲でもってそんなイメージは鮮やかに具現化されます。
重力を悪戯に
ひっくり返して
この世の 虹を全部
両手に 集めて
世界が逆さまに落ちていくのを見てた
(「霓(にじ)」とは、はっきりと見える「虹」に対し、その外側に薄く見える副虹を指すそうです。これぞまさに裏側であるとは言えないでしょうか…)
4. Slawek Jaskulke 『Park.Live』 (2020)
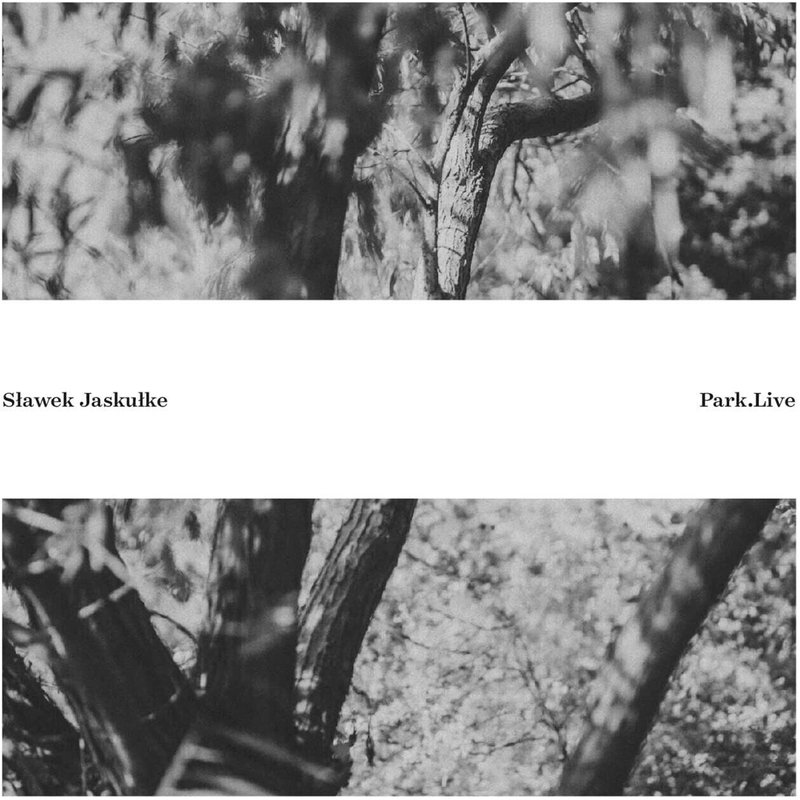
ただ単に一番好きな楽器というのもあるんですが、「私が今追い求めている理想の音楽はピアノソロ、もしくはそれに準じた音楽だ」という気が今年ずっとしていて、色々なピアノ作品を聴きました。その中でのNo.1。
ポーランドのピアニストSlawek Jaskulkeが、自身の住む街ソポトにある歴史博物館の野外庭園で開催したコンサート演奏を録音したのが本作です。Slawek Jaskulkeと言えば、自身の娘が安らかに眠れるようにと作られた『Senne』という作品を背景にして、ダウンピッチング(通常の440 Hzから10 Hz近く落としてピアノを調律する)を施した音色がシグニチャーというべき要素です。ここで少しピアノの調律について歴史を調べてみると、バッハなどのバロック期のピッチが415 Hzで、モーツァルトの時代で421 Hz程度、ベートーヴェン辺りにきてようやく430 Hzなんだそう(諸説あり)。つまり楽器のピッチは時代と共にどんどん上がっていったと言えます。現代中の現代の音楽に慣れ親しんだこの耳で聴くSlawekの音色は、浮遊感や少し電子的にも聴こえる柔らかさがあり、どこか現代のピアノという楽器のアイデンティティや記名性から解き放たれていく行くようにも聴こえます。それは近年サム・ゲンデルがサックスでやっていることと案外近いのかもなとそんな考えがふとよぎりました。
また、音色以外にもフレーズ、タイム感というところを取ってみても、あまりに完璧で惚れ惚れしてしまいます。どの曲も長い周期を1フレーズとして捉えているような意識があって、ゆっくりと打ち寄せる波を見ているような。複雑に絡まり合った頭の中の糸が一か所ずつほどかれていくような、そんな感覚を覚えるのでした。
3. 折坂悠太『心理』 (2021)
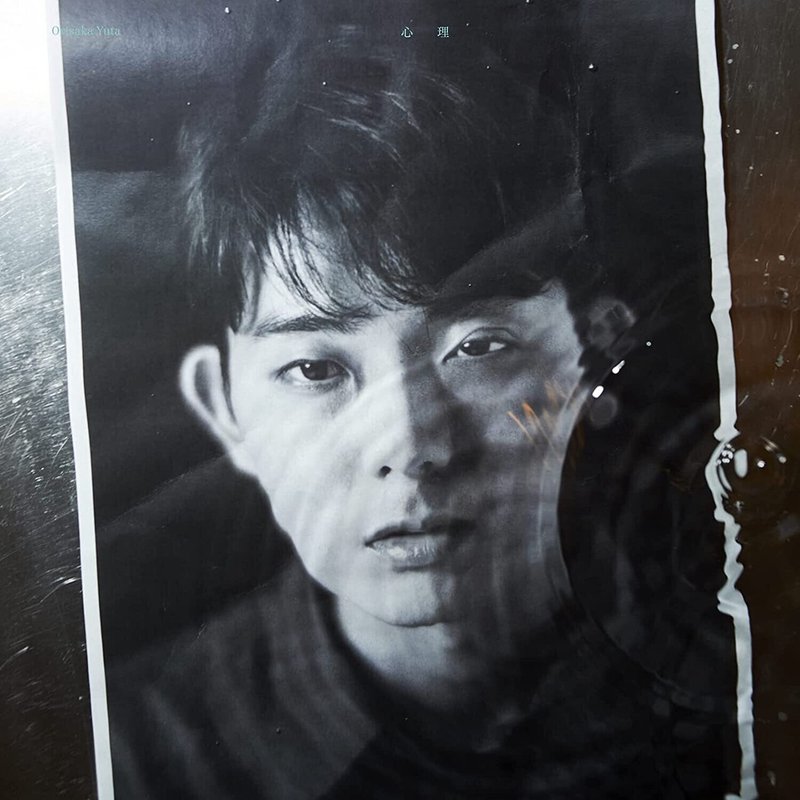
アンサンブルに尽きる。そんな作品だと思います。音響的に明らかにソリッドであったり、目立つ音色があったりというわけではなく、ぼんやりと聴いてみると、全体的にまとまりがあるなというくらいにしか最初聴こえなかったのが正直なところ。しかし、聴けば聴くほど音のレイヤー、積み重ね方というか、そんなポイントに底なしの旨みを感じて引きずり込まれていくような作品でした。
具体的には、どこでどの楽器がどれくらい聴こえてほしいという音色の階層のコントロールが完璧だと思うのです。それはまるで、数秒、それ以下コンマ何秒ごとに切り替わる各パートのソロを聴いているような感覚に陥るほど。平たく言えばバンド演奏を解体して再構築したようなそれは録音技術やポストプロダクションだけでなせる業ではなく、ベースには重奏バンドのプレイヤビリティというところが大きいのは想像に難くありません。
さらにその恩恵として、かなり小さな音量で聴いたとしても演奏がとても面白く聴けるというのは、地味ですがかなり衝撃的なポイントとして触れておきたいところです。ときにそれこそが、彼らのアンサンブルに対する拘りが如何に鮮やかに達成されているかの何よりの証左ではないかと思うのです。
加えて、相反する感情をも併せ持った各曲の言葉がもつ複雑性に、重奏バンドの演奏や折坂悠太の歌唱が重畳された結果、そのグラデーションは一層深みを増し、一つの感情が立たない滑らかな丸みを帯びた音楽を形成することに成功しているように思います。その時の聴き手の気分に対応して、丸みはちょっとずつ形を変え歪みます。そんな本作との付き合いはとても楽で、これも曇りの音楽だなと思いました。
2. World Standard『色彩音楽』 (2020) 『Eden』 (2021)
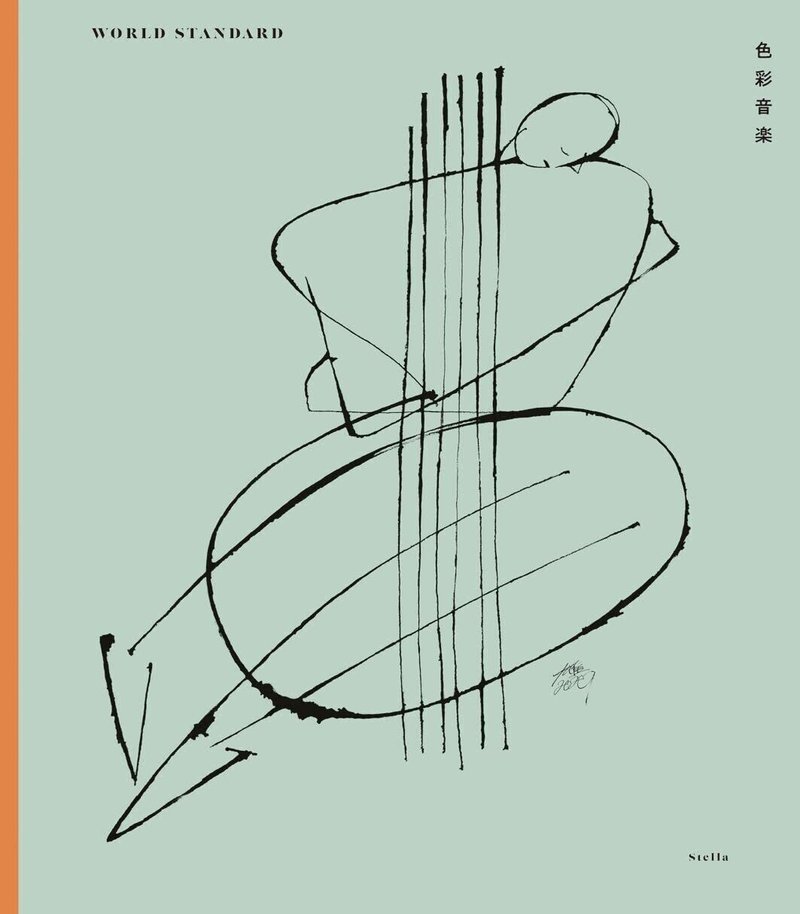
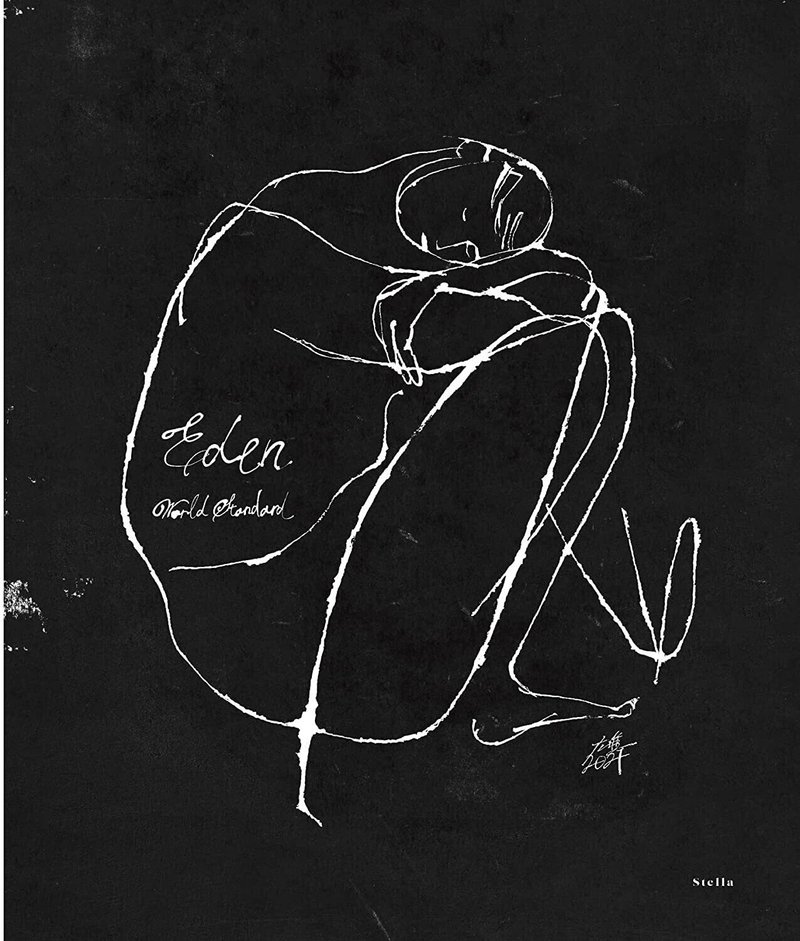
去年の暮れに『色彩音楽』を手に取ったところを出会いとして、この一年、日々は常に鈴木惣一朗 ( a.k.a World Standard) の音楽、文章と共にあったと言っても過言ではありません。2021年はどこを目指して歩いても鈴木惣一朗に行き着いてしまうような感覚さえありました。私が毎月書いているnoteでは、この一年ほとんど毎回のメインテーマが、いかに鈴木惣一朗の生み出す音楽、文章へ傾倒しているか、となりました。
ほとんどぴったり1年のスパンでリリースされた『色彩音楽』と『Eden』は、コンセプト、音楽性、装丁といった多くのポイントで切っても切り離せず、アートワークやタイトルからも見て取れるように、ときには兄弟さながらに、またときには対となって響き合うようなアルバムだと思うので、2枚で1枚というカウントにさせてください。
まずは、キャリア35年で初めての鈴木惣一朗自身による歌ものアルバムとなった『色彩音楽』。本人の弾くギター伴奏を中心とした文字通りの歌ものアルバムとして聴ける反面、インスト主体の過去作よりむしろ細かいサウンドに意識が向くという現象がこの作品を特別たらしめています。それは間の使い方によるものというか、「歌う時」と「歌わない時」という新しい間を獲得したからこその、35年を経てたどり着いた境地のようなものである気がしてなりません。付属のイラストブックで「夢の月影」という曲に付された文章の<光>と<影>というモチーフは前述のイメージを補完するように響きます。
かつては<光>のことを<影>という呼び方もしていたそうです。連歌師・桜井基佐の歌にも「山かづら また星かげに 鶯の羽 たたきて鳴く 梅の枝末に」とあります。大好きな影絵作家の藤城清治さんも「光と影が人生なんだ」と仰っていました。
次は『Eden』。『色彩音楽』と比べて一曲の中のフックとなるようなポイントは減り、代わりに時にドローンミュージックのようにも聴こえるストリングスやシンセサイザーの、深く長いフレーズが作品全体を包み込みます。それは無声の叫びのようにも、穏やかななぎのようにも聴こえてきます。
切れはしには「シズカナ コエ サワガシイ ココロ」と書かれています。何度も読み返すうちに、それは8つの歌になりました。この2年という時間でぼくのこころは、ほとんどいっぱいなんです。
ー『Eden』イラストブック
長いフレーズの雲の切れ間から、静かに優しく、決意や覚悟を湛えた鈴木惣一朗のボーカルが聴こえてきます。それは光です。その光に導かれて私は、もう一度、と青空の元へ踏み出していくのです。
1. Yumbo『鬼火』 (2016)
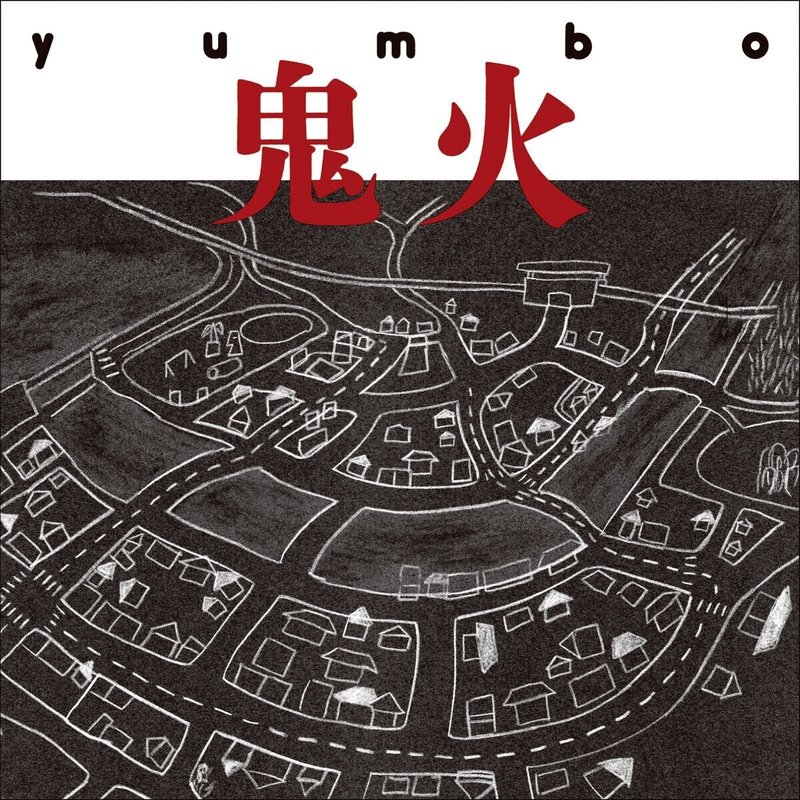
文字にすると何かが薄まってしまうような気がして、この音楽について書くのが少し怖いです。Yumboの音楽からは分からないもの、目に見えないものに敬意を払い、それをただ見つめ続けることによって大切にしていこうとするような姿勢を感じるから。それによって澁谷浩次を中心に、Yumboの作り出す楽曲には、まるで今ここではないどこか、それはもしかするとあの世にいるような不思議な奥行きが生まれています。でも一方で地に足はついている。浮遊感に逃げない。そんな質感。
タイトルトラック「鬼火」はそんなYumboというバンドの在り方を象徴するかのように響きます。
鬼火が
わたしの戸口に灯っている
夜明けまで
酒のなかでちらついている
澁谷浩次を初めとしてこの作品に参加したメンバーが演奏しながら、はたまた我々リスナーが聴きながら思い浮かべた全ての魂が手を叩き、脚を踏み鳴らし、歌っているようなそんな重厚な震動が、「鬼火」を始めとするこのアルバムの音楽からは聴こえてくるような気がするのです。時代を越えすべての魂を鎮める歌。残されたものの背中をそっと押す再生の歌。
バンドの結成から23年、『鬼火』リリースから6年、ようやくYumboの音楽に出会えてよかったです。2021年、もうそれだけで幸せだったような気さえします。『鬼火』だけに限定しても、ソングライティングのこと、アレンジのこと、各プレイヤーのこと、リリックのこと、アートワークの背景のこと、バンドの在り方のこと、話したい事がたくさんあります。でもここではあえてそれを書くことはしません。みなさんYumboを聴きましょう。そしていつの日か私と、どこがあーだこうだと結論のない話をしましょう。
少し長いあとがきのようなもの。ここまで書いてきて一つ思い浮かんだことがあるので最後に変な遊びをしてみようと思います。
いきなりですが、キーワードというか媒質を最初に挙げておくと、
「Quiet Corner 2」、「マヘル・シャラル・ハシュ・バズ」、「イ・ラン」、「トウヤマタケオ」、「徳澤青弦」
となります。
これで分かる人いるでしょうか?
まずは「Quiet Corner 2」。
「Quiet Corner 2」では、Caoimhín Ó Raghallaigh & Thomas Bartlett『Caoimhín Ó Raghallaigh & Thomas Bartlett』、Slawek Jaskulke 『Park.Live』、World Standard『色彩音楽』が選盤されています。
しかも鈴木惣一朗は「Quiet Corner 2」の中で、Slawek JaskulkeとBrian Enoを並列で取り上げてコラム書いているということでちょっと無理矢理ですが、
Caoimhín Ó Raghallaigh & Thomas Bartlett ー Slawek Jaskulke ー Harold Budd & Brian Eno ー 鈴木惣一朗 (World Standard)
と繋ぐことができます。
さらに鈴木惣一朗から先に繋ぎます。私がやろうとしていること、皆さんもうお分かりですね。
次のキーワードは工藤冬里がリーダーの「マヘル・シャラル・ハシュ・バズ」というバンドです。
マヘル・シャラル・ハシュ・バズにしばしば参加している久下恵生と鈴木惣一朗はパンゴという不定形ユニットで80年代に共演してアルバムを残しています。(今年パンゴのCD買ったんですがあんまり聴けていない・・・)
そして、マヘル・シャラル・ハシュ・バズといえば澁谷浩次です。澁谷がマヘルに、工藤冬里がYumboに、とそれぞれの作品で共演を果たしています。
よって、
鈴木惣一朗 ー Yumbo (澁谷浩次)
が繋がります。
次のキーワードは「イ・ラン」
折坂悠太の『心理』にイ・ランが参加していることはもはや言うまでもないですね。
そして、イ・ランはYumboのライブに参加したこともあり (この時共演した『鬼火』の音源はBandcampで買えます。あまりに素晴らしいので気になった人はぜひ。)、しかも『Lots of Birds』のSpecial Thanks欄にもイ・ランの名がある仲です。
ということで、
Yumbo (澁谷浩次) ー 折坂悠太
まで来ました。
ここでさらに、折坂悠太の『心理』にはSam Gendelも客演しているので、
折坂悠太 ー Sam Gendel
とテンポよく直接繋いでしまいましょう。
次は、一旦澁谷浩次に戻って2又に分かれます。キーワードは「トウヤマタケオ」というピアニスト。
来年1/9に予定されているトウヤマタケオ『四辺は森として (あたりはしんとして)』 レコ発公演のゲストは澁谷浩次です!!(チケット取りました!楽しみ!)
またトウヤマタケオは、Tsuki No Wa『Ninth Elegy』のプロデューサーAmephoneが全面的にミックスを担当した「飛ばない日」というアルバムを2013年にリリースしています。
ということで、
Yumbo (澁谷浩次) ー Tsuki No Wa
さらにトウヤマタケオは徳澤青弦とThrowing a Spoon名義でコラボレーション作品を産み落としています。
徳澤青弦とのコラボレーションといえばROTH BART BARON『無限のHAKU』も同じですので、最後はトウヤマタケオ、徳澤青弦と2媒質挟んで
Tsuki No Wa ー ROTH BART BARON
で全てを繋げきることができると、そういうことでした。図解は各自頭の中でお願いします。(仕事中とかならともかく、こういうときにすぐ図解しようとしたり、諸々をまとめようとする人が少し苦手です。分かりやすさによって逆に見えなくなってしまうものがあると、常々そう思っているのです。)
ここで挙げた繋がりきっかけで聴いた作品は皆無なのが、個人的にたまらなくおもしろいポイントです。別に近しいところを手あたり次第聴いたみたいなラインナップでもないように思いますし…何か磁場のようなものが働いて、それぞれの作品が2021年に出会うべくして私の前に立ち現れた、そう考えるのは少しこじつけが過ぎるでしょうか。
どうぞお気軽にコメント等くださいね。
