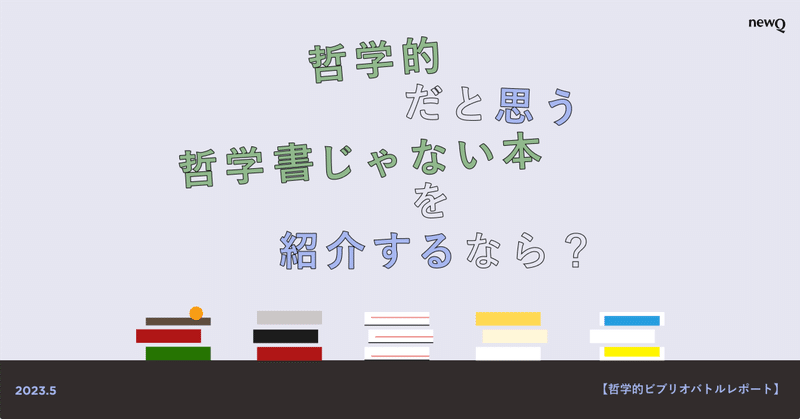
【哲学的ビブリオバトルレポート】哲学的だと思う哲学書じゃない本を紹介するなら?
newQメンバー5人で哲学的ビブリオバトルを開催しました。お互いに「哲学的だと思う哲学書ではない本」を持ち寄り、おすすめし合います。newQ賞をその手に掴むのは誰か……。その白熱のディスカッションの模様をお届けします。練習から始まり、愛するとは何かという話まで。みなさんの本棚のご参考に。お楽しみください。
練習を考えることから始まる哲学とは?:ハル・クック『ハウ・トゥ・インプロヴァイズ』
瀬尾 まず、私が紹介したい本は、ハル・クック『ハウ・トゥ・インプロヴァイズ』(佐藤研司監修、愛川篤人訳)です。
この本はジャズの即興演奏のための定番の教則本なのですが、ふつうの本とは違い、「そもそもインプロヴィゼーションとは何か?」といった抽象的な問いを考えることから始まります。例えば、有名な序文は次のように始まります。
インプロヴィゼイションは入り組んだ性質をもっているために、多くのプレイヤーは、入手可能な膨大なデータを敢えて無視し、私が Ready, Fire, Aim(準備を整え、撃ち、狙いを定める)と呼んでいるアプローチをとっている。これを一言でいえば、目を閉じ、耳を開いて、ホーンをブロウーし、結果がうまくことを期待する、ということである。
考えるべきことがあまりにもたくさんあるので、このアプローチには、考えることに比べ確かにある種の利点がある。事実、これは一般に、正確にインプロヴァイズするための理想的な方法と考えられている。
〔……〕
しかし、このReady, Fire, Aim という方法には、偶然に頼った要素があまりにも多くあるために、インプロヴィゼイションを練習するための唯一の方法としては、致命的な限界がある。〔……〕少なくとも常に何らかの進歩を得、また聴覚と直感だけによって到達できる以上のものを得るためには、学修の方法を秩序立てて構成する必要があることに気づくであろう。Ready, Fire, Aimというアプローチは、パフォーマンスするためには適切であるが、練習にはReady, Aim, Fire(準備を整え、狙いを定め、撃つ)というアプローチが使われなければならない。そうなると問題は、それをどのようにしてインプロヴィゼイションに適用すればよいのか? ということになる。(クック 2021, 4)
練習を考えるとはつまり、やろうとしている試みの分解、分類である以上に、コンセプトの探索でもある、ということだと思います。それはつまり(音楽であれば)どのような演奏のアプローチに美的な価値や可能性を感じているか考えることになり、練習をしていくことで、初めて見える世界があるということです。そこで浮かんできた問いは、このような身体性をともなった探求とは一体どのようなものなのだろうか、というものです。
私の考える哲学ポイントは、次のようなものです。
🐬哲学ポイント🐬
練習を考えることから始まる哲学とは?
難波 哲学における練習とは何かを考えていました。哲学では、他の学問よりもいっそう練習の仕方があまり教えられていないように思います。みんないったいどうやって練習しているんだろう? 私は中高は吹奏楽にいたので練習が大好きで、研究のときもその練習態度を継続している感覚がありますね。
瀬尾 確かに、本を読めば知識を得られるかもしれませんが、哲学の技能はどうやって身につけるのか、私も知りたいですね。
今井 人文系での練習が文献購読なんじゃないでしょうか? 教員や先輩をリーダーとして難しい文献を丁寧に読んでいくことで、文章の読み方を学んでいく。千葉雅也の『勉強の哲学』を読むのとかも人文系の練習かも。
難波 確かに。文献購読は練習の一つですね。すると人文系の練習は一人でできるものが少ないのでしょうか。
大島 知識という話に注目すると、知識では得られないものは練習が必要だと言えるのかもしれないですね。例えば、「観察する」ことも練習しなければいけないなと。『観察の練習』は実際にやった「観察」を分類しまとめられた本なので、とてもためになりました。
瀬尾 いま話を聞いていて、練習、と聞くと具体的な方法の話にすぐ行ってしまいがちですが、概念的な探求がつねにあることが面白いと改めて感じます。
今井 そうですね。料理本にもスピリチュアルな本から具体的なテクニックのものまで幅広くあります。
瀬尾 先ほど例に挙げられた哲学における文献購読は、ジャズにおける先人の演奏のコピーとアナライズに近いと思うのですが、この本に書かれているのは、そこからある要素を取り出して、その部分を集中的に練習したり応用発展するやり方でした。自分の見立てとして、いま、練習の時代が来ている、と思います。例えば、ジャズではプロの多くがやっていることをうまく言語化して練習法に落とし込み、そしてそれをSNSなどで人に伝えてくれる人が多いという肌感覚があります。練習について考えると、新しい問いが見つかりそうだと思いました。
小説の概念を哲学する(小説で):三輪太郎『憂国者たち』
今井 私は、三輪太郎『憂国者たち』 をみなさんにぜひ読んでほしいと思います。
まずあらすじを紹介します。
ボスニア・ヘルツェゴヴィナの内戦で、大量虐殺の罪に問われたラドヴァン・カラジッチ。 じつは彼は三島由紀夫の愛読者だった──。この事実を知った女子大生・橘アカネは、三島 文学の本質を探るため、虐殺の地へと赴く。一方、アカネのかつての恋人・鷲見恭一朗は、 ある右翼結社の代表と知り合ったことから三島へと接近する。それぞれのアプローチが交錯 するとき、現代日本の姿と三島文学の本質が浮かび上がる! 三島論でデビューした著者が、 没後45年に迫る新たな三島由紀夫像。
瀬尾 すでにおもしろそうです。
今井 まずは、私とこの本の出会いからお話します。
私がこの本を読んだのは、2016年の4月。出版されたのが2015年の11月なので、少し経った頃です。私は大学院生で、研究室でぼーっとしたりおしゃべりしたりたまに研究のようなことをしたりしていました。ある日、同じ研究室にいるとにかく本をよく読む先輩二人から、興奮冷めやらぬ様子で「絶対に読んだ方がいい」と言われて借りたのがこの本を知るきっかけです。二人はこの本について「文学界の事件」「大風が吹いた」「精神的過呼吸になった」等と口々に言っていましたが、私自身も一晩で一気に読み干して、二人が言っていたことが決して誇張ではないことがわかり、読後、すごい体験をしてしまった!と震えました。
内容ももちろん面白いですが、物語の構造が独特というか、鮮やかな技法で「小説」の概念を再構築しているように感じました。小説を通して新たに小説を発明する、「小説」の概念工学実践と言えるのではないかと思います。
––––私の思う哲学ポイントは二つです。
🦌哲学ポイント🦌
・小説を通して「小説」概念の再解釈を行なっている点
・読後、作者が行なった概念工学について読者が議論できる点
瀬尾 筆者の三島由紀夫研究がミステリー小説の形に昇華されるというプロセスが、とても気になります。
アメリカと、多様な「強さ」の肯定:江藤淳『アメリカと私』
山本 その流れで、私も保守思想家の江藤淳『アメリカと私』を紹介します。
『アメリカと私』は、29歳の江藤がプリンストン大学に二年間滞在しながら執筆したエッセイです。江藤は、憧れの作家も同じくこの大学を歩いたものの、自分は彼らと違った肌を持ち違った宗教を信じることや、自分と彼らが違った倫理と生活態度のもと生きるといった、そのような違った文化において自分がアメリカに居るという現実を強く認識していました。本書ではいろいろな形でそれらが現れています。
文章からは1960年代のリアリティを生々しく感じることができます。また、その当時どのように彼が国家を見ていたのかを窺い知ることができる点をわたしは興味深く読みました。例えば、江藤が滞在している頃のアメリカではミシシッピ大学暴動が起こります。江藤はその出来事を報道越しに目撃しながら、白人から黒人に対する差別だけではなく、アングロサクソン系からケルトやラテン、スラヴ、ユダヤ、諸人種の東洋人への差別の存在にも言及します。大学の中で起こった相互排斥は、合衆国を構成する具体的な権力である州政府の力が垣間見える瞬間であり、江藤は州が連邦から分離するほど強い遠心力を持っているという印象を述べています。
江頭はアメリカのみならず日本の文化についても言及し、日本に滞在する外国人についても言及します。『「親日家」はひょっとして、深く誰よりも日本を憎んでいる外国人のことであるかもしれない』と語る江藤は、彼ら(外国人)は日本と彼らのの間にある超え難い距離に耐えることを求められているとして、アメリカと日本とではそこに暮らす外国人の受け入れる土壌には明らかな違いがあるとしている点を指摘します。
また江藤は「強者の勝利」といった力によるアメリカ的正義を、理想的ではないものの「必ずしも不愉快ではない」というふうに述べているところも面白いなと感じました。その表現は一見おかしなものに見えますが、江藤はアメリカの苛酷な生活にしっくりくる場面もあるとして以下のように書いていました。
日本の社会にはまりこんでいるかぎり、私は、自分に幸福に暮して行くためのなにかが決定的に欠けていることを、いつも感じつづけていなければならなかった。それは、日本の社会が不幸で、米国の社会が幸福だということではない。むしろ、日本の社会は、米国の社会にくらべれば、いろいろな点で温かさや余裕をとどめているように見えた。
問題は、そういう幸福な日本の社会が私のなにかを弾きかえし、冷酷にギスギスした米国の社会に、私のある部分を受けいれるものがあるということである。
たとえば、ここでは、いくらむきになって勉強しても、私はそれにてれる必要がなかった。孤独であることは、ここでは「悪」ではなくて、強さのしるしとされる。淋しい人間が周囲にいくらでもいる以上、淋しさは常態であって、特別な病気ではないからである。(江藤 2007, 147)
この一冊の中で、私はこの文章に最も共感しました。温かいはずの日本において同時に「弾かれる経験」をするといった江藤の言葉は、わたしが感じたアメリカに対する開放感を代弁する言葉だと感じます。江藤の生きたアメリカのように、ストイックに過ごしながら孤独であっても構わないと、自信を持って行動できる環境のことです。逆に、日本で生きる自分がストイックさと寂しさを混同してしまうのはなぜなのだろうとも思っています。
🐧哲学ポイント🐧
「弾かれる経験」とは何か? 孤独とストイックの関係とは何か?
瀬尾 たしかに、自律的でいるという感覚はアメリカを旅行をしているときに感じますね。あとアメリカは関西っぽい気安さもある気もします(笑)。街を歩いていて色々な人に話しかけられる。
難波 うーむ。「日本から弾かれる経験」が全然分からないですね。でもとりわけ保守思想家はアメリカ的な力への憧れ、その風通しの良さを発見する感覚に優れていると感じます。例えば保守思想家の西部邁もアメリカを批判しつつ、「日本から弾かれる経験」を繰り返し書いていたようにも感じます。右翼的思想の態度は実のところあくまでも独立独歩であり、実は大衆と結びつくことができない。にも関わらず保守である限り結びつかなければならない。左翼的思想の態度は実のところあくまでも連帯であり、実は大衆と結びついてしまう。にも関わらず革新であるかぎり結びついてはいけない。といった交差を感じますね。
物語をつくることで人間を理解する:K・M・ワイランド『キャラクターからつくる物語創作再入門』
難波 自分は物語創作本、K・M・ワイランド『キャラクターからつくる物語創作再入門』を取り上げます。この本で紹介されているのは「キャラクターアーク」(登場人物の変化の軌跡)から魅力的な物語を作り出す方法です。
『トイ・ストーリー』『スターウォーズ』を始めとする名作を「キャラクターアーク」から分析するステップとキャラクタの「信じ込んでいる嘘」を描く、「NEED」と「WANT」を書き出す、などの実践的な指南で構成されていて、これを頼りに物語を書いていけば人を惹きつける物語が書ける、と感じて実際に物語を書くときに参考にする軸の一つになっています。
『トイ・ストーリー』に感動するとき、私たちは何に心動かされているのか。それを考えることは、私たちが世界に「こうあって欲しい」と望むことは何かを明らかにすることだと思います。哲学が世界をより深く理解しようとする試みなら、物語は格好の分析対象で、なぜならそこに私たちの世界観が反映されているからです。
🪼哲学ポイント🪼
物語を分析し、書く技法とは、世界と人間に対して持つ私たちの期待と理解のシステムを操作し、変容する技法にもなりうるのではないか
今井 キャラクターアークという概念はおもしろいと思いました。小物や動作や視線や服装の変化といった、言葉以外に現れるものからアークを描くよさがありますよね。
瀬尾 キャラクターがアークする映画は面白いのですが、一方でタルコフスキー作品のように、キャラクターが殆どアークしない映画もまた気になります。観る側が変化しているのかもしれないですね。
難波 キャラクターがアークしない物語はオーディエンスの関心を引き続けることが難しそうです。そのため、アークしないと難しい作品になっていくイメージもありますね。
瀬尾 最近のA24作品を見ていると、映画の語法が変化してきたと感じます。キャラクタのアークがありながら、その変化があまり一般的でない。物語をとおしてラディカルな主張が行われている印象があります。タルコフスキーとトイ・ストーリーを足し合わせたような鑑賞後感を持つシナリオがたまにあります。
難波 なるほど。
大島 キャラクターアークからつくる、と書いていますが、物語とキャラクタはどちらが先に考えられるんすかね?
難波 自分がつくるときは交互に制作していく印象がありますね。自分の言いたいことがあって、現実の人やフィクションからピースが集まってできた気になるキャラクタの設定があり、その両方がいい感じに組み合わさるときに物語が動き出す印象があります。
接続と切断のバランス:町田洋『日食ステレオサウンド』
大島 町田洋『日食ステレオサウンド』という漫画作品を紹介します。これは、「44年前に1冊だけ名作を残したきり、人との関わりを絶っていた小説家と、彼に出会った絵描きの青年を描いた」読み切り作品です。
物語の概要は次になります。
人との関わりと44年前から断ち切ったおじいさんの家に、ペンキ塗りの仕事としてくる青年。やり取りは秘書としてい たのでその作家本人とは会ったことがなかった。
その青年は良くも悪くも人に悪意をもたない(もしくは興味がない)人間。ある日仕事中にその作家おじいさんに話しかけられる。ペンキの色で文句を言われたが特に何も感じずに帰る。あとになって仕事仲間からその豪邸に住んでいる人がす ごい作家だと知るが特に深い感想はもたない。
おじいさんは対人恐怖症でそれには理由があり、秘書とある契約を交わしたのことで、名作を作ることは出来るが人の 悪意が透けてみえるようになってしまったのである。ある言葉を言えばその呪いは解けるのだが44年間それは訪れず。
ひょんなことから、ペンキ塗りの青年と作家のおじいさん自体は45年ぶりとなる日食をみる。こうなる前に仲間と一緒 に見た日食のことを思い出し、その忘れてた想い出を抱きながら「人を愛したい」といって泣くおじいさんとともにその呪いと秘書は消える。
どこからか流れてきたフェスの音楽とともに踊りだすおじいさんと青年。
この作品を読んでいて3つの問いが浮かびました。
🐿️哲学ポイント🐿️
・対話ってなんだろう?
・青年の、立場に関係なく接することの出来るバランス感覚とは何なのだろう?
・おじいさんが本当に大切にしたかったことって?
どれもに共通しているのは、人との関わりにおける接続と切断のバランスはどうあるべきなのだろう、という問いかもしれません。
この作品を読むと、存在とどう向き合うかを考えます。人とこれくらいラフに関わりたいかも。自分は常に人との距離のことを考えていて、対等で有りたいと思う時、価値観や立場での上下関係を切り離しつつ、互いに対する気遣いをもちたいと感じます。その気遣いが他者の管理にならないようにするという難しさがある……総じて、愛って大切、だな、という思いになっていきます。
瀬尾 舞台設定に優れていると感じました。先程の話で言えば、キャラクターアークを可能にさせ、人との距離感を考えるための舞台設定をどう用意するのかを考えられるな、と思いました。
難波 舞台設定の妙がありますね。SFというよりファンタジックな作品で、ファンタジーの価値を感じました。モンスターや魔法を描くことでしか、描けない現実があると思います。そうした現実が描かれているんじゃないかな、と感じました。
今井 ペンキの少年もある意味でこの世ならざる存在ですね。
大島 ここで秘書がそんな青年のことをちゃんと「異常ね」と提言しているのが好印象でした。
今井 悪意が見える、ということは人を愛することにおいてどれほど苦しいのかな、と疑問に思いました。それほど苦しくないんじゃないんだろうか。
大島 当事者じゃなくてもSNSで悪意を感じると嫌になってしまう、という人をよく見かける気がします。その気持は分かるようで、なぜそうなるのだろうと疑問に思っています。また、別の問いですが、関わりを持たないことと興味を持たないことは全然違うのでは、と思っていて、青年はどちらなのだろうか、と気になりますね。
今回の勝者は……?
どれも話が盛り上がったので、みんな勝ちということにしてしまいました。
みなさんも会社メンバーや仲間でビブリオバトル、いかがでしょうか。お読みくださりありがとうございました。
参考文献
江藤淳. 2007. 『アメリカと私』講談社.
ハル・クルック. 2021. 『改訂版 ハウ・トゥ・インプロヴァイズ––––アドリブの画期的な練習法』佐藤研司監修・愛川篤人訳. エー・ティー・エヌ.
町田洋. 2023. 『日食ステレオサウンド』講談社.
三輪太郎. 2015. 『憂国者たち』 講談社.
K・M・ワイランド. 2019. 『キャラクターからつくる物語創作再入門––––「キャラクターアーク」で読者の心をつかむ』シカ・マッケンジー訳. フィルムアート社.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
