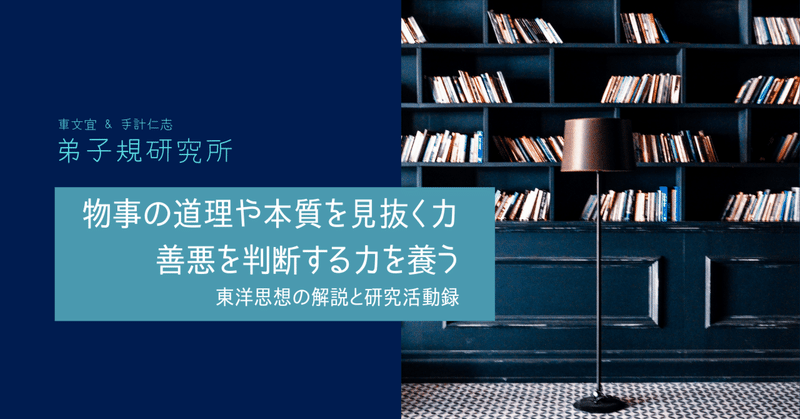
徳を積むとはなにか?
勉強と学習の違い
幼い頃に「なんで勉強しなきゃいけないの?」と思ったり、親に尋ねたことがある人も多いと思います。この「勉強」という言葉、実は「気の進まないことを無理に励むこと」という意味なんです。ではみずから行う勉強は何という?それは「学習」です。勉強と学習、あまり使い分けていないかも知れませんが、その意味は大きく異なります。そして「学」と「習」にはそれぞれ意味があります。
学:学問を自ら求めること
習:習慣化し熟達するまで繰り返し実践すること
知らないことやわからないこと、面白いと思うことに対しての好奇心が、学びの原動力です。そして物事の道理や本質をしっかりと学んだ上で、実践を始めて少しずつ習慣化し、やがて無意識でも自然とできるようになるまでが学習の基本プロセスです。無理に強いられるもの、言い換えれば自発的に求める心がないもの(勉強)は、本来の学びではないし実践も続きません。
さらに古い東洋の教えである『弟子規』では、順番を逆にして「習学」と表現しています。なぜでしょうか?実は、私たちが生きていく上で必要な基礎教育は、すべて習→学の順番で行われているからです。生まれた子は、本能以外のことは親を真似して学びます。始めは道理や本質などわからないままです。その後、人格が形成される15歳くらいまでに、後から経典などを通じてその意味や理論を学ぶのです。
『弟子規』は3歳までの基礎教育といわれており、理論ではなく実践として、両親や祖父母、親戚たちがお手本として子供に示すべき行動内容が示されています。
『弟子規』の最初には何が書いてある?
現代の書籍のページをめくると最初は文字通り「はじめに」とあり、本論へ誘う文章や、ときには購買意欲を煽る文章が書いていたりします。一方で古い東洋の経典では最初に要旨が書いてあります。『弟子規』も同様です。
弟子規 聖人訓 弟子(学生)規(規範)は聖人賢者の教訓。(つまり規範は正道であり、邪道ではない)
首孝弟 次謹信 先ず父母に孝行をつくし、兄など年長者によくつかえる。 次に言動を慎み、信用を得る。
泛愛衆 而親仁 人をひろく愛し、仁徳のある人に親しく学ぶ 。
有余力 則学文 さらに力があれば、文学をすすめる。
『弟子規』の出だしは、泛愛衆までが習(両親を真似して実践する)、その後が学(他者や教師から学ぶ)で構成されています。習を担う両親と学を担う教師には密接な協力関係が求められます。家と学校が連動することで、子供は高い効率の「習学」を進めることができます。
正道と邪道
ここでいう正道の定義は易経に見ることができます。
蒙以養正 聖功也(子供を純正で無邪な品徳に育むことは、神聖な功業)
もともと「正」とは以下の意味です(詳しくは以前のnoteもご参考)。
①子供が一生ずっと純粋で居続ける、天真爛漫で目がキラキラした状態を保つよう親愛・慈愛をもって育むこと
②子供が純粋で無邪気な品徳を、親や兄弟へ、社会へ、そしてすべてモノとの関係性に拡大していくよう親愛・慈愛をもって育むこと
正道か邪道かの違いは、子が成長した後に社会に対して有益な影響力を発揮するか、有害な影響をもたらすかです。『弟子規』では、社会において正しく具体的な教育について、簡単な漢字を用いながらとても深い内容を表しています。さらには、親と教師が子の成長ために重要な責任を果たしていく仕組みも設計してあります。
「積む」という実践
東洋思想の教育において常に中心にある視点は「社会への影響力」です。上記①②のような子供が成長すれば、おのずと人のため大衆のために考え行動します。それは社会への貢献となり、また社会課題への気づきにもつながります。
だからといって、自分を疎かにしたり我慢する必要はありません。前回のnote「なぜ徳が必要なのか?」に書いたように、徳を積むと自分自身が「自由自在」になれるというメリットがあります。私たち自身の心や精神を豊かにするために、この社会という場を借りて学び、実践をするのです。
徳を積むとは、人々のため、社会のために本分を立て、学び、実践することにより、自身の心(内境)をアップグレードしていくことです。
車文宜&手計仁志
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
