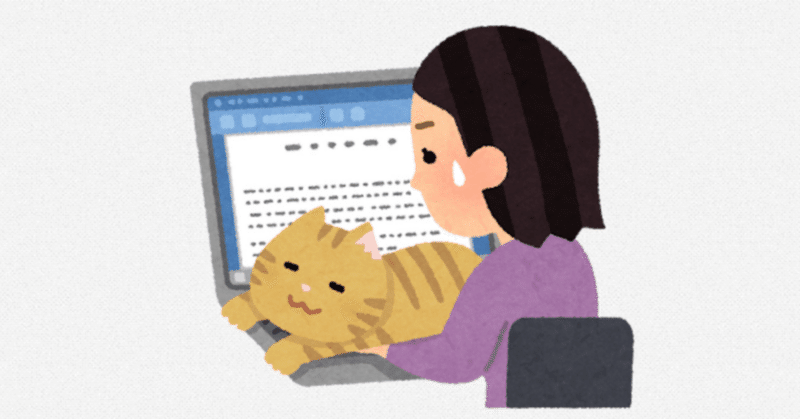
仕事の進め方
新人さん、ベテランさんも含めて、仕事の進め方を考えてみます。ここでは管理職さんではなく、最終的に現場の作業者を対象にします。
予定
今日もがんばるぞー!と言っても、何をするのかはっきりしていないと効率が悪いです。なるべく具体的な方が良いですが、その時々で依頼された仕事をこなす場合もあります。
予定は前日に決めておきます。仕事当日の朝にチェックしてやることを決める、という人もいますが、それだとやらなきゃいけないことを忘れてしまいます。毎日、毎週やることがあれば、そのリストを毎日作っておきます。それ以外の仕事がある場合はそこに追加します。スケジュール帳スタイルでも良いですが、常に見えるか、1日の間で何回も確認できる位置にあると良いです。予定は忘れるものです。なので紙に書いておいたり、コンピュータに記録して確認することで必要な仕事を思い出すようにします。忘れません!というのは実際に無理があります。忘れることを受け入れて、思い出すきっかけを作るようにします。
仕事量を把握する
1日の時間は24時間で、その中で仕事に使える時間はもっと少なくなります。法律の制限もあります。現実にサービス残業などをやっている人もいますが、それでも終わらない人は要注意です。悪い言い方をすれば、自ら奴隷になっています。
自分の仕事がどれくらいあるのかを理解するには、細かい仕事や雑用と呼ぶものも含めて全てを書き出してみます。とんでもなく多くても、書ききれないことはありません。ただし同じ種類の仕事、例えば申請書類の確認数が多くて大変というのは分かります。週に一回、月に一回のような仕事もあります。
仕事を把握することは、いつ、何をしたら良いのかを整理することにも繋がります。あまりにも忙しい場合、やらなきゃいけないことを忘れたりもします。改めてスケジュールを立てることができます。
とても仕事が多くてこなせないことも理解できます。その中で、何を他の人に任せて、何をやらなくても良いか、などの整理もできますし、具体的に相談することもできます。何をしているのかを具体的に把握していないと、誰かに手伝ってもらうこともできません。出来ることなら、そいういうコントロールは管理職の人がやったら良いです。末端の作業員は言われたら何でもやらなきゃいけないと考える人もいます。できません!と断る人もいます。断った分は、断れない人にお願いしてしまうと悪循環になります。
新しい作業
いつもの安定した作業なら、いつも通りにやれば良いです。忙しいのに無理に改善する必要もありません。暇があればやっても良いです。
新しい作業は突然やってきます。ここでは通常の仕事にトラブルがあり、その対策として何かを追加で始める場合を考えます。仕事で失敗した時には「次は注意します」はほぼ効果がありません。人は忘れてしまうからです。そのため具体的に何かをやることが良いのですが、その時の注意です。
こういう工程を追加する、このやり方をあのやり方に変える、ここを確認する、とかやりますが、その方法が本当にできるのか、効果があるのか、を前もって確認します。考えた方法をすぐに導入したい、アレコレ言われているからすぐに何かやらなきゃいけない、というのも分かります。しかし実際にやってみるとうまく出来なかったり、あまり効果がない場合もあります。これはレアケースではありません。そういう対策をやったけど、実際にはほとんど改善されていないことはよくあります。だからと言って、完璧な対策を見つけることは困難です。現実的に実行できて、十分な効果が認められれば良いです。
実際にやってみて、効果はあるか、やりやすいか、作業時間やコストは許容できるか、を検討します。出来るなら、追加コストや時間が発生しない方が良いです。あまり大きな追加コストは導入までに時間がかかったり、予算を確保できなかったり、利益が大きく減ったりします。そもそもその作業自体をやる必要がない、やらなくて済むなら、その作業を廃止するのが良いです。作業自体をやらなければ失敗もありませんし、コストも時間もかかりません。そんな仕事があるわけない、と思う人もいるかもしれませんが、調べてみるとそういう仕事はいくつかあります。実際に作業をなくす時は、他の作業にも影響がないかなども調べなければなりませんが効果は絶大です。ただし、インパクトは小さいです。目立ちたいならあまりオススメしません。
良く考えない作業のススメ
私は「良く考えない作業」推進派です。作業をする時は考えないでするほど間違いが無く、効率が良いです。メチャクチャに仕事をしていいわけじゃありません。ほとんど考えることなく作業出来る環境、手順を構築しておきます。このときは良く考えて、手順を作成し、作業が適切に実施出来るのか、結果は良好かを検証するのです。作成する作業手順は、なるべく考えないで簡単な作業になるようにします。そういうことが作業品質のバラツキを減らします。良く考えて作業をする場合、その製品品質はバラツキがでやすくなります。何か失敗するたびに「良く考えて仕事を進めろ!」というのはやめるべきです。良く考えるのは作業方法を決める時。実際の作業では考えないで進められるような作業方法が良いのです。
現状を打開できるか
現状では作業手順もなく、やりながら覚える環境の場合、手順書を作ろうとしても同意を得られない可能性はあります。今まで行ってきたことを組織としても個人としても変えることに不安があります。それなら今までのやり方で良いと言うのです。それなら個人レベルで実施しても差し支えないことを始めたら良いです。個人で任された仕事は自分で手順を決めて文書化してみます。そうしておけば、仕事を教えたり、引き継いだりする時は手順書を見ながら教えることはできるし、その後も分からないことは手順書を見て作業をすることができます。
手順書を作ると言っても簡単じゃないし、内容が不十分なら手順書を見ても作業手順がわからず、使われなくなります。なので他にもいろいろとやることはあります。
仕事をしっかりやれないことが、不要な叱責やイジメにも繋がります。その時々で良く考えて作業をする人は良さそうに見えますが、良く考えた結果が適切なものとは限りません。事前に十分検討を行なって、適切に作業ができる手順を決めておくことが大事だと考えています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
