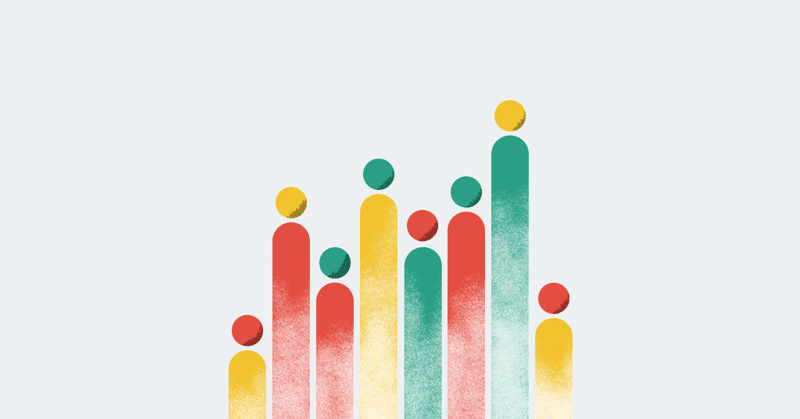
Photo by
4hintaro
#1561 一斉授業は「協働」ではなく「競争」を志向する
教師が学習をコントロールする「一斉授業」では,子どもたちの「協働」ではなく,「競争」を志向してしまう。
それが「教師の意図に反していても」である。
なぜなら,一斉授業においては,子どもたちが「早押しクイズ」のように挙手をしたり,大きな声で我先に正解を発表したり,グループ活動で一人が目立ったりするからだ。
これは,教師が学習をコントロールしているからであり,かつ「正解主義」に陥っているからである。
これでは,学級内における「協働」は遠のき,「競争」が渦巻いてしまう。
これを打破するためには,教師が子どもたちの学習をコントロールする「一斉授業」を克服することが必要なのである。
教師が「グループワーク」「グループでの話合い」「グループ活動」を意図的に組織したとしても,それは「協働」に値しない。
逆にそれは「競争」に向かってしまうのだ。
この構造に自覚的になり,子どもたちが自然に「協働」するように,授業を工夫することが求められる。
教師は「協働」のための仕組みを作っていくのだ。
今回の記事は以上である。
では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
