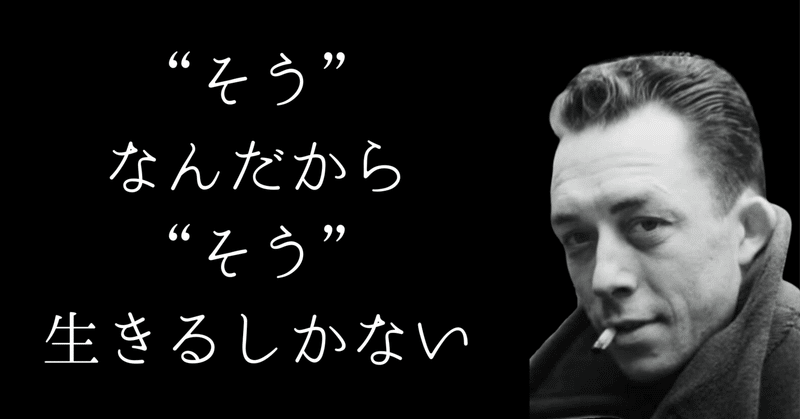
メインチャンネル『シーシュポスの神話』の書き出し文
◻︎提供スポンサー
◻︎本文
アルベール・カミュはフランスの小説家、劇作家、哲学者です *1
フランス出身と言っても、ルーツはフランス領だったアルジェリアにあり、彼の作品には、アルジェリアにおける太陽と海のイメージが多く用いられています。代表作は『ペスト』『異邦人』『カリギュラ』など。1957年には、当時史上二番目の若さでノーベル文学賞を受賞しています *2
カミュの生涯はまさに「不条理」を感じさせるものでした。生まれた家は裕福とは言えず、父親は移民系の農業従事者で、母親には聴覚障害があり、家の中で文字の読み書きができる人間はいませんでした。だから、彼の幼少期は文学よりも自然と戯れる毎日だった。
とはいえ、彼には才能がありました。家の家計状況的に高校進学などはとてもできなかったのですが、小学校の教諭であったルイ=ジェルマンがカミュの才能を見抜き、奨学金を受けて高校に進むことを家族に説得してくれたのです *3
高校ではサッカーをはじめ、学業も優秀で順調な生活を送ります。しかし17歳のとき結核を発症し、喀血してしまいます。26歳、第二次世界大戦が始まると、彼は徴兵を志願しますが、結核を理由にこれを拒否されてしまいます。このように、彼は結核と生涯付き合っていくことになりました。
徴兵を拒否されたカミュは、その後徹底した平和主義を主張します。検閲により何度も出版社への出入りを禁止されますが、それでも彼は主張を曲げることをしませんでした。ちなみに、今回紹介する『シーシュポスの神話』が刊行されたのは世界大戦開始の2年後である1942年です。この年、彼は結核の悪化によって療養生活を余儀なくされていました。
彼の人生は1960年に交通事故によって急に閉じられます。享年47歳。最後まで「不条理」な性質を持つ人生だったと言えるでしょう。
カミュは「不条理」や「反抗」というテーマのもと、当時の時代を席巻していたイデオロギーと戦い続けました。その中でも「マルクス主義」と「実存主義」との戦いは、非常に熾烈なものでした。特に実存主義者の代表格であるサルトルとの論争は激しく「カミュ=サルトル論争」として、現在でも研究の対象になっています。
彼は一体何と戦っていたのでしょうか。紹介がひと段落したところで、『シーシュポスの神話』で語られる思想について検討していきましょう *4
『シーシュポスの神話』では「不条理との向き合い方」が検討されます。
カミュは人生を「不条理」なものであると捉えました。
私たちは訳もわからず人生という舞台に投げ込まれます。RPGゲームなどとは違い、そこに明確な目的はありません。クリア目標もないし、用意されたストーリーもない。しかも、それらがないことすら説明してもらえないのです。私たちは偶然的にただそこに現れただけであって、そういう意味で世界と決定的に断絶している。このような状況を、カミュは「不条理」と表現しました *5
近代以前には、このような「不条理」は顕在化していませんでした。人々の多くはそれぞれの神を信じ、神が定めた「意味」を生きることで擬似的に世界と繋がりを持っていたのです。
しかし近代以降、科学の力によって神の存在が遠ざけられます。それにより、人々は別の文脈から意味を見つけなくてはいけなくなった。その瞬間、カミュのいう「不条理」が顕在化し、彼らは生きる意味を見つけるための苦しい戦いを始めるのです。サルトルなどは、この苦しみを「自由の刑」と名付けました。
カミュの時代、実存主義という思想がヨーロッパを席巻していました。キルケゴールやヤスパース、サルトルやメルロ=ポンティといった論者は、世界における真実や、存在における本質よりも前に、今実際にここにある存在に目を向けて哲学をする必要性を説きます。特にサルトルの「実存は本質に先立つ」という言葉は有名ですね。存在には本質がない。つまり、私という存在においても、私という存在に先立って設定されている意味のようなものは存在しないというわけです。
カミュもこの主張に同意します。しかし、ここから先の論理展開において、彼は実存主義者(特にサルトル)と対立するのです。
サルトルは、本質的に意味のない人生に対してそれでも意味を付与することを目指します。彼は「自由の刑」に処された人間は、他者からの拘束ではなく、むしろ自ら自身を拘束することにより(アンガージュマン)内側から生きる意味を設定・受諾することができると考えました。そしてその思想は社会参加・政治参加という方向に進み、彼はやがてマルクス主義に傾倒していくことになります。
カミュは、サルトルの結論を認めません。
サルトルは「目的は手段を正当化する」とし、共産主義革命における暴力を肯定していました。カミュはこれに対して「目的によって手段を正当化した瞬間から堕落が始まる」と反論し、革命におけるいかなる暴力も否定すべきという立場を取ります。
それだけではありません。カミュは、サルトルをはじめとした実存主義者が行う「意味のない人生にそれでも意味を付与する」という行為、それ自体を批判するのです。
存在に先立った本質はありえない *6
だから、私たちの生に特別な意味はない。ある種、意味がないのが世界の摂理である。実存主義者がやろうとしているのは摂理に背く行為である。そのような行為、つまり世界との断絶を無理やり埋めようとする行為は、世界との断絶をより広げる結果に繋がってしまう。したがって、実存主義的アプローチは人間の苦痛を増幅させてしまうものである。
彼は実存主義者の主張を「不条理」に向き合っていないという意味で「理性の放棄」であり「哲学上の自殺」であると断罪します *7
確かに言っていることはわかるような気もしますが、では、私たちは「不条理」とどう向き合えば良いのでしょうか。
『シーシュポスの神話』では「不条理」に対する向き合い方の中で有力だと思われる幾つかの方法が検討されます。
第一に「自殺」はどうか。
人生に全く意味がないのならば、極論自殺しても良いはずです。むしろ「不条理」に対する向き合い方としては「自殺」は合理的な判断なのではないでしょうか。
しかしカミュは違うと言います。
彼は生きている人間が自殺に至るとき、そこに筋の通った”貫かれた”論理があるかを検討し、そのようなものは存在できないことを明らかにします。よって「自殺」という判断は思考の放棄である *8
カミュは人間に備わった「理性」というものを重視した人ですから「理性」を捨て去るような選択肢を認めませんでした。だから「自殺」という不条理に対する向き合い方は間違っている。
では第二に「希望」はどうでしょうか。
これについては先に述べた実存主義に対する批判が当てはまりますね。本来的に意味がない人生には、それに先立つ希望も存在していません。だから、希望を意図的に付与するという試みは、世界の構造に対して間違った対応の仕方をしていると言え、そうした行為はむしろ世界との対立を強めます。それでも希望に縋ろうとする姿勢は、宗教的な信仰と何ら違いのないものであり、これは全く理性的な行いではない。
このようにして「実存主義」も「宗教」も不条理に対する向き合い方として適切ではないと斥けられます。
こうなってくると、もはやどうしたら良いかわからなくなってきます。まぁ、このような「どうしたら良いか全くわからない様」が、まさにカミュのいう「不条理」なんですけどね。
では、私たちは不条理に対して全くの無力なのでしょうか。不条理に対して向き合う姿勢は皆無なのでしょうか。これに対してカミュは「一つだけ方法がある」と言います。
それが「不条理を受容すること」です。
世界は不条理であり、私はその中に投げ込まれた偶然的な存在である。このことを丸ごと認め、それを前提に生きていくこと。これがカミュが考える不条理に対する向き合い方です。
そして、その生き方の理想像として提示されるのが『シーシュポスの神話』なのです。
シーシュポスとは、ギリシア神話に登場する人物です。彼はギリシア中部のテッサリアを治める王、アイオロスの息子として生まれます。その後、兄弟のサルモーネウスとの後継者争いのいざこざによってシーシュポスは神々の怒りを買ってしまいました。神は彼をタルタロス(奈落)に連行するように、死の神であるタナトスに命じます。しかし、シーシュポスはタナトスを言葉巧みに騙し、タナトスに手錠をかけ、軟禁してしまいます。タナトスは死を司る神ですから、この出来事が原因で人間はどんな状態になっても死ぬことができなくなってしまいました。結果的にゼウスとヘラの息子であるアレスがタナトスを助け、シーシュポスを捉えることになるのですが、二度も神からの怒りを買った彼は罰を受けることになりました。その罰とは「無限の労苦」です。彼は巨大な岩を大きな山の山頂まで運ぶことを命じられます。山頂付近まで岩を運ぶと、岩はまた山の麓まで転がり落ちていき、それを再度山頂まで運び始めます。彼は、この”労働”を無限に行わなければならなかったのです *9
日本においての「賽の河原」と同様に、一般的にこのエピソードはネガティブな意味で捉えられます。しかし、カミュはそう考えません。
シーシュポスは、彼の不条理な人生を受容していたのではないか。無限の労苦を与えられて尚「そうか、それならそれで全て良し」と、不条理という事実を真っ向から受け止めていたのではないか。そして、不条理を受容することこそが幸福であり、彼は幸福な内的感覚を持った上で無限の労苦を過ごしていたのではないか。
この寓話と比較することは難しいですが、我々の人生にも、極端にいえば「無限の労苦」のような性質があります。わけもわからず偶然的に世界に投げ込まれた我々は、基本的には繰り返しの毎日を過ごすことを強制されます。それはどこか閉鎖的で終わりの見えない連続です。まさにそのような状況を、カミュは「不条理」と呼ぶわけです。
そして、その不条理に対する正しい向き合い方は、その繰り返しの毎日を「ならばそれで良し」と受け入れることであり、それはすなわち、毎日を納得して”ただ生きていく”ことなのです。カミュは、そうした生き方こそ幸福なのだと主張しました。
ちなみに彼は、不条理に対するこうした姿勢のことを「反抗(ノン)」と表現します。『シーシュポスの神話』では、この反抗に対して詳しく触れてはいませんが、続く『反抗的人間』でその主張を明確に著しています。
ここでいう反抗とは、不条理に対する直接的な反抗ではありません。仮に私たちが不条理を受容し、それを納得して”ただ生きた”場合、その精神を揺るがすような外的刺激がひっきりなしにやってきます。一番わかりやすいのは、実存主義的な「希望」ですね。こうした、自分の覚悟を揺るがすような外的刺激に対する姿勢が「反抗(ノン)」なのです。
先に触れたとおり、カミュは当時圧倒的な力を持っていた実存主義やマルクス主義、あるいはそれに伴った革命の機運に対して、徹底的に「ノン」の姿勢を貫いていました。まさに彼こそがシーシュポスの生き方を体現していたのかもしれません。
また、カミュが著した他の著作には必ず「不条理への向き合い方」というテーマが込められています。
『異邦人』の主人公であるムルソーは、不条理な世界から「異邦人」として弾かれた人生を最後まで自分に正直に生き抜き、(散々な最後だったのにも関わらず)圧倒的な幸福感を感じながら死んでいきました。
『ペスト』の主人公であるリウーは、隔離された不条理な街で最後まで諦めずに働き、最後にはほとんど全てを失ってしまったのにも関わらず、その事実を書物に書き残すことにしました。
それは彼の友人であるタルーが、彼と同じようにペストに対して”ただ”戦い、ペストによって命を落とす間際に「ありがとう」「全てはこれでよし」と言ったこと、つまり不条理に対する反抗の姿勢を後世に残したかったという動機からだったと考えられます。
哲学に詳しい方は、カミュのこの主張がニーチェの永劫回帰とそれに対する超人の概念に似ていることに気づくかもしれません。
自分の人生が無限に繰り返されるとしたとき、それでもその事実を「ならばやったるか」と強く受容する姿勢。まさにそれは不条理に対する”反抗”です。
哲学の世界では、それまで「人生の意味」が長く論じられてきました。人々はときに哲学的に人生の意味を考え、またときに宗教的に運命を信仰する。しかしカミュはそうではないと言います。本質的に意味がない人生において無理やり意味を見出そうとするのは、理性の行使ではなく、むしろ理性の放棄(哲学上の自殺)であると。
仮に人生に意味的なものが見出せるのだとしたら、それは自分の人生を振り返ったときのみであり *10
そういう意味で「生がなんであるか」は実際に生き続けてみないとわからない。
自身の不条理な状態を受け入れて、その生を生き続けることこそ、本当の理性の行使であると、カミュは考えるのですね。
彼が『シーシュポスの神話』あるいは『反抗的人間』で語った思想は時代的な要請によるものも大きかったのだと思われます。ですから、現代においてそのまま受容することは難しいかもしれません。しかし、彼が提示する不条理の性質は、私たちが生きる世界にも当てはまるものですし、その事実がある以上「反抗」という不条理に対する姿勢は、私たちの生になんらかのヒントを与える概念なのだと思います。
□注釈と引用
*1 カミュを「哲学者」と表現することには賛否があるかと思いますが、私はぜひ彼のことを「哲学者」と呼びたい。思想と実践という意味で、彼ほどの哲学者はそうそういないと思います。
*2 最年少の受賞者は1907年に41歳で受賞したイギリスの作家、ラドヤード・キプリング。
*3 ちなみに、カミュはこの時の恩をずっと忘れずに持ち続けており、ノーベル賞受賞の記念出版の際には「ルイ=ジェルマンへ」という賛辞を送っています。
*4 今回の動画における資料の中心は『シーシュポスの神話』ですが、追加して『反抗的人間』という書籍も参照しています。この本が手に入りづらくてですね、めちゃくちゃ困りました。(結果としては知り合いに貸してもらいました。本当に手元に欲しい本なので、誰か譲ってください・・・)
*5 シーシュポスの神話|アルベール・カミュ(清水徹 訳) 新潮文庫
ー幸福と理性への欲望が自分の中でうずくのを感じる。このようにして、人間的な呼びかけと世界の不当な沈黙とが対置される。そこから不条理が生まれるのだ。
*6 サルトルもこのことを強く主張しています。存在に先立った本質があり得るのは、世界を創造した神的な存在が実在する場合のみです。だから、無神論の立場を取った瞬間に「存在に先立つ本質」は成立不可能になります。
*7 シーシュポスの神話|アルベール・カミュ(清水徹 訳) 新潮文庫
ーここで、彼ら一連の実存哲学者たちのような態度を、哲学上の自殺と呼ばせていただこう。しかし、この呼び方は価値判断を含んでいない。これは、思考が思考自体を否定し、自己を乗り超えて、この否定を行うもの自体のなかへと向かおうとする動きを、便宜上こう名づけたまでにすぎない。
*8 カミュは自殺と同様に「人生には希望がある、意味がある」と考えることも思考の放棄であると言いました。厳しい・・・
*9 ちなみに、この罰を知った妻のメロペーは、あまりの恥ずかしさから姿を隠すようになったと残されています。これはBC2000年ごろ、おうし座のプレアデス星団の星が一つ消えたことを暗喩したエピソードだと言われています。
*10 もちろんその際の「意味」は、後付けで恣意的なものになります。
□参考文献
シーシュポスの神話 (新潮文庫) カミュ (著), 清水 徹 (翻訳)
異邦人 (新潮文庫) カミュ (著), 窪田 啓作 (翻訳)
ペスト (新潮文庫) カミュ (著), 宮崎 嶺雄 (翻訳)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
