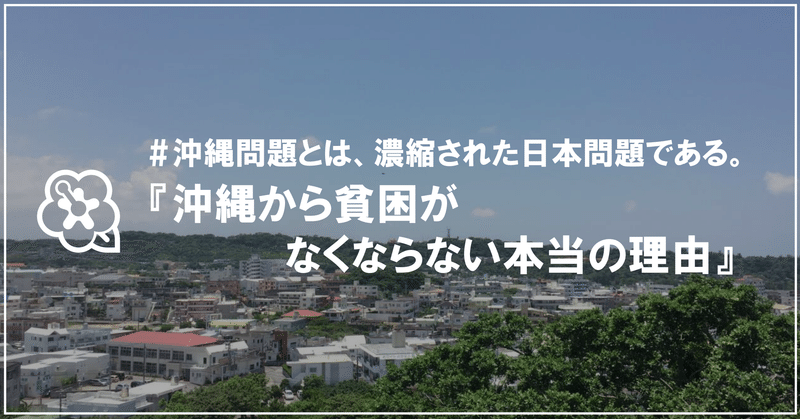
沖縄問題とは、濃縮された日本問題である。|『沖縄から貧困がなくならない本当の理由』樋口耕太郎
皆さん、こんにちは!社会問題と向き合う人のクラウドファンディング GoodMorning(CAMPFIREのグループ会社)ファンドレイジングプランナーのてっちゃんです。現在、沖縄に生きるすべての子どもたちが誰一人として見過ごされず、包摂される社会を実現するために、仲間と一緒に沖縄での事業の立ち上げに向けて、準備を進めています。
本日は、先月発売された『沖縄から貧困がなくならない本当の理由』をご紹介します。この本は沖縄大学の人文学部准教授の樋口耕太郎さんが、沖縄の貧困問題の経済的な要因と、その根本的な原因について、一つひとつ丁寧に、分かりやすく整理されている本です。
今回は、まだまだ勉強中のため未熟な文章かと思いますが、本書の紹介と感想を書き記していきたいと思います。皆さんと一緒に、沖縄の子ども・若者たちを取り巻く社会問題について考える、きっかけとなれば幸いです。
1. 貧困率「断トツ全国1位」の謎

沖縄経済は2012年以降「バブル超え」の絶好調であり、沖縄への観光客は年間で1,000万人を超え、ハワイへの年間の観光客数を超えています。一人当たりの県民所得は四年連続で上昇し、過去最高を更新し続けています。
一方で、沖縄の貧困に関連する問題は、数々のデータが存在し、いずれも47都道府県で最低水準の数値となっています。
子どもの貧困率(1位※全国平均の約2倍)
給食費未納率(1位)
一人当たりの県民所得(最下位)
非正規雇用率(1位)
失業率(2018年まで1位)
離職率(1位)
若年離職・失業率・高校・大学卒業後の無業率(1位)
高校・大学進学率(最下位)
高校中退率(1位)
10代婚姻率(1位)
10代の出産割合(1位※全国平均の約2倍)
離婚率(1位)
デキ婚率(1位)
シングルマザー世帯出現率(1位※全国平均の約2倍)
一人親世帯の子どもの貧困率(1位※約58.9%)
僕も昨年、沖縄を訪問しましたが、気候もそこで暮らす人々も本当に温かく、穏やかで、優しい地域でした。一方で、上記の問題に起因する、沖縄社会の自殺率や重犯罪、家庭内暴力などの問題は、全国でも他の地域を圧倒しています。なぜ「好景気」の中で貧困が生じ、「優しさ」の中で人が苦しむのか?という筆者の問いから、この本は始まります。
2. 経済的な要因と社会的な要因

沖縄の貧困問題の直接の原因は、労働者の所得が圧倒的に低いこと(労働者の平均収入は全国最低水準で、就労者の18%が年収100万円未満、47%が200万円未満)であり、その原因の一つが「非正規雇用の圧倒的な多さ」です。
沖縄県内の非正規雇用率は全国で最も高い43.1%であり、正規雇用の求人数は全体の約3割程度。有効求人倍率が1.0倍を超えていても、それは非正規雇用の求人が多いためであり、正規雇用倍率は0.58倍(全国の正規雇用倍率は1.21倍)しかありません。
この経済的な要因に、47都道府県の中でも非常に深刻である、デキ婚率や若年層の婚姻率や出産割合、離婚率、シングルマザー世帯出現率の高さなどの社会的な要因が加わることで、貧困は爆発的に顕在化すると筆者は述べています。
3. 沖縄は「貧困」に支えられている

上記で説明した沖縄の貧困問題は、水面下に沈んでいる巨大な社会構造の上に、少しだけ顔を表している氷山の一角に過ぎず、貧困の根本原因を探るためには、沖縄の見えない社会構造への理解が必要であると、筆者は述べています。
その上で、沖縄の貧困問題を生み出している沖縄の社会構造は、(1)昇進・昇級を望まない労働者、(2)定番商品を買い続ける消費者、(3)現状維持が最も利益を生む経営者、の三者の利害が合致することで成立し、その利害を強固に繋ぎ合わせているのが、現状維持を優先し、他人にNOと言えない、沖縄社会の人間関係であると述べています。
(1) 昇進・昇級を望まない労働者
「小中学校のときに、みださー(場を乱す人)と言われることを恐れて何もできないことが多かった。人より何か目立っている人、違うことをする人が仲間外れになりやすい」
「友人数人と食事にいったときに、自分一人だけみんなと違うものを食べようとしたときにみださーと呼ばれた。沖縄ではみださーと呼ばれる人は自己中だというレッテルを貼られる」
(『沖縄から貧困がなくならない本当の理由』沖縄大学の学生の声より)
貧困とは一義的に所得が低いことであり、所得が低いことのさらに一義な原因は、経営者が従業員に十分な賃金を払わないためです。しかし、沖縄の場合はそれ以上に、従業員が報酬を積極的に受け取らないという、驚くべき傾向があり、有能な人材が管理職になりたがらず、パートも正社員になりたがらない実態があるようです。
上記の沖縄大学の学生の声からも分かるように、責任のある立場に置かれて目立つことや、同僚に注意・指摘をしなければいけない役割になること、いつも一緒にお昼ご飯を食べている同僚と上下関係が生まれてしまうことは、これまでの人間関係が大きく崩れ、一気に周囲から孤立することを意味します。
そして、人間関係が緊密な「シマ社会」沖縄において、周囲への気遣いは何よりも重要であり、一旦人間関係がこじれると、周囲の人間関係を巻き込んで、一生の問題になり得ます。故に、人間関係に波風を立てないためには、現状維持が安全な選択肢であり、昇進や昇級を断ることには合理性が存在すると、筆者は述べています。
(2) 定番商品を買い続ける消費者
「ファッションも個性的なものより、一般的なものを選ぶときが多い。私は何か選択するときに、自分の好き嫌いや利益などと同時に、これを選択したら人にどう思われるかを考えてしまう」
「親や周囲がそうしているから、それに反するものは買えない。商品の内容や良し悪しは気にしないし、考えない」
(『沖縄から貧困がなくならない本当の理由』沖縄大学の学生の声より)
自己主張をすることが難しく、他人の感情を害さないように、細心の注意を払わなければならない沖縄社会では、商品よりもサービスよりも、ときには価格よりも、人間関係のバランスによって経済が動く、と筆者は述べています。
周囲から目立たないようにするための消費性向や、「ゆいまーる」と呼ばれる沖縄の互助的(ときには同調圧力的)な消費性向に反すれば、それが「出る杭」や「裏切り」となり、周囲との人間関係に非常に大きな支障をきたす可能性が非常に高くなります。そのため、沖縄では品質の良いもの、価値のあるもの、優れたサービスを顧客に提供しても、売り上げに繋がりにくく、付加価値の高い事業が収益を上げにくい実態があるようです。
このような環境下では、品質改善への重要性は低く、想像力は発揮されないため、開発力、革新力、サービス力が低下し、沖縄県外の「厳しい」顧客に訴求する商品やサービスを生み出すことは難しくなります。
そして、県外から「外貨」を稼ぐことができなければ、社会は消費を維持するために補助金に頼らざるを得なくなり、補助金を手にした瞬間から、事業家は付加価値を生み出す努力を止めてしまうため、それが更なる生産性の低下を招いている、と筆者は述べています。
(3) 現状維持が最も利益を生む経営者
商品の良し悪しに拘らず、昔ながらの定番商品を買い続けてくれる消費者は、沖縄の経営者にとって最高の存在です。そして、保守的な消費者が同じ物を買い続けてくれるということは、逆にどれだけ質の良いものを提供しても、評価されにくいということです。
故に、事業的な変化は少ないほど好ましく、現状維持が経済合理的であるため、現状を変えないことに全力を尽くすことが、経営者の責務になっているようです。
事業者は質の良いものを提供できず、また提供する意味もないため、安かろう悪かろうの商品が市場に溢れ、その結果、沖縄県の労働生産性はあらゆる産業で日本の最低水準です。そして、労働生産性の低い企業が利益を確保するためには、人件費を削るしかありません。そして、経営者にとって都合の良いことに、労働者は自ら適正な報酬を要求しません。そのため、低い人件費が企業利益の源泉となって、経営者を支えている実態がある、と筆者は述べています。
(4) 沖縄から貧困がなくならない本当の理由
上記の通り、沖縄の社会構造が貧困を生み出していると同時に、沖縄経済が貧困によって維持されている実態があるようです。
そのため、沖縄企業が無敵であるにも関わらず、なぜ貧困が生じているのか?という問い方自体が間違っていて、「沖縄の貧困(沖縄の低所得者層)」が沖縄企業を強固に支えており、沖縄の社会構造の中で悪意なく変化を止め、無意識のうちに足を引っ張り、個性を殺し、成長を避けることが「経済合理的」な判断とされているようです。
つまり「沖縄社会が貧困なのは貧困であることに合理性が存在する」ことこそが、沖縄から貧困がなくならない本当の理由であり、世の中の問題の多くは非合理によって生じるのではなく、現象の裏側に「そうあるべき」事情が存在する、と筆者は述べています。
4. まとめー沖縄問題とは、濃縮された日本問題である。ー
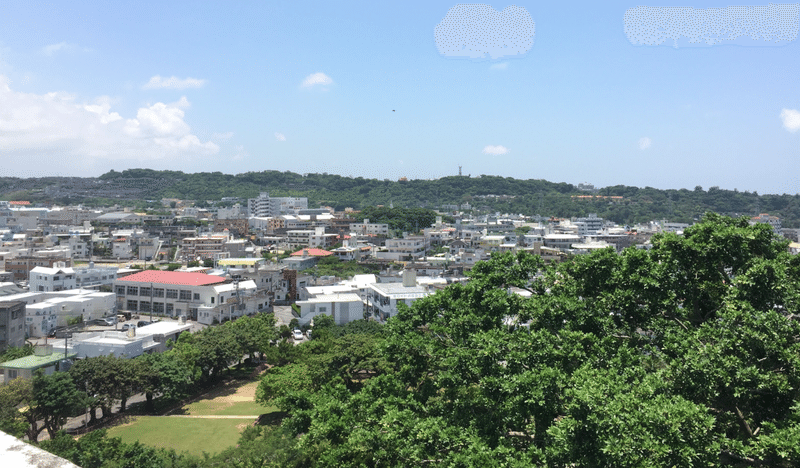
本書では、ここから更に踏み込んで沖縄県民の「自尊心の低さ」にまで言及しているのですが、ここまで沖縄の貧困問題を経済的な観点から、丁寧に、分かりやすく整理して説明された本がこれまでなかったので、本当に勉強になりました。非常に読みやすい本なので、気になる方はぜひ読んでみてください。
それと同時に、著者の樋口耕太郎さんが何度も強調されていた、社会問題を「正しく問う」姿勢は、自身が沖縄で事業を立ち上げ、沖縄の「子どもの貧困」を本質的に解決するために、非常に重要な視点だと改めて感じました。どのような深度の課題意識で事業を立ち上げられるかが、打ち手の筋の良さを左右し、それが課題解決のスピードを決め、沖縄に生きる子どもたちの未来を決める。引き続き、沖縄の社会問題に関するインプットのスピードを落とさずに、学び続けたいと思いました。
同調圧力があるのは沖縄だけではない。本土社会にも画一を好む強い圧力が存在する。「出る杭は打たれる」という格言は、日本社会の代名詞のようなものだ。日本社会は、新しいことへの挑戦に不寛容で、自分を生きるよりも社会の枠組みを、創造よりも前例を踏襲する社会風土を守り続けている。(中略)沖縄問題は、濃縮された日本問題である。
(『沖縄から貧困がなくならない本当の理由』より)
上記は、筆者が本書の終盤で述べていた主張です。「沖縄問題は、濃縮された日本問題である。」という問題提起、僕にはそれが「希望」であると感じています。
何故なら、課題先進県である沖縄には、東京都内と比較すると、課題解決に向けた人材やナレッジも、資金等のリソースは大きく不足していますが、一方で課題が激しく顕在化した沖縄の課題解決は、日本全体の課題解決に繋がり、日本の最南端から社会変革のうねりを起こすことができる可能性を秘めているからです。
よく埼玉県民の僕が沖縄の話をすると、「どうして、わざわざ沖縄県で挑戦したいのか?」と聞かれることがあります。それに対する僕の回答はいつも「これは沖縄の問題ではなく、日本の問題だから」ということと、「沖縄の問題解決が、日本国内の問題解決に繋がる可能性を秘めているから」ということです。
それをしっかりとした実感と根拠を持って語り、いつか僕が沖縄で挑戦することに対する周囲の「違和感」が「必然」に変わるその日まで、スピード感を持ってインプットとアウトプットを続けていきたいと思います。近いうちに今後の方向性について、ご報告できると思います。
本日は、『沖縄から貧困がなくならない本当の理由』をご紹介しました。これからも沖縄の子ども・若者たちを取り巻く社会問題について、引き続き勉強しながら、情報発信をしていきます。沖縄に生きるすべての子どもたちが誰一人として見過ごされず、包摂される社会のために。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
