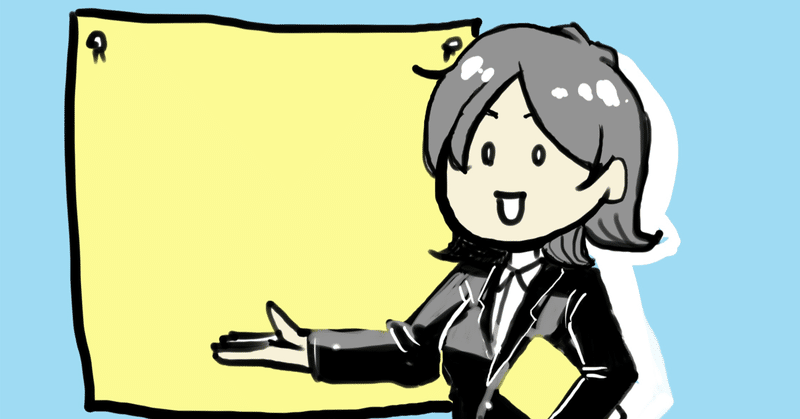
Beyond MAP Grammar?
「意味順」でまた新しくNHK出版から本が出ました.シンプルによくまとまっています.
『ゼロから覚醒 はじめよう英作文』でもStage 2は「意味順」の考え方とつながります.でも,本当に大事なのは,「意味順」的な発想によってセンテンスをつくることのハードルが下がったことそのものではなくて,そこで自分がユーザーとしてどういう英語を生み出していくかに意識が向くことです.
でも,そうではなくて文法が好きな人も嫌いな人も文法の沼にハマってしまっている人たちが多くいて,それはちょっと違うのではないのかな,と個人的には感じています.まあ,前者の文法が好きという人はそれでもいいでしょう.でも,嫌いな人に「結局文法は必要」ということを過度に意識づけてもしょうがないような気がします.「意識させずにいつの間にか身につけていた」でもよい気がします.「意味順」もそういう使われ方をするべきだとぼく個人は考えています.
文法用語や文法的な説明の仕方,センテンスを超えた文章の構造を示すtopic sentence, supporting sentence/detail, introduction(書き出し), body(中心部), conclusion(結論・まとめ), cause and effect(因果関係)などはmetalanguage(メタ言語・ことばを語るためのことば)とよばれある程度は必要で,言語教育的な側面からすればこのような形で記述しない限り客観化・標準化・一般化できない,という事情はわかります,でも,文法のマスターが目的化したり,「トピックセンテンスが書けるか/あるか」だけに執着しすぎると本質からすれていきます.テキストにおけるcohesion(つながり)とcoherence(まとまり) の問題だって,『英文を編む技術』(DHC/絶版.今年中には別の出版社から変更・加筆の上,新しい本として出ます)のP. 34-P.35にもかいてあるHallidayのつながりの出し方のモデルだって,これだけで読みやすい英語のテキストになるのかというとそういうことではないのです.
まあ,ここでこういうことを書くと「結局なんなんだよ」という話にもなってくるので,TOEICの攻略本ではないけれども,ある程度バシッと一旦は明示化したほうがかえってものごとがスッキリ見えるということはあります.とはいえ,TOEIC沼にハマる人も多いので,結局,スナフキンではないけれども「何かを信じすぎてはいけない」ということに留めておきます.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
