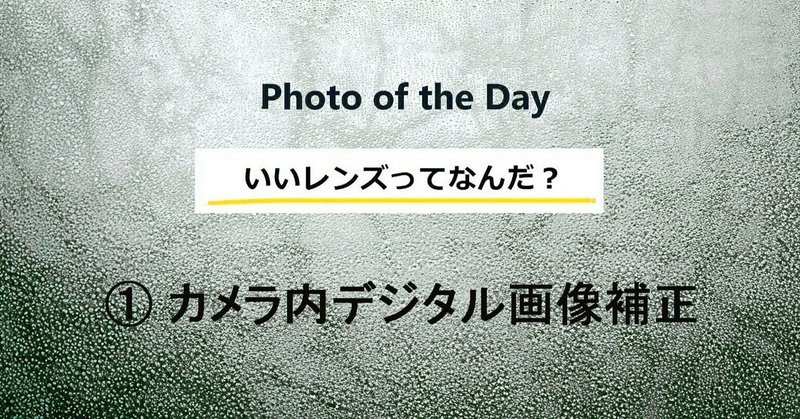
レンズ性能向上の方法や技術・その1
カメラ内のデジタル画像処理ってなんだろう
デジタル画像処理で収差の補正はできるのだろうか
撮影と同時にカメラ内で自動補正するカメラは多くなったのか
レンズの「欠点」をデジタル補正してしまうことがいいことだろうか
最近の撮影レンズは、光学設計や製造技術の進歩などで収差が、そこそこ補正できるようになった。とは言え完全に無収差の撮影レンズを作ることは今も不可能だ。収差ゼロのレンズは理想のレンズ、と言われ続けるゆえんだ。
収差を目立たなくするには、優れた光学設計と精密な鏡枠設計をして、非球面レンズや特殊低分散ガラスなど特殊ガラスレンズ(硝材)を使用することが第一の条件。その上で、高度な検査機器を使う、あるいは職人技といったアナログ的手法で精度の高いレンズを組み立てて収差の発生を最小限に抑えるのが第二の条件。
といった、設計、製造、調整の方法に頼るしかなかったのがフィルムカメラ時代のレンズだった。
デジタル画像処理による収差補正
ところがデジタルカメラの時代になるとカメラ内部や外部でのデジタル画像処理の技術を応用することで、収差などの ―― 収差以外の回折現象やモアレ、周辺光量不足などなども含めて ―― 補正ができるようになった。
最近のデジタルカメラの多くは、デジタル画像処理をカメラ内部でおこなってレンズの欠点を補う機能を取り入れている。撮影と同時にカメラ内で自動的にデジタル画像処理がおこなわれ、一部の収差などはほぼ完全に補正できるようになった。
カメラ内処理で補正が不可能な収差などでも、パソコンと優れた画像処理ソフトを使えば補正が可能なものもある。
カメラ内でレンズ光学系の補正ができるものは、「歪曲収差」「色収差(倍率色収差)」「周辺光量不足」「モアレ」そして「回折現象」の低減や「解像力」の向上などである。
デジタルカメラ時代になってから自動的なレンズ補正だけでなく、その他さまざまな補正や調整の画像処理がされるカメラが多くなっている。
じつはコンパクトデジタルカメラではレンズが固定式なので、「レンズ情報」が一定不変であるためデジタル画像処理も比較的容易だ。自動補正化は(ユーザーが気づかないまま)当たり前の機能として搭載されていた。
ところがレンズ交換式カメラとなると、収差を補正するにしても使用するレンズごとの「さまざまな情報」が異なり、それぞれに1つ1つ対応することが難しいという問題点もあった。その解決策としてレンズごとに詳細な「レンズ情報」を持たせるようになり、カメラにセットすると同時にカメラボディ側がレンズ情報を読み取ってそのレンズに最適なデジタル画像処理がおこなえるようになった。むろん情報を持っていないレンズやカメラボディ側が情報を読み取れなければ自動補正処理の恩恵を受けることはできない。
歪曲収差や倍率色収差のデジタル画像処理
画像処理でレンズ補正が積極的におこなわれているのは、おもに歪曲収差や周辺光量不足、倍率色収差の補正などだ。それぞれほとんど目立たない程度にまで自動的に補正がおこなわれるカメラも多く出てきた。
■ 歪曲収差補正
たとえば歪曲収差の補正をレンズ光学設計だけでやろうとすれば、光学レンズの構成枚数が多くなりレンズ自体が大型になるだけでなく、コストアップにもつながる。歪曲補正を画像処理でおこなえる最大のメリットは、レンズが小型軽量、低価格に設計できることである。
逆に画像処理によるデメリットとしては、画質低下がほんのわずかだが出てくること。あるいは一眼レフの場合だが、光学ファインダーを使って見ている視野画像よりも歪曲補正された画像のほうが画角が狭くなることなどの不満もあった。
しかしミラーレスカメラになると、液晶モニターやEVFのライブビュー画面はリアルタイムで補正されているため画角の変化はわからないようになってきた。
ただし、過度に歪みを補正しすぎると画質低下や画角変化だけでなく、遠近感の描写が不自然になってしまう場合もあり、そのため補正具合のバランスをとりながら意図的に歪曲を少し残しているレンズもある。また、補正をするかしないかユーザーに任せて機能を選択できるようにしているカメラも多い。

上の(図・1)はキヤノン・EOS 5D Mk4の歪曲収差補正のメニュー画面とその説明。使用レンズに情報(補正データ)が入っていれば「する」が選べて最適な補正が自動的におこなわれる。補正データを持たないレンズは自動的に適正な補正がされない。

上の(図・2)はニコン・Zシリーズの歪曲収差補正(ゆがみ補正)の設定解説。Zシリーズ用の交換レンズは自動的に歪曲収差の補正がおこなわれる。使用するレンズの種類によってはON固定でOFFが選べないこともあるようだ。

こちら(図・3)は富士フイルム・Xシリーズの歪曲収差補正の機能説明。マウントアダプターを使用して他社レンズを使用したときだけ〝手動で〟歪曲の補正が可能になるといった、やや変則的な機能を備えている。Xシリーズ用レンズは完全自動で歪曲収差の補正がおこなわれON/OFFの切り替え設定はできない。
■ 色収差補正
いっぽう色収差のデジタル補正は、歪曲補正や周辺光量補正などに比べると補正パラメーターがとても多く難易度は高い。そのため従来型のデジタルカメラではカメラ内処理に時間がかかりすぎるため撮影後にPCなどを使って処理するのが一般的だった。
ところが最新のカメラになると内蔵CPUの性能が大幅アップしたり処理アルゴリズムの改良などにより、処理速度を気にしなくてもよくなりカメラ内で自動的におこなえるようになった。
ただし色収差のうちデジタル補正がおこなわれるのは、一般的には倍率色収差のほうだけで、軸上色収差のデジタル補正は倍率色収差の補正に比べるとかなり難しいようだ。
ところが最新の情報によると、ニコンが新しくマルチフォーカス方式(撮影距離に応じて高精度なフォーカス制御をおこなう)技術を採用して、近距離でとくに目立つ軸上色収差も補正できるようになったという(実写確認していないのでどの程度までなのか不明だけど)。
下の(図・4)がマルチフォーカス方式の解説だ。とてもわかりやすく説明されているが、それによると軸上色収差の補正は近距離時のみで遠距離の被写体では効果があまり期待できないようだ。しかし注目していい将来の展開が期待できる機能である。

参考までに、撮影時の自動補正ではないが撮影後にカメラ内RAW現像処理をすることで軸上色収差の補正がおこなえるものもある。
軸上色収差の派生(一種?)のひとつといわれているパープルフリンジをカメラ内でRAW現像処理をして補正し目立たなくするという方法をペンタックスのカメラでおこなっている。

(図・5)はペンタックス・Kシリーズのカメラ内RAW現像処理の設定画面。オート、弱、中、強、そしてオフの4種から選んで設定できる。


(図・6)が撮影画面で赤枠部分を拡大表示したのが(図・7)。
(図・7)の左が「フリンジ補正・オフ」右が「フリンジ補正・強」。矢印の部分を左右の画面で見比べると、グラウンドの照明器や遠くのネオン看板の周囲に紫色のパープルフリンジが出ているが、フリンジ補正・強で補正処理をすると薄くなったり消えているのが見える。
色収差補正を効率的に最適におこなうにはレンズの詳細な情報、つまりどの波長の光がどれくらい屈折して、どれくらいの量の色ずれが起るかなどの複雑な情報が必要になる。一般的には、そうしたレンズ情報を持っていない(得られない)レンズではデジタル補正をしない(できない)。
であるのだが ━━ やや横道に逸れるけれど ━━ 以前、あるメーカーのカメラでは撮影した画像だけを「見て」、瞬時に倍率色収差補正を自動処理しているものもあった。レンズの種類を問わない制限なし。しかし(なにか大人の事情でもあったのか)現在ではその処理をやめている。他社製レンズを組み合わせても、倍率色収差はメーカー製レンズと等しく最適にデジタル補正してくれて「いいカメラ」だなあと思っていたのだが、残念。
■ 周辺光量補正
周辺光量不足(シェーディング)は、収差ではないが、レンズの〝正しい〟描写にとって悩みの種のひとつである。補正するもっとも簡単な方法は開放絞り値で撮ることを避け、少し絞り込んで写すことだ。たったそれだけで開放絞りで目立っていた周辺部の光量不足はかなり改善される。
ところがデジタル画像処理を応用すれば、開放絞り値のままでも周辺光量不足のない均一な明るさの画面に仕上げることができるのだ。ただしこの補正についても、カメラ内で最適な補正処理をしようとするとレンズ情報が必要となる。

(図・8)ニコン・Zシリーズカメラのヴィネットコントロール(周辺光量補正)の機能解説。自動補正はできないようで、手動で補正量の強弱の設定を選んでおこなう。この手動式補正方法では最適な周辺光量補正はかなり難しそうだ。

(図・9)ソニー・α9IIIのレンズ補正の機能解説。ニコン・Zシリーズと違って周辺光量補正は自動的に処理する機能を備えているし、手動(弱の設定のみ)でもオフにすることもできる。「ご注意」の説明(言い訳)がなかなかおもしろい。

上の(図・10)の左画像は周辺光量不足の処理をOFFで、右画像は処理をONにして撮影したものだ。
周辺光量不足の現象は、画面周辺部が中央部に比べて少し暗くなる現象なのだが、そのほうが描写に味があると考えるユーザーも多い。カメラ側が一括して自動的に光量補正をしてしまうのが「気にくわない」と不満をいだく人もいるに違いない。また、暗くなった周辺部を画像処理で部分的にゲインアップするためノイズが目立ってくることもある。
そうした理由もあって、周辺光量不足の補正についてはユーザー自身がON/OFFできるようにしてるメーカーは多いようだが、一部のカメラでは「うむを言わさず一括自動処理」をしてるものもある。
■ 回折補正
回折現象はレンズを絞り込むほどにコントラストが低下して解像描写力が損なわれる現象である。これも収差ではないが収差よりも〝タチの悪い〟現象だ。ところがデジタルカメラ時代になって、回折現象を補正(影響を減少)できるようになってきた。いっきに脚光を浴びつつある画像処理技術のひとつである。
回折が補正できる、などとはフィルムカメラの時代では考えられもしなかったことだったのだが、デジタルカメラ時代になってカメラ内またはPCを使って処理できる機種が最近増えてきた。

(図・11)はキヤノンのカメラに搭載されているデジタルレンズオプティマイザの機能解説。デジタルレンズオプティマイザ機能は改良、進化しているようで将来、もっと良くなる可能性を秘めている。注目しておきたい機能だ。この機能は収差補正だけでなく回折現象の影響を低減して解像感を向上させることもできるようだ。
回折現象を補正低減する機能を備えているキヤノン以外のカメラとしては、たとえば富士フイルム・Xシリーズやペンタックスなどのカメラで見られる。
回折現象による影響を抑える処理は ━━ まだまだ満足できるレベルではないけれど ━━ デコンボリューション(点像分布関数計算処理をもちいて逆演算することでぼけを取り除く復元処理)技術や、コントラストMTFを最適化するなどの方法があるようだ(私には詳細をウマく説明できないが)。いずれの処理も膨大なレンズからの情報が必要となることは確かだ。
もともとテレビなどの画像処理から発展した超解像(見かけ上の解像感をアップする)技術と併せて、これからのレンズの描写を向上させるための画像処理として注目されているし、今後、さらにこうした補正技術は進化していくだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
