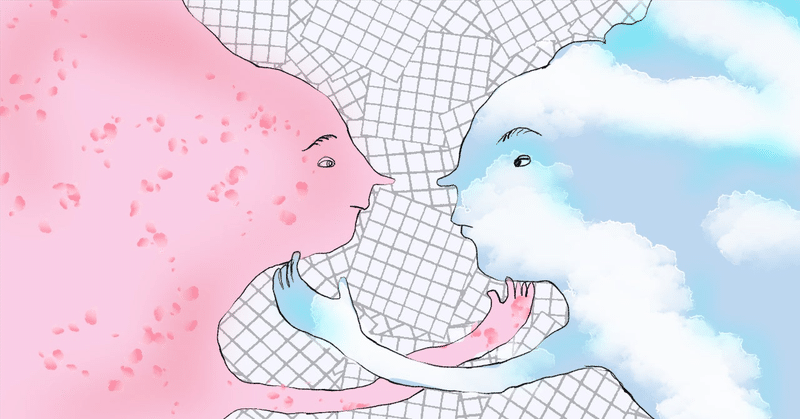
三面鏡
彼女は三面鏡を見る。化粧のためでなく観察するために。まるで鏡の中に、だれも気づかないけれど見過ごしにしてはならない何かが潜んでいないかと探るように。
右の目の下に泣きぼくろがあるせいか、右半面は少し悲しそうだ。左半面はやや険があり意地悪そうに見える。低くてやや上を向いた丸く不器量な鼻は母から、泣き腫らしたようにふくらんだまぶたは父から、ぼさぼさの濃い眉毛は母方の祖父から、それぞれ受け継いだ。額の横じわが10代のころから中年のような印象を与えていた。
高校生のころ、彼女は密かに「気仙沼ちゃん」と呼ばれていた。欽ドンのレギュラーだった気仙沼ちゃんは、東北弁でりんご顔の、絵に描いたような天然田舎娘というキャラクターだった。明らかに「ブスキャラ」だからか、面と向かって嘲笑する同級生はいなかったが、同じころ上の姉も大学でそうあだなされていたらしいから、きっとかなり似ていたのだろう。
東北で民宿を経営している、くだんの気仙沼ちゃんこと白幡美千子さん(56歳)は、3.11に罹災し民宿が床上浸水してしばらく安否がわからなかった。ニュースの画像では、欽ちゃんの応援を受けて民宿を再開しようと頑張っている、照れたようないい笑顔があった。
「30年以上経ってもやっぱり雰囲気は似ているかも知れないな、がんばってほしいな。」彼女は気仙沼ちゃんに初めて親近感を覚えた。
目のしたの皮膚がたるんで隈ができているのが日々の疲労感を、尖ったせりふがつぶやかれそうな薄い唇と、下がった口角が日々の鬱屈した不機嫌を現して、無表情な時にはとりわけ印象を暗く重いものにしている。
不仕合わせそうなオバサン。スーパーですれ違って、あの人、なんであんな面白くもなんともないみたいな顔をひとに晒して歩いているのだろうと不思議に思うような不機嫌な顔。
鏡の中に写る自分はあまり好きじゃないなと彼女は思う。
ふと、母親がだぶって見える瞬間がある。
だんごっ鼻が似ているせいもあるが、むしろまなざしのなかに虚無感のようななにか仄暗いものが感じられるせいかも知れない。
彼女の母は写真に撮られるときにわざとのように、目線をわずかに外した。嫌悪とか不服とかの強い意志ではなく、誰かに自分を委ねてしまった人のような、つかみ所のない空虚な感じとでも言えばいいだろうか。
役目に徹する暮らしのなかで、母という個人が立ち上がる余裕はすでに失われていたのだろうか。晴れやかに笑う顔は味わいのあるいい表情をしているし、長年の農作業で日差しに焼かれた肌はなめし皮のように光り、逞しくよく動く手足とつり合って揺ぎ無いひとのかたちをつくっていたのに、なぜか彼女には母の茫洋としたまなざしが強く印象に残っている。
「たぶん、悲しかったんだ。苦しい残念な母を見るのが、私は、ずっと、こどものころから悲しかったんだ。」と、このごろ彼女は認めることを自分に許した。
くよくよ甲斐のなさをこぼす母を。
精一杯働いているのに父に無理やり働かされているように感じる母を。
過剰なまでに増大する父の夢の実現になりふりかまわぬ献身をした母を。
家族の中で必要とされているのに誰からも感謝されないように感じる母を。姑に小馬鹿にされる母を。
夫に守られながら、愛されないように感じる母を。
「母のようにはなりたくない。」と心の奥で見下してきた自分の傲慢さを、彼女は自覚している。なぜなら、いま彼女が感じている自己評価こそ、母への評価と同じだからだ。
彼女の母が67歳で自死したとき、それが母のこころの中に巣くう、茫洋とした、気概なさ、空疎さによって、起こるべくして起こったことのように彼女はふと感じた。
そしてすぐに否定した。
あの母からは絶対ありえない、あるはずのないことが偶然、運悪く起きてしまった、という相反する考えに拘った。
いまは分からない。
ただひとつ言えることは、母は自死という行為によって、唯一無二のかけがえのない、尊ばれるべき、敬われるべき、愛すべき人間として、彼女の記憶の奥底にはっきりした輪郭ですっくと立ち上がった、という衝撃である。
またまた
へんな
下降のループになっている
たまたま
へんな
落とし穴に
ころげこむように落ちたんだ
くよくよ
へんな
思考の罠に囚われて身動きができない
よくよく
へんな
罠をしかけたのはなんだわたしなんだ
彼女は化粧をめったにしないから皮膚は荒れていない。幼いころから「色白でもち肌」というのが、彼女に与えられた、容姿についての数少ない褒め言葉だった。じゃぶじゃぶと水で洗っただけの肌は清潔でしっとりと手に馴染む。52歳になっても変わらない美点だ。
彼女が破顔すると、開けっぴろげで屈託のない表情に一変する。「器量はいまひとつだけど愛嬌のある子だよ、このこは」そう言って母は、彼女に将来を楽観させてくれていた。
「この顔で生きてきたのだもの、実はそんなに嫌いじゃない」、と彼女は鏡に向かってにっこり笑ってみる。そうすると鏡の中のひともふわりと顔をほころばせて、「この顔のなかには懐かしい人たちが大勢いるのだもの。こどもたちにも「色白でもち肌」は受け継がれているのだもの。すきでいてよ。ダイジョウブだよ。このままでいいよ」と答えてくれる。
彼女は三面鏡を見るようなやりかたで文章を綴る。
書くのはなんのためだろう。思いをかたちに残すとはどんな意味があるのだろう。彼女は、大切なものを見失ったり流されたりしないで踏みとどまるための、なにか結び目のようなものが欲しいと思って書いてきた。
時には、現実の人間関係の中では言い出せないけれどもどうしても言わずにはすまなかったことばたちの「捨て場所」でもあったのかなとも思う。つまり、書くことは彼女の存在が立ち上がるための作業であり、存在を確認するためのツールなのだ。
「自分を愛する。」
ただそれだけのことがこんなにも難しい。
(7月19日 台風6号のどしゃぶりの雨音のなかで)
「もらとりあむ30号 2011年夏草」収録
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
