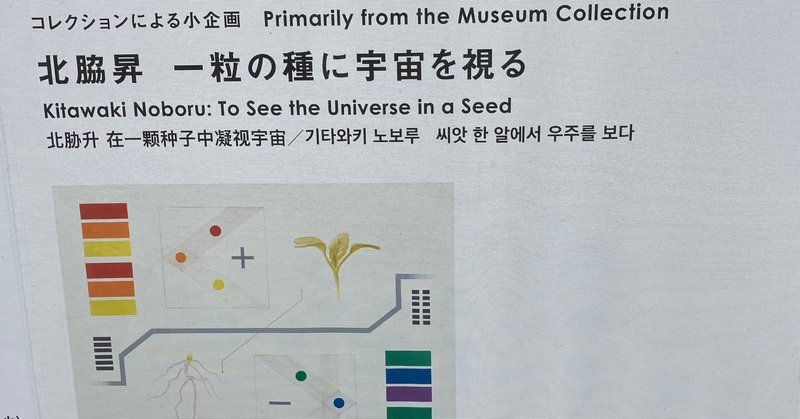
「北脇昇 一粒の種に宇宙を視る」展
竹橋にある東京国立近代美術館へ。車で往復。お目当てはギャラリー4で開かれている「コレクションによる小企画」である「北脇昇 一粒の種に宇宙を視る」展。事前に東京国立近代美術館のWebサイトにて公開されている解説動画、NHKの「日曜美術館 アートシーン」にて予習してから出かけた。そのおかげで、より一層楽しめたし、そして思いがけぬ絵と出逢えた、大変収穫の多い美術展であった。
(東京国立近代美術館のサイトを以下に紹介する。解説動画がお勧め)
*本展は既に終了しています
思いがけぬランチ
本題に入る前に。昼時に訪れた私、いつも入り口前に軽食を提供してくれるトラックがいるのでそこで軽く食べようと思っていた。しかし今般のウィルス禍の影響か、今日は出ていないではないか…。あのお店の方、大丈夫かな?心配。いやしかし、昼食どうしよう…。ここまで来たらもう選択肢は一つしかない。美術館併設のL'ART ET MIKUNIだ。

有名シェフ三國 清三のお店、お値段張るだろうなぁ、とこれまで何度か来ても一度も入ったことなかったが。ランチメニューはピッコロ3500円税別とグランデ5500円税別。予定外の出費でもあり、もちろんピッコロをオーダー。でもお値段だけのことはあるなぁ!前菜からデザートまで、実に堪能させていただきました…。思いがけぬランチとなったが、幸先良し。さあいざ美術館へ!
北脇昇とシュルレアリスム、コンテクストと芸術
フェイスシールドをした受付の方に検温していただき、消毒をしてから館内へ。近代美術を対象としていることもあって人はまばらでもあり、このウィルス禍の状況下でも安心して美術を楽しめた。
さて北脇昇。美術に疎い一般人である私などはお名前も全く存じ上げなかったが、この美術館の常設展の方では何作か観た憶えはあった。見立ての妙があり且つシュルレアリスムも同時に感じさせる『空港』『空の訣別』連作、東洋の陰陽道を材に採った『周易解理図<乾坤>』といったあたりだったか。しかし、これらの作を楽しむのはなかなか難しく感じたのが実感であった。まずは絵を観る。うーん、何がテーマなのだろう、何が言いたいのかな?考えてもわからない…。絵の傍にある解説板を見る。なるほど…これは日中戦争時にあった実際の撃墜の様子をカエデの種子とサンゴであらわしたのか…。なるほどこちらは易や陰陽道で用いられる記号を使っているということか…。解説を読んで初めてわかる。解説を踏まえてもう一度観てみると、なるほどなぁ、とおもしろさを受け取れる。
しかしこのように、コンテクスト(文脈)を知らないと、調べないとわからない芸術ってどうなのだろうか…。テクストだけ、作品だけで勝負するべきなのではないのかなあ。素人としてはそのように感じてしまうのが正直なところ。
この気持ちには館内で配られていたパンフレットがしっかり配慮してくれていて、北脇自身の言葉を引用してくれている。こうだ。
一つのタブロー(筆者注:絵画)が何等かの解説を要求すると云ふ事は、多分に不純であると謂はれ得るかも知れない。然しそれは意図の正統な表明を妨げるものではないと思ふ。のみならずそれは明晰を愛する今日の画人の一つの義務であるかも知れない。
この画家のキーワードはここにある「明晰」であるかもしれない。非常に頭脳明晰な人であったことは作品を観ていても感じる。そして全てを論理だてて考えた人だったのであろうなぁ、と。パンフレットにある本展のキュレーター大谷省吾の文章も、それをあらわしていると思う。
北脇が(中略)本当にやりたかったことは何だったのか(後略)。それは、私たちをとりまくこの世界の背後にある見えない法則を解き明かし、世界観のモデルを示すことでした。北脇はそうした信念のもと(中略)、独自の図式的な絵画を生み出しました。
一粒の種子が発芽し、成長をとげ、開花し実を結び、そして新たな種子を生み出すことに、天地の法則すべてが凝縮されていることを見出そうとした彼の、他に類をみない制作の歩み(後略)
コンテクストを持つ芸術、コンテクストを知り得ないと充分に鑑賞できないと感じる芸術、というものが在り得べきものなのか?という問いは先に引いた北脇の言葉を読んでも腑に落ちたわけではない私だが、北脇が真率にこの世に対峙した人であったことはよくわかった。そして生きにくかった戦前・戦中・戦後を懸命に生き抜いた人であったことも。
見立て
予習で学ばせてもらったこと――京都には「見立て」の文化が色濃い。何かを別の何かに見立てて楽しむということ。9歳の時から京都の叔父のもとで育った北脇が自然に体得した文化であったということ。
今回の美術展は1937年から彼の死の年1951年までの作品が並んでいるが、特に1937~38年頃の作品に見立てが多く使われているようだ。
まずは1937年、日中戦争が起きたキナ臭い年ではあったが、彼はその中で多くの作品を書いている。今回の展示においても先述の『空港』『空の訣別』がこの年。カエデの種子を飛行機に見立てたシュルレアリスム的絵画。そして『樹の根と芽』も既に陰陽や植物への関心を窺わせる。絵の真ん中にドーンとした存在感の大きな切り株、そこから萌える新しい芽、そして空には細い月。この月は満ち欠けの表現、つまり時の移ろいを表現しているのだろう。死した切り株とそこから萌える新しい生。鮮やかな対比。
翌年にかけて描かれたものか、「観相学シリーズ」と名付けられた連作もおもしろい。『変生(観相学シリーズ)』は英訳Metamorphosis of Life, Series of Physiognomyが添えられている。欧州系の観念メタモルフォーゼがテーマなのだな。英訳も一つのコンテクストとなり鑑賞者の助けになるという一例か。じっと立ち止まって観る。ほかにこのシリーズから『影』『聚落』『情景』が展示されており、見立てを楽しみながら色々考えを巡らせる時間を持てた。こういう感じを鑑賞者が持つことを作者は狙っているのかな…それはわからないが自分なりに楽しく観ることができた。
生命、特に植物への特別な関心
ジャンルを超え全分野的に活躍した偉人ゲーテの植物変化論、植物生理学に大きな影響を受けたという北脇。生命、特に植物に特別に強い関心を寄せたのはそこから来ているのだろう。作中における植物のイメージはそこかしこにある。特に植物の生命力への共感が感じられる。1938年の『孤独な終末』では枯木から出るタンポポの綿毛。同じ年の『浄火』では絵全体を赤茶色に染め上げて「世の中すべてを浄化する火」というイメージを鮮烈にしておきつつ、物陰からソッと芽が萌えだしている。これは当然戦時下というコンテクストがあっての絵でもあろう。戦いに明け暮れる世ではあるが、その焼け跡からも新たに生命は生まれ出る、という信念をあらわしたものか。
1940年の『<(A+B)2意味構造>』、1941年の連作『周易解理図<八卦>』『周易解理図<乾坤>』『周易解理図<巽兌>』になると、また違った作風になっている北脇。解説を読みながら鑑賞するに、世の摂理を数式的に解明せんとしたものであったり、図としてあらわそうとしたものであったりと、私のような者には思いもよらぬ大それた事に取り組んでいるものだとわかる。ちょっと考えすぎではないか、北脇さん…、息苦しくないですか…、と私などは感じてしまうが…。戦中の息苦しさのなかで、考えに考えながら、自らの芸術や生き方を模索、追究していた人なのであろう。
そしてそんな論理中心で描かれた作品の中にも植物のイメージを色濃く置くのが北脇の北脇らしいところか。芽と根、天に向かって伸びるものと、底に向かって伸びるもの。或る種二元論的であり、且つ二元の交流に世界を観るという北脇の思想が感じられる。
そしてここまで観てきた殆どの絵が油彩で描かれているのだが、油絵と言えばゴッホのように塗り重ねられたゴツゴツしたマチエールをイメージしてしまう私にとって、全般に塗り重ね感が無く、陶器の表面のように平らかな本来の意味でのマチエールとなっているのが北脇絵画の特徴と感じた。非常に論理的に、かつ細部の下絵も重ねるなど計画だてて描かれた絵画であろうと。
鉛筆画、自画像
大展示室と小展示室とを連結した感じの今回の展示場、大展示室では油彩が飾られており、小展示室では鉛筆画が中心に置かれていた。
大展示室の終わり近くには1947年、46歳ぐらいで描かれたものであろう自画像があった。自画像と言ってもちょっと変わっている。まず現在の自分を描いたものであろう肖像が左側に描かれている。その自画像の後ろには黒い影、そして傍には釣り糸を垂れる物寂しい釣り人が寒々としたセピア色で添えられている。釣り人の足もとから伸びた線の先には何故か真っ赤なサイコロがある…。そして絵の右側には自身の幼少期の心象を示したものでもあろうか、お皿を前に顔をしかめる少年と掘っ立て小屋のような小屋が描かれている。
うーん…、自画像と言っても一筋縄ではいかない人だな。単なる顔を描くのではなく、人生や心象までも対象として描いているのだな。
などと考えながら小展示室へと歩を進めた私。こちらの部屋では最初の数点のみが油彩。
最初の『数学的スリル』は隣にオブジェとして並べて展示されている変わった形の木を材に、数学的あるいは図形的なおもしろさを狙った作品。さらには京都の景観の中から三角形を抽出した作品もある。植物や図形への偏愛を思わせる作品たち。
その後に続くのは、先述の通り油彩とは打って変わって鉛筆画中心の白黒の世界。多く展示されている鉛筆での『素描』群は、下絵として描かれたものだろう。小さな植物や実などが一品一品描かれている。しかも大変丁寧に描かれており、下絵といわず、これだけで作品として成立している感がある。解説板にもあったとおり、ジッと観ているとちょっとした草を描いているかのようなものが大木のように見えてきたりする不思議な感覚に誘われたりして。
ここから先は
¥ 500
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
