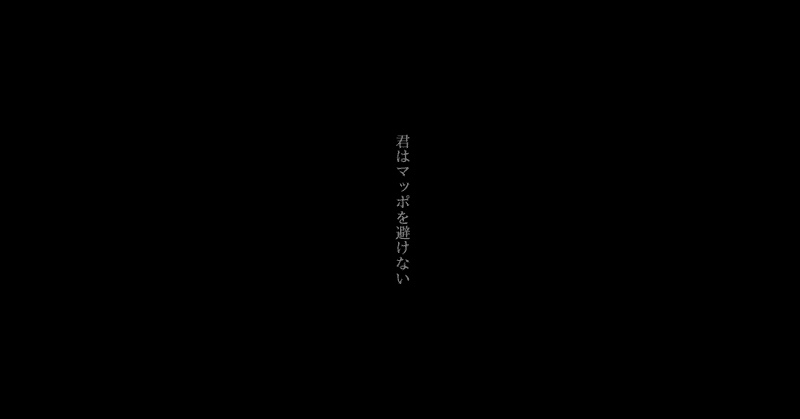
パロディ小説『君はマッポを避けない』
『君はロックを聴かない』あいみょん
***
久しぶりの学校。久しぶりの授業。
「じゃあ~これわかるヤツいるか? なぜ警察のことを『マッポ』と呼ぶのか」
社会科の教師が教室を見回す。目が合った。白いチョークを向けられる。
「はい、じゃあおまえ。1か月ぶりに学校来たんだから、ちょっと答えてみろ」
僕に視線が集まる。生徒たちが笑い声を押し殺している。
「わかんねえよ」
「おいおい、そうツッパるな。暴走族の友達連れてこないでくれよ」
教師が大きく肩をすくめた。手のひらを上に向けるポーズもとった。
「……うるせえな」
小さな声で言うと、僕の近くに座る生徒たちが黙った。僕が机を蹴っ飛ばすのを期待しているのだろうか。沈黙は教室中に連鎖した。真面目くさった顔をつくって、社会科の教師が口をひらく。
「……おまえな、留年決まったぐらいでいじけるなって。他校の不良とつるんでもいいことないぞ。今ならまだ間に合うから。1浪したと思って、気を取り直して勉強がんばれ」
教師が背を向けた。質問の答えを黒板に書いていく。どうやらマッポとは、「薩摩」という言葉に由来しているらしい。明治初期、警察官には薩摩藩出身者が多かった。そのため彼らは「さつまっぽう」と呼ばれた。それが次第に短縮され、できた言葉がマッポ。教師の説明はわかりやすかった。雑学としても、なかなか面白い。
僕はこれを誰かに伝えたくなった。日露戦争について板書する教師の背中を見ながら教室を出る。たった今得た知識を共有したい相手に、LINEをしてみた。
《なにしてんの?》
すぐに返事が来た。
《地区センのまえのファミマ。後輩とダベってる》
《了解。すぐ行く》
授業中の静まりかえった校舎を後にする。月に1回くらいは顔を見せようと思ったけれど、やっぱり学校なんて来るんじゃなかった。路地裏に隠していた原付にまたがる。エンジンをかけた。フルスロットルでコンビニへ向かった。
***
マッポの話は、誰も興味を持ってくれなかった。
「そんなのどうでもいいんだよ。マッポの名前の由来なんか。それより、試験受けないでバイクの免許とる方法教えてくれって」
君がそう言うと、後輩たちがガハハと笑った。平日の昼間、誰もいないコンビニの駐車場に声が響く。
「てかよ、おまえ明日の『走り』来るだろ? 後ろ乗っけてやっから」
「え、いいの?」
僕が驚くと、君が肩を小突いてきた。
「あたりめーだろ。もう知り合って2ヶ月じゃんか。そろそろ『走り』にも参加しねえと、仲間に入ったことにならないっしょ」
後輩たちが金髪を揺らしてうなずいている。僕は嬉しかった。仲間なんてヤンキー漫画みたいでダサいけれど、遊び相手がいるのは頼もしいことだ――。
僕らが知り合ったのは2ヶ月まえだった。場所はこの駐車場。最初はカツアゲみたいな感じだった。しかし僕の身の上を話すと、「なんだよ、頭いい高校のヤツでも留年するんだな。面白えじゃん。もう学校なんて行かなくていいべ。一緒に時間潰すっしょ」と君が誘ってくれた。
地元で秀才と呼ばれる進学校に入学し、勉強についていけなくなり、学校を休みがちになっていた僕にとって、君の提案は心がおどった。どうせ大人はもう、僕にあまり期待していないのだ。両親は留年が決まった瞬間からなにも言わなくなった。大学生の兄は「大丈夫。2浪でも3浪でも大学にいっぱいいるから」と励ましてくれたが、これ以上勉強を頑張れる気がしなかった。僕はもう進学を諦めたのだ。かと言って特に目標があるわけじゃない。そんなとき君に出会った。無免許で自由にバイクを操るその奔放な姿に、憧れを抱いた。
「うし、じゃあちょっと江の島行くか」
君が音頭を取ると、後輩たちがそれぞれ原付にまたがった。僕もそれに倣う。
「明日はでっけえバイク乗せてやっからな。CB400ってHONDAのバイク。楽しみにしとけよ。じゃあ行くぞ――」
君が原付を急発進させる。黒煙を辺りにまき散らした。僕は煙を浴びて涙目になりながら、君と後輩たちの原付に置いていかれないように、必死にアクセルを回した。
***
「最近バイク乗ってるんだって?」
夕食後、ソファでくつろいでいたら父に話しかけられた。久しぶりのことだった。
「うん。なんで?」
「いや、なんでって…。車庫にあるの見たからな」
父が隣に座る。
「おまえが学校へ行ってないのは知ってる。でも別に、勉強しろって言ってるわけじゃない。大学だって行かなくてもいいし。ただ、もっとこう健全な趣味というか、安全な遊びというか…。そういうのをやったらどうだ? バイクはほら、危ないだろ。単純に」
父の言うことはもっともだ。頭ごなしに叱りつけたりもしない。勉強もしなくていいと言う。理想の父じゃないだろうか。しかし僕は彼の期待にこたえられない。
「うん。考えとく」
ソファから立ち上がり、2階の自室に向かう。リビングから出るとき、
「ヘルメットだけはちゃんとするんだぞ」
という父の声が背中にぶつかった。部屋に入ってベッドに腰をおろす。机の上に置いた半帽のヘルメットが、ライトを受けて黒く光っている。
父ががっかりする気持ちはわかる。うちの親族はみんな優秀で、今は専業主婦の母も大学院まで出ている。でも、勉強ができない僕に対して、いちばん落胆しているのは自分自身だ。中学まで己の顔に貼ってあった「秀才」というシールを剥がされ、恥ずかしくなり、ぜんぶが嫌になっていじけているのは他でもない自分だ。それはわかっている。親は悪くないし、教師も悪くない。でも僕は「できない自分」と対峙したくないのだ。だったらいっそ、戦いの場から逃げたほうが気が楽。ダラダラと青春の音が流れるコンビニの駐車場で、毎日くだらないお喋りに興じていたほうが僕にとっては心地いい。それには友達の存在が必要で、君とか後輩とか、勉強とは無縁の人たちと一緒にいるのがいい。彼らの存在はありがたかった。向こうも僕みたいな立ち位置の人間がグループにいることで、日々のマンネリを和らげているようだった。利害が一致していた。誰にも迷惑はかけていなかった。
明日乗るらしいHONDAのバイクを検索する。原付とは比べ物にならないほど大きかった。エンジンが剥き出しで、メカっぽくてかっこよかった。これの後ろに乗れるのか――。君と出会えてラッキーだった。自分じゃこんなバイクに乗ることなど、たぶん一生なかっただろう。
***
翌日の夜、君と後輩たちと駅で待ち合わせた。
「いいか、ノボルさんってのが総長だ。最初に挨拶すっからおまえも顔覚えてもらえよ。んで、今日はこのバイクが先頭だからな。1番まえ走ってぶっ飛ばしてやるから」
君がまたがっていたのは、僕がネットで見たバイクとまるで違っていた。ライトには変な丸いカウルが付いていて、マフラーは竹みたいに細長い。シートはエナメルで、キルティングが入っている。ボディサイドには「亀羽目派」。どうやらこれがチームの名前らしい。実際に目のまえにすると、暴走族のバイクはなにかのキャラクターみたいだった。
「うん。落ちないようにつかまってる」
僕はリアシートに座った。背もたれがいい感じだ。なんだかワクワクしてきた。父が見たら泣くよ、とささやくもう1人の自分は無視した。
「じゃあ行くぞ」
君がアクセルを吹かす。雷が落ちて来たかと思った。思わず耳をふさぐ。が、取っ手につかまっていないと振り落とされそうだった。ものすごい風が顔にぶつかる。時速60kmを超えると、涙が出ることを初めて知った。原付から見る世界とは、まったく別物だった。
江の島大橋には、数十のバイクが集っていた。
「ノボルさん、今日は先頭やらせてもらえて光栄っす! こいつは俺の仲間で、後ろに乗せて走るんでよろしくっす」
君が頭を下げると、総長が僕のことを下から上に向かって見た。
「…ダセえ『走り』すんじゃねえぞ」
その目は真剣だった。僕は首をぶんぶんと縦に振った。
「よっしゃ! 行くぞ」
総長のかけ声で、江の島に雷の嵐が降った。バイクが急発進する。リアシートに背中が張り付いた。君の運転するバイクは横須賀方面に向けて走っている。僕の祖母の家は逗子にあるから通り道だ。彼女がこの音で心臓発作でも起こさないかと、無用な心配をした。
***
数十分ほど風を切った。コンビニで小休止。駐車場にいる車たちは、僕らが入っていくと一目散に逃げだした。なんだか気持ちがよかった。体の中にたまった鬱憤が、体外へ飛び出していくようだった。
「どうだ。ハンパねえだろ」
君がニカッと笑う。その顔は自信に満ちていた。
「うん、風が気持ちいい」
僕がそう言うと、
「馬鹿。もっと感想あんだろ」
と嬉しそうに僕の頭を叩いてきた。
「こっからスピード上げっからよ。落ちんなよ」
君がバイクにまたがる。僕も後部座席に飛び乗った。数十のバイクがエンジンをうならす。総長が近寄ってきた。
「この先、検問やってるらしい。わかってるな? おまえが突っ切れ」
総長が君の肩にパンチした。君は嬉しそうだった。
「聞いたか? ぜってー落ちんなよ」
バイクが走り出した。顔に当たる風の勢いが増した。このまま飛んでいったらどうなるんだろう。死ぬのかな。壁とかにぶつかって、骨が折れるのかな。そんなことを考える。不思議と怖くはなかった。ただ、体は正直だ。心臓のBPMは190になっていた。高速で流れる景色を追うため、嘘みたいに目が泳いだ。頭の中で警報音みたいなメロディーが鳴っている。その乾いた音が、止むことはなかった。
……数百メートル先に、大きなカーブが見える。そしてその先。カーブを曲がりきったところに、いくつもの赤い光が点灯している。検問だ。警察だって、ルールを無視して走る連中を放っておくほどお人よしじゃない。爆音の鳴り響く中、僕は運転する君の耳元で叫んだ。
「本当に突っ切るつもり!?」
君が少しだけ首をひねって、
「あたりめーだろ!」
とちょっと困った顔で返事をした。
僕はそれ以上、なにも言わなかった。エナメルのシートに背中を預ける。頭上を見上げた。夜空にはたくさんの星があった。僕らはぶつかったら死んじゃうくらいのスピードで移動しているのに、星の位置はぴくりとも動かない。速度制限の看板は一瞬で後方へ消えていくのに、夜空の星は数センチだって動かない。いや、正確には動いているのだろう。それもバイクなんかとは比較にならない速さで。でも僕から見た星は同じ位置にいる。あと数百メートルで自分の行く末がわからなくなるせいか、僕は意味のないことを考えるよう努めた。
でもやっぱり、死ぬのは嫌だなあ。父や母の顔が浮かぶ。兄や教師の心配そうな表情も。後悔はしていない。たとえ一瞬でも、さっきのコンビニで感じたみたいな気持ちよさ、自分自身のダサい部分をぶっ飛ばせたのだから、君には感謝している。君と会えてよかったと思った。たとえパトカーにぶつかって死んでも、悔いのない人生だった。ただ、それでも――。
君はマッポなんか避けないと 思いながら
あと少しスピード 落として欲しくて
マッポなんか避けない と思うけれども
僕はこんなバイク あんなバイク
別に乗りたくはなかった
……君は検問のまえでバイクを止めた。総長が走ってきて君をボコボコに殴った。その後、僕は大学に受かった。君はベンチャー企業の社長になった。先日、『ABEMA Prime』に元暴走族社長という肩書で君が出演しているのを観た。君はあのころと同じように、口は悪いが魅力的な人物だった。当時のことを思い出して、僕はこんな日記を書いた――。
(完)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
