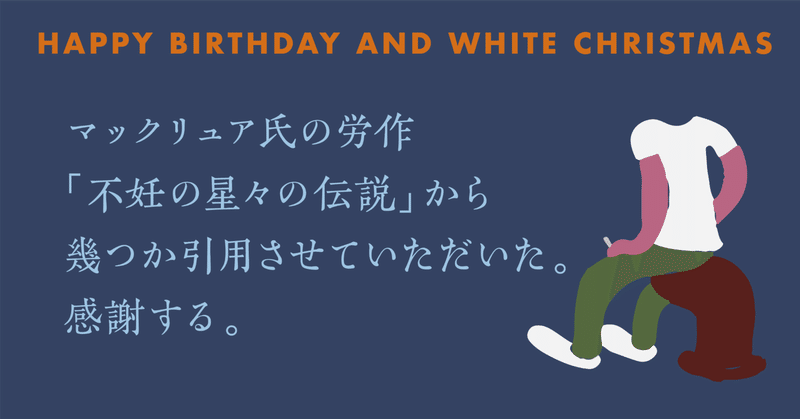
「風の歌を聴け」を読め
本稿は、私が村上春樹の処女作「風の歌を聴け」を如何に好きであるかを書き連ねることを目的としており、書評ではない為、粗筋などを紹介するつもりは毛頭ない。
故に未読の方には、殆ど内容が伝わらない文章になろうかと思う。
所謂ハルキストと呼ばれる方々が、こよなく愛するのは主に著者の中期から後期の長編作品である事が多いのに対し、私は群を抜いて本作を溺愛しており、ハルキストの仲間にはきっと入れてもらえない事だろう。
本作と言えば、村上文学を代表する一節、
「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。」
との書き出しがあまりに有名であるが、寧ろ私は章毎や、段落毎の書き終わりこそを好んでいる。
本作は40の短いチャプターと後書きで構成されており、チャプターはそのどれもが短い。最も短いチャプターは一行で終わる。
私が書き終わりと呼ぶものの中で最も有名な文章は
「あらゆるものは通り過ぎる。誰にもそれを捉えることはできない。僕たちはそんな風にして生きている。」
という一節だろうと思う。本作を象徴する文章であり、虚無的な切なさと、諸行の無常さを感じさせられる素晴らしい文章だと思う。
他にも私の好きな書き終わりを幾つか紹介させていただくと
「ピーターポール&マリーが唄っている『もう何も考えるな。終わったことじゃないか。』」
「『みんなの楽しい合言葉、M.I.C.K.E.Y. M.O.U.S.E.』確かに良い時代だったのかもしれない。」
「夜中の3時に寝静まった台所の冷蔵庫を漁るような人間には、それだけの文章しか書くことはできない。そして、それが僕だ。」
「彼の墓碑には遺言に従って、ニーチェの次のような言葉が引用されている。『昼の光に、夜の闇の深さがわかるものか。』」
などが、ある。まだまだ幾らでも挙げられるのだが、中でも私が最も愛するのは
「そしてその時、象は平原に還り僕はより美しい言葉で世界を語り始めるだろう。」
と言う一行である。
読後の余韻を楽しませてくれる作家や作品は多いが、本作の書き終わりが持つ独特な余韻と、その味わいの多彩さは、村上初期作品群の中であっても私は本作にしか見出せないでいる。
処女作ならではの若々しさを湛えた気取った言い回しや、気障な台詞、翻訳文めいた著者らしい文体、描き過ぎない描写、語感とリズムの良さ、余白だらけの登場人物と、不遇の作家デレク・ハートフィールド。好きな箇所の枚挙には暇が無い。
本作は決して面白い物語では全くないし、何度読んだところで楽しくも、悲しくもない。然し本作しか与えてくれない感慨を私は好んでいる。読む度に心に、少しだけぽっかりと空いた虚空のようなスペースの存在を感じさせてくれ、その空白を体の中心で燻らせるように読書時間を愉しむ事が出来るところを、とても好んでいる。
共感いただける方は少なそうだが、原点にして頂点とは、本作の為にある言葉だと私は思う。
既読の方も未読の方も、是非今一度本作の余韻にその身を浸していただけたらなんとも幸甚である。
最後に後書きの締めの文章を記させていただいて本稿を終えたい。
「『宇宙の複雑さに比べれば』とハートフィールドは言っている。『この我々の世界などミミズの脳味噌のようなものだ。』そうであってほしい、と僕も願っている。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
