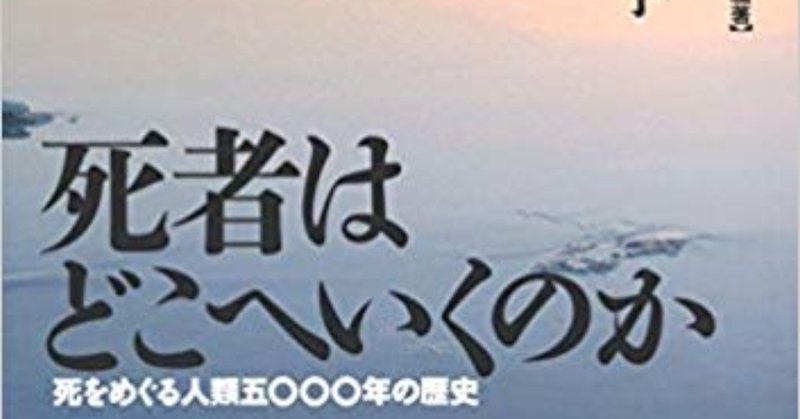
題:大城道則編 「死者はどこへいくのか 死をめぐる人類5000年の歴史」を読んで
題名に惹かれて読んだ本である。無論、ルドルフ・シュタイナーの「神秘学概論」のような壮大な霊魂の話を期待したわけではない。ただ、魂の行方が何処に行くのか気になっただけである。一般的に著者が多数居ると知識の断片的な切り張りになる恐れが多分にあり、本書もその例に漏れず説明的な文章によって書かれていて、大元の思想を欠いているがゆえに読むとどことなく虚しい。編者は「死生観」を考察したものと「はじめに」記しているが、難しくて無理だと放棄している著者さえいるのである。死者がどこに行くかなど分かりはしない。死者の魂が薄らぼんやりと見えてくることすらない。結論から述べると、本書よりも柳田国男の「先祖の話」、鈴木大拙の「日本的霊性」、折口信夫の「死者の書」、川崎定信訳「チベットの死者の書」、ジョルジュ・バタイユの「宗教の理論」、阿満利麿の「宗教の深層」などなど一人の著者による本の方が、魂や霊魂に関して話がまとまっていて読みやすいし、読んで楽しい。また知識は偏りながらも深まるはずである。特に日本で言えば「先祖の話」が、死者の魂が盆や正月や先祖神と絡んで記述されていて魂の在りかが分かる良い本である。
本書は、旧約聖書、ギリシア・ローマ、エジプト、イスラム教、インド、日本先史時代、古代日本人、近代日本人の合計八の記述からなる、それぞれの別の著者による論考と言うよりエッセイのようなものである。無論、それぞれ専門家が書いているために読み流してもそれなりに幅広い知識は得られる。特に関心を引いたのが、エジプトにおける「死者の手紙」や息を口に吹き込む「開口の儀礼」、イスラムにおける美しき処女、いわよるフーリーの火獄などの歴史的事実や、日本における「死=母に抱かれる」というという魅力に満ちたな思想的な指摘である。イスラムにおける死とエロシチズムについては大いに関心を引いてもっと記述して欲しかったと思っている。
日本における「古事記」を中心にした「死=母に抱かれる」思想については少しばかり感想を述べたい。「古事記」とは作成された物語であり、「黄泉の国」とは作り出された概念である。「日本霊異記」とは聖人(天皇制)を正当化する霊異な出来事を記述した書である。では、なぜ穢れた黄泉の国と「日本霊異記」の説く因果応報と極楽浄土がほぼ同時期に両立し得たのか。それは概念が思想としてのみとして作動するのに対して、因果応報と極楽浄土は日常生活に密着しているが故にすぐさま溶け込んだためであろう。また、縄文時代のストーンサークル(環状列石)が共同体社会における厳粛かつ尊い儀式を表しているとするなら、死者に対する思想も受け継がれているはずであり、死者は穢れた「黄泉の国」に行くよりも、尊い先祖の霊として奉られるはずである。このため再度言うが、仏による因果応報と極楽浄土の思想がもたらされると、縄文時代から続く死に対する共同体の思想との親和性にゆえに、すぐさま日常世界に広まり規範として受け入れられたのである。
共同体の原理は厳しさと同時に安らぎをもたらすはずであり「黄泉の国」の穢れとはほぼ無縁である。即ち、イザナミが母なる生の神であると同時に「黄泉の国」の「黄泉津大神」として死の神になる、この暗く穢れた「黄泉の国」の死の神に、死者は抱かれるはずはないのである。この神は概念であり、いわば感覚的に心に内在する神である。著者が言質として引用する三島由紀夫は、ある著書で暗い地の底の国に引き込まれる感覚を記述していたことがある。こうした感覚は人によって生じる特有の感覚であって一般的ではない。従って「楢山節考」における三島由紀夫の「母の暗い母胎に引き込まれる感覚」という言質は「楢山節考」に対する三島由紀夫の感覚であることに注意しなければならない。この言質は三島の「楢山節考」に対する見方であり、「楢山節考」では母を背負って果てしなく山を昇って行くために、むしろ天国や極楽浄土に近くなるとが一般的な読み方であろう。従って、死して土に還る、もしくは蓮の葉に乗ると言うのが一般的であり、恵みの母に抱かれるか極楽に往生するはずなのである。即ち、母なる「黄泉津大神」ではなくて、言わば西洋的に言えば大地の母なるガイアに抱かれる、もしくは成仏して仏様なる極楽に抱かれると言うのが適切であろう。
こうしてみると「死生観」とは空間と時間の連続性の視点を持って解かなければならない。「死生観」は独自に生まれ、相互に浸透して、また育まれる。それは共同体という暮らしの場を明るみに出すであろう。「古事記」を例にあげるならば「黄泉の国」とは空間的に地続きである。イザナギとイザナミが諍って死者と生者の数を互いに述べた後、遮断の岩は取り除かれて、「黄泉の国」は母を恋してスサノオも行くし、誰もが行く所となる。またイザナギが還ってきてイザナミの穢れを禊ぐと、多くの神々も生まれるでてくる。生んだ母は誰かなどと野暮な問いはしないが、命はこのように時間と言う系譜に連続して生み出されて、生み出し終えると死に至るのである。インドとイスラムの「死生観」は共鳴して、インドの「死生観」は日本という空間に持ち込まれて育まれる。そういう意味で、本書は「死生観」を思考するトリガーとしての意味は果たしている。でも、死者がどこに行くべきか思想のまとめは無いし、死者もどこに行くか迷っている。
以上
詩や小説に哲学の好きな者です。表現主義、超現実主義など。哲学的には、生の哲学、脱ポスト構造主義など。記紀歌謡や夏目漱石などに、詩人では白石かずこや吉岡実など。フランツ・カフカやサミュエル・ベケットやアンドレ・ブルドンに、哲学者はアンリ・ベルグソンやジル・ドゥルーズなどに傾斜。
